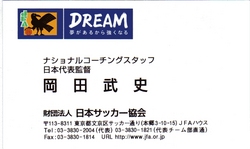起業メンター日記
自由からの逃走
最近、日本では新型インフルエンザも大分落ち着いてきたようです。
それでも蔓延を防ぐための方策がいろいろ考えられています。
その1つに「法的拘束力」が注目されています。
新型インフルエンザ感染を防ぐためのルールに従わない人がいるのは確かです。
今朝の新聞に、飛行機内でマスクをするというルールに従わず、飛行機から下ろされた人がいたという記事がありました。
その人には「マスクをしないという自由」は有りますが、密閉された飛行この中では、他の人の不安に対する思いやりというもの必要でしょう。
ルールに従わない人に対して、ルールに強制力を持たせる「法的拘束力」が必要だという声が多くあります。
ただこの「法的拘束力」に一旦頼ると、簡単に人の自由が制限されます。
もしかすると、その方が「管理する側」も「される側」も楽なのかも知れません。
考え、判断する必要がなくなるからです。
社会心理学者エーリッヒ・フロムが言った言葉に「自由からの逃走」というものがあります。自由でいる責任に耐えかねて逃げ出したくなる心理。
その心理こそが全体主義を起こし、ドイツにナチスを生み出しました。
今の中国の共産党独裁体制もそうなのかも知れません。
新型インフルエンザを機に、世界中に「自由からの逃走」の機運が高まり、全体主義的風潮が生まれる。
そんな不安な気持ちになっています。
レンタルオフィス シェアオフィス 「札幌オフィスプレイス」
コロナの前と後
ある心理学の本に「人間の心と体は禁欲的で社会から孤立するような形では進化してこなかった」と書いてありました。
人間は、人と交わることが出来なければ成長出来ません。
現在の様に、コロナのために世界中が禁欲的生活を強いられ、自粛することで社会から孤立してしまっては人間としての生活は出来ません。
この状態はいつ解けるのでしょうか。
孤立状態が続けば世界中の全ての分野における経済も立ちゆかなくなります。
私は経済の凍結がこの世の中の仕組みを壊す。
その様な恐れを抱いています。
マスクをしない人を許さないという不寛容な人が増えています。
「自分の言うことは正しい」という独善的な風潮が起きています。
これは個人ばかりでなく、国家間でも起きつつあります。
コロナ前と後とで、今までと全く違った価値観、倫理観が生まれてくるとは考えられません。
ただコロナによる行動規制や束縛感が人の感性を変えている。
そんな不安な気持ちにさせられます。
レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
多角的思考
今朝の日経新聞の「春秋」に書いてあったこと。物事を見て判断する時、「批判的思考」が大切だと書いてありました。物事を批判的に見る事で別の面が見えてくると言います。確かにそれもあるでしょう。しかし私はそれに対して同調できません。見るべき見方とすれば「多角的思考」こそが大切だと考えます。「批判的思考」だと批判的という観点に捉われすぎます。多角的に見てこそ、その本質にたどり着ける事ができます。経営者にとって「多角的思考」はとても大切な経営資質です。一方的な思いつきや思入れは判断を狂わせます。多くの情報が飛び交うこの世の中、特に心しなければならない事だと考えます。
レンタルオフィス シェアオフィス 札幌オフィスプレイス
交差点にて
我が家近くの交差点でのこと。
ある日、我が家の近くの保育園の子供達が、保育士さん達に連れられて散歩。
散歩の帰りにその交差点に来ました。
渡る方の信号は青でしたが、保育士さん達は渡りません。
しばらく経つと、その信号の青が赤になり、再び青になった時、子供達を連れて渡り出しました。
青信号を1つやり過ごしたのは、安全に渡るための方法だったのでしょう。
同じ交差点で、足が悪そうで、ゆっくりにしか歩けないお年寄りが歩いてきました。
信号の青が点滅しそうなので、止まるかと思ったのですが渡り出しました。
案の定、道路の真ん中あたりで信号は赤。
そのお年寄りはゆっくりにしか歩けません。
彼は彼のために止まっている車の方を気にする様子もなく、悠然と歩いて行きました。
子供連れのお母さん。
青信号が点滅しているのに、子供の手を引っ張って、走って渡って行きました。
交差点に立っていると、色々な人の渡り方を見て考えさせられます。
私も交差点を渡る時は気を付けています。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
レジ袋
7月1日今日からコンビニもレジ袋の有料化が始まります。
スーパーなどは以前から有料化になっていました。
ただ、この有料化について少し疑問に思うことがあります。
環境のためという名目でレジ袋の使用を制限するのが目的なのでしょう。
レジ袋が海に流れてウミガメがクラゲと間違えて食べて死ぬとか、マイクロプラスチックになって魚が食べるとか言われています。
でも疑問に思うのは、日本では普段、レジ袋は使い終わればゴミ収集日に出します。
それであれば海に流れることはありません。
海に流れていくのは海や川に捨てる人がいるせいでしょう。
それならば、むやみに捨てないように呼びかければ良いことです。
捨てられるのはレジ袋ばかりではありません。
プラスチックトレーもそうです。
プラスチックトレーの方が圧倒的に数は多いはず。
この対策の話は中々出て来ません。
確かに、現代は使い捨てのプラスチック製品が多いことは確かです。
少し不便でも、環境を保持するために自分たちの生活を見直すのは大切なことです。
昔のようにガラスや壺、経木を使うことは難しいでしょうが。
先日、東急ハンズでレジ袋に代わる「マイバック」を買いました。
縦・横・厚が5.5㎝×4㎝×3㎝の小ささです。
私は今日からこれを使います。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
自信の無い人
以前、会社で仕事をしている時、ある事があり、人に注意した時のことがあります。
注意されたその人は大いに反発しました。
注意の仕方にもよりますが、注意を受けた人は大きく分けて2通りの反応をします。
1つは注意を受けたことに直ぐ反発する人。
もう1つは「はい分かりました」と素直に答える人。
前者は注意された時、「自分否定をされた」と思い込みます。
言われたことの善し悪しを考えるより、先に自己肯定の行動として感情的に反発してしまいます。
やはりこの様な反発は自分に自信がないことの裏返しです。
また、後者の方は一見すると素直でいいように思いますが、これも自分に自信がない為、自己判断するより相手の言うままに聞いておく方が楽だと思っています。
どちらも自信が無い人の反応パターンですが、それでは自信のある人はどうするか。
自信ある人は、注意している相手の言っている話をまず受け止め、その内容を理解しようとします。
その時、内容確認のために質問はしますが、その後は「それでは〇〇のようにします。」と、これからの自分の対応を述べます。
そして理解した上で行動します。
部下に対して注意したことのある人は経験あると思いますが、人に注意をすることは余り気が進みません。
注意して嫌われたくないという気持ちがあります。
それでも仕事の上ではしなければならないことです。
注意された人が、注意受けることで成長してくれる。
それこそが、仕事をする上でのやり甲斐でもあります。
起業支援 レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
インフレ
ここへ来て、新型コロナウイルスの感染者も少し減少の傾向が見られて、先週の15日に政府も緊急事態宣言の解除に踏み出しました。
そろそろ、この新型コロナウイルス騒動後のことが心配されます。
その中でも、やはり経済に関することが心配です。
日曜日の日経新聞の一面に「忍び寄る世界デフレ」という見出しの記事が載っていました。
確かに一時的には物販が停滞し、物余り状態が続き、デフレ傾向になります。
しかし、それは一時的な現象だと考えます。
新型コロナウイルスの前と後では人の考え方と行動が変わると思います。
そして意識が変わります。
コロナ禍によって商売をしている人は痛感していると思います。
内部留保の重要性、そして如何に手元資金を確保しておかなければならないか。
今までは日本はデフレの風が吹いていて、安くしなければ買ってくれないという風潮がありました。
そして薄利多売という考え方が主流でした。
しかし、これからはそうはいかないはずです。
コロナ禍が落ち着いた時、経営者はこの騒動で失った売上・利益を早急に取り戻さなければならないと考えます。
そして、商品を高売りし、利益を確保する考えに変わっていくのではないでしょうか。
新型コロナウイルス後は各分野における値上げが始まります。
そしてインフレ発生が大いに予想されます。
これは日本ばかりではありません。
各国の中央銀行が新型コロナウイルスによる経済影響対策のために、現在大胆な金融緩和を実施し、お金をばらまいています。
金融緩和は仕方が無いことですが、これは大きなインフレ要因となっています。
そして世界の中央銀行や企業が抱える債務は2京7000兆円になっています。
もしかすると、今年の秋口からインフレの兆候が出てくるのではと予想します。
社長は会社の「仕入額」と「販売価格」を見直し、適正な販売価格を示していかなければなりません。
稲盛和夫さんが常に話している言葉に「売値は社長の責任」があります。
先手先手を打って値決めしていく。
これは社長の責任です。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
直筆メッセージ
今般の新型コロナウイルスの流行で、飲食店への影響が甚大です。
飲食店は中小の規模の店がほとんどでしょう。
自粛という名の下に閉店させられる。
それでも、少しでも収入を得ようと努力している店があります。
テイクアウトや通信販売を始めるところもあります。
私も知人の店の通信販売を利用し、先日品物が送られて来ました。
ホッケの干物や、鮭とば等が入っており美味しく頂きました。
品物と一緒に食べ方の説明書と挨拶文が入っていました。
丁寧な挨拶文でしたが、少し物足りない気分。
それは印刷の挨拶文のせいでしょう。
チョットでも直筆のメッセージでも書いてあればいいのに!
正直、そんな気持ちでした。
きれいな紙に印刷された挨拶文は、文字の伝達は出来ても、「思い」をそれに載せることは難しいです。
最近、テレビCMに吉永小百合さんが出ています。
パイロット万年筆のCMで、吉永小百合さんが手紙を書いている姿が映っています。
万年筆でゆっくり書く姿が素敵です。
ネットのこの時代だからこそ、あえて万年筆で書くことがいい。
そんなことを表現しているのでしょうか。
時あるごとに、お客様へ葉書を出している経営者がいます。
それも直筆で。
簡単な内容ですが、それがお客様に喜ばれているのです。
困った時に助けてくれたお客様にお例のメッセージを一言添える。
チョットした手間ですが、そんなことが今とても大事なことだと考えます。
お客様がフアンになってくれる時だと思います。
起業支援 レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
母の日のプレゼント
今度の日曜日5月10日は母の日です。
先日、妻が白いカーネーションを買ってきました。
私達夫婦の両親は既にいなくなっているので、白いカーネーションにしました。
白だけでは淋しいので赤色も少しあります。
妻は先日、子供達から「母の日のプレゼント何が欲しい?」と聞かれました。
妻の返事は「子供達家族全員の写真とお母さんの良いところを10個書いて送るように」と言ったそうです。
さて、5人の子供達はどんなことを書いて送ってくれるのか。
妻は今から楽しみにしています。
再起支援
なかなか治まりそうにない新型コロナウイルス。
外出もままならない中で、私達は精神的・経済的影響を受けています。
その中でも特に、満足に商売が出来なく苦しんでいる「小企業」の経営者達。
志に燃え起業した経営者。
彼らには資金の余裕はありません。
懸命に自分の会社・店を守り抜こうとしていますが、今のような状態は少なくとも6ヶ月間は続く可能性があります。
1ヶ月後、2ヶ月後まで守り抜けるでしょうか。
もしかしたら多くの会社が倒産していくかもしれません。
素晴らしいビジネスプランがあり、熱い心で高い志を抱いた経営者なのに、この新型コロナウイルスという、人の力では如何しても太刀打ちでいない怪物の前では敗退していく人も多いことでしょう。
大きな借金を抱えていく人も多いです。
何ヶ月後なり、このコロナ騒動が治まった時、彼らはどうするでしょう。
彼らに再度挑戦せよと言っても難しいでしょう。
今の日本の金融制度の中では彼らを救えないのかもしれません。
しかし、だからといって素晴らしいビジネスプランや人材をそのまま捨て置くのは、日本の将来に対し大きな損失になります。
新型コロナウイルスの対策に莫大な費用をかけた国や自治体には彼らを助ける余力は無いでしょう。
その時にこそ、個人投資家やベンチャーキャピタル、そしてクラウドファンディングがその役目を負うのではないでしょうか?
大きな規模の投資額ばかりを言うのではなく、自分の住む地域単位でも良いです。
一度失敗したからといっても、その経営方法が悪かったわけではないのです。
不可抗力だったのです。
その彼らに再起を促す。
その方法を考える必要があります。
その1つに、失意にあっても志の高いの経営者に少額でも資金提供が出来る。
その「資金提供者」を集める。
そのような考え方が生まれると、地域活性化の基になります。
ある報道の中に、その1つの形の現れとして、実際にクラウドファンディングが立ち上がっているようです。
益々その機運がが盛り上がること期待します。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
新型コロナウイルス克服その後
新型コロナウイルスの流行は益々広がり、先行きが不明どころか大変不安になります。
オーバーシュート状態になるのを防ぐためにも、早期に緊急事態宣言を発するようにと日本医師会や諮問委員会でも提言しています。
それなのに、なぜ安倍総理は躊躇しているのでしょうか。
予想するに、緊急事態宣言を発する時は、同時に経済的損失補償も提示しなければなりません。
経済的保証がなければ「死ね!」と言っていることになります。
これがネックになっているのではないでしょうか。
日本の財政はこのコロナウイルス問題以前から逼迫した状態にあります。
102兆円を超す今年の国家予算も32兆円の赤字国債発行が予定されています。
税収は63兆円と予想していますが、このコロナウイルス蔓延のため経済活動が止まりつつあります。
そこに緊急事態宣言を出すと、各業界では90%以上会社が赤字になることが予想されます。
となると、予想していた税収63兆円は大幅な未達になる恐れがあります。
その上、緊急事態宣言に伴う経済損失補償が発生すれば日本の財政はパンクします。
経済損失補償が発生すれば、国は大幅な赤字国債発行いう事になるでしょう。
しかし大幅な赤字国債を発行で来るでしょうか?
買ったくれるところがあるでしょうか?
世界各国でも同様な国債発行をするでしょう。
日本は今でさえ1100兆円を超す国債を発行しています。
それを主に購入しているところは日本銀行。
追加発行した国債を日銀が本当に購入出来るでしょうか?
日銀は今までも大量のETFも購入しています。
このままでは日銀が持たないという話も出ています。
この新型コロナウイルスの恐ろしさはまだまだこれから起こるかもしれません。
しかし、いつの日かそれを克服しても、眼前にあるのは凋落して日本経済。
そしてそれを救えない日本政府・日銀。
そういう世界が生まれそうな予想があります。
4月1日付けで国家安全保障局に「経済班」というのが発足しました。
その時のための準備。
そのような思いもします。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
「自分」株式会社
今朝の日経新聞の「大機小機」に「自分」株式会社という言葉が紹介されていました。
「自分」株式会社という考え方は、カナダ・ヨーク大学のモシェ・ミレブスキー教授の本の中で表した言葉です。
1人1人が「自分」株式会社の最高経営責任者兼最高財務責任者として、その企業価値を最大にしていきなさいと説いています。
「自分」株式会社に込められた意味は、生涯にわたる長期の視野を持ち、経済的に自立して生きることの大切さです。
新型コロナウイルスのパンデミックがいずれ去った後、世界経済も個人の価値観も大きく変質しているでしょう。
最後には、「自分」株式会社の資産を増やすには、自分という人的資本に投資し続けながら、リスクをコントロールし、賢くお金を増やしていくことが大切と書かれています。
この「大機小機」に書かれているように、このパンディミックが終わった時、世界の経済状況も価値観も激変していることが予想されます。
「こんなことになるとは思わなかった」などと言ってもどうしようもありません。
個々人が自分の力で乗り越えなければならないことが起きます。
その時こそ、「自分」株式会社をしっかり維持していきたいものです。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
経営者は外へ出よう!
今やコロナウイルスの拡大は各業種にわたって多大な影響を及ぼしています。
特に観光業や飲食業は「在庫出来ない業種」であり、その日その日失った売上は取り戻すことが出来ません。
昨夜は東京オリンピック延期の話が出てきて、観光業飲食業にとっては、益々先行きの不安が増えてきました。
しかし、不安を口にし、嘆いていても仕方がありません。
何とかしなければなりません。
と言って、何とかしなければならないと分かっていても何も出来ない!
それでも何とかしなければ店や会社はつぶれてしまいます。
経営者は1人で考えてはダメです。
会社全体で考え、アイディアを募りましょう。
そして外部の知恵も借りましょう。
外部といっても同業者はダメです。
同業者はお互いを牽制するし、また業界が同じなので、同じような概念の人達の集まり。
良いアイディアは出にくいでしょう。
親しい異業種の人達とのミーティンは効果あります。
人は「自分の事」となると、出来ないことや、出来ない理由が先に立ち、アイディアが詰まってしまいます。
しかし他業種や他人のこととなると、好き勝手なことが言えます。
その好き勝手な話の中に良いアイディアが潜んでいます。
それを見つけ出し、会社に戻り、皆でそのアイディアを練って、新製品、新しい販売手段、新しい対応等が作り出される可能性があります。
今こそ経営者は会社で頭を抱えるのではなく、外へ出ましょう!
素晴らしいアイディアが待っています!
日銀のETF
コロナウイルスは世界中に、そしてあらゆる分野に多大な被害を及ぼしています。
昨日のアメリカの株式相場は先日に続いて、1400ドルを超す大幅な下げとなりました。
それをネットで見た時、円高が進み、対ドルで100円位なっているかと思うと、104円台で昨日と変わらない状態。
以前は世界に経済的異変が起きると、避難通貨として「円」が買われ円高が進みました。
それが最近はそうではなくなりました。
円高になりにくいのです。
その理由の1つには日本国内でのコロナウイルスの拡大があります。
日本経済も大きな影響を受け、避難通貨と成りにくくなっています。
しかし、もう1つ大きな理由があると考えています。
「円」の信用に及ぼす異常事態が発生しているのではないでしょうか。
以前から問題視されている1100兆円を超す借金体質の日本の財政があります。
日銀は政府が発行する国債のほとんどを買っています。
その上、日本の株価を支えるために、他国の中央銀行が決して行わなかった、上場投資信託(ETF)を買い進めています。
中央銀行がETFを購入するのは異例ですが、今は1日に1000億円購入し、保有する残高は29兆円。
今後も年間6兆円以上を投入するとも言われます。
この日銀が購入しているETFについて、昨日の日経新聞に日銀の黒田総裁の発言が掲載されていました。
10日に開かれた参院財政金融委員会で国会で発言です。
その内容は、「日銀が保有しているETFの損益分岐点は日経平均株価19,500円」と明言しています。
今日12日10時20分現在の日経平均は大幅に下がり、18,819円で19500円より681円低くなっています。
もう既に日銀は含み損を起こしているのです。
これは大変な事です。
今後の「円」に対する信用問題に関わってきます。
避難通貨どころか、「円」の売りが続き、円安が進むことが予想されます。
これは単なる私の私的予想ですが、「円」がこれからどうなるか注視していきます。
起業支援 レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
在庫出来る業種
以前に「特別融資」という題名でも書きましたが、「商品」を在庫出来る業種と、在庫出来ない業種の違い。
製造業の場合、製品が売れない時でも作り置きできます。
それを在庫しておけば、その後経済状況が変わると一気に売れ、売上を急激に伸ばすことが出来ます。
しかし在庫の出来ない業種、ホテルや飲食店のようなところは、商品を在庫出来ないので、失った売上は永遠に取り戻すことが出来ません。
そして一気に売上を上げることが出来ません。
今回のように、コロナウイルス問題で一時売上が下がり、その後状況が回復しても失った売上を挽回することは出来ません。
製造業の場合は売上が上がらない時、特別融資を受けてもその後、失った売上を取り戻せるので借入返済も可能でしょう。
しかしホテル・飲食店等はそれは出来ません。
会社の底力は、やはり内部留保があるかないかにかかってきます。
これは机上論ではなく、実務・実際論です。
起業支援 レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
内部留保
1月に起きたコロナウイルス騒動。
ここへ来て、コロナウイルスによる各分野への影響とそれに対する対応が毎日のように発表されています。
個人の生活・活動も制限されてきています。
1ヶ月ほど前は、コロナウイルスに対する対応も場所限定的で、自分たちの生活まで影響が及ぶとは思っていませんでした。
しかしここへ来て、多くの学校への休校指示、会社の自宅勤務、そして人が集まる各行事の中止・延期の要請。
ついでながら、私が通う音楽教室も昨日から休校になりました。
ビジネス・観光客の激減、それと飲食関連、特に3月を中心に予定されていた送別会はドンドンキャンセルされています。
私共のホテルも大きな影響が出そうです。
また、一般飲食店などもお客が激減していると聞きます。
経済に対しての甚大な影響が心配です。
各国の株価は軒並み激減。
どもまで落ちるのか!
リーマンショック並の影響が出るかもしれません。
そして、会社倒産が起きてきています。
体力の無い会社は一気に淘汰されていくでしょう。
会社の体力とは「内部留保」です。
「内部留保」が無い会社はこの危機を防ぎきれず、淘汰されます。
しばらく前には、会社の「内部留保」の多さが非難された時もありました。
しかしこれからは、「内部留保」の多さで会社が維持されるかどうか決まります。
人・物・金が動かなくなります。
これから経験したことのないことが起きそうな予感。
守りを堅くしなければなりません。
起業支援レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
新聞の存在
今、日本中で一番の関心事はやはりコロナウイルスでしょう。
確かに私もいつも気になり、テレビのニュースをよく見ています。
お昼のワイドショーもその関連の話が流れています。
それ以外の流れる話題は芸能人の不倫問題。
勿論コロナウイルスに関する情報は大事なことですが、このニュースばかりにテレビニュースの時間が割かれ、他の大事な情報が流れて来ない。
そんな風に感じませんか?
テレビなどは時間的制限があるため、コロナウイルスに関する報道ばかりだと、政治や経済に関する報道は限られてきています。
その点、新聞は違います。
時間的制限はありません。
新聞は紙面を増やせば多くの情報を伝えることが出来ます。
新聞の報道ではコロナウイルスの情報は勿論掲載されていますが、それ以外の情報・ニュースも多く報道されています。
政治・経済は勿論、国際・各企業情報、そして科学技術の分野もあります。
新聞にはテレビやネットのような即時性はありませんが、広い分野の情報や知識を得ることが出来きる。
新聞を見直しています。
起業支援 レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
特別融資
先月末に発生したコロナウイルスは世界各地、そして色々な分野で人・物の流れに支障が起こしています。
特に人の移動が制限されているのが大きいです。
中国からの観光客の減少は日本各地の観光地に多大な影響を起こしています。
そして極端な売上の減少が発生しています。
札幌でも昨日まで開催されていた雪祭りの来場者数は前年比25%の減少になっています。
テレビなどの報道によると、各地の自治体は観光関連業者への支援として特別融資を実施すると発表しています。
観光客の減少による売上が下がり、資金繰りに困る会社が多く出ているようです。
確かに困った時に支援してくれる特別融資はありがたいのですが、しかしこの融資を受けるのは慎重にしなければなりません。
特にホテルや旅館のような客室数が限定されているような業種は慎重にしなければならないと思います。
例えば100室のホテルは、当たり前ですが100室以上は売れません。
昨日50室しか売れなかったとしても、その失った昨日の50室は永遠に売れません。
ここが製造業と違うところです。
製造業の場合は生産性を上げれば、過去の売上減少分は取り戻せる可能性がありますが、ホテルの場合それはありません。
観光客が減少して売れなかった客室は、その後いくら頑張っても取り戻せません。
いくら頑張っても稼働率100%以上にはなりません。
この事は店の席数が決まっている飲食店にも言えます。
金利が安いといって、融資を安易に借りても、その借入返済によって、後々の経営に響いて来ることがあります。
熟慮して融資を受けなければなりません。
新型コロナウイルス
新型コロナウイルスに関する報道が連日流されています。
テレビをつければワイドショウでも、そのニュースが流れています。
如何しても気になりますので、私も見てしまいます。
でも考えてみれば、まだ身近に保菌者がいる様子もないので、普通の生活をすればいいのです。
従来からあるA型B型インフルエンザ予防と同じように手洗いとうがいをすれば良いでしょう。
それでも、先日、銀行に行ってみると窓口の女性は皆マスク姿。
電車の中もマスク姿の人が多いです。
旅行先の宿に、中国人が宿泊しているかを確認し、宿泊しているとわかるとキャンセルする人が出てきている報道もありました。
皆さん神経質になってきているようです。
この新型コロナウイルスの感染者数は4月5月がピークとい情報が流れていますが、それよりウイルスに対する恐怖心が先行しているようです。
実際のウイルスの恐怖より、心理的パニックを起こす危険性の方が高くなってきているように思います。
東京オリンピックが心配です。
起業支援 レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
人の魅力
「魅(み)は与(よ)より生じ、求(ぐ)によって滅する」
これは無能唱元さんの言葉です。
無能唱元さんという人は仏教を学び、仏教にある「アラヤ識」を活用した「人蕩術」という考えを広めた人です。
「唱元」という法名をも授かっています。
「魅は与(よ)より生じ、求(ぐ)によって滅する」の意味するところは、「人を引き寄せる魅力は、人に何かを与えることで生まれ、逆に人から何かを欲しがった時に無くなる」という意味です。
人にお金やモノを上げれば喜び、くれた人に好意を持ちます。
逆に、人にお金やモノを欲しがれば敬遠されます。
人に喜びを与えようとすれば好まれ、自分のことばかり考えて、得る事ばかり考えていれば嫌われます。
お金やモノばかりではありません。
こんなこともあります。
会社の社長で、自分のことばかり話したがる人がいます。
自分の会社のことや取引先とのトラブル、ゴルフ等の話と、要するに自分の事ばかりです。
20分位話しています。
そして、今度相手が話し出すと、おもむろにタバコを出し、火を付けます。
相手が話をしていても、いかにも興味なさそうに、ぼんやりした目つきで聞いている。
こんな社長を見かけませんか?
これこそ「求(ぐ)」です。
この社長は相手に対して「聞いてもらうことだけを求めている」のです。
そして、逆に相手が話していても、その「求め」には応じていない。
まさしく「魅は与(よ)より生じ、求(ぐ)によって滅する」の逆のパターンです。
ワンマン社長の姿です。
歴史的に見て、魅力的な人物の代表、それは豊臣秀吉。
まさに、「魅は与(よ)より生じ、求(ぐ)によって滅する」を証明した人です。
参考にするところが沢山あります。
起業支援 レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
年間活動計画書
起業を志す人は銀行から融資を受ける時に事業計画書を作成します。
しかし、多くの起業家は「事業計画書はお金を借りる時に必要な書類」としか考えていない。
そのような人が多いような気がします。
そして、起業してしばらく経つと、事業計画書どころか、年間活動計画書も作らなくなり、ただ目の前の仕事のネタを探すのに一生懸命になっています。
結果、先行きの売上の予想も立たないし、キャッシュフローさえ掴めない。
それでいて、「なぜ売上が上がらないのだろうか?」等と考えます。
なぜ売上が上がらないのか!
それは当たり前で、「どこに、どのようなお客様がいるのか」を知ろうと努力していないからです。
お客様は、月ごと、催し物ごと、季節ごとに生まれます。
そのお客様を予想する上で、年間活動計画書は絶対必要なのです。
その年間活動計画書に合わせ、前もってお客様獲得のための工作準備や、受け入れ体制を整えたりすることが出来ます。
「先の見える経営」が出来るようになります。
この「先の見える経営」が事業を成功させる上で大変大切なことなのです。
起業支援 「レンタルオフィス」 「札幌オフィスプレイス」
目的・目標
起業した人が仕事を進める上で大事なことは、事業の目標・目標は明確にすることです。
なぜこんなに一生懸命仕事をしているのか!
その理由が明確でなければ方向性も分からなくなるし、情熱も湧きません。
一生懸命働く理由、それが「目的・目標」です。
「目的・目標」が明確だと、「強烈な願望」を心に抱くことが出来ます。
「強烈な願望」を心に抱けば、「誰にも負けない努力」をすることが出来ます。
「誰にも負けない努力」をすれば、会社の業績は伸びます。
「目的・目標を明確にする」「強烈な願望を心に抱く」「誰にも泣けない努力をする」
この3つ思いは、常に関連し合います。
仕事に疲れた時、「何のために働くのか」の目的を思い出します。
「その目的・目標を達成するために働くのだ」ということを再認識し、それがまた働く情熱の原動力となります。
この3つの思いを大事にすれば事業は成功し、会社の業績は伸びます。
成功した多くの会社がそれを証明しています。
自分ホメ
昔に読んだ遠藤周作の本に、主人公の住むアパートの2階から、毎夜大きな叫び声が聞こえたという場面が書かれていました。
その日の夜、自分にあった事柄を思い出し、後悔の叫びだったようです。
1日の終わりに、その日の自分の行動を振り返り、反省することは大切です。
稲盛和夫さんも毎夜、その日にあったこと思い返し、悪かった自分を反省し、鏡に映った自分に向かって叱るそうです。
そして最後に「神様ごめんなさい」と言って反省は終わると言っていました。
反省はそこで終わらなければズーと引きずり、先程書いたように夜中に大きな叫び声を上げてしまいます。
稲盛さんは「六つの精進」の中で「感性的な悩みはしない」と言い切っています。
人はどうも自分を否定的見てしまいがちです。
「頑張っているのに仕事の成績が上がらない。もっと頑張らなければならない!」とか、「自分は能力がない!」「周りからの評価が低い!」等と自己否定することが多いです。
私も昔はそうでした。
でも今は少し変わりました。
「自分ホメ」を実践しています。
そして人にも勧めています。
落ち込んだ時や、辛い時に「伸幸、お前は頑張っている!偉い!」などと、声に出して「自分ホメ」をします。
落ち込んでいる時などは、自分が出している声なのに、天から誰かが言ってくれているような思いになります。
辛い時だからこそ、その声で励まされ、ジーンとしてうっすら涙まで出てきます。
そんなことをしている内に元気になり、自己否定することも少なくなり、自信が持てるようになりました。
「自分ホメ」
是非とも試されると良いですよ。
起業支援レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
健康寿命
日本の男性の平均寿命は81歳。
また、日常生活が支障なく生活出来る期間を健康寿命といい、72歳です。
私は今年で71歳になりますので、もうそろそろこの年齢に当たります。
この頃は私も、身体の至る所に問題がありますが、今のところ普段の生活は支障なく出来ています。
私は団塊の世代の最後の世代に当たります。
3歳上の団塊の世代は、もうすぐ75歳になり、後期高齢者と言われる世代です。
高齢者が増えてくると、当たり前のことですが、平均寿命を延ばすより、健康寿命を延ばすことの方が重要です。
寿命が少なくなってきているのだから、好きなことをして生きたらいいと言って、家の中で好きなモノを飲み食いするような生活はダメです。
寿命が少なくなっているのだからこそ、年寄りは毎日の生き方を真剣に考えなければなりません。
それは自分のためにも、また子供孫達世代のためにも大事なこと。
周りの人達に迷惑をかけない。
常に前向きに考え、行動していく。
今、改めて思っています。
起業支援レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
ギックリ腰
1週間前、旅先でギックリ腰になりました。
初めての経験なのでギックリ腰なのかは分かりませんが、帰り支度をしている時、少し腰をかがめた途端に激痛。
暫く動けなくなりました。
2時間ほど横になっているうちに少し痛みはなくなり、ゆっくりなら歩けるようになりました。
浅草から羽田空港までタクシーを手配し、やっとの思いで帰ってきました。
旅行前に整形外科で脊柱管狭窄症と言われていたのでそれが原因?
歳を取ると色々なところで支障が出てきます。
30年前になった頸椎ヘルニア。
それに今度の脊柱管狭窄症。
まだまだ動き回りたいので、色々な支障と仲良くしながら生活しようと思います。
少し筋肉も付けましょう。
君のその判断は美しいのか!
「君のその判断は美しいのか!」
これはある人の文章の中にあった言葉です。
「君のその判断は正しいのか」と問われることはあります。
「善悪」で判断することは良いのですが、もしかすると堅苦しいところと、判断しにくいところがあります。
しかし、判断する時「美しいか・醜いか」を基準にするとわかりやすいのではないでしょうか。
日の出を見て、その荘厳さを美しいと思う心。
バラの花を見て美しいと思う心。
交差点で、足の悪い老人の手を引いていく人。
その行動を美しいと思う心。
自分の行動を自分で見て、美しいと思えるのか!醜いと思えるのか!
誰でもなく、自分がしていることを自分が見て、美しいと思えるのか!
そんな思いを抱いて生きていく。
今年はそんな年にしたいと思います。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
2020年
今日はクリスマス。
12月に入り今までクリスマス一色でしたが、明日からは一気に正月に向かって世の中は流れていきます。
毎年のことですが、この急変には驚きます。
来年はオリンピックの年です。
マラソンや競歩が札幌で行われます。
明るい話です。
一方、オリンピック後の景気が落ち込むという話。
英国とEU、アメリカと中国、日本と韓国などの国際問題。
最近多くなってきている関東の地震に関連づけて大地震の話。
また、年号が分かると大きな出来事が起こるという噂話。
大正の年号が変わった時に起きた第一次世界大戦。
昭和が始まり暫くして起きた世界大恐慌。
平成に入ってからのバブル経済とその終焉。
それらの話を引き合いにして、年号が変わると経済の大変革が起きるという話をする人もいます。
そんな話を聞きながらも、来年はいい年だと信じたい。
自分が出来る範囲で頑張る。それがいい年になるという思いに繋がります。
私の好きな言葉があります。
落語のオチに「俺には金も何もないけれど、手つかずの真っ新の来年があるんだ」
いい年をお迎えください。
レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
盛和塾解散
先週の11日水曜日に、盛和塾東日本忘年会が開かれました。
今年いっぱいで解散となる盛和塾の最後の行事でした。
私も参加し、別れをしてきました。
来年の1月に88歳になる稲盛さんは、体力の衰えと共に盛和塾を解散することを決意しました。
10年以上前から「自分の引退と共に盛和塾は解散します」と宣言されていた通りです。
私は15年前に盛和塾に入塾し、「経営の勉強」、そして「人としてどう生きるか」を教えていただきました。
現在、世界中に14,000名を超す塾生の中には、来年以降地域ごとに塾生同士で勉強会を作り勉強を続けていく人がいます。
私は彼らとは別に1人で引き続き稲盛さんの教えを学んでいこうと思っています。
150冊を超える会報、それに多くの書籍。
それに盛和塾生だった人だけが利用出来る「稲盛ライブラリー図書館」があります。
ここには過去に稲盛さんが講演されたビデオと文章が数多く掲載されており、ネット上でいつでも見ることが出来ます。
今まで稲盛さんから受けた教え。
これからは、それぞれ1人1人がそれを自分で血肉化して生きていく。
これが大事なことだと、稲盛さんが私達に伝えています
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
人前で叱る
人前で叱る
私がまだ若い頃は、ある経営の本を読むと、「人に注意する時は人前で叱ってはいけない」と書いてありました。
人前で叱ると、叱られたその人間に恥をかかせることになり、素直に聞かないということです。
私は「成る程」なほどと理解しました。
しかし、今、それは違っているとはっきり言えます。
叱られて恥だと思えて、恥ずかしい思いをした時、心深くその記憶が残ります。
それにより2度と同じミスをしないと、心に落とし込むことが出来ます。
叱られたことを恨むなら、その人はそれだけの人です。
経営の本のように、後で2人きりになり本人を叱るとどうなるでしょうか。
時間が経ってから叱られると本人は、何のことで叱られたのか分からないと思います。
その時、その場所で叱るから本人は肝に感じれらるのです。
また叱る方は大概忙しく、「後で叱る」ほど暇ではありません。
先日、若い知人が人前で不用意な言葉を発しました。
その時、私はすぐその場で「そのような言い方はやめた方がいいよ」と注意しました。
それに対して、彼が発した言葉は「このような人前で言わない下さい」と言ったのです。
私は言葉を失いました。
彼はきっとどこかのコンサルタントの書いた「人前で叱ってはいけない」と言うような本を読んだのかもしれません。
メンツにこだわり、恥をかかされたと思う気持ちが先に立っているのでしょう。
その人のために注意したことなのに素直に受け入れられない。
素直な人とそうでない人。
今後は大きく、その違いが現れて来ると思います。
レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
モラトリアム法
先日のNHKの番組「大廃業時代」というのがありました。
会社が廃業する原因として、人手不足、後継者不足があります。
また大きい原因として日本のモラトリアム法と言われた「中小企業円滑法」があります。
2009年、前年に起きたリーマンショックを受けた中小企業を救済するために出来た法律です。
中小企業が金融機関から借りていた借入金を「返済の猶予」や「返済期間」の延長を認めるという、借りる側に優しい法律です。
その法律はすでに終わっていますが、その影響は続いていました。
法律が出来た当初から、私はこれは悪法だと思っていました。
借りたお金が予定通り返せなくなった理由は、上げればいくらでもあります。
でも一番の原因は、安易に借入を決断した未熟な判断力と、計画通りに売上や利益を出せなかったことにあります。
経営者が頑張って会社経営をしても、如何してもダメな時はあります。
その時の見切りが大事です。
早い見切りによって、負債額も少なくて済み、再スタートも切れやすい環境が出来ます。
それが、この中小企業円滑法によって買い入れ額が膨らみ続けました。
助けられたと思ったのが、逆に深いダメージを与えられ、再起不能になったのです。
「小善は大悪に似たり」
この言葉通りで法律でした。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
ZOZO
Yahooがファッション通販サイト「ZOZOTOWN」を運営するZOZOを子会社化したとの報道が流れています。
ZOZOの社長前澤氏も保有株を売り、2000億円以上のお金を手にしたと言われています。
創業した会社を大きくし、それを高い値段で売却する。
アメリカでは昔からあり、日本でも増えてきているようです。
でもその遣り方は社長は莫大なお金を手に出来ますが、一方では社員を捨てる行為です。
「後はよろしく頼む」ということでしょうか。
私は好きではありません。
「全従業員の物心両面の幸福を追求する」という経営理念を掲げている会社があります。
稲盛和夫さんが創業した京セラとKDDI、再建したJALはその経営理念を掲げて、トップと社員一体になって頑張ります。
稲盛さんはこうも言います。
「自分に与えられた能力は、たまたま自分に来ただけのこと」「才能を私物化してはならない」
だから私は稲盛和夫さんに心酔しています
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
老い
昨日、メガネ屋に行ってきました。
遠近用のメガネがのレンズが欠けたので、レンズ交換のためです。
メガネのフレームは25年ほど前に買ったローデンストックのフレーム。
25年経っても歪みもなく、これからも愛用しようと思っています。
レンズを交換するにあたり、まずは目の状態を念入りに検査してくれました。
このメガネ屋さんに前回お世話になったのは4年前。
検査結果は4年前より良くなっているとのこと。
目は左右とも0.8で前回より0.1良くなっています。
乱視も良くなっていました。
白内障の症状もあまりないとのこと。
なかなか嬉しい結果でした。
少し前に耳の検査をしましたが、4・5年前と変わらない結果。
毎日食事に気を遣う「「老いへの抵抗」。
少しは成功しているようです。
小善と大善
日本の将来に対する不安。
第一に財政問題があります。
1000兆円を遙かに超す借金。
それなのに国家予算は毎年のように増えています。
来年度予算は過去最高と言われています。
財源は国債という借金。
優しい政策は国民に喜ばれるが、そのツケは計り知れない辛いものになると予想されています。
国民に辛抱を強いることになります。
まさに
「小善は大悪に似たり」
子供や孫の将来を考えると、「大善は非常に似たり」を覚悟しなければなりません。
財政改革には大変な痛みを伴います。
早くそれに手を付けなければ債務は拡大するばかり。
早くに国民に国の現状を知らしめ、共に苦楽を共にする覚悟をしてもらうことが大切です。
その非情と思われる政策は将来、大善をもたらすことになるのです。
小善は大悪に似たり
大善は非常に似たり
レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
子供向けホテル
先週、東京から来た孫達をつれて「森のソラニワ」という温泉ホテルに行ってきました。
中山峠を越した山の中の北湯沢温泉にあります。
北湯沢温泉にはこのホテルを入れて、3ホテルしかありません。
温泉街はなくその上、店舗は1軒もありません。
山の中のホテルです。
事前に見たホテルの内容紹介では、このホテルは子供が楽しめるための仕掛けが沢山あります。
食事も子供が喜ぶメニーも用意しています。
それは逆に言うと、「大人にとってはどうかな?」という疑問がありました。
ところが大人が満足出来る料理・温泉施設も用意されています。
感想としては満足です。
昔、日本の温泉旅館は会社単位の団体客を受け入れて営業していました。
ところがいつの間にか、その団体客が一気にいなくなり、温泉旅館は苦境に立たされることになりました。
倒産していったところも多くありました。
その後はカップル向けや家族をターゲットに形態を変えて行きました。
しかしそうなると、客室単価は下がってきます。
団体客の時は10畳間に8人位突っ込んだりしたので、客室単価は高いモノでした。
しかしカップルや家族利用は2名から4名位にしかなりません。
どころがこの「森のソラニワ」一室あたりの人数が多いのです。
子供をターゲットにしたこのホテルは、子供や両親の他に爺さんや婆さんも付いてきます。
そうすると6人位にはなります。
私が泊まった部屋は32畳になっていますので、狭く感じません。
これが平均的な広さのようです。
ターゲットを小さい子供に絞り込む。
この戦略は当たったと思います。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
従業員第一主義
今日の日経新聞のネットニュース上に「米主要企業の経営者が所属する経済団体、ビジネス・ラウンドテーブルは19日、『株主第一主義』を見直し、従業員や地域社会などに配慮した事業運営に取り組むと宣言した。」という記事が載っていました。
京セラ創業者の稲盛和夫さんは従来より従業員を大事にするという考え方を持っていました。
稲盛さんが関連する企業、京セラやKDD、JALが掲げている経営理念にもそれが書かれています。
「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること。」
株主第一主義のアメリカの経営者もやっと気付いたのでしょうか。
あんバタサン
先程、柳月に「あんバタサン」を買いに行きました。
しかし既に売れ切れ。
聞くと 毎日販売されると直ぐに売れ切れてしまうとのこと。
予約買いをしないとダメだとの情報があります。
その情報筋から聞くと、柳月では24時間体制で作っても間に合わないとのこと。
このお菓子買い騒動に火を付けたのは、NHKの朝の連続ドラマ「なつそら」です。
そのドラマ中に出てきた帯広の「雪月」が作ったお菓子と似ているそうです。
「柳月」と「雪月」
会社名も似ていますね。
何かのきっかけで突然売れるという現象は良くあります。
カーリング女子が食べていた北見の「赤いサイロ」というお菓子もそうです。
最近では渋野日向子さんが英女子オープンで優勝し、渋野さんが着ていたウェアーがあっと言う間に売れ切れ。
何がきっかけで売れ出すのか分かりません。
ただ言えるのは、それまでに地道にいい物を作ってきたその結果だということです。
「柳月」という会社もそうです。
私が注目してる会社です。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
小さなズル
先日、新千歳空港からJRに乗り、Uシートに座っていました。
Uシートは指定席です。
私達の前のシートが空席になっていましたが、出発直前に若い2連れが座りました。
出発して暫くすると、車掌が検札に来ました。
先程、前のシートに座った2連れのところで車掌が止まりました。
2人は指定券を買っていません。
車掌は2人にその席を立つように言って去りました。
ところが車掌が去った後もその2人は座り続け、再度車掌が来た時になってやっと席を立ちました。
それから暫くするとまた別の若い2人連れが来て座ります。
2駅を過ぎると、車掌が来る前に列車を降りていきました。
この2人も指定券を持っていない様子でした。
偶然にも2組の若いカップルが指定券なしで座った場面に出会いました。
指定券を持たず、気後れもせず、堂々と指定席に座るということは私のような小心者には出来ません。
後ろめたさがあります。
それが普通のように思います。
なのに目の前で2組4人の若者が平気でズルをする。
「不正!」とまでは言いませんが、平気なのが信じられません。
「知られなければ少し位のズルはいいではないか。」「見つかったら謝ればいい。」
そんな気持ちなのでしょう。
悪いことは悪い。悪いことはしない。
親から教えられただろうそんな当たり前のことが出来ない。
淋しい気持ちになりました
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
ユニバーサルデザイン
先週末に利尻島・礼文島への旅行に行ってきました。
千歳空港から利尻空港に出発する時、利尻が濃霧のため状況確認中とい言われました。
添乗員さんから「旅行中止または利尻まで飛び、着陸出来なければ稚内空港に着陸し、その後フェリーで行く可能性がある」と言われました。
でも私の普段の行いがいいせいか、無事に飛び、予定時刻に利尻空港に着きました。
2泊3日の旅は毎食が海鮮料理。
最後の昼食では豪華なウニ丼。
しばらくは刺身も寿司もいりません。
妻とのいい思い出の旅になりました。
この度の中で考えさせられることがありました。
宿泊した礼文島のホテルでのことです。
ホテルのテレビを付けた時、全ての番組みに文字が流れていました。
耳の聞こえない人のための文字放送なのでしょう。
でもその文字が画面の真ん中に出てくるので、肝心なところの画面が隠れてしまいます。
その文字放送を消そうとしたのですが、操作出来ません。
調べてみると、変更操作出来ないように設定されていました。
文字放送は耳の聞こえない人にとっては必要な伝達手段です。
でも健常者にとっては不要です。
ユニバーサルデザインという考えがあります。
健常者も障害者も、年寄りも小さな子供も、全ての人が不自由なく使える形や仕組みを作っていくことです。
社会的弱者である障害者の人達だけに焦点を合わせると違ったモノになってきます。
帰りのフェリーも同じようなことがありました。
乗船すると客席はジュウタン席がほとんどです。
「椅子席はないのですか?」と聞くと、「障害者のの人のためにジュウタン席にしています。」
椅子席希望の人は外の甲板にある椅子を利用して下さいとのこと。
足腰が弱く、床に上手く座れない年寄りにはジュウタン席は辛い。
私達は甲板にある椅子を利用しました。
結果、景色も良く快適でしたが、あの船員さんの説明はやはり引っかかります。
ユニバーサルデザインという考え方はもっと広まってもいいのではないでしょうか。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
遅読
本を読む時「速読」という読書法があります。
以前はこの読書法に憧れ、「速読」に関する本を買って読みました。
その本に書かれているように少し訓練もしました。
でも結果、私にはこの「速読」は出来ませんでした。
そして自分には合わないと思いました。
私はどちらかというと「遅読」が得意です。
自分が気に入った本をじっくり時間を掛け、行間に書かれていることも推測しながら読むのがいいです。
心に残る本は「遅読」で読んだ本ばかりです。
そして今は時々「音読」をしています。
「音読」のいいのは、文字を目で見、声を出すことで耳から内容が入って来ます。
また声を出すことで、自分が語っているような錯覚に陥り、その言葉が自分の言葉のような気持ちになります。
読む速度は確かに遅いですが、確実にその内容が自分のモノになっているように思います。
毎日30分と決めて「音読」をしていますが、なかなかいいですよ。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
プリンターのインク
2年ほど前に買ったインクジェットのプリンターが故障しました。
青い色のシアンのインクが全然出なくなりました。
プリントヘッド清掃を何度しても一向に良くなりません。
仕事に支障も起きるので、一層のこと買い換えようと思い、ネットでプリンターを探そうとしました。
その時なにげなく、「プリンターのインクが出ない」と言うフレーズでクリックすると、プリントヘッド清掃用のインクカセットがあるという情報が出てきました。
カセットで4色で2300円位。
ダメ元だと思い、プリンターを買うのをやめてそれをネット注文。
今日それが届きましたので早速試してみました。
その結果!
驚くことに、すっかり復活しました。
びっくりです。
教訓
インクヘッドのチェックと清掃は頻繁にすること!
商品
今、テレビのワイドショーで流れている吉本興業の問題。
もうそろそろ辟易した気分になってきました。
元々は、芸人の反社会集団との営業問題が発端でした。
その騒動の中から吉本興業の旧態とした経営体質が表に出てきたのです。
私はこの騒動の中で考えさせられるのは経営者の考え方なり行動です。
会社にとって一番大事なのは商品です。
消費者に素晴らしい商品を選び、育てて売っていくのが商売であり経営です。
騒動をテレビでみる限りで言えるのは、吉本興業は商品である所属タレントに対する対応なり態度です。
商品を大事にしているとはとても思えません。
芸能界というのは特殊な世界かもしれませんが経営者のあるべき姿はどこでも同じです。
芸能界は特殊な世界だから許され事ではないと思います。
レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
風邪
何年振りかで風邪を引いてしまいました。
ここ最近は寒暖の差が激しく、対応出来なかったようです。
風邪を引かなくなるというヨーグルトの○○を毎日飲んでいたのですがダメでした。
最初は喉が少しいがらっぽく、その時食べたサクランボのアレルギーかな?と思ったのですが、その後咳が出るようになり、喉が痛くなりました。
その時に初めて「風邪を引いた!」と認識しました
熱はあまり高くないのですが、夜の咳が酷く、ここ4日間眠れません。
ここでまた勉強しました。
自分は歳をとっているという認識をしなければなりません。
若い頃と同じつもりになり、薄着のままでいたこと。
早めに風邪薬を飲むなど自分のケアを自分でしなければならない。
今、思うことは、妻に風邪がうつらなければいいな。
レンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」
発注書
今朝、○○豆腐店さん宛の発注のFAXが流れてきました。
2ヶ月ほど前から何回か流れてきています。
この○○豆腐店さんは有名豆腐店さんで、10年ほど前には私共のレンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」に入居されていましたが、8・9年ほど前には出て行かれています。
発注会社は何を見て発注のFAXを流しているのでしょうか。
何回もFAX続くので、先程FAXに書かれている発注会社に電話をしました。
担当者がいなかったので、電話に出た人に「○○豆腐さんは8.9年ほど前に退出されています。何度も発注FAXが流れてきましたので電話しました。発注大丈夫でしたか?」と聞くと相手は驚き、「大変なことです」と言っていました。
それにしても担当者は何を見て発注したのでしょうか。
そして、今まで発注した品物が入ってこなかったことに疑問を持たなかったのでしょうか。
この点が気になりましたが、そのまま電話を切りました。
担当者も悪いけど、それを管理する人もまずい。
この会社は結構大きな会社のようですが、大丈夫なのか。
少し心配になりました
レンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」
リブラ
2020年にfacebookが発行を目指すデジタル通貨「リブラ」。
世界の中央銀行がこの「リブラ」に警戒しています
facebook利用者である世界の23億人がその利用対象となり、世界の通貨制度を揺るがす恐れがあります
私が「リブラ」発行の話を聞いた時に思ったのは、近い将来この「リブラ」がドルに変わる基軸通貨となるという可能性です。
過去にはドルに代わる基軸通貨の話は出てきましが、未だ生まれていませんでした。
しかしその一番の候補と言えるのが「リブラ」だと思っています。
新しい基軸通貨発行が望まれるその背景には、アメリカが中心となる世界経済に対して抗する国々があります。
また、最近はアメリカが他国との経済摩擦も気にせず、自国第一主義を掲げている事もあります。
そしてアメリカは必要だと思う時には必要なだけドル紙幣を刷り続けることの出来ることもおかしな話です。
対アメリカに対する不信感が世界中に広まれば、新基軸通貨としてデジタル通貨。
特にこの「リブラ」がその候補として上がってくることも十分可能と思います。
これからは現金からキャッシュレスの時代になることでしょう。
尚のこと、デジタル通貨としての「リブラ」が注目されていきそうです。
レンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」
本
稲盛和夫さんが書いた「心」という新しい本を買い、読んでいます。
書かれている内容は、過去に稲盛さんがお話したり書いてきたことがほとんどです。
でも改めてこの本を読むと心にしみます。
毎朝、この本を声を出して読んでます。
声を出しながら読むことで、目と耳から内容が染み込んでくるようです。
最近、本屋で稲盛さんの書いた本だと思って手にしてみると、別の人や団体がまとめたものが多いように思います。
稲盛さんは87歳。盛和塾も今年いっぱいで解散します。
稲盛さんが書く本は今後少なくなっていくと考えます。
「心」という本、大切に読みたいと思っています。
レンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」
免許返上
3年ほど前から70歳になったら運転免許を返上しようと考えていました。
今年の8月で満70歳になります。
また翌月の9月は丁度、運転免許書の切り替えの時です
7月になったら返上手続きをしようと思っています。
最近は高齢者の交通事故がメディアに取り上げられています。
高齢者の交通事故は今に始まったことではないのでしょうが、クローズアップされています。
3年前に70歳になったら返上しようと「決めた」のは、決めなかったらいつまでも返上出来ないと考えたからです。
「決めて」良かったと思います。
「70歳になったら返上する」と自分で周りの人にも公言していました。
そして自分で「決めた」ことを守る。
それだから出来るのだと思います。
運転はまだ大丈夫だと思えば、まだ大丈夫です。
でも、それがズルズル返上時期を引き延ばせば、大変な事を起こすかもしれません。
自分で決める。
これが大事です。
レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
我が家の朝食
約1年ほど前から、我が家の朝食は私が作っています。
妻があらかじめ作り置きし冷凍しておいた野菜スープを鍋に入れます。
それに自家製の梅干しを刻んで入れ、刻み昆布、干した小エビやシジミを入れます。
少し煮立ってきたところに入れるのが一膳分の玄米。
3分位煮込んでから火を止め10分位冷まします。
冷ましている間に玄米に味がしみ込みます。
その後また鍋を火にかけ、溶き卵を2個分入れ出来上がり。
この玄米粥を妻と仲良く半分にして食べます。
ほとんど毎日このような朝食になります。
以前はご飯に味噌汁、おかずは納豆や卵や魚。
この朝食では私には少し重たかったようで、午前中頭の動きが今ひとつ。
玄米粥にしてからは胃も楽になり、朝から頭の回転が良くなったように思います。
ただ月曜日から金曜日まで同じメニューなので少し飽きます。
土・日曜日は妻がパンとサラダとコーヒーの朝食を作ってくれます。
玄米粥は作るのも早くて簡単。
一度、試されたらいかがですか?
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
日銀の保有株式
先程ネットで確認すると、日経平均が下がり続け、現在は20,394円となっています。
その日本の株の最大の株主は日銀です。
日銀の雨宮副総裁は今年の3月14日の国会で、日経平均が18,000円を割り込むと、日銀保有の株式が評価損を起こすと言いました
あと2,000円程度です。
実際に18,000円を割り込まなくても、その数字に近くなった時、日本の「円」に対する信用が急落する恐れがあります。
安全資産と言われる「円」の評価が激変する。
その時、大変なことが起きる。
そんな恐れを抱きます
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」http://www.yamachi-office.com/sop
弁当のご飯
先日妻が旅行に行っている間、暫く1人暮らしをしている時、お昼にイオンの弁当を買いました。
驚き!
ご飯がまずい!
まずいと言うより固くてなって噛みにくい。
まるで干飯のような固いところがあるのです。
私はどんな料理を食べてもまずいと思うことはほとんどありません。
勿論、妻が作った料理はいつも美味しい美味しいと言って食べます。
決してグルメではないのです。
何でも美味しいと思えることは幸せだと思っています。
その私がまずいというのは余程です。
お米が違うのか。
イオンの弁当代は500円以下がほとんど。
価格が安いからそうなのか?
もう少し値段は高くてもいいから普通のお米を使って欲しい。
そう言えば、イオンの中にある焼き鳥を売っている店の弁当も米がまずかった!
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
札幌オフィスプレイスについて②
札幌オフィスプレイスに付属する部屋があります。
そこは会議室、面談室があり、オフィスプレイスの入居者が無料で使用出来ます
会議室は20名まで座れます。
レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
札幌オフィスプレイスについて①
5月1日より札幌オフィスプレイスは少し狭くなりました。
その代わり、札幌オフィスプレイスに入居されている人達がお仕事状必要になる会議室や個室を用意しました。
これからしばらくの間その内容をお知らせしていきます。
レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
けなす人
先日気付いたことがあります。
他の人や会社の遣り方を批判する人、けなす人。
多いように思います。
そのような人は自分の方が優れているということを言いたいのかもしれません。
そのような人には、学ぼうという姿勢が見られません。
人の話を聞こうともしません。
勿論、素直さもありません。
頭が優秀で自信がある人に多く見られます。
そして、その人が社長だと会社経営は致命的です。
私は何も言えず黙って聞くしかありません。
残念です。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
人に優しい車社会
今朝の日経の「春秋」に書かれていたことです。
日本の交通事故の特徴は「車が人をはねる」である。
欧米では死者の多くが車同士によるものであると書かれていました。
日本では人より「車優先」の考え方がそこに存在しているのではないでしょうか
昨年、娘家族が住むスエーデンに行った時のこと。
街を歩き、道路を横断しようとすると、横断歩道でなくても車が止まってくれます。
私が躊躇していると、「車のことは気にしないで渡っていいの」と言います。
スエーデンでは人が横断しようとする時、車が止まってくれるのが当たり前なのだそうです。
日本の交通事情とは大違いです。
日本の自動車業界は、車が人にぶつかりそうになった時、自動的に車が止まってくれる。
そんな車を考えています。
自動的に止まる車を考えるより先に、人優先の車社会を作る方が先です。
「人に優しい車社会」
そんな標語があったように思います。
本当にそうあって欲しいと思います。
レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
新紙幣の発表
昨日、麻生財務大臣より新紙幣の発表がありました。
5年後の2024年に発行とのことです。
この「5年後」というのに少し疑問を感じました。
過去の新紙幣の発表から発行までの期間を調べてみると、前回は2年3ヶ月、前々回は3年4ヶ月です。
それが5年というのは少し長すぎます。
ある政治評論家が「政府が新元号と新紙幣発行を一緒に発表して、人気を取りたかったのでしょう」という評論は楽観的で、まったく違うと思います。
そんな単純なものでないと思います。
経済評論家であり参院議員の藤巻健史氏のfacebookでの発言が気になります。
藤巻氏はこのように書いています。
「すぐに市場に流通させるのなら慶事関係と思うが、流通させるのが数年先ならば気持ち悪い。
ハイパーインフレや紙幣価値が暴落したとき、昭和21年には預金封鎖&新券発行があった。新紙幣の発行が間に合わずに当初は旧紙幣にシールを張ったという。
新券準備を秘密裏に行うのは難しい。これなら堂々と準備できる。
政府・日銀は異次元緩和に出口がないことがもう十分すぎるほどわかっているので、準備を開始したのか、と私は思ってしまった。
私は昭和21年のような預金封鎖ではなく、ドイツ型処理(かっての中央銀行ライヒスバンクをつぶして新中央銀行ブンデスバンクを設立し新紙幣を発行)を予想していたのだがーー。」
藤巻氏が書いているように、昭和21年に日本で起きたハイパーインフレの時、次のことが起きました。
「現金保有を制限させるため、発表翌日の17日より預金封鎖し、従来の紙幣(旧円)は強制的に銀行へ預金させる一方で、1946年3月3日付けで旧円の市場流通の差し止め、一世帯月の引き出し額を500円以内に制限させる等の金融制限策を実施した。(Wikipedia)」
現在、日本のタンス預金が50兆円あると言われています。
それを吐き出させるために今まで政府や日銀はあらゆる経済政策をしてきました。
それでもタンス預金は市中に出てこない。
1100兆円を超す日本の借金が近い将来、大きな問題を起こした時の備え。
今回の新紙幣発行の準備はそんなことを予感させます。
レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
妻の話
今日は1日。
毎月の行事として今月も神宮参拝をしました。
その帰りの時に聞いた妻の話を紹介します
私と結婚した頃、妻は私の父から手紙をもらったそうです。(この事は初めて知りました)
その中に書かれていたこと。
人に言われたことは、自分で手を胸に当てて考えてみるように。
自分が悪いと思えば直せばいい。
考えても悪いと思うことがなければ、言った人を馬鹿だと思えばいい。
気にするなと言うことでしょう。
私の父親がそんな優しいこと言ったの?
でも納得します。
この言葉は今でも妻の心にあるそうです。
もう1つ妻から聞いた話です。
人が神様の前で悪いことをしたり、無礼なことをするとバチが当たると言われます。
私も小さい頃、親からそう言われました。
でも違うようです。
神様はバチは与えません。
バチは与えませんが、その人がいざという時、無視するそうです。
ここ一番という時に神頼みしてもダメなのです。
バチが当たるより、こちらの方が辛いことですね。
神宮参拝の帰りに聞いた妻の話。
妙に納得しました。
消費税
今年の10月から消費税率が上がり、10%になりそうです。
日本はこれから少子高齢化の現象が進み、福祉関連費が益々増えることでしょう
その為の消費税アップと言われます。
日本は今回上がっても10%ですが、福祉大国といわれるフィンランドやスエーデンの消費税は25%です。
25%は高いですが不満を言う国民は少ないようです
それは老後の心配がないからと言われています。
以前にフィンランドとスエーデンを訪問して障害者や老人の福祉施設を回った時、その施設・設備とシステムの充実振りに驚かさせました。
フィンランドの男性と結婚した日本の女性が驚いていました。
フィンランドでは子供は親の老後の面倒を看るという考えがないと言うのです。
国が年老いた親達の面倒を手厚く看てくれるので、子供達が介護する事がないのです。
日本のように、親の介護のために会社を辞め、人付き合いもやめ、孤独の中、費用的にも精神的にも辛い思いをすることがないのです。
私の子供達もそろそろ親の私達の心配をしているかもしれません。
子供達に私達の介護などで迷惑を掛けたくない。
親なら皆思うことでしょう。
高い消費税の見合う国民生活の幸福。
これが見えれば25%の高い消費税も納得します。
老後の心配がなければ、現役世代は老後のために無駄にお金を貯めず、生活を楽しめます。
ただ、フィンランドにしてもスエーデンにしても税金を使った福祉サービスに対する監視体制はしっかりしています。
ある介護施設では、約10の機関が監査に入ってくるそうです。
国関連、市関連、福祉団体関連、民間団体関連等が入って来て、施設側は対応が大変だと言っていました。
無駄に税金は使われていないか。
適切な介護は受けているか。
介護を受ける人達やその家族達からも聞き取りをするそうです。
税金を徴収されても、日本人が不満に思っていることの1つに、「適正に税金が使われているか」という疑問です。
ここが今後消費税を上げて行く時のポイントになると思います。
レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
夢と希望の持てる言葉
毎週日曜日5時30分からのテレビ番組「笑点」はよく見ています。
特に大喜利は面白いですね。
ただ時々円楽さんが語る政治風刺。
政治家が悪いことをしたことを面白く話します。
少し気になります。
また、「相棒」というドラマも好きですが、そこにも警察官僚を悪い階級のように描かれる場面が出てきます
テレビの影響は大きいです。
特に子供達の心に深く刻まれます。
私は中学生・高校生の時、先生達が折に触れて金持の批判をしていました
その為、「金持ちは悪いことをして金儲けをしている」という印象が子供心に残りました。
ある時、父に向かって「金儲けは悪い」ようなことを言って父を怒らせたことがあります。
父は真面目に一生懸命頑張って事業を発展させていました。
勿論、結果お金も入ってきました。
決して悪いことをして稼いだのではありません。
同じように真面目に政治をしている人もいます。
官僚となり頑張って国を支えている人もいます。
そうでなければ日本という国はとうの昔に崩壊しています。
そのことは子供達には分かりません。
テレビで見たり聞いたりしたことが本当のことのように思ってしまいます。
これは怖いことです。
将来の仕事として、政治家や官僚、経営者になろうという気持ちが生まれません。
私達はもうそろそろ、自虐的な言葉をやめ、希望の持てる言葉を発していかなければなりません。
マスコミも一部の悪い人だけを指摘して、その分野の全てを語るような論調も考えるべきです。
夢と希望の持てる言葉を発する。
それが大人の責任であり、務めだと考えます。
弱者のズルさ
この世の中には多くの強者と弱者がいます。
強者も時には弱者になり、弱者が強者になることもあります。
強者と弱者とは。
健常者と障害者、大人と子供、男と女、社長と社員、先生と生徒などいろいろあります。
世論は概して弱者に有利な論調になりがちです。
先日テレビで生徒を殴る先生の姿が流れました。
暴力先生としてマスコミから叩かれています
しかし、考えてみると誰かが事前に準備して、その殴る様子をスマホで撮影していたのです。
なぜそんなことが出来たのか。
疑問に思います。
生徒達に仕組まれた悪質な行為だったのかもしれません。
しかし一般的に強者の先生の横暴として捉えられがちです。
そこには弱者のズルさがあります。
車と自転車という関係もあります。
今朝、雪道の車道を自転車が走っていました。
自転車は冬用タイヤをはいてはいますから決して違反行為ではありません。
しかし狭く滑る雪道で運転するドライバーにとっては、自転車にぶつけないように注意深く運転しなければなりません。
ぶつければ強者の車の責任が大になります。
弱者と言われる自転車も注意して自転車に乗っているのでしょうが、「ぶつけるお前の方が悪い」というように大胆に自転車に乗っています。
「ドライバーの注意深い運転によって自分は守られている」ということを自転車側は認識するべきでないでしょうか。
弱者が弱者の立場を逆手にしたような行為をよく見かけます。
でも指摘されない。
違和感を感じます。
怖い父親
私の子供が小さい頃、私は怖いお父さんでした。
俗に言うカミナリ親父でした。
子供を叩いたりはしませんが、約束が守れないとか挨拶が出来ない時はしっかり怒りました。
先日妻が話してくれたことがあります。
子供達が学生の時、色々アルバイトをしました
その時に仕事を通して世の中のことを知ったようです。
その中でも面白いのは「お父さんはとてもやかましかったけれど、世の中にはもっとすごい人がいる」と言っていたそうです。
今は5人の子供達は皆、社会人として生活しています。
ハードな仕事や厄介な上司。
それに耐えているようですが、私に鍛えられたのが良かったのでしょうか。
そんな話を妻から聞いて私は少し「ニンマリ」しています。
グルメとグルマン
人は食べることが大好きです。
テレビでもグルメ番組が多くあるのもその為でしょう
「あの人はグルメだね」という言葉が出てきます。
一方、あまり言葉として出てきませんが「グルマン」という言葉もあります。
その違いは「グルメ」は美食家であり、グルマンは食道楽と分けられます。
料理を食べてみて、素材やその作り方の違いが分かる人がグルメ
グルマンは美味しい料理を探して食事を楽しむ人です。
料理を仕事としている人はグルメでなければならないでしょう。
厳選された素材の味とその違いが分かり調理にもこだわりがあります。
ワインなどのお酒に関しても微妙な違いが分かります。
しかし私達のように食事を楽しみたい人には「グルメ」は必要ありません。
食事を楽しむ食道楽として「グルマン」でいいのです。
時に顔をしかめながら食事をしている人を見ます。
どの産の肉を使い、油は何を使い、添え物の野菜は有機なのか?
出汁はどこ産の昆布を使っているのか?
そんなことを考えて食べても美味しくありません。
そこそこ美味しければ「美味しいね。美味しいね!」と話しながら食べる方がいいに決まっています。
浅草で有名な天丼屋で食べる天丼も旨いけれど、「てんや」で食べる500円の天丼も美味しい。
1人1万円の寿司屋の寿司も旨いけれど、回転寿司「トリトン」の寿司も美味しい。
食べることの喜び。
それを感じられる今に幸せを感じます。
執着心
中村元氏の書いた「ブッタのことば」から。
悪魔パーピマンがいった。
子あるものは子について喜び、また牛のあるものは牛について喜ぶ
人間の執着するもとのものは喜びである。
執着するもののない人は実に喜ぶことがない。
師は答えた。
子のあるものは子について憂い、また牛のあるものは牛について憂う。
実に人間の憂いは執着するもとのものである。
執着するもとのもののない人は憂うことがない。
私達は色々な欲望にさいなまれています。
知らなければ起きない欲望も,知ってしまったから起きます。
その執着心に打ち勝つことが、正しく生きること。
そのように思います。
独立心を育てる
以前ある集まりがあり,その中で「独立心を作るために何が必要か」ということが話し合われました。
家庭なのか,学校なのか,会社なのか,社会なのか。
色々な意見が出ました。
子供の独立心を育てるのは家庭で育てるしかないと私は思っています。
しかし現実は子育てを放棄して、子供と仲良い関係だけを作っていく親を多く見受けます。
優しい関係は一見いいように見えますが、それだけでは子供は自立しないし独立心は生まれません。
躾や善悪の考え方などを厳しく教え,時には突き放すことをしなければ、社会人として子供は育ちません。
あたかも姉妹のように、兄弟のように見られることを願っている親がいます。
子供とのもめ事を避ける親がいます。
親がするべき教育を放棄して、学校教育に求めます。
学校は勉学を学ぶところで,家庭教育の代わりは出来ません。
満足に精神的な自立が出来ないまま,学校の成績がいいということで会社に入ります。
結局、会社で人格教育をしなければ使い物にならない。
改めて言いますが,子供の教育は家庭で行われることであり、親の責任です。
子供は「授かり者」ではなく、「預かり者」と考えることが大切です。
生まれた子供は可愛い。
ついペットのように可愛がります。
しかし、いつかは親元から離れ、世の中に出て自立していくことを考えると、それまでの「預かり者」と考えるべきでしょう。
「かぐや姫」という物語はそれを表していると言われます。
レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」
ブラック企業
「パワハラ」とか「ブラック」とかの言葉を毎日のように見聞きします。
実際に「パワハラ」「ブラック」と言われる会社はあると思います。
勿論、そうでない会社も多くあります。
ある人がテレビの「下町ロケット」の佃製作所はブラック企業だと言います。
確かに何日も徹夜をして仕事をしている姿を見るとそう言う人もいるでしょう。
しかし、経営者と社員が価値観を共有している会社はブラック問題は起きにくいものです。
なぜなら彼らはそれぞれが同じ目的や目標を目指し,その思いを共有しているからです。
その思いに共有できない人は会社から離れていくでしょう。
無理に共有させるとブラックという意識が生まれます。
思いを共有出来ない人にとっては同じ会社がブラック企業に映るのです。
また、本当にブラックな企業もあります。
その会社に共通しているのは社員を大事にしていません。
社員を愛していないから起きます。
社員の幸せを心底から願っていれば「ブラック」というのは出てこない言葉です。
3カ国旅行
先週の6日土曜日に日本を発ち、昨夜帰ってきました。
スエーデンのヨーテボリに住む娘家族のところに行ってきました。
私達夫婦と私の妹家族、合わせて6名での旅行。
まずはフィンランドのヘルシンキまでJALで飛びそこで1泊
その後は船や高速列車に乗り継いでヨーテボリへ。
その気になればヘルシンキから直接飛行機で行けるのですが、折角なので船や高速列車を使いました。
ヨーテボリでは娘や孫達と会い、近くのホテルで2泊。
その後は娘達家族も連れてデンマークのコペンハーゲンへ。
ここでも孫達と遊びました。
帰りはパリ経由で24時間以上掛けて帰宅。
長い旅行でした。
私は13年ほど前にもフィンランドとスエーデンに行きました。
その時は福祉財団のツアーに参加しましたので、添乗員さんがいて、移動は専用バス。
点から点を結ぶような旅でした。
今回は全て自分たちが航空券や船、列車、ホテルの予約をしたので、自由に街歩きが出来ました。
街中の移動には地下鉄やトラムという市電を利用しました。
今回3カ国を回って驚いたことを何点か紹介します。
1つ目。
鉄道や地下鉄、トラムに乗る時、改札口がありません。
乗車券を券売機で買って乗るだけです。
駅に着いてもプラットホームからそのまま町中へ行けます。
無賃乗車もあるのでしょうが、時々巡回している検査員に見つかると、高額の罰金を払わなければなりません。
2つ目。これらの国のトイレはほとんどが男女共用です。
男性用、女性用の区別がありません。
日本人にとっては違和感がありますが、これも男女平等の姿なのかもしれません。
ヘルシンキもストックホルムもコペンハーゲンも歩道は石畳。
それも15センチ角の石でスキ間が1センチ以上も空いているので旅行カバンの車輪が挟まります。
乳母車も大変です。
その為か車椅子の人はほとんど見かけませんでした。
日本なら「バリアフリーにするべきだ」と皆が言い出し、すぐ全てをアスファルトにしてしまうでしょう。
フィンランドもスエーデンも2つの国とも福祉の国です。
トラムやバスには乳母車や車椅子用のスペースがあります。
その国が石畳にこだわる。
何か大事な理由があるのかもしれません。
両国とも道端に物乞いがいます。
諸費税が25%なので福祉が行き届いているはずです。
貧しい人への配慮も深いはずです。
ヨーテボリに住む娘婿に、「福祉の国なのに物乞いがなぜいるか」と聞いても分かりません。
物乞いはアラブ系の人が多いようです。
最後にもう1つ。
フィンランドの通貨はユーロー。スエーデンはスエーデンクローネ。デンマークはデンマーククローネ。
それぞれ通貨は違いましたが、3カ国ともキャッシュレスがほとんどで現金は使いませんでした。
なので両替の必要がありませんでした。
屋台でも「Card Only」と表示されています。
何の苦労なく、スーパーや屋台で買い物がカードで出来、キャッシュレスの便利さを実感しました。
ただ家に帰ってきて財布の中を見るとレシートが沢山。
次回の決済日に通帳からいくら落ちるか。
その金額が気になるところです。
コーチング
大坂なおみさんがテニスの全米オープンで優勝しました。
メンタルで弱かった彼女を変えたのはドイツ人のサーシャ・バインコーチと言われています。
「できるだけ楽しく、ポジティブな雰囲気を作ろうと思っている」と語っています。
パッピーでポジティブな言葉で彼女を変えました。
以前に日本と欧米のコーチとの違いを本で読んだことがあります。
欧米のコーチは選手の優れたところを見付け、褒めて褒めてその才能を伸ばします。
日本のコーチは欠点を見付け出し、それを克服するために厳しく指導します。
いざ本番の時にその力を出し切れたのは欧米の選手です。
日本のスポーツ界ではパワハラ問題がテレビ等で取り上げられています。
今回の大坂選手が出した素晴らしい結果は、コーチングとは何かを改めて浮き彫りにしたように思います。
コダックと富士フイルム
盆休みに面白い本を読みました。
そして気付かされたことが多くありました。
以前から「なぜ?」と思っていたことがあります。
かってカメラフィルムメーカーとして世界トップの座にあったコダックと日本の富士フィルムのその後です。
同じフィルム会社であるのに一方は衰退し、一方は生き延び業績を伸ばしていました。
その違いは何か?
富士フイルムは多角化を図ったが、コダックはそれが出来なかったという見方があります。
しかし実際はコダックは80年代に医薬品事業、医療機器事業、複写機事業の分野と多角化していきました。
それが90年代になってコダックは多角化した事業を相次いで売却していったのです。
なぜか?
それは株主の要求に応じた結果でした。
90年代のアメリカでは、主要企業の株の半分以上を機関投資家である年金基金がコントロールするようになっていたのです。
投資家が経営に口を出すようになった結果、コダックは衰退していったのです。
一方、富士フイルムはデジタルカメラの他に医薬品、医療機器、化粧品や健康食品も手がけて業績を伸ばしています。
紹介したこの本は「経済の不都合な話」という新書です。
富士ゼロックスとアメリカのゼロックス本体の関係について。
富士ゼロックスがアメリカのゼロックスの株を買って一体化しようとしましたが、ゼロックス側の大株主からの反対で頓挫しそうです。
また、東芝は会社再建のために、半導体等の優良事業を売却して生き残りを図っています。
2つとも、なんとなくコダックと似たような構造です。
企業経営の継続を図る経営者と短期利益を求める投資家の攻防。
日本の企業にもその波が来ているのでしょうか。
レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス
夏は終わりました
我が家の夏はもう終わりました。
長女家族が7月11日から10日間帰ってきて、それから1週間後、イギリスから3女家族が1ヶ月間ほど滞在していました。
その間には長男家族・2女家族が集合。
先日の土曜日に、最後まで残っていた3女家族もイギリスに戻っていきました。
この1ヶ月半間ほどの間は、我が家は子供や孫中心の生活。
今やっと普段の生活が戻ってきました。
子供や孫が来てくれるのは嬉しいですが、帰ってホッとしているのも事実です。
「孫は来てよし帰ってよし」の言葉そのままです。
今は長い間出来なかった家の中のモノを整理し、掃除をしています。
庭に広げたビニールプールや椅子も片付けします。
空気もいつの間にか変わり、今朝は涼しい風が吹いています。
「今年の夏は終わったな~」というのが実感。
あっという間の夏でした。
先日の台風が去るとともに我が家の夏も終わりました。
これから夫婦で実りある秋を迎えます。
2人で美味しいモノ食べに出かけます。
これからの人生
先日、若い経営者と話していた時、「早く仕事を離れて好きなことをしたい」と言っているのを聞いて少し驚きました。
私の学生時代、大橋巨泉さんがテレビをセミリタイアしたいと言って実行しました。
しかし、大橋さんは実際は自分のお店をカナダなどで経営し、テレビ以外の仕事をしていました。
資産や収入はしっかり確保していたのです
私達はどうでしょうか。
昨日、知人と話したことですが、会社を60歳定年で退職して、90歳まで生きたとすると、その間30年あります。
今の日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳ですから、90歳寿命もあり得ます。
1年に300万円使うと、30年間で9000万円になります。
年間300万円の生活はそれほど豊かな生活ではありません。
それでも30年間で9000万円が必要になります。
年金も合わせてですが、皆さんはそれほどの財産資産をお持ちでしょうか?
簡単に仕事をリタイアして、好きなことをして残りの人生を過ごしたいと言っても無理なのではないでしょうか?
これから日本の財政を考えると、年金が減らされることも予想されます。
如何に長く元気に仕事が出来るか!
それによって、「いい人生だった」と言うことになると思います。
子を育てる
今朝のテレビで、夏休み明け時の子供の不登校対策が報道されていました。
子供が学校に行きたくないという理由は色々あるでしょう。
行きたくなければ、行かなくてもいいと私は思っています。
無理に行かせると精神的に追い詰めることになります
また別の番組ですが、学校に行きたくても、経済的事情で行けない国の子供達のことが流されていました。
この両方の子供を比較し、良い悪いと言うつもりはありません。
事情や環境が違います。
ただ、学校に行きたいと「思う」か「思わない」か。
そこに何があるのか。
別の次元で考えてみます。
私が中学生時代。
クラスに経済的に恵まれない家庭の子供がいました。
朝、新聞配達のアルバイトをしていました。
彼らが働いて得たお金は家計の助けになります。
もらった給料をお母さんに渡すとお母さんは喜んでくれます。
お母さんから感謝されるので、彼は働く喜びを得ます。
一方、裕福な家庭では、家の仕事をすればお小遣いがもらえると頑張る子供もいました。
親から家の仕事をしなさいと言われてもしない。
仕方が無く、親は交換条件としてお小遣いを上げると言います。
嫌な仕事でも、すればお金がもらえることを子供は学びます。
その後その子供達はどう違っているか。
これは私の想像も入っています。
経済的に恵まれない家の子供は新聞配達の仕事をすることで母親が喜ぶことを知っています。
仕事をする喜びを知りました。
一方、裕福なところの子供は嫌な仕事でも頑張ればお金をもらえることを知っています。
その為、もらえるお金相当の仕事はします。
しかし彼えらにはそれ以上は仕事をする意味を持ちません。
仕事に対して割り切ります。
これも、どちらが良い悪いと言うことではありません
しかし、どちらが満足ある人生が過ごせるしょうか。
私はそれが大事だと思っています。
働く喜びを感じることが出来ることは幸せなことだと思っています。
先に書いた、学校に行く行かないも、学校に行くことに喜びを見出すことが出来れば喜んで行くことでしょう。
私は幸せなことに、「学校に行きたくない」と思ったことは1度もありませんでした。
毎日が愉しかったように思います。
家の仕事をしても親は決してお小遣いはくれませんでした。
それが今は良かったように思います。
社会人になってからも、お金につられて仕事をした覚えはありません。
親として、子供を育てると言うことは大変なことです。
それを私も十分経験してきました。
若いお父さんお母さん、頑張って下さい!
勉強は誰のために
会社を良くするために社長は色々考えます。
時にはコンサルタントを入れ指導を受けることもあります。
それでも会社が良くならない。変わらない。
良くならない第一の要因は社長にあることがほとんどです。
社長の考えが変わらないのに社員が変わり、会社が変わるはずはないのです。
極論を言えば、社長を替えれば会社が良くなることもあります。
しかし社長としてはそれを認めることが出来ないでしょう。
一生懸命勉強する社長は多くいます。
それは会社を良くするのがその目的です。
社員教育するための情報・知識を得ようとするのです。
しかし本当の勉強は、社長である自分が変わるための勉強であるべきです。
そこのところが分かっていない。
自分は変わらないで、社員達を変えようとする。
自分は出来ていないのに社員に強要しようとする。
「誰に負けない努力をしよう!」「燃える闘魂!」「お客様が第一!」「感謝の気持ちを持とう!」「利己でなく利他の心を大切に!」
「お客様第一!」
そのようなことは社長がまず第一に実行しなければ、社員はそれを実行しようとしません。
どのようにするのか社長が手本を見せねばなりません。
それをしなければ社員も会社も変わるはずはありません。
勉強は誰のための勉強なのか。
そこのところをよく考える必要があります。
勘違いして、勉強で得た知識をすぐ社員に使いたがる社長がいます。
全く逆です。
そこのところ分からないと社員教育が無駄になってしまう。
社長は分かっているはずなのに実行している社長が少ない。
「優れた社長」と「そうでない社長」との違いはここにあります。
数字
来月の金曜日に予定を入れようとしたらその日は13日。
13日の金曜日です。
昔に「13日の金曜日」というアメリカの恐怖映画があり、13日は縁起の悪い日と言われています。
日本では4は死、9は苦の言葉に結びつき、縁起が悪い数字と言われます。
昔、厄歳の人は厄落としのために、人の見ていないところでひっそりと櫛(くし)を道端に落とすといいと言われました。
苦と死を落とすためです。
ですから、間違っても道ばたに落ちている櫛を拾ってはいけないのです。
拾った人に苦と死が付くそうです。
以前、私がホテルを開業する時に、客室の番号には4と9の数字は使わないようにしました。
階数を表す数字の部分は仕方がありませんが、それ以外は避けました。
201,202,203,205、206,207,208,210のように。
ホテルが開業してしばらく経った頃、宿泊されたあるお客様からクレームが入りました。
「13を使った客室があるのは非常識だ」と言うのです。
そのお客様の部屋番号は213のように13を使っていました。
お客様はキリスト教の信者だったのかもしれません。
その時ばかりは何も弁解出来ず、謝るしかありませんでした。
中国では7,ネパールでは3と8が縁起悪い数字だそうです。
多くの外国人が来日されている今の日本。
客室番号にここまで気を使うことは必要ないでしょう。
そう言えば、日本の縁起の悪い4と9を足すと13になります。
関連あるのでしょうか?!
ある彫刻家
週末に阿寒湖に行って来ました。
中学生時代の修学旅行と学生時代の冬の一人旅。
それから50年ほど経っています。
阿寒湖畔にあるアイヌコタンには土産店が並んでいます。
折角阿寒に来たので、記念になるモノを買おうと1つの店に入りました
店頭で若者がセッセと彫り物をしています。
彫り物をしている彼のそばに制作途中の大きな木彫刻がありました。
私が宿泊しているホテルに展示されている木彫刻と良く似ています。
その若者に「あなたが彫っているのですか?」と聞くと、「父の作品です。父は昨年亡くなりました」とのこと。
そのお父さんの名前は滝口政満さんといいます。
滝口さんの最後の作品になる彫刻でした。
滝口政満さんの作品は宿泊ホテル内のロビーに数多く展示されています。
私はその作品の素晴らしさに引き付けられこともあり、偶然の息子さんとの出会いに驚きました。
若者は小さな作品を彫っていますが、お父さんの様な道には進まないと言うことです。
札幌市内駅前通にある時計台ラーメンの店頭に、雪除け頭巾をかぶった女性の木彫が飾られています。
これも滝口さんの作品で、時計台ラーメンの社長に依頼されたとのこと。
帰りがけに娘のために可愛い花の木彫の耳飾りを買いました。
才能を私物化しない
先日、盛和塾の世界大会の案内をもらい早速申し込みしました。
今年で26回になります。
思い返すと、稲盛和夫さんという経営者の存在を知り、盛和塾に入塾してもう15年ほどになります。
稲盛さんを常に心の「師」と思い、その言葉と行動に影響を受けてきました。
稲盛さんの多くの言葉の中で最近反復する言葉があります
「才能を私物化しない」
稲盛さんは著書「成功への情熱」の中で次のように書いています。
「リーダーとしての必要条件を考える時、自分には能力もある、指導力もある、素晴らしい人格も備えている。だから自分はリーダーとしての資格があるというように思うかもしれません。
天がなぜ、自分にそのようなりーダーとしての才能を授けてくれたか、それには理由があるはずです。
誰か他の人でも良かったわけです。
自分がたまたまそういう才能を持っていたとしても、その才能は世界のため、社会のため、、そして集団のために使うべきなのです。
決して自分だけのために使うべきではないのです。
リーダーとしての義務を果たさなければなりません。
決して傲岸不遜になってはならないのです。」
会社を経営する時、優れた社長は自分の才能に溺れ、優れた人間のように自己評価してしまうことが多いようです。
それを自戒させるための言葉です。
それと同時に私が最近思うのは、世界の貧富の格差についてです。
優れた経営者が会社を成功させ多くの富を手に入れています。
優れた自分が得た富をどうしようが自分の自由。
結果、世界の富の多くが限られた富裕層に占められています。
金儲けのが上手いという才能は、たまたまその人に与えられたのであり、もしかしたらその人以外でも良かったのです。
得た富は決して独り占めすモノではないはすです。
飢餓で毎日多くの子供達が死んでいる世界がある一方、富集めに奔走している金持ちの世界。
そのような世界。
考えさせられます。
ウイスキー

先日

、サントリーの「山崎10年」ものを探したのですが、どこの店にも置いていません。
ネットで調べると1本18000円で売られていました。
噂によると中国の人がドンドン買っていくそうです。
もう高くて買えません。
ところで私は4月から月1度のペースで「シングルモルトの会」を開いています。
ウイスキー好きの人達と旨いシングルモルトを学んででいます
4月はシングルモルトのロールスロイスと言われる「マッカラン12年」と「ラフロイグ10年」。
5月は先週に開き、「ボウモア12年」と「アードベック10年」を呑み、一生懸命にシングルモルトの「勉強」をしました。
作家の村上春樹氏は若い頃バーを経営していたそうで、ウイスキーの造詣が深く「もしも僕らのことばがウイスキーであったなら」を書いています。
その中にボウモアのウイスキー職人から教えられた食べ物が紹介されています。
「生牡蠣にシングルモルトをかけて食べるとうまいいんだ!」
勿論、私達も勉強のため真似てみました
旨い!
以下は村上春樹氏が書いている感想です
「僕はそれを実行してみた。レストランで生牡蠣の皿と一緒にダブルのシングルモルトを注文し、殻の中の牡蠣にとくとくと垂らし、そのまま口に運ぶ。うーん。いや、これがたまらなくうまい。。牡蠣の潮くささと、アイラ・ウイスキーのあの個性的な、海霧のような煙っぽさが、口の中でとろりと和合するのだ。」
ご興味がありましたら、皆さんもお試し下さい。
亭主元気で留守がいい
「亭主元気で留守がいい」という言葉があります。
若い頃にこの言葉を聞いた時は、「冷たい関係だな〜」と思いました。
結婚してみると「成る程!」と納得。
しかし、歳をとってみると、「夫婦がそれぞれ自分らしく生きる方法」と実感しています。
連休が続く今朝、思い当たりました。
挨拶
最近よく見る光景ですが、店に入ると「いらっしゃいませ!」と沢山の声がかかります。
誰が挨拶しているのだろうかと見渡すと誰だか分かりません。
私の後に入ってきた人に対しても挨拶がかかります。
よく見ると、誰もお客さんの方を向いていないで声だけ出しています。
お客さんに尻を向けながらの挨拶。
呆れてしまいます。
先程、久しぶりにある銀行に行ったのですが、ここもお客さんを見ないでの挨拶。
「やっぱり!」と思いながら受付マシンからカードを取り、呼ばれるのを待っていたのですがなかなか呼ばれない。
待っている人は私の前に1人だけ。
カウンター窓口には3人の女行員が座っています。
すぐ呼ばれるかと思ったのですが、結局15分ほど待ちました。
私の番が来て、事務処理が終わり通帳を渡される時、ツイ言ってしまいました。
「カウンター窓口の人は、ここで後方事務処理をするより、目の前のお客様優先で仕事をしたら如何ですか?」と。
言わなくていいのに言ってしまいました。
「いらっしゃいませ。」「ありがとうございました。」の口だけの挨拶より、目の前のお客様1人1人を大事にする。
この銀行は35年ほど前まで私が勤めていた銀行です。
変わってしまったのでしょうか。
残念です。
質素
「HARD THINGS(ハード・シングス)」という本を読んだところです。
読みながら色々赤線を引きました。
赤線を引いた箇所に、「企業文化の構築」という章に書かれていたアマゾンの創業者ベゾスの言葉があります。
「われられは最低のコストで最高のサービスを提供するために、あらゆる機会をとらえて1セントでも節約しなければならない」と言います
1例としては、ホームセンターで買ったドアに脚を付け、デスクを作らせました。
それは1000億ドルを超えるアマゾンの時価総額とはマッチしません。
それでもベゾスは「質素」という「企業文化」を打ち立てました。
「売上を最大に、経費を最少に」
これは会社経営の基本です。
会社の規模が大きくなると ツイ無駄なお金が使われます。
ベゾスの言葉はそれをいさめた言葉です。
起業して業績が拡大して行くと、自称「必要経費」ということで、無駄なお金が流れ出て行きます。
さて、自分の会社はどうなのか
改めて見直す必要はあると思います。
翻訳本
最近、続けて2冊、読んでも理解出来ない本に出会っています。
経済関連の本ですが、何度読み返しても理解出来ないのです。
2000円以上するハードカバーの本です。
最初は一生懸命読み込んだのですが、ついに放棄しました
2冊とも翻訳本です。
読み始めた最初は、私の理解力が足りないのだと思ったのですが、そうではないと断言します。
絶対、翻訳が下手なのだ!と思っています。
直訳に近い翻訳で、日本語になっていない。
そう思っています。
私達は本を買う時、原作者は選べれますが、翻訳者までは分かりません。
これからは少しじっくり立ち読みしてから買うことにします。
お金が勿体なかったと、少し残念に思います。
出会い
人は人生の中で、色々な出会いに遭遇します。
本との出会い、人との出会い。
その時に必要とされる本であったり、人であったりします。
本に出会い、影響を受けた本は手放せません。
私が一番影響を受けた本は稲盛和夫さんの「生き方」です
当時、仕事の上で悩んでいました。
その時、「生き方」に出会い、読み、感動しました。
読んだ後、本に書かれていた著者紹介の中に「盛和塾の」存在を知り、すぐに入会申し込みしました。
入会後は稲盛さんの考えに心酔し、如何に自分の考えとして吸収していくか。
CDも買い聞き込んでいきました。
「稲盛さんに出会えて自分の考えが変わり、人生も変わった」
私はしみじみそう思っています。
1冊の本に導かれた師との出会い。
「もっと若い内に稲盛さんと出会えていたら、私の人生はもっと良くなっていただろう!」と思ったことがあります。
しかし、そうではありません。
若い頃はきっと、稲盛さんの考えに興味を示さなかっただろうと思います。
必要な時にこそ、必要な出会いが目の前に現れます。
これからも大事な出会いがあると思います。
楽しみにしています。
商売道徳
今月の初めの新聞に「限定人形100体買い占め」という見出しの記事が載っていました。
100体限定、1人2体まで購入可能として売り出された人形。
1体当たり12万円を超える価格で売り出された人形を、前もって手配した50人に買わせ、その後買い取り、結局1人が買い占めしたようです
転売目的のようで、中国の通販サイトにその人形の情報が掲載されているとのこと
この記事を見て、「成る程!こういう商売の方法もあるのか!」と思う人もいれば、「合法的とは言え、商道徳的に嫌だ!」と思う人もいるでしょう。
商売に関して目端の利く人はいます。
思いがけないところに商売のチャンスやヒントが落ちています。
そのことは大切です。
今回の話もその1つかもしれません。
ただ私はこのような商売方法は嫌ですし、そのような商売をする人は好きになれません。
価値観の違いもありますが、それ以外に思うことがあります。
勉学においても、経営においても、またそれ他の分野においても優秀な人はいます。
仕事も難なくこなすことが出来ます。
そういう人はエリートと言われます。
でも私が思うに、人が優れているかどうかは、人としての「質」によるモノだと思います。
この「質」は生まれ、育って来る中で培われてきます。
人としての優しさや強さ、包容力であり、人を引きつける情熱。
数値化出来ないモノです。
経営者はこの「質」が問われます。
儲かればいいのではなく、どう儲けるか。
これが大事です。
正々堂々と商売をすることです。
普通の店
先日、ある経営者の話を聞きました。
彼は父親の理容室を受け継いで22年。
現在は千葉県内で40を超えるヘアーサロンを展開しています。
父親から会社を引き継いだ時は店舗が1つ
売上が年間5000万円。
経常利益は65万円ほどでした。
長男は理容室を引き継がず、別の道へ
次男である彼は引き継いだ後「何でこんな店を俺が・・・!」と悩んだそうです。
その会社は22年後、売上15億円、経常利益1億5千万円を出せる会社になっています。
従業員の給料も他のヘアーサロンより年収で100万円高く支給しているそうです。
それで利益率10%はすごい会社です。
昔からある美容室や理容室。
なかなか業績が上がらず、店をたたむところもあるようです。
そのような平凡な業種なのにこの業績拡大。
経営者によってこうも変わるのです。
同じ業種でも経営者の考え方1つで大きく違っていきます。
もう1つ別の例です。
同じ様に昔からある店の紹介。
私の母方の祖父の店は酒類・米類を扱って居ました。
その店は伯父の代でローソンのコンビニなりました。
私の従兄弟は別の会社に勤めていたのですが、嫌々その店を引き継ぐことになりました。
嫌々引き継いだのですが、彼は考えました。
どうせ引き継いだからにはコンビニの店舗拡大を図ろうと頑張りました。
その彼はもの凄い馬力がある人です。
30年ほどの間にローソンの店を45店舗ほどに拡大しました。
売上等は分かりませんが、「コンビニは儲からない」と言いながら、札幌の地下街や千歳空港の国内線、国際線のターミナルビルにも出店しています。
酒類・米販売の店にしても、理容室にしても、どこにでもある店です。
決して目新しいビジネス形態ではありません。
それでも経営者によって店や会社は変わっていくのです。
経営者の考え方と行動力。
如何に大切か考えさせられます。
元気になる方法
人は時に落ち込んだり、自信をなくしたりすることがあります。
そんな時、元気になる方法。
何があるでしょうか?
叱咤激励の言葉や、優しい言葉。
残念ながら、そのような言葉を掛けられても、なかなかその気になれません
そんな時にチョット試してみるといいのは、心打たれ、涙を流す様な話や文章を読むことです。
私は昔から涙もろくて、チョットしたいい話を聞いたり、読んだりするとすぐ泣いてしまいます。
少し涙が出ると、モヤモヤしたモノがフッと消えていきます。
私が今まで気になる言葉や文章を書き留めてきた「銘肝録」にもそのような文章があり、時々読んでいます。
「一杯のかけそば」もその1つです。
この作者は色々問題がありましたが、作者は別にして、この「一杯のかけそば」の話はいいですね。
今朝も読んで少し涙しました。
「銘肝録」は手帳サイズのノートを張り重ね、6冊に太りました。
国民栄誉賞
報道によると、先の平昌五輪のフィギアスケート男子で金メダルを取った羽生選手に国民栄誉賞を授与することが決まったようです。
五輪選手と言えば、女子レスリングでは2012年に吉田選手、2016年には伊調選手が受賞しています。
それぞれの選手はそれに相当する成績を残しました。
受賞に関して意見するモノではありません。
ただ、気になる事があります。
受賞を喜んでいる皆さんからは批判されるかもしれませんが、あえて書きます。
それは少し若過ぎるのではないかと思うのです。
若い内に「国民栄誉賞」という重い賞を貰うことで、その後の人生において重い負担になる気がします。
これまでの受賞者は第1回目が野球の王さんです。
その後、作曲家古賀政男さん、俳優の長谷川一夫さん、冒険家の植村直己さんなどそうそうたる人達でした。
またある程度歳を取られてからの受賞です。
昔に聞いた言葉です。
「若い頃の功は禄で報い、地位で報いてはならない。」
「若者の評価はお金で報いるべきで、決して地位で報いてはならない。」と言うことです。
たとえ、大きな功績あった若者でも、その後どのような人生を歩むか分かりません。
「もしも道から少し外れた人生を進むと、この賞に傷を付けてしまう」と余計な抑圧を感じてしまうかもしれません。
受賞したことによって、その後の言動や人生が制約される恐れがあります。
その若者にとっては、避けるべき事だと思います。
この2・3日、急に出てきた伊調選手に関しての報道も可哀想な気がします。
孤独
「孤独」という言葉にはあまりいいイメージがないようです。
今朝の日経新聞の「春秋」に書かれていたこと。
先月イギリスのメイ首相は「孤独担当大臣」という閣僚ポストを作ったそうです
イギリスでは6500万人の国民の内、900万人以上の人が日常孤独を感じているそうです。
日本でも「孤独死」などと言われて問題になってます。
10年ほど前にフィンランドに入った時に聞いたの話です。
フィンランド人と結婚した日本人女性通訳は「老後は国が全て面倒をみてくれるので、フィンランドの多くの若い人達は親の面倒をみない。
自分たちの生活だけを考えている」と言っていました。
その為に高い税金を払っていると言うのです。
確かに消費税24%です。
しかし年老いた親は孤独感を感じているのと私は思います。
福祉国家と言われても、「孤独担当大臣」が必要になってくるのでしょう。
もう1つの考え方。
「孤独」は人に必要なことだと思っています。
「群れる」より私は1人でいる方が好きです。
「孤独」を楽しむことが出来ればいいのです。
こんな言葉があります。
「有名になると堕落する。
じゃあどうすればいいか。
孤独でいること」
会社の業績がいい社長に贈る言葉です。
国際郵便
我が家にユニクロ等の通販会社から品物がまとまって届きます。
私達夫婦が買っているのではなく、娘達が買って中継先として実家である我が家に送るのです。
スペインとスエーデンにいる娘達は、ネットで好きなモノを買ってから妻に電話してきます。
「ユニクロで買った品物が届くので送って!」
妻は言われるがまま送ります
そしてどうせ送るならと、娘や孫が喜びそうな食べ物や衣料品を沢山買って一緒に送ります。
梅干しや海苔、調味料やインスタント食品、それに孫が喜ぶアンパンマンのふりかけ等細々としたモノです。
それが大きめの段ボール1つになります
送るのは国際郵便なので郵便局まで車で運びます。
その郵便局での事務的な段取りが大変のようです。
段ボールに入っている品物を全て英語で書き出さなければなりません。
それを書き終わるまで1時間以上かかるそうです。
送料も2万円以上かかります。
その一連の作業を妻が1人でします。
お金は私が出します。
最近また、宅配物が貯まってきました。
もうそろそろ送る準備が始まります。
私にしてみれば面倒くさい作業に見えますが、妻はそうもないようです。
今日、一緒に送る品物を買いにデパートに行くと言っていました。
当てにされ、頼りにされるのが母親として嬉しいようです。
ネバダ・リポート
「ネバダ・リポート」というモノをご存じでしょうか。
私は先日、本を読んでいる時に知りました。
2001年にIMFが日本に対して財政再建に必要な項目として提示したモノです。
そこには日本の財政を再建するために厳しい内容が書かれています
1.公務員の人員の総数を30%カット、給料も30%カット 。
ボーナナスも全てカット 。
2.公務員の退職金は100%カット。
3.年金は一律30%カット 。
4.国債の利払いは5~10年間停止。
5.消費税は15%引き上げて20%へ 。
6.課税最低限の年収100万円までの引き下げ。
7.資産税を導入し、不動産に対しては公示価格の5%を課税。
債権・社債については5~15%の課税、株式は取得金額の1%課税。
8.預金は一律ペイオフを実施するとともに、第二段階として預金額を30~40%
カットする 。
読んでいただければ分かるように厳しい内容で、特に公務員の人にとっては死活問題になります。
このネバダ・リポートは2002年に国会で質問された経緯があります。
当時の日本の国債は700兆円以下でした。
その借金の額で、このネバダリポートのような厳しい事をしなければならなかったのです。
現在は1050兆円を超しています。
この対応はどうなるか想像もつきません。
ただ、IMFがこのようなレポートを出しても、今の日本がクラッシュを起こした場合、IMFは日本の再建は出来ません。
1997年に起きた韓国の通貨危機の時、IFMが介入して韓国経済は復興しました。
その時は、IFMが中心となり570億ドル、約6兆8千億円を出資しました。
一方、日本の借金は現在1050兆円を超しています。
その上、IMFの資金量は80兆円しかありません。
規模が全然違います。
日本がクラッシュすると、世界経済に大きな影響が出るでしょう。
2年後に行われるオリンピックの建築関連事業は来年度中には終わります。
そして来年度は消費税の増税が予定されています。
結果、来年度は極端な日本経済の落ち込みが予想されます。
私達はただ不安を持ちながら見ているだけなのでしょうか。
年配の仲居さん
この前の連休を利用してお伊勢参りに言ってきました。
先に上京していた妻が、東京に住む10歳になる孫を連れて、札幌から向かった私と名古屋で待ち合わせ。
毎年のお伊勢参りは今年で7回目になります。
行く前から妻と「今回で一区切りししよう」と決めていました。
宿泊先はいつも泊まる神宮会館。
人気のある会館なので、半年以上前から予約していました。
内宮に近く宿泊料金は朝食付きで1人8千円台
格安です。
11日にお参りを済ませた私達はその後「鳥羽」に向かいました。
鳥羽の駅から迎えのバスに乗り、30分かけて海辺の温泉宿。
案内された部屋に入るとビックリ!
海側の壁面が一面ガラス戸になって、目の前に海が広がっています。
丁度東向きなので、海から昇る朝日が見えます。(残念ながら翌朝は曇りでした)
私達の部屋の担当仲居さんにもビックリ!
優に80歳を超えると思われる小柄のおばあさん。
でも元気!
その仲居さんは、私が持つと言うのに、私のバックを無理矢理持って部屋へ案内してくれます。
その動きの機敏なこと。
夕食は部屋食となっています。
10畳間の私達の部屋に料理を運んできてくれます。
その仲居さんが1人で。
何回も部屋と調理場とを行き来しながら揃えてくれます。
そして、その料理の豪華なこと!
伊勢エビの刺身、生アワビの踊り焼き(少し可愛そう)、それにウニご飯等を中心に15種類ほど出ました。
当然食べきれません。
食事が終わった後、あの仲居さんが来て「布団を敷きます」と言います。
流石に私も、「私達が敷きますよ」と言ったのですが、私がしますとテキパキと敷いてくれました。
あまりにも元気な仲居さんと少し話をしました。
昔は海女さんだったそうです。
ここの浜は海女さん達の浜のようです。
この仲居さんは若い頃にご主人を亡くされ、女手1人で子供を育てました。
今は息子さん家族と一緒に暮らし、お嫁さんとも上手くやっているようです。
「このホテルの社長がいい人で、私を雇ってくれている。
若い人はこの土地にはいないしね。」
確かに他の若い仲居さん達はほとんどが外国人。
その仲居さん達の中で、80歳を超すこの仲居さんの動きの良いこと。
他の若い仲居さん以上に気が付き、キビキビ働いています。
若い頃に海に潜って、一所懸命働いてき蓄積が今の気力・体力と動きになっているのでしょうか。
前向きに働く姿を見て、働くことに歳は関係ないことを改めて知らされました。
帰りにバスに向かって元気に手を振る仲居さんの姿は忘れられません。
ところで、このホテル旅館の宿泊費は気になるでしょう?
豪華の夕食と朝食が付いて、素晴らしい風景の部屋で1人9,999円。
格安です。
眞子様の結婚
昨夜テレビを見ていると「眞子様の結婚延期」という速報が流れていました。
一瞬週刊誌等で取り上げられている小室さんの実家の問題がその原因かと思ってしまいました。
しかし新聞発表ではその原因は、同年に天皇陛下の退位や皇太子様の即位に関する儀式があるためとされています。
その一方、眞子様の「私達の未熟さゆえ」という言葉も気になります。
今朝の日経新聞に井上編集委員の解説がありましたが、その内容に強く賛同しました。
少しの文章を紹介します。
「婚約者の小室さんの家庭の事情に関して、バッシングと言える報道が続けられている。
憂慮されるのは、一連の報道が『皇族の結婚相手としてふさわしくない家柄』とレッテルを貼る空気を助長することだ。
『婚姻は両性の合意にのみ基づいて成立する』と憲法は保障している。
これ以外の用件は何もない。
もし、『家柄』や『経済力』などへの懸念、批判が圧力とになったとしたら、民主主義国家としての恥であろう。」
現在、「マスコミこそが正義」のような風潮で、人を陥れています。
愛する二人の間に余計なクサビを打ち込む報道。
この報道が出るまで眞子様の結婚に関して「良いことだな」との程度しか思っていませんでした。
今は、色々ある障害を乗り越え是非お二人幸せになって欲しいという気持ちが強くなりました。
それにしてもつまらない雑誌が多くなりましたね。
凡人
世の中には色々な分野で一流と言われる人がいます。
一流の舌を持った調理人。
材料の組み合わせを考えただけでその味が予想出来ると言います。
一口食べただけでその食材を当てます。
一流の耳を持った演奏家は一度音楽を聴いただけでその音楽をモノにすると言われます。
絶対音感を持っていたり、複雑なクラシックの演奏を聴いて、些細な演奏間違いを指摘したりします。
一流の眼を持った人は微妙な色の違いを生かし、新しい絵の世界を創ります。
また、絵画の真贋も見分けることが出来ます。
彼らは私のような凡人には理解出来ないようなレベルで仕事を追求していきます。
その追求が絶え間なく続けられ結果、その分野の質が高まっていきます。
それが世の中の発展と言われるのでしょう。
それに対し凡人はそれほど高い「舌」も「耳」も「眼」が無くてもそこそこ満足して生活出来ます。
B級グルメを美味しく食べ、好きな音楽を聴き、気に入った絵を飾ります。
それだけで幸せを感じます。
圧倒的に多い凡人と言われる人達。
極限を追求という苦しみを感じなくて済む分、幸せなのだと思います。
ベットメイク
1週間程前にニュースで流れていた話。
中国の5つ星ホテルでベットメイク係が便器ブラシでコップを洗っている様子が流れていました。
その上、グラスを宿泊者が使用したタオルで拭いています
ニュースを紹介したアナウンサーが驚いていました。
しかしそれは日本でも起きています
お客様は知らないだけ。
以前にホテルの支配人をしていた時、ベットメイクの責任者の女性から聞いた話。
彼女が昔、新宿のホテルに研修に行った時、指導するベットメイク係が宿泊客が使用したタオルでグラスを拭いているのです。
彼女がそれを指摘すると、「面倒くさいし、誰も分からないからいいの」と言っていたそうです。
そのホテルの名前を出せば誰でも知っている有名なホテルです。
その現場を見た彼女はそれを教訓に、ベットメイク責任者として常に目を光らしていました。
ホテル側は経費削減の一環として、下請けのベットメイク会社に作業料金を下げさせることがあります。
そうすると1人当たり1日7室の清掃していたのが、10室になったりします。
ベットメイク係は忙しさと面倒くささから雑な仕事をしてしまいます。
中国のベットメイク係と同じようなことをしているかもしれません。
結局、削減してはいけない経費を削減したことが大きな問題を起こしているのです。
潔癖症の人はホテルや旅館に宿泊する時、スリッパやグラス・カップは持参します。
分かる気がします。
私も、もしかして知らないうちにそのような人が清掃した部屋に入るかもしれません。
その時は仕方が無いとあきらめています。
朝食
今日は1日。
いつものように朝6時30分に家を出、琴似神社と北海道神宮に参拝しました。
朝食を食べずに出かけるので、参拝後どこかで朝食を摂りたいのです。
しかし、朝が早いので開いている店がありません。
以前はロイヤルホストが24時間営業ということで、そこでよく朝食を摂っていました。
「時には外で朝食を」と思っている年配者は多いと思います。
かって、早朝に行ったロイヤルホストには年配者が8割ほどの席を占めていました。
今はロイヤルホストも営業時間を変え、9時オープンとなりました。
朝7時位から開店する朝食専門のレストランあると流行ると思います。
マンションの多いところなどは狙い目ではないでしょうか。
1人暮らしの人達も利用すると思います。
今朝は参拝の帰りに見付けたコメダコーヒーに行ってモーニング食べました。
食べられて良かった!
ブロックチェーン
最近ブロックチェーンに興味があり、関連する本を3〜4冊読んでいます。
ブロックチェーンの仕組みはインターネットが出現した時と同じように世の中を大きく変革させると言われています。
今後、各分野で利用され、大きく変わっていく事が予想されています。
ただ、ブロックチェーンを基に作られたビットコインのような仮想通貨にはあまり興味はありません。
純粋にブロックチェーンに興味があります。
私はこのようなIT関連の分野は不得意で、理解するのに苦労しています。
本を読んでいても疑問に思うことが数多くあります。
簡単にそれについての回答が得られません。
セミナーがあれば参加したいと思います。
時々仮想通貨に関してのセミナーはあるようなのですが、多くは勧誘目的のようです。
初心者でも分かるようなブロックチェーンについてのセミナー。
あれば聞きに行きたいと思います。
最近強く思っていることです。
仮想通貨
スーパーなどのレジでよく見る光景。
お年寄りがお金を支払うのに時間がかかっています。
後ろに並ぶ若い人はイライラしているようですが。
歳を取ると今まで出来たことが中々出来なくなります。
お金の計算に時間がかかります。
歳を取ると仕方が無いことです
そんな時に思い浮かべる言葉があります。
「子供叱るな来た道だ。老人笑うな行く道だ」
いつか歳を取ると皆そうなります。
私もソロソロ危ないかも。
そんなお金の受け渡しが簡単になる時代が近づいています。
ビットコインのような仮想通貨の普及です。
電子決済もそうでしょう。
仮想通貨は元々、現状のビットコインのような投資目的ではありません。
送金や決済に使われるものです。
日本の銀行や各国の中央銀行でも発行を検討しています。
この方面で一番進んでいると言われるスエーデンでは、2018年末までに仮想通貨「eクローナ」を発行する可否を決めると言われています。
ここ数年でお金の形、それに伴う銀行の経営が大きく変わっていくことでしょう。
毎日、もの凄い大きな実験が行われる。
私達はそれの目撃者になる。
そんな気持ちになります。
フローとストック
昨年の末に5年ぶりでiphoneを買い換えました。
思い切ってiphoneXにしました。
でも、その価格、結構高い。
私の場合、買い換えは5年振りなので長持ちしている方でしょうか。
若い人達は買い換えがもっと早いと聞きます。
iphone等のスマートフォンやipad等のタブレットを使うと、毎月通信料やアプリ等のソフト料金が別にかかります。
その費用が何万円にもなります。
10万円を超す人もいると聞きます。
世の中は大きく分けて「フロー経済」と「ストック経済」に分かれます。
スマートフォンにかかる費用は流れ出て行きます。
「財」としては残りません。
一方、ストックは財産が貯まっていきます。
サービスを受けると、お金はフローとして流れ出ていきます。
耐久物を買うとストックとして残ります。
どちらを選択した方が良いのか。
それはそれぞれの人の評価によるでしょうが、確実に言えるのはストック経済を選択した方が財産は残ります。
国としてもフロー経済の国とストック経済の国。
結果は大きく違います。
必要と思われるような生活費を犠牲にしてでもスマートフフォンにお金を掛ける若者。
将来本当に豊かな生活が出来るのか。
人ごとながら心配です。
風邪
1週間ほど前から風邪を引き、今やっと治ったところです。
私が治ったと思ったら、今度は妻に私の風邪が移ったようです。
今日の昼に家に帰ると、赤い顔をしているので寝るように言ったのですが、中々言うことを聞かなく、家事をしています。
私の場合は弱音を吐いて寝てしまいますが、妻は強い。
それでも昼に家を出る時は「寝ていなさい!」と命令してきたので、今頃は寝ていることでしょう。
今日の夕食は私が作ろうと思い妻に言ったのですが、お弁当買う様に言われました。
張り切って作ろうと思ったのですが仕方が無い。
弁当を買って帰ります。
今インフルエンザが流行っているようです。
私達はインフルエンザでは無いと思うのですが、皆さんどうぞお気を付けて!
正々堂々
最近、有名企業や経営者達の不祥事が発生しています。
少し心配なのは、お金を儲ける事への不信が若い人達に広がることです。
金持ちは皆、悪いことをして儲けていると思ってしまうのではないだろうか。
以前にも書きましたが、日本は起業家に対する評価が低いように思います
もっと頑張る人を応援して欲しいと思います。
一般の人からは、リスクを負って起業する人への憧れもないように感じます。
経済界での不祥事は確かに多いですが、私達経営者はお金を儲けることに躊躇してはいけません。
「正々堂々」と胸を張ってお金儲けをして良いのです。
沢山儲けて良いのです。
「正々堂々」と商売をするというにはもう1つの意味があります。
それはお天道様に恥じない商道徳に基づいて商売をすることです。
後ろ指を指される事の無い商売をするのです。
そんな起業家に年金問題もあります
会社を辞めて個人事業主になれば、厚生年金が外れて国民年金だけになります。
それでは折角起業した個人事業主の老後が心配です。
起業家や経営者が若い人達から憧れる。
頑張る人が評価される。
そんな国になってくれれば、日本はもっと活気ある国になる様な気がします。
朝起きた時
朝起きて、まず第一に何を考えますか?
まずは「会社へ行くの嫌だなー」と考えたりする人が多いのではないでしょうか?
「もっと寝ていたい!」と思う人もいるかもしれません。
スティーブ・ジョブズの有名な言葉があります
朝起きた時、自分に問うのです。
「もし今日が人生最後の日だったら、僕は今からすることを"したい"と思うだろうか?
その質問に対して、あまりにもノーが毎日続くようなら、それは何かを変えないといけない証拠だろう」
これは、毎日の生活がマンネリで、挑戦する熱い心が失われているのではないかを自分に問い、そのようなことにならないために自己チェックする言葉なのでしょう。
また、アメリカ独立宣言の起草者のベンジャミン・フランクリンは毎朝起きた時、「どんな良いことをしよう?」と自分に問いかけていたと言われています。
スティーブ・ジョブズにしてもベンジャミン・フランクリンにしても朝の時間は如何に大事かということを語っています。
時間ギリギリまで寝て出社しているとそんな気持ちになれません。
まずは早起きが大事と言われます。
しかし早起きも、何のために早起きするか分からなければそれも長続きしません。
早起きして何をするのか!?
勉強をする。
仕事の段取りをする。
そのことは、ワクワクとした気持ちになることでなければ続きません。
私は少し早く起きます。
5時30分に起き、7時30分出社。
早起きは習慣になっていますが、出社する時少しワクワクしています。
愉しいことがありそう。
そんな気持ちになっています。
バッテリーが上がってしまいました。
今年の10月に車を買い換えました。
とは言っても会社が支給してくれる中古車です。
トヨタのアリオン
走行距離が3万キロ。
4WDなので雪道も安心です。
ところが、この車すぐバッテリーが上がってしまいます。
中古車と行っても決して安くはありません。
最初は11月。
3日間乗らなかっただけでダメでした。
すぐにトヨタの会社に連絡し対応して貰いました。
原因は分かりませんでした。
不安に思いながら暫く使っていたのですが、先日の22日にまたバッテリー上がりました。
10日間乗らなかっただけ。
また電話でトヨタの会社に連絡したのですが、担当者は「冬場はバッテリーが上がりやすいのでそれが原因ではないでしょうか」と言います。
私はツイ「馬鹿なこというな!」と叱責してしまいました。
駐車していた会社の駐車場は地下にあり、シャッターもついています。
いくら冬の時期でも駐車場の気温は零下になっていないはず。
また、40年以上自動車に乗っていた経験からも、そんな短期間でバッテリーが上がることはありません。
その場しのぎにごまかそうとするその言葉。
誠意を感じられません。
営業マン失格です。
今日その営業マンが来る予定です。
しっかりお話ししようと思います。
(おかげで奥さんから頼まれた年末の買い出しは、リックサックを背にイオンのショッピングセンターまで30分歩き。
帰りは荷物が重く、また雪道が滑るのでタクシーで帰ってきました。
良い運動にはなりました。)
正しいこと
ズルをするわけではない。
勿論法律に違反することでもない
少しくらいなら甘え、緩めての良いのかなと思うことがあります。
がんじがらめに自分を縛る付けるとストレスが増えると言う人もいます。
でもそれを許すと、自分の自分に対する規範が崩れてしまう。
矜持が失われてしまうことになります。
これは経営者が持たねばならない心構えです。
常に社員から、世間から見られています。
自分に甘くして、少しぐらいズルしても誰も文句は言いません。
でも、ズルした事実は自分は知っています。
知っていて、知らんぷりは出来ません。
もしもそれが出来た時、その時から上に立つ者としての矜持は失われてしまいます。
「たかがそんなこと!」
と思った時から経営者失格です。
経営者には倫理観が求められます。
如何に自分に厳しく出来るか。
昨今、日本の大企業で起きている倒産の危機と言われる不祥事。
その始まりは取るに堪えない些細な事だったのかもしれません。
しかし倒産の危機を迎えたのは、それを見逃し続けた結果です。
後になって考えてもその原因は分からないでしょう。
その始まりはいかにも些細なことだったからです。
「自分に厳しく!」
上に立つ者の志です。
素直な心
私は人から「自分の人生が良くなるためにはどうしたらいいですか?」と聞かれると、「素直になること」と言っています。
昔の私は少し皮肉れ者で、あまのじゃく的なところがありました。
人の話を素直に聞かないし、信じようとしなかったように思います。
それが変わったきっかけは、自分の「師」と思える人に出会えたことです。
その人が話すことは素直に信じられる
その通りに生きてみようと思う。
世の中には立派な人は沢山います。
しかしその中で自分の琴線に触れる人に出会える事。
これは縁であり幸せなことです。
宗教の中に素直な自分を見付ける人もいるでしょう。
それに似たようなモノかもしれません。
私にとっての「師」は稲盛和夫さんです。
明日、稲盛さんが塾長として主宰する盛和塾の忘年会があります。
稲盛さんの講演会も予定されています。
稲盛さんは85歳になられました。
お身体が弱って来ているので、これからは中々お話を聞く機会が無くなるでしょう。
素直な気持ちになり、お話を聞いてこようと思います。
父親
今年も残すところ後、半月ほどになりました。
年末には子供達が孫を連れて来てくれます。
子供達も親として頑張っているようです
その子供達を見て、「私はいい親だっただろうか?父親らしいことをしただろうか?」と思うことがあります。
その「父親」に関しての文章、ネットで見てそれを書き留めていました
「厳しい父親」と「優しい父親」。
その文章、少し長くなりますが紹介します。
宜しければ読んでください。
「厳しい父親」
正しいことは正しい 悪いことは悪いという物差しを子供に持たせることは親の責務である。
親や近隣の人に挨拶をする。目上の人に礼儀正しくする。
いわゆる躾と言われるものは特にそうだ。
辛く苦しいことでもとにかくやらせる。
時には叩くこともする。
焼け火箸と同じ事で、痛さで分からせることは最も心に残る。
言葉だけで言ってもそれを実感できないからだ。
実感できないものは、知識として記憶が出来ても、行動や知恵にならない。
ただ、言うまでも無いことだが、親や大人が子供を自分の感情のはけ口にしているような場合は、何の教育にもならない。
むしろ何をされようと、大人の言うことなど聞くのもかと思うようになる。
それにまつわる、ある親子の話がある。
子供が仏壇に置いてあったお金盗んだ。
それに気付いた父親は「ならぬ事はならぬ。ならぬと言え!」に従い子供に厳しい罰を与えた。
季節は真冬。
庭には雪が積もっている。
息子を庭の井戸端に連れて行くと「おまえは人としていけないことをした。
よって戒めとしてこの井戸の水を10杯掛けてやる。
しかし、そんな息子に育てたのは親であるわしの責任でもある。
お前に水をかぶせる前にまずわしが罰を受けると言うやいなや、氷のように冷たい井戸水を桶で頭から10杯かぶった。
それを呆然と見ていた息子は途中から泣き出し、自分の非をわびた。
父親は自分がかぶり終わると「次はお前の番じゃ」と言って、桶にたっぷりの水を続けて3杯息子の頭から浴びせた。
4杯目からは形ばかりの水の量。
そして5杯でやめた。
相手を厳しく叱るとは同時に自分自身のあり方への深い内省を伴わなくてはならない。
「子供に言う前に、親として叱るだけのことを自分が出来ているのか。
自分のあり方はどうだったのか」
そこには自分に向ける厳しさが不可欠である。
そうしたモノがあってこそ、初めて相手に深く伝わる。
単純に厳しく叱ることが愛情だと言う人がいるが、そこのところを良く気を付けなければならない。
相手が愛情から出た行為であること認め、受け入れてくれなければ何の意味も無い。
(二千日回峰行者 酒井雄哉大阿闍梨の言葉)
「優しい父親」
「三笠会館」という有名なレストランが銀座にある。
創業者の谷さんは奈良のご出身であり、
在家仏教で名を成した方でもあった。
現社長の仏前結婚に筆者もお招きを受け感動した日が忘れられない。
樋口さんの友人で、よく貧乏に耐えて勉学にひたむきに努める人がいた。
その友人が勉学に励んだ動機は、「おやじの弁当」だという。
彼はある日、母の作る父の弁当を間違えて持って行ってしまった。
彼曰く、「おやじの弁当は軽く、俺の弁当は重かった。
おやじの弁当箱はご飯が半分で、自分のにはいっぱい入っており、
おやじの弁当のおかずは味噌がご飯の上に載せてあっただけなのに、
自分のにはメザシが入っていたことを、間違えて初めて知った。
父子の弁当の内容を一番よく知っている両親は一切黙して語らず。
肉体労働をしている親が子供の分量の半分でおかずのない弁当を持ってゆく。
これを知った瞬間、『子を思う親の真(愛)情』が分かり、胸つまり、涙あふれ、その弁当すら食べられなかった。
その感動の涙が勉学の決意になり、涙しながら両親の期待を裏切るまいと心に誓った」
という。
それに引き換え、戦後の私権の主張のみに急な世相の中では、
「お父さんの弁当の中身は少ないが、お前のはちゃんとした弁当だから頑張れ」
などと発言しがちであるが、それでは「恩、愛の押し売りはごめんだ」と生意気な子供の言葉がはね返ってくるのがオチであろう。
(「致知」ネットニュース。『致知』2009年1月号の「巻頭の言葉」)
この2人の父親。
読んでみて、私の厳しかった父親を思い出します。
小学2〜3年生の頃、同じような悪いことをして、父から怒鳴られ叩かれたことを思い出します。
それが今、真っ当な生活が出来ている自分の根底にあります。
その恩を改めて感じています。
葉書
今月になって何回目かの忘年会、先日札幌の「てまひま」という名前の居酒屋でありました。
私達は8人で行ったのですが、50席程の店内はほぼ満席。
そこのホールを1人の女性が中心になり、スムーズに仕事をこなしていました。
用事がありチョット手を上げると、すぐに気付き来てくれます。
20代後半?位の若い女性なのに気働きが出来ています。
帰り際に、「料理もサービスも良かったよ」と言って彼女と名刺交換しました。
2〜3日後彼女から礼状が来ました。
添付した写真にあるように手書きの葉書です。
もしかしたら同じような文面で多くのお客様にも送っているのでしょう。
それでのいいのです。
ネットの世界だからこそ、メールでない手書きが際立ちます。
貰った客は私のように嬉しくなり、このブログのようについ紹介してしまいます。
チョットの「てまひま」を掛けての葉書。
いいですね。
皮膚科
ここしばらく、顔の眉毛や頬のところが赤くなり、痒みもありました。
我慢していたのですが、やっと先日皮膚科に行ってきました
その症状名は言われたのですが、難しい名前で忘れました
先生によると、皮膚が赤くなった原因は炭水化物の取り過ぎとのこと。
それを聞いて驚きました。
つい、「本当ですか?!」と疑いの質問をしまいました。
多くの日本人は炭水化物中心の食生活をしてきたはずです。
確かに私もご飯が好きです。
筋子のおにぎりならいくらでも食べられます。
でもここしばらくは健康のこともあり、半膳。
食事の時は茶碗半分位にしています。
それも玄米にして。
それでもそのような症状が出てきた。
そうなると原因はもう1つ。
お酒です。
ここズーと、お酒を飲む機会が続いていました。
飲み過ぎのせいでしょうか。
先生に聞くと、「そうだ!」と言います。
心の中で「呑兵衛は皆そうなるのか!」と思いながら聞いていました
今日からしばらく飲む機会が増えます。
貰った軟膏を顔に塗りながら、お酒自重します?!
誰に
新規に事業を立ち上げる時、大切なのは「なぜ」「誰に」「何を」を明確にすることです。
その内、「何を売るか」は事業を立ち上げた時は既に分かっているはずです。
また「誰に」売るかが分かれば、「なぜ」売るかも分かります。
「誰にでも売る」という漠然とした考えでは何も売れません
大事なのは「誰に」売るかです。
ここを突き詰めていかないとターゲットの焦点がボケます。
ランチェスターの法則でも書いていますが、「弱者の法則」は市場を絞り込むことです。
「「誰に」と考えると、一般的に性別や年齢などを重視しますが、それだけではダメです。
性別にしてもバイセクシャルも有りますし、年齢でも細かく分ける必要があります。
高齢者と言っても元気な人とそうでない人。
子供も高校生・中学生・小学生・幼児・赤ん坊と分けられます。
国籍の違い、宗教の違い、所得の違い、趣味の世界、文化の違い。
それぞれの組み合わせを考えると、売る相手の「誰に」は無数に考えられます。
最近改めて「顧客セグメント」という言葉が重要視されています。
自分のお客様は誰なのか。
じっくり考えてみませんか?
残念な人
私の近くに、いい人なのに上手く行っていない人がいます。
私が見るところ、彼が上手く行かないのは素直でないこと。
間違えを指摘されても素直に直そうとしない。
褒められても素直に喜ばない。
悩んでいるのでアドバイスをしても反応がない。
彼のためにと思って買ってあげた本も読んでくれない。
それでいて、何か上手く行く方法はないかと常に考えている彼。
上手く行くには、それは簡単なこと。
素直になればいいのに。
それだけです。
それが分からない内は、何時までもグルグル同じところを回っている。
その繰り返し。
残念です。
悩み事はありません
昨夜、今年初めての望年会が有りました。
その望年会の時、ある人から言われました
「山地さんは悩み事など無いようですね。」
私は即答で、「そうです。悩み事はありません」と応えました。
本当に無いのです。
今の自分は周りの人達に恵まれ、困る事もありません。
ただ私も以前は悩むことも、苦しんだことも沢山有りました。
時には自作自演のような悩みもありました。
今も悩もうと思えば、悩む材料は沢山あると思います。
でも今は嫌なことや辛いこと、面白くないことには焦点を合わせないことにしています。
フォーカスしないのです。
自分の気に添わないことがあっても、見ないふり、知らないことにしています。
もしも、それにフォーカスすると、余計なことを考えてしまいます。
邪推したりする事にもなります。
サラッと流します。
自分で作った標語
「するは自分の責任、評価は人の勝手」
楽に生きる方が愉しいことが増えます。
昨夜の飲み会は私にとって望年会の始まり。
これから10回ほどあります。
身体に気を付け、休肝日を作りながら、愉しく飲みます!
パワハラ
最近、ブラック企業やパワハラの話を良く聞きます。
今、報道されている相撲界における暴力問題もパワハラです
「躾、礼儀を教えるためだ」と口にした横綱。
それは躾と称して子供を虐待している親と同じです
反抗できない者に、その立場を利用しての暴力。
その上、その周りに居た人間は止めなかった。
その人達も同罪です。
愛のムチという言葉があります。
今回もその類のことを言っているのでしょう。
「愛のムチだった」と言えるのは、打たれた人間です。
打たれた人間が自分の非を認めて言う言葉です。
決してムチ打った人間が言う言葉ではありません。
自分の感情のままに怒ってムチ打ったのにかかわらず、叱るためにした行為だ。
それを記者会見で平然と言える日馬富士。
好きな力士だったのですが残念です。
幸せは自己申告
お笑いタレントの綾小路きみまろさんの台詞に「幸せは自己申告」というのがあります。
「私は幸せだ」と思えば幸せなのです。
私の経験からも、それは本当だと思っています。
「幸せだ」と口に出し続ければ、本当に幸せになっていきます。
反対にいつも愚痴や文句を言っている人は不幸せになっています。
愚痴や文句を言っていながら、幸せになった人に会ったことがありません。
幸せだと口に出せば、その後に自然と「ありがとうございます」という感謝の気持ちが生まれてきます。
手を合わせて言ったりします。
そうすれば益々、幸せ感が高まります。
益々幸せになります。
単純なことなのです。
でも、大切なのはそんな単純なことに、いつ気付くか。
馬鹿馬鹿しいと思ったらそれで終わりです。
大事なのは「本当に心の底からそう思えるか」です。
タクシー料金
昨日台湾から帰ってきました。
近くに住む末娘夫婦を連れ、4日間の観光旅行でした。
台北の気温は25度ほどあり、夏日です。
札幌との温度差は25度。
事前の予報では、台北は4日間雨でしたが、晴れ男の私がそれを防ぎ、傘は必要ありませんでした。
台北での移動はタクシーを使いました。
バスや地下鉄もあるのですが、面倒なのでタクシーばかり利用しました。
そのタクシー料金がとても安いんです。
5〜6㎞走っても500円位。
以前行ったことのある中国やスペインでもタクシー料金はとても安かったのを覚えています。
バスや地下鉄は地元の人にとっては使いやすいのですが、観光客にとっては戸惑うことが多いです。
それよりタクシーでの移動が一番便利です。
近年、来日する観光客が増えています。
彼らが戸惑うのはタクシー料金の高さという話を聞きます。
中国の観光客相手の白タクが増えているということも、それに関連したことでしょうか。
高い料金の日本のタクシー。
その運転手の給料は安いと言われています。
一方、安い料金制度の海外のタクシー運転手はそれなりに生活できています
色々考えても、なぜ日本のタクシーの料金が高いのか分かりません。
料金を安くしないよう国土交通省が指導しているのも不思議なことです。
来日する観光客が益々増えると、一般の人が自家用車で有償送迎する「ライドシェア(相乗り)も認められてくるのではないでしょうか。
料金が高くて思うようにタクシーの使えない。
もしかすると、それが観光誘致のネックになりそうな気がします。
経常利益率
今朝の朝刊に「7%の壁」という言葉が載っていました。
上場企業の経常利益率が7%を突破したようです。
長い間、経常利益率7%を超えられず、壁のような存在だった。
それを超えたのはバブル崩壊後初めてだそうです。
経営規模の小さい企業では経常利益率が7%を超しているところも多くありますが、しかし何千億の売上のある大企業がそれを達成するのは大変なことです。
京セラ名誉会長の稲盛和夫さんは常に「会社の経常利益率は10%を超さなければいけない」と語っています。
稲盛さんが経営してきた京セラは過去、経常利益率10%を切ったことはありません。
これは大変なことだと思います。
5年ほど前まで私のレンタルオフィスに入居されていた起業家の話です。
ある時、我が社に来られ言いました。
山地さんに言われたように、しっかり稼いで税金を払っています。
いくら位納めたの?と聞くと、その額は約4000万円。
売上が3億円位?で、経常利益率はわかりませんが、経常利益が1億円とのことです。
従業員5名ほどのIT関連の会社です。
以前に私が彼に話したことは、「仕事が上手く行き、利益が出たらちゃんと税金を払うのですよ。
節税と称して、納税額を減らすために無駄な経費を使い、利益を少なくするようなことをしてはいけない。
しっかり稼ぎ、しっかり納税しましょう。
それで残ったお金が会社の財産になるのです。
それが内部留保というもので、それを積み重ねていけばチョット位の不景気が来てもビクともしない会社になれます。
従業員を首にしないで持ちこたえれます。」
そのようなことを話しましたが、良く覚えていてくれたものです。
この話は稲盛さんからの受け売りですが、本当にそう思っています。
会社経営者は高い経常利益・経常利益率を目指さなければなりません。
それが経営者の大事な役目なのです。
リストラ
今年も年末近くなりました。
それと共に、色々なところで人手不足が益々深刻化しているという話を聞きます。
先日の新聞にはヤマト運輸は年末配送の運転手の時給が2000円、アマゾンの荷分けの仕事の時給が1850円と書かれていました
必要な人手が集まらず、人手不足倒産という話も聞きます
つい5〜6年ほど前までは不況と言われ、人手が余り、リストラと称して首切りもありました。
今になって、慌てて人集めしています。
リストラは本来は「リストラクチャリング」と言われ、事業の規模や組織の再構築が行われることを意味しています。
単に人員整理を言っているわけではありません。
不況時に本来のリストラをして、人を辞めさせず組織の構造を変えていた会社は、今は急激に伸びています。
人員整理した会社が、慌てて人集めしている時に、人を辞めさせなかったその会社は、人材がその力を発揮しています。
過去何回も繰り返されてきた事です。
松下幸之助さんが「不況時こそチャンス」と言っていたことはこの事でしょうか。
まだしばらく人手不足は続きそうです。
市場
以前にも紹介したことがありますが、私が住む町には市場がまだ2カ所あります。
その内の1つは今でも活況を呈しています。
店の人と客とのやり取りが交わされ、温かい雰囲気です
私が幼い頃は家に冷蔵庫がなかったので、母は毎日のように市場に買い物に出かけました。
甘えん坊の私も母にくっついて行くと、お総菜屋で買ったコロッケを食べさせてくれたのを今でも覚えています。
その頃は家の中にはアイロン以外の電化製品は無く、ほとんどが手仕事でした。
母は普段から着物を着ていましたので、着物をほどいて洗い張り、そしてまた縫い上げていました。
布団も綿を洗いに出して、戻った綿でまた布団にします。
勿論、私達の食事3食も作ってくれていました。
母は毎日の仕事が終わり、寝る時に言っていた言葉があります。
「寝るほどの楽は無かりけり」
電気洗濯機、電気釜、冷蔵庫、掃除機などが普及され、女性の仕事は大変軽減されました。
家に冷蔵庫があるようになり、毎日買い物に行くこともなくなりました。
母も少しずつ家事の量が減ってくると、時間を見付けては踊りなどの趣味を始めました。
やっと自分の楽しみを見付けたようでした。
今の私の歳(68歳)の頃は調理師学校に入って2年間通い調理師免許まで取りました。
母の新しい挑戦にビックリしたモノです。
何のために取ったか私には分かりませんが、子か孫と同じような学生達と学校生活を楽しんでいました。
今の私にはそんなエネルギーはありません。
母が居なくなって6年になります。
今日、たまたま市場を見て母を思い出しました。
将来の課税対象
企業の貯蓄額の話です。
2010年から2015年までの平均で、日欧米の企業の貯蓄額が50兆円になるそうです。
日本政府はその企業の内部留保に目を付け、課税をする話があります
お金のあるところから税金を徴収しようという考えでしょうか
また、金融広報中央委員会が発表した2017年の「家計の金融行動に関する世論調査」によると、金融資産の平均世帯保有額は1151万円とのことです。
そして個人の金融資産総額は1800兆円です。
企業の内部留保も企業の貯蓄。
その企業の貯蓄に課税しようとしているのですから、将来個人の貯蓄も課税対象になる可能性はあります。
それにしても、日本の国債等の負債が1000兆円超はあまりにも巨額です。
マクドナルド創業者
「成功はゴミ箱の中に」という本を読みました。
マクドナルド創業者レイ・ロック氏の自伝です。
10年ほど前に出版されています
古本屋で、本の帯にユニクロの柳井氏とソフトバンクの孫正義氏の「これが僕たちの人生バイブル」という言葉に惹かれ読みました。
読み終わっての感想です。
レイ・ロックという人は自己顕示欲の強い人。
人を陥れてでも、のし上がる上昇志向の強い人。
人の痛みを感じられない人。
柳井氏や孫氏とは違う感想を持ちました。
マクドナルド兄弟から取り上げた「マクドナルド」
文章の中では自分の行動を正当化していますが、その行為には同調できません。
また、同僚の奥さんに恋し、長年添い上げてきた奥さんを捨ててしまうという行為。
その上、その恋した奥さんと結婚できないとなると、別の女性と結婚。
時が経ち、以前に恋した奥さんがその気になった時、また離婚して結婚。
それも恋した奥さんの主人はマクドナルド店のオーナー。
ハチャメチャな行動もレイ・ロック氏はきれい事のように書いています。
確かにレイ・ロック氏は逆境に遭ってもそれを乗り越えていく力を持っています。
50歳を過ぎてから冠たるマクドナルドチェーンを築き上げました。
そこのところが柳井氏や孫氏が尊敬するところなのかもしれません。
でも、私とは「観点」と言うか「感点」が違うのでしょう。
そして、そこがビック経営者になれないところなのでしょう。
結婚記念日
今月の22日は「いい夫婦の日」です。
最近知ったのですが、私達夫婦の婚姻届がこの日になっていました。
11月22日が私達夫婦の結婚記念日なのです。
私共夫婦が結婚した時、色々事情があり、結婚式はなく、結婚祝賀会が3回ありました。
1回目は妻の友人達が中心の祝賀会。
30人位の友人が新宿の喫茶店を貸し切り、祝ってくれました。
2回目は当時の私の勤務先である銀行の2階会議室で行われた銀行の仲間達だけの祝賀会。
この時、50人ほどの仲間の前で、支店長と次長に婚姻届の保証人欄にサインしていただきました。
その婚姻届を提出してのが11月22日だったのです。
当時は「いい夫婦の日」なんてなかったので、偶然の一致です。
3回目は家族・親戚だけの祝賀会。
最近になって戸籍謄本を見てわかりました。
今まで40年間、結婚記念日を祝ったことはありませんでした。
でも今年は初めての結婚記念日を2人で祝います。
これから近くの美味しい寿司屋さんに予約を入れます。
チョット照れくさい気がします。
優しい日本
昨日ある会合があり、参加しました。
そこで出会った、私より年上の男性Tさんの話です。
以前は東京でプロのフルート奏者として、ラマンチャの男の舞台や歌手の金子由香利さんのバックで演奏したりしていたそうです。
3年前に父親の介護で札幌に戻りました
そのTさんの50年ほど前の話。
学生時代、東京から40日間程かけて鹿児島まで無銭旅行をしたそうです。
ヒッチハイクしたり、知り合った人に食事をご馳走してもらったりして旅を続けました。
よく車に乗せてくれた運転手さんは陸送の仕事をしている人だったそうです。
その運転手さん達からも食事もいただきました。
宿泊先はその土地で知り合った人の家。
それがダメなら駅のベンチ。
旅の中で怖かった町は京都と九州の小倉だったそうです。
特に、小倉では泊まるところがなかったので警察署に行って「ベンチを貸してください」とお願いすると許可をもらえたそうです。
その夜寝ていると、仕事が終わった警察官が日本酒を持ってきて「一緒に飲まないか」と誘われました。
酒好きのTさんは喜んで参加し、5人の警察官と一緒に10本飲み開けたそうです。
Tさんが飲んだのは一升瓶3本。
グデングデンになって寝ました。
今では考えられない、小説の中のような話。
家に帰り、その話を妻に話したところ、妻からも20代の時、北海道を一人旅行していた頃の話が出てきました。
ある駅で夜、ウトウトしていたら、駅員さんが「そんなに疲れているなら奥の部屋で休んだらいいよ」と言われ、休んでいる内に寝込んでしまいました。
気が付いた時はもう朝だったそうです。
寝てる間は何事もなかったようです。
この2人の話は40年、50年ほど前の話です。
今では考えられない、別世界です。
でも同じ日本なのです。
優しい日本。
いつの間にか無くなってしまったのでしょうか。
起業家
昨日、知人が訪ねてきました。
彼は今年の春に起業した人で、私の勉強会にも参加していました。
その彼が11月よりある会社に就職すると報告に来たのです。
彼は独立してから結構苦労していました。
起業家としての勉強をしようと、札幌市が開いていた「起業道場」に参加しました。
起業を目指す人、また起業ばかりの人向けに、起業が成功するように教え励ます講座です。
彼はそこで講師をしていた会社の社長から入社しないかと誘われたのです。
彼は仕事で悩んでいたこともあり、その誘いに乗りました。
私としては、「折角、覚悟して起業したのに」との思いもありましたが、彼にとっては就職もいいのかとも思います。
世の中の景気が良くなると人手不足になり、起業する人が少なくなって来るようです。
残念です。
それにしても起業道場で講師をしいた社長が、講座に参加した人の中から、めぼしい人を自社に入社させる。
少しルール違反な気がします。
どうでもいい話ですが
今朝の妻との会話です。
私の家と会社まで歩いて10分かからないので、いつも昼食は家で食べます。
出勤する時、妻から言われました
「今日は用事があるので、昼食にカレーを準備しておきます
ゆで玉子とラッキョウも添えて置きます」と。
それに対して私が「愛情も添えて置いてください」と言うと、「それはありません」のとの返事。
でも、先程食べたら、ちゃんと隠し味としてありました。
妻のカレーは旨いのです。
海外資産
日本の財政が赤字で、借金が1,000兆円を軽く超えています。
そのことについて、ある政治家が言っていました。
「大丈夫です。日本は海外に600兆円の資産を持っています。」と。
あれ?その600兆円は政府のお金ではないでしょう?
民間のお金です。
ゴッチャにしているようです。
その海外にある民間資金もいざという時は頼りになります。
6年前の東日本大震災の時、日本の経済はダメだと思われ、一時円安が進みました。
日本からお金が逃げていくだろうと思われました。
確かに1次的には大幅な円安になりましたが、すぐに円高に変わりました。
それは海外に資産を持っていた日本の企業が日本再建のために資金を戻したためでした。
日本が危機に陥った時、国民も企業も一致して再建に動いたのです。
勿論、企業ですから投資物件としてみていたのも確かです。
でも、海外に資産を分散することは、リスク分散になっています。
企業の内部留保が政治問題になっていますが、別の見方も出来るのではないでしょうか?
フェイクニュース
今朝の朝刊に「フェイクニュース対応策討議」という見出しで、日本新聞協会の新聞大会が開かれた記事が掲載されていました
ネット等でフェイクニュースが流されていることへの問題が提起されています。
その記事の中で日経新聞の社長が「有料メディアが記事の分析力で違いを際立たせることで競争力を持たせることが大事だ」と述べています。
私は新聞報道にはあまり信頼は置いていません
「事実」を正確に報道していていても、それは「真実」ではない。
今の報道では、新聞社の主義主張が先に立ち、切り口が独善的になっています。
新聞社は記事対象の全体像や背景を正確に伝え、その上で分析を進めるべきです。
例えば「円柱」の物体を説明するとします。
ある新聞社は真上から見て、これは丸い円であると主張します。
読者は円形のボールみたいな物体と想像します。
ある新聞社は真横から見て、長方形であると主張します。
読者は羊羹のような長方形物体だと思います。
どちらの新聞社も「事実」としては正しい主張です。
しかし正しい「報道」とは、まず全体像の円柱であることを示さなければなりません
その上で様々な切り口で分析する。
そして1つの切り口ばかりでないことが重要です。
そのような報道姿勢が新聞に対する信頼が生まれます。
私はそう思います。
青臭いことを言うな!
青臭いこと言うな!
大人になれ!
若い頃に言われた言葉です。
「正しいことをしましょう!」と言った時に言われました。
最近、また大企業の経営・運営に関する不正が新聞等で取り上げられています。
東芝にしても神戸製鋼にしても、一流と認められた会社です。
優秀な大学を卒業し、頭もいい人達が集まった会社でもあります。
その会社が不正行為を長年続けてきた。
誰も「正しいことをしましょう!」と言わなかったのでしょうか。
もしかしたら正義感に燃えた社員がそう言ったのかもしれません。
それに対して「青臭いことを言うな!」と言われたのかもしれません。
稲盛さんが言われる「損得で考えるのでなく、善悪で考えなさい」の言葉が頭に浮かびます。
また、「人生の成功方程式=考え方×熱意×能力」も浮かびます。
優秀な大学を卒業するほどの才能があり、熱意を持って一生懸命仕事しても、考え方が悪いとその結果は取り返しがつかないものになります。
不正が行われる企業は大企業より小企業や中企業の方が起きやすいと思います。
社長の考え方一つでどのようにも変わっていくからです。
しかし現在、不正を許さないという眼は到る所にあります。
お客様、仕入れ業者、社員、そして世間が見ています。
これからの経営者は身を正した経営をしなければ淘汰されていく。
それを良く自覚しなければなりません。
毎日の仕事
我が家の近くを通る幹線道路
それに沿った歩道の改修工事が続いています
傾斜し凸凹していた歩道。
その傾斜を直し、カラーブロックを敷き直しています。
我が家の近くはやっと終わりきれいになりました。
今日の昼1時頃、そこを通った時、私の前を歩く年配の女性が休憩を終えたばかりの若い作業員に「ありがとうね」と声を掛けました。
改修し、きれいになり、歩きやすくなった歩道に満足し、つい声を掛けたのでしょうか。
その時、若い作業員は反射的に大きな声で「はい!」と応えていました。
素直に「はい」と応えたその姿。
ビックリした様子。
道路工事はそこを通る人には不便を掛けます。
文句を言う人もいます。
そんな時に「ありがとうね」と言われたら嬉しいと思います。
杖をついていた年配の女性。
ゆっくり、そしてしっかり歩いていました。
当たり前にしている毎日の仕事。
それを見ていてくれる人がいる。
そう思うとやり甲斐がありますね。
講座が終わりました。
「作ってみようカフェの事業計画書」の講座が昨日で終わりました
最終日には日本政策金融公庫の創業支援のセンターの所長さんにも参加していただき、受講者の方々に事業計画を発表をしていただきました。
初めての事業計画書を作られた割には皆さんしっかり作られていたのには感心させられました。
すぐにでも実行に移せるほどに考えられた計画もあります。
講座は4日間。
夜の7時から9時まで。
皆さんは熱心に受講されました。
私もまた新しい出会いと情熱をいただきました。
感謝です。
高いモチベーションを維持するために
社長は常に高いモチベーション維持が求められます。
社員は社長の顔色を常に気にします。
今日は機嫌がいいのかな?悪いのかな?
でも、それでは社員の仕事への意欲に影響を与えてしまします。
また社長自身も自己管理上、心身ともベストの状態でなければなりません。
しかし社長も人間です。
気持ちが落ち込むこともあります。
マイナス思考に陥ることもあります。
そのような時、あえてモチベーションを高める為に、私がいいと思っている方法があります。
褒めてもらうことが第一。
「あなたはツイているから大丈夫よ」とか「あなたの仕事はとても素敵です。」 と言われるだけでもいいのです。
お客様から褒められる。友達から褒められる。
また、家族の中で褒め合う習慣。
ご主人や奥さんから褒めてもらうこと。
これが一番。
褒めてもらうために一生懸命仕事をします。
次には、他の人が褒めてくれなければ、自分を自分で褒めます。
それも声に出して褒めます。
落ち込んだ時こそ、自分で自分を褒めます。
他の人も褒めて上げます。
そうすれば相手は決して嫌な思いはしません。
あなたのファンになり、あなたに会いたくなります。
明るく、愉しく、元気なあなたに、お客様が会いに来てくれます。
そうするとあなたも嬉しくなります。
お客様に喜んでもらうことを考えてみます。
そうするとワクワクする気持ちがわきます。
上手く行くからワクワクするのではなく、ワクワクするから上手く行くのです。
私はそんな思いで、まずは妻を褒めています。
効果ありますよ。
域際収支
域際(いきさい)収支というのをご存じでしょうか。
私は知らない言葉でしたが、ネットで調べると「国内の地域間の財やサービスなどの取引における収入・支出関係を示すもの」と書かれています。
先日の新聞に北海道の域際収支は年間1〜2兆円の赤字だと書かれていました。
北海道が各地に出す農産物や魚介類、それに各製品・商品を売っていただくお金より、他地域から購入するに使うお金が多いと言うことです。
貿易収支の赤字と同じようなモノ。
北海道は農産物や魚介類が豊富であっても、価値を生み出す製品作り・商品作りがまだまだ遅れている。
改めて知らされました。
時差ボケ
先週の水曜日にスペインから帰って1週間。
いまだ時差ボケから抜けられないようです。
夜は10時に寝て、朝はいつものように5時30分に起きています。
睡眠時間は十分取れているはずなのですが、午前中フッと眠気がきます。
本を読んでいても10分ほどで目を閉じています
ブログを書いていても進みません。
私のこの時差ボケの状況を見ると、世界中を飛び回っているビジネスマンはすごいです。
時差ボケを克服しています。
私の場合、緊張感が足りないのかもしれませんね。
マヨリカ島より
21日にスペインのマヨルカ島から妻を連れて帰ってきました。
私は1週間ほどの旅行でしたが、妻は1ヶ月間娘の家に滞在。
娘の出産の手伝いでしたが、生まれた孫に少し懸念されることがあり、孫だけそのまま入院。
朝と夜に病院に通う娘に代わって、2歳の孫の面倒を見ていました。
それでも私が滞在している間はマヨルカ島のホテルに宿泊し、時間を見ては市内観光をしました。
マヨルカ島には日本人ばかりでなく、東洋人はほとんど見かけません。
片言の英語で買い物をしたり食事をしたりスペインの時間を楽しみました。
滞在最後の日にはイギリスから婿さんのお母さんも来て食事会。
美味しいスペイン料理でした。
帰国する日、LINEに娘から孫の「はな」が無事に退院したという連絡ありました。
私は「はな」に会えなかったけれど、それを聞いて一安心。
この旅行のためにWifiのルーターを買いました。
グローカルネットという名前のルーターですが、使いよく、これがあったので妻や娘と絶えず連絡を取ることが出来ました。
16時間使用できるという持久力も頼もしいです。
今回は行く時は私1人。
帰りは妻と2人。
この旅で、これからは人に頼らず、2人で海外に気軽に行ける自信が付きました!?
次は長女の住むスエーデン。
自分をコントロールする
先程、ビックカメラで買い物をしていた時のこと
私の近くにいた若い女性が店員さんに向かって言う言葉がすごい!
女性から質問された店員さんが満足に答えられなかったからなのでしょう
「そんなことも分からないの!」「ビックカメラには分からない人ばかりね!」と威圧的な言葉を発していました
「人にそんな言い方するの?」と思い、ついその女性の顔を見ました。
まだ10代か20代初めの若い女性です。
言われている店員さんは40歳代?
客商売とは言え、自分の娘みたいな女性から罵倒されかわいそうになりました。
その若い女性は、お客という立場から、威圧的な話し方をしても当たり前と思っているのでしょうか。
でも何か違う気がします。
会社で、人を呼ぶ時、必ず「○○さん」とさん付けする人がいます。
たとえ年下に対してでも、部下に対してでもです。
「○○」と名前の呼び捨てや「○○君」ではないのです。
若い社員に対して「○○さん」と呼びかける上役は必ず部下に慕われています。
さん付けされた部下は、自分は大事にされていると思います。
大事にされていると思うとその人を尊敬します。
そしてそのような上役はリーダーシップを発揮することが出来ます。
皆の心を捕まえているからです。
細やかな心遣い。
それが出来るのは自分をコントロール出来ているから。
自分の心をコントロール出来るか出来ないか
これは大切な事です。
私も苦労しながら頑張っています。
出産
先程、スペインにいる妻からLINEがあり、三女に女の赤ん坊が無事に生まれたとのこと。
ほぼ予定通りの日です。
三女にとっては2人目。
写真が送られてきたのですが、イギリス人の旦那に似ているようです
髪の毛は既に生えていてブロンド。
上が男の子で2歳になります。
この子は私に似ているようです。
特に足の長さが短いところが。
それがまた可愛い。
三女の入院は1泊だけ。
すぐに家に返されます。
出産は病気でないのですね。
その代わり、旦那は1ヶ月間育児休暇がもらえます。
旦那はとても「家族大事」な人なので、家事や子供の世話をドンドンするようです。
折角行っている私の妻の出番がありません。
来週、妻を迎えに私もスペインに行きます。
孫達に会えるのが楽しみです。
お祭り
9月3日4日は地元、琴似神社の秋祭りでした。
3日は宵宮、4日は本祭り。
その本祭りのメインイベントは神輿行列。
私も裃を着て参加しました。
参加した人の多くは私より年配者
参加するのが愉しそうです。
しかし一方、若い人があまりいません。
若い人がもっと参加しなければ伝統行事の引き継ぎが上手く行くのか。
それが心配です。
神輿を担ぐ地域では、担ぎ手がいないと問題になっていると聞きます。
お祭りは皆が愉しい気持ちになります。
しかし今は、参加するというより、見物する気持ちの方が強いのではないでしょうか。
私の小・中学校の頃、この祭りの間は学校も地元の会社も休みになり、皆で祝った記憶があります。
会社の若い人達は祭りの手伝いに出かけます。
家では母がちらし寿司を作っていました。
祭りは日本の文化でしょう。
そして地元の神様を大切にする事で、地域の結びつきも強くなっていきます。
いつの頃からかでしょうか。
参加する祭りでなく見物する祭りに変わったのは。
「宗教の自由」という建前と束縛がそうさせたのでしょうか。
これから地域の伝統を守る事ができるのか。
心配です。
それにしても母が作ったちらし寿司を思い出しました。
食べたいです。
作詞の勉強本
たまたま本屋で見付けた「作詞の勉強本」を読んでいます。
私は作詞家になるつもりはありませんよ。
ただ面白そうだから買いました。
この本の最初の方に面白いことが書かれています。
作詞の基本は出来るだけ多くの人に共感してもらえるような詞でなければなりません。
オリジナリティは大事ですがそれに固執すると「目線が」狭くなってしまいます。
人と違うモノを求めて、奇をてらったモノがオリジナリティと勘違いしてしまう。
そういうことが多い。
この筆者が作詞する時に心がけているのは
①自分以外の人が聞いても感情移入してもらえるか
②第三者の立場に置き換えて聞けるかどうか
③自己満足ではなく、多くの人々を相手に出来ているか
④自分の書いた歌詞に自分自身が共感・感激できるか
これを読んだ目にした時、経営に近いモノを感じました。
言い換えてみると
①多くの人に喜ばれる商品なのか。
②お客様の立場になって商品を作っているか。
③自分の執着から抜け出した商品か。
④まず自分が惚れ込むことの出来る商品なのか。
この4つは経営者が心するべきポイントだと思います。
この本をもう少し、しっかり読んでいきます。
お客様を見付ける方法
私の三女が9月に2人目を出産するので、妻が三女のところに行っています。
この三女は独身時代にJICAの青年海外協力隊の隊員として中南米のホンジャラスに3年ほど活動していました
彼女は針灸・指圧の国家免許を持ているので現地でその指導をしてきたようです
ホンジャラスでは針灸は出来ないので指圧やマッサージの技術を教えてきたそうです。
JICAから指導されている事ですが、彼女が心がけたのは、現地の人が指圧やマッサージの技術を身に付け、自立する為の方法を教えたことです。
大事なのはその人に食べ物を与えるのではなく、自分が食べ物を得るために自立できる方法を教えることです。
同じようなことが私の周りにもあります。
経営者の中には中々仕事が上手く行かず困っている人がいます。
話を聞いてみると、「誰かお客さんを紹介して欲しい」という話が多いです。
そのような場合、誰かを紹介してもまた「他に誰かいませんか?」となります。
それではいつまで経ってもその経営者の会社は良くなりません。
大事なのはどのようにして新しいお客様を見付けることが出来るか。
その方法を学ばなければならないのです。
それを学ばなければ会社の発展はありません。
その方法さえ知れば、ドンドン新しいお客様を開拓したり発掘したり出来ます。
当たり前のことなのにその方法を知ろうとしません。
いつまでも食べ物を求めてばかりになります。
先程のホジャラスでの例のように、食べ物をもらうのでなく、食べるための方法、技術を身に付けなければならないのです。
Jアラート
今朝のJアラートにはびっくりしました。
私はその時には起きていたのですが、携帯電話に流れてきた音は不安感をかき立てる音がしました。
すぐにテレビを付けました。
NHKは速報が流れていましたが、民法はのんびりコマーシャル中
「1秒でも早く知らせなければならないのに」という思いがしました。
不思議な思いをしたのがもう1つ。
日本の上空をミサイルが越して行き、日本がその当事国なのに、「円」が買われて円高になっています。
日本の安全に不安を抱き、株価は下がっているのに、円は逆に高くなっているのです。
その理由を経済アナリストは「ドルを売って安全な円買いに進んでいるから」と言います。
その矛盾は何?
為替の世界では不思議なことが起きています。
炒飯屋
皆さんは急に「炒飯食べたい!」と思ったことはありませんか?
元々私は炒飯が好きでしたが、先週の金曜日になぜか急に「旨い炒飯食べたい!」思う気持ちが高まりました。
早速、ネットで近くにある旨い炒飯の店を探しました
ありました!
自宅から歩いて30分ほどのところに「炒飯屋」という店を見付けました。
土曜日に運動もかねて徒歩で、勇んで出かけ、11時30分開店の5分前に到着。
店の前には既に車で来た人達の車が停まっていました。
私はすぐに玄関の前に立ち、開店と同時に入店。
早速、一番人気という焼豚炒飯を注文しました。
お腹がすいていたので大盛で。
注文から10分かからず炒飯が出てきました。
その炒飯を見て少し驚き。
「多い!」「食べれるか?」
食べ始めると、ご飯は少し固めでパラパラ。
本来の炒飯の食感。
味も深く、塩も少なめ。
スプーンで掻き込むように食べました。
しかし案の定、半分くらい食べたところでお腹がいっぱいになって来ました。
「食べ切れるか?!」
そんな不安が・・・
でも「大盛りを頼みながら、残すのは恥ずかしい」
そんな思いから、お腹に「まだ入れるぞ」と言い聞かせながら食べ続けました。
炒飯と一緒に出された大椀に入った豚汁。
旨いのですが、飲み干す余裕がありません。
店員さんに聞くと、並盛りで米1合。
大盛りだと1合半。茶碗3膳分あります。
注文する時に聞いておけば良かった!
これからは、いくら好きなモノでも大盛りはもう止めよう!
そう思いました。
それにしてもこの店、炒飯しかありません。
焼豚炒飯の他には、高菜炒飯、海鮮炒飯、かに炒飯、ガーリック炒飯があります。
また炒飯が食べたくなったらこの店に来ようと思います。
ラーメンが食べたくなったらラーメン屋。
スープカレーが食べたくなったらカレー屋。
そして炒飯が食べたくなったら炒飯屋と思うのですが、炒飯専門店という店はあまりないのではないでしょうか
これから炒飯専門店。
流行るかもしれませんね。
それにしてもこの店、11時30分開店なのですが10分ほどで、席テーブル、カウンター席が一杯になりました。
人気があります。
役得
昨日の勉強会で「公私のけじめを大切にする」と言うことが題材になりました。
会社の中では一般社員も仕事によっては「役得」が発生します。
営業マンは出張の時に飛行機を使えばマイレージが貯まります。
貯まったマイレージを私的利用が出来ます。
出張のない社員にしてみれば羨ましいことです
仕入担当の人は業者からの盆暮れの贈り物や接待の誘いがあります。
「これも仕事だ!」と言って、飲み歩く人もいるかもしれません。
それらの「役得」が個人の「得」に結びつくと問題が起きます。
1人1人が「利己」に陥ることなく、心して行かなければなりません。
その時こそ、会社のトップたる社長が手本を見せなければなりません。
社長の接待費の公表。
社長の行動予定の公表。
公用車を私的利用をしない等あります。
「役得」を自分が勝ち得た権利だと勘違いをする。
大きな間違いです。
「野にして粗だが卑ではない」
卑なる人間にはなりたくありません。
リスク対策
「金」についての話です。
中国人やヨーロッパの人達は「金」を保有する人が多いと聞きます。
過去に戦乱があった国の人達は、いざという時の「金」の大切さを知っています。
家族が少なくとも1ヶ月間は暮らせるだけの金貨を手元に置いておくという話も聞きます。
国民1人当たりの金保有量ではスイスが世界で一番です
永世中立国として自立するスイスらしいと言えます。
それに比べ、金や金貨を保有している日本人は少ないのではないでしょうか。
そして、リスク対策においては日本人はその意識が薄いように思います。
朝鮮半島で起きている事は、いつ日本の有事となるか分かりません。
日本の財政もいつ破綻するかも危惧されています。
それらは全て日本人1人1人に関わった来る大きな災害です。
今、私達がするべきことは、自分の会社、自分の家族を守る為に何が出来るか。
金を買うこともあるかもしれません
しかしそればかりではありません。
何をしなければならないか。
そろそろ考えておく必要があるように思います。
日本人1人1人が自分でしなければなりません。
誰も最後のリスクは負ってくれません。
ふるさと納税
「ふるさと納税」について。
今朝の新聞に「ふるさと納税」の額が減少しているとありました
総務省が高額返礼について待ったを掛けたため、それを目当てに寄付する人が減ったためだそうです。
平成20年に始まったこの制度は「遠く離れた自分のふるさと」や「好きな町」を応援しようという趣旨で始まったはずです。
それがいつの間にか高額返礼を目当てに寄付をするようになり、その為のHow to本まで出ているようです。
ふるさと納税は、希望する人が自発的に、「支援したい」「応援したい」という思いで、自分で選んだ自治体に寄附金を送るという制度です。
偉そうなことを言うつもりはありませんが、今の現状を見ると少し情けないという思いがします。
高額返礼を廃止し、お礼状だけにした時、どれほどの人が寄付をするでしょうか。
その時に初めて日本人の志のレベルが分かる気がします。
自分史
先日、街を歩いていると、「自分史を作ります」という看板を見付けました。
「自分史」とは自分の過去の事柄をまとめて本にすることです。
歳を取り、そろそろ人生も終わりかなと思って、自分の過去の事柄を書き残しておこうということなのでしょう。
普通の人が「自分史」作りをするようです
子孫達に自分の生きた証を残すことが願いなのでしょうか。
私は作ろうとは思いません。
子孫にとっても迷惑な話だと思います。
そんな親や爺さんの「自分史」を読みたいとも思うはずもありません。
会社を創業し、実績を上げた創業者が生前に自分の銅像を造ろうとした話も聞きます。
あまり好きではありません。
人が生きている間に成したことは、たいしたことは無いと思います。
それでも他者がその人の功績を評価してくれた時、その人の名前は残るのでしょう。
市井の人の1人として、するべき仕事を一生懸命し、正しく生き、死んで行く。
それが一番いいのだと私は思っています。
亡くなった永六輔さんは「人は2度死ぬ」と言ったそうです。
1つめは肉体的な死。
2つ目の死は、その人が生きていたということが忘れられた時だそうです。
自分史作りや銅像造りは2つ目の死を恐れたからなのでしょうか。
私は忘れられてもいいと思っています。
法事の時やお盆の時、思い出してくれれば、それでいいでしょう。
それも思い出してくれるのはせいぜい私の子供達だけ。
それ以上はいいです。
きれいに死んでいく。
それも1つの生き方だと思います。
アプリ
iphonに新しいアプリを入れました。
その中でも「Google翻訳」にはびっくりです。
このアプリは音声機能付きで、iphonに向かって日本語で話すと、それがそのまま「英語」や「スペイン語」の音声になって出ます。
写真機能も付いているので、写真で撮った外国語の文章が日本語訳に変換されます。
勿論正確な翻訳ではないのですが、それなりに分かります
レストランのメニュー内容くらいは分かるのではないでしょうか。
これがあれば海外に行っても便利でしょう。
一方、海外に行った時、iphonが常にネット出来る状態でないと「Google翻訳」は使えません。
色々なところに流れている無料WiFiもあるのですが安全性など考えると少し心配です。
そんな時、「グローカルネット」という会社のWiFiルーターを見付けました。
国内は勿論、世界中111カ国、複数のキャリアが利用できるWiFiルーターです。
買い取りのルーターですが、連続14時間使えるのが魅力的です。
このWiFiルータがあれば常にLINEが使えます。
LINEで通話も出来ます。
私の知らない便利なアプリやグッズが沢山あるのですね。
妻の不在
来週から妻が1ヶ月ほど家を空けます。
その間は私、独身生活となります。
今まで家事については一切妻任せなので、ゴミ出しの日や洗濯機の使い方が分かりません。
いま妻がそれぞれの引継書を書いてくれています。
食事はあまり外食を好みません。
家で食べるのがいいのですが、私は料理が下手です。
どんぶりご飯に缶詰のサバ煮を盛り、インスタント味噌汁で食べます。
インスタントカレー、牛丼などもいいですね。。
1ヶ月後にはやせているのではないでしょうか!
丁度ダイエットしなければと思っていましたので、グッドタイミングです。
掃除は大丈夫です。
トイレ掃除は毎日しています。
平凡な日常
盆休みも終わり、今日から出社しています。
約1週間の休みは長すぎたようです。
体重も確実に1キロ以上増えました。
今日から毎日の当たり前の生活を始めています
8月15日の終戦記念日
日本を取り巻くきな臭い情勢。
そのような状況の中でも平凡ながら平和な日常。
ありがたく感じます。
お盆です
昨日息子家族が我が家に来ました。
男の孫2人元気です。
明日から私も盆休みに入ります。
予定は特になし
今夜から飲み会が続くのか
ツキと幸運
ある本に書かれていた言葉です。
「素早くやってくる富は、素早く離れてしまう。」
宝くじなどで1億円当たった人も、なぜか不幸になってしまうという話を聞きます。
長くとどまって持ち主に喜びと満足をもたらす富は少しずつやって来ます。
小さな富を重ねることを長年続けることで大きな富になります。
もう一つ
「何の努力もしないで、ものすごく望ましいことが現れる。
それを幸運だと思ってはいけません。
それは幸運では無く、単なるツキです。」
ツキはいくら望んでも引き寄せることは出来ません。
幸運は何か行動を起こし、努力した後にやって来ます。
その時、引き寄せることが出来ます。
虫歯
久しぶりに歯科医院に行ってきました。
かかりつけの歯科医院で、従兄弟が先生です。
以前に彼から歯磨きの指導を受けて、それを守っているので歯槽膿漏の心配はありませんでした。
ところが3日前から歯茎が腫れ、歯ブラシすると血が出ます
心配をしながら看てもらうと、磨き過ぎとのこと。
歯槽膿漏はありませんでした。
しかし、虫歯が3カ所にあるのを発見!
少し驚きでした。
何年も虫歯にはなっていませんでした。
原因は何か!
思い当たることがあります。
最近、夜に妻と好きなミステリーを見るのですが、その時に煎餅等のお菓子を食べるようになりました。
原因はこれしかありません。
しっかり歯磨きをするのですが、糖分が残っていたのでしょう。
今日からは煎餅を食べるのを止めようと思いますが、知人からいただいた煎餅が大きな缶に沢山に入っています。
妻1人に食べさせると妻も虫歯になりそう。
さて、どうしたモノか!?
デジカメ
長年使っていた小さなデジカメ。
このカメラで撮った写真に黒点が1つ。
最近気付きました。
レンズにゴミでも付いているのかと思って、レンズを拭いたのですがとれません。
カメラの内部の問題のようで、直せないようです。
先程、近くのヤマダ電機に行って見てきたのですが、ポケットに入るような小さなデジカメは5種類くらいしかありません。
展示されている多くは一眼レフの高級カメラばかり。
スマートフォンのカメラの性能が良くなり、従来のポケット式デジカメに取って代わったようです。
私はどうもスマートフォンのカメラは良く使いこなせません。
ついデジカメに行ってしまいます。
今度の休みに札幌の街に行った時、デジカメを買おうと思います。
1万円位。
お小遣いで買えそうです。
幸せを感じる
いつもマイナス思考で話す人がいます。
そういう人は、小さな嫌のことを探すのが上手い人です。
身の回りの嫌なこと、苦しいことを探し出します。
一方いつもプラス思考で明るい人は、小さな嬉しいことを探す人です。
夕食のおかずは好物のハンバーグがあった。
幸せだ!
いつも電車で会う人と今朝初めて挨拶が出来た。
幸せだ!
今日はミス無く仕事が出来た。
幸せだ!
身の回りで起こる小さな嬉しいこと、愉しいことを探し出せる人のところに幸せは来ます。
それがその人に良き「運」を運びます。
とても単純なことです。
「人生はそんな単純なモノでない!」と言う人もいます。
でも私は単純だと思います。
不幸だと思う人は自分で複雑にしているだけです。
いいと言われることを素直にしてみようと思うことが大切です。
信じなくてもいいのです。
最初は信じなくても、大事なのは「やってみようか」と思うことです。
思うことが大事です
思って、実際にやってみる。
そうすると「アレ!これはいいかも」と思います。
会社からの帰りに、いつも通る道だけれど、信号が青ばかり続く。
「これは運がいいぞ」と感じてみてください。
家に帰れば奥さんがいて、夕食の支度をしています。
「ありがたいな!」と思います。
そうすると自然と優しい言葉を奥さんに掛けます。
「ただいま。美味しそうな夕食だね」
奥さんは「あれどうしたの?」と驚きながら笑顔を見せてくれます。
そうするとまた嬉しい気持ちになります。
今、この世に生きている人は皆さん運がいいはずです。
生きているだけで運がいいのです。
ありがたいと思ったら自然と手が合わさっています。
寝る時に布団の中からでも、手を合わせて「今日も1日ありがとうございました」
ぐっすり寝られるはずです。
人手不足
今、人手不足で嘆いている会社が多くあります。
10年前は就職難といわれ、就職先がないと言われていました。
嘘のようです。
人は歳を取ります。
いくら有能な人でも、ある年齢になると会社を離れていきます。
その人は長年会社に貢献してきた人達です。
その代わりになる人を急に探そうとしても無理です。
人材紹介会社から紹介されてもそうそういい人はいません。
10年先、20年先を見定めて人の採用と教育。
これは社長の仕事です。
そして社長しか出来ないことです。
社長が目先のことばかりに捕らわれていると取り返しがつかなくなります。
経営、営業、採用、教育。
全てにおいて必要なのは大局観。
これから人手不足が益々激しくなるのか。
または、不況になり、人余りが起きるのか
分かりません。
でも大切なのは「時代に流されない経営」。
そう思います。
細心にて大胆
「細心にて大胆」
経営者に求められる資質の1つです。
裏付けや分析・仮説を繰り返し、成功するための方策を探り、60〜70%見込みありと判断したら、思いっきり挑戦する。
そして始めたからには躊躇することなく突き進む。
一方、これと間違えてしまうのが「小心にて粗暴」です。
判断すること、決めることに不安を覚え、安易な方法を探ります。
常に「失敗したらどうしようか」という自己保身が先に立ちます。
判断が出来ないまま、決断しなければならない時を迎え、大した裏付けもなく目をつぶって決めてしまう。
その後は成り行き任せ。
自分は「細心にて大胆」であろうとしているのに、実際は「小心にて粗暴」なのではないか!?
常に自問することが大切です。
勉強
昨夜は私が主宰する「身丈会」がありました。
私が講師をした「身の丈で起業しましょう」という講座に参加した人達が中心になって、もう6年になります。
毎月1回開いています。
今は稲盛和夫さんが書いた「京セラフィロソフィ」のいう本を読みながら、その感想を述べる内容になっています。
参加する人は、起業した人より一般のお仕事をしている人が多いです。
今の勉強会では、起業に直接結びつく話はあまりしません。
勉強会を開いた当初の起業についての内容から少し変わってきています。
満足した自分の生活が如何に出来るか。
これが大事なことではないかと思っています。
今の自分の環境を少しでも変えたい。
毎日満足して生活を送りたい。
その為に自分をどう変えていくか
その為に学ぶ。
そのような考え方で勉強会を進めています。
人に教えられるより自分で気付く。
この事が大切です。
本を読み、項目別に解説担当者が自分の考えを述べます。
それにより理解が深まります。
そして気付かされることもあります。
自分が幸せになるために自分を変える。
そのための勉強。
それが大切だと思います。
孫
23日日曜日から遊びに来ていた8歳の孫が今日帰京します。
JALの「キッズおでかけサポート」で1人で来ました。
25・26日の2日間。
私達夫婦と孫の3人で旅をして来ました。
初めての孫と旅。
積丹へ行って嫌になるほどウニを食べました。
楽しい旅でした。
この男の孫。
孫自慢になりますが、行動的で物怖じしません。
また集中力がすごい。
「ダレン シャン」という子供向けの本があります。
この本は13巻あり、今は30歳になっている息子が小学生の時読んだ本です。
その本を孫が夢中になって読んでいます。
2日間の旅の間、電車やバスの中で読むふけりました。
2日間で4冊。
一心不乱に読みます。
その集中力は私にはありません。
私はすぐ飽きてしまうタイプです。
誰に似たのでしょうか。
そう言えば、私の妻は絵を描き出したら、私のことも忘れて一心不乱になります。
妻に似たのかもしれませんね。
孫との5日間。
愉しい思い出が出来ました。
作業現場
先日、「新国立競技場建設現場で働く社員が過労が原因で自殺」というニュースが流れていました。
ただでさえ限られた短い工期の中で行われる作業にもかかわらず、設計変更などで現場にしわ寄せが来た結果、残業が月200時間近くあったと言われています。
私共の会社は家具を作っています。
コントラクト家具といわれる家具が主です。
コントラクト家具とは学校や病院、図書館などの公共施設や商業施設などで利用される箱物や椅子・テーブル等のことです。
この家具の納入は躯体工事が終了した工事最終時期になります。
建物の内部意匠についてはオーナー側が一番気にするところで、その最終決定までは変更変更の繰り返しです。
一方、家具の納入日は決められています。
決定遅れのしわ寄せは私共の会社に来ます。
ほとんど制作期間がない中、残業をしてでも完成させることになります。
工程通りにオーナー側が決定していけばいいのですが、そうはいきません。
意匠決定が決められた日より大幅に過ぎてもオーナー側は責任を負いません。
一度決定したことも平気で覆します。
設計者はオーナーの意向をそのまま建築会社に指示します。
建築会社は下請けに指示し、工期だけは変わらない旨伝えます。
負担は下請け会社、そしてその従業員に来ます。
断ることが出来ません。
出来ないと言えば他社に仕事が取られます。
今回新聞記事になった件も、亡くなった社員の所属会社1社では何も出来ません。
仕組みそのものを根本から変えなければ解決できない。
根深いモノがあります。
菓子会社
先日、ある菓子メーカーのT社長と昼食を摂りました。
その会社は北海道でも有名で、名前を出せば多くの人が分かる菓子メーカーです。
食事をしながら、私から何気ない質問をしました。
「お菓子会社の人達はいつも味見や試食して虫歯になっている人が多いと聞きますが実際は如何ですか?」
考えてみれば失礼な質問でした。
T社長によれば虫歯についてはよく分からない。
ただ全従業員の健康診断を見ると、糖尿病の人は1人もいないとのこと。
700名以上いる従業員に糖尿病の人が1人もいないということは少し驚きでした。
そしてT社長は言います。
「最近、菓子は健康の敵みたいなことを言う人がいますが、それは違います。
毎日、菓子を食べている私達がそれを証明しています。
菓子と健康について研究をしてくれる学者がいるといいのですが・・・」
T社長は従業員を大事にする社長です。
従業員全員の健康診断の内容を把握している。
それだけでも素晴らしいことです。
そのような社長は少ないのではないでしょうか。
T社長には色々教えていただきました。
暑い
先週末、札幌も最高気温が30度超え。
夜も暑くて寝られませんでした。
でも昨日から急変し、最高気温が23度。
夜はタオルケットだけでは寒かった。
ビールを飲みたかったのが、突然熱燗が飲みたい。
そんな気候の変化。
もう夏バテ!?
そんな気がします。
先が思いやられます。
皆さんも気を付けて!
ボランティア
同じ仕事をしていても、「生き生きしている人」と「つまらなそうにしている人」がいます。
どうせなら、生き生きと仕事をした方が楽しいに決まっています。
どうしてそのような差が生まれるのでしょうか。
それは、その仕事の意義を「見付けられる」か「見付けようとしない」か
その違いです。
仕事の意義も「誰かのために」という思いが強いとやり甲斐が生まれます。
九州での大雨による大被害。
ボランティアの人達が駆けつけています。
誰かに強制されたわけでも無いのに、炎天下に無償の労働をしています。
誰かの役に立ちたい。
困っている人を助けたい。
そんな純粋な思いで参加しているのでしょう。
頭が下がる思いがします。
被害を受けられた人達が元気を取り戻し、早く日常生活に戻って行かれることを祈っています。
若い頃
若い頃に思った事。
歳を取った現実。
違う事。
いくら食べても太らずスリムだった学生時代。
中年太りに悩んでいる人の話を聞く度に、なぜそんなに太るのだろうと思っていました。
テレビで酒飲みのお父さんが、「酒を飲むとご飯を食べない」と言う話を聞いて、ご飯を食べないで大丈夫なのだろうかと思っていました
今の私。
メタボです。
その原因の1つがお酒を飲むこと。
お酒を飲む時はご飯は食べません。
若い頃に感じた不思議なことを、今になって実体験しています。
お金に関してもそうです。
若い頃、お金持ちになっている人は真面なことで稼いではいないと思っていました。
不正なことをしているという疑惑がありました。
でも社会に出て仕事をしてみると、お金を稼ぐ大変さを知りました。
ズルをして稼ぐお金はあぶく銭。
お金を稼ぐには、真面目に、誰にも負けない努力をし、お客様に喜ばれる商品を売る。
そのような行為の結果としてお金をいただける。
決して不正をしている訳ではありません。
お金を稼ぐことの大切さ。
若い頃に知っていれば、良かったと思います。
それと共に、小さい頃からお金を稼ぐことの大切さを教えることも大事ではないかと思います。
学校での起業教育も必要ではないでしょうか。
配送
ヤマト宅急便がアマゾンの配送契約の見直しというニュースが何ヶ月か前に流れました。
その時から「配送」という業界が「脇役から表舞台に出て来た」という思いがしました。
ネットでモノを買う人が増えことでアマゾンや楽天が業績を伸ばしてきました。
それに伴って「配送」が重要な役割を担ってきています。
「配送」が出来なければ品物がお客様に届きません。
ヤマト運輸がアマゾンとの「配送料金」の見直しと「当日配送」の縮小の意向を打ち出しました。
その為、アマゾンはその対策のため、地域限定の配送事業者と提携を進めていました。
しかし先日のニュースでは配送トラブルが発生しているそうです。
品物が確実に届くには、長年蓄積されたノウハウと信用がベースにあります。
簡単に代替は出来ないと思われます。
以前に読んだ「宅急便」を創った小倉昌男さんの「経営学」に書かれていたことです。
昭和30年頃から百貨店の配送業務が運送会社にとって大きな売上の割合を占めていました。
しかし運送会社とデパートとの関係は上下関係でした。
特にヤマト運輸と三越との関係は隷属的関係だったようです。
その関係に耐えきれず、ヤマト運輸は昭和53年には三越との配送契約を解除し、それを機に宅配事業に進んでいきました。
今は配送会社とアマゾン等の依頼会社との関係は対等となっています。
しかしもしかすると、これからは配送会社が依頼会社の業務の生命線を握るようになるのではないでしょうか。
宅配会社が持っている配送関するノウハウはアマゾンのような依頼会社が簡単に創り上げられるモノではありません。
そして日本では益々高齢化社会になっていきます。
個人向け配送の割合は益々増えるでしょう。
そう言えばセブン&アイ・ホールディングスとアスクルがネット通販で提携するという話があります。
「配送」を軸にこれから世の中が変わってくるのではないでしょうか。
半袖出勤
今日の札幌の気温は32度になりそうです。
今年初めての真夏日です。
出社時はいつもネクタイとスーツなのですが、25度を超したところからノーネクタイ。
30度を超した今日は、上着なしの半袖のYシャツになりました。
いつもはスーツの上着には財布、手帳、ペン、名刺入れ、キーホルダー、それに車のキーを入れています。
上着がない今日は困りました。
入れるところがありません。
仕方が無く、ブリーフケースに入れ出勤。
いつもと勝手が違う。
市内を歩き回る時、いつもは何も持たないで出かけるのに、今日はブリーフケース持参。
慣れないせいか面倒です。
今、気付きました。
自宅に車のキーを忘れてきました。
会社においてある車。
今日は乗って帰ろうとしたのに。
これから合い鍵探します。
1人
先日妻から言われたことです。
人は生まれる時は1人、死ぬ時も1人。
「結局、人は1人」なのだと一般的に言われています。
確かに「1人」なのですが、1人で生まれてこれるわけではありません。
生まれる時は母親のお腹を痛めて生まれてきます。
死ぬ時も、「1人」で死んだからと言っても、その後始末は誰かがします。
「1人」で生きていくといっても誰かのおかげで生きている。
そんなことを改めて教えられました。
新幹線
新幹線が2016年に函館まで開通しました。
2030年頃には札幌まで延伸される予定です。
その新幹線、私が所有する土地の地下を通っていくようです。
当初は地上に高架を掛け、そこを通る予定でしたが、最近地下を通すと決定になったと新聞報道がありました。
ホッとしています。
地上を通ると土地が分断されます。
その関係でしょうか、先日地盤調査会社の人が訪ねてきました。
地質調査をしたいのだけれど、その許可をもらいたいということ。
特に問題ないと思い許可した。
ところが先程「来週調査をします」との電話がありました。
チョット待って!どこに、どのような調査をして、どれ程の期間かかるのか。
何も示さず工事すると言います。
納得しないので、もう一度調査実施資料を持って説明して欲しいと話しました。
今日の午後から来るようです。
決してごねるつもりはありませんが、手順を踏んで進めてほしいものです。
地下に新幹線が走ると何か影響があるのか。
それも気になります。
女性経営者
最近、豊田真由子衆院議員の騒動がテレビなどで音声を伴って紹介されています。
聞くに堪えない罵詈雑言。
これは豊田議員個人の資質の問題でしょう。
ただ、この話題が出てきた時、思ったことがあります。
現在、多くの女性が政界や経済界にドンドン出て来て活躍しています。
起業の世界でもマムプレナーといわれるお母さん起業も増えています。
とてもいいことだと思います。
もっと増えて欲しいと思います。
ただ一部ですが、残念だなと思う人がいます。
「男に負けない!」という意識が強くて、言葉遣いや態度も男性化してきている人がいます。
折角頑張っているのに勘違いして、女性としての長所を生かしていない。
そのような気がします。
以前、私の会社で仕事をしていた女性常務。
一時私の上司でした。
この常務は仕事に対しては厳しいのですが、言葉遣いは丁寧でした。
常務が部下に指示した仕事。
その仕事の報告に来た部下に対しては、「ありがとう。助かりました」と必ず言います。
この常務の実力は他の男性役員も一目置いていました。
何か問題があると相談に来ていました。
いつも優しく応対してくれるからです。
女性の優しさは男が真似できない武器です。
この武器をみすみす放棄している女性政治家や経営者は勿体ないことをしていると思います。
大分昔に聞いた話ですが、アート引越センターの寺田千代乃社長はバレンタインデーの時、全男性社員にチョコレートを渡すという話を聞いたことがあります。
義理でもチョコレートをもらうと嬉しいモノです。
バレンタインデーにこのようなことが出来るのは女性社長だからです。
女性の良さを発揮して欲しいと思います。
決断
今朝の日経新聞の一面に「国民皆保険による医療」と題された記事が載っていました。
日経が実施したアンケートによると、医師の半数が国民皆保険は今後維持不能と考えているようです。
医療費が高度化して薬剤などが高額になっていることと、急激な高齢者の増加にその要因があります。
国民医療費は2015年度で概算41.5兆円、2025年度には54兆円になる見込みです。
54兆円とは日本の歳入とほぼ同じです。
このままでは8年後、日本の歳入のほぼ全てが国民医療費に消えてしまうのです。
と言うことは、確実に2025年より前に国家の財政破綻に陥ることが予想されます。
今こそ国民と政治家の大きな「決断」が必要となってきます。
「決断」とは将来、そして全体を見て、たとえ犠牲が伴っても最適と考えることを実行することです。
その時は必ず反対やそれによって救われない人が出てきます。
それでも実行しなければならない。
それが「決断」です。
昔、農業が主要産業だった頃、治水事業がその土地の領主の大きな仕事でした。
当時の治水工事には限界がありました。
たとえ洪水の対策をしていても、ひとたび大雨が降れば洪水は起きます。
大雨が降り、洪水の恐れが起きた時、領主は重大な「決断」が求められます。
いかに洪水の被害を最小にするか。
その方法として、川の堤をあえて破るのです。
一番被害の少ないだろうと思われる堤を破り、洪水を起こさせます。
その地域の農民にとっては大きな打撃です。
しかし、国全体をを見れば最適な方法となります。
そこから生まれたのが「決断という言葉です。
「決断」という言葉を、私なりに分解してみました。
分解するとその意味が分かります。
「決」という字は、川の水の意味を持つ「さんずい」、その横に真ん中の意味を持つ「央」があります。
その「央」の左の棒を取った字にさんずいを着ければ「決」になります。
そして「断」という字は堤を切ると断ずることです。
すなわち、「決断」とは川の堤をあえて切って、洪水を起こさせるところから来ていると思います。
文字通り、多少の犠牲を覚悟の上で決めることを「決断」と言います。
反対がない時に決めることは「決断」とは言いません
全ての人の都合がいいようにすることは大事です。
しかし変革する時はそれが出来ません。
決断は批判に負けない強い信念がなければ出来ません。
先程の医療費についても、今まで何度も問題視されてきましたが、解決の先送りでどの政治家も根本的解決の「決断」をしてきませんでした。
今こそ、日本の将来を背負い、つらい「決断」を下す覚悟のある政治家が求められていると思います。
紹介
今日は「紹介」について。
仕事柄、多くの起業家と知り合うことも多くなっています。
その人達を応援する上で、仕事や取引先の紹介も必要なことです。
必要だと思っているのですが、私は中々しません。
以前には多くの人に紹介したことがありました。
しかし色々問題が発生しました。
起業家に仕事や取引先を紹介して上げると、当初は両者とも喜んでくれます。
紹介の後の話し合いは当事者同士に任せます。
しかし暫くすると、紹介した起業家が私を避けるようになっているのです。
そして他の人から「取引はしていない」という噂を聞きます。
両者の遣り方や考え方の相違があり、取引がなくなってしまっているのです。
主には紹介した取引先に問題の原因がある場合が多いようです。
やり取りの途中の状況は私の耳に入って来ません。
紹介した起業家も、一言私に連絡をくれればいいのですが、遠慮してなのか、または私に期待していないのか分かりませんが連絡がありません。
両者によかれと思って紹介しても、結果的に共に避けられるようになるのです。
そんな経験から紹介はしていません。
私に問題があるのかもしれませんね。
人の成長
先日、久しぶりに会った50歳代の女性が「私は毎日これはしようと決めてもなかか出来ない。
ダメな人間です。」と言いました
この女性は真面目な人です。
真面目な人は出来ない自分を責めてしまいがちです。
私は彼女に「出来なくていいのではないでしょうか。もう、自分に対して優しくして上げていいと思います」と話しました。
人は向上心があり、常に成長しようとします。
それはとてもいいことです。
でもそれは年齢とともに変わっていくモノだと思います。
古代インドでは人生を4つの時期に分けています。
「学生期」 「家住期」 「林住期」 「遊行期」
人の成長の変遷は次のように私は考えます。
小学生までは、人としての善悪を教え、人間としても基礎的な考え方を強制的に教え込みます。
中学・高校生は論理的思考方法を学びます。
大学生や20歳代の人は、社会人としての素養の習得、人間性の向上を図ります。
30歳代・40歳代は覚悟の取り方を学びます。
50歳代になれば今の自分の姿を認めます。
60歳代からは、もう自分の未熟さを許してもいいのです。
私の経験から、人は他人から学ぼうとする素直な気持ちは30歳代まで。
それ以降は自分で学ぶ気持ちがなければ向上しません。
歳を取って60歳を過ぎると、身体的にも脳力的にも思い通りになりません。
その時は今の自分を許して、自分の出来る範囲で楽しんでいいと思います。
ただ若い時は自分の限界に挑戦しなければなりません。
これ無くしては自分の成長は成り立ちません。
それがベースとなり人生が開かれていきます。
そして、ある程度の歳になった時、頑張った自分を褒めて上げられるはずです。
万年筆
札幌市内にある大手文具店で「ペンクリニック」があると聞いたので、先程万年筆を持って行ってきました。
40年近く前に買ったモンブランの万年筆。
買ったばかりの時、子供達にいたずれされて、ペン先が曲がり、モンブランの会社に修理に出しました。
その修理が上手くなかった為か、書いていても引っかかる感じがあり、今回見てもらったのです。
修理してくれた人の話では、モンブランでの修理が下手で完全に良くはならないとのこと。
それでも30分ほどオイルストーンで磨いたりし直してくれました。
直してもらうと以前とは違って大分良くなりました。
この修理は無料。
ありがたいです。
このモンブランの万年筆。
これからも私と付き合ってくれるでしょう。
大事にします。
深山の桜
「深山の桜」
このような題名の小説が本屋で並んでいました。
「深山の桜」とは人が入っていけないような奥深い山にも桜は美しく咲いているという意味です。
ネットで調べてみると「あれを見よ 深山の桜 咲きにけり 真心尽くせ 人知らずとも」という和歌があるそうです
人に置き換えてみると
「人の目に触れないような分野でも、美しく懸命に生きていく」となるのでしょうか。
そのような魂を磨くような生き方
この歳になると憧れます。
外国へ
ここ5日間、悩み事がありました。
スペインのマヨリカ島に住んでいる娘が9月に2子を出産する予定です。
イギリス人の婿さんの考え方で、出産は自分達ですると言っていました。
ところが5日前に娘から妻に連絡があり、婿さんが重度のぎっくり腰になったとのこと。
また出産入院する病院が小さい子供と一緒の入院はダメだと言われました。
そうすると娘が入院中、1歳半になる男の子の面倒を見る人がいません。
その為、娘から急遽、妻にスペインに来て欲しいとの要請がありました。
妻は簡単に『いいよ〜』と応えたのですが、妻は英語もスペイン語も出来ません。
その上1人で海外旅行もしたこともありません。
スペインのマドリードで国内線に乗り換えマヨリカ島まで無事に着けるか。
大変心配になります。
私が一緒に行ければいいのですが、9月は担当する講座が入っており、外せません。
そんな中でやっと一緒に行ってくれる人を探しました。
英語が得意な従姉妹が「連れて行くだけならいいよ」と言ってくれました。
彼女の航空券は私が負担します。
マヨリカ島はリゾート地としてヨーロッパでは有名なところ。
観光も楽しんでくるようです。
妻が帰る時は9月下旬。
1ヶ月近くスペインにいれば、海外の雰囲気にも慣れて1人で帰ってこれるでしょう。
それにしても海外に家族がいるということは楽しみもありますが不安もあります。
何かあったらすぐに行くことができるか。
その為の「心構え」と「お金」。
大事なことだと改めて知らされました。
人手不足
今、どの業界でも人手不足で困っています。
先日、コンビニを経営している従兄弟と話す機会がありました。
「人を採用するの大変でしょう?」と聞いたところ、意外にも全然大丈夫とのこと。
少し驚きました
詳しく聞くと、もっともな話でした。
彼の会社ではアルバイトさんの都合に合わせて勤務シフトを作っています。
一般の店は自社の勤務シフトに合わせて人を採用します。
1日8時間勤務とか、1日最低4時間は働いてもらいたいとか。
ところが彼のコンビニは、1日1時間勤務でもOKなのです。
その上、自分の都合いい時間に出勤出来るようにしています。
シフト管理する方の会社は大変ですが、働く人にとっては働きやすいのです。
そうすると子供が学校行っているその時間だけ働きたいとするお母さんも出てきます。
働きたい人は沢山います。
でも自分の都合に勤務時間を合わせてくれる会社がない。
それが叶う店だから働きたい人が沢山いるのでしょう。
人の採用も「考える軸」を会社から働く人に移すだけで違ってくるのです。
従兄弟のコンビニは20店舗以上あるそうです。
しかり稼いでいるようです。
宅急便
宅急便を創り出したヤマト運輸の社長だった小倉昌男さんが書いた「経営学」の中の一説を紹介します。
宅配でお客様訪問したが不在でお渡しできない時の対応についてです。
「ヤマト運輸の社員の方からすれば、せっかく配達に行ったのにお客様が留守で渡せなかったのは、お客様が悪いのだと思っている。
だが、本当にそうだろうか。
お客様の言い分はこんな風ではないか。
1日中留守だったわけではない。
たまたまお使いに出ていた間にヤマト運輸が配達に来たのだが、30分後には帰ってきて、その後は1日中家にいた。
だから、留守の時に来たヤマト運輸が悪いのだ。
こうなると両者の言い分が全く違うのは当然である。
私は思った。サービスを供給する者の論理と、サービスを受ける利用者の論理は、正反対の場合が多い。
供給者はとかく自分の立場に立って考える。
つまり、自分の都合を中心に考えるのである。
でもそれは間違っていないか。
その考えから不在対策でなく『在宅時配達』という考え方に切り替えたのである。」
サービス関連の会社はほとんどが「お客様第一」という看板を掲げています。
それでいて実際はお客様の立場より供給者の論理を優先しがちです。
小倉さんのこの本には「お客様の立場優先」「利益よりサービスが先」という考え方がベースになっています。
だからこそ、当初誰もが失敗すると思われた宅配事業を小倉さんは一大産業に創り上げることが出来たのです。
現在はその再配達が宅配会社の大きな負担になっています。
今度は供給者側の宅配会社ばかりでなく、受ける側のお客側も自費で宅配ボックスを設置する等、双方によるサービスの維持という現象が起きています。
それは新しいく面白いサービスの動きだと思い、注目しています。
社長の勉強
社長には3つの型があります。
「優れた社長」「普通の社長」「ダメな社長」
「優れた社長」は業績を上げ、利益を拡大しています。
「普通の社長」は現状維持。
その会社はいずれ衰退して行くかもしれません。
「ダメな社長」は会社を潰す社長です。
一見その違いは分かりません。
素晴らしい考え方を持っていても会社を潰す社長はいます。
非情でひどくワンマンな社長でも、業績を上げている社長は「優れた社長」です。
全て結果です。
経営方法や社長としての考え方を勉強していても、会社を潰す社長は多いと思います。
それを見ると、「何のための勉強なのか!」と思ってしまいます。
勉強のための勉強。
自分のための修養であれば引退してからすればいい。
自己満足、見栄、交友関係を深めるため。
それより会社の業績を伸ばし利益を出さなければ、いくら勉強しても意味がありません。
最近、日本の大企業の隠蔽体質が問題になっています。
最近ではシャープ、東芝、富士ゼロックス。
少し前は東洋ゴムや三菱自動車。
それらの社長達は一流大学を出た、優秀な人達です。
問題発覚までは皆、「優れた社長」と思われていました。
でも結果、会社をダメにした「ダメ社長」です。
経営の勉強はしたのでしょうが、本当に大事な「善・悪」という当たり前のことが出来なかった。
それを経営に生かす勉強をしてこなかった。
「そんなの知っている!」「小さい頃から言われてきた!」「常識だ!」
そのように当たり前と思っていても、勉強の手を抜くと、当たり前のことが出来なくまります。
いつになっても社長にとって勉強は必要です。
それは会社を発展させ、業績を伸ばすためです。
勉強なくしては出来ません。
「優れた社長」でなければダメなのです。
経営に生かせる勉強。
自分にとってそれは何か。
まだ勉強していない社長は一度考えてみる必要があります。
ほうれん草
「ほうれん草」
この言葉は多くの方も知っているように「報告・連絡・相談」を意味します。
でもこの「報告」と「連絡」
良く似ています。
その違いはネット調べると「報告は義務、連絡は主体的」と書かれていますがよく分かりません。
私なりに理解しているのは「報告」は下の者から上の者に対する告知。
部下に報告するとは言いません。
矢印で表すと「↑」です。
「連絡」は同僚や部下に対する告知。
矢印に表すと「→」「↓」
「相談」は方向性が見えない事柄を話し合うこと。
図形でいえば「○」
「ほうれん草」に1語付け加えた言葉があります。
「ほうれん草だ」
「報告・連絡・相談・打合せ」
この「打合せ」は方向性が明確になっていて、その戦術を話し合うことだと思います。
矢印で言えば「⇅」でしょうか。
私は「ほうれん草だ」の意味をそのように理解してきました。
皆さんは如何でしょうか?
シニア起業
先日、知人女性が学校を定年退職し、一段落したので訪ねてこられました。
これからは誰か人のために役立つ仕事をしたいと言います。
歳を取り、退職した人の多くは同じような思いに至ります。
そして出来ればボランティアでなく、自分が持っている能力を生かしていきたい。
そのように思う人は多いです。
彼女も趣味を生かして、人に喜ばれる仕事をしています。
しかし採算が合わず赤字だといいます。
色々な理由で、価格設定を高くは出来ないそうです。
でも人のためとは言いながら、赤字では続けられません。
その仕事の儲ける仕組みを練り直すか、別の分野に進むか。
それしかないと思います。
先日の日経新聞に「シニア世代の起業家は63万人」との表題で記事が載っていました。
63万人は多いように思いますが、その割合はシニア世代の4%程度でしかありません。
これからの日本の財政は不安です。
年金もどうなるか分かりません。
年金不足を補う上でもシニアの起業者は増えると予想されます。
しかしシニア起業しても儲からなければ意味がありません。
「起業したために退職金を失った」ということになったら大変です。
シニアの起業では無理をしない「身の丈起業」の考えが大切です。
そして起業の時、気を付けなければならないことがあります。
シニアは頭が固くなっていると自覚することです。
素直に人の意見を聞くより、自分の経験や遣り方に固執する傾向があります。
ここのとことをよく自覚しなければなりません。
これから国や市がシニア起業支援を進めるでしょう。
その時、事業計画書の作り方や借り入れの方法を教えたり、金を出すより、大切な事があります。
それは「意識改革」の為の講座作りです。
現役時代、成功体験のあるシニアは特に必要です。
自意識の強さ、頑固な考え。
それをなくし、新しいことを受け入れる柔軟性と素直さ。
それを理解させる講座です。
自分を変える努力。
それがなければ、いくら素晴らしい起業プランがあっても成功は難しい。
私はそう思います。
電信柱
今朝の日経新聞のコラムに、東京都議会が都道での電信柱新設を原則禁止する条例を可決したという記事が載っていました。
これからは益々電信柱の需要がなくなっていきます。
以前にもブログで書きましたが、私が卒業した札幌西高校では、近くの山に「学校林」を持っています。
それは「西高山」と呼ばれ、札幌市内に3ヶ所、延べ11万6000坪所有しています
「学校林」の始まりは明治中期の札幌二中時代からです。
電信柱として売る目的で育てた樹木は多くがエゾマツ、トドマツ、カラマツです。
この種の樹木は成長は早いのですが、脂が多かったり、捻れやすかったり、電信柱以外には使いにくい木材です。
今ではほとんどの電信柱はコンクリート製なので、それらの木の電信柱は全く使われていません。
それでも在校生やOBの人達が樹木の手入れをしています。
現在は木材加工技術も高まり、それらのマツも建築材として使い道が出てきているようです。
札幌西高校が「学校林」を始めたその理由は、植林し売却した利益を教育費や教材費などに充てるためだったそうです。
貧しくて学業が続けられない生徒のために使われました。
「学校林」は札幌市内の他の高校にもあります。
「生徒の教育を守る」
そのような崇高な目的のためだったのです。
教育の自立と自活のための活動だったのです。
今でもその売却代金で育英奨学金をはじめ、楽器補修や学校花壇整備に使われているそうです。
パソコン操作
最近知人から聞いた話です。
お若い人達の多くがパソコンを使うことが出来ないと言うのです。
私はそれを聞いて驚きました。
「まさか!」という言葉が出てきました。
しかし話をよく聞いてみるとその理由が分かりました。
若者はiphonやiPadを使ってメールやブログ等のSNS、LINE等を使いこなしています。
しかし、それはパソコンではありません。
iphonやiPadでブログは書けても、プレゼン資料を作ったり表計算が出来るわけではないのです。
作ろうと思えばiphonやiPadでも作れるのでしょうが結構大変です。
そして日常はiphonやiPadで間に合うので、パソコンが1台もないという家もあるそうです。
今、就職活動が盛んな時です。
彼ら彼女等が会社に入社した時、社員教育としてまずパソコン操作を教えなければなりません。
20年前は年配者が若者にパソコン操作を教えてもらいましたが、今はそれが逆になっているようです。
不思議な状況です。
でも本当なのでしょうか?
まだ信じられません。
名字の由来
私の姓は「山地」です。
日本にどれほどの数の「山地」がいるのか。
気になっていました。
「名字由来net」というサイトがあります。
調べてみると「山地」という名字は1,443位、人の数11,600名もいるようです。
香川県に多く居るようです。
私の先祖も明治の頃、香川県・金比羅山の近くから北海道に出てきました。
「山地」の名前の由来も書かれています。
「現和歌山県と三重県南部である紀伊国日高郡山地荘が起源(ルーツ)である、玉置氏子孫。
ほか古代氏族であり、美努(みの)王の妻県犬養(あがたのいぬかい)三千代が橘宿禰(すくね)の氏姓を与えられることに始まる橘氏楠木氏流(現香川県である讃岐)などにもみられる。「山」は山の地形を表す。」と書かれています。
チョット難しく書かれていてよく分かりません。
ただ、なんとなく由緒正しい氏素性のようです。
有名人として紹介されているのは、芸能人の六角精児さんも本名は「山地」だそうです。
もしもご興味ありましたら、皆さんもご自分の名字を調べてみませんか?
「名字由来.net」
https://myoji-yurai.net
「利他」に隠された
今朝のテレビに流れているニュースを見ていて。
北海道版の地方ニュースですが、2026年の冬期オリンピックを札幌に誘致したいという活動が行われているようです。
その中心になっているのが札幌市と札幌商工会議所。
この前まで札幌まで新幹線を延伸しようと活動してきましたが、延伸が決まり一段落したところで今度は冬期オリンピック。
「子供達に夢と希望を与え、冬季スポーツを振興し、世界平和に貢献する」という開催趣旨を出しています。
北海道民のため、札幌市民のため、子供達の夢と希望を、という誰からも否定されにくい目標です。
札幌市や商工会議所の本当の目的はそうでしょうか。
札幌市や北海道の外郭団体に福祉という名称の付いた団体が多くあります。
福祉と題してあると誰もその設立に文句は言いにくいモノです。
でもその真の設立目的は?
団体の理事達は多くが元札幌市や北海道の職員。
「利他」という看板を掲げて、実際は「利己」。
よく見ると見えてくるモノです。
経営者もそうです。
会社の経営理念では「社会貢献」「お客様のため」「社員のため」という文句を掲げても、実際はどうでしょう。
看板に偽りあり。
社員は既に見抜いています。
お客様のためと称してもお客様は見抜いています。
「偽りの看板を上げている」
本人が一番分かっていると思います。
でも、もしかしたら利己のために、見えなくなっているかもしれません。
カリスマ
カリスマ。
「あの社長はカリスマ性を身につけている」という話を聞きます。
ただ単に権力を持てばカリスマ人間になれるわけではありません。
「人間として正しいことを正しく、強く主張する。
そしてそれを部下に分かってもらい、指導していく。
これが正しいカリスマの姿です」と稲盛さんは言います。
以前に買って置いた「日暮硯(ひぐらしすずり)」を改めて読みました。
江戸時代、松代藩の財政を立て直した恩田木工のことが書かれています。
彼は藩主真田幸弘に仕えていました。
真田幸弘は13才ながら聡明な藩主でした。
当時の松代藩は水害等で財政が悪化し、幕府から1万両の借金をして急場をしのいでいたのですが、それでも逼迫の一途をたどっていました。
真田幸弘は老職の末席にいた恩田木工に藩の財政再建を任せたのです。
恩田はそれに応えてたった5年で再建しました。
その時、彼が取った姿が、「正直・信頼・思いやり」でした。
再建を決意した時、彼は決めました。
決して嘘をつかない。
食事は飯と1汁のみ。
着物は木綿。
しかしその様な生活は恩田家のみ。
多の者には強いませんでした。
彼は「勘略奉行(財政再建のための行政改革の責任者)」として強権を発するわけでなく、藩士、農民、商人に「理」を持って再建の協力を依頼しました。
その時、彼は誰に対しても「正直・信頼・思いやり」の思いを持って接したのです。
結果、賛同と協力をもらい藩の財政再建と果たしました。
その後恩田木工はどうなったのか。
この日暮硯には書かれていませんが、木工は46歳の時の病没。
墓所は、藩主真田家の菩提寺長国寺の境内にあるそうです。
日暮硯の恩田木工から「カリスマ」について改めて考えさせられました。
ありがとう
「ありがとう」について考えてみました。
「ありがとう」は人の好意に対して感謝する時に発します。
もう1つは今の自分の状態に満足した時に発します。
嬉しい時はツイ手を合わせて小さな声で「ありがとうございます」と言っています。
稲盛和夫さんは人から何か言われる時、自然と手を合わせて話を聞いています。
私も稲盛さんの真似ではないのですが、何かあるとソッと手を合わせています。
「なんまん なんまん ありがとう」という言葉は稲盛さんの小さい頃からの口癖だそうです。
私も神社やお寺に参拝に行く時、手を合わせ「ありがとうございます」と言うだけにしています。
今の幸せに感謝するだけです。
幸せだから感謝の言葉しかありません。
そうでなければ「○○してください」というお願いをします。
神社やお寺で長い間、手を合わせてと願い事をしている人がいます。
それは出来ていないことがあったり、満たされていないからです。
だからお願いするという行為はそれを自分で認めていることになります。
極論を言うと、自分は満たされていないと宣言しているようなモノ。
「引き寄せの法則」からいうとそれは幸せでない状態を引き寄せてしまうことになります。
そうでなく肯定的に「幸せだ」と口に出せば、幸せを引き寄せることが出来ます。
「ありがとう」という言葉は、いま幸せに満たされていると発していることです。
だから「ありがとう」という言葉は幸せを引き寄せる為の強力な言葉なのです。
日常生活の中で常に「ありがとう」という言葉を発する習慣が出来れば、益々幸せを引き寄せることになるでしょう。
更年期障害
更年期障害。
女性の更年期障害はよく聞きますが、男性の更年期障害もあるようです。
先日、馴染みのおでん屋の親父さんが、どうも気力が出なく疲れやすい。
人に聞くと、それは更年期障害の症状だと言われたそうです。
親父さんは今年で68才。
私と同じ歳です。
そう言われれば私も更年期障害になっているかも。
ここしばらく気力が減退し、持続力がなくなり、本を読んでもすぐ眠たくなる。
これは更年期障害の症状のようです。
決して、怠け癖がついた訳ではなかったのです。
さてその対処法は何か!
ネットを見ても、「これ!」という解決用はあまりありません。
また、自分を責め、突き詰めて考えるとウツになるそうです。
気楽に構えていきます。
先程のおでん屋の親父さんも、日曜日と月曜日に休む週休2日にしました。
真面目な性格の親父さん。
のんびり好きなように商売をする。
それがお客にとってもいいのです。
幸せ探し
年を取ってくると夫婦の会話の中には昔話が多くなってきます。
先日も携帯電話の話をしている内に、「電話」についての昔話が出てきました。
子供の頃、電話を置いている家庭は多くありませんでした。
私の家は商売をしていたので電話があり、近所の人宛にかかってきた電話を、その人の家まで知らせに行き連れてきたこと。
また近所の人が電話を借りに来たこともありました。
1人1台スマートフォンを持っている今の若い人には信じられないような話です。
また私の父は新しいモノ好きなので、早い内から白黒テレビを買いました。
夕方になると近所の子供達が「月光仮面」や「名犬リンチンチン」等を見に毎日来ていました。
映画「三丁目の夕日」のようなことが当たり前にありました。
私と同年代の人はよく覚えていると思います。
当時はまだ今と比べれば日本中、物資も少なく、生活は質素。
いつも甘いものを欲していました。
時々飲めるジュースは渡辺の粉末ジュースの素。
それを飲むと口の中が真っ赤になったものです。
それでも楽しかった。
今の時代は当時と比べればモノにあふれ、欲しいモノが無いと言われるほどモノは豊かになっています。
それでも精神的不安を抱えている人は多いように思います。
そのような時は改めて今の自分の幸せを認識してみます。
「幸せ探し」
不幸な出来事やツイてないことを数えるのでなく、今の自分の幸せを1つ1つ見つけ出してみます。
そうすると自分の幸せの深さがよく分かると思います。
「幸せ探し上手」
これが幸せの秘訣でしょう。
セッション
昨夜、知人に誘われて楽器のセッションに参加してきました。
初めてのセッションです。
「遊びだから気楽に」と言われ、アルトサックスを担いで行ってきました。
メンバーはいつもは5〜6人程いるそうですが、昨夜はピアノとドラムの人だけ。
私は他の楽器の人と合わせて演奏するのは初めてです。
初めは中々合わせて演奏するのが難しかったのですが、その内に慣れて来ました。
ドラムのリズムに合わせてサックスを吹くと、一流プレーヤーになった気分。
これがセッションの楽しみなのかと思いました。
ピアニストもドラマーも65才?。
おじさんバンド。
皆さんに遊んで頂きました。
2人の社長
今朝の新聞に「2人社長 スピード経営」という記事が載っていました。
社長が2人?!
私はそのような会社があることは知りませんでした。
2人社長の会社はトップとしての役割分担が出来、いざという事態が起きても事業の継続性を保つことが出来るそうです。
この2人社長の会社は実際に存在しています。
最終責任者は誰が取るのか。
事業が上手く行っている時はいいが、そうでない時はどうなるのか。
部下達はどちらの顔を見て仕事するのか。
私は疑問に思います。
起業する時、共同経営者という話を聞きます。
起業時の苦しい時に支え合う経営者が別にいるのは心強いでしょう。
しかし経営が順調に伸び出すと、上下関係・利害関係・責任問題でギクシャクして、会社が上手く回らず、倒産することになりかねません。
業績が上がらず、上手く行かない時は互いに責任のなすり合い。
会社を引っ張っていくのは社長です。
その社長が2人いては力も社員も二分されそうです。
会社は1人の最終責任を明確にしなければ成り立ちません。
私はそう思います。
努力
ある人のブログに本田宗一郎さんの言葉が紹介されていました。
「努力はその時の情勢に必要な効力を生んで初めて努力として認められる。
努力したが結果は駄目だったでは、努力したことにならない。
仕事の中に能力を活用しなかったり、方法を選ばなかったら、それは徒労という一種の道楽に終わる。」
私はこの「努力」という言葉に反応しました。
本田さんが言われるように、いくら努力しても結果を出さなければ「徒労」です。
「努力することが大切!」と言う人がいます。
それはそうです。
小さい子供に教える段階では正しいでしょう。
しかし社会に出て働く時には成果を求められます。
ましてや経営者になった時、「一生懸命努力しましたが会社は倒産しました」では許されません。
私も若い頃、訪問件数を上げなければ成果が出ないと言われて1日100軒並み訪問したことがあります。
一生懸命廻りました。
でも、ほとんど成果は生まれませんでした。
残ったのは「俺は一生懸命努力した」という自己満足でしかありませんでした。
これこそ徒労です。
だからといって努力することが悪いことだというわけではありません。
要領よく結果を出せばいいのかというとそういうことでもありません。
努力することは大事です。
仕事をする時、情勢を見て、より効率的な方法を考え、その上努力して成果を出すのです。
現在、「努力不要論」なる風潮があるようです。
携帯電話などを使いネットで簡単に何でも分かってしまう時代。
若い人の中には、簡単に済ますことが当たり前のようになっているのではないでしょうか。
どんな時代でも、努力するという行為は大事です。
ただ、徒労に終わらない「努力」が必要だということです。
「豚のシッポのようになるな!」
豚のシッポは常に一生懸命動いていますが、何の役にも立っていません。
若い頃に言われた言葉です。
朝食
若い頃は出張でホテルに泊まる時、価格が安いホテルを探しました。
サービスで朝食が付いていれば「御の字」でした。
最近は少し贅沢になりました。
朝食の美味しいホテルを探すようになりました。
客室は狭くても清潔であればいいです。
でも朝食は少しこだわります。
その土地らしいメニューがあれば嬉しいですね。
ホテルの朝食でよく出て来るウインナーやベーコン・卵焼き・焼き鮭は敬遠します。
朝食でもその土地らしいメニュー。
函館では海鮮メニュー。
浅草では深川飯。
横浜では朝カレー。
奈良では茶がゆ。
今日、また出張のホテルを予約しました。
「朝ご飯フェスティバル」で1位を獲得したホテルです。
美味しそうな朝食が出るようで楽しみです。
立ち読み
私はよく本屋に行きます。
1週間に2〜3日は行きます。
新聞広告などで見た本で、興味ある本は一度目を通さないと買えません。
ネットで買うにしても内容が分かって納得している本しか買いません。
本屋で興味ある本を立ち読みしますが、立ち読み出来ない本があります。
漫画本とHな本です。
そのような本でも立ち読みするのは今の世の中普通なのでしょうが、「いい格好しい」の私には出来ません。
先日も50才過ぎのネクタイ・スーツ姿の男性が漫画の本を一生懸命に立ち読みしていました。
私は古い価値観の人間なのでしょうね。
違和感を感じます。
昔の話です。
私の子供達が小さかった頃、娘が通う幼稚園の男性の園長先生がコンビニで雑誌を立ち読みしていました。
それはHな雑誌でした。
人の目を気にしないで一生懸命見ているのです。
それを見て、私は少し不安を感じました。
いつ誰が見ているか分かりません。
気を付けなければ・・・・
上京
明日から妻と上京します。
義弟の1周忌です。
末娘夫婦も連れて行く予定です。
場所は谷中のお寺。
法要には妻の姉妹達、それに私の子供・孫達も集まります。
1人で上京することは良くありますが、連れがいるという機会はあまりありません。
今回も浅草のホテルに2泊し、皆で浅草を楽しみたいと思っています。
昼食は大黒家の天丼。
夜はポピー通りで一杯。
デンキブランで有名な神谷バーにも予約を入れました。
法要なのにとは思いますが、皆が楽しんでいるのを義弟も喜んでくれると思います。
心配と心配り
「心配」と「心配り」
ほとんど同じ字を書くのに意味は違っています。
「心配」とは、これから起こることに対する自分の不安な気持ちを言います。
「心配り」は他の人に対する思いやりの深さを意味します。
「心配」は自分中心。
「心配り」に似ている言葉で、自分中心の思いの行動は「気配り」です。
「気配り」は自分が間違いを犯さないようにする注意の仕方です。
やはり自分中心です。
「心配り」は自分ではなく、他の人に対する気持ちです。
他の人が心地良くいることが出来るための思いやりです。
もう1歩深くなると「心に添う」状態になります。
「心配り」「心に添う」
そのような気持ちをいつも持ち続ける。
そんな人に憧れます。
花見での話
昨夜、今年最後になるだろう花見に行ってきました。
私が住む町、琴似の大地主さんの前庭で開かれました。
会社の総務から依頼され初めての参加。
17時から始まったその会場には50名以上はいたでしょうか。
初めて参加しましたので、会場には知っている人はほとんどいなく、仕方がないので知らない人達の中に座りました。
会が始まり飲み食いしている内に同じ席の知らない人とも仲良くなり、色々面白い話が聞けました。
1つのグループは庭師の職人さん達。
もう1つのグループは地域テレビのスタッフ。
庭師さん達はその大地主さんの庭の管理を一手に引き受けています。
剪定や肥料やり。
秋には冬囲い。
春にはそれを外す作業。
また立派な赤松の大木は年に1度手で幹をしごいて磨き上げるそうです。
そうしなければ赤松の幹肌の美しさは生まれないと言います。
地域テレビのスタッフからは、テレビの視聴範囲は半径2キロ程度しかなく、ごく限られた地域限定。
視聴者を増やす努力をしているが、ネックになっているのがジェイコムだと教えてくれました。
ジェイコムを使っているテレビは視聴できないそうです。
そういえば私の家のテレビはジェイコムなので見れないわけです。
接続出来るようジェイコムに依頼しているけれどなかなか許可が下りないと嘆いていました。
知らない人同士の話で知らないその業界の話が聞けました。
仲間同士で飲むのもいいですが、知らない人と出会えるのもいいものですね。
孫の悩み
長いゴールデンウイークが終わりました。
この連休中に東京にいる次女と孫2人が遊びに来ていました。
孫達は毎日近くの公園でキックボードの練習。
元気な孫達です。
孫は男の子と女の子。
上の男の子がある日の夜、お祖母ちゃん(私の妻)に「相談したい事がある」と言ってきました。
「好きな女の子がいるという相談か?」と妻に聞くと、そうではありませんでした。
「今、サッカーチームに入っているのだけれど、辞めたい。
でも辞めると言うと、お父さんが『辞めたら殴るぞ』と脅しをかけている」そうです。
勿論、そんな乱暴なお父さんではないのです。
習い事を辞めるのを簡単には認めないためです。
ただ、婿さんはある武道を習得した体育会系のお父さんなので、孫にとってはやはり怖い存在です。
孫は「どうしたら殴られずに辞められるか」を真剣に悩んでいたのです。
私はその相談の結果は聞いていません。
ただ、そんなことにでも真剣に悩んでいる孫がかわいい。
また、父親として存在感を持っている婿さんも格好いい。
まだ小学校4年生の孫。
成長が楽しみです。
イジリとイジメ
ネット上でコメディアンのキングコング西野さんが出したコメントが気になりました。
「信頼関係ない相手の『イジリ』は『イジメ』」
テレビの中でお笑いの人たちがお互いイジリ合っているのを見ます。
時には自分の方から「イジッてください」と言っている人もいます。
そこにはツッコミとボケのように、お互いに信頼関係があるからこそ成り立ちます。
それなのに今日初めて会ったような人が上から目線でイジッて来るとそれはイジメでしかない。
そのようなことを言っていました。
子供達が見たテレビの中で芸人達がイジリ合っているのを面白がって、それを真似て学校でもしてみる。
そして結構受けていると思ってしまう。
そんな光景が想像されます。
しかし本来はそこに「信頼関係があって成り立っている」ことを子供達は知りません。
表面的な面白さを楽しもうとします。
イジッた方はイジメとは思っていないのかもしれません。
でもそれが「イジメ」の芽になっているのかもしれません。
大人の責任です。
そしてテレビ局などの伝える側が心していかなければなりません。
子供達はただ表面的なことばかり吸収します。
そんなことを思いました。
工芸製品
昨日、札幌の大通からJR札幌駅までの地下歩道を歩いていると「北の暮らしの工芸祭」と称して小さな店が沢山並んでいました。
65人の職人や作家が制作した作品・製品を展示販売していました。
家具木工、金属加工、紙工芸、陶磁器、繊維・布製品などの店があり、全てを廻るのは大変でした。
何が大変かというと、どんどん欲しいモノが見つかってしまうのです。
私の場合は木製品、金属製品、陶器に興味があり、これも欲しい、あれも欲しいとなります。
店を廻ってみると、若い作家さんや職人さんが多いです。
真面目に一生懸命作った作品ばかり。
応援したい気持ちも生まれ、ついつい買ってしまいました。
1つ目は「うきしき」という名前の木の皿。
材質は桜で、機械彫りでなく、全て手で仕上げています。
2つめは銅製のコップ。
内側に錫を流し込んであります。
ビールやアイスコーヒーが旨くなりそう。
3つめは、くびれた曲線が美しいコーヒーカップ。
4つめはスッとした姿の白磁のお猪口。
その他にも欲しいものはありましたが、いつの間にか私の財布は空っぽに。
3万円あったはずですが、残金はダラ銭のみ。
帰ったその日の夕食。
木の皿には「おつまみ」を載せ、まずは銅製のカップでビールで妻と飲み会が始まりました。
そして、白磁のお猪口には、北海道栗山にある酒倉「北の錦」の「 秘蔵純米酒 」
お酒がすすみました。
そして良いモノを買えたという満足感でいっぱいでした。
独断と独裁
ある人が言った言葉です。
「独裁すれど独断せず!」
「独裁」と「独断」の違いが分からないとこの意味が分かりません。
社長が1つの決断をする時、それ以前に調査し、研究し、多くの情報を集めます。
会社内では地位や役職に関係なく、多くの部下の意見も聞きます。
社内ばかりでなく社外からも意見を聞きます。
自分1人で思い込みをしない事です。
それが「独断せず」です。
そして最終的に決定する時は自分1人で決定します。
これが独裁です。
全ての責任はトップである社長1人にあります。
だから独裁するのです。
ところが時として「民主経営」と称して集団で決めるという経営者もいるようです。
これは論外です。
誰が最終責任者なのか。
皆が責任逃れをする会社になってしまいます。
衆知を集めて最終的決断は社長1人がする。
当たり前のことが時々出来ていない会社。
有ります。
誰かのために
日京都で開かれた盛和塾例会での話です。
例会では2人の経営者が経営体験発表されました。
どちらも素晴らしい話でしたが、2人目に発表された宮田運輸(株)の宮田社長の話をご紹介します。
1967年に創業された運輸会社です。
宮田社長は売上をいかにして上げていくかを懸命に考え経営していました。
仕事の量が増えると必然的に運転手達への負担が高くなっていきます。
運転手達から待遇改善を求められることもありました。
そのような時に阪神・淡路大震災が起きました。
寸断された道路の復旧を待って、多くの救援物資が被災地に運ばれていきます。
しかし関西圏には救援物資を運ぶトラックが足りません。
宮田運輸に対しても輸送要請がありました。
運転手や社員達はその要請に対して勇んで取り組みました。
連日、休みも無く、昼夜問わず救援物資を運び続けました。
現場から戻ってきたばかりなのに、すぐに物資を積み込むと被災地に向かいます。
宮田社長は運転手に向かって、「大変だろうが頑張ってくれ」と言うと、ニコッと笑って出かけていきます。
宮田社長は頭が下がる思いをしたと言います。
人は強制されて働くのでなく、使命感で働くのです。
誰かのために働くのです。
宮田社長はそう確信したそうです。
その後何年か経って、それを改めて思い起こされることがありました。
今から4年程前に、宮田運輸のトラックの運転手がバイクと接触し、死亡事故を起こしてしまいました。
運転手は警察に拘留中。
宮田社長はすぐに亡くなられたご家族のところへ謝罪に行きました。
頭を床にすりつけて謝りました。
その時に亡くなられた男性の父親からの言葉が忘れられないと言います。
「たった今、息子が命を落としたこと。息子には小学3年の女の子がいたこと。それだけは分かってくれな。」
すぐに宮田社長は事故を2度と起こさないための取り組みを始めました。
何度も安全運転の講習会を開きました。
そして安全のためのスローガンを作ろうと皆で考えたのです。
その時、先程のお父さんの言葉を思い出しました。
運転手にも家族がいるのだと。
子供がお父さんの帰りを待っているのだと。
そこで運転手達の子供達からお父さんへ向けたメッセージと絵を描いてもらうことにしました。
画かれたその絵を拡大し、トラックの荷台にラッピングしたのです。
「あんぜんうんてん」「ありがとう」「おしごとがんばってね」の子供の文字と絵はお父さんを頑張らせました。
必然お父さんは安全運転をします。
誰かのために働く。
家族のために。子供のために。
その子供の絵がラッピングされたトラックはNHKのテレビでも放映されました。
私もたまたま朝の番組で見たのを記憶しています。
そのトラックから発せられたメッセージは道路を走っている他のドライバーにも安全運転を訴えています。
このことがテレビなどで紹介されてからのある日、1通の手紙が宮田社長のところに届きました。
差出人は4年前に亡くなられた男性のお母さんでした。
そこには「とても良いことをしていますね」という内容のものが書かれていました。
宮田社長はその手紙を読んで泣いたそうです。
「こどもミュージアムプロジェクト」と名付けられた「ラッピングトラック」は他の会社にも広がっているようです。
私もそのトラックをどこかで見てみたいものです。
比叡山延暦寺
先週の木曜日に京都で稲盛和夫さん主宰の盛和塾例会に参加してきました。
そのついでに、妻と久しぶりの京都観光をしました。
21日の金曜日の朝は京都駅近くの「東寺」へ。
国宝の五重塔、金堂などを廻り、多くの仏像に参拝してきました。
訪れた21日は丁度「東寺」の縁日でした。
知らずに訪れたのですが、すごい人混み。
歩くのもやっとという状態でした。
それでも縁日に参拝できたのも「縁」なのかとも思っています。
その後、この観光の一番の目的地である比叡山に向かいました。
1日に2本程しかない京都バスに乗り、比叡山延暦寺へ。
「根本中堂」「東塔」「阿弥陀堂」に参拝。
「根本中堂」は国宝に指定されており、延暦寺の総本堂で、開祖伝教大師最澄が最初に開いた草庵跡に建てられています。
ここには1200年前に最澄がともした灯明「不滅の法灯」が今でも守られています。
灯を守る意味で「油断大敵」という言葉が生まれました。
私が宿泊したホテルは延暦寺近くにあるホテル。
このホテルに宿泊すると、毎朝「根本中堂」で行われる勤行に参加できます。
6時発のマイクロバスでホテルを出発し、6時30分からの勤行です。
運良く、私が座った場所は本尊「薬師瑠璃光如来」の正面に位置し、対面しながらのお参り。
キリッと冷えた空気の中、30分程の時間でしたが、荘厳な建物の中に響く読経。
私の心も少しは清められた気がしました。
忘れられない経験でありました。
営業
ある本を読んでいて、気付かされたことがあります。
営業に関することです。
営業する時、目標があり、それを達成するために、あと何個売らなければならないと思い、片っ端から電話を掛け、訪問したりします。
それは自己都合で売り込んでいることです。
当たり前のことですが、そのような営業はお客様が買ってくれるかどうかで目標の達成が決まります。
目標達成がお客様次第となり、自分でコントロールが出来なくなります。
そうなるとストレスを感じるとともに自己嫌悪に陥ります。
そこで自分で営業をコントロールできる方法は何かを考えてみます。
思い切って目標設定を変えます。
目標をお客様に「商品を売ること」でなく「商品の良さを伝えること」とします。
商品サービスの品質を上げることを目標とします。
その目標なら自分でコントロールできます。
自分都合で商品を売るのでなく、お客様サイドに立ち、商品の良さを伝える努力をするのです。
商品の良さを適切に伝える内に必ず買ってくれる人が出てきます。
「お客様の役立ちたい」という自分の思い。
そこに目標を置くのです。
そうすればストレス無く目標が達成され、課せられたノルマも達成できるのです。
私は色々な営業をしてきました。
銀行で預金勧誘。
ホテルで宴会・婚礼の営業。
住宅会社での住宅販売
不動産会社でのテナント集め。
売上という目標を達成するために懸命に営業しました。
無理強いして、お客様から水を掛けられたと言うことを自慢する営業マンもいました。
そこにはやりがいとともに激しいストレスも感じていました。
やはり自分都合で営業していたのだと思います。
視点を変えて、お客様サイドに立って営業する。
そんな当たり前なことが出来ていなかったのです。
今はもう既に遅いですが、改めて反省しています。
定年退職
先程、我が社の1人が退職の挨拶に来ました。
65歳で役員定年退職です。
彼とはともに仕事をし、酒も飲んだ仲です。
会社のあり方についても大いに語り合いました。
彼は退職を楽しみにしていたそうです。
これから1年間は何もしないと言っていました。
ただ優秀な彼のことです。
また何かを始めることでしょう。
これからしばらくは同年代の親しい人たちの定年退職が続きそうです。
寂しいですね。
まあ、いいか
最近は老眼が少し進んでいるのか、老眼鏡が手放せません。
老眼鏡がなければ、モノを見てもボケてしまいます。
老眼鏡を忘れて出かけてしまうと、「眼鏡買わなくちゃ!」と100円ショップを探します。
100円ショップの老眼鏡でもよく見えます。
老眼の為ではないでしょうが、最近物事をボカして見るのが上手くなってきたように思います。
以前は仕事上で、常に全体に目を行き渡らせ、人の行動が気になりました。
細かいことが目に入ってきました。
「顕微鏡」とは言いませんが、心の中に「拡大鏡」「望遠鏡」を持っていました。
最近はその「拡大鏡」も「望遠鏡」も曇ってきました。
それはそれでいいと思っています。
人の行動をあまり注視しないようになりました。
そうすると私の心も穏やかになったきました。
周りの人も和やかになっています。
若い頃は「拡大鏡」や「望遠鏡」のオン・オフが上手くできず悩みました。
それが歳とともに「まあ、いいか」とボカすことが出来るようになりました。
歳とともに私の心も変わってきました。
新人
テレビのニュースを見ていると、新年度からスタッフが変わり、新しいアナウンサーが出ています。
緊張しているせいか、言葉が詰まったり、噛んだりしていますが一所懸命さが伝わり、思わず応援したくなります。
近くのスーパーに行って精算する時、たどたどしくレジを打っている新人さんらしき人がいました。
私の後ろにお客さんがいなかったので、「新人さんですか?」と聞くと、「4月1日からです」と答えます。
隣には先輩の女性がいてフォローしています。
つい新人さんに「頑張ってね」と言うと、ニコッと笑って「ありがとうございます」と返ってきました。
いつまでもその笑顔を忘れないでほしいものです。
お店に行ったら、時々店員さんに声を掛け、コミュニケーションをとってみる。
それだけでその新人さんが自信を持つのではないでしょうか。
お客さんが新人さんを育てる。
その様に思います。
会社を守る
この4月になってから、朝鮮半島を中心に不穏な動きが続いています。
万が一朝鮮半島で戦争になれば、今の私達の生活も一変します。
日本だけ安全という訳にはいきません。
今まで世界中のどこかで紛争が起きれば、日本の通貨「円」は安全資産と言われて買いが起き、対ドルに対して「円」が上がりました。
しかし、朝鮮半島で「何」かが起きれば、近隣の国日本の「円」は一気に売られ、円安になる可能性があります。
それを契機に日本の財政問題が浮き彫りになると益々「円」が売られる事も予想されます。
日本の経済は大混乱に陥ります。
もしも日本が戦争に巻き込まれたらそれどころではありません。
経済学者や評論家が将来の構想を語っても、それは平和な時の話、
戦争や大災害などの思いがけないことが起きた時。
自分の力ではどうしようもないことが起きた時。
どうするのか。
経営者はどのように会社を守り、社員を守るのか。
それを考えなければならない時。
それが今のよう気がします。
朝食は大事
朝食について書きます。
「朝食は大事!」とよく言われます。
私も以前はそう思って、朝食は卵焼き、納豆、焼き魚、ご飯、味噌汁といったメニューを中心に食してきました
また前の日の夕食がカレーライスだと、カレーが好きなので朝カレー。
二日酔いの時はラーメンが食べたくなり、朝ラーメン。
そしてダイエットを意識した時は、バナナ1本、リンゴ1個という時もありました。
そんな朝食をしていると、会社へ行っても頭が上手く回りません。
頭がボーとするのです。
食べ過ぎであったり、食べなさ過ぎで脳に糖が行かなかったせいかもしれません。
以前我が家に来ていたイギリス人の婿さんの朝食を見て、驚きました。
身体がデカいのに、食パン1枚と紅茶のみです。
ただし食パンにはたっぷりのバターとジャムを塗っていましたが、毎朝それだけです。
聞くと長年そういう朝食だそうです。
私も彼を真似て、ある日から朝食はパンにしました
焼いたライ麦パン1枚。
それにオリーブオイルと少々の塩を掛け、飲み物はコーヒー。
なかなか良かったのです。
午前中の仕事もはかどりました。
今はそのライ麦パンをやめ、「和」に変えました。
冷蔵庫に入れてある1膳分の玄米を解凍し、それに秋に庭で収穫し塩漬けした紫蘇の実とトロロ昆布。
時には自家製の梅干しを載せます。
それを湯漬けにしたり、ほうじ茶の茶漬けにして食べます。
それと自家製のヨーグルト。
それだけでお腹は満腹ですが、頭はスッキリ。
毎朝6時30分のラジオ体操が終わってから朝食を摂りますが、お昼までお腹は減りません。
朝食では色々な変遷がありましたが、本当に朝食は大事だ改めて思っています。
しばらくこのパターンを続けます。
白内障
今日15時30分から妻の白内障の手術が始まります。
日帰りの手術で、今日は片目、来週はもう片目を手術する予定。
それほど大変な手術ではないので、妻は1人で行くと言います。
私としては心配です。
術後を見計らって迎えに行こうと思います。
私自身は2度の手術をしましたが、今回妻の手術は簡単だとはいえ心配です。
待つ身の気持ちがわかります。
読書
少し前まで私の机のそばには本が積み上がっていました。
なかなか読めず「積読」の状態です。
「積読」されている本は少し固い本です。
そこで1ヵ月ほど前に決めました。
「1週間に1冊のペースで読みこなす」と。
300ページ程の本を5日間で読むとなると、1日60ページ読むことになります。
読む時は朝と決めました。
7時30分過ぎに出社し、清掃が終わった後、すぐに読みます。
読み始めるのは8時頃から1時間ほど掛けます。
私は読むのが遅いのでそれ位かかるのです。
以前は朝一番にメールチェックから仕事を始めました。
本を読むのは時間が出来た時と思っていましたが、昼過ぎなどは頭が「ボー」として読めません。
それで朝一番に読むことにしました。
これまでには地政学、コーチィング、歴史、為替、金利などの本を読めました。
朝一番ですから本が良く理解できます。
これも1人でする朝活でしょうか。
本に出会う
私は本屋によく行くのですが、同じ事柄に関して全く違う意見の本が何冊か有ります。
そのような本の中には、書いているその部分は確かに事実なのですが、自分の都合のよい事実だけを取り上げてい本があります。
あえて意見を対立させ、自分の本を目立たせる為なのでしょうか。
また、常識と違うことを書くと目立つと考えて出されている本もあるようです。
病気についても本を信じてその通りした結果、大病になったと言う話もあるようです。
起業についても極端な題名の本があります。
題名に惹かれて読んでみると、その人だから出来た特別のことをまるで誰でも出来るような書き方をしています。
真似てみると上手く行きません。
本は参考にするモノだと思います。
バイブルのような本はそうありません。
それが見つかって座右の書になれば大変ラッキーなこと。
そのように思って本屋で本を探すと楽しいです。
経営者と宗教
私の事務所の近くに、大手印刷会社の北海道支社があります。
その支社の駐車場の隅に赤い鳥居と稲荷宮が祭られています。
道路側に接した大きな稲荷宮です。
お稲荷さんは商売の神様と言われています。
経営者と宗教は結構つながりが強いようです。
出光興産創業者の出光佐三氏は宗像大社の熱心な信仰者でした。
土光敏夫さんは法華経。
稲盛和夫さんも出家しています。
経営者が宗教に興味を持つのは商売繁盛を願ったばかりではないようです。
経営者は大変孤独です。
経営者の判断で会社の運命、そして全社員の生活がかかっています。
経営者は自分の決断の結果の全ての責任を負わねばなりません。
逃げることが出来ません。
そんなつらい時、神様や仏様にすがる。
そんな気持ちになることだって有るはずです。
以前起業セミナの講師をしていた時、受講生に次のようなことを話していました。
「勇んで起業しても、孤独を感じたり落ち込む時が必ずあります。
落ち込んだ時、自分を元気にすることの出来る「ルーティン」を作るといいですよ。
近くの神社にお参りに行くだけでも気分が変わるかもしれません。」
また、経営者が宗教に近づくもう1つの意味があると思います。
それは神様や仏様の前では素直になれるということです。
経営者は会社の中で一番の権力を持っています。
もしかすると傲慢な人間になってしまうかもしれません。
でも神様や仏様の前では素直にならざるを得ません。
素直に自分の考えや行動を振り返る。
そのような反省の場を与えてくれているのかもしれません。
贅沢
先程来社した人と話していた時の話です。
持ち物について。
「どうせならいいモノを持ちたいですね」という点で一致しました。
有名とかブランド品だからではなく、自分が気に入ったモノ。
私の基準は「長く使えるモノ」です。
値段が高くても自分が気に入ったモノを持つことは満足感とともに、自信になると思います。
以下は私のお気に入りです。
父の形見のバーバリーコート。
叔父から40年ほど前にもらった金張のパーカーボールペン。
25年前に買ったレビュートーメンの金張の腕時計。
これは手巻きでアラーム機能付き。
35年前に買ったモンブランの「マイスターシュテュック」万年筆。
5年前に買ったHERZのダレスバッグ。
10年前に買ったコードバンの長財布。
これらは毎日使っています。
使っている内に傷も付いてきます。
それがいいのです。
何年も使い続けているとモノが時間に磨かれていきます。
時間に磨かれたモノは新品には無い味わいがあります。
時間に磨かれるモノのには条件があると思います。
それは耐久性と飽きないデザインです。
昨日靴屋に修理に出した革靴も修理しながら15年間履いています。
15年使っていることに店の人も驚かれました。
数は少なくてもいい。
本当に気に入ったモノが身近に有る。
それだけで贅沢な気持ちになります。
仕事=喜び
「学び=喜び」と考えなさい。
「学び=苦痛」では有りません。
ある本に書かれていました。
「学び=喜び」であったなら、学校の成績も良かっただろうにと、昔を振り返ってしまいます。
成績の悪かった私は、「学び=苦痛」だったように思います。
今の時代に当てはめてみれば、仕事に対する姿勢でしょうか。
「仕事=楽しい」でなければ経営者は成り立ちません。
でも、「仕事=苦痛」と思っている経営者は多くいるようです。
仕事が楽しく、一心不乱に仕事をすれば事業は発展していきます。
フッと「仕事ばかりが人生でない」と思った時は、仕事が苦痛になっている時です。
ディソシエーションという言葉があります。
ディソシエーション(dissociation)とは、冷静に自分を観察している心の状態のことです。
仕事が苦しいと思った時は俯瞰的に自分を見てみる。
自分の頭の斜め後方の上から自分を見ているような意識で今の自分の状態を見てみるのです。
その時、何が苦痛の原因か。
それを客観的に見ることが出来ると思います。
仕事が楽しい。
休みの日も仕事がしたくてウズウズする。
そのような経営者になりたいものですね。
コミュニティイベント
先程「コミュニティ・イベント」というモノに行ってきました。
自分で作ったアクセサリーやパンの販売、ヒーリングや耳つぼマッサージなどのコーナーがありました。
以前にも同じようなイベントに行きましたが、ほとんどの店のオーナーは女性です。
男性はいても1人か2人程度。
過去色々なケースを見ていますが、男性が起業する時はどちらかというと、形や構えから入りがちです。
大きな事を考えてしまいがちです。
そして結局、お金を掛けた割には儲からず、失敗してしまう事が多いのです。
一方、女性は何かを始める時は、なるべくお金を掛けず、自分が出来る範囲から始めます。
無理はしません。
身の丈です。
女性は堅実だと思います。
大きな儲けを求めるより、家計の足しや、趣味を生かせればというところから始まるので、大きな事業には成りにくいのかもしれません。
利益は少なくても確実に儲けることを考えるので大きな失敗はしません。
これこそマムプレナーです。
孫娘
昨年の8月から一緒に暮らしていた長女と2人の孫娘。
今日、札幌を発ち東京経由でスエーデンに向かいました。
私ども夫婦には7人の孫がいますが、孫と一緒に暮らせるとは思っていませんでしたので、戸惑いながらも楽しい時間でした。
3人が来た8月は偶然にも私の前立腺癌の手術をした時。
札幌を発った今月は私の大腸ポリープの手術をした月。
少し因縁めいたモノを感じます。
おかげで手術後も至って元気になっています。
これからまた夫婦2人の生活になります。
来月は京都旅行の予定しており、2人仲良く暮らします。
Yシャツ
先程、近くのスーパーに行ってきました。
以前そこで買ったYシャツの袖丈が長すぎるので測ってもらいました。
私は普段から袖丈78センチのYシャツを買っており、このシャツもその表示のモノを買いました。
襟にも78センチと表示されています。
スーパーに行き、店員さんに測ってもらうと84センチもあります。
6センチも長いのです。
道理で手が袖から出てこなかったわけです。
驚きました。
24歳の新入社員の時からYシャツを買っていますが、今までそんなことは有りません。
スーパーの人も「初めてです」と驚いていました。
Yシャツは2枚買いましたが2枚ともそうのようです。
1枚4000円程度のYシャツですが無駄にならず済みました。
大量生産をしたYシャツの内、検品漏れがあったのでしょうか。
でも、それが2枚ともというのは不思議です。
率先垂範
「率先垂範」という言葉があります。
昨日の勉強会でこのことについて話し合いました。
社長は現場に出て、先頭に立ち働くのがいいのか。
または後ろに下がって会社全体を見るのがいいのか。
経営の本には後ろに下がって経営全般を見る方がいいと書いてあります。
また多くの社長がそのスタイルをとっています。
しかしそれに関しては少し疑問があります。
多くの問題点や、新規事業のヒントは現場にあります。
それを拾い上げるのは社長の仕事です。
また、社長が率先垂範をして現場に出て範を示さなければ、部長や課長達も仕事を部下に任せきりになります。
後方にいる方が楽なのです。
経営全般を見ると言いながら楽をしているのです。
現場に降りていく時は勇気が必要です。
現場で質問されたら、現場のことがわからないので答えられない。
それが怖いのです。
社長以下役席は現場に降りていくためには常に勉強をしなければなりません。
稲盛和夫さんは常に「率先垂範」が大切と言っています。
日本航空を再建した時も、再建会議の合間を縫っては飛行機整備場やCAなどクルーのいる現場に行って、自分の考えを話し、また意見も聞いて歩いたそうです。
経営の全てが現場にあります。
マムプレナー
以前にマムプレナーといわれる主婦起業家の人から相談されたことがあります。
それは名刺に書く住所についてです。
名刺に自宅の住所を書くのには抵抗があるのです。
名刺に自宅の住所を書いたため子供に何かあったらと思うと、家庭を守るためにも書きたくないそうです。
そういうこともあってか、頂く名刺の中でマムプレナーの方の住所が空欄になっている名刺もあります。
住所を得るだけのだけのために、シェアオフィスやレンタルオフィスを借りるにもコストがかかります。
料金の安いバーチャルオフィスというのもありますが、借りる人が様々で、その運営にも疑問を持っています。
住所の他に、マムプレナーにとっては、打ち合わせ場所も自宅以外に必要になります。
また教室を開くとなると部屋を借りるコストもかかります。
そこで私が考えていることがあります。
私が管理している事務所があります。
その1つの事務所の中は9室のドア付き個室に分かれています。
その部屋はそれほど大きくはないのですが、1室当たり6名ほどが打ち合わせ出来る広さがあります。
この部屋を面談や教室として使えるようにします。
占有個室ではなく、共同使用とします。
そしてこの事務所をマムプレナーの会社住所として使えるようにします。
会費は月3000円。
登録会員は30名ほど。
この程度の金額であればマムプレナーにとっても負担が少ないと思います。
3000円で住所も教室も持てるのです。
広い部屋を借りれるようになるまで、小さな個室を教室にして実績を作ります。
これならマムプレナーの起業成功の支援になるのではないでしょう。
まだ構想段階ですが。
ご意見がありましたらお聞かせください。
おもんばかる
今、森友学園の問題が連日マスコミで取り上げられています。
今朝のラジオでそのことに触れた評論家が、役人が政治家達の気持ちを「おもんばかった」事が問題だと言っていました。
森友学園の問題に関しては色々疑問もありますが、それは別としてその評論家の人が言った「おもんばかった事が問題です」の言葉に引っかかりました。
「おもんばかること」が悪いことのように言っていましたが、そういうことはありません。
「おもんばかる」という意味は周囲の状況をよく考えることです。
先ほどの評論家は役人が保身のため、政治家の為を思い「おもんばかった」事を批判しているのでしょう。
でも、おもんばかる事は決して悪いことはではありません。
似たような言葉で「忖度(そんたく)する」もありますが、その意味は他人の気持ちを推し量ることです。
社会人としてこれらのことが出来ないと不適格者と言われます。
サービス業で気配り・心配りをして、おもんばかることが出来ないと仕事になりません。
また仕事を任されている人が決断を求められた場合、自分の判断ばかりでなく、上司の心を忖度し、その状況を推し量り判断します。
それが出来ず、その都度いちいち上司の指示を受けたり、また逆に独断で決めると信用を失います。
「おもんばかる」という言葉はこの森友学園問題に関して大阪の松井知事が使ったことから取り上げられ、その言葉がクローズアップされたようです。
「おもんばかる」という言葉が誤解して受け取られていることに違和感を持ちました。
孤独
何日か前の日経新聞の「交遊録」に書かれていた言葉です。
「有名になると堕落する」
「それではどうしたらいいのか」という問いには
「孤独でいること」
この事の意味について、先ほど来社した知人と話をしていました。
社長もそうです。
少し事業が上手くいき、素晴らしい社長だと褒められるとその気になり堕落する。
今までそういう社長を多く見てきました。
そうならないためには、そういう評判から離れて孤独でいることです。
社長は孤独なものです。
全ての最終責任は自分にあり、誰も助けてくれない。
悩み事も社員には決して言ってはいけない。
社長は孤独なのです。
孤独に耐えるには慣れしかないと思います。
そして孤独に耐えてこそ人間的に成長する。
私はそう思います。
勉強会の意味
経営者の集まりというものが沢山あります。
ローターリークラブ、ライオンズクラブは代表的なものですが、異業種交流会、そして勉強会などがあります。
経営に役立つという理由で参加されている経営者も多くいます。
参加されるのはいいのですが、大事なのはその会の中での「立ち位置」だと思います。
その会にのめり込んで、肝心の経営がおろそかになっては全く意味がないのです。
経営の勉強会で学んだことを実践で生かし、会社を発展させることが大切です。
ところがその会に参加することや仲間作りに熱心になり、勉強が実際の経営に生かされていない。
そんな経営者をよく見かけます。
勉強会は大切です。
決してそれを否定しているのではありません。
ただ、正しい考え方や思いを学び、経営者としての自己を高めること。
経営のノウハウを学んで会社を発展させること。
どんな立派なことを学んでもそれを生かさなければ全く意味がありません。
残念ながら多くの場合、学んだことはすぐに経営の中で形に表れません。
それでもそれを繰り返し繰り返し試してみる、挑戦するところに勉強を継続する意味がある思います。
その内にその経営者の社長としての器が成長し、その会社独自の経営形態が出来上がるのです。
勉強会という他の人に引っ張られて飛ぶグライダー経営ではなく、自力で飛べる飛行機にならなければなりません。
ソフト
私が今使っているパソコンはMACのノートパソコンです。
2年程前まではWindowsでした。
その時は漢字変換などがスムーズに出来ていたのですが、MACになってからそれが上手く出来ません。
ある人の忠告で、ATOKを入れるといいと聞き、早速ビックカメラへ行ってソフトを買いました。
その後は快適に仕事が出来るようになりました。
ソフトを買いに行って気が付いたのですが、ソフト売り場が小さくなっていました。
そして、あっても会計ソフト程度のものしか置いていません。
私が探していたATOKのソフトも係員に言うとバック倉庫から持ってきました。
その上、そのソフトのケースを開けるとインストール操作の説明書が入っているだけ。
USBメモリーさえありません。
もうソフトは店で買う時代でなく、ネットで購入しダウンロードする時代になったのですね。
世の中の流れに追いついていけてない私でした。
キリンビール
昨日、元キリンビールの副社長だった田村潤氏の講演会に行ってきました。
田村氏は「キリンビール高知支店の奇跡」という本を出し、ベストセラーになっています。
2時間の講演でしたが、大変面白く参考になる話がたくさん聞けました。
その中で印象に残った話が冒頭にありました。
以前、キリンビールはビール国内トップシェアを誇り、シェア6割を超える時代が続きました。
あまりにもの寡占状態であったため、1975年に独禁法違反に問われ、それをきっかけに社内の風土が内向き官僚的になっていったそうです。
当時、ランチェスター戦略の本の中に、ビール業界のことが例として書かれていました。
圧倒的にシェアの大きいキリンビールはガリバー企業。
これを凌駕することは不可能で、2位3位のサッポロビールとアサヒビールの争いでしかないと書かれていたのを記憶しています。
そのキリンビールが1987年頃にアサヒのスーパードライの大ヒットによってシェアが急落します。
売れ筋のラガービールの味を変えたのがシェア低下に拍車がかかりました。
現在のキリンビールはシェア1位に返り咲いていますが、あの巨人と言われたキリンビールの凋落と復活。
その話は興味深いものでした。
言い続ける
会社の社長として、部下に仕事を指示する時、気を付けなければならないことがあります。
それは、「人は自分の経験の中で得た判断基準でしか、物事は理解できない」ということです。
人は自分が経験していないことは理解できないのです。
その為、仕事上未経験のことをさせる時。何回も何回も言い続けることが大切です。
100回でも1000回でも、しつこいと言われるくらい言い続けなければなりません。
それが社長の仕事です。
理解できない部下を理解できるまで言い続ける。
多くの社長は何度か言ったきりで、部下は理解していると思ってしまいます。
そんなことはないのです。
「前にも言っただろう」ではダメなのです。
社長も自分に当てはめてみれば分かるはずです。
自分が経験以上のことは理解できないはずです。
このことが分かれば、言い続ける重要性が納得できると思います。
松下幸之助さんも「同じことを何回も言い続けることが大切。言い方を工夫しながら、同じことを言い続けるのです。」と言っています。
社長の忍耐力が試されます。
ヤマト宅急便
インターネットの時代、大変便利になりました。
iPhoneを使って買物もできます。
家にいながら多くのサイトから好きなモノが買えます。
大変便利になりました。
一方、それを支えているのはアナログの世界です。
人の手が関わっています。
ヤマト宅急便が今までの仕組みを変えると新聞でも取り上げられています。
時間的にも料金的にも従来のシステムでは無理なのです。
将来にはドローンで運ぶこともあるでしょうが、今は人の手で運びます。
ネットでいかに便利になろうとそれを支えているのは人の手です。
ヤマト宅急便の問題提起で、当たり前のように便利なネットの社会を支えている縁の下の力持ちの存在が改めて実感されました。
「アマゾンの送料は無料が当たり前」という認識もなくなるでしょう。
送料を注文者が負担してまでネットで購入するのか。
ネット販売のあり方も変わって行くのでしょう。
母港
子供達が自立し家を出て行くと、親の役目は一旦終わります。
夫婦2人の生活になりますが、時々は子供達も家族連れで帰ってきます。
自立し、家庭を持って毎日一生懸命生活している子供達にとって、普段、親や実家はあまり気に留めないものです。
でも時として、毎日の生活や子育てに疲れたりすると、フット親を思い出すようです。
それでいいのです。
実家に帰って来た子供達は手足を伸ばしってゆっくりします。
母親に甘えます。
「孫は可愛いでしょう」と言って、孫達を私達に預けます。
しばらく居て、元気を充填したのちは自分の家に帰っていきます。
前にも書きましたが、実家は「母港」です。
出航した船が帰ってくるところです。
母港はいつ帰って来てもいいように、ウェルカムの状態でなければなりません。
ただ、母親が元気でなければ「母港」とは言えません。
決して「父港」ではないのです。
母親に甘えようかと思うから「母港」に帰ろうかなという気が起きます。
将来万が一、母親が先に死に、父親だけになってしまうと、「父港」には父親の世話や介護に来ることになるだけでしょうか。
父親と母親の違いは大変大きいです。
今月末にはしばらく一緒に暮らして居た長女家族も出航し「母港」を離れる予定です。
3月3日
今日は3月3日、雛祭りです。
朝から上の孫娘がおめかしをしています。
下の孫娘にとっては初節句となります。
今晩はチラシ寿司を作りお祝いするようです。
私も白酒として日本酒を飲んで参加します。
子供達が小さい頃は毎年のように我が家でもしていましたが、妻と2人暮らしになってから20年、遠い存在の行事でした。
今日は我が家にとって久しぶりの桃の節句です。
この桃の節句のように、日本には昔からいろいろな節句がありました。
「七草の節句」「桃の節句」「菖蒲の節句」「七夕」「菊の節句」があります。
その他の生活行事としては「節分」「花見」「春・秋のお彼岸」「月見」「七五三」と、形は昔とは違ってきていますが、今でも生活の中で生きています。
そのような生活の風習や行事。
孫の時代にも日本が平和で、平穏な中で続いて行ってもらいたいものだと、つくづく思っています。
健康診断
昨日は休みをもらい、病院に行ってきました。
昨年の10月に行われた会社の健康診断。
結果は要再検査。
大したことないだろうと思ってしばらくほっておいたのですが、先日総務の女性から「まだ行っていませんね。早く再検査行ってください!」と言われました。
昨日の検査の結果は「問題あり」ということです。
治療のため別の病院を紹介されました。
近日中に行ってこようと思っています。
あの時、総務の女性からきつく言われなければ、再検査に行かず、状態が進んでいたかもしれません。
その女性に感謝です。
私は変なところで変な自信があります。
人間は素直にならなければダメですね。
自戒しました。
フグ料理
私、今年で68歳になりますが、今まで食べたくても食べる機会がなかった料理がありました。
それはフグです。
私の妻も同様に食べたことがありませんでした。
「死ぬ前に食べよう!」ということで、近くの寿司・和食の店「雪峰」の女将さんにお願いしました。
1週間ほど前に予約し、当日が大変楽しみでした。
雪峰は馴染みの店で、ご主人は若い頃京都で修行し、その後有名ホテルなどで働き、10年ほど前に琴似で開業しました。
いつも美味い料理を出してもらい、楽しんでいます。
今回も私たちのための特別献立を用意していただき、大変満足しました。
そのメニューを紹介します。
1・先付:フグの燻製
2・前菜:フグ皮煮こごり、ウニ和え、湯引き。
3・造り:鉄刺
4・焼物:西京焼き
5・揚物:唐揚げザンギ風
6・鍋:鉄ちり
7・雑炊
8・デザート
お酒は「琴似」という女将さん達の仲間で作った吟醸酒。
3時間がアッという間に過ぎた幸せな時間でした。
プレミアムフライデー
「半ドン」という言葉を久しぶりに聞きました。
午前中で仕事を仕上げ、昼には退社することです。
半ドンという言葉は死語になっていました。
それが今日、半ドンする会社があるそうです。
今日はプレミアムフライデーとのこと。
毎月最終金曜日は3時に会社を退社しましょう、とお役所が決めました。
昔は土曜日が半ドンでしたが、これからは金曜日が半ドンになるようです。
プレミアムフライデーには社員に早く退社してもらい、飲食や旅行業界の個人消費を増やしてもらいたい。
経済活動を活性化さたいという意図があります。
しかしこの制度も一部の大企業や部門に限られることでしょう。
完全週休2日も満足にできていない中小企業には夢のような話です。
そういえば昔に「花金」と言う言葉がありました。
花の金曜日。
「金曜日にはワインを買って帰ります!」というコマーシャルもありました。
私は今日の金曜日、日本酒を買って帰ります。
宅配総量抑制
今一緒に住んでる長女はよくアマゾンから買い物をしています。
日常品から電化製品までよく買います。
今の時代は「通販で買い物」が当たり前になっているようです。
忙しいのは宅配業者です。
今朝の新聞にヤマト宅急便の記事が載っていました。
宅配の総量を抑制するそうです。
宅配の扱い量を抑えるということです。
人手不足がその原因です。
再配達や夜間時間帯指定サービス等もその1つのようです。
新聞記事によると、これを契機に宅配便の値上げの可能性や再配達の見直しもありそうと書かれていました。
宅配は人手のかかる商売です。
スーパーの宅配サービスも変わるかもしれません。
宅配料が安いのが前提で広がった通販はこれからどうなるのでしょうか?
通販業界に大きな影響がありそうです。
ドローンによる配達というのもあるそうですがまだ先のことでしょう。
教育国債
「大学の授業料免除など教育無償化」ということが国会などで議論されています。
その財源はまたもや安易な国債発行。
来年度の日本の予想歳入は57兆円です。
その歳入の98%が社会保障費と国債費に使われます。
残りあと2%しかないのです。
国債費だけで23.5兆円です。
(国債費とは公債や借入金の償還,利子の支払いに必要な経費)
予算の残り分は国債発行で穴埋めしています。
本来は歳入だけで予算が作られるべきです。
日本の予算作りは国債頼みとなっています。
その現状なのに新たに「教育国債」を発行する。
子供の世代にツケを回すだけです。
また、「大学の授業料免除など教育無償化」そのものに問題があります。
その考えのベースには、大学に行く子供だけを重視しているように思われます。
子供の進む道は様々です。
子供の適性やまたその環境によっては職人の世界に入って行く者もいるはずです。
「大学の授業料免除など教育無償化」は職人や専門の世界に入る子供たちには関係ないことです。
長い期間コツコツ技術を積み重ね、培われてきた日本の技術。
日本が世界に誇れる伝統的技法は、地道に手に職を付けてきた若者がいたからこそです。
ビル建築も優秀な鉄筋工や型枠工がいるからです。
日本の経済、伝統の基になっている職人の世界に入って行く若者達。
もっと優遇されていいはずだと思います。
起業希望者
先日の新聞報道に起業についての記事が掲載されていました。
日本での「起業に無関心な人は72%」だそうです。
これは男女合わせて2000人を対象とした調査の結果です。
海外での同様の調査ではアメリカでは23%、ドイツは31%、英国は36%だそうです。
起業に無関心な人が72%ということは、関心ある人が27%ということでしょうか。
関心ある人はアメリカでは77%で、日本とは真逆です。
この結果から経産省は起業直後の企業に信用保証協会が全額保証する限度額を1000万円から2000万円にして支援するそうです。
大して効果はないような気がします。
起業で必要なのは資金もありますが、必要条件ではありません。
また起業を支援してくれる機関やシステムでもありません。
大事なのは「起業する人って素晴らしい」と起業家に憧れる環境を作ることです。
起業をする人が尊敬されることは大事です。
学校で起業の大切を教える教育も必要です。
日本にはお金を稼ぐ行為を低く見てしまう傾向があります。
お金を稼ぐことは大切なことと教えることです。
起業に無関心な人が72%いるということは、リスクもわず、冒険もしない。
安楽に生活が保証される生き方。
そのような生活を選ぶのです。
だから公務員になりたいという人が多いのでしょう。
皆が公務員になったら誰が稼ぐのですか!
破綻したギリシャでは、労働者の半数が公務員だと言われています。
起業希望者が少ないということは国の稼ぐ力が落ちていくことを意味します。
挑戦する人が増えて欲しい。
そして、そのような人を認め支援する環境作りこそ急務です。
逆らう
札幌中央区にある地下歩道は左側通行です。
地下鉄が出来た当時からそうです。
一般道路では右側通行なのにどうしてなのか。
地下の歩道だけは、なぜ左側通行なのか。
どこにも左側通行とは書かれていません。
ある人によると、人間の心臓は左側にあります。
心臓を守ろうとする人間の本能から左側通行になってしまったと言います。
先ほども地下歩道を歩いてきました。
左側通行です。
でも時折、逆方向すなわち右側を歩く人がて、人を縫うようにして歩いていました。
「あれ?左側通行に気が付かないのかな?」と思ってしまいます。
流れに逆らうと本人も大変でしょうが、周りも迷惑します。
これは人の生き方に似ています。
無意識の内に「流れ」に逆らっていいる人がいます。
逆らっているのに気が付かない。
やたらと人とぶつかったりします。
逆風に向かって歩けば、一生懸命歩いているのに前に進まない。
ただ決して「成り行きに任せろ」と言っているのではありません。
頑張る方向が自分のことばかり考えているのか、人のために考えているのか。
人の言うことを聞かず自己主張ばかりするのか。
それより周りに気を配る事のできる「心配り」と「素直な心」。
そんな簡単なことなのに気が付かない。
そんな風に思えてしまいます。
やりたいこと
「自分は何をやったらいいかわからない」とか「やりたいことがない」
そう言う人は結構いると思います。
「私の天職は何だろう」と思うと、もっとわからなくなります。
幸いにもやるべきことを見つけた人はあることをしています。
「何をすればいいのか」
それをなんとか探そうとして相当の時間とお金をかけて動き回った結果、見つけることができます。
ただジッとして、考えているだけでは見つけられません。
そして誰も「こうしたらいいよ」などと教えてくれもしません。
口を開けて待っていても牡丹餅は落ちてきません。
これは私の経験でもあります。
こう書いている私、仕事が一段落して、最近同じことを考え出していました。
再度動き回って見つけてみようかと思っています。
社長とは
昨日はスポーツの個人競技と団体競技について書きました。
書いた内容は、個人競技と団体競技のプレーヤーの違いです。
個人競技は孤独で、責任は常に自分にあります。
苦しくても誰も替わってくれません。
団体競技は個々人の力を発揮させるために優秀な監督やリーダーが必要です。
そのことを会社経営に置き換えてみました。
会社の社長に求められるもの。
それはこの個人競技・団体競技それぞれで必要とされる能力が求められるのではないでしょうか。
社長は最終的責任は自分にあるという覚悟が必要です。
経営判断ミスが会社の命取りになることもあります。
そして誰も替わってくれない孤独な決断を常に求められます。
また一方、社長には社員の能力を遺憾なく発揮させるための指導力が必要です
社員1人1人を見抜く力も求められます。
そしてその会社を率いていくリーダーシップを発揮しなければなりません。
考えてみると社長の仕事は大変ハードなものです。
アスリートとしての闘争心も必要な要素なのでしょう。
個人競技
スポーツ競技は個人競技と団体競技の2つに大別されます。
柔道や剣道、体操、スキー・スケートは個人競技です。
団体競技は野球やサッカー、バレー、バスケットなどがあります。
個人競技は個人の才能・能力、そして孤独に勝てる精神力が不可欠となります。
団体競技には個人の才能・能力も勿論求められますが、チームワークの力が重要となります。
その中でもそのチームを引っ張る監督・コーチそしてリーダーの力量が試されます。
団体競技では万が一、誰かがミスをしても他の者がカバーすることが出来ます。
個人競技は1つのミスが命取りになります。
ミスをしても誰もカバーしてくれません。
誰も替わってくれません。
高校生の時、校内のスキー大会があり、私もアルペン競技の滑降と大回転の選手として出場しました。
その時の記憶は今でも鮮明に覚えています。
練習では好成績を出したのですが、本番に弱かったのです。
スタート時は皆から注目され、スタートの秒読みが緊張感を高めます。
その時の緊張感と孤独は今でも忘れられません。
今月19日から北海道では冬季アジア大会が開催されます。
この冬季アジア大会の競技はほとんどが個人競技です。
緊張感と孤独に打ち勝ち、自分の力を出し切ったものが勝てるのです。
緊張感を自分の力に変える能力。
私には無いものです。
日常と非日常
先週の土日に伊勢神宮参拝して来ました。
11日は建国記念日ということもあってか、ものすごい人出でした。
私達夫婦にとって今年は6回目の参拝です。
宿泊はいつもの神宮会館。
1泊朝食付きにして、夕食は惣菜と旨い酒を買って、妻と部屋でとることにしました。
この神宮会館の周りは「おはらい町」や「おかげ横丁」があり、美味しいものが沢山売られています。
私達も夕食に合う蒲鉾やさんま寿司、それに旨そうな地酒を買いました。
最後に足りないものを買おうとコンビニを探しました。
でも見つけられません。
昨年までファミリマートがあったのですが。
そこで近くの店の人に聞くと、ファミリーマートは閉店になったとのこと。
それを聞いて少しびっくり。
この「おはらい町」や「おかげ横丁」には溢れんばかりの参拝客がいます。
どの店も繁盛しています。
それなのにファミリマートはなぜ撤退したのか。
色々考えてみました。
考えられることは、コンビニは店として、それなりに利益は上げていたと思いますが、この町には適合しなかった。
参拝客がこの町に求めているものは別にあるのです。
コンビニは普段の「日常生活」には欠かせないものです。
一方この「おはらい町」や「おかげ横丁」にあるものは江戸時代の街並みを再現した「非日常」です。
来ている参拝客は、「日常生活」とは違ったものを求めている人達です。
「非日常」を求めた参拝客にとって、「日常生活」で見かけるコンビニは「そぐわないモノ」に映ったのかもしれません。
それのため、極端に言うとコンビニは淘汰された。
そう思います。
この「おはらい町」や「おかげ横丁」にある店は夕方5時半には店を閉めます。
6時になると町の通りには参拝客はほとんど居なくなります。
あれほどいた参拝客が一気に居なくなるのです。
変化もすごい。
やはりここは非日常的な場所なのです。
論語読みの論語知らず
「論語読みの論語知らず」という言葉があります。
論語を一生懸命勉強しているけれど、その本質を理解しておらず、実践もされていないことを言います。
経営の勉強会でも同じようなことがあります。
誰より熱心に学んでいるはずなのに、その経営者の会社の業績はあまり芳しくない。
経営を勉強することに熱心になるあまり、自分の会社経営が疎かになっているのか、学んだことを実践できない実践力の無さなのか。
それとも勉強仲間との交流を楽しんでいるだけなのか。
若い経営者にそのような傾向が見えます。
「知行合一」
学んだ知識は実践してこそ生きてきます。
経営者として改めて身に付けて欲しい心構えです。
また、折角学んだ経営の勉強なので、それを生かすとともに、経営は本来割り切れず、泥臭いモノだということも理解して欲しい。
会社経営に関わる1つ1つの問題を拾い上げ、地道に解決し続けるミクロ的な思考と、将来に向かい、目的・目標を追い続けるマクロ的思考。
この2つの思考が常に求められるのが経営者だと私は思います。
神棚にお参りをする
私は毎朝、家にある神棚をお参りします。
時々今一緒に住んでる5歳になる孫娘も私の真似をして、「2礼2泊1礼」をしています。
初めは「何しているの?」と聞かれました。
「ありがとうございます、と神様に感謝するためだよ」教えました。
「昨日も1日、家族皆無事に過ごせました。ありがとうございます」と感謝するのです。
孫娘はあまり理解していなかったようですが、大事なのは「感謝することだ」ということは少し理解したようです。
そんなこともあってか、時々手を合わせ「ありがとうございます」というようになりました。
このようなことは形から入っていいと思います。
そして何かをお願いするより先に、ありがとうございますという感謝の気持ちを持つ。
そんな子になってくれたらいいとお爺ちゃんは思っています。
必死と本気
必死」と「本気」
何が違うのでしょう。
必死になるのはプレッシャーがある時に生まれる心理です。
そのプレッシャーから逃れるために一生懸命になるのであって、それがなくなればまた元に戻ります。
「本気」とは明確な目標がある時に生まれる熱意です。
そしてどのようにすればそれが達成できるかを考えています。
一見すると、必死な方が一生懸命仕事をしているように見えます。
しかし、もしかしたらその一生懸命さは、例えば期日に落ちない手形の金策をしている必死な姿かもしれません。
一方、目標を持っている人は遠くを見て今を見ます。
先が見えています。
なので余裕があります。
先の見えない経営ほど怖いものはありません。
事業を成功させる人は本気の人です。
風邪をひいて
先日の土曜日、物置の屋根に積もった雪の下ろし作業をしました。
深さ1メートル50センチを超える雪の量。
1人で下ろす作業は結構きつく、体力消耗してしまいました。
そしてその夜は約束していた娘夫婦との外食。
この2つが重なったためか、それまで風邪気味だったのが進み、一気に熱が出てしまい日曜日はダウン。
インフルエンザではないようです。
孫娘2人の風邪が感染ったようです。
月曜日も会社を休みました。
今日は少し体調も良くなったので、予定していた定期検診のために病院へ行って、今は帰ってきたところです。
久しぶりに風邪で会社を休みました。
家で寝ていても、何かズル休みして寝ているような気分になります。
でも、あまり無理はできない歳と身体になっているので、少し自分を甘やかしてやろうと思っています。
家族的経営
先日、新聞報道で「パナソニックは長時間労働を行わないようにするため、工場を含めて国内すべての従業員10万人に対して午後8時までに退社するよう社長が通達しました。」との記事が載っていました。
過度の残業の廃止が目的であり、多くの大企業も始めているようです。
一方、中小企業はどうでしょうか。
仕事が無く、時間調整しているところは、残業もない状態です。
でも、仕事が入ってくれば無理してでもこなします。
そうしなければ次の仕事が入ってこなくなります。
そしてそう言う仕事は納入期日もギリギリの時です。
社長は従業員に対して無理を強いてでも、時には休日勤務・深夜勤務になってでも仕事をしてもらわなければなりません。
それをしなければ会社の存続に関わるのです。
その時、社長の意向に従って従業員がキツイ仕事に向かうのか。
ここが問題です。
同じ仕事をするにしても、なぜキツイ仕事をしなければならないのかを知っているのと知らないのと大きな違いがあります。
社長から従業員に対してよく説明し納得してもらう。
そのような行動が社長には求められます。
しかし、「社長命令だ」の一言で仕事をさせ、言った社長本人は休んでいる。
そのような会社が多いように思います。
中小企業は「家族的経営」と言われます。
それはお互いを大切に思いやる関係を言うのであって、亭主関白や頑固おやじのように一方的関係ではありません。
日本の中小企業には中小企業なりの経営スタイルがあります。
思いやりのある「家族的経営」。
もう一度見直してみる必要はあります。
成功する起業家
成功する起業家とはどういう人か。
以下は私が考えることです。
1・成功する起業家は事業が成功するためにはどうするべきかを常に考えます。
2・成功する起業家は将来の会社の姿を明確にします。
3・成功する起業家は確立した将来の会社の姿から逆算して、これから何をするべきかを考えます。
今の自分を基準にして将来の自分を決めてしまうとドンドン視野と選択肢が狭くなります。
起業して失敗する多くの人が陥るのは、今の自分を基準にして経営を考えるからです。
最初に「夢を持とう!」とか「事業の目的」「やりたいことを明確にする」ことが大事だと言われます。
それが無いと、事業を持続しようとする「欲のエネルギー」が無くなるのです。
毎日の仕事がマンネリになります。
現状の自分を基準にして物事を考え出すようになれば黄色信号。
もしもそのようなことになったら、あえて自分を叱ってくれそうな経営者に会いに行くこと。
経営経験、そして経営の悩みも乗り越えてきた先輩経営者こそ良きアドバイザー。
厳しい意見を聞くのです。
叱ってもらうのです。
格好悪い!恥ずかし!メンツが立たない!
そんなことを思っている内に会社は倒産してしまいます。
必要なのは勇気。
その勇気が有るか無いか
それで人も会社も変わります。
そんなことをつくづく考えることが多くなりました
社長の万が一
最近、知人社長が亡くなりました。
経営者仲間の話によると、その社長が亡くなった後、社内は混乱しているようです。
残された社員達は何をどうすれば良いのか分からない状態。
顧客の管理、お金の管理など諸々のことは社長がしており、社員は社長の指示を受けていただけのようです。
同じようなことは多くの会社でも起きます。
社長が全てを把握し、社員の先頭に立ち突き進んで業績を上げている。
でもいつ社長に万が一のことがあるか分かりません。
その万が一の時の対処は準備して置かなければなりません。
準備しようと思っている社長は多くいると思います。
しかし、「自分はまだ大丈夫だから」とか「もう少し後でも良いだろう」と思ってしまいます。
その内に、万が一が起きるのです。
今年65歳になる社長は「まだまだ社長として頑張れる。〇〇さんも70歳を過ぎても頑張っている」と言います。
その会社は確かに業績は良いのですが、社長の右腕と言われる人はいないようです。
人は歳を取り、いつかは消えて行く時が来ます。
残された家族はもちろん、社長として社員のことも考えておく責任があります。
会社は社長個人のモノではないのです。
代金前払い依頼
私の事務所でネットセキュリティー向上のため、改良工事をしようと、ある会社と今まで話を詰めてきました。
今日その工事費支払方法を話してきた時のことです。
「初めての取引先は工事代金前払いでお願いいたします」と言ってきました。
私は過去いろいろな会社で仕事の発注をしてきましたが、前払いを依頼されたのは初めてです。
驚きです。
前払い依頼は「あなたの会社を信用していませんよ」と言っているのと同じです。
先方が当社をそう思うなら、当社も依頼した工事が目的通りに完了するかしないか不安です。
目的通りに工事が出来なければ、前払いしていればこちらが損をします。
一方的にお客様に負担を強いるその会社の経営方針は間違いです。
会社の信用に不安がある場合は前払い請求することもあります。
しかし、そのようなケースは稀でしょう。
前払い、もちろんキッパリ断りました。
それにしてもこの会社、今までこのような前払い依頼の仕事をしてきたのでしょうか。
もしかしたら過去に代金未収問題があったためにこのようなことをするのでしょうか。
色々なことが想像されます。
それにしてもこのような後ろ向きと言える商売をしていると逆に信用を失います。
三刃
新聞などの報道では、日本の学生の留学希望者が少ないというのがあります。
それに比べ、中国の学生の留学希望者の多いこと。
あるデータによるとハーバード大学の学部と大学院の学生数は
日本人:107人に対して中国人: 421人と言われています。
日本人は減少傾向にあり、中国人は増加傾向にあります。
中国人は昔から海外志向が高かったようです。
アメリカをはじめ世界の各国に中華街があります。
ご存知かもしれませんが、中国には「三刀」という言葉があります。
3つの刃とは包丁、ハサミ、カミソリのことです。
調理人、仕立て師、理髪師として三刃さえ持っていれば、どこでも生活していけるという生活能力の高さがあります。
伝統的に中国人には海外志向が高かったようです。
対して日本人には「三刃」にあたるものは何か?
私にはなかなか思いつきません。
ただ、「三刃」という言葉から、誰にも大事なことがあります。
それは自信の持てる技術や能力を身につける、またそれを伸ばすことです。
仕事や勉強ばかりでなく、遊びでもいいでしょう。
プラモデルを作らせれば誰にも負けにも負けない。
字が上手で、習字に関心がある。
食べることに対しては執着心が強く、グルマンとして身を立てる。
ファッションに興味がありスタイリストとして生きて行く。
自分をもう一度見つめ直して考えてみる。
そして自信の持てる好きなことを見出す。
それが今の若者にとても大切なことのように思います。
読書ノート
本棚を整理していたら、昔に書いた「読書ノート」が出てきました。
ある時から書くのを止めて、本棚に仕舞われていたようです。
仕舞った記憶がないのです。
中身を見てみると11冊分の本の要点が抜粋されています。
私の字ですからあまり綺麗ではないのですが、いいことが書かれています。
書いた内容はもちろん、こんな本を読んだということも忘れています。
きっとノートに書いたことで、読んだ本をマスターした気になっていたのでしょう。
読み返してみると「成る程!成る程!」と感じ入ることばかりです。
ただもしかしたら、読んだ本の内容はよく覚えていなくても、知らぬ内に今の私の考え方の裏付けになっているのかもしれません。
今読んでる本もこのノートの書き留めることにします。
これからはその書き留めたノートを見返すことで、知識の蓄積がうまくできるかもしれません。
そして読み返しやすいように「字」も綺麗に書きます。
冬季アジア大会
今朝出社すると1枚のFAXが流れて来ていました。
「2017年冬季アジア大会開会式動員協力のお願い」というものです。
2月19日(日曜日)に開会式が開催され冬季アジア大会が始まります。
31カ国2200名の選手役員が参加されるそうです。
16時から始まり、1部はセレモニー、2部はウェルカムパフォーマンス、3部はスペシャルライブとして「DREAMS COME TRUE」が歌います。
この開会式の招待券を差し上げますというFAXの内容でした。
2月19日まで1カ月ありません。
私も冬季アジア大会があるということ忘れていました。
この時期に動員協力のお願いが来るのは余程人気がないのでしょうか。
私の周りの人たちに声をかけていますが、どれほどの人が「行きたい」と手を挙げるでしょう。
盛り上げに欠ける冬季アジア大会となっています。
開会式がこの状態ですから、各競技の入場予想ははどうなっているのでしょうか。
観客の少ない大会になると寂しく残念です。
日本の近代史
多くの人は歴史に関心があると思います。
私も興味があります。
特に日本の近代史。
戦後から現代に渡るまでの歴史に興味があります。
隠れた事実を見つけ出した時、驚きがあります。
戦後の日本はGHQによる統治があり、その中で様々なイデオロギーが交差していて、思いがけずに重要な事実が埋もれているようです。
戦後70年間の近代史は、何が今の日本の政治、経済、生活にどのように影響しているのかなものなのかを教えてくれます。
日本の敗戦後はアメリカ軍の占領下にありました。
でも事実を知ると、もしかしたらドイツと同じように戦勝国により分割統治されていたかもしれないのです。
Wikipediaによる記述があります。
1945年8月11日にアメリカ国務・陸・海軍三省調整委員会が承認し、8月18日にトルーマン大統領が承認した大統領宛覚書「日本の敗北後における本土占領軍の国家的構成」にはその分割統治が記されています。
ソ連:北海道、東北地方。
アメリカ:本州中央、関東、信越、東海、北陸、近畿。
中華民国:四国。
イギリス:西日本(中国、九州)をそれぞれ統治
東京は四カ国共同占領。
一年後、各国兵力を半数以下に削減し、米軍は13万5千人程となる。
そのような記述です。
1946年2月にはイギリス軍、オーストラリア軍、ニュージーランド軍、インド軍などのイギリス連邦占領軍が中国地方、四国を統治したという事実もあります。
分割統治の一部は実施されましたが、その後はアメリカの単独統治となりました。
それが幸いしたのかもしれません。
当時の中国は中華民国と中華人民共和国との内戦状態でした。
とても日本統治に参加する余裕はありませんでした。
結果日本は分割統治されずにすみました。
そうでなければ、もしかしたらドイツと同じようにアメリカと中国との分割統治が行われ、日本は分断されていたのかもしれません。
四国は中国領土ということになっていたのかもしれません。
そのような、私が知らなかった歴史を調べていくち、今の日本は危ない綱渡りの中で奇跡的に存続し、経済成長出来て来たかが良くわかります。
これからの日本の将来を考える上でも、近代史を学びたいと思います。
また今の日本における組織体制の中にはその流れを汲むモノがあります。
東京地検特捜部です。
悪者を摘発するイメージがあります。
しかし東京地検特捜部は元々GHQのために働く捜査機関として生まれました。
戦後日本で隠された物資を探し出すために作られたのです。
1つの例として、三菱信託銀行の地下からダイヤモンド16万カラットを見つけ出しアメリカが接収しました。
それが今東京地検特捜部につながっています。
このことについてはまたいつか後日の。
保護主義
今月の20日にアメリカの新しい大統領にトランプ氏が就任します。
トランプ氏が掲げるのは「アメリカファースト」。
アメリカを第一に考える。
それは「保護主義」であり、内向き政策をするということです。
もっと突っ込んで言えば、「利己主義をします」と宣言しているようなもの。
従来からあった「グローガリズム」も問題がありました。
Wikipediaでは「グローバリズムは多国籍企業による市場の寡占もしくは独占固定化に至る可能性が高い」と示されています。
「アメリカファースト」や「保護主義政策」はより内向きで、グローバリズムより利己的な政策です。
アメリカ大統領が自国のことだけ考えて政策を進めれば、各企業も自社の利益ばかりを優先するでしょう。
経営者も従業員も「自分ファースト」になってしまいます。
結果、益々経済貧富の格差は広がるように思います。
それが果たして幸せな姿なのでしょうか。
今後各国が「自国ファースト」と言い出していく時、国民は利己中心になり、人々の心も荒廃していきます。
世界中にネットを中心にして情報が行き交うこの時代。
自由に世界中を旅行に行けるこの時代。
各国の生活や人々の様子がわかる時代に内向き志向が増大していく。
ネットを見たりすることが自分の欲望を満たすための情報収集。
他国や他者を出し抜くための操作。
そんなことも想像されます。
そんな世界だけは拒否したいものです。
大殺界
「六星占術」という占いがあります。
以前にも書きましたが、私は今、その中で一番悪い時期の大殺界に当たります。
大殺界は3年間続きます。
昨年から始まり今年が一番の大殺界。
来年まで続きます。
とは言え、占いなどあまり信じない人も多いでしょう。
私はこの「六星占術」は結構信じています。
私は10年置き位に、身の回りや自分自身に変化が起きてきました。
自分ではどうしようもない流れのように感じています。
若い頃はそれに逆らったこともありましたが、今は素直に受け入れるようにしています。
その流れは今自分にとって必要な流れなのだと思うのです。
確かに昨年より仕事も生活も少しズレているように思います。
昨年は少し大きな病気もしました。
仕事も思い通りにいかないことも多くなりました。
ある本には大殺界の時は我慢の時と書いてあります。
転居、転職、結婚などの新しいことを始めることはダメです。
ただじっと我慢するだけだそうです。
その本の中でなるほどということも書かれていました。
大殺界の時は苦手な人と付き合うとか、コツコツと仕事をする時なのだそうです。
修養もいいのかも知れません。
大殺界の時は、もう一度自分を振り返り、内に力を貯める時なのでしょう。
色々な勉強をしてみよう。
そう思います。
イエスマン
正月に「イエスマン」という映画を観ました。
いつも否定的で、物事から逃げていた主人公が、あるセミナーで聞いた話がきっかけで変わります。
「人生にノーというのは死んだも同然だ」というセミナーのカリスマ主催者に言われます。
頼まれたら必ず「イエス」ということ。
映画では「イエス」と言い続ける主人公のドタバタ劇が続きました。
この映画は実在するイギリス人の経験を基に作られたそうです。
確かに人は時として消極的だあったり、懐疑的になって、頼まれてもそれを避けたり否定的になったりします。
自己保身がそれを成すのでしょうが、もったいないことです。
新しいことに挑戦できるチャンスだったのかもしれません。
「イエス」と言うことで得られるモノ、失うモノ。
「ノー」と言って得られるんモノ、失うモノ。
少し考えてもわかることです。
「リスク」は「イエス」と言っても「ノー」と言っても共にあります。
しかし得れるモノは「イエス」の方がはるかに大きいはずです。
頼まれたら「イエス」
今年は意識してみたいと思います。
メガネ屋
昨日、日中に妻から電話がありました。
ちょっと車で迎えに来て欲しいとのこと。
指定した所へ行って、拾って家に連れて行きました。
妻はメガネ屋にメガネを修理してもらおうと来たのだけれど、メガネ屋さんが修理途中でメガネを壊してしまったとのこと。
妻は近眼で乱視がひどいのです。
眼鏡がないとツルツルの雪道を歩いて家に帰れなかったようです。
眼鏡は翌日には修理を仕上げてくれるそうです。
家には古い眼鏡があるので、1日2日はなんとかなります。
しかし私は少し疑問に思いました。
メガネがなければ歩けない人のメガネを壊してしまった時のお店側の対応です。
車で家まで送ってくれるとか、タクシーを呼んでくれるとしてくれても良さそうに思います。
メガネの修理代はお店の負担で直してくれると言いますが・・・・
疑問符がいっぱい浮かびました。
ある経営者の死
先日仲間の経営者が亡くなりました。
ガンでした。
1年ほど前からの闘病生活でした。
彼は死ぬ直前まで仕事をしていました。
今月の5日に仕事始めで会社に行き、その後銀行回りをすると出かけた時、意識がなくなり救急車で病院へ。
3日後、彼は亡くなりました。
先月の15日、東京で行われた忘年会にも頑張って札幌から仲間たちと一緒に出席していました。
体は辛そうでしたが、話し方はしっかりしていました。
それが彼とお会いした最後でした。
さて自分はどうか?
最後まで自分に課せられた仕事をしっかりやり切ることができるのであろうか!
短い人生、悔いなく楽しく暮らそうと言って、仕事も辞め勝手な生き方をしてしまうのではないか!
そんなことを考えてしまいます。
命の期限が近づいていても、彼のように淡々として仕事をやり続ける。
そんな生き方。
尊敬する生き方を見せてくれた経営者でした。
本との出会い
新聞の広告欄に時々新刊の宣伝が載っています。
その中に本を読んだ人からの書評が書かれています。
書評の中には「若い時に読んでいれば良かった」というようなものが見受けられます。
私も本を読んで感動し、そう思ったことはありました。
でもそうでしょうか?
20代30代の時に読んで果たして理解できたでしょうか?
理解できなかったと思います。
また若い頃はそのような本は買って読もうとも思わなかったでしょう。
今、読んで理解できるのは、長い年月、苦労や経験をしてきて、若い頃よりは人としての修養を積んできたからだと思います。
そして今読んだその本は、今の私に必要な本なのです。
本との出会いは人と同じで、必要な時に出会うものです。
その本を読んで、その後の生き方が変わることもあります。
本に出会った幸運を感謝することもあります。
私はよく近くの本屋に行きます。
色々な分野の本を見て、新しい出会いを探しています。
皆さんも時々は本屋に行きませんか?
新しい出会いがあるかもしれません。
無責任一代男
先日テレビを観ているとクレイジーキャッツの特集がありました。
クレイジーキャッツは半世紀前に一世を風靡したコメディーバンドです。
1960年代、私の中学生時代です。
どのチャンネルをつけてもクレイジーキャッツが出ていました。
その歌詞からの風潮に、団塊世代が大きな影響を受けました。
クレイジーキャッツの歌には「スーダラ節」「無責任一代男」「日本一のホラ吹き男」などがあります。
この中でも特に「無責任一代男」の歌詞は衝撃的でした。
「楽して儲けるスタイル」とか「とかくこの世は無責任。コツコツやる奴はご苦労さん」などの歌詞。
面白可笑しく流されるこの歌詞の影響からか、「要領良く」生きるのが良い生き方のような勘違いを起こしてしまいました。
これは私ばかりでなく、同世代の子供たちにも影響を与えたと思います。
人から、「もっと要領良くしろ」とか、「余計な苦労はするな」と言われました。
コツコツ仕事をする人を「要領が悪いな!」と思ったものでした。
今は勿論コツコツ仕事を重ねて行くことこそが大事だとわかっています。
しかし子供の頃に受けた影響はなかなか抜けませんでした。
そして周りの大人もそれを指摘してくれませんでした。
真面目なことを言うと、「何を青臭いことを言う!」とバカにされました。
今更に、当時のテレビは子供達に大きな影響を与えたのだと思います。
たかがテレビ番組ですが、改めてその影響の大きさを考えさせられます。
プリンター
事務所で使っているインクジェットプリンターが、とうとう使えなくなりました。
15年前に買い、7年ほど前に1度メンテナンスに出して使い続けてきましたプリンターです。
紙が入って行きません。
紙送り用のゴムローラーがダメのようです。
汚れ取りシートを使い、きれいにして見たのですが、それでもダメです。
それ以外の機能は問題なく正常に動くのに。
この耐久性。
改めて日本メーカー製品の優秀さに驚きます。
15年も使っていればもう十分元は取れているのですが、まだまだ使え勿体無い。
そう思っていました。
でもこの状態では仕事ができません。
決心して、先ほど新しいプリンター買っていました。
同じメーカのエプソンです。
来週セッティングします。
これから使って15年後、私は82歳。
プリンターと私。
どちらが長生きできるか!!
フッとそんなこと考えてしまう年の初めです。
正月明け
今日から仕事始め。
7日間の正月休みとなりました。
2家族の子供たち家族と新しい年を迎えました。
1日には息子家族、そして今日、長女の夫もスエーデンに発ちました。
一気に居なくなり寂しくなります。
それでも今いる長女と孫娘2人。
楽しい日がしばらくは続きます。
今年も良い年でありますように願って居ます。
日本酒
今日は29日、年末大詰め。
忘年会は終わりましたが、これからもまた年越しだ!正月だ!新年会だ!と飲み会が続きます。
冬、それも正月に飲むなら日本酒でしょうか?
先日読んだ雑誌サライに日本酒特集が載っていました。
その中に日本酒の燗の温度による呼び名が書かれていました。
紹介します。
5度 雪冷え
10度 花冷え
15度 涼(すず)冷え
30度 日向(ひなた)燗
35度 人肌燗
40度 ぬる燗
45度 上(じょう)燗
50度 熱燗
55度以上 飛び切り燗
「雪冷え」「花冷え」「涼冷え」という呼び名は素敵ですね。
また、ここまで細かく分けて名前まで付けているのはやはり日本人らしです。
これからお酒を飲む時、豆知識として披露してみてはいかがですか?
酒の場も盛り上がりそうです。
仕事納め
今日は仕事納め。
掃除をし、正月飾りをして帰ります。
昨夜から長男家族が来ており、既に来ている長女家族と合わせて10人で正月を迎えます。
長男家族は毎年来てくれるます。
親が2人で過ごすのを寂しいと思っているのでしょう。
でも決してそんなことはありません。
私たち夫婦2人で正月を迎える時はとても静かに正月を迎えていました。
この正月は賑やかになりそう。
子供達の優しさが嬉しいものです。
通信簿
自宅の私の本棚を整理していると、束になった私の通知簿が出てきました。
小学校、中学校、高校までの全ての通信簿がありました。
それに小学校、中学校の卒業証書、小学校運動会での徒競走で1等になった時の賞状、中学校3年間の皆勤賞までありました。
思い出しました。
私が結婚した時、母が私に渡してくれたものです。
もらった当時は今更見る気にもならず、仕舞い込んでいたのです。
でも、今になってみれば、いかに私を大切と思っていてくれたのか!
机の上にある父母の写真に手を合わせました。
通知簿の中身はそれ相応の内容でした。
大事なものはスキャナー保存し、あとは証拠隠滅しました。
今、母を身近に感じています。
柿
先日、市場で柿を買いました。
冬のこの時期に柿です。
大きな柿が4個で100円。
つい8個買いました。
熟しきった柿だから安かったのでしょう。
私は小さい頃からこの柔らかくなった柿が好きでした。
柿の上の方を少し切って、スプーンですくって食べます。
トロトロで甘いのです。
私の父も大好きでした。
東京生まれの妻は嫌がります。
「柿は硬いもの」と言います。
カリカリした柿が好きです。
私もカリカリした柿は好きですが、柔らかい柿の方が好きです。
北海道の柿が柔らかいのには理由があるのです。
柿が採れない北海道は、柿は内地から貨車で運ばれれて来ました。
運ばれている内に熟し柔らかくなってしまいます。
だから柿が柔らかいのは当たり前でした。
柔らかい柿の皮をむいて、垂れる果汁を吸い込むように食べました。
それをしばらく置いておくと、スプーンですくって食べられるくらい柔らかくなります。
今朝、最後の1個食べてきました。
やはり旨かった。
普通の生活
ある小説に「結婚をして大勢の子供を育てている真面目な者の方が、人口問題を語っている者よりずっと世の中の役に立っているというのが私の持論だ」という節があります。
仕事を持ち、結婚し、子を産み、しっかり育てて行くという普通の生活をする人は沢山います。
決して特別なことはしないが、毎日一生懸命に生きて行く。
特別頭がいいわけでもない。
容姿が特にいいわけでもない。
どこでもいる、ごくごく普通の人の生活。
それこそが世の中、社会を作っている。
それを改めて思わせてくれました。
普通の生活ができるということは素晴らしいことです。
勇気
「勇気とは慣れた自分を捨てること」
これはラグビー日本代表ヘッドコーチだったエディ・ジョーンズ氏の言葉です。
頑張って、高くて安住した生活を手に入れると、人はそれに慣れて生きます。
常にチャレンジし続けて、何度も自分を脱皮する。
それはなかなか、凡人にはできないことです。
この言葉を読んで思ったのはピカソでした。
ピカソは常に新しいことに挑戦していました。
ピカソの画風は常に変わっていったそうです。
調べてみると「青の時代」「バラ色の時代」「アフリカ彫刻の時代」「キュビズムの時代」「新古典主義の時代」「シュルレアリスムの時代」があります。
普通は、天才と言われた画家でも、1つの自分の型が出来るとその傾向の絵ばかり書きます。
それで絵も売れ、名声も得れます。
しかし頻繁に自分の型を壊し、新しい型を作っていたのはピカソくらいでしょうか。
10月に折角スペインに行ったのにピカソの絵を見ていなかった。
今、後悔しています。
食器収納ケース
今日、我が家に食器収納ケースが入りました。
妻の買いたいとのたっての願いで、2週間ほど前に自分でショールームへ行き決めて来ました。
お昼食時に家に帰りそれを見たのですが、普通の食器棚と違います。
ステンレスのカウンターでキッチンの延長のようなもので、幅が2メートルあります。
壁には棚も取り付けられています。
専門業者が来て取り付けていました。
今頃は作業も終わり、嬉しそうに食器を収納している妻の顔が目に浮かびます。
妻は今まで「節約・節約」と色々我慢してきたこともあり、時には大きな買い物もいいでしょう。
私はこれで妻が料理作りに熱を入れてくれると美味しいものが食べられるので嬉しいのです。
が、果たしてその思い伝わっているか少し不安です。
外国人スタッフ
14日から上京し、浅草のホテルに宿泊し、きょうチェックアウトとします。
このホテルはまだ新しいようで、なかなかい居心地のいいホテルです。
朝、食事をしにレストランに入ると、びっくり。
スタッフ全員が白人系の男女の外国人ばかり。
もちろん全員日本語ができ、会話に支障はないのですが、「なぜ?」という疑問符が頭に浮かびました。
人手が足りなく、外国人を雇用する例はよくあります。
でもその場合は、ほとんどがアジア系か南米系のひとです。
なぜこのホテルは白人ばかり揃えたのか。
朝食代は2,500円で、内容も充実したメニューです。
食事をする人は半分くらいが外国人。
白人スタッフ雇用するのはステータスアップのためか。
興味あるので、チェックアウト時にフロントで聞いたみたいと思います。
煮物
ある本を読んでいて、成程と思うことが書かれていましたので紹介します。
「煮物っていう料理は煮れば味が沁み込むということはない。
火を止めて、冷ます時に、味が沁み込んでいく。
人生もそうではないか」
確かに、懸命に生きてきても、時として寂しい時や辛い時、つまり冷えている時に人間味が増してくるのではないかということです。
人生は順風満帆ばかりではありません。
寂しい時辛い時があります。
それを味わってこそ人間味が出ます。
それを避けて生きていては、少しも魂は磨かれません。
歳を取ると実感してくることです。
温かい気持ち
不便さは人を優しくするかもしれません。
雪国では雪が降った時、歩道は畦道状態になります。
人1人通るがやっとという狭さです。
先日も狭い雪道を歩いていると、急に前がつかえていました。
先頭には足の悪そうな杖をついた高齢の女性がいました。
雪道が滑るので、より慎重に歩きます。
そのためほとんど前に進みません。
その後ろの人達は黙ってその歩く速度に合わせていました。
文句も言いません。
でもその足の悪い女性は自分の後ろに人がいるのに気付いて、「アッごめんなさい。どうぞ」道を譲ってくれました。
後ろの人達に向かって「ごめんなさい」と言い、後ろの人は「ありがとうございます」と言って横を歩いて行きます。
見知らぬ同士が街中で声を掛け合います。
ある時はその狭い雪道で、子供を乗せたソリを引くお母さんい行き違いました。
私は傍に寄って通るのを待っていると、お母さんは「ありがとうございます」と言います。
ソリに乗っている子供も「ありがとう」と言って行きました。
不便な時はお互い様。
少しの心の余裕が優しい気持ちにさせてくれます。
「どうぞ」「ありがとうございます」
そんな当たり前の言葉が自然に出て来る。
不便な雪国の暮らしですが温かい気持ちになります。
自分
仕事時間が終わり、ふと1日を振り返ると、今日1日何をしたのか!
時々そんな思いに陥ります。
先ほど本屋に行ったとき目に入ったのが、「今日が人生最後の日だと思って生きなさい」という本です。
読みはしませんでしたが、確かにそう思います。
その繰り返しの中で、1年がアッという間に過ぎていきます。
そして確実に自分の人生を刻んでいきます。
1日1日大事だと思いつつ、また無駄に過ごしている自分。
反省を繰り返す。
それが私なのかもしれません。
3という数字
たまたま知りましたが、スカイツリーの足は3本だそうです。
東京タワーは4本足で、4本足の方が安定するのではないかと思っていました。
3本足というと、古代中国の器で鼎(かなえ)も3本足です。
スカイツリーはわかりませんが、3本足の方が安定します。
床がデコボコしていても3本足なら安定します。
4本足の椅子だとグラグラします。
足が5本6本と増えれば増えるほど安定しません。
3次元というのもあります。
1次元・2次元より具体的です。
飛び出す時も「1・2の3」と掛け声を出す方が勢いがつきます。
会社の方針も3本にまとめて置く方がわかりやすいです。
社員も理解しやすいし、覚えやすい。
また事業も数多く手掛けず、3事業に集中するのがいいのではないでしょうか。
3という数字は不思議な数字だと思います。
子供の姿
先日、JR留萌線が廃止になりました。
最終駅の増毛駅は高倉健さん主演の「駅 STATION」でその舞台となりました。
少し寂しいです。
高倉健さん主演で北海道の鉄道を舞台とした映画はその他にも「鉄道員(ぽっぽや」があります。
その舞台となった幾寅駅は幌舞駅という名前で出ていました。
幾寅駅は無人駅ですがまだ使われているようです。
先日テレビで「鉄道員(ぽっぽや)を観ました。
観るのは3回目でしょうか。
観るたびに涙腺が緩みます。
高倉健さんが演じる主人公の佐藤乙松には娘がいました。
その娘は赤ん坊の時に死んだのですが、なぜか姿を変えて乙松の前に出てきます。
そして最後には末広涼子さんが演じる高校生の姿で現れ、その時に乙松も死んだ自分の娘が姿を変えて現れてくれたのだとわかります。
一生懸命仕事に生きてきたお父さんに「お疲れ様」という思いを表すために出てきたのです。
映画でその様子を見た時、こんなことを思いました。
同じ子供でも、赤ん坊の時、幼児の時、幼稚園の時、小学生の時、高校生の時と、その時々で違った人格で生きています。
その時その時が、かけがえのないその子の姿なのです。
そう思うと、これから2度とない今の子供の姿の存在そのものが愛おしくなってきます。
しばらく前から孫と一緒に過ごしています。
可愛い2人の孫娘。
毎日そのような気持ちで接しています。
雪道
昨日、路面に降った湿った雪が今朝は凍っています。
どこもかしこもスケートリンク状態。
特に交差点の路面は鏡のように太陽の光が反射していました。
そんな道を夏タイヤの自転車が走ります。
本人も怖いはずですが、周りの人、そして車の運転手がより怖い思いをしているはずです。
ツルッと横滑りして引っ掛けられたり、車の下に入ると考えただけでゾッとします。
歩く人は足元を見て転ばないように歩きます。
それなのにスマホを見ながら歩いている人がいます。
信じられない!
雪道を歩く時、大切なのは靴です。
滑らないように工夫されている靴を選びます。
価格が少し高くても、怪我をすることを考えればいい靴を買うべきです。
私の靴は「どの靴より滑らない」と定評ある靴です。
確かに他の靴より滑らない・・・・
と思うのですが気のせいかもしれません。
何か時忙しい師走。
走らないようにします。
狭小な意見
人と話していて、よく思うことなのですが、あまりにも狭小的な考え方をする人が多くなっているように思います。
これだけ情報が溢れている時代で多様な意見を知ることができるのに、自分の考えに固執する人が多くなったように思います。
それはもしかしたら情報が溢れていて、それに流されないようにしようと思うためなのでしょうか。
そのような現象は世界中で起きています。
極右と極左、宗教の中でも原理主義の主張など、極端な方向に人の心が惹かれています。
相手が間違えている。
自分の意見を絶対に譲らない。
自分の考えが絶対に正しい。
そして自己主張こそが自分表現であり、それは正しいこと。
それが自由主義・民主主義だと世界中で教えられてきました。
それは正しいのですが、それに固執するあまり、逆に自分自身を失っているように思います。
極端な考え方に傾倒するのは、考える努力を放棄しているのかもしれません。
極端な考え方をする方が楽なのです。
では今、必要なことは何か。
1つは人の意見を受け入れることのできる度量を身につけること。
それを身につけるには古典などを通しての人間学を学ぶこと。
もう1つは、人の意見を理解するための勉強です。
ネット情報に頼るだけでなく、本を読むこと。
本を読むことで深い理解が得られます。
特に反対意見の本を読むこと。
今の世の中で真っ当に生きるには、この2つが大切なことのように思います。
京都の経営者
先日、奈良の経営者のことを書きました。
その時、奈良の経営者と京都の経営者とは何が違うのか。
京都には日本を代表するような企業が数多くあります。
奈良には古いけれど大きくなりきれない企業が多いのです。
何が違うのか。
今日稲盛さんが20年前に書かれた本を読んでいると、京都の経営者のことが書かれていました。
京都はベンチャー企業発祥の地だと言われているようです。
ローム、ワコール、オムロン、村田製作所、任天堂、京セラ等がそうです。
そのようなベンチャー企業がなぜ京都で生まれたのでしょうか。
稲盛さんは京都の経営者に共通した気質があると言います。
1つは冒険心が強いこと。
2つ目には挑戦的であること。
3つ目は勝ち気で負けん気が強いこと。
4つ目は創造的であり独創的であること。
5つ目は正義感に溢れていること。
6つ目は陽気で積極的なこと。
7つ目は反骨精神、反権力的精神の旺盛なところ。
8つ目は大変努力家。
稲盛さんはこの8つをあげていますが、先に上げた企業は互いに親密な交流があるようです。
京都という狭い土地にあるのですから、競争相手であっても互いに切磋琢磨し刺激し合う環境にあることも、優良企業育成の土壌になっていたのかもしれません。
12月
先ほど東の空に綺麗な虹が出ていました。
虹を見るたびに「虹の根元には宝がある」という話を思い出します。
この歳になってもフッとそのことが思い起こされます。
今日から12月。
クリスマスです。
サンタクロースもそうですね。
おとぎ話とは分かっていても、孫娘と話す時は結構その気になっています。
歳を取っても空想の世界を垣間見る。
そんな季節になってきました。
自己主張
人とトラブルを起こして新聞沙汰になっているという事件がよく見受けられます。
互いに自己主張が強いとそのような問題が起きます。
戦後、日本には民主主義とともに西洋的考え方が入ってきました。
自己主張もその1つです。
自己主張は自分の存在を示すことであるとして奨励されました。
相手を論破するデイベートで訓練することもあります。
あえて対立の状況を設定して、相手を言い負かす訓練です。
それとは逆に日本は昔から自己を抑えることが美徳とされてきました。
高倉健さんのヤクザ映画のように耐え忍ぶ姿に共感を感じたものです。
「人様に迷惑をかけないようにしなさい」と親からも教えられました。
戦後そのような考え方は否定されてきたように思います。
自己を主張するという考えは西洋的考え方です。
それが日本人にとって幸せな生き方なのでしょうか。
疑問に思います。
自分を主張して相手をやつけてしまう。
自己顕示欲を満たす生き方。
それがいいのでしょうか。
自分を抑えて、周りの人に心を払い、慎ましく生きていく。
それにより人間性が養われていく。
私はそのような生き方がいいと思うのですが・・・
悪口
先日、一緒に住んでいる孫娘が急に、「おじいちゃんのバカ」と言いました。
それまで悪い言葉を言ったことがないのでびっくり。
悪口を注意して、どこでバカという言葉を覚えたのかを聞くと、テレビの番組アンパンマンで知ったそうです。
世の中には悪口の言葉が溢れています。
子供の世界でも、悪口を言うことが当り前のようになっています。
だからこそ我が家では悪い言葉は使わないようにしています。
時として、人は悪い言葉を口にして他人を罵ります。
そして悪口を言う者同士はすぐ同調してしまいます。
結果イジメなどが起きます。
いい言葉はなかなか口から出てきません。
訓練が必要です。
ならば小さい頃からいい言葉を使うことを教えるのが大切なのです。
孫には「いい言葉を使えば運が良くなる」「いいことがたくさん起きるよ」
そんなことを言ってあげます。
子供騙しと言う人がいるかもしれませんが、そうではありません。
本当にいい言葉、優しい言葉を口にする人にはいい人が集まります。
そうするといいことが起きます。
悪い言葉を言う人には悪い人が集まります。
そうすると悪いことが起きます。
同じモノを引き寄せてしまうのです。
大人になってもそんな大事なことがわからない。
単純なことがなかなか出来ない。
そんな大人が多いです。
私は「おじいちゃん」としてそんなことを孫から学んでいます。
奈良の経営者
昨夜、奈良の経営者の話を聞きました。
奈良は古い町だけに何代も続く店が多いようです。
でも決して大きく事業を拡大してこなかった。
仕来りや伝統が邪魔をしてきたのではないかと奈良の経営者は言います。
一方、すぐ隣にある京都は同じ古都でありながら、日本を代表する大企業が軒をなしています。
奈良も京都も仕来りや伝統があるのは同じでしょうが、なぜこんなに事業の規模が違うのでしょうか。
昨夜の宴席で私の隣に座ったのは鳥取の若い経営者でした。
人口50万人の鳥取でも事業の拡大は難しいと言います。
何が違うのでしょうか。
地域によって、住む人によって何が違うのか、
何を変えれば変われるのか。
地域格差だけでない何かがあるはずです。
それを研究している人もいるのでしょうが、本当に興味があります。
エゴブーム
昨日から奈良に来ています。
宿泊しているのはJR奈良駅近くのビジネスホテルです。
このホテルには歯ブラシや髭剃りセットがありません。
必要ならブロントへ申し出るそうです。
「エコ」のようです。
「エコ」といえば、いつ時からかスーパーでエコ袋が3円ほどで売られるようになりました。
「環境のためにマイバックを使いましょう」という考えから始まったはずですが、今では無料だったレジ袋が3円で売られているだけの結果のように思います。
単純計算すると、スーパーにしてみれば、3円の経費がなくなり、逆に3円の売上増。
最終的に利益が6円増えたことになります。
昨日、買い物するために入った奈良のスーパーは、レジ精算時に「レッジ袋はいらない」と言ったら2円引いてくれました。
このやり方の方が「レジ袋分の売上増をねらった」と思われません。
北海道とは考え方が違っているようです。
今、宿泊しているホテルは昔からある全国チェーンのホテルですが、色々なところで「節約」しています。
先ほどの歯ブラシや髭剃りセットがないばかりか、固形石鹸もなくバスのところにあるボディーシャンプーを使うようです。
それはそれでもいいのですが・・・・
トイレも清掃不十分で「サボったリング」が浮いています。
長い髪の毛が落ちています。(ちなみに私は坊主頭)
昔に流行った「エコブーム」
いつの間にかお客様を忘れた「エゴブーム」になっていないでしょうか。
このホテルは、この内容で宿泊費は1万円以上します。
高くなったものです。
奈良
24日木曜日に奈良で盛和塾大和の開塾式があり、私も参加して来ます。
明日23日は勤労感謝の日、休日なので1日早く行くことにしました。
奈良観光の目的の1つは法隆寺にある「九面(くめ)観音」を見ることです。
だいぶ以前になりますが、新聞でその観音様の写真を見た時、あまりにも可愛らしい観音様であったので、その写真を切り抜いて壁に貼っています。
その法隆寺のそばに藤ノ木古墳もありますのでそちらも見学して来ます。
斑鳩の道を歩くのも楽しみです。
法事
昨日、父の7回忌を開き、私どものホテルに30人程の人に来ていただきました。
普段会えず、法事でしか会えない人達もいます。
法事というものは日本独特な風習のようで、つくづくいい仕組みだと思います。
人が亡くなると、その人を通して繋がっていた縁も薄くなっていきます。
法事はその縁を再確認されてくれる行事です。
またひょんな事で、互いに遠い親戚同士が意気投合することもあります。
私の父方の従兄弟と母方の従兄弟は互いに遠い親戚であったため、挨拶をする程度でした。
その2人は経営者です。
昨日は私が紹介したきっかけでお互いに親しくなったようです
父の写真の前で2人で写真を撮っていました。
経営者同士の新しい付き合いが生まれそうです。
それも父が結んだ縁なのかもしれません。
来年は母の7回忌です。
皆さんにまたお会い出来るのが楽しみです。
雪が嫌い
北海道札幌にも雪のシーズンがやってきました。
東京から来て一緒に住んでいる4歳の孫娘は雪が大好き。
雪が降ると大はしゃぎ。
先日に20センチの雪が降った時は、1人で雪の中を遊びまわり、その夜は体調を崩してしました。
湿った雪のため手足が冷たくなったために体調不良が起きたようです。
私は雪が嫌いです。
私は雪が降ると「嫌だな・・・」と思います。
「冷たい、寒い、滑る、暗い」というイメージが湧いて来ます。
でもこんな私でも、昔は雪が降るとワクワクしたものでした。
いつの時から雪が嫌になったのでしょうか。
社会人になってもスキーに行く楽しみがあり、雪は嫌ではありませんでした。
もしかしたら結婚した頃かもしれません。
でもなぜ雪が嫌になったのかよく分かりません。
それでもその頃から私自身も何かが変わったように思います。
無邪気に雪を喜ぶ孫娘を見ていると小さい頃を思い出します。
この冬は孫娘と一緒に「かまくら」でも作って、雪遊びを楽しもうかと思っています。
長女と孫娘は来年春にはスエーデンに行ってしまい、しばらく会えなくなリます。
孫娘4歳
私67歳
2人の思い出を作ろうかな。
「和」
「和」が大事です。
よく言われることです。
ご存知のように、これは聖徳太子の言葉「和ともって貴しとなす」からきています。
喧嘩をしないで仲良くしなさいという意味と理解されています。
私もそう理解していました。
しかしそうではないようです。
哲学者の梅原猛さんの説によると、「和」があれば議論ができるということです。
和があれば議論ができて、色々なことをあげつらうことができます。
あげつらえれば理が通り、理が通りから事が成る。
すなわち議論を尽くすことが大事ということです。
議論が対立した時「まあまあ」と行ってことを収めることではないのです。
一つまた知識が増えました。
教養と修養
昨日、本屋で立ち読みをしていたら、ある本の中に「教養」と「修養」の違いについて書かれていました。
「教養」とは学問・知識をしっかり身につけること。
「修養」とは徳性をみがき、人格を高めること。
大学の1年生の時に、一般教養課程である「教養部」というのがあります。
歳をとって学ぶのは「教養」ではなく「修養」でしょうか。
修養の教材としては古典だとその本では述べています。
納得し、これから古典を学んでみようかと思っています。
平和と平等
「平和な格差」「平等な戦争」
ある本を読んでいる時にピケティが言った言葉として紹介されていました。
ピケティは「21世紀の資本論」を書いて注目されました。
「平和な格差」とは平和であれば経済格差が生まれていくもの。
一方、「戦争」になれば全ての者が「平等」に戦争に行くことになります。
読んでいる本は佐藤優氏と池上彰氏の対談で、題名は「新・リーダー論」
その中で佐藤氏は「平和と結びつくのは平等ではなく格差。
そして平等に結びつくのは戦争。
戦争が起これば金持ちの子供も、庶民の子供も『平等』に戦争に行かざるを得ない。
これはピケティの『21世紀の資本』から読み取れます。」と述べています。
アメリカのトランプ氏が大統領になりました。
妙に結びつけてしまうこれからの世界の政治の流れ。
少し怖いものを感じます。
資本主義
稲盛和夫さんと梅原猛さんとの対談が書かれた本を読んでいます。
対談の題名は「原・資本主義のすすめ」です。
その内容は現状の資本主義における弊害について語られています。
この対談は平成7年にされたものですから21年も前ですが、現在にも通じる内容です。
主な内容は、利潤追求が自己目的化している資本主義の問題点を指摘しています。
話の冒頭にで出てきたのがマックスウェバーが説くプロステンティズムをベースとした資本主義です。
資本主義が勃興した時は倫理観に裏付けされた資本主義でした。
その様子を梅原さんは「片方にバイブル、片方にそろばん」と言っています。
これは渋沢栄一が書いた「論語と算盤」と同じことでしょうか。
そして稲盛さんは次のように言っています。
利潤を追求することは大切ですが追求した利潤をいかに散財するか。
従業員のため、株主のため、さらにお客様に対する利益の分配。
さらに利潤があれば文化や社会に還元する。
倫理観に基づく資本主義の大切さを述べています。
今、アメリカ大統領選挙が行われており、今日その結果が出ます。
アメリカはプロテスタンティズムに基づいた資本主義発祥の地です。
そのアメリカの資本主義は爛熟しています。
選挙の結果がどうなるにしても今の流れは変わらないでしょう。
しかし、世界中に新しい資本主義を模索する動きはあります。
その時、一度原点に戻ってみるのもいいかもしれません。
頑張る日本
電通に厚生労働省の労働局が家宅捜索に入ったというニュースが流れてきました。
200時間を超す残業、それを会社くるみで隠蔽したという疑いがあります。
新入社員が自殺したというのがキッカケのようです。
その自殺した女性社員は東大出で、ガッツのある人だったようです。
その人が自殺したというのは余程のことだったのでしょう。
社員を自殺に追いやる会社は論外です。
働く社員を幸せにすることは社長の責任です。
一方、このような超過残業による問題が提起されるたびに、「働くことが「『苦』なんだ」という誤解が若者に広まるのが心配です。
稲盛さんがいう「誰にも負けない努力をしなさい」というのは第一に会社のトップに向かって言っている言葉です。
社長が誰よりも働いて会社を引っ張って行くのです。
そして働くことの意味、やりがいや楽しさを教えていくのが社長の仕事です。
仕事に意味を見つけ、働く喜びを社員が知れば、少しぐらい厳しい仕事でも立ち向かっていけます。
今の日本の豊かさは20年30年前頑張った先人たちの結果です。
その豊かさを20年ご30年後までに伝えて行くのは今の私達の義務です。
頑張る人を応援し支援する日本。
そんな活気ある日本を守っていかなければなりません。
アドラーの心理学
アドラーの「嫌われる勇気」を読み返しています。
アドラーはフロイト・ユングとともに3大心理学者として有名です。
この本を読んで思うことは心理学は哲学であるということです。
また、稲盛さんの考え、仏教的思想に相通ずるところがあります。
この本に影響されている人が身近にいます。
この本の内容を少し自分のものにしたいと思っています。
高校野球
昨日テレビのニュースを見ていると、高校野球秋季東京大会の結果が流されていました。
その時のインタビューで話された、勝ったW高校の主将の言葉が少し気になりました。
彼はプロも注目する選手ですが、当日はスランプで全く打てません。
それでも他の選手が活躍し勝てました。
インタビューでその主将が「周りに助けられました」と言いっていたのです。
「?」と思ったのが「周り」という言葉です。
「周り」とは他の選手のことを言っているのでしょうが、「周り」の選手がいるということは「中心」の選手がいるということです。
それが自分であると言っているようなもの。
勿論、チョットした言葉の間違いかもしれません。
本来なら「他の選手皆んなのおかげです」と言えばよかったのです。
高校生の時から注目される選手は自分が1番と思い、周囲の人もそれを認めます。
だからこそ側にいる大人たちが精神的に支えなければなりません。
将来1人の人間として成長していくためには、高校生の時のしっかりした指導が大切です。
その本人の将来のためにも、嫌のことを言う大人が必要なのです。
ただこの選手は才能ある選手です。
これからが楽しみであることは確かです。
カップの取っ手
今朝コーヒを飲んでいる時に思ったことです。
取るに足りないことなのですが。
西洋から入ってきたカップには取っ手が付いています。
同じ器でも日本の器には取っ手が付いていません。
なぜだろう?
取っ手が付いている方が片手で持つことが出来、持ちやすいです。
持ちやすいのであれば、なぜ日本の器には取ってを付けなかったのだろうかと考えました。
器に入っているものは飲み物であり食べ物です。
日本人にとっては、口にする物が入った器を両手で持つことが重要だったのではないでしょうか。
感謝の気持ちを込めて「いただきます」の意味があったのかもしれません。
本当にそう意味だったのか分かりません。
私の理屈です。
でも私はそう思うことにしました。
モーレツ
人の働き方には色々あっていいと思います。
「趣味の時間を大切にしたい」「育児に時間をかけたい」「遊びに行きたい」という思いがあって、仕事よりそちらの方に時間をかけたいと考える人もいるでしょう。
それで幸せならそれでいいのです。
ただ一方、仕事をモーレツに頑張り、仕事を生きがいにする人もいます。
彼らや彼女らは、それなりに大きな夢があります。
皆が遊んでいる時、寝ている時でも頑張っています。
それは自分の夢を叶えるため。
ところが今の時代はそれを否定する風潮があるような気がします。
以前にも書きましたが12時間以上働いても苦でなく、休みがなくても生き生きとして働く人がいます。
このような人が会社を引っ張り、国を支えていると私は思っています。
モーレツに働く人がいて日本の会社が世界で戦っていけます。
仕事の時間を限定し、自分の時間を大切し、趣味で生きる人はそれでいて幸せであればいいです。
ただしモーレツな生き方をする人とは確実に金銭的、社会的地位の格差が生まれます。
それ踏まえた上で、決して格差を妬まず自分の時間を過ごしてほしいものだと考えます。
頑張った人には頑張った結果が格差として歴然と現れてきます。
その結果は平等です。
私は頑張る人を応援します。
今日はその頑張る人たちの勉強会、「北海道起業支援メンター協会」のマッチング会があります。
頑張っている人達の話を聞くのが楽しみです。
基礎的研究
今年のノーベル医学生理学賞に大隅良典・東京工業大栄誉教授が選ばれました。
大隈教授で日本人のノーベル賞受賞者は25人になります。
これからも日本からノーベル賞受賞者が輩出されるか。
気になるところです。
今の日本人のノーベル賞は20年、30年前の研究に対しての評価です。
地道で独自な基礎的研究が30年後に日の目を見たのです。
それに対して現在はどうでしょうか。
科学の基礎的研究より応用研究の方に重きが置かれているのが大勢です。
そのため20年後を不安視する声があります。
実業界でも同じことが見受けられます。
自社で地道な独自研究をして新製品商品を出すという、かってのソーニーのような企業が減っているように思います。
自社にない技術は手っ取り早く、パテントを購入したり、資金があればM&Aで会社ごと買ってしまうこともあります。
そうすれば早く儲かる商品を出すことが出来ます。
自社で基礎的研究するより効率的と考えるのでしょう。
大学の研究もそのような実業界の要望に応えようとしています。
そう考えると益々日本の研究・技術の蓄積がなくなり、刹那的な様相が見えてきます。
大いに心配なところです。
労働問題
「同一労働同一賃金」「過労死」「実力主義」
人手不足という状況もあり、労働に関する話が新聞等で取り上げられています。
仕事を8時間働くことも、人によっては苦痛と思う人もいます。
12時間働いても嬉々として働いている人もいます。
働く限りはやはり楽しく働きたいものです。
楽しく働くためにどうするか。
これが一番の問題です。
仕事に価値を見出し、やりがいを持たせることがいいと思います。
その安易な方法の1つがお金で釣ること。
歩合制があります。
しかしお金で釣ることは仕事の質を下げます。
これは過去の実例で明らかなこと
新聞に、ある人災派遣会社のことが取り上げられていました。
その会社は入社1年で平社員から部長に昇格できるという謳い文句で募集しています。
部長になれば年収1千万円になります。
その会社の求職に人が殺到しているそうです。
これも疑問に思います。
評価でも役職評価と金銭評価とは意味合いが全然違います。
仕事の実績はお金で評価することはあります。
しかし役職は人格・徳で選びます。
安易な方法で人を釣ると仕事の質が落ち、会社経営にも悪い影響を残します。
大事なのは「何のためにその仕事をしているのか」「目的は何なのか」「働く喜びは何なのか」
それを社員とじっくり話し合うことこそがやりがいのあり、質の高い仕事ができると思います。
それが経営者の大事な仕事です。
その経営者の仕事を放棄したのが歩合制であり昇進制度です。
経営者失格だと思います。
バフラバフラ
「バフラバフラするんでない!」と言ったら、キョトンとしている人がいました。
食事中に大きな布をたたんでいる時に言った言葉です。
相手は意味がわからなかったようです。
調べてみるとこれは北海道弁とのこと。
方言だと知らず使っていていました。
今の歳になって気づきました。
「へーそうなの」という気持ちです。
ネットで調べると「バフラ」とは布を振ったりする時に出る音の意味です。
60歳後半になるまで、いつも使っている言葉が方言だとは知りませんでした。
身の回りにはまだまだ知っているつもりでも、その意味を知らない言葉や仕草があるようです。
最近チョット驚いたことを書きました。
高齢者の最後の選択
私は60代後半になりました。
元気な年寄りが増え、ますます高齢者人口が増えて行くことでしょう。
先日新聞に、高齢化とともに益々医療費がかさむとありました。
またガンの高額医療のことも問題になっています。
一方、日本の財政は破綻に瀕しています。
このような財政では今まで通りの医療の保証がなされるとは考えられません。
それではどうするか。
そこで高齢者の心構えが重要になってきます。
ガンになって抗ガン剤をいつまで使うのか。
高度医療をいつから断るのか。
限られた財源しかない中で、寿命が少ない高齢者より、使うなら30代40代の人に使うのがベターです。
ある程度の年齢になれば、そのような医療を遠慮し、残された人生を有意義に使うことを考える。
それが高齢者のこの世に残して行く最後の役目なのではないでしょうか。
残された子や孫達のためにするべきことは無駄な医療をしないこと。
そのことが大切に思います。
直行便
今日の朝刊に「スペインへ直行便」という記事が出ていました。
今月の18日から就航したそうです。
私たちがスペインに向かったのが8日ですから10日後になります。
色々な事情で日程が変更できなかったので直行便を使うことが出来ませんでしたが、時間の違いは大きいです。
私たちが向かった時はパリ経由でした。
羽田からパリまで12時間。
パリで乗り換えのため5時間半待ち、エアフランス機で2時間かかりマドリードに到着。
20時間程かかりました。
直行便だと14時間30分ほどです。
この5時間30分の違いは大きいです。
歳をとると海外へ向かう時の時間は結構体にこたえます。
旅行出来るのもここ10年位でしょうか。
それでもスペインにいる娘夫婦に会いにまた行く時はぜひ使いたいものです。
山手と下町
先のスペイン旅行では古都トレドにも行きました。
トレドは大聖堂などがある旧市街全域が「古都トレド」としてユネスコの世界遺産に登録されています。
この観光の時のガイドさんの話です。
山の方には貴族や金持ちが住み、下の方には貧しい人達が住んでいました。
当時、ゴミや汚物は家の中から道路に捨てたそうです。
その臭いや不衛生な環境は大変なものだったようですが、雨が降るとそれらの汚いものは下の方に流れていきます。
結果、雨が降ると山手の方はキレイになり、下町の方はゴミが溜まります。
そのような環境ではペストなどの伝染病も流行るはずです。
東京でも山手と下町に分かれていました。
山手には上流階級が住み、下町には庶民が住む。
どこでも同じような構造だったのでしょうか。
スペイン旅行
15日にスペインから帰ってきました。
約10日間の旅。
バルセロナでマジョリカ島に住む娘家族と会うのも目的の1つでした。
今回の旅行は妻と妹家族、それに従姉妹を入れた6人旅。
マドリードのプラド美術館やバルセロナにあるガウディが設計したサグラダ・ファミリアなどを見て回りました。
観光と共に良かったのはやはり食事。
生ハムと、チーズ、ワイン。
皆旨かった!
その中でも、娘夫婦に連れられて行ったバルセロナ旧市街地にある「バル」が1番印象に残りました。
観光客がほとんどいない地元の人が集まる「バル」です。
食べ物もワインもこれまた旨かった!
それに人懐っこく、元気な親父さん。
古い町並みの一角にある「バル」は、まるで物語に出てくるような雰囲気のある店でした。
本当にいい旅の思い出になりました。
10年ごとに
高校を卒業し、浪人2年を入れて6年で銀行勤務。
銀行勤務が8年経験し、父の会社入社。
入社10年後に東京にホテル開業し支配人就任。
10年支配人を経て札幌の家具の会社へ配属。
それからもう14年経っています。
もうそろそろ変わる時期です。
残り少ない人生。
どのように変わっていくか楽しみです。
出来るという気持ち
10年ほど前、あるセミナーに参加しました。
2泊3日、昼食と夕食時間を除き、朝9時から夜中の2時までぶっ通しの講座が続きました。
2日目の夜には火渡り、最終日には弓の鏃を喉元に押し当てて矢を折るということも参加者全員させられました。
参加者は皆、火渡りも矢を折ることも出来ました。
このセミナーの目的は、「『出来ない』と思う弱い心に打ち勝ち、自分の可能性を信じること」だったと思います。
確かに「自分でも出来るんだ」と思う気持ちも沸きました。
「怖いけれど皆んな出来るのだから自分も出来るのだ!」という気持ちになります。
しかし今、改めてその研修効果のことを考えてみると、逆効果の方が心に残ったのではないかと思うようになりました。
「皆が出来る。なら自分も出来る!」となるのですが、もしも誰かが出来なかったとすると途端に「自分も出来ない」となってしまいます。
1人で挑戦しても失敗するのが怖い。
でも皆がするのであれば大丈夫だという他者依存の状態になってしまいます。
本当に大事なのは、失敗を恐れず挑戦する強い心。
誰かが失敗したかもしれない。
それでも自分はやりたい!
自分を燃え立たせる情熱。
そのためにはこのセミナーとは別のやり方があるはずです。
挑戦してみようという気持ち。
皆がやっていることを単に後追いするだけでは新しいことは何も出来ません。
あのセミナーは色々なことを教えてくれました。
四住期
五木寛之さんの本に「林住期」というのがあります。
インドヒンズー教のバラモンの言葉の「四住期」からきたものではないでしょうか。
「四住期」をネットで調べると人生は「学生期」「家住期「林棲期」「遊行期」とに分かれます。
学生期・・師のもとでヴェーダを学ぶ時期
家住期・・ 家庭にあって子をもうけ一家の祭式を主宰する時期
林棲期・・ 森林に隠棲して修行する時期
遊行期・・ 一定の住所をもたず乞食遊行する時期
若い頃は学び、成人してからは家族を持ち、子供を育てます。
定年になり、仕事が一段落すれば人生について学びます。
それが終わると、死ぬまでの間は何ものにもとらわれず生きて行く。
そのように理解しています。
今の私は「林棲期」でしょうか。
人生について学んでいます。
それはこれから迎える「遊行期」のためです。
何者にもとらわれない生き方。
それを学び、心の底に落とし込むためです。
欲も名誉も名声も求めない。
名もない一人の人間として死んでいくための準備です。
歳取ってもまだ世の中の役に立ちたいと思う「欲」さえ捨てます。
ただ単なる人間として死んでいく。
ただし、魂だけは磨いて。
そんな生き方がいいですね。
アンチエイジング
タレントの小泉今日子さんが「アンチエイジングは大嫌い」と言ったことが評判になっているそうです。
テレビの番組などを見ていると、年配の女性が若く見られ、「美魔女」ともてはやされ、喜んでいるのが流れています。
それは人の好き嫌いなので、それがダメだとは言いませんが、「アンチエイジングは大嫌いという小泉今日子さんの思いに共感します。
また「私は『中年の星』でいいんじゃないかと思ってます」とも言っています。
私の妻はほとんど化粧をしません。
出かける時に少し口紅を塗る程度です。
それでも年相応に妻らしさが出て私は好きです。
若いと言われることが嬉しいと思えることは、年取った自分が嫌だということ。
表面的にそれを隠すことです。
あるがままの自分であっていいいいのです。
本来の自分をそのまま見せて自然体で暮らす。
あるがままの自分を見せながら、心は常に好奇心を持ち挑戦し続ける姿こそが、その人が生き生きとして見えるのです。
その方が胸を張って生きていけるような気がします。
戦後71年
ある本を読んでいると「日清戦争」のことが書いてありました。
明治になって、日本にとっての初めての戦争です。
明治政府が出来てから今まで、日清戦争、日露戦争、第1次世界大戦、第2次世界大戦と4つの大きな戦争を経てきました。
幸いなことに第2次世界大戦以降、日本は直接戦争に巻き込まれてはいません。
終戦の年が1945年。
今年が2016年ですからその期間は71年になります。
一方、明治元年が1868年なので、日本にとって最後の戦争である第2次世界戦争が終わった1945年までの77年間、4回も戦争をしてきました。
同じくらいの期間、1度もその戦争を体験してこなかったのです。
これは凄いことです。
勿論、日本の平和憲法によるところが多いでしょう。
これからも平和が続くことを願います。
第2次世界大戦後、「戦争はもう嫌だ」と思う世界中の人の思いが国々の垣根をなくし、思いを共有しようという風潮が作られてきました。
しかし長い間、大きな戦争がない中で、その平和を求める思いに変化が起きてきました。
世界中でナショナリズム的思想が生まれてきています。
自国のことが第一。
他国の人のことはどうでもいい。
たとえ争いが起きても構わない。
そんな考えの人々が多くの国で増えて来ています。
自国のことを優先するあまり他国に敵対的態度をとる流れが生まれてきています。
またそれを煽る指導者が支持されています。
今の時代、世界中に自由に旅行が出来、ネットで各国の事情も分かり合える環境にあるのに、閉鎖的な考え方が増えきているのです。
不思議なことだと思います。
そのような世界の流れの中で、日本は自国の平和を守るため何をしたらいいのか。
それを真剣に考えなければならない時が来ているように思います。
エエかっこ
新聞などの報道で、地方議員の政務費不正取得問題が取り上げられています。
富山県の議員などは何人も不正議員が出てきています。
想像するに、善悪より損得勘定が働いたのでしょう。
「エエかっこ」という言葉があります。
「エエかっこするな」と言う人がいます。
昔、私の周りにもそう言う人がいました。
周りがズルいことをしていても、それを注意すると「エエかっこするな!」「お前もやれ!」となるのです。
「四角四面で物事考えるな!」と言われます。
そんな中で「エエかっこ」するというのは勇気がいります。
「エエかっこする」ことのどこが恥ずかしいのか。
人から偽善者と言われる。
甘い言葉に惑わされることもあります。
それでも「利己心を抑え込むために力(りき)むのです。
「エエかっこ」をするのです。
「利己心」を抑え込むために力(りき)むのです。
やせ我慢でいい。
勿論、完璧に利己心を抑え込むことが出来る人はいません。
でも、そうしようと思い、努力し、力むことが大切。
そう思います。
たらし
「たらし」という言葉は「女たらし」などと使われます。
女性を騙したり、言葉巧みに誘惑して弄ぶことを言います。
いい意味では使われません。
でも「人たらし」「人間たらし」はリーダーとして一番の条件です。
昔のヤクザの親分子分の関係もそうですが、会社のトップの条件でもあります。
またその「人間たらし」は1人に対してでなく、大勢の人をたらし込まなければなりません。
稲盛さんも「社員から惚れ込まれるような社長でなければならない」と言います。
惚れ込んでもらうためには、先に相手を惚れ込むことです。
社員1人1人を好きになり惚れ込むからこそ、惚れられるのです。
好かれる社長になるには、その前に社員を好きになることが大事です。
これが抜けると単に人気取りの行為になってしまいます。
仕事で厳しいことを言っても、社長に付いてきてくれる。
社員が社長に惚れているからこそなのです。
心の四季
芹洋子さんが歌う「四季の歌」という歌があります。
たまたまネットを見ていると、鮫島輝明さんという人が書いた「心の四季」という詩がありました。
春: 人に接する時は温かい春の心
夏: 仕事をする時は燃えるような夏の心
秋: 考え、思索する時は澄んだ秋の心
冬: 自分に向かう時は厳しい冬の心
さて自分はどうなのだろうか
自問させられる詩です。
東京と地方
新聞を見ているとよく討論会や講演会などの告知が載っています。
各種展示会も頻繁に開催されています。
有料・無料色々ありますが、そのほとんどの開催場所は東京です。
大手企業の経営者や有名評論家や作家などの話が無料で聞ける会もあります。
以前東京勤務の時は時間を見つけてはよく聞きに行っていました。
その時に聞いた色々な人の話はよく覚えています。
札幌にいると余程でない限り出かけて聞きに行きません。
地方と東京の格差は情報の格差、そしてビジネスチャンスの格差になるのかもしれません。
しかし地方にいてもビジネス情報やチャンスを求めて上京する経営者はたくさんいます。
以前にも書いたかもしれませんが、調剤薬局チェーンのアインファーマシーズ等を創業したアイングループの大谷喜一さんは、会社がまだ小さい頃、毎週のように上京して情報取集や人脈作りをしたという話を聞きました。
その母体である株)アインホールディングスは年間売上2,300億円を超す東京1部上場の会社になっています。
東京にいるとつい「いつでも行ける」「いつでも聞ける」「いつでも見れる」
そんな気になり、せっかくの機会を失っていることがかもしれません。
東京にいても、地方にいてもやはり志の有る無し、またその高さが結果を生むのでしょう。
これは私の反省です。
札幌の農業
先週、「札幌の農業を学ぶツアー」というイベントに参加してきました。
朝8時30分にバスで出発し、札幌市内にある農家などを訪問。
トウキビやさつまいの収穫体験、それに蕎麦打ち体験もあり、内容の濃いツアーでした。
移動するバスの中では札幌の農業実態の説明がありました。
札幌の人口は200万人弱の都会ですが、農家もあります。
しかしその耕地面積は年々減少しています。
平成2年には4,564haあった耕地が、20年後の平成22年には2,002haと半分以下になっています。
農業産出額も平成2年度は99億7千9百万円だったのが、15年後の平成17年度には40億2千2百万円と4割近くに減少しています。
農家戸数は平成22年度現在で993戸ですが、専業農家は全体の3割の293戸、あとは兼業農家です。
農家戸数の減少の原因には高齢化、農業所得の伸び悩み、それに伴い後継者が少なくなっているという理由があるそうです。
また市街化調整区域にある農地が将来、市街化区域になり住宅地として売るのを待っているという農家もあるようです。
今回訪問した農家は専業農家であり、懸命に作物の改良にも取り組んでいました。
このような頑張る農家が報われ、若い人が農業をしたいと思う農業構造の新しい仕組み作り。
その為には農地法の抜本的改革も必要かと思っています。
一方、北海道全体で見ると、カロリーベースですが食料自給率は北海道全体で208%(26年度概算)となっています。
大都会の東京や大阪は1%、神奈川も2%です。
いかに北海道の食料貢献度が高いことか。
益々農家の所得がもっと多くなることこそが大事だと思います。
このツアー出発場所が札幌JA北農ビルでしたが、大きく立派なビルでした。
農家の所得が低いままなのに・・・・・・・
そんな思いも感じました。
少数精鋭
会社経営において「少数精鋭」がいいという話をよく聞きます。
確かに無駄に人が多いよりはいいのですが、その「少数」とはどの程度を言うのかが問題です。
ある社長も「少数精鋭がいい」と言っていたのですが、幹部の1人が病気になり、急遽長期入院となりました。
1人の離脱により、途端に会社の運営に支障をきたしました。
他の社員は一杯一杯で仕事をしていたので、手が回りません。
幹部がいなくなったのですから、急遽人を手当てしようと思っても簡単に補うことは出来ません。
結局業績は低迷してしまいました。
少数精鋭の会社にするには、1人が何役もできる会社体制を作らなければなりません。
また小さい会社であれば、社長が欠員補充に入るのは当たり前です。
適正な社員数はどの程度なのか。
常に考えていなければならないのも社長の仕事です。
母
今朝、明け方に5年前に亡くなった母の夢を見ました。
夢の内容は私に子供が生まれ、子供を見せに実家に帰ったというものでした。
母の少しボケているような様子に、「頻繁に来てやららないとダメだな」と思ったのです。
目が覚めてすぐに思い出したのが、今日は母の5年目の命日なのです。
タイミングよく夢に出てきてくれたのでしょう。
朝は念入りに読経しました。
ちょうど5年前の今頃の時間に、お産で帰っていた長女から「おばあちゃんが今、息を引き取ったみたい」という電話を受けました。
母の最後は自宅で迎えれるようにしていました。
その時の長女も丁度今、子供を連れて里帰りしています。
幸せな私達を見守ってくれる気がします。
コセイヲ ノバセ
先日、電車に乗っている時、ある大学の新入生募集のポスターを見ました。
「コセイヲ ノバセ」と書いてありました。
「個性を伸ばせ」ということです。
最高学府である大学の広告にしては少し物足りなさを感じました。
それにしても「個性」という言葉は色々な意味に取られ解釈することができます。
辞書では「個性は他の人と違った、その人特有の性質・性格」とあります。
他人の目を気にせず自分の優れた個性を伸ばしなさい。
自由という言葉もそうですが、わがままな生き方も本人には個性的な生き方なのかもしれません。
どちらにしても、自分が生きやすい生き方がいいのですが、そこには大事なルールがあります。
自己責任です。
権利主張の一方には責任があります。
この2つを認識した上で個性的に生きていかなければなりません。
時として個性的な生き方を強調するあまり、それに必ず伴う責任についての認識が忘られています。
それでは責任を取りたくないから何もしないで、ひっそり生きていくことがいいのかというと、それもいいでしょう。
しかし満足しないそのような生き方も自分の責任です。
どちらにしても生きていくということは責任が伴います。
それなら、自分らしい生き方をする。
その覚悟で個性的な生き方を追求する。
結果。満足できる生き方ができるのではないでしょうか。
ありがたいことに日本という国は他の国に比べて安全で、命が取られるということはありません。
責任さえ取ればどのような生き方もできます。
歳を取るとしがらみが少なくなります。
これからは私も自分を生かし自由に生きれる時なのかもしれません。
人との出会い
フッと自分の人生を振り返ってみると、数え切れない人たちと出会ってきました。
会うその度に、良きことも悪いことも教えを受け、今の自分があると思っています。
多くの人たちのお世話になり今の人生があるのです。
今も多くの人にお会いします。
ついこの間までお会いしていた人と「最近会っていないー」と思うことがあります。
でも人との出会いは必要に応じて自然とセッチングされています。
時期が来れば人は離れ、また必要とされる人と出会います。
人間的成長とともに、出会いが生まれ、離れていきます。
それがその人の成長なのです。
それを不義理だと思う人がいるかもしれませんが決してそうではありません。
人は人との出会いで成長していきます。
いつまでも同じ人とばかり会っていては成長がありません。
私の歳になると、私と出会った人が成長していく姿は嬉しいものです。
これからも多くの人との出会いを楽しみにしています。
勢に求め 人に責めず
「勢いに求め、人に責(もと)めず」
本を読んでいて出てきた言葉です。
これは古代中国の孫氏の言葉です。
その意味は、「勝負は個々の人の能力より、勢いが大切だ」ということです。
広島カープの勝ち進む今の勢いがそれを表しています。
こんな時、監督は一々指示をしなくても、勢いで勝ち進むものです。
同じことが会社でも言えます。
トップが細かいことを一々指示している会社は能力ある社員がいても萎縮してその力を発揮出来ません。
逆に、社員が仕事しやすい環境を作り、雰囲気のいい会社は勢いがあります。
私の従兄弟の会社はそんな会社です。
彼はもうそろそろ60歳になるのですが、若い社員達と良くハイタッチをします。
会社ぐるみで「ほめ達」運動をして、テレビにも紹介されました。
今年の夏には、いかに多くの人とハイタッチをするかというギネスブックの記録に挑戦して新しい記録も立てました。
「ポケモンGO!」は出るとすぐ始めています。
会社に勢いを求める
これは社長の仕事です。
社長しかそれは出来ません。
仕事は厳しくても楽しい会社。
社員の勢いを大切にする会社。
これが成長する会社だと思います。
ウィッシュリスト
先日、朝のテレビにテニスプレーヤーの杉山愛さんが出て、阿川 佐和子と対談していました。
その対談の中で出た話です。
杉山さんがテニスプレーヤーとして現役を引退した時、何に向かって行けばいいのか分からなくなったそうです。
そこで今、自分のしたいことは何があるのか。
100個書き出しました。
ところが実際に書き出してみると30個ほどしか書けません。
「本当に自分は何をしたいのか」
それが分かっていないのが分かったと言います。
それでも時間をかけ、100個を書き出しました。
現在、書き出したウィッシュリストの内、30個は達成したそうです。
ネットで杉山愛というワードで探すと「杉山愛の"ウィッシュリスト100" 願いを叶える、笑顔になる方法 」という本が出てきます。
ウィッシュリストについては以前にも紹介したことがあります。
アメリカのバーバラ・アンさんが「Wish List」という本を出し、その本に感動した宇宙飛行士の向井千秋さんが翻訳して日本で出版しました。
「自分は今、何をしたらいいのだろうか」
そんなことで悩んでいる人は多くいると思います。
杉山さんのように一度、100個のWishの書き上げに挑戦してみてはいかがでしょうか。
私も以前書いたことがありますが、もう一度Wish List作りにチャレンジしてみようと思います。
参拝
今、長女とその孫娘2名と一緒に暮らしています。
上は3歳、下は4ヶ月。
上の孫が最近、朝、私が神棚向かい、お参りをする時、一緒にお参りするようになりました。
私の見よう見まねで、2礼2拍1礼をします。
「お参りをするといいことがあるよ」と教えています。
参拝する時、神様にお願いする人と、神様に感謝する人がいます。
お願いする人はまだ満たされていない人。
感謝する人は今は既に満たされている人です。
満たされている今に感謝する。
感謝するからまた満たされていく。
癌になったけれど、なったことを悲しむより、軽かったことに感謝します。
それが善循環になっているような気がします。
孫娘はまだ幼いので分からないでしょうから「いいことがあるよと」言っています。
神様という意識をもたせ、神様の前では謙虚になる。
その気持ちが感謝に結びつく。
それが大切だと思っています。
秋祭り
明日から琴似神社の秋祭りが始まります。
明日の3日は宵宮、4日は例祭になります。
私が小学校の頃は学校も休みだったのですがいまはそうではないようです。
4日の「渡御行列」には私も裃を着て参加します。
まだ暑い日が続き、汗だくになりますが楽しんで参加してきます。
夜には直会があるのですが、私は1ヶ月程前から禁酒中!
さて、お神酒を目の前にして我慢出来るか!
永六輔さん 2
昨日夕方、テレビのニュースを見ていると永六輔さんの葬儀の様子が映し出されていました。
黒柳徹子さんが弔辞を読んでいるとことでした。
永さんが夜中に欠伸がひどくて、つい自分の頬を叩くとアゴが外れてしまい、病院に行こうとタクシーに乗っても話すことが出来なかったことをユーモラスに話していました。
私も深夜放送のラジオにかじりついていた若い頃、永さんが同じ話をしていたのを覚えています。
葬儀の中で、ジェリー藤尾さんが永さんが作詞した「遠くへ行きたい」を歌っていました。
その時、フッとこの歌が作られた経緯を永さんが話していたのを思い出しました。
記憶が少しアヤフヤですが、それを少し紹介します。
永さんはインドの詩人タゴールの詩に影響を受けこの詩を書きました。
1人の若者がある時、「この世には私にふさわしく、私を待ってくれている人が必ずいる」と思い立ちました。
それから毎日旅をし探し続けました。
しかしいくら探しても見つかりません。
歳だけがどんどん取っていきます。
若者もいつの間にか老人になっていました。
ある冬の夜、旅の途中で道に迷いました。
寒い山の中、人にも会えず、ただ歩き続けました。
そうすと、遠くの方に明かりが灯る1軒屋がありました。
彼はやっとの思いでその家に辿り着ます。
その家には1人の女性が住んでいました。
彼は「今宵一晩泊めてください」とお願いします。
すると、その女性は振り向いて言いました。
「あなたが来るのを待っていました」と
老人はやっと会えたのです。
私を待ってくれている人がいたのだという喜びとともに、彼は力尽きその場で死んでいきました。
そう言うストーリです。
そんな話を思いながら「遠くへ行きたい」を聴くとまた感慨深いものがあります。
と同時に若い頃の自分も思い出します。
幸せにも私は見つけることが出来ましたが・・・・
小説
先週の金曜日に知人の千葉さんが来社されました。
千葉さんは商業ディザイナーながら、北海道に関する本を書いています。
先日も「勝納川(カツナイガワ)」という本を書き上げ、持ってこられました。
千葉さんが書くのは主に明治時代の北海道を舞台にし、史実に基づいた小説。
この「勝納川」という本は、明治元年に穂足内(ヲタルナイ)で起きた騒動を描いています。
この穂足内は現在の小樽にあり、この近くの銭函と同様にニシン漁で栄えた漁村でした。
当時はこの海岸線に多くの人が住みついており、まだ小樽も札幌もほとんど人が住んでいない時代です。
穂足内には役所があり、その近くの漁村や町を管理していました。
小説ではその穂足内役所を総勢600名が襲撃した俗に言う「穂足内騒動」と言われた騒動とその顛末を中心に書かれています。
題名の勝納川は穂足内を流れる川で、首謀者達4人が晒し首にされた場所です。
北海道で最初で最後の晒し首だったそうです。
千葉さんはこの「勝納川」以前にも「明治臨界」という小説も書いています。
これも史実を調べ、明治の頃の札幌・小樽の出来事、「札幌大火」「屯田兵と日清戦争」「遊郭」などが小説風に書かれています。
千葉さんは私より年上の70歳と少し。
本を書くために、図書館や資料館に足をはこび、現場にも出向きます。
ライフワークとして明治時代の北海道を書き続けています。
それが元気の元なのでしょう。
千葉さんの本、これからも楽しみです。
自分褒め
「自分褒めの勧め」
自分を褒めると言うと、少し首をかしげる人がいるかもしれません。
自分には厳しく、他人には優しくするのがいいと言われています。
でも本当に一生懸命仕事をしていてもなかなか結果が出ない。
色々しても先が見えない。
そしてどんどん自信がなくなり、不安になって来る。
そんなことありませんか?
そんな時には自分を褒めるのです。
例えば「伸幸!お前はよく頑張っている!」「伸幸!お前はえらい!」「絶対良くなるぞ!」と声に出して自分を褒めます。
声に出さなければダメです。
会社へ行く時、家から駅までの行き帰りに声を出して自分褒めをします。
自分で声を出しているのですが、その声を聞くと、自分以外の人が褒めてくれているような錯覚になります。
一生懸命頑張っている姿は神様が見ています。
神様が応援してくれているような気になります。
私も過去の苦しい時にこれを毎日しばらく続けました。
それにより、精神的にも落ち込みことなく頑張ることが出来ました。
一生懸命頑張っている自分。
こんなに頑張っている自分を自分が褒めなくて誰が褒めるのだ!
そんな想いです。
ちょっと辛い時。
「自分褒め」を試してみませんか?
きっと良くなりますよ。
経費について
最近思うことがあります。
会社経営において、利益の根幹は、稲盛和夫さんが言われるように「売上最大。経費最小」です。
私が疑問に思うことはこの「経費最小」とは、どのようなことを言うのだろうかということです。
経費は最小にしなければなりませんが、必要な経費は使わなければなりません。
「必要な」との程度は何を基準にするのか。
電気1つとっても、ホテルなどのサービス業ではお客様利用部分の照明をケチるわけにいきません。
従業員が使うバック部門の照明を小まめに入り切りすればいいのか。
でも照明を暗くすれば気持も暗くなり、それがスタッフの気持に影響を及ぼさないのか。
工場などは照明が暗くなればミスも多くなります。
メモ用紙を節約するために、チラシの裏を利用するということもあります。
でもそれでどれだけの経費が節約されるのでしょうか。
それより、経営者がそんな小さなことに神経を使うと、大きな事業構想が生まれないということもあります。
またサービスの最前線に立つ人は、権限委譲を受けなければ現場対応が出来ません。
権限委譲の中には「使用経費」も与えなければ、臨機応変に対応出来ません。
必要経費の捉え方は、結局その経営者の考え方によるのでしょう。
視点が社員にあるのか、お客様にあるのか。
近視眼的か長期的・全体的視点を持っているのか。
必要という意味をどう取るのか。
大きく言うとその経営者の器の大きさによるのだと思います。
行動力
昨夜はメンター協会のマッチング会がありました。
その時に出て来た話です。
最近の若い人達は何かあるとスマホなどを使ってネットで調べることが出来ます。
若い起業家も分からないことや調べたいことがあればネットで探し出します。
それは大変便利なことなのですが、ここが大きな落とし穴になっています。
ネットで調べて、それで全て分かった気になってしまう。
そのことが怖いのです。
経営者にとって大事なのは実際に確認することです。
現場に行き、見て、聞かなければ分かりません。
それでも分からなければ、多くの人を訪ね歩かなければなりません。
事業に成功している人のほとんどの人はそれを実践しています。
事実かどうかは自分の目で見て、聞いて、嗅いで、触ってそして時には味わうのです。
5感で感じて、理解するものです。
ネットの情報はあくまでも情報であり、事実かどうか分かりません。
昨夜、マッチング会に参加した起業経営者たちはそれを実践している人達です。
そしてその結果を出しつつある人たちです。
彼らの事業拡大の期待が益々高まります。
謙虚な心構え
盆休みから「村上海賊の娘」という本を読み始めています。
ご存知の方も多いでしょうが、この本は2014年の「本屋大賞」を受賞した本です。
面白い本です。
まだ読んでいる途中ですが、本の中心になっているのが、信長と一向宗大阪本願寺派との戦いです。
この中に一向宗本願寺派の軍旗のことが書かれています。
2行で12文字。
「進者往生極楽(すすまばおうじょうごくらく) 退者無間地獄(ひかばむげんじごく)」
この文言を記した軍旗は現在でも保存されているようです。
この部分を読んで、嫌な気持ちになりました。
人の心の弱さを救うはずの宗教が、その弱さを利用して信者を戦わせる。
そんな姿が見えます。
これは今のイスラム教のテロが用いる「自爆テロ」に似ています。
子供の自爆テロもあるようです。
宗教に帰依する人は心の安らぎを求め、素直で、謙虚な心になることを目指します。
ところが率いるリーダーによっては、時として全く別物になってしまう。
その時、信じている人は盲目となっています。
ただただ信じて言われたとおりのことをする。
人の心とは本当に弱く脆いモノです。
「私の信念は固い」と思っている人こそ、一度それを疑ってみる必要があります。
時として軟弱と言われる人の方が、色々な見方ができ、本当の姿が見えてくることもあるのでしょう。
今の世の中、正しいと言われていることも、本当は違うかもしれません。
変な考え方だと思っても、本当はその中に真実があるかもしれません。
何にも偏らないニュートラルな気持ちでいるのは難しかもしれません。
それでも、意見の違う人の話に耳を傾ける。
そんな謙虚な心構えが大切なように思います。
今日より出社
長い夏休みが終わり、今日22日から出社です。
休み期間は9日からちょうど2週間になります。
この間に色々なことがありました。
9日に入院・手術があり、12日の誕生日に退院。
翌13日から1週間、子供・孫ら17人が我が家に集まり過ごしました。
やっと今日から正常な生活に戻ります。
とはいえ、長女と孫2人は来年の春過ぎまで一緒に暮らします。
春になり少し暖かくなってからスエーデンに転居します。
それまでの間、少し賑やかな日が続きます。
孫は4ヶ月と、3歳の女の子。
この間まで妻と2人暮らしだったのが一変です。
でも楽しい日が続きそうです。
十省
何かあると私が書き綴ってきたノート「銘肝録」
それを見ていると、10年以上前に書いた「ノブの十省」を見つけました。
ノブとは私の名前です。
何かを真似て書いたと思うのですが、なかなかいいことが書かれています。
今日1日
1・満足した1日であったか!
2・充実した1日であったか!
3・生きている実感あったか!
4・生きている喜びあったか!
5・人を愛する喜びあったか!
6・人を喜ばすことあったか!
7・人に恥じぬ日であったか!
8・目的を持った仕事できたか!
9・会社の利益のこと考えたか!
10・一生懸命頑張ったか!
この「ノブの十省」、書いただけでしばらく忘れていました。
これからはこれを見て反省するようにします。
講座終了
7月7日から始まった「本気でお店つくり」講座が昨日終わりました。
最終日には日本政策金融公庫創業支援センターの所長にもお話をいただき、聞いた受講生の人たちも金融機関への垣根が低くなったように感じました。
今回の受講生は起業・創業を真剣に考えているようで、最終日に発表した事業計画書・収支計画書も大変充実した内容になっていました。
新しい起業家が誕生する。
そんな予感がします。
今後とも支援して行きます。
命の宝
昨夜の夢の中の話です。
私が誰かと話している時に口にした言葉がありました。
それが「命の宝」です。
夢の中で私は「これは大事な言葉だから忘れてはいけない」と言い、繰り返し口に出していました。
目が覚めた時、しっかり記憶されていました。
「命の宝」
それはまるで禅問問答のような言葉です。
私自身よく分かりません。
分かりませんが、何か大事なことのような気がします。
31日に叔父が亡くなり、通夜・告別式が昨日終わりました。
そんなことも関係しているのかもしれません。
しばらくは「命の宝」という言葉の意味を考えてみたいと思っています。
孫
三女がイギリスから家族と一緒に遊びに来ています。
今回初めて会った孫。
まだ1歳を過ぎたくらい。
名前はエンゾと言います。
この孫はよく食べよく寝ます。
回転寿司に連れて行くと、口の中いっぱいに寿司を突っ込んで、巻き寿司を2皿、フライドポテト1皿、それにいなり寿司1個食べ、その食欲には驚きです。
大きくなる予感。
この孫が寝る時、親は添い寝をしません。
エンゾはベビーベットに1人寝かされ、親が頭を撫でている内に寝ます。
途中で起きても余程のことでなければ親は子供のところに行きません。
これはイギリスでは当たり前のことだそうです。
小さい内から1人で寝かせる習慣をつけさせます。
日本とは大分違うみたいです。
あと2週間ほど滞在する予定です。
ちなみにこの孫、私に似ているところが2つあります。
鼻の低さと足の短さ。
可哀想という声もありますが・・・・
清濁併せ呑む
今、書店に田中角栄氏に関する本が多く並んでいます。
田中氏は人間的魅力に溢れた政治家だったと言われています。
私のイメージでは田中角栄氏は「清濁併せ呑む」人だったと思います。
度量の広さ。
それが人間的魅力だったのです。
その「清濁併せ呑む人」の意味ですが、「善いところも悪いところも併せ持っている人」という意味ではありません。
善人でも悪人でも、来る者はすべて受け入れる度量の大きさを表しています。
最近、世の中は、他人に対して寛容のない風潮が広まっているように思います。
小さな間違いをことさら大きく指摘することが正義のような考えがあります。
いかにも「自分は正しい人間なのだ」とあたかも主張しているようです。
勿論、正しい考え方を持ち、それを実践することは大切です。
常に自分の心を高める努力はしなければなりません。
しかし自分と意見が違うというだけで相手を拒否してしまうことは如何なものでしょう。
それではあまりにも狭小です。
会社などでもトップに立つ者は、常に高い見識を持ちながらも、清濁併せ呑む度量を持ち、大所高所から判断する能力が求められます。
最近田中角栄氏が見直されているのは、その度量の大きさに対する憧れがあるからなのかもしれません。
OODA
私は先日知ったのですが、OODAループ理論と言われる意思決定理論があります。
朝鮮戦争時のアメリカの戦略から来た理論ですから、大分以前からあったようです。
従来は意思決定理論としてPDCAと言うのがありました。
PDCAは「P:計画 D:実行 C:チェック A:行動」というサイクルです。
それに対しOODAは、Oが「Observe=観察」、Oが「Orient=方向付け」、Dが「Decide=決心」、Aが「Act=実行」となります。
2つの大きな違いはOODAは観察し方向付けるとことから始まることです。
一方、PDCAは計画して実行します。
サービス業などの現場のことを考えてみます。
PDCAは、前もってお客様の行動などを予測・計画してマニュアルを作ります。
そのため時として現場でマニュアルとは違うことが起きるとサービススタッフは対応できなくなります。
OODAは観察して方向付けることが先にきます。
マニュアル優先ではなく、お客様の行動や好みなどを観察し、方向付けます。
そのため現場にあったサービスができるのです。
またOODAではスタッフ1人1人の現場能力求められます。
結果スタッフが成長できます。
これからOODAループ理論が注目されるのではないでしょうか。
家族
今晩遅くにイギリスから三女家族が到着します。
初めて会う孫も一緒。
三女の家族が来るのを皮切りに、こらからの約1ヶ月間、我が家は賑やかな夏になりそうです。
賑やかどころか大混乱が予想されます。
来月4日から4日間は三女の友人が2人遊びに来ます。
そのあと、私の他の子供家族たちも帰省し、13日から総勢17人(大人10人、子供7人)が同じ屋根の下で暮らします。
その間、私の居場所はありません。
また盆には、私の妹家族5人も栃木から来るので大パーティを開く予定です。
楽しいことがたくさん起きそうな夏。
そんな気がしています。
利口な人
あなたは人から「賢い人ですね」と言われると気持ちがいいと思います。
でも「利口な人」と言われて嬉しいものでしょうか。
利口な人と言われると少し意味が違うようです。
利口という意味には頭がいいということと共に、ずる賢いという意味もあるようです。
賢い人と利口な人は外見わかりませんが、考え方や行動が違います。
全体を見る人と、その場その場の損得を見る人。
自分を抑えて利他を考える人と自分中心で考える利己な人。
そのような違いがあるように思います。
似たような言葉も英語にあります。
cleverとsmartです。
ネットで調べると、イギリスではcleverが賢いの意味があり、smartは狡賢いという意味があります。
アメリカではそれと反対にsmartが賢いで cleverは狡賢いという意味だそうです。
イギリスとアメリカではそれを分かった上で使い分けないとトラブルの元になりそうですね。
どちらにしても狡賢い利口な奴と思われたくはありません。
まだ、馬鹿な奴と思われる方が救われます。
一日一善
今はなぜか聞かなくなった言葉で「一日一善」というのがありました。
「1日に1回はいいことをしましょう」という意味です。
何十年も前に「一日一善運動」というのが日本中で言われました。
これを実行することは結構大変なことです。
善いことを1つすればいいと思っても、そのために1日それを意識して生きていかなけらばなりません。
朝に善いことをしようと思い、1日それを意識して暮らし、夜にそれが出来たかを確認する。
毎日の生活を意識して暮らすことで、結果充実した生活が出来ることになります。
その積み重ねがその人を成長させ、満足出来る人生が築けます。
「一日一善」という行為が習慣化することでその人の考え方が変わり、行動が変わり、結果環境が良くなっていく。
「一日一善」は人のためでもありますが、自分の人間としての成長を高めてくれることになります。
「情けは人の為ならず」に通じるのかもしれません。。
謙虚
人と話をしている時、話をしている最中に割り込んで自分の意見を言う人が時々います。
そうすると、話を遮られた人は感情的に反発したくなります。
先日もそのような人がいました。
その時は感情的にはあまりならず、「そういえば昔の私もそうだったな」と思ってしまいました。
人の話を遮ってまで話そうとする人は概して熱い人です。
そして同時に人の話を聞く耳がふさがっています。
叩き上げた中小企業の社長にはそのような人が多いようです。
自分に自信があり、自分が一番分かって正しいと思っているのです。
そのような会社はその社長の器以上にはなりません。
本当に多くの中小企業の社長がそうです。
逆に言うと、一歩引いて人の話を聞く姿勢さえ出来れば、その他大勢の大きくなれない中小企業の社長から脱却できるのです。
それが出来るかどうか。
謙虚さがあるかないかで決まると私は思います。
ことわざで「謙のみ福を受く」というのがあります。
その通りなのでしょう。
自信の無い若者
最近改めて思うことですが、若い人の中に素直に話を聞かない人が多いように思います。
アドバイスをしても自分の意見を主張します。
自分の意見を持って主張するから大丈夫かなと思って見ているとあまり上手くいかない。
むやみに自己主張する。
その原因を考察してみると、その若者の自信の無さから来るのでしょうか。
小さい頃から、親などの周りから一方的に言われ続けたきた。
結果、自分に自信が持てなくなってしまう。
そして人からの言葉を攻撃と捉え、自然と自己防御をする形が自己主張なのかもせれません。
益々素直で無くなり、自分の殻に閉じこもってしまいます。
これを打開する方法はあるのか考えてみました。
大変難しと思います。
ただ、本人は今の自分のことがわかっていて、変えたいと思っているはずです。
思っていても素直になれない。
これを打開する方法として1つ。
誰かこの人だけは自分のことを分かってくれると思える人を見つけること。
もしもそのような人に巡り会えなければ、本の中にそのような人を見付け出し、その人の本を徹底的に読んでみる。
そして人に知られることなく、コッソリと自分でその人が言っていることをやってみる。
この場合、本人にとっては「人知れず」することが大事だと思います。
変えようとしていることを人に知られるのを嫌がるはずです。
私の近くにもそのような若者がいます。
フォローしてあげたいと思っています。
転機
最近思うことですが、私の周りが大きく変わっているようです。
昨年暮れから今年にかけ、一時、左目の滑車神経がおかしくなりました。
また最近チョットした病気が見つかり8月に手術することになりました。
生活面では、長女の夫がスエーデンに転勤が決まり、長女も来年春に行くまで孫と札幌に来て住むことになりそうです。
また秋には三女家族がスペインに移住します。
その前に家族で日本に一時帰ります。
それに合わせ、私の誕生日の8月12日の翌日に家族全員19名が集まります。
12日は私の退院の日です。
私の意志とは別に私の周りが動いている。
そんな気がします。
私にとって今は、何か新しい転機が訪れているのかもしれません。
そんな思いで、これから起きることを楽しみにしています。
幸せ
幸せそうな人を見て、少しバカにしたように「幸せそうでいいですね」言う人がいます。
「あんたは苦労知らずでいいね。俺は苦労ばかりしているんだ!」という気持ちがあるようです。
幸せな人は本当に幸せな顔をしています。
いつも笑顔で、楽しい話をします。
だからますます幸せが流れ込んできます。
「俺は苦労ばかりしているんだ!」と思っている人は苦労が流れ込んできます。
幸せそうな人の幸せは、与えられた幸せではなく、自分で掴む努力をした結果です。
でも、幸せな人はそれを顔に出しません。
だから勘違いされます。
「幸せは与えられるものでなく、自分で獲得していくもの」
これが分かる人と分からない人でその結果が大きく変わります。
浅草寺
昨日、上京しました。
今日から2日間開催される盛和塾世界大会参加のためです。
第1日目の今日は参加しますが、残念ながら明日は予定が入っているので明日の午前中に帰札します。
昨日上京し、高校生時代の友人と旨い酒を飲みました。
そして宿泊はいつもの浅草のホテル。
早朝、参拝客の少ない浅草寺と浅草神社に参拝しました。
浅草寺は母が信仰していたお寺です。
お参りすると、いつも母の顔が浮かびます。
さあ、今日も頑張るぞ!
永六輔さん
永六輔さんが亡くなられました。
私の学生時代から今まで多くの影響を受けた人です。
浪人時代、勉強しなければならないのに深夜に永さんの「パックインミュージック」を聴いてました。
この番組で色々な豆知識を得ました。
「井の中の蛙大海を知らずの」や「沈黙は金なり」等の「ことわざ」の本当の意味を永さんの話で知りました。
そして、そこで得た豆知識を友人に披露し、得意ぶっていた事を思い出します。
永さんは数多くの歌の作詞を書きましたが、ある時からピッタリ止めました。
そのあとは俳句の世界に入って行きました。
少ない言葉で全てを表す俳句の方が作詞より魅力があったようです。
そんな話もラジオで聴きました。
今、テレビでは日本の高い技術や文化を見直し、「世界に誇れるモノ」として流しています。
永さんは日本の伝統技術や芸能に対して造詣が深く、何十年も前から地方にいる技術者を探し出し、埋もれている芸能を堀起し、紹介してきました。
1日に何十枚もハガキを書いていたという話も聴きました。
多くの事を学びました。
少し寂しいです。
ご冥福をお祈りいたします。
鳥井信治郎さん
日経新聞の朝刊に新聞小説が掲載されています。
7月より伊集院静さんの「琥珀の夢」という小説が始まりました。
サントリー創業者の鳥井信治郎さんの物語です。
その小説で興味深い事が書かれていました。
鳥井信治郎さんは大阪で寿屋洋酒店を経営していました。
その鳥井信治郎さんとの出逢いにより大きな影響を受けた人。
それが松下幸之助さんでした。
幸之助さんがまだ五代自転車店の小僧の時、その出逢いがあったとこの小説で書かれています。
読んだ人もいるかと思いますが少し紹介します。
幸之助さんは生涯、鳥井信治郎氏との出逢いを忘れる事はありませんでした。
生涯、鳥井信治郎さんを商いの先輩としてばかりでなく、その人柄に魅了され、尊敬し続けました。
鳥井信治郎さんが亡くなって19年後、サントリーの工場内に鳥井信治郎さんの銅像が完成し、その除幕式が行われることになりました。
その招待状は幸之助さんのところにも届きました。
この時、幸之助さんは87歳。
体調を崩し、公の場にほとんど出る事はなかったそうです。
出席は無理かと思われる中、その幸之助さんが「喜んで出席させていただきます」と返事を出します。
幸之助さんの体調がすぐれなく、欠席かと思っていたサントリー本社は驚きました。
そして誰よりも驚いたのが、当時のサントリー社長の佐治さんです。
鳥井信治郎さんと幸之助さんのことは知っていましたが、「そこまでオヤジのことを・・・」
当日、サントリーは幸之助さんを受け入れるため万全の態勢を取り、佐治社長が自ら幸之助さんを出迎えました。
事前の打ち合わせで、幸之助さんが望んでスピーチをしたいと申し出がありました。
壇上に立った幸之助さんは鳥井信治郎さんとの出会いからの思い出話を語りました。
会場はシーンとしてその話に聞き入りました。
佐治社長はそのスピーチに感激し、大粒の涙を流したそうです。
佐治社長はその日の幸之助さんの恩義を忘れませんでした。
幸之助さんの葬儀の時、佐治社長は自らその棺を抱えたそうです。
鳥井信治郎さん、松下幸之助さん、そして佐治敬三さん。
また鳥井信治郎さんとつながりの深いニッカ創業者のマッサンこと亀山政春さん。
人の出逢いは世の中の大きな物語を作り上げる。
そんな思いで読みました。
話し方
少し前、ある落語家が浮気をして、それが発覚し、週刊誌に掲載されたことがありました。
その落語家がテレビの前で釈明会見をした時、印象に残った話です。
「『マスコミから叩かれたのは身から出たサビ』と奥さんに言ったら、奥さんは『サビも味のうち』と言われた」と話していました。
奥さんが本当にそう言ったのか分かりませんが、「上手いこと言うな!」と思った人も多かったのではないでしょうか。
本当にそう奥さんが言ったとすれば、その機智の素晴らしさもそうですが、本当は許せない旦那に「逃げ道」を作って上げた。
そのように私は思いました。
相手に非がある時、感情のあまり、逃げ道を塞ぐような、そして相手を追い詰めるような話し方をする人がいます。
そうすると人は反発してしまいます。
間違えたと反省するより、反発する気持ちの方が大きくなります。
これは仕事の上でもそうです。
相手が「素直に間違えた」「やり直そう」と思わせる感情を抑えた話し方。
これが上に立つ者に求められる能力です。
先ほどの落語家の奥さんは、良き上司の素質がありそうです。
本気でお店創り
今日から「本気でお店創り」という講座を8月まで5回にわたり開講します。
会場は「ふうしゃ」というカフェを19時からお借りします。
先月まで大通高校で開いていた「自分の会社創り」という講座の続きのような位置付けで、それの実践編です。
今回の講座を契機に実際にお店を開業する人が出てくる。
そうなれば嬉しいです。
もしも実際に開業する人がいれば、私も全力で応援・支援していきたいと思います。
今日、どのような人が参加されるのか。
楽しみです。
体温上昇
先日、病院である検査の為、朝昼晩定期的に体温を測りました。
そうすると36.2度から36.8度でした。
これは平熱と言われる体温です。
ところが私は普段35.5程度なので、これは1度ほど高くなっているのです。
驚きました。
体温が36度台以上ないと抵抗力が低下し、基礎代謝も低くなり、太りやすいと言われていました。
その為なんとか体温を上るよう努力したのですがなかなか上がりませんでした。
それがいつの間にか高くなっていたのです。
考えられる理由は1つ。
朝食を食べなくなったことしかありません。
今まで習慣的に食べていた朝食は無理に食べなくなりました。
食べてもライ麦パンを1枚程度。
(ただし旅行行ったらしっかり食べます)
結果、若干体重も下がりましたが、体温が高くなったことは驚きです。
食事の量も全体的に低下しているようです。
食事量が減っているのは年なので、いいことだと思っています。
これからは頭が健康であるよう努めます。
握手
昨日、帯広で稲盛和夫さんの「市民フーラム」があり、そのお手伝いのために私も帯広に行ってきました。
来場者は会場がイッパイになる1500名ほど。
帯広市民ばかりでなく、札幌など周辺の街からも多くの人が参加していました。
市民フォーラムの後、帯広の北海道ホテルの中庭で懇親会が行われました。
稲盛さんを中心に盛和塾の人達が100名ほど集まり、十勝のブランド牛である豊西牛のステーキやローストビーフなどの料理がいっぱい出ました。
それに盛和塾メンバーである、お菓子の柳月さんからは特製の「ケーキ」に「ぜんざい」が出されました。
その懇親会の席で柳月の田村社長と話すことが出来ました。
その時の話を少し紹介します。
田村社長は常に道内にある柳月の店を回っています。
私が住む札幌琴似にあるイオンの柳月でもお会いしたことがあります。
田村社長は各店舗を次から次と回るため、1店舗あたり10分程度しか滞在できないそうです。
主にお客様目線で店内を見て、お菓子の並べ方などを指導します。
そして最後に必ず店員さん全員と握手するそうです。
ポイントは相手の手をグッと自分の胸の方に持ってきて「ありがとう」と言いながら握手するのです。
この握手の効果はとても高いそうです。
若い女性店員さんの中には感激のあまり泣く人もいるそうです。
会社の忘年会などでも全員と握手すると言っていました。
お酒を注いで回るより時間がかからない上に、社員との一体感が感じ取られるようです。
この握手するというコミュニケーションは「稲盛さんの行動から学びました」と言っています。
確かに稲盛さんは多くの人と握手しています。
私も握手したことがあります。
とても感激しました。
稲盛さんの手はとても柔らかい手でした。
田村社長とも握手したのですが同じように手が柔かったのが印象的でした。
社員と握手するということは日本の会社ではあまり一般的でないかもしれません。
でも「ありがとう」の感謝を伝えるにはとてもいい方法です。
とても有意義な田村社長との話でした。
アンケート
先週、私が受け持ったある講座が終わりました。
8回にわたり起業するための準備を中心にお話ししました。
その最終日に教室で感想のアンケートを書いて頂き、そのコピーが先ほど事務局から送られてきました。
それぞれのアンケートを見てみると、多くの方は満足頂いたようですが、お一人だけ感想文を手紙にして後日郵送されて来ました。
読んでみると大変ご不満だったようです。
厳しご意見がありました。
いつも満足していただくアンケートが多かったので、正直これほどのご意見をいただくのは驚きでした。
しかし真摯にこのご意見を受け、今後の活動に生かしていきたいと思います。
ただ残念なのは、誤解されていることが多かったことです。
稲盛和夫さんや斉藤一人さんの考え方を話したのですが、それが宗教的であったとか、私が主催する「身丈会」という勉強会の紹介したことが自分の事業に勧誘しようとしていると思われたことです。
本当に残念です。
私の言動に問題があったのでしょう。
少し落ち込みます。
来週からまた別の講座が始まります。
今回のご意見を十分に踏まえ準備していきます。
ボケ防止
最近、モノや人の名前が思い出せない。
老化であることはわかっているのですが、同時に認知症の初期症状か!と考えてしまいます。
つい認知症防止の情報に目が行き易くなりました。
私の趣味はサックスであり、帆船作りです。
共に指を使います。
この文章もパソコンで書いていますから、日頃から指は使います。
指を使うと認知症防止になると聞きます。
それでも物忘れが進んでいるように思うのです。
先日テレビで瀬戸内 寂聴さんのインタビューが流れていました。
90歳を過ぎて体は弱っていますが、頭はしっかりしている。
「すごいな」と思って聞いていると、寂聴さんの好きなことの第一は「書くこと」だそうです。
死ぬ時は机に向かってペンを握りながら死にたいとも言っていました。
ネットで調べてみると、書くことは認知症防止にとって一番効果があるとのことです。
色々なことを考え、想像して構想を立てます。
その構想に基づいて文章を組み見立てていきます。
そしてペンを指に握り、原稿用紙に書き上げていく。
それがいいのだそうです。
寂聴さんはそれそのものを実行している。
なるほど!
となれば私も、せめてこのブログだけでも毎日書き続ければ認知症防止になるかも。
そう思い立ちました。
書くことは誰のためでもなく自分のため。
そんな風に思うことにしました。(読まされている人は迷惑な話ですが・・)
退院
検査入院も終わり、今日退院です。
「健康は健康な人にはわからない」
そんな言葉も少しわかった気がする入院でした。
それにしてもたった3日間の入院でしたが早く家に帰りたいという気持ちが高まりました。
することがが制限される生活。
長い入院生活されている人の気持ちを考えると、「頑張れ」という思いしかありません。
「健康の大切さ」を改めて考えさせられました。
本番は8月です。
あと1カ月と少し。
するべきことは済ましておきます。
10月には「スペイン旅行」
大丈夫だろう!?
入院
検査のために昨日から入院しています。
現在はいたって健康なので体を持て余しています。
退院は明日です。
入院は26歳の時盲腸で入院した時以来。
それにしてもすることが限られており、不自由この上ない。
幸いにも個室に入院しているので、周りに気を使うこともないのがありがたい。
本格入院は8月です。
それまでにすることが沢山あります。
やることが沢山あるということが、そしてそれが出来ることが幸せである。
たった2日間の入院しかたっていませんがそう思います。
番屋で遊ぼう会
先日の土曜日、銭函にある番屋で「番屋で遊ぼう会」を開きました。
当日は朝から雨でどうなるかと思ったのですが、15時頃から回復し、時折太陽も出てくれました。
幹事である私は16時30分頃到着。
開始は17時からと伝えていたのですが、2時間前からすでに来られている人も多く、すでに宴席は始まっていました。
この会は今回で何回目になるでようか。
その度に多くの人が集まって頂いています。
今回も25名ほどの人達と、夜の22時頃まで宴会は続きました。
私も参加された方々に感謝しながら大いに楽しみました。
北海道起業メンター協会
先日の水曜日に2回目の「北海道起業メンター協会」の「マッチング会」がありました。
メンターが3人、起業経営者が5人が参加し、前回より突っ込んだ話ができたと思います。
経営者にとって大事なのは第一に営業です。
先日の「マッチング会」では起業経営者の現在の営業状態を話してもらいました。
それに対してメンターからより効率の良いアドバイスを受け、今後の方策などが話されました。
また起業したばかりの経営者は一人社長、また少人数の社員と仕事をしているので、監視されることもありません。
時として怠け癖が出ます。
それを抑えるためにも、月に1回の「マッチング会」で継続的に営業状況を確かめ合い、1カ月の営業行動の結果報告をします。
「マッチング会」ごとに自分をチェックすることができ、結果、経営者本人の営業意識が育成され、それが会社の業績向上に繋がる。
それが目的です。
この「マッチング会」は異業種交流会ではありません。
メンターを中心に参加者同士互いに考えアイディアを出し、各会社の業績向上が目的です。
次回は7月27日水曜日です。
まだ少しの起業経営者の受け入れはできます。
参加したい思われる経営者はどうぞ申し込みください。
会費は1000円です。
アイディアを発見する
ビジネスのアイディアを見つけるのは「発明する」より「発見する」ことです。
「発明しよう」とするからいつまでもアイディアが手にすることが出来ません。
アイディアのネタを「発見する」ために常にアンテナを張り続けることが大切です。
機会やモノ、人との出会いは意識というアンテナに引っかかってきます。
意識の度合いが強いほど強力なアンテナが張れます。
これは私の経験から得た実感です。
自然災害と日本人
今、九州を中心に大雨が降り続いています。
ついこの間、熊本では大地震があったばかりです。
5年前には東北の大地震。
大災害が続きます。
これから日本は地震が増えると言われ、南海トラフ大地震、東海地震が予想されています。
過去、日本は自然災害の繰り返しの歴史があります。
しかしその度に立ち上がり、今の日本を作り上げてきました。
打ちのめされ、それからの復興。
それを延々と繰り返してきました。
その度に日本人は日本人としての思考や感性が生まれ育てられてきた。
私はそのように思います。
大災害にあっても略奪行為もなく、日本人は皆共に協力的で建設的です。
それが海外では素晴らしいとして賞賛されていますが、それは過去の辛い自然災害の結果生まれてきた連帯感なのかもしれません。
毎年来襲する台風や火山や地震の不安が常の伴う国、日本。
それは逃れようのないものです。
人間の力では防ぎようのない自然災害。
それを受け入れるしかそこに住むことができない
それが日本です。
その土地の厳しさが人を育てるのです。
これからも大きな災害が起きるかもしれませんが、その時こそ日本人らしい力を見せ克服していく。
そんな風に思っています。
日本人は打たれ強いのです。
家族
先日の日曜日は父の日。
子供達からプレゼントやカード、メッセージをもらいました。
カードやメッセージはいいのですが、プレゼントをもらうと、親としては「そんなお金使うことないのに」と思ってしまいます。
そんな子供達が今年の夏に家族を連れて皆が札幌に集まります。
その中に、まだ会ったことのない孫も2人います。
私たち夫婦をいれて総勢19名。
近くに住む娘夫婦を除いても17名がしばらく我が家で生活します。
寝る部屋はなんとかなりますが、食事、洗濯、風呂の段取りなど、諸々の準備が大変。
冷蔵庫は大型のものを買う予定です。
3女の家族はイギリスから今度スペインに移住します。
長女の旦那はスエーデンに転勤になり、家族でスエーデンに行くようです。
それぞれが自分たちの生活をし、それぞれの道を歩んでいきます。
子供達家族全員が揃うのは、きっとこれが最初で最後でしょう。
今年の夏。どんなことになることやら。
今から楽しみです。
セコイ
「セコイ」という言葉が東京都知事の「事件」でクローズアップされています。
「セコイ」という言葉は卑しい、ずるい、ケチという意味です。
そして、そうする人は自分の利益のことだけを考える人です。
似たような言葉に「節約」があります。
2つの違いとして「節約」には自分の欲望を抑える行為が伴います。
欲望のままにお金を求めるか、欲望を抑えてお金を残すか。
それが違いでしょう。
先日の新聞の記事で、「ふるさと納税」の返礼費用が納税金額の平均4割、多いところでは7割になると書かれていました。
本来、「ふるさと納税」はその地域を応援するために納税するものです。
受けた地域は「ありがとうございます」という気持ちでお礼の品物を送る。
それがエスカレートして、今は「豪華なお礼」を目当てに納税するようになっています。
ある雑誌では各自治体が出している「豪華なお礼」の比較をしていました。
「ふるさと納税」の本来の意味が失われてきています。
受け入れる自治体にも問題がありますが、納税者もセコイ。
「粗にして野だが卑ではない」
明治にの実業家石田礼助の言葉が頭に浮かんできます。
心の石を磨く
今朝の新聞やテレビの報道でイチローが日米通算4257本のヒットを打ったとのニュースが流れています。
嬉しい限りです。
毎日新聞に野球「侍ジャパン」の監督である小久保さんの話が載っていました。
それを紹介します。
「1995年にパ・リーグの本塁打王になった時、勘違いして、てんぐになった。
そのため翌96年のシーズンに入ると成績は散々。
一方でイチローは3年連続の首位打者にばく進していた。
その年のオールスターゲーム、外野を2人でランニング中にイチローに聞いた。
『モチベーションが下がったことないの?』
するとイチローは私の目を見つめながら『小久保さんは数字を残すために野球やっているんですか?』と言った。
『僕は心の中に磨き上げたい石がある。それを野球を通じて輝かしたい』
自分はなんと恥ずかしい質問をしたのかと、顔が赤くなった。
彼の一言で『野球を通じて人間力を磨く』というキーワードを得た。
それ以来、イチローと食事に行く時は手帳を横に置いて、気になった言葉をメモしている。
例えば『準備の準備』という言葉。
準備に入る前に、その準備をする。
それほど自己管理が徹底しているからこそ、レギュラーでなくなった今でも、パッと試合に出た時にあれだけ打てる。
試合に出て当たり前だった選手が出られない葛藤は計り知れないはずだが、それでも準備を怠らない。」
そして小久保さんは次のように言っています。
「人間は『この人には勝てない』と思った時に初めて謙虚になれる。
イチローは2歳年下だけれども、私にとってそういう存在だ。」
年下のイチローの言葉を素直に聞き入れた小久保さんもすごいと私は思います。
だからこそ侍ジャパンの監督に任命されたのでしょう。
この小久保さんの言葉、私の「銘肝録」に書き入れておきます。
それにしてもイチローの「心の石を磨く」という言葉、稲盛さんが言う「魂を磨く」という言葉。
同じことです。
改めて感じるものがあります。
税務申告
今日税務申告してきました。
税金を払うということは社会貢献になります
その意義を感じることが大切だと思っています。
稲盛和夫さんの市民フォーラム
稲盛和夫さんの「市民フォーラム」が来月4日帯広で開かれます。
「市民フォーラム」は1年ほど前に一旦終了したのですが、各地からの要望で再開されることになったようです。
札幌の仲間と共に手伝いを兼ねていく予定です。
また、もうお歳で、今年は海外の盛和塾に出席する予定はなかったのですが、中国の経営者から熱烈な訪問の要望があり、9月に中国瀋陽で盛和塾が開かれ、稲盛さんが行くことになりました。
体調によっては稲盛さんが直前に参加できなくなることもあるのですが、それを承知での参加者募集が始まりました。
私も申し込みしましたが、定員100名ということで抽選になりそうです。
どちらにしても今年84歳になっても尚、中小企業経営者の教育に力を注ぐ稲盛さん。
頭が下がる思いです。
自己判断
先ほど車に乗っている時の事です。
赤信号で信号待ちしている時、小さな女子を連れたお母さんが青信号が点滅し出した道路を子供の手を引っ張って横断しました。
道路の真ん中ぐらいで赤信号になっています。
走って渡りました。
それを見て「自分の子供を殺す気か!」と言葉に出てしまいました。
赤信号を渡った今の事を言っているのではありません。
近い内にその女の子が1人で横断する時、お母さんに教えられたように信号が点滅しても渡ってしまう恐れがあります。
結果、交通事故にあう可能性があります。
「赤信号はもちろん、信号が点滅したら横断しない」と教えなければなりません。
聞いた話ですが、子供と年寄りに交通事故が多いのは理由があるそうです。
横断する時、共に車の遠近感が若い人と違っているそうです。
遠近感がよく分からず、大丈夫だと判断して飛び出し、車にはねられるのです。
自分の行動によって、他の人が影響を受ける。
特に親子なら尚更です。
先ほどのお母さんも分かって欲しいものです。
高齢化社会
歳をとると、最後の時の覚悟について考えます。
どう死ぬかを考えます。
先日、日経新聞に「望まないケア意思表示」という表題で、これからの日本の高齢化社会について書かれていました。
その中に65歳以上の認知症患者は9年後の2025年に約700万人。
高齢者の5人に1人が発症する。
介護人材は2035年には68万人不足するという予想数字が算出されています。
その記事の中に国際医療福祉大学の高橋教授の興味ある話が載っていました。
「現在の介護施設側は明治・大正時代型のサービスを続けている。
自ら食べれなくなった人に食事介助で食べさせる。
飲み込めなくなったら直接栄養を入れる胃ろうをつくろうとする。
今はそれも変わろうとしている。
そのような事を望まない人は『食事介助はいらない』『延命治療はいらない』と声を上げなければならない。」と述べています。
教授は1990年代に北欧で現地調査した時の事も述べています。
「当時すでに、介護施設に寝たきりの高齢者はほどんどいなかった。
自分で食べれなくなったら死ぬという考えが広がっていたから。
その代わり、高齢者が食べ物を飲み下す事を訓練し、トイレに連れて行く。
これらが自力で無理になったら自然な形で看取る。
高齢者は寝たきりになる前に、静かに息を引き取って行く」
これから日本にも、この様な考え方を広め、仕組みを変えていく事が大切だと思います。
私たち夫婦も既にお互い延命治療拒否を言い合っています。
だから動けるうちに楽しい事をたくさんしています。
これからも。
今の世界の流れ
最近、新聞やテレビを見ていると世の中、日本中、世界中が異次元の方向に大きく向かっているような気がします。
決していい方向ではなく、不安な方向です。
何が原因なのでしょうか。
「100匹目の猿」現象が頭に浮かびます。
これは何年か前、船井幸雄さんも本で紹介したことです。
宮崎県の幸島にいる猿の1頭がイモを洗って食べるようになり、それが100匹を超えた時、その行動が群れ全体に広がり、そしてそれが大分県高崎山の猿の群れでも突然この行動が見られるようになったというストーリーです。
現在はこの現象はオカルト的として無視されています。
ただ、今更それを再度言うつもりはありませんが、世界中が同じような風潮になっているのを見ると「そんなこともあるのかな?」と不思議な気がします。
世界中で起きている流れでを見ていると、共通しているある要因があるように思います。
それは「貧富の格差」ではないでしょうか。
国同士、またその国の国民の中でそれがあります。
「頑張ったから裕福になれたのであり、貧乏なのは頑張らなかったから」という論理はもう説得がありません。
過去の世界歴史の中で、栄えた裕福な国が近隣の蛮族に征服されていきました
これも1つの格差の解消行為だったのかもしれません。
この現代にそんことが別な形で行われようとしている。
そんな不安が湧いてきます。
芸術家サロン
先日、東京の知人が来社されました。
その時、女性画家を連れてこられました。
その女性はお若いのですが、道展(北海道美術協会)の会員です。
いろいろ話をしていくうちに、道内の画家は画家だけで食べている人が少ないということが話題になりました。
実際に道内に絵画が分かり、その画家の絵が欲しいと思う人がどれほどいるでしょうか。
油絵の価格は1号(22.1センチ×16.6センチ)の大きさで額代も入れて最低でも5万円です。
一般住宅に今に飾る適当な大きさの6号で30万円。
そのお金を出して絵を買う人が北海道にどれほどいるでしょうか。
それほど多くはないはずです。
それでも必ずいるはずです。
それではその人がどこにいるのか。
出会いの場が大切だと考えます。
私が提案したのは、画家等の芸術家達と彼らを支援してくれる人達のサロン作りです。
ある程度購入してくれる所得の高い人達の集まりを作り、交流の場を作るのです。
それにより、個人的の支援してくれるパトロンができるかもしれません。
ここで必要なのはその支援者集めです。
それには画家たちがその気になって依頼していかなければならないのです。
問題は画家たちはそのような意欲はないことです。
芸術家という孤高精神が強すぎて、依頼することが苦手なのかもしれません。
生活の糧を得る行為と芸術を結びつけるのはタブーなのかもしれません。
もしもそのようなサロンが出来たら私も参加して好きな画家を支援応援したいと思います。
ニュース
今、ネットニュースで北海道大沼の山林で行方不明になっていた男の子が見つかったと流れてきました。
ほとんどの人たちが絶望視している中での嬉しいニュース。
思わず涙が出てきました。
それにしても28日から1週間、よく頑張ったのだと思います。
7歳の子供がクマも出るかもしれない山中で、どのように生き延びたのか。
本当に嬉しいニュースです。
働き方
日曜日の日経新聞に「働き方改革に終わりなし」という題で、ユニクロの柳井会長の言葉が掲載されていました。
柳井さんという経営者は以前から私が好きな経営者の1人です。
働くことについて次のように語っています。
日本の社会は「働くということ」について真剣に考えていなかったと思う。
大学までの教育は知識を詰め込む暗記型が中心だが、社会が求めるのは、現実の問題にぶつかった時に過去の知識も踏まえて臨機応変に対応する力であり、知識を応用して実行する力だ。
今の若者は会社に入るまでのことしか考えていない。
当社は12年から大学1年生にも内定を出しており、累計100人に達した。
この制度を導入したのは、社会に出てから求められる理解力や判断力を身につけるために、大学時代にどのような勉強をしなければならないのかを早くわかってもらうため。
(山地の私見:1年生から内定を出すことは、極端な「青田刈り」となり、問題があるのかもしれませんが、ただ漠然と勉強するより、勉強の意味を知って勉強する方が身になることは確かです。)
また仕事についても言っています。
社員に「明日の仕事を今日やれ」と言っている。
本当の仕事は明日何が起きるかを予測し、そのための準備や計画を明日までにに間に合うようにしておくことだ。
それ以外は作業だ。
作業だと毎日の繰り返しになってしまい、会社は変わることができない。
この柳井さんの新聞記事。
スクラップしておきます。
専門職大学
今日の朝刊に「専門職業大学」を制度化するという答申がなされたという記事が掲載されていました。
「やっとできたか!」という思いです。
今のところ観光やIT,農業などの分野で考えられているようです。
まだこれからというところでしょう。
今後は日本の伝統工芸技術に携わる人材を育成すること。
また、土方・大工と言われる肉体労働者に対する低い評価も見直される機会になればと思います。
専門学校の大学化に伴い、多くの技術分野での専門学校設立も増える思います。
「専門職大学」という制度が「技術国日本」の支えになっていくと信じます。
4つの切り口
私は今、札幌の大通高校で週に1度「自分の会社創り」という講座を担当しています。
この講座には社会人と高校生が参加しています。
先日の講座では各自に自分が創りたいと思う「会社の業種」は何か考えてもらいました。
社会人と高校生が混ざって3つのグループに分かれ、その中で互いにアイディアを出してもらいました。
喫茶店やイタリアンの店、ネット販売などが出てきましたが、それがどういう店や会社なのか。
それがなかなか出てきません。
まだ本当に「したいもの」が見つからないからなのでしょう。
例えば「◯◯屋さんをしたい」と思ってもどのような営業をしたいのか。
「業種」は出てきますが「業態」が出てきません。
それでは前に進めません。
その時、目安になるのが4つの切り口です。
「モノ」「ワザ・スキル」「知識・情報」「場」
この4つの内、何を売るのか。
喫茶店でも「モノ」としてコーヒーを売るのか紅茶かまたは日本茶や中国茶。
「ワザ・スキル」としては、優秀なバリスタの技術を売り物にするのか。
「知識・情報」として同じコーヒーでも世界中のコーヒーを売るのか。それとも産地に特化しするのか。
「たまり場」として「場を提供するのか。
この4つの切り口で経営を考えると、具体的な運営の姿が見えてきます。
次回の講座ではこの点を具体的に説明していきたいと思っています。
琴似神社春祭
今日5月27日は琴似神社の春祭です。
朝から出店が並んでいます。
春祭が5月27日になった理由は、屯田兵が西南の役から帰ってきた日だと聞いています。
ネット情報によると屯田兵は、西南戦争、日清戦争、日露戦争に参戦しています。
西南戦争では、琴似屯田兵の多くが仙台藩、会津藩、亘藩の士族出身が多かったため、戊辰戦争の敵だった薩摩士族を相手とするこの戦いには奮い立ったそうです。
しかし、上官や将校は黒田清隆を中心とする薩摩閥が占めていたため戦意が乏しかったようです。
戦死者は1名だったと言われています。
歴史を感じます。
他力本願経営
札幌市は2026年冬季オリンピックを札幌に誘致しようと思っているようです。
その経済効果が昨日報道されました。
道内では8,850億円、札幌市内でも6,447億円だそうです。
「経済効果高いから誘致すべき」の意向のようです。
これは北海道経済界の考えでもあるのでしょう。
私はこの話を聞くと「またか!」と思ってしまいます。
北海道は北海道開発庁があった時代の他力本願的な経済からまだ抜け出していないようです。
自力で何かを作り上げるより、「他所から引っ張ってくる」「他所からお金を出してもらう」発想から抜け出していないよいうです。
北海道新幹線もそうです。
経済効果が高いと謳いながら引っ張ってきて、開業後はその収益予想の赤字の大きさに驚いています。
土木・建築を中心として発展してきた北海道経済にとって、新幹線やオリンピックはとの時だけの格好の商売のネタでしかありません。
開業後のこと等は考えていないように思います。
私も経営に携わってきた者として、また起業を支援する者として、北海道経済を活性化するためには喜んで協力します。
でも、それは創意工夫をし努力して作り上げるモノでなければ本物ではありません。
「他力」から抜け出さなければ「自力」が生まれてきません。
早くそうなってほしいと願っています。
ipad pro9.7
ipad pro9.7を買いました。
これまでは初代のipadを使っていましたが、さすがに不便になり買い替ることにしました。
その初代ipadは昨日ビックカメラへ持って行き買い取ってもらいました。
価格1350円。
安いけれど捨てるよりいいか。
そんな気持ちでした。
新しいipadと一緒にApple Pencil も購入。
手書きでメモを書き、それをメールで送ることもできるようです。
これからはipadを手元に置き、いろいろなことやってみようと思います。
絵も描いてみようかな?
無声呼人
今朝のYahooニュースの中に福寿園会長の福井さんの話が載っていました。
福寿園はサントリーの伊右衛門というお茶で知られていますが、226年も続くお茶の老舗です。
福寿園は店を事業という考えではなく、家業という視点で経営されてきたそうです。
福井さんの話の中で「なるほどな」と思ったのが「無声呼人」という福井家家訓です。
商売はバナナの叩き売りのように大声で売るのではない。
良いものは自然と売れていく。
逆に言えば、徳を積むこと、自分を磨くことによって人が集まる。
お金を儲けるというより、商品にも徳や品格が必要であり、それがあれば、自然と商売は成り立つという意味だそうです。
安売りではなく商品価値を高めることの重要性を示しているのです。
日本の経済はまたデフレになりつつあるようです。
しかしその中でも自社の商品価値を高める努力。
それがトップの責任なのでしょう。
自分の顔
先日、街を歩いていたら、一緒にいた妻が、「前を歩く女性はバレーの経験ある人だよ」と言います。
なぜ分かるのかその理由を聞くと「姿勢が良く、それでいて足が少しガニ股に歩くのはバレーをしている人特有な歩き方」なのだそうです。
娘たちがバレーを習っていたので、その先生達の立ち姿から知ったようです。
踊りをする人は姿勢がいいとか、野球をしている人は利き腕が長いと言われます。
その人の姿や身体的特徴を見て、何をしてきた人かある程度想像できます。
顔もそうです。
仕事の内容によって、身体的な違いは出てきますが、その人がどのような思い、考えで生きてきたか。
その結果は顔に出てきます。
昔、「男の顔は履歴書」という映画がありました。
また、アメリカのリンカーン大統領は、「男は40歳になったら自分の顔に責任を持たなくてはならない」と言ったそうです。
その人の経験してきた生き様は顔に出て来るのでしょう。
さて、私はどうなのか。
気になります。
幸せ
昨日、チョットしたことで落ち込みました。
その原因は誰のせいでもありません。
何気なく言われた言葉が響いたのですが、言った本人は何も悪気はなく話していたはずです。
ただ、受けた私が勝手に落ち込んでいるだけなのです。
その様に人の心は弱いものかと改めて思います。
そして人の幸、不幸も自分の気持ちでしかないのです。
人と比べるものではないのです。
私の周りには沢山の幸せがあります。
たとえそれが小さなものであっても、それを感じ取れる心が大切です。
小さな幸せを感じれる心が豊かな気持ちにさせてくれます。
それだけでも私は幸せなのです。
北海道起業メンター協会「マッチング会」
昨夜、「北海道起業メンター協会」の初めての会合「マッチング会」が開かれました。
協会の設立の目的は「起業の成功率を高める」です。
リスクを負い、折角起業しても3年後の生存率が30%と言われる起業の実態があります。
なぜそれほど失敗するのか。
多くは独断で進めてしまった結果です。
なぜ独断で進めたのか。
それは相談する人がいなかったからです。
経験豊富な先輩経営者の話を聞く機会がなかったからです。
その様な状況を改善しようとしてこの勉強会を始めました。
昨夜は起業メンターとして4名、起業経営者が8名の人が集まりました。
はじめに各自の自己紹介の後、起業経営者からの質問。
その質問に対して、4人のメンターはそれぞれの経験をふまえ、具体的に応えていきました。
4人のメンターは経営経験が違うので、やり方は違いますが、考え方は同じです。
参加された起業経営者がこのアドバイスを仕事に生かしてもらえれば嬉しいです。
次回は来月22日に開きます。
より突っ込んだ勉強会になっていきそうな予感がします。
社長という仕事
昨日勉強会がありました。
稲盛さんのビデオを見て討論する勉強会です。
その中で心に残る言葉がありました。
「採算は良くても悪くてもリーダーの毎日の意思と行動と生き様の結果である」
「社長は個人の時間があってはならない。
常に会社のことを意識し考えていなければならない。
会社のことを意思するのをやめた時、会社は意識を失ってしまう。」
社長という仕事は厳しいものです。
「ツイている」シール
先日「ツイている」シールを手に入れました。
このシールは小樽の菓子メーカー「ルタオ」の親会社である「壽城」という菓子メーカーの社長が広めているものです。
「ルタオ」の「ドゥーブルフロマージュ」というチーズケーキはとても有名です。
「ルタオ」の運営会社は株式会社ケイシイシイという会社で「壽城」の子会社18社の1つです。
その社長である河越氏が高校の後輩である渡部訓久氏が考案したこのシールを広めたのです。
「ツイている」と唱えれば運が良くなるというのは斎藤一人さんと同じ考え方です。
私も益々運が良くなりそうです。
さて、これから周りの人にこのシールと運を分けて上げましょう!
大善は非情に似たり
昨夜から蜷川幸雄さんという演出家が亡くなったというニュースが流れます。
それと同時に多くの役者さんやタレントさんたちが心底その死を悼んでいるメッセージが出されています。
蜷川さんは多くの優秀な役者さんを育ててきた演出家として有名です。
その指導方法は「鬼の演出家」「灰皿を投げる演出家」と言われてる程の厳しいものがあったそうです。
それでも役者さんたちから慕われている。
厳しさの一面、他では溢れるばかりの愛情があったのでしょう。
憎まれて当たり前の指導方法でありながら、多くの人に慕われているのはその人間性に惹かれているのでしょう。
経営者の中でも部下指導で厳しい経営者はたくさんいました。
その指導のおかげで育った人材はいかに多くいたことか。
いつも言っていることですが「大善は非情に似たり」という言葉が頭に浮かびます。
北海道起業メンター協会「マッチング会」
以前にもお知らせしました北海道起業メンター協会の初めての「マッチング会」を開きます。
今月の17日火曜日18時30分。
場所はヤマチオフィス(札幌市西区琴似2条4丁目ヤマチビル2階)です。
この協会は経営コンサルタントの朝岡さん、クロッカス北海道ビジネスサポートセンターの運営者であり、インキュベーションマネージャーの吉澤さんと設立しました。
「マッチング会」は異業種交流会ではありません。
起業した会社がより成長するために、先輩経営者からアドバイスをもらい、経営に生かしていくことを目的としています。
多くの起業経営者の参加をお待ちしています。
朝岡さん、吉澤さんのFacebookでも紹介されています。
乗車マナー
テレビのニュースで乗車マナーのことが流れていました。
以前は床にベタ座りしていた高校生や、足を通路に投げ出して座っている人が多かったのですが、最近は少なくなったように思います。
ただ背中にザックを背負ったまま、混んでいる電車に乗り込んで、平気でいる人が多くなったように思います。
混んでいる時はザックを下ろして手に持っているのがマナーだと思います。
背の高い若者がザックを背にしていると、ザックが私の顔に当たってきます。
そのような時、私は注意するのですが、注意する前に気付かないものなのか!
人に迷惑をかけないようにする気配りが欠けている。
想像力の欠如にも原因があるかもしれませんね。
貯え
今朝、妻から聞いた話です。
妻が30歳代の頃、知人から「収入の半分を貯める」ことを勧められたそうです。
どのように環境が変わろうと、それだけの貯えをしておけば安心なのです。
また収入の半分で生活すると質素に暮らせます。
私たちには子供が5人います。
妻は「将来子供たちを大学まで入れる為に!」と決心し、私には一切言わないでそれを実行しました。
実際は給料の半分を貯めることは出来なかったそうですが、それでも3分の1は貯めれたそうです。
貧しいほどの食生活に、ある日長女が妻に「もっと美味しいものが食べたい」と言ったそうです。
その時、妻は長女に聞きました。
「大学行くのと美味しものを食べるのとどっちがいい?」
そうすると長女は「大学行く方がいい」と言って、それから文句は言わなかったそうです。
そのような話は今朝妻から聞くまで知りませんでした。
妻にも子供たちにも可哀想なことをしました。
そのような生活でも、妻は私に対しては「お付き合いで必要なお金があれば言って」と言っていたのを記憶しています。
お陰様で子供たちは5人とも希望する大学や学校に行けました。
今更ながら妻に感謝です。
起業家と先輩経営者とのマッチング会
起業してもなかなか上手くいかない。
何が原因かもわからない。
そんな風に悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そのような時に必要なのは先輩経営者からのアドバイスであり知恵です。
でも、中々そのような経営者と巡り会うもは難しいものです。
今回、その一助となればとの思いから「北海道起業メンター協会」を設立し、起業家と経営者とが出会う場を作りました。
その第1回目の「マッチグ会」を開催します。
5月17日火曜日18時30分からです。
詳しくは添付した資料をごらんください。
良きメンターに出会えますように!
出勤日
今日は連休の中日。
「今日出勤日でよかった」という思いです。
8連休、10連休だと毎日何をしたらいいのか。
今日と金曜日が仕事日で丁度いいです。
今日中にまとめなければならない仕事が2つ。
これから頑張ります。
アドラー心理学
先日テレビを観ているとフリーアナンサーの 小林麻耶さんが同じ本を何回も読み、3冊がボロボロになって、今は4冊目を買って読んでいるという話がありました。
その本が「嫌われる勇気」という本です。
その題名だけで「そうだ!」と思いました。
人はいつも「いい人」でいなければならないという錯覚のもと、自分の心を偽ってしまう。
そうすると、辛くなり心が萎えてきます。
私がそうでした。
「いい人」でいるに疲れ、ある時から「私は馬鹿でーす」と思うようにしました。
「するは自分の責任!評価は人の勝手!」と思うようにしました。
人からの評価はどうでもいい。
人からどう思われようといい。
そう思うようにしたのです。
「嫌われる勇気」という本は、心理学者のアドラーの思想を紹介したものだそうです。
今朝の新聞コラムにその本が紹介されていました。
従来の心理学は「原因論の問い」で「私はどこから来たの?何が私に影響を与えたか?何でこんな自分になったか?」というものでした。
アドラー心理学は「目的論の問い」で「私はどこに向かっている?何のために生きている?私はどういう人間になりたいのか」を考えるのです。
この考え方は稲盛さんが常に言っている「目的・理念はなんなのか!何のために生きるのか!自分の魂を磨きなさい!」と同じことです。
アドラー心理学、今度勉強してみます。
運がいい人
フッとした時「幸せだな〜」と思う時があります。
出世したとか、お金がたくさん儲かったからではありません。
妻と自宅で夕食を食べている時、夜寝床に入った時、コーヒーを飲んでいる時、フッと感じます。
人から見ればたわいもないことなのに、心が満たされています。
この「幸せだな〜」と思うことが沢山あると、「私は幸せな人間なのだ」「運がいいのだ」と思うようになります。
運がないと思っている人はまず、身の回りで些細なことでも幸せを見つけることです。
その小さな幸せを十分感じた時、また新しい小さな幸せが現れます。
その幸せを見つけ感じているうちに、自然と全てのものに「ありがとうございます」という感謝の気持ちが湧き出てくようになりまします。
そうなったらもう良い運が来る状態になっています。
こんな「小さな幸せ」を感じられるようになれるかなれないか。
これが運が良い人と悪い人との大きな違いだと思っています。
友人の息子
2週間ほど前に突然電話をかけて来て「お会いしたいです」という人がいました。
聞けば20年ほど前に亡くなった高校の同期生S君の息子さんです。
S君は小学校の先生でしたが、非常に教育に熱心で、小学校勤務のかたわら子育てに悩んでいたお母さん達向けに講演をしたり、本出していました。
そのS君の息子さんが昨日訪ねて来ました。
用件は特になく、昔にS君が私のことを話していたことがあったので会いたくなったとのこと。
2時間弱話して帰りました。
S君が亡くなった時、彼は14歳でした。
彼は高校卒業してからアメリカの大学で学び、起業もし、日本に帰って来またそうです。
東京渋谷で会社を立ち上げ、アメリカのオーガニク製品を輸入する仕事をしているようです。
34歳になって、たくましい息子。
話していて「S君は良き息子を育てたのだ」と感慨深いものがありました。
レストラン
昨日の日曜日、妻と札幌の街を歩き食事をしました。
私の舌は鈍感だと言われるほどで、何でも美味しく感じることが出来ます。
B級グルメが好きですが、たまには少し良さそうなレストランもいいかなと、以前から気になっていた店に入りました。
旧道庁前の赤煉瓦通りに面した1階にある洋食レストランです。
入店した時、タバコのヤニの臭いが鼻につきました。
「アレ!」と思いました。
黒服に先導され、座った椅子は座席の角が破け、木組みが見えます。
また、目の前の1段高くなったフロアーの下にはびっしり段ボール箱の列。
布で隠そうとしていましたが、丸見え。
期待していた幻想が崩れていきました。
私は「漁師風のスパゲッティ」を注文。
妻はステーキセット。
初めにも書きましたが、私の舌は鈍感だと思っています。
なんでも美味しいと思って食べる方です。
その私がそのスパゲッティを一口食べた時、「これは食べれない!」と思いました。
小さなムール貝が3つ、エビが一匹が乗ったそのスパゲッティは生臭い塩水をかけたようなモノでした。
頑張って2口食べましたがダメ。
食べれません。
残しました。
妻が注文したステーキはどうかと食べてみると、筋が多く硬い。
噛んでも噛んでもガムのよう。
そのまま飲み込むしかありません。
この店の内装は、当初はお金をかけた造りになっています。
しかし開業してから10年間、メンテナンスをほとんどしていない様子。
サービスの女性は愛想は良かったのですが、責任者らしき黒服は不愛想。
店のオーナーは気付かないのでしょうか。
この店はじきにダメになりそうな気がします。
ダメにになる典型が全てこの店にあります。
人間的魅力
毎月開いている「身丈会」の勉強会が昨夜ありました。
今回からは稲盛和夫さんの「京セラフィロソフィ」という本を教材に始めました。
この本の冒頭に、稲盛さんが27歳の時、京セラの前身京都セラミックスという会社を作っていただいたことが書かれています。
京都セラミックスという会社は、前に勤めていた会社の7人の仲間と立ち上げたのですが、稲盛さんは1円も出資していません。
周りの人達がお金を集め、300万円の資本金でスタートしましたのです。
出資者の中には自宅の土地建物まで担保にしてくれた人もいました。
私はこのところの話が大変興味あります。
いくらファインセラミックスという技術があったからといって、27歳の若者に自分の財産や人生をかける人が多くいたということです。
今の稲盛さんではないのです。
言ってみれば27歳の「若造」です。
しかりした考え方、実績はあったにしても周りの人を惹きつける魅力。
人間としても魅力があったのだと思います。
これから改めて「京セラフィロソフィ」を通して稲盛さんの考え方を学んで行きますが、考え方と共に人を惹きつけるその魅力についても考察していきたいと考えています。
新規事業
当社の関連する会社の中にホテルがあります。
そのホテルでは、宿泊やレストラン以外に宴会も承っています。
ホテル開業当時は一般宴会とともに結婚式の獲得にも力を入れていました。
しかし、開業後20年ほど過ぎ、若い人が減少するとともに結婚式の件数も減少していきました
そのため営業方針を大幅な方向転換をし、法事に力を入れるようになりました。
結婚式はハレの場、法事はその反対にあります。
当初はホテル内で法事をすることに抵抗があったようですが、その後ホテルで法事をすることが一つの流れになり、一時は当ホテルが北海道で1番多くの法事の件数を獲得するようになりました。
しかし今はまた、法事をする家が少なくなってきたようで、私たちのホテルも減少気味。
新しい分野を開拓しなければなりません。
どのような仕事でもニーズを探し出すことが必要でしょう。
その時は発明でなく発見です。
組み合わせを考えることも大切です。
東京では葬儀場とホテルが組み合わさった葬儀ホテルのようなものがあるそうです。
一般のホテルと同じようにレストランがあり、宿泊も出来ます。
ただ宴会場が葬儀場と言うだけです。
葬儀場とホテル。
相反するもの同士の組み合わせというのもあるのでしょう。
だからと言って当ホテルは葬儀ホテルになる予定は一切ありません。
念のため。
緊急支援
熊本での大地震。
テレビで見るだけで何もできない。
昨日、妹から連絡があり、旦那が熊本に急遽救援に行くとのこと。
今日、出発するようです。
義弟は宇都宮の病院で緊急医療の現場責任者です。
専門は外科。
タフガイな彼はきっと熊本で活躍することだろうと思います。
私達夫婦も応援しています。
私達ができることは寄付ぐらいしかないかもしれません。
近い内にしてきます。
子育て
最近、テレビのニュースを見ていると、「母親が自分の子供に手にかけた」等の報道が多くなってきたように思います。
子供にとって一番に守ってくれ、甘えれる母親に殺される。
こんな悲劇はないです。
このような話を妻としていた時、妻から「母親が育児で悩み逃げ場所がなくなっているからかも」と言われました。
「私も大変だったわ」
「うちの娘たちは大丈夫?」と聞くと、「結構大変みたい」
「お前は5人の子供を育てたのだから、そのアドバイスをすればいいのに」と私。
妻は「私の言うことは聞かない」と言います。
なぜ?
その理由は保健所などから「自分の母親の子育ての話は聞かないように」と言われているそうです。
間違えていたり、やり方が古かったりするからだそうです。
ちょっと待て。それはおかしい。
保健所から言われたような画一的な子育てをしようとするから、その通りしようと思うあまり逃げ場がなくなってしまう。
その母親の性格や考え方をよくわかっているのはその母親です。
子育てする母親に合ったアドバイスもできるはず。
そうすればその母親なりの子育てができるはずです。
私達の娘達にとって、5人の子供を育てた母親の知恵は、保健所より育児書より優れている。
私はそう思います。
大人の溜まり場
先週の土曜日、ジャズライブに行ってきました。
友人のM君がベースを弾いていました。
バーボンを飲みながらの2時間。
曲名はよくわかりませんが、音楽に浸っていました。
ジャズライブが行われたのはKenny Burrell(ケニー・バレル)というプライベートのジャズバーです。
広さは横5メートル、奥行き7メートルと小さいのですが、天井高が5メートルもあるので圧迫感を感じさせません。
3メートル程もあるウォールナットの1枚天板のカウンターの他にテーブルと椅子を散らせて、40名弱の人が聞き入っていました。
この「ケニー・バレル」はオーナーのTさんが自社ビルの5階に作ったジャスバーです。
Tさんのギターも素晴らしい演奏でした。
「ケニー・バレル」は有名なアメリカのジャズギター奏者の名前。
Tさんはケニー・バレルに憧れ、彼をこのバーに招いて演奏をしてもらいがため作りました。
何度も来訪の依頼を出してきたそうです。
返事はいただいているそうですが、未だ来訪はならず。
ケニー・バレルも84歳となり、もう無理そうだとのこと。
このジャズバーはT氏のケニー・バレルへの憧れが作り上げた「大人の溜まり場」です。
このバーは普段は営業しておらず、週末に友人たちと音楽を楽しんでいます。
Tさんは札幌でも有名な建築家。
仕事と趣味を両立させています。
素敵な生き方ですね。
かぐや姫の話
私には子供が5人います。
5人もいると1人1人への愛情は分散されます。
結果それが良かったようです。
溺愛することはなかったです。
そして口うるさい父親から離れたいと考えたようで、早くから自立心もあったように思います。
お陰様で皆結婚もして子供もいます。
ある人が言った言葉です。
「子供は預かり者(もの)。
所有物ではない。
かぐや姫の話はそれを比喩したもの。」
花と蝶
花の周りには蝶が集まる。
糞の周りにはハエが集まる。
だから「徳」を高めなければならない。
納得する話です。
メモを取る
昨日、人と話をしていて話題になったことです。
仕事上で指示をしてもメモを取らない若い部下が結構います。
またメモを取った内容を復唱させたところ、指示したことが良く伝わっていないこともあります。
それは指示した人の話し方が悪かったのかもしれません。
それでもメモを取らせ復唱させたから、誤解を防ぐことができました。
私のところに起業した人が相談に来ることがあります。
その時、一生懸命メモを取る人と、まったく取らない人がいます。
その差が仕事の結果として現れているような気がします。
メモする代わりに録音する人がいるそうです。
これも論外です。
私の背広の内ポケットに手帳サイズのノートを入れています。
このノートに色々なことをメモっていきます。
忘備録の役目もあります。
メモ帳を持たないで話を聞きに行く人の気持ちが分かりません。
ぬくもりの宿
週末、定山渓温泉にある「ふる川」という宿屋に行ってきました。
ここは「ぬくもりの宿」と自称しているだけあって大変安らげる宿屋でした。
大きな旅館ではできない細かい所まで心配りがなされています。
この宿屋には遊技場もカラオケもありません。
宿泊客のための「ヨガ教室」、食前に果実酒が飲める落ち着いた部屋、甘酒をふるまってくれるコーナーがあります。
朝は暖炉が燃える部屋でゆっくりコーヒーも飲めます。
これらはすべて無料。
「相田みつを」の書が宿屋中に飾られており、「相田みつを」の部屋まであります。
夕食は食事処で食べますが、1品ずつ運んできてくれ、料理の説明してくれます。
全てが手作りの料理ばかり。
朝食も満足いくものでした。
ウインナーソーセイジやベーコンを切っただけというものはありません。
夕食が終わり部屋に戻ると布団がひいてありましたが、枕元にはメッセージとカモミールのティーバックが添えられています。
高さや硬さが違う枕も部屋に用意されていました。
もうひとつ感心したのは宿のスタッフです。
夕食の時、料理を説明してくれが人が、朝チェックアウトの手続きをしていました。
1人で何役もこなしているのでしょう。
それでいて皆が笑顔で応対しています。
この宿は満足できる旅館として人気があります。
値段は少し高いですが満足度も高いです。
定宿にしたい宿屋です。
賭け事
最近、スポーツ選手の金銭に絡むニュースが多くなっています。
八百長は勿論ダメです。
論外です。
ただ合法的な賭け事はOKで、合法でない賭け事はダメというのは少し疑問があります。
パチンコや競馬・競輪等も賭け事で、行為そのものは同じです。
国が認めているかどうかの違いだけ。
これでは青少年にとって分かりにくい構造です。
大人のご都合主義と言えます。
また、すべての賭け事を合法にすればいいという問題でもありません。
賭け事そのものが問題です。
歯止めがつかない人にとっては、その人の人生をダメにしてしまいます。
そんな人が多くいます。
日本国内にカジノを作ろうという考えがあります。
大人のご都合主義・二枚舌。
子供にどう映るでしょうか!
ipad pro9.7
先ほど近くのソフトバンクの店に行きipad pro9.7を注文してきました。
37ギガ容量のipadを注文したのですが、いつ入荷するかわからないと言われました。
今回のipadは大変な人気で、店員さんの話ではipad pro9.7が発売された時に予約したお客様の分がまだ届いていないとのことです。
発売日が3月31日でしたから1週間経っても届いていないのです。
となると私の注文文は何時に届くやら。
楽しみに待っています。
ちなみに私は初代ipadを今まで使っていました。
古いのでいろいろ支障を来してきました。
この初代ipadは2010年5月に発売されたもので、もう6年経っています。
先日このipadの下取り価格を聞いてみましたら、最高の下取価格が2000円とのこと。
引き取ってもらえるだけでいいです。
私は普段MACを使い、経理処理の時はWindows8を使います。
電話はiphone、家ではipad.
自宅の無線Lanの設定も自分でしました。
それでも何歳頃まで新しいIT機器についていけるか。
何時までも新しいモノに興味を持ち続けたいと思っています。
営業と恋愛
「営業は女性を口説くのと同じだ!」
これは若い頃、先輩から教えられたことです。
好きな女性をアタックする時は、会いに行き、手紙を出し、電話もする。
営業マンがお客様にアタックする時も同じです。
日経新聞の「キャリアアップ」というページに「営業を究める」という題名で2人の営業マンが紹介されていました。
その内の1人で東京日産自動車販売の金谷さんという女性は凄腕の営業ウーマンです。
彼女には約500件の顧客がいて、その1人1人と月1度の接点を持つように心がています。
お客様に来店していただくため、電話やメール、手紙を出すのは当たり前。
金谷さんが不在時にお客様が来店した時、必ずお詫びやお礼の電話などをしてフォローするそうです。
あらゆる方法を用いてお客様との接点を持ち続けるのです。
「一回電話したから、メールしたから大丈夫!」のような手抜きはないようです。
私が思うに、大事なのは「お客様に惚れ込む」こと。
営業は恋愛と同じです。
ルール
ある人の話で「警察官と先生は商売人には向いていない」というのがありました。
人に頭を下げる商売でないからです。
また法律や規則という決まりごとから抜け出せられないというのもその要因の1つです。
それなら役人や銀行員もそうです。
銀行員は商売に長けているように思うかもしれませんが誤解です。
中小企業の経営者へお金を貸すという立場から、財務分析や経営分析をしますが、だからといって経営ができるというわけでは決してありません。
その上、銀行には「銀行規定」というルールがあり、そのルールを外れる行為は許されません。
一方、商売では臨機応変という優柔不断な対応が求められます。
「ルール」や「決まり事」で商売をしているとお客様は逃げていきます。
元銀行員だった私も銀行を辞めて父の会社に入った時、このことは思い知らされました。
銀行には膨大な規定があります。
その規定集を読み、深くそして広く知っていれば銀行員としては一人前です。
しかし中小企業での仕事にはほとんどルールや決め事はありません。
極点に言えば、「儲かるか儲からないか」
「いいことか悪いことか」
そのように判断基準しかありません。
あとは経験です。
そして即断が求められます。
1つの例をあげます。
レストランで家族と一緒に食事をしましたが、食べ残してしまいました。
残った料理の持ち帰りをお願いをすると、「規則ですからダメです」というところと「よろしいですが、今日中にお召し上がりくださいね」と許してくれるところがあります。
どちらがお客様満足になるでしょうか。
「善悪」に引っかかる判断でなければ、お客様が喜ぶことを選択する。
そうすれば「商売繁盛」間違いなしです。
簡単なことですが出来ていない店が多いようです。
※注意
(警察官や先生、役人や銀行員の中でも素晴らしい経営者になっている人もいます。念のため。)
ありがとう
誰かに何かをしていただいた時、すぐに「ありがとう」と言えるかどうか。
「ありがとう」という言葉を口に出すようにしていかないと、心の中に本当の感謝の気持ちは生まれないものです。
「心で感謝しているからいい」と思っていいると、相手に伝わらないのです。
何度も何度も感謝の言葉を口にしていると、心の底から感謝する気持ちが湧き出てきます。
私の知り合いのラーメン店主は家と店との間を徒歩で往復していました。
その時は常に「ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。・・・・・・・」と小さな声を出しながら歩いているそうです。
そうすると全てのことに感謝の念が生まれ、何をされても「ありがたい」と思うようになるのです。
感謝の気持ちがない人には商売は無理です。
どんなに資金があり、頭が良くて、アイディアがあってもダメです。
お客様にモノを売っても、「買っていただいた」と思う気持ちではなく、「売ってやった」という気持ちがお客様に伝わります。
日頃から感謝の「言葉」と「気持ち」を持つよう訓練しなければなりません。
訓練で本当の感謝の「気持ち」が生まれます。
本当です。
でも素直でない人は結局しません。
だから商売がうまくいきません。
残念なことです。
4月1日
今日は4月1日。
エイプリルフールでもありますが新年度です。
ここ数ヶ月間は車を運転できなかったので、恒例の1日参拝ができませんでした。
久しぶりに北海道神宮で参拝してきました。
今日は早く目が覚めたので5時に起き、琴似神社その後神宮に到着。
ちょうど6時30分前なのでラジオ体操の人たちが大勢が集まっていました。
いつもの通り、お礼のご挨拶をして参りました。
やはり朝早く参拝すると気持ちがいいものです。
会社にも7時前に到着。
仕事がたくさんできます!?
楽観的 悲観的
「楽観主義は不可能を可能にする。悲観主義は可能を不可能にする」という言葉があります。
この言葉は正しいのですが、楽観主義は能天気なことではありません。
この点、誤解ないように!
何も準備もせず「成るように成るさ!」という気持ちでは決して成功しません。
楽観主義というのは、その前に十分に準備し、心して臨むことが必要です。
自信を持って楽観的に臨めば、余裕が生まれます。
その余裕が不意に訪れる運も掴むことができます。
悲観的な人はすべて否定していきますから、可能な芽も知らず知らずに踏み散らして、折角訪れた運も気付きません。
怖い怖いと思って一歩も前に足を踏み出しません。
だだし悲観的な考えも全てを否定はしません。
楽観的思考があれば、悲観的考察は大切なことです。
「楽観的に構想し、悲観的に検討し、実行する時は楽観的に進む」
これは稲盛和夫さんから教えたいただいたことです。
北海道起業メンター協会
昨日、「北海道起業メンター協会」を設立することにしました。
発起人はインキュベーションマネージャーの吉澤さんと経営コンサルタントの朝岡さん、そして山地です。
「起業はしたけれど業績が伸びない。誰に相談したらいいのか」
そんな思いを抱いている起業家が多くいます。
早めに相談していれば良かったのにと思う起業家がいます。
その起業家が相談する相手はやはり経営者でしょう。
それも長年経営に努力を重ね、経験豊富な先輩経営者です。
私達が目指そうとするのは、起業家と先輩経営者達との出会いの場を作り、経営者がメンターとなって起業家を育てることです。
その場で経営の話を相談しながら、互いに相性を見極め個々にメンターになっていただく。
協会の設立目的は「道内の起業家の成功を導く」です。
5月頃に最初の会合を予定しています。
これからメンターとなっていいただける経営者を集めます。
これが結構大変そうですが頑張ります。
貞観政要
先日「貞観政要(じょうがんせいよう)」を読み終わりました。
若い頃にも読んだのですが、改めて読んでみました。
「貞観政要」という本は以前にも紹介しましたが、古来より帝王学を学ぶ唯一の教科書と言われてきました。
この本は中国唐の時代、名君の誉れが高い太宗とその名臣たちとの政治問答をまとめたものです。
この本は、鎌倉時代に「尼将軍」と言われた北条政子、徳川家康、そして明治天皇も読み学んだそうです。
「創業と守成どちらが難しいか」が問われています。
「会社を創業するのと、その会社を維持するのとではどちらが難しいことか」ということです。
「守成」こそが難しいのです。
「貞観政要」のほどんどがこの「守成」の心得が書かれています。
私はこの本の中で太宗夫人の文徳皇后の話が特に心に残りました。
この皇后は13歳で嫁してより倹約を守り、読書に励み、内助に努めたと言われています。
この文徳皇后のエピソードを紹介します。
太宗が臣下に対する賞罰について皇后に聞いた時、皇后は「牝鶏(ひんけい)の晨(あした)するは、これ家の索(つ)くなり」と言って答えようとしませんでした。
これは「女がでしゃばると家を滅ぼすことになります」と言う意味です。
また太宗が皇后の実兄を宰相にしようとした時も「妾(わらわ)の兄を持って宰執とすることなかれ」といって最後まで反対しました。
そして、皇后が36歳で亡くなる時も「妾の縁者を顕要の地位につけないよいうに」「妾の葬儀はごくごく簡素なものに」と遺言したそうです。
現代、中小企業の中には社長夫人の意見が強いところもあるようです。
これは見っともないものです。
北海道新幹線
26日、北海道新幹線が開業しました。
朝から全てのテレビ局はこればっかり。
開業前からマスコミ挙ってお祭り騒ぎです。
しかしそのマスコミも開業後は例によって、新幹線の問題点を上げて否定的な論調になるのではないでしょうか
北海道新幹線の経済効果は140億円と言われていますが、新幹線の収支予想は48億円の赤字です。
48億円の赤字は税金で補われるのでしょう。
これが札幌延伸となる15年後まで続くとすると720億円の赤字です。
開業フィーバーが続いている開業後7日間の満席率は25%程度です。
その上、年間48億円の赤字予想も「取らぬ狸の皮算用」的な数字かもしれませんので、実際はもっと増える可能性もあります。
この風景は昔のことを思い出します。
JRの前の国鉄時代、線路の延伸は政治家、土木業者を中心とする経済界が中心になって推し進められてきました。
結果、国鉄は莫大の借金を負い、税金投入が続いていました。
やっとの思いでその国鉄を整理し、28年前に民営化され国鉄はJRになりました。
しかし今また、その繰り返しのようです。
現在の日本の借金が1000兆円を越して出血が止まらない、社会保障のお金が足りないと言われる状況の中で、また税金が投入されます。
誰がその責任を負うのでしょうか。
札幌延伸は必要ないと思います。
勉強会
月に1回、私の事務所で開かれる「身丈会」という勉強会があります。
以前に私が講師をした「身の丈起業のススメ」を受講された方々が中心となっています。
「身丈会」で教材として使われていた稲盛和夫さんの「心を高める 経営を伸ばす」は昨日の勉強会で終了しました。
255ページの本ですが、終了まで3年半かかりました。
次回からは「京セラフィロソフィ」を教材として再開します。
経営者として、人として、何が正しいのかが書かれている稲盛さんの本は、読む度に私の考え方の軌道を修正をしてくれます。
しかし、折角勉強しても2〜3日経てば少し忘れ、知らす知らずのうちに軸がズレていきます。
この勉強会はそのズレた軸を修正してくれます。
いつもその繰り返しです。
色々と報道されているように、大企業の東芝やシャープの経営が苦境に陥り、経営者の責任が問われています。
あれほどの大会社の役員です。
優秀な大学を出ています。
「正しいこと、悪いこと」の判断くらいはできるはずです。
でもそれが結果、正しい道を踏み外してしまいました。
「正しいことをすることは大事だと分かっている」と思っていても、「人間だから間違いはある」とか「この位はいいだろう」と思ってしまう。
しかし、そのように自分を野放しにすると、本来ある姿からズレていきます。
常に正しいことができなくても、正しいことをしようと「思うこと」が大切です。
そのために素直に学ぶ機会を持つこと。
これが大事です。
「身丈会」は私にとっての大事な勉強会です。
鈴ちゃん
プライベートな話です。
先日生まれた孫娘の名前が決まりました。
東京に手伝いに行った妻からメールが入りました。
「鈴」です。
一文字で「鈴」
桜が咲いた頃に生まれたので、私は「桜子」がいいと提案したのですが却下。
それでも「鈴」という名前もいいです。
シンプルな名前で「鈴ちゃん」というのも可愛い。
私は以前から「鈴」が好きで車のキーに付け、常に持ち歩いています
「鈴」というのは魔除けと言われたいます。
幸運をもたらす子になりそうです。
人工頭脳
最近、人工頭脳が囲碁のプロ棋士に勝ったと話題になりました。
ITが人間に取って代わる。
工場ではロボットが中心になり、工場スタッフは少なくなってきました。
会計ソフトが良くなり、経理職の人は余ってきました。
ここ20〜30年ほどの間にパソコンが普及し、ソフトも充実して、従来からある人間の仕事が取って代わられています。
これからも人工頭脳はより優れたモノが開発されていくことでしょう。
そうすると人はますます余ってきます。
一方、日本は今後少子化により、経済は衰退していくと言われていますが、人工頭脳などITシステムがそれを補っていくことになるのかもしれません。
また新聞の記事によると、スエーデンでは8時間の労働時間が6時間に縮めている会社が出現しているそうです。
それにより余裕ある生活が出来るのかもしれません。
そして人間が働く時間が減った分、産業効率を維持するために人工頭脳がそれを補っていきます。
従来からある「労働時間は8時間」という考えも変わっていきます。
将来、人工頭脳がドンドン人間の仕事の分野を侵していけば、人間がする仕事は限られてきます。
人工頭脳を作り供給する側とそれを使う側。
それ以外の人間は何をしたらいいのでしょうか。
それは人間しか出来ないこと。
優しさや、人を思いやる心が必要な職業。
サービス業や保育園・幼稚園の先生や介護職員。
それは「人間力」が必要な仕事です。
これからは益々「人間力」を磨く勉強が必要な時代になってくるのではないでしょうか。
売らない勇気
宝石や洋服を売る店の販売員は、如何に売上を上げようかと一生懸命です。
時には一生懸命すぎて、売る付けてしまうこともあるようです。
何でも売ろうとするあまり、そのお客様に似合わないモノまで売ってしまいます。
お客様は家に帰り、冷静にその商品を見て自分に似合わないというのが分かってしまうと、その店に対する信用は全くなくなり、2度と行きません。
店側にしてみても、一時的な売上は上がりますが、その内に尻つぼみになります。
お客様本人が「これがいい」と思って、買おうと販売員に相談して決めても、家に帰り家族から似合わないと言われると「似合わないモノを売る付けられた」と思い、店に対しての印象は悪くなります。
優秀な販売員は、例えお客様が好みで選んだとしても、また高い商品で売上が上がる商品であったとしても、お客様に似合わないと思えばはっきり「お似合いになりませんのでお勧めできません」とはっきり言いいます。
それが本当の接客サービスだと思います。
そして価格が安くてもお客様に似合う商品を勧める。
それが結果、販売員や店の信頼が高まります。
顧客も増えていきます。
「売らない勇気」
これが必要です。
起業メンター
「経営学を学んだから経営者になれるとは限らない」
松下幸之助さんが言った言葉です。
当たり前のことですが、◯◯大学卒業と聞くとそれだけで「すごいな!」と思ってしまう。
MBAを取得したというと、素晴らしい経営ができると思ってしまう。
そんな傾向があるようです。
近頃ネットでも流れていますが、ある経営コンサルタントの経歴詐称問題。
これは大手テレビ局もまんまと騙され、コメンテーターとして褒め称えていました。
今、経歴詐称が問題になっていますが、本当の問題はそこではないと思います。
「ハーバード大学を卒業し、MBAを取得しているから経営のことがわかっている」
そんな理由でテレビ局はコメンテーターとして採用したのでしょう。
一般評論家として経済・経営を語ることは誰でもできます。
しかし本当にその人にコンサルタントを依頼して業績が上がるのか。
大学で経営を学んで、本をたくさん読んだからといって知識だけで経営はできません。
汗を流し、悔し涙を流して経験したものこそ本物だと思います。
今、企画していることがあります。
起業して、懸命に働いてもなかなか業績が上がらない。
そのようなことで思い悩んでいる起業家が多くいます。
その時に大切なのは相談できる人です。
経験豊かな経営者に経営相談をする。
現場から得た本当の経営知識を教えてもらう。
そのような、起業家と経営経験豊かな中小企業経営者とがつながる「場作り」を考えています。
その場で良きメンターと出会うのです。
そのメンターとはその場限りではなく、その後も起業家の経営のアドバイスをいただくのです。
専用のメンターとなっていただくのです。
現在は企画の段階ですが、具体的な形に持っていきたいと、同じ志の人と企画を進めていきます。
私自身も起業メンターですが、これから多くの経営者にも起業メンターになっていただき、起業家の事業成功率を高めていきたい。
それが目的です。
今の幸せ
今、世界では重大なことが多数起きています。
宗教対立による紛争、独裁者による扇動、モンロー主義的風潮、ナショナリズムの高まり。
その中でヨーロッパでは難民問題が起きています。
シリアを中心とする難民たちの姿をテレビで見るにつけ、その国の指導者たちの不能、無策ぶりが分かります。
マズローが唱えた「人間の欲求5段階説」というものがあります。
その説では最下位の段階が「生存の欲求」
次が「安全の欲求」です。
人間として生きていくための最低限の欲求です。
難民の人達はこの最低限の欲求さえ満たされていません。
食べるものもなく、安全も保証されない中で暮らしています。
国は長年の歴史の中で作られた生活があります。
それが突然失われてしまう。
いつ日本でも起こるか分かりません。
日本に暮らす私達は、今の幸せを噛みしめながら、その幸せを守る努力をしなければなりません。
単に今の幸せを享受するだけでは幸せは続きません。
子や孫の世代に平和と幸せを渡していく義務があります。
日本に住むことのできる幸せとそれを守る責任。
日本人一人ひとりに問われているのです。
現状打破の勉強会
少し前になりますが、東京で起業家を支援しているKさんから電話がありました。
若い人が起業して、ある程度の売上や利益まで行くとそれ以上伸びない。
「何が問題なのか?」という話です。
私も考えてみました。
伸ばす方法が分からないのか。
または現状で満足して、それ以上を目指していないのか。
目指していないのであれば、それはそれでいいのです。
しかし伸ばしたくてもその方法が分からないという人は多くいると思います。
年収が300万円そこそこなら札幌ではなんとか生活ができます。
その起業が年輩者の第二の人生や家庭の奥さんが副業としての「身の丈起業」であれば、それで十分いいのかもしれません。
しかし、若い人が折角決心し、リスクを負って起業したのに300万円程度では物足りません。
「一生懸命仕事をしている。でもそれ以上伸びない」と思い悩んでいる人。
「もうこれでいいや」と諦めている人。
諦めている人はもう仕方がありません。
しかしなんとか上を目指したいと思っている人は応援したいものです。
上を目指し頑張っている人の多くが、間違えた考え方や仕事の仕方をしているのに気がついていません。
毎日一生懸命仕事をしているのに売上が上がらない。
利益が出ない
それを改善するには仕事のやり方を見直さないとダメです。
私も経験があります。
毎日何十件も営業しても注文が取れない。
「こんなに頑張っているのに!」と悩んでいました。
今だからその時のやり方が悪かったことが分かります。
でも当時は、頑張っている自分に満足しているだけで、考え方ややり方を変えようとしませんでした。
自己満足と自己慰めで終わっていました。
もしもその時、考え方ややり方を変える機会があったら、もっと注文も取れ、売上も上がったのだと思います。
伸び悩む起業家にとって必要なのは、自社の現状から目をそらさず、現状分析することです。
実態を知ることです。
私は悩む起業家とともに勉強会を企画したいと考えています。
その勉強会では教えてもらうのではなく、それぞれの起業家が自社の現状を分析し、これからのやり方を考え出すのです。
現状を変えるために何かをすることが面倒だと思う人は無理です。
変えたい、変えよう、変えることができると思う人。
そういう人が伸びて行きます。
サービスの力
昨日大きい病院に検査のため行きました。
その病院は多くの患者さんにミスなく対応するため、都度必ず「お名前と生年月日を教えてください」と聞かれます。
最初に受ける看護師さんの問診、注射時、検査時と聞かれます。
ある検査ブロックで検査室から「なんで何回も同じことを聞くんだ!」と怒っている患者さんの声が聞こえました。
それに対して看護師さんが「お手数をおかけして申し訳ありません。ただ間違いようにするためにはどうしても必要なことなのです」と低姿勢に説明していました。
それでもその患者さんは文句を続けます。
「名前や生年月日を言わなくていいような仕組み考えろ!」
看護師さんが言います。
「もしもそのような目的のために患者さんにタグなどつけると、俺は商品じゃないと叱られるかもしれません。
そのようなことも出来ません。」
それを聞いて私は「なるほどその通り!」
「看護師さんんがんばれ!」と応援したくなりました。
結局はその患者さんはなんとか納得したようです。
そんなこともあってか、その後に検査してもらった私への対応は、「そこまでしなくてもいいよ」思うほど丁寧で親切。
今の病院は以前と違って患者サービスが徹底されています。
ある意味、サービス業になってきました。
ただ、すべての人に満足される仕組み作りは難しいものです。
仕組み作りはベストは無理でもベターの繰り返し。
そして、、その不足分を補うのは人の力。
そこに「サービスの力」が問われてくるのでしょう。
冷やかしのお客様
土・日曜日は時々、妻と街中を歩いてウインドーショッッピングをします。
「面白そうだな」と思って店内に入った時、居心地いい店とそうでない店があります。
店員さんの視線を強く感じられるとあまり長居しません。
また、ホッポられても寂しいものです。
店員さんの視線を隠すような商品展示の工夫。
また店員さんは黙って立っていず、棚にある商品のチェックなどの仕事をしていてして、お客様をあまり気にかけない振りをする。
それでも必要があればすぐ声をかけられるような側にいる。
そのような店がいいと思います。
お客様の中には私達のような冷やかしのお客様もいるでしょう。
冷やかしのお客様への対応も大事です。
後で本当のお客様として購入してくれることもあります。
また、冷やかしのお客様でも店内にいるだけで、別のお客様が入りやすい雰囲気になります。
店の中が常に賑やかだと、それだけでお客様の吸引力が高くなります。
週末また妻と街歩きをして、ウインドーショッピングしようと思っています。
箸の話
札幌も少し暖かくなって来ましたが、春は遠い感じがします。
それでも春になれば雪も溶けるので、外を歩き回りたいものです。
そんな時は弁当を食べる機会もあるでしょう。
弁当などを食べる時は「マイ箸」を使う人もいますが、私は付いている割り箸を使います。
そして弁当を食べ終わると必ず箸を折ります。
そうすると周りの人から不思議な顔をされます。
なぜ私は食べ終わると箸を折るのか。
以前に読んだ箸に関しての話です。
箸は食べ物と口を結ぶ架け橋であり、それには神や使う人の魂が宿ると言われています。
使い終わり、魂が宿った箸をそのままにしておくと、粗末に扱われたとされ、災いが起きる恐れがあります。
箸を折るのは、魂を自分に戻す「作法」です。
この「作法」をしないと餓鬼を呼ぶとも言われています。
箸の話をもう1つ。
人を呼ぶ時、食器を箸で叩いている人がいます。
マナーとしてあまり良くないことです。
しかし民俗学によると、ハレの日には食前に箸で食器を叩いて神様を招いたと言われています。
ただ日頃の生活では神様を呼ぶことがないから、むやみに叩いてはいけないとも言われています。
箸1つでも色々な話があるものです。
クレームの後
昨日はクレームに対してどう対処するかを書きました。
今日はそのクレームは最高のアドバイスとして捉え、どう活用するかについて書きます。
1つ目はクレームを受けたら「たらい回し」にしないで、直接対応し、その場で解決するよう努力します。
そこで対応力が鍛えられます。
2つ目はクレームから得た情報の共有。
「貴重なご意見ありごとうございました。関係部署に伝え参考にさせていただきます」という苦情対応の常套句を実際に実行します。
今後の商品の改良やサービス向上に生かせられます。
3つ目は会社の各部署に「キーマン」を育て用意します。
何かあった時、そのクレーム内容に適した部署の「キーマン」を通して解決方法を探ります。
4つ目は自分の商品やサービスに自信を持つことです。
自分の仕事や商品にプライドが持てれば、クレームに前向きに対応できます。
5つ目は、まずはお見舞いや反省の言葉から始めます。
理不尽なことを言われてもまずはお詫びの言葉から。
まずはお客様の感情がおさまることが第一です。
会社や店の「ファン」が生まれる場合の多くはクレーム客から始まる時が多いです。
対応の良さから、単なる顧客だはなく「ファン」になるのです。
大分昔に聞いた話ですが、トヨタの車が何故人気があるかというと、その理由はクレームの対応の良さだったそうです。
お客様のところに新車が来て乗っている時、少し不都合があって連絡すると驚くほど早く対応してくれたそうです。
そのため「都市伝説」が生まれました。
「トヨタは車を出荷する時、あえて少しトラブルを起こすように調整していた」というのです。
クレーム対応の良さを誇張する「伝説」となったのでしょう。
クレーム処理
新聞を見ていると、書籍広告に株式会社武蔵野の小山社長の本がよく紹介されています。
私は20年ほど前に小山社長から経営ノウハウを教えていただいたことあります。
社長室も見せていただきました。
その時に教えたいただいたことは、その後の私の経営にも生かしています。
その教えの1つにクレーム処理があります。
株式会社武蔵野はダスキンを扱っています。
家庭を訪問する仕事で、担当者は会社の最前線で働いています。
数多くの顧客がいますのでクレームも発生します。
クレームが発生した時、それをすぐに上に報告しなければなりません。
しかし時として担当者がそのクレームを隠してしまい、後で大きな問題になることがあります。
小山社長は必ずクレーム報告させる仕組みを考えました。
現場で担当者がクレームを発生させたとしても「担当者の責任は問わない。
その責任は社長にある」と決めました。
「ただし、そのクレームを報告しなかった場合は厳しく責任を問う」としたのです。
クレームをいかに隠さず報告させるかの仕組みです。
またクレームが発生した時、その現場からすぐさま担当者がボイスメールで社長以下部課長全員にそれを報告します。
その知らせを受けた者の中で、現場に一番近くにいる上司がすぐさま駆けつけます。
あまりにも早い対応にクレームを言ったお客様が驚かれ、またその対応に感心されるそうです。
そしてその早い行動により、お客様の気持ちも落ち着くようです。
どのような仕事でもクレームは必ず起こるものです。
それをいかに早く処理するか。
その処理について小山社長の方針。
今でも肝に命じて忘れません。
立食パーティに参加する時
最近は出不精になり、若い頃と違ってパーティーに出る機会がなくなりました。
パーティーは人脈を増やすいい機会です。
そのパーティーでの遊泳術について書いてみます。
若い頃に仕入れた情報です。
今は頻繁に宴会やパーティーが開かれているので、それに参加することには慣れている人も多いでしょう。
でも、仕事関連の立食パーティの場合、心構えとしての大事なポイントがあります。
「立食パーティーの達人」の教えがあります。
それを紹介します。
1・仕事関連でパーティに出席するのであれば、「自らを出席者に印象付ける」「参加者の人間関係を観察する」の2点に重点を置きます。
2・できるだけ早く主賓客の人に挨拶に行きます。
そうすることで、主賓客に礼を尽くすと同時に、「あの人は誰?」と思った周囲の人が挨拶に来るようになります。
3・気になる人の動向をチェックします。
誰と話し込んでいたか、誰と話をしなかったか等を観察します。
人間関係を知ることができます。
4・食事に熱中しないように。
パーティー前に少しお腹に何か入れて参加するといいです。
食べることが目的ではありません。(ご馳走を食べるのを少し我慢!)
5・名刺交換は相手の飲食中は避けます。
6・特定の人を10分間以上拘束してはいけません。
新製品の売り込みや資料出しはご法度。
7・立食パーティーでは上座も下座もありません。
積極的に前の方に行きます。
8・他の出席者に資料やお土産を渡したい時もありますが、会場内で渡すのはヤボ。
クロークなどに渡したい荷物を預け、その預かり証を相手に渡すとスマート。
9・早めに帰る時は必ず主催者に一声かけ、できれば握手して自分を印象付けます。
これらのことを頭に入れて参加すれば、仕事に生きるパーティーとなるでしょう。
ただし、これは公的なパーティーです。
フレンドリーなパーティーではまた違うでしょう。
TPOで使い分けすることです。
格言
資料を整理していると昔に集めた情報が出てきます。
その中から5つ。
1・1番手の法則
2・口説きタイムは食事時
3・平均値に明日はない
4・商い上手の早仕舞い
5・2対8の法則
これらの格言はすでに知っている方も多いでしょう。
「1番手の法則」とは、最初に始めた人の名前は覚えているが、2番手の人の名前は覚えていない。
業界1位の会社の名前は覚えているけれど2位の会社は覚えてもらえない。
なんでも1番にならないとダメだということです。
「口説きタイムは食事時」は人は食べている時、警戒心を解き、説得され易いのです。
ビジネスランチは商売に効果的です。
「平均値に明日はない」について。
売上などのデーターを比較する時、一般的に平均値を使います。
しかし平均値ばかりに目が行くより、あえて平均値から外れた事象を突き詰めると何かが発見できます。
「商い上手は早仕舞い」は商店などで、数が少ないモノとか、日持ちしないモノに対し消費者は購買意欲が高まるということです。
顧客心理に響く販売方法の一つです。
「2対8の法則」は経済学者パレートが唱えた法則です。
20%の富裕層が80%の資産を所有しているとか、20%のトップセールスマンが会社の売り上げの80%を稼いでいるというモノ。
これらの格言は昔からよく言われてきました。
私の経験からも納得する格言です。
昔から言われてきた格言はやはり生きているということです。
過去を捨てる
私の事務所にある過去の資料等の整理を昨日から始めています。
1年前にもしましたが、まだ多くが残っています。
月日が経つと、当時大切だと思っていた書類が今は必要ないモノになっています。
それを後生大事に持っていることは、過去を捨てられない自分がいるのに気が付きます。
過去の栄光や成功体験。
それを捨てなければいけないのです。
不幸にも火事によって全てを失った人は、全く新しい人生を送ると言われます。
人によってはそれを捨てると自分の全否定することになると勘違いしている人がいます。
でも大事なのは今の自分。
過去のことはすでに幻です。
今の自分で生きる。
身辺整理はそういう意味でもあると思っています。
それにしてもまだまだ捨てられないモノが多い私。
まだ過去から抜け出していないようです。
挨拶
朝、会社に向かう途中の交差点に、黄色い旗を持ったおばさんがいます。
小学生達の交通安全指導をしています。
その女性と時々会うと、向こうから「おはようございます」と声を掛けてくれます。
私も「おはようございます」と返します。
今朝はその女性とは会わなかったのですが、別の女性から言われました。
その女性は若いお母さんで、2歳頃のヨチヨチ歩きの女の子の手を引いて、私の前を歩いていました。
狭い雪道をヨチヨチ歩きで歩いていたので、横を通り抜ける時「ごめんなさいね」と声をかけて通り過ぎました。
その時「おはようございます」とそのお母さんから声を掛けられたのです。
挨拶されたのに、私からお返しの「おはようございます」という言葉が出てきませんでした。
「挨拶は大事だ」といつも人に言っている私ですが、言えませんでした。
とっさに出てきません。
私はまだまだです。
それにしてもその若いお母さんは素晴らしい。
知らない人にすぐ「おはようございます」と朝の挨拶ができる。
街中では知らない人には中々なかなかできません
自分の親が普通に挨拶をしている。
それを見ている子供は当たり前にできるようになります。
「挨拶は大事」と教えるより、親がしているのを見ていると、子供も素直に出てくるようになります。
今朝受けた「おはようございます」の挨拶。
清々しい気持ちと自分の未熟の念がチョット湧きました。
お伊勢参り
先週末に伊勢神宮参拝してきました。
土曜日に外宮、翌日は内宮参拝。
今年で5年目です。
あと2年、合計7年参拝するつもりです。
今回は朝熊金剛證寺(あさまこんごうしょうじ)にもお参りに行ってきました。
このお寺は伊勢神宮の丑寅(北東)に位置するため「伊勢神宮の鬼門を守る寺」として伊勢信仰と結びついたようです。
「お伊勢参らば朝熊をかけよ、朝熊かけねば片参り」
昔から伊勢神宮を参拝した後はこの金剛證寺(こんごうしょうじ)を参って1セットだったようです。
このお寺の創建は6世紀半ば、欽明天皇が僧・暁台に命じて明星堂を建てたのが初めといわれています。
その後、平安時代の825年(天長2年)に空海が真言密教道場として当寺を中興したと伝えられています。(ウィキペディア)
現在は臨済宗のお寺となっています。
このお寺に行くのに1つ問題があります。
この金剛證寺に行くには伊勢志摩スカイラインを通って行くしかありません。
そのため一般の旅行者がこのお寺に行くための交通手段はバスのみ。
その上、そのバスも、土・日曜日に運行する5往復と少ないのです。
そのせいか旅行客は少なく、日曜日に乗ったバスの乗客は私たち夫婦を入れて6名。
帰りは私たち夫婦だけでした。
それでも境内は静かで、お参りして回っていると厳かな気持ちになります。
帰りにはバスを待つ間、境内の茶店でコーヒーを飲みました。
勿論、その店の客も私たち夫婦だけ。
昨日の月曜日に帰ってきましたが、北海道の天候は大荒れ。
セントリアからの千歳行きの飛行機は欠航が続いていましたが、私たちの乗った飛行機は1時間遅れでしたが、無事飛びました。
お伊勢参りの御利益(ごりやく)か。
家に帰り、夫婦でそんな話をしていました。
自分を律する
「瓜田(かでん)に履(くつ)を納(い)れず、李下(りか)に冠を正さず」という言葉が新聞のコラム掲載されていました。
疑われるようなことをするなという教えです。
今、賄賂で揉める大臣や、不倫問題の政治家や芸能人。
上に立つものは常に人から後ろ指を指されないように律しなければなりません。
常に意識しなければなりません。
どんなに隠しても「天知る、地知る、我知る、人知る」のです。
経営者も社員に見られています。
それを意識するようにしなければなりません。
仰げば尊し
もうそろそろ2月が終わり3月です。
3月と聞いただけで、雪深い札幌にいても春を感じます。
また3月は卒業シーズン。
先日CDに入っている「仰げば尊し」を聞きました。
つい涙ぐんでしまいました。
最近の卒業式では「仰げば尊し」は歌わなくなったそうです。
歌の意味が分かりにくいとか、立身出世を煽るとの理由があるそうです。
また「我が師の恩」がおかしいという意見もあるようです。
自分の人生を振り返ってみれば、多くの人の「恩」のお陰で生きてきました。
勿論、学校の恩師も沢山います。
生きている間に、いろいろな人から教えを受け育てていただきました。
その都度「師」と思える人がいました。
自分に「師」がいるということは幸せなことです。
今の私にとっての「師」はやはり稲盛和夫さんでしょうか。
稲盛さんの教えに出会えて人生が変わったと思います。
「仰げば尊し」を聞いて、「師」を持つ幸せと大切さを改めて感じています
教育
小説を読んでいると、ストーリーの中に東京芸術大学(芸大)受験のことが書かれていました。
芸大は芸術家を育てる大学の最高峰です。
優秀な芸術家を輩出しています。
その芸大に入学するには技術選考の前に学科試験があります。
音楽関連は国語、外国語(英・独・仏)の2教科。
美術関連は国語、外国語、地歴など3教科。
芸大に入るためには、どんなに芸術的才能があっても学科選考を通らなければ入れません。
妻とも時々このことを話をします。
人の技術的・芸術的才能を伸ばすのに、足かせとして、学力が一定基準を満たさなければならないというのは少しおかしい。
どの分野においても、人の才能を伸ばすのであれば、小さい頃にその才能を見つけ伸ばしてあげる。
皆が平等という名の下に、画一的な教育をするより、その子の優れたところを伸ばし、芸術家、職人、俳優になっていく生き方の方が余程その子のためです。
好きなことをして、その才能を伸ばしていく内に、英語や歴史や国語が必要になっていきます。
その時に学べばいいのです。
その時に学んだ方がが本当に身になっていきます。
私の妻は芸大に入れるほどの技量はありませんが絵を描きます。
長女も美大卒です。
そのようなこともあって、つい画一的な教育について書いてしまいました。
相談者
人は仕事においても人生においても、調子のいい時は明るく朗らかで、多くの人に会い、語りかけていきます。
これはとてもいいことでネットワークも広がり、自信も付くことでしょう。
しかし、それがある時から調子が悪くなると、ネガティブになり人にも会わなくなります。
なぜ仕事がうまくいかないのか、物事がうまく運ばないのか、1人で考えてもなかなか結論は出てきません。
たとえ解決方法がわかっても、ネガティブになっていると、踏み出すこともできません。
大切なのは、そのような時こそ、人に会わなければならないのです。
1人で考えてもどんどん悪い方向へ気持ちが進んでいきます。
恥ずかしいとか、体裁悪いなどと思わないことです。
いつも心配してくれている人は必ず近くにいるはずです。
行って相談するべきです。
いろいろな理由を付けて、会いにいけないと思っているかもしれません。
でも相談者は相談してくれるのを待っています。
相談者は勝手にその人のところへ行って「何か困っているのか?」とは言ってくれません。
困っていることがわかっていないからです。
起業した人たちが、少しうまく行った後、業績が落ち込んで悩んでいる時、このようなことが起きがちです。
遠慮なく甘えることも大切です。
読書ノート
本を読むのに「速読」という読み方があります。
1分間に1200語読んでしまうそうで、1冊の本をアッと言う間に読み終えてしまいます。
その上、内容も理解しているそうです。
羨ましいことです。
私は「速読」どころか「遅読」です。
歳を取ると尚その傾向が強くなりました。
本を読んでいる最中、何度も読み返すこともあります。
読み終わっても「いい本だったな」と思うのですが、内容を忘れていることもあります。
「本を読んだ」という思いだけになってしまいます。
その為、私は「読書ノート」を作ることにしています。
本はマーカーを引きながら読みます。
読み終えるとマーカーを引いた部分を抜粋してノートに書き写します。
そうすると同じ本を2回3回読み返すことになります。
1冊読み終えるのに数日かかるほどの「遅読」です。
「読書ノート」を作って気付いたことです。
本の要点を抜き出したそのノートを読み返してみると、読んだ別々の本の内容がお互いに絡み合ってきます。
化学反応を起こしたように、時に新しい考えや気付きが「フッ」と湧き出てくることがあります。
難しい本を読んでいると時に眠気に襲われてきます。
この眠気に負けず、これからも読み続けたいと思います。
治りました
昨日、2ヶ月半ぶりに車を運転しました。
以前にも書きましたが、昨年の12月5日の朝、起きた時から目の焦点が合わない状態になっていました。
眼科で「右目の滑車神経麻痺」と診断されました。
老化が原因と言われ、治るとも治らないとも言われません。
左側を見ると右目と左目の焦点が上下で合わず、外を歩くだけでも大変でした。
不安にかられ、ネットで「滑車神経麻痺」を色々調べて見ました。
ある病院の情報で、滑車神経麻痺は3〜6カ月で治る「可能性」もありますと書かれていました。
その情報を見てからは、ただそれを望みに、リハビリーと思い、無理してでも左側を見るようにして焦点合わせる努力をしていました。
目はすぐ疲れてしまいます。
涙も出てきます。
その努力のせいでしょうか、1月の中旬頃から少し左側の焦点が合う気がしました。
気のせいかと思っていたのですが、その内に少しずつ良くなってきたようです。
今は完全とは言いませんが、生活に支障ないほどに回復しました。
2月に入ってから、どんどん良くなっていくのが分かります。
人の体は障害を起こしたところを修繕しようとか補完しようとするそうです。
私の場合も、麻痺した神経の代わりに新しい神経ができたり、血管が繋がったりしたのでしょう。
「滑車神経麻痺」の原因は老化と言われましたが、復活した今は、「まだまだ若いぞ!」と思っています。
仕方がない
「仕方がない」という言葉は負けの言葉です。
言ってはいけない言葉だと思っています。
でも、年を取り、老化が始まり病気になった時、自分の力でどう頑張ってもどうにもならない。
そんなことが自分の体に起きます。
その時、「なぜだ!なぜ自分に起きるのだ!」と思うと辛くなります。
自分の力ではどうしようもないことが起きるのです。
その時、素直にその状態を受け入れる時の言葉が「仕方がない」です。
どうあがいても人は年を取るのです。
それに抵抗してもどうしようもありません。
年とともにだんだんそのような気持ちになってきました。
人生の価値
あるネット動画の中で、見つけた言葉です。
「人生の価値は、速さと広がりではなく、方向性と深さです」
若い頃は、早く出世したいとか、金持ちになりたいなど思い、ガムシャラに頑張っていました。
人とのネットワークを広げて行きました。
何か大きなことを早く成し遂げることにばかりに気が急いていました。
しかし、今、過去を振り返って思うのです。
自分の人生の価値は何なのだろうか。
それは大きなことを成し遂げることでも、急く人生でもなく、本当に大切なことを見つけ、それを深く追求していくこと。
そのように理解します。
もしかしたら自分の大切なものは足元にあるのかもしれません。
それを見つけることが出来た時こそ、自分の人生が価値あったと思えるのではないでしょうか。
そんな人生を過ごしたいと思うのです。
イエスマン
昨夜、知人Nさんと寿司屋に行きました。
この店は以前にも紹介しましたが「雪峰」というお店です。
ネットのグルメランキングでも地域1位の評価を取るほどの店です。
その店で美味しい料理と旨い酒を飲みながら話をしていた時、大変感心したことがありました。
Nさんとは今まで数回ほど宴席でご一緒する程度の中でした。
先日の新年会の時、「今度ゆっくり食事をしながらお話しましょう」とお誘いしたのです。
プライベートなことも含め、色々な話をしている中で、「私は今まで人からの頼まれごとを断ったことがありません」と言います。
私などは、すぐ「嫌です」「嫌いだ」という気持ちが先に立ってしまいがちですが、その人はそのような気持ちを持つよりも先に「はい」と言っているのです。
「結果、いいことばかりでした」と言います。
以前に上映されたアメリカ映画「イエスマン」のような人です。
話していて温和な性格がよくわかります。
年齢は私と同じ66歳。
私ももっと素直に生きてみようと思います。
新入社員、辞めたらお金をあげる
「0ベース思考」という本を読んでいると面白いことが書かれていました。
その内容を紹介します。
「ザッポス」という会社の人事採用について書かれています。
「ザッポス」はアメリカのラスベガスに本社を置き、靴や衣料、アクセサリーなどを販売するオンライン小売会社です。
この会社は新入社員を採用し研修期間を終えた時点で、新入社員に会社を辞めるチャンスを与えるのです。
「せっかく採用した社員をやめさせる?」
そんな疑問が湧きます。
その上「ザップス」は辞める人には研修期間中の給料の他に、1か月分の給料(約2000ドル)も支払ってあげます。
「この会社では働かない!」と決めたら2000ドルをあげると新入社員に言うのです。
驚きです。
その理由として「ザッポス」のCEOは「この制度は『お金を選びますか?それともこの文化と会社を選びますか?』と社員に迫ることです。
楽して儲かるお金を選ぶような人は、たぶんうちに向いていない」と言います。
楽に儲かることを考える人はその内に辞めていき、結果2000ドル以上のコストが会社にかかります。
辞めた社員を採用するのに4000ドル以上のコストがかかるようです。
そして採用した1人の不良社員が、生産性やモラルの低下といった面で会社に与える損害は2万5000ドルを超えるというデーターもあるそうです。
このシステムには、より良い新入社員を採用したいとの会社の思いがあります。
ただ、簡単にこの仕組みを真似するのは難しいでしょう。
会社の風土が違います。
でも「良き人を採用したい」と思う気持ちは経営者は皆同じです。
人を採用する時、何が大切なのか。
原点に戻って考えてみる。
「0ベース思考」で考えてみる。
参考になる話だと思います。
信じる
人の話を信じるかという話です。
人は今の生活に満足している時、良きアドバイスがあっても、それを取り入れて生活を変えようとは思いません。
いいアドバイスと思っていても、心の中では「そうかもしれないし、そうでないかもしれない」と思う程度です。
疑いの気持ちもあります。
今満足しているその人にとっては、それはそれでいいのでしょう。
良きアドバイスを受けたいと思っいる人は、本当に困っている人です。
そういう人は「藁をもつかむ」思いで、その話を信じます。
本当に困っている時、その人の心や魂はそのアドバイスを受け入れる準備ができています。
それしか自分が救われるものがないと思うからです。
しかし「困っている」と口では言っても、心の中で魂の段階で信じていなければ、その通り実行しても効果は出ません。
魂が信じないものをたとえ実行しても効果は出ません。
そうすると「なんだ、何も効果がない」とますます信じなくなります。
その人は本当に困っていないのです。
それともか素直でない人です。
新興宗教の中で邪教といわれる宗教は本当に困り悩んでいる人の魂に入り込み、訴えることで信者を増やしています。
学歴があり、賢いと言われる人でも、心の底の魂で困っている時は受け入れてしまいます。
この現象を生活の中で、正しく自分に受け入れていけば、新しい自分を創ることも、変化も実感できるのではないでしょうか。
自己暗示やリラクゼーションという手法もその準備段階なのかもしれません。
どちらにしても素直に、正しい心を持って、魂の段階で信じ、実行してみる。
それにより人は変わるはずです。
業績が回復した時
今日は夢や目的を持ち続けることの大切さを書いてみたいと思います。
毎日の仕事を懸命に為すことは大切です。
毎日の積み重ねが実績を生み、目的に近づきます。
しかし、時々は今どこにいるのかを確認しながら、方向性を間違わないようにしなければなりません。
会社経営していると、時には経営不振に陥ります。
なんとかして回復して利益を出そうと努力します。
常に考え、行動して頑張ります。
毎日毎日業績が回復することを願っています。
ある日その努力が報われる時がきます。
業績が回復した時、人はホッとします。
達成感に浸ります。
その状態がズーと続ければいいと思います。
そのような状況は初めのうちはいいのですが、それが当たり前の感覚になってしまうとそれ以上の発展を望まなくなります。
現状維持でいいと思ってしまいます。
この段階が危ないのです。
起業した会社の発展阻害の大きな要因になります。
会社が苦しい時、なんとか頑張って業績を回復しようと思う気持ちが目標と目的を混同してしまっているのです。
業績が回復した時、あたかも目的が達成したこのような錯覚に陥ってしまいます。
結果、やる気がそこで止まり、停滞してしまいます。
そうなると会社の業績は徐々に下降していきます。
何のための起業だったのか!
自分の夢はなんだったのか!
常にその目的・夢を追いかける情熱は忘れないようにしなければなりません。
病院
昨日、病院に行ってきました。
3か月ほど前の健康診断の結果、再審査が必要と言われたからです。
歳をとると病院に行く機会が増えます。
それぞれの病院ごとに、受付の職員や先生の応対も気になります。
患者さんの名前に「様」をつけるのが流行っているようで、盛んに「◯◯様」と読んでいます。
患者もお客様として対応しようとしているのでしょうか。
でも、笑顔がない応対は、より冷たさを感じさせます。
今朝の日経新聞の1面に「大病院の実績開示義務」との見出しが出ていました。
病院ごとに「年代別の入院患者数」「診療科別・施術別の入院日数」など7項目の公表を求めるます。
患者が病院の内容を把握し比較しやすいようにというのが目的です。
病院も特別なものでなく、1つの企業体なのです。
競争の中で切磋琢磨して医療の質の向上と効率化を促すのです。
それにサービス業としての位置付けも必要と思います。
人生は二毛作
「人生は二毛作」という言葉を聞きました。
「二期作」ではありません。
「二期作」は2度目も同じお米を作ると言う意味ですが、「二毛作」は米以外のモノを作ります。
60歳は還暦ですが人生はまだまだ長い。
60歳は仕事を長年勤め上げ、子育ても終わった時期。
その後の人生は、今までと違った人生でもいいのかもしれませ。
以前テレビの番組で観た清水 建宇(しみずたてお)さん。
元朝日新聞の論説委員でしたが、第2の人生はスペインバルセロナで豆腐店を開業しています。
現役時代に取材で訪れたバルセロに憧れ移住したのです。
その時、それまでの仕事とは離れたことをしようとして選んだのが豆腐店。
自分自身が豆腐や揚げのない生活が出来ないということもあり、選んだのが豆腐店。
退職後豆腐店に修行に入ったそうです。
その清水さんが言っていた言葉も「二毛作」です。
今までの経験や名声を捨てて、新しいことに挑戦するのは勇気がいります。
それでも挑戦すると、自分の人生は2倍になり豊かになるはずです。
さて自分はどうか。
まだ二期作的なことをしている。
もう少し挑戦しなければと考えています。
お客様の心理
「お客様のニースに合った商品作り」
よく言われる言葉です。
一方、街中に行くと商品があふれています。
全てがお客様のニーズに合った商品です。
でも欲しいものはありません。
必要なモノは買います。
しかし決してお客様のニーズに合った商品が売れるとは限りません。
それではどうしたら売れるのか。
驚きや感動を与えるモノがいいと言われます。
確かにそうかもしれません。
珍しいモノや体験は人をワクワクさせてくれます。
ディズニーランドやユニバーサルスタジオなどはその例でしょう。
しかし、これも常に変化していかなければ飽きられてしまいます。
もう1つは、ターゲットを絞り、限られた分野や人に対して商品化する。
ニッチの市場です。
そして、今注目されているのは、隠れた需要を堀起し、それを顧客に教えて、伝え広めることでしょう。
そのいい例がユニクロの「フリース」
ユニクロの「フリース」は1994年に発売し、98年にフリースブームを巻き起こしました。
顧客に「フリース」の温かさを教え、伝え広めて行き、ユニクロのブランド急成長の重要なアイテムになりました。
「お金はあるけれど、欲しいモノがわからない」というお客様の心理。
その心理を汲み取った商品作りが需要になってくるのでしょう。
層雲峡への旅
先週末に層雲峡に行ってきました。
層雲峡は北海道の中央にある山間の温泉郷です。
訪れるのは中学校の修学旅行以来です。
札幌から層雲峡の旅館までバスで4時間ほどの道のり。
札幌を12時に出発し、途中吹雪のため高速道路を降り一般道を走りました。
私たちの席は最前列なので、真っ白な視界の中よく運転しているものと感心しました。
ある地点に来ると再び高速道路に乗って走行。
ところが途中からバスの中に警報音が鳴り響きます。
近くのパーキングに停めて調べると、エンジンのオイルが漏れ、そのまま走行すると危険とのこと。
替わりのバスを手配し、それに乗り換えました。
遅れを取り戻そうとする新しいバスの運転手さん。
気が急いたのか、バスの荷物入れのドアが締まっていなく、カーブを回ったところで荷物が転げ落ちました。
乗客の指摘で気付いた運転手さんは慌ててそれを回収。
やっとの思いで旅館に到着。5時間かかりました。
旅館でチェックインの手続きすると、遅れたお詫びだと、フロントの人が菓子折りを私と妻の分として2折くれました。
2食付きの宿泊。
その上、札幌からの往復バスは無料。
そして先ほどの菓子折りまでいただいて、1人料金1万円。
驚くほどの安さ!
食事も夕食は部屋食でゆっくりいただけました。
時々お得なプランを見つける冬の北海道です。
罪悪感
人は生来、罪の意識を持っていると言われます。
特に宗教的な意味ではありません。
ズルいことをした時、「悪いことをしたな」と思う気持ちです。
それを引きづりすぎると、自己嫌悪になってしまいますから、あるところでそれを断ち切る必要があります。
しかし悪いことをしたと思う「罪悪感」は人間として持っていなければならない「心」です。
最近この「罪悪感」を持たない人が多くなっているのが気になります。
オレオレ詐欺、食品偽装、お金のごまかしなど多くのことが身の廻りに起きています。
「俺はそんな悪いことはしないから大丈夫」と思っていても、つい浮気をしてしまうあなた。
浮気は文化だと嘯く人もいます。
人を裏切って自分だけ楽しい思いをする人が多いです。
ある人が言っていました。
「『罪悪感』を持たない人はモンスターである」と。
人間ではなく、化け物です。
せめて家族は裏切らない。
そんなことから始めていかなければならないと思います。
本当の自分の声
以前にも書きました「引き寄せの法則」についてです。
「引き寄せの法則」を使って欲しいモノやなりたいことなどを書いても、なかなか叶わない。
そんなことありませんか?
叶わないその理由は、心の奥底にある魂がそれを信じていないからです。
口ではそうなりたいと願っていても、心の奥底にいる本当の自分は「そんなの無理だ」と思っているのです。
それでは実現しません。
本当に願い、そのための工作や工夫をしているうちに、それが本当に実現するように思えてきます。
それが実現した時の楽しさや達成感を感じ取れるくらいに熟れてくると、心の奥底の自分も「そうなるかもしれない」と思うのです。
そうすると、願いは引き寄せることができるのです。
信じて行動する。
それは素直ということです。
私はそう思います。
ベートーヴェンの「徳」
昨日、本を読んでいると、ベートーベンの遺書の一部が掲載されていました。
それを紹介します。
「弟カルルよ、お前には、前からお前が示してくれた親切に感謝する。
僕の望みはお前たちが僕より幸福な、わずらいのない生涯を送ることだ。
お前の子供には『徳』をすすめよ。
『徳』のみが幸福をもたらすことができるのだ。
金ではない。
僕は経験からこう言うのだ
逆境の中にあって僕を励ましたものこそ『徳』であった。
僕が自殺によって生涯を終わらなかったことは、我が芸術と並んで『徳』に負うているのだ」(ベートーヴェン書簡集)
あのベートーヴェンが「徳」の大切さを説いているのです。
これは驚きでした。
彼は音楽家として致命的な聴力を失いながら偉大な音楽を作曲しました。
一方、彼は欠点だらけの人であったとも伝えられています。
不機嫌で怒りっぽく、しかも嫉妬深かったと言われています。
結婚の夢も諦め、ベートーヴェン自身は決して癒されることはなかったようです。
でも、彼の音楽は素晴らしく癒された人も多かったのです。
その彼が、人にとって大切なのはお金より「徳」だと言っているのです。
その言葉に重みを感じます。
仕事
「この社会は、自分の好きなことを仕事にしている人たちだけによって支えられているのでない。
辛い仕事を社会の必要に応じて、それを仕事にしている人たちが沢山いる。
それを忘れてはいけない。
その人たちの努力によって社会が支えられ、自分が支えられている。
それを理解せず、ただ自分の好きなことをしたいというレベルでは、単なる駄々っ子と同じである。」
これはある本に書かれていたことで、改めて言うことでもありませんが大事なことです。
仕事と恋愛は似ていると思います。
自分の魅力は80レベルなのに、若い頃は90、100レベルの異性に憧れます。
しかし、結婚し本当に幸せを手にするのは自分のレベルに合った人です。
その人と共に努力して、80のレベルを90、100レベルにし、幸せを手にすることが出来ます。
頑張る若者にエールを送りたい。
従兄弟
法要の後は会食昨日、母方の叔父の1周忌法要があり、私も行ってきました。
親族30名くらいが集まりまり、法要そして会食。
会食の間は施主である従兄弟が各テーブルを何回も廻って歩きます。
会食間、食事も満足せず、廻り続けていました。
施主としてしっかり務めを果たしていました。
彼はコンビニ「ローソン」のオーナーです。
現在18日店を展開しており、今年中に20店を超えるのこと。
千歳空港にあるローソン4店は全て彼の店です。
彼は優れた経営者です。
ただ心配なことが1つ。
お酒の飲み過ぎです。
2〜3時間の間にワインを2本くらい開けてしまうそうです。
酒飲みの私もかないません。
その上、タバコも吸います。
健康あっての仕事です。
彼はまだ50歳代。
まだまだ頑張らなければなりません。
少し心配です。
上気元
斎藤一人さんの本を読んでとてもいい話が書いてありました。
それを紹介します。
斎藤さんは自分が元気で機嫌がいいことを「上気元」と言います。
大事なのは自分が「上気元(じょうきげん)」でいるために意識することです。
世の中には、自分の思い通りにいかないことなんて山ほどあります。
それをいちいち、自分の思い通りにいかないからといって自分の機嫌を損ねていったら、ずっと腹を立てていなないといけなくなってしまいます。
だから自分の機嫌はしっかりとること。
機嫌をとる時に大切なのは、自分に起こった出来事をどうとらえるかということ。
どんなことが起こっても、「自分の機嫌をとる」という習慣を身につけること。
どんなことが起こっても、自分に起きた現象は自分にとって一番良いことだと思うようにする。
訓練・修行だと思うこと。
そして自分の器を大きくするための訓練だと思えば良いのです。
自分の機嫌が良くなるようにするために必要なのは"理性"です。
腹が立つのはそこに感情があるからです。
仕事や商売で失敗する人って、えてして我の強い人が多いんです。
そういう人は自分の個性を出そうとするんです。
でも個性と我は違います。
何か強い人は常に自分が正しいと思いたいのです。
でも仕事や商売では正しいかどうかは自分が決めることでなく、お客様が決めることなんです。
自分"が"という「我」を無くしていけば自然と器量は大きくなっていくのです。
「あいつが許せないです。あいつにされたことを思うと、悔しくて夜も眠れません!」そのように言う人がいるけれど、その人が眠れないほど悔しがっている時に、その相手は気持ち良く寝ているのです。
結局、「許せる」「許せない」というのも、どっちが得かということです。
許せない相手を恨んだり、憎む日々を過ごすのが得なのか。
それよりも、その時間とエネルギーを他のことに使って、自分が楽しく、幸せになることに使った方が得なのかということです。
人を許せるのも器量です。そして許せることの多い方が、人は幸せになれると思います。
いつも「上気元」でいられるために必要なのは「意思」です。
天気は自分で決めることはできません。でもその天気がいい天気か悪い天気かは自分が決められるのです。
雨が降ってきたら「外に出られなくて嫌な天気だね」というのか「いいお湿りだね」「草木も喜んでいる」というか、その人の意思が決めることです。
以上が斎藤さんの言葉です。
大事なのは自分の「心」です。
その「心」が「上気元」でいるための方策が述べられています。
皆さんも参考になれば・・・・・
引き寄せの法則
「引き寄せの法則」について書きます。
しばらく前に「引き寄せの法則」に関する多くの本が出版されました。
私も何冊か買って読みました。
簡単に言うと、「自分の望む物を紙に書くと、それを引き寄せて実現する」という内容です。
私も実際に紙に書いたり、口に出したりしました。
でもそれほどの効果があったかというと、そうでもありません。
考えてみると、「同じモノ同士が引き合う」というのは科学的に言って成り立ちません。
「+」と「+」は引き合うのではなく反発し合います。
それではどうすればいいのか。
「引き寄せる」のでなく「同調」すればいいのではないでしょうか。
自分の行動によって、それに合致する流れと同調することだと思います。
自分の行動が伴って初めて願いは叶うのです。
それは昔からある「因果応報」の考え方。
良き考えで、良き行いをすれば、良い結果が生まれる。
紙に書いてただ願うのでなく、それに沿うような行動をすることで良き結果が生まれます。
私はそう考えます。
価値を作り出す
「どうしたら物は売れるか」について考えてみます。
物を作り出す。
農業や製造業。
農業にしても製造業にしても、質の高い物を作る技術は大切です。
ただ、いくら質の高い物を作っても、売れるとは限りません。
大事なのはその物の「価値」を作り出すことでしょう。
「質の高さ=価値の高さ」ではありません。
質が高い製品も、価値を見出してこそ売れます。
そして売ることで大きな利益を得ることができます。
価値の高さが利益の高さになります。
ブランド製品はその典型でしょう。
しかしブランド化するというのはそう簡単ではありません。
でも、物に「価値付けする」という訓練はできると思います。
自分の身の回りにある日常品。
コーヒーカップ、ノート、ペン等を取り上げてみます。
これにどう工夫をすれば新しい価値が生まれるか。
どう価値付けするか。
考えてみるだけでも訓練になりそうです。
自己判断
昨日から全国で大雪になっています。
テレビの報道では、東京で降った雪のため電車などの交通が大混乱。
テレビの解説者は「雪が降るたびに同じように電車が大混乱を起こす。抜本的な解決をしなければならない」などと言っていました。
しかし、年に数回しか降らない雪の為に、雪国並みの装備や設備は難しいでしょう。
それはすべて運賃に跳ね返ってきます。
それより、雪が降って、電車などが大混乱するなら、会社への出勤しなくていいという考えを持つべきであり、その仕組みを作るべきでしょう。
日本人は時間を守り、真面目に決められたことをしようとします。
しかし寒い中、何時間も雪の中に立って電車やバスを待ているだけで体調を崩します。
そのため病欠となると会社にとっては、その後何日もの間、仕事に支障をきたすことになります。
めったにない「災害」の時は個人個人が自己責任で行動すべきです。
何か問題が起こると、国や自治体、また交通機関などの組織の責任を追及しますが、私たち1人1人が考えて、自己責任でベストの方法を選択する柔軟な思考が大切だと思います。
右の頬を叩かれたら
以前ネットを見て知った話です。
「右の頬を叩かれたら、すぐさま左の頬を出しなさい」というキリストの言葉があります。
この言葉の解釈について書かれていました。
それまで私はこの言葉は「叩いた相手を許しなさい」という寛容の精神を表していると思っていました。
ところが違うようです。
多くの人は右利きです。
相手を叩く時、人は右手で相手の左の頬を叩きます。
ところがキリストの言葉では右の頬が叩かれたのです。
相手の右の頬を叩く為には手のひらの裏で叩かなければなりません。
裏拳です。
当時これは相手を侮辱し、奴隷とみなす行為だったそうです。
卑しい奴隷を叩く時、手のひらで叩くと手が汚れると思って手の裏で叩いたのです。
叩かれた者はその侮辱的な行為に対して左の頬を出します。
左の頬を出されると今度は手の「ひら」で叩くことになります。
それで「上下」関係でなく「対等」の関係になれます。
逆に言うと、これは主人にとっては屈辱的な行為です。
キリストの言葉は人間の尊厳について語られているのです。
普段使っていることわざの中には、真意は違うことわざが結構ありそうです。
マネジメント
ドラッカー関連の本を読んでいると、ドラッカーがマネジメントという言葉を発明したことがわかりました。
そしてそれについて定義をしています。
「方向付けを行う」「使命を決める」「目標を定める」「資源を動員する」です。
これは「経営理念」「経営目標」「経営戦略」「人・モノ・金・情報の活用」を管理することと言い換えられます。
それはまた稲盛和夫さんが教えてくれる「経営の12か条」の中に示されていることと同じ内容です。
日本においてのマネジメントとは単に管理するということでなく、人間臭い営みのことです。
データーマネジメントやナレッジマネジメントとは違います。
人としての関係が存在しないマネジメントは単なる「人間管理」に陥りやすいモノです。
その点気をつけるべきです。
青年就農給付金
昨日の日経新聞の特集コラム「農業を解き放て」に「補助金は要らない」という話が載っていました。
農業で起業する2人の女性の話が取り上げられています。
2人は青年就農給付金制度のついて話しています。
この制度は農業を始める人に最大150万円を5年間受け取れる制度です。
1人の女性は「受け取っても農業を続けられなくなる人がいると聞きます。
お金をもらうより技術や経営ノウハウを学ぶ場が欲しい」と言います。
もう1人の女性は町役場からこの制度を是非受けるように勧められたけれど断りました。
アルバイトをしながら農業研修を受け、生産者として伸びようとしているのに、補助金をもらって自分の覚悟が鈍るのが心配と言います。
私は以前から補助金制度は原則的に反対の意見です。
補助金をもらうために時間と労力を使い、本業がおろそかになってしまいます。
その上、やっとの思いで補助金をもらうと、何か一仕事を終えたような錯覚に陥り満足してしまいます。
起業はどの分野でも自分の仕事と真剣勝負です。
余計な誘惑に惑わされては本業で成功などできません。
余計なお金は志をなくします。
この青年就農給付金は2012年度に始まって、受給者は3年間で16000人弱の数になります
年間150万円×16000名=240億円。
この給付金を受け取った人の内、どれほどの人が農業を続けていくのでしょうか。
補助金よりアドバイザー制度、ヘルパー制度を設けてこそ、本当の起業支援となるのではないでしょうか。
それは起業者が「対価を支払わない」人的支援。
民間では出来ないそのような仕組み作りこそ公的機関がする起業支援と考えます。
円と株
昨日の日経平均がまた下がりました。
対ドルで円も上がっています。
原油が1バーレル30ドルを割り、最盛期の3分の1となったと言われています。
中国の株価も急激に下がっています。
世界の経済がマイナスのスパイラルに入ったみたいです。
円が上がっているのは日本の経済がいいと評価されたわけではなく、単に円が避難通貨と認識されているため日本の国債が買われているだけと見えます。
しかしこの日本の国債も過去累計で1000兆円を超すほど発行されており、いつその価値が下落するかわからないと言われています。
経済状況は全て綱渡り状態です。
もし日本で大災害やテロが起きると、それをきっかけに円の暴落が起きることも考えられます。
大地震、噴火、テロ。
テロはISばかりでなく、日本の場合は北朝鮮も心配です。
円の暴落が起きると何が起きるのか。
それを見通し、自分で出来る備えは必要かと思います。
経済アナリストは、経済の動きを中心に注目して、予想を出しますが、政治、経済、環境は全て連動しています。
今、円高が続いていますが、私はそう長く続かないと思います。
世界の投資家が一時的に円を買っていても、あくまでも一時的です。
今後、不安定要因が高い円は、何かをきっかけに円安に動き出すと思います。
一旦円安に動き出すと日本の国債の評価が一気に下がり金利が高騰します。
その時が怖いです。
これからの政治、経済、環境、それに宗教にも、より注視していきたいと考えています。
ゆっくり歩く
ゆっくり歩く。
テレビである医者は「歳をとると歩くスピードが遅くなる。歩くスピードは歳をとったバロメーターだ」と言います
私が言っているのは、それと違います。
「お先にどうぞ」という気持ちになれるかどうかです。
仕事をしていると、常に効率を考え、時短や、スピードを上げることに意識がいきます。
頭の中では常に先を考え行動しています。
それは時として、競争を生みます。
仕事の上で競争には勝たねばなりません。
より効率良い仕事をするかを常に考えています。
しかし気を付けなければ、それが心のゆとりを失うことになりかねません。
周りが見えなくなってしまうことがあります。
どこかでオンオフの切り替えをしなければなりません。
切り替えスイッチ。
それが「ゆっくり」歩くこと。
人をかき分けて歩かない。
「赤信号になりそうだから急ごう!」など思わないで、周りの景色を見ながらゆっくり歩く。
心に余裕が生まれると、人にも優しい気持ちになれます。
そうすると他の動作も「ゆっくり」になります。
普段見えないものが見えてくることもあります。
一度、休みの日に意識してゆっくり歩いてみてください。
いろいろなものが見えてきますよ。
器量
「あの娘は器量がいいね」という言葉があります。
可愛いとか綺麗という意味で使われます。
また、別の意味としては「器の大きさ」を言います。
「大器」とも言われ、人徳の大きさを意味しています。
先日、「器」という本を買い、読みました。
その本の中で、斎藤一人さんは「我(が)を外した、人間らしい正しい考え方を"器"と言うんじゃないかと思うのです。
どうでもいいことはどうでもいいのです。
本当に必要ないと言えることは必要ないと言えることなのです。」と書いています。
確かに「我」が強いと、どうでもいいことまで口を挟み、文句を言います。
部下が優秀で出世した時「よかったね。おめでとう」と言えるか。
人が幸せになった時、本当に喜んであげれるか。
我が強いと「なんであいつが認めらるのだ!」とか「なんであんな娘がいい男と結婚出来るの!」との妬みが生まれます。
だからといって我を単に抑えると「我慢」になります。
我慢はストレスになり、いつか爆発します。
そうではなく、「我」から離れて「心の有り様」を変えることが大切なのだと思います。
そのために「自分の心を高める」ための勉強をする。
私はそのように考えます。
種まき
年が新しくなり、初詣に出かけた方も多いことでしょう。
今年の運勢を知るためにお御籤を買った人もいるかもしれません。
大吉を引いた人は「何かいいことが起こるかも」と思います。
私も引きましたが小吉でした。
何かいいことが起きればいいなと思うのは皆同じです。
でも本当にいいことが起き、自分の願いが叶うのは「種まき」をしているからです。
「種まき」もしないで「何かいいことが起きればいいな」と思ってもなかなか叶いません。
当たり前のことですが、それを忘れて「成果」や「収穫」だけを願います。
まずは「種まき」
今年はどんな「種をまく」のか。
新年の初めにそれを考えてみます。
きれい
昨年末に大掃除をして、新年は「きれい」な会社で仕事初めという皆さんが多いでしょう。
「きれい」という言葉は美しいという意味もありますが、汚れや余計なモノがない状態のことです。
雑然とした机の上では仕事の効率が上がらないことは誰でも経験しています。
それでも、せっかく「きれい」にした机の上は、いつの間にか雑然とした状態になってしまいます。
稲盛和夫さんは机の上に余計なモノを置くのをひどく嫌うそうです。
また、書類も斜めに置くと指摘されます。
身の周りが雑然としていると、気持ちが集中しません。
稲盛さんは科学者でもあります。
試作する時などは作業の精度を高めるために、身の回りを整理整頓したのでしょう。
そうしなければ試作は成功しません。
そしてそれが習い性になって行ったのだと想像します。
稲盛さんは経営者として大切な「有意注意」という考えを説いています。
それに通じるものがあります。
私の身の回りは今のところ「きれい」になっています。
この状態、続けていきます!
誕生からの日数
明けましておめでとうございます。
今日は1月5日。
私は今日から仕事始めです。
そしてまた歳を1つ取りました。
日数で言うと今日は私が生まれてから24,252日目です。
昨年、会合である人が「私は毎日書く日記帳に生まれて何日目かをも書いています」と言ったのを覚えていて、今年の初めに自分の日数を調べてみました。
ネット上に計算をしてくれるサイトがあり、そこですぐわかります。(http://birth.twitter-tools.net)
今までは年齢で自分が生きてきた期間を知りましたが、日数になると改めて自分の人生を思いやるような気持ちになります。
1日1日生きてきたんだという気持ちとともに、「これからの1日1日を大切にしていかなければ」という気持ちにさせてくれます。
それにしても24,252日は長いです。
今はフッと昔のことを思い出しています。
私が節目の25,000日目を迎えるのは748日後の2018年1月21日です。
元気にその日を迎えるようにします。
順風と逆風
風に向かっていく人。
勇ましそうに見えます。
逆境に負けないつもりなのかも知りません。
でもそれは単に意地を張って生きているだけなのかもしれません。
結果、一生懸命頑張ったのに1歩も前に進めまない。
そして貧しいとか不遇だと嘆いています。
それはなぜなのか。
逆風に向かっているからです。
順風に乗ればいいだけなのになぜそうしないのか。
それは素直でないからです。
道理を知り、素直になってそれに沿った生き方をする。
そうすれば風に乗れます。
この世に吹く風は良き方向に吹いてます。
その方向に沿った風は順風となり、逆らって生きる人には逆風となります。
どうせなら順風に乗って生きればいいのです。
ただ、風任せという生き方は吹き溜まりの中に落ちていきます。
しっかり頑張って風を受ける帆を張る努力をしなければなりません。
その帆も穴が開かないように常に手入れをします。
大きな帆、しっかりした帆を掲げれるか。
それはその人の心の有り様によります。
そして大切なのは明確な目的・目標が必要です。
自分の進むべき方向に向かっていくのです。
また人の心は弱いものです。
人生の中でつまずいたりすると、つい投げやりな気持ちになることもあります。
それでも帆は張り続けましょう。
気落ちし、帆を張る努力をしないと吹き溜まりの中に落ちていきます。
辛くても、しっかりした帆を張り続ける。
このことが大切だと考えます。
6人の羅漢さん?
今日は25日の金曜日。
クリスマスですが、明日の土曜日から休みに入るので、今日は大掃除という会社も多いでしょう。
掃除をすると改めて「ああこれあったな〜」というモノを見つけます。
自宅で自分の部屋を掃除をしていると、机の上の棚のところに可愛い6人の羅漢さん?の像があるのを改めて気付きました。
20年ほど前から私の手元にありますが、その入手経緯はよく覚えていません。
いつの間にか私のところに来ていました。
6人の羅漢さん。
居眠りをしている人、背伸びしている人、怒っている人もいます。
この6人はなんなのでしょうか?
誰かお分かりの方がいれば教えてください。
ただ、この6人の羅漢さんが来てからいいことが起きているような気がします。
そしてこの6人の仕草を見ているとホッとします。
当り前のこと
先日のテレビで、今治タオルの偽装問題が報道されていました。
日本の繊維関連会社は長い間中国製品などに押され苦しんできました。
その中で愛媛では何年か前に苦労して今治タオルブランドを立ち上げ、一気に人気が出てきたのです。
そのな中での今回の偽装問題。
今治タオルを作っている中の1つの会社が起こした問題ですが、それだけでブランドに大きな傷を付けていましました。
日本ではその他にも多くの会社の偽装問題が起きています。
化血研という会社も大きな問題を起こしています。
偽装は会社ぐるみもあれば、現場責任者の独断もあるかもしれません。
偽装ではありませんが、以前は食品工場で異物を入れるという問題も起きています。
1つの偽装が会社の存続問題に発展していきます。
経営者が知らない間に現場で起きたからといって言い訳はできませんん。
日本人の考え方が変わってきたのでしょうか。
私たちが親から教えられた「正直に真面目に生きる」という「当り前」のことができていない。
日本人は昔から「正直に真面目に」モノを作ってきました。
だからこそ日本製品は世界から信頼されているのです。
このままではその信頼が崩れてしまいます。
年末のこの時期、経営者は今年の反省と来年の構想を考えているかもしれません。
利益率や効率などの数字も大切ですが、自社で「当り前」の土台が出来ているのか。
それを改めて考えてみるいい機会かと思います。
ご近所先生企画講座
先週の土曜日、「ご近所先生企画講座」の交流会に参加してきました。
この講座の講師ばかり50名以上が集まりました。
「ご近所先生企画講座」というのは札幌市生涯学習センターが7年前より始めた事業で、講座の講師は希望する札幌の一般市民です。
私はこの講師として4年ほど前から参加しています。
私の担当は「身の丈起業のススメ」
この講座の講師になったのはチョットしたキッカケからです。
講師になったおかげで、今までとは違った人達とのネットワークができました。
身丈会という会もできました。
それまでの知り合いと言えば経営者が中心で、そのような団体にも入っていました。
しかしご近所先生の講師を務めてからは、さまざまな仕事の人達との出会いが一気に増加。
年代層も20歳代から70歳代。
楽しいことがたくさん生まれました。
この「ご近所先生企画講座」がそのキッカケを作ってくれたと感謝しています。
「ご近所先生企画講座」の交流会のあと忘年会、2次会と続きました。
講師同士の交流も生まれています。
絵画展示会
昨日は親しい友人たちとホテルでランチ会をし、その帰りに1人でリボンハウス絵画教室の「クリスマス展示発表会」に行ってきました。
その絵画教室は札幌を中心に何百人の数の生徒さんに絵を教えています。
リボンハウス絵画教室とのお付き合いは4〜5年ほどになります。
毎年春には、アメリカの子供達と桜の絵の交換プロジェクトに参加していただいています。
「クリスマス展示発表会」には2歳児から大人までの1000点ほどの絵などが飾られていました。
その展示されている中で特に感動したのは5歳児たちの絵です。
画面から飛び出さんばかりに大きくか描かれた牛やパンダやサメなどの動物達。
その使っている色も明るくそして大胆。
「5歳児がこんな絵をかあくの?」と驚きます。
説明していただいた岩田先生によると「5歳児だから大胆に描けるので、大きくなるにつてその良さがなくなっていきます」と言います。
この子供達の絵をそれぞれが自宅に持ち帰り、部屋に飾るとパッと明るくなることでしょう。
子供の絵ってすごいですね。
この展示発表会は今月の19日まで札幌の時計台ギャラリーで開催されています。
ご興味ある方はどうぞ行って見てください。
元気をもらえますよ。
人間力
仕事をしていると「段取り8分」などと言われます。
準備することは大事です。
しかし、それと同時に突発的な問題が発生した時に必要なのは「対応力」であり「対処力」です。
どんな万全な計画や対策を練っても、100%その通りにはいきません。
思った通りに進まない。
思いがけない問題が発生した。
という時こそ「対応力」や「対処力」が求められます。
それはまた「人間力」とも言えるでしょう。
「経験」「「情報」「ネットワーク」
それと「勇気」です。
「頼りになる人」
「人間力」のある「頼りになる人」
それこそ、会社において社長に求められる第1の資質だと考えます。
モチベーション
モチベーション。
身体的不調や、環境によって「今日は仕事したくないな〜」と思うことは誰にもあります。
あの稲盛和夫さんにもあったと聞きました。
その時、色々な方法でモチベーションを高める努力をします。
社員の「モチベーション上げ」を管理者やマネージャーの仕事をしている会社があります。
仕事がしやすい環境作りは管理者やマネージャの仕事ですが、個々人の心の持ちようは各自の責任です。
やる気を出すか出さないか。
それは本人の問題であり、管理者やマネージャの責任ではありません。
「やる気のない人がいるからこそ、やる気のある人に成功のチャンスがある」
そう思った時、またモチベーションが高くなるのかもしれません。
モチベーション。
心の有り様。
これは常に自己責任です。
I(アイ)ターン
先週末東京で、ある起業支援団体の集まりがあり参加してきました。
80名ほどの人が集まり、ビジネスプランのプレゼンテーションなどがなされました。
また東北を中心として地域おこしのイベントアイディアの募集なども行われました。
メイン行事の1つに「地方で起業! UIターンで起業!その魅力を語り尽くす」という題でのパネルディスカションもあり、私もそのメンバーとして少し話しました。
北海道は150年ほど前、日本中から人々が集まり、創り上げられた土地です。
言うなれば北海道は「Iターン」の人々によって創られたのです。
だからこそ、北海道には他所者に対して優しい風土があります。
北海道で起業している人の中で「Iターン」して他所から来た人の割合が7割ほどあると私は思っています。
最近は農業での起業ばかり注目されていますが、北海道には漁業もあります。
林業だってあります。
北海道はまだまだ起業の可能性の高い土地です。
これからも全国から北海道に若い人が集まってくるかもしれません。
これからの北海道、楽しみです。
良いところ
「優れた経営者「と「そうでない経営者」
その違いの1つに、自社の良いところを数え上げることができるか、悪いところを数え上げるかの違いです。
どのような会社でも欠点や不足部分はあります。
それを取り上げて嘆いていても、進まないどころか落っこちてしまいます。
キリがありません。
それより良いところや長所を見出しそれを伸ばしていく。
足が悪い人。手がきかない人。
身体が不自由な人がいます。
そのような人でも、それを嘆くより、まだ目が見える、耳が聞こえるという長所を見出し、イキイキと生活している人が多くいます。
人も会社も、自分の良いところを数え上げれば、悪いところの数より絶対に多いはずです。
それを自信にして積極的に踏み出していく。
経営者のチョットした考えで業績も変えることができるはずです。
利他の心
世界は1つ。
人類は皆兄弟。
これはいつの時代に言われていた言葉でしょうか。
昨今の報道を見るにつけ読むにつけ、利己主義の国や人々ばかり。
アメリカの孤立主義。
ロシア、中国、北朝鮮などの独裁体制。
近くでは、日本と中国・韓国との軋轢。
そこにあるのは排他的な考え方しかありません。
過去にこれだけ自由に海外を往来できた時代はありませんでした。
ネットでも簡単に情報を得ることができます。
より他国を知ることが出来る時代です
それなのにより閉鎖的になっています。
排他主義になっています。
世界中がそのような悪い流れになりつつあります。
なぜでしょうか?
それは自国のことしか、自分のことしか考えないから。
今の時代にこそ大切なのは「利他の心」
世界中、国という単位では悪い方向に流れて行こうとしていますが、それに疑問を持っている人は世界中に数多くいます。
1人でも多くの人が他を助ける「利他の心」を持てれば悪い流れを止めることが出来るかもしれません。
そのような思いを1人1人持ち続けることが必要。
そう考えます。
スナックのマスター
昨日、私の事務所に来られて方の話です。
先週の金曜日に友人と行った近くにあるスナックのマスターです。
そのマスターは友人の知り合いで、元大手広告会社電通のデザイナーでした。
スナックは1960年代のアメリカのグッズが飾られ、当時のレコードからジャズが流れています。
彼が選んで飾られた小物は、古き良き時代のアッメリカグッズで、「欲しい」と思う物ばかりです。
その店も今月いっぱいで閉じてしまうとのこと。
今後は「物書き」として腰を据えて小説を書いていくと言います。
彼はすでに何冊かの本を出版していて、その1冊をいただきました。
「And I Love You So」という恋愛小説です。
彼は70歳になります。
その歳になってもこのような本が書ける。
素晴らしいことです。
マスターはこれから自分の先祖を調べながら、それを題材とした明治からのノンフィクションを書くとのことです。
そのためには、図書館や古文書館、また現地調査をしたり人に会ったりしなければなりません。
ますます忙しくなるようです。
「このような生きがいある道もあるのか」と感心しながら話を聞いていました。
これから交流が深まりそうです。
ツブ貝その2
昨日、「目の焦点が合わない」という話を書きました。
昨日早速に主治医の内科の先生のところへ行きました。
その先生も原因がわからず、「念のため脳の検査をしましょう」ということで紹介状をいただき脳神経外科へ。
MRI・MRAの検査をしましたが全く異常はありませんでした。
それを聞いた時、本当にホッとしました。
「脳梗塞か?」という心配がありました。
でも原因がわかりません。
脳診断した先生から、「念のため神経科の先生に診てもらうといいですね。」と言われ、同じ病院の別の先生に診てもらいました。
それでも原因はわかりません。
日曜日から眼科、内科、脳、神経の4人の先生に診てもらいましたが、原因もその処置もわかりません。
「その内に良くなりますよ」という言葉をいただき終わりました。
未だに目の焦点が合わず物が2重に見えます。
ただ、今回の件で脳の検査をしてもらい、異常が無かったということは良かったと思っています。
今回診てもらった4人の先生に「ツブ貝の毒」についてお話しましたが皆さんは即座に否定しました。
ネット上には札幌市から食中毒情報として発信されて、「物が二重に見えるなどの視覚異常やめまいが起きる」と掲載されているのに・・・・
ツブ貝
先週の金曜日に昔からの友人と酒を飲みました。
1人はKさんで木工作家でありながらイラストレーターでもあります。
彼が書いた「熊出没注意」のイラストが北海道中のみやげ店で色々なグッズや飲料として売られています。
30年ほど前からの付き合い。
もう1人はステンドグラス作家のFさん。
札幌市豊平川サケ科学館のステンドグラスなどを手がけています。
彼女とは幼稚園からの付き合いです。
以前は彼らも含め、異業種の人達と「美味しいものを食べる会」を作って定期的に会っていました。
金曜日は彼らと久しぶりの飲み会。
楽しい会話と美味い酒に酔いました。
そして楽しく会が終わりました。
ところが翌朝起きた時、びっくり。
寝床で目を開けると、まだ酔ったように目の焦点が合いません。
二日酔いではないようですがフラフラします。
その症状が日曜日になっても治らず、日曜日も診察している眼科に診察してもらいましたが、目に異常はありません。
ネットで調べました。
①脳梗塞の前兆
②ツブ貝の貝毒によるめまい
その症状の原因として、この2つが出てきました。
確かに金曜日に大きくて美味いつぶ貝を1個食べました。
それが原因か?
ネットの情報には「貝毒の目まいなどの症状は2〜3時間ほどで消える」書かれていましたが、今日になっても取れません。
さて、それでは脳梗塞の前兆か?
とりあえず今日病院に行きます。
今日参加予定していた忘年会はキャンセルしました。
どうぞ皆さん、お体大切に、そして貝毒に気をつけてください!
知らないことなど無い!
エネオスのテレビCMで女優の吉田羊さんが「私には知らないことなど無いんだから!」と言うセリフがあります。
「知らなかったな〜」というセリフも後から続きます。
人は往往にして知らないと言えず、知ったかぶりをしてしまいガチです。
「知らない」と言えず、そのまま話が流れて行き、話に参加することが出来ないことがあります。
会社の会議で、何でもかんでも知らないと言うと「少しは勉強してこい!」と言われたり、話の腰を折ると思われたりしますが、知らないことを知らないと言える勇気は必要です。
そのような勇気を持っている人は間違いなく伸びます。
「自分はなんでも知っている人間」に見せようとすると辛いものです。
「自分は何も知らない人間ですから教えて下さい」と言える。
歳をとるとそれが出来なくなりがち。
気を付けたいと思っています。
カシオペア
札幌を16時12分出発し、上野には翌朝の9時25分到着する17時間ほどの旅でした。
このカシオペアは来年の3月に廃止になる事が決まっています。
妻は昔から北斗星、カシオペア、トワイライトエキスプレスのどれかに乗るのが夢でした。
それがやっと叶いました。
今、実際に走っているのはカシオペアしかありません。
そのカシオペアはいつも満席で、今回も満席。
私達は1か月以上前から予約をして取れました。
私達の部屋はスイートルームでリビングルームとベットルームに分けられています。
ウエルカムドリンクやモーニングコーヒーのサービス、朝刊もサービス。
夕食は食堂車で。
豪華な旅を経験しました。
それにしても常に満席のこのカシオペアが廃止になるのが不思議です。
北海道新幹線が開通するのが原因だそうですが、勿体無い話です。
その北海道新幹線は料金が高いと言われていながら、収支予想は赤字とのこと。
私達札幌に住んでいる者の内、東京に行くのに新幹線利用するという人はほどんどいません。
飛行機を使う方が、料金的にも時間的にもいいのです。
新幹線開業の意味がわかりません。
速さや便利さは飛行機。
旅行の楽しさは鉄道。
その鉄道旅行の楽しさの1つが来年3月無くなります。
誠に残念!
命日
昨日は父の5年目の命日でした。
坊さんを呼んでお経をあげてもらい、夜は会食。
私たち兄弟姉妹4人揃ったのは1年ぶり。
昨年も父母の命日でした。
私たち兄弟姉妹は仲がいいと思います。
それはとても幸せな事であり、亡くなった父母も喜んでいる事でしょう。
そう言えば、父も生前は弟2人と毎週金曜日に一緒にランチを食べるのを「決め事」としていました。
「兄弟は他人の始まり」と言われます。
親が死ぬと兄弟姉妹が疎遠になっていく。
そんな話も聞きます。
私達兄弟姉妹は来年、夫婦で旅行へ行く話も出ています。
フッと父母が喜び、笑う顔が目に浮かんできます。
専業主婦
来年の夏に、イギリスに嫁いでいる三女の家族が遊びに来るのが決まりそうです。
その時は東京・神奈川・千葉にいる兄弟姉妹の家族も呼ぶ計画です。
私たち夫婦が元気なうちに皆んな集まって大宴会をしようと思っています。
私達には子供が5人います。
それの連れ合いが5人、それに孫が6人ですが、来年にはもう1人増えそうです。
私たち夫婦入れて19人になります。
考えてみれば、私と妻の2人から始まった家族が19人になりました。
これはただただ妻のおかげです。
妻は私の安い給料の中で5人の子供を育てました。
5人が子供がいましたので働きに出る事も出来ませんでした。
(妻が稼ぐお金より保育料の方が高くなります)
専業主婦として子供を育て、私を支えてくれました。
でも今の時代、その専業主婦が肩身を狭い思いをしています。
働く女性を支援することはもちろんいい事ですが、多くの子供を育てるために頑張る専業主婦も認めてあげていいと思います。
それなのに一律に専業主婦の扶養控除が廃止されようとしています。
少し疑問に思う此の頃です。
15歳起業
今朝、出がけのNHKのニュースで「15歳で起業」という特集が流れていました。
題名だけ見て出て来たので、詳しくはわかりませんが「15歳で起業」というところが少し気になります。
私の小学生・中学生の頃、先生から「金儲けは悪」的は話を聞いていましたので、金持ちは不正なことをしてお金を稼いだと思っていました。
その考えが大学生の頃までひきづっていて学生運動もしました。
社長をしていた父とも衝突しました。
でも父は経営者として真面目に仕事をしてきたことは私にも良くわかっています。
あの小学校・中学校のときの先生の「金儲けは悪」的な考えは偏向的な話と思ってます。
日本が欧米・中国のように起業家が育たなかった理由がそこにあるようにも思います。
とは言っても今15歳で起業というのも少し気にかかります。
自分のしたいことを始めるのに歳は関係ないのですが、15歳の中学生にとってその時期は大事な時。
これからの人生で必要な基本的な考え方は小中学生で身に付くものだと私は考えています。
規則正しい生活、友達作り、クラブ内の上級生との関係、成績を上げるために頑張る努力。
それに挨拶や感謝する心。
人間としての基盤は小中学生の時に作り上げられるものです。
それを身に付けた上で、持ち続けた起業への思いに挑戦する。
それでも遅くはなく、またその方が大きく花開くと思います。
15歳の起業。
応援したい気持ちを持ちながら、少し気に掛かります。
経営者はコメンテーターではない
テレビの情報番組を見ていると、コメンテーターと言われる人が出ています。
評論家とは違います。
評論家とコメンテーターの違いは評論を職業とする人か、ただ意見を言う人かの違いだと思います。
評論家はそれなりに筋の通った考えを話しますが、コメンテーターはその場の雰囲気や時勢を見て意見を言います。
ただ時として、どちらも自説に都合のいい情報を集めてきて述べていることも多いように思います。
一方経営者はどうでしょう。
経営者は評論家でもコメンテーターでもダメです。
実践者です。
でも、時として評論家やコメンテーターのように、自分にとって自社にとって都合のいいデーターや情報だけを当てにして経営判断していることはないでしょうか。
現場に入って現状を認識し、その中で問題点を探し出す。
現場に入るのを嫌がり、悪い情報を避ける経営者は経営者失格。
私はそう思います。
抱負
「夢を持ちなさい」
よく言われる言葉です。
確かに、夢を持ちそれを追いかける人はいます。
しかし、実際に自分の夢を持っている人はどれほどいるでようか。
時として、その夢を持たなければという思いで、無駄な「夢探し」をしている場合があります。
年末の今の時期、「来年の抱負は?」と聞かれることがよくあります。
先日テレビを見ていた時、料理愛好家の平野レミさんがこの抱負についていいことを言っていました。
「抱負なんて言われてもそんなのは分からない。
それより今自分が好きなことを一所懸命していればいい。
一所懸命していて、ふと自分のしてきたことを振り返ると1本の道になっている。」
そのようなことを言っていました。
今自分の目の前にあることを一所懸命していければそれが自分の人生。
振り返ると自分の道はしっかり1本道になっている。
そのうちに生き甲斐や、やりがいが生まれてきます。
そう考えると、人まねでない、しっかりした自分の生き方ができます。
目の前にあることを一生懸命してきた結果、多くの人や事柄に出会い、若い頃に思い描いていた人生とは違うけれど満足できる人生を送れる。
私はそう思います。
ホテル再建
昨夜見たフジテレビの「アンビリバボー」という番組。
途中から見たのですが感動的な内容なでした。
ご覧になった方も多かったのではないでしょうか。
「ホテルアソシア 名古屋ターミナル」というホテルの再建物語です。
21年前、近隣に出来た大型ホテルの影響を受け業績は最悪の状態でした。
そこに雇用対策室長として赴任してきたのは、ホテル未経験で、鉄道の労働組合委員長であった柴田秋雄氏です。
赴任早々、彼は社長から人員整理を命ぜられました。
結果、従業員150名の内110名をリストラし、残った40名と補強したアルバイトで営業を続けることになりました。
リストラする時、彼が心がけたのは、他のホテルでも採用されるだろう優秀な人から声を掛けて辞めてもらったのです。
再就職しやすい人から辞めてもらったのです。
残った従業員は他企業に転職できなかったり、転職する勇気もなくホテルに残った従業員です。
どちらかというと「落ちこぼれ」です。
柴田氏はリストラの後に総支配人となり、彼らを率いたのです。
ホテル存続の危機の中、従業員達の士気は最低でした。
そこで柴田総支配人が最初に手を掛けたのは、社員食堂などを整備したり社員の誕生会を開いたり、従業員のための改革を始めました。
社内からは経費の無駄という抗議も受けましたが、「お客様が笑顔になっていただくためには私たちが笑顔でなければならない」という考えが総支配人にはありました。
そして「日本一幸せな従業員が働けるホテルにしたい」という思いもありました。
その後色々な紆余曲折はありましたが、業績は回復して行きました。
このホテルは5年前に建物の老朽化により閉館しましたが、2017年に名古屋駅前に新たにオープンする予定とのこと。
この再建劇の中で特に心に残ったのは、柴田総支配人が率いた「落ちこぼれ」と言われた従業員達に自信をもたせたことです。
そこには「日本一幸せな従業員にする」という熱い思いがありました。
ホテルにとっての財産。
それはそこで働く人達です。
お客様より先に従業員を大切にする。
この考え方こそが再建の大きな要因であったように思います。
焦点ぼかし法
「焦点ぼかし法」とは、あえて焦点をズラすとか曖昧にするという意味です。
私の造語です。
仕事をする上で大切なのは、常に意識を集中し問題点を見つけ出す力です。
「有意注意」です。
しかし仕事を離れた時は「焦点ぼかし法」に切り替えるのです。
それは人との調和の基になります。
普段の生活の中でちょっとした人のミスが気になり咎めてしまう。
咎めなくても心の中に引っかかり、面白くない気持ちになる。
そうするといつもイライラした気持ちになったり悩んだりする。
そうならないために大切なのは人のミスに焦点を合わせないことです。
「どうでもいいこと」と思うことです。
そうすれば人に優しくなれるはずです。
この歳になってそれが少し分かってきました。
焦点を集中する時とぼかす時。
その切り替えが大切になります。
その基準は自分にとって「何が大切か」「誰が大切か」が明確になっていればできるはずです。
大切な仕事に対しては厳しくても、仕事を離れれば「部下が大切」であり「家族が大切」になります。
大切な人には「焦点ぼかし法」。
私も妻に使っています。
セトモノ
「セトモノとセトモノと
ぶつかりっこするとすぐこわれちゃう
どっちかやわらかければだいじょうぶ
やわらかいこころをもちましょう
そういうわたしはいつもセトモノ」
これは相田みつをさんの詩で、ACジャパンの広告としてテレビで流れています。
先日のフランスでのテロは私たちに大きな衝撃を与えました。
今朝のニュースでは「イスラム国対G20」の戦いが本格的に始まると報道されました。
互いにどんどん硬化している状態です。
また一方、G20の国々も互いに張り合っこしています。
ロシアと欧米、中国と日本・アメリカ、アラブとイスラエル。
その他数え切れないほどの対立が起きています。
対立の始まりは「正しい」「正しくない」の観点で、相手を非難します。
互いに理論武装して防備を固くしています。
ちょっとぶつかれば欠けるし、下手すると粉々になってしまいます。
「イスラム国とG20」や「イスラエル対アラブ」は宗教的対立でもあります。
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、それぞれが自分の宗教が正しい。
相手の宗教は邪教だと言って非難しています。
そんな時、斉藤一人さんの言葉を思い出します。
「正しい」を「楽しい」に置き換えると争いはなくなります。
「キリスト教徒の人が『私の宗教は楽しい』と言えば、イスラム教徒の人は『いや私の宗教のほうが楽しい』と言います。
そうすると『お互いの宗教が楽しくてよかったね』となりケンカが起きません。」
「正しい」を「楽しい」に置き換えて物事を考えれば、セトモノからやわらかいモノになっていく。
世界のことを考えることは必要ですが、自分の身の回りのことから考えていくことも大切だと思います。
講座終了
先週の木曜日に私が担当していた講座が終了しました。
今回の講座のための準備は3ヶ月前からしており、肩の荷が下りた気がします。
この講座を通して感じたことの1番は、参加者の受講に対する熱意です。
毎週木曜日、全5回の講座でしたが、その講座ごとに宿題を出しました。
レストランを開業する想定で、近隣調査、市場調査、競合店調査をしてもらいました。
翌週の講座まで実施してもらい、その結果に基づいて料理コンセプト、店舗コンセプトを作成してもらいます。
それを踏まえて事業計画書、収支計画書、資金計画書、返済計画書を実際に作成。
1講座の時間は2時間ですから、その作成作業は講座の中ではできません。
自宅でしていただきました。
講座では収集したデーターの確認と方向性を決めました。
最終日には各グループから事業計画書、収支計画書、資金計画書、返済計画書を発表。
最終日に参加していただいた日本政策金融公庫の創業支援センターの所長さんから講評をいただきました。
この講座では、参加者の熱心さに押され、私も毎回しっかり下調べなどの準備をして臨みました。
自分自身、改めて勉強しました。
私の講座の後も講座は続きます。
作り上げた店の事業をどのように告知していけばいいのか。
その講座が別の講師によって続けられます。
ホームページの作成、その管理、またブログ・Facebookやツイッターなどを活用した告知です。
12月17日まで続きますが、中身の濃い講座になると思います。
鬼が笑う
もう今月も10日を過ぎました。
この時期は、月末から12月にかけ忘年会の予定が入ってきています。
今年の12月は特に行事が立て込んでおり、既に忘年会を入れられる日は少なくなってきました。
「来年のことを言うと鬼が笑う」という言葉があります。
人の寿命を知っている地獄の鬼が「お前は来年のことを話しているが、お前には来年はないんだぞ!」と笑うのです。
あと残り1ヶ月半の今年。
十分気をつけて過ごしていきたいものです。
お母さんをパチンコ屋に連れて行く
以前に紹介しました、稲盛和夫さんの本「ごてやん」の中に、心に残る話がありました。
「もしも今、母が生きていたら・・・・
そんなふうに夢想してみる。
田舎の家のちゃぶ台の前に座り、母が作ってくれる美味しい味噌汁や魚の干物を食べさせてもらえたら幸せだ。
母と今もし一緒にどこに出かけられるとしたら、鹿児島に帰り、パチンコ屋へ連れて行ってあげたい。」
稲盛さんが京セラの社長と大成された頃はお母さんの毎日にも余裕が生まれました。
お母さんは小遣いができるたびにパチンコ屋に行くのを楽しみにしていたそうです。
稲盛さんも鹿児島に帰るとその度に一緒にパチンコ屋に出かけたようです。
そんなことから、今お母さんが生きていたらパチンコ屋に連れて行ってあげたいというのです。
パチンコをするお母さんをお父さんは面白くなかったようですが、稲盛さんはお母さんがしたいことをして上げました。
世間体も気にしなかったのです。
稲盛さんは本当に「お母さん子」だったのでしょう。
私の父も「お母さん子」だったようです。
先日、妻が生前の私の母から聞いた話だと言って教えてくれました。
祖母が同居していた時、祖母の部屋と父母の部屋とは居間を挟んで向かい合わせにありました。
父は寝る時、祖母が寂しがらないようにと、2つの部屋の引き戸を少し開けて寝たそうです。
ともにお母さんを大事にする話。
そんな話を聞いて、ほのぼのとした気持ちになりました。
人生は一筆書きのようなもの
ある本を読んでいると「人生は一筆書きのようなもの」という言葉がありました。
過去に書いた出来事は今更書き変えることはできません。
でも、自分の現在そして将来は自由に描くことができるということです。
確かに過去のことは変えることはできませんが、これからは自分の思うままに夢を描くことができます。
しかし、夢を描こうとしても実際に自分の夢を持っている人はどれほどいるでしょうか。
自分の夢を明確に持っていれば、いままでの人生も後悔するものではなかったはずです。
多くの人は自分の夢を持ちたいと思っても、何が夢なの分かっていない。
それを知ろうとしている内に月日は過ぎていきました。
もしかしたらこれからも、自分の夢が何か分からないまま月日が無駄に過ぎていくのかもしれません。
それなら今、自分がしていることを一生懸命してみる。
今の仕事を一所懸命に頑張ってみる。
1日1日を大事にしていく。
そうしていく内に自分の夢が見つかかもしれません。
1日1日を一生懸命頑張って現在を描いていく。
そうすることで、自分の満足いく将来を描いける。
私はそう思います。
腕を組む
昨夜、夕食を摂ろうとあるカフェに入ろうとした時の話です。
店に入ろうとした時、店主らしき人が腕を組んで入口の方を向いていました。
途端に私は店に入るのを止めました。
店主が腕を組んでいるところには入れません。
腕を組むポーズは「拒絶のポーズ」です。
その店主は知らずに、癖で腕を組んでいたのかもしれません。
しかし、腕を組むポーズは「入ってくるな!」というメッセージをお客様に与えてしまいます。
店の人達が知らず知らずにしていた行為が多くあります。
髪の毛がボサボサの人が料理を作っていたり、カウンタの中でタバコを吸っている調理人。
お客様にお尻を向けておしゃべりをしているウエイトレス。
「ありがとうございました」と言いながらお客様の方を向いていないレジ係
「お客様の入りが悪い。どうしてか分からない」と言う店主がいますが、自分達の気づかない行為がお客様を遠ざけているのです。
そう言えば、雑誌などで有名料理人の写真を見る時、ほとんどの人が腕を組んでいます。
「俺は凄いんだぞ!」と言っているように見えます。
そう見えるのは私だけでしょうか。
ごてやん
昨日、稲盛さんの新刊「ごてやん」を買ってきました。
「ごてやん」とは鹿児島の言葉で「ごねる」という意味で、素直に言うことを聞かず、わがままを言って相手を困らせることだそうです。
「ごてやん」は稲盛さんのお母さんのことが書かれています。
稲盛さんはこれまで多くの本を出してきましたが、ほとんどが経営に関することや、人としての生き方について書かれている本がほとんどでした。
プライベートなそしてお母さんのことに書かれている本は初めてではないでしょうか。
この本を半分ほど読みましたが、稲盛さんは60歳を過ぎた頃より、1日に何度か「お母さん」とつぶやいているそうです。
何かあると「お母さんありがとう」とか、お酒を飲み過ぎた時は「お母さんごめんなさい」と言うのです。
本の中で、堂々と「自分はマザコンだ」と言い切っているように見えますが、それがとても微笑ましいのです。
そう言えば私も何かある度に「お父さん」とか「お母さん」と口にしています。
口にすると、いつも側にいてくれるような気持ちになります。
きっと私もマザコンなのでしょうね。
2代目社長
稲盛さんが主催する盛和塾には2代目3代目社長が多くいます。
その社長たちに、「経営とはなんであるかを教える」のが盛和塾と稲盛さんは言われます。
先日小説を読んでいると2代目社長のことが書かれていました。
「2代目が社長になると、会社はエネルギーなしに勝手に動き続ける自動機械のように思っている。
経営はそんな甘いものじゃない。
誰かが魂のエネルギーを注ぎ続けない限り、その機能はやがて必ず停止する」
誰が会社を引き継いでも創業者が作り上げた会社のシステムは動き続けます。
番頭さんみたいな人が仕切ってくれるので、誰が社長になっても暫くは経営に大きな変化はありません。
その為、社長は楽なものと錯覚してしまいます。
「人脈を増やすのも社長の仕事だ」と言って青年会議所やロータリークラブに入り、ゴルフにも精を出します。
その内に会社はジリ貧で衰退していく。
そうすると今度はコンサルトに相談し、頼ってしまいます。
「何としても社員を守り、会社を成長させるのだ」との強い思いがなければ社長になる資格はありません。
社長は利己を捨て、真剣に取り組んでこそ会社は成り立つ。
やはり社長の魂のエネルギーを注ぎ込む情熱がなければ会社は淘汰されます。
甘え上手
部下と上司。若者と年配者。
そのような「上下関係」はいろいろな場面であります。
最近フッと思うことがあります。
「甘え上手」と「甘え下手」と言う言葉です。
「甘え上手」と言うと「手練手管を使って落とし込む」とか「ゴマスリ」の悪いイメージがあります。
でも、私はその人に可愛がってもらおうとか、教えを請おうとする姿勢は大事だと思います。
目的が上の者を騙す行為でなければ、「甘える」ことはいいと思っています。
それより「甘え下手」の人の方が問題です。
「甘える」ためには本当の自分を晒け出す行為が必要で、勇気がいることです。
本当の自分を見られたくないとか「いい格好」でいたいと思うと甘えられません。
思い切って飛び込んで、教えを請おうとしない。
そして「甘え上手な人」をゴマスリだと言ってしまう。
「甘え下手」のもう1つのパターンは「控えることを知らない人」です。
「甘える」という行為と「土足で相手の心に入り込む」のとは違います。
これをわきまえないと、嫌われてしまいます。
私は過去を振り返ると「甘え上手」だったと思います。
新入社員で銀行に入った時から、現在に至るまで、多くの上司・先輩に恵まれ、助けていただきました。
引き上げていただきました。
現在の私があるのはそのような人たちのおかげです。
その感謝は今、「恩送り」でお返ししようと思っています。
若い人に言いたいです。
遠慮なく甘えましょう!
プレオープン
私が住む琴似の街に新規オープンの飲食店が増えています。
ステーキの店が3軒、立ち喰い寿司の店が1軒、蕎麦屋が1軒、イタリアンが1軒。
先日、オープン前の立ち喰い寿司、立ち喰いステーキの店の前を通ると、テレビ局のカメラが入っていました。
翌日の新聞にはチラシが入っており、オープンから1週間ほど半額程度の料金で提供とありました。
そして今月22日に大々的オープンをしました。
オープン当日は開店前から行列が出来ていました。
オープンの翌日、13時頃偶然その店の前を通ると、店主らしき人が慌てて暖簾を下ろし、閉店の看板を出していました。
13時はまだ営業時間中です。
よく分かりませんが、何かトラブルが発生したようです。
飲食店がオープンする時、往々にして前宣伝や特別割引などをして、お客様を集めようとします。
しかし、オープン当初は店は、料理提供、サービス、会計など、まだ慣れておらず、不慣れな状態の場合がほとんどです。
そんな時、多くのお客様が殺到すると、クレームの山を築きます。
「こんな店2度と来るか!」と思わせてお客様を帰らせてしまいます。
料金割引や、宣伝してお金をかけても、結果的にはクレーム客を作っているのです。
対策としては「こっそりオープンする」ことです。
本格オープンする前に、親しい人達向けのプレオープンをして、自分たちの仕事の流れを確認し、不手際のところを指摘していただきます。
その時のお客様は仲間内ですから協力的です。
料理提供や、サービスの流れが修正出来てから、グランドオープンをします。
その時こそ大々的宣伝して、お客様が沢山来ていただいても大丈夫です。
クレームは格段に少なくなります。
近い内に、先ほど書きましたオープンした各店に行ってみようと思います。
どんな美味しいものが食べれるか、楽しみです。
横ライン
昨夜ある社長の話を聞いていると「クチコミは横ラインで広がる」と言っていました。
縦ラインではないのです。
クチコミは仲間同士で広まります。
仲間同士は横ラインです。
コミックは同好の士で広がります。
金持ち同士も横ラインです。
商品を売る時、クチコミ利用は大切です。
方法はいろいろあるでしょうが、どのような層に広まって欲しいのか。
ターゲットが明確でないと効果が薄れます。
女性がターゲットと言っても、年齢・年収・趣味によって購買意欲が違ってきます。
どの横のラインを選定するのか。
これが大切なところです。
公私混同
今日は「公私混同」について書きます。
「公私混同」の意味は「公のことと私的のことを混同する」ことです。
会社の物やお金を勝手に私することは禁じられています。
それが発覚すると懲戒ものです。
「公私混同」というとそれだけのことに思われがちです。
しかし逆のことも同様です。
例えば、会社の経費とするところを自分のお金で処理してしまうことも含まれます。
営業で使った電車代や飲食代を経費として処理するところを面倒だからといって自分のお金で済ましてしまう。
そうすると頭の中に「あの時の経費は自腹で支払いをしていた」と常に思っています。
ある日友人と食事した時、「この間、経費を自腹で支払ったから、この食事代は接待費として経費計上しよう」と思ってしまいます。
結果、私的費用なのに経費として請求します。
公私混同して、お金に対して感覚がルーズになっているのです。
社長は社員が公私混同をしないよいうに徹底しなければなりません。
しかし一方、社長自身も公私混同しないように努めなければなりません。
自分のお金を出資して会社の資本金としていると思うと、会社が自分のもののように勘違いしてしまがちです。
そのため、時として社員を私的な用事に使用したり、友人と遊んだお金を接待交際費として計上したりします。
これも公私混同です。
トップのしていることは常に社員に見られています。
社長は心しなければなりません。
レストラン開業擬似体験講座
「本気で会社創り」という講座を先週から始め、昨夜は2回目でした。
「ちえりあ」という札幌市生涯学習センター内にある「空きレストラン」が教室です。
講座では、この「空きレストラン」を借り受けて開業すると設定していました。
面積227㎡、68席のレストランを教室に開業擬似体験をしてもらいます。
希望により、1人で体験したい人、グループで体験したい人に分けました。
それぞれで会社を作り、作業をしてもらいます。
グループで体験する人達は社長やそれぞれの役割を決めてもらいました。
レストランを開業するにはまず「業種」を決め、「業態」を決めていきます。
そしてレストランを開業する上で重要なのは「コンセプト」です。
これが決まらなければ「業態」も決まらず、「事業計画書」もできません。
そのためにその資料として、このレストランの近隣調査表、地域調査表、競合店調査表を作り、実際に調査してもらい、料理コンセプトを作ります。
それぞれの調査は担当者別に分け、次回講座日までに作り上げてもらうことにしました。
受講者の皆さんは週末の休日に調査してくれるでしょう。
次回はそれぞれの調査結果を踏まえ、社長を中心にレストランの「コンセプト設計図」を作り上げる予定です。
最終日には、実施した調査の具体的データーを基に事業計画書を作成し、発表してもらいます。
その時には日本政策金融公庫の創業支援センターの所長さんにも同席していただく予定です。
講座参加者には、この一連の作業を通して、開業実務を学んでいただきます。
この講座が終わった時、受講者の皆さんに開業の自信が少しでも芽生えれば嬉しいです。
モノマネ経営
セブン&アイ・ホールディング会長の鈴木さんがある雑誌に「モノマネ経営」について書いていました。
それを紹介します。
新しいニーズはどこにあるか。
セブン&アイはアイディアの仮説を立て、挑戦し、結果を検証します。
儲かる仕組みは、仮説と検証を積み重ねる中で作られていきます。
仮説検証にはリスクが伴います。
しかし、変化の激しい時代こそ今まで通りのことをし続けることの方がリスクが大きくなります。
また、どこかの会社が成功したことをマネする会社も多くあります。
マネ経営をする方が楽のように思えますが、モノマネは相手の動きが気になって、進む道が制約され、差別化できないまま、やがて単純な価格競争に巻き込まれていきます。
一方モノマネしない経営はいかに新しいものを生み出せるかが勝負で、常に挑戦を求められ大変そうに見えます。
しかし、全方向に広角度で自由に考えられるので、むしろ楽であるという発想に切り替えるべきです。
以上のようなことが書かれていました。
当社にとっても耳の痛い話です。
尊敬される
昨晩、若い人たちとお酒を飲みました。
旨い酒と料理を出す店で、大いに盛り上がりました。
その中の1人のお話です。
彼は長く勤めていた会社を辞めたそうです。
辞めた理由として、社長の考えについていけなかったと言います。
その社長は一代でチェーンの飲食店を作り上げた人です。
いわゆる遣り手です。
しかし、彼がどうしても我慢が出来なかったことの1つが、社長の「誤魔化す」という行為でした。
社長は払うべき税金を減らすために、業務に関係しないモノでも、何でもかんでもでも領収書を集めてくるように指示するそうです。
社長はその領収書を経費として計上します。
そのような「誤魔化す」行為が仕事の色々な面で見られたようです。
ワンマンで、会社を私物化するのは、創業者で成功している遣り手社長に多いものです。
彼としては社長のそのような「考え方」や「行為」について行けず、精神的に参ったようです。
円形脱毛症になったと言います。
今、彼は会社を辞めて新しい生き方を探しています。
彼が今後再就職する時はきっと、その会社の社長が尊敬できる人か、自分と善悪の価値基準が一致する人か。
それを見極めていくことでしょう。
社長はお客様から、そして社員から尊敬される人でなければならない。
改めて思います。
バスの運転手
先日、出張の後泊の為に、羽田空港近くのホテルに宿泊しました。
そのホテルは羽田空港までバスで送迎をしてくれます。
朝、ホテルから空港までバスで送ってもらいました。
その時の運転手さんのことです。
歳は私より上で70歳くらいでしょうか。
まずは、その運転手さんの接客態度やその口上に感心しました。
バスへの荷物の運び込み、出発前の挨拶、運行中のアナウンス。
全て、紋切り的で、マニュアル通りにしているのです。
それでもそれがものすごく丁寧で、一生懸命なのです。
マニュアル通りの接客は無味乾燥で、あまりいい接客とは言われません。
でもその運転手さんのその姿に感動してしまいました。
歳を取ると変に意固地になったり、分かった振りをしたりするものです。
若い人には少しぞんざいな態度をとったりします。
それがその運転手さんにはありません。
まるで学校出たての新入社員のように行動しています。
この運転手さんも新人なのかもしれません。
それでも、歳を取っても、真面目で、仕事に真摯になり、懸命に勤めている。
暗記した口上を懸命に話している姿には、つい「頑張れ!」と言いたくなるくらいです。
そんな運転手さんの態度・行動は私の見本です。
素直な心、真面目さ、仕事への姿勢。
学びたいものです。
ただ、私より年配の人に重たいスーツケースを運び込んでもらうことには、少し申し訳ない気持ちになりました。
鮭料理教室
先日の土曜日、鮭料理教室が開かれました。
久保さんの漁師番屋を教室に、イクラのしょうゆ漬けを作り、鮭をさばき切り身を作り、そして白子の燻製作り。
その後はいつものように飲み会。
佐々木さんが持ち込んだ「日輪田、山廃、ひやおろし」の日本酒。
これが旨かった。
肴の白子の燻製もまた旨い。
鮭の白子の燻製を初めて食べた人も多かったようです。
空は快晴、海は凪。
気温も20度程度と、海辺の飲み会にはとてもいい天気。
午前の10時から始まり、家に帰り着いたのは18時でした。
さばいた鮭に、イクラ。
結構な重さで、持ち帰るのが大変。
でもとても楽しい「勉強会」でした。
今朝妻から言われました。
「これからしばらく鮭料理が続きますよ」
いいですよ!
今晩は石狩鍋のようです。
うまい日本酒買っていかなければ・・・
日本のギャンブル
今月は飛行機に乗ることが多く、乗る時はJALがほとんどです。
飛行機の座席には機内誌があり、なんとなく読んでいると、作家の浅田次郎氏のエッセイがありました。
読まれた方も多い方思いますが、それが興味深かったので紹介します。
浅田氏は無類のギャンブル好きで、各国のカジノなどにも出かけていきます。
その浅田氏がエッセイの中で日本のギャンブル事情を説明しています。
日本のギャンブルのトップはやはり競馬。
日本中央競馬会の年間売上は2兆5千億円。
競艇は9千5百億円、競輪6千億円、地方競馬3千5百億円、オートレース7百億円。
合計で4兆4千7百億円になります。
それに宝くじ9千億円を加えると5兆3千7百億円です。
また、それにパチンコやパチスロを入れると日本のギャンブル年間売上は20兆円になるそうです。
日本各地でカジノ作りが言われていますが、このエッセイの中で浅田氏は反対しています。
海外のカジノまで出かける、ギャンブル好きの浅田氏が反対しています。
既に多くのギャンブル施設が日本に存在しています。
これ以上のギャンブルは必要ないと言うのです。
私も大賛成です。
それにしても、日本の年間税収が50兆円、国債発行が同じ額があると言われる中、ギャンブルに年間20兆円も費やす日本の国民は裕福なのでしょうか。
色々考えてしまいます。
「ウルトラマン」と「ピカソ」
以前にある経営者から聞いた話です。
聞いた話ですから、どこまで正確にお伝えでいるかわかりませんが、それを紹介します。
星野リゾートの星野社長が講演で話したことです。
星野リゾートは軽井沢にあった「星野温泉旅館」を引き継いだ2代目の星野佳路社長が、日本各地に旅館やリゾート施設、結婚式場を展開している会社です。
それらの施設の中にはかって営業不振に陥ったモノも多く、それを独自の企画力を持って立て直してきました。
その星野社長が講演で話したのは、施設を立て直したり、新規に造る時、必要な人材のことです。
必要な人材は「ウルトラマン」と「ピカソ」。
「ウルトラマン」は物凄い力を発揮し、新規に開業・開発し施設を造り上げます。
しかし「ウルトラマン」は3分間しか力を発揮できません。
そのあと引き継ぐのは「ピカソ」です。
「ピカソ」は独創的発想で面白い仕組みと施設を考え出します。
人は適材適所と言われます。
新規事業に燃える人でもそのあとの運営は上手くないことが多いです。
その力を発揮するのは立ち上げの短期間しかありません。
また、いいアイディアを発揮する人でも、事業を立ち上げる情熱はあまりないものです。
しかし、その人たちを絶妙に組み合わせをして、画期的結果がもたらせられることが多いのです。
そして、人材を見つけ出し、適所につけるのは社長の見る眼の力です。
私の過去の経験からも思い当たることです。
新規に何かを始める時、最初に「ウルトラマン」。
次に「ピカソ」という順番を考えておくと、新規事業も上手くいくかと思います。
経営者が経営者を叱る
「経営者が経営者を叱る」
一般的に、会社の経営はそれぞれ独立しており、経営者は自分の会社を責任持って経営するものです。
他の人からとやかく言われる筋合いはありません。
でも盛和塾の中では「経営者が経営者を叱る」ことがよくあります。
先日ハワイでの盛和塾例会の時もその話が出ていました。
ハワイの盛和塾生の要望で、日本から何人もの盛和塾の経営者を招待し、指導してもらっているのです。
その時はあからさまに本音で話しているようです。
指導の基本内容は稲盛さんの教えです。
経営者である社長は会社の中では誰も叱ってくれません。
せいぜいコンサルタントから指導は受けるでしょうが、叱ってはくれません。
叱る方も叱られる方も、「経営を良くして上げよう」という利他の心と、素直に「なんとしても良くなりたい」とい気持ちがあってこそ出来るものです。
また「経営者が経営者を叱る」という行為は両者に信頼関係があって成り立つものです。
盛和塾の経営者同士は「ソウルメイト」と言われるのはそのようなことからでしょうか。
ハワイ例会
今日は盛和塾ハワイ例会の2日目です。
先ほど午前中の勉強会で終了。
昼食は弁当です。
手渡しされたその弁当、その量に驚きです。
ゆうに3食分あります。
今日の夕方に「お別れ会」という懇親会があり、明日ハワイを発つ予定です。
今回、わざわざハワイま時間とお金とを掛け、「羨ましいですね〜」という言葉を背に受け参加しましたが、やはり参加して良かったです。
滅多に聞けないアメリカ本土、ハワイ経営者の経営の話が聞けたのは大変な収穫です。
塾生はシカゴ、ニューヨーク、シリコンバレー、ロサンジェルスからも参加しています。
発表された経営者は中小企業が多く、苦労して経営していることがよくわかります。
その中で皆さんは稲盛さんのフィロソフィの教えを経営に取り込もうと努力しています。
英語しか話さない経営者もたくさんいました。
「アメリカ人にも稲盛フィロソフィが分かるのかな?」という疑問を持ったのですが、それは杞憂でした。
「素直」とか、「真面目」「正しいことをする」などは万国共通です。
逆に合理的な考えを持つアメリカ人にとっては新鮮に映るようです。
ただハワイの日本人経営者に聞くと、「誰にも負けない努力をする」となると、自分の時間を犠牲にしてまで仕事をするということに抵抗感を持っている人もやはりいるそうです。
昨日の懇親会の時、私の隣に座ったハワイの経営者とお話していると意気投合し、私の知人の日本の経営者とを引き合わせる約束をしました。
そのハワイの経営者は日本の経営者とのつながりが欲しく、また日本の経営者も同じ気持ちの人がいました。
ともにIT関連のお仕事をしているので、互いにいい出会いになればと思っています。
私は明日帰ります。
家族の中で金の話をするな!
家族の中で金の話をするな!」
これは私が子供頃、父が怒鳴って叱った時の言葉です。
私が母から家の手伝を言われた時、「幾らもらえるの?」など言ったらテキメンです。
正月のお年玉の金額で文句も許されません。
兄弟の間でお金の貸借りも禁じられました。
今になって「いい教えだった」と思っています。
おかげで兄弟姉妹間でお金のトラブルはありません。
それは同じように私の子供たちにも伝えていることです。
家族の中で、「得した」とか「損した」とかの思いがあると、その家族は決してうまくきません。
「良いこと」「悪いこと」が価値基準でなければなりません。
新聞を見るにつけ家族間の争いの記事が多いように思います。
多くが損得の感情がこじれた結果でしょう。
「家族の中で金の話をするな!」という言葉。
今度、改めて子供達に伝えたいと思っています。
相続税
今日は相続税の話をします。
相続税は今年の1月より課税対象者の拡大や税率の引き上げが行われました。
これにより相続税の対象者が拡大し、税収も増えます。
相続税に対しては「親の財産をもらうのだから税金を払っても当たり前だ」と思う人も多いでしょう。
しかし、この相続税を支払うために会社を閉鎖せざるを得ないという中小企業の経営者も多いのです。
日本の企業の95%以上割合を占める中小企業の経営者はそれほど高くない報酬で働いています。
年収1000万円ももらえればいい方でしょう。
その上、個人保証までして銀行から借り入れしています。
社長が頑張り、会社の業績が良くなると会社の株の評価額が高くなります。
真面目な社長は、自分の財産を作ることより、生活を質素にしながら会社のことばかり考えて頑張ります。
しかし社長が万が一亡くなると相続税が発生します。
社長の財産は会社の株がほとんどということもあります。
先日の日経新聞の「税金考」という特集記事に、ある中小企業の時価評価額が額面の500倍になっていたというのが紹介されていました。
1000万円の資本金で、株を全て社長が持っていれば50億円になります。
100倍でも1億円です。
それに対して相続税が計算されます。
しかし中小企業の株は上場企業と違って、ほとんど売買されません。
時価評価が高くても売れない財産。
相続する子供たちは支払えず、もしかすると会社閉鎖ということになります。
日本には一生懸命頑張っている中小企業の社長が数多くいます。
しかし一生懸命頑張った結果が会社閉鎖となるのはやり切れません。
「相続税が発生する人は金持ちだから」と単純な考えにには疑問を感じます。
リスクを負って起業し、頑張って会社を成長させ、社員の生活も向上させている中小企業経営者。
もっと報われていいと思います。
旅館「澤の屋」
昨日の日経新聞に旅館「澤の屋」の澤さんのことが大きく掲載されていました。
懐かしく読みました。
澤さんは東京谷中にある昔ながらの日本旅館「澤の屋」のご主人です。
私が東京でホテルの支配人をしていた時、澤さんにはお世話になりました。
当時私のホテルの宿泊稼働率が非常に悪く30%台でした。
そこで海外からの旅行客を獲得したいと思い、教えを請いに何度かお伺いしました。
澤さんはご自分も苦労した経験があり、惜しみなく私に多くのことを教えていただきました。
初めての外国旅行客からの予約の受け方、キャンセル防止の方法など実際役に立つことばかり。
今、中国人を中心に多くの外国人が来日するようになっています。
以前は外国人の旅行客は少なく、また欧米人がほとんどでした。
宿泊するのはシティホテルがほとんどです。
その中で「澤の屋」さんは宿泊稼働率90%以上で、宿泊客はほとんどが外国人です。
「澤の屋」さんは昔ながらのビジネス旅館で、和室が6畳、8畳間。
部屋には風呂もトイレもありません。
当時、日本のビジネスマンはビジネス旅館を敬遠して、ビジネスホテルに泊まるようになっていました。
そのような流れの中で澤さんは生き残りをかけ、お客様のターゲットを外国人に絞ったのです。
日本人から見れば、バストイレもない畳の部屋に外国人が泊まるのかという疑問がありましたが、外国からの旅行者は好んでこの旅館に泊まりました。
そして口コミでどんどんお客が増えていきました。
また同じように昔ながらのビジネス旅館で集客に苦しんでいた仲間と「ジャパニーズイングループ」というも作りました。
そして情報の共有を図ったのです。
なぜ外国人旅行者に人気があるかといえば、彼らは日本の日常の生活体験をしたいのです。
自国では家族1人1人に部屋があり、寝る時も1人。
それがこの「澤の屋」に泊まると、親子が川の字になって布団で寝ます。
ビジネスで来日すると帝国ホテルに泊まる人でも、プライベートでは「澤の屋」に泊まります。
それが彼らにとって新鮮であり、日本の生活が体験できると言います。
澤の屋」の近くの食堂に依頼し、外国の旅行客には日本らしい料理の提供を、郵便局にはわかりやすい案内をお願いしたり、地域ぐるみで「おもてなし」をしていました。
草の根的「おもてなし」です。
澤さんは年に1度、海外に奥さんと旅行に行くと言っていました。
「澤の屋」に宿泊した外国のお客様から、是非来て欲しいとの招待を受けるそうです。
新聞の記事では、澤さんは「観光は平和のパスポート」と言っています。
澤さんのお仕事そのものが外国との架け橋になっているように思います。
起業志願者
1ヶ月程前に、若い男性が私が運営するレンタルオフィスを借りたいと来社されました。
嬉しいお話です。
オフィスを見ていただいた後、お話を聞きました。
彼は借りたいという意向は強いのですが、仕事は何かを聞きますと、「これから起業するので何をすればいいかこれから考えます。」と言います。
起業調査するためにオフィスを借りるというのです。
そこで余計なお節介かもしれませんが、「何で起業するかを考えるのなら、本を読み、調査に出かけ、人にも会います。
オフィスを借りてもそこにいる時間などありませんよ。
自宅で十分です。
無駄なお金は使わないほうがいいです。」と話しました。
いろいろ話をして、彼も納得したようです。
せっかくのお客様を逃してしまいました。
起業を考える時、「何で起業するか」
それを知る方法の一つに自分の棚卸があります。
過去の自分の実績を思い出し、好きなこと、熱中したこと、経験したことなどを知るのです。
具体的にはマトリックス図を作ります
横軸に過去経験したアルバイトや勤めた会社の名前を書きます。
縦軸には営業、総務、企画、経理、受付、サービスなどの仕事内容、免許取得などを書き、縦と横の交差するマスに経験した仕事を書きます。
学生さんの場合は横軸に小学校、中学校、高校、大学を書きます。
縦軸には好きな学科、嫌いな学科、所属クラブ、好きな友達、嫌いな友達、ボランティア活動などを書き、同じように縦横交差するマスに具体的活動を書きます。
そのような作業をすることで、忘れていて、気付かなかった自分の才能や仕事作業の喜びを再認識できます。
それによって自分を知ることができます。
自分の「好きなこと」「考え」そして「経験」がわかれば、自分は何で起業してらいいのか知る助けになるはずです。
私も実際にこの作業をしましたし、起業講座でも話していることです。
先ほどの彼は、先日私が主宰した身丈会の勉強会に参加しました。
起業応援したいと思います。
人は何のために生きるのか
昨夜、勉強会があり、稲盛和夫さんのDVDを見ました。
その題名は「人は何のために生きるのか」
このDVDは2002年から各地で開かれた「市民フォーラム」で稲盛さんが語り続けてきた内容です。
2015年の台湾での開催を最後に、57回続けてきた市民フォーラムは終了しています。
今まで10万人が参加したそうです。
人生は「運命」という縦糸と「因果の法則」という横糸で織り込まれた布のようなモノ。
良きことを考え良きことを行えば運命も変わりその人の人生も好転します。
そのことを宇宙が素粒子から始まり拡大している現象からも説明しています。
宇宙は良き方向に進む風を起こしている。
他力という風を受けることができるのです。
そして最後に、生きるということは心を磨く、魂を磨くこと。
生まれてきた無垢な魂を少しでもより良いモノにしていく。
それが生きることだと言います
1時間20分ほどのDVDでしたが、勉強会に参加された20名の人は静かに聴き入っていました。
昔の親
先日私より一回りほど若い経営者と話した時、2人同感したことがありました。
以前にも書きましたが、私は若い頃1人でアメリカに行きました。
父からの条件は旅行業社を使わず全て自分の手で手配・予約し旅することでした。
今のようにインターネットも携帯もない時代、限られた情報の中での旅行。
先ほどの若い経営者も同じような経緯でアメリカに行ったそうです。
そんな話をしている時、当時の親の気持ちを推測ってみました。
知り合いもツテもないアメリカに子供を1人旅たたせること。
ものすごい不安を持っていたのではないでしょうか。
自分に置き換えてみて、同じようなことを子供出来るであろうか?
心配で心配で、子供にそのようなことをさせることは出来ないのではないでしょうか。
それでも私達の親は子供を送り出しました。
その時の親の心の内を考えてみました。
親は子供が心身ともに成長することを期待します。
同時に、子供に降りかかる危険から守ろうとします。
子供に危険なことをさせたくないという思いは、子供に万が一のことがあった時、その子供がかわいそうという気持ちがあります。
それと同時に、親として心配する自分の姿に堪えられないという思いが強いのではないでしょうか。
「心配する自分」になりたくないのです。
子供のことより、自分への気持ちが先に立っているのです。
手元に置いて危険なことから避ける。
その方が安心だから。
でもそうすると、子供は親離れできず、親も子離れできない関係になってしまいます。
本当に子供の成長を願うのであれば、心配する自分の気持ちを押し殺さなければなりません。
気持ちを押し殺して、子供に成長の機会を与える。
そんなことが私達の親は出来ていたのです。
その点において2人同感しました。
浅草
昨日帰札しました。
上京した時は必ず浅草寺に参拝に行くので、16日はその近くのホテルに宿泊。
そのホテルに行く途中、ホッピー通りというところがあり、道の両脇にテーブルや椅子を出している飲み屋が並んでいます。
呑兵衛の私は、ホテルにチェックインした後、早速行きました。
夕食を食べた後なのでお腹がきついのですが、ホッピーやビール、それに牛の煮込みを注文。
私の学生時代、一番安い酒の肴がこの牛の煮込みでした。
それは臭く、冷えると油が浮いてきます。
今回は40年ぶりの牛モツの煮込みです。
昔と比べて今の牛モツの煮込みの美味しいこと。
ただ、決して安くはなく、小さな器に入っていて600円。
牛丼より高いです。
それでも浅草で一人飲む酒は美味かった。
浅草には私の知らない独特の雰囲気があります。
これから上京した時は浅草に泊まろうかと、密かに思っています。
武士の娘
「武士の娘」という本をご存知でしょうか。
昨日この本を読み終えました。
この本は明治の時に杉本鉞子(えつこ)という女性が英語で書き、アメリカで出版されました。
出版されるとアメリカ人に感銘を与えたと言われています。
アメリカの有名な詩人ホイットマンにも賞賛されました。
ヘミングウェイの「日はまた昇る」という本にも伍したと言われています。
その本はベストセラーとなり、イギリスやフランス等7か国でも出版されました。
日本人が英語で書いた本といえば、内村鑑三が書いた「代表的日本人」や、新渡戸稲造の「武士道」が有名です。
「武士の娘」は大正時代に日本でも翻訳され出版されましたが、今の日本ではあまり知られていませんでした。
あの司馬遼太郎でさえ「峠」という本の取材中にこの本を知り、その内容に感動したと言われています。
私はたまたま本屋で、同じ題名で、この本の内容を解説している、内田義雄氏の本を見つけ読みました。
ですから正確にはまだ杉本鉞子が書いた「武士の娘」は読んでいません。
内田義雄氏は「武士の娘」がどのように書かれたのか、その時代背景や杉本鉞子の生い立ち、そしてなぜアメリカに嫁いだのか、そしてその一生はどうであったかが書かれています。
杉本鉞子の父は司馬遼太郎が書いた歴史小説「峠」の主人公河井継之助と対立した、同じく越後長岡藩の家老稲垣平助の娘でした。
その河井継之助と稲垣平助が対立した経緯も大変興味深いものがあります。
内田氏は「武士の娘」には新渡戸稲造が書いた武士道と同じように「恥を知る」「廉恥を重んずる」という武士の娘としての思いが書かれていると書しています。
それでいて、アメリカ人も長く愛され、終戦後多くのアメリカ人が杉本鉞子の家を訪ねたと言われています。
杉本鉞子が書いた「武士の娘」はちくま文庫から出版されています。
私も近いうちのこの「本家本」を読む予定です。
若さの象徴
昨日、フッと若い時の自分と今の自分を比較してみました。
若い頃に比べ、人間として少しは成長したかとは思います。
しかし失ったものがありました。
それは「無鉄砲さ」であり、「怖いもの知らず」。
それらは「無計画」であり、「行き当たりばったり」として、今の私は避けてしまうところです。
そのような私を見て、父は「濡れた丸木橋を高下駄を履いて渡るようで、危なっかしい」言っていました。
丸木橋を渡るのは慎重にしなければならないのに、橋が雨で濡れている上に、足元の不安定な高下駄を履いて橋を渡るのはこの上なく危険だという事です。
「段取り八分」とか、「読みを深くする」など事前に計画を立てて進むのとは全く違います。
私が学生の時、諸処の事情がありアメリカに1人で旅する事になりました。
40年以上前の事です。
行く時、旅行会社を使わず全て自分で手配することになっていました。
パスポート、ビザ、の取得、航空券、それにアメリカのグレイハンドバスのフリーパスを購入して出発。
持ち物は下着とTシャツ、ズボン、それに英語辞書を詰めた小さなボストンバックだけ。
取り敢えずの滞在先としてオクラホマにあるオクラホマ大学の学生寮だけは確保していました。
飛行機はハワイで給油してアメリカのロサンジェルスには夜遅く到着。
私はその夜泊まるホテルは決めていませんでした。
それからの旅は毎日その日暮らし。
旅行ガイドブックと地図を見ながら、「明日はこの町に行こう」と決め、ハスを乗り継いでアメリカを一周しました。
それが数カ月続きました。
英語はほどんどしゃべれません。
知って使える言葉は「How much?」と「Were can I get」の2つだけ。
今の自分にはそのような無謀と思える旅行はできません。
でも当時は不思議にほとんど不安に思ったことはありませんでした。
「なんとかなる」と思っていました。
また「知らない人に会える」という思いの方が強かったようです。
年をとって失ってしまったその「なんとかなる」という「気楽さ」と「図太さ」。
懐かしいです。
「なんとかなる」という「気楽さ」と「図太さ」は若さの象徴のように思います。
2つの記事
今朝の日経新聞の記事からです。
1面に「春秋」というコラムがあり、その記事の上には「新産業創世記」という特集記事が掲載されています。
その2つの記事が対比する内容になっていて面白いのです。
「春秋」では今報道されている司法試験不正問題が取り上げられています。
超難関と言われる司法試験を受け、合格すると法曹者になれます。
弁護士や検事なれるのです。
そのため不正してでもその資格が欲しいという思いにとらわれてしまったようです。
しかし今は司法試験に合格したからといって、安定した生活が送れるという状況にはありません。
今回の事件は合格さえできれば、免許さえあれば自分の生活がバラ色だという思いにとらわれて生まれた事件です。
一方「新産業創世記」には安定も知名度も興味なく、自分の可能性を追求し続ける人達が紹介されています。
紹介されている1人、25歳の松元氏は、ロボット市場を開拓してきたファナックという会社がその彼の能力に惚れ込んでいます。
松元氏は高校時代にコンピューターのプログラミングの国際大会で上位入賞をし、東大大学院を出たエリートですが大企業を選ばず社員数30人ほどのPFNという会社で活躍しています。
松元氏に惚れ込んだファナックはPFNと研究協力を結びました。
この「新産業創世記」ではその他にも、自分の力を磨ける場所を求めて活躍している人達が紹介されています。
現代は免許や資格などで簡単にバラ色の生活が出来る時代ではなくなってきています。
免許や資格を取るための勉強も大事でしょうが、自分の好きなことを見つけ、それを磨く事がいかに大事か。
自慢話
最近、若い人と話している時、つい自慢話をしている自分がいます。
その時は得意げに話しているのですが、後から振り返ると恥ずかしい思いになります。
きっとつい若い人と対を張っているつもりになっているのかもしれません。
人に何かを伝えたり、教えたりする時、時としてこの自慢話になりがちです。
話している相手に重点を置いた話しているのか、自分に重点を置いた話しているのか。
それによって実体験から学んだ教えとなるか、単なる自慢話となるか。
ここが分かれ目でしょう。
年をとるとツイ自慢話をしがちになります。
十分注意していきます。
勉強会
昨夜勉強会がありました。
そこで改めて学んだことです。
新規事業を手掛ける時、大事な2つのこと。
1・自社は何が強いのかを知る。新規事業はその延長戦にある事業。
決して「飛び石」は打たない。
2・新規事業を手掛ける人材がいること。誰でもいいわけではない。
海外進出する時。
本社は本丸なので、それを守ることが第一。
海外に出て行くのは社長が先頭に立ちます。
また本丸を守るためNO2、NO3の人は連れて行きません。
連れて行くの者は本社からいなくなっても影響のない人。
海外でその人達の挑戦にもなるのです。
またその事業から撤退を決めることが出来るのはただ一人、それも社長の仕事。
そのほかに経営計画はトップダウンで決める。
社長に必要なのは推理力であり想像力です。
人は権威や権力では使えない。
信頼と尊敬。
これらは稲盛和夫さんの教えです。
5年以内に起業するぞ!
以前にまとめた資料を見ていると「男5年、女3キロ」という言葉が出てきました。
これは起業本などを出している本田健さんが言っている言葉です。
その意味するところは、「男は『5年以内に起業するぞ!』と言い、女は『あと3キロ痩せるぞ!』と言う。
ほとんどの場合達成されることはない。」と言っているのです。
女性の「あと3キロ痩せるぞ!」という言葉は別にして、男性が「5年以内に起業するぞ!」と言っても、やはり起業しないということはよく分かります。
起業をしたいと思っても、すごい起業をした人を見て、自分には能力がないと思ってしまうことが多いのです。
しかし、自分の身の丈に合った起業という方法はあるはずです。
常に意識していればそれを見つけることができる。
私はそう思います。
そのためには常に準備をし、意識していなければなりません。
チャンスは目の前を通り過ぎていきます。
コミニュケーション
会社内において大切なものの1つにコミュニケーションがあります。
それが上手くなされている会社の社員には「やる気」も生まれるし「達成感」も得ることができます。
ネットを見ていると、コミニュケーションを良くするために社員が「社長に望むこと」というのがありました。
1.透明性:全てに関して嘘がなく、正直な実態や情報が上司から開示されること。
2.公平性:全ては公平の原則で経営がなされるべき。
条件を公平にして差をつけるのは全て給与でいい。
3.指示:具体的な指示ばかりされては社員は考えることをやめてしまう。
「どうすべきと思う?」など社員に物事を考えさせながら動かす「質問的指示」が1番社員の力がつく。
4.具体性:「だいたい〜」とか「〜を努力する」など曖昧な言葉を排除して全て数値に置き換えてものを言う。
5.アメとムチ:褒め方と叱り方をしっかり身につけてほしい。
6.実行:1番の説得力のあるコミニュケーションは徹底した実行であることを知ってほしい。
社員がこのようなことを社長の求めることができる会社は間違いなく業績が伸びると思います。
子供の勉強
電車に乗っていると時々お年寄りに席を譲らない人がいます。
その時、自分の子供がそばにいたらどうでしょう。
子供は親を見ています。
親を見て素直に勉強しています。
親が席を譲らなかったり、食べた後のゴミをシートの隙間に押し込んだのを見みています。
そうでなく、笑顔を見せながらスッと席を譲る母親を見たら子供はどう思うでしょうか
自分もしようと思います。
お爺ちゃんやお婆ちゃんを大事にしている親を見ると、親孝行っていいものだなと子供は思います。
段差で困っている車椅子の人に手を差し伸べているのを見たら、今度私もしようと思います。
子供は親のそのような優しさを見て勉強します。
先日、交差点で信号が点滅している時に、母親が小さな子供の手を引いて走って渡っていました。
子供が真似て、そんなことをしたらどうなるでしょうか。
親は自分の言葉と行動に気をつけなければなりません。
私も今度は孫に見られます。
気をつけます。
人格
先日流れてきたある雑誌のメールの中にいいことが書かれていました。
「人格=性格+哲学」というものです。
性格は持って生まれてきた「先天的」なものです。
哲学は人生を歩む中で身につけて、学びそして経験して得た「後天的」なものです。
持って生まれた性格が哲学によって淘汰され人格が形成されていくと言うのです。
納得します。
さとり世代
新聞に「さとり世代」という言葉が載っていました。
その世代は淡白で高望みしなく、生活も仕事もコストパフォーマンス重視するそうです。
そのような思考をもって「さとり」と名付けるのは如何なものか。
本来「さとり」とは「心の迷いがとけて真理がわかること」です。
下手に「さとり」とう言葉をその若者たちに使うことで、その生き方が正しいという錯覚にさせてしまう危険性があるのではないでしょうか。
高望みせず質素に暮らしながらも、志は高く持って一所懸命に生きることをしなければ、生まれてきた意味がありません。
「高望みせず生活もほどほどでいい」という生き方が出来るのは、誰か懸命に頑張った成果、生まれた富で生活しているだけです。
そのような生活はいつまでも続くという保障はありません。
いつ今の日本の経済状態が激変するかわかりません。
今のような豊かな生活は出来なくなります。
その時、一所懸命に頑張っている人しか生き延びれません。
稲盛さん和夫さんがいつも言う「小善は大悪に似たり。大善は非情に似たり。」
私の祖母が言っていた「下見て暮らせ。上見て励め。」
どちらも今の時代に大事な言葉のように思います。
富良野
週末、富良野に行ってきました。
20代に行ってから40年ぶりになります。
富良野は倉本聰さんのテレビドラマの舞台になったところ。
倉本さんは日経新聞で今月1カ月間「私の履歴書」を連載され、その話のほとんどは富良野についての生活です。
それを読んで、私は急に富良野行きを思い立ち、妻と1泊旅行。
宿泊は新富良野プリンスホテルでした。
このホテルの敷地内には「北の国から」で舞台になった「ニングルテラス」、「優しい時間」で使われた珈琲店「森の時計」。
それに「風のガーデン」も中井貴一さんが主人公のドラマの舞台です。
「森の時計」でコーヒーを飲み、「ニングルテラス」では小さな店を1件1件まわり、買い物。
翌朝は「風のガーデン」をゆっくり歩きました。
「風のガーデン」の係員に「熊は出ますか?」と聞くと、「先日も出ました、でも大丈夫です。駆除しましたから。一昨日。」
駆除したのはいいけれど、それは「一昨日」という言葉に妻は少しビビりました。
この3箇所は倉本さんの「富良野三部作」と言われ、ドラマという「物語」があります。
人はたとえ架空のものであっても「物語」に惹かれます。
そこでは自分も「物語」の中の1人になった気がするのでしょうか。
私もニングルテラスにある「森のろうそく屋」でカラマツのろうそくを買いました。
カラマツの幹そっくりのろうそくで、火を灯すとカラマツの香りが漂います。
またこの店は「北の国から」のドラマの中で竹下景子さんが扮する雪子おばさんが働いていた店でもあります。
その店にあったのが、倉本さんの言葉「森は無口です。無口で口下手です。」
私もすっかり倉本ワールドにはまってしまいました。
会社のITメンター
色々なところで起業についての話をすることがあります。
そこに集まる人達は、もちろん起業に興味を持っています。
その人達に、「パソコンやタブレットを持っている人?」と聞くと2割程度の人だけが手を挙げます。
その内メール、Facebook、ブログをする人はもっと減ります。
起業する時、絶対条件がパソコンなどのIT機器操作です。
情報を集めるのも、自社を広めるのも、人脈を増やすのもパソコンが無ければなかなか出来ません。
パソコンなどのIT機器は道具です。
道具を使える人と使えない人とでは、その過程と結果に雲泥の差が出てきます。
今朝の日経新聞の「春秋」に面白い話が載っていました。
アクサ生命保険では社長ら3役員が20歳代の社員から、交流サイトなどのIT情報の知識を仕入れているそうです。
20歳代の社員が社長達の「ITメンター」としての相談役です。
上司が若い人を指導するというのはありますが、若い人が上司のIT相談に乗り、IT啓蒙活動をするという発想です。
この面白い発想によって、会社の上下関係に新しい風が流れてくるのではないでしょうか。
価値創造の方法
カレーハウスcoco壱番屋の浜島社長が「価値」について話した記事がありました。
浜島社長は『「価値」は「質」+「サービス」+「清潔さ」+「雰囲気」+「信頼」を「価格」で割ったモノという方式になる。』と言いっています。
そうすると、それを見てすぐに、「価値」を上げようとして分母である「価格」を下げるほうを選ぶ人が多いのです。
工夫しなく簡単だからです。
でもそうすると利益がない出血サービス競争に陥ります。
分母を見るのでなく、分子のほうを見て、それを検討するのです。
分母の「価格」を下げるのでなく、それ以外の方法で「価値」を上げる工夫をするのです。
「質」を高め、「サービス」を良くし、常に清潔に心がける。
心地よい「雰囲気」を作り出し、お客様の期待と「信頼」を維持する。
そのために何をするのか。
そこの視点が大切です。
今、お客様から頂戴している値段でお金をかけず「価値」を上げる。
まだまだ出来ることはないか。
常に考えるのです。
それが経営者の仕事です。
飲食店探検隊
週末の土曜日、末娘夫婦と夜に食事に行きました。
琴似で流行っているバルです。
その店は美味しいと評判の店です。
2時間、美味しい料理とワインを飲んでいましたが、いつの間にか店は満席。
カウンターまでびっしりです。
それほど大きい店ではないのですが、それにしてもすごい人気。
入店する時に、混み合う見込みなので2時間制限とさせて欲しいという依頼があり、2時間で退席。
店の外に出ると、隣にその店と同程度の大きさの和食の店がありましたが、閑散とした様子。
2つの店の違いは何でしょう。
今はバルが流行っているからなのでしょうか。
その後、以前に行ったことのあるバーテンダーのいるバーに連れて行きました。
落ち着いたシックな雰囲気のその店も閑散としていました。
帰るまでお客は私たち3人だけ。
まだ夜の8時過ぎのためなのかもしれませんが、せっかくいい店なのにもったいない。
琴似は飲食店も多く、夜は結構若い人たちが集まるようになっています。
それでも満席の店も閑散とした店もあります。
その違いは何でしょうか。
今度仲間と「飲食店探検隊」を作って飲み歩いていようかとも思います。
調べてみると面白いと思いますよ。
東京駅開業100周年記念Suica
2〜3日前に「東京駅開業100周年記念Suica」が届きました。
半年以上前に申し込み、代金も振り込みしてありました。
先ほどネットでJR東日本のHPで受付状況を見ると、申し込みは226.5万件499.1万枚あったそうです。
その内の1件2枚が私。
皆さんご存知のように、このSuicaは当初2014年12月20日に数量限定で発売する予定でした。
数量は15,000枚限定で1人3枚まで購入可能。
そころがあまりにも多くの人が殺到したため中止。
JR東日本の過少予測と対応の悪さでマスコミなどで非難されました。
その後再度希望者全員に販売するということになり、私もそれの応募しました。
札幌でも使えるSuicaなので、記念に買うことにしたのです。
このSuicaは1枚4000円です。
販売枚数は499.1万枚ので総売上は199億6千4百万円になります。
当初の販売予定は15000人×3枚=45000枚。
その売上は1億8千万円です。
それと比べれば約110倍の売上です。
今回の騒動でJR東日本は大きな利益を上げたのではないでしょうか。
災い転じて福となす。
いい見本例のように思います。
鞄メーカー
今、私が仕事で使って鞄は1年ほど前に買ったものです。
鞄は好きな方で、今までいろいろなものを買いました。
今、使っている鞄が仕事用としては最後かと思っていいものを買いました。
HERZ(ヘルツ)という鞄メーカーをご存知でしょうか。
私はここのソフトダレスバックを買いました。
厚い牛革と真鍮の金具だけで、内張りもないシンプルな鞄です。
それでいてデザインもいい。
全ては日本で手作りで作られています。
このメーカーの「私達がお作りするのは80%まで、残りの20%はお客様に使っていただく事によって仕上げられるのです」という信条が私の購入意欲をそそりました。
時々鞄にオイルを塗りながら使っているうちに、経年変化により色が濃くなってきました。
また少々の傷が味となっています。
日本には数多くの鞄メーカーがありますが、このHERZは自社の製品にこだわりを持つ「ファン作り」に長けていると思います。
ついつい私も、ソフトダレスバックの他に,リュックも買い,また娘婿へのプレゼントとして色違いのソフトダレスバックも買いました
一度HPを見られると参考になると思います。(http://www.herz-bag.jp/webshop/)
この会社は注文を受けてから製作するので、注文してから届くのに6週間ほどかかります。
宣伝ぽくなりましたが,このメーカーご紹介します。
やまびこ
今日は高校野球の準決勝の日です。
第1試合第2試合とも興味があります。
30年以上前に徳島の池田高校という強豪チームがありました。
春夏の大会で優勝しています。
その高校の打線は「やまびこ打線」と言われました。
高校が山間部にあり、打撃の音がこだましたということもありますが、次から次に打つ打者の快音が互いに木霊したようだからとも言われています。
打者同士、互いに刺激しあったのでしょうか。
この「こだます」ということについて考えてみます。
ある人の本に書かれていたことです。
人からの評価は、良いにつけ悪いにつけその通りになります。
まるで「こだましている」ように。
「あの人は優しい人だ」と自分が言われると「優しい人であろう」とします。
逆に「あの人は何をやってもダメな人だ」と言われると「どうせ何をやってもダメんだ」と思い、本当にダメになっていきます。
まるで「こだます」ようになっていきます。
つい子供に対しても、会社の部下に対しても、劣等感を与えるような言葉を発していないでしょうか。
私は振り返るとその轍を踏んできました。
嘘はつくことはありませんが、楽しくなる言葉、明るくなる言葉を常に口にしていくこと。
大切だと思います。
引き算
「もったいない」という言葉があります。
2004年にノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイさんが「もったいない」という言葉を使い、再認識されました。
一方、無駄のものを捨てるシンプルライフという生き方も注目されています。
「もったいない」はモノを捨てず溜め込むイメージがあります。
しかし本来その言葉は「物の価値を十分に生かしきれておらず無駄になっている」状態やそのような状態にしてしまう行為を、戒める意味で使用されることです。(Wikipedia)
物の価値を十分生かしきれば、それ以外の物は捨てることができます。
本質がわからないから溜め込むのでしょう。
日本には昔から「引き算」の考え方がありました。
利休の茶室は無駄な物を究極まで省き、タタミ2畳の「待庵」を作りました。
本質がわかれば無駄を削ぎ落とし、シンプルな生き方ができます。
経営についても言えます。
今、10月に開く起業講座のための資料を作っています。
いろいろ考えていくと、経営はシンプルなほど成功すると思うようになりました。
経営者は会社経営している内に、当初の目的と違う余計な物を足して行くことが多いものです。
その内に、何に向かって、どんな経営をしているのかわからなくなってしまいます。
例えば、蕎麦屋だった店が、いつの間にかうどんも出し、丼物も出す。
しまいに蕎麦屋だか食堂だかわからなくなります。
子供服店だった店が、お母さん向けの婦人服も置き、しまいには婦人用バックまで置いてしまう。
子供服は片隅に。
自社が求めている本質は何か。
そのコンセプトが明確でないと、結局溜め込む経営になります。
盆が終わり
お盆も終わり今日から出社。
お盆は親戚や家族が我が家に集まりました。
15日の土曜日は、宇都宮から帰ってきた妹家族5人、里帰りしていた長女家族。
それに近くに住む末娘夫婦、甥っ子。
総勢大人12人子供1人で大宴会をしました。
先日偶然にも手に入れたニッカの「竹鶴17年」2本を中心に、用意したビール・ワインを全て開けてしまいました。
楽しくて、おかげで昨日は二日酔い。
それでも久しぶりに大いに語り、飲み、食い明かしました。
盆が過ぎて、明日には妹家族、長女たちも帰りも帰ります。
ついで妻も長女について東京に行くとのこと。
明日からしばらく1人暮らし。
急に寂しくなりそうです。
たまにはそれもいいかなと思っています。
誕生日
今朝、いつものように起き、顔を洗い、自分の部屋に入り、座っている時のこと。
何気なく合掌していました。
その時フイに涙が流れて、自分でもびっくり。
今日8月12日は日航機が御巣鷹山に墜落して30年目になります。
ど同時に、私の誕生日でもあります。
その2つを思って出た涙だったのかもしれません。
私は誕生日は父母、特に母に感謝する日だと思っています。
以前に読んだ本に書かれていた言葉に影響を受けました。
台湾の総統だった蒋介石氏の言葉です。
「私は自分の誕生日には食事を一切しない。
私が生まれた時、母は産みの苦しみをしたはず。
それにより生まれた私は母に感謝するしかない。
だから誕生日には母の苦しみを少しでも知るために、1日食事を取らず、感謝して過ごす。」
それに倣って、やはり私も1日感謝して過ごそうと思っています。
食事制限するわけではありませんが・・・
置き薬
昨夜の勉強会で、「置き薬」会社の社長の話を聞きました。
置き薬は配置薬とも言われ、室町時代からある日本独特の販売方法です。
年配の人はよくご存知でしょう。
その仕組みは薬の販売員が家庭を訪問し、薬の入っている配置箱を置き、定期的に回って使った分の薬代をいただく。
「先用後利」という考え方です。
お互い信用があって成り立つ商売です。
日本だから成り立つ商売と言えましょう。
その置き薬の販売員は1人で約1000軒ほどのお得意先を持っています。
社長の話では、1軒あたりの薬の売上は1回1500円程度に過ぎません。
そのため、売上増を図るため健康食品や日常雑貨も一緒にセールスしているそうです。
確かに家庭の中まで入れる商売はメリットが高い。
我が家に定期的に来るクリーニング屋さんも、クリーニングの他に、米や加工食品などのチラシを置いていきます。
妻は定期的に米やレトルトカレーなどを買っているようです。
これも家庭に入り込んでいる仕事だからこそできる商売です。
漫画のサザエさんの中に出てくる三河屋さんのように、置き薬や、クリーニング、そしてダスキンなどの会社も「御用聞き商売」です。
「御用聞き商売」は高齢者家庭が増えるこれから必要になって来る商売でしょう。
知らないこと
イギリスの文豪サマセット・モームは晩年に「知らないことを認めることがこんなに簡単だとは、年をとって初めてわかった」と言ったそうです。
人は時として自分が知らないということ知られるのを恥じます。
そのような気持ちになる時があります。
それは自分に自信がないために起きると考えます。
人の話を聞いていると、自分が知らない言葉を耳にした時、「スミマセン。今の◯◯はどういう意味ですか?」と聞けるか、ということです。
話の腰を折ってはいけないと思う気持ちもありますが、「知らないというのを知られるのが嫌だ」という思いになっているのです。
知らないのに知ったふりをする。
やはり自分に自信がないからです。
私の父は人の話を聞いている時、「それはどういう意味?」としきりに聞いていました。
その時、私は「そんな言葉も知らないの?」少しバカにした気持ちを持ったものでした。
でも、知らないことを知らないから質問することは当たり前のことです。
知ったふりして、話の内容がわからず、そのままにしていると後で恥じをかくことになります。
「知らないことを知らない」と言えるのは素直な気持ちでなければ出来ません。
いい格好をしないこと。
私も年をとって分かる気がします。
商売の土俵
私が住む琴似の街にあった、ある大手居酒屋チェーン店が最近閉鎖になりました。
しかしその近くにある地元の居酒屋は繁盛しているようです。
大手チェーン店のような大量仕入で安い値段で飲食を提供するが、メニューは画一的。
それより個性的メニューを出す飲食店の方が今の消費者には受け入れられている。
そんな風に思います。
商売をしていれば競合することは当たり前。
どの業界でもあります。
そして同じ土俵で戦えば、資金や力のあるものが勝ちます。
しかし土俵を変えればそうでもありません。
いかようにもやれるはずです。
飲食関係で言えば、今は「バル」や「多国籍料理」の店が流行っているようです。
札幌狸小路の外れの方にある飲食店はそのような店が多く、毎夜若者たちで賑わっています。
土俵の区分けを「材料の違い」「時間」「価格」「技術力」「面白い」などで分けるだけで差別化ができます。
「材料の違い」で言えば「やさい家さくら」という店は野菜にこだわった料理を提供して繁盛しています。
「時間」で分ければ、昼の営業をやめ、夜から朝まで営業している定食屋が東京にあり、いつも混んでいると言われます。
「価格」で考えれば、仕入を工夫して驚くほどの安さで提供します。
折り紙付きの「技術力」があれば高い価格の料理を提供しても繁盛します。
「面白い」を考えれば「監獄レストラン」というのもあります。
どの土俵で勝負するか。
それを決める時、重要なのが店の「コンセプト」作り。
「コンセプト」が明確でなければ差別化は生まれません。
最初に店の「コンセプト」を決める。
大事なことです。
夫婦
今日はプライベートの話です。
私たち夫婦は結婚して38年経ちます。
2人とも結婚記念日は覚えていません。
長女が今年37歳になるので、それより1年前に結婚したことだけ記憶しています。
結婚生活が長く続いて、互いに幸せだと思っています。
子供5人は皆結婚しています。
長く添い遂げて欲しいと思ってます。
私たち夫婦が色々ありながらそれなりに続けれたのは何か考えてみました。
1つ目は互いに「自分が正しい」「相手が間違えている」と言い争わないことです。
「正しい」でなく「楽しい」という言葉に置き換えると喧嘩しません。
「私は楽しい」「お前も楽しい」となります。
2つ目はたとえ言い争っても、相手を余地なく突き詰めることはやめること。
逃げ道を作ってあげることです。
3つ目は夫婦の役割分担です。
夫は懸命に働き家族を幸せにするよう努めます。
妻はそのような夫に頼る気持ちになります。
夫は頼られる存在。
一方男は元来甘えん坊。
なので妻は夫を甘えさせてあげること。
男は一生懸命外で働いて頑張っています。
辛いことがあっても愚痴も言わず、笑っていなければなりません。
家に帰ってきた時くらいはその愚痴を聞いてあげてください。
話せるのは妻しかいません。
以前読んだ本の中に松下幸之助んさんと奥さんのむめのさんとのことが書かれていました。
社長である幸之助さんは会社であった悩みや苦しみは誰にも話せれません。
たとえ直属の部下である専務であろうと言えません。
1人で抱え込むの孤独さを感じるのが社長。
しかしただ1人、幸之助さんの話を聞いてくれたのが奥さんであったむめのさんです。
あの松下幸之助さんでさえ奥さんに甘えていたのです。
妻が一方的に夫に頼り、その上甘えていると、夫は自分のはけ口が無くなり、外にそれを求めてしまいます。
それが家庭不和の原因にもなります。
とりあえずこの3つが夫婦円満の秘訣。
子供達が今度家に帰って来たらじっくり話して聞かそうと思っています。
粗利益率
利益率の話です。
稲盛和夫さんは経常利益率10%は確保しなさいと言います。
しかし、それに伴って粗利益率を◯◯にしなさいとは言っていません。
概して経営者は全ての利益率が高い方がいいと思いがちです。
もちろんいいに越したことはありません。
しかし粗利益率が高いということは、売上高の増減に大きく影響を受けます。
一例です。
売上高100万円で10%の粗利益率だと粗利益は10万円です。
50%と高い粗利益率だと50万円です。
ところが売上が10%下がり、90万円になったらどうなるでしょう。
10%の粗利益率の場合は1万円の粗利益減です。
一方、50%の粗利益率の場合は5万円の粗利益減です。
売上が10%減しただけで5万円の粗利益減少です。
また50%の粗利益を出す会社は概して人件費などの固定費も高く設定されています。
そのため損益分岐点が高くなっています。
下手をすれば、これはすぐに経常利益に影響して赤字に転落ということもあります。
粗利益率ばかりに目が行ってしますと、経営を危うくする。
そんなこともあります。
店の評価
先日あるラーメン屋の前を通ると、店の前に「のぼり旗」が立っていました。
その旗には「本場の味」と書かれています。
美味しいラーメン店であるという意味から書いたのでしょう。
これを見て、「本場ってどこ?」と思ってしまいました。
日本中どこでもラーメンがあります。
札幌ラーメン、博多ラーメン、喜多方ラーメンなど沢山あり、それぞれ旨さを競っています。
また、中華料理の本場中国には麺類の料理はありますが、日本のラーメンとは違います。
ラーメンは日本独特のもの。
さて、本場はどこでしょう?
つい味の良さを強調するため「本場の味」と使ってしまったのでしょう。
「日本で1番旨い!」とか「日本で2番目に旨い!」と味自慢の店もあります。
食べてみると普通だったりします。
自己評価したお店はどちらかというと自滅しているように思います。
「ぐるなび」などで他人評価されている店はそれなりに流行っています。
「ぐるなび」で評価されている店に行くとそれなりに満足します。
でもそのような店のもいいですが、できれば自分で美味しい店を探し出す楽しみもあります。
私が行くおでん屋は旨いのですが、あまり知られていないようです。
その主人は店がマスコミで紹介されるのが嫌いで積極的に売り込みしていません。
それでも旨いので常連客がその店をしっかり支えています。
日本には数えきれぬ程の飲食店があります。
私たちの周りにもあります。
その中から自分好みの、馴染みの店を見つけ出す。
そんな楽しみがってもいいのかもしれません。
先ほど紹介したおでん屋。
時々出す、「カニの身の甲羅詰め」
これは安く、そして絶品です。
ススキノ
先日何年ぶりかで、夜のススキノに行ってきました。
高校の同期会があり、その3次会です。
私は原則として、会合は1次会で帰るのですが、その日は特別でした。
夜の11時頃のススキノ。
すごい人の数。
20歳代と思われる若者が多いこと。
歩いているうちにフッと気付いたのです。
スーツ姿の人がいません。
ブレザー姿も私達くらいです。
夏の土曜日ということもあってそうなのかもしれませんが、以前は結構スーツ姿の人が多かったと記憶しています。
ススキノの飲食店は北海道の土木・建築業界が元気だった頃に繁盛しました。
北海道開発予算という特別の予算が北海道経済を潤してきました。
そして接待目的でススキノが利用されてきたのです。
その予算もなくなり、何年か前はススキノからお客さんが消えたと言われていました。
今のススキノにはスーツ姿の人達に変わって、若者が元気に闊歩しています。
友人の行きつけのスナックに行こうとあるビルに入りました。
その店のあるフロアーには10店舗ほどのスナックがあるのですが、ほとんどが閉鎖状態。
その店だけがかろうじて営業していました。
でもその店も土曜日の夜なのにお客さんは2名ほど。
先ほど歩いて来た通りにある居酒屋やバルなどの店は人が溢れていました。
大きな違いです。
スナックやクラブのように、座っただけでチャージ料やチャーム料を取られて酒を飲む。
もうそのような店には若者は行かないのでしょう。
3次会はまだ続きそうだったので、私は先に帰りました。
ビール1杯くらい飲みましたが、精算すると1人4000円とのこと、
やはり若者は来ないでしょうね。
種をまく
昔、あるところに荒れ果てた畑で作業する老人がいました。
通行人が不思議に思い、老人に近寄りたずねました。
「あなたはこんなところでいったい何の種をまいているのですか?」
老人は答えました。
「種をまいているのではない。収穫しているのだ」と
通行人は驚き「収穫ですって?作物はどこにも見当たりませんが?」
老人はその質問に答えず、ひたすら作業を続けていました。
これはある本に書かれていたお話です。
種をまかないで、いくら作業をしても収穫は得られるはずはありません。
そんな話、馬鹿馬鹿しいと思うかもしれませんが、世の中にはたくさんある話です。
自分では特に何もしないで、収穫だけを願う。
今の私たちが豊かな生活ができるのも、過去の人達がまいた種が実り、それを収穫しているだけなのかもしれません。
ところで私達は将来に向かって種まきをしているでしょうか?
国の借金が1050兆円を越し、それでもまだ無駄使いをしている。
将来の実りの為に種を蒔くどころか、子孫に負債を負わしている。
それが現状です。
「収穫に恵まれている人をうらやむな!そんな暇があれば今すぐ種をまけ!子孫の為に」
ゼネコン
新聞を見るとマンションなどの建築費の高騰が報じられています。
資材や人件費が上がっているためとされます。
確かに円安で資材高や人手不足で人件費が高くなっています。
一方ゼネコンの業績も良くなり、売上も利益も高い伸び率にっています。
このゼネコンという組織を考えてみました。
セネコンは日本独自の組織です。
海外にはゼネコンというものはないと聞きます。
海外では設計管理と施工業者が分業されています。
当社がベトナムにホテルを建築した時もそのような形式でした。
日本のゼネコンは官庁や民間から土木・建築の仕事を受注をします。
それを下請け会社、孫下請け会社に流していく仕組みで。
そして現場働くのは職人です。
建築費高騰原因の1つが、その職人へ支払われる人件費が高くなってためだと言われているのです。
しかし、現場の職人はそんなに高給取りでしょうか。
日本の配筋工や型枠工の技術は世界でもトップクラスと言われています。
その職人の給料はとび職や配筋工の人で日当15000円位。
月収35万円程度。
年収420万円です。
高い技術を持ち、暑い日も寒い日も外で働きながら年収420万円。
決して魅力的な仕事とは言えません。
極端に言えば、日本の土木や建築業界は下請けや職人の低賃金の上に成り立っているのです。
これから書くの事は私の思い違いかもしれません。
日本の土木・建築業界ではゼネコンにお金が集まる仕組みになっているように思います。
この日本独特のゼネコン組織がなくなり、設計管理と施工が分離すれば単独で1社だけ儲かるという事はなくなります。
そうすれば下請け会社や職人への待遇環境も変わってくるのではないでしょうか。
その為には建築業界にも外国業者が参入してくるような劇的変化が必要です。
それにより高くて堅い壁が破れると思うのですが。
競争相手
以前東京でホテルの支配人をしていた時、ホテル間の競争は激しかったです。
私のホテルも苦労しました。
そこで差別化を図るためのサービスを始めました。
羽田空港まで無料送客サービスです。
このサービスが当たり、飛躍的に「羽田前泊客」が増えました。
朝の飛行機に乗るために高崎や宇都宮・甲府からも来て宿泊していただけました。
他のホテルはそのようなサービスはまだほとんなく、独占状態でした。
しかし2年ほど経って、競争相手はバス会社になりました。
早朝飛行機に乗るためのお客様を狙って、高崎・宇都宮・甲府、その他の都市から直通バスを出すようになりました。
いつの間にか競争相手がホテルからバス会社に変わっているのです。
ホテル間の競争のついでの話をすれば、深夜帰宅客を取り合う競争相手はホテルばかりでなく、タクシー会社も参入しています。
ホテルとタクシー。
どちらが安く、また楽なのか
異業種間の競争が生まれています。
ドトールやスタバの競争相手は喫茶店でなくコンビニになっています。
ミスタードーナッツの競争相手もコンビニになっています。
最近は一気に異業種間の参入障壁が低くなっているのでしょうか。
私は時々100円寿司に行くのですが、そこでは最近ラーメンを出すようになりました。
蕎麦やうどんは以前から出していました。
最初は「寿司屋でラーメン?」と疑問に思いましたが、食べてみると結構うまい。
量は少なのですが、それなりに満足します。
「今日のランチは寿司にしようか、ラーメンにしようか」と思っている人には両方食べれるのです。
もしかしたら、これから寿司屋にカレーライスも置くようになるかもしれません。
益々自社の競争相手がどこなのか、わからなくなってきそうです。
叱る
昨日は「ほめ達」の講習会に参加したことを書きました。
「ほめる」ことが上手くなると、人との関係が良くなります。
それは確かです。
それと同時にもう一つ大事なことがあります。
「叱る」ことです。
ただよく見るのは、叱り方がわからず、感情で怒ってしまったのに、後であれは叱っていたのだというのがあります。
私がそうでした。
怒るとは思い通りにならない相手に感情をぶつけることで、叱るとは相手が良くなってほしいという思う気持ちで、語気を強めて言うこと。
辞書にはそのようなことが書かれています。
ともに大きい声を出して言うのです。
でもそれを受けた相手は大声を出されると「怒られた」と感じてしまいます。
大声を出さないで注意するとそれは「諭す」ということになります。
ただ、「諭して」もわからないからつい大声になってしまうのです。
怒るにしても叱るにしてもまた諭すにしても、相手の性格を知ることもは必要です。
叱らなくても諭せばわかる人、
諭してわからなく、叱ってわかる人
叱ってもわからない人。
それは諦めます。
叱ってもわからない人は、怒ってもわからず、逆に恨みを抱かれてしまいます。
叱るということは大事ですが大変難しい。
上手く叱れない経営者は、時として経営が出来ません。
「ほめる達人」を作ると同じように、「叱る達人」作りも大切だと思います。
ほめ達
昨日の日曜日、「ほめ達」の講習に参加してきました。
「ほめ達」とは「ほめる達人」ということです。
大阪にある日本ほめる達人協会が主宰してしています。
あまり興味はなかったのですが、知人に勧められて参加しました。
講習の中で「なるほど」と思うことがありました。
それは「ほめる」ということは「その人」「モノ」「出来事」の価値を発見して伝えること。
その人やそれに伴う「モノ」や「出来事」の良いところを見出し、それを伝えることでその人との関係が良くなるのです。
対人関係でうまくいかない人に対しても、無理してでもいいからその人の価値を見出して、それを伝える。
それによって相手も心が開くこともあります。
従来からよく言われていることですが改めて学びました。
この「ほめ達」は3級・2級・1級とそれそれの検定試験があります。
またほめ達アカデミーというモノもあり、「ほめるという行為」が「ほめ達」として商品化、システム化されています。
この点に若干抵抗感がある人もいるようですが。
この「ほめ達」の講習を受けて思うことがあります。
ほめる目的は何なのか?
打算的な目的であれば、「その人との関係を良くしたい」「その人に好かれたい」となるでしょう。
花柳界には「太鼓持ち」と言われる人がいます。
今では数が少なくなっていますが、お客様が喜びそうな言葉で「ほめ上げ」ます。
お客の方もお世辞だと思っても嬉しくなって、つい心付けを沢山渡します。
「ほめる」という行為の目的は沢山の心付けをもらう打算的な目的があります。
やはり「ほめる」時は「その人を良くしたい」「その人を評価したい」「わかり合いたい」「喜ばしてあげたい」「自信をもたせてあげたい」という相手を思う気持ちが大切でしょう。
その方が自分も楽しくなります。
共通意識
昨夜の勉強会で思った事です。
勉強会で読んだ稲盛和夫さんの本の中にある「世代を超えた共鳴を得る」についてです。
「会社には親子ほどの年齢が開いた従業員がいます。
互いにその時代背景が違うので、経営者と若い従業員とは理解にギャップが生まれます。
そこで経営者が若い人にも理解してもらうには、互いの人間共通の基盤が必要になります。
『人間として正しいこと』という、原理原則に立脚した考えは世代を超えて共鳴してくれます。」
稲盛さんはそのように説いています。
年代が違うと共通意識を持つことは難しいです。
昨夜勉強会に参加した人たちは年配者が多かったこともあり、今の若者との考えの相違を感じている人がいました。
昔は会社行事として運動会や旅行会がありました。
それがいつの間にか「参加する、しないは個人の自由」という理由で無くなってしまいました。
でもそのような行事が会社の中の連体感を高めたと思っています。
最近そのような運動会や旅行会を復活し始めている会社が結構出てきました。
そしてそのような会社は元気があり、会社の業績も向上しているようです。
現代は「個々人の自由を大事にする」という風潮の一方、孤独感を感じている若者が結構いるのではないでしょうか。
常にスマートフォンで誰かと繋がっていなければ不安になってしまう。
そんな若者が増えているようです。
そんな若者にとって、皆と共通するモノが持てれば安心します。
そのような不安心理の若者が多いように思います。
今、改めて会社の従業員にとっても行事は共通意識を持つために必要なことなのかもしれません。
以前ある大学の先生が話してくれました。
「私は学生とのコンパで最初の乾杯は強制的にビールにさせています。
何も言わなければ、各自自分の好きな飲み物を頼んでしまう。
折角コンパで連体感を高めようとするのにそれでは意味がありません」と言うのです。
そして「それは社会に出たら大事なことだ」と学生に説くそうです。
これから社会に出て行く学生にとって素晴らしい教育です。
私もこれから飲み会での最初の乾杯は強制的にビールにします。
車道を歩く人
先日、街を歩いていると私より年配のお婆さんが車道を歩いているのを見ました。
その通りは幹線道路で車が勢いよく走っています。
そこには7〜8mの歩道があるのですが、あえて車道を歩いています。
私はつい「そこを歩くと危ないですよ」と声をかけました。
その方は「私は足が痛いので歩道のは歩きづらい」と言うのです。
確かに歩道は雨水を流すため車道側に傾斜して歩きにくくなっています。
でも事故が起きる方が怖いので、無理に歩道側を歩くように言いました。
でもやはり傾斜している歩道は歩きにくいものです。
以前、車椅子の方も操作しにくいと言っていました。
健常者にとっては気にならなくても「弱者」にとっては辛い。
傾斜をなくすことは難しいでしょうが、勾配を少なくするなどの改良は必要かと思います。
以前行ったことのあるスエーデンやノールウェー。
街には古い石畳の道があります。
歩くのも、車椅子を操作するのも辛いと思います。
日本ではすぐアスファルトで舗装してしまいそうです。
2つの国とも高福祉の国ですが、一方歴史的資産は大事にしています。
福祉も歴史的資産も大事。
一方だけの選択はできません。
「福祉が大切だ」とか「歴史的遺産は一度失うと元に戻らない」言い合うと問題は解決しません。
それではそれを両立させるには何が必要か。
解決は簡単ではありません。
でも弱者の人も歴史資産の大切さを認め、一方その人たちが道を歩く時は手を貸してあげたり、車椅子を押してあげる。
互いに相手を「大切」だと認め合うこと。
それが基本かと思います。
あの時、おばあさんに手を貸してあげれば良かったな・・・・
長考
「長考すると『ノー』という答えしか出てこない」という言葉に出会いました。
同感です。
「長考」とは長く考える事。
長く考えれば的確な判断ができると思いがちですが実際は違います。
人間はマイナス思考しがちです。
考えていくうちに色々なリスクを考えていきます。
結果「ノー」になります。
大切なのは「即断即決」
私はこの事をホテル時代に実感し体得しました。
目の前にいるお客様からの要望に対しては「即断即決」をしなければなりません。
「明日まで考えさせてください」とは言えません。
瞬時に状況を把握し、状況判断をし、何をするかを決めます。
そして「ベスト」でなく「ベター」の決断をします。
その軸になるのは「お客様のためになるか」
次に「スタフのためになるか」です。
そのような判断で、概ね大きな判断ミスは少なかったと思っています。
常に「軸となる考え」を持つ。
大事な事だと思います。
不安感と危機感
今の世の中、毎日のように色々なことが起きます。
そのため、将来に対してつい不安感を抱きます。
一度「不安感」を抱くと常に頭にあり夜も寝れないこともあります。
「不安感」に似た言葉に「危機感」があります。
この2つの言葉の違いはなんでしょう。
「危機感」を持っている人は、今起きている現実を分析し、将来起こるリスクを防ぐか、または減少させるための方策を考えます。
そのため勉強もします。
周りに対しても将来への厳しさを説きながらも、その対応処置を伝え具体的行動をします。
「外向き思考」です。
「不安感」を持っているだけの人は、その不安を周りに撒き散らし、時には不安を増長したします。
具体的対策も行動も取りません。
「内向き思考」になります。
「不安感」と「危機感」
似たような言葉ですが、その意味は全く違います。
皆さんはどちらですか?
パートナー
何かを始める時、「いろいろ検討しても結局何も踏み出さない」という人は結構います。
だからと言って、何も準備もせず始めてしまう人もいます。
何も準備しないで始めるので、結果失敗してしまう。
このような人は時として「実践や行動が大切である」という言葉を無計画の口実にしています。
一方、立派な計画は立てるが机の中にしまいこんで、計画を作るのが趣味のような経営者もいます。
そのような「すぐ行動する人」と「しっかり計画を立てる人」が出会ったらどうなるでしょう。
ペアを組み、お互いの欠点を補い、得意とするモノを出し合えば、大な力を発揮することができます。
良きパートナーに出会う。
自分の夢を成就させるのに大事なことです。
今治タオル
我が家には頂き物のタオルがたくさんあります。
ある朝、顔をふくのに使ったタオル。
「なにこれ!」と思う衝撃?がありました。
柔らかい上にタオル生地がしっかりして吸水性も高いのです。
それが「今治タオル」でした。
これも頂き物です。
「今治タオル」のことは以前からニュースなどで知っていました。
「たかがタオル」との思いでしたが、実際に使ってみると普通のタオルとの断然とした違いがわかります。
今、多くの人はネット通販で買い物をします。
画面と説明でその商品を買うのが当たり前になっています。
ただ、実際にその商品に触れることができないのが欠点。
販売者はその欠点を補い、購入者が安心して買えるように、写真をたくさん使い、購入者のコメントなどを載せて購買意欲を高める努力をしています。
しかしこの「今治タオル」のようなモノはいくら画面で説明しても、「触れる」に勝つことはできません。
触れながら確認する買い物の楽しさ。
それが買い物の喜びなのかもしれません。
今、うちの奥さんが買うタオルは「今治タオル」になりました。
業種と業態と形態
起業する人の中で、飲食店の開業を考えている人が多くいます。
自分の経験があれば、「イタリアンの店をしょう」「寿司屋がいいな」とそれに合う店作りを目指します。
店を開業する人の多くは「業種」で決めるのです。
「業種」は大事ですが、もう1つ、「業態」を明確にする必要があります。
それによって売値の価格帯も違ってきます。
これは飲食店に限りません。
1つの例として寿司屋を取り上げます。
私の小さい頃は寿司屋は高嶺の花。
寿司はめったに食べれませんでした。
それがある時、小僧寿司という寿司テイクアウトの店が出来、評判になりました。
安く寿司が食べれると思ったものです。
その後、北海道では「とんでん」という店が出来、寿司が700円代で店内で食べれるというのも出来ました。
その後、回転寿司店が出来、今は寿司屋というと回転寿司と子供達は答えるくらいです。
一方、東京銀座の「久兵衛」や札幌では「すし善」という高級寿司店も存在しています。
その他、寿司を気軽に食べれる「立ち食い寿司」も一時は流行りました。
寿司屋を開業したいと考えた時、どの業態を目指すのか。
この検討と選択がとても重要です。
最近、北海道で展開する地元回転寿司チェーンの1社が倒産しました。
その要因は何でしょう。
同じ回転寿司でも100円寿司なのか高級寿司なのか。
これは「業態」というより「形態」が大きく2つの分かれます。
同業者の社長に聞くと、倒産した回転寿司チェーンはこの中間の価格帯でした。
それにより顧客の選択から漏れていったようです。
「業態」と「形態」の選択で店の生死がかかってくるのです。
「業種」「業態」とともに「形態」の検討。
これも大事なことです。
甘え殺し
「ほめ殺し」という言葉はご存知でしょう。
ほめ過ぎて、相手がダメになってしまうことです。
ウィキペディアによると「歌舞伎などの芸能関係で使われてきた用語で、頭角を現し有望格と見なされた若手を必要以上に褒めることで有頂天にさせ、結局その才能をだめにしてしまうこと。」
ダメにしてしまうことを目的として使う人もいます。
これに似た言葉として「甘え殺し」
この言葉は私が勝手に作った言葉ですが、優しさの度が過ぎて甘えさせ、その人をダメにしてしまうことです。
優しいことは大切なことですが、「優しくする」と「甘えさす」とは違います。
その人のことを思い、時として厳しく教えることのできる心に広さが「優しさ」
嫌われたくなく、相手の思うがままにさせることが「甘えさす」こと。
料理の世界に「塩梅」という言葉があるように、甘さだけではダメです。
塩辛さがその料理を引き立てるのです。
今の時代には塩辛い言葉が大切のように思います。
愛読書
ネットを見ていると、高校生の就職に関しての話が出ていました。
滋賀県の教育委員会が「就職試験を受けた高校生が、面接で不適正な質問を受けていたケースが73社で82件あった」と発表しました。
不適正な質問の中には、「愛読書」や「尊敬する人」を聞くことも入っているというのを見て、私は驚きました。
厚生労働省の指針により、面接の時は憲法で自由が保障されている事柄の質問は不適正とされているというのです。
そのため、「愛読書」や「尊敬する人」を聞くと「就職差別」に当たるという見解です。
採用する側にとって、その人を知るためには何に興味を持って、どのような考え方をしているかを知らねばなりません。
それに関する質問が「就職差別」と言われれば何を質問すればいいのか。
疑問です。
労務問題に詳しい弁護士によると、この指針は厚労省の解釈に過ぎないということです。
法的強制力はありません。
最高裁の判断は「労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項について申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない」とされています。
「『愛読書』や『尊敬する人』を聞いても法律違反になることはない」ということです。
それにしても厚生労働省の指針に対しては何か釈然としない思いがあります。
メールが来ない
ここ2・3日、知り合いからメール「送ったんだけれど」という電話を受けました。
受信トレイには入っていません。
少し調べると先月の6月19日から受信停止になっていました。
慌てました。
原因は契約しているサーバーの容量がメールでいっぱいになっていたためです。
これを防ぐには「取得したメッセージのコピーをサーバーに残す」のチェックを外しておけばよかったのです。
それがわかり、早速処置をしてのですがまだダメみたい。
これから今日1日処置にかかりきりになりそうです。
商品開発の3つのポイント
昔の資料を見ていると、エステー化学の当時社長だった鈴木 喬氏の話がありました。
エステー化学は商品開発に力を入れ、面白い商品を出す会社です。
その鈴木社長が商品開発のための3つのキーワード示しています。
「聞いてわかる」「見てわかる」「使ってわかる」
「聞いてわかる」はネーミング。
「見てわかる」はデザインやパッケージ。
「使ってわかる」は機能。
この三位一体が大切なのです。
いくらいいものを作っても、お客様に伝え、訴えることができなければ売れません。
「聞いてわかる」「見てわかる」「使ってわかる」
商品開発に大切な言葉です。
自慢話
「自慢話は自分の優越感であり、相手には劣等感を与える。」
ある人が言っていた言葉です。
話している本人はそのつもりが無くても、それを聞いている相手が「いいなー」「羨ましいな」と思わせます。
話している本人はドンドンいい気持ちになります。
逆に言うと、相手にいい思いをさせるには相手の自慢話を引き出してあげること。
武田鉄矢の歌じゃありませんが「あんたが大将!」という思いで話を聞いてあげる。
いけないのは、折角人がいい気持ちで自慢話をしているのに横から入り込んで、「それ私も経験あります」と言って横取りする人です。
やはり結局は「話上手だな」と思わせる人は「聞き上手」な人です。
私はいつも話し過ぎるので痛く反省します。
会社の飲み会
昨夜勉強会があり、稲盛和夫さんのDVDを見ました。
その中では中小企業経営者からの質問に答えていました。
ある経営者が「トップの思いを社員にいかに伝え、浸透させるか」という質問をしました。
それに対して稲盛さんは「経営者は従業員から尊敬される人にならなければなりません。
尊敬されなければ誰もついて来てくれません。
また、それは商売の極意でもあります。
商売で大事なのは信用でなく尊敬されることです。
そして信者を作ることです。」と言いました。
また従業員とのコミュニケーションをはかる上で、「飲み会」の大切さを説いていました。
経営者にとって「飲み会は修行の場です」という言葉は記憶に残りました。
飲み会で従業員1人1人に酒を注ぎ、胸襟を開いて話す時、不平や文句を言われるかもしれません。
それに対して、逃げずに本音の話をしていく。
いい加減な経営をしている経営者は答えることができません。
また会社の現場のことを経営者が知っていないと、どんな話が出るか怖くなります。
それでも飲み会を開き、話を聞いていく。
まさに経営者の人格が試される「修行の場」です。
そのためにも経営者は常に勉強しなければなりません。
勉強は経営のための知識・情報を知るためばかりでなく、現場に下りて、現場の人と話ができるための知識・情報を知らねばなりません。
下りていくための勇気。
それが試される場が「飲み会」なのでしょう。
プラトンとギリシャ問題
今朝のテレビでギリシャで行われた国民投票の結果が報道されていました。
事前の予想では財政緊縮策に対する賛否は拮抗しているとされていましたが、圧倒的に反対が多かったようです。
今後ギリシャ経済はどうなるのでしょうか。
このギリシャの緊縮財政報道を見て思い出したのは「日本の自殺」という論文です。
何年か前にもこの論文は紹介したことがあります。
「日本の自殺」という論文は1975年に文藝春秋で発表されました。
その35年後の2012年に朝日新聞の主筆がこの論文に注目し、朝刊で紹介しました。
そこには「『日本の自殺』がかってなく現実味を帯びて感じられる」と記されていました。
その論文は日本の財政悪化の原因を世界の歴史から指摘したものです。
その中でギリシャ・ローマの没落の研究と比較をしています。
ギリシャの哲学者プラトンの言葉があります。
「ギリシャの没落の原因は欲望の肥大化と平等主義とエゴイズムの反乱にある。
道徳的自制を欠いた野放図な「自由」の主張と大衆迎合主義とが、無責任と放埓とを通じて社会秩序を崩壊させていった。」
この言葉はまさに今のギリシャそのもののように読めます。
歴史は繰り返すのでしょうか。
振り返って見れば日本も同様です。
この論文が発表された1975年の日本の借金はいくらであったかわかりませんが、今よりはるかに少ない額だったでしょう。
現在日本の国債などの借金は1100兆円を越していると言われ、GDP比で233.8%もあり、世界の国々の中で断然トップです。
トップと言っても悪い方からトップです。
これからの日本経済、ますます心配です。
顔を見ただけで
昨日は金比羅さん参りのことを書きました。
その続きになります。
折角、香川県に来たのだからと、高松城、栗林公園、丸亀城を回りました。
その丸亀城で、不思議な人に会いました。
丸亀城の天守を見て降りてくると、先に降りていた妻と話している男性がいました。
83歳のその人は私の顔を見るなり、突然「あんた心臓が悪いでしょう」と言うのです。
確かに私は不整脈で長年病院に通い、薬も飲んでいます。
その人は柔道整復術を習得しているそうで、私に「少し診てあげるからそのベンチに寝なさい」と言いました。
戸惑いながらも、素直な私はベンチにうつ伏せになりました。
そして背骨をなぞって、「ここの部分が陥没している」と言います。
妻にそこを触らせると確かに引っ込んでいると言います。
丁度心臓の後ろ側です。
そしてその男性は私の背中に膝を当て、羽交い締め状態で少し力を入れます。
その時背中の関節が「ボキッ」と音がしました。
「あまり無理をするといけないからこれくらいがいい」と1回だけで終わりました。
そして妻には見ただけで、「あなたは子供を沢山生んだでしょう。骨盤がずれている。帰ったらゴムバンドを買って骨盤に巻き、腰を回すことしばらくの間していると治る」と言いました。
歩き方がおかしかったのでしょうか。
その男性は少し話をした後、何もなく別れて行きました。
なぜ私の顔を見ただけで心臓が悪いと言い、歩く姿を見て子供を沢山生んだということがわかるのか。
気のせいかその後心臓の動悸も良くなったように思いました。
不思議な体験でした。
金比羅さん参り
昨日、香川県から帰ってきました。
29日に高松市で盛和塾の塾長例会があり、参加してきました。
香川県は山地家の出身地。
一度はご先祖様の地に行ってみたいと願っていました。
今回それが叶いました。
折角ですから今回は妻を誘い、1日伸ばして金比羅さん参りをしてきました。
きっとご先祖様も参拝したであろうと思い、今までのお礼を兼ねてお参りしました。
また昨日は7月1日でした。
「1日参り」も出来ました。
雨降る中、参道途中にある「とら丸旅館」から8時30分に出発。
右手には金剛杖、左手に傘を持ちながら、延々と続く石段を登り、やっとの思いで登りきりました。
神殿の前に立つと、「月初めの祭事」が行われていました。
朝早い雨の中なので、参拝者はほどんどいません。
静かな中、厳かな祭事に接することができました。
帰りは滑る石段に気をつけながら1歩1歩。
清々しい気持ちで下りました。
また妻と共有する想い出が作れました。
本気で会社創り
今日の26日で、4月から始まった「自分の会社創り(基礎編)」の講座が終わります。
今日の最終日は竹田さんというIT専門家を招いてホームページの作り方を教えていただきます。
Jimdoという無料のホームページ作成ソフトがあるので、それを使って作成します。
「ホームページを作るって大変そう!」と思っている人も、この授業の中で実際に作る過程を見れば「私でも出来るかも?」と思えると思います。
今日でこの講座は終わりますが、10月から「さっぽろ市民カレッジ」で「本気で会社創り」という講座が始まります。
今度の講座の対象者は「まだ場所も時期も決まっていないが、1〜2年の間にお店を持ちたい」と思っている人向けになります。
従来あるような教室の中で事業計画書を作るのではなく、元中華レストランだった店を「実験場」に、そこで自分が店を持つとしたらどのような事業計画書ができるか。
「飲食店」でも、「塾」でも、「たまり場」でもいいです。
ただ実際にこの「元中華レストラン」で開業するということではありません。
ここはあくまでも「実験場」であり「シュミレーション店」です。
そこで実習します。
参加者各自で業種が決まれば、その周辺の人口調査、競合店調査、客層調査を各自が実施し、事業計画書を具体的裏付けをしながら作成します。
この講座は私が教えるというより、参加者に実際に動いて、考えてもらい、必要に応じて私がアドバイスをすることになると思います。
私はマーケッティングなどの勉強をしたことがありません。
ですからその専門家から見れば稚拙の教えしかならないかもしれません。
専門的な教えは出来ませんが、私の経験に基づいたアドバイスは出来ると思っています。
講座の具体的な内容はこれから作り上げていきます。
私も改めて勉強し直そうと思っています。
私の講座は5回ですが、そのあとはまた竹田さんが5回にわたりIT活用を中心とした講座になります。
開業した店をホームページ、Facebook、ブログ、Twitterを使った告知方法を学びます。
店のしっかりした事業計画が出来、自分で上手く告知方法ができれば、事業の成功度が高まるはずです。
この講座は15人の定員です。
今から楽しみです。
<a href="http://blog-imgs-73.fc2.com/y/a/m/yamachioffice/20150626092206a41.jpg" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-73.fc2.com/y/a/m/yamachioffice/20150626092206a41s.jpg" alt="本気で会社創り" border="0" width="84" height="120" /></a>
マーケッティング
以前集めた資料を見ていると、12年前のマーケッターの話がありました。
当時のマーケッティングについてです
それによると当時、消費者は「総マーケッターになっている」と述べています。
消費者が売り手に負けないほどの知識を持ち、売買の主導権を消費者に取られているのです。
彼はそれの対処として、売り手側が「プロの消費者になる」ことと断じています。
消費者は「買う・持つ」ことの知識は熟知していますが、それを「使う技術」は未開拓なので、それを教えていくことで売り手側が優位に立てると言うのです。
しかし、それから12年後の現在、ネットの社会ではその「使う技術」も自由に手に入れることができます。
欲しい情報は無料で手に入れられる時代です。
売り手が「使う技術」を教えることは必要なくなっています。
それでは売り手側が優位に立てるに必要なものは何か?
それは無いと思います。
現在は売り手が消費者より優位に立てる時代ではなくなっているのです。
消費者に選ばれるモノが「売れる商品」となります。
いつまでも売り手側が優位と考えていると、商品が売れない苦しみに陥ります。
ただ、それの解決の1つに「検索キーワード」があるのではないでしょうか。
ネット上で検索されている「キーワード」とは「知りたいキーワード」であり「売れ筋のキーワード」でもあります。
この「キーワード」を分析し、消費者が求めているモノを知ることで商品作りに生かせます。
私の知人はこの検索キーワードの達人で、彼の会社は急激に売上を伸ばしています。
これからも消費者の購買心理は変化していきます。
世の中の急激の変化に売り手がついて行けるでしょうか。
80点を目指す?
ある記事を見ていて、気になることが書かれていました。
大きな会社の社長の言葉です。
「新入社員にも100点満点を狙わずに80点でいいと説いている。
満点狙いで頑張ると、上から順に解こうとして途中で詰まったりする。
最初から80点を目指せば、やさしい問題だけを探して解き進んでいけるからだ。」
これを読んで皆さんはどう考えるでしょうか?
私は少し疑問に思います。
100点を狙わなければ、いつまでも100点はとれません。
初めから80点狙いでいいのでしょうか。
そこそこ頑張って、もしかしたら60点・70点で終わるかもしれません。
会社は否応なしに競争社会で生きています。
生き延びるためには、社員には努力を求めるべきです。
しかし、努力の結果、成し遂げれなければ、それは仕方がありません。
社員はたとえ成し遂げれなくても、努力したことで、人間としての成長も、周りからの評価も高まります。
今の時代、厳しい会社は「ブラック企業」とレッテルが貼られるかもしれません。
「ブラック企業」は会社のためと言いながら、歩合制の高額給与をチラつかせ、社員を使い捨てします。
実際は社長達経営者のためです。
同じく仕事が厳しくても「ホワイト企業」の社長は、社員の物心両面の幸せがわかり、それを守り、その理念を共有していこうとします。
その姿勢に社員は共感し、納得して努力します。
「小善は大悪に似たり。大善は非情に似たり。」です。
運が良かった
昨日、街を歩いていて、青信号の交差点を渡ろうとしたところ、勢いよく左折してきた乗用車が私の寸前で止まりました。
その間30センチくらいでしょうか。
「ぶつかる!」と思わず身が固くなり、防御のためか、思わず相手の車のボンネットを叩いていました。
その車の運転手は女性のようでしたが、チョット頭を下げ、そのまま行ってしまいました。
私は一時放心状態。
それでも交差点を渡り終わった時、思わず神様に「ありがとうございます」と手を合わせていました。
「私は運が良かった」とつくづく思いました。
災難はいつでも起きます。
予測もしない時に起きます。
その時「運が良いか」「そうでないのか」
それが30センチの違いになってきます。
また、結果事故にならず、車の運転手も「運が良かった」と言えるのかもしれません。
その交差点には右折しようと信号待ちしていた白バイが1台停まっていました。
ぶつかりそうになった状況はよく見えていたと思います。
白バイはその車の後を追いかけて行きました。
さて、その後どうなったでしょうか。
サクランボ
昨日知人からサクランボが送られてきました。
大粒の佐藤錦です。
私はサクランボが大好きですが、妻は体質的に食べられません。
いくら好きでも一人では食べきれないので、近くに住む娘夫婦に分けてあげました。
今、スーパーに行けば日本のサクランボと並んでアメリカンチェリーというサクランボがあります。
37年前の昭和53年に自由化になりスーパーに並ぶようになりました。
当時、日本のサクランボが壊滅的打撃を受けるとして、激しい反対運動があったのを記憶しています。
一時的には影響があったようですが、やはり日本のサクランボは人気があります。
少し高くても日本のサクランボが買われています。
それには生産者たちの品質改良などの努力もありました。
品種も生産量も増えています。
また、佐藤錦などのサクランボは日持ちせず、輸出に不向きとされてきたが、新しい品種の「紅秀峰」は佐藤錦などの他品種と比較して倍近く鮮度を保つことができるそうです。
これから輸出も盛んになっていくかもしれません。
日本の農業は強い。
沢山サクランボを食べて応援します。
父の日
明後日の日曜日は父の日です。
母の日はカーネーションを贈るそうですが、父の日はバラだそうです。
私の子供達は5人いますが、いままではなぜかその日にはお酒を贈ってきました。
余程私が呑兵衛だと思っているのでしょうか。
確かにお酒は好きですが・・・
今年からは「プレゼントはいらない」と妻を通して言ってあります。
それほど裕福でないのだし、無理することはないのです。
カードをもらっても照れくさいので「いらない」と言ってあります。
プレゼントやカードをもらうより、それぞれの子供が幸せに暮らしてくれさえいれば、それが十分なプレゼント。
ただ、妻を通して子供達に1つ言ってあります。
父の日の朝起きたら、空に向かって「お父さん大好き!」と言ってくれればそれでいいのです。
頑固でカミナリ親父だった私に、
さて、言ってくれるかな?
5秒ルール
私がいつも読んでいる武沢信行さんのブログに書いてあった話です。
とても参考になる話でしたのでご紹介します。
武沢さんが友人と食事に行った時の話です。
そのお店は満席で、接客サービスをする中居さんの動きはキビキビしています。
動きはキビキビしているのに、どことなく落ち着きがあります。
中居さん相手に、つい軽口をたたいたり、料理や酒の質問したりする余裕も出てきます。
同席した友人も同じように感じていて、感心していました。
仲居さんの「なにか違う」というのは、目にみえる会話やサービスのことではないようです。
目にみえない何かの雰囲気が違うのです。
食事が終わり会計の時、武沢さんは店長を呼んでそのことを聞いてみました。
店長が言うには「混んでいる店特有のバタバタした接客では中高年のお客さまは納得されません。
ですから当店では【5秒ルール】を徹底させています」
それは、お客さまとの会話が終わってもすぐに立ち去るのではなく、5秒間そこに残って、にこやかにたたずんでいなさい、と定めたルールだったのです。
それは一流の料亭や割烹では自然にできているサービスでもあるそうです。
その5秒によって追加の注文がもらえることもありますし、お客様とのコミュニケーションが深まります。
この「5秒ルール」接客業には大切な要点のように思います。
近所のレストランに入った時、ウエイターやウエイトレスの受け答えも良く、キビキビ働くけれど、マニュアル化したサービスのように思えることがあります。
食事が食べ終わると、サッとお皿を下げてしまうこともあります。
「5秒ルール」
このたった5秒の余裕がその店の評価を上げる。
いい話をいただきました。
チラシ
新聞などに折り込まれているチラシを見ていると、自分の商品を「美味しい」とか「優れている」とか、自分で褒めているチラシが多いように思います。
店側が自分褒めで「美味しい」と言ってもお客様は信じるでしょうか。
行ってみたいと思うでしょうか。
今は「ぐるなび」や「食べログ」など、ネット上の情報の方を信じる人の方が多いかもしれません。
チラシ作りで重要なのは「美味しいに違いない」「優れているに違いない」と思わせる情報の提供です。
そしてお客様は情報の裏にある「物語」が好きです。
その「物語」を知って、お客様の頭の中に「美味しいに違いない」「優れているに違いない」と思わせる事ができます。
来店客が少ないあるレストランがありました。
オーナーは、何度かチラシを作り、集客に努めてきました。
しかし、いくら写真入りのキレイなチラシを作ってもそれほどお客様は増えません。
そしてとうとう、チラシを作るお金もなくなりました。
そこで思い余って、あるコンサルタントに相談しました。
コンサルタントから言われたことは「今までのような写真のあるキレイなチラシはやめましょう。
ご主人、あなたの思いを込めた手書きのチラシを作りましょう」と手作りのチラシ作りを勧められました。
オーナーは言われたように、夫婦で続けてきたそのレストランに対する思い、料理に対する情熱を、汚い字だけれど懸命に「わら半紙」に書きました。
それを同じ「わら半紙」に印刷して、最後のチラシとして配布しました。
その一風変わったチラシの効果は物凄いモノでした。
多くの人がチラシを読み、「物語」を知り、オーナーの思いを込めたレストランでその料理を食べに来たのです。
告知や広告にはいろいろな方法があります。
自分なりの方法、探してみると見つかると思いますよ。
TTP
「TTP」という言葉。
昨夜の勉強会で、サンマルコ食品の藤井社長の話の中に出てきた言葉です。
「TPP」ではありません。
ご存知の方も多いかもしれませんが「TTP」は「徹底的にパクる」という意味だそうです。
昨日の私が書いたブログでは「アイディアの出し方」を書きましたが、このアイディアを出す時「TTP」の発想も大事です。
いいと言われる「事」や「モノ」を素直に取り入れて、自社に適した方法で活かす。
「モノマネは嫌だ!」と言ってはダメ。
優れているモノは認め、それを使わしていただく。
今の世の中に出ている多くの商品は、いいモノの組み合わせです。
昔、松下電器(現パナソニック)は「マネシタ電器」と言われました。
他社が新しく作り出した製品の売れ行きを注視し、同時に生産準備もします。
そして売れると見込んだら自社で大量生産をし、他社より安い価格で売り出す。
結果その分野でナンバーワンのシェアを獲得。
狡いと思われるかもしれませんが、それでいいのです。
メンツなんか考えない。
図太い神経が大切です。
そう言えば、松下電器は関西の会社。
やはり実を取りに行きます。
アイディア
アイディアは「発明」ではなく「発見」
これはよく言われることです。
それなのに「他の人が考え付かないような」アイディアを「発明」しようとしている人がいます。
それは時間の無駄です。
またアイディアは「組み合わせ」です。
◯◯と△△を組み合わせたら⬜︎⬜︎が生まれる。
その◯◯や△△を「発見」することが大事なこと。
またこの時、大切なのは野次馬根性。
なんでも首を突っ込みたくなったり、面白いと言われるものを見に行きたくなったりするような性分の人はそれに適しています。
人ごみの中で知人をすぐ見つけることができる人も適しています。
常に周りに気を配り、何かを発見する。
アイディアが生まれる最初のネタは、それを気に留めていなくても心のどこかに引っかかっているものです。
ある時、別のモノを見た時、自然と2つのものが結びつく。
素晴らしいアイディアはそんなところから生まれると思います。
やはり野次馬根性は大切です。
青春
昨夜は一昨日の夜に続いて「バル」で食事(飲み会?)をしました。
「バル」とはご存知だと思いますが、食堂とバーが一緒になったような飲食店のことをいいます。
一昨日、昨夜と、店は別なのですがそれぞれ料理が美味かった。
昨夜は東京から帰ってきたばかりの妻を連れ、栃木から来ている妹夫婦、それに従姉妹と叔母たちとの食事会です。
カウンターの席しかないその店は、私たちでほぼ満席。
店主1人で作る料理は美味いのですが、1人なので作るのに時間がかかります。
店主が料理に合うというワインを6種類ほど用意してくれましたが、ワインのすすむこと。
料理とワインを充分楽しみました。
一緒に食事した叔母は88歳。
皆と同じようにワインを飲み、料理も食べます。
普段から元気な人で、池坊の先生をしており、一人で京都まで行ったりします。
その叔母から甥っ子や姪っ子の私たちに対して、「青春はいいわね」と言われました。
60歳代はまだ青春なのです。
また叔父は94歳です。
この叔父も雪かきはするし、叔母に頼まれればすぐお買い物までするフットワークの良さ。
ボケもなく、自分の好きなことをしている叔父叔母の元気な姿を見て、私たち甥っ子姪っ子は嬉しくなります。
「もう年だ!」なんて叔父や叔母の前では決して言えません。
青春を謳歌します。
教養
今朝の日経新聞「春秋」に大学教育のことが書かれていました。
文部科学省が全国の国立大学に対して「社会的要請」に鑑み、教員養成系や人文社会科学系の学部は組織の廃止・分野転換を進めるように求めています。
すなわち「教養」は必要ないというのです。
もう一つ、昨日の新聞記事に池上彰さんの話が載っていました。
「10年後、20年後、30年後にも役立つ、人間としての基礎・基盤となる『知の基盤』が教養です。」
そして慶応義塾大学の塾長であった小泉信三氏の「すぐに役立つことは、すぐ役に立たなくなる」という言葉も紹介しています。
国の、何か刹那的教育方針。
私は池上さんが言っていることの方が正しいと思います。
皆さんはどう思われますか?
勤労者の年収
先日、経済アナリストであり、参議院議員である藤巻健史氏のブログを見ていましたら、考えさせる資料が載っていました。
国会で勤労者の平均年収を国税庁に質問したところ414万円だとのことです。
そうすると、400万円の年収の人で、配偶者と高校生2人いる家庭では税金や社会保障費を引いた手取り額が330万円。
次に厚労省に「配偶者と高校生の子供2人いる50歳代の人の生活保護者への給付額」を聞きいたところ、三鷹市では340万円だそうです。
生活保護者は税金も社会保障費も払っていないでしょうから、勤労者の平均と同じレベルの手取り額です。
また、生活保護家庭は医療費、介護費用、都営地下鉄代、バスなどが無料です。
勤労者は当然これらのコストは自分で払います。
この資料からは、生活保護者の方が平均的勤労者より実収入が多いことになります。
これには賛否両論あるでしょう。
でも今まで知らない実態でした。
改めていろいろ考えさせられました。
価格
最近、モノの値段が上がっています。
円高などでによるのでしょうか。
また、単にモノが高くなっているのとは別に、「チョット価格の高いいい品物」が出てきました。
私の昨夜の夕食は、イオンで売っている「五島塩ローストビーフ」でした。
1枚980円もします。
少し贅沢ですが奮発して買いました。
またテレビのコマーシャルでは、吉野家が「鰻重」を出したそうです。
蒲焼1枚乗せが820円、2枚乗せが1220円、3枚乗せが1720円だそうです。
つい最近まで、牛丼各会社が200円台の牛丼の売り込み競争をしていたのとは別次元の世界になってきました。
ガストも、牛の貴重な部位を使った「ミスジステーキ」を1000円以上で売り出しています。
皆、従来からのメニューは残しながら、それまでより1段階も2段階も価格の高い商品を出しています。
そしてそれが売れています。
一方、私が住んでいる町の飲食店では相変わらず「安い」だけを売りにしている店が多いようです。
まだ、他社・他店の「様子見」をしているのかもしれません。
でも今、商売の潮流は変わっていると思います。
「少し高くてもいいモノ」を買うお客様が確実に増えているようです。
私も今度、吉野家の「鰻重」食べに行きたいと思ってます。
思い切って「3枚乗せ」いっちゃうかな・・・
食事
先週末から妻が東京にいる子供達のところに行っています。
留守中の私の食事のために、料理を作り置きしてくれると言いましたが、ご飯を冷凍にする程度であとは断りました。
作った料理があると、それを食べなければならないという強迫観念が働き、無理して食べてしまいます。
ただ、朝・昼・晩の食事のことをその都度考えるのは少し面倒。
外食もあまり好きではありません。
食べようと思えば、レトルトのカレーもカップヌードルも家にあります。
近くにはスーパーもあるので、好きな時に好きなモノが買えます。
それでも食事は、食べたければ食べ、食べたくなければ食べない。
そんな自由もいいかな。
妻の居ない1週間はダイエット期間になりそうです。
妻が帰ってくるまでの間に少しは痩せるかも。
「歳」を楽しむ
その「歳」を楽しむ。
「年」でなく「歳」です。
そんな風に最近思っています。
最近、歯が弱くなりました。
歯医者に診てもらって歯槽膿漏がないのに固いものが少し噛めなくなりました。
目は黒いものが飛んでいる飛蚊症。
耳は元々右耳しか聞こえませんが、耳鳴りがします。
首は頚椎ヘルニア。
その他数え上げれば沢山あります。
それらは全て老化現象と診断されました。
「入れ歯になったら」「耳が聞こえなくなったら」「目がより悪くなったら」と一時は心配もしました。
でも考え直してみると、歳なんですから仕方がありません。
抵抗してもどうしようもありません。
そう思うと、「その歳を楽しむ」ことに考え方を変えました。
60歳、70歳になったのだから、若い時より不自由になって当たり前です。
不自由になっても、その歳を味合う。
アンチエイジングはしません。
60、70歳になったら、40、50歳代には未練はありません。
もう過去にその「歳」は経験しています。
せっかく長生きして60、70、80歳になれたのなら、その「歳」を楽しまなければ勿体無い。
体が不自由になり行動が制限されてもいいじゃありませんか。
その世界ではそれなりの別の価値を見い出せるかもしれません。
私はそう思います。
ただ頭のアンチエイジングだけはしないと人に迷惑をかけます。
それだけは気をつけています。
ナンプレはいいと言われ、今、はまっています。
不良品を流す
ある会社の工場でわざわざ不良品を流しているというのを雑誌の記事で読んだことがります。
なぜそのようなことをするかというと、不良品のチェック体制を確認するためです。
これは社員を信用していないのかという感情論もあるでしょう。
しかし、どんなしっかりしたチェック体制を作っても、チェックするのは人間。
いくら人間性が優れている人でも時としてミスをします。
でも「人間だからミスも仕方がない」ではすみません。
ちょっとしたミスで会社が消滅してしまうことがあります。
不良品を流し、それ見逃した場合、何が原因だったのか。
改良の余地はどこにあるのか。
それがわかります。
「人は信用しても、その仕事は信用しない」
これが品質管理には必要なことです。
認知的焦点化理論

昨日、机の中を整理していたらプレジデントという雑誌の切り抜きが出てきました。
その中に、京都大学大学院工学研究科の藤井教授が唱えている「認知的焦点化理論」についての記事が出てきました。
これは人が心の奥底で何に焦点を当てているか。
そこに着目した心理学上の研究です。
この理論では「利己」と「利他」の関係を説明し、結果「運がいい人」と「運が悪い人」に分けられることを理論的に説明しています。
簡単にその内容を書きます。
自分はそんなに悪い人間でないつもりなのに、いつも損をする。
頑張っているのに不運続きだ。
そう思っている人は一度、自分の心の奥底で本当に何に焦点を当てているか、考えてみることです。
人を陥れるほどのことをしていなくても、自分の不安感や近い将来のことばかり気にしていないでしょうか。
図に示すように、「利己」と「利他」は別次元に位置する対立概念でなく、地続きの連続するものです。(図はプレジデントに記載されているものです)
そして「利己」と「利他」は面積の大小の程度です。
一見、気が利くタイプなのに評価が上がらない人は、自分の心の幅、つまり潜在的な配慮範囲が少し狭く、利他性が低いことに原因が潜んでいるのかもしれません。
他の人のことも思いやる、配慮範囲の広い考えを一度してみてはいかがでしょうか。
私はこの藤井教授の理論を改めて読んでみて、ストンとお腹におさまりました。
稲盛和夫さんが言われる「善行、利他行を積む」
それが心理学的に説明されています。
「認知的焦点化理論」
ご興味ありましたら探してみてください。
ネットですぐに出てきます。
日本のこれから
以前に読んだ新聞記事の話です。
スエーデンは高福祉国で有名です。
そのスエーデンにおける調査内容です。
調査によると、スエーデンで信頼度が高い官庁は消費者庁と国税庁です。
意外なのは国税庁が国民からの信頼度が高いのです。
その国税庁のシンボルマークは3つの羽を模した形をしています。
扇風機と思いきや、吸引機の意味なのだそうです。
「税金を吸い上げる」という、ある意味露骨なシンボルマークです。
スエーデン国民にとって税金は政府に取られるものでなく投資だという人がいます。
スエーデンでは原則、医療費はなく、教育費も大学を出るまでタダ。
老後の保障もあります。
日本の消費税にあたるスエーデンの付加価値税は25%。
その他に所得税と住民税を合わせた所得課税の最高額は56%以上。
その上、年金、失業給付、育児休業給付も課税対象になっており、国民の96%が税を負担しています。
それに比べ、日本の所得税支払義務者は総人口の50%です。
スエーデンと比べ、極端に低い税負担です。
一方、現在日本の財政が大変で、再建策が政府で検討されています。
国の借金が1050兆円を超え、このままでは日本の財政は持ちません。
日本国民が本来負うべき負担を回避して、享受することばかりを追いかけてきたツケです。
それが分かっていながらその対策を後回しにしてきました。
その責任は私たち大人にあります。
これから否応なしに日本人は高負担を負わされるでしょう。
逃げようがありません。
しかし私たち大人がこの問題を処理しないと、子供・孫にその負担を残します。
消費税も含め高い税負担、そして少ない公的サービス。
それを受け入れなければならないのです。
近い将来、日本人の意識と価値観の変革が求められる時代の大変革が起きそうな気がします。
社員と食事する時
人とコミュニケーションをとる方法の1つに食事があります。
会社でも社長が社員を連れて食事に行くことがあります。
食事をしながら話すと、人はお互いに素直な気持ちで話し合うことができます。
ただ食事の後会計の時、社長が領収書をもらっている姿を時々見ます。
これでは食事に連れていく価値が半減します。
社長が会社経費で食事したいがために社員を連れて行っているように見えます。
社長が自腹で食事に連れて行ってくれるから社員は感謝するのです。
また食事に行き自腹でご馳走する時は、まず最初に社長が高い価格の料理を注文すること。
社長が選ぶメニューは好き嫌いより価格です。
社員に対して「好きなモノを注文しなさい」と言いながら、社長が安い料理を注文してはいけません。
高い価格の料理を注文します。
そうすることで社員も遠慮なく食べたい料理を選ぶことができます。
自腹で払う時、この心遣いができるかできないか。
大事なところです。
運の上に胡座をかく
昨日、1ヶ月に1回開いている勉強会がありました。
勉強会の中で、1人の参加者から「会社に無気力の男性社員がいて、その社員をなんとか1人前にしようと皆が努力しているが、なかなか本人がその気にならない。何かいい方法があるか」という話が出ました。
それに対して勉強会に参加している人達から色々な意見が出されました。
その男性社員の生い立ちや生活環境を聞くと、不自由なく育てられ、大学もそこそこの大学に行け、今の会社へ就職したのもなんとなく受けたら入社できた。
そこそこ女性にもモテ、彼女もいて現在同棲しているそうです。
また、その本人にとって会社の成績が上がらず、ミスが多くても他の人がフォローしてくれるので困らない。
頑張らなくても生きていけるのです。
結局、事態を変えるには、本人が困り、その気にならなければ変わりません。
今、日本にはそのような若者が多くなっているのではないでしょうか。
今の日本社会はあまりにも優しいのです。
しかし優しいだけだと人は退化します。
頑張らなくても生きていけると頑張りません。
また、先ほどの男性社員は、恵まれた「運」をただ享受しているだけで、生かそうとしていません。
たまたま「運」がいいことに胡座をかいて努力をしないと「運」に見放されます。
実に勿体無い話です。
勉強
仕事をしていると、時として問題にぶちあたります。
それを解決しようとして勉強することがあります。
その時、簡単には「how to本」を買ってきて、勉強しただけでは上っ面のことしかわかりません。
また、根本を勉強しようとして、軸を外した勉強をしてしまい、遠回りする時もあります。
これは私も経験したことです。
なぜそのような勉強をするかというと、気持ちの中で真正面から取り組むのを避けるきらいがありました。
真剣でないのです。
真剣でなければ、楽な方に行こうとします。
逃げようとする気持ちがあります。
そんな時思い出すのが、小学6年生担任の先生の言葉です。
「山地!嫌なことから逃げるな!」
友達とふざけてドアのガラスを割ってしまったことがあります。
怒られるの怖くてグズグズしている時に言われた言葉です。
仕事で問題が起きた時もそう。
解決するに真正面から向き合う。
嫌なことから逃げない。
そしてその対処こそが勉強です。
バター不足
新聞やテレビを見ていると、今年もまたバターが足りなくなりそうだと報道されています。
国はバターの輸入を増やすそうですが、バターの輸入には1次関税35%、またその量がある程度を越すと2次関税がかかります。
輸入バターは高いバターになります。
一方、国産バターの量が少ない理由として、酪農家が減っているからとか、生乳を牛乳に回すためバター生産量が少なくなっていると言われています。
でもこれはあまり説得力がありません。
足りなければ生乳の生産量を増やせばいいだけの話。
生乳の量が少なく、生産すれば売れるのであれば、酪農をしようと思う人は増えるはずです。
円安で益々外国産のバターが高くなってくるのですから、生産者が増える余地は十分にあるはずです。
外国では安い乳製品が普通です。
外国でも暑い夏の日には生乳生産減少もあるでしょう。
乳製品の競争相手も多いでしょう。
そのような条件は同じ。
でも日本より安い、
日本だけ特別です。
昨日、円が123円台になり、益々円安が進んでいます。
円が75円になった4年前時と比べ、60%程円が安くなっています。
と言うことは、4年前と比べ輸入品は高くなっていますが、輸出はしやすい環境になっています。
そんな時だからこそ農業国北海道の出番です。
現在自給率500%の北海道。
頑張れば700%以上になるかもしれません。
海外では北海道の農産物・乳製品が美味しいと人気があります。
輸出拡大が見込まれます。
保護されている産業は伸びません。
農業もそうです。
円安が進む時こそ、観光と農業で北海道の時代が来ます。
ビジネスチャンスも出てきます。
リミットを設けない
本を読んでいると、面白い話が載っていました。
お金持ちの話です。
彼女はあるユダヤ人と出会い、結婚し、生活の中でユダヤ人の教えを学びました。
ユダヤ人は金に対してネガティブな思いは抱きません。
また「これで十分だ」というリミットも自分で作りません。
そして稼いだお金の10%は寄付します。
それが10倍になって戻ってくるという教えがあるそうです。
だから喜んで寄付するのです。
沢山稼いでたくさん寄付します。
彼女はその後離婚をし、フリーの仕事をしました。
その時もユダヤ人の教えに従いました。
「自分でリミットを設けない」
「自分の運命を他人に任せない」
「それによってかかるリスクは自分で負う」
彼女は現在6億の不動産を運用しているそうです。
この話を読んで「日本人とユダヤ人」いう本を思い出しました。
動物的直感
「致知」という雑誌を読んでいると、ある対談の中で、東日本大震災を経験され、生き延びたおじいさん話が書かれていました。
ある人がそのおじいさんに、「震災で生き残れた体験から活かせることは何でしょか?」と質問しました。
おじいさんは次のように言っています。
「今、自分ができる最善のことは何かを注意深く考えること。毎日がその訓練だ。
普段は覆われてわからないけれども、人間には深い深い知恵がある。
今日のご飯は何にしようかということから始まって、人との付き合い方はこれでいいのだろうか、この商品を選んでいいのだろうか、など人間は毎日色々な場で選択を迫られる。
常に最善を選択する訓練をしておく。
すると、すわ一大事という時に眠っていた本領が発揮できるのではないか。
それによって生き延びることができた。」
動物的直感といえるモノでしょう。
人間は本来持っている動物的直感も、毎日安全に囲まれていると使われず退化していきます。
常に意識を持って最善を選択し行動する。
ここでもやはり「有意注意」の大切さを感じました。
マイナンバー
今年の10月から「マイナンバー」がスタートします。
この法律は2013年の5月に成立しましたが、すんなり成立したようで、その時の状況は私の記憶にありません。
私が学生時代、佐藤栄作内閣の時に一度「国民総背番号制度」が実施されようとしました。
その時「徴兵制につながる」と野党やマスコミが批判し反対しました。
同じ「国民総背番号制度」が「マイナンバー」として登場し、今度はすんなり成立したのです。
その背景にある一番の理由は「年金不正処理問題」や「税金逃れ」があったようです。
それにしても昔あんなに反対運動が起きたのに、すんなり通過したことに少し違和感を感じます。
現在の情報化社会では仕方がないかと思いながらも、全てが国に管理されるということは抵抗があります。
決して悪いことをするつもりはありませんが、この制度では将来個人生活まで知られてしまいます。
知ろうとすれば、その人の趣味・趣向までわかってしまいます。
あと残されるのは「心の自由」だけと思いますが、それもテレビやネットで情報操作されるかもしれません。
これから「どのような世界になるか?」と少し不安です。
バックアップ
昨日何気なしに、日常使っているMacのバックアップ状況を調べてみましたら、ここ1ヶ月ほどバックアップされていませんでした。
MacのTime Machineを使って、データを外付けのHDに入れているはずなのに入っていません。
そして、その外付けHDの認識さえ出来ません。
少し慌てています。
外付けのHDを復活させるには、初期化しなければならないよいうです。
となると今までのバックアップデーターは消滅してしまいます。
今日中に対処しようと思いますが、「上手くいくかな?」と心配です。
何気なく使っているパソコンも突然クラッシュすると聞きます。
バックアップなしでクラッシュしたらどうなるのか!
そんな不安が生まれました。
それと同時に、全て無くなれば、それはそれで過去のしがらみを全て無くすことが出来る。
と思ったりしますが、進行中の仕事もあります。
そうはいかないでしょう。
さあ、これから処理始めます!
忘れることもいいモノです
最近、妻は日中に放映されている、あるテレビドラマを録画してくれます。
その番組は再放送なのですが、私も妻も好きな番組なので夜2人で見ています。
その時に出る会話は「これ見ていなかったよね」です。
そんなんことを話していると、死んだ父母のことが話題になりました。
父母は「水戸黄門」という番組が大好きで、妻はいつも録画をとって、父母に見せていました。
少し忘れぽくなっていた父母は「これまだ見ていなかったね」と言って、何回も見ている番組をまた見ます。
時には朝に見たものを午後にまた見て楽しんでいることもありました。
その父母と同じ言葉を発している私たち夫婦。
笑ってしまいました。
と同時に、「忘れるって結構いいこともあるのだな」と夫婦二人で納得しています。
自社の強みは?
昨日は「ターゲットを絞り込む」話を書きました。
今日はその続きになります。
小さな会社にとって、限られた「お金」と「人」を集中するには、「自社の強み」を生かさなければなりません。
その「自社の強み」は何か。
多くの経営者に「自社の強みは?」と聞いてもよく分かっていない人がいます。
製造業の場合、その会社の強さは、「緊急対応が出来る」「小ロット生産が得意」「塗装職人の技が生かせれる」など有ります。
飲食業も同様です。
洋食屋は「ハンバーグが得意」オムライスが美味い」など得意分野が有ります。
そして単に洋食屋とするより、「ハンバーグ」や「オムレツ」に特化し、それを深化させることで専門店になれます。
それなのに、「自社の強み」に自信が持てず、その他のメニューも出します。
その結果、多くの洋食屋の1つに埋没してしまいます。
札幌にある「牛亭」はハンバーグの店。
「創作オムライスポムの樹」はオムライスの店。
また「自社の強み」の他に「他社と異なるところ」も作らねばなりません。
他社のハンバーグ店やオムライス店との差別化をしていかなければ、その分野で抜きん出ることができません。
それに成功した「牛亭」はハンバーグで札幌で店を展開し、「創作オムライスポムの樹」はオムライスで全国展開しています。
「自社の強さ+他社と異なるところ」が「ターゲットと絞り込んだお客様」と結び付けば、大きな成果が得れるはずです。
ターゲットを絞り込む
新規事業を始めたり、新製品を発売する時、ターゲットとなるお客様を絞り込みます。
男性、女性、若者、老人という分け方ばかりでなく、より具体的な設定をします。
あるホテルは開業にあたり、設計の段階から自社の顧客を具体的に設定し、そのお客様に合わせたホテル規模、部屋の大きさ、備品、インテリアを計画しました。
例えば「年収1000万円、子供2人の4人家族。
ご主人の仕事は◯◯で、趣味は△△、奥様の趣味は⬜︎⬜︎で、洋服のセンスがいい。」など決めるのです。
昔の記事があります。
日産はアメリカで新車開発の時、顧客モデルを据え、自動車開発をしたという話が載っています。
8000人近いターゲット候補の中から35歳のスティーブ氏を選び、モデル顧客としました。
スティーブ氏の仕事はIT関連の仕事で、年収は12万ドル。
カルフォニアに住み、自己主張がはっきりしていて、スキーが趣味。
結婚しており、小学校の子供が1人います。
家族との時間を大切にしている。
日産の開発担当者はスティーブ氏の話を何度も聞き、価値観や注文を聞き、車を作り上げました。
その車が「FX45」(排気量4500cc、44000ドル)。
これは北米で大変売れたそうで。
顧客となるターゲットを絞り込む。
これは大企業より、小企業の方が大事な戦略です。
「誰にでも売れるもの」を売るのでなく、絞り込んだターベットのお客様に絞り込む。
それによって限られた「お金・人手」がつぎ込められます。
お客様を絞り込むことは他のお客様を捨てることになります。
ですからお客様の絞り込みは勇気がいります。
でも小さい会社には必要なことだと私は考えます。
成功するまで・・・
せっかくいい製品を開発しても、うまく売り出せないことがあります。
販路を探し、顧客探しをいても一向に売れない。
その原因はその製品が「いい製品」でも「欲しい製品」ではないからです。
このようなことは従来から言われてきたことです。
しかし人間という者はどうしても「自分は違う」と思いがちです。
私も今まで何種かの新製品を開発したり、その実用新案を取得したりしました。
大手会社に売り込んだり、「通販生活」などの通販会社に売り込んだりしましたが売れません。
しかし、ある程度のところでその営業活動を止めることができました。
製品も見本程度しか作っていませんでしたので、大きな実害はありません。
私は元々自分に対しての自信がない人間だと思っています。
時々、自分の頭の斜め上から自分を見るようにしています。
そうすることで、客観的に見て、これほど調査しても売れそうもないなら「売れないモノ」なのだろうと思えます。
反対に、自分に自信がある人は「これは間違いなく売れるとの思い込みが強く」なかなか諦めません。
また「自分にはこれを売るしかない」という思い込みに陥っている人も、抜け出せられません。
「成功するまで諦めないことが成功の秘訣」と言われます。
しかし、それは世の中のある程度の割合の人から求められた製品や商品だから言えることです。
受け入れられないモノに執着することとは違います。
起業の時、時としてこの執着心が起きやすいものです。
この「見極めする」ことは大事だと思います。
自社に自信を持つ
ある資料を見ていると、面白い会社が紹介されていました。
その会社は合い見積もりを要求されたら「それなら当社は結構です!」と断るそうです。
またその会社の社長は「御用聞き商売はするな!
お客様に好かれるということは、役に立つ提案や情報を提供することであって、おべんちゃらなど使うな」と言います。
その会社はデザインや印刷、販促提案をしている会社ですが、業績を伸ばしているそうです。
自社の商品や技術・サービスに自信があるからでしょう。
またある会社は、「◯◯はしますが、△△はしません」と「しないこと」を明示した宣言文を、チラシやパンフレット・ホームページ上に載せているそうです。
自社の仕事の得意を特化している商売です。
次はあるコンサルタントの言葉です。
「営業マンは買ってもらおうと思うな!必要かどうかを尋ね歩く感覚で営業をすること。」
「販売の時の秘訣は売ろうとしないこと。必要な人に早く会うこと。」
その意味するところは、お客様を尋ねて説明しても興味がないと分かればすぐに退席します。
そして別のお客様のところに行きます。
その時、「早く断ってくれてラッキー。時間を有効に使えるぞ!次回ろう」となり、ストレスが軽減されます。
これを「調査型営業」と言うそうですが、これも自社製品に自信がなければできません。
自社の強み、商品の優秀さを知り、自信を持って経営をする。
経営者の大事なスタンスです。
交渉要求は高く
先日ネットを見ていると「初頭要求極大化の法則」という言葉が書いてありました。
それは「大きく要求すれば大きく得られる」ということです。
逆に、遠慮して要求が低いと低いだけしか得られません。
日本人にはこの法則をうまく生かしていない人が多いようです。
日本人は真面目に裏付けされた真っ当な数字を出して交渉しますが、他国の人はその何倍も平気で出してきます。
例えば交通事故の損害賠償交渉の時、加害者である日本人は50万円と出すとします。
一方、被害者である欧米人は平気で10倍高い500万円位の要求をします。
欧米人は、交渉結果で50万円で妥結するかもしれないと思っても最初に500万円要求します。
ほとんどの場合、結果は50万円以上の金額で妥結することが多いです。
欧米では「ギブ・アンド・テイク」の考え方があります。
最初にあるのは「ギブ」です。
高い金額を提示し、「私はここまでギブするから、あなたはどこまでテイクしてくれるか」となります。
ギブする幅が広いほど優位になります。
ネゴシエーションに日本人は弱いと言われるのはここにあります。
もう1つ例え話。
中国人と日本人が広い会議室で団体交渉の会議を始めようとする時、中国側に大きなゾウがいました。
日本人は「そんな大きなゾウは邪魔だから除いて欲しい」と要求しました。
そうすると中国人側から「除けて上げる代わりに、あなた達は私たちに何をしてくれますか」と聞きます。
日本人からすると、途方も無いことを言ってきます。
これは笑い話ですが、華僑と言われる人たちも凄いネゴシエーターです。
日帰りツアー
昨日、初めて日帰りバスツアーに妻と一緒に参加してきました。
「小樽・余市のお酒めぐりと寿司食べ放題の満喫ツアー」という、私にピッタリのツアーです。
朝8時20分札幌を出発して、まずは北海道ワインの工場へ。
ワインの小セミナーを聞き、試飲。
その後は買い物。
ここでワインを1本買いました。
次は日本酒の田中酒造。
ここでも試飲をした後、金賞を取ったというお酒を1本買いました。
ニッカウヰスキー余市蒸留所へも行きましたが、やはりマッサン人気で、凄い数の人。
私もその1人ですが。
ここでは10年モノの「余市」というウヰスキーが無料試飲でフリーです。
また、こことは別に有料の試飲バーもあります。
そこはクラシックな雰囲気のバーで、1990年モノのウヰスキーを1杯。
これは美味かった!
帰りには世界コンクールで1位を取ったと言われる「余市17年」を1本。
そのほかに黒ひげラベルのウヰスキーを1本。
昼間から少し飲みすぎました。
このツアーのランチは「お寿司食べ放題」が付いています。
妻と2人、十分満足しました。
ツアーが終わり、家路につく時、担いだカバンがお酒で重いこと。
このお酒は私1人では飲ましてくれません。
「誰かお客様が来られた時に出すモノ」と妻から言われています。
来月に妹夫婦が札幌に来るので、その時まで取っておきます。
飲み疲れましたが、楽しい1日でした。
市場を小さくとらえる
「市場を小さくとらえる」
身の丈起業を考える時の基本です。
夢は大きく見てもいいですが、最初の土俵は限定された所とか特化されたモノとか、ニッチ市場を狙うべきです。
先月より大通り高校で「自分の会社創り」という講座を担当しています。
今日、話す内容は小さな起業の実例を予定しています。
「市場を小さくとらえた」実例です。
例1:ある会社が甘納豆を売るために考えた限定売り先は動物園でした。
かわいいゴリラのイラストの袋に入れ「ゴリラの鼻くそ」と命名して売り出したところ爆発的に売れました。
例2:ワインを差別化して売ろうと、量り売りをしているお店があります。
今はオリーブオイルも量り売りしています。
例3:ある若者が花屋をしたいと思いました。
でもお金がない。
それで考えたのは自分の自転車の前と後ろの荷台に花を沢山載せ、夕方駅前で売りました。
近くの駐車場に駐車していた車から花をセッセと運びながら売り、毎日売り続けました。
その後その若者は1軒の花屋をオープンさせました。
今日の講座では、その他にも私が面白いと集めてきた小さい起業の実例を話そうと思います。
お金も経験も実績も無くてもアイディアは出てきます。
またアイディアが出なければ、真似ても構いません。
起業の時「場所」「商品」「顧客」などを限定し特化することで差別化が生まれます。
休酒
長い連休も終わり、今日から出勤。
私はこの連休に入る前に急に歯が痛くなりました。
急遽従兄弟の歯医者に電話をして診てもらいました。
歯は年とともに悪くなります。
歯は気を付けているつもりでも、手入れができていないものです。
この従兄弟は親身になって、歯の毎日のケアを指導してくれます。
その指導に従って、私は歯磨き時は3種類の歯ブラシを使います。
以前は歯槽膿漏気味の歯が多かったのですが、その指導のおかげでほとんどなくなりました。
半年ごとの検診時も褒められることが多くなりました。
そんなに気を付けているのに歯が痛くなる。
少し自信を失くしながら医院に行きました。
でも歯の手入れはOKとのこと。
歯痛の原因は硬いものをかみすぎて、歯の根が炎症を起こしていたからでした。
歯を少し削ってもらい、おかげで歯痛は解消。
そのかわり「連休中はお酒はダメですよ」と言われました。
仕方がなく、従兄弟の言うことを聞いて連休中はお酒は休み。
禁酒でなく休酒です。
妻には言っていませんが、休酒中はなんとなく体の調子も良さそうでした。
でも妻にそれを言うと、いらぬ問題が発生しますので言っていません。
今日からまたお酒再開します。
笑顔
今日は5月1日金曜日。
明日から連休という人も多いでしょうね。
連休中は旅をしたり、行楽地に行ったり、そして料理の美味しい店にも行くでしょう。
その楽しい思い出を作る時、その店の対応ひとつで想いが倍になることがあります。
私が東京のホテルの支配人をしていた時、スタッフに伝えていた思いは「私たちはお客様の思い出作りのお手伝いをします」でした。
東京にはディズニーランドに行くお子様とか、海外からのお客様。
それの修学旅行生もいました。
ホテルスタッフもお客様の楽しい思い出作りのお手伝いができると思うと、自分の仕事に意義を見出し、やる気が出ます。
その時スタッフに気をつけるように注意していたのは「笑顔」です。
心からの笑顔。
取って付けたような笑顔ではなく、何があっても笑顔で応えます。
最初、笑顔で応対していても、何かあるとすぐ真顔になったり、眉に皺を寄せたりする人がいます。
またいつもニタニタしているのも違います。
スタッフにこの笑顔を作ってもらうには、その本人ばかりでなく、会社の対応が大事です。
社長と支配人。支配人とスタッフ。
その間が常に笑顔で会話されていると、自然と笑顔あふれる職場になります。
また、笑顔はタダではありません。
笑顔で応対してもらうにはスタッフの待遇、教育などにお金をかけなければなりません。
時として、単に笑顔を強制する社長がいますが、することしなければ本当の笑顔は出てきません。
そして笑顔ほどリピーター客作りに大切なものはありません。
花見
昨日は祝日。
妻と2人で円山公園に花見に行ってきました。
具沢山のおにぎりをリュックに詰め、自宅から歩いて行きました。
途中、家々の桜や梅の花、それにコブシの花など見ながら45分で到着。
予想はしていましたが、ものすごい人の数。
花は満開を過ぎ散り始めていましたが、それでも桜の木の下で昼食。
歩いた後のおにぎりの美味かったこと。
その後は円山動物園へ。
妻は動物園の年間パスポートがあり、私は65歳以上。
2人とも無料で入園できました。
円山動物園では白熊の赤ちゃんが生まれ、デビュー。
可愛い仕草で、つい笑顔になってしまいます。
人間も動物も赤ちゃんは可愛いですね。
私にも先日7人目の孫が生まれました。
先ほど娘から写真がメールで送られてきました。
名前はEnzo(えんぞ)です。
フェラーリの創業者と同じ名前だそうです。
娘によれば「人の縁に恵まれますように」との意味を込めたそうです。
円山からの帰りに「マルヤマクラス」で美味しそうなパンを買い、帰りは電車で帰りました。
今回のレジャーの出費は帰りの電車代とパン代だけ。
それでも心身ともに充実した1日でした。
私が作った1句
「花薫る 卯月の空に 立ち昇る 柴の煙と 我が想いかな」
お粗末でした。
難問を分割せよ
「我思う、故に我あり」
これはデカルトの言葉です。
今朝の新聞に掲載されていました。
全てに疑いの目で臨んだが、疑う自分の存在だけは疑いようがない。
そのような意味です。
「難問は分割せよ」
これもデカルトの言葉です。
「難しいことは細かく見ていくと大事なポイントが見えてくる」という意味です。
「利益が出ない」
そうすると「売上を上げろ!経費を少なくしろ!」となります。
でも社長が闇雲にいくら叱咤激励してもダメです。
その原因を細かく分析して、その対策を示さなければなりません。
そして分析の結果、単に「売上を上げろ!」と言うのでなく、「◯◯を△△に売り込め!」とか、
「仕入れ先を変えて仕入れ価格を⬜︎⬜︎まで下げろ!」と細かく指示をする。
そうすることで重要なポイントを押さえた行動が出来、その上、会社の力が集中出来ます。
「難問は分割せよ!」
経営に生かせる言葉です。
中古住宅
今朝の日経新聞一面に「中古住宅診断義務化」という見出しが出ていました。
中古住宅の市場活性化を目的としているようです。
現在、日本の住宅は新築時から年々その資産価値が減少し、20年を越すとほぼセロになります。
資産価値のない上物(うわもの)という住宅は評価されず、下手するとその解体費用を換算され、土地の売買価格が低くなることさえあります。
それが制度が変わり、古くなっても資産として住宅が評価されることはいいことです。
そうなると住宅に使用される材料も1ランク上のものを使うことになるでしょう。
日本古来の建築方式である在来工法で使用される柱は、従来は3寸5分(約10センチ)幅の柱を使っていました。
それが4寸(約12センチ)幅の柱を使うことで住宅の耐久度が全然違うと言われます。
今までは見栄えのいい住宅をいかに安く建築するかのところで住宅会社は競争してきました。
そこには30年くらい経ったら家は建て替えるという風潮がありました。
住宅はストック財産ではなくフロー財産になってしまいます。
いい材料を使えば、欧米のように50年以上の住宅が資産価値として認められ、活発な市場が形成されることになるでしょう。
またリフォーム産業を中心に、評価員制度の拡充など、新しい事業生まれることになるでしょう。
ただ「中古住宅の診断義務化」には政府のもう一つ隠れた思惑があるように思います。
それは住宅の評価を高めて、その固定資産税の増加を目論んでいるのではないということです。
マイナンバー制度の導入と絡めて税金徴収を増やそうという考えが見え隠れしているようです。
続「断捨離」
以前から断捨離を少しずつしています。
過去の経営資料などはセッセとシュレッダーにかけ、それ以外は古紙として出しました。
あとは身の回りにあった未使用の文房具などがあります。
それも昨日の勉強会の時、参加された方に持って行っていただきました。
ほとんどなくなりました。
万年筆3本、ボールペン10本、システム手帳3冊、ノート類10冊以上、その他モロモロ。
文房具とは別に座椅子も差し上げました。
実用新案特許をとった「楽マット」座椅子2脚。
それに「ほっかいどうグッドデザインコンペティション」で入選した「ベットチェアー」2脚。
周りから物が無くなるとスッキリするとともに少し寂しくもあります。
今日は「家具修理セット」を手放します。
このセットはプロ仕様の物で、この道具さえあれば木製品の傷修理はほとんど出来てしまいます。
また寂しくなりそうです。
利益率の高い商売
テレビを見ていると、安いということを売りにしたレストランや店が未だに多く紹介されています。
長いデフレの時代の中で、安くなければ売れないと思っているレストランや店が多いのでしょうか。
「安くて量が多くて」となると「材料は何を使っているのだろうか?」と疑問に思います。
薄利多売は労が多くても利益は少ない。
今朝の日経新聞の1面に日経平均が15年ぶりに2万円を回復したと報じられています。
しかし、それでも日本企業の収益力は低く、売上高純利益率は3%。
欧米企業の8%と比べると日本の企業収益力の低さがよくわかります。
その中でも一部の企業の中には利益率を高めるところも出てきています。
稲盛和夫さんは利益率は10%なければならないと言います。
安くなければ売れないという幻想から離れることが大事です。
早くに安売りから脱却していかなければ、単なる安売り会社として時代に取り残されてしまいます。
今のお客様はプチリッチ的な買い物をする人が増えています。
少量でもいいので、ちょっと贅沢して美味しいものや本物が欲しいと思っています。
私たち夫婦も2人暮らし。
時々、デパートの地下にある食品売り場で美味しそうなお惣菜を買って食事を楽しんでいます。
価格はスーパーより少し高いですが、ちょっとした贅沢。
いいものです。
WhatとHow
商売で一番大事なのは何を売るかです。
間違える人がいますが、商売で売るのは「製品」でなく「商品」です。
物としての価値は「製品」にもありますが、欲しいと思わせる要素が加わった物が「商品」です。
商売で大事なのは、何(What)を売るかです。
「シズル感」という言葉はマーケティングの世界で使われます。
ステーキを売る時、単に肉を見せるのでなく、ジュージューと音を出している状況を見せることを言います。
それにより食欲が増し購買意欲がわきます。
食べ物ばかりではありません。
色々な商品に言えます
例えば、バックはデザインの良さを見せるために、人気モデルに持たせ写真を撮るのか。
手帳や手帳の収納状況を見せて使い勝手の良さを訴えるのか。
それによって同じバックでも「何を売るのか」が変わってきます。
何(What)を売るかが決まってから、その後にどう売るかのHowを考えなければなりません。
何を売るかが明確でなければHowも出来ません。
時々、物としての「製品」を売っているだけの経営者を見かけます。
売り上げが伸び無いなと思っている経営者は、もう一度自分の会社は何を売っているのかを明確にする必要があります。
作り出す仕事
4月も後半になりました。
新しく社会人になった人にとっては少し緊張も解け、仕事にも慣れてきた頃かもしれません。
それと同時にこれから5月病に罹る人も出てくる時期です。
「仕事が自分に合わない」とか「会社の雰囲気に馴染めない」と悩みます。
与えられた仕事が面白く無いということもあります。
昨夜に見たテレビの番組にホリエモンこと堀江貴文さん出ていました。
ご自分の失敗談を話す「しくじり先生 俺みたいになるな!!」という番組名です。
ご覧になった方もいたかと思います。
堀江さんの話は大変興味深かったです。
その中で特に記憶に残った言葉がありました。
「与えられた仕事を、作り出す仕事に変える。」
新入社員ばかりでなく、会社員として働く時、多くは与えられた仕事であり、時としてつまら無いと思えることがあります。
しかし、それも自分の工夫で自分が作り出す仕事に変えていけば、興味も湧くというのです。
私が新入社員として銀行に入った時、最初に与えられたのは帳票綴りの仕事でした。
銀行は3月の決算が終わると、前年度の帳票を整理をします。
それが新入社員の仕事です。
1年分の膨大な量の帳票を綴る単純な仕事です。
つまら無いと言えばつまら無い。
しかし、その仕事をしている内に、面白味を見つけました。
綴っている内に、新入社員の仲間同士でいかに綺麗にそして早く処理できるかを競争していました。
そして自分の頭で考え工夫している内に、その仕事が面白くなりました。
どの世界でも、仕事は雑用と言われることから始まります。
昔のホテルの新入社員の仕事はトイレ掃除から始まったそうです。
でもそれを通して何を得ることができるのか。
つまら無いと文句ばかり言っているのか。
その違いが成長度の違いになってきます。
堀江さんの言葉で新入社員の頃を思い出しました。
通じる言葉
時々、人の話を聞いていると「理解は出来るが、スキッと納得できない」という気持ちになることがあります。
話の筋も内容も分かるのだけれど腑に落ちない。
それは聞き手の問題より話し手の問題です。
話に温かみや心が無い時、それを感じます。
頭のいい人が、理路整然と話す時感じます。
逆に、鈍臭く、朴訥(ぼくとつ)とした話しぶりの方が心を打つ時があります。
以前に何かで読んだ言葉があります。
「心で抱きしめて言葉を発する」
相手を思いやる気持ちがあってこそ言葉が通じる。
そんな話し方が出来ればいいですね。
うなずき上手
人と会い、話をしている時、こちらが熱心に話をしても無反応な人が時々います。
そうすると、話している内容が相手の意に沿わないのかと考えてしまいます。
相手は意識しているのか無意識なのかわかりませんが、こちらの気持ちが萎えてきます。
「聞き上手な人」は「うなずき上手」です。
うなずいてくれると「自分の話を納得してくれているのだろう」と安心して話し続けられます。
また、「聞き上手」になりたいのなら「うなずき上手」になることです。
意識して、頭を振ります。
「聞き上手」な人のところには色々な情報を持って多くの人が来てくれます。
うなずきながらチョット微笑みを見せる。
そんな女性の上司が昔いたのを思い出します。
私はまだまだです。
想像力
経営者にとって身に付いていなければならない大切なことは色々あります。
その中で特に重要なのは「想像力」です。
「創造力」も大事ですが「想像力」です。
現状分析の時、データを見ながらそれを具体的に頭の中で想像できるのか。
お客様の気持ちを思いやりを想像できるか。
従業員の働く意欲を想像できるか。
経営者は常に判断を求められます。
自分の頭で考え、それを自分の頭で描く力がなければ何も対応できません。
そのような先の見えない経営者が多いように思います。
発した1つの言葉がどれほどの結果を生むのかを想像できないから、失言と非難されます。
「想像力」がどれほどあるか。
それが経営者の頭の良さです。
何もしない
今、日本経済が少し上向いて、企業業績も順調に推移してきた会社も増えてきたようです。
この間までは売上が上がらず利益も出ない。
苦しんでいた会社も多かったはずです。
ところが特別何かをしたわけではないけれど経営が良くなってみると、今までのやり方でもいいのだという思いに陥ることがあります。
経営者は往々にして過去の成功体験に寄り掛かりがちです。
「累積経験量」という経験の多さを誇るのです。
たまたま経営環境が良くなっただけであるのに自分の力だと思い込んでしまう。
そして経営が順調になるとますますやり方を変えようとしません。
しかしきっと将来にはまた環境が変動し、経営変革を迫れることになります。
そのため経営が回復した今こそ、次の変革時に備えて会社組織の見直し、新規事業の開発に手をつけなければなりません。
それが分かっていても、実行しない経営者のいかに多いことか。
ドラッカーはマーケティングとイノベーションの重要性を唱えました。
マーケティングは「買ってもらうにはどうするか」
イノベーションは「変化しないと死んでしまうので、自ずと変化していかなければならない」ということです。
今は経営者の自己変革の時です。
不揃いが強い
以前に新聞に掲載されていたコラムの紹介です。
神社・仏閣の建築や修復に携わる宮大工の小川三夫さんについて書かれていました。
小川さんは法隆寺宮大工であった西岡常一さんの唯一の内弟子として修行しました。
今までは徒弟制度を踏襲し、100人以上の弟子を育ててきました。
しかし小川さんは「育てたのではない」と言います。
「育てたのでなく弟子が自力で育つ環境を用意しただけ。
よくあるように懇切丁寧な指導では、自分で考えることができないひ弱な人間が出来てしまう。
教えずに放り出し、本人が這い上がっていくようにしなくてはダメだ。」と説きます。
「弟子に簡単に教えたりするのが当たり前になると、何かできないと『教わっていません』というふうになる」
「教わらないで自分で苦労して考えた弟子はその限界を乗り越えられる。」
「放っておいて気づくまで待つということをしていかなくちゃ、人なんか育っていかない」
また小川さんは「木も人も不揃いでないと強くならない」と言います。
「昔は木を上から下に引く鋸がなかった。だから縦に木を割る。
そうすると木は生まれたままにしか割れませんから、どれといって同じものはない。
そのような不揃いの木の方が1本1本に強みを生かして支え合っていける。
それだから建物は強くなる。」
確かに古民家の梁などを見ても、曲がった梁同士が組み合わさっているのを見ます。
それは梁の木の曲がりを生かしているのです。
現代は製材機で簡単に木の繊維を切ってしまうから弱いのです。
確かに真っ直ぐな木の方が細工しやすいのですが、木の力は削がれてしまいます。
小川さんのコラムを読んで、人を育てるということを改めて考えさせられました。
子育ても社員教育も同じですね。
ブックオフ
東京を中心に「俺のフレンチ」や「俺のイタリアン」を展開している「俺の株式会社」社長坂本孝さんの話です。
坂本さんは「ブックオフ」の創業者でもあります。
その創業時のことです。
坂本さんがブックオフを創業したのは50歳の時でした。
古本屋を始めようとし、話を聞きに神田の古本屋を尋ねると「ここは目利きの世界で1本立ちするには10年かかる。明日から修行に来い」と言われたそうです。
「10年経つと自分は60歳になる」と暗い気分になりました。
そこで坂本さんは考えを変えました。
「人マネをしようという気持ちがいけなかった。自分のやり方で1から作るしかない」
その考えが古本業界に革命を起こしました。
暗くカビ臭い古本屋のイメージを変える。
女性が夜でも入れるように明るい店舗。
買取は綺麗な本だけ。
3ヶ月売れない本は一律100円。
仕入れから代金回収まで全て20代の若い店長に任せる。
このような仕組みを独自に作りました。
人は起業・創業する時、その業界の経験を必要とします。
しかし一方その業界にある「遅れの部分」を見つけ出し、新しい仕組みを作れば競争相手のいない新しい世界が開かれます。
競争相手のいないブルーオーシャン戦略そのものです。
その後、坂本さんはこの戦略でレストランの業界に革命を起こし、「俺のフレンチ」「俺のイタリアン」など新しい形態のレストランを展開しています。
坂本さんは現在75歳。
71歳の時レストラン業界に参入しました。
凄い経営者であり起業家です。
早出
最近テレビや新聞の報道を見ていると、残業を減らし、早出を勧めている会社が多くなっているそうです。
早出は私は大賛成。
「早起き企業に倒産なし」という言葉もあります。
朝早く会社に来て就業時間前に段取りをつけ、就業時間開始と同時に行動する。
必然的に生産性に差が出てきます。
「早起き⇨倒産なし」は一見、因果関係はないように思われても、あるのです。
会社のトイレが汚い⇨管理が甘い。
社長が注目され、テレビに出るようになる⇨会社が衰退する。
同様に自分に関係ないと思い込んでいることを言われた時、「何っているんだ!関係ないだろう!」と思うか、
または「何かそこには隠れた合理性やヒントがあるんでは?」と考えるか。
そこが成長の分かれ目です。
無口な職場
「無口な職場」
このような職場にどのようなイメージが湧くでしょうか。
経理など数字に追われる職場はこの雰囲気があります。
しかし会社全体で「無駄口をたたかず仕事をしろ!」いう雰囲気の職場もあります。
そこでは咳払い一つも気になり、同僚と少しでも話をするとジロッと睨まれます。
今はそのような職場はほとんどなくなったと思います。
昔はありました。
そのよう会社は組織が「硬直」した状態です。
一方、「ワイワイガヤガヤ」している職場もあります。
仕事が進まないと思われますが、そこでは色々なアイディアも出てきます。
思いがけない工夫やヒット商品が生み出されることが多いです。
ある経営者が言っていました。
ヒット商品を出すには「おしゃべりな組織」が必要と。
しかし、それには経営者の明確な意思がなければ生まれません。
そして経営者の「言語化能力」が試されることになります。
メカケの手抜き
身の回りを整理していると昔に書いていたノートが出てきました。
楽書(たのしいしょ)と題したノートが5冊。
経営に対する考えを書いたり、経営に関する切り抜きを貼り付けています。
それを読み返していると、書いたのに忘れていることがたくさんありました。
その1つが「メカケの手抜き」です。
誰かの言葉を書き留めたものだと思います。
それは「目は掛けるが手は掛けない」という意味です。
部下に対して、熱心に一緒になって考え、教えてあげたりすると相手の「考える力」を削いでしまうのです。
常に目を向けていますが、必要以上に手を掛けないのです。
その方が部下にとって何がいいかが客観的に見えてきます。
営業マンにも言えます。
営業マンがお客様のためと言って、親身になってお客様の悩みを「自分のことのように」一緒になって考える人がいます。
一見お客様のためになっているように思いますがそうではありません。
自分のことのように悩むあまり、お客様に感情移入し、空回りしてしまう場合があります。
他人の悩みとして客観的に見ることにより、「悩みの芯」だけを見ることができます。
これはコーチングの手法に似ています。
悩みを解決するには「今何を手放して、何を獲得するのがいいだろうか」の選別が必要です。
全てを手にしたいと思うあまり、自分が何をしたいのかを見失うことになります。
「断捨離」途中経過
以前に「これから断捨離をしてシンプルライフを目指します」と書きました。
少しずつ「断捨離」をしていますが「シンプルライフ」はまだはるか先のようです。
「断捨離」するということは「5 S」をすることです。
特に5Sの内「整理」「整頓」「清掃」が断捨離になります。
「整理」とは必要な物と不要な物を分け、不要な物を捨てること。
「整頓」とは必要な時に必要な物をなるべく早く取り出せるようにすること。
「清掃」はゴミをなくし、汚れのないきれいな状態にすること。
そして5Sの4番目の「清潔」は整理・整頓・清掃を実行し、汚れのないきれいな状態を維持することです。
私は場合、現状はまだ「整理」の状態。
それにしても不用品が多いこと。
今まで捨てられなかったのは、「いつか役に立つだろう」という思いと、思い出にまつわる物が多かったからです。
断捨離は「しがらみ」を捨てること。
早く身軽になりたいものです。
ブラックマンデー
今日は月曜日。
ブラックマンデーという言葉があるそうです。
学校や会社に行くのが憂鬱になってしまう現象です。
サザエさん症候群という言葉もあります。
日曜日の夜、ザサエさんの番組を見ると、つくづく「明日から仕事だ・・・」と思い、暗くなってしまうのです。
以前に私の婿さんが同じようなことを言っていました。
同じようなことは私も覚えがあります。
一般の会社員の中で、「仕事が楽しく月曜日が待ち遠しい」と言う人は少ないでしょう。
しかし、経営者は違います。
経営者がブラックマンデー病になっていては会社運営が成り立ちません。
自分を鼓舞してでも、ブラックマンデー状態の社員を明るく楽しくしなければなりません。
笑顔を見せ、大きな明るい声で引っ張っていく。
これは月曜日の朝の経営者の仕事です。
そういえば、札幌では今日から新学期。
ワクワクした気持ちで学校へ行く子供も多いでしょうね。
ワクワクする気持ちを作り出すことが大切です。
地球の体温
今日、札幌は朝から雨が降っています。
大雨注意報も出ています。
雪は3月中に街から消えました。
3月の初め頃、妻は「3月中に例年のようにまた大雪が降るでしょうね。」と言っていましたが降りませんでした。
今は5月上旬の気温です。
本格的な春が待ち遠しいです。
しかし、別の見方からすればこれも異常気象。
異常気象とは地球の変化です。
ある学者が「地球もひとつの生命体」と言っていました。
地球も平穏であれば私たちも平穏です。
しかし地球がクシャミすれば大型台風。
ケイレンを起こせば大地震。
カンシャクを起こせば大噴火。
いつまた大災害が起きるかわかりません。
地球の平均体温は15度と言われています。
人間は36度です。
温暖化により、地球は今世紀末に3度高くなると言われています。
3度程って大したことないと思うかもしれませんが、3度高くなるということは地球は18度。
人間に置き換えてみると、体温が3度高くなり、39度になるのと同じです。
病気になった時の体温です。
年々それに向かっていきます。
そう考えると、これから何が起こるかわかりません。
ある時、生活環境が激変するかもしれません。
今、起きるかもしれないし、私たちの子や孫の時代に起きるかもしれません。
これは人間の力では防ぎようがありません。
「何が起きても大丈夫」という覚悟が必要な時代になるかもしれませんね。
新入社員
昨日は4月1日ということで、街には新入社員らしき人が多くいました。
新入社員にとって会社の人は皆偉い人のように見えることでしょう。
テレビのニュースを見ていると、会社側も新人にいかに早く溶け込んでもらおうと工夫を凝らすところもあるようです。
迎い入れる会社側としては、新人に早く溶け込んでもらうとともに、戦力として活躍してもらわなければなりません。
会社によっては現場に入る前に社員教育して育てる会社もあれば、すぐ現場に放り込んで育てる会社もあります。
その時、新人に直接接する人が重要です。
仕事ができる人を担当にすることがありますが、仕事が有能であることも大切ですがやはり人格でしょう。
大切なのは仕事の「方法」を教えるより、仕事に対する「心構え」であり「考え方」です。
そしてそれをその担当者が身に付けていることがポイントです。
一般社員は毎日の仕事に追われています。
社員の仕事を見て「習わせる」のはいいですが、「育てる」まではいきません
小さな会社ではそれはトップの仕事かもしれません。
社長が一定期間、新人を側に置いて行動を共にします。
仕事に対する考え方を行動で見せます。
それにより仕事の厳しさと喜びを教える。
社長の側で仕事を見ることにより、新人は仕事への考え方を身に付けるとともに、自分は大事にされていると実感します
そうすれば、社長への尊敬と、会社への愛着が生まれます。
簡単に会社を辞めなくなります。
だからこそ社長は「自分磨き」が大切なのです。
営業
最近フッと若い頃、営業していた時のことを思い出します。
最初は銀行員のお得先係として預金獲得。
次はホテルマンとして婚礼や宴会のセールス。
その次は住宅会社の営業として働きました。
最後は東京のホテル時代に支配人として先頭に立っての宿泊客営業でした。
その頃の営業方法を改めて思い返すと、いかに非効率的だあったか。
無駄な、そして自己満足的な営業だったか。
馬鹿なことをしたなと反省します。
その時代、「営業は足で稼げ」と言われ、やみくもに訪問していました。
訪問件数を競うのです。
最後は根性論です。
「結果は後から付いてくる」と言うのです。
私はなぜそうしたか。
言われた通りのことしかしなかった。
効率的な営業を考えることを避けてきた。
そうです。考えることを止めて、ただ歩き回っていました。
今だったらどうするでしょうか。
自分は何を売っているか、自分の商品を熟知しているか。
どこにお客様はいるのか。
それはどのようなお客様か。
そのお客様に会えるのはどしたらいいのか。
その方法は?
40歳を過ぎた頃、東京のホテル支配人をしていた時はなんとかそのような営業ができるようになっていました。
どこにお客様がいて、そのお客様をどうしたら得ることができるかを考えました。
その為に「仮説と検証」の繰り返し。
その結果大きな客層を得ることができました。
ビジネス客以外に、インバウンド(来日)客の獲得。
新プラン「羽田前泊」の告知と集客。
そして航空会社日本エアシステムのキャビンアテンダントの定宿となりました。
結果、安定的に稼働率の高いホテルになることができました。
頭を使い営業する。
この当たり前なことが40歳を過ぎて知ったこと。
それが私の若い頃の営業でした。
土光敏夫さん
先日、知人から土光敏夫さんのドキメンタリー番組が吹き込まれたICレコーダを貸していただきました。
テレビ番組から取り込んだものです。
音声だけですが、改めて土光さんの人間としての偉大さを感じました。
私は現在、稲盛和夫さんの教えを学んでいます。
しかしその前は松下幸之助さん、そして土光敏夫さんの本を一生懸命読んでいました。
一時は土光さんに傾倒しました。
土光さんは石川島造船所に入社し、石川島重工の社長になった時に播磨造船と合併し、世界一の造船会社にしました。
その後依頼されて、当時経営が傾いた東芝の社長になりこれも再建に成功。
その後経団連の会長になりましたが土光さんが85歳の時、当時の総理大臣鈴木善幸氏に依頼され、臨時行政調査会の会長に就任しました。
当時日本の借金、国債発行額は82兆円でこのままでは100兆円を超すという危機的状態でした。
そこで日本の再建を土光さんに任せたのです。
その成果の1つとして、国鉄・電電公社が民営化されたのです。
土光さんは財界のトップでありながら、その生活は質素でした。
その生活の様子がテレビで放映されました。
メザシを食べているところが映され、「メザシの土光さん」と言われるようになりました。
清貧の人と言われました。
毎朝4時に起床し読経し、6時30分には家を出て、バスや電車で2時間かけて会社に通いました。
社用車や公用車は使いません。
政治家との宴会も嫌っていました。
趣味は家庭菜園。
また稼いだお金のほとんどをお母さんが創立した橘学苑に寄付していました。
お母さんが橘学苑を創立した時、お母さんの年齢は71歳。
これもすごい。
お母さんお教えは「個人は質素に、社会は豊かに」で、土光さんはそれに即した生き方をしました。
東芝の社長当時、自宅にはクーラーもなく、「東芝の社長の家にクーラーないのは問題です」と言われ、無理やり付けられたそうですが使わなかったようです。
テレビも白黒にこだわりました。
あるとき贈収賄事件に巻き込まれましたが、平屋の古い自宅を尋ねて来た刑事は、その清貧な生活を見て、「土光さんは違うな」と思ったそうです。
モノにも、お金にも拘らない生活はシンプルライフそのものです。
現在日本の借金は1000兆円をはるかに超えています。
土光さんが日本の再建に取り掛かった時の10倍以上になっています。
危機的状態です。
今こそ、土光さんのように人が日本に必要な時ではないでしょうか。
自分のことばかりを考える「我利我利亡者(がりがりもうじゃ)」
そうではなく「利他の心」そして「個人は質素に、社会は豊かに」
そう考える人が増えなければなりません。
土光さんを特集したyoutubeがあります。
よろしければご覧になってください。
http://www.youtube.com/watch?v=E3qfeuKO3HQ
シンプルライフ
私の周りで、断捨離やシンプルライフを目指す人が増えています。
私もしようと思い片付けるのですが、一つ一つのモノには思い出があり、手が進みません。
「モッタイナイ」という思いと、それにまつわる思い出を捨てることが出来ないのでしょう。
モノを捨てるとその思いまで捨ててしまう。
「それは寂しい」となるのです。
周りを片付け綺麗にすると心が落ち着くと言われます。
断捨離やシンプルライフの極致は出家でしょう。
ブッタは、人もモノも思いも捨ててこそ悩みから解放されると言います。
今の時代は出家はしなくてもシンプルライフ。
これは憧れの生活です。
私も始めることにします。
とらわれない
昨夜、身丈会の勉強会がありました。
その勉強会の前、早目に来られた方との話の内容です。
それは私が2年ほど前にタイに行った時の話です。
タイは仏教国でお坊さんを敬います。
お坊さんは毎朝托鉢で家を回り、食べ物をもらいます。
その時、食べ物を差し出した人が頭を下げ、お坊さんは平然としています。
それを見て、私は「アレッ」と思いました。
日本でも托鉢僧が道に立っていて、お布施をいただくとお坊さんが頭を下げます。
モノをいただいた人が頭をさげる。
それが当たり前だと思っていた私は、タイのお坊さんが尊大に見えました。
日本に帰って、たまたま「ブッダの言葉」という本を読んだ時その理由がわかりました。
ブッダの教えでは、托鉢でいただく食べ物は、有るとか無いとか、多いとか少ないとか、美味しいとか美味くないとか思ってはならないのです。
いただいて嬉しいと思ってもいけないのです。
だから平然といただきます。
ブッタの教えには、上も下も、右も左も、また中間とかいう考えも否定します。
モノや考えにとらわれているからそのように思うのです。
そしてモノや考えにとらわれるから悩みや苦しみが生じます。
托鉢の食べ物も、生きて行くためのモノとして考え、それ以上でもそれ以下でもない。
そんな考えが托鉢の行為の中にあるようです。
モノや考えにとらわれる私は、なかなかブッダの教えの境地には至らないようでです。
お金持と経営者
私の周りに起業を考えている人が多くいます。
その中には、起業目的が「お金持になること」と思っている人もいます。
起業の目的が「お金持になること」でも勿論いいです。
それを考えたらワクワクするように気持ちになるものが起業の推進力になります。
ただ、起業して会社を経営していくうちに、お金持と経営者は相反するものだと分かっていくのだと思います。
お金持が金持であるのは、お金が好きで、稼いだお金を使わないからです。
そのお金でルイヴィトンのバックを買ってしまえば、お金が好きなのではなくルイヴィトンのバックが好きなのです。
お金持はお金は使いません。
一方経営者は稼いだお金は投資に回します。
会社を成長させ発展させるために稼いだお金を使います。
内部留保もしますが会社を発展させるには投資もしなければなりません。
稼いだお金を使わないで貯めるだけだと、ゆくゆく会社は衰退していきます。
お金持はお金を使わない人。
経営者はお金を使う人。
極端に言うとそうなります。
優秀な経営者は、会社が発展するに従って収入も増え、結果的にお金持になります。
それでもそのような経営者は往々にして自分のお金に無頓着な人が多いと思います。
また、そのお金さえも会社に投資する人もいます。
お金持と優秀な経営者。
あなたはどちらがいいですか?
打たれ強さ
今、新聞やテレビを見ていると「マタハラ」問題が取り上げられています。
今までも「セクハラ」や「パワハラ」の問題も提起されています。
「モラハラ」もあります。
このような「弱い者いじめ」は見るにつけ、聞くにつけ腹立たしくなります。
「セクハラ」や「マタハラ」の被害者は女性が多いようです。
「パワハラ」は男性も受けています。
ハラスメント行為をする加害者は非難されるべきです。
しかし、もう一方被害者ももう少し打たれ強くあることを私は願います。
このようなことを言うと「ハラスメントを容認している」と非難されるかもしれませんが、決してそうではありません。
起業する時、この「打たれ強さ」の精神は絶対必要です。
起業した時、自分がいかに弱い立場かがわかります。
思い通りにいきません。
お客様から怒られ、仕入先からいじわるされることも当たり前です。
それをかわしながら、ニコッと笑って交渉する精神的な強さが必要です。
理屈が通らないクレーマーなどはものすごいパワハラです。
悔し涙を流すこともあります。
起業した時、誰も自分を守ってくれません。
自分で守るしかありません。
打たれ強い自分を作っていくしかありません。
それでいて、お客様に喜ばれるモノを提供する、社員の生活を守るという「利他の心」も必要です。
実に、起業し経営をするということは「心の修養」と言えるかもしれません。
間違えない達人
先日の日経新聞に「起業と大学教育シンポジューム」の基調講演が掲載されていました。
講演者はDeNA創業者の南場智子氏です。
この講演記事の中に、国別の起業希望者割合が紹介されていました。
3年以内に起業したいと思っている人は、中国では19%、アメリカは12%。
それに比べ日本は2.5%と最下位です。
南部氏は「日本に起業者が少ない理由の1つに、日本人は失敗を恐れる傾向が強いためだ」と言っています。
「その問題の根本は『間違えない達人』を量産する教育にあるのではないか」ということです。
そして「日本の教育では答えが1つと教えるが、我々が現在戦っている世界ではそれでは役に立たない」とも言います。
確かに経営する時、正解は1つではなく、方法もいろいろあります。
全般を見渡し分析する柔軟性が必要になります。
正解は1つというのは詰め込み式教育の欠陥かもしれません。
ただ、「間違いない達人」を目指すことで日本の産業は成長してきたことも事実だと思います。
「間違いない達人」によって日本製品の高品質を維持されてきました。
研ぎ澄まされた職人の世界を作り上げた要因でもあります。
起業を目指す経営者はゼネラリスト。
製造者はスペシャリスト。
人は目指すものによってそのように区別されるのではないでしょうか?
「感」ではなく「観」
ここ暫く、日本、中国、韓国の間では歴史に関しての考えの相違によって政治的交流が途絶えています。
その論争の中で「歴史観」という言葉が出てきます。
この歴史観の「観」はなんでしょうか。
「感」ではないのです。
「観」には本質を観るという意味があります。
「感」は気持ちや感情込めて見ることです。
事実を追求するには感情を抑えて事実確認することが「観る」ことになります。
このことは経営においても言えます。
経営者にとってカンも大事な要素です。
しかし、事実と違う思い込みによって経営を判断したとすれば、失敗につながります。
事実を常に確認する。
すなわち現場にて確認することが重要です。
スズキ自動車の鈴木修会長は「現場にお金が落ちている」という言葉で有名です。
徹底した現場主義者です。
現場で事実を「観る」のです。
「仕事感」や「経営感」でなく、「仕事観」「経営観」を持った経営者でなければなりません。
現場で事実確認をする。
それによって正しい経営判断ができるのです。
板にへばり付いた蒲鉾のように、現場に降りず自分の地位にへばり付く「板付経営者」は以外と多いものです。
人様の目は神様の目
年をとると、残り短い人生を考えます。
あるお坊さんが語っています。
「年をとり、これからいかに死ぬかを考えていたが、それは間違いであった。
いかに生きるかが大切なことだと悟った」
いかに死ぬかという「終活」より、「生活」でなのです。
「生活」するということは、単に生きるということでなく、いかに生きるかということなのだと私は思います。
私は小さい頃、親から「人様に後ろ指を指されないようにしなさい」と言われました。
そのように親から言われた人は多いのではないでしょうか。
いつどこで人に見られているかわかりません。
だからこそ常に恥ずかしくない行動をする。
それが「生活」するということでしょう。
それはまた、神様に恥ずかしくない生き方をするということにつながります。
「人様の目は神様の目」
そのように思うことがあります。
本気の会社作り講座
私は時々、札幌西区にある「ちえりあ」で「身の丈起業のススメ」という講座を開いています。
昨日、「ちえりあ」の担当の方が来社され、従来と違う新しい講座の打ち合わせをしました。
今回検討しているのは、今までの講座からもう一歩進めたワークショップ形式の講座です。
1年ほど前まで「ちえりあ」の1階に中華レストランがありました。
現在そのレストランは撤退して、空き店舗となっています。
今回のワークショップではこの店舗を会場にして開く予定です。
この空き店舗を題材にして、参加者は「業種」「立地」「広さ」「賃料」などを考慮し、そこでの事業計画を作り上げます。
実物を題材にして起業を考えるのですから現実味が出てきます。
勿論、「ちえりあ」の為にこの空き店舗を埋めることを目的とはしていません。
具体的な内容はこれから検討しますが、大まかな構想は次の通りです。
最初にオーナー側からの賃貸契約の説明を受けます。
その条件の中でどのような商売が可能か。
その「収益性」「実現性」「新規性」はあるのか。
参加者が各自実際に自分の足でその周辺調査をします。
商売する環境、競合店の有無、その客状況調査などし、マーケッティング活動をします。
最終講では、可能であれば金融機関にお願いし、作り上げた事業計画書を実際に融資担当者にも見ていただきその評価も受けます。
私の講座は5回で終わりますが、その後には別の講師が引き続き講座を開きます。
その講座では「開業した会社」の告知方法を学びます。
会社が出来てもその告知が上手くいかなければ、商売が軌道に乗りません。
jimdoなどを使ったホームページやfacebook、ブログ、ツイッターなどのSNSの作り方も学び、実際に参加者が作り上げます。
2つの講座は分かれていますが、連動します。
今までと違って、実際に開業する人のための講座に出来ればと考えています。
講座名は仮称ですが「本気の会社作り講座」です。
これから講座の構想を作り上げますが、どのような講座ができるか、今からワクワクしています。
伊勢旅行
昨夜、伊勢から帰ってきました。
今回も伊勢の神宮会館に2泊して、外宮・内宮の正宮の他に別宮13社を参拝しました。
今回は歩きました。
1日目は18000歩、2日目は26000歩、3日目は16000歩です。
2日目は足が痛かったのですが、今は回復。
まだ身体が若いのか?
1年間のお礼を述べ、元気を頂いてきました。
お伊勢参り
今度の日曜日から妻と伊勢参りに行ってきます。
最近は毎年参拝に行っています。
いつも内宮近くにある神宮会館に1泊宿泊しますが、今回は2泊して、外宮・内宮以外のお宮にもできるだけ多く参拝してきます。
今まで伊勢神宮に参拝に行くたびに心の何かが変化しているように感じています。
今年も参拝できることに感謝します。
日米の子供たちの絵画交流プロジェクト
この春、「日米の子供たちの絵画交流プロジェクト」という催し物があります。
このプロジェクトの趣旨は、桜の時期に合わせ日米の小学生に桜の絵を描いてもらい、相互に交換し東京・三鷹とアメリカ・ワシントンで展示するものです。
絵を通して日米の子供達の交流を図るのが目的です。
このプロジェクトは東京三鷹市にある「友情の桜と緑の会」が主催しています。
2012年から始まり今年で4回目になります。
私は1回目からこのプロジェクトに協力し、札幌にある「リボンハウス絵画教室」の小学生の皆さんに参加をお願いしています。
昨日、お願いしていた絵が出来上がりいただいてきました。
21人の絵、それぞれが個性的で可愛いです。
アメリカの小学生に向けてのコメントも書いています。
今日これから東京に向け送ります。
この絵の展示日程は
米国ワシントン会場 3月28日(土)~4月12日(日)
三鷹会場 4月15日(水)~5月6日(水)
三鷹会場は
三鷹市市民協働センター:三鷹市下連雀4-17-23
MISHOP:三鷹市下連雀3-30-12・三鷹市中央通りタウンプラザ4階
の2カ所になります。
ご興味ある方は行って見てください。
新入社員
今日は朝早くから同系会社の経営計画発表会に行ってきました。
その時の話です。
その会社の社長から色々な話ある中で、「社員の採用と教育」に関していい話をしていました。
新入社員に対し「すぐ活躍し、もっと活躍し、ずっと活躍する」ことを念頭に教育すると言います。
これは新入社員に対する期待の大きさを語っています。
この会社は楽しく仕事をするとモットーにしています。
そこから「すぐ楽しく、もっと楽しく、ずっと楽しく」を目指しています。
それを新入社員に対しての言葉として「すぐ活躍し、もっと活躍し、ずっと活躍する」という言葉になったのでしょう。
この言葉は新入社員にとっても仕事へのやる気を奮い立たせると思います。
この会社の社員は現在540名になっています。
大きくなりました。
ホテル
先日の旅行で思ったことです。
旅行先で大事なのはホテルでの過ごし方です。
ホテルは代表的はサービス業種です。
ホテルのサービス内容はその宿泊の料金によって変わります。
そして、そのレベルに合わせて設備や物は用意されています。
それでも折角用意されているのに残念ということがあります。
広くて素敵な風呂だけれど、蛇口の回し栓の形状が丸く石鹸の付いた手では回せない。
デザインはいいのだけれど・・・・
コーヒーのパックがあるのだけれど、その包装が開けにくい。
暖房があるのだけれど調整が出来ず暑すぎ。
ウォシュレットは付いているけれどペーパーが硬い。
歯ブラシはあるけれどブラシ部分が硬く歯茎が傷つく。
タオルがごわごわ。
靴ヘラはあるけどヘラ部分が厚くて靴が履きにくい。
折角、設備や物が揃っているのだけれど使いにくい。
ホテル側がお客様へのサービスで必要と思い、ただ「物」を揃えるのは「気配り」
その使い心地や使い易さまで気を使うのは「心配り」
一度自分たちで使ってみればわかるはずなのだけれどと思います。
料金の高い安いとは関係なく、お客様への「心配り」あるホテルは少ないように感じています。
諺(ことわざ)
先日、ある本を読んでいると、二つの諺が出てきました。
「君子危うきに近寄らず」と「虎穴に入らずんば虎子を得ず」
それは一見相反しているようです。
前者は「危険を冒さないようにしなさい」の意味があり、後者は「危険を冒さなければ欲しいものが手に入らない」と言う意味です。
前者のように「危険を冒さない生き方」がいいように見えます。
しかしこの解釈は若干違うと思います。
「危うき」というのは物事に挑戦をするのを止めることではありません。
この「危うき」とは、「悪いことへの誘惑」です。
心を乱してしまうようなところには近づかないようにしなさい。
自分を悪い方に誘惑する人とは付き合わないようにしなさい。
そういう意味だと私は解釈します。
何かを始めようとすることは不確定なことに挑戦することです。
そこには勇気が必要です。
「虎穴に入らずんば虎子を得ず」はその勇気の必要性を言っていると思います。
新しいことに挑戦する人は素晴らしいです。
羽田空港送迎サービス
4日、台湾からの帰りの飛行機が羽田に着いたは20時頃でした。
その時間では乗り継ぎの千歳に向かう飛行機がなく、やむ得ず羽田空港近くのホテルに宿泊しました。
そのホテルは羽田空港への送迎バスを出しています。
そのバス乗り場に行ってみると、そこは送迎サービスを実施しているホテル専用のバスプールになっており、多くのホテルの送迎バスが利用していました。
これほど多くのホテルが羽田送迎サービスをしているのかと驚きました。
私が東京蒲田でホテルの支配人をしていた20年ほど前、ホテルの宿泊稼働率の低さに悩んでいました。
その時、羽田空港に近いということもあり、羽田空港までの無料送客サービスを始めました。
送客だけです。
初めはタクシーなどを使い始めました。
当時、送迎サービスを実施していたのは空港に近い羽田東急ホテルだけでした。
私のホテルが始めた送客サービスは、早朝に羽田空港を出発するお客様に便利なこともあり、宿泊されるお客様が増え、一気に宿泊稼働率は上昇しました。
タクシー代の送客コストも十分まかなえました。
現在羽田空港は国際線も就航し、利用客が増えました。
今やその送迎サービスが通常のサービスとして定着しているようです。
今回、私が宿泊したホテル、朝食時に見た宿泊客のほとんどが外国人でした。
送迎サービスを利用しているのでしょう。
改めて考えてみました。
20年前、新しかった羽田送客サービスは「先行利得」でした。
しかし、今のこのような送迎競争の中では戦えなかったでしょう。
もしも私が今だにそのホテルの支配人だったら何をしていただろうか。
どのような新規サービスを考えていただろうか。
そんなことをフッと思ってみました。
そう思ってみると面白そうなアイディア出てきそうです。
お客様に尊敬される
昨夜は「身丈会」という勉強会がありました。
今回も稲盛和夫さんの著書、「心を高める、経営を伸ばす」の中から学びました。
この本の中に「お客様に尊敬される」という項目があります。
「いい品物を安く、正確な納期で、そして素晴らしい奉仕の精神でお客様に提供することで、信用を得れますが、売る側に徳性や人徳があるとしますとそれは信用を超えて、お客様から尊敬されるという状態になります。」
「商いの極意というのは、お客様から尊敬されることだろうと考えます。」
この項目を読んで思うことがあります。
ある回転寿司の店が食中毒を起こしたことがあります。
勿論その店は営業停止になりました。
驚いたのはその時とった経営者の行動です。
その時、その経営者は自主的に系列の店全てを営業停止しました。
それも2ヶ月間ほどにわたってです。
普通、食中毒などの営業停止は起こした店のみで、期間も1週間ほどでしょうか。
それを自主的に全店を2カ月ほど営業を停止し、原因追求とその対策に努めました。
営業停止期間中は、各店の前で社員が店に来られたお客様に対してお詫びとともに次回来店したとき使える500円の割引券を配っていました。
この一連の動きは経営者のお詫びの気持ちがよく分かる行動でした。
そして、その行動はお客様に理解していただけたのでしょう。
再開した回転寿司の各店は以前に増して繁盛しています。
一度大変なことを起こしましたが、それに対する姿勢と行動。
これもまた「お客様に尊敬される」姿だと思います。
私はこの一連の流れを見てもう1つ思うことがあります。
2ヶ月間も営業をやめていても、会社が存続できたことです
思うに、それはその回転寿司の会社がしっかりした内部留保があったからでしょう。
2ヶ月間も営業しなければ普通の会社は資金的に持ちません。
「稲盛さんは税金も経費とみなし、節税などということをせず、税金を支払いながら内部留保を高めることが会社を強くすること」と言っています。
全てのことは繋がっています。
尊敬される会社にするためには強い会社でなければならないのです。
商売の十訓
昨日は「身の丈起業」の話の中で、近江商人のことを書きました。
以前にも紹介しましたが、「近江商人 『商売の十教訓』」というのがあります。
だいぶ昔にネットで見つけたものです。
いいことが書かれていますので紹介します。
1・商売は世の為、人の為の奉仕にして、利益はその当然の報酬なり。
2・店の大小よりも場所の良否、場所の良否よりも品の如何。
3・売る前のお世辞より売った後の奉仕。これこそ永遠の客をつくる。
4・資金の少なきを憂うるなかれ。信用の足らざるを憂うべし。
5・無理に売るな、客の好むものを売るな。客の為になるものを売れ。
6・良き品を売ることは善なり。良き品を広告して多く売ることはさらに善なり。
7・紙一枚でも景品はお客を喜ばせるものだ。つけてあげられるもののない時は、笑顔を景品にせよ。
8・正札を守れ。値引きは却って気持ちを悪くするくらいが落ちだ。
9・常に考えよ、今日の損益を。今日の損益を明らかにしないでは寝に就かぬ習慣にせよ。
10・商売には好況、不況はない。いずれにしても儲けねばならぬ。
この「商売の十訓」は全て現代の商売に通じるものです。
そして昔の近江商人が長年の商売の中で得てきた本物の知恵があります。
1の「商売は世の為、人の為の奉仕にして、利益はその当然の報酬なり。」は松下幸之助さんも常に言っていた言葉です。
3の「売る前のお世辞より売った後の奉仕。これこそ永遠の客をつくる。」
これはアフターサービスの大切さを表しています。
4の「資金の少なきを憂うるなかれ。信用の足らざるを憂うべし。」は資金が少ない身の丈起業家に向けての言葉です。
5の「無理に売るな、客の好むものを売るな。客の為になるものを売れ。」
この「客の好むものを売るな」という言葉は新鮮です。
お客様にとって何が大切かを考える経営です。
7の「紙一枚でも景品はお客を喜ばせるものだ。つけてあげられるもののない時は、笑顔を景品にせよ。」
「お客様に喜んでいただくことは何か!」を問うているようです。
この「十訓」は読んでみると身が引き締まる思いがします。
私も時々読んでいます。
身の丈起業
「身の丈起業のススメ」の講座は昨夜無事終わりました。
その講座の最後に少ししか時間がない中、「近江商人 商売の十教訓」を説明しました。
近江商人は天秤棒一つで商売をしていました。
はじめは店を持たず、自分の体と天秤棒一つで商売をしたのです。
言うなれば「身の丈起業」の典型です。
「お金がない」とか「経験がない」とかの言い訳もなく、自分の足と自分の才覚で全国を歩きながら商売をしていきました。
「身の丈起業」に必要な環境は「資金無し」です。
お金が必要以上にあるとムダ金使いをします。
そして「身の丈起業」で必要なのは「客あり」「商品無し」です。
起業で失敗する例は、自分の思い込みで売れると思い、商品を仕入れてから客探しをする。
結果売れずに商品在庫だけが残ります。
「身の丈起業」で大切なのは、まず買ってくれるお客を探してからそれに見合う商品を仕入れます。
そうすれば確実に売れ在庫が発生しません。
言われてみると当たり前のことですがなかなか出来ていません。
伊藤忠商事、丸紅、双日、トーメン、兼松などの商社が近江商人の流れをくむと言われています。
天秤棒一つの「身の丈起業」で大きくなったのもだと思います。
自分褒め
先月から毎週火曜日「ちえりあ」というところで「身の丈起業のススメ」という講座を開いています。
今日はその最終講の日です。
その講座の中でお話ししていることの1つを紹介します。
私達は常にポジティブな考えで、積極的に行動しようと努力します。
しかし人間ですから時として思い通りにいかず、気が弱くなったり、気力が落ちる時があります。
その時、皆さんはどうするでしょうか?
そのことに関して皆さんの体験をお聞きしていものです。
私は色々ありますが、一番いいのは人に褒めてもらうことです。
人は落ち込んでいる時、褒められると元気になります。
身近にそのような人がいるといいですね。
夫婦やカップルであればその連れ合いから「あなたは頑張っている。凄い!応援している」と言われると元気になります。
そのような連れ合いがいない人はどうするか。
その時は自分で自分を褒めるのです。
これは私の経験でもあります。
仕事が思い通りにいかず、自信がなくなった時、声に出して自分を褒めるのです。
家と駅の間を歩く朝夕に、「伸幸!お前は頑張っている!お前は偉い!きっと良くなるぞ!」と声を出して歩くのです。(私の名前は伸幸と言います)
自分で自分の名前を声に出し、それを聞いているだけなのに新鮮に聞こえます。
歩いている時、他の人が近づいてきたら声をひそめ、人がいなくなれば少し大きい声を出します。
ついでに「お前はツイているぞ!」とも言います。
私の場合は3か月経った頃から少し好転していきました。
今では私は普段から声を出して自分を褒めます。
そして「ありがとうございます」「感謝いたします」とも声に出します。
これは私にとって魔法の言葉だと思っています。
声に出して自分を褒める。
感謝の言葉を口にする。
皆さんも、もしも何か気になることがあった時、このことを思い出し試してみてください。
3日、3週間、3か月ごとに変わっていくはずですよ。
判断力
組織のトップや経営者は常に判断力が求められます。
でも時折、その判断に悩むことがあります。
ある本の中に「判断力」について書かれていました。
「判断力とは現実的には次の2つのことを的確にやる力」。
1つは突き付けられている複数の問題をランク付けする力。
2つ目は問題の前に立ちふさがるネック(障害)を解決する力。
判断力はまず、最重要問題は何かを見出せる力が大事です。
大切で重要な問題を後回しにし、後に回すべき問題を先に取り組む。
そうすると「無能」と呼ばれます。
次に問題のネックを捉え、問題を解決する。
その時、その事実を回避しようとする弱い心を抑え、現実に直視する強い意志が求められます。
人は往往にして手の付け易い問題から解決しがちになります。
それでは問題を回避していると見られます。
「判断力」は組織の上に立つ者ほど求められる力でしょう。
落し物
2週間程前に妻がICカードのスピカを落としました。
カードに名前は書いてあったのですが、「きっと使われているよ」と話していました。
でも念のためと思い、札幌市交通局の落し物センターに電話したところ、届いているとのこと。
先日、落し物センターまで受け取りに行ってきました。
受付で待っていると、係の人が持って来たホルダーファイルに沢山のICカードが挟まっていました。
全て落し物です。
ネコババされず、これ程のカードが届けられている。
「日本人ってすごいな!」と改めて感心しました。
戻った妻のICカードで買い物をすると、中身のお金もチャンと手付かずのまま。
「きっと使われているよ」と疑った私が恥ずかしいです。
稼働率と高価格
今月の18日から春節が始まりました。
テレビでは中国や台湾からの観光客が大勢来日している様子が映し出されています。
各観光地でも旅行客で賑わっているようです。
私はこの混雑する直前の週末に登別温泉に行ってきました。
その時期は予約が少なくて、格安で泊まれました。
2食付きで1人8千円ほど。
宿泊した温泉旅館は「楽天トラベルアワード」に何回も選ばれた旅館で、食事も充実しています。
夕食はバイキンですが、焼きたてのステーキ、揚げたての天麩羅、温かいビーフシチュー、カニ、寿司等数十種類の料理が並びます。
温泉は露天風呂もあり、肌にいいという硫黄温泉に入りました。
登別までは専用バスがあり、往復で1人1000円。
この旅行での費用は夫婦で合わせて2万円かかりませんでした。
旅館を出る時、旅館の人に聞くと、私達が宿泊した日は200室以上ある部屋がほぼ満室だったそうです。
ホテルや旅館の商売のポイントは第一に「部屋を埋める」こと。
次に「定価販売」に努めることです。
混み合う日は部屋を高く売り、暇の時は価格を安くしてでも稼働率を上げます。
ホテルも旅館も部屋の「在庫」が出来ない商売です。
今日売るの分の部屋を売れ残した時、それは取り戻せません。
混み合う時は安売りせず定価で売る。
「稼働率」と「高価格」
それを見極めながら最大の売り上げを目指す。
当たり前のようですがなかなかその見極めが出来ないのです。
でもこれが大切です。
部下に任せる
昨日は松下幸之助さんが言った「部下が偉く見える」について書きました。
そのあと改めて考えてみました。
松下幸之助さんはどうしてそのような謙虚な気持ちを持ち得たのであろうか。
松下さんは尋常小学校を中退した人です。
昔は尋常小学校にも行けなかった人もいたのでしょう。
そのように学歴がない経営者は往々として叩き上げの経営者となります。
努力の末、会社が大きくなると、「学歴がなんだ!大卒がなんだ!」「人間やる気なんだ!」と言いがちになります。
つい自分の力を誇示するようになります。
松下幸之助さんはそう成らなかった。
なぜ松下さんそう成らなかったのか。
松下さんは体が弱く寝込むことが多かったそうです。
動けない自分。
しかし、病床にあっても毎日経営者として決定し、指示しなければなりません。
その時に「部下を認め、任せる」という気持ちになったのではないでしょうか。
結果、常に一歩引いた状態で会社を観ることが出来る。
そんな客観的に会社を観ていたからこそ、部下の姿も観れたのでしょう。
松下電器が大会社なっても、「自分には学歴がないから皆さんの話を聞かせていただきます」と言い続けていたそうです。
一流大学を出た社長はつい自分が偉く見えて、部下が無能に見える。
逆に学歴がなければ、叩き上げの自分の凄さを誇る。
共に部下が観えなくなっています。
やはり経営者は「心を高める」ことが大切だと考えます。
部下が偉く見える
松下幸之助さんの本を読んでいると、「部下が偉く見える」という一節があります。
「社長という立場から、時として部下をボロクソに叱りとばすことがあります。
責務上叱り飛ばしていますが、叱りながら内心では「この人は自分より偉い」という気持ちになることがあります。
そのように人を使い、接してきました。
それがこれといって取り柄のない私でも、多少とも商売に成功し、、経営や人使いがうまいと言われるようになった原因でないかと思います。
お得意さんの社長の中には、『どうもうちの社員はアカンわ。困っとるんや』と言う人がいます。
そういう会社はうまくいっていない。
社長の手腕があるからこそ、部下が物足りなく見えるのかもしれません。
上に立つ人が、自分の部下が自分より偉いと思うか、それともアカンと思うかによって、商売の成否が別れてくると言ってもいいように思います。
そんなチョットしたところに経営なり、人使いのコツがあるのです。」
「謙虚にして驕らず」
できるようでなかなか出来ない。
経営のコツなのですね。
分別
今、地下鉄に乗ると多くの人がスマートフォンと「にらめっこ」状態です。
普通の風景になってしまいました。
時々、隣の人の画面を覗いてみると、メールチェックしている人もいますが、多くはゲーム。
15年ほど前、私が東京勤務の時、電車の中での朝の風景は、スポーツ新聞を読んでいるか漫画に熱中している人が多くいました。
今はそれがスマートフォンに変わっています。
こう言っては年寄りじみて説教くさいと思いますが、社会人としてこれから「仕事に行くぞ!」という時に漫画やゲームに熱中しているのを見ると、「?」という思いがします。
朝仕事場に向かう時は、「今日の仕事はどう段取りするか」を考えたり、「今朝の情報は何があるか」と日経新聞を読むとか、朝の時間は大切な時間です。
朝から漫画やゲームをしていては、漫画の頭であり、ゲームの頭になってしまいます。
それではその日の仕事に関して満足な結果は得れません。
この心構えの差が仕事の差になってきます。
漫画やゲームがダメだと言っているわけではありません。
仕事が終わり、帰りの電車で頭を休めるには漫画もゲームもいいでしょう。
「生活の区切り」「分別を知る」
大切なことだと思いますが・・・・
するべき経営
今、振り返ってみると、長く仕事をしている間、多くの経営者とお付き合いし、その経営する姿を見てきました。
また素晴らしい業績を残している経営者の本も色々と読んできました。
その中で思うことがあります。
経営には「これだけが手本となる経営方法だ」というものはありませんない。
叱咤激励しながら社員を引っ張っていく経営者がいます。
皆が楽しくなることを第一に考え経営している経営者もいます。
稲盛和夫さんは会社を創業し、理念を掲げ、自分が先頭になり、旗を振りながら、社員を引っ張ってきました。
同じ創業者の松下幸之助さんは体が弱く、病気がちだったので、人を活用して会社を大きくしました。
ホンダの本田宗一郎さんは自分の好きな現場に入り切り、総務や営業などはパートナーに任せました。
やり方はそれぞれ違います。
ただ共通しているのは、皆が「事業の目的」を持ち、「具体的な目標」を立て、「強烈な願望」を抱き、「誰にも負けない努力」をしました。
表面的なことだけ見ると、別々のやり方で仕事をしているように見えても、するべきことは同じことを踏まえています。
経営の成否はその4つの基本が出来るか出来ないかにかかっています。
やり方は千差万別だけど、やることは同じなのです。
本物
昨日は「一流」について書きました。
その「一流」という言葉で思い出したことがあります。
20年ほど前、東京のホテルの支配人をしていた時、「グレープストーン」という会社を訪問した時があります。
この会社は今では東京銘菓「東京ばな奈」というお菓子でも有名な会社です。
この会社はお菓子の店の他に、パスタなどのお店も運営していていましたので、ホテルレストランの参考にしたいと思い、経営者の方にお会いしに訪問しました。
東京阿佐ヶ谷にある本店を訪問した時です。
事務所や店舗にいろいろな飾り物が置いていました。
陶器類やグラス、絵画などです。
経営者の方に聞くとそれは全て価値の高いもので、人間国宝という人が作ったものまでありました。
誰でも触れるようになっています。
つい「壊れたり、傷ついたりする恐れがあるのでは?」と聞くと、経営者は「社員に本物を知ってもらうためです」と言います。
本物に接していないと本物が分かりません。
また本物が分かるとると、偽物がわかるのだそうです。
目で見、手で触り、その重みを知る。
触れてこそ本物・一流が分かるのだそうです。
優れた社員教育がそこにありました。
ご存知のように、この会社はその後大躍進をしています。
本物を求めて経営した結果なのかもしれません。
一流
仕事の上での大きな発想や新しい着想はその人の余裕や贅沢さから生まれます。
300万円の年収の人は300万円クラスの人を相手にします。
年収1000万円以上の人のお客様は、年収1000万円以上の人です。
それでは300万円の年収の人は1000万円以上の人をお客様には出来ないのでしょうか?
そうとも言えません。
1つに絞り込んでそれに時間とお金を投資する。
そうすればその部分で1000万円の人に通じるものが自分の中に作れます。
30年ほど前に、ある大手ホテルの支配人に教えられた話があります。
ホテルのレストランに新卒で就職したコックは、レストランで出されている料理の味見など出来ません。
それでも自分で舌を鍛えなければなりません。
新卒のコックは給料が安いです。
美味しいものを食べに行く余裕がありません。
必然的に食べるものが貧相になります。
しかし毎日安いラーメンばかり食べているコックの舌は、いつまでたってもラーメンの舌でしかありません。
いつまでも舌が育ちません。
一流のフランス料理の味などは出せません。
それではどうするか。
舌を育てるために、生活を切り詰め、お金を貯めて、一流と言われる料理を食べに行くのです。
それを月に1度でも続けていくことで自分の舌を育て、鍛えていきます。
一流の料理を食べているうちに、今までの自分の舌はどうなっているのか分かります。
仕事の上で一流を目指すなら、自分も一流を味合う。
これも自己鍛錬です。
色紙
昨日ネットを見ていたら、野球選手で監督だった落合氏が書いた色紙の事が載っていました。
落合氏は色紙の金箔がふられている方にサインをするそうです。
ところで皆さん、色紙の表と裏の区別が出来ますか?
大分昔に、ラジオで永六輔さんが話していたのを覚えています。
色紙の金箔がふられている面が表。
白い方が裏なのです。
色紙には約束事があります。
サインを求められた時「私はまだ未熟者なので裏に書かせていただきます。
そして私が一人前になった時には改めて表に書かせていただきます。」という意味があるそうです。
ですから表と裏にサインが書かれて初めて色紙は完成するのです。
一流選手であり監督であった落合氏は、そのような事を分かった上で、色紙の表面にサインをしたのかも知れません。
今日は私の「知ったかぶり」を披露しました。
敵を作らない
今朝のNHKニュースで日本ハムが旅行業を開始すると報道されていました。
日本ハムは札幌ドームで開催される主催試合の観客動員数を年間200万人目標を掲げています。
それが現在190万人と、まだ未達のようです。
今後は観客数を増やすため各地で観戦ツアーを企画して観客増を図るようです。
この報道が流れた時、なぜ既存の旅行会社と企画を組まないのかと疑問に思いました。
JTBや近畿日本ツーリストなどの既存の旅行会社は喜んで企画すると思うのですが。
日本ハムは大きな会社ですから、反発を受けぬよう色々な布石は組んでいると思います。
小さな会社の場合は少し違います。
商売をする時、如何に多くのお客様を獲得するか、そしてそのお客様をファンにするかが大事です。
それと同時に、決して敵を作ってはいけません。
同業者に対しても、仕入れ業者に対してもそうです。
仕事上で自社の得意な部分と不得意な部分があります。
不得意な部分は外部に委託するのがいいでしょう。
そうすると委託した業者は自社の支援者になってくれます。
ところがその仕事を「儲かりそう」だからと言って自社で行おうとする。
やってみると思いの外、慣れない仕事で戦力が分散してしまう。
その上、上手くしないと委託業者は反発し、敵を作ってしまう結果になります。
小さな会社にとって大切なのはファンと支援者を作る事であり、足を引っ張る敵を作ってはいけないのです。
これは忘れてはいけません。
身丈起業
今日は立春。
新しい年の始まりと言われています。
そんな事もあってでしょうか、最近「何かを始めたい」「こんな事を考えている」という人からのご相談が多くあります。
皆さん素晴らしい志や楽しい思いを抱いています。
そのような人に言うのは、「まず行動する事」です。
いくら素晴らしい考えでも、動いてみないことには始まりません。
情報を得に見学したり、人に会いに行きます。
同じ思いを抱く人と語りあいます。
そしてその夢や思いを数字に落としてみます。
その後にお客様となる人を集めます。
お客様となる人が何れだけいるか。
その結果、起業するかの判断をします。
失敗するのは、自分の思いと、実際の需要との乖離に気付かない時です。
お客様になる人がいてから起業すれば失敗はありません。
お金をかけ、設備し、品物を仕入れてから営業を開始する。
だから失敗するのです。
最初に思いや志を抱き、調査行動し、事業計画し、それに基づいて事前営業します。
その後に起業。
この順番が大切。
これが「身丈起業」のポイントかと思います。
シルバーシート
札幌の地下鉄の電車に乗ると、シルバーシートがだいたい空いていることが多いです。
若い人が座るに座れず、空席のシルバーシートの前に立っているのを良く見ます。
本来はシルバーシートに若い人も座ってもいいはずです。
お年寄りや障がい者の人が来たら席を譲ればいいのですが、シルバーシートに座ると罪悪感を感じるようです。
私も若い頃はそうでした。
他の普通席を見ると、私より年配のお年寄りが座っています。
その人がシルバーシートに座れば、その席に若い人が座れるはずです。
私もいつの間にか65歳を過ぎ「高齢者」と言われる部類に属しています。
それなのにシルバーシートに座ると自分から「年寄りだ」と宣言しているように思い、座るのを躊躇している自分がいます。
そんな事に気付いた先日から、「人助けだ!」と思い、シルバーシートに座るようにしました。
一緒に座った妻が「私達座っていいのかしら」と言っています。
慣れるまでにしばらくかかりそうです。
お客様を断る時
昨日の日曜日、妻と二人であるレストランに行って来ました。
そのレストランは私の会社の関連会社が先月の中旬にオープンしたイタリアンの店です。
最寄りの地下鉄の駅から吹雪の中歩いて約20分、やっと着きました。
お昼の12時少し前に到着し、お店に入ると「予約で一杯です」とのこと。
あらかじめ予約しようかと思っていたのですが、天候は吹雪なのでだ「丈夫かな?」と思った私が甘かったです。
仕方がないので「分かりました」と言って店を出たのですが、何か引っかかりました。
店の応対です。
私と応対した女性は「予約されてますか?」と聞いたので、「していません」と私が言うと、後ろを振り返って責任者らしい人に顔を向けました。
そうするとその男性は、黙って首を横に振りました。
そして女性が「予約で一杯です」と言ったのです。
私が引っかかったのはその男性の様子です。
その時、男性が「折角お出でいただいたのに申し訳ございません。あいにく今日は満席になっております。
どうぞこれに懲りずまたお出で下さい。
宜しければご予約いただければお席をご用意致します」と言ってくれれば、「今度予約してから必ず来ますね。」と言えたはずです。
聞くところによると、そのレストランは連日満席のようです。
いい事です。
きっと魅力的なところなのでしょう。
ただ私の経験から言えば、満席でお客様を断る時こそ注意しなければなりません。
ディズニーランドは人事採用の時、採用に落ち、ディズニーランドのスタッフになれないと決まった人に対しては、その時点でお客様としての対応に切り替えるそうです。
不採用になったという事で悪い評判を起こさせない為に、1人のお客様として丁寧な対応をするそうです。
レストランと言えどサービス業。
「おもてなしの心」が大切です。
スカイマーク
スカイマークが民事再生法を申請しました。
また、昔のような航空会社2社体制になってしまうのでしょうか。
20年程前、それまで高価格であった航空代を安くしようと、北海道の有志がエアドゥを立ち上げました。
しかし、そのエアドゥも今は全日空の傘下です。
その結果エアドゥの航空代はスカイマークより高くなっています。
LCCという格安航空もありますが、多くが日航や全日空の傘下です。
またLCCは価格は安いけれど、時間通りの飛ばない事も多く、仕事ではなかなか使えません。
国土交通省は3極としてスカイマークを捉えていましたが、結局見放しました。
新聞記事を見ると官庁と政治家の思惑が垣間見えます。
現在は新千歳からの航空代金は以前と比べれば安くなりました。
これからも低価格が維持されるのでしょうか。
また、高い「北海道価格」が復活するのではと心配です。
おもてなし
札幌の街を歩いていると、外国からの観光客を良く見かけるようになりました。
ある資料によると、外国からの観光客には日本独特の「おもてなしの心」が好評のようです。
日本人の「おもてなしの心」は「思いやる心」から生まれて来ていると私は思っています。
その「思いやる心」は昔からの日本の住宅事情や生活環境で育まれたのかもしれません。
昔の日本の住宅は狭く、その上に襖や障子で仕切られていました。
中の様子を伺おうとすれば伺えますが、あえて知らない振りをします。
ひそひそ話をしていれば、聞いてほしくないのだと思い聞かないようにします。
狭いところで暮らしているから生まれる相手を「思いやる心」。
それが日本人独特の「機微」を生み出し、「思いやる心」そして「おもてなしの心」が作られて来たのかと考えます。
ところが最近住宅事情は変わりました。
住宅の防音性能も高まり、部屋も個室生活になり、人に関心を持たなくて済む生活になってきました。
もしかしたら、これから日本人独特の「思いやる心」も変化してくるのかもしれません。
少し心配です。
雑用
ある本を読んでいたら「雑用」という言葉が気になりました。
その意味は「こまごまとした用事」
取るに足らない用事というニュアンスもあります。
反対語はなんと言うのでしょう。
調べても明確なものはありません。
自分がしたい事や仕事がその反対語と言えるのでしょうか。
雑用と言うと、掃除や洗濯、皿洗いなど日常的な事まで指す事もあります。
しかし用事に「雑」というものはありません。
全て必要な事です。
「雑」というのは「心が雑になって用を為す」から雑用というのでしょう。
1つ1つ心を込めて事を為せば出てくる言葉でありません。
お寺や、稽古事での修行の時は掃除、洗濯、皿洗いをさせられます。
それぞれの仕事を心を込めてこなしていく。
それにより心が養われていく。
そう考えて毎日を過ごせば、雑用という言葉は無くなります。
以上の事は自戒の意味を込めて書きました。
器用貧乏
「器用貧乏」という言葉。
ご存知だと思いますが、これは「色々なことに興味があり、それなりに上手くこなすことが出来るが大成しない」という意味です。
色々な資格取得に挑戦して、多くの資格を持っている人がいます。
また、何かに興味を持ち挑戦し、それなりの事は出来るようになるけれど、また他のものに興味を持ってしまう人がいます。
もしかしたら、私もこの部類かもしれません。
色々な分野に興味があって、それなりの知識を習得している人は、営業向きかもしれません。
そのような人はお客様の嗜好に合わせて、どのようにも話を合わせることが出来ます。
しかし、経営者となるとそうではありません。
1つのことに突き詰めて挑戦し続ける集中力が必要です。
経営するの中で壁にぶつかった時、それを乗り越えようと努力をする。
根気と集中力が必要です。
しかし関心が広く、多くの事に興味を持っている経営者は、新規事業と称して他の事に手を付けてしまいがちです。
それでは結局、共にダメで倒産してしまう。
経営者を目指した時は、自分の全ての趣味を捨てて経営に集中する。
この気構えが大切になると思います。
笑顔
昨夜、身丈会の勉強会があり、18名程の人が集まりました。
今回は中国重慶にある「重慶行知教育集団董事長」の呉安鳴さんの講演内容を皆で読みました。
私が昨年6月に中国杭州で開催された中国盛和塾に参加した時、特に感銘を受けた呉安鳴さんの話です。
その時の内容を身丈会の皆さんに読んでいただき、その感想や思いを聞きました。
色々な意見が出ました。
少し否定的な意見もありました。
ただ、皆さんが一応に感心した呉さんの言葉があります。
「礼儀は人の道徳が外に表れたもので、他人を尊重すれば必ず報われます。
笑顔は最も美しい紹介状です。」
この「笑顔は最も美しい紹介状です」という言葉は特に心に残りました。
判断と決断
経営者の中には決断がなかなか下せられない人がいます。
現状を判断することは出来、するべきことも分かっていても動かない。
これは判断力はあっても決断力がないからです。
決断力がない経営者に見られるのは、「失敗したら大変だ」「責任を負わされる」という自己保身があるようです。
一流大学を出て頭が優秀な経営者は判断力はあります。
頭がいいと先の先まで考えることが出来ます。
しかし同時に失敗した時のことを考えがちです。
「判断」とは起きている事実を確認することです。
「決断」は退路を断ち決定すること。
そこには実行が伴います。
判断力はあっても決断力がない。
結局現状維持のまま。
そんな会社が多いように思います。
変節
私は時々妻と外食します。
美味しい店を見つけると、人に教えたり連れて行ったりもします。
そんな店もある時「あれ味が変わったかもしれない?」と感じることがあります。
また、親しくお付き合いしている人がいても、ある時「この人の考え方が変わっちゃったのではないか?」と思うこともあります。
でも、もしかしたら店の味や親しい人の考えが変わったのでなく、自分が変わっているのかもしれません。
美味しい店は相変わらず繁盛していたり、親しい人はいつも人に囲まれています。
相手は変わっていないのです。
自分が変節している。
そのことに気付かないと独善的な考え方になりがち。
最近気をつけねばと思っていることです。
経営者
昨夜、盛和塾の新年会で稲盛さんのDVDを見ました。
稲盛さんの話に、改めて納得。
経営者について語っています。
1.感動出来る人でなければ経営者になれない。
2.積極的な行動ができなければ経営者になれない。
きれいな心だけではダメである。
3.ぼやきを口にするだけで経営者失格である。
愚痴、不満は禁句である。特に従業員も前では。
4.素晴らしい考えもそれを数字に置き換えなければ経営にならない。
5.自社の経営環境が悪くても、それを神様が試練を与えている。励ましてくれていると考えてみる。
そうすれば、ぼやきも愚痴も口に出さず経営に挑戦していける。
その同じ環境が受け取る人によって良くも悪くもなる。
それを契機により大きな飛躍がある。
そのような話でした。
楽天的で、ものごとを善意にとる。
そのような人は経営者に限らず、人生で成功する人ですね。
生き方
人の生き方を示す本やことわざは沢山あります。
論語の中にも有名な一節。
「私は十五歳で学問に志し、三十になって独立した立場を持って、四十になってあれこれ迷わず・・・」という言葉もあります。
ある日の新聞にギリシャの哲学者クレアルコスの言葉が紹介されていました。
「少年の時は良き態度を学び
青年の時は感情を制御することを学び
中年の時は正義を学び
老年になってからは良き助言者となることを学ぶ
そして悔いなく死ぬ。」
この言葉を読んで自分を振り返ってみました。
少年の時は良き先生や大人のおかげで、今の自分の人としての基本的な態度を学びました。
中年の時は本を読み、経験して、何が正しいかを学びました
ただ青年の時は感情を制御することは難しかったように思います。
感情のままに行動していた気がします。
今、老年になってからは良き助言者となることを学ぼうと思います。
それでも青年の時、学び切れなかった感情を制することがまだ不十分の自分がいます。
死ぬまでこれを学びながら生きていくことになりそうです。
三将
昨日探し物をしていたら、昔読んだ本の抜粋したメモが出てきました。
その本の題名は「太公望」です。
その中から抜粋していた部分を紹介します。
「将」には「礼将」「力将」「止欲の将」の3将があります。
「礼将」とは冬に暖かい毛皮を着ず、夏に扇を使わない。
雨が降っても傘を差さない。
自ら礼を持って兵士と苦労を共にする将。
「力将」とは険悪な道、泥濘の道を行軍する際に、必ず車から降りて歩行する。
自らの力を尽くして兵士と苦労を共にする将。
「止欲の将」とは兵の宿泊場が定まってから自らの宿舎に入る。
兵の食が行き渡ってから自らの食事を摂る。
軍中、火を燃やさないときは自らも燃やさない。
欲望をとどめて兵の苦労を知る将。
太公望という人は中国・周の文王と武王に仕えて、優れた軍略で殷王朝を打倒した軍師です。
太公望は「六韜(りくとう)」という兵法書はを残しています。
その1つが「虎韜」で、俗に「虎の巻」と言われています。
兵法の極意として「虎の巻」という言葉は今でも使われています。
「三将」の教えは組織の上に立つ者の心得として、今でも通じると思います。
集う
最近気になっている言葉で「群れる」と「集(つど)う」があります。
人との付き合いは苦手と思っている人も、時として多くの人と交わりたいものです。
賑やかで楽しそうな集まりに行きたくなります。
中高生のような多感な年代は、時として夜に寂しくなるとツイ明るい街中に出て行くことがあります。
そしてお互い寂しそうな者同士が集まります。
そのような状態を「群れる」と言います。
「群れる」と主体性のない行動になりがちです。
社会人のグループや団体にもそのようなものはあるように私は思います。
「集う」と「「群れる」との解釈の違いは色々あります。
ここでは私なりの解釈をしてみます。
「集う」には目的とする対象があります。
人はそれを求めて集まります。
そこにあるのは個々人の主体性。
求める目的があるわけで、そこには学ぶ姿勢があり前向きです。
前向きで学ぶので楽しくなり正の連鎖が起きます。
反対に「群れる」は目的がありません。
主体性がなく、他人や雰囲気に流されます。
互いの傷をなめ合うだけで終わります。
集う人は他人の傷を慰めつつも、同時にプラス思考で問題解決しようとします。
人は辛いことが多いと慰めを求めます。
それは自然なこと。
その状態を良き方向に向かう為には人の力も必要です。
良き人の「集い」こそが人を成長させると思います。
仕事を信じるな
昨日私が処理した仕事を、今朝自己チェックしたところ、間違いが2件ありました。
単純なミスで、普段は発生しないはずです。
ガッカリです。
何故かなと反省してみると、言い訳かもしれませんが、体調が本調子でなかったせいかと思います。
そんな時、昔に人から言われたことを思い出しました。
「人は信じても、仕事は信じるな!」
優秀な人で、仕事に間違いはないと信じていても、体調が悪い時は間違えるかもしれません。
また、真面目な人も、もしかして誘惑に負けて仕事で不正を犯すかもしれません。
会社で不正が発生した時、会社の上司が「◯◯さんを信用していたので・・・」と言い訳をしているのを良く見ます。
それは上司がするべきチェックを怠っていた言い訳にすぎません。
チェックが厳しいと、時に部下から「私を信用しないのですか?」と言われることがあります。
しかしその時こそ、「人は信じても、仕事を信じるな」と肝に銘じながら職務遂行するべきです。
風邪
私はここ1週間程風邪を引いていました。
先週の7日の午後から昨日まで会社を休みました。
今日から出社です。
今年はインフルエンザの流行が早いと言われています。
私の場合、熱は37.5度程でインフルエンザでないとは思います。
昨年末は色々予定もあり、気が張っていました。
気が張っていると風邪は引かないものです。
「正月明けは風邪を引くかも?」と思っていましたら案の定引きました。
生活環境も医療も整っていなかった昔、風邪は人の死亡原因の1つでした。
ネットで調べると「風邪を<u>引く</u>」という言葉の意味が書かれていました。
「吹く風が運んでくる『邪気』を体の中に引き込んでしまう」ことだそうです。
平安時代は風病(ふうびょう)と言われていたようです。
私の風邪はなんとか収まりました。
ただ、それの後遺症でしょうか、臭覚が機能しなくなっています。
食事をしても、しょっぱいとか、甘いは分かるのですが、香りがしません。
何を食べても皆同じような味で、美味しくありません。
回復するのに少しかかるのでしょうか。
皆さん、風邪を引かぬようにご自愛を!
機心
先日、お坊さんである松原泰道さんの本を読んでいると面白いことが書かれていました。
少し紹介します。
「荘子」に書かれていることです。
「子貢(孔子の高弟)が旅先で農夫が井戸から水を汲み上げては水田に運ぶのに出会います。
子貢は、労力を省く為に、テコの理を応用したハネつるべの使用を教えます。
詳しい説明を聞いた農夫は、初めは感心していましたが、子貢の話が終わると激怒して反論します。
『私は、自分の先生から言われたことがある。
機械を使うと、人間は機械的になる。
機械のような心の持ち主となる。
そして機械的に行動する。
素朴さを失う。
精神の制御が不安定になる。
すると、正しい思慮分別ができなくなり、想像力をなくす、と。
私はハネつるべを知らぬことを恥じるより、それを使う人間になることを恥じるのだ」
この話を聞いた孔子は「今の世にも、そうした尊い人間がいるのか」感じ入りました。
鈴木大拙という仏教学者はこの話を引用して機械に頼る心を「機心」と名付け、機心は想像力を失うと言いました。
現代に生きる私達は便利な機械に囲まれています。
便利な機械が増えるにつれ、大事なモノを失っている。
そのような気がします。
欽ちゃんと王さん
日経新聞に毎日「私の履歴書」が掲載されています。
昨年の12月は欽ちゃん(萩本欽一さん)で今月は王貞治さんが書いています。
欽ちゃんは素晴らしいコメディアンであり、王さんは偉大な野球選手です。
私が大好きな人達です。
「私の履歴書」を読んで2人の人なりが分かります。
2人の「私の履歴書」は切り抜いてファイリングしています。
欽ちゃんの話は毎回ホロリとされました。
欽ちゃん生き方には「2歩下がって」という考えが一貫してあります。
その一文を紹介します。
「僕は『ダメな子』だった。
『できる子』と同じ土俵で競争しても勝ち目はない。
だから僕の信条は『2歩下がって』
下がった場所で自分なりに人のやらない努力をして、必死でがんばる。
やがて先を走っている「できる奴』に追いつき、追い越すことだってできる」
王さんの「私の履歴書」はまだ4日分ですが、感じ入る話が書かれています。
私は以前から王さんは野球界の紳士だと思っていました。
その理由が書かれています。
大リーグの通算本塁打記録を超した756号が出た時です。
「打った瞬間万歳はしたが、すぐに相手の鈴木康二郎投手のことが気になった。
そして淡々とベースを回った。」
そこには「万事控えめ」というお父さんの教えがあったそうです。
後日、王さんがワシントンのホワイトハウスに表敬訪問した時、パウエル国務長官が、この時のビデオを見て「スイングも見事だが、はしゃがず、おごらずベースを回る姿に気品がある」と言ったそうです。
やはり王さんの紳士たる姿は、見ている人は見ているのですね。
これから王さんの話が楽しみです。
1つの目標
あけましておめでとうございます。
長い正月休みが終わりました。
今日から仕事始めです。
休みの間は、遊びにきていた4人の孫達の相手をしながらも、小説の本を3冊読みました。
もう1つ挑戦しし始めたのが「21世紀の資本」という本です。
今評判の本ですが600ページ程の厚い本で読み終わるのにしばらくかかりそうです。
「富の格差」の要因を探る本です。
私は読む速度が遅い方です。
また難しい本を読むと眠たくなります。
それでもなんとか今月中に読み終わりたいと思います。
年の初めから1つの目標が出来ました。
御用納め
今日は26日。
御用納めというところも多いでしょう。
私の事務所も仕事納めです。
午前中にある中学校で集まりがあり、そこで少しお話をして、それで全ての仕事が終わりになります。
午後は事務所清掃します。
この1年は公私ともに色々な事がありました。
私的には喪中という事もありました。
それでも多くの人との出会いもあり、充実した1年でした。
来年は「手つかず」で「真新しい」、そして皆が平等に与えられる1年。
新しい1年、歳を取りますがワクワクした気持ちで迎えたいものです。
サンタクロース
今朝のラジオで、アメリカ軍とカナダ軍で作るNORAD(北米航空宇宙防衛司令部)が24日からサンタクロースの追跡を開始したというニュースが流れていました。
普段は弾道ミサイルの警戒監視をしている空軍の部署です。
ニュースによると、NORADがサンタクロースの追跡を始めたのは、59年前に子どもからの間違い電話を司令官が受けて、サンタクロースの位置を教えてあげたことがきっかけとなり、毎年行われているそうです。
また、100年以上前に「サンタクロースはいるのですか」という質問に答えたアメリカの新聞社ニューヨーク・サンに掲載された社説は有名な話です。
どちらも子供の夢を壊さないように、そして自分が子供だった頃の思いも忘れず、大人が応えています。
アメリカ人のユーモアと心の余裕を感じさせます。
ちなみにサンタクロースは6トンのプレゼントをトナカイのソリに乗せて、日本時間の24日午後6時すぎ、北極上空を出発したそうです。
幸せ上手
今日は12月24日クリスマスイブです。
色々な人達がそれぞれにクリスマスを楽しむことでしょう。
豪華なパーティーをする人も、2人でささやかな食事会をする人もいるでしょう。
もしかしたら1人で迎える事があるかもしれません。
私は大人になってもクリスマスが来るとウキウキするのです。
そしてサンタクロースがいると信じる子供達が好きです。
1人1人自分の幸せを感じているのがいいです。
普段は現実的問題を抱えていても、クリスマスは妙に楽しくなれるのです。
そんな時、思うのです。
幸せと感じることが出来るのが幸せなのだと。
幸せな人と言われる人は普段からささやかでも自分の幸せを感じることが出来ます。
そのような人は「幸せ上手」な人なだと思います。
そして「幸せ上手」になれる切っ掛けがこのクリスマスなのかもしれません。
今日、私は家で妻とホットワイン飲む予定です。
テレビ
昨夜放映されたSTV(札幌テレビ放送)の番組「ホットサンド」に私、少し出ていました。
お笑いタレントの「サンドウィッチマン」の番組で、今回は琴似商店街を紹介するがテーマです。
出演の切っ掛けを作ってくれたのは「風船の魔法使いエリサ」さんです。
エリサさんがSTVのディレクターに紹介していただいたのです。
勿論、エリサさんも同じ番組で風船のパフォーマンスを見せています。
番組のことでSTVのディレクターと電話でお話した時、最初は「出演依頼されたら断ろう」と思っていました。
なのですが、ディレクターが来社され打ち合わせの後、「出演してください」と言われた時、つい「はい」と言っていました。
テレビ撮影されたのは11月の下旬。
30分程の収録時間でしたが楽しい時間でした。
サンドウィッチマンの優しい人柄に触れる事も出来ました。
この番組で私は「グルメ王子」となっています。
少し気恥ずかしい称号です。
私が作ったホームページ「琴似観光協会」で「琴似のランチ」というページがあります。
その中で琴似でランチを提供している全ての店67軒の食べ歩きを紹介しています。
称号はそんなところから出てきたのでしょう。
私が紹介したお店は「キッチンしろくま」という今年開店した食堂です。
この店の一押しは「親子丼」
番組でも紹介されています。
店主はまだ30代。
若い店主が頑張っています。
機会があれば一度食べに行ってみてください。
お駄賃貧乏
ある本に「お駄賃貧乏」という言葉が書いてありました。
子供が嫌がる家の仕事や宿題をさせる時、「◯◯したら300円上げる」と言う親がいます。
仕事の対価だと理解しているのかもしれません。
しかし、子供がお駄賃をもらって嫌な家のお手伝いや宿題をすると、「お金=嫌な仕事をするともらえる」という考えになります。
そして作業をする前に金額が決まっているので「如何に楽をして作業を終わらせるか」という思考になります。
将来は給料の範囲しか仕事をしなくなるのかもしれません。
それでは仕事への意気込みも、何かを起こそうという気力も生まれません。
子供の内から、「お金=嫌な仕事をするともらえる」という意識が植え付けられると、「嫌な仕事をしてお金を沢山稼ぐのは嫌だ」となってしまうのではないでしょうか?
「そこそこの生活が出来ればいい」という思いになってしまいます。
そう言えば、私が小さい頃、母から家の仕事をするよう言われた時、「お駄賃ちょうだい」と言ってこっぴどく叱られた事があります。
何気ない子供への甘やかしが子供の性格に大きな影響を与えるのだと考えます。
たくさん喜ばせる
世の中を見渡すと、世のため、人のために大きな功績を上げている人達がいます。
宗教家、科学者、哲学者、政治家、経営者など。
稲盛和夫さんは中小企業の経営者が成功する為にと思い、多くの人に経営の要を説いています。
マザーテレサは一修道女として、貧しい多くの人達を救ってきました。
二宮尊徳は農業を通して国を豊かにしようとしました。
それらの人はたくさんの人が良くなるよう、幸せになるよう努めてきました。
たくさんの人を喜ばせてきたのです。
私も多くの人の為に何かをしたいと思っています。
ただ同時に、もう1つ大切な事があるのではと思っています。
人にはその人を大事にしてくれる人がいるのです。
「たくさん」の人を喜ばせる事も大事ですが、たった1人の身近な人を「たくさん」喜ばせる事も大切なのではないでしょうか。
そのように思っています。
小さな約束
毎日の日常生活の中で約束事は発生します。
仕事やプライベートに関わらず起きます。
仕事での約束事は守らなければ大変なことが起きます。
守らなければ信用を無くします。
納品時期や価格など仕事に関わる大きな約束事はほとんどの人は守ろうと努力します。
ところが小さな約束事はどうでしょう。
例えば「美味しいレストランがありますので今度食事でもどうですか?」「◯◯さんが興味ありそうな資料ありましたので後で差し上げます」「スキーしにいきましょう」など仕事から離れたプライベートの約束事は忘れてしまうことがあります。
私はこの小さな約束事を守ることこそが「その人の信用」を高めるものだと思ってます。
たかが小さな約束事だと思っても、相手が忘れず実行してくれた時は感激するものです。
約束の内容が小さければ小さい程そうです。
逆に小さな約束事を、忙しかったからということで実行しなければ、「あの人忘れているんだな・・・でも、まいいか」「当てにした自分が悪かった」と相手に思われてしまいます。
人は、小さな約束事が守ってくれたと思うと自分のことを大切にしてくれていると感じ入るものです。
小さな約束こそ守りましょう!
投票率
今朝の新聞に衆院議員選挙の結果が一面に掲載されていました。
ここではその結果については語りません。
ただ、投票率が56.98%というのが残念です。
前回平成24年に行われた衆院議員選挙では59.32%でした。
今回の投票の年代別内訳はまだ出ていません。
平成24年の選挙の内訳は20代37.89%、30代50.10%。
それに比べ50代58.62%、60代74.91%と高くなっています。
若い人、特に20代の投票率が低くなっています。
投票権の獲得には、日本でも過去多くの人の苦労の結果得てきました。
それなのにこの低い投票率。
外国では選挙権・投票権が無い国が数多くあります。
それを得る為に戦っています。
一方、先進国といわれる国では18歳成人、そして投票権を認めている国もあります。
日本でも18歳から投票権を認めようとしています。
しかし世間では、このように低い投票率では、投票権を18歳に認めてもどれほどの若者が選挙に行くのかという思いもあります。
ここで大事なのは教育です。
18歳となると学校教育の中で身近な自分の権利として、また選挙の大切さを教えることが出来ます。
それにより、大人としての自覚を持たせることができるかもしれません。
今のままでは若者の選挙離れが益々ひどくなっていきそうです。
何か手を打つべきです。
望年会
昨夜は「身丈会」という勉強会の望年会でした。
私の事務所で25名程の人がそれぞれ食物・飲物持参で参加いただきました。
手作りの「いくら丼」「稲荷寿司」「ピザ」「ケーキ」「パン」その他の食べ物。
飲物はビール、ワインや焼酎、それに「大信州の槽場詰めしぼりたて生酒」一升瓶もいただきました。
18時から始まり21時過ぎまで。
大変楽しい会でした。
今回は身丈会のメンバー以外の方も10人程参加されました。
参加された方々はそれぞれ違うお仕事をしています。
経験も価値観も違う人が一緒に集う。
新しいつながりが生まれるかも知れません。
私が一番楽しんだ望年会でした。
<a href="http://blog-imgs-50.fc2.com/y/a/m/yamachioffice/20141212093151c95.jpg" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-50.fc2.com/y/a/m/yamachioffice/20141212093151c95s.jpg" alt="望年会" border="0" width="120" height="90" /></a>
お客さんの長居
月曜日から昨日まで上京していました。
昨日は浅草寺にお参りに行き、帰りにはいつものように「大黒家」の天丼を食べました。
11時30分頃行くと、一人分が空いていてすぐに座れました。
私の後は満席で店の前は行列。
この店の一番安い天丼が1550円。
結構高いのにも関わらず常に満席です。
また、お客さんは食べたらすぐに席を立ち帰ります。
注文してから食べ終わるまで30分かかりません。
席の回転がとてもいいです。
食べ終わっても長居する人はいません。
お店にとってはいい流れになっています。
飲食店にとってこの回転数というのは大事です。
最近マクドナルドや、ロイヤルホスト、スタバなどに行くと、コーヒー1杯で何時間も席を占有している光景が見受けます。
学生達が教科書を持ち込んで勉強いたりしています。
最近お会いした回転寿司やおにぎり屋の経営者からもお店でもそのような光景があり困っていると聞きました。
また別の経営者の話です。
200〜300円の飲物で何時間も粘っているお客さんがいたので、席を空けるようにお願いしたところ「私はお客だ」と反論されたそうです。
その経営者は「それではお金は入りませんのでお帰りください」と言ったそうです。
飲食店も客商売です。
そのように言い切るにも余程のことがあったのだと思います。
単価の安い飲食店は席の回転数で稼ぐしかありません。
お客さんの長居は死活問題です。
一方お客さんにとっては長居の出来る店を欲しがっています。
学生が勉強部屋変わりに飲食店で長居をするのは論外ですが、それなりの要望はあります
年配の女性はお友達とランチをした後、3時間くらい話が出来るところを探しています。
それが出来る店はそのようなお客さんで一杯です。
店側もそれを考慮して単価の高いランチになっています。
飲食店の経営者は店を守らなければなりません。
自分の店はどのような方針で経営するのか、その為にどういう運営をとるのか、トラブルが起きたらどう対処するのか。
経営者が先頭に立って見せていく姿勢が必要です。
高い送料
昨日、通信販売で売られているシールを買おうとその会社に電話しました。
1枚1000円です。
それを注文しようと思ったのですが、その送料がなんと1480円。
金額そのものからいうと送料は高くないのですが、シール1枚1000円と比較するとびっくりします。
商品より高いのです。
なぜ高いのかを聞くと、その会社の商品は全てヤマト宅急便に依頼しているからとのこと。
封筒に入れて送ってくれれば82円で済みます。
それを言っても受けてくれません。
商品より高い送料なのにそれが不思議と思わない。
会社としては送付作業上業者を1カ所に決めておけば効率いいのかもしれません。
でもこれは会社の自己都合。
お客様の立場に立って考えてほしいものです。
たかが1000円+1480円=2480円を払うのですが、やはり心地良くないです。
この会社は菓子製造販売の大きな会社です。
大きすぎてこんな小さなことまで気が回らないのかもしれません。
シール購入は止めました。
考える
「自分で考える」独自性。
それと反対の意見を聞く「余裕」と「勇気」。
そんなことが大切と私は改めて思っています。
ある人はモノを見て「三角形だ」と言います。
またある人は「違う!円形だ」と言います。
どちらも正しいのです。
でも実態は「円錐形」
真横から見れば三角形。
真上から見れば円形
それぞれの見方からすればどちらも正しいのです。
でも実態は違います。
ものごとは決めつけると視野が狭くなります。
反対の人の意見も聞きながら、そして自分で考える。
今の時こそ大切なことのように思います。
45周年
昨日あるお店から葉書が届きました。
毛筆で書かれたその葉書は、あるスナックの2代目ママからです。
今月の8日に開店45年を迎えるとのこと。
2代目ママは初代の娘さん。
このスナックは私の父が通っていて、それを私が引き継いだようになっています。
とは言っても私は最近、お付き合い以外に飲みに行くことがなく、このスナックにもご無沙汰しています。
それにしても45周年も続くスナック。
大したものです。
8日は残念ながら出張と重なりお祝いに行けません。
お花とメッセージを送ることにします。
帰ったら顔を出しに行って来ます。
そして父の思い出話をしてきます。
痛みを伴う改革
今日2日は衆議院議員総選挙公示日です。
選挙にむかって各党党首から選挙への公約、主張がテレビなどで述べられています。
それは耳に聞こえのいいモノばかりです。
どの党も「痛み」についての話はありません。
日本の財政は現在、大変厳しい状況にあります。
国の借金は1030兆円を超しています。
しかしそれを解消するための施策が明確にされていません。
今朝の新聞に「アメリカ格付会社ムーディーズが日本の国債の格付を1段階引き下げた」との報道がありました。
「Aa3」から「A1」となり、日本の国債の格付けは中国や韓国より低なっています。
今まで日本の国民も「痛み」を先送りし続けてきました。
今が良ければ嫌なことは後回し。
政治家はそれがわかっていたから「痛み」を伴う改革の声を出してきませんでした。
「日本の財政は大変な状態で改革しなければならない」という総論は皆が賛成します。
しかし「自分のところ」の各論になると、「それは反対だ」「嫌だ」となります。
今は、将来のため、自分達の子供や孫等の若い人達のため何をしなければならないか。
そして国民が改革に伴う「痛み」を直視し、それを受け入れる心構えをしていかなければならない時。
選挙を迎えるにあたってそう思います。
選挙には必ず行きましょう!
税金
以前このブログで、利益1億円を得て、6000万円を内部留保した会社の話を書きました。
6000万円を内部留保したということは、4000万円の税金を支払ったということです。
社員5名の会社が凄い金額の税金を支払ったものです。
1人の若者が起業したおかげで4000万円の税金が生まれたのです。
素晴らしい社会貢献です。
得てして税金は「取られる」モノという観念があります。
しかし税金を「支払う」と考え、それが社会貢献になると思えば、税金に対する考えも変わってきます。
勿論、その税率にもよります。
税金で半分以上の利益が無くなると、経営者のモチベーションが下がります。
時として儲かっているところから沢山の税金を取ろうと考えがちになりますが、そうするとリスクを背負い起業に挑戦しようと思う人も減少します。
先ほどの1億円の利益を出した会社も、税率が40%でなく60%だと、6000万円の税金を支払い、残り利益が4000万円になります。
それでは働く意欲も下がります。
現在、国内では消費税増額や法人税減額等税金に関する問題がクローズアップされています。
税金は「嫌なモノ」と考えるのでなく、必要なモノ。
「喜んで税金を支払う」仕組みを考えて見るのもいいかもしれません。
楽しい日
昨日は楽しい1日でした。
昼には素敵な女性と食事をし、夜には気さくな仲間とお酒を飲みました。
お酒を飲んだところは私の隠れ家である「おでん屋」。
狭い店のカウンターに5人が座り、美味しいおでんと酒。
それに楽しい話。
つい飲み過ぎてしまいましたが、充分満足の1日でした。
ただ後悔しているのは、今朝イギリスに帰る娘を車で送っていけなかったことです。
二日酔いでした。
今日は金曜日。
恒例の「ご苦労さん会」を妻と二人で自宅でします。
今夜は飲み過ぎないようにします。
新規事業
先日Googleの「インドアビュー」をすすめに「認定パートナー」会社の人が来社ました。
「ストリートビュー」は知っていましたが「インドアビュー」というのは私は知りませんでした。
「インドアビュー」は「ストリートビュー」の室内版です。
お店や施設の内部を「ストリートビュー」と同じように360度展開で見せます。
集客を目的とするお店にはいいモノかもしれません。
Googleという会社は検索から始まって、地図、翻訳、ショッピングなど自社の強みを伸ばしつつ事業を拡大しています。
楽天もそうです。
楽天市場から始まって、「旅の窓口」を買収して「楽天トラベル」。
アイリオ生命を買収して「楽天生命」。
その他にも「楽天オークション」や「楽天ブックス」「楽天カード」もあります。
「楽天ダイニング」という事業を始めました。
これは「食べログ」のような店舗案内機能に「楽天カード」という決済機能を結びつけた新しい事業を展開しています。
私のレンタルオフィスに入居している会社がその札幌地域を担当しています。
自社の事業を拡大展開出来るのはGoogleや楽天のような大きな会社ばかりではありません。
小さな会社でも自社の強みを見つけること。
それを何と結びつければ、どのような新規事業になるのか。
新規事業は「発明」ではなく「発見」です。
それに気付いた会社が発展するのではないでしょうか。
内部留保
私が運営する「札幌オフィスプレイス」というレンタルオフィスは7年程前に開業しました。
今まで多くの人が起業の出発点として利用いただき、ここを飛び立っていきました。
時には入居者の人達とランチを食べながら、お酒を飲みながら夢を語りました。
そんな時「起業メンター」である私は「経営」についてのウンチクを語ったりします。
その語ったことがどれほどの効果があったかわかりません。
昨日「札幌オフィスプレイス」OBのAさんが訪ねてきてくれました。
5年前に入居入していただいた方です。
少しお話した時、「山地さんから教えられたように内部留保を高めています」と言ってくれました。
昨年の利益が1億円。
税金を払った残りの6000万円は内部留保にしていますとのこと。
起業して6年で利益を1億も出せる会社にされたのも嬉しかったですが、私が話したことを忘れず、内部留保を高めていると言ってくれたことが嬉しいです。
話した本人である私が、話したことを忘れているのに。
税金を払うのがもったいないと言って「節税」みたいなことをすると内部留保が出来ません。
内部留保が高まると会社は安定します。
投資もしやすくなります。
「税金は経費の1つとして考える」
これも稲盛和夫さんの教えです。
これからもAさんの会社は益々成長していくことでしょう。
今後が楽しみです。
本の読み方
本を読む。
歳とともに読む量が減ってきた気がします。
老眼、集中力の減退、それに眠気。
そして本をしばらく読まないと、益々読解力が落ちてきます。
読解力が落ちないよう本を読もうとすると、どうしても興味ある本に偏りがちになります
私の場合もどうしても偏った分野の本ばかりを選んでしまいます。
本当は色々な分野の本を読めばいいのでしょうが、興味がないと読書が進みません。
昔、ある人がテレビで自分の本の読み方を話していました。
定期的に本屋に行って、各分野の本を買いまくるそうです。
哲学、宗教、経済、科学、社会、小説、芸能関係、グラビア、それに俗に言うエロ雑誌まで買います。
自分の考えを偏らないための読書方法だそうです。
当時私は「その方法はいいな」と思ったのですが、読みこなすエネルギーは大変なモノです。
私には無理でした。
でも、広く色々な分野の本を読むということは自分磨きにはいいことです。
私は今度、今まであまり読んだことのない科学分野の本に挑戦してみようと思います。
眠気に負けず頑張ります。
そして読む時は、眠くならないよう体調を整えて臨みます。
サービス業の価格
商売をする時、製造業は製品を作って売ります。
販売会社は商品を仕入れて売ります。
どちらの商売も現物があります。
現物があるから価格は決めやすいのです。
ところが現物がないサービス業は価格決めが難しいものです。
またどこまでが無料で、どこからが有料なのかの線引きもしづらい。
客寄せのためと思い、ついついお金をいただくべきところまでサービスしてしまう。
元来サービスの意味には無料と言う意味はありませんが、日本では「それくらいサービスしろよ!」と言われるように無料という意味があります。
でもそれでは売上に結びつきません。
弁護士や司法書士などの「士業」の人達は協会などで価格の取り決めがあり、価格提示しやすいです。
しかしそれ以外のサービス業は自分で決めなければなりません。
そしれ「価格」と「有料・無料の境目」は最低、自分で決めなければダメです。
「価格」は高めに設定するべき。
「価格」は下げることは出来ても、簡単に上げることは出来ません。
「有料・無料の境界線」を決めるにはまず、自分のサービスのキーポイントは何かを明確にすることです。
商品価値のあるそのキーポイントとなるサービスに導くために、導入部分でどこまで無料で教えるか、その範囲を決めます。
それともう1つ、常にブロクでもFacebookでも、何かを発信して自分を売り、その仕事では一目置かれる存在にすることです。
自分が一段上になってお客様と話を進めると、設定されたサービス内容にも納得していただけます。
先生と言われる立場になるのです。
お金を払うべきと思わせること。
稲盛和夫さんが言う「値決めは経営」
その通りです。
朝三暮四
今朝の日経新聞の「春秋」にあった言葉を紹介します。
「朝三暮四(ちょうさんぼし)」
この言葉を「春秋」では次のように書いています。
「昔、宋の国に多くの猿を養っている人がいた。
急に貧しくなり、餌のドングリを減らすことにした。
朝三、夕四でと猿に言うと立ち上がって怒る。
では、朝四、夕三ならどうかと聞くと、みな伏して喜んだ。
目先の違いにとらわれるのを笑う故事である」
これと同じように、傍目から見れば笑われるようなことが今の日本で起きている。
そんな気がします。
遠い将来のことではなく、近い将来でさえ目をそらしています。
今さえ良ければいい。
そんな風潮が心配です。
高倉健さん
高倉健さんが亡くなり、テレビでは関連ニュースが流れています。
私の学生時代、健さんの映画を見て出てくる男達は、胸を張って、肩で風を切って出てくる人が多かったと言われます。
当時は政治的に右翼にも左翼と言われる人にも大人気でした。
ニュースの中で紹介された座右の銘
「往く道は精進にして 忍びて終わり悔いなし」
この言葉は胸を打ちました。
国民栄誉賞の話も出ています。
私は賛成です。
それにしても健さんが死んだと言うニュースは寂しいニュースです。
素人考え
最近マスコミの報道について改めて思うことがあります。
新聞雑誌やテレビラジオなどのマスコミは「先に結論あり」の報道が目立ように思います。
景気の動向、経済の動き、政界の動き、中国や韓国、またアメリカに対する観点、慰安婦問題、原発再開など多くの事柄が私達の周りに発生しています。
それらの問題にに対して、初めから先に結論があり、結論に導くための情報を流していように思います。
私達はその報道に左右され、「声の大きい」報道に引っ張られてく恐れさえあります。
以前は1つの政治体制が煽動することを恐れていましたが、今はマスコミが煽動することを恐れます。
人は自分は中立と思っても傍目から見ると偏っているかもしれません。
でも、それでもいいと私は思います。
マスコミに煽動されさえしなければ。
人それぞれ考え方は違います。
自分なりの考えを持っていくことは大切です。
起きている状況をあやふやな情報に右往左往されず観察する方法。
私が心がけていることがあります。
「定点観測」です。
例えば景気の動向がどうなるかを見る時、地下鉄の吊り広告の増減や、飲食店やデパートの人の混雑状況を見てみます。
今の時期ですと、忘年会やクリスマスの吊り下げ広告が増えているか、飲食店は行列ができていたり、デパートが混雑しているか。
そうなら、皆の財布の紐が緩んで少し景気がいいのかな?
マスコミでは地方は景気が悪いと言っているけれど違うのではないか?
また日本の財政状況を踏まえて円と株価の動きを見ます。
今までは円安と株高が連動していたのに、ここへ来て逆の動きをしだした。
株が急激に下がっても円が高くならない。
以前は株が下がれば円高になっていたはず。
そんなところから今後の景気の動向に対して自分なりの予想が立ちます。
マスコミやインターネット等の情報が溢れている時代。
「素人考え」でいいです。
情報に流され、誤った方向に煽動されないためにも、自分の「定点」を持つ事は大切と思います。
アビガン
今、西アフリカを中心にエボラ熱が拡大しています。
その中で、ある「治療薬」が注目されています。
その「治療薬」は富山化学工業が創ったインフルエンザ治療薬「アビガン」です。
ギニア政府は今月内にも、「アビガン」を実際の患者に投与する臨床試験を始め、12月にはその結果が発表されるとの報道がありました。
正式に認められれば世界初の「治療承認薬」となります。
この富山化学工業は富士フイルムの傘下にあります。
日経のネットニュースで詳しいことが書かれていました。
富山化学工業は元々は大正製薬の傘下でした。
当時赤字会社であった富山化学工業を富士フイルムは1300億円で買収したのです。
その富山化学工業が創った「アビガン」が世界中から注目され、親会社である富士フイルムの株価はうなぎ上りです。
こうして見ると、買った富士フィルムと売った大正製薬の動きについて考えさせられることがあります。
「アビガン」は今年の3月にインフルエンザ薬としての製造販売承認を受け販売されました。
「アビガン」は他のインフルエンザ薬とは仕組みが違います。
タミフルなどの従来の薬は、ウイルスを細胞内に閉じ込めて増殖を防ぎます。
それに対して「アビガン」は細胞内でウイルスが遺伝子を複製すること自体を阻止します。
富士フイルムは「アビガン」のところを、研究段階から注目しました。
「アビガン」という薬に対する富士フイルムと大正製薬それぞれの経営者の認識判断の違いが「金の卵」を手にした会社と手放した会社の違いになってきました。
報道によれば製薬とは門外漢だった富士フイルムが成功したのは、明確なコンセプトを持っていたためのようです。
富士フイルムは製薬分野に進出する時、既存の大手製薬会社に勝つため、「がん」「認知症」「感染症」の3大分野に絞り、他にはない仕組みで治療する医薬品開発を狙ったそうです。
「素人」や「門外漢」は参入するその業界の「常識」や「習慣」等にとらわれず、素直な目で見ることが出来ます。
この「アビガン」が正式に治療薬として認識されれば、大きな朗報となるでしょう。
「自分が一生懸命苦労して経営していた会社が、別の人が経営したとたん業績が上がることはよくある」
これは昔に父が話してくれた言葉です。
納得します。
「V・W」
2〜3日前から稲盛和夫さんと山中伸弥教授が対談している本を読んでいます。
題名は「賢く生きるより、辛抱強いバカになれ」です。
興味深いことが沢山語られています。
この本の中で山中教授が語っていることを1つ紹介します。
若い頃アメリカの研究所に留学している時の話です。
その研究所の所長が20名程の研究者達を集めて話をしましたした。
「研究者として成功する秘訣は「V・W」だ。
「V・W」さえ実行すれば君たちは必ず成功する。
研究者にとってだけでなく人生にとっても大事なのは「V・W」だ。
「V・W」は魔法の言葉だ」
Vはビジョンで長期的な目標。
Wはワークハードで一生懸命に働くことです。
研究者にとっても人間としてもこの2つが大事なのです。
この言葉は稲盛さんが常に言う「事業の目的意義を明確にする」「誰にも負けない努力をする」と同じことです。
東西、国に関わらず、大事なことは共通している。
改めて納得しました。
リスクを取る
今、「リスクを取らないリスク」という本を読んでいます。
この題名に引かれて買いました。
何かに挑戦する人と、何もしない人。
人は大きく分けると、この2つに分けられるのではないでしょうか。
リスクを負いながらも何かを始める。
時には失敗もあるけれど、大きな成果も生まれます。
そのような人達によって世界が広がってきたのです。
起業する人は自分の夢を求め、リスクを負いながら人一倍努力します。
その結果、大きな会社を経営し、人がうらやむ生活をしるかも知れません。
「あのアイディアは昔に俺も考えついたのだ」
「学生時代、俺の方があいつより成績は良かったんだ」
何も挑戦しないで、そんなことを口走る人がいます。
「だったらあなたも挑戦してらよかったのに」とつい言いたくなります。
リスクを取って挑戦した人と、挑戦しない人の結果が「格差」となって現れます。
「起業する人」「1人海外に出て行く人」「新しい研究をする人」「新規事業を始める会社」
もっと身近で言えば「家を建てる人」「資格の勉強をする人」「投資する人」
様々の挑戦が身の回りにあります。
これからは「リスクを取る人」と「リスクを取らない人」の差は益々広がっていくと考えます。
年を取ってから、「俺だって出来たのに・・・」とつぶやく。
そうはなりたくないですね。
中田翔選手
昨日facebookを見ていると、日本ハムの秋季キャップ中の中田翔選手を映した動画が紹介されていました。
あるファンが撮影したものです。
それを見ていると無性に腹立たしくなりました。
練習に中田選手が後輩の杉谷内野手を小突いたり、蹴っ飛ばしたりする姿が映っています。
いたずら程度でなく執拗に繰り返しています。
それに杉谷内野手は黙って耐えています。
しまいにコーチから注意を受けていますが、馬耳東風。
その後は後ろ向きで舌を出している中田選手の顔が映っています。
私は昔から、地位や立場を笠に着て、威張ったり横柄な人間が大嫌いです。
私は日本ハムのフアンの1人です。
ですからこんな選手が日本ハムの4番打者と思うと情けなくなります。
野球が上手いだけで小さい頃から甘やかされてきたのでしょう。
小さい頃、私は巨人フアンでした。
その頃は長島選手や王選手がいた時代です。
その巨人の選手に対して、当時巨人軍のオーナーだった正力松太郎氏が「巨人軍選手は常に紳士たれ!」と言われました。
子供達が憧れる野球選手に対する諌めの言葉です。
この中田選手がこのままでいると来年の日本ハムの優勝はないでしょう。
野球チームも会社も同じです。
トップがどのように対応するか。
実績を上げるためにはチームワークが大切です。
それを保持するために毅然とした態度が取れるか。
日本ハムトップは「大善は非情に似たり」が出来るでしょうか。
大事なことを言い続ける
昨夜勉強会があり、そこで稲盛和夫さんのDVDを見ました。
17年前に講演された時のDVDです。
当時、稲盛さんは禅寺で得度したばかりで、坊主頭のまま。
初めて見る稲盛さんの坊主頭は新鮮な感じがしました。
その講演での話です。
禅寺で得度する時、10の戒律を守ることを約束されます。
1つずつ「守れるか!」と問われ、その都度「守れます!」と答えていきます。
しかし10の戒律を守るように約束されたにもかかわらず、日常の生活では戒律を外す行いをしてしまう。
それでもまた反省し戒律を守ろうとする。
そしてまた気付けば違うことをしている。
その繰り返し。
それでも「戒律を守ろうとして生きる」ことと「戒律を守ろうとしないで生きる」とでは結果大きな違いが生まれるます。
そのような話を聞いて思うことがあります。
父親として家庭で子供に対して、また社長として会社で社員に対して「するべきこと」を話すことがあります。
「誰にも負けない努力をしよう」とか「謙虚に生きよう」とか。
でも時として、話している自分も守れていないのに気付くことがあります。
自分が守れないのに子供や社員に対して「守ろう」と言うのはおかしいと言われることがあるかもしれません。
また自分自身がそう思うと何も言えなくなります。
でも、端から守れない自分がいるけれど、大事なことは言い続ける。
守ろうとして生きるのと、諦めて何も言わないのどでは大きな違いは生まれます。
「私もなかなか守れないけれど、一緒に守る努力をしていこう」と言い続けることが大事。
そのように思います。
毛糸巻き
札幌は今週、雪の予想が出ています。
手袋も欲しくなってくる季節です。
小さい頃、母は毎年手袋を編んでくれました。
編んでくれるのですが、毛糸なのですぐ穴が開きます。
それをまた繕ってくれながら一冬使います。
この手袋を編む前には毛糸巻きの作業があります。
当時、毛糸は大きな輪になったものが撚られて売られていました。
手袋を編む前、それを毛糸玉にしなければなりません。
その作業は2人掛かりです。
1人が大きく輪になった毛糸に両手を通し、もう1人がその毛糸を取り出して毛糸玉を作っていきます。
我が家ではこの役目がなぜか何時も私でした。
長い間母も前に座らされ、突き出した手もだるくなります。
そんな時は仕方がなく母と色々な話をすることになります。
普段は面と向かって母と話をすることなどありません。
何を話したか覚えていませんが、今の季節は懐かしくなります。
童謡の「母さん」にある「かあさんは 夜なべをして 手ぶくろ編んでくれた♫」の歌詞のところを歌うと少しウルッとしてしまいます。
母との毛糸巻き。
私と同じような思い出がある人は多いのではないでしょうか。
3だけ
今朝のNHKのラジオ番組で「今だけ、金だけ、自分だけ」という「3だけ」について話されていました。
将来のことを考えず、今のことしか考えていない。
お金ばかりを追求している。
自分のことしか考えていない。
「3だけ」にはそのような意味を持っています。
この「3だけ」を追求するとエゴになります。
利己そのものです。
でもこれはまた、別の面から考えると色々な意味を持っていると考えます。
起業する人は「人のため」「世のため」という思いより、お金を稼ぎたいとか有名になりたいとか思う気持ちを持ち頑張ります。
「将来は今日の積み重ね」という考え方もあります。
今を一生懸命頑張れば将来に繋がります。
「自分だけ」のことを考えるのはダメと言っても、全ては自分が出発点であり、自分あっての仕事であり、何かを成し遂げることが出来ます。
「今だけ、金だけ、自分だけ」という「3だけ」は利己ですが、全否定はどうでしょうか?
初めに利己があって利他が生まれます。
極論かもしれませんが、「欲」と言う利己が「起業」というロケットが飛び出すときの推進力になります。
我利我利亡者はいけませんが、人の「欲」も大事です。
めっこ飯
昨日、2〜3ヵ月前にオープンした食堂に行って来ました。
ランチには少し早いですが11時半くらいに行き「野菜エキスたっぷりの牛すじビーフカレー」600円を注文。
カレーは10分程で出てきました。
まずは私が開いているホームページ「琴似観光協会」の「琴似のランチ」のページに載せるべく、写真を撮り、早速食べました。
その時「何!固い!」
ご飯が固いのです。
初めは写真を撮っている内にご飯が乾いてしまったかな?と思ったのですが、中も固い。
それでも「ここはカレー用に固めのライスを用意しているかな」と思いつつ食べました。
が、固くて1口食べるのに時間がかかること。
とうとう店員さんを呼んで「このご飯固くない?」とそのご飯を渡して聞きました。
暫くすると店長さんらしき女性が出てきて「申し訳ありません。ご飯の炊き方間違えました」と平謝。
「お代は結構です」とか「飲物をサービスします」と申し出がありましたが、丁重にお断りし、食べ残したまま600円払い出てきました。
実は私も若い頃、ホテル内の和食堂の店長をしていた時、同じようなことを起こしました。
お客様に固い「めっこ飯」を出してしまい、怒られた経験があります。
この店と私の和食堂が同じ「めっこ飯」を出したのには共通点があります。
それは開業してから2〜3ヵ月経っていた時に起きているのです。
店のオープン時は気を入れて仕事をしますが、少し慣れてくると気が緩みます。
そのような時に起こしています。
オープンして2〜3ヵ月の頃は、経営者・管理者が特に気をつけなければならない時期です。
それにしても、私以外のお客様はどうしたのでしょうか?
この食堂には私が最初に入り、後に10人くらいのお客さんが入店していました。
そのお客様のご飯どうしたのでしょうか?
チョット心配です。
この店、気になりますので、後日また行ってきます。
*参考:「めっこ飯」は北海道の方言で固くて芯があるようなご飯のことです。
親心
ここ2・3日で札幌もすっかり冬になりました。
これからが冬本番。
そんな寒い日にも外で働く人達がいます。
寒い中、午前中の仕事を終え、車の中でお弁当を食べて一時程休んでいるお父さんらしき人の姿をよく見ます。
奥さんが作ったランチジャーのお弁当を食べ午後からまた働きます。
家族のため一生懸命頑張るお父さんの姿は素晴らしいです。
お弁当に関してある本の中に感動する随筆がありました。
樋口清之国学院大学名誉教授が書いた随筆です。
「私の友人で、貧しさに耐えてよく勉強するのがいました。
彼が学問に意欲を持つようになったのは、小学校時代に持っていったお弁当が動機だったというのです。
彼はある日、やはり母が作る父の弁当を間違えて持って学校に行きました。
彼はいいます『オヤジの弁当は軽かったが俺のは重かった』と。
そして彼は、初めてオヤジの弁当箱にはご飯が半分しか入っておらず、自分のには一杯入っていたこと、オレの弁当のお菜はメザシだったが、オヤジのは味噌がご飯の上に載せてあったことを知ったのです。
父と子の弁当箱の内容を一番良く知っている母も父も黙っている。
オヤジは肉体労働をするのに、子供の分量の半分にして、おかずのない弁当を持っていく。
『これが親というものの愛情なのか』と思うと、泣けて、彼はその弁当が食べれなかったと言います。
そして彼は『あの親達に将来決して心配はかけまい、良い成績を取ろう』と決心したのです。
もしも彼の両親が『お父さんのお弁当の中味は少ないが、お前にはチャンとしたお弁当を作っている』と言ってしまったでは何もなりません。
両親とも黙っているところに、子供が感動したのではないでしょうか。」
親のありがたさとお弁当にまつわる話でした。
無垢な魂
昨日は孫の初七日でした。
一生懸命生きた5ヶ月間の短い人生でしたが、父・母、爺・婆達に愛されました。
無垢な魂が無垢のまま帰っていきました。
「花はなぜ美しいのか
ひとすじの気持ちで
咲いているから」
八木重吉の詩です。
心に響きます。
一休さんの言葉
「爺死に、婆死、父死に、母死に、子死に、孫死に」
これを聞いた人は皆、「こんなめでたい時に死ぬなどと言うのは不謹慎だ」と怒ったそうです。
でも一休さんはこう言いました
「順番に死んでいくことが一番幸せなこと」
「それが順番が逆だったらどうでしょう。不幸な事です」
ここ3日間、その言葉が身に染み入りました。
24時間営業の食堂
先日ある統計を見ていると、日本の生活保護受給者は今年の4月現在216万人います。
1995年は100万人を大きく割っていました。
「人」を大きく分けると「働く人」と「働けない人」、そして「働かない人」がいます。
働きたくても働けない人には出来るだけの支援は惜しみません。
一方、働けるのに働かない人も相当数いるのではないでしょうか。
昨夜早目に帰宅してテレビを見ていると24時間営業している食堂が取り上げられていました。
店の名前は「ねこ膳」といい、新宿で小野さんいう夫婦が8年程前から始めた食堂です。
ご主人がリストラされ仕方がなく始めました。
初めの頃は普通に夜は店を閉めていました。
ところがある若い人をアルバイトに雇ったのが切っ掛けで24時間営業になりました。
その若いアルバイトの知り合いが次から次と働きたいと来たのです。
彼らは俳優や声優の卵です。
彼らには稽古や練習の他に、オーディションや面接を受けます。
ところがそれが時々、突然にセッティングされることがあります。
小野さん夫婦はその突然のオーディションや面接に行けるよう対応しています。
だから「ねこ膳」は俳優や声優の若者にとって働きやすい店なのです
小野さん夫婦はそのような頑張る若い人達を応援しようと多くのアルバイトを雇います。
小さな店なのにアルバイトは11人もいます。
小野さん夫婦はその多くのアルバイトを雇うために食堂を24に間営業に替えたのです。
夫婦は交代でお店を管理しています。
毎日すれ違いの生活。
それでもその夫婦は「頑張る人を応援したいからこれからも続ける」と言います。
経営的には人件費を抑えて運営するというのが本当でしょうが、この夫婦は8年前自分たちがリストラされ辛かった事と重なり、自分の身を粉にして頑張る人を応援しているのです。
このように頑張る若い人のために頑張っている夫婦の姿。
胸に響きました。
上京した時、「ねこ膳」に行ってみます。
同窓会
先週の土曜日に札幌西高の同窓会が開催されました。
参加者は600名以上になり、私の同期も集まりました。
残念ながらその数は少なかったですが。
札幌西高は1912年(明治45年)に旧制中学校として創立されました。
創立から100年を越し、北海道では歴史のある高校の1つです。
札幌西高の卒業生は学校への思い入れは深く、また同窓生同士のつながりも強いものがあります。
同窓という事だけで仕事が上手くいく事もあります。
同窓会幹事は毎年卒業期ごと順送りされます。
今年は西高36期・西定37期で90名以上の人達が務めました。
その中にはイギリスからこの同窓会のためだけに帰ってきた女性もいました。
何年か前の同窓会で、幹事の中にどこかで見たと思われる人が幹事のジャンパーを着て会場内を走り回っていた人がいました。
元マイクロソフト日本の社長だった成毛さんです。
人づてで聞いた話ですが、成毛さんは北海道で仕事をするつもりはないが、卒業した札幌西高、そして同期の仲間を大事にしたいとの思いが強く、1人の幹事として参加したそうです。
私も懐かしい顔に合えるのを楽しみに毎年参加しています。
ところで何年か前から札幌西高では「西高実行精神」というものを掲げています。
「やる事はやる。やる時はやる。やれるだけやる」
私の学生時代にはありませんでした。
「やる事はやる」と「やる時はやる」はいいのですが、「やれるだけやる」は少し問題です。
「やれるだけやる」は一生懸命さがありません。
「出来なくてもいい」の意味も含まれているように思います。
やはり「やり遂げるまでやる」でなければならないでしょう。
同窓会後は同期の人達と2次会でまた飲みました。
楽しい夜でした。
公明正大に利益を追求する
昨夜勉強会がありました。
毎月開いている「身丈会」です。
今回も稲盛和夫さんの「心を高める経営を伸ばす」という本を題材にして勉強しました。
今日はその中でも「公明正大に利益を追求する」を紹介します。
稲盛さんは本の中で、「経営者は自分の企業、集団のために、利益を追求しなければなりません。
これは決して恥ずべき事ではありません。
堂々と商いをし、得た利益は正当なものです。
しかし利益を追求するあまり、人の道として恥ずべき手段を持って経営を行ってはなりません。」
これは至極当たり前の事です。
ただ、利益を追求すると言う事を曲解して理解している人がいます。
「利他」と「利己」。
自分の会社の利益ばかりを追求する事は「利己」ではないかと言うのです。
「利他」を考えれば自社の利益はほどほどの利益でいいのではないかと。
この考えはいいように思えます。
でも間違えています。
稲盛さんも次のように書いています。
「アスファルト道路の割れ目から顔を出す名も知らない雑草達はもがき合いながら必死に生きようとしています。
それぞれの草が他の草より少しでも多くの太陽を受け、もっと大きくなろうとして精一杯葉を広げ、茎を伸ばすことを競っています。
相手を負かすために一生懸命生きているのではありません。
自分が生きていく事に一生懸命になるように、自然は元々出来ているのです。
必死に生きていない植物など、絶対にありません。
私達もただ単に成功するためだけに、一生懸命働かなければならないのではありません。
生きていくためにも、『誰にも負けない努力』で働く、それが自然の摂理なのです」
最近お金儲けは「良くないよう思っている」若い人が時々見受けます。
残念なことです。
公明正大に利益を追求して、税金をしっかり払っていく。
それによってこそ日本の国が豊かになっていくのです。
大事な事です。
知行合一
「分かっちゃいるけど止められない♫」は昔に流行った植木等さんの歌です。
理屈では分かっているけれど止められない。
庶民の気持ちを代弁している言葉として当時とても流行ました。
でも何かをなそうとしたら、何かを止めて始めなければならない。
それは分かっているけど出来ない。
それと反対の言葉は「知行合一」でしょうか。
「知識と行為は一体である」という意味です。
大事だと思いつつ実行出来ない。
実行するのにはどうしたら良いか。
その手助けとなるのは「習慣化」ではないかと私は思います。
大事だと思う事が100個あっても何も出来ないより、1つでも2つでも確実に身につけていく。
それには大事だと思う事を習慣にすることです。
習慣にするには1日の行動をパターン化することです。
1つの例です。
人は1日に3回の食事を摂ります。
その食事に合わて行動するのです。
持病を持っている人は食事の後に必ず薬を飲む習慣があります。
毎朝、朝食前にラジオ体操を習慣にしている人がいます。
ラジオ体操前に6時から始まるNHK英会話講座を聴く人がいます。
散歩や読書など、朝食前に色々な事を習慣にしている人は多いです。
日常行動に合わせて習慣化すると、仕事の中でも習慣化する事に慣れ、普段の考え方や行動が変わってきます。
そう言う私は100個の内まだ2・3個しか出来ていないのかもしれません。
それでも長年続けています。
そしてその数も増やしていこうとしています。
それにより、大事だと思う事が習慣化して考え方や行動が変わり、自分の人生がいい方向に向かっている気がします。
「知行合一」と「習慣化」
いい組み合わせだと思います。
現場経験
私は若い頃、父親から会社の「現場」に入って仕事をする事を教えられました。
ホテル勤務の時は営業担当であっても、夜は宴会のウエイターとして働きました。
住宅会社の時は住宅現場の帳場として仕事をし、その後には住宅営業もしました。
現場に入って仕事をする事はその会社の全容を掴むために大事な経験です。
ところが最近の若い経営者の中には現場の経験がないまま、常務とか専務そして社長になっているケースがあります。
そのような経営者は常に現場に「負い目」を感じているはずです。
そして自分の出来ない事や現場の判断を他者に任せてしまうのです。
権限委譲という名の下に責任放棄してしまう。
現場で何か問題が発生するとその責任者の責任だけを追及する。
そのような経営者は現場へ<u>下りる</u>のが怖いのです。
しかし現場を知らなければ従業員の気持ちを汲み取る事も、現状把握をして事業展開を図る事も出来ません。
セールス経験のない販売店の社長。
工場経験のない製造会社の社長。
気付いたとき思い切って週1回は現場に入る日を決めて汗水たらしてみる。
その時、従業員との連帯感が生まれるはずです。
一畑グループ
昨日は出雲大社へ行ったと書きましたが、その出雲に行って驚いた事が1つありました。
出雲市・松江市を中心に事業展開する「一畑」という名前の企業グループがあります。
私達が宿泊したホテルもそうですし、市内や空港間のバス、電車、タクシー、百貨店、レストラン、お土産店、不動産、建築などあらゆる分野で事業を展開しています。
高円宮家の典子様と出雲大社の千家国麿さんの結婚披露宴も一畑グループのホテルで開かれました。
出雲空港に着いた時に、カウンターで買った「縁結びパーフェクトチケット」は3日間バスや電車乗り放題で、お土産店や施設入場料金も安くなります。
このチケットは出雲市ばかりでなく松江市でも使えます。
小泉八雲記念館や松江歴史館でも使えました。
僅か3日の観光で分かったつもりにはなりませんが、見て回った中で思った事です。
市内には大手企業の進出は余り多くはないようです。
ローソンは1店舗見ましたが、その他のコンビニは見ていません。
調べてみるとコンビニの数は島根県全体で175店舗しかありません。
日本全体の中では少ない方から3番目。
スーパーもイオンが5店舗、イトーヨーカドーはありません。
島根の県庁所在地である松江の人口は20万人を切っています。
島根県全体でも71万人。
そのような人口の少ない環境で、「一畑グループ」は各分野で業界を仕切っています。
またそのように人口が少ない地域では大手企業が入り込んでも共倒れになってしまいます。
一畑グループの地域独占になっています。
1つの「参入障壁」になっています。
そして新規参入が出来ません。
それが島根経済活性化の妨げになっているのかもしれません。
これを崩すのは大変な事です。
このような事例は島根県ばかりでなく日本中にあるのかもしれません。
地方活性化と言われてますが、そう簡単な事ではない。
色々考えさせられました。
出雲大社
週末に出雲大社に行って来ました。
夏場は札幌から出雲空港までの直行便があったのですが、今の時期は羽田経由になります。
初めての出雲大社参拝であり、山陰地方初めての旅行です。
今年は出雲大社の遷宮が終わり、また今月5日の高円宮家の次女、典子様と出雲大社の神職、千家国麿さんのご結婚の余韻が出雲の街に残っていました。
出雲大社では「2礼、4拍手、1礼」でお参りをしてきました。
出雲大社は「縁結びの神様」として有名です。
「縁結び」というとすぐ「結婚」に結びつけますが、「人との縁」を結ぶという意味でビジネスの神様でもあります。
参拝の後は有名な出雲そばを食べ、その後松江に向かいました。
小泉八雲の記念館や松江城を見学。
松江城から眺めた景色は落ち着いた城下町そのもの。
それは高い建物がなく、広告看板がないためです。
松江市には景観条例があり、厳しく規制されています。
他の観光地にあるようなネオンや大きな看板はありません。
それが落ち着いた街並みになっているのでしょう。
松江市の人口は19.4万人で、私が住む札幌市西区の21.2万人より少ないです。
でも、歴史と昔物語が溢れ、落ち着いた街。
歴史が浅い札幌の人間にとっては羨ましい街です。
楽しい旅でした。
「向上心」と「足るを知る」
フッと思う事があり、考えてみました。
「向上心」と「足るを知る」という言葉です。
どちらも大事な言葉でありながら相反するのように思えます。
時として「頑張らないでいいよ」「程々でいいよ」と言われるのと同じように「足るを知る」が使われます。
同じ意味でしょうか?
「頑張らないでいいよ」や「程々でいいよ」は「怠け心」に近いものです。
「怠け心」の反対語が「向上心」です。
これは「心の有り様」を表す言葉。
「足るを知る」は「物欲」を抑える言葉で、その反対語は「贅沢」。
「贅沢」の上を目指せば際限がありません。
テレビで時々放映される大富豪の生活は贅沢そのもので、彼らは満足を知りません。
利己そのものです。
�
同じ上を目指すのでも、利他のために頑張るのが「向上心」
一方「足るを知る」を実感するにはどうしたらいいのでしょうか。
私が思うに、自分の「出来ない事」を嘆くより「出来る事」を知る。
自分の「不幸」の数を数えるより「幸せ」の数を数える。
それが「足るを知る」こと。
そんな風に思います。
そして私はそんな風に思える歳になってきました。
粗にして野だが卑ではない
最近何かあると頭に浮かぶ言葉があります。
「粗にして野だが卑ではない」
これの言葉は�以前にも紹介しました。
城山三郎氏の小説の題名です。
国鉄総裁だった石田 礼助氏�の半生記を書いています。
「粗にして野だが卑でない」
する事が粗雑で、礼を失していて野蛮なところはあるかも知れないが、�卑劣な考えや行動は決してしない。
自分を律する言葉として頭に浮かんできます。
裏を返せば、卑劣な自分を意識しているのかもしれません。
今の私の座右の銘です。
子供を育てる
私には孫が6人います。
スクスクと育ってほしいと願っています。
しかし新聞等では子供が被害を受ける報道をよく見ます。
その度に、心配と怒りが湧いてきます。
事件が起きる度に、親は子供に「知らない人と話してはいけない」等と人間不信に近い事を教えなければなりません。
20年程前、私が住んでいた所は子供達が多くいて、毎日大きな声を出して走り回っていました。
私の子供が5人、それに近所の子供達を入れると10人位の子供になります。
夏には庭にテントを張って近所の子供達も一緒になってキャンプをしていました。
そのように自由に子供達が遊べたのは、近所の大人達が見守ってくれたからです。
何かあると子供達に声をかけていました。
大人が持つ地域に対する責任の1つに、子供達を守り育てることだと私は思います。
しかし、そのように思う人がいる一方、地域の子供達に無関心な大人も多くなったように思います。
テレビを見ていると、自分の住んでいる近所に保育園が出来るのを反対している所が多くあるそうです。
保育園が出来ると子供の声がうるさくなり、住環境が壊されると言って反対運動が起きているのです。
確かに夜に働いて、昼間に寝る人にとってはうるさいという事もあるでしょう。
でも「静かな住宅地に保育園が出来ることで住環境が悪くなる」と言って反対するのはいかがなものでしょうか。
「個人主義」と「利己主義」という言葉があります。
「個人主義」は、自分の人間としての権利が保障されるよう求めると同時に、自分が属している社会に対して同様の責任が生じると言う考え方。
「利己主義」は、自分の利益だけを求める行為で、他の人のことや社会の利益に対して全く考慮することなしに、自分が益する生き方を求める考え方。
赤ん坊は泣くのが仕事。
子供は元気に大声を出すのは当たり前。
それらの子供を地域で育てる。
大事な事だと6人のお祖父ちゃんは考えます。
ノーベル賞
昨夜家に帰りニュースを見ていると、日本人3人がノーベル物理学賞を受賞したと流れていました。
ついつい嬉しくなって、真剣にテレビを見てしまいました。
その3人の中で天野さんが20歳代、中村さんが30歳代の時に研究したLED研究の�評価です。
20歳代30歳代です。
研究していた時に、その若い研究者を導いた先輩がいました。
若い研究者のたゆまない研究努力と幸運があったと報道されていますが、その背景には励まし、後押しをする人達がいました。
どのような人がどのような環境を作ったのか。
とても興味のあるところです。
また、受賞されたのは「考えて論ずるばかりでなく、実際に行動した結果」です。
評論家より実行者。
そんなんことを考えさせた嬉しいニュースでした。
おにぎり屋さん
昨夜の勉強会。
札幌で有名な「おにぎり屋さん」の社長の講話です。
1個540円の「おにぎり」がドンドン売れていると言います。
コンビニでは100円であり、500円も出せばお弁当が買えるのに何故540円もする「おにぎり」が売れるのか。
それは美味しいからと言います。
当たり前の事ですがこれが大事。
そこには「美味しいモノを出せばお客様は来てくれる」という社長の信念があります。
お客様は値段で選ぶのでなく、美味しいその「おにぎり」を食べる事を目指してきます。
ですからリピーター客が多いのです。
路面にある店にはベンツ等の高級車を乗り付けてくる人も多くいます。
この「おにぎり屋さん」は5店舗あります。
この会社の特色の1つに「値切りは一切しない」ことです。
たとえ大量注文を受けても値切りません。
一般の製造業の考え方だと10個の注文より、100個の注文の方が会社としては嬉しいと思います。
しかしこのような手作りの「おにぎり」の場合、作る人は10個より100個作る方が大変。
大変なのに何故安くする必要があるのかという考え方が成り立ちます。
この会社は社長は男性ですが従業員は皆女性です。
採用した女性には2〜3ヵ月間「おにぎり」を握る研修をさせてから店に出します。
女性に技術をつけさせ、自立させる事も社長は目指しています。
ですから従業員にはシングルマザーが多いそうです。
この「おにぎり屋さん」の事を書いていると無性に食べたくなりました。
540円の筋子の「おにぎり」
美味いですよ!
「おにぎり屋さん」の名前は「ありんこ」です。
先頭に立つ
最近はあまり出なくなりましたが、私は本来、外で美味しいモノを食べるのが好きです。
色々回っていると、流行っている店とそうでない店があります。
流行っているお店に共通しているのは、店の主人が店頭に立って仕事をしているところです。
店の味、接客、店作りなどは、店の誰よりも気を使い先頭に立って店を守り育てています。
ところが店が少し流行り、店が順調に成長したと思うと、つい「付き合いが大事だ」とか「勉強だ」と称して外に出るようになる主人がいます。
店が順調に推移し出し、気持ちが一段落するのでしょう。
緊張感が薄れるのかもしれません。
でも主人がいない店は少しずつ輝きが薄れ、気付かないうちに客数は減っていきます。
そしてそういう店は自然と消えていきます。
このような事は飲食店ばかりではありません。
どの会社でもあり得ます。
トップである店主や社長は常に先頭に立って旗を振り続けなければなりません。
これはよく言われる事で、本人も分かっているはずです。
でも出来ない。
「試練は困難な時ばかりでなく幸運な時にもある」
「幸運も災難も試練」
改めて考えさせる言葉です。
分かっていても、なかなか出来ないのですね。
黄色い家
5年前まで私は黄色い家に住んでいました。
この家は35年程前に建てましたが、今でも土台も躯体もしっかりしています。
昔の住宅と現代建てられる住宅と大きく違うのは、使われている材料です。
昔の住宅はドアや窓の枠は無垢の木、床も銘板を貼ったフロアー。
外壁はモルタルで煙突付きです。
今の住宅は枠・ドアも天井・床も全てビニールのようなシートが張られています。
天井・壁・床は全部が化学的シートの囲まれ、湿気を吸収してくれません。
見た目はきれいですが人には優しくありません。
今度この黄色い家に、私の末娘一家が入ります。
生まれた孫が心臓が悪く、未だ呼吸器をつけている状態。
お祖父ちゃんとしてはその孫のために貸す事にしました。(賃料はしっかり取りますよ。)
傷ついていた床は無垢材のフローリングに変えました。
畳や壁紙も張り替え、キッチンも新品のシステムキッチンに替え、灯油タンク、ストーブも新品。
専門業者に最後の清掃もしてもらい、明日引っ越しです。
引っ越しする前の今日は、琴似神社の神主さんに来ていただきお祓いをします。
この黄色い家は私達家族を守り、5人の子供達が元気に育った家です。
これから末娘家族も守ってくれる家だと信じています。
尚、この家が黄色いのは、風水を意識したわけでなく、きれいな芥子色を目指したのが、目指したモノと違って単に黄色い家になってしまいました。
�明日、私は引っ越し要員になっていないので、引っ越しの間は孫の面倒を見ています。
少し楽しみです。
子育て
子供が生まれると、父親は子供を可愛がり、子供目線で会話をしようとします。
赤ちゃん言葉を使ったり、面白いお父さんになって子供に好かれようとします。
子供が小さい内は子供も喜びますが、成長するにつれて、「面白い父親」より「尊敬する父親」を求めるようになります。
ところが子供が成長しても父親はまだ子供の成長に気付かず、いつまでもふざけて面白いお父さんのまま。
そこで子供は父親を「尊敬出来る父親」と見ず、心が離れていきます。
これは昨日、車の中でラジオから流れてきた話です。
確かに納得いく話です。
私の父親は厳格な人でした。
余り甘やかされた記憶は有りません。
小さい頃、動物園とかドライブに連れて行ってくれた若干の記憶は有りますがそれも数える程。
だから友達と遊ぶ方が楽しくなりました。
一方、父親が遊んでくれなかったから嫌いなったかというとそうではありません。
夜遅くまで一生懸命働く父親を見て、中学生の頃より尊敬の念は持っていました。
そして今まで「父親を超えることが出来ない」という思いは続きます。
振り返って自分の子育てはどうだっただろうか。
うるさいだけの父親だったような気がします。
フッとそんな事考えてしまいます。
神宮にて
今日は1日。
例月のごとく琴似神社と北海道神宮にお参りしてきました。
今回は不思議なことに懐かしい人達にお会いしました。
神宮で手水舎に向かっていると、久しぶりにNPO法人のK理事長にばったり。
お参りを終わり帰ろうとすると拝殿の前で、今度は家内が知人と10年ぶりでばったり。
その後、1日の参拝の後はいつものように、ローヤルホストで朝食を摂ります。
そのローヤルホストで保険の仕事をしているKさんと8年ぶりでばったり。
食事をしながら外を見ていると、自転車で知人のMさんが通り抜けていきました。
これらの事を特に結びつけるつもりは有りませんが、不思議な感じがしました。
話は違いますが、ローヤルホストの朝食「ボイルエッグ&トースト」はフリードリンク付きで450円。
毎月1日はこれで朝食。
ちょっとした贅沢です。
握手
人とお会いすると、「初めまして」とか「お久しぶりです」と頭を下げてお辞儀します。
最近はお辞儀の代わりに握手する事も多くなりました。
外国人ですとハグするのですが、日本人の場合はそこまではいっていません。
お辞儀の代わりに握手すると、相手と触れ合うわけですから、より親密になる気がします。
先日稲盛和夫さんを囲んだ懇親会があり、最後にお見送りする時、稲盛さんは参加者の皆さんと握手をしながら会場を出て行きました。
私も握手しました。
その稲盛さんの手は驚く程に柔らかく厚いのです。
「人は握手をしてみると、その人の性格が分かる」とある本に書いていたのを思い出しました。
手に厚みが有り、柔らかい人は心優しく、情熱的で、社会的にも成功する人なのだそうです。
たとえ手を使う仕事でマメが出来ていても、そのような人の手は柔らかいそうです。
だから初めて会って、その人と何かを始める時は握手をしてそれを確かめるといいと言います。
良きパートナーとなるか確認するのです。
さて私の手はどうでしょう。
厚みは有るのですが柔らかさが足りないようです。
優しさが足りないのでしょうね。
これからも心高める修行を続けます。
円安
今日は円安の話です。
今月の中旬に「週刊エコノミスト」という雑誌を買いました。
「円安インフレが来る」の特集が掲載されています。
その中にエコノミスト3名がその時点でのドル・円相場予想を出していました。
3者とも来年1月までの予想は最大(最低?)で107円です。
でも実際はその2週間後に109円になってしまいました。
プロのエコノミストでさえ、今の円安の予想値を出すのは難しいという事でしょうか。
ただ、大きな流れとしては円安傾向がより強まるのは間違いないと、素人の私でも思います。
平成26年度の日本の予算は96兆円。
税収は55兆円と想定し、足りない分は国債を発行して借金運営です。
現在、国債などの発行額は1000兆円を超しています。
これを一般家庭に例えれば、年収550万円なのに、支出は960万円になり、足りない分は借金。
そして現在、借金総額は1億円を超している。
そのような状態で、破綻しない方がおかしいのです。
円安の話は以前にも書きましたが、もうすぐ10月。
この10月から12月までの経済の動き、円安の動きがとても気になります。
北見に行って
24・25日に北見に行ってきました。
稲盛和夫さんの「市民フォーラム」が北見の市民会館で開催され、そのお手伝いに仲間達と一緒に行って来ました。
1300名収容出来る大ホールにも入り切れない程のお客様が来られ、入り切らないお客様には小ホールに大型ビジョンを用意して話を聞いていただきました。
演題は「人は何のために生きるのか」です。
全国各地で開かれる市民フォーラムで同じ演題で話されています。
私も5回程聞く機会がありました。
同じ話なのですが、その都度気付かされています。
今回も2つありました。
「幸福も災難と同様に試練なのだ。慢心を起こさないように努めなければならない」
それと「運命のままに生きる馬鹿がいるか!」です。
稲盛さんの講演の中で、中国明時代の袁了凡(えんりょうぼん)という人が書いた「陰騭録(いんしつろく)」が紹介されています。
人生は運命という縦糸と因果の法則という横糸で作られた布のようなもの。
因果の法則を生かせば人生も変わっていく。
偉いお坊さんがそれを袁了凡に教える時に、袁了凡を叱りつけた言葉です。
共によく分かっているつもりの言葉ですが、改めて大事にします。
トップの心構え
今朝NHKのニュースを見ていると永田秀次郎という人が紹介されていました。
大正12年の関東大震災が発生した時の東京市長です。(当時、東京は市でした。)
その人が高野山に奉納した陶板が発見されました。
以下はそのニュースの要約です。
10万5000人あまりが亡くなった関東大震災の犠牲者の名前を記した大量の名簿が和歌山県の高野山にある慰霊堂の地下で見つかりました。
震災当時、永田は市長として、衛生上の理由から膨大な数にのぼる遺体を身元を確認しないまま火葬にするという苦渋の決断をしたのです。
永田は後、その時の気持ちを「心中は実に痛苦に堪えざりし所なり」と記しています。
永田は震災の7年後に私費を投じ高野山に慰霊堂を建てました。
そこには永田が可能な限り調べた犠牲者の名簿が書かれています。
また犠牲者の名前を長く残すため、変質しにくい陶器製に書き残したのです。
名簿には震災で犠牲になったアメリカ人の名前もあり、タイルに焼付けられた犠牲者の名前は5万5000人にのぼっています。
人から非難されようと、病気の蔓延という2次災害を防ぐため、犠牲者の身元確認もせず、まとめて火葬にしてしまう永田市長の冷徹な判断力と大胆な実行力。
そこにはブレない心の強さがあります。
永田市長はその時の苦渋の思いを抱き続け、7年後私費を投じて陶板に死んだ人の名簿を書き残し、慰霊塔に安置したのです。
「溢れるばかりの情を持ちながら、冷徹な判断をする」
これは組織のトップに立つ者の「心構え」でしょう。
IT+アナログ
先日あるセミナーがありました。
その時に聞いた話です。
講師は北海道大学大学院教授の平本先生です。
先生はある会社が起こした事業紹介を通して、起業する時のポイントをお話されました。
その会社は「感動いちば」という通信販売の会社です。
この会社は北海道の物産を扱っています。
通信販売で北海道物産を扱っている会社は沢山あります。
でもこの「感動いちば」の特色は「IT+アナログ」というところです。
このアナログは「新聞チラシ」です。
「感動いちば」の顧客は北海道以外に住んでいる人。
この会社は日本各地にある朝日新聞販売店と提携して「ASA」マーク入りの北海道物産紹介のチラシをその地域の家庭・会社に配布します。
その地域に住んでいる人々には、朝日新聞の販売店扱いチラシという事で、信頼・信用が生まれます。
「感動いちば」には「新聞チラシ」と言うアナログを使った明確なビジネスモデルが出来上がっています。
「ニッチ」を狙ったビジネスです。
この「ITとアナログ」という話を聞いて、思いついた事があります。
NTTが発刊している「イエローページ」です。
現在はインターネットで検索出来る時代になりました。
今では若い人達のほとんどの人が使っています。
でも、65歳のインタ−ネット利用者は60%、70歳は40%と、年齢が高い世代はまだまだ使い切れていません。
年配の人達は、何か業者を捜す時は「イエローページ」を使います。
また「イエローページ」は地域が明確なので、自分が住む地域の業者を捜すには便利で、使う人は意外と多いようです。
このイエローページをうまく使ったビジネス。
どうでしょう。
先ほどの新聞チラシと同じようにITと組み合わせると新しいビジネスが生まれるかも知れません。
これも「ニッチ」ビジネスです。
モノ作り
今月初めの新聞記事に、2014年度版中小企業白書の内容が掲載されていました。
その中に製造業の開業率について書かれていました。
2009年から12年の製造業の開業率は0.7%で10年前と比べて5分の1の水準に低下しています。
製造業で起業する人が減少しているのです。
20年程前から大手企業は円高の経済環境を避け、また安い労働力を求めて海外へ進出していきました。
それに連なる関連企業も進出していきました。
力ある製造業は海外進出していきました。
進出出来ない裾野関連企業は衰退しています。
日本にモノ作りの環境が無くなっています。
明治の頃から日本はモノ作りで発展してきた国です。
ところがその得意なモノ作りも技術面、販売面で外国の企業が日本を上回りつつあります。
IT、サービス、観光、農業も大事な産業ですが、やはりモノ作りが経済の基礎にないと経済の安定はないと思います。
3Dプリンターなどの製造業起業支援が行われていますがまだ物足りないです。
今年の末からドルと円の関係が激変するという予想もあります
予想では円が安くなるのです。
その時、輸入品は高くなりますが、輸出するにいい環境になります。
原材料を輸入して、工業製品を売る。
国の経済基盤であるモノ作り。
私の関連会社は家具作りの会社です。
私の出来る支援考えてみたいと思います。
僕
私は若い頃、自分の事を「僕」と言っていました。
それが今のように「私」と言うようになったのは何時頃か定かではありません。
ただ、若い頃「僕は」とか「僕の」と、いつも「僕」という言葉を使っていたので、しまいに「僕ちゃん」と言われた事もありました。
昨日読んだ本の中に、この「僕」という言葉に関して興味ある事が書かれていました。
日本で初めて自分のことを「僕」を使ったのは幕末の偉人吉田松陰だそうです。
中国の「漢書」の中にその言葉が書かれています。
吉田松陰はその「漢書」を読み影響を受けたようです。
昔から「漢書」は日本でも読まれていました。
なので「僕」という字は日本でも以前から知られたいました。
ただ、それまでは「僕」を「やつがれ」読んだそうです。
へりくだった自称です。
その「僕」を吉田松陰が初めて「ぼく」として使いました。
謙称として使ったようです。
吉田松陰が使い出したので、吉田松陰が主宰していた松下村塾の塾生達も使い始めたそうです。
あの高杉晋作も使っていたようです。
現在も謙称として使えばいいのでしょうが、今使うと単なる「甘えん坊」に思われてしまう。
時代が違うのでしょうね。
因果応報
「因果応報」
よく聞く言葉です。
良き事を行えば良き事が起き、悪い事を行えば悪い事が起きるという意味です。
ところで昔に「1日1善」という言葉が流行りました。
1日に1度は善い事をしようと言う運動です。
この事はいい事です。
これを習い性として普段の中で行動すれば「因果応報」の法則の結果も出てくるのでしょう。
ただ1回や2回、善い事をしても簡単には出てきません。
先日読んだ曽野綾子さんの本の中におもしろ事が書かれていました。
それを紹介します。
「現世で正確に因果応報があったら、それは自動販売機と同じである。
いい事をした分だけいい結果を受けるのだったら、商行為と同じことだ。
それを狙っていいことをする人だらけになる。
人がいいことをするのは報いがなくてもするという純粋性の為である」
私はこの文章を読んで「そうだ!」と思わず膝を叩きました。
「現世利益」だけを求めていく生き方。
刹那的で嫌ですね。
危機管理
今朝は3時頃から携帯電話から警報音が鳴り、大雨の警戒情報が流れ続けました。
私も家内も寝不足ですが、災害になるかどうかの大事な警報。
幸い今のところ私の地域は警戒地域になっていませんが、同じ札幌市内でも川が氾濫しているところも出てきています。
そんな時、「私のところだけは大丈夫」という根拠のない自信があることに気づきました。
それはただ単に、今まで安全だったという経験だけしかなく、そしてそれがまだ続くと無意識で思い込んでいるのです。
安全が当たり前。
誰かが自分の安全を守ってくれるという「他人まかせ」
そして安全な生活の中で忘れてしまっている「危機意識」
自分の安全は自分で守るという「危機管理」
それを改めて気付かさせてくれた警戒警報でした。
それにしても携帯電話に流れてくる危機警報。
大変有り難いと思います。
経営理念の大切さ
今日も少しだけ盛和塾世界大会での事を書かせてください。
昨日も書きましたように、世界大会では8人の経営者による体験発表がありました。
その中から最優秀者が選出されます。
今回選出された経営者は株式会社オロの川田篤さんでした。
川田さんは現在40歳。
大学を卒業してすぐに友人と起業しました。
事業内容はビジネスソリューション事業、コミュニケーション事業を手がけています。
起業後14年たった現在、売上24億円以上、経常利益率も14%を上げ、従業員も300名を超えています。
国内各地に支社をつくり、マレーシア、ベトナム、シンガポールには現地法人を設立しています。
この若い経営者の体験発表の中で、私が特に感心した事があります。
それは起業当時の仲間のほとんどがまだ共に仕事をしているという事です。
一般にベンチャー企業の多くは、一時的に急成長しても長く続かず、事業が頓挫していきます。
その頓挫する大きな原因の1つが仲間の不和です。
もめ事が多くなり、ダメになっていく例が数多くあります。
そのようなベンチャー企業が多い中でこの「オロ」という会社はその轍を踏んでいません。
それは起業して早いうちに「仲間同士の価値観の共有」の重要性に気づいたからです。
会社で何か迷いが起きた時、何に基づいて判断すれば良いのか。
社員が何に向かって頑張るのか。
そのために経営理念を作りました。
「社員全員が世界に誇れる物(組織・製品・サービス)を創造し、より多くの人々(同僚・家族・取引先・株主・社会)に対してより多くの「幸せ・喜び」を提供する企業となる。そのための努力を通じて社員全員の自己実現を達成する。」
この理念を目的とし、またそれを判断規範として会社をまとめていったのです。
若い経営者が大切なこの点に早くに気づいたことは素晴らしい事です。
その結果が24億円を超す売上げとなっているのでしょう。
今後の目標は100億であり、将来は日本ばかりでなく世界に通じる会社にしたいという抱負を語っていました。
川田さんは札幌出身との事。
尚一層、この会社の成長を見守りたいものです。
他力の風
先週は3日から上京し、盛和塾世界大会に参加してきました。
今年は4488名の参加者。
海外はアメリカ、ブラジル、中国、台湾の他に初めて韓国からオブザーバーとして15名参加されました。
2日間にわたる大会は8人の経営者による「経営体験発表」の後、最後には稲盛和夫さんの「塾長講話」がありました。
今回は「思いは必ず実現する」と題して話されました。
内容を少し抜粋して紹介します。
「思う」ことは「考える」より大きな力を持つ。
「思い」は人間のあらゆる行動の源となっている。
夢のような「思い」が大きな動機となっていく。
「思い付き」は大事。
出発は「思う」ことから始まる。
「思い」の積み重ねが人格を作る。
それは、エゲツナイ「思い」を重ねる人はエゲツナイ人となる。
優しい「思い」を重ねる人は好い人となる。
「思い」の集積は人間の境遇・運命を作っていく。
そのようなお話でした。
またその他に、「利他を行う時には自己犠牲が伴う」という事も話されました。
経営者が利他の心で「全従業員の幸せを追求する」という「思い」には自己犠牲が伴います。
稲盛さん自身も社長の時は休みはなく、子供の学校行事に1度も出席できず、家族サービスは一切出来なかったそうです。
妻や子供たちに申し訳ないと思う気持ちを抱きながら、会社や社員優先となった生活でした。
それでも自分の仕事を理解してもらおうと、稲盛さんは夜遅く帰宅しても、その日会社であったことを奥さんに話したそうです。
それは自分がしていることを少しでも理解してもらおうとする気持だったのです。
そのようなご自分体験談を話してくれました。
最後に「他力の風」の話です。
宇宙には「他力の風」が流れています。
それを受けなければ何事も成功はしないのです。
そのために、よき良きことを思い、良き行いをするのです。
利己のことばかり考えていると自分の船の「帆」は穴だらけで、「他力の風」を受けることができません。
良きことを思い、良き行いをしてきれいな「帆」を上げてこそ「他力の風」を力強く受けることができるのです。
2日間の大会。
良き勉強をさせていただきました。
素直
人と話をしていると、時々今の生活に満足していない人がいます。
今の生活に満足していないなら、満足出来るように変えればいいのです。
もしも今の自分の考え方や生活に満足しているのであれば、特に変える必要はありません。
これは本当に単純な話です。
今の生活に満足していないならば、今までの「考え方」や「やり方」を変えなければなりません。
「今の生活が嫌だ。もっといい生活がしたい」と思うのであれば変えればいいのです。
でも多くの人は変えていません。
人から「こうしたら良くなる」「こう考えたらいい」とか、アドバイスを受けても今までの生活から変えようとしません。
自分が変わろうとしないのに、生活だけ良くなりたいと思い続けます。
そして自己改革セミナーなどに参加します。
そのような人に共通するのは「素直でない」ということです。
自分は素直だと思っていても、「変えていない」のは素直でないのです。
素直な人は、チョットした人の話を聞いても、本を読んでいていい言葉に出合っても、「そうだな!」と思い、素直に実行します。
実行するから行動が変わります。
行動すると生活が変わります。
こんな単純で当たり前の事が出来ない人が如何に多いか。
でも世の中、そんな人が多いからこそ、素直にそれを実行出来る人は、大した努力をしなくても変わっていき、仕事でも頭角を現せていく事が出来ます。
これに気づきましょう!
私の経験では、「いい」と思って素直に行動する人のほとんどが女性です。
思って行動し、その変化を実感しています。
一方、男には「男の沽券(こけん)」と言うモノが邪魔するのでしょうか。
素直でない人が多いようです。
男性は変わりにくい動物のようです。
そう言う私もそうです。
だからなるべく素直になろうと努力しています。
歳を取ると益々意固地になりそうな心を抑えていきます。
琴似神社
今日は9月1日。
1日なので毎月しているように、今朝も琴似神社と北海道神宮にお参りに行って来ました。
遊びに来ている娘と孫娘も一緒です。
神社にまつわるお話を1つ紹介します。
先日聞いた琴似神社と北海道神宮、そして明治神宮との繋がり話です。
北海道神宮が祭っている御祭神の4柱のうち1柱が明治天皇です。
その関係からか北海道神宮の宮司は明治神宮から来られるそうです。
そしてその明治神宮の現在の宮司は中島精太郎宮司で、琴似神社の先代宮司の弟さんとの事です。
どういう経緯で琴似神社と明治神宮が繋がっているのか興味が有ります。
3つの神社、神宮とも明治以降に造られました。
不思議な因縁のトライアングルです。
その琴似神社の秋のお祭りは今月の3日4日です。
琴似神社のお祭りには北海道神宮の神主さん達も来て祝詞をあげるそうです。
以上琴似神社、北海道神宮、明治神宮に関するお話でした。
もう1つ。
琴似神社はパワースポットとしても有名です。
機会があれば一度お参りしてみてはいかがですか?
筋子のおにぎり
昨日の我が家の夕食はおにぎり。
今、長女が娘とともに我が家に来ています。
来週早々には東京に帰る予定。
「帰る前に何食べたい?」と聞くと、「筋子のおにぎり」との事。
それで早速筋子を買ってきました。
筋子は塩筋子ですが、その種類は大きく分けて鱒と鮭の2種類が有りますが、勿論断然鮭が美味いです。
価格も鱒の倍以上します。
私も大好きで沢山食べました。
北海道はもう秋の気配。
これからの北海道は美味いモノが出回ります。
サンマ、鮭、鱒、カボチャ、ジャガイモなど沢山。
また、もうそろそろ我が家では家内のイクラ作りが始まります。
生筋子を買ってきてイクラの醤油漬けを作ります。
東京に居る兄弟や子供達にセッセセッセと作り送ります。
その量は何キロにも。
皆が北海道の味を楽しみにしているようです。
北海道の秋は短く、すぐ冬です。
短くても凝縮した秋。
私も楽しみたいと思います。
人が出来る事
今朝の日経新聞に「プログラマー不要」という記事が有りました。
「富士通が金融機関や企業の基幹システムの開発を大幅に簡素化する支援ソフトを開発した」と書かれています。
コンピューターのプログラム言語というのは専門の知識が必要で、ちょっとパソコンを知っている程度では入り込めないと思われていた分野です。
それが新しい支援ソフトで容易に出来るようになる。
また専門職が消えていきます。
ワープロが生まれて和文タイプが消えました。
パソコンが生まれて経理の人員が減りました。
ソフト開発が進み、無料ソフトが溢れ、そのため従来の商売が消えていきます。
雇用が減り、人がする仕事が益々限定されていきます。
何もしなければ、その流れに抵抗出来ず、流されてしまいます。
そんな時、人には何が必要なのでしょうか。
人にしか出来ない事。
美しいモノを見出す美的感覚や優れた技術力、創造する力?
それを生み出すのは人間の感性?
そしてそれを操る理性と考え方?
人には何が必要なのか。
それを考える事が今、とても大切な事のように思えます。
目的と手段
人は自分の夢や目的を立て進んでいきます。
生きがいをその夢に託して努力しています。
ところがある切っ掛けがあって、その自分の夢や目的を他の人の為に止める。
他の人の目的の為に自分の夢を「手段」に変える。
そんな話を先日、稲盛和夫さんのDVD見ていて気付きました。
京セラが創業した当初の目的は「稲盛和夫の技術を世界に問う」というモノでした。
ところが創業間もない頃、入社したばかりの若者達が、待遇の改善や将来の保証を求めてきました。
何日もかかって彼らを説得した後、稲盛さんは会社を創業した事を少し後悔しました。
しかしそれでも「これからは社員の為に会社を発展させなければならない」と思い直したのです。
その時に作ったのが京セラの経営理念です。
「全従業員の物心両面の幸福を追求する」
それまでの会社の目的であった「稲盛和夫の技術を世界に問う」は無くなりました。
稲盛和夫の技術は新しい経営理念の「全従業員の物心両面の幸福を追求する」為の「手段」になったのです。
「今までの目的」を捨て、それを「手段」に変える事は難しいです。
それは「自我を捨て去り、利他に生きる」そのもののように思います。
私にはなかなか出来ません。
社員のモチベーションアップ
先日ある経営の勉強会で話し合っている時、1人の若い経営者が従業員の給料アップについて話を出しました。
それに吊られるように、別の経営者からも給料等の待遇改善要求が店長からあり困っているとのこと。
安倍総理が唱えた経営政策の結果、安倍ノミックス効果で日本経済は景気が少し良くなり、従業員給料アップの事が話題になっています。
それに刺激されての事でしょう。
先の若い経営者の話では月当たり契約社員は1万円、社員には5万円アップしたそうです。
その結果なのか翌月の業績がよくなったと言っていました。
元の給料がいくらなのかは分かりませんが、私は少し上げ過ぎだと思います。
人件費は固定経費です。
適正な金額でなければ、経営を圧迫させる大きな原因になります。
給料を上げてもらうと従業員の人達は喜びます。
やる気も出るでしょう。
しかし、そのやる気は一時的なモノになりがちです。
しばらく経てば、上げられた給料も当たり前の事になってしまい、モチベーションは下がります。
勿論、給料は適正な金額を払わなければ、人は辞めていきます。
ただ人は給料だけでは働きません。
何の為に働くのか、その目的を明確にし、目標を提示し、それに向かって働く喜びを共有す環境作る。
それこそが重要です。
自分は期待されているという「思い」と、働く「意義」。
それを感じられれば人は一生懸命は働きます。
経営の勉強会ではそれを学んでいるはずなのですが、「学んだ事」と実際の「経営」が無意識の中で切り離されている。
知行合一
経営者にとって、ここを認識する事がとても重要な事のように思います。
札幌市中央卸売市場
先週の土曜日「札幌市中央卸売市場」を見学をしに行ってきました。
「札幌市中央卸売市場」は私の小さい頃、札幌市民にとって身近な市場でした。
それが何十年か前の北海道観光ブームの時「場外市場」を中心として観光客相手の商売が盛んになりました。
観光客向けの価格の高い海産物や食べ物が多くなり、札幌市民からは縁遠い市場になっていきました。
最近は観光客からも少し飽きられているようです。
市場に詳しい人の話では、市場内の店の閉鎖も増えていると聞きます。
1ヵ月程前、私が主宰する会でこの事が話題になりました。
そこで、改めて札幌市民である私達がまず市場を知ろうという事になり、見学の参加者を募りました。
当日は子供も含め、20名を超える参加者が集まりました。
札幌市中央卸売市場は5時15分のマグロのセリから始まるのですが、その時間では電車がまだ動いておらず、仕方がなく6時45分集合し、7時から見学を開始をしました。
前もって市場に詳しい人にお願いしていたので、「札幌市中央卸売市場協会」の人が案内人として先導していただけました。
最初はビデオで「市場紹介」、その後1時間程かけて青果・水産のセリを見て歩きました。
セリの様子はテレビでも見ていましたが、本物はやはり迫力があります。
卸売業者のセリ人が台に立ち、「手やり」で値段を示し、仲卸人がその値段で落とします。
「手やり」の仕方は青果と水産とでは違うそうです。
また案内をしていただいた人の話では、札幌市中央卸売市場で扱うマグロは全て生だけとのこと。
だから市場から仕入れている札幌市内の回転寿司のマグロはほとんどが生。
それゆえ、札幌の回転寿司は日本で一番美味いと言っていました。
見学終了後は、市場関係者の食堂で朝食。
朝食は海鮮丼定食です。
値段は780円ですが、ボリュームたっぷりで美味い。
場外市場にある食堂では2000円位はする内容です。
丼一杯のサラダに味噌汁も付いています。
鮭のアラの味噌汁。
これも美味い。
この食堂は一般の人でも食べれるそうです。
今度、知人達を誘ってまた来ようと思っています。
解散したのは9時30分
朝から頭もお腹も充実した1日でした。
臆病者
先日、本を読んでいると、主人公の女性が言った言葉が妙に心に残りました。
一部分を紹介します。
「時として平和主義者も一皮むけばただの臆病者。
無実の人が殺害されようとするのを止める為に、相手を殺すくらいなら見逃す方が正しいと本気で信じている人達もいる。
それは間違っている。
なぜなら、悪と戦わなければ、片棒を担ぐのと同じだからである。
引き金を引くのと同罪。」
今の日本の中でも似たような事があります。
目の前で困っている人を見て見ぬ振りをする。
以前に実際あった事件です。
列車の中に大勢の人がいたのに関わらず、1人の女性が悪い男に絡まれているのを見て見ぬ振りをしました。
ついに女性はトイレの中で強姦されました。
見て見ぬ振りをして、止めようとしなかった人達。
彼らも同罪です。
被害者にとっては許せない人達です。
今の自分が傷つくのを恐れて戦おうとしない。
「穏便に穏便に」と言う。
平和主義という名を借りた臆病者。
最近、日本で増えてきたように思います。
現場力
「現場力」
日本の強みだった「現場力」が最近が弱まっていると、今朝のNHK「ビジネス展望」で話されていました。
「現場力」については以前にも書きました。
職人、技術者と言われる人達が減ってきています。
従来、現場で高い技術力を持って働いてきたのは、多くは団塊の世代を中心とした人達でした。
今、その人達が定年などで現場から離れていっています。
彼らの中には中学卒業で地方から集団就職として上京してきた人達も多かったです。
若い内から現場で鍛えられた彼らは高い技術を身に付けたにも関わらず、賃金は安い状態でした。
その背景には学歴主義があります。
どんなに高い技術があっても、中卒の彼らの給料は学卒よりはるかに低く抑えられてきました。
そのような給与体系が今まで続いています。
彼らが定年などで現場から居なくなった今、「現場力」が大事と言い出し、「肉体労働者」と言ってきた人に対して「技術者」とか「職人」と言っても若い人は集まりません。
技術相応の給料体系、そして現場で働く人達に対する世間的評価の見直し。
これこそが今の日本に必要な事ではないでしょうか。
また、現場の人間が少なくなったと言って、外国から賃金の安い労働者を入れようとする考えは、従来の「肉体労働者は安く使え」の発想と同じです。
現場で働く人達の給料が高くなって、結果的に生産物や建物代金が高くなっても、それを受け入れる経済の仕組みを再構築する。
大げさかもしれませんが、新しい世界が生まれるかもしれません。
社員を幸せにする
今朝のNHKラジオ「ビジネス展望」で法政大学大学院教授の坂本光司さんが「社員を幸せにする企業経営」という話をしていました。
会社の多くは株式会社であり、法律上は会社は株主のモノです。
また、買っていただく得意先やお客様も大事な存在です。
それでも社員を第一に考え、社員を幸せにする事が大切だと言います。
坂本教授によると、日本の会社の中で経常利益率5%以上出している会社は1割程度しかないそうです。
その利益を出している会社の多くが社員を大事にしている会社との事です。
社員を大事にし幸せにしようとする会社こそが伸びているのです。
これは私がよくここで紹介しています、稲盛和夫さんが京セラ、KDDI、日本航空の経営理念に「全従業員の物心両面の幸福を追求する」と唱えている事と共通するところです。
「社員を幸せにする」
「利益を出す会社にする」ためには大事なポイントのようです。
古い酒を飲んで考えました
今、我が家にはお酒が溢れんばかりにあります。
最近偶然にいただいたモノです。
その中に親戚から送られた酒があります。
その親戚は30年程前まで酒屋を経営していました。
酒屋を経営していたのですが、その親戚は皆酒が飲めなく、在庫として残っていたブランディーやウイスキーなど5本が送られてきました。
30年経ったお酒です。
周りの者からは「酢になっている」とか「おかしくなっている」とか言われました。
お盆に兄弟達が集まった時に開けました。
5本とも高そうなお酒なので、口はコルク栓になっています。
開けようと引っ張ると「ボロッ」と崩れてしまいました。
濾過しながら一旦別の瓶に入れ替えます。
それから皆でおそるおそる飲んだのですが、これが美味い!
10年モノのスコッチウイスキーなどは40年モノになって、味わいが深い。
その他もそれなりに美味しくなっていました。
それにしても思うに、お酒が飲めない人がよく酒屋を経営していけたものだと。
その理由は、2001年までは酒類販売には「アルコール専売法」と言う法律があり、免許制度で守られていました。
その権利を持つ者だけが販売出来ました。
その免許があったため、酒の事が分からなくても商売が成り立っていたのです。
今はその法律もなくなり、誰でも申請すれば販売出来るようになりました。
そうすると権利の上で成り立っていた店は必然的に淘汰されていきます。
塩もタバコもアルコールと同様に専売制度は廃止されました。
専売制の上に成り立っていた業界には競争がありません。
ですから胡座をかいていた店は自由競争の中では生き残れません。
TPP問題でもまた経営環境も変わっていくのでしょう。
規制で守られている業界は競争に弱い。
自力があり、競争の中で勝ち残ってきた会社のみが生き残れるのです。
孫来る
長いお盆休みも終わりました。
この1週間は孫が2人来て、我が家は遊園地状態。
長女の娘が2歳、次女の息子が6歳。
まるで兄妹のように仲良く遊んでいました。
6歳の孫は小学1年生。
JALの「キッズおでかけサポート」というサービスを利用して1人で来ました。
親から離れ、1人飛行機に乗り、北海道に来るという事に孫が不安がるかと心配したのですが、本人は全く平気の様子。
1週間いて昨日帰ったのですが、一度も親を恋しがりません。
私の孫ながら、たくましい者です。
2歳の孫は長女とまだしばらくいるようです。
東京の暑さが一段落するまで居る様子。
妻と2人の平穏で静かな生活はまだ先になりますが、孫との生活楽しみます。
盛和塾札幌
昨夜、盛和塾「札幌」の説明会・講演会がありました。
札幌だけで現在107名程の塾生がいますが、もっと多くの塾生を増やすのが目的です。
なぜ塾生を増やそうとするのか。
それは多くの経営者により良い経営をしていただきたいからです。
経営を知っていると思っていても「本物」を知らず。
知っていたとしても、それを生かす「方法」が分からない。
本を読むだけでは如何にいい考えでも生かしにくいのもです。
盛和塾とは経営の責任者である社長としての心構え・考え方を学ぶところです。
会社が成長するかしないか。
8割以上が社長の責任です。
盛和塾「札幌」に入塾して会社の業績が伸びたという人が沢山います。
800万円の売上げだった会社が入塾後約5年で8000万円になった若手経営者がいます。
スナック経営をして年間3000万円程度の売上げを出していた経営者が、寿司経営に転向し、盛和塾入塾後30億円以上の売上を築き上げた経営者がいます。
盛和塾は単なる交流会ではありません。
経営者同士が切磋琢磨し経営を伸ばすところです。
盛和塾塾長である稲盛和夫さんは「盛和塾に入塾して勉強すれば、会社が伸びない方がおかしい」と言い切ります。
昨夜の説明会・講演会には、盛和塾に興味を持たれた方々が60名以上集まりました。
この会をきっかけにどの程度の方が入塾されるか楽しみです。
厳しさ
昨日は「人手不足」ということを書きました。
また土木や建築に携わり、外で働く人のことも書きました。
彼らは立派な技術者です。
その技術を身につけるには単に知識の取得ばかりでなく、現場での経験が重要です。
現場では常に厳しい叱責もあります。
その中で鍛えられていくのです。
それを甘やかすと、それなりの技術しか身に付きません。
しかし最近は「厳しくすると辞める」という話を良く聞きます。
辞められると困るから雇用者は甘くなる。
結果「職人」と言われるプロが少なくなっていきます。
私の今住んでいる家は5年前に当社の関連住宅会社に依頼しました。
大工さんは昔から知っている人で、親子で造ってくれました。
1階部分は父親、2階は息子が担当。
その出来映え。
全然違います。
父親は幅木や台輪のつなぎ目等の正確さは流石です。
息子は鋸の刃一枚違います。
クレームではないですが、住宅会社の担当者にそれを話すと腕の差を認めていました。
「父親が息子に厳しく言えない。それで甘い仕事になる。
そのことを父親に何度も言っているんだけれども厳しくなれない。
将来、父親が引退したら息子は棟梁として認めてもらえないだろうね。」話していました。
父親は若い頃、宮大工としての厳しい修行の経験もあり、その腕は素晴らしいモノです。
相当の熟練が必要と言われる床の間作りも出来ます。
それに比べて息子の技量は大したことがありません。
厳しさこそ人を育てる。
その見本のような話でした。
人手不足
今、日本中で「人手不足」が話題になっています。
牛丼店の「すき家」の人手不足は特にマスコミで取り上げられています。
それに比べて同じように人出不足だろうと思われる他の牛丼店の松屋や吉野家はそれ程取り上げられていません。
「すき家」のゼンショーのマスコミ対応が悪かったのでしょうか。
ゼンショーはブラック企業とのレッテルも貼られています。
今、景気が少し良くなってきただけでこの人手不足。
震災復興や、オリンピックに向けて益々人手不足が深刻になると思います。
と同時にそれは働く人の待遇が良くなっていくチャンスかもしれません。
私の家の近くに建築現場があります。
そこでは多くの土木作業員、鉄筋工の人達が炎天下の中働いています。
この業種の人達も人手が不足してとのことです。
それと同時に賃金は上がっているそうです。
でも上がっても日当13000円程度。
それでは1か月30万円くらいにしかなりません。
過酷な環境で働く技術者の待遇としては決して高くありません。
以前聞いた話ですが、日本、特に北海道の型枠工は海外で人気があるそうです。
北海道は冬があるので、型枠工は短い期間内で早く、そして正確な仕事が求められます
話をしてくれた人は、近いうちにその型枠工達を連れて台湾で会社設立すると言っていました。
台湾のゼネコンから誘われているのです。
現在日本では、ITや家電、その他の分野の技術者が海外に流出していると言われています。
日本でしっかりした仕事環境を作っていかなければ、土木や建築の優秀な技術者も海外へ流出していくかもしれません。
人を大事にする経営。
今それが求められています。
孫帰札
6月初めに手術の為に東京に運ばれた孫が昨日札幌に帰ってきました。
多くの方にご心配いただきました。
ありがとうございます。
無事2回の手術を終えて帰ってきました。
千歳に着いて、また救急車に乗せられそのまま病院へ。
念のため2週間程入院するそうですが元気のようです。
面会出来そうなので近いうちに会いに行ってきます。
また、これからお盆にかけて、東京にいる小学1年の孫が1人で、また娘夫婦や妹の一家が遊びにきます。
忙しくなりそうですが、楽しみでもあります。
良き習慣
毎日、同じような生活の中で、時として自分の感情に流されることがあります。
そんな時思うのは「良き習慣」を身につけることの大切さです。
振り返って自分の毎日を見てみると、朝5時30分位起床し7時30分に家を出るまでの行動は、何年も変わらず繰り返されています。
毎日決まったことをこなすことで毎日のペースがつかめるのだと思います。
このような習慣も「良き習慣」の1つでしょうが、もっと大切な習慣。
それは「心の有り様」でしょうか。
「人の話を素直に聞く」「悪く考えない」「これから益々良くなると考える」「人に優しく」等が出来る。
そのような思考と行動。
それが自然に日常の中で行えることこそが「良き習慣」なのでしょう。
最初は意識して行います。
それを常に意識しているうちに潜在意識に落とし込まれ習慣となります。
それがその人の性格を変えます。
そして人格になります。
この年になってやっとそれが分かりました。
これから新しい「良き習慣」を身につけたいと思っています。
「気」
先日読んだ本に書かれていたことです。
日本人は「気」を大事にします。
心が積極的になっている時は「気」は+になっています。
逆に消極的になっている時は−です。
その境目を「気分」と言います。
そしてその「気」が病になると「病気」になります。
これは今ベストセラーになっている「おかげさまで生きる」という本に書かれています。
「気」の他にもお天道様に恥じない生き方、
死後の世界のことも書いています。
毎日、人の生と死を見つめている救急医療医である矢作直樹先生が書きました。
素直に納得出来ることが書かれています。
一度読まれることお勧めします。
冒険
今朝のNHKラジオの「今日は何の日」という番組で、今日はサン・テグジュペリが飛行機に乗って行方不明になった日だと言っていました。
サン・テグジュペリとは「星の王子様」と言う本を書いたフランスの作家です。
サン・テグジュペリが行方不明になった日ですとアナウンサーが言った時、一緒に聞いていた妻が言ったことです。
「サン・テグジュペリが残した言葉で『冒険とは自分がそれをすることで誰かが後に続く行為』みたいなことを言っていた」というのです。
ただ単に危険な行為をすることは冒険と言わないのです。
それは単なる無謀。
コロンブスやマゼランのような新天地の発見。
アメリカ人のピアリーによる北極点到達。
ノールウェー人アムンセン・スコットによる南極点到達。
道を切り開いた人がいて、その後に続く人がいて、結果、開発、新しい発見や研究が生まれました。
日本人の中にも間宮林蔵のような人もいますが、概して日本人の中には少ないように思います。
私達の日常生活の中には冒険と言われるような危険を伴うことはまずありません。
ただ何かに挑戦する。リスクがあってもやってみようと思う小さな冒険。
これはあるはず。
起業もその1つだと思います。
リスクを伴う起業も、起業することで、雇用が生まれ、納税も出来ます。
人の役に立つ、小さいけれど1つの冒険です。
冒険心はいつまでも持っていたいものです。
お金の使い方
昨夜帰宅の途中、馴染みのおでん屋さんに顔を出しました。
勿論顔を出したついでに飲みました。
そこには常連さんが2人。
話をしているうち、何かのきっかけで、「思いかけず1000万円を貰ったらどうする?」という話が出ました。
良くある話です。
1人の人は好きなモノを食べ飲んで思いっきり使いたいと言います。
もう1人の人は、「全額寄付します」と言いました。
その理由を聞くと、今の自分の生活に満足しているし、余計なお金は持ちたくないのだそうです。
同じ1000万円を、「貰ったからには自分のモノ」と思うか、「預かりモノ」と思うかの違いでしょうか。
本当のお金の使い方を知っているのは「預かりモノ」と捉える人だと私は考えます。
それは経営者にも言えます。
経営者がどちらの考えを持って経営するか。
「俺が全て作り上げた会社だから全ては俺のモノだ」と思う経営者がいます。
また他方「皆で作り上げた会社だと思う経営者がいます。
会社の利益をどう使うか。
社長の給料を高くし、株主配当を多くするか。
社員への配分を考えたり、事業への投資資金として活用するか。
お金は「預かりモノ」と考える。
お金の捉え方で経営方法は変わったくるのではないかと思います。
中古住宅
イギリスへ嫁いだ娘夫婦が近いうちに家を買うそうです。
50年くらい経った家で、それをこれから自分達でリフォームをして暮らすとのこと。
イギリスでは50年くらいはまだ新しい方です。
イギリスでは家を長く使い伝えていくようです。
私も5年程前まで30年近く住んでいた家を今リフォームしています。
勿論、業者に頼んでです。
屋根と壁の塗り替えは10年おきにしてきました。
壁は幸運を呼ぶ黄色い色。
今回はキッチンを取り替え、畳、床・壁紙、それに外にある灯油タンクも取り替えます。
私が初めて建てた家です。
5人の子供が育ちました。
ヤマチホームで建てたので、造りもしっかりして歪みなどは一切ありません。
4LDKの大きさです。
庭には駐車場、私達が作ったレンガの歩道、花壇があります。
子供が小さい頃、この庭にテントを張り近所の子供達とキャンプをさせました。
すぐそばに発寒川が流れ、子供達が遊べる大きな公園もあります。
JR,地下鉄の琴似駅までそれぞれ10分くらい。
ダイエー、ヨーカドーまでも10分。
この家は50年は持たせたいと思っています。
リフォームが終わりましたら、この家を大事にする人がいれば借りていただきたいと考えています。
アッ、誤解しないでください。
このブログは決して借り手募集の広告ではありません。
私の独り言です。
「諦める」について
昨日ある本を読んで「成る程!」と思ったことです。
人は何かを決める時、迷って1つに決めることが出来ないということよくあります。
それは「諦(あきら)める」ことが出来ないからです。
そして「決めれない」のは「情」に流されるために起こることがほとんどです。
「智に働けば角が立つ、情に棹させば流される」という言葉があります。
「智に働いて角が立つこと」を恐れてしまうと決断出来ないのです。
決めるということは何かを諦めることです。
「諦める」は「明(あき)らめる」なのです。
ものごとを明らかにする。
<u>道理に基づいて</u>考えれば明らかになるのです。
結果、他を捨てて1つに決めることが出来ます。
「理屈ではそうだが・・」という言葉は判断を曇らせます。
「諦める」は「明らめる」こと。
これは組織のトップに立つ人の大切な心構えだと考えます。
百匹目の猿現象
「百匹目の猿現象」という言葉をご存知でしょうか?
Wikipediaによるとこの言葉はライアル・ワトソン氏が発表し、日本では船井幸雄氏が「百匹目の猿―思いが世界を変える」という本で広めました。
「ある行動、考えなどが、ある一定数を超えると、これが接触のない同類の仲間にも伝播する」という現象を指します。
これが今、世の中で起きているような気がします。
ウクライナにおけるマレーシア航空機撃墜、その前のマレーシア航空機の不明、そして昨日のアルジェリア航空機の墜落。
またウクライナ、ガザでの戦闘、アジアでは東シナ海、南シナ海での中国との領海領土問題。
その他に世界的な各国の財政問題。
良いことの「百匹目の猿現象」ならいいのですが、悪いことの「百匹目の猿現象」は嫌です。
マッチポンプ的な報道などに影響されず、付和雷同することないこと。
何が正しいか、何が良いのか。
今こそしっかり極める目が必要ではないかと考えます。
海の翼
昨夜、本を1冊読み終わりました。
「海の翼」という題名です。
とてもいい本なので、その一部紹介します。
昭和60年(1985年)に起きたイランイラク戦争の時、イランには約330人の日本人がいました。
イラクのフセイン大統領は3月17日に「19日20時30分を期してイラン上空を飛ぶ全ての航空機は無差別に撃墜する」と宣言します。
48時間しか猶予がない中、空港にはイラン脱出する人達で大混乱。
各国は自国民救出のため民間・軍用機を差し向けます。
しかし、当時日本では自衛隊機の海外派遣が認められていませんでした。
また日本航空は航空機を出そうと機長も決めたのですが、危険だという理由で組合が反対して出せません
結局日本からは一機も飛び立ちませんでした。
そんな絶望的な中、イラン駐在の日本大使が中心となって航空券を手に入れようと懸命に働きます。
しかし各航空会社は自国民優先で飛行機に乗せようとします。
なかなか航空券が手に入りません。
やっとの思いで手に入れた航空券は123名分だけ。
あとの200名以上の日本人の航空券はありません。
そんな時、日本大使は最後の頼みの綱として親しいトルコ大使を訪問しました。
断れることをほぼ覚悟して、日本人のために航空機を用意してくれるよう依頼したのです。
ところが思いもよらず、トルコ大使は日本大使の話を聞き即座に「至急日本人を救うための航空機を派遣してもらえるよう本国に電報を打ちましょう」と言ったのです。
当時のトルコの首相オザル氏もその申請に同意し、すぐ手配をしました。
航空機派遣の理由を、その首相も大使も口にしたのは「エルトゥールル号の恩返し」でした。
エルトゥールル号とはトルコの軍艦で、明治23年(1890年)使節団を乗せて日本訪問しました。
その帰りに台風に遭い紀伊半島沖で沈没したのです。
その時、嵐の中紀伊大島の島民達が命がけで船員達を助けました。
助けられたのは600名中70名程でしたが、島民は懸命に介抱し、死んだ人達を弔いました。
明治政府も天皇自ら指導し、手厚く介抱し、生き残ったトルコ船員を日本の軍艦2隻で送り届けたのです。
そのエルトゥールル号の話はトルコの子供達は小さい頃から教科書などで習っているそうです。
ですからほとんどのトルコ国民はこのことを「100年前の恩」として引き継がれています。
イランイラク戦争時にトルコの飛行機で日本人が救われたことは、私も当時新聞で読んで知っていました。
またエルトゥールル号のことも知っていました。
ただ、その詳しい経緯はこの本を読むまで知りませんでした。
フセイン大統領が宣言した時間が迫っている時、イランにまだ600名のトルコ人がいました
それにも関わらず、最後の飛行機に日本人を乗せたのです。
知りませんでした。
本ではこの後その詳しいことが解き明かされます。
平成11年(1999年)トルコで大地震が発生しました。
その時日本政府や日本人が取った行動も書かれています。
この本を読んで思うのは、「他者を思う優しい心」が引き継がれることの美しさです。
恨みは恨みしか生みませんが、優しさは優しさを生みます。
この「海の翼」、いい本です。
お勧めします。
琴似のランチ

今年の3月3日から始まった「琴似のランチ」を食べ尽くす「仕事」は昨日の7月22日に終了しました。
全てで67軒。
4ヵ月以上かかりました。
ただ、「松屋」「ケンタッキーフライドチキン」「モスバーガー」は皆さんが知っているチェーン店なので特に紹介していません。
店の内訳はラーメン店11軒、カレー店6軒、うどん・そば5軒、イタリアン5軒等、皆それぞれ美味しいお店でした。
その中で料金的にも、その内容でもオススメのお店があります。
「コン・ブリオひだまり」というお店です。
コン・ブリオはイタリア語で元気に満ちているという意味です。
添付した料理の写真を見てください。
トンカツ定食ですがその内容は、ニンジンとダイコンの味噌汁、トンカツ・キャベツ添え、ナスとピーマンの煮物、揚げとフキの煮物、小エビ入りサラダ、漬け物、ご飯。
これで520円。
この店は知的障がい者が働くお店です。
料理を作っているのは明るく元気のいいおばさん。
障がい者の人が働くお店の中には、「障がい者の店」だからということで、内容が貧相でまたその割に価格が高い。
お客さんは「仕方が無いか」という思いで食べるところもあります。
でもこの店は違います。
精一杯いい料理を出そうとしています。
会計の時つい「こんなに良くてこの料金でいいの?」と聞いてしまいました。
またこの店には妻を連れて行こうと思っています。
美味しい料理を食べ、それで障がい者の人達が仕事の喜びを感じられるなら、互いにこんないいことはありません。
私が生まれ育ち、今住んでいる琴似。
これからもホームページ「琴似観光協会」で紹介していきます。
今度は「琴似の酒場」の紹介に挑戦?する予定です。
休日
昨日までの3連休。
私は主に帆船模型作りをしていました。
この模型は「デアゴスティーニ・ジャパン」という会社が通信販売しているキットです。
毎日は作れませんので時間がある時に少しずつ手がけています。
始めてから既に2年。
これからまだ1年位かかりそうです。
模型作りは細かい仕事ばかりです。
その上、よく解説書を読みこなさないと先に進めません。
手先の器用さと、読解力が必要です。
最近作りながら思うのです。
これは老化防止には最適だと。
妻からは「よくそんな細かいことやり続けれるね。気がおかしくなりそう」と言われますが、私は楽しくやっています。
1年後には長さ1250mm、高さ850mmm、幅450mmになります。
こんな大きい帆船どこに置くか。
それが今から悩みです。
人任せの経営
今日は社長について。
社長の中に会社のことを全て知らなければ気が済まないという人がいます。
一方、仕事をどんどん人に任せる社長もいます。
私は前者の社長が社長としてあるべき姿かと思っています。
「そんな小さなことまで」と思う人がいるかもしれませんが、そんな小さなことが本当は重要なことということがあります。
大きな事故や事件はそんな小さなところを見逃した為に起きていることがあります。
手抜かりなく細かいことも気にして経営をしても従業員の数が増え、社長1人では手が回らなくなってきます。
その時に「自分の分身が欲しい」と思うようになるでしょう。
稲盛和夫さんは同じように「自分の分身が欲しい」と思い「アメーバー経営」を考え出しました。
この「アメーバー経営」を会社に導入する時、そこには土台が必要です。
それは社長のきめ細かい経営姿勢です。
その土台がなければ、「アメーバー経営」を入れても余り効果はないでしょう。
人任せの経営と「アメーバー経営」とは違います。
また人任せの経営に「アメーバー経営」を入れる会社がおかしくなります。
有意注意のきめ細かい経営姿勢こそ大切です。
ところがいざ家庭となるとチョット違います。
家庭内では男性は余り細かいことには立ち入らない方が家庭内の平和が保てると私は信じています。
家でまで気を使っていては身体が持たないでしょう。
家庭内では細かいことは奥さんにまかせます。
その指示に従います。
家庭内では「言わぬが花、知らぬが仏」の精神ですね。
会社と社員
昨日午後から運転免許の更新のため警察に行って来ました。
待つ間に「今回で何回目の更新手続きだろうか?」とか「次回は70歳。もう車の運転はやめようか」など考えていました。
私が運転免許を取ったのは、銀行に入行して2年程経ってからです。
当時私は車の免許は取らないという考えだったのですが、上司からの命令で強制的に運転教習所に行かされました。
その経費は全て銀行持ち。
それで仕方がなく取ったのです。
改めて考えてみると、銀行は当時、色々な面で行員を金銭的に補助してくれていました。
個人が勉強する講座の費用も全額銀行持ち。
またその他に住宅手当、家族手当、燃料手当などもありました。
私は当時3人子供がいましたので、家族手当は多かったはずです。
燃料手当は当時で18万円くらいもらっていたように思います。
今の世間の会社では考えられないような「厚遇」でした。
当時は終身雇用製が当たり前であり、社員に対しても家族主義的な風潮があったのでしょう。
今となればそんな会社と社員の関係が懐かしく思います。
嘘
「嘘をついてはいけない」
これは小さい頃から親に言われてきた言葉です。
自分が犯した間違いを素直に言わねばならないということ。
隠そうと思うと、嘘を重ねていって、取り返しがつかなくなることがあります。
嘘についてもう1つ。
「噓も方便」というのがあります。
「お釈迦様が言った」とか言われますがよくわかりません。
ただ、これは正しいと思います。
自分が犯した間違いを隠したり正当化ための嘘は罪ですが、相手を思いやる嘘はいいのです。
その時に使うのが「嘘も方便」ということでしょう。
話している相手の間違いを指摘する時、そのままに「悪い」とか「間違えている」とか言っても相手は聞く耳を持ちません。
例えば、上司が部下に「君は毎日一生懸命仕事をしていると思う。だけどこの方法は間違えている」と言われるのと「君の仕事、この方法は間違えている」と言われたのでは前者の方が、聞く耳を持ちます。
素直に聞こうと思います。
「君は毎日一生懸命に仕事している」という部分が少し誇張する嘘でもいいのです。
それで部下が間違いを理解し、納得して仕事が上手く行けばいいのです。
それを「俺は嘘をつかず、何でも正直に話す」と言って、部下の欠点をズバズバ言っている人がいます。
これは子供の頃、嘘をついてはいけないとい言われただけを守っているだけで、大人に成り切れていない人です。
大人の「嘘も方便」
それで人間関係を良くすることは大事なのです。
日曜日の1日
今、妻は上京中で私は1人暮らしです。
日曜日の昨日は朝5時30分に起き、庭に実っている赤いラズベリー実を摘み、朝食用のトマトとインゲンを収穫。
ラズベリーは毎日摘んで冷凍庫に入れます。
今月の終わり頃、まとめて大量のジャムを作る予定です。(欲しい方入らしたら差し上げますよ)
昨日1日は外出もせず、読書三昧。
テレビは一切見ず、ラジオもほとんどかけず、静かな家の中。
本は時代物小説と少し固い本の2冊を交互に読みます。
眠たくなったらベットで仮眠。
起きたら、ドリップでたっぷりのコーヒーを入れ、また読書。
食事はお腹がすいたら適当にあるモノで済ませます。
夜はバーボンを飲みながらまた読書。
1日の時間がゆっくり流れます。
久しぶりに「1人も時にはいいな」と思える1日でした。
ありがとう
私は最近、朝はラジオを聞きながら食事をしています。
このラジオ、なぜかNHKしか入らず、最初は仕方なく聞いていました。
でも今はNHKの方が落ち着いて聞けています。
7時前に「ビジネス展望」という番組があり、各分野の人がお話をします。
なかなか面白い話が聞けます。
ただその番組の最後にいつも気になることがあります。
アナウンサーの人が「今朝はありがとうございました。」というと、今まで話していた人は「ありがとうございました」と返す人と。「はい」と言っただけの人がいます。
私の偏見かもしれませんが、「はい」というだけの人は大学の先生や有名な評論家の人が多いようです。
「はい」と言うだけだと、「教えたやったぞ」という上からの返事のように聞こえます。
普段から「ありがとう」という言葉を口にしていないのだろうと想像します。
たかが「ありがとう」という言葉。
それを言える人と言えない人。
改めて「ありがとう」という言葉の大切さを知りました。
「字」の意味
何日か前にここで紹介しました、中国で行われた稲盛和夫経営哲学報告会にて発表した呉さん。
その呉さんが学校を作ろうとした動機の1つに少年院を訪問した時の体験がありました。
その後、たまたまFacebookの紹介リンクの中の「ゴルゴ松本が少年院で行った『漢字の授業』」という動画を見ました。
とても感動する内容です。
一度見ることをお勧めします。
その中で紹介されていた漢字の意味も「成る程!」と感心しました。
故事付けもあるでしょうが納得します。
弱音を吐くという「吐」という字のマイナス(ー)を取ると「叶」という字になります。
幸せの「幸」という字のから1つ取ると「辛』という字になります。
「命」という字は人が1ずつ叩くと書いて、心臓の意味になります。
考えさせられます。
先の稲盛和夫経営哲学報告会で、食品を扱う社長が話していました。
人に良いものと書いて「食」と言います。
また昔聞いた「親」という字です。
「親」という字は「木の上に立って見る」と書き、子供はある程度離れて、見守るべきとの意味だそうです。
改めて自分の回りにある漢字を見てみると面白い成り立ちの字があるかもしれませんね。
丸儲け
「人生、生きているだけで丸儲け」
これは私の知人の女性が以前にFacebookでつぶやいた言葉です。
早速私の「銘肝録」に書いておきました。
自分の状況・有り様を常に謙虚に捉えていると、起こる全てのことが有り難いと思えます。
「足るを知る」に似ていますね。
ただこの「足るを知る」だけでは無気力な生き方に感じてしまいます。
「人生、生きているだけで丸儲け」という言葉には「だから何にも怖くない。何でもやちゃうぞ!」という意気込みがあります。
チョット心が弱くなった時、「人生、生きているだけで丸儲け」を口にすると元気が出てきそうです。
番屋で遊ぼう会
先週の土曜日「番屋で遊ぼう会」という飲み会を開きました。
「番屋で遊ぼう会」については以前にも紹介しています。
今回で5回目?になります。
その都度参加メンバーが違い、参加者同士で新しい交流が生まれているようです。
番屋がある場所は札幌から小樽に向かうJR銭函駅から歩いて10分くらいのところにあります。
列車が走り抜ける線路沿いの細い道を歩いていきます。
番屋は「グルメ亭」という名前がついてGoogleの地図にも載っています。
「グルメ亭」といっても、通常は営業していなく、お願いした時だけお酒と料理を提供してくれます。
海に面したテラスの上では、大きな炉端で時鮭のちゃんちゃん焼き、ほっけ、ニシンなどの焼き魚、焼きそば、
寿司の職人さんが作ってくれた刺身の舟盛りと寿司。
その他、ワカメや昆布等の調理。
私は夕方の4時半頃から、お手伝いと称して早目に行き、早速飲み始めました。
程良い気温といい天気。
心地よい海の風に吹かれているうちに飲み過ぎたようです。
帰りは久しぶりに千鳥足で帰りました。
美味い肴と酒、そして良き仲間に囲まれ至福の時を過ごしました。
稲盛和夫経営哲学報告会
先日の中国旅行の続きです。
最後に杭州で開かれた「稲盛和夫経営哲学報告会」の内容を紹介します。
5人の中国経営者、1人の日本人経営者による経営体験発表です。
そこでは経営に対しての志の高さが語られました。
その中で特に私が感動した人の話を紹介します。
話された内容から抜粋したモノですが、それでも長いです。
よろしければ読んでみてください。
その人は「盛和塾重慶」に属する「重慶行知教育集団」董事長 呉安鳴(女性)さんです。
呉さんの話を書きます。
私は1994年に12年間勤めていた公立学校を辞め1998年に「行知職業訓練学校」を設立しました。
学校を作るきっかけは2つあります。
1つ目は友人に誘われて少年院を訪れた時です。
収監されているのは12〜17歳の子供達。
その時、彼らが過去正しい教育を受けてきたのであればこの年でこのようなところにいるだろうか、不十分な家庭教育と、不適切な学校教育が少年達を誤った道に踏み入れさせたのだと思いました。
もう1つは、私が22歳で教師になった頃の話。
その学校内には「最悪」な問題児を集めた特殊クラスがありました。
その担任は警棒を持った公安局の人で法治と体育の授業しかありません。
座学はありません。
このクラスの生徒は暴言を吐き、喧嘩、窃盗を繰り返しています。
当時血気盛んだった私は、彼らを良くしたいという衝動に駆られ、上司を説得して外国語の授業をする了解をもらいました。
初日、私が教室に入って行くと、教壇に上がるまでにおさげの髪にはフックが掛けられ、服には幽霊と描かれた絵が貼られてしまいました。
頭にはチョークが次々と投げつけられました。
教壇に上がり彼らと対面した時、彼らはある者は机に座り、ある者は椅子に上がり歌い踊っています。
私はおさげのフックと貼られた紙を取り、2分間沈黙した後、一気にしゃべり出しました。
彼らよりさらに狂った眼差しと言葉で激しく攻撃し、息を継ぐ暇も与えず、4時間しゃべり倒しました。
その内に子供達は授業が終わるのも、トイレを行くのも忘れて聞き入り、そしておとなしく、可愛くなりました。
気付くと彼らの目に涙、私自身も涙で顔が濡れていました。
午後からも3時間彼らと腹を割った話をし、家庭環境、自分の将来について、本音はどうなのか、全てを吐き出させました。
子供達の心が落ち着いたのを見計って「明日から他のクラスと同じような教養の授業を小学1年生の勉強から始める」と宣言し、皆同意しました。
その後、この生徒達は皆優れた人間になりました。
私はこの出来事を通して、教育には人を変える力があることを実感しました。
私は1950年に建てられた屋根もない古い建物を借りて学校を始めましした。
最初に雇用した19人の職員と一緒に屋根を張り、建物を修繕し荒れた敷地をきれいにしました。
その19人の職員の半数以上は校舎を貸してくれた国営企業をリストラされた人達でした。
彼らを雇うことが校舎と用地を貸してくれる条件でした。
学校経営を始めた時、彼らとのことで苦しみました。
手に負えなくクビになった彼ら。
それでも機会を見つけては彼らに教育のやりがいを語り始めました。
彼らも私が率先して懸命に仕事を見て、ほどなく信頼されるようになりました。
また、ある年の卒業式の時のことです。
式の後にある子供の保護者が職員室に来て、私の手を握り「自分の子供は現在ある会社で実習中です。仕事もよくやっているようで、今日は先生のお礼を言いたくてきました。」と言い、お金の入った包みを渡されました。
当然その場で受け取りを拒絶しました。
そうするとその保護者は突然に土下座したのです。
あわてて起こすと、驚くことに滂沱の涙を流していました。
その生徒は私の知っている限りでは明るく学業も優秀な生徒でした。
しかし保護者の話では「学校に入ったときは少年院から釈放されたばかりでした。
それまで喧嘩、障害、窃盗、役人の恐喝などで7回も入院し、保釈金と賠償金で17万元を超していた」とのことです。
後日その生徒にあって聞くと「僕が学校に入った1日目、36度の熱帯夜の中、先生はグランドで立ったまま3時間ぶっ通しで話をし「良知」について教えたくれました。
その夜、僕は興奮して眠れず、今までと違う生き方をしたい、尊厳ある人になろうと決意しました」と言うのです。
私はよく教師達に、子供は皆柔軟で生き生きとした命を持っており、未成年期の過ちは教師と保護者に責任があると語っています。
教鞭を振り下ろす先にワットが、冷ややかな目の先にニュートンが、あざけりの中にエジソンがいるのです。
ほんの少しの見落としが、子供にとって自分の一生を変える機会を失わせてしまうのです。
呉安鳴さんは12年間働いていた公立学校を辞め、4年間必死働き、設立資金をつくり80万元を貯めました。
友人から借りた20万元とあわせて合計100万元を投資して学校を作ったのです。
教職員19名、生徒数75名から始まった学校も、現在は教職員300名、生徒数7000人になっています
中国の人は拝金主義的傾向の人が多いと、私は勝手に思っていた。
この報告会でこのような志の高い教育者・経営者がいるとのを改めて認識させられました。
呉さんの発表の後、中国人・日本人問わず、その場にいた参加者からの賞賛の拍手が鳴り止みませんでした。
涙を流した人も多くいました。
稲盛さんからも激賞の言葉ばかり。
稲盛さんは最後には呉さんが経営しているその学校を訪問したいとまで言っていました。
稲盛さんも児童養護施設・乳児院「大和の家」を作っています。
気持ちが相通じるのでしょう。
日本に帰ったらまた子供達に会いにいきますとも言っていました。
今回の旅もいい旅でした。
中国旅行とJAL
昨日は中国杭州旅行のことを書きました。
今日はその旅行に搭乗したJALのサービスについて紹介します。
飛行機は盛和塾のチャーター便ということで、JALの方々から色々の「もてなし」を受けました。
搭乗口のところではJALスタッフが「ご搭乗ありがとうございます」という看板で迎えられ、またボーディング・ブリッジを渡って飛行機に乗る時、窓の外を見ると、20人程の整備スタッフ達も大きな看板を掲げ、見送られました。
それだけでも感激です。
機内では機長から搭乗と支援を受けたお礼をの言葉を、ご家族のことも添えて、切々と述べられました。
これまたつい涙ぐんでしまいました。
機内は盛和塾会員と、キャビンアテンダントの人達とは同士のような交流がありました。
そして皆に配られた記念品。
これまた素晴らしい。
JALの関係会社・部署の職員が書いた感謝カードが17枚。
盛和塾チャーター便が出るということを関係会社・部署に連絡したところ、1週間で2000枚も集まったとのことです。
そしてもう1つ。
整備士の人達が作ってくれたキーホルダーが入っていました。
これは使用済みのジェット機エンジンのファンブレードで加工されたチタンで出来ています。
飛行機の尾翼の形をし、鶴丸のマークが刻印されています。
チャーター便だけの特別の手作りです。
機内食は「俺の機内食」。
「俺のイタリアン」「俺のフレンチ」を展開している「俺の株式会社」社長である坂本さんも盛和塾の会員です。
なぜこれほどまでにJAL職員が歓待してくれるか。
それは稲盛さんがJAL再建に入った時、私達盛和塾の会員はいつも経営指導を受けている稲盛さんへの恩に報いる為、盛和塾が「JAL応援団」となり、全面的に支援しました。
会社で使う飛行機はJAL.
各社の取引先にも「JAL応援カード」を渡し、搭乗を依頼しました。
そのようなこともあってのJALと盛和塾のつながりです。
3時間少しの飛行時間でしたが、感動の時間でした。
中国杭州
杭州は中国南宋の時代に臨安府と言われる都が置かれ、その頃は中国芸術の最盛期だったと言われます。
水滸伝の舞台でもありました。
物語に登場する宋義士「武松」の墓も西湖のほとりにあります。
私達が宿泊したホテルはその西湖のほとりにあります。
西湖はいつも霞にかすんでいます。
その風景を描いたのが墨絵の始まりともいわれています。
確かに霞にかすんだ山々や木々は白黒の世界そのものでした。
この霞はスモッグとは違うようです。
また、西湖は物語「白蛇伝」の舞台となったところです。
流石中国!
色々なところに歴史があります。
中国抗州
明日から中国に行って来ます。
中国抗州で開催される「稲盛経営哲学報告会」に参加してきます。
聞くところによると中国各地から2000人の経営者が集まるとのこと。
日本からも羽田からJALチャーター機で300人弱の人が参加します。
この報告会では中国の経営者6名、日本の経営者1名がフィロソフィに基づいた経営体験を発表。
また、この旅行では紹興酒の工場なども見学も予定されています。
現在、日本と中国は領土問題、政治的問題でギクシャクしています。
そんな時期だからこそ、同じ稲盛フィロソフィを語れる中小企業の経営者同士の交流は意味があると私は考えます。
帰ってきましたらまたその様子を書きます。明日から中国に行って来ます。
中国抗州で開催される「稲盛経営哲学報告会」に参加してきます。
聞くところによると中国各地から2000人の経営者が集まるとのこと。
日本からも羽田からJALチャーター機で300人弱の人が参加します。
この報告会では中国の経営者6名、日本の経営者1名がフィロソフィに基づいた経営体験を発表。
また、この旅行では紹興酒の工場なども見学も予定されています。
現在、日本と中国は領土問題、政治的問題でギクシャクしています。
そんな時期だからこそ、同じ稲盛フィロソフィを語れる中小企業の経営者同士の交流は意味があると私は考えます。
帰ってきましたらまたその様子を書きます。
ご主人のお金
何日か前の新聞に専業主婦率の記事が出ていました。
日本は38%に対して、スエーデンは2%。
日本の年金制度のような主婦に対する年金制度がないスエーデンでは、働かないと最低限の年金しかもらえない等の理由もあるようです。
専業主婦率や共稼ぎのこと、少し考えてみました。
日本ではほとんどの家庭で、ご主人が働いたお金は全て奥さんに渡ります。
その中からご主人は僅かばかりのお小遣いをもらいます。
ご主人が稼いだお金のすべてを奥さんが管理しています。
(我が家もそうです)
ところがイギリスの嫁いだ娘の話ではそうではないようです。
イギリス人の旦那さんは稼いだお金は全て自分のもので、その中から必要な家庭費を出します。
余分なお金は出てきません。
そんなこともあり、奥さんである我が娘も働きに出て稼ぎ、それなりに家庭費を分担し、同時に自分の自由になるお金も確保します。
もう1つ。
日本の場合、奥さんが自分で働いて稼いだお金も、ご主人が稼いだお金も奥さんが管理します。
日本の男性は管理してもらった方が楽でいいと思っているのかもしれません。
そんなそれぞれの国の習慣や考え方で、共稼ぎの考え方も違ってくるのではないでしょうか。
キョウイク
昨夜、異業種交流会「きっかけ会」がありました。
多くの人が集まり楽しい会でした。
その時に聞いた話があります。
シニアになると必要な物が2つ。
1つは「キョウイク」、もう1つが「キョウヨウ」です。
「キョウイク」は教育でなく「今日行くところ」
「キョウヨウ」は教養でなく「今日の用事」です。
何もしなくなるとボケる。
ボケなくなる為に「自分が行くところ」や「自分がする用事を作る」のです。
私は今のところ「行くところ」も「用事」もあるので、しみじみありがたい。
「今日行くところ」と「今日の用事」の他に付け加えるなら「キョウカン」。
「共感」を得ることが出来る仲間も大切と思います。
論語と算盤
先日、私の知人がfacebookで渋沢栄一氏が書いた「論語と算盤(そろばん)」について感想を書いていました。
そういえば昔、私も読んだことがあると思い、本箱から引っ張りだしました。
薄汚れてしまったその本、ホコリを払って読み出すと面白い。
この本の裏を見ると1985年に発刊されたとあります。
約30年前、私が35歳頃です。
この本を買った理由を今でも覚えています。
若い頃「経営は利益追求が第一」と言われている時、それに対して私は疑問を持っていました。
モンモンとし、スッキリしない気持ちの時にこの本に出会いました。
「論語と算盤」は両立する。
すなわち、仁義道徳の道理が経営にも生かせるし、生かせなければならないということが書かれています。
私は今月末、旅行に行く予定です。
その時、持参して再読してみようと思っています。
クレドカード
先週の金曜日に、4月から始まった札幌市大通高校での講座が修了しました。
週に1回の講座ですが、その講座ごとしっかり時間をかけて準備しました。
終わった時はそれなりの満足感を味合うことが出来ました。
ただ受講生の方々はどうだか分かりませんが・・
最終日には「クレドカード」を作っていただきました。
「クレドカード」はホテルリッツカールトンで使われていて有名になりました。
クレドは「信条」という意味のラテン語。
今回は「ミッション」と「クレド」を10個を書く様にプリントした2ツ折名刺の用紙を用意しました。
「ミッション」はこれから自分の生き方を、「クレド」は自分がするべき行動を具体的に書きます。
クレドカードは人に見せるモノでなく、書くことで自分が自分に約束するのです。
また、それは名刺サイズですから名刺入れなどに入れて持ち歩き、時折見て確認することが出来ます。
私も以前に作ったクレドカードから新しく作り直しました。
作り直すと、まるで新しい出発のような気持ちになります。
テレビ
私は今、ある願掛けの為に「◯◯断ち」をしています。
◯◯はテレビです。
日常、習慣的にテレビを付けることが多かったのですが、2週間程前から一切見ないことにしています。
最初は音が恋しくなり、ラジオや音楽を聴いていましたが、しまいに音のない日常になれてきました。
気付くことは時間が思いの外あると言うこと。
ズーとテレビを見ない人にとっては、今更と思うことかもしれませんが。
本が読めます。
整理・整頓・掃除が出来ます。
趣味のことが出来ます。
そして、妻との会話も増えました。
願が叶えられれば、分かりませんが、今、新鮮な生活を感じています。
「命」
安岡正篤さんの本を読むと「命(めい)」について書かれていました。
「命」というと普通は「いのち」と理解しますが、それは「命」の一部です。
自分がどういう素質や能力を天から与えられているのか、それを「命」と言います。
それを知ることが「知命」です。
私達の身近にある言葉で「命名」というのがあります。
「命名」とは、生まれてきた子供に単に名前を付けるということではないのです。
安岡さんは「この子はこの名前の如く生きねばならない。こういう必然、あるいは絶対の意味を持って付けて初めて命名ということが出来る。」と書いています。
子供が生まれると最近は変わった名前が多くなっています。
また、字画がいいからと言って決めています。
私もそうでした。
でもそれは「命名」と言わず「付名」と言うそうです。
「命」には運命、宿命、立命など大事な言葉の中に使われています。
これから少し「命」について考えてみようと思っています。
人口減少
新聞を読むと、日本の人口は1億3000万人を切っているそうです。
政府も人口減少対策を色々出しています。
将来、日本の人口は1億人を切るかもしれませんが、私は余り悲観していません。
同じ先進国と言われる、イギリスの人口は6300万人、ドイツも8200万人程度。
人口は1億人に及びませんが、それらの国の人達は充分豊かな生活をしています。
心配することないです。
それに人口が減少しても、今後もITなどを中心に各分野で生産性が高まっていくことは充分に予想されます。
また、ここ20年程頑張れば、私たちの団塊の世代の人口はドンドン減っていきます。
それとともに若い人の負担も減っていきます。
また人口の数とは別に、豊かな生活をする工夫は必要です。
参考にするべき生活はイギリス。
イギリス人の婿さんは余計なものを買いません。
生活は質素。
決して貧乏ではありませんが、Tシャツなどは穴があくまで着ます。
そして本当に必要な物はいい物を買います。
結果お金は残ります。
今度、家を買うそうです。
古い小さな家を買って、自分たちで時間をかけリフォームするとのこと。
自分の思いのまま、使い捨ての生活をしていては結局何も残らない今の日本。
人口減少に合わせ、生活様式を変えていくことが必要だと考えます。
道は開ける
昨日、私の本箱の中から昔に買った本がまた出て来ました。
D.カーネギーの「道は開ける」です。
D.カーネギーは「人を動かせる」という本で有名ですが、「道は開ける」も読まれているようです。
「人を動かす」は私が大事にしている本、子供達にも贈っています。
この本は人を能動的にさせる本です。
一方「道は開ける」という本は受動的で、悩みを解決するためのアドバイスが書かれています。
本の後ろの版数を見ると、25年程前に買ったようです。
40歳代の初め頃の私、悩んでいたようです。
今、この本を手に取ってみると、余り読んだ記憶がありません。
私の悩みは大したことなかったようです。
でも今一度読んでみようと昨日から読み始めました。
決して今、悩み事がある訳ではないのですが、面白そうなので読んでみます。
昔に買った本で、また新しい気付きに出会えそうです。
業績悪化
会社経営をしていると色々あります。
高い業績を上げている時、思わぬことで急激な業績の悪化を招く時があります。
その時、経営者は谷底に落ち込んでしまったと悲観するかもしれません。
でもそれは錯覚で、普通の業績レベルのこともあります。
例えば高い山の頂上から一気に平地に下がって来た時と同じです。
谷底はそれより下です。
会社の業績が悪くなった時、経営者は孤独で、つい先行きを悪く考えてしまいます。
「感性的な悩みをしない」は稲盛和夫さんの言葉。
社員を信じて頑張ることです。
経営の要諦
今日は「経営3つの要諦」をご紹介します。
これは稲盛和夫さんが、「この3つを何年も何年も繰り返し徹底していけば経営は必ず上手く行く」と言っている言葉です。
1.従業員を自分に惚れ込ませ、一体感が持てるような人間関係をつくる。
2.月次の損益計算書を次の月初の2、3日中に出し、月次の売上げと経費を細かくチェックする。問題があれば適切な改善の手を打つ。(売上げ最大に、経費は最少に)
3.フィロソフィ(哲学)を全従業員で共有する。(皆が同じ判断基準を持つ)
この3つで難しいと思われるのは最初の「自分に惚れ込ませよ」ということでしょうか。
経営善し悪しは社長で決まる。
そのことを言っているのでしょう。
老舗
先日あるセミナーに参加して来ました。
その話の中で羊羹の「虎屋」が取り上げられていました。
この「虎屋」は480年続く老舗です。
私は「虎屋」は昔から変わらない、ただの羊羹作りの会社かと思っていましたが、そうではないようです。
常に新しいことに挑戦し続けているそうです。
「虎屋」には「伝統は革新の連続である」という教えがあると言います。
100年以上続く老舗は、ただ昔からの商売のやり方を繰り返しをしているだけかと思っていました。
しかし、それでは世の中が進んでいく中、取り残され衰退していくだけで、100年持ちません。
それが生き残って来たということは、伝統を守りつつも、時代とともに商売の方法を変えて来たからなのでしょう。
表面上は変わらなくても、店が生き残るために、常に動き回っているのです。
それは水の上を優雅に進む水鳥が水の中で懸命に足を動かしているのに似ています。
一方、一般の会社はどうでしょう。
業績が順調に行っていると、そのそのやり方を変えようとしません。
1つの成功体験から抜け出すことが出来ず、何ものにも挑戦しなくなり、自滅していく会社がいかに多いことか。
そんな会社が私の周りにもあります。
「成功は1日で捨て去れ」と言っているユニクロの柳井正氏の言葉の通りです。
同じ老舗である伊勢の「赤福」はどうなのでしょう。
京セラフィロソフィ
先日、本屋に行くと稲盛和夫さんが書いた「京フィロソフィ」が山高く積み上げられていました。
それを見て「アッ、とうとう出版されたのだ」と瞬間思いました。
「京セラフィロソフィ」とは京セラが稲盛さんの考えを社員に浸透させるために作った「京セラフィロしフィ手帳」がもとになっています。
この手帳が社員教育の原動力になり、京セラは創業以来一度も赤字にならない高収益企業に発展していきました。
その手帳は京セラ社員だけに限定されており、稲盛さんの勉強会である盛和塾の会員でさえ手にすることはありませんでした。
それが5年程前、その手帳に稲盛さんの解説を付けた「京セラフィロソフィ」という本が盛和塾の会員限定で販売されました。
会員限定と言われながら、社員用に購入する人が多く、増刷増刷と版を重ねました。
それがとうとう市販されることになったのです。
本の内容は会社経営のことばかりでなく、人間としての生き方も書かれています。
私はこの本を今まで何度も読み返し、勉強会も行い、学んでいましたが、まだまだ吸収しきれていません。
この本は600ページ以上あり、価格は税込で2,592円と少し高いですが、ぜひ皆さんに購入をお勧めします。
そして自分で読むばかりでなく、機会がありましたら勉強会などを開いて語り合うこともいいと思います。
新しい気付きが得れるはずです。
孫
先週の火曜日の夜、6人目の孫が生まれました。
その日の内に妻と病院に行き、生まれたばかりの孫と対面。
小さすぎて私には怖くて抱けませんでした。
家に帰って祝杯を上げました。
その後、寝て暫くして娘からメール。
生まれた孫の心臓に疾患があり、急遽大きい病院へ転送されたとのこと。
まんじりともせず夜が明けました。
翌日、妻が病院へ行って話を聞くと、その病院では手術は出来ない。
このままだと2週間の命と言われました。
この手術出来る病院は少なく、道内では北大病院。
しかし、北大病院でも10の手術例しかありません。
そこで手術経験が豊富で、100の手術例があるという東京の病院に移送することになりました。
それが一昨日の火曜日。
娘と妻が付き添い、お医者さんと看護婦さん同行で、救急車で空港へ。
無事東京の病院に着き、翌日手術が行われました。
本手術前は1ヵ月後に行われるようです。
また手術はその後も続き、最低でも3回予定されています。
昨日の11時に始まった手術は3時間程かかりました。
手術が成功したとのメールを妻からもらった時、少し涙ぐみました。
折角生まれて来た命。
私に何が出来るか分かりませんが、しっかり守ってやりたいと思います。
経営数字
会社経営する時、必要なモノの1つに数字を見る力があります。
経営者はせめて自社の貸借対照表や損益計算書を見て理解出来ること。
それが出来ないと適正な経営は出来ません。
会社の現在と将来が見えてきません。
今どこを走っていて、どこに向かうのかが分かりません。
将来が見えない経営は怖いです。
また逆に数字だけを見て経営する経営者がいますがこれもダメです。
経営は人の働き、文字通り「人」が「動いて」成り立ちます。
汗水たらす中から成果が生まれます。
後方の社長室で、現場から上がってくる数字だけを見ては実態が見えません。
数字だけ見て現場に指示しても現場は動けません。
ここの使い分けが出来ない経営者が間違えた経営をしてしまいます。
「数字がなければ経営は出来ない。しかし数字だけでも経営は出来ない」
これは大切なことです。
伸びる会社
ついこの間まで、不景気で人手も余り、若い人の就職先がないと言われていました。
それが今、その状況が変わり、建築や飲食産業を中心に会社は人手不足で困っています。
その人手不足の原因は、不景気だと言われている時、簡単に人員を整理をしてきた結果です。
そのような会社は社員教育もしていませんので人が育っていません。
一方、同じ建築や飲食産業の会社でも困っていない会社があります。
不景気と言われている時でも、我慢して人手を確保してきました。
その会社は景気が回復した今こそ、その力を発揮しています。
昔から「不景気の時こそ飛躍のチャンスだ」と言われてきましたが、それはこのようなことを言うのでしょう。
将来景気回復する時のために、辛くても人員整理をせず人を確保し、社員教育を施し、人材を育てる。
余剰になっている人手を新規開拓や新製品開発に向かわせる。
そして景気が回復した時は、縮んでいた身体から一気に伸び上がるように、会社は急激な発展を遂げていきます。
それが今なのでしょう。
他力
事業で成功した人の話を本で読んだり聞いたりすると、多くの人が「私の力ばかりでなく多くの人のおかげです」とか「運が良かったからです」と言います。
ある評論家は「それは成功者の成功の要因をあえて言わず、謙遜しているからです」と書いています。
でも私の周りの成功している経営者は「他力」ということを言います。
その「他力」は「自力」がなければ生まれてこないことは当たり前ですが、「自力」だけでは上手く行きません。
そして「他力」を受けることの出来る「生き方」が重要です。
この重要な示唆を早く知った人が成功へ導かれていくのでしょうね。
昔の本
先日、本棚を整理していたら学生時代に読んだジブラーンの「The Prophet」(予言者)という本が出て来ました。
学生時代、アメリカで短期留学している時、大失恋をしました。
その時に知人が英文の「The Prophet」をくれました。
訳しながら読みましたが、日本に帰って来て翻訳本を改めて一生懸命読みました。
特に「愛について」の章は何度も読みました。
Wikipediaによるとジブラーンはレバノン人で少年期にアメリカへ。
彼は詩人、画家、彫刻家であり、彼が書いた本はアメリカの知識人家庭には必ず一冊以上あると言わています。
「The Prophet」は1923年に発刊されました
現在30ヶ国語以上に訳され、数十ヶ国以上で2000万人以上の人に読まれていると言われています。
ジョン・レノンがビートルズの曲 "ジュリア "の詩にも引用されているようです。
また、皇后美智子様が皇太子妃だった頃、レバノン大統領から贈られ愛読したとも言われています。
「愛があなたを招く時は、愛に従いなさい。
たとえその道が、苦しく険しくとも。
愛の翼があなたを包む時は、愛に身を任せなさい。
たとえ羽交(はが)いに隠された愛の剣(つるぎ)が、あなたを傷つけるようになろうとも。」と始まります。
今65歳になり、この本を読むと40年以上前の若い頃を懐かしく思い出しています。
日本の若者
先日の新聞に、内閣府が調査した「日本の若者の意識調査結果」が発表されていました。
2013年11月から12月に、日本、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スエーデンの若者(13〜29歳)にインターネットで調査したモノです。
結果、「自分自身に満足している」と答えたのは1位がアメリカ86.0%、6位の韓国でも71.5%でした。
日本は45.8%と著しく低かったようです。
「自分には長所がある」の項目も日本は68.9%で最下位。
それに対してアメリカ93.1%、スエーデン73.5%です。
一方「自国のために役立つことをしたい」と考える若者は、日本が54・5%で1位。
これはすごいですね。
特に10代後半から20代前半が多かったようです。
しかし「自分の参加で社会現象が少し変えられるかもしれない」との項目では、前向きに考えると考える日本の若者は30.2%と他国より低いようです。
この結果を見て私が思うに、日本の若者は「誰かのために役立ちたい、しかし自信がない。」のではないでしょうか。
自信が持てないという原因にひとつに、日本の過保護社会があると考えます。
折角、若者が自立しようとする時、大人が手を出し口を出します。
大学入学式・卒業式や会社入社式に父兄が同伴するのもその1つ。
若い時、苦しい思い、痛い思いをしなければなりません。
それが若者の自立に必要な糧です。
自分のためでなく「誰かのために役立ちたい」という考えは尊いです。
若者が持っているその思いを叶えて上げる。
若者がその思いを実現出来る土壌作り。
社員造反
ネットを見ていたらこんな問題がありました。
孫正義さん出題の「思考力を磨く設問」というモノです。
「社長が入院中に部下20人が離反、競合会社設立。慰留に努力するか」
孫さんの答えは「慰留しない」です。
私も納得します。
社長が入院している時、このようなことが起きるのは「離反」ではなく、謀反を起こすという意味で「造反」です。
また、このようなことはよくあります。
社内で有能だと思われる人が起こします。
社長から絶対的信頼があった人が起こすのです。
そのため社長が受けるそのショックは相当なモノです。
昔、関連会社でもありました。
造反を起こした人達は主に損得で結びついている人が多いようです。
正しい主義主張があってではないので、造反した会社もゆくゆくは衰退していくのです。
そして、このようなことが起きる一番の原因は社長にあります。
任せっぱなしにし、助長させたこと。
社長の責任は大です。
社員を信頼するのはいいのですが、社長としてチェックするとことはチェックし、会社の要(かなめ)としての社長の仕事は放棄しては行けません。
三角山
先週の金曜日にフィールドワークに行って来ました。
今回は札幌近郊にある三角山。
正式には琴似山というそうです。
標高311メートルの小さな山です。
私も小さい頃から何回も登りました。
現在は山道も整備され、大変登りやすい山です。
幼稚園の子供達も登って、頂上付近でお昼ご飯を食べていました。
私たちは一緒に登ったアウトドアコーディネーターの橋詰さんから、花や木々の説明を受けながらゆっくり時間をかけて登りました。
頂上には「一等三角点」があります。
「一等三角点」は日本の国土を測量するための骨格点で重要な三角点です。
全国に980カ所あります。
ちなみに富士山頂の剣が峰にあるのは2等三角点です。
なんとなく「三角山の方が勝った」気分。
三角山山頂から見ると、眼下に大通が延びていっています。
明治の頃札幌の街を整備する時、この三角山に登り、最初にこの大通を決めたそうです。
ゆっくり登り下りて所要時間は2時間程。
熊も出ない?安全な山です。
とはいえ久しぶりの山登り。
少し足に疲れが残りました。
体力の衰え、実感しました。
小善と大善
昨夜、勉強会があり、そこでお話ししたことです。
以前にも紹介したことがあります「小善は大悪に似たり。大善は非情に似たり。」
優しいだけの「小善」は、結果その人をダメにします。
「非情」と思われても、愛情を持って厳しく接すれば、その人は大きく育つという仏教の言葉です。
今は優しさや、癒しだけが好しとされて、厳しいこと辛いことは避ける風潮があります。
人は誰でも優しいことを欲しがり、優しい人に集まり、癒しを求めます。
でもそれだけでは人の成長はありません。
少し辛くても「頑張る」ことも必要です。
それを子供に教えなければ、大人になった時、かわいそうな状態になって仕舞います。
今朝の新聞の広告欄に「努力する人間になってはいけない」という本が紹介されていました。
確かに精神的に追いつめられた状態の一部の人には、それ以上強いることをしてはいけません。
しかしそれを万人に適用することは大いに疑問です。
一方、別の考え方をしてみます。
この世の中が厳しいことや辛いことを避け、優しさや癒しばかりを求めている人が多くなった時。
その時は少し頑張れる人はその結果、大きなモノを得ること環境になったと言えます。
ただ全体的に見れば日本の国力が低くなっていく可能性も高いです。
10年後20年後が心配です。
函館旅行
先週末、妻と函館に行って来ました。
予定は全て妻が立ててくれたのですが、なかなかいいプランでした。
朝8時過ぎの特急で函館に向かいました
まず電車に乗る前に買った駅弁で朝食。
4時間で函館到着。
1時頃に最初の目的地「五島軒」へ。
「五島軒」は明治12年開業のレストランでカレーが有名。
その後ハリス教会などを見て回り、ホテル「ラ・ビスタ函館ベイ」へ。
このホテルは13階に露天風呂があり、源泉掛け流し。
それに朝食が日本で1位2位を争う程美味しいとの評判。
翌朝に備えて夕食はこれまた函館名物「ハセガワストアー」の焼き鳥弁当で済ましました。
朝食はバイキング形式で、イクラ、タラコ、エビ、マグロ、イカが山盛りに置いてあり、丼飯に盛り放題。
その他の食材も豊富。
充分満足。
9階の客室からはライトアップされた箱館山と町並みがきれいです。
2日目は少しでもエネルギーを使おうと徒歩で函館観光。
昼食はこれまた函館で有名な塩ラーメン「あじさい」へ
2日間の函館観光充分楽しみました。
旅の終わりに、これまたまた日本で一番美味いと言われる程有名な「ラッキーピエロ」のハンバーガーを買いました。
娘夫婦の土産も考えて少し多めに。
帰宅後夕食で食べましたがこれまた美味かった。
今回はB級グルメの旅になってしまいましたが、楽しい旅でした。
少し太りました。
スーパーマーケット
今朝の日経新聞「春秋」の欄に書かれていたことです。
1960年代に誕生したスーパーマーケット。
そのトップであったダイエーが1972年に小売業として売上高日本一の座を三越から奪ったのです。
このコラムを読んで当時のことを思い出しました。
当時私は大学生で、新宿の三越のお酒売り場でアルバイトしていました。
ある日の朝礼で上司から「小売業売上で三越はダイエーに抜かれてしまいました。」と発表がありました。
「三越がダイエーに抜かれた?!」
皆が驚きの声を上げたのを覚えています。
その時からスーパーマーケットとデパートとの売上げの差がドンドン広がっていきました。
大げさに言えば、私は歴史的転換時にその場にいたような思いがします。
40年程前のことでした。
そのスーパーマーケットもコンビに追いかけられ、そして今はネット通販に抜かれています。
つくづく世の中の移り変わり感じます。
おもてなし
元NHKアナウンサーだった鈴木健二氏が書いた「気配りのすすめ」という本が大分以前ベストセラーになりました。
また今、「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことで、海外では日本の「おもてなしの心」が注目されているようです。
海外では注目されている「おもてなし」も、日本では昔から自然になされていたサービスだと思います。
「気配り」や「おもてなし」を少し自分なりに分析してみました。
<strong>目配り</strong>:何か起きていないかチェックする。
<strong>気遣い</strong>:心配するに近い気持ち。
<strong>気配り</strong>:相手に気を使う。
<strong>気働き</strong>:目の前の事ばかりでなく、先の事、全体の動きを気にする。
<strong>心遣い</strong>:心配り:思いやりの心。
<strong>心に添う</strong>:自分の心をお客様の心に合わせる。
日本のサービスの世界では、「気配り」まで出来る人は多くいますが、「気働き」以上のサービスが出来る人はまだ少ないようです。
また、「心に添う」接待が、「おもてなしの心」の究極と思います。
「おもてなし」というと10年以上前に出版された「おこしやす」という本を思い出します。
京都老舗旅館「柊家」で60年中居をしていた田口八重さんが書いた本です。
機会があったら読まれるといいです。
ボケ防止
先日テレビで認知症のひとつであるアルツハイマーに関しての番組がありました。
ちょっと興味がありましたので、妻に大事なところをテェックしてもらうように依頼しておきました。
そのメモがここにあります。
メモには、「食事はカレーがいい」
その中でもウコンがいいそうです。
2つ目に「雑談を楽しむこと」
相手の話をどう聞いて、どう広げていくかを考えるようにする事。
3つ目「アウェーの場所に身を置く」
4つ目「ど忘れ、物忘れを思い出すようにする」
5つ目「指先を使うようにする」
6つ目「新しい事を習う」
この6つがあります。
この中で私が一番「アッそうだ!」と思った事は3つ目の「アウェーの場所に身を置く」です。
以前は知らない所や、知らない人に会いに毎日のように行っていたのが今はそれも少なくなりました。
異業種交流会にも出なくなりました。
この6つの「アルツハイマーにならない行動」
これから意識していきます。
餃子店の女性
先日ランチを食べに地元の餃子店に行きました。
餃子もおいしかったのですが、そこでカウンター内で働いている女性の気働きの良さに感心しました。
その後日、持ち帰りの餃子を買いに行った時、「どのくらい勤めているのですか?」と聞くと23年との事。
その後、知人からその女性の事を聞く機会がありました。
その話では「彼女は伝説の人ですよ」とのこと。
彼女の気働きに感心したある店のオーナーがスカウトしたそうです。
その時彼女は提示された月50万円の報酬を蹴ったとのこと。
そしてそのまま今のお店で働いています。
その店には働きがいがあるのでしょう。
彼女のような従業員はその餃子の会社にとって宝です。
またそのような彼女が「勤め続けたい」と思う会社も働きやすい素晴らしい会社なのでしょう。
この餃子店は「みよしの」琴似店です。
ご存知の方もいるのではないでしょうか?
JAZZbar
昨夜は友人に誘われてライブバー「DeeDee」に行って来ました。
この店は西区24軒にあります。
以前は美容室があった場所ですが、しばらく空き店舗のままでした。
今のマスターがそれを1年以上前から借り、ライブバーにしています。
この店は毎週火曜日はJAZZセッションの日と決め、楽器の好きな人たちが自分の楽器を持ち寄りセッションしています。
昨夜はサックス、トランペット、トロンボーンを持ち寄った人達が楽しそうに演奏していました。
私の友人はベース担当。
皆のバック演奏のためにズーっと弾きっぱなし。
昨夜のこの店は、演奏目的のお客さんで満杯になり大盛況。
「素人の人に自分の楽器を演奏する場を提供する」という目論見が当たったようです。
立地的にはこの店は住宅地にあり、決して恵まれていません。
それでも音楽を楽しむ目的のあるお客様は来てくれます。
土曜日は「歌いたがりサンデー」と謳い、ピアノの伴奏で歌えます。
歌いたい人が集まって来ます。
その他に「JAZZ勉強会」を開いたり、「ソロギターの演奏会の日」を作るなど、マスターは色々な仕掛けをしてお客さんを集めています。
商売は仕組み作り。
経営の参考にもなるお店です。
また、行ってみます。
真剣さ
何日か前に、ある人と親の話をしている時、父の事が題材になりました。
その時、私は「父はこうすればもっと良くなり、会社もこうなっていた」と話していました。
決して批判したつもりはありません。
その夜、父の夢を見ました。
夢の中で父は私の後ろの方から刀を持って追いかけて来たのです。
びっくりしましたが、振り返りすぐに父と対峙しました。
その時、父は真剣を持っているます。
私は木刀です。
「何それ?」と思って夢は終わりました。
夢の中で父は一言も話していません。
不思議な夢だなと思っていましたが、ハタッと気付きました。
父は仕事に対して真剣で対峙していた。
それに比べ私は真剣を持てず、ただ木刀を振りかざしているだけ。
翌日その話を妻に話すと「昨日はお父さんの月命日だった」言います。
偉そうな事を言っている私に、父は夢の中に出てきて仕事への「真剣さ」を教えてくれた。
そんな気がします。
感謝
今、札幌大通高校で、起業支援の講座を開いて、参加者の皆さんに色々な話しながら、私自身改めて心に落とし込んでいる事があります。
「感謝する」ことです。
自分の過去の出来事や現在の有り様を不満に思っていると、何事においても文句が口から出て来ます。
素直になれず不満ばかり言っています。
そして益々自分が惨めになります。
そんな自分が嫌になった時は自分を変えるチャンスです。
チョットだけ自分の意識を変えてみます。
自分の人生を振り返り、今まで生かしていただいた事に感謝し、辛かった事や苦労もいろいろ経験をさせていただいたと考えてみます。
そして真似事でもいいから手を合わせて、心の中で「感謝します」と唱えてみます。
しばらく続けていると、何となく心が変わってくるのが分かるはずです。
自分の心が少し変わると言動も変わります。
その内に自分の現在の環境を見る目も変わって来ます。
気付きが生まれて来ます。
その内に自然と感謝して手を合わせている事に気付きます。
「感謝せよ!」は稲盛和夫さんからの教えでもあります。
「お前には感謝の『か』の字もないのか!」
10年前の自分と少しだけでも変わることが出来たのは、「感謝」という言葉を気付かされたからだと思っています。
感謝!
もめ事
起業している人の中で、人との「もめ事」を起こす人と起こさない人がいます。
勿論「もめ事」を起こさない人の方が起業は成功しています。
その理由は簡単です。
「もめ事」を起こさない人は成功の風に乗っていくから、楽くにそれほど苦労なく進みます。
ところが「もめ事」を起こす人はその風に向かって進もうとするから、自分は頑張っているようでほとんど前に進みません。
下手すると押し戻されされてしまいます。
「もめ事」を起こさない人は「素直」で、人を思いやる「利他の心」があります。
ですから支援してくれる人が周りに沢山います。
「もめ事」を起こす人はこの逆です。
自分中心の考えをしているのと、支援してくれる人は少なくなり、足を引っ張る人が現れます。
成功する人とそうでない人。
チョットした違いなのですが、それに気付き、自分を変えれるか
成功する人は自分を変えて来た人です。
「徳」
「功ある者には禄にて報い、徳ある者には地位にて報いる」という言葉を知っている人も多いと思います。
ただ、これを知っていてもそれを経営に生かし切れていない例をよく見ます。
特に若い社員の場合に見受けられます。
業績を上げている人を報酬で評価するだけだと、それに満足せず会社を辞め、別会社に行くか独立してしまいます。
だからと言って業績を上げただけで、簡単に主任や係長という地位を与える事で、組織がおかしくなる事もあります。
一方、若くてもその地位を与える事でその人間が成長するという考えもあります。
そのような事例も私は見て来ました。
やはり人には「徳」なのでしょう。
生まれながら持っている「質」もあるのでしょうが、家庭、学校、そして会社においての教育。
これによって人は育てられる。
そしてその手本となる、親、先生、上司の生き方も問われてきます。
会社の大義名分
会社を経営する時、大事なものの1つに「大義名分」があると思います。
それはの経営理念として示される事が多いでしょう。
会社は登記手続きすれば誰でも作れます。
しかし、それに事業が伴って初めて会社になります。
事業にはそこで働く人がついています。
働く人がいて事業と言えます。
ある会社の例
会社が事業を拡大して利益を出します。
その利益で優良土地を買いました。
その土地が駐車場として成り立つ場合、それも1つの事業になります。
時が経ち、本来の事業に限りが見えた時、社長はその事業を子会社化し、専務を社長にし、本体会社から切り離します。
本体会社は駐車場事業だけで、一人社長でも経営出来ます。
駐車場経営はほとんど経費もかかりません。
利益を十分出します。
しかしこれは誰のための事業でしょうか。
一方、切り離された子会社は、多難な経営環境が待ち受けています。
そこには働く多くの従業員がいます。
子会社の経営が上手く行かなければ倒産です。
でも子会社が倒産してもは別会社ですから、本体会社には影響がありません。
本体会社は駐車場経営で営々と生き延びて行けます。
そのような会社が最近多くなって来ているのではないでしょうか。
社会のため、従業員の幸せのためと言う会社の存在の「大義名分」を失った結果です。
5月
今日から5月。
そして1日。
今朝、妻と共に琴似神社と北海道神宮で参拝して来ました。
5月になると札幌も春本番。
そして、毎年5月になるとつい口ずさむ詩(うた)があります。
「風薫る、五月の空に、立ち昇る、柴の煙と吾が思いかな」
庵千秋(いおりせんしゅう)の詩です。
今月もいい事が沢山起きそうな気がします。
追伸
庵千秋は私のペンネームです
「損」について
先日の新聞の広告欄にあった本の中の言葉です。
「損をしたくないと考えるか、損をさせたくないと考えるか」
これはいい言葉だと思います。
会社を経営する時、経営者は損得を第一に考えます。
経営者はどんな立派な事を言っても、利益を出さない経営者は失格です。
しかし、自分の利益だけを考えても会社は衰退していきます。
自分以外のお客様や取引先の事を考えないと、商売は縮小していきます。
だいぶ昔に読んだダスキンの駒井元社長が書いた本の言葉を思い出します。
「ダスキンは損と得の道あらば損の道を行く」
人が嫌がり、損をするかもしれない事をしてこそ、そこに仕事はある。
「損だと思っても儲けの道はある」という事でしょうか。
今の日本、「経営はきれい事でない」と言って、自分の事、自分の会社の事しか考えない経営者が多くいます。
そのような時だからこそ「損をしたくないと考えるか、損をさせたくないと考えるか」という言葉が光ります。
「利他の心」や近江商人の「三方良し」も同じ事でしょう。
星置緑地
先週の金曜日は予定通りフィールドワークに行ってきました。
私が住んでいる琴似からJRで10分くらいにある、星置という所です。
星置駅から歩いて10分くらいの所に「星置緑地」があります
ここは周りを住宅に囲まれながら湿地緑地として管理されています。
木道を歩きながら谷地ダモの木の間に水芭蕉、キクザキイチゲ、エゾノリュウキンカの花。
水面にはアカガエルの卵と孵ったばかりのカエル。
ペアの鴨も水面に首を突っ込み、懸命にエサ食べていました。
同行していただいた講師の方が北大演習林勤務時代にこの「星置緑地」作りに尽力されたそうです。
ですから、最高の先生からの野外授業です。
花や木々の植物の話ばかりでなく、その写真の撮り方も教えていただきました。
札幌の市街地でこれだけの水芭蕉がある場所は他にありません。
この楽しいフィールドワークは毎月1回、9月まで続く予定です。
来月は三角山の予定です。
<a href="http://blog-imgs-69.fc2.com/y/a/m/yamachioffice/P1000319.jpg" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-69.fc2.com/y/a/m/yamachioffice/P1000319s.jpg" alt="水芭蕉" border="0" width="90" height="120" /></a>
フィールドワーク
今日はこれからフィールドワークに出かけます。
レンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」に入居しているミスネットワークさんが主宰する「ヤマチカルチャーサロン」の講座の1つです。
北大演習林に勤めていた方が講師。
水芭蕉などの花や、芽吹いたばかりの木々を見に行ってきます。
札幌の天気は晴れ。
予想気温は22度。
楽しみです。
また今日の夜は札幌大通高校での講座があります。
12時頃にフィールドワークから戻り、最終準備予定。
チョット忙しくなりそうです。
お金の使い方
週1回の札幌大通高校での講座が明日あります。
先週の講座の時、いろいろな質問が生徒さんから質問表で提出されました。
明日の講座ではそれについて私なりの考えで答えていこうと思っています。
その質問の中の1つに「お金の使い方」がありました。
今日はこのことについて書きます。
第一に、お金はお金が好きな人のところに集まります。
人にお金が好きかと聞いても、お金が嫌いだという人はほとんどいないでしょう。
皆が好きだと答えます。
それでいて、ここに100万円があり、好きに使っていいと言われれば、それまでほしいと思っていたブランドのバックを買ったり、海外旅行に行くかもしれません。
そうするとお金は無くなります。
結局その人は本当はお金が好きよりブランドのバックが好きであり、海外旅行が好きなのです。
お金一番好きなのではないのです。
だからお金が無くなってしまうのです。
昔に聞いた貧乏人、普通の人、金持ちの話です。
コップにジュースを注ぐと、コップにいっぱいにならない内に飲み干してしまうのは貧乏人。
コップにいっぱいになるまで我慢して、いっぱいになってから飲む人は普通の人。
金持ちはジュースがいっぱいになっても飲まず、溢れ出すジュースを受け皿で受け、それだけを飲みます。
だからいつもコップ1杯分のジュースは残っているのです。
これはお金の使い方と同じです。
お金に好かれる生き方。
お金持ちの多くはそんな生活をしているのではないでしょうか。
起業家
昨夜、起業家の交流会がありました。
その時ある人から「もう私たちは起業家なのだろうか?」という意見が出ました。
この交流会は5年ほど前に立ち上がり、その時のメンバーも今では既に社長としてしっかり仕事をしています。
ですからもう既に起業家ではなくなって、一人前の経営者になっていると言うのです。
確かにそうです。
でもそれでは起業家というのはどの時点までを言うのでしょうか?
少し疑問に思いました。
自分なりに考え、その末に思い当ったこと。
それは、「経営者が常に挑戦心を持ち続けている限りは起業家なのだ」ということです。
毎日の仕事に慣れ、上を目指さなくなった時、起業家ではなくなる。
そんな風に思います。
そんな事もあり、今までの起業家の交流会は昨日で一旦幕を下ろしました。
次回は新しいメンバーを迎える交流会を開く事が決まりました。
また新しい人との出会い。
楽しみです。
起業!いやその前に
先週の金曜日から札幌大通高校での講座が始まりました。
昨年に引き続き2回目です。
昨年のテーマは「身の丈起業について」でしたが、今年は「起業!いやその前に」と題して進めます。
社会人の方の参加は5名、その他は高校の3年生が中心です。
テーマを「起業!いやその前に」と題した理由です。
たとえ起業家が作ったビジネスプランがいくら良くても、また事業計画書が良く出来ていたとしても、起業の成否は経営者の人間としての「質」大きく影響すると私は考えます。
今まで多くの起業家や経営者とお会いし、話をしてきました。
成功する人はそれなりの理由が、失敗する人はそれなりの原因があります。
講座ではその経験と稲盛和夫さんからの教えを中心にお話しようと思っています。
6月までの続く講座、今から毎回が楽しみです。
トップセールスウーマン
先日同系会社の株主総会があり、そこでの話です。
その会社は住宅部門が中心となっているのですが、その営業のトップスリーが女性だそうです。
そのの中でもトップは毎年その位置を維持し、年間22棟受注。
驚く事に、50歳代のその彼女は過去営業経験はなかったそうです。
今の営業の前は別部門でコーヒーショップのサービスをしていました。
その仕事ぶりが買われ営業になった経緯があります。
社長の話では、好成績の1番の要因は人柄だという事です。
誠実でお客様から信頼を得、その上人柄が良いとのこと。
私も過去営業経験が長く、営業では色々な苦労がありました。
セールストークの勉強、マーケティング調査などをしましたが、結局基本は「人」なのですね。
「人柄」「人格」「考え方」です。
難しく考えず、ただ「自分磨き」をする。
その彼女に会いたくなりました。
「寝がけ」学習
先日鹿児島へ行った時、鹿児島大学で講義を受けたと以前に書きました。
その時受けた講座で教えられた事を1つ披露します。
ご存知のように、人の頭の中には「プラス思考」と「マイナス思考」があります。
そして圧倒的に「マイナス思考」が頭の大部分を占めています。
だからつい消極的な考え方になりがちです。
それを改善する1つの方法を教えてもらいました。
「寝がけ」を利用するのです。
「寝がけ」とは夜寝る直前、ウツラウツラしている状態です。
寝床に入ってウツラウツラ時に、心安らぐ、ポジティブな考えになれる本を読みます。
昔に流行った睡眠学習法のようなモノです。
ウツラウツラしているので、抵抗なく頭の中に「ポジチブ思考」が入り込んでいきます。
稲盛和夫さんも昔から毎日寝床で本を読むそうです。
酔っぱらって帰って来た時でも必ずそうしているそうです。
元来素直な私は早速それを真似ています。
始めたばかりでまだ効果は出てきませんが、これから続けてみようと思います。
女房と畳は
日本の言葉について。
昔からの言葉で「女房と畳は新しい方がいい」とか「糠味噌女房」というのがあります。
どちらも「使い古した女房」として悪く比喩した言葉と私は理解してきました。
ところがある本を読むと「そうでない」と説明されています。
「女房と畳は新しい方がいい」は「亭主と畳は新しい方がいい」と言い換えてもいいのです。
畳は藁で出来た畳床と、その上にイグサで作られた畳表で出来ています。
畳替えをするというのは、畳床は変えず、畳表を裏返しにしたりして新しくします。
好きで一緒になった夫婦も、毎日の生活の中で男は生活に疲れ、女は恋に倦んでくる。
古い畳を表替えした畳がいいように、男も女も新鮮でいなければならないという意味のことわざなのです。
また「糠味噌女房」もそうです。
毎日ごちそうばかり食べていると飽きてきます。
やはり美味いお茶漬けが欲しくなります。
美味い茶漬けには美味い新香、香の物が必要です。
毎日糠味噌をかき混ぜながら美味しい新香を作る事の出来る女房。
人生の旨味が出て来た偉い女房、賢い女房を「糠味噌女房」と言うのだそうです。
このように説明していましたが、よく考えてみたら「女房と畳は新しい方がいい」とか「糠味噌女房」という言葉は
今ではほとんど使われていませんね。
折角に日本のいい言葉。
残したいものです。
配偶者控除廃止
新聞やTVの報道で「配偶者控除廃止」に関してニュースが多いです。
安倍首相の話では、「女性の就労拡大が目的」だと謳っています。
でも実際は増税目的である事は明白です。
借金が1000兆円を超える今の日本の財務状況を見れば仕方が無いのでしょう。
これからも、とれる所から取っていこうという政策が増えると思っています。
この「配偶者控除廃止」について妻と話した事があります。
妻は「私たちのように5人も子供がいたら、働きに出れなかった。
5人の保育料を払うだけで稼いだお金以上が飛んで行ってしまう」と言います。
確かにそうです。
また、統計資料によると、子供1人当たりの保育にかかる公的資金は月当たり20万円かかるとあります。
公的資金とは税金です。
私たちは5人の子供がいますので、全員を保育に出せば単純計算で20万円×5人=100万円の税金がかかる事になります。
年間1200万円です。
妻が専業主婦であったため、子供を保育園に出さず、国や市にその税負担をさせなかった。
その分私たちが支払ったようなモノです。
妻と私2人の話の結論としては、「これからは5人も子供を産む事は、産みたくても産めない日本になっていくね」という事でした。
これはまた国の少子化対策に逆行するような気もしますが。
鹿児島
先日は福岡で開かれた盛和塾例会がありました。
その時、折角九州まで来たのだからと、10人ほどの仲間と鹿児島まで行きました。
「西郷南州顕彰館」では西郷さんの本当の名前は西郷隆永(たかなが)というのを知りました。
江戸時代島津家の別邸であった仙巌園(せんがんえん)では島津家の末裔である島津さんに迎えていただき、案内していただきました。
案内していただいた島津さんも盛和塾生です。
仙巌園隣の集成館で「薩摩切子」が作られています。
少し高かったのですが「杯」を1つ買いました。
夜6時からは鹿児島大学内で、私達だけのために講座を開いてくれました。
鹿児島大学は稲盛さんの母校。
そこに稲盛さんの経営学を専門に研究している奥教授がいます。
奥教授に2時間にわたり、経営の12か条、フィロソフィーについて教えていただきました。
深く分析され、考察された話に目から鱗が落ちる思いがしました。
夜は島津さん奥教授も参加していただき宴会。
翌朝は鹿児島県内にある知覧に行きました。
武家屋敷も有名ですが、知覧は戦時中「特攻基地」があった所です。
そこから多くの若者が飛び立って行きました。
特攻に飛び立って行った隊員の遺書等が展示されている「知覧特攻平和会館」
「特攻の母」と慕われた鳥浜トメさんが営んでいた「富谷食堂」を復元した「ホタル館」
涙流しながら見入りました。
その日夜遅く帰宅しました。
振り返ってみても本当に充実した3日間でした。
尊敬される営業マン
8日から昨日10日まで、初めて九州に行って来ました。
8日は福岡で稲盛和夫さんの勉強会「盛和塾」の例会がありました。
全国・海外から塾生が集まり、参加者は1400名を超えていました。
例会では2人の経営者による「経営体験発表」があり、それぞれに稲盛さんがコメントを述べられます。
その発表者の1人のS社長の話です。
高卒とともに義兄の医薬品卸の会社に入社し、すぐに営業担当となりました。
担当先は九州大学医学部。
当時Sさんの会社は九州医学部との取引は圧倒的に少ない状況にありました。
しかも競合会社の営業担当は営業部長。
「高卒」対「部長」の構図です。
圧倒的な不利な立場。
Sさんは経験が無いながら、取引拡大すべく毎日昼夜関係なく病院内を廻りました。
競合会社の担当者が会社を退社する夜の6時からも医学部に顔を出し、若さを武器にきめ細かい営業を続けました。
仕事を通して信用を得、人脈を作っていったのです。
Sさんの懸命な働きにより、ついには九州大学医学部の病院のほぼすべての仕事を受ける事が出来ました。
このSさんの経営体験発表に対して稲盛さんから賞賛の言葉がありました。
稲盛さんの言葉の中で私が特に心の残った言葉がありました。
「あなたが営業マンとしてものすごい成績が残せたのは、信用以上に尊敬される営業マンになったからです。」というものです。
「尊敬される営業マン」
素晴らしいです。
Sさんの会社は、入社時1億円程度の会社が、彼が社長になった今485億円になっています。
翌日は折角九州まで来たという事で、鹿児島まで足を伸ばしました。
そこでも色々な体験と驚きがありました。
それは次回ご紹介します。
福岡・鹿児島旅行
今日から福岡・鹿児島へ行きます。
今日、福岡で稲盛和夫さんの勉強会「盛和塾」例会が開かれます。
今回は九州まで行きますので、ついでに稲盛さんの故郷鹿児島にも行く予定です。
夜は鹿児島の塾生と懇親会がある予定。
芋焼酎を飲み過ぎないよう気をつけなければ!
この旅行は15人位の仲間と一緒で楽しい旅行になりそうです。
番屋
先週の金曜日の夜。
銭函海岸にある「番屋」で会を催しました。
その「番屋」は知人が所有する建物で、中は食堂形式、それに海にせり出した10坪ほどのベランダがあります。
この「番屋」は普段は開いておらず、お願いをするとその知人が開店し、漁師料理を作ってくれます。
天気がよければそのベランダの炉端で魚や貝などを焼きながらお酒が飲めるのですが、その日はあいにく強い風と雨の悪天候。
それでもその日本海の荒海を眺めながら美味い酒を飲みました。
荒海を見ながら飲むのもいいものです。
またその日はその番屋に寿司の職人さんが来てくれ、美味い焼き魚の他に豪華な舟盛り。
そして寿司の握り。
握ったそばからドンドン食べていく。
会は大いに盛り上がりました。
7月にまた「番屋で遊ぼう会」を開く予定です。
その時はまた、良き仲間と海に輝るきれいな夕日を見ながら楽しめそうです。
社畜という言葉
時々新聞などで見る言葉で「社畜」というのがあります。
「社畜」とは会社に飼いならされたという蔑視の意味があります。
好きな言葉ではありません。
誰がそのようなことを誰に向かって言うのでしょうか?
動物の世界では、野生だった犬や豚は人間から安全と食べ物を与えられて家畜化します。
社畜とはそのことを言っているのでしょうか?
会社では社長が先頭に立って会社を発展させ、社員の物心両面の幸せを追求します。
社員が安心して生活が出来、幸せを感じれるようにするのです。
それを家畜と同じというのでしょうか。
世間受けしそうな、変にセンセーショナルな言葉が最近出て来ているように思います。
小判サメ商法
昨日昼食を食べに行った店の話です。
この店はメイン通りから脇道に100mほど離れ、地下鉄やJRの駅からも離れている場所にあります。
普通の食堂です。
入店した時は、お客さんがいなく、「入らない店か?」かと思っていました。
12時に前に食事が終わり出ようと思った時、お客さんがドドッとと入って来てました。
25席ほどある店は一気にいっぱいになりました。
お客さんのほどんどは、道を挟んだ向かいにある区民センターの利用客のようです。
区民センターでサークル活動をした人達が仲間と一緒に食事に来たのです。
店員さんに聞くと毎日とのこと。
この店の周りにはあまり飲食店は無く、区民センター利用者のたまり場なのかもしれません。
区民センターという別の施設が人を集めてくれます。
ある意味この店は「小判サメ商法」をうまく取り入れていると言えるでしょう。
その上、この店は出前も積極的にしており、私の会社にもチラシがよく入ってきます。
そう言えば食事中にこの店の電話がよく鳴っていました。
出前の注文なのでしょう。
店の売上+出前の売上。
効率のいい商売の様です。
場所も脇道に入っているので店の賃料も安い。
よく考えられた経営コンセプトだと感心しました。
消費税アップ
今日4月1日から消費税が3%上がり、8%になりました。
先月末からマスコミが国民の不安感を煽るような報道しています。
それに釣られて買い溜めする人も多いようです。
一方、先日には、日本の「食品ロス」が年間500トンから800トンもあると報道されていました。
あるデータによると、これは国民が毎日おにぎりを2個捨てているようなものです。
その「食品ロス」の半分以上が家庭から出ています。
買い溜めしたけど賞味期限が1日過ぎたからと言ってまだ食べれるのに捨てるとか、面倒だからと言ってまだ食べられる菜っ葉の切れ端を捨てるとかする
食品をゴミにしています。
裕福さの中で、日本人の思考が節約するよりも買いだめに走る。
このアンバランスさが恐い気がします。
大事なのは日々の無駄をなくすこと。
勿論これは自戒を込めて書いています。
お伊勢参り
先週末、伊勢神宮に行ってきました。
今年で3度目。
年々参拝者が増えているようです。
1日目は外宮に、2日目は内宮へ参拝。
いつものように神宮会館に宿泊し、翌朝6時30分内宮参拝へ。
神宮会館の係員の先導で、2時間弱かけて内宮にある各お宮の説明を受けながら歩きます。
去年は遷宮の年で、外宮と内宮の正宮が新旧共に建っていました。
日中は混雑して参拝も大変ですが、朝のこの時間はゆっくりお参りして歩けます。
昼頃に「おかげ横丁」を歩きましたが、ここも大変な混雑で歩くもの大変。
ランチは念願であった、「豚捨(ぶたすて)」の牛丼を食べました。
昨年も一昨年もタイミングが悪く食べれませんでしたので、3年越しの牛丼です。
松坂牛を使った牛丼、1000円と少し高いですが美味かった!
妻と2人の「お伊勢参り」
毎年の2人の行事としています。
久しぶりにゆっくり妻と話が出来ました。
サイゼリア
昨日ランチを食べに「サイゼリア」に行ってきました。
行くのは2度目。
サイゼリアのランチは500円。
スパゲティでもハンバーグ定食でも、スープ(お変わり自由)がついて500円です。
プラス100円でコーヒーやソフトドリンクが飲み放題。
グランドメニューで一番値段が高いリブステーキでも1000円以下。
ネットで調べるとサイゼリアは全国でも同様のサービスをしているようです。
このような価格と内容では周辺の他店はランチ戦争で苦戦していることでしょう。
ラーメンとか寿司のように業態が違えば太刀打ちできるでしょうが。
イタリアンの店がこの周辺に3~4件ありますが、大変でしょう。
サイゼリアは500円でも十分採算が取れる戦略を作り上げて店を展開しています。
飲食産業では売上利益率が平均5%と言われているところサイゼリアは10%もあります。
世界で1000店舗展開している会社とまともに価格で競争するのは無理です。
同じ琴似にあり、夫婦で経営するあるイタリアンレストランはミシュランにも載っています。
そこは予約しなければ入れません。
価格はそれほど高くはないのですが何が違うのでしょうか。
今月初めから琴似のランチ食べ歩きを始めて17軒。
美味しいモノを食べるばかりでなく、その店の業態と、店の方針、その営業方法などがを見ると経営の参考になります。
食べ歩きは来月も続けます。
食べ歩きをしながらいい勉強をさせてもらっています。
人の能力
「おだてりゃブタも木に登る。けなせば河童もおぼれ死ぬ。」
この言葉は皆さん聞いたことあるでしょう。
しかし知っている言葉なのに、それを実際にそれを生かしているでしょうか。
会社の中で優秀な人、普通の人、ダメと思われている人、さまざまな人がいます。
その人達の力を最大限に引き出す。
それが出来るかが会社の成長を左右します
またそれが会社の中で出来る人は、直接の現場から離れている社長しかないと思います。
何千人の大企業にならばそういかないでしょうが、そうでなければ社長の職務としてしなければならない事でしょう。
実際に多くの社員と定期的に直接面談をしている社長もいます。
社長にとって全ての社員は、会社のために働いてくれる可愛い社員です。
その社員の力を見出し引き上げる。
自分の子供を育てるようなものでしょう。
昔に読んだ本の中に、ある会社の中に渉外担当取締役(記憶違いかも?)という肩書きの人が紹介されていました。
その人は恰幅が良くまた大変温和な人です。
彼の仕事は、会社に関係する冠婚葬祭の時、社長など役員の代わりに出席するだけの仕事です。
その人が出席すると「取締役の人が来てくれた」と相手方は喜びます。
また本人も会社を代表している思いをもって、仕事に満足します。
その人の特性を生かした仕事です。
本当にそのようなことがあったのか不確かですが、私は何かある度にそのことを思い出します。
ぜひとも、社員の事を知りましょう。
社員の能力を見い出さず、「うちの会社には人材がいない」と嘆くのは止めましょう。
金融円滑化法
先週の日経新聞に「中小企業の転廃業促す」という見出しの記事がありました。
「金融庁は中小企業金融円滑化法に基づき返済猶予を受けて来た中小企業に対し、転廃業を促す方針に転換した」と書いてあります。
円滑化法は去年の3月に終了していましたが、その後も中小企業に対しての借入返済期限の延長はなされてきました。
表向きは各金融機関の判断とされていましたが、急激な企業倒産を防ぐため金融庁からの指示い基づいていたと思われます。
それが今回は表だって金融庁から円滑化法の中止が告げられたのです。
これからは金融機関の借入企業にたしする対応は激変すると思われます。
今後、各金融機関は支援している借入企業に対して①早期の事業再生②事業再編③業態転換④休廃業を迫まることが出来ます。
しかし①~③までの方法は、出来る企業は既にしています。
出来ていない企業がほとんどでしょう。
そうなると④の休廃業しかありません。
このように大事なニュースもテレビでは報道されていません。
不思議なものです。
13年の4月から12月までの対象融資件数は86万件。
今まではその内の97%に対して融資延期を認めてきました。
今後はそうはいかないでしょう。
4月以降消費税が上がると消費が落ち込むことが予想されます。
それに伴い倒産件数が急激に増えそうです。
該当する企業は、「会社を早目に止める」という経営者の決断も傷口を広げない為には必要かもしれません。
日本の財政
昨日藤巻健史氏の講演会に行ってきました。
ご存じの方も多いと思いますが、藤巻氏はアメリカのモルガン銀行で屈指のディーラーとして実績を上げ、初の外銀日本人支店長として活躍されました。
現在は㈱フジマキ・ジャパンを立上げ、経済コメンテータとして一目置かれています。
また現在は参議院議員でもあります。
講演は「新・日本経済論」と題して、日本の財政事情と今後の予想についてです。
話しの最初に日本財政の現状を説明されました。
平成25年12月現在の国債発行額は1018兆円。
また平成25年度の実績は、歳入が47兆円、歳出が93兆円、差し引き46兆円の赤字国債が発行されました。
今年の予算も先日決まり、その内訳は歳入が55兆円、歳出は96兆円で、41兆円の赤字国債発行予定です。
改めて数字で見ると借金はどんどん膨らみ、日本の財政は大変な状況です。
このままでは近い内に日本の財政は破綻することが予想されています。
藤巻氏の話では、もはや対処の方法はなく、個々人でその時に備える必要性を説いていました。
今年の年末は注意が必要とのことです。
三浦雄一郎氏
昨日銀行が主催する講演会に行ってきました。
講師は三浦雄一郎さん。
演題は「80歳エベレスト登頂 希望への軌跡、そして未来」です。
冒頭DVDで登頂の記録を流し、その後に三浦さんのお話。
エベレスト登頂は様々な危険があります。
遭難はいつ起きてもありません。
それが起きるのは3対7の割合で登る時より下りの方が多いそうです。
現に三浦さんも下りの時に疲労困憊して、やっとの思いで下山したのです。
またエベレストを昇るルートはネパール側とチベット側にあります。
チベット側の方は5000m位までは車等を利用して行けるのに対して、ネパール側は麓から登らなければなりません。
ネパール側からの方が登山者にとって負担が重いのです。
現在チベットは中国の管轄内のためチベット側からの登りは難しいようです。
三浦さんは70歳でエベレスト登頂に成功しましたが、信じられないことに60歳の頃はメタボで成人病もたくさん抱え、狭心症でもありました。
身長165㎝なのに体重は90kg。
少し階段を上るのも息が切れたそうです。
そこで三浦さんは一大決心をしました。
エベレスト登頂を目指したのです。
メタボで成人病だらけの人が10年後にエベレスト登頂に成功したのです。
また、登ろうと思ったその気力に驚きです。
最初、トレーニングの初めとして自宅の裏にあった札幌藻岩山を登りました。
ところがたった500mほどの山を登れず、途中で断念しました。
自分体力の無さが情けなく、また恥ずかしかったそうです。
それから本格的にトレーニングを開始しました。
足にアンクルウェイトという重りを付け、鉄アレイの入ったザックを背負い、どこへ出掛けるのもその格好で行きました。
講演の最後にそのような経験から三浦さんは2つの健康法について話してくれました。
「守りの健康法」と「攻めの健康法」
「守りの健康法」は肉食を避けるとか脂のある食べ物を避ける、野菜を多く取る等なるべく健康の悪いことをしない方法。
「攻めの健康」はあえて身体に負荷をかける方法です。
身体に重りを付けるのはまさにそうした健康法です。
以前見たテレビで医者が「身体に負担をかける方が骨が強くなる。骨粗鬆症を防げる」と言っていました。
「攻めの健康法」は理にかなっているのかもしれません。
講演は大変いいお話でした。
私もアンクルウェイト付けてみようか?と思っています。
小さい火は暖かい
最近、ロシアや中国が領土拡大に向いているような報道が為されています。
「キナ臭い風潮が世界に蔓延している?」と心配します。
昔のコマーシャルで「♫大きいことはいいことだ・・」という歌がテレビがら流れていました。
チョコレートやお菓子ならいいですが、国の拡張主義は困ります。
会社も大きければいいというものではありません。
シェア―獲得に精力を注ぎ、業界1位になっても反面利益率が悪い。
結果、実入りが少ない割に苦労ばかり多く、社員も疲弊してしまいます。
図体ばかり大きくては上手く舵も切れません。
若い頃に読んだ本の中に「小さい火は暖かい」というインディアンの言葉がありました。
大きい火は熱すぎて近寄れなく、結局寒い。
小さい火は皆で囲んで温まることが出来るということです。
何のためにそれはあるのか?
大きいばかりではない。
人を幸せにするためにこそ国も会社も存在する。
大事なことだと思います。
プルートス効果
昨日の新聞に「プルースト効果」という言葉が書かれていました。
ネットで調べると、嗅覚や味覚から過去の記憶が呼び覚まされる心理現象のことです
フッとある匂いを嗅ぐことで、それに結び付いた過去の記憶や思い出が一瞬に感じ取れることです。
このような経験は皆さんにもあることでしょう。
北海道の今の時期、雪が溶けだしてくる頃の春の匂い。
私にとってこれが一瞬にして幼稚園の頃を思い出させてくれます。
いつの間にか「♫春よ来い、早く来い、歩き始めたみいちゃんが・・・♫」の「春よ来い」という歌を口ずさんでいます。
それでは、この「プルートス効果」を使って将来へ向けての「幸せ作り」の準備をすることが出来るのではないでしょうか。
例えば楽しいことがあった時、それに結び付けてある匂いを嗅ぐようにするのです。
そうすると将来その臭いをかいだ時、幸せだった頃が思い出されることでしょう。
毎朝、私は娘からもらったベルモットのアロマを焚いて楽しんでいます。
今よりもっと年老いた時、ベルモットの匂い嗅ぐ度に、今の幸せな時を思い出すはずです。
「プルースト効果」は老人の認知症予防にもいいとのこと。
試してみる価値はあると思いますよ。
あきらめ
先週14日に伊予灘を震源とする地震がありました。
11日は東北の地震から3年経った時ですから、またかと思いました。
この伊予灘付近も昔から地震があったそうです。
東海・東南海・南海連動型地震もいつ起こりかと不安視されています。
日本人は過去長きにわたって地震、津波等の大災害に会ってきました。
それでも、いつまでもその悲しみに引きづられては生きていけません。
その度に復活をなしていました。
多くの人が死に、悲しみに溢れていたのをその都度克服してきたのです。
そのような大きな悲しみを何度も体験してきた日本人の心と、仏教の無常観というものが強く結び付いてきたのではないでしょうか。
またそのような無常感が強くある日本人だからこそ、自然を身近に感じ、親しみ、その中から日本独特の文化も生まれてきました。
先の戦争で原爆に会い、大空襲にあって多くの人が死にました。
その悲しみを抱き、そして事実を忘れない中で、それに引きずられず、未来志向で生きて来たのは日本人独特の無常観があったからだと思います。
いい意味での「あきらめ」です。
「あきらめ」
それも生きる上で大切なことのように思います。
幼馴染
今「三匹のおっさん」というテレビドラマが放映されています。
幼馴染のおっさん3人が主人公です。
それとは関係ないのですが、昨夜幼馴染と一緒にお酒を飲みました。
私が小さい頃の思い出と言えば彼の記憶が鮮明に残っています。
魚屋の息子でお父さんのマネをして、いつもいがぐり坊主の頭に手ぬぐいを捲いていました。
幼稚園の頃小学校の頃に良く遊んだ記憶があります。
進学するにつれ、会う機会が無くなり、昨日は約50年ぶりの再会です。
たまたま彼のお父さんの法事を私のホテルでしていただきました。
その時、その法事の担当者を通じてそのことを知ると共に、彼の連作先がわかり、やっと会うことが出来ました。
飲んだ場所は私が行きつけのおでん屋。
たまたまそのオヤジさんも私達と同じ歳ということで、大変話が盛り上がりました。
幼馴染は現在7カ所で算盤教室を運営し、18人の先生がいる珠算学校の経営者です。
懐かしい昔話と現在の話。
昨夜は楽しい話と美味い酒に酔ってしまいました。
幼馴染もそのおでん屋が気に入り、またここで飲むことを約束しました。
また友達が出来ました。
カッコいい会社
「きれい事を唱えても経営にならない」という社長は沢山います。
でも、きれい事を唱えている会社があります。
昨日、系列会社の「キックオフ」という事業発表+決起集会に出席してきました。
300名を越す社員が出席し札幌市内のホテルで行われましいた。
社長は私の従兄弟でまだ50歳代。
その社長が掲げたのは「カッコいい会社を目指す」です。
明確で、若い人にも理解しやすい言葉です。
日経新聞の調査でこの会社は北海道の学生人気ランキング11位になっています。
テレビ局や大手旅行会社を押さえて上位に立っています。
この会社が追い求めている思いと学生の思いが一致しているからでしょう。
この会社の2013年度の売上は140億円を越しています。
社員が自分の思いと同化する会社の方針。
きれい事で成長している会社がここにあります。
身内の会社を褒めすぎたかな?
社長の度量
会社の話です。
起業して会社が成長するとともに従業員も増えていきます。
従業員は社長と同じ色の人ばかりを集めてはいけないと言われます。
確かにその通りです。
性格の違う人、いろいろな才能がある人、クセのある人が集まってきます。
色々な考え方があるから会社の発展があります。
ただそれを野放しにすると、収拾がつかなくなります。
その為に社長は会社が進むべき「方向」を明確に示す必要があります。
また、その為にどうしたら皆が力を合わせてそれを達成出来るかの「方法」を考えさせます。
そのように色々な考えを持った社員をまとめるのは社長です。
ただその時、後ろ向きで、愚痴を言い、人の悪口を言う人間は排除しなければなりません。
そういう人間に限っていい大学を出て頭が良かったり、口が上手く巧みに自己主張する人です。
そういう人を外すのも社長の役目です。
社長は「いい人」だけでは務まりません。
ここで1つ問題です。
そのようなダメな人と、本当は優秀な人なのに、社長の度量が低く、自分の意向に沿わないからダメだと思う人を一緒くたに見てしまう社長がいます。
そうなると大事な人を放出してしまうことになります。
多くの会社で起きうることです。
その為には社長はどうするか。
経営ばかりでない勉強が必要になり、自分を高めるしかないと思います。
繁盛店
私が住む琴似にある「寿司割烹店」の話です。
この店の事は以前にも紹介しました。
先日、この店の女将さんからお店をもう少し大きくしたいの相談にのって欲しいとの話があり行ってきました。
お店が繁盛し、予約を断ることが多くなり、お客様に迷惑をかけているとのこと。
開業して4年目。
同じ琴似の街で移転を考えているようです。
今営業している場所は表通りでなく脇道にそれたところにあります。
それでも繁盛しています。
腕のいいご主人と、気働きの出来る女将さん。
そして季節を取り入れ、工夫を凝らした料理は値段的にもリーズナブルです。
休みは決めていなく、予約が入っていない日を選んで休日にしているようです。
仕事優先、お客様第一。
繁盛する店はサービスが良く、雰囲気が良く、料理が美味く、納得できる値段。
繁盛店の1つの姿がこの店にあります。
移転に適した場所、私も探そうと思っています。
ラーメン店
あることを思い立ち、今週から琴似のランチ食べ歩きを始めました。
昨日行ったラーメン店は以前から気になっていた店でした。
「炙り味噌らーめん」をメインに売っている「真武咲弥」という店です。
単なる味噌ラーメンではなく、中華鍋で味噌を炙ることにより、味わい深いラーメンとなって大変美味しくいただきました。
店に行ったのは11時30分を過ぎた頃で、まだお客さんは1人。
その店長と少し話をすることが出来ました。
この店は現在東京に2店舗、千葉に1店舗展開しているそうです。
社長は現在東京で陣頭指揮をとっています。
2004年に北海道の留萌で始め、2007年札幌琴似に進出。
店長の話ではラーメン店の廃業率は高いそうで20分に1店の割合で潰れていると言います。
ネットで調べても、3年間で90%は潰れるとも書いてありました。
この店が10年頑張っているというのは大変なことです。
「真武咲弥」の社長が店長に常に言っていることは「いくら味が良くても経営を間違えれば潰れる」
社長は経営の勉強を熱心にしているそうです。
店長は年末に琴似店をテコ入れするために東京から派遣されてきました。
元気溌剌としていて仕事の動きに無駄がありません。
挨拶や会話もお客を気持ちよくさせてくれます。
ラーメンに入っている卵の黄身がゼリー状になっていて、大変美味かったです。
「ありがとう」という言葉
今日は社長の話です。
社員が会社の仕事の厳しさに対して、鍛えられていると思うか、こき使われていると思うか。
それは社長の表現力によって違ってきます。
社員が一生懸命仕事をしているのを認めて、「ありがたい」と思っても、口に出し「ご苦労さん」「ありがとう」と言えるかどうか。
素直にそれを口に出せない社長がいかに多いことか。
社員が頑張った結果を社長が一緒に喜び、「ご苦労さん。ありがとうな」と言ってもらえれば、社員のモチベーションはグーンと上がります。
起業して社員が少ない時は、まだそのような気持をもっている社長も多いです。
ところが会社も大きくなり、それなりに社長としての自信がつくと、それと共に社長の威厳みたいなものを付けようと勘違いする人がいます。
そのような勘違いが起こると、社員から「ありがとうございます」と言われても自分から「ありがとう」と言わなくなります。
そのような言葉を出すことで自分の威厳が損なわれると思っているのでしょうか。
たとえ心の中に感謝の念をもっていても、それを口に出さなければ伝わりません。
社員が高いノルマを達成するために夜遅くまで外出している時、自分も帰らず会社で帰りを待つ社長もいます。
そんな社長が言う「ご苦労さん」の一言が如何に社員の気持ちを奮い立たせることか。
意識して「ご苦労さん」「ありがとう」を口癖にするといいです。
寝床の中で
毎月開いている「身丈会」という勉強会があります。
先週開いた勉強会の後、宿題を参加者の皆さんに提示しました。
その宿題は難しくありません。
単に「寝床の中で楽しいことを思い浮かべて寝るようにしましょう!」です。
自分がなりたい姿を想像し、あたかもその世界の主人公として振る舞っている様子を想像するのです。
その時、環境も今とは変わり、周りの人達の喜びの声も聞こえるように想像します。
一見、他愛も無いことのように思う人もいるかもしれませんが、効果はあります。
辛いことがあった時などは、寝床で辛いことを思い浮かべて寝れない時も、無理やり楽しいことを思い浮かべるのです。
自分がなりたい姿を想像することで、それを現実に引き寄せる効果があります。
自分が描く夢へのバリヤーを低くし、出来ないと思う気持ちを無くしてしまうのです。
それをしている内に普段の生活の中でも思えるようになります。
思い描く姿が細かいところまで見通せるようになると「カラーで見えるよう」に鮮明になります。
そうなると6割7割は既に実現化に向かっているようなもの。
私も過去に経験しています。
今月の20日勉強会があります。
1カ月間程度では目立った効果はないかも知れませんが、参加者皆さんの体験感想はどうなのか。
それを聞くのが楽しみです。
大事な人の写真
昔、アメリカの映画やテレビを見ていると、会社の場面で机の上に家族の写真を置いているシーンがありました。
最近の日本のテレビでもそんなシーンがあります。
ある会社では全社員に対して、自分の机の上に大事な人の写真を置くようにという指示があったと聞きました。
両親の写真、家族の写真、恋人の写真等。
その写真を見れば元気が出て来ます。
人は「誰かのために」とか「この人に認めてもらいたい」とか、その人の写真を見るとモチベーションが高くなるものです。
また、少しズルをしようとか思っても、写真を見れば思い止まります。
私も会社の机の上に亡くなった両親の写真を置いています。
朝に挨拶をして仕事を始めます。
やはり一所懸命がんばろうという気持ちになります。
まだの方は一度試されたらいかがですか?
冠婚葬祭
先週の土曜日にお通夜に行ってきました。
社員の母親の葬儀です。
式場では久しぶりに会う人も多かったです。
人生には色々な冠婚葬祭があります。
その中で特に大事にしなければならないのは「葬」だと思っています。
大事な人を亡くして悲しんでいる時こそ、行って励まし支えてあげる意味があります。
「冠・婚・祭」のような目出度いことは、本人は楽しく幸せなので、あえて「おめでとう」と言いに行かなくてもいいでしょう。
私が住宅会社にいた時の話です。
ある社員の父親が亡くなった時、大工さん達は葬儀に参列するため、札幌から奥尻島まで車で一晩かけて行きました。
忙しい仕事を休み、時間とお金をかけて行ったのです。
悲しい思いをしている葬儀こそは万難を排して参列する。
大工さん達の熱いその思いに社員は大変感激していました。
「人が幸せな時は遠くから祝福し、悲しい時にこそ寄り添う。」
そのような優しさ。
大工さん達から教えられたことです。
平気で生きていく
少し歳を取ったせいか、最近色々なところで「終活」なる言葉が目に入ります。
「終活」とは死に向かってその準備をしておくことです。
私も「成程な!」と思って少し手を付けています。
また死ぬということに関しても意識をしています。
そんな時、あるメルマガを読んでいて1つの言葉に出会えました。
「人間はいつ死んでもいいと思うのが悟りやと思うておった。
ところがそれは間違いやった。
平気で生きていることが悟りやった。」
これは永平寺 78世貫首の宮崎奕保(みやざきえきほ)さんの言葉です。
「覚悟をして如何に心安らかに死を迎えるか」ではなく、「苦しみも悲しみもまた喜びも平気で受け入れて生きていくこと」が大切だということです。
大切なのは「死に方」より「生き方」
平気で生きていけるか。
凡人にはなかなか出来ませんが、1つの生き方を教えられた気がします。
現在に生きる
ある人のFacebook読んでいると「昔、頭がキレ、仕事っぷりもよかった人に会いに行ったところ、10年前の自分の昔話しかしていないおっさんになっていた」と書いてありました。
これを読んでズキンとしました。
勿論私の事を書いているわけではないのですが、ある程度歳を取ってくると誰でもあり得る話です。
過去に華やかな活躍をされた人ほど、現役を離れ仕事がない人には良くあることです。
現在の自分とのギャプを意識し、過去の自分に引きづられてているのです。
今朝のテレビで報道された元TBSアナウンサーで今はフリーアナウンサーの山本文郎氏のように、79歳で亡くなられるまで現役で活躍する人などは現在に生きています。
その証拠に73歳の時に30歳年下の女性と結婚されました。
人は誰でも歳を取ります。
問題はその取り方です。
現在に生き、現在に生甲斐が持てる生き方。
誰でも歳を取ると問われる問題の様に思います。
当座買い
何日か前の新聞にANAがコスト増を回避するために為替予約をしたと書かれていました。
飛行機の燃油費は運航コストの3割を占めています。
ドル建ての輸入が多く、円安が進めば価格が上昇し収益を圧迫すると予想して来期分を早目に外貨手当てをしたのです。
ある意味、燃料が安い時の「先買い」と言えます。
一方、JALはその期に必要な為替予約に限るそうです。
この記事を読んだ時、JALでは元会長の稲盛さんの教えが生きているのかと思いました。
稲盛さんは「当座買い」を常に言います。
安いからとか言って大量に買うと目算が狂うことがあります。
その時その時に適量買う方が結局無駄がないのです。
当社でも以前「大量に買うと安いから」といって買ったものが、結局不良在庫となったことがあります。
そういえば4月から消費税が上がると言って、お酒や缶詰などを大量に買っている人がいます。
それも結果、後から見れば無駄のことも多いのではないでしょうか。
「当座買い」は無駄を無くす1つの方法だと思います。
想像力
最近、他人事ながら気になることがあります。
マクドナルドやドトールのようなお店で長い間勉強したり仕事をしたりしている人が目立ちます。
私も以前ホテルの支配人をしていましたので、レストランの客席回転率などを考えると「店側はどう思っているのだろう?」と考えてしまいます。
以前ネットの情報で、マクドナルドの業績低下は家族層の減少と書かれていました。
その大きな要因の1つに、学生やビジネスマンが多くの席を占有し、子供連れのお母さん達が入りにくくなっているそうです。
一方コーヒー1杯で長時間席を占拠している人達の心理はどうなのでしょう。
「自分は客なのだから文句言われる筋合いはない」と思っているのでしょうか?
私は小さい頃に親から「人様の迷惑を考えなさい!」と言われて育ちました。
気に過ぎるのも良くないでしょうが、今でもやはり周りに気を配る習慣はあるつもりです。
人様の迷惑になるかどうかは想像力が関係しています。
人様への迷惑が分からない人は想像力が欠如しているからでしょう。
俯瞰(ふかん)的に、客観的にその状況を見る力がないのです。
互いに気配る優しい社会。
混んでる電車の中で背中のザックを下している若者もいます。
素敵な若者に見えてしまいます。
図書館
調べ事があり、昨日何年振りかで図書館に行って来ました。
「山の手図書館」が歩いて20分位のところにあります。
図書館と言えば思い出があります。
大学受験の浪人時代、自宅は札幌から東京に移っていました。
当時住んでいた池上線の御嶽山駅から3駅の洗足池にある洗足池図書館に毎日のように通っていました。
朝10時頃から夕方4時くらいまで受験勉強をしていました。
お昼はそこの売店で買うホットドッグのみ。
毎日同じような生活をしている時、時々高校時代の友人が図書館まで来てくれました。
その友人は既に大学生でしたが、大学は学生運動で授業も無く、「暇だから」と言って来てくれました。
それでも来てくれることが嬉しく、その時は勉強も中断し、洗足池の周りを歩きながら語っていました。
彼のお陰で単調な受験生活もいい思い出になっています。
今でも私が上京する時は彼と会います。
酒を飲みながら家族の事、友人の事、昔の話をします。
その彼も今年65歳で第2の会社も4月で定年退職とのこと。
千葉の田舎で暮らすそうです。
これからなかなか会えなくなります。
昨日図書館で本を読んでいて、フッとそんなことを思い出し、懐かしさと寂しさを感じました。
魔法のノート
昨日机を整理していたら「魔法のノート」が出て来ました。
正式な題名は「21日間で夢をかなえる魔法ノート」
21日間書き続けると習慣性が生まれ、夢がかなう行動がとれるという考えで作られています。
5~6年ほど前、少し悩んでいた時期に買ったものです。
その本の通り21日間書き続けました。
21日間書き続けても、それほどの変化は感じませんでした。
昨日それを見付け読み返してみると、「アレ?今そんなふうになっているなー」と唸ってしまいました。
その本に書かれていた7つの習慣があります。
1.夢を常にイメージする
2.悪口や愚痴を言わない
3.他人の良いところを見付ける
4.感謝する
5.心を感動で満たす
6.失敗を恐れずチャレンジする
7.あなたの運命はあなた次第
当り前の言葉ですが、いい言葉です。
興味がありましたら本を買い、試してみたらいかがですか?
高齢者の就業
今朝の日経新聞の一面に「高齢者働く人の1割に」という見出しの記事が出ていました。
主に人手不足の建設業界で高齢者の雇用が高くなっているためとのこと。
これは建設業界のことばかりではなく、日本人の高齢者の就業数は確かに欧米諸国と比べても断然高いようです。
ヨーロッパのイギリスやフランスは特に低いです。
そう言えば、昨年3女が嫁いだイギリス人のダンのお父さんは60歳過ぎたばかりですが、仕事をせず悠々自適に毎日自宅の庭いじりをしています。
古くて広い庭をマメに手入れしています。
素晴らしい「イギリスガーデン」が自慢の様です。
そんな生活も羨ましくもありますが、やはり日本人の私は働き続けたいと思っています。
その違いは宗教や倫理の違いかもしれません。
キリスト教、特にカトリックは「働くことは罰」の考え方があります。
だから早くリタイアして好きなことをしたいと思っています。
イギリスやフランスはカトリックです。
プロテスタントのアメリカは少し違います。
マックス・ヴェーバーが書いた「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を体現したアメリカは働く意義を見出しています。
この新聞の記事でもアメリカは日本と同じくらい高齢者になっても働きたいと思っている人は多いようです。
これから日本の高齢者が働き続ける人の割合はもっと増えていくでしょう
総務省の労働力調査では生産年齢人口を15歳~64歳としていますが、実情にはあっていません。
15歳で働く数は少なく65歳以上で働く人は増えています。
近い内に統計データーの変更もあることでしょう。
絶対王者
今月7日から始まった冬季オリンピック、連日日本人選手が活躍しています。
私が応援しているカーリングも頑張っています。
競技は字のごとく技を競い合います。
優れた技をもっている人が自分の力を出し切った時、金メダルを手にします。
テレビで競技を見ていると、つい競争相手の失敗を願っている自分がいます。
選手の中にもそういう人はいるでしょう。
一方、そうでないスポーツ選手がいます。
何かで読んだののですが、ゴルフのタイガー・ウッズ氏は一緒にラウンドを廻っている相手がここ一番でカップに入れるかどうかという時に「入れ!」と願うそうです。
普通は「入るな!」と願うはずです。
それはなぜか?
相手のパットがカップに「入るな!」と自分が思う時は自分の力量が不足している証拠だと言うのです。
絶対的な自信がある自分は、相手がベストの時に勝ってこそ、自分がナンバーワンになのだと自覚出来るのです。
それほどの力量と自信があればこそアメリカのツアーで46勝、国際試合で9勝、総計55勝を20代で記録出来たのでしょう。
絶対王者とはそういう人の事。
そうは思いつつも連日頑張る日本選手に今日もテレビの前で応援していきます。
商売の基本
数日前の新聞のコラムに、商売は「足し算、引き算、そして掛け算で成り立っている」とありました。
足し算は売上を上げること。
引き算は経費を少なくすること。
掛け算はブランドやM&Aで飛躍すること。
この話であまり合点がいかないのは掛け算という考え方です。
商売の基本は「売上最大、経費最少」の積み重ねです。
この地道な努力の結果が会社成長の原点です。
掛け算という考えは、ギャンブル的経営になりがちです。
起業して地道に商売を続けていると、時として飽きが来、もっと効率的な方法とか、儲かる商売がないかと迷いが起きます。
ある時、その誘惑に負けて安易に手を出してしまうことがあります。
これが失敗の元。
そのような起業家の例を多く見て来ました。
よく言われるように「商いは飽きないこと」です。
毎日の積み重ねこそが王道。
禁酒・禁煙
私の知人に最近お酒を止めた人がいます。
健康のためです。
健康のためにタバコを止める人も多いです。
私も20年ほど前にタバコを止めました。
2度の失敗の後、3度目で成功。
2度失敗した要因はのは「止める」と強い決意したことです。
変に思われるでしょうが、強く決意すると、心の中の欲望が押さえつけられ、反対にタバコを吸いたいという気持ちも大きくなります。
夢の中にも頻繁に出て来ます。
結局誘惑に負けて元に戻って行きました。
3度目の禁煙に成功したのは無理して禁煙しようとしなかったことです。
ニコチンの少ない煙草に変えつつ1日2箱は吸っていました。
風邪ひいた時や二日酔いの時の様な気分の悪い時はタバコを吸いません。
その内にタバコが切れても少し我慢出来るようになって行きます。
そうなると1日1箱位になります。
次のステップは「もらいタバコ」をするようにします。
自分のタバコを買わずに、傍にいる人に「1本タバコくれる?」とお願いします。
いつももらう人には経済的に負担掛けて悪いので、時々タバコを買って上げます。
その時も自分のタバコは買いません。
しばらくその「もらいタバコ」をしていると、お願いしてタバコをもらうのにも気が引けるようになります。
そうすると気付かない内に「今日1日タバコ吸っていなかった!」となります。
そうなるとほとんど禁煙に成功したようなもの。
禁酒も禁煙も「ながら禁酒」「ながら禁煙」の方が成功率が高いと思います。
もっとも私は禁煙しましたが、今のところ禁酒するつもりはありませんが・・・
無財の七施
ある本を読んでいると「無財の七施」というのが仏教の教えにあると書かれていました。
1.眼施(げんせ) 優しい眼差(まなざ)しで人に接する
2.和顔施(わげんせ) にこやかな顔で接する
3.愛語施(あいごせ) やさしい言葉で接する
4.身施(しんせ) 自分の身体で出来ることで奉仕する
5.心施(しんせ) 他のために心を配る
6.床座施(しょうざせ) 席や場所を譲る
7.房舎施(ぼうじゃせ) 自分の家を提供する
これは毎日に仏教の修行ということですが、私達も毎日心していくにいい言葉ですね。
1~5までは特にサービス業では「優しいまなざしと、笑顔でお客様を迎えし、お客様に心配りをし言葉をかけ、身を粉にして働く」
大切な「おもてなしの心」になります。
私の感銘録に書き入れました。
人間は考える葦である
何日か前の新聞に「機械学習」というものが紹介されていました。
これはコンピューターに記憶させた大量のデーターの中から、一定のルールを導き出し、コンピューターが人間の判断能力を補助するものです。
イメージとしては冷蔵庫にその能力を備えたコンピュータを入れておくと、今日の晩御飯のメニューを提示してくれます。
在庫している食材、家族構成、アレルギーの有無などを考慮してコンピューターが応えてくれるのです。
人の経験や勘に頼っていた分野をコンピューターが補助するということがコンセプトのようです。
でもこのような生活が快適な生活でしょうか。
大いに疑問があります。
IT社会が進むにつれ、人は考える事が少なくなってきました。
毎日多くの情報が入って来ます。
それを整理してくれる人がいて、その意見も知ることが出来ます。
自分で判断する事を放棄します。
人が判断したことを好き嫌いで選択すればいい。
そんな社会は問題です。
経営者の中にもその傾向があります。
社長は経営方針や人事等、経営に関する全ての事を最終的判断をする人です。
ところが、それを放棄している人がいます。
会計士の先生や外部のコンサルタントにそれを丸投げしています。
本来社長が苦しんで結論を出すべき事を避けているのです。
「人間は考える葦である」とパスカルは言いました。
考えることを放棄すれば人間で無くなります。
便利な仕組みは時として人間が持っている力を削いでしまいます。
人間を堕落させまます。
IT社会が進むにつて、コンピューターに使われないよう、人の話を鵜呑みすることのないように。
自分の頭で考えましょう。
立春を過ぎて
[立春過ぎればまた陽は昇る」
これは昔に聞いた言葉です。
最近寒い日は続きますが、確かに陽が昇るのが早くなっています。
「立春過ぎればまた陽は昇る」という言葉を口に出すだけで、心はもう春に向かっています。
今朝、妻と昨年の8月に旅行に行った時の写真を見ていて、つくづく思いました。
たったこの半年間で色々なことが私達の周りで起きました。
ありがたいことに全ていいことばかりです。
半年の間に海外旅行3回、2人の娘の結婚、孫が1人生まれました。
これらは自分であえて望んだというより、全ては大きな流れの中の出来事です。
立春が本当の新しい年の幕開けと言われます。
今年もこれからまた色々なことが起こるでしょう。
感謝しながら楽しみにしています。
酒を飲む
ある本を読んでいたら「酒は量なし、乱に及ばず」という論語の言葉がありました。
「酒はいくら飲んでも乱れてはいけない」ということです。
この本の中に三菱財閥創業者の岩崎弥太郎氏の事が書かれています。
岩崎氏は人と酒を一緒に飲んでその人を見抜いたそうです。
酒を全く飲めない人は余程の偉物でなければなければ大体出世できない。
飲んで醜態を見せればそれも落第。
いくら飲んでも、酒を楽しみ、変わらない。
いくら飲んでも正気を失わず、酒では乱れない。
そのような人物でなければ認められないのです。
人生で一番の誘惑は酒色です。
色の間違いの初めは酒です。
ほどほどのお酒を楽しむ。
そのほどほどがどの程度か?
それが問題です。
私は最近お酒が弱くなりました。
ほどほどの量を毎日探しています。
立つ位置
昨夜、知人のNさんとお酒を飲みました。
彼と知り合ったのは4年ほど前。
Nさんが北海道銀行の琴似支店から釧路支店に転勤になる時、もう一人の仲間と一緒に送別会をして以来です。
その仲間が亡くなり、札幌に戻ってきたNさんと2人で、昨夜は偲ぶ会となりました。
Nさんは札幌の本部に戻り、今は執行役員という立場で忙しい毎日のようです。
このNさんと久しぶりにお会いし、話をして感じたことがあります。
以前より物事をより大きく捉え、そして広く見ているようです。
執行役員として、立つ位置が変わったからでしょう。
また、Nさんの話の中に女子カーリング日本代表の小笠原さんのことも出て来ました。
小笠原さんは北海道銀行チームのキャプテンです。
Nさんが小笠原さんと話をすると、とてもしっかりした考え方を持っているようです。
オリンピック壮行会で挨拶した内容も、Nさんが敵わないというほどの内容ある話しぶりだったそうです。
日本代表としてオリンピックに臨む立つ位置によって心構えが変わるのでしょう。
11日はそのカーリング初戦。
北海道銀行の頭取も応援のために10日出発するそうです。
私も元北海道銀行員としてテレビの前で応援します。
君の失敗は僕の失敗
「君の失敗は僕の失敗」
これは昨夜NHKの番組「プロフェッショナル仕事の流儀」で紹介された洋菓子職人横溝治夫さんが紹介していた言葉です。
横溝さんがヨーロッパで修行中、パン生地が上手く出来なく悩んでいる時、自分にとっては雲の上のような存在のシェフが付きっきりで教えてくれました。
そのシェフから言われた言葉です。
その時横溝さんは「このような親方になりたい」と思い、今それを弟子教育に生かしています。
手取り足取り教えています。
昔、日本の調理の世界では「技は盗んで覚えろ」と言われ、直接教えられることは稀だったようです。
しかし人を育てる時は、時に手取り足取り教えることも必要です。
手取り足取り教えるというと山本五十六さんの言葉を思い出します。
「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」
この言葉は知っている人も多いと思います。
共に会社における社員教育に通じるものです。
心の持ちよう
仕事を部下に指示し、業務を担当させる時、「させられたと思う人」と「させていただいたと思う人」がいます。
同じ仕事でもその結果は雲泥の差が出て来ます。
仕事が終わった時の本人の満足度も全く違います。
その結果の大きい違いは、初めに持ちチョットした心の持ちようによります。
そのことが分かると、立ち位置が1段も2段も上がり、見る風景が違ってきます。
そしてこの事に早く気付く人は幸せな人生を送れます。
昨今、若い人達の活躍が報道されています。
先日は万能細胞で若い女性が、今朝はクラッシックバレーで活躍した高校生がいます。
「心の持ち方」でこのようにも人生が変わって行くのか。
教えてくれているようです。
運命は自分で変えられる。
私はそう思います。
新しいパソコン
先日ノートパソコンを買いました。
今使っているパソコンのOSがWindowsXPなので買い変えることにしました。
「安くてもいいや」と思っていたのですが、少し高いNECのパソコンでした。
そのパソコンは超軽く800グラム位の重さです。
入っているOSはWindows8.1です。Windows7にしようかとも思ったのですが。
今そのパソコン操作に悪戦苦闘中。
1年前に買ったMACの操作にやっと慣れてきたのですが、今度はWindows8.1に挑戦です。
固くなってきた頭の体操と思って頑張っています。
今日からWindowsXPの古いパソコンからソフトやデーターの移し替えをします。
しばらく悪戦苦闘が続きます。
万能細胞
今朝のニュースで万能細胞を作る方法を発見したと報道されていました。
それも30歳の若く美しい女性。
その研究者小保方(おぼかた)晴子さんは大学を出てまだ10年も経たない内に世界的発見をしたことに私は驚きました。
当初、科学誌ネイチャーに論文を投稿しても「科学を愚弄する」と非難された、却下されること3回。
それでも研究し続けての発表です。
その陰には優秀な日本・アメリカの研究者のサポートがあったそうです。
その研究者も一流の研究者。
当時はまだ20歳代の若者が、自分より年上で優秀と言われる人から協力をもらえたということに私は興味を持ちます。
その一流の研究者がサポートするほどの研究内容、そして小保方さんの人間としても魅力。
小保方さんはこれからいろいろ人として、その生き方や考え方がテレビ等で紹介されるでしょう。
ただこの事で、人知れずコツコツ努力をし続け、苦節何十年かけて研究するという従来のイメージは一新されました。
新しい研究者そして若者が現れた様な気がします。
サケとマス
食品偽装表示問題が起きて、先日消費者庁からメニュー表示のガイドラインが出されました。
そのガイドラインに対して色々な意見があります。
特にサケとマスの表示について問題提起されています。
現在、サケと表示され販売されているほとんどがサーモントラウトという養殖のマスです。
養殖マスは消費者の好みに合わせ、脂をのせることも、色を赤くすることもエサ次第で自由に出来ます。
スーパーに売っている甘塩サケも養殖マスです。
そんなこともあり、消費者庁が厳密に表示を区別するように指導しようとしていることに反発が強いようです。
また、養殖サーモンの味にならされた私達の舌に、サケはパサついて美味しくないという人が多いです。
養殖サーモンの味にならされても、私はもっと本物のサケを食べたいと思います。
北海道に住んでいるのだから北海道のサケが欲しいと思いスーパーに行っても、残念ながらサケはほとんど置いていません。
サケとマスはその味が違います。
1つの例が卵です。
筋子と言えば本来サケの卵ですが、価格の安いマスの卵もあります。
しかしその味は格段に違います。
身にしてもサケはしっかり歯ごたえがあります。
わたしは明確にサケとマスの表示はして欲しいと思っていますし、もっと多くのスーパーでサケを扱ってほしい。
子供の頃は塩サケ一切れでご飯3膳位食べました。
美味い新巻きサケ、塩サケを食べたい!
安全について
知人が水販売を始めたと言ってパンフレットを持って来ました。
今、そのパンフレットを見てイザヤ・ベンダサンが書いた「日本人とユダヤ人」を思い出しました。
日本人は以前「水と安全はタダ」という考え方がありました。
それは世界的に見れば大変特殊で恵まれた事なのです。
私も日本でミネラルウォーターが売られた時、「本当に水を買う人がいるの?」と思ったものでした。
でも今は高い値段で水が売られています。
また安全も日本では徹底されています。
何か事故が起これば自己責任が問われるより、何かのせい誰かのせいとなってしまい、細かいことまで安全な環境が求められます。
ここまで清潔で安全な国に暮らしていると、人間の抵抗力が無くなってきています。
日本人が海外に行くと必ずお腹を壊す、すぐ病気になるというのもひ弱な身体のせいです。
私の義理の息子ダンは40カ国以上を旅していましたが、旅行する前は身体を鍛えるためにと言って「拾い食い」をするそうです。
少し位汚れた食べ物でもフッと吹いて食べてしまいます。
菌への耐性を身に付けるのだそうです。
小さい頃、拾い食いをしたり傷だらけだ遊んだ私達団塊の世代は、まだ抵抗力や危機感受意識は持っています。
今の子供や若い人達が心配です。
自己責任を問われず、誰かに安全に守られている存在はその場所しか生きていけないのです。
この事を良く理解し認識すること、大切だと考えます。
見放さない
自分の好きなものを身の周りにあると満足するものです。
鞄や靴、万年筆等は使えば使うほど愛着が生まれます。
モノに対しては一方的に好きなるばかりですが、生き物に対しては見返りを求めてしまいます。
ペットに対して愛情を注いで、なついてくれないことまあります。
人間に対しても自分の想いが相手に伝わらず苦しむことがあります。
自分の子供についても言えます。
子供の事を思い愛情を注ぎ、時には厳しいことを言う時もあります。
こんなに大事に思っているのに、どうしても自分の愛情に応えてくれないこともあります。
その時、怒って「もういいや。どうでもしてくれ!」と思ってはダメです。
見放してはダメです。
見放すと相手は本当にダメになります。
見放すと相手は自然とそれが分かります。
もう少しで良くなったかもしれないものを壊してしまいます。
会社の社員にも言えることです。
愛情には根気が必要だとつくづく思います。
知行合一
昨夜「身丈会」の勉強会がありました。
以前に私が担当した起業講座を受講した人達が講座終了後も月に1度集まり、「身丈会」と称した生き方や起業に関しての勉強会です。
教材として稲盛さんの本を使用しています。
昨夜の勉強会でお話ししたことは「知行合一」の大切さです。
この言葉は中国の王陽明が説いた陽明学の基本思想の1つです。
学んだことも行動が伴わないと学ぶ意味がないということ。
私もそうですが、学ぶことはするのですが、それが実際に行動に移していることはどれほどあるでしょうか。
難しいことではなく、人として当り前の事を学んでいるのですが、学んだ端からすぐ忘れ、全く反対なことをしています。
そんな反省から、勉強会で学んだことを1つでもいいから次回の勉強会の時まで、実行し続けようと皆さんに提案しました。
次回勉強会まで「これがないから、あれがないから出来ない」をまず克服することを目指します。
起業するにしても、お金がないから出来ない、人がいないから出来ない、技術がないから出来ないと言う人は、いつまでたっても何も出来ません。
出来ないと言う癖を無くすことが大切です。
日常の生活の中で、つい出来ない理由を考えている自分がいます。
それを「1つでも出来る為の事を考える工夫をする」
次回の勉強会の時、その成果のほどを勉強会参加者の皆さんに問うことにしました。
勿論私も含めてです。
「有意注意」しながら生活します。
雪明り
昨夜寝る時、妙に外が明るくなっていました。
雪明りです。
雪が降っていたようです。
私の寝室は窓にはカーテンを引かず障子戸になっているので、外の明りがそのまま寝室に入り込んできます。
まるで月の光が直接入ってくるように。
寒い雪国の人にとって嫌な雪も、こうして雪明りの中で寝る事が出来るのはいいモノです。
いい夢が見れました。
モノ真似
自分の身の回りをよく見てみると自分より優れた人が沢山います。
その人の優れたところを見付けたら真似たいものです。
その時、真似ることが出来る人と真似る事が出来ない人の2通りいます。
その違いは謙虚か謙虚でないか、素直か素直でないかの違いでしょう。
また時として真似ることは良くないと言う人がいます。
自分独自な考えやアイディアを持つべきだと言います。
でもこの世の中にある多くのモノの基本は真似ることから出来ていると私は思っています。
特許を侵すような法律に反することや、人に迷惑を掛ける事でなければ優れたモノはドンドン受け入れていけばいいのです。
それを取り入れてそれから発展させた時にその人なりの考えやモノが作られていきます。
モノ真似が出来る人、モノ真似さえ出来ない人、そしてモノ真似で終わらない人。
謙虚で素直に生きていきたいと思います。
人格
企業経営する時、才覚と努力で会社を発展させる人は多いです。
しかし時として上手くいかない時、何が足りないか。
それは経営者の人格です。
才覚があり努力する人こそ人格を磨かないといけません。
それでは人格とは何か。
人は生まれながらにして持っている性格とその後に身に付ける哲学によって人格は作られます。
哲学を身に付けなければ、生まれた時の性格がそのままその人になります。
性格+哲学=人格
この哲学とは特別なことではなく、素直である、人を騙さない、謙虚である、反省する等当り前の事。
そして、その当り前のことを知っていても、実践出来ていないと人格が形成されず、経営者として間違いを犯します。
また、この当り前な哲学は毎日繰り返し学び実践しなければなりません。
それはまるでアスリートが毎日練習を繰り返すよなうなものです。
1日でもそれを怠ると筋肉が衰えていきます。
だから毎日繰り返し学ばなければなりません。
以上の話は昨夜勉強会で聞いた稲盛和夫さんのお話です。
また気付きを得た勉強会でした。
人格
企業経営する時、才覚と努力で会社を発展させる人は多いです。
しかし時として上手くいかない時、何が足りないか。
それは経営者の人格です。
才覚があり努力する人こそ人格を磨かないといけません。
それでは人格とは何か。
人は生まれながらにして持っている性格とその後に身に付ける哲学によって人格は作られます。
哲学を身に付けなければ、生まれた時の性格がそのままその人になります。
性格+哲学=人格
この哲学とは特別なことではなく、素直である、人を騙さない、謙虚である、反省する等当り前の事。
そして、その当り前のことを知っていても、実践出来ていないと人格が形成されず、経営者として間違いを犯します。
また、この当り前な哲学は毎日繰り返し学び実践しなければなりません。
それはまるでアスリートが毎日練習を繰り返すよなうなものです。
1日でもそれを怠ると筋肉が衰えていきます。
だから毎日繰り返し学ばなければなりません。
以上の話は昨夜勉強会で聞いた稲盛和夫さんのお話です。
また気付きを得た勉強会でした。
スリランカ
先週、夜にテレビをつけたらスリランカという国が紹介されていました。
昔はセイロンと言われ、セイロン茶として紅茶で有名です。
今は多くの日本企業も進出しており、その中でも陶器会社のノリタケは1972年から地元企業として根付いています。
このテレビ番組の中でスリランカ国民が如何に親日的であるかが紹介されていました。
そのもとになった大きな力はセイロン初代大統領であったジャヤワルダナ氏の力によるものが大きかったようです。
第二次世界大戦後サンフランシスコ講和条約の席上、当時大蔵大臣であったジャヤワルダナ氏の演説が日本を救いました。
当時は日本が独立国となるのに反対する国々がまだあり、日本の4分割論もあった中、ジャヤワルダナ氏は「日本があらゆる制約を受けずに自由と独立した国家として認めるように」と演説しました。
また、「日本はわが国と同じ仏教国であり、憎しみは憎しみによって止むのではなく、慈愛によって止む」と話し、大きな感動を呼びました。
そしてセイロンは対日賠償請求権の行使を放棄し、世界で一番早く正式に日本と外交関係を結びました。
サンフランシスコ講和条約に出席していた吉田茂首相はこの演説を聞き「日本は後世までこの大恩を忘れてはならない」と言ったそうです。
私はこのテレビを見て初めてこの事を知りました。
大恩を忘れてはいけないと言いながら、それが伝わらなかったのです。
昭和天皇の大葬の席で、当時現職を退いたジャヤワルダナ氏はアメリカより先にお悔やみを申し上げました。
ジャヤワルダナ氏が無くなる時、遺言で「片目をスリランカ人に、もう片方を日本人に」と角膜提供してくれたそうです。
現在もスリランカから日本への角膜提供率は世界一だそうです。(参照:インターネットブログJapaLanka)
このテレビ番組を見てスリランカという国に大変興味を持ちました。
機会があれが一度訪問したいと考えています。
製造業
昨日妻と話していた時、最近の子供は周りの皆と同じでなけれ不安になるという話を言っていました。
私の子供のことを話題にしていた時の話です。
人との違いを容認する事の大切さは以前にも書きました。
他の人と同じでなければ自分は皆から疎外されると思いこんでしまうようです。
変な平等意識がゆがんだ形になっているのでしょうか。
平等と均等の違いが分かっていないのでしょうか。
皆と同じ傾向と言うと最近起業する人達の選ぶ業種もITとかサービス業が多いです。
製造業で起業する人は本当に少ないです。
その傾向に私は危機感を持ちます。
経団連の次期会長選出の時、米倉前会長は次期会長は製造業から出て欲しいという要望を出しました。
もっと製造業に力を入れる政策も必要です。
将来円安が加速する時、日本の製造業の出番です。
3Dプリンター程度の製造業でない本当のモノ作りの産業が活性化して行くことが国力増強になる気がします。
出会う
年明けに出社した時、年賀状と一緒に懐かしい人から葉書が届いていました。
その人とは1年以上お会いしていません。
以前は月に1度は来社していただき色々なお話をしました。
ところがある時からフッと音沙汰が無くなり、心配していました。
何か気に障るような事を言って嫌われたかなと思っていましたので、その葉書を見た時はホッとしました。
ただ、その方は人知れず悩んでいたそうです。
今は沖縄に仕事場を移して頑張っているようです。
その方との折角の出会い。
北海道と沖縄、遠く離れていてもその出会いを大切にしたいと思います。
人との「であい」は「出合う」「出会う」「出逢う」があります。
「出逢う」は男女の関係。
「出合う」はモノがであうこと。
「出会う」は人がであうこと。
辞書的には違うかもしれませんが、私はそのように理解しています。
これからも多くの人との「出会い」があればと願っています。
もしも20歳なら
昨日は成人式について書きましたが、もしも自分が20歳だったとしたら、今の私は若い自分に何を言いたいか。
考えてみました。
それは何をするにしてもその目的・目標を持つこと。
私は若い頃、素直で、真面目で結構一生懸命になるタイプでした。
目の前にあることは頑張ってやり遂げました。
でもそれは与えられたモノを懸命にこなしていただけだったように思います。
今の若い人が言われる「指示待ち族」と同じでした。
もしも20歳の時、良き師や良き本に出会えていれば、もっと違った人生だったのかもしれません。
そして今の若い人達にも同じことを言いたいと思います。
自分の生きる目的・目標を得る為に、良き師・良き本に出会えること。
そしてその大切さを知ることです。
成人式
昨日は成人の日でした。
各地で成人式が行われ、華やかな式典が催しされたようです。
私が20歳の時、成人式には出ませんでした。
私の友人も出る人はほとんどいません。
当時は学生運動の盛んな頃で、「反体制を叫んでいる人間が体制側の式典に出れるか!」という思いがありました。
私の長女の成人式。
成人式の招待状には平服でご参加くださいと書いてあったので、妻は「スーツいい」と言って出したところ、周りの皆は振り袖姿。
帰って来て怒ること。
可哀そうなことをしたと思います。
それにしても今の成人式お金をかけ過ぎです。
成人とは一人前の大人になることです。
それなのに親がかりでお金を掛けて着飾ることは、独り立ちする式典としては逆行しているように思います。
私の知人が20歳の時の話です。
親から「20歳になったのだから親の務めは終わった。家を出て1人で暮らせ」と言われ、家を追い出されました。
1人暮らしを始めたそうです。
アルバイトしながら頑張りました。
今、その彼は社長として頑張っています。
それにしても厳しい親ですね。
痛飲
昨夜は「経営者変人会」と称する飲み会を私の事務所でしました。
経営者の他に北大の先生その教え子の学生達も参加して、12名による単なる飲み会です。
様々の仕事をしている人達が参加しますので話題が絶えません。
また各自が好きな食べ物飲物を持ち込んでの飲み会ですから様々の食べ物とお酒が集まりました。
珍しいモノは、ホタルイカの干物、フグの卵の粕漬、焼き鯖の押しずし。
それに参加者のお母さんが漬けたホッケの飯寿司。
お酒はシャンパン、ワイン、ビール、焼酎、日本酒。
豪華な内容です。
ワインと日本酒だけで12本位。一升瓶もありました。
それを全て飲んでしまいました。
大変楽しい会でした。
痛飲とはお酒を沢山飲む事です。
今朝はその名の如く、二日酔いで少し頭が痛い。
戦後日本史
私は以前から第二次世界大戦前と後の日本人の心の変化に興味を持っていました。
来年で終戦70年になります。
そこで少しずつ当時の事を調べてみようと思っています。
先日の日経新聞にマッカーサー占領軍最高司令官の事が掲載されていました。
戦時中は鬼畜米英として戦ってきた相手に対して、戦後日本中から50万通のファンレターを出す日本人。
征服者に対して50万通のファンレターを出す国民は他にないと袖井法政大学名誉教授は書いています。
日本におけるそれまでの指導者に対する不満のはけ口とも言えますが、同じ敗戦国であるイタリアやドイツではそんなことはありませんでした。
戦後日本史はつい最近の出来事です。
まだ生存している人もいる時代のことです。
それなのに、如何に知らないことが多いことか。
知らなかったというより知らされてこなかったのかもしれません。
あまり政治的に偏らず、なるべく中立的立場で調べてみようと思います。
現状認識
昨日の新聞を読んで思ったことです。
「強い農業 異分野と育成」と題され、アシストスーツを使い、高齢者の農業作業を手助けするという記事が掲載されていました。
確かに高齢者が作業する時には役立つでしょう。
農業従事者の平均年齢は65歳と言われています。
しかし農業で今大事なのは若返りです。
制度を変えて、新規参入希望している若い人達を増やすことではないでしょうか。
高齢者の人達は直接作業するより、指導する等経験を生かした仕事に移行する方が農業のためにはいいこと。
このアシストスーツが農業分野で本当に普及するのでしょうか。
この記事では農水省も参画いるのですが、チョット方向違いの様に気もします。
似たことは会社でもあります。
会社経営していると、新規事業を手掛ける時があります。
会社にはノウハウも技術もあるので手掛けるのですが、その時、開拓するその分野の現状をしっかり把握し認識してからでなければその事業は頓挫してしまいます。
その分野の現状を間違えてとらえていたわけですから、土台が崩れ、計画がひっくり返ってしまうことになります。
昨日の新聞の記事の内容はそれと似たことだと感じました。
思う力
昨日本屋に行って色々本を見ていると、題名が「心配事の9割は起こらない」という本がありました。
手に取って見てはいませんが、「将来の事はそんなに心配することはない」ということが書かれているのかと想像します。
確かに「取り越し苦労」は無駄なことです。
それは分かった上で、9割は起こらないけれど1割は起こるのだと考えることも出来ます。
心配性の人はその1割が心配になってしまうのです。
それでは「心配事」でなく、「嬉しい事」はどうでしょうか。
「嬉しい事」や「夢」もやはり9割起こらず1割しか起こらないのでしょうか。
私は違うと思います。
自分が願い思う気持ちが強ければ強いほどその願いは実現するはずです。
可能性は1割も無い、不可能だと思われるような事を成し遂げた人は、実現の可能性を3割4割5割6割と高め、10割まで持っていった人です。
願う思いの強さが夢を引き寄せたのでしょう。
新年に当たりそう思いました。
正月休み
明けましておめでとうございます。
正月休みがやっと終わりました。
「やっと」という気持が大きいです。
この休みの間は、年末に風邪をひいたこともあり、初詣で近所の琴似神社に行っただけでほとんど家の中。
その為か風邪は治ったけれど、休み後半は食欲も無くなり、2日間はダウン。
断食状態でしたが、昨夜におかゆを食べて少し良くなりました。
ところが今日から仕事となると、昨日までダウンしていたのに不思議と万全な状態に復活しました。
何もしないで長い期間休むと、精神的にも肉体的にも低下するモノなのでしょうか。
今年も今日からフルに頑張ります。
仕事納め
今日は27日、例年より1日早い仕事納め。
この1年振り返ってみるとやはりいい年でした。
感謝します。
年を越すと、誰にとっても「手つかずの1年」があります。
どのような1年にするにしても自分次第。
私の今年の反省は「有言不実行」の事が多かったこと。
「言うは易き。行うは難し」
感謝して年越しをし、希望を持って新しい年を迎えます。
鍵山秀三郎氏
昨日,以前に人から頂いたDVDを観ました。
イエローハット創業者鍵山秀三郎氏の講演DVDです。
題名は「凡事徹底」
鍵山氏が行商から始めた創業時の話からです。
商売を通して、「鬼のようなお客様」「仏のようなお客様」と出合い、それによって独自の経営哲学が確立されました。
その経営哲学の中で「成程!」と思った言葉を紹介します。
〇「忍激の二字は禍福の関所」:怒るか怒らないか。それが幸せの分かれ目。
〇滅びる人の道は「傲慢」「無反省」「忘恩」の3つ。反対をすれば栄える道。
〇「やっておいて良かった」と「やっておけば良かった」は似たような言葉だが正反対。「やっておいて良かった」人生を歩むこと。
〇無感動な人を直すことは出来ない。残念ながらこのような人は感謝が出来ない人。
〇守るモノを持っていると強く成れる。母親が子を守る時の強さのように。
〇真の幸せは自由にあるのではなく、義務を甘受する中になる。
年の終りにいいDVDを観るとことが出来ました。
子供の幸福度
今朝の新聞にユニセフが調査した「子供幸福度」が掲載されていました。
それによると先進31カ国中日本は6位です。
「教育」と「日常生活上のリスクの低さ」は1位です。
気になるのが「物質的豊かさ」が21位なこと。
これが総合6位と順位を下げた要因です。
この事に関して記事には「子供がしわ寄せを受けている実態が浮き彫りになっている」と評しているのですが、この評こは疑問を持ちます。
これほど豊かでモノが溢れている日本で、どこに子供にしわ寄せがあるというのでしょうか?
物質的に満たされていないとはどういうことでしょうか。
私は逆に、子供たちが足るを知らない「限度を知らない欲求の高さに」に不安を抱いてしまいます。
昨日はクリスマスイブ。
夜には子供達は沢山のプレゼントをもらったことでしょう。
プレゼントをもらう喜びと一緒に、その幸せを感じてほしいと思います。
ホワイトクリスマス
今日はクリスマスイブです。
皆が優しい気持ちになる時です。
ベトナム戦争の時もクリスマス休戦というのもありました。
クリスマスは戦争とは無縁のものです。
クリスマスに謳われる歌は「きよしこの夜」「ジングルベル」「クリスマスイブ」等があります。
私にとっての一番のクリスマスソングは「ホワイトクリスマス」です。
この「ホワイトクリスマス」は第2次世界大戦の時、ヨーロッパで戦っていたアメリカ兵士たちが故郷を思い、ラジオから流れるその曲を聞き、歌っていました。
それを思って「ホワイトクリスマス」を聞くと「I'm dreaming of a white Christmas・・・・」で始まる歌詞は切ない気持ちにさせます。
先日の日曜日に映画「永遠の0」を妻と一緒に見て来ました。
より一層平和の大切さを感じさせてくれます。
今日のクリスマスは静かに過ごします。
忘年会
昨夜は身丈会という勉強会の忘年会が私の事務所でありました。
15人ほどの人がそれぞれ1000円相当の飲物・食べ物を持ち寄り、皆で楽しみます。
料理を作って来てくれる人もいて、食べ切れないほどの料理が並びました。
私の事務所ですから誰にも気兼ねが無く、皆と飲み食べ語らいました。
今週は3日ほど続いた忘年会もこれが今年最後かと思ったのですが、また来週入ってきました。
今度は美味しいおでんを食べる会?です。
人と話し、飲み食いするのが好きな私。
まだまだ頑張ります。
赤い糸
年末、年賀状を書く時期となり、この1年を振り返ると、大きな出来事はやはり2人の娘が嫁いだことでしょうか。
結婚の話を聞くと思うことがあります。
「赤い糸」の話です。
結婚する2人は赤い糸で結ばれているという話は昔から言われています。
私も確かにそうだと思います。
ただこの糸は大変切れやすいのです。
好きで結婚しても互いに我を張りあうと糸が切れてしまいます。
その糸をもう一度結ぶためには、互いに近寄って結び目を作ります。
長い結婚生活の中では、喧嘩するたびに切れ、結び目を作ることが何度も続いて行きます。
そうしている内にその赤い糸には結び目が沢山出来、そして糸の長さも短くなっていきます。
赤い糸が短くなるということは、互いの心が近づいて行くことになります。
どんなに好きな人と結婚しても喧嘩します。
喧嘩して赤い糸の結び目が沢山出来ることはその人との絆が強くなること。
私は今もその結び目を増やしつつあります。
タライの水の原理
昨日ある雑誌を読んでいたら「タライの水の原理」について書かれていました。
「タライの水の原理」はご存じの方も多いと思います。
タライの水を自分の方にかき寄せると反対の方に流れていく。
そうではなく、その水を向こう側(相手)に「どうぞ」と言って水を押し出すと水は自分の方に帰ってくるというものです。
この「タライの水の原理は」二宮尊徳が言った言葉だそうです。
そしてその本質がその雑誌に書かれていました。
「人間は皆空っぽのタライのような状態で生まれてくる。
つまり最初は財産も能力も何も持たずに生まれてくる。
そのタライに自然やたくさんの人々が水を満たしてくれる。
その水のありがたさに気付いた人だけが他人にも上げたくなり、誰かに幸せになって欲しいと感じて水を相手の方に押しやる。
幸せというのは、自分はもう要りませんと他人に譲ってもまた戻ってくるし、絶対に自分から離れないものだけれど、その水を自分のモノだと考えたり、水を満たしてもらうことを当り前と錯覚して、足りない足りない、ともっとかき集めようとすると、幸せが逃げていく。」
このように話されたのは二宮金次郎七代目子孫の中桐万里子さんです。
二宮尊徳は600以上の農村を復興してそこに米・財産を作り上げた人です。
なのに自身が死んだ時、財産はほとんど無かったとと言われています。
無私の人だったのでしょう。
「タライの水の原理」「無私」という言葉は、言うは簡単ですが、自分を振り返ってみると難しいものです。
和して同ぜず
人は考える事を放棄すると、すぐに付和雷同、意見の強い方に流されてしまいがちです。
オセロの駒のように、周りの状況・環境が変わると白が一気に黒になったりします。
最近の風潮はそのような気がします。
本来、人はいろいろな色を持っているはずです。
色は大きく分けて、赤・黄・青等の「彩度」と白・黒の「明度」に分けられます。
人も寒色系の人・暖色系の人、明るい人・暗い人がいます。
それぞれが個性です。
人は個性を保つためにも勉強しなければなりません。
本を読む、人に会に行く、その場所に行ってみる。
大事なのは行動することです。
学び、自分の考えをしっかり持ち、そして「和して同ぜず」
これが大切だと思います。
妻の幸福は夫の降伏
昨夜のテレビを見ていて「成程!」と膝を打った言葉がありました。
「妻の幸福(こうふく)は夫の降伏(こうふく)」
これは夫婦円満の秘訣。
特に私の様な亭主関白の人間にピッタリ!
私の「銘肝録」に書き入れました。
琴似観光協会
私はここ2・3日の間、地元琴似をより活性化しようと考えている人達とお会いしています。
琴似という街は札幌西区にあります。
この街は私の生まれ育った所で、今も住んでいます。
明治8年に日本初の屯田兵村が琴似に作られ、琴似商店街は狸小路商店街に次いで2番目に古い商店街です。
現在琴似という地域は国道5号線からJR琴似駅までの長さ約1000m、発寒川から東へ幅約500mの狭い地域を指します。
この狭い地域に神社、お寺、区役所、区民センター、保健所、小学校、ホテル、ダイエー、イトーヨーカドー、昔ながらの市場が2カ所、地下鉄の駅、JRの駅、劇場などがあります。
メイン通りである「本通り」には商店、飲食店がびっしり並び、空き店舗がほとんどありません。
また琴似には住宅・マンションが多く、JR琴似駅近くには30階建てマンションが1棟、40階建てマンションが2棟が建っており、琴似の人口密度は高いものです。
札幌の中でも一番活気のある街ではないでしょうか。
今、私達が話題にしているのは、この琴似の街の良さを再発見して、それを対外的に発信していこうという考えです。
住んでいる私達が気付かないいモノを探し出し、琴似の魅力を対外的に発信するものです。
内外の観光客が行ってみたいと思われる街にしたいと思っています。
そこで出てきたのが「琴似観光協会」設立の話です。
観光協会というと大きな街単位で設立されますが、こんな小さな街にあっていいのではないでしょうか。
来年度はもっと詰めた話が出てくると期待しています。
2代目経営者
は師走。
忘年会が続きます。
昨夜は琴似にある2軒の飲み屋さんを廻りました。
2軒目の店は30年ほど前からの馴染みですが、ここしばらく行っていませんでした。
行ってみるとママはいなく、代わりにその娘さんがカウンターに立っています。
お客様の入りが悪く、10月には店を閉じようとしたのを娘さんが引き継いだとのこと。
彼女は既に結婚し子供もいますが、あえて店運営を買って出ました。
今までも時々はお母さんの手伝いで店に出ていましたが、これからは全ての責任を負って運営することになります。
2代目経営者です。
この娘さんは高校生の時から知っていますが、明るく元気な人です。
その彼女が経営者立ち上がったのですから、成功出来るよう応援・支援していくつもりです。
とは言え、そう頻繁に飲みに行けませんので、別の方面から応援・支援して行きます。
ある講演会
昨夜ある講演会があり行きました。
行きましたが、講演が始まって30分位で退席しました。
過去数多くの講演会に参加してきましたが、途中で退席したのは初めてです。
講演者の本を以前に読んでいたので、是非話を聞きたいと思って参加したのですが。
話の内容は興味ある内容でした。
ただ話の中で織り込むコメントが他者批判。
聞くに堪えませんでした。
自分の偉さを誇示しているような話し方。
自分では面白く話しているつもりなのでしょう。
札幌に来る前日は宮崎で講演してきたそうです。
年間400件の講演をこなしていると言っています。
そんなに人気があるのでしょうか。
不思議です。
意見の相違
人と話をしていて、意見が違うことは良くあります。
相手から自分と違う意見を言われた時どうするでしょうか?
大きく分けると2つ。
すぐさま反対意見を言い返す人、言われたらそのまま引きさがる人。
言われたまま引きさがるのは無責任。
だからと言って、意見が違うからと喧嘩腰になるのもダメです。
話の上手な人は相手の意見をまずは受け入れます。
受け入れてからそれに対して自分の意見を言います。
自分の意見を一旦受け入れられるので、話した人はある意味「ホッ」とします。
対立感情が生まれにくくなります。
そして話しの上手な人は根気強い人です。
時間をかけて丁寧に話をするので、相手は納得する割合が高いです。
話し合いで一番いけないのは、自分の意見を否定された時、自分の人格まで否定されたと思う人。
そのような人はすぐ激高します。
どちらかというと、功成り名を遂げた人に多いように思います。
会社のトップたる人が業績を上げ、高い評価を受けている時に起きます。
必要なのは謙虚な心。
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」という言葉が頭に浮かびました。
結婚
末娘が結婚することになり、昨日先方のご両親達と顔合わせの食事会をしました。
これで私の子供5人が全てが結婚することになり、ホッとしています。
先方のご両親は若くそして真面目で、明るい家庭のようでした。
安心しました。
食事会の帰り、妻が途中で買い物に行き、私と娘二人で歩いて帰りました。
私が何気なく話す言葉に、素直にうなづきながら応える娘。
愛おしく思えました。
そんな時に思ったのが、親は子供を教育してきたつもりが、逆に教えられてきたのかということです。
子供を育て、物事を教えている時、同時に自分も正されてきたのです。
「悪いことをしないで正しいことをしなさい」「正直で素直でいなさい」という言葉は、言っている親も問われています。
来年はまた家族が増えます。
親友
今上京中で、今日来札します。
昨夜は1年ぶりに高校生時代の友人と上野で会いました。
彼とは考え方も意見も違うのですが、妙に馬が合い親友の一人です。
昨夜も政治・経済・宗教に至るまで、飲みながら語らいました。
3時間ほどで終わり、飲み屋を出て上野駅に向かう時、フッと出たのが「死ぬまで何回会えるだろうね」という言葉です。
年を取るとともに、大事にする事が1つ1つ増えてきます。
私の幸福論
昨夜、横浜で盛和塾忘年塾長例会があり参加してきました。
800名の塾生が集まり、稲盛さんのお話を聞き、その後は忘年会。
忘年会で私が座った席は、運良く稲盛さんと同じテーブルでした。
ただ、残念な事に稲盛さんと対面の席でしたので、お話をするには離れすぎていました。
それでも思いがけない稲盛さんの人間的な優しさ、面白さ、その上可愛らしさを見る事が出来ました。
忘年会前の稲盛さんのお話を紹介します。
演題は「私の幸福論ー幸福は心のあり方によってきまる」です。
1時間30分にわたるお話は納得させられる事ばかりでした。
その中で「利己」とl「利他」についてのお話を紹介します。
利他の心は人知を超えた力を得る事が出来ます。
ヨットに例えての話。
ヨットは自力では走れません。帆を張って他力という風を受けて走ります。
その帆は自力で上げなければなりません。
その帆も美しい心がなければいい帆を上げることができません。
もしも利己の心で上げたのであれば、帆は穴だらけで、風を受けても前に進みません。
幸せを得るには利他の心です。
不幸せの元は3毒といわれる「愚痴・妬み・怒り」。
幸せの元は「勤勉・感謝・反省」です。
この事は稲盛さんご自分が身を以て体験された事であると強調されていました。
そして良い事をなす事に喜びを見出す事で、経営者の幸せを感じているとも言われます。
昨夜は、いいお話と美味しいお酒に酔った夜でした。
日本と台湾2
昨日の続きです。
「終戦時、中国から引き揚げてきた民間人4万人、将兵35万人の命を繋いでくれた中華民国と蒋介石氏に対して対し、当時北支那派遣軍の中将だった根本氏がその恩義に応えるべく行動した」と書きました。
第二次世界大戦が終わった後、中国では中華人民共和国軍と蒋介石氏が率いる中華民国軍との間で激戦が続けられていました。
その戦は中華民国軍の連敗続きでした。
根本氏は日本にて中華民国軍劣勢の戦況を聞き、蒋介石氏から受けた恩義に報いる為の行動を起こします。
北支那派遣軍で一緒だった部下達と連絡を取り合い、台湾にいる同士の用意した漁船で日本を脱出して台湾に向かったのです。
当時、アメリカの管理下にあった日本を脱出するのは大変苦労したようです。
根本氏は台湾では蒋介石氏に会い、以前受けた恩義に報いる為、戦いの最前線に出ることを希望します。
そして大陸近くの金門島に渡り、参謀として戦いました。
それまで連敗続きであった中華民国軍はここで劇的な勝利を得ます。
この結果、現在でも大陸に近いこの金門島は未だ台湾領です。
その影の力は根本元中将達17人の日本人でした。
台湾本島に戻った根本氏達は蒋介石氏から礼を言われ、記念の花瓶をもらいます。
その花瓶は対になっており、現在1つは根本家にあり、もう1つは蒋介石の顕彰施設である中正紀念堂に飾られています。
ただ、この日本人の活躍は中華民国軍にとって都合のいいものではありませんでした。
その事実は長い間伏せられていました。
金門島の戦いで勝利してから60年になる2009年のことです。
その式典準備をしている時、その戦いに日本人が参加していたという話が出て来ました。
それでも大きな話題にはなりませんでした。
2009年10月に開かれた式典に日本人関係者の子孫が招待されます。
その時、思いもかけず出席していた馬英九総統から歓迎の言葉を受けたのです。
2011年3月11日に起きた東日本大震災が発生した時、台湾はどこよりも早く救援隊を派遣してくれました。
馬英九総統は自らテレビに出演して日本への援助を呼びかけました。
その結果、人口わずか2300万人にすぎない台湾が200億円を超える義援金を送ってくれたのです。
日本の占領下にあった台湾であるにもかかわらず、日本との強い結びつきは続いています。
この本を読んで改めて台湾が好きになりました。
日本と台湾
この週末に本を1冊読み終えました。
門田隆将氏が書いた「この命 義に捧ぐ」という題名です。
以前から疑問に思っていたことがこの本を読んで分かりました。
第二次世界大戦が終わった時、満州にいた関東軍は無条件降伏し武器放棄したにもかかわらず、ソビエト兵に虐殺され捕虜とされた兵隊はシベリア抑留になりました。
民間人も虐殺されたり略奪され、孤児も生まれました。
一方中国から無事に帰った軍人や民間人も多数いました。
その違いはどこにあったのか、私は疑問に思っていました。
そのことがこの本に書いてあります。
終戦時、関東軍の司令官は命令に従い武装解除を受け入れ、結果悲惨な事態が起きました。
一方、無事に日本に帰国できたのは内蒙古にいた4万人の民間人、北支那派遣軍の35万人の将兵達です。
その派遣軍のの司令官が根本中将。
この本の主人公です。
彼は攻めてくるソビエト軍から民間人を守るために、武装解除の命令に反し、ソビエト軍と戦いました。
それと同時に中国の中華民国政府と交渉し、北京で降伏文書に署名しました。
日本の民間人、軍の将兵の無事帰国を約束し署名したのです。
中華民国の蒋介石氏はそれを実行しました。
民間人4万人、将兵35万人の命を繋いでくれたことに対し、根本氏がその恩義に応えるべく行動したことがこの小説に書かれています。
小説を読んで、私は思いがけない事実を知りました。
それが今の台湾と日本の親密なつながりの原点の1つだったようです。
そのことは明日書きます。
正しいと思う気持ち
当り前のことなのに、この歳になって何となく分かってきたことがあります。
「人はそれぞれ違う」のです。
「今さら何を!」と思うでしょうが、言葉で理解し、分かっているつもりでも実際は「自分が正しい」という思いの方が強かったように思います。
「人を受け入れる」という心の余裕。
人が話すことに対し、間髪入れず反論することありませんか?
自分の主張が強く、自分の考えが正しいという思いは強くありませんか?
それはいけないことだと思っているのに、実際は同じことをしている自分を見たことありませんか?
今でもまだ引きずっている私ですが、この10年間で変わったように思います。
齊藤一人さんも言っています。
エビの背中が曲がっているのが当たり前なのに、「背中をピンとしろ!」と言っても無理です。
軟体動物のタコに「シャキッとしろ!」と言っても出来ません。
それぞれをありのままに受け入れる。
そしてあまり「自分が正しい」ということを言わない。
「自分は楽しい」と言えば喧嘩にならない。
世界中にユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教と宗教間でも対立が見られます。
互いに自分が正しいと言い張るから争いになるのです。
「自分の宗教は楽しい!」と言い合えば、「あなたも私も、みんな楽しくて良かったね」となります。
争いになりません。
10年前より、ほんの少し良くなった私です。(自画自賛)
さとり世代
最近「さとり世代」という言葉を聞きます。
ネットのkotobankで見ると「インターネットの掲示板『2ちゃんねる』で生まれ、広まった、堅実で高望みをしない生き方。」
1980年代半ば以降に生まれた世代。「ゆとり教育」を受けた世代に当たります。
具体的な特徴として、「車やブランド品に興味がない」「欲がなく、ほどほどで満足する」「恋愛に淡泊」「海外旅行に関心が薄く、休日を自宅やその周辺で過ごすことを好む」「節約志向で無駄遣いはしないが、趣味にはお金を惜しまない」「様々な局面に合わせて友達を選び、気の合わない人とは付き合わない」などが挙げられます。
このような生活は質素で「足るを知る」生活のように見えますが、私から言わせれば単に怠惰で我がままとしか言えません。
そして「さとり」という言葉を使って欲しくありません。
以前にこのブログでも書きましたが、今の安住した生活は過去の私達の先輩が汗水たらし、歯を食いしばってこの国の経済を作り上げてきた「成果」であり「果実」です。
それを何もしないでその「果実」を当り前のようにして食べるだけ。
将来、彼らの子供達はどうなるのでしょう。
「残されたのは親の世代の食い散らかしばかり」という状態にもなりかねません。
「さとり」という言葉に誤魔化されないように!
下を見て暮せ!上を見て励め!
頑張る人を評価する
最近新聞を見ていると増税に関する記事が多いように思います。
消費税は勿論、相続税、今年末で5000万円以上の海外資産を持つ人の申告義務。
そして今朝の新聞に年収2000万円を越す会社役員の所得控除の圧縮と載っていました。
国はこのような増税方針によって、税収を増やそうとしているのでしょう。
5000万円の海外資産も2000万円以上の年収も無い私でも、少し疑問に思います。
何億円も年収をもらっている人なら分かりますが、2000万円位の年収でも狙い撃ちされてくる。
少しでもお金を稼いでいる人から取ろうとする方針。
頑張って経営した人も、得たお金は結果的に罰金のように多くが税金として持っていかれる。
どうなのでしょう。
今の日本で必要なのは起業家であり頑張る経営者です。
大きなリスクを負いながらも起業し、それなりの報酬をもらったのに大きな税金を負わされる。
頑張った人が評価されない。
アメリカや中国は日本と比べ、起業家への尊敬度が高いと言われています。
それなりの報酬を得ている人は、その過程では誰にも負けない努力をしているはずです。
それを評価して上げることが大切です。
「妬み」より「憧れ」
日本では自分よりいい生活している人の足を「引っ張る」人が多いように思います。
アメリカは自分よりいい生活している人がいれば自分も「引き上げて」欲しいと思うようです。
どちらが健全でしょうか。
頑張る人が沢山出てくる日本。
頑張る人を評価し、憧れになる日本。
そのような国であって欲しいと思います。
驚いたこと
先日見た驚きの光景。
左手に白杖を持った目の不自由な人が、右手に火がついたタバコを持って人通りの多い歩道を歩いていました。
傍に介助者らしき人がついているのに。
子供の顔の高さにタバコがあります。
もう1つ。
これは良く見るのですが、電動車椅子に乗り結構なスピードで歩道を走っている姿。
人を縫って走っています。
また、走ってはいけない車道を走っているので、後ろには車が渋滞している時もあります。
その時思ったのです。
相手が健常者だったら注意したかもしれないことでも、相手が障がい者だった時、少し躊躇している自分がいました。
それではいけないと思っているのですが、弱者と言われる人に対する遠慮なのでしょうか。
悔しさ貯金
先日テレビを見ていたらタレントの関根勤さんがいいことを言っていました。
それを紹介します。
心に残ったののは2つあります。
1つ目は「男性は結婚してからも、いつまでも男と女の愛情を持ち続ける。一方、女性は結婚して子供が生まれ、育てていく内に人間愛に目覚めていきます。そこに男女の愛情と価値観の差が生まれる」というような話をしていました。
納得出来る気がします。
もう1つ。
それは「悔しさ貯金」です。
若い時に色々苦労や辛いことを経験して悔しい気持ちが生まれれば、「何クソ!」という生きる原動力が生まれます。
それが大切です。
自分を大きく変えていく力になるのです。
私のの経験に置き換えても納得します。
「若い時の苦労は買ってでもせよ!」と昔から言われた言葉はその通りです。
若い頃にどれだけ「悔しさ貯金」を貯めることが出来るか。
辛いことにぶつかった時、それから逃げず、「自分の糧にする!」「肥やしにする!」という思いで立ち向かう。
それがその人を「大器」として育てていく力になるのです。
「情「と「理」
経営者の大事な心得の1つに「情」と「理」の使い分けがあります。
これを使い間違えると会社を左右させることも起きます。
夏目漱石の「草枕」の冒頭に「智に働けば角が立つ。情に棹(さお)させば流される。」という言葉があります。
経営者は時として、角が立つこともしなければなりません。
しかしその前提として、情のある人でなければなりません。
その使い分けが大切です。
間違いを犯す経営者は「情」で判断する時に「理」で判断し、「理」で判断することを「情」で決めてしまいます。
また「情」の無い人は冷たい人です。
「情」のある人が「理」の判断をした時は、冷たい判断でなく厳しい判断になります。
厳しいけれど正しい判断をします。
「冷たい」と「厳しい」は違います。
「溢れるばかりの情を持ち、時として厳しい判断が出来る」
これが優れた経営者の姿といえます。
ある女性経営者
昨日ある本を読んでいると女性経営者の体験話が載っていました。
彼女は20年ほど前に親の病院を受け継ぎました。
当時その病院は老人病院でした。
当時は認知症ケアなど無く、病院は老人を寝かせただけですんでいました。
彼女はその病院を認知症対応が出来る老人保健施設に変えるべく、203床の病床の70%を捨てました。
それに対しては多くの人の反対がありました。
病床数が既得権益である医療業界では異端児として煙たがれる行為です。
それでも今では「大人の学校」という名称の全く新しいコンセプトの高齢者施設も経営しています。
売上は22億円以上、従業員も400名以上の病院になっています。
彼女は4人の子供を持つシングルマザーの身で経営者。
いろいろ苦労する中である時、自分には感謝の心が足りないのではないか思ったのです。
それで毎日お風呂の湯船の中で「ありがとう!ありがとう!」と節をつけながら唱えました。
吐き気がするほど嫌な思いをした相手の顔を思いながら「ありがとう」と言うのです。
それを続けて1週間ほど経ったころ、ハッとして「ああ・・」と涙が出てきたそうです。
こんな嫌な人でも居てくれたから自分は成長できた。
それを思った時、どんな嫌な人にも感謝の気持ちが生まれ、どんなことでも「来るなら来い」という強い気持ちになったそうです。
自分を励ます言葉を口に出す。
それによって自分が変わる。
本当に言霊なのですね。
ある女性経営者
昨日ある本を読んでいると女性経営者の体験話が載っていました。
彼女は20年ほど前に親の病院を受け継ぎました。
当時その病院は老人病院でした。
当時は認知症ケアなど無く、病院は老人を寝かせただけですんでいました。
彼女はその病院を認知症対応が出来る老人保健施設に変えるべく、203床の病床の70%を捨てました。
それに対しては多くの人の反対がありました。
病床数が既得権益である医療業界では異端児として煙たがれる行為です。
それでも今では「大人の学校」という名称の全く新しいコンセプトの高齢者施設も経営しています。
売上は22億円以上、従業員も400名以上の病院になっています。
彼女は4人の子供を持つシングルマザーの身で経営者。
いろいろ苦労する中である時、自分には感謝の心が足りないのではないか思ったのです。
それで毎日お風呂の湯船の中で「ありがとう!ありがとう!」と節をつけながら唱えました。
吐き気がするほど嫌な思いをした相手の顔を思いながら「ありがとう」と言うのです。
それを続けて1週間ほど経ったころ、ハッとして「ああ・・」と涙が出てきたそうです。
こんな嫌な人でも居てくれたから自分は成長できた。
それを思った時、どんな嫌な人にも感謝の気持ちが生まれ、どんなことでも「来るなら来い」という強い気持ちになったそうです。
自分を励ます言葉を口に出す。
それによって自分が変わる。
本当に言霊なのですね。
度量の広さ
社長がこぼす言葉に「うちの会社には参謀に足る人間がいない」「右腕と言われる人間が育っていない」があります。
ある程度会社が大きくなってくるとそのような人が必要になってきます。
「人がいない」と言われるその会社を良く見てみると、良い人材と思われる人がいます。
でも社長はそれを認めません。
これは良くあるパターンです。
社長はあまりにも高い理想の人材を思い描いているためそのギャップが出てくるのです。
でも本当は、「参謀や右腕がいない」のは社長に問題があるからです。
参謀や右腕となる人は社長のために懸命に働きます。
だからこそ社長は彼らをすべて認める度量がなければなりません。
「このところは認めるが、あの部分はダメだ」というのでは認めたことになりません。
その人の優れたところを生かそうとするならその人の欠点も受け入れる。
また、人は育つ内に欠点も縮小していくものです。
人の欠点をその人の個性と思い、受け入れる度量の広さ。
それが発展する会社のトップに立つ人の資質だと思います。
Windows
昨年の12月にMACProを買ってそろそろ1年になります。
本来はWindows一辺倒で、Windowsは20年ほど前から使っています。
ただ昔からMACのデザインが良く憧れがあり、昨年思い切って買ってしまいました。
勿論Macはすぐには使いこなせれないので、取り合えずword excel等のソフトを入れ使っています。
Macを買って操作が分からなくても「One to One]というサービスがあり、操作方法を店頭で直接教えてくれるので大変助かります。
Macに入れられない会計ソフトなどは従来通りWindowsのパソコンを使い、現在は2台のパソコンを使っています。
WindowsはXPを使っているので、そろそろ新しいオペレーティングシステムを入れなければなりません。
一番新しいWindowsのオペレーティングシステム「Windows8」ですが、ビジネスで使うなら「7」という話も聞きます。
操作性は出来ればXPに近いモノがいいですね。
今、何にしようか、またパソコンも変えてしまおうか、悩んでいるところです。
頑張る人
最近、若い人の話を聞くと日本は「無理して経済成長しなくてもいい」「今の生活で十分」という人がいます。
でも今、楽しく生活が出来るのは、先人が苦労して築いた今の日本経済の上で生活しているからです。
一方、今の快適な生活を支えている日本の財政はどのようなものでしょうか。
家庭で例えると、平均430万円の年収の人が900万円の支出をしています。
足りないお金は借金。
その借金の総額が1億円。
そんな家庭はとっくに自己破産しています。
今朝の日経新聞の一面の見出しは「社会保障費膨張続く」。
2011年度の国民医療費だけで38.6兆円、13年度には40兆円を突破するそうです。
年間の日本の税収が43兆円ほどですがら、医療費だけでほとんど使っています。
近い将来、日本財政の破たんが現実になった時、今の様な安楽な生活はとても出来ません。
先ほどの若者のように「今の生活でいい」など言っていれません。
嫌だと言っても財政破綻という現実問題が迫ってきています。
その時、年金は激減し、病気になっても病院にかかることが出来なくなります。
お金が無いからと言って生活保護申請しても無理でしょう。
そんな時こそ、自分の足で立ち上がり、困難を切り開いていく人が必要です。
国や会社に頼らず、自分で創業、起業出来る、自分でお金を稼いでいける人が生き抜いて行けます。
精神的にも強くならなければなりません。
そんな時代は、全ての価値観が変わり、世の中が「ガラガラポン」と日本の借金も無くなり、失うモノをまだ持っていない若い人達が活躍できる時代なのかもしれません。
北海道の観光
昨日ある講演会に行ってきました。
そこで紹介された北海道の観光に関する話です。
旅行雑誌「じゃらん」が作成した統計です。
それは各項目ごとに都道府県のランキングが付けられています。
「地元ならではの美味しい食べ物」の項目ではは2位。
「魅力ある特産品や土産物」は3位。
「魅力的な宿泊施設」は8位とだんだん悪くなって行きます。
そして「若者が楽しめるスポットや施設・体験」では11位以下で、「地元の人のホスピタリティ」は20番台だそうです。
これらを見て考えるに、北海道の観光は新鮮な魚介類や農産物に頼って、「おもてなしの心」が足りないのでしょうか。
ヒューマンパワーが足りないようです。
そして素材を観光商品化する努力もまだ足りません。
北海道料理は新鮮な食材を出せばそれだけでお客様は喜ぶと誤解しているようです。
食材が良いからこそ、調理人の腕が上がらない。
努力工夫をしなくても切って出せばそれだけで喜ばれる。
一方、新鮮な食材が手に入らない京都は工夫を重ねて京料理を作り上げました。
最近は北海道の料理人の腕も上がっていると言われています。
これからが楽しみです。
もう1つ。
海外での北海道のブランドは日本の各都府県の中でも高いようです。
しかし札幌の知名度はあまり無いという統計があり、少し驚きました。
私の思い込みで、北海道=札幌という見誤った考えがあったようです。
北海道は観光立国と言われていますが、まだまだ課題は多いようです。
カジノ建設
今日は「カジノ」について書きます。
最初に申し上げますが、私は「カジノ」建設には絶対反対です。
日本では国が認可すると賭博でも合法になります。
認可されないと罪になり牢屋に入れられます。
行為は同じなのに国が認めれば堂々と商売と認められ、テレビに評論家まで出て来ます。
昔日本では賭博は隠れてしたものです。
賭博はアウトサイダーなもので真っ当な人間がするものでない。
ヤクザ者がするモノでした。
それが今、堂々と「カジノ」建設を唱えている人達が沢山います。
党派を超えた政治家、経済人、官庁がこぞってその気になっています。
彼らに共通しているのは「お金」です。
日本に「カジノ」を造れば世界中からお金持ちがお金を使いに来て、それで日本や自治体が潤う。
結局お金です。
「カジノ」で行われる賭博で、如何に多くの人がそれに溺れ、身を崩すことでしょう。
本人が悪いこともあります。
ギャンブル依存症という問題もあります。
しかしそのような環境を作らなければ真っ当な生活をした人さえ引きずり込んでしまいます。
パチンコ通いがひどく、家庭崩壊の例は沢山あります。
生活保護を受けている人がパチンコ屋通いをしている現実もあります。
生活弱者と言われる人達が「もしかしたら儲かるかも」という夢見て通います。
大切なのは、お金が入る、お金が儲かるという損得ではなく、人として何が正しいことなのかなのです。
財閥の1つである住友家の家訓に「浮利(ふり)を負わず」という言葉があります。
「浮利」とはまともなやり方でない方法で得る利益。あぶく銭。
事業家が得るべきでない利益のとこです。
「浮利」を追う「カジノ」建設は絶対反対です。
社員を思う気持ち
昨夜は盛和塾の勉強会でした。
講師に名古屋から経営者Kさんをお呼びし講演していただました。
いいお話しを沢山されましたが、その中で紹介したいお話を1つ。
Kさんの会社はハートランドという住宅販売の会社です。
会社の名前を考えた時、付けたかったのは「愛があれば大丈夫」という社名です。
しかしこれでは住宅会社とは思われないため、英語に置き換え「ハートランド」としたそうです。
Kさんも以前より盛和塾に入っていて、稲盛さんの教えを充分に受けている人です。
社員を思う気持ち、お客様を思う気持ちが強く、それが先ほどの「愛があれば大丈夫」という名前にしようとしたのです。
社員を思う気持の変化として1つの例を紹介されました。
社員が遅刻した時、以前だと、なぜ遅刻したのか、なぜチャンと出来ないのかと怒る気持ちが先に立ちました。
しかし社員を思う気持が強くなった時、変わりました。
心配の気持ちが先に立つそうです。
病気でないのか、事故にあっていないのか。
「怒る気持ちより心配をする気持ちが先に立つ」のです。
理屈でわかっていても本当にそう思えることは難しいことです。
つい先に文句が出がちです。
Kさんの会社「ハートランド」の経営理念は「全従業員の物心両面の幸福と追求する」とあります。
それを実践している1つです。
売上は23億円、経常利益も10%の2億円稼いでいます。
Kさんの演題は「改心への道のり」ですが、それを実践した結果です。
大変参考になるお話でした。
準備する
人は何をするにしても準備が大切です。
「段取り8分」とは準備が十分できていれば8割達成したようなものという意味です。
準備が出来ていない時は心構えも出来ていません。
稲盛和夫さんは人生を3つに分けてお話します。
「自分は80歳くらいまで生きるだろうと想定し、人生を3期に分けて考えていました。
生まれてからの20年が第1期。これは社会に出るための準備期間です。
その次の40年は社会のために働く期間です。
第3期、最後の20年を、死ぬための準備期間としていました」
準備とその心構え。
どんな時にも大切なことです。
その時になってもあわてず迎える覚悟。
私も今、整理する期間に入っているのでしょう。
これからじっくり準備していきます。
タイ旅行2
昨日書きましたタイ旅行の続きです。
タイの経済事情を説明してくれたのは、北洋銀行からバンコク銀行に出向しているTさんです。
バンコクは漢字で「盤谷」と書きます。
その名の通り中国華僑の影響力は絶大です。
バンコク銀行の頭取も華僑。
タイの政府は外国の企業の進出を歓迎しており、バンコク銀行も多くの国の銀行から出向者を受け入れています。
その数は13カ国にもなり、日本の各銀行からも23人出向しています。
バンコクの経済は24時間動いているそうで、バンコク銀行も24時間開いています。
Tさんの話ではタイでは時間の制限も無く働くそうです。
打ち合わせが夜の10時などは当り前で、時に頭取が出席する会議は夜中の1時集合というのもあります。
過酷な勤務状況だそうです。
街中のATMも24時間利用可能、バスも24時間運行しています。
バンコクの街は24時間活動できる環境が整っています。
タイには4万人の日本人が暮らしています。
タイで事業を起こすには「合弁」でなければなりません。
その上株式51%以上はタイ企業が持つことになっています。
そんなこともあってか、日本からの進出企業の半分は赤字だとのことです。
北海道札幌ととタイバンコクとは直行便が飛んでおり、10月より毎日運航になっています。
私が乗った飛行機も満席状態。
タイの人は北海道に対して良い印象を抱いています。
ただ寒い冬は苦手のよう。
人気がある観光地は「歌登」です。
ご存知ですか?
そこではグリーンパークホテルに泊まることが目的。
このホテルは以前日本のTVでも紹介されていました。
「1度で日本を味わいつくす」というコンセプトで、夕食時和太鼓でお客様を迎え、鮭の解体ショーを見せ、餅つきを体験させ、握り鮨やたこ焼きを食べさせます。
流し素麺まであります。
北海道の片隅のホテルがタイで評判を呼んでいるのとにびっくり。
またバンコクのショッピングセンターを歩いていると、「大戸屋」がありました。
日本のメニューの「しまホッケ定食」まであります。
諸問題はあるのでしょうが、確実にタイと日本の経済の結びつきは深まっています。
これからも色々な経済交流の発展があるだろうことを実感しました。
タイ旅行
1週間ぶりのブログです。
この間タイに行ってきました。
銀行主催のタイ視察(実際は観光)旅行です。
古い都のチェンマイ、タイ最古の都スターコイ、そして首都バンコクです。
旅行中はどこへ行っても感じたことは、仏教に対してタイ国民は敬虔な信者だということです。
しかし宗教は複雑で、ヒンズー教も信仰されており、タイの国王は仏教、ヒンズー教どちらも信仰しています。
国王というと、タイではその権威は絶対的で犯してはならないモノです。
またその王族にも権威は絶対的です。
タイ駐在の日本人銀行員の話です。
ある時ヨットの乗っていた皇太子が転落して溺れそうになった時、1人の士官が助け上げたそうです。
普通はその行動によって表彰されると思います。
ところがその士官は絞首刑になりました。
王族の人の身体には触れてはいけないのです。
その法律があるがため、またそれを守るために絞首刑にされたのです。
このように王族は絶対的です。
またそのような権威と権利を持って、タイの経済を握っていると言われます。
明日はこの話をしてくれたタイ駐在の日本人銀行員から聞いたお話しを紹介します。
エンゲージメント
今、新聞やテレビでは毎日のようにホテルやレストランで食品偽装が報道されています。
一方、JR北海道での点検・保全及び運行に関して問題発覚とその調査が行われています。
そこには共通の問題点があるように思います。
そんなことが思っている中で、先日ネットでダイヤモンド社の記事を見ました。
「世界でダントツ最下位!日本企業の社員のやる気はなぜこんなに低いのか?」と題したものです。
アメリカの 人事コンサルティング会社ケネクサの調査によるものです。
その調査は「従業員エンゲージメント」についての調査しています。
「エンゲージメント」とはある辞書で、「個人が目指す成長の方向性と組織が目指す成長の方向性がどれだけ連動している関係なのかを表すもの」と説明されています。
組織に対する「ロイヤルティー(忠誠心)」を発展させたような概念です。
即ち「やる気」。
調査は28ヵ国の社員100名以上の企業・団体に所属する社員(フルタイムの従業員)を対象に行なわれました。
サンプル数は約3万3000名に及びます。
その結果、世界最高はインドで77%です。
アメリカが59%で5位。
中国は57%で韓国は40%。
日本は31%でダントツの最下位です。
ヨーロッパの国々も低く40%台後半で、概して先進国が低いようです。
経済豊かな生活に囲まれ、頑張らなくてもそこそこ生きていける環境だからなのでしょうか。
冒険や挑戦する人達が少なくなってきているのです。
でも現状を嘆いていてもしょうがありません。
「やる気」を高める、「エンゲージメント」を高める為に必要なものと考えます。
それは会社と社員が共有できる共通理念の保持とそれを継続するための工夫だと思います。
これこそ経営トップの仕事です。
やはり最後は経営者の責任に帰するように思います。
携帯電話の普及
携帯電話は世界で物凄い勢いで広がっているようです。
テレビを見ている時、砂漠に住む人達が普通に携帯電話を使っているのが映っていました。
それでその普及状況に興味を持ちました。
ある資料によると、2013年現在、携帯電話の世界での普及率は対人口当たり先進国128.2%、新興国89.4%、平均96.2%にもなって、毎年増加しています。
一方、固定電話は先進国41.6%、新興国11.1%、平均16.5%で各国とも年々減少しています。
昔、日本では固定電話は金持ちの象徴でした。
そして電話を設置する時、電話債券を買わされました。
私も銀行員時、窓口で電話債券を扱った覚えがあります。
確か1台当たり10万円位だったでしょうか。
電話を設備するには莫大なお金がかかるというのが電話債券発行の理由でした。
確かに電話局、交換機、、電柱設置、電線管理等の投資、そしてそれらのメンテナンスには莫大な時間と費用がかかります。
それに比べ携帯電話は極端なことを言えばアンテナ塔を立てればつながってしまいます。
固定電話に比べほとんど費用がかかりません。
だからこそ砂漠の真ん中に暮らす人も電話が使えるのです。
それはある意味、長年莫大の資金を投資はぜず、色々な苦労や努力も無く、成果の恩恵だけを受けている「幸運」のように見えます。
でも先進国と比べ技術の蓄積はありません。
人の教育もありません。
そこが国力の違いになってくるのでしょう。
なんだか人の成長に似ているように思えます。
パーソナルサービス
商売をしていると頭を下げることが多いです。
その時、何に対して頭を下げているのでしょう?
お客様に対して頭を下げて入るつもりでも、実際は無意識の内にお金に対し頭を下げているのではないでしょうか。
銀行に普通預金を持っているだけのお客様より、1億円預けてくれるお客様。1万円の指輪を買ってくれるお客様より、100万円の指輪を買ってくれるお客様には、自然と最敬礼するのではないでしょうか。
それが普通です。
でも皆が普通のことしかしない時に、それ以上の事をすると感動を与えます。
その方法は人によりそれぞれ違います。
個性があっていいと思います。
そしてそれがお客様1人1人に対して細かく対応する「パーソナルサービス」ということになります。
自分しか出来ない「パーソナルサービス」
一度考えてみるといいかもしれません。
経理
先週、ある会計士さんの話を聞きました。
その話は会計士さんの本音です。
建前として1人で起業した時はしっかり事業計画を立て、稼ぎ、その結果である試算表を作り、次の仕事に生かすと言われています。
しかし、実際はある程度の事業計画書があれば、稼ぐことが大事で、如何に多くの利益を出すことが大事で、経理処理、試算表作りなどは二の次でいいと会計士さんは言います。
これには私も賛成です。
1人の時は売上を上げることが何よりも大事で、少しでも多くの利益を得ることです。
経理などは後処理で十分。
しかし、人を雇用した時は違ってきます。
誰がどのようにして、どこで売上を上げ、利益をどの程度出したかを知る必要があります。
そして対策を考え次の手を打ちます。
その時にバランスシートや損益計算書が必要になります。
またその時は経理も自社で処理し、試算表は遅くとも翌月7日までには作り、「結果検証と対策」が出来るような仕組みを作らなければなりません。
外部に経理を依頼すると、その月の試算表の出来上がりが翌月末、下手すると翌翌月になることもあります。
それでは意味をなしません。
税務申告するだけの試算表作りでしかなくなります。
人を雇って経営するには試算表は不可欠のモノになります。
1人で起業した時、経理は二の次で、営業に力を入れる。
次に人を雇用した時は、効率良い事業展開するために、自社で経理を行い、試算表を確認して「結果検証と対策」を繰り返し、全社的経営効率を図る。
それがトップの仕事です。
近江商人
昨夜は私が毎月開いている身丈会という起業を志す人の勉強会でした。
今月は「てんびんの詩」というDVDの鑑賞会でした。
以前にも「てんびんの詩」について書いたと思います。
「鍋ふた行商」を通して近江商人として少年が成長していく姿を映しています。
90分のDVD鑑賞のあとに近江商人の「商売の十訓」を皆さんにお渡ししました。
これはどこからの出典か分かりません。
インターネット上にあったモノです。
読んでみると「てんびんの詩」で映されていることと、「商売十訓」がピッタリ一致しています。
「無理に売るな、客の好むものも売るな。客に為になるものを売れ」
この言葉は今の売れない時代において考えさせられる言葉です。
次回は11月21日です。
今度は稲盛和夫さんの本「心を高める経営を伸ばす」の輪読会です。
参加希望な方いらっしゃればどうぞ。

割り勘
普段、人と食事に行く時は日本では割り勘が当り前です。
でも中国や韓国では割り勘を申し出る行為が相手を侮辱することなるとWikipediaに書いてありました。
私の場合、時々年下の人に飲み行こうと誘う時は割り勘でなく私が払うことが多いです。
でもそんなことが続くと相手が「申し訳ない」という気持ちが強くなり、あまり楽しめなくなります。
でもまた、それでは割り勘となると、収入が少ない若い人に申し訳ない気持ちになります。
それで考えました。
「年齢の割合いで勘定」するか「収入の割合で勘定」する割り勘もあっていいかと。
例えば若い人と一緒に2人で食事や飲みに行った場合、勘定が1万円位だとすると、「今日は割り勘ですよ」と言って3000円をいただく。
7000円は私負担。
それであれば、若い人にとっても「申し訳ない」という気持ちは薄くなるのではないでしょうか。
厳密な割り勘をする人がいますが、それでは折角の楽しい食事が台無しになります。
当り前のように「年齢差による割り勘」等、あってもいいと思います。
日本酒
先日「秋の道産酒を楽しむ会」に参加してきました。
これは私が運営する札幌オフィスプレイスに入っているミズネットワークの木村さんが主宰したものです。
木村さんは札幌ホテルヤマチ内で「ヤマチカルチャーサロン」を開き、多くの講座を開講運営しています。
その活動の1つとして開かれた日本酒を楽しむ会です。
講師には銘柄「北の錦」を製造している小林酒造の小林専務です。
7種類のお酒を飲みながら、その違いと製造工程を説明していただきました。
1本1万円するという大吟醸は美味かったです。
料理は日本酒に合うものということでホテルヤマチが提供しました。
日本酒は日本の文化です。
そう言えば今朝のニュースで和食がユネスコの無形文化遺産に登録になる見通しとの報道がありました。
ニュースを聞いて誇らしい気持ちになります。
また、和食と合うお酒はやはり日本酒。
和食がユネスコの無形文化遺産になれば日本酒もより注目を浴びそうです。
日本文化を勉強するためにもこれから日本酒を楽しみたいと思います。
次回の勉強会が待ち遠しいです。
ワクワク・ドキドキ
人が何かを起こす時、そこにはワクワク感やドキドキ感があります。
それが原動力となって突き進んで行くことが出来ます。
それを阻害するのは「あきらめ」。
それをカッコ良く言う言葉が「達観している」です。
本来「達観」という言葉は「目先の細かなことに迷わされず、 真理・道理を悟ること。さとりの境地で物事にのぞむこと」です。
なかなか達することが出来ない境地です。
その「達観しているから」と言って自分を誤魔化す。
歳をとった人がよく言う言葉です。
いつまでもワクワク感・ドキドキ感を持ち続ける為に必要なのは「欲」です。
「欲」を持つことは悪いことではありません。
それが我欲にこだわると災いが起こりことを分かっていればいいです。
利他を自分の欲となればいいのですが、それには時間がかかります。
ロケットが地上から離れる時の1段ロケットは一番大きな推進力を必要とします。
何かをなすには、まず飛びあがらなければなりません。
大きな欲を持ち、ワクワク感・ドキドキ感を持ち続けることが夢を叶える原動力です。
これはワクワク感・ドキドキ感を少し無くしかけている自分に対する言葉でもありす。
台湾のうどん店
今日も中国で行われた盛和塾のお話しをします。
経営体験発表者の中に台湾の経営者が1人いました。
彼のお話を紹介します。
名前は厳心鏞さんといいます。
昨年の4月より台湾で日本のうどん店を展開しています。
4ヵ店104名の従業員がいます。
厳さんの創業理念は「家の貧しい若者を助け、事業を発展させ、物質的に豊かな生活を送れるようにすると同時に、若者が心を高め親孝行をし、次世代のより多くの若者に愛を伝えること」です。
彼は色々な仕事の経験の中で、ある尊敬する人に出会いました。
その人から「創業こそ青年にとって最大の助けになる」と聞かされます。
またその人から贈られた稲盛さんの本「生き方」を読み、その後の自分の生き方を決めました。
そして日本式うどん店事業を始める時、将来の創業条件にあう若者を4名選らび雇いました。
彼らはいずれも家庭が貧しいか、片親に育てられていて、また極めて親孝行でした。
親孝行と貧困は最も重要な選択条件だったそうです。
親孝行であれば同僚やお客様にもきっと良くしてくれ、また貧しかったからこそ、他人の恩に対して感謝の気持ちが深くなると言います。
厳さんの事業は順調に発展して、現在売上高1億2800万台湾ドル(約4億3000万円)、経常利益率20.5%です。
店のモットーがあります。
「敬事如神(敬うこと神の如く)」
これはうどんを作る時、1碗1碗神聖な気持ちを込めて作る。
「待客如親(客に相対すること親に対する如く)」
お客様に対しては親孝行するように対応してほしい。
厳さんは自分の生き方を、うどん店を通しての「若者の創業」に置いています。
大変共感できます。
テレビを見て
最近のニュースの話。
国会内で吉野家の牛丼、その高級版「牛重」が話題になっています。
そのニュースに対して、「そんなに高い昼食を食べ庶民の気持ち分かるのか!」と言う声もあります。
お金のある人が高いモノを買うことに対して問題はないでしょう。
お金のある人が高いモノを買うことで経済が活性化します。
遠慮なくドンドン使うべきです。
ただ、口では庶民の味方的な言葉をしゃべりながら、実際は庶民と離れた行動をする政治家に対して違和感を感じるのです。
同じことをテレビを見て思います。
有名キャスターと言われる人がテレビに出て、1日何百万円の出演ギャラをもらいながら、年金問題、雇用問題、生活保護者に関する話をしても、真剣さを感じられません。
何百円、何千円単位の話をしても違和感を感じます。
同じように感じている人も多いのではないでしょうか。
庶民と同じレベルで話すなら局アナであるべきです。
最近のテレビを見てそのように思っています。
中国人経営者
先日の13日、中国成都で行われました「稲盛和夫経営哲学成都報告会」の様子を書きます。
中国人1500名、日本から160名の人が参加して行われました。
9時から22時まで13時間のロングランです。
中国から5名、台湾1名、日本人1名の経営体験発表が行われました。
今回の発表会はいつも聞いている日本人ばかりのとは大分違いました。
中国人経営者達は稲盛哲学を如何に実践しているか、そしてその結果、効果が如何に大きいのかを話します。
稲盛哲学即ち日本で言うフィロソフィ―は、「正直であれ」とか、「損得でなく善悪で判断しなさい」等当り前のことが書かれています。
ですから、従来の日本人経営者の発表はそれを当り前に行った上で、如何に苦労して経営しているかを語ります。
しかし中国は違います。
日本で当たり前のことが、今の中国では重要なのです。
中国人経営者から、お客様を騙さないで正直な商売をしたら信頼され売上が上がったとか、従来は従業員の事でなく自分の損得ばかり考えていたが、「従業員の物心両面の幸せを追求する」と経営理念を作ったところ、従業員の仕事ぶりが上がったという報告があります。
その話を聞いて思うのは、中国はまだまだ商業道徳的な環境は整っていないという思いと、そのような環境だからこそ、それに気付いて稲盛哲学を導入にした会社が伸びれる余地が大きいのだということです。
発表者の1人は創業9年目の会社を33億円の売上、5500名の従業員を擁する会社に伸ばしています。
稲盛さんが私達によく話をする「人生の成功方程式」があります。
人生の成功=考え方×熱意×能力
その中で一番大事なのは考え方。
考え方は-100から+100まであります。
マイナスの考え方をすると間違えた人生になります。
中国の経営者の話を聞いていると熱意は日本人以上に高いものがあります。
中国の教育も日本以上に熱心です。
ただ考え方だけが不十分だったのです。
経営にフィロソフィ―を導入することによって、中国の経済は大きく発展していきそうな気がします。
日本にいると新聞等の報道で、中国は不正や誤魔化しばかり横行していると書かれています。
しかし実際はそれを正して、日本人以上の熱意を持って経営している経営者がいるということ。
今回会った中国経営者から教えられました。
中国成都
昨夜中国から帰りました。
飛行機の遅延などで家に着いた時は夜の11時頃。
今日は寝坊してしまいました。
四川省の省都である成都に4泊して、丸1日は勉強会、2日観光です。
ホテルは5つ星ホテルで、50㎡以上の広さがあり、内装・装備ともで過去に経験ないほどに豪華。
同じホテルで4連泊しました。
ただやはり中国と思ったことは、インターネット状況です。
ホテル内はWiFi環境にあるですが、つながるサイトと規制されているサイトがあるようです。
Facebookはつながりません。
ブログのFc2もつながりません。
やはり中国なのですね。
ただ、中国の経営者は熱いです。
1500名を超える中国経営者が集まった勉強会などの様子は明日改めて書きます。
中国成都
今日これから中国に向かいます。
中国四川省の省都である成都です。
中国の盛和塾が主催する「稲盛経営哲学報告会」が成都で開催され、それに参加するためです。
日本からも参加者は多いと思います。
参加者数は中国の盛和塾生を中心に総勢1500名になるとのこと。
4泊5日の日程で、その内丸1日が勉強会です。
中国の発表者6名、台湾から1名、日本から1名の経営者が「我が経営」を語ります。
そしてそれぞれに稲盛さんからコメントが述べられます。
報告会最後には稲盛さんから「講話」。
稲盛さんの「講話」も楽しみですが、中国の経営者からどんな話が出るのかも興味があります。
楽しみと言えば、観光ですね。
四川と言えば三国志。
成都にある劉備玄徳、諸葛亮孔明が祭られている「武候祠」へ行く予定です。
パワーを貰ってきます。
創業・起業社長
先週の金曜日は、私も参加している「競争戦略」の勉強会最終日でした。
北大の平本教授も参加していただいての勉強会。
この日は私が講師役を務め「日本企業の問題と戦略の重要性」を説明しました。
概略を説明しますと
日本の企業はモノ作りには必死であっても、それが利益に結びつかないのは「戦略のアンバランス」にあるのです。
その上現在は日本はモノを作る能力自体も劣ってきています。
そしてまた、従来持っていた能力が環境の変化に適合しなくなっています。
日本企業の強さの源泉であった現場や労働者のスキルアップ、そして動機付けの仕組みが台湾や欧米企業に持っていかれているのです。
この勉強会が終わった後、平本教授と話し合いました。
教授は日本の企業にはプロの経営者が少ないと言います。
日本の大企業の経営者は多くがサラリーマン経営者です。
大企業の中で元気なのは創業者が社長か影響力を持っている会社。
創業者一族が経営している会社です。
トヨタ、日本電産、ワコール、堀場製作所、オムロン、ソフトバンク、島津製作所等。
プロ経営者がいるのは日産でしょうか。
平本教授の話では欧米ではプロの経営者を作るために、長い時間かけて育て、また一旦社長になると10年20年と長い間その仕事を遂行します。
日本大企業の社長は3年か5年で交代します。
そこには「とりあえず任期過ぎるまでは・・・」とい考え方が生まれ、サラリーマン社長の素地ができていまうのでしょう。
創業社長・プロ社長とサラリーマン社長との違いは一言で言えば「覚悟」です。
逃げない、逃げれないという確固たる「覚悟」があるかどうかだと思います。
日本は外国と比べ起業・創業者数が少ないと言われます。
日本に多くの創業・起業する人が増え、日本の現状を変革する人が出てくることが、今の日本にとって重要なことのように思います。
命もいらぬ名もいらぬ
今日は小説の話をします。
昨日やっと長い小説を読み終わりました。
私は原則、小説はお風呂の中で読むことにしています。
その為1日に読める時間は長くて40分くらいが限度。
そのようにして今回読んだのが山本兼一氏の「命もいらず名もいらず」です。
上下巻それぞれ500ページ以上ある小説です。
主人公は山岡鉄舟。
幕末の三舟(勝海舟、高橋泥舟、山岡鉄舟)と言われた1人です。
剣豪であり、そして高い精神性を身につけた人です。
大政奉還を成功させた立役者であり、また幕臣でありながら明治天皇の教育係も務めた人です。
この小説の題名になっている「命もいらず名もいらず」は西郷隆盛の言葉として伝わっています。
山岡鉄舟は将軍の命を受けて、天皇に対しての謹慎と江戸城無血開城の意思を伝える為に、官軍の中をかいくぐり、大変な苦労をして駿府にいた西郷隆盛に会い、将軍の意を伝えました。
その後、江戸に入った西郷隆盛は薩摩屋敷(東京三田付近)で勝海舟と会い、江戸城無血開城の話し合いをしました。
その時、西郷が勝に山岡鉄舟を評して言った言葉です。
「あの人の眼中には敵味方の区別がないようだ。あんな命も名もいらぬ人は、敵も味方も始末に困るものです。しかしこの始末に困る人でなければ、ともに天下の大事を語ることが出来ませぬな。」
山岡鉄舟はお金にも名誉にも無頓着だったようです。
しかし仁・義に篤く、多くの人から慕われました。
あの清水次郎長もその1人です。
色々考えさせられる本です。
久しぶりにいい本を読みました。
競争の中で頑張る
私の家には小さな庭があります。
少しばかりの種を撒き、実ったその野菜を食べて楽しんでいます。
その庭に撒く種も、芽を出すモノ出さないモノがあります。
また芽を出して一所懸命大きくなろうとしているモノと伸びずに枯れてしまうものがあります。
そんな光景を見ていると、自然の中にも競争はあるのだろうなと思います。
確か稲盛さんも同じことを言っていたことを思い出します。
自然界の草木は生まれたからには一所懸命伸びて太陽を浴び、またもっと大きくなろうと努力します。
その競争に負けた草木は枯れていきます。
そこで見る自然界には競争はあってもズルはありません。
大きく伸びる草木はその過程で、他の草を引っこ抜いたりの邪魔をしません。
大きくなった草木はそれぞれが一所懸命大きくなろうとした努力の結果です。
一方、最近の日本においてはどうでしょう。
一生懸命頑張ることがそれほど評価されていないように思います。
頑張るより、「無理をしない」とか「ほどほどに生きる」。
そんな生き方がもてはやされているように思います。
でも頑張る人がいなければどうなるのでしょう?
頑張る人がいるから、無理をしないでほどほどに生きていく人も生活が出来るのです。
私の周りにいる起業家は、多くのリスクを背負いながら一生懸命頑張っています。
競争の中で頑張っています。
今、日本で必要なのは、共に競争しながら頑張ることであり、またそのような人を支援・応援する環境を作ることです。
欲をかかないで「足るを知る」ことも大切ですが、上を見て頑張ることはもっと大切です。
庭の草木を見てそう思いました。
心のありよう
先日ある人と話していた時、「生き方」の話しになりました。
私は「魂を磨く」や「因果の法則」などの話しをしました。
その時、そばにいた別の人から「山地さん、何かの宗教に入っているのですか?」と尋ねられました。
「人のために良いことをしよう」とか「損得より善悪で判断」の話をすると、宗教に入っているとか、何かにかぶれていると思われるのでしょう。
「そのように思う人がまだ多くいるのだな」と改めて認識しました。
私の若い頃、そのような話をある経営者にした時のことを思い出します。
思いを込めて話しても「何時までもそんな青臭いことを言っているようじゃダメだ」と言われました。
そのようなことは何回もありました。
今振り返ってみると、そのようなことを言った会社はその時は良かったのですが、今は無くなっているか衰退しています。
経営者は、たまたま会社が順調に推移している時、つい「俺はすごい経営者だ」と思ってしまいます。
自分の力だけで成功したと思っているのです。
「おかげ様」と言う思いがありません。
そのような思いが会社をダメにしてしまいました。
今まで長い間多くの経営者を見て来ましたが、経営者と話をすると、成功する人、そうでない人の違いが分かるようになりました。
「心のありよう」
単純なことだけれど人として大切なことです。
「心のありよう」
常に意識したいと思います
偽装問題
今、お米の偽装問題が発生して新聞やTVで報道されています。
以前は牛肉の偽装問題もありました。
偽装を起こしたその業界では、1社でもそのような行為をすればその業界全体が疑われてしまいます。
ほとんどの会社は真っ当な商売をしているはずです。
偽装を起こした会社は「善悪」でなく「損得」で考え、間違えた方向に踏み出していったのでしょう。
そのような会社は弁護するに値しません。
しかし一方見方を変えれば、そうでもしなければ生きていけないほどの過酷な競争を強いられているという見方も出来ます。
以前から不審に思っていることがあります。
今回お米の偽装問題で、被害者的立場のイオンやダイエー等の大手小売店に対してです。
大手小売店は「消費者の味方」的立場に立ち、特売と称して安売りをします。
しかし安くした「ツケ」は自分達が持つのではなく、全て下請や納入業者に持たせます。
自分達はしっかり利益を保持しています。
ギリギリの利益しかない下請や納入業者の犠牲の上に成り立つ特売です。
この構造は多くの業界でもそうでしょう。
私の会社の家具製造会社でもそうです。
安売りは一見消費者にとって味方のように見えますが、回り回って消費者、すなわち国民の首を絞めているようなものです。
消費税率のアップが決まりました。
消費税還元という名の下で、下請や納入業者いじめが始まることのないように願っています。
因果の法則
1日、2日と仙台に行ってきました。
また稲盛和夫さんの市民フォーラムでの話を聞きにです。
9月12日に函館で行われた市民フォーラムでの話と同じ内容であるとことを承知で行ってきました。
そこでまた「気付き」がありました。
「善きことを思い、善き行いをすれば、善き結果が生まれる」
これは稲盛さんがよく言われるお話です。
ご自分の体験を通してのお話です。
KDDIの前身である第二電電を作る時、「新しい電話会社をつくるというのは、本当に世のため人のためになると思ってするのか?自分の名誉・名声のためにするのではないのか?」と自分に問いました。
「動機善なりや、私心なかりしか」
また、78歳の時にJAL再建に取り組んだ時も同じことを考えられたそうです。
この市民フォーラムでのお話は、「この成功は自分の力ではなく、自分が善きことを思い、善き行いをしたから神様が良き結果を与えてくれた」と言います。
「自分が善きことを思い、善き行いをしたから良き結果が生まれた」という言葉を普段私達が使うと「自分の行いを自分で褒めている」と思われる恐れがあります。
稲盛さんは誤解されることを分かった上で、あえて「自分の行いは善き行いだったから良き結果が生まれた」と言うのです。
人から如何に思われようとも、本当に「因果の法則」が存在するということを言いたかったのだと思います。
あえて稲盛さんが誤解を恐れず話した「因果の法則」の存在を、今回改めて強く意識しました。
過度の期待
先日妻と話していた時の話題です。
最近、子供達は周りの大人達から、「あなたには特別の才能がある」とか「あなただけの能力がある」とか、選ばれた人間のように言われる風潮があります。
そんな風に言われて子供達はそれを見付けられるでしょか。
自分の好きなことさえ見付けられない子供たちも多いはずです。
周りから「あなただけが特別な能力がある」子供だと言われて、素直に信じ、探すとしても見つからない。
結果、それは見付けれられなかったという余計な劣等感を与えていることにならないでしょうか。
中学生、高校生、大学生になるにつれ、そんな能力が見つからず自信を無くしている子供が増えているように思います。
今の大人だって見付けられない人が多くいるはずです。
それを子供に過大な負担を与えることはないです。
それよりも、何でも今、一生懸命頑張ることが素晴らしいことと教える。
そのことが大切です。
子供はその成長の時々に、一生懸命遊び、勉強している内に何かを見付けていきます。
楽しいこと、苦しいこと、悲しいことなどを経験しながら、人の痛み、喜びを知って行くうちに、社会とのかかわりを持ちます。
その中で、好きなこと、得意なことが見つかり、運が良ければ自分の生きる道が見つかって行きます。
親は子供に過度の期待はしないこと。
親と言う字は「木の上に立って見る」と書きます。
親は子供の最大の応援団。
それでも遠くから子供を見守る。
それが大事だと思います。
親しき仲にも礼儀あり
最近テレビを見ていてチョット嫌な気分になる時があります。
若いタレントが街中を歩きながらの番組の中で、素人、特に年上の人にタメ口を聞くのを見て、「なんだ!」と思ってしまいます。
テレビに出て少し有名だからと思って勘違いしているのでしょう。
また、それを許している大人が悪いのです。
昔、演歌歌手の三波春夫さんは「お客様は神様です」と言っていました。
テレビタレントも客商売。サービス業なのです。
私達商売人からすると、お客様に対してのタメ口はもっての外です。
お客様への気配り、心配り、そしてお客様の心に寄り添うのです。
「親しい仲にも礼儀あり」
たとえ親しくなっても越えてはいけない一線があります。
「慇懃無礼」もダメですが、一線を越えての「慣れ合い」もダメです。
飲み屋さんでマスターと友達のように親しくなって馬鹿話をする時も、一線を知っているマスターは決してお客を馬鹿にしません。
だからお客様は居心地が良くなって通うのです。
一流のマスターは「親しさ」と「慣れ合い」の違いをわきまえています。
真理把持
先日「真理把持(しんりはじ)」と言う言葉を聞きました。
これはインドを独立に導いたガンジーが唱えた言葉です。
その意味するところは、真理の把握が暴力による不正を打破する武器になり力になるということです。
正しいことは何か。
真理・真実を知らなければ現状を変えることも出来ません
今のインドの人達に広く知られた考え方で、それが生き方になっているようです。
彼らが何かを学ぶ時、教える側にすると、質問が多く、また大変理屈っぽくて素直に聞いてくれないそうです。
ところが一旦その本質が分かるとその応用が素晴らしく、ドンドン前に進んで行くと言います。
これがインド人が優れていると言われる1つの要因。
確かに本質を掴むことが出来れば、考えにブレが無くなり、自信を持って仕事も出来、発想も広がって行きます。
「真理把持」
私の「銘肝録」に書き入れました。
心の準備
仕事をしていると、突然誰かから依頼されることがあります。
会社の中では上司から「〇〇さんの仕事を引き継いでくれ」とか「△△の仕事を任せるからやってくれ」と言われることがあります。
その時の人の反応は2種類に分けられます。
「何で俺なの?他にも居るじゃないか!」と思う人と、「私にやらしてもらえるのか?」と思う人。
この2人の違いは受身と能動の違いです。
その結果は自ずと決まってきます。
常に上を目指す人。
そんな人はその時に備え準備をしています。
その為の勉強と心の準備。
仕事ではありませんが、ある社長から聞いた話です。
会合に出席していると、突然スピーチを依頼されることがあるそうです。
突然ですから普通は断るか、話しても満足な話が出来ない人が多いでしょう。
でも、その社長はどの会合に出ても突然の依頼に備えて、簡単なスピーチ内容を考えているそうです。
これも心の準備が出来ているということですね。
SLニセコ号
先日の日曜日、友人たちと余市でパークゴルフしてきました。
8時31分発のSLニセコ号で出発。
小樽で30分ほど停まり撮影会。
10時30分頃にやっと余市に到着です。
SLに乗ったのは何年ぶりでしょうか。
昔は煙に悩まされ、きれいなワイシャツなどは薄汚れてしまいました。
それなのに今乗ると、その煙の臭いが懐かしく感じられてしまいます。
乗車していた人達のほとんどが私より若い方ばかりで、懐かしさではなく珍しさで乗っているようでした。
余市の駅で停車している時、SLの機関士と話を機会がありました。
40代の機関士ですから、彼がJRに入社した時はSLは既に過去のものでした。
SLの運転は先輩機関士からビッチリ教えられたそうです。
その先輩SL機関士も一番若くて65歳。既に退職しています。
私にはSLと言うより蒸気機関車と言った方がなじみがあります。
また蒸気機関車を運転するのは運転手と言わず、機関士です。
機関車の中の機械類を見れば機関士と言う言葉はピッタリ。
40代の機関士と話をしていると「技術は伝承される」のが分かります。
今、騒がれているJR北海道の不祥事。
それは別のモノのように思えてきて、複雑な気持になってしまいます。
人たらし
昨日は「人の弱みにつけ込む」について書きました。
一見、良くないことのように思える言葉でも、考え方で違う。
そのような言葉として今日は「人たらし」について書きます。
「人たらし」と言うと「女たらし」と言う言葉も思い浮かべます。
「たらし」とは「だます」という意味なので、「人をだます」「女をだます」となります。
「人たらし」で有名なのは豊臣秀吉です。
「人をたらす」ためには、相手の気持ちを察知し、汲み取り、先回りしてして欲しいことをして上げる。
女性を口説くのも同じでしょう。(私は苦手ですが)
でも、この「人たらし」「女たらし」の手法が上手く身に付いていれば素晴らしいサービスマンになれます。
自然にその行為が出来るのであれば素晴らしいです。
たとえ計算ずくでも、お客様が喜ぶことを常に考え先回りをしてして差し上げる。
そこには感動が生まれます。
秀吉がまだ藤吉郎の時、信長の草履を懐に入れ温め、信長を驚かしたように。
「人たらし」はサービスマンにとって大事な「心得」ではないでしょうか。
皆さんも「人たらし」を目指しませんか?
人の弱みにつけ込む
ある本にオムロン創業者である立石一真さんの言葉が紹介されていました。
商売のポイントは「人の弱みにつけ込む」
「人の弱みにつけ込む」というのはゆすり・たかりのように悪いイメージですが、「世の中の要望に応える考え」と捉えると人を幸せにすることになります。
きれいになりたい、痩せたいと思う女性の「弱みにつけ込んで」化粧品、機能食品、洋服やアクセサリーが売られます。
美味しいものを食べたい飲みたいという「弱みにつけ込んで」グルメ番組があります。
身の回りにある「人の弱みを見付ける」という観点から、新しい企画が生まれるかもしれません。
「人の弱みを見付ける」というテーマでブレーンストーミングすると面白い話しが出てきそうですね。
リーンスタートアップ
先日「リーンスタートアップ」のセミナーに出席してきました。
「リーンスタートアップ」という言葉を知らなかったので、興味を持って行きました。
講師は「リーンスタートアップジャパン」の和波氏です。
「リーンスタートアップ」の「リーン」とは無駄が無く効率的という意味で、効率の良い起業や新規事業のための方法を探し出し、実行することです。
このセミナーで講師が特に強調していたポイントは「売り先が決まってからお金をつぎ込む」ことです。
買ってくれる人がどれほどいるか、十分な調査をしないで、売れるだろうという思い込みで製品を作ったり、仕入れをする。
しかしそれでは実際は売れず失敗ということが多いのです。
この事は「リーンスタートアップ」に限らず、昔から言われてきたことです。
特に小規模で起業する場合などは、資金が乏しいわけですからこの原則を踏まえなければ、失敗の可能性が大きくなります。
必要なことは十分な調査です。
ただ、成功の可能性が8割9割あるかまで詰ることは不可能です。
6割程度の見込みを付けることです。
その為に和波氏は「フィード・バック・ループ」の必要性を強調します。
「フィード・バック・ループ」は「原因⇔結果」の検討を繰り返すことで、結果が増幅されていくことです。
「PDCAサイクル」や「仮説・検証」に似ています。
どの方法をとるにしても、検証を行った上で、最適な部分に資金を効率的に投資する。
起業の原則です。
このセミナーは「リーンスタートアップ」を勉強するいい機会をいただきました。
近い内に「リーンスタートアップ」に関する本読んでみます。
善因善果
先週の12日、稲盛和夫さんの講演のお手伝いのため函館に行ってきました。
講演開始1時間30分前の14時に受付を開始しましたが、既に多くの人が並んでいました。
約1300名収容の会場は満席。
私の会場内での仕事は、入場された人を前方から詰めて順に座ってもらうように案内する係です。
お願いしても勝手に好きなところに座る人もいましたが、多くの人は指示に従ってくれました。
講演の演題は「人は何のために生きるか」です。
今まで何回も聞いてきた内容ですが、改めて気付かされる事がありました。
その中でも「人生は運命と因果の法則で形成されている」という話は改めて心に残りました。
因果とは因果応報のことです。
良きことを行えば良き結果が起き、悪いことを行えば悪い結果が起きる。
「善因善果」「悪因悪果」です。
人生は運命を縦糸とすれば、因果の法則は横糸となり、人生という布は織り上げられていきます。
良き人生であったかどうかは、運命より因果という横糸がいかに多く織られていたかによって決まります。
「善因善果」心したいと思います。
この講演の後は湯の川旅館で盛和塾の塾生が稲盛さんを囲んでの宴会がありました。
函館の美味しい食べ物・お酒を堪能しました。
そして翌朝は早くにお風呂に行って前夜のお酒を抜いていると、稲盛さんが入ってきました。
たまたま入っていた盛和塾の塾生2人も一緒になり、4人で暫くの間、風呂に浸かりながら稲盛さんとお話しをすることが出来ました。
良き思い出になりました。
函館市民フォーラム
明日は朝早くにバスに乗り函館に行きます。
函館で稲盛和夫さんの市民フォーラムが開かれます。
会場の函館市民会館の収容人数は1300名ほどですから、1000名以上の人が集まると思います。
主催は「盛和塾はこだて」で、私達は札幌からの応援・手伝いという名目で稲盛さんの話を聞きに行きます。
従来、稲盛さんの講演は盛和塾等限られたところで行われたいましたが、今回は函館市民の皆さんに向けてお話しします。
「人は何のために生きるのか」という演題の予定です。
稲盛さんは今年の春にJAL再建の仕事を終え、それ以降の仕事として日本各地で市民フォーラムを開いています。
明日の講演を手伝いに行く札幌からの人は総勢60名以上になりそうです。
稲盛さんのお話を聞いて、また新しい刺激を受けて来ます。
バリアアリー
先週の新聞の記事に、「バリアアリ―」という言葉がありました。
「バリアフリー」ではなく、あえて「バリア」を作るということです。
それの発信元は作業療法士で「社会福祉法人ゆめのみずうみ村」の理事長を務める藤原茂さんです。
今までの介護施設は「バリアフリー」が当り前です。
そこでは入居者は「上げ膳据え膳」の生活に慣れ、生活能力が衰えていきます。
手厚い介護が逆に生活力を奪う結果になっています。
藤原さんの施設では廊下に手すりは無く段差も多い。
利用者は家具などにつかまりながら歩きます。
昼食時は足の不自由な人ですら歩いて自分の料理を運びます。
私は以前から「バリアフリー」推進には少し疑問を持っていました。
ですからこの記事を見た時「我が意を得たり」と思いました。
「過度の優しさは人を弱くする」と考えます。
坂道の多い街の年寄は長生きの人が多いと言われます。
普段の生活で足腰が鍛えられるからだと言います。
福祉国家の北欧の町並みはアスファルトの所ばかりでなく石畳で足元がおぼつかない道もあります。
古い建物も入り口の段差が高く、入るのが大変です。
それでもバリアフリーにしません。
人にはある程度の負荷が必要です。
そしてストレスも必要と言われます。
ボケないために。
そのために何かに挑戦しようという気持ちも生まれて来ます。
私、英語の勉強始めました。
オリンピック
日曜日の朝からいい気持ちです。
勿論オリンピック開催が東京で決ったためです。
ただ今日は新聞が休刊日。これは少し淋しい。
日本はこれから景気が良くなるでしょう。
まだ開かれていない株式市場の動向も気になります。
景気というと経済成長の事を思いますが、ウィキペディアの説明では「昔は景色・雰囲気などの意味合いを込めて使われてきた。」とあります。
その意味でも、このオリンピック東京開催というニュースは人の気持ちを明るく前向きにしていくはずです。
以前の東京オリンピックの時、私は小学生。
7年後は70歳を越しています。
長い年月を感じます。
札幌でもサッカーの試合があるそうです。
楽しみが増えました。
お母さん
昨日も書きましたが、私は毎週「週刊朝日」を買っています。
いつもは週刊誌はほとんど買わないのですが、3週間前から稲盛和夫さんの対談が連載されています。
12回続くとのことですからしばらく買い続けます。
ところで今週の対談の中で意外なことが書かれていました。
稲盛さんは1日に4回・5回ほど「お母さん」という言葉が口から出てくると言います。
「しんどい時も『お母さん』、嬉しい時も『お母さん』。良きにつけ、悪しきにつけ『お母さん』という言葉が出て来ます」と言っています。
お母さんに助けて欲しいという気持ちではないそうです。
「お母さん」という言葉と「神様」という言葉と似た気持で言っているようです。
経営者として尊敬され、人格的にも多くの人から慕われている稲盛さんが「お母さん」という言葉を毎日口にしている。
それは驚きと共に納得させられることでした。
私の両親は3年前父、2年前母が亡くなりました。
時々私も「お父さん、お母さん」と何かにつけ口から出て来ます。
寝る時も布団の中に入ってから1日を振り返り、「お父さん、お母さん、ありがとう」と口から出て来ます。
明後日の日曜日は母の3回忌です。
週刊誌の稲盛さんのお話はとてもいいタイミングでした。
改めて父・母を思っています。
一工夫(ひとくふう)
昨日週刊朝日に目を通していると、内館牧子さんのエッセイが載っていました。
「おむすびコロリン」という題名で新幹線に乗った時の出来事ついて書いています。
内館さんとは通路を挟んだ隣の席に70歳代の夫婦が座っていました。
その夫婦は昼食におにぎりを食べようと袋から取り出し、おにぎりを包んでいるセロファンをはがそうとしています。
苦労していましたが上手くはがせず、とうとうおにぎりは床の落ちてコロコロ。
思い余って内館さんが開け方を教え上げたそうです。
内館さんは同じようなことを以前にも経験していました。
知人がサンドウィッチの包装を開けるに苦労していましたが、それも真ん中にあるのテープを引っ張ると簡単に開けれるのを教えられビックリ。
一般的には普通に広まっている便利な工夫も、知らなければ意味をなさないのです。
老眼の目にも分かる大きな文字表示も必要でしょう。
世の中にはもう少し工夫してほしいと思うことがあります。
例えば力のない人にとっては、ペットボトルのキャップを回すのも大変です。
キャップの形状を蝶ネジのように羽根を付ければ開けやすいと思うのですが。
なぜ無いのでしょう?
誰か作ってみませんか?
幸せ探し
今テレビを付けると、福島原発の汚染水問題が映し出されます。
これは大変深刻な問題です。
誰の責任というより、即刻処理しなければならない問題です。
その他に取上げられているのは消費税問題。
またTPP交渉のニュースもあります。
それらは大変重要な問題です。
それを分かった上の話ですが、あまりそればかり見ていると心の中に怒りや不安が生まれて来ます。
心に怒りや不安だけを生む話を聞くと気持ちがおかしくなります。
テレビで繰り返し繰り返し同じようなニュースを流すと、私はテレビを消してしまいます。
現実問題を直視することは大切だとは分かっていても、心を乱すような問題は事実を知るだけでいいです。
仏陀は怒りは人の心を傷つける一番の原因と言っています。
人の心はストレスと楽しさのバランスの上に立っていると思います。
楽しさばかりでストレスがなければ心も身体も退化します。
バランスが大切。
そして今のこのような時代、人にとって大切なのは「幸せ探し」だと思っています。
自分の周りに起こっているイライラすることを気にするより、小さなことでも「嬉しい」「楽しい」と思える事柄を探していく。
その1つ1つを探していく内に「ありがたい」と思う感謝の気持ちが生まれます。
そして「ありがとう」と言う言葉が口から出て来ます。
私は、人の幸せの度合いは、どれだけ多く「ありがとう」を言うことだ思っています。
幸せはその数に比例します。
大変な時代だからこそ、自分を大切にすることが重要。
意識して自分の周りで「幸せ探し」をしてみてください。
沢山出て来ますよ。
根本
今日と明日は琴似神社のお祭です。
今日は宵宮、明日が本祭り。
明日は私も神輿行列に連なる予定です。
琴似神社には太くて大きな銀杏の木があります。
秋には沢山の実を成らせます。
この銀杏の木は根がしっかり張っています。
それゆえ長い間風雪に耐えています。
目に見えない多くの部分を地中に隠してるのが木の「根本」です。
そんな銀杏の木を見て、自分に置き換えてみました。
見栄えばかりを気にしていないか。
人の評判を気にしていないか。
「いざ」という時の心の備えはあるか。
心を磨いているか。
大事なのはやはり「人の根」です。
表面的な現象を知るより、その元を学ぶ。
それは哲学、フィロソフィ―を学ぶことに繋がります。
そしてそれを実践して身に付く。
この違いで人の大きさが違ってくるのでしょう。
まだまだ勉強不足です。
聞く耳を持つ
ある本の中にあった文章です。
「主人に諫言する家来あれば家は治る。我儘をとどめて神妙に聞くがよい。我がことを人より良く言われる時は快いものだがそれは為にならない。へつらいだからだ。」
経営者の中には2代目3代目という人も多いでしょう。
私もその1人です。
2代目3代目は創業者の様な苦労は知りません。
だからどうしても判断が甘くなる時があります。
そんな時、番頭的な人が必要です。
私にもそのような人はいました。
私は元来素直?なほうですから、言われることは良く聞きました。
またその人は私心がない人でした。
自分にとって耳の痛いことを言ってくれる人をそばに置くかどうか。
それでその社長の器も変わってきます。
以前にも紹介しました佐高信氏の書いた「逆命利君」
上司の意向に反してでも、その上司のために働く。
そのような人は宝です。
あなたの傍にもその宝が埋もれているかもしれません。
見出してください。
働くお父さん
昨日次女が子供を連れて遊びに来ました。
長女も子供連れでお盆から遊びに来ています。
昨夜は孫が3人。賑やかでした。
娘達も孫達も元気で幸せそうです。
そんな娘や孫を見ていると、東京で働いている婿さん達のことを思ってしまいます。
家族のために一生懸命働くお父さん。
特に次女の婿さんはエレベーター点検の仕事をしています。
毎日契約先ビルのエレベーター機械室に入り点検作業をします。
ご存じのように、今年の東京の暑さはひどいものです。
エレベーター機械室の中はエアコンなどはなく、50度くらいの気温になり、その中での作業とのこと。
いつもは手弁当だそうですが、夏場は悪くなる可能性があり、弁当代をもらっているようです。
婿さんは好きのモノが買って食べれ、それが嬉しいらしいです。
何百円かの弁当を買って食べて、そして働く。
元気な孫達の顔を見ていると婿さんの顔が浮かんできます。
土曜日にその婿さんも札幌に来ます。
日曜日には彼が好きな焼肉屋に連れて行き、好きなだけ食べさせて上げようと思っています。
感謝感謝です。
一生懸命働くお父さんは素晴らしい!
権利の上に胡坐をかく
「権利の上に胡坐をかく」
昔に聞いた言葉です。
自分の権利は行使してこそ、その権利は守られるのです。
ただ権利だとそれを振り回しても行使しなければダメなのです。
その1例として。
昔、ある高利貸しが死んだので、その仕事を息子が継ぎました。
その息子はとても心が優しい人でした。
ある日、彼はお金を貸した人のところに行って、滞っているお金の返済を迫りました。
でも借りた人は「貧しく、食べるお金もない。もう少し待ってください」と土下座をしてお願いします。
そばには小さな子供。
心優しい息子は取り立てをせず、返せるまで待ってあげました。
そんなことをしている内に、借金の時効5年が過ぎてしまいました。
時効が過ぎて、息子はあわてて借手のところに行くと、借手は以前とは違い胸を張って「もう時効が過ぎたから返す必要はない」と言い張ります。
いくらお願いしても、結局お金は返してもらえませんでした。
返済してもらえる権利を正当に行使しなければその権利を失うということです。
権利の上に胡坐をかいてはいけないのです。
同じことが今の日本の中で起きています。
7月に行われた参院選の投票率は52・61%で戦後3番目の低さでした。
今月25日に投開票された横浜市長選は、29・05%という過去最低の投票率でした。
参院選では約5割、横浜市長選では約7割の人が自分の権利を放棄しているのです。
それでいて政治が悪いと言っても意味がないのです。
テレビなどが街頭で国民や市民の声を聞いていると、政治が悪いという人が多くいます。
その時、「あなたは選挙に行きましたか?」とぜひ聞いて欲しいものです。
選挙に行ってはじめて政治に対して文句が言えるのです。
極論ですが、国民の権利を放棄した人に政治に対し批判は出来ません。
如何に日本を良くしようと思って投票している人達と同等ではないのです。
これからの日本は政治的にも経済的にも益々混沌として行きます。
国民の権利を行使してこそ本当に自分が愛する日本になって行くのです。
「権利の上に胡坐をかかない」
今、大事なことです。
税金への関心
今、消費税を上げるかどうかで政府が専門家から話を聞く「集中点検会合」が行われています。
上げるにしても、上げないにしてもどちらもリスクがあります。
この消費税を別の面から見てみます。
日本の消費税は内税式になっていますが、外税の場合日本人には抵抗が大きいように思います。
それはモノの価格以外に余分にお金を払うことへの抵抗です。
ところが、チップを払うのが習慣の国にとっては、そのモノの価格以外に約1割程度のチップを支払います。
価格以外のお金を払うという点において、消費税を払う抵抗が少ないのかと私は勝手に思っています。
もう1つ。
スエーデンなどの北欧諸国は25%の消費税になっています。
大変高い消費税を払っているせいでしょうか、その税金の使い方に対する国民の関心は高いようです。
10年ほど前にスエーデンとフィンランドの福祉関連の施設を訪れた時に確認したことです。
税金の使い方への関心が高いのです。
国や自治体から支払われる補助金等が適正に使われているか、施設運営が正当に運営されているかを約10カ所の機関が徹底的にチェックします。
25%という重税感が、税金の使い道に対する関心を高くしているのかもしれません。
日本人は口では「税金の無駄使いを無くせ」と言いますが、それほど効果が出ていません。
このようなことを言うと叱られるのかも知れませんが、日本人の税金に対する重税感は比較的低いようです。
だから税金の使い方に対する関心度が低いのです。
今後消費税が高くなるとそれとともに、その使い方への国民の厳しい監視機運が高めて行かなければなりません。
私達の税金への関心を高めるよう意識を変えることが大切です。
ヤクルト宮本選手
昨夜、テレビでヤクルトの宮本選手の退団記者会見を見ました。
19年間の野球人生。
「悔いはない」という言葉と共に「野球を楽しいと思ったことは1度も無かった」という言葉が印象に残りました。
野球が好きで入った野球界。
しかし、宮本選手は1試合1試合真剣に、そしてストイックに取り組んできたその姿勢が見えて来ます。
それは修行僧のようなイチローの姿に繋がるモノがあります。
世界大会やオリンピックに出場する選手の中に「楽しんできます」という言葉に違和感を覚えていた私にとって、この宮本選手の言葉が心に響いてきました。
「何をやるにしても、やるからには真剣に!」
そんな生き方をしたいです。
経営資源
毎月に1度のペースで「競争戦略論」の勉強会をしています。
今月は私がスピーカーになり、「全社戦略」についての説明をしました。
その中で改めて納得したことがありました。
経営資源の活用についてです。
会社を経営する時、大切な経営資源は「人・モノ・カネ」です。
社長はこれを使って商売をします。
でもこの3つの経営資源は有限な資源です。
効率よく使わないと無くなってしまいます。
一方、別の経営資源もあります。
それは「技術・ブランド」です。
これはいくら使っても無くなるモノではありません。
会社がいくつかの事業を手掛けている時、その事業は同じ経営資源を使って商売をします。
有限な経営資源である「人・モノ・カネ」はその割り振りに苦労します。
しかし「技術やブランド」の様な、無限な経営資源はいくらでも使えます。
埋もれている技術も掘り起こしてみる必要があります。
各事業は同じ経営資源を使いながら、売上を上げる努力をします。
だからこそ事業体がそれそれ単独で運営されては効率が悪くなります。
事業体が互いに良き影響を与える「波及効果」がなければ会社全体の成長は期待できません。
「波及効果」はシナジーとも呼ばれますが、同じ経営資源を使っていることを再認識してその効果を高めること。
これは社長の仕事です。
この勉強会は次回で最終回です。
今後は学んだことをどう生かすか
この課題に進みます。
第3セクター
第3セクターというものがあります。
官・民合同で会社を経営することを意味します。
ちなみに第1セクターは官庁が経営する公会社。
民間会社は第2セクターと言われています。
先日の新聞に北海道庁が筆頭株主になっている航空会社北海道エアシステム(HAC)の記事が掲載されていました。
このHACも第3セクターです。
記事にはHACの再建問題で道庁がJALに株を譲渡し経営を移管したいと、自民党政治家を通して交渉しているとのことです。
HACは当初日本エアシステムと道庁の第3セクター方式で始められました。
当初から採算が合わない会社を無理やり作ったのです。
2004年にJASとの経営統合をしたJALが一旦はHACの経営も引き継いだのですが、2009年のJAL再建の時、赤字会社のHACを切り離したのです。
それをまたJALに押し付けようとしています。
第2セクター方式の民間会社と第1セクター第三セクタ―企業の官庁がらみの会社は経営に対する責任度が全く違います。
官庁がらみの会社は利益出さなくても責任を問われません。
民間会社は利益を出さなければなりません。
もっと極端に言うと、利益を出さない会社は存在理由がないから退場しなければなりません。
必要とされない会社だから売上が上がらないのです。
HACもそうです。
必要とされていれば売上も上がります。
また、もしかしてHACも完全に民間が経営していれば利益を出す会社だったのかもしれません。
官が入っている経営で成功した会社を私は知りません。
そして政・官は民を支援することがその立場です。
それなのに政・官がその権力で民の力を奪う。
論外です。
美輪さんの言葉
昨夜NHKの番組に美輪明宏さんが出ていました。
見た方も多いのかもしれませんね。
いつもは10時に寝るところ、30分ほど延ばして見ました。
美輪さんが話した中に、お腹にストンと落ちた言葉がありました。
「誰にも使命感があります。それを自覚できないのは、劣等感が邪魔しているからです。」
成程!
「謙虚」という言葉で誤魔化されている劣等感。
その劣等感によって、意味無く自信を無くしている。
勿論、虚栄を張る必要はありませんが、正しく自分を知ることは大切です。
そして自分の持っている能力を知ること。
自分の能力を自覚した時、自信を持って行動が起こせるのでしょう。
誰でも皆が持っている劣等感。
それを少し払しょくして、自分らしい生き方をする。
いい言葉をいただきました。
デフレからインフレへ
今の日本経済はまだデフレから脱却出来ないようです。
でもこれだけインフレ政策を政府が進めているのですから、いったんインフレ傾向が動き出したら止まらなく、極端なインフレになるのではないかと不安に思っています。
私が社会人になった時は高度成長で、インフレが当り前でした。
物価も上がりましたが給料も上がりました。
土地も上がるのが当り前。
それが15年ほど前からデフレ経済に入りました。
今の35歳以下の若い人にとってはデフレ経済が当り前。
デフレ経済下では給料は上がらないけれど、物価は安く、無理をしなくてもそこそこ生活出来る環境にあります。
一方、インフレ経済は頑張らないとドンドン後れをとって行く世界です。
厳しい世界です。
インフレだった高度成長時代には「モーレツ社員」ばかり。
今、デフレからそのインフレの世界に変わろうとしています。
それも過去に経験ないほどの急激な変化。
それが起きそうな予感がします。
デフレ経済に慣れた身体と思考。
ついて行けるでしょうか。
特に商売をしている人はその準備が必要です。
劇的変化がピンチになるか、チャンスになるか。
それはその備えによって違います。
その時、何が売れ、何が売れないのか。
在庫は増やすのか、減らすのか。
経営方針も守りに入るのか。
一旦は守りに入っても、何時攻めに入るのか。
社内教育によって社員の意識変換も必要になります。
今、必要なのはその準備。
変化がチャンスになるよう作戦を練っておきましょう!
自己管理
お盆も終り、昨日から仕事を再始動。
でも、なかなか以前の様なペースで仕事が出来ないと思っている人も少なくないでしょう。
無理をしないで頑張りましょう。
頑張って仕事をするというと、夜遅くまで仕事をする人は「頑張っている人」。
定時に帰る人は「頑張っていない人」。
そういう評価が私の若い頃にはありました。
今もまだそう見る人は多いようです。
でも夜遅くまで仕事をしても、そう能率が上がっているとは思いません。
朝早く起き、人より早く会社に来て、段取りを付け、効率的に仕事を進める。
そして定時に帰る。
これが理想的。
今朝の日経新聞の「春秋」の欄に「ゴー・ホーム・クイックリー」という言葉が紹介されていました。
50年ほど前にキャノンが提唱した社内運動で、出来るだけ早く仕事を終えて家に帰ろうというのです。
これは「マイホーム主義」でを推奨しているのではなく、自分で時間を自己管理し、懸命に働こうということを意味しています。
単に夜遅くまで仕事をする「ダラダラ仕事」は本人にとっても家族にとっても意味のないこと。
ビジネスでもプライベートでも時間を大切にしたいものです。
盆が終わり
お盆も終り今日から出社。
長い夏休みでした。
お盆にはご先祖様が帰ってきますが、子供や孫、妹たちも札幌に帰ってきました。
お盆はご先祖様が帰ってきて、「家族・兄弟が仲良くある素晴らしさ」を教えてくれているのでしょう。
本当に感謝です。
今日から残っている仕事をかたずけます。
運動不足のため、チョット膨らんだお腹。
少し節制もします。
品格
本屋に行くと時々品格とか品性という言葉が題名の本があります。
品性とか品格とは何でしょうか。
人柄とか清廉高尚な人格とか言うようです。
私の手元にある本に品格を作る「3つの柱」というものを紹介しています。
1柱:まだ不完全だと自覚から染み出る謙虚さ。
2柱:より以上のモノを目指して生きること。
3柱:人の役に立つ存在になること。
この1柱、2柱の言葉は私の祖母が言っていた「下を見て暮せ!上を見て励め!」の言葉に通じます。
小学校も行かなかった祖母が常に言っていた言葉。
身内ながら品格のあった人なのかと、今、改めて思っています。
今はお盆。
だからのでしょうか、祖母の言葉を改めて噛み締めています。
教えられていると思う
最近テレビで流れているある宣伝の文句が気に入っています。
「怒られていると思うか、教えられていると思うか、自分次第」です。
人は世の中に出れば働かなければなりません。
学生も世の中に出れば懸命に働かなければなりません。
仕事をするのに楽しさばかり追っても不可能なこと。
叱られながら、怒られながら仕事を覚えてゆきます。
特に職人の世界は「見て覚えれ!」とされ、間違えると怒鳴られるのが当り前。
私もそのような時代に生まれ育ち、社会に出ました。
しかし最近は大分違うようです。
打たれ弱い人が多くなったように思います。
大事に安全に真綿に包まれて育てられた人。
親にさえ怒られたことが無い人。
そんな人が世の中に出て、現実の厳しさに直面するのです。
教えられ、叱られても、それを怒られたと思う。
結果、「叱る人が悪い、怒る人が悪い」となってしまいます。
表面的な優しさばかりを求めています。
本当の優しさは厳しさの中にあります。
日本全体が過保護状態なのではと少し危惧しています。
事業計画書
旅行から帰って来ると、1週間分の新聞がたまっていました。
目を通すだけで結構の時間がかかりました。
私は記事と一緒に本の新刊広告も見ます。
その中でチョット気になった題名の本がありました。
「金融機関からお金を引っ張る事業計画書の作り方」と題されています。
中身を見ないで題名だけで判断するのも如何なものかとは思いつつ、「金融機関からお金を引っ張るため」という考えは間違えています。
事業計画書は見栄え良く作ろうとすればいくらでも作れます。
結果的にお金が借り入れたとしても、実際に事業を始めた時その事業計画通りにはいかないでしょう。
事業計画書を作る目的は、「何を」「誰に」「どのように」売るかを示しているモノです。
そして実際に計画達成可能な計画書でなければなりません。
事業計画書は銀行に提示するためののもではありません。
経営者が事業を進める時の指針になるモノです。
そこを間違えないようにしなければなりません。
イギリスから帰りました
イギリス旅行が終わり、7日の夜10時過ぎに家に着きました。
ロンドンのホテルを出てから24時間、ただただ疲れました。
今回の旅行は3女の結婚パーティに出席が目的でした。
また、旅行には私の兄弟達も参加してくれ、初めての兄弟姉妹の旅行にもなりました。
結婚パーティはイギリス本島の南側にあるワイト島で開かれました。
ここはリゾート地でヨットレースが行われ、ヨットがいっぱいです。
パーティ前日には婿さんの実家で行われた食事会。
その後80年以上前に作られたといわれる、オープンタイプのクラシックバスで島観光。
結婚パーティ当日は90人ほどが集まり、4時から始まり、終わったのは夜の2時頃。
イギリスの日照時間は長く、夜の8時過ぎまで太陽が出ています。
翌日は午前中に実家の庭で行われたガーデンパーティ。
婿さんのご両親の歓迎ぶりに、ただただ驚き感謝しました。
英語が不得意な私は十分にその感謝の気持ちを伝えられなかった事が残念です。
それにしても異国に新しい血縁が生まれるという事は嬉しいモノです。
世界が広がったような基がします。
忙しく、疲れた旅行でしたが全ての人と感謝の気持ちでいっぱいです。
追伸
イギリスには蚊がいないそうです。
野外でパーティをしたのですが全然虫の心配はありませんでした。
イギリスへ
まだまだ先だと思ったイギリス行きが今日から始まります。
今晩は千歳空港に前泊して、明日イギリスに向かいます。
ロンドンに2泊してからポーツマスまで行き、フェリーに乗り換えてワイト島へ。
3女の結婚パーティはワイト島にある婿さんの実家の庭で開かれます。
私はそこでスピーチをしなければならず、今、文案を練っています。
英語でスピーチ?
いえ、勿論日本語です。
通訳がいますので大丈夫です。
乾杯は日本から送った1合枡に日本酒を入れて乾杯する予定です。
旅行の準備は妻がしていますので、旅は妻任せです。
さてどんな旅になるか楽しみです。
途中のポーツマスにはネルソン提督が乗り、トラファルガーの海戦で戦った戦艦ビクトリーが保存されています。
今、私はビクトリーの模型を製作中です。
時間があれば見に行きたいと思っています。
「も」と「しか」
最近JR北海道の車両事故が増えています。
先日もNHKでその特集が放映されていました。
その中で気になった言葉があります。
取材したNHK記者の言葉です。
「エンジン付近から煙が発生するという事故は続いて起きました。同じような事故が2度目に起きた時、JR北海道の受け止める対応意識がおかしい。」
記者は同じような事故が「2度も起きた」と思ったのに対し、JR北海道側は「まだ2度しか起きていない」という意識なのです。
美白化粧品問題で揺れているカネボウも当初は小さなクレームがあったそうです。
その時カネボウは適切な対処をせず、そのクレームを軽く見ていたと言われています。
JR北海道も同じです。
仕事に流され、慣れと怠慢によって深刻な問題を見過ごす盲点がそこにあります。
これは経営者にとって「他山の石」です。
太田国土交通大臣がJR北海道に対して、JR東日本への保守点検の協力要請を検討するよう求めたと報道されています。
JR北海道は要請を表明したのでしょうか?
早く正常な運行を期待しています。
渦の中心で仕事をする
昨夜は勉強会がありました。
その中で「渦の中で仕事をする」について話し合いました。
自分が中心になって仕事を進めていく。
経営者は渦の中心になって仕事する人でなければなりません。
しかし、皆がそういう人ばかりでもありません。
良きパートナーとなって補佐することに長けている人もいます。
それでも自分のペースで仕事をするには、人のペースに流されては自分の仕事が出来ません。
やはり、小さくても自分の仕事の渦は自分で作らなければなりません。
自分で渦の中心になるために必要なことは段取りです。
段取りがしっかりしていると自分のペースで仕事が出来ます。
それが出来る1番いい方法があります。
早起きして、早く会社に行くことです。
9時始業なら7時に行って、その日の準備、段取り、メールチェック、情報収集などをします。
9時には既に臨戦態勢に入っているので、すぐに仕事の指示が出来ます。
9時ぎりぎりに出社する人はそういう人から指示を受け、その人のペースで仕事をするしかありません。
人の渦に巻き込まれる仕事しか出来ません。
早起きは「3文の得」以上の効果があります。
孫が生まれて
一昨日に5人目の孫が生まれました。
イギリスのロイヤルベビーと1日違いの男の子です。
母子とも健康だとのこと。
東京で生んだので札幌に連れて来てくれるのは正月頃かと思います。
子供が5人、孫が5人になると、益々この国の将来を考えてしまいます。
政治・経済ばかりでなく生活面の激変。
テレビや新聞の報道を見ると、人の心も変わってきたようです。
「モノは足りて、心欠ける」
そんな気がします。
幸い私の周りは心温かい人達ばかりです。
この人達とともに、この国そして住む地域に対して、自分の出来る限りの貢献はしていかなければならないと改めて思っています。
ひらめき
昨日近くの本屋に行き、立ち読みしました。
立ち読みした本の中で、題名も著者もわからないのですが、「クリエイティブ・ジャンプ」と言葉がありました。
その意味は「ひらめき」という意味の様です。
インターネットで見るとそのための講座もあるようです。
でもこの「ひらめき」は学んで得るものでしょうか?
これは生き方に関わっているように思います。
また、「ひらめき」と「思いつき」は似ているようですが違います。
ある問題に長い間取り組んで思考の錯誤の中で「ハッ」と得れるモノ。
その状況があまりにも急に来るので「ジャンプ」と言われるのでしょう。
真剣に取り組む中で生まれるものです。
「決してあきらめない!」「ネバーギブアップ!」の中でしか生まれません。
私も自分の人生の中でそのような経験あっただろうかと考えてしまいます。
一方「思いつき」は日常生活を送っている内によく浮かびます。
チョットしたアイディアはこれに当たります。
「思いつき」は刹那的なところがあります。
画期的な「モノ」に結び付くことはほとんどないでしょう。
何かに挑戦し、悩み、苦しむことで得れる「ひらめく」。
経験したいものです。
口の上手い人
ある会議でのこと。
1つの議題について話し合いをしている時、久しぶりに参加した人が発言をしました。
その発言は明快で、言葉も心地よく、いい意見だなと思いました。
参加者からも「流石ですね」とおほめの言葉。
私も初めはそう思ったのですが、しかし話の内容を良く思い返してみると、具体的な論点がぼやかされ、発言した人が何をしたいのか、自分は何をするのかが抜けているのです。
問題点と方向性しか話していないのです。
問題点と、方向性は誰でも分かっていました。
それを美辞麗句を使い、話すことで素晴らしい話しをしたように思えてしまう。
具体的に何をしなければならないのか、自分もどう参加するのかを言う必要があります。
人は様々な人がいます。
口先の上手い人もいます。
本人は意識していないのかもしれませんが、上手い話し方が出来て、その人の意見に惑わされてしまいます。
参議院選挙も終わりました。
当選した議員さんも口先だけの人だったのか、しっかり見てゆきたいと思います。
3つの力
週は17日から上京していました。
盛和塾世界大会に参加するためです。
盛和塾とは稲盛和夫さんが主宰する経営者の勉強会で中国・台湾・アメリカ・ブラジルそして日本に8300名の会員がいます。
今回の大会は4300名ほどの参加者があり、2日間にわたって、8人の経営者の経営体験発表が行われました。
最終日の最後には稲盛さんからの講話。
今回の演題は「経営の12カ条」です。
そのなかで「経営で大事な3つの力」についても教えてくれました。
1つは経営者が持っている力。
経営者としての力。
それは「経営の12カ条」を実行していくことに繋がります。
2つ目は「良きパートナー」を得ること。
自分と同じ気持ちで経営してくれる人を得ることは大変重要だということ。
自分1人の力では限界があります。
例えば、ホンダには本田宗一郎氏と藤沢武夫氏、松下電器には松下幸之助氏と高橋荒太郎氏というパートナがいました。
パートナーは人生観、使命感が共鳴する人でなければなりません。
そして3つ目が「宇宙の力、自然の力受けることのできる能力」
運命を変える力です。
稲盛さんはJAL再生を進める上でこの力を感じたそうです。
心が手入れされれば人が変わり、人格が変わり、人相まで変わります。
幸運は作られるものです。
3つの力の内、1つ目は「自力」、後の2つは「他力」です。
やはり謙虚でなければならないのです。
この盛和塾の世界大会は毎年開かれます。
もしかすると来年の参加者が5000名を越すかもしれません。
今回の会場の横浜パシフィコは収容人数が5000名です。
他の会場があるのでしょうか。
チョット気になります。
ウソ
「ウソらしいウソはついてもいいが、誠らしいウソは許されない!」
ウソらしいウソは皆が笑えて楽しいものです。
しかし大事な時に誠らしいウソをつくと信用を失います。
時々この区別がつかない経営者がいます。
本人は冗談だと言っても許されません。
心したいものです。
もう1つ。
大風呂敷を広げて話す経営者がいます。
何でも大げさに言ってしまいます。
これも信用されません。
私が若い頃の銀行時代。
会議の中でA社の〇〇専務が話した内容が紹介されました。
途端に支店長から「〇〇専務の話すことは信用出来ない」と断言。
支店長は何回か〇〇専務と会い、話したことがあります。
そこで感じたモノがあったようです。
ウソとは言えないにしても、大げさに話す事はあるかもしれません。
時と場合を選ばないと社内でも社外でも信用を無くします。
建築業界
先日ある集まりでの話。
建築会社の社長に聞きました。
「いま、東日本を中心に建築関係の仕事が多いのに、人手が足りなく、見込んで輸入したコンパネが値崩れを起こしていると新聞に書いてあったけれど本当?」
社長の話では本当に人手が足りなくて困っているそうです。
熟練工と言われる人材ばかりでなく、人手も足りないそうです。
その大きな原因は、ここ数年の不況と併せ、公共工事が減少したことです。
そのため建築会社が淘汰され、人員も整理されました。
ここへ来て急に仕事が増えても、需要に追いついていけないのが現状です。
ただ、このような時こそ会社の格差が出てくるのかもしれません。
稲盛和夫さんの話です。
稲盛さんが経営する京セラも石油ショックなどの不況を経験して来ました。
稲盛さんはその都度、仕事が無くても人を辞めさせず耐えたのです。
その結果、景気が回復した時はすぐに臨戦体制に入れ、売上を伸ばすことが出来ました。
「人こそ財産」で、不景気は会社を成長させるステップだったのです。
ところが、景気が悪く売上・利益が少ないからと言ってすぐ人員カットした会社もありました。
そのような会社は景気が良くなっても人がいないので完全に出遅れてしまいます。
稲盛さんが常に言う「内部留保が重要だ」ということが、会社の「自力」の差として出て来ています。
今回の建築業界も同じ環境とは言えないにしても、人手不足と言われても、人材・人員が揃っている会社はあるのではないでしょうか。
その様な会社とそうでない会社との差がこれから出てくるのでしょう。
講座修了して
先日の9日火曜日は札幌市立大通高校での最終講義した。
4月から始まり、休みも挟みながら10講義。
この日はそれまでに作り上げた事業計画書の発表日です。
社会人の人達はしっかりパソコンで作成していました。
今まで一度も計画書らしきものを書いたことの無い人達でも書けています。
そして高校生も事業計画書の発表をしました。
高校生でも出来るのですね。
一緒に同伴していた教師の方もびっくりしていました。
今まで何回か「身の丈起業」に関する講座を持って来ました。
その度に人との出会いがありました。
講座を開いた時、私にとっての楽しみはこの出会いです。
講座の前日まで、毎回その準備は結構大変でした。
でもそれは私の勉強でもありました。
これから出来ることであれば、高校生・大学生の起業に関するお手伝いが出来ればと願っています。
北海道の時代
昨日の札幌は蒸し暑かったです。
夜になっても気温は下がらず、寝苦しく睡眠不足です。
「東京方面はこんなもんじゃない!」と言われる方も多いでしょうが、涼しい北海道にの気候に慣れた身体にはきついです。
以前東京のホテルの支配人をしている時、お中元時期には品物を持ちお客様に回りをしました。
その時の服装はホテルマンらしくということで、ダブルのスーツにネクタイをしていました。
回る私達もきつかったですが、今考えるとそんな暑苦しい格好で来られるお客様も嫌だったことでしょう。
北海道・札幌に戻って10年以上経ち、すっかり北海道の気候に合った身体に戻りました。
それにしても最近の異常と言われるほどの東京方面の気温の高さ。
私の周りにはその東京から移り住んで来る人が少なくありません。
その上、札幌は日本でもっとも地震が少ないと予想される地域です。
地震のリスクと暑さを逃れ北海道に来る人。
もしかすると企業も多くなるのではないでしょうか。
ここ数年北海道の人口が減少進んでいますが、もしかしたらそれが止まるのかもしれません。
これからは「北海道の時代」かも。
感謝したこと
先日妻と話したことです。
結婚して35年が過ぎ、子供が5人、孫は今月生まれる予定の者入れて5人。
2人が結婚したことで、この世に10人が生まれた。
生まれるべくして生まれた10人。
そのことだけで、私達2人が生まれ、育ち、結婚したことの意味があったのでしょう。
そのことに感謝してしまいました。
大人の責任
先週の土曜日、地下鉄に乗った時のことです。
10人位の中学生?が座席を占領したように座っていました。
通路や座席の上に大きな鞄を置き、足を大股に開いたり通路に足を投げ出しているのです。
私は無理やりその中に行き、「鞄をどけなさい!」と言って座りました。
しぶしぶ席を空けましたが、他は変わりません。
乗り込んで来る大人達は離れたところに立ち、誰も注意しません。
この中学生達はバスケットの選手のようです。
その場には責任者もリーダーらしき人もいません。
もう少し規律正しい行動があってもいいのかと思います。
昔から日本にはスポーツに「道」という言葉を使っています。
柔道、剣道、弓道。野球も野球道とも言います。
そこには技が上達するとともに、人としての生き方まで教えられます。
日経新聞の「私の履歴書」に、今は囲碁棋士の大竹英雄さんが書かれています。
小学校の時に囲碁の師匠の内弟子となり、成長していく姿が書かれています。
その師匠の家に暮らしても師匠からは囲碁の指導はありません。
それより礼儀、躾を厳しく教えられました。
何より「人作り」が大事であり最初だったのです。
「上手ければそれでいい!」という今の風潮とは違います。
子供に教える大人がいなくなりました。
我儘な子供がはびこるのは、やはり大人の責任です。
「優しいばかりでなく厳しさを!」
私はそう思ってしまいます。
弁護士
昨日知人の紹介で、その知人と若い弁護士さんとランチをしました。
その弁護士さんは30代の女性弁護士です。
東京生まれながら北海度に渡って来ました。
医者がいない無医村に医者が赴くように、弁護士がいないところに行こうと若い頃に志し、最初に遠軽に入ったそうです。
遠軽で頑張り、その後後輩にそこを譲り、4年前に私の住む札幌市西区琴似で弁護士事務所を開業しています。
彼女と話していて、読書の話しが出ました。
私の先入観で、「弁護士さんだから結構多くの本読むでしょう?」と聞くとあまり読まないとのことです。
「弁護士には読解力が必要でしょう?」と聞くと、弁護士には国語力より数学的発想が大切だと言います。
弁護を有利に進めるためには、論理的・数学的組み合わせで、事実と法律を積み上げていく作業が必要だそうです。
国語力より数学的論理。
法律や判例も全て記憶する必要はなく、必要な時に見ればいいのです。
話は聞いてみないと分からないものです。
女性弁護士ですから持ち込まれる相談はやはり夫婦問題が多いそうです。
それでも、地元に密着した活動をしたいということで、私の周りにいる起業家への協力も受けていただきました。
新しい出会いに感謝です。
高校生起業
以前にも紹介しましたが、私は現在週1回程度、札幌市立大通高校で講座を持っています。
社会人と高校生の合同講座です。
講座名は「身の丈起業のススメ」ということで、最終的に各自に事業計画書を作成し発表してもらいます。
先日の2日はその事業計画書の最終作成日でした。
「自分の好きなこと」と「過去の自分の経験」を組み合わせて起業する事業を決めるのです。
事業決めの時は、社会人、高校生でブレーンストーミングしながらアイディアやヒントを出し合いました。
その結果、面白い事業が出て来ました。
特に高校生が考えた事業はユニークです。
ここに書いて皆さんに教えれば「成程、それはいい!」と言っていただけると思います。
でも今は秘密です。
昨日来社された起業支援しているコンサルタントの方に話すと、その事業内容に賛同を得ました。
「実行に移す時はお手伝いしますよ」とまで言われました。
来週の9日はこの講座の最終講になります。
事業計画を各自から発表してもらいます。
「高校生でも事業計画書が書ける!」
次回は楽しみであり、少し名残惜しい気持ちです。
日本語
つくづく思うのですが、日本語の表現は美しいです。
好きだという表現に、愛するとか愛(いと)しいがあります。
美しいには端正、涼やか、眉目秀麗、見目麗し等があります。
花が散る様子も違います。
桜は「散る」ですが、椿は「落ちる」、梅は「こぼれる」と表現します。
先日テレビを見ていると若い女性が、「ヤバイ」とか「クソ」という言葉を使っています。
美味しいものを食べても「クソ、ヤバイ」と使います。
本来まずいことが起きた時に使う言葉です。
語彙不足なのでしょう。
日本人なのに日本語を使えなくなってきています。
時折、若い経営者でも若者言葉を使っています。
若いから許されると思っているのでしょうが、仕事上は許されません。
社長ともなれば対外的責任を持った行動と言葉を使わなければなりません。
また社内においても、色々な表現を使って話をするよう努めなければ、説得力が生まれません。
社長にとって必要なのは表現力・発信力です。
その勉強にいいのは本を読むことではないでしょうか。
数多くなくてもいいから読むことです。
時には詩集や短歌・俳句もいいですね。
めいげんそ言葉
「めいげんそ」言葉というのをご存じでしょうか?
「明元素」と書きます。
最近、久しぶりにネット上で目にしました。
この言葉はヒューマンウェア研究所の清水英雄さんという方が提唱している言葉です。
「めいげんそ」言葉には
「充実している ●簡単だ ●できる●楽だ ●金がある ●まだ若い●可能だ ●努力します ●試みた●幸せだ ●元気だ ●楽しい●きれいだ ●素晴らしい ●やれる●イケる ●おいしい ●美しい●すてきだ ●やってみよう ●おもしろい●利口だ ●頑張ります」
これを声に出すと元気になれます。
反対の言葉は「あんびょうたん(暗病反)」言葉です。
「忙しい ●疲れた ●難しい●つまらない ●できない ●いやだ●困難だ ●だめだ ●金がない●まずい ●もう年だ ●きたない●どうしょう ●バカだ ●不幸だ●大変だ ●マイッタ ●困った●苦しい ●つらい ●失敗した●やりたくない ●分かりません」
私がこの言葉に出合ったのは20年近く前だったと思います。
この「めいげんそ」言葉を書いた紙を自宅の居間に貼っておくと、子供たちが暇さえあれば声を出して唱えていました。
勿論、声に出したのは「あんびょたん」言葉でなく「めいげんそ」言葉です。
「あんびょうたん」言葉を口に出すとダメです。
引き寄せの法則でそれを引き寄せてしまいます。
「めいげんそ」言葉を口にしていた子供達は唱えている内に、独特のメロディーまで付けていました。
毎日「めいげんそ」言葉を口にしていた子供達はお陰様で元気で明るい子に育ちました。
だまされたと思って、1度皆さんも声に出して唱えてみませんか?
元気になれますよ
納税
私の会社㈱ヤマチオフィスの決算は4月で、税務申告は6月末です。
先週に申告を終え、今日納税します。
税金を納める時、それほどの額ではないにしろ、支出は支出です。
少ないけれど「この税金しっかり使ってくれよ」と思います。
稲盛さんは税金も経費として考えなさいと言います。
そうでなければ税金を節税と称してごまかそうと言う気持ちになってしまいます。
私は税金を日本国、北海道、札幌市に年に一度行う寄付行為と思っています。
日本国、北海道、札幌市のために寄付をしていると思うと、気持良くお金を出せます。
一生懸命仕事をして、利益を出し税金を納めることは、優れたボランティア活動と同じように、世の中の為になる行為です。
今日から我が社の新年度。
頑張って来年も税金を納めます。
札幌人図鑑
昨日「札幌人図鑑」を発行している福津さんが来社されました。
それまで私は「札幌人図鑑」についてよくわからなかったのですが、札幌で活躍している人にインタビューしてその様子を録画しネットで流している「メディア」です。
福津さんの話しでは、昨年の4月から始めて既に1年を越しているそうです。
毎日1名に取材し毎日発信し続けています。
年中休みなしです。
私は初めて福津さんにお会いしたのですが、きめ細やかな優しい応対と、毎日続けている粘り強い努力に感心しました。
最初は札幌で活躍している人を紹介するという、ただそれだけの目的で始めたそうです。
その人数は既に365名を超え500名に向かっています。
1000名が1つの区切りだそうです。
起業家が成功するためには「素直」「真面目」「一生懸命努力する」の3つが大事な要素です。
福津さんを見ていると、成功する起業家の姿が見えてきます。
人は努力する過程で、1つの区切りごとに見える風景が違ってきます。
段階が上がれば上がるほど違ってきます。
福津さんの1000名のインタビュ―が終わった時、福津さんにはどのような風景が見えるか、その時にまた聞いてみたいものです。
参考:札幌人図鑑 http://sapporojinzukan.saplog.com/
心の立つ位置を変える
仕事をしていると、人との間に摩擦・軋轢が生じます。
その時、それから逃げる人と、それにぶつかって行く人がいます。
逃げる人はいつも及び腰です。
ぶつかって行く人は体力を消耗してしまいます。
よりいいのは、それを避けながらその中に進んで行くことでしょうか。
その中に進んで行くと一致点が見い出せます。
その方法としては、真正面からばかりでなく、横からとか上から見すことです。
視点が変われば見方も考えも変わることが出来ます。
「視点が変われば見方も変わる」事の1つとして「過去」があります。
人は「過去は変えられないけれど将来はどのようにでもなる」と言います。
私もそう思っていました。
でも、「過去」も変えることが出来るのではないかと思います。
過去に起きた事実は勿論変えれませんが、それが辛いとか悲しい出来事が、見方を変えれば今の自分を作り上げた大事な起点だったのかもしれません。
そう思うと、辛かったり悲しかった過去の出来事が全て「ありがたい」と思えるようになります。
いつも一方方向からばかり見るのではなく、立つ位置を変えてみる。
心の立つ位置を変えてみる。
時々やって見ると気持が楽になりますよ。
おせっかい
昨日の日経新聞の生活面に「世話焼きおばさん 頑張る」と題した記事が載っていました。
昔近所に良く居た「世話焼きおばさん」はもういないのかなと思ったのですが、しっかり頑張っているようです。
お見合い相手を探すばかりでなく、高齢者や障がい者のお手伝いをしています。
日帰りツアーを企画し、参加者を募り、仲間作りのお手伝いをしたり、地元役所と協力して婚活ツアーに同行したり、地域の助け合い関係を深めようとイベントを企画したりしています。
この記事には「おせっかいのコツ」というのが紹介されています。
1.出し惜しみせず全力を尽くし、周りの人を楽しませる。
2.誰にでも出来ることを、誰にも出来ないくらい心をこめてやってみる。
3.ためらうよりもまず行動。声をかけ手を差し伸べる。
4.見返りを求めない。喜んでもらいたいからやるだけ。
5.迷惑がられても悩まない。気に入ってもらえなかった理由を考え、次に生かす。
6.思いを手紙に。相手を思う気持ちが行間から伝わる。
7.地位や立場、年齢などで垣根を作らず、笑顔で接する。
8.おせっかいには自分の子供にではなく、地域や社会に。
この中で2つ目の「誰にでも出来ることを誰にも出来ないくらい心をこめてやってみる」が気に入っています。
私も将来は「おせっかい爺さん」になろうかと思います。
この記事の最後に「『利己』を求めてゆき過ぎた孤独の時代が、『利他』の方向に揺り戻される。その象徴が『世話焼き』『おせっかい』なのかもしれない」と書いてあります。
考えさせられました。
欠点
人が何かに挑戦しようとする時、やる気満々の人とそうでない人がいます。
やる気の無い人は自信が無いと言います。
経験が無い、お金が無い、ネットワークが無い等、無いことを並べます。
松下幸之助さんがいいことを言っていました。
「私には3つの財産がある。それは『学校へ行かなかったこと』『健康にすぐれなかったこと』『決断に弱かったこと』
だから人が教えてくれたり、助けてくれたりしてくれた。」
小学校も満足に行けなく、生来身体が悪かった幸之助さん。
他の人にとっては欠点と思えることを自分にとってプラスに変換しています。
欠点を欠点と認め、そこから何が出来るか考える。
大事なことですね。
恥心
「恥心」という言葉をある本で見ました。
「自分の至らないことを恥じて精進すること」とあります。
私が幼い頃、よく母親に言われました。
「人前で恥ずかしいことをするでない!」と言われたものです。
子供の頃なので、他所の家に行ってお菓子が出されるとつい2個も3個も食べようとします。
フッと母親の方を見ると目で「ダメ」と言っています。
意地汚さを叱られました。
この「してはいけない」という思いが強くなりすぎると自己規制が強くなりますが、それでも「してはいけないことは」幼い頃に教えられないとダメです。
日本には「お天道様の下でまっとうに生きる」とか「人から後ろ指を指されないように」という言葉があります。
今の日本には、自分のことしか考えないという人も多くなりましたが、それでも多くの日本人は「恥心」を持っています。
日本人の優れた資質かなと思っています。
「みる」
テレビを見終わって気付くことがあります。
あれ!何を見ていたのか?
物忘れが激しくなったわけではありません。
漫然と「見て」いただけなのです。
日本語の「みる」には「見る」「観る」「診る」「看る」等があります。
普通は「見る」事が多いです。
自分で意識すると「観る」事が出来ます。
「観劇する」も注意して見ることです。
「観察」は「観る」の意味をよくあらわしています。
「大事なことを見落とした」という時は注意力散漫な時に起きます。
人は訓練によって失敗を防ぐことが出来ます。
それは「観る」訓練をすること。
意識を持って事に当たる。
「有意注意」になります。
「有意注意」の時は「観る」目を持たなければなりません。
これは人の上に立つ者の条件のように思います。
意欲
人は時に、何かの拍子で不幸が起き、名誉を無くしたり、お金が無くなったりします。
会社が倒産し、全てを失ってしまうかもしれません。
ところがこの「全て」というところが問題です。
他のモノは失っても、失っていけないモノがあります
それのは「意欲」です。
生きる意欲、頑張る意欲、再度挑戦する意欲。
「意欲」の中に「欲」という字があります。
何を無くしても「欲」を持ち続けること。
「欲」には高次元のモノも低次元のモノもあります。
たとえ低次元のモノでも、無いよりマシです。
生活していて、時折元気が無くなくなることはありませんか?、
その時自分の「欲」をチェックしてみます。
自分のしたいこと、成りたいもの、会いたい人、行きたいところ、食べたいもの。
自分の原動力となるような「欲」。
それを再チェックし、書き出してみましょう。
「欲」を無くすと、「運」にも気がつかず、「ツキ」にも見放されるかもしれませんよ。
上に立つ者の気概
G8サミットが終わったようです。
アベノミックスがおおむね評価されましたが、それと同時に財政の健全化を約束させられました。
日本政府は8月をめどに中期財政計画をまとめる予定で、具体的な歳出削減策などを提示する予定です。
今の日本の財政を見ると大変不安です。
現在47兆円の歳入に対して国債費(利払いや償還費用)は22兆円に達しています。
借金返済に歳入の約半分使われています。
今度の財政計画では、きれいごとの提案ではもう済まされません。
そして政治家は言わなければならないことは、たとえ国民に強いることであっても、発言していかねければなりません。
今、ネットやマスコミで有名人や政治家の失言に対してバッシングが発生しています。
人を貶めるような発言に対しては責められても仕方がありません。
しかし、政治家は日本の政治に対して重要だと思うことに対しては、国民におもねることなく発言しなければなりません。
会社経営もそうです。
社長は社長としての責任において会社経営しています。
会社を倒産させないように、辛いことでも、しなければならないことは社員に強いらなければなりません。
もしも「社員に好かれよう」と思た時点で社長失格です。
上に立つ者の気概が試される時です。
これから政治・経済環境において日本社会は厳しい現実を迎えそうに思います。
新製品開発
昨夜はある銀行が主催する外交ジャーナリストの手嶋龍一氏の講演がありました。
日本を取り巻く北東アジアの情勢を分かりやすく分析し、北海道の未来を語ってくれました。
丁寧な語り口で良く理解できました。
この講演で手嶋氏は北海道芦別市出身ということを知りました。
講演後に懇親会があり、次は私の隣に座った人のお話です。
札幌市西区にある警備会社の社長です。
警備の仕事も価格競争の大変だなど話したあと、ipadで面白い写真を見せてくれました。
それは「エレベーター専用Q命ボックス」というものです。
エレベーターの隅に置いておくスツールですが、その中に飲料水、缶入りパン、防寒シートが入っています。
でも1番のポイントはいざという時トイレになることです。
防災グッズ入り椅子でトイレにもなるのです。
エレベータはトラブル起こした時、建前上は自動的に最寄りの階で止まることになっていますが、実際は閉じこめられることが非常に多いそうです。
特に地震などの時は簡単に助けに来てくれません。
そこで何時間も閉じ込められていて困るのがトイレです。
その為の非常用トイレがこれです。
防寒シートで覆うことでプライバシーを確保
またこのトイレは閉鎖された空間で使うため、濃縮消臭剤と凝固剤が備え付けられています。
この商品はテレビ東京の「ワールドビジネスサテライト」の「トレンディーたまご」にも取上げられとのこと。
ある会社との共同開発をして発売中です。
「私のような小さな会社は生き延びる為に様々なことを考えなければいけない」と言いながら社長の表情は自信にあふれていました。
防犯カメラ
先週、私が運営するレンタルオフィス内に防犯カメラを設置しました。
オフィス内でトラブルが発生したからではなく、あくまでも防犯のためです。
たまたまオフィス内で起業している人がネットワークカメラを取り扱うようになり、応援の意味もあり設置してもらいました。
このネットワークカメラはインターネットを経由してパソコンでも、スマートフォンでも見ることが出来ます。
また、ハードディスクに録画が出来ます。
このカメラは色々な使い方が出来そうです。
家に設置しておけば、親が子供を残して外出しても、留守番をしている子供の様子がわかります。
また離れたところに暮らす、年老いた親の茶の間に設置していれば、万が一の時すぐに気付けます。
このカメラ、安いものだと設置費用も入れて35000円くらいから購入できます。
このようなカメラは以前は大変高いものでした。
安くなったので、今後いろいろ使い道を考え利用価値は高まると思います。
ただ逆に悪用されることもありますのでご注意を。
伝わる
昨日デザイン関連のセミナーに行ってきました。
「伝わるものづくり」という題名です。
この「伝わる」というのがミソです。
商品に力があれば、その良さはお客様に「伝わり」ます。
逆に力がなければ、「伝える」という行動を伴わないと売れません。
「伝わる」モノを作るための1つにデザインがあります。
「伝わる」モノ作りのために必要なことは
「面白いモノ」「楽しみながら作る」「販路がある」の3つになります。
そしてその前提となるのがやはり最初に明確なコンセプトを作ること。
このセミナーの講師は木全賢氏です。
色々な実績を積み重ねた方で、今回は「フォトラ」という商品撮影セットの開発の過程を例にしながら、具体的な商品開発手法を話してくれました。
この「フォトラ」という商品こそ「伝わる」商品で、ほとんど宣伝をせず、プレスリリースに載せただけで、新聞テレビで取り上げられました。
結果ネット直販だけだったのですが、6月よりヨドバシカメラで売られることになったそうです。
「伝わる」商品作り。
改めて自社商品を見てみると考えさせられます。
この「フォトラ」はデジカメできれいに写真を撮ることが出来る撮影セットです。
私も欲しいと思っています。
ご興味ありましたらHPをご覧になってください。
http://www.photola.co.jp/
ロックフェラー3世
ある本にロックフェラー3世の言葉が紹介されていました。
ロックフェラー家は石油で巨万の富を得た一族です。
その一族の中でロックフェラー3世は人格者と言われています。
親日家で中村天風さんに師事したそうです。
彼は屋敷は持たず、ニューヨークに建てたマンションに住み、手を上げればタクシーが止まるからと言って自家用車も持っていませんでした。
時計はお祖父さんからお下がりの精工舎の時計。
元々大金持ちなので、それなりの生活はしたでしょうが、社会に貢献したいという思いは強かったようです。
「私はただ、世の中の人が、私の事業を通じて幸せになってくれればそれでいいのです」と言っていました。
次のような言葉も残しています。
「幸福への道は、2つの簡単な原則に集約される。
1つ目は興味があり、自分が得意とするものを見つけること。
2つ目は、1つ目で見つけたものに、情熱と才能とエネルギー、もてるもののすべてを注ぎ込んで全力でそれにあたることである」
起業の心構えの言葉の様です。
ウソ
長年生きて来て、振り返るとお世話になった人、素敵な人、好きな人等は思い出しますが、嫌な人はと思うとあまり思い出しません。
居たと思うのですが、忘れてしまったのかもしれません。
人は生きていく時「あまり好きでないな」と思う人に会うと思います。
「気が合わないな」と思う人がいます。
きっと相手も同じように思っているはずです。
そんな時ウソを言うのです。
何かを言われた時、「ご助言ありがとうございます」とか「いいお話を聞かせていただきました」と言うのです。
本当は心にわだかまりがあっても言うのです。
ウソでもそう言うと相手の心は変わります。
また不思議なことに、ウソでも口に出して言うと、言っている自分も本当にそう思えるようになります。
自分も周りの人も幸せになるウソはドンドン言ってもいいのです。
「おべんちゃらを言っている」と言われてもいいのです。
私には高校時代からの友人が沢山います。
その中で大変な変わり者がいます。
独善的で、自己主張が強いので、あまり友人はいませんでした。
でも正義感は強いのです。
私も今だったら彼との間に一線を引いてしまうかもしれません。
でも高校時代、何かのキッカケで口をきくようになり、友人になりました。
全くタイプが違うと互いに認め合っているその友人から色々なことを学びました。
人と親しくなる環境は自分から作っていくもの。
時にはウソもいいです。
来月上京した時、彼と会うつもりです。
歳と共に冴えてきた彼の毒舌。
会うのが楽しみです。
報・連・相
昨夜は久しぶりに盛和塾の勉強会に参加してきました。
今回は「我が経営を語る」ということで2人の社長と会長の話。
2人とも稲盛和夫さんが提唱している「経営の12カ条」に則した経営をしています。
起業してから今までの体験を、良いこと悪いことも含め率直に話してくれました。
その話の中で2つ紹介します。
ある仕事をしている時、お客様の意向で途中設計変更が発生しました。
それに対して1人の社員が「その変更費用お客さんから取れるの?」と聞きました。
その時、その社長は「お金はお客さんから取るのもでなく、お客様から頂くものだ」と注意しました。
それと同時に、社長自身が日常業務の中でその社員にそのような意識を持たせていたということに気付き反省したそうです。
またもう1つ。
事業展開のために東京に社長自身が営業をかけている時、不在がちな札幌の社員との間に意識の齟齬が発生しました。
それまでは連帯意識があると思っていたつもりが、1人の社員を失う結果になってしまったのです。
その時に社長は悩んだそうです。
そして気付いたのは、今まで「報・連・相」の徹底を社員に求めていたが、社長自身が部下に対して「報・連・相」をしていなかったこと。
部下に対しては常に報告を求めているのに、部下に対して連絡・相談をしていない。
これは、自分に自信がある優秀な社長こそ陥りやすい穴です。
昨日の勉強会、本当に勉強になりました
経営者の仕事
1人で起業しても、業績が上がってくると従業員を雇います。
その従業員に効率よく仕事をしてもらうため、経営者は的確な指示を出します。
起業したばかりの時は、自分の手足となって働いてくれる人が必要です。
時には的確に指示が出来なく、遊んでいる従業員がいる会社もあります。
会社が成長するためには、経営者はいかに的確に指示をし、効率よく従業員に仕事をしてもらうか。
ここが第一の関門です。
次に、会社が成長し、人も増えてくると今度は自分の手足になる人間でなく、経営者と同じ頭を持つ人を育てなければなりません。
その為にどうするか。
今度は経営者は指示を出さないのです。
従業員自身に自分で考させます。
苦悩しながら自分の頭を絞り、考えを出させます。
そうしなければ、いつまでたっても指示待ち人間ばかりになってしまいます。
松下幸之助さんは新製品の試作の段階で、簡単にはOKを出さなかったそうです。
「これは少し大き過ぎるね」とか「少し重すぎるね」と言うだけでそれ以上の事は言わなかったそうです。
そして改良してきた試作品を見ても「しっくりこないね」等言うだけです。
その都度、担当者は試行錯誤を重ね、何回か繰り返した後で、幸之助さんから許可が出ます。
結果、開発担当者も、出来上がった製品を改めて見てみると、見た目も使い勝手もいい商品だと改めて納得したのです。
アップルのスティーブ・ジョブズも「ダメ出し」が徹底していたそうです。
具体的なことを言わないで、自分の頭で考えさせる。
それによって人を育てる。
根気が必要ですが、これも経営者の仕事です。
長所と短所
人には長所と短所があります。
子供が小さい頃は、親は子供の短所が気になり直そうとします。
本当は短所でないのに、短所だと思って直そうとすることもあります。
私が子供の頃、左利きの子供が、無理やり右利きにされようとしているのを見たことがあります。
その子はいつもイライラした子でした。
親が強制することで精神的に辛かったのでしょう。
左利きでも将来は素晴らしいサウスポー投手になったかもしれません。
短所と思うことが、実はその子の長所だということがあります。
先日小さい男の子が道路際の草むらのところに座り込んでジッと何かを見ていました。
アリ等の虫がいたのかもしれません。
その子のすぐ傍に母親らしき人が何も言わず黙って立っていて、その子がしているのを見ています。
そして子供の上に日傘で影を作って、暑さから守っています。
それを見て「いい光景だな」と思いました。
その子は将来ファーブルのような昆虫学者になるかもしれません
そのような親とは反対に、子供が歩いている時、何かに興味持っても無理やり引っ張って行く親もいます。
子供が興味持ったことを親の判断でその良し悪しを決めるより、我慢強く暫く見守る。
それも大事な教育でしょう。
また、子供が小さい頃は、その子の長所・短所は早い時期から決めつけない方がいいと思います。
短所と思われることが、実は長所となる事例が沢山あります。
長所が見つかればそれを伸ばして上げる。
長所が伸びることでその子が評価され、もしかしたらその子の短所は人間味としての評価に変わるかもしれません。
色メガネ
最近「飛蚊症(ひぶんしょう)」がひどくなっているような気がします。
飛蚊症とは、目の中の水晶体に浮遊物が出来、それがまるで蚊が飛んでいるように見えるところから「飛蚊症」と呼ばれています。
本を読んでいても、黒い浮遊物が文字と重なり見にくくなります。
私の「飛蚊症」の症状は40代の初め頃から始まりました。
眼科に行くと、加齢によると言われます。
また原因の1つに紫外線が影響しているそうです。
そこで、これ以上悪くならない為にもある決断をしました。
それはサングラスをかけることです。
日中天気がいい時はなるべくサングラスをかけるようにと、いつもスーツの胸ポケットに入れています。
ただ、普段から人相・風ぼうが悪い私がサングラスをかけると、「ヤクザみたい」と妻から言われます。
知人と会っても「ちょい悪親父」と言われます。
私も以前はスーツを着てサングラスをかけている人を見ると、「普通の人ではないな!」と見てしまいます。
それでも、そんな逆境にめげず、かけ続けようと思っています。
「色メガネをかけてモノを見る」という言葉があります。
偏見を持って人を見るという意味です。
今の私は色メガネ(サングラス)をかけているゆえに、色メガネで見られてしまいそうです。
でも人からどう思われようといいです。
サングラスかけ続けます!
予想を立てる
昨夜のサッカー、引き分けで日本のワールドカップ出場が決まりましたね。
良かった!!
試合前には「専門家」と言われる人が色々予想していました。
「勝ち」「負け」「引き分け」に分かれていました。
スポーツの試合は何が起こるか分からない。
結局「やってみなければわからない」のです。
また、ここ1~2週間に起きている日本の株の大暴落にも言えます。
「専門家」が予想していた以上の事が起きています。
これからの動きも予想されていますが、当たるか外れるか分かりません。
博打みたいものです。
では経営についてはどうでしょうか。
「上手く行くか、行かないか、やってみなければわからない!」では経営者失格です。
常に状況分析し、先読みし、仮説を立て検証し、慎重に進まなければいけません。
勿論、検証の結果、進む方向が決まれば敢然と進めていきます。
経営は博打ではありません。
時々「丸木橋を下駄を履いて走って渡る」ような無謀な経営者がいます。
経営者に必要なのは「ビビり」と言われるほどの慎重さだと思います。
魔法の言葉
今朝、ダイヤモンド社から出版された「心は変えられる」と言う本を読み終わりました。
この本には「自分、人、会社ー全員で成し遂げた『JAL再生』40のフィロソフィ」という副題がついています。
副題のように、JAL社員がJAL倒産した時から今までの環境の変化と、再生と共に成長した自分の心の変化が述べられています。
稲盛さんが語った言葉の紹介もされていますが、多くがJALの各部署で働く1人1人の言葉が紹介されています。
元気がもらえる本です。
この本の中に「利他のスイッチが入る魔法の言葉、『お手伝いしましょうか?』」というのがあります。
「お手伝いしましょうか?」は当り前の言葉ですが、改めて思うといい言葉です。
人を思いやる心、優しい心。
時には自分のことを差し置いて相手を助ける。
生活の中では勿論、会社の中でも「お手伝いしましょうか」と言う言葉から、「横のつながり」「連帯感」が生まれます。
「お手伝いしましょうか?」は住みやすい世界を作る「魔法の言葉」です。
襟を正す
私が仕事で履く靴は昔から紐式の靴です。
若い時は、その靴の紐を少し緩めにして履き易い様にしていました。
今は履く時は、靴紐をキリリと締めあげるようにして結びます。
脱ぐ時はその都度解きます。
靴を履くのに以前より時間はかかりますが、家を出る時の儀式のようなもので、「仕事に行くぞ」と言う気持ちにしてくれます。
実際に足元がしっかりしていると、歩き易く、大股で胸を張って歩けます。
締めるというと、ネクタイもあります。
夏場は暑くネクタイは辛いものです。
ただ、私はネクタイをしている時と、外している時とではやはり気持が違います。
外していると、少しオフ気分になり、心が緩みがちになります。
「襟を正す」と言う言葉があります。
「自己の乱れた衣服や姿勢を整える」と「態度を改め、気持を引き締める」の意味です。
暑い日は服装は緩みがちになりますが、心だけは襟を正す姿勢を持ちたいと思っています。
沈黙は金
イギリスの思想家トーマス・カーライルが言ったことわざに「沈黙は金なり、雄弁は銀なり」というのがあります。
雄弁より沈黙の方がいいのだという意味です。
「いや、そうでない。」と言う人もいます。
トーマス・カーライルの時代は金より銀の方が価値があったので、雄弁の方がいいという意味だと言う人もいます。
沈黙がいいか、雄弁がいいか。
会社の中を見回すと、よくしゃべる人と、無口な人がいます。
ところがいざ会議になると、なぜか皆無口になってしまいます。
雄弁なのは社長1人。
社長がしゃべり過ぎるので、部下が口をはさめないこともあります。
結局、社長の独演会で終わってしまいます。
会議では社長は沈黙を守り、雄弁に語る部下の意見を聞く。
会議で社長が第一に気を付けなければならない事です。
昔の私の反省を込めて書きました
3分の1ルール
今朝、NHKのニュースを見ていると、「フードロス」というテーマで話し合われていました。
その中で賞味期限の話しがありました。
食品製造会社では「3分の1ルール」というものがあるそうです。
例えば、あるジュース製造会社が賞味期限が6カ月のジュースを作っているとします。
製造後1カ月から6カ月のジュースが在庫としてある時、出荷するジュースは1カ月と2カ月のジュースだけで、後は全て廃棄されてしますそうです。
3分の2は捨てられるのです。
「もったいない!」と皆さん思われるでしょう。
工場が出荷しないで捨てる原因は消費者にあります。
賞味期限が少ないジュースは消費者が敬遠し、売れ行きが悪くなり、売れ残る可能性が高いのだそうです。
食品製造業界では「フードロス」を無くするため、「3分の1ルール」から「2分の1ルール」に変えていこうとしているいようです。
それにしても大量のモノが捨てられているのです。
まだ賞味期限がある食品を廃棄しないで有効利用する方法は無いでしょうか。
製造会社としては廃棄物の積極利用を図ると、正規に売っている商品の売上に影響が及び大胆に踏み込めないようです。
ただ現実には陰では有効利用し、重宝しているホテルやレストランはあります。
「こんな値段でよくバイキング料理が出来るな」と思うことがありますが、そこに結構使われています。
フォードロスを減らすには日本人の敏感な「きれい好き」から、本来日本人が持っている「もったいない」意識に変更させていくこと。
それとフードロスを商品化するシステム作りが必要です。
大規模にこのシステムが出来れば、「システム開発会社」「製造者」「消費者」が喜ぶ「3方良し」の他に日本食糧自給率アップになります。
もう挑戦している人もいるかもしれませんが、あなたも身近なところから挑戦しませんか?
何様
第一生命が募集した「サラリーマン川柳」が先日発表されました。
その第二位が『電話口 「何様ですか?」と 聞く新人』というのがありました。
本人は丁寧な言葉と思って使っているのです。
「貴様」という言葉もあります。
同等か目下の者に言う時は「キサマ」と呼び、喧嘩する時などにも使います。
でももう1つの意味があり、目上の者にいう時は「あなた様」となります。
だからと言って、手紙で「貴様」と書くと、「喧嘩売ってのか!」思われますので気を付けましょう。
誤解されやすい言葉で「情けは人のためならず」があります。
若い人は「その人のためにならないから、情けをかけない」と理解している人が多いようです。
本来とは全く逆の意味で理解しているのです。
だからなのでしょうか、そういう人は「ツイていない、ツイていない」いいます。
人のために何かをするから、回り回って自分に帰ってくるのです。
それをしなければツキも回ってきません。
こう言う私も、もしかすると自分が使っている言葉を間違えて理解していることがあるかもしれません。
気を付けます。
良いストーリー
皆さんは自分の将来に対してどの様に考えるでしょうか。
「良いストーリー」を考えるか、反対に「悪いストーリー」を考えるか。
私が知る限りでは、多くの人は「悪いストーリー」を考えがちです。
「良いストーリー」を考えても、万が一にも悪い方向に行った時のショックを和らげるために、自己防御のため予め悪く想定するようです。
でも不思議なことに「悪くなるかもしれない」と思うと、思う通りに悪くなってしまいます。
願いは叶うのです。
「悪いストーリー」が叶ってしまうのです。
「願いは叶う」ということが本当ならば、願いはやはり「良いストーリ」でなければなりません。
それでは「良いストーリー」を考える為にはどうするか。
常に口に出して「良いストーリー」を言うことです。
日常の生活の中でチョットした時、また弱気が出てきた時は口に出して言うのです。
何度も口に出している内に、自己暗示で自分もその気になってきます。
それともう1つ。
ワクワクする気持を持つこと。
「良いストーリ」が叶った時を夢見ることです。
ワクワクする時は「良いストーリー」を夢見ます。
この話、信じるか!信じないか!
それはあなた次第です。(どこかで聞いたセリフ)
Why思考
仕事をしている時、必ず予期せぬことが起きます。
その時、多くの人が「どうしよう。どうしたらいいの」と考えます。
そして次には「頑張ろう!」として努力します。
でも努力してもなかなか良くなりません。
なぜか。
その思考に欠けている工程は、「なぜ失敗したか」を検証することです。
学校の試験でいい点数が取れなかった時と同じです。
返却された答案用紙をチェックし、どこが間違えで、正解は何であったかということを確認しなければ、また同じ間違いを犯すのと同じです。
「なぜそうなったの?」というのがWhy思考。
「どうすればいいの?」というのがHow思考。
学校もビジネスも同じです。
愛妻弁当
札幌も桜が終わり、やっと春になってきました。
気温も少し上がり、建築や土木など外で仕事をする人も仕事の効率が上がっているようです。
寒い冬の札幌での外の作業は大変です。
冬に見る働く人の風景で一番印象に残るのは、お昼に車の中で1人黙々と愛妻弁当を食べている姿です。
寒い外での作業、少しの時間、温かい車の中で、保温された温かい愛妻弁当を食べてる姿を見ると、いつも「ウッ!」と熱いものがこみ上げて来ます。
一生懸命家族のために働くお父さん。
その後ろには家族がいて、そしてご主人のために美味しい弁当を作る奥さんの姿を想像してしまいます。
男にとって一番の幸せは家族のために一生懸命働くことです。
そして、そのお父さんに感謝する家族がいることが、全ての幸せの原点だと思います。
家族のために働くお父さん。
頑張れ!頑張れ!
売らない商売
今、日本はアベノミクスと言われ景気いい話しが出てきています。
それでも実体はまだデフレからは出そうにもありません。
相変わらず安売り競争です。
その中で「売らない商売」というものがあります。
強気の商売です。
京都祇園等には「一見(いちげん)さんお断り」というところがあります。
行きたいと思ってもお店の方から断られるのです。
いくらお金を積んでも紹介者が居なければ入店できません。
また、人気があり、いくら売れても量産しないというパン屋があったりします。
先日も北大の先生と話している時、北大近くの焼鳥屋の話が出ました。
予約しないと入れないし、予約も取りにくい店です。
決してきれいでもないし、狭く、メニューも塩味の美唄焼鳥だけです。
タレ味もなければ別メニューもありません
あるのは鶏ガラで取ったかけ蕎麦だけ。
焼き鳥は確かに美味いのです。
その店はほぼ毎日、8時頃になると焼き鳥が無くなります。
これほど流行っているのに店を広げようともしないし、焼き鳥の本数を増やそうともしません。
「限定」というところがいいのかもしれません。
北大の先生と、なぜこの焼鳥屋が流行るのか話しあったのですが良くわかりません。
ただ「売らない商売」は「限定」とか、「やり方を変えない」ことが魅力なのかもしれません。
焼き鳥の話しを書いたら、その焼鳥屋の焼鳥、食べたくなりました。
その焼鳥屋の名前知りたいですか?
残念ながら教えられません。
競争相手が増えてしまうので。
悪しからず。
美輪さんの言葉
美輪明宏さんの言葉で、「小さい頃、家が貧乏でひもじい中、苦労して努力してきたことはその人の財産になる」というのがあります。
今は苦しくても頑張って努力すればそれが財産となり、将来実を結ぶということを言っています。
確かに裕福な今の日本にも貧乏で苦しい人はいます。
励みになる言葉です。
でも一方、日本人の多くは生活に困らない生活をしています。
そのような苦労知らずに育った子供と貧乏で苦労して育った子供とでは生活力は違ってきます。
貧乏の中、苦労して頑張ってきた子供はその努力が財産となります。
それでは普通の家で苦労知らずに育った子供はどうしたらいいのでしょうか。
それは今の生活に感謝して生きることです。
苦労知らずに生活出来ているということは大変運がいいこと。
自分は運がいいことを自覚し感謝すれば自然と素直になります。
感謝と素直な心。これも大きな財産です。
生活する上で大切なことは、人は自分の生きている環境を否定しないで受け入れること。
そこから自分らしい生き方が始まるのではないでしょうか。
美輪さんの言葉を聞いてそう思いました。
新規事業
会社の社長はよく「新規事業を始めなければならない」と言います。
このことに異論をはさむ人はほとんどいません。
でも実際に新規事業に着手し、実行する社長はどれほどいるでしょうか。
私の周りでは多くの社長が口で言うだけで、実行しません。
そして特に経営に自信があり、経営数字に敏感な社長は特にその傾向が強いようです。
そういう社長は新規事業を考える時、数字が先に立ってしまします。
でも最初から数字で考えると否定した方向に行ってしまいます。
本来はまず何がしたいのか、将来会社がどうあるべきか、その夢を膨らませる。
そしてその為に何をするか。
これを押さえてから具体的計画段階の時、夢を数字に置き換えて再検討をし、ネック部分を取り除く。
それで新規事業が始まります。
それが最初から「儲かるか儲からないか」。数字だけで考えるとそこで止まってしまいます。
挑戦しようという気持ちもわきません。
良くあるパターン。
社長は部下に新規事業を考えろと言います。
部下が一生懸命頑張ってアクセルをふかしているのに、横にいる社長がブレーキを踏み続けている状態。
結局いつまでたっても新規事業は始まりません。
業績が悪くなって、あわてて「新規事業を」と言っても、もう間に合いません。
結局、新規事業を始めることが出来るか出来ないかは、優秀な部下が居るか居ないかではなく、するという決断が出来る社長が居るか居ないかで決まってしまいます。
白黒
先日あるお母さんが子育てのお話しをしていました。
お話しの大筋は、「正しいこと、悪いことをしっかり教えて来た」とのことです。
子供の内から、正しいこと悪いことを教えるのはとても大事です。
人としての基本になるところです。
ただ、それと同時にお話しを聞いていると少し不安になるところもありました。
世の中では正しいこと悪いこと以外にも選択肢があるのです。
「善悪で判断できないこともある」ということを教えなければ、子供が社会に出た時、苦労しそうな気がしました。
私もそうですが、人は概して物事の判断に「白黒」をつけたがる傾向があります。
極端に分かれます。
でも、世の中は白黒以外のグレーの部分が多く、そのところの判断が出来なくて困ることがあります。
例えば人間的にぐ優れて、仕事もしっかりしている人が、間違えて事故を起こしてしまうと、今までの評価が手のひらを返したように変わってしまいます。
その人を不適格者としか見なくなります。
確かに間違いは犯したけれど、止む得ない事情があっても善悪でしか見ないのです。
会社のトップに立つ時、このグレー部分の判断が的確に出来るようにならないと、従業員も成長しないし、会社も大きくなりません。
清濁併せ呑む、度量の広い人はこのグレー部分の許容範囲の広い人のことです。
子供には、善悪の判断基準をしっかり教えることと同時に、世の中にはそれ以外のグレー部分が多いということも合わせて教えていかなければならないでしょう。
3つの「ち」
昨夜は月に1回開く「身丈会」の勉強会がありました。
その勉強会で、ある参加者から教えられた言葉です。
「3つのち」
両親や家系から流れる「血」
生まれ育った場所、そこの習慣から流れ込んでいる「地」
時代から流れ込む価値観の「知」
この「3つのち」によって人間1人1人違っていて、個性があるのです。
互いの違いを認識し、共生することが大事だと言っているのでしょう。
ネットを見ているともう1つ別の「3つのち」が紹介されていました。
作家の山口瞳さんが言ったとされています。
人には、「知性」「稚性」「痴性」の3つの「ち性」が必要であると言うのです。
人としての持っていなければならない教養や知識等の「知性」
子供心を持つ、愛嬌ある無邪気さの「稚性」
見栄を張らず、自分の表も裏も見せることが出来る「痴性」
この「3つのち性」を持つと、人間としての幅も広がるし、あるがままに、そして素直に生きていけそうです。
自分に甘く
ある本に書いていたことです。
お父さんが大事にしている壺がありました。
子供には「絶対触ってはいけない!」と言っていました。
でも「触るな!」と言われると触りたくなるものです。
ある時、子供がついその壺に触り、なでているうちに割ってしまいました。
勿論お父さんはカンカンになって怒りました。
ところが、もし自分がその壺を誤って割ってしまったらどうするでしょう。
せいぜい「馬鹿なことをしたなー」と言って肩をすぼめて少しの間落ち込む程度でしょう。
同じように壺を割ったのに、人がすれば責め、自分がすれば仕方がないと思う。
人間は如何に自分に甘く、人には厳しいか。
自分がした悪いことはそんなに気にしないのに、他人のしたことは何十倍も何百倍も悪く思うものです。
今の日本の風潮もそんなところが見受けられます。
充分に自分を律するよう意識しなければ本能に流されます。
先の話は、子供に触られたくなければ子供が手の届かないところに置かなかった自分を責めるべきことですね。
夫婦
最近私の周りの若い人が1人2人と結婚しています。
嬉しそうな顔を見ると「いつまでも幸せに」と思います。
結婚について色々言う人はいます。
「結婚は人生の墓場だ」と言った人もいます。
自由が束縛されてしまうからのでしょうか。
結婚して幸せな関係も、暫く経つと我儘が出てきます。
時々フッと思い出すのは、私が独身時代に聞いた随筆家の楠本憲吉さんが言った言葉です。
テレビで司会者の人から「今の奥様と別れてまた結婚したいと思いますか?」と聞かれた時、「普通の石だった妻をいつも磨いて今は玉になった。また同じ苦労はしたくありません」と答えたのです。
この表現は奥さんを少し下に見ているような言い方に思えますが、共に切磋琢磨していまの円満な夫婦関係が出来たと言いたいのでしょう。
私も結婚して35年を過ぎ、振り返ってみれば色々ありました。
楠本さんと同じように石に例えれば「夫婦という2つの角ばった石。ぶつかり合っている内に角が取れ、歳と共に磨かれ共に玉になる」
そう思います。
これからは磨かれた玉を割らないように気を付けなければ・・・・
攻めのリハビリ
先日テレビを見ていると、「攻めのリハビリ」という言葉が耳に入ってきました。
NHKの「プロフェッショナル仕事の流儀」という番組でリハビリ医・酒向正春氏が取り上げれれていました。
「重症患者も体を動かせ!脳梗塞患者を家族の元に帰したい」という副題がついています。
脳卒中などで失われた体の機能を取り戻すには、重症患者でも早い段階から積極的に体を動かすほうが効果が高いという信念で患者に向き合っています。
体の回復を待ってからではリハビリの効果は少ないのです。
痛がる患者に強いて身体を動かせる。
傍目から見れば「そんなに無理させては可哀そう」とか[もっと優しくしてあげたら」という思いあるでしょうが、社会に復帰する事を希望する本人にとってはそれが必要なのです。
「厳しさこそ人を鍛える」とか[大善は非情に似たり」という言葉が思い浮かびます。
「子供を育てる、人を育てる」に通じるところです。
定山渓温泉
土日にかけて定山渓温泉に行ってきました。
定山渓温泉は札幌の奥座敷と言われ、1時間ほどで行けます。
今、妻は東京にいる娘達のところに出張中なので、土日1人で家にいるのもつまらないと思い、1人で行ってきました。
泊まった宿は源泉掛け流しお風呂があり、夕食は部屋まで持ってきてくれます。
料金は朝夕食付きで1万円しません。
格安です。
宿は古いのですが、それなりに清掃もされ、部屋も1人では充分の広さです。
定山渓までは車で行けるのですが、今回は宿の無料バスを利用して途中の車窓の風景も楽しみました。
夕食は部屋食なので、美味しい日本酒を持ちこみ楽しみました。
宿に着いたのは2時30分。
窓からの風景は眼下に川が流れ、その川の向こう岸に張ったロープには鯉幟がはためいています。
宿ではテレビを見ないようにし、持ち込んだ2冊の本を読みふけりましいた。
気持のいい温泉、美味しい料理とお酒。
のんびりした週末でした。
会社の名前
今朝の日経新聞の「春秋」に「東大阪の街は看板の偽りが多い」と書いてあります。
それは悪い意味ではなく、お客様の要望に「どないかします」という言葉で引き受けた結果です。
こんな部品を作れないかと言われれば、決して無理と言わない柔軟性と積極性を評価しているのです。
結果看板と違う方向へ会社が向かってしまった姿と言えます。
株式会社豊田自動織機もその名前とは違うトヨタの自動車を作っていました。
一般的には会社の名前を見ただけでその会社を想像してしまいます。
私は以前「株式会社〇〇興業」と「興業」いう名前がついた会社は「暴力団系」かと思っていました。
でも喜劇の吉本興業、東京の大手バス会社の国際興業などしっかりした大手企業もあります。
同じ「こうぎょう」でも「工業」はモノを作ること。
「興業」は新しく事業を興すことや産業を盛んにすること
「興行」は芸能スポーツを催すこと。
色々と会社の名前を見ていると、創業者の会社に対する思いが見えてきそうです。
感謝の心
昨日読んだ本の中に「一番早く年をとるモノは何か。それは感謝の心」というギリシャの格言が書かれていました。
誰でも会社に入った時は、一生懸命お客様の声に耳を傾け、より良いものを提供しお客様に喜んでいただく。
そしてそこには感謝の気持ちが湧いてきます。
ところが時が経ち、会社も安定して来ると、居心地のいいオフィスの中から出ることが少なくなります。
そうすると謙虚にお客様の声に耳を傾けなくなり、感謝の心を忘れてゆきます。
「安定してくると最初に無くすモノ。それは感謝の心」だということです
肝に銘じて仕事をしなければなりません。
私より年上の知人で、過去に仕事で大きな実績を上げた人がいます。
今、引きこもり支援の仕事をしています。
彼は仕事場へ向かう時、30分歩いて通うそうです。
その時、歩きながら「ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。・・・・・」と何百、何千回も歩きながら唱え続けるそうです。
そうすると本当に全てのモノに感謝の気持ちが湧いてくると言います。
見習いたいと思っています。
会社は熱気球
昨日のブログでアサヒビールの中興の祖と言われる樋口さんのことを書きました。
その樋口さんが住友銀行当時から言っていた言葉に「熱気球論」というのがあります。
会社で働く皆が熱意を持って頑張れば、熱で気球が上がるように会社も上昇していきます。
でも、誰かが重い悩みを抱えているとその重さで上がりません。
それで樋口さん部下の困ったことを取り除けば上手くいくのかと思い、現場を回り、部下1人1人と面談し、「困ったことがあったら3つ言いなさい」言ったそうです。
樋口さんはどうしても出来ないことはとにかく、出来ることを順に取り除いてあげたそうです。
「おもりを取り除いてあげると、人間とか組織は自然に上がって行くモノです」と言います。
経営者の仕事の1つがここにあります。
優しい人は忘れっぽい
ゴールデンウイークが終わりました。
この休みの間、私は主に帆船作りに没頭。
時々本を読みました。
その中である小説の中に書いてあった言葉が気に入っています。
「忘れっぽい人は優しい人。というより優しい人は忘れっぽい人」というフレーズがありました。
優しくない人はチョットした嫌なことも忘れず、根に持ち続けます。
優しい人はどんな辛いことがあっても、時と共に忘れていきます。
だから憎しむという気持になりません。
ただどんな優しい人も忘れてはいけないことはあります。
それには忘れない工夫が必要です。
それについて、昔に読んだ本の内容を思い出しました。
その本は、住友銀行からアサヒビールを立て直すために社長に就任した樋口廣太郎さんが書いた「念ずれば花ひらく」です。
樋口さん低迷していたアサヒビールをテコ入れし、「スーパードライ」というビールでアサヒビールを復活させた人です。
会社が軌道に乗ってから、大阪吹田に「先人の碑」というのを作ったとあります。
そこには2本の石碑が建っています。
過去アサヒビールを築き上げた先輩社員を祀る石碑。
もう1つはアサヒビールが苦しい時も支援・応援していただいた小売店、問屋、料飲店の人達の供養塔。
お世話になった人達への感謝の気持ちだけは、どんなに忘れっぽい優しい人も忘れてはいけない。
その為の「先人の碑」なのです。
起業時は苦しく、いろいろな人のお世話になったことも、仕事が上手く行き出すと、あたかも自分の力だけで出来たように思う人がいます。
感謝の気持を忘れないことが大切です。
でも思うだけではすぐ忘れてしまいます。
忘れ、傲慢になった時、思い出す。
それを見れば思い出すようなモノ。
身近に置くといいのかもしれません
起業家育成
先日の新聞にイオンが社内で「起業家育成塾」を始めたとう記事がありました。
イオングループ従業員の中からアイディアを募り、選ばれた人には社内外の経営陣が講師となり、事業化ノウハウを伝授します。
1期生は40名ほどが選ばれ、その後も年に1~2回のペースで募集します。
従業員のアイディアを新規事業に生かすことを目的としています。
以前多くの企業で試みた「企業内起業家」の育成でしょう。
起業家育成と言うとリクルートがすぐ頭に浮かびます。
リクルートでは会社が社員を育成するというより、社員が入社する時に将来に起業することを念頭に置いて仕事をする人が多いそうです。
以前聞いた話では30歳頃には退社して起業するとのことでした。
確かに私の周りにも元リクルート社員で起業し成功している人達が多いです。
イオンとリクルートではその社員の起業に対するモチベーションは違うかもしれません。
しかし何かに挑戦しようとする思いは大切です。
企業の使命としても「人を育てる」があります。
多くの起業家が育つことを願います。
謙虚
私が小さい頃、「人様に迷惑をかけないように」と親からよく言われました。
あまり出しゃばらないように育てられました。
「変わった子」と言われないようにするのです。
私達の世代は結構そのように育てられました。
テレビの公開番組でも、マイクを向けられて子供は恥ずかしがって逃げていました。
その後、「個性を大事に」という有名教育者達の言葉から「自由に生きる」ということが奨励されました。
「我がまま」と「自由」、「利己主義」と「個人主義」の違いも教えられないまま育つと、謙虚さが無くなります。
「恥ずかしがり」と「謙虚」は違いますが、自分を恥じるという気持ちがあると謙虚さが生まれます。
「実るほど 頭(こうべ)を垂れる 稲穂かな」
今回の猪瀬東京都知事の言動を見てそう思いました。
バイキング料理
最近は、ホテルのレストランでランチをしたいと思っても、ほとんどがバイキング形式のところが多いようです。
昨日は休日なので海の見えるレストランでランチしようと、小樽のホテルに行きました。
やはりこのホテルのレストランもバイキング形式でした。
本当は、ほどほどの量の料理で、ゆっくり食事を楽しみたかったのですが少しがっかり。
でも折角来たのだからと思いレストランに入りました。
レストランは多くのお客さんがいて大混雑。
行列に並び料理を取っていくと、お皿に溢れんばかりになってしまいます。
「ほどほどの量を」と思っていたのに、この量の多さ。
つくづく自分の意志の弱さを感じてしまいました。
バイキング形式の食事はお腹いっぱい食べれても、食べ終わった後「何が美味しかったか?」と聞かれてもよくわかりません。
食事したというより、何となくエサを詰め込んだという感じ。
お腹いっぱいになって家に帰り、夕食は少しの野菜だけ。
年とともに食べる量が減ってきています。
やはり少量でいいから、美味しい料理を食べたいと思います。
体重も増えたようです。
反省の1日でした。
日本文具大賞
「日本文具大賞」というコンテストをご存知でしょうか?
「国際文具・紙製品展ISOT2013」の中で表彰されます。
機能面・デザイン面において最も優れた文具に送られるアワードです。
たまたまあるところからのメールでその存在を知り、締切は今日26日で、私も昨日申込しました。
出品したのは「自分で作る『日めくり暦』大事にしたい今日の言葉」という「暦」です。
この「暦」は希望される知人に使っていただいていますが、おおむね好評です。
どのような結果になるか分かりませんが楽しみです。
「ダメ元」でも「もしかしたら」とい思いを持って待っているとワクワクします。
日本女子プロ将棋協会
先日私のオフィスに女流棋士の中井さんが来られました。
知人がお連れになり、1時間ほど話をしました。
私は将棋はほとんど出来ません。囲碁もダメです。
本当は何度か挑戦したのですが、熱心でなかったのでしょう、はさみ将棋になってしまいました。
そんな私の所に女流棋士が来られたのです。
中井さんはクイーン名人という称号もお持ちです。
私のところに来られた訳は、札幌で将棋をもっと広めたいという思いと、中井さんが所属している「日本女子プロ将棋協会」の告知活動のために協力してほしいとのです。
以前、女子棋士は「日本将棋連盟」に属していました。
男性中心の「日本将棋連盟」では常に女子棋士は抑圧された状態だったそうです。
1981年に「女流棋士会」が発足し、2008年に「一般社団法人日本女子プロ将棋協会」に変更し、2012年より公益社団法人になりました。
出来たばかりの公益社団法人としてその活動を広めているところです。
6月に私の知人が「カルチャーサロン」を開く予定です。
その活動は私も協力していますが、そのサロンの中に「将棋サロン」なるモノを作れば、協力の一石になるかと考えています。
中井さんの話では女子棋士の地位は将棋の世界では低く、棋戦の賞金額も男子の10分の1とのこと。
女流棋士の認知を高めたいとの思いは中井さんのお話から充分受けることが出来ました。
中井さんは北海道稚内市の出身。
小学5年生の時、親の反対を説き伏せ東京の将棋の師匠のところで修行を始めた程の大変ポジティブな人です。
人一倍北海道にも愛着を持っています。
今後私も出来る協力はして行きたいと思っています。
個人保証
昨日の日経新聞に「経営者 全財産没収せず」という見出しの記事がありました。
経営者の「個人保証制度に新指針」と言う副題になっています。
中小企業の場合、金融機関から融資を受けた時、「個人保証」を求められます。
万が一会社が倒産すると経営者の個人財産まで全額没収されかねません。
株式会社であれば本来「有限責任」で、出資したお金しか責任を負わなくてもいいはずです。
ところがこの個人保証という制度のため「無限責任」を負わされています。
その為日本では倒産した会社の経営者の再挑戦が大変難しい状況にあります。
中小企業庁と金融庁が出したこの新しい「指針」では、経営者の再起を促すために、倒産した場合でも全額をとらず生活出来るお金は残すというものです。
外国ではどうでしょう。
ネットの情報によれば、アメリカでは連帯保証人がないそうです。
担保は付けますが、その対象は不動産や有価証券、その他に売掛金や商品在庫も対象になります。
会社が借入を返済出来ない時は担保で相殺されます。
たとえ不動産担保の評価額が下落して元本割れを起こした場合でもそれは銀行側の自己責任で、それ以上請求しないとのことです。
だからアメリカでは会社が倒産してもその経営者は再挑戦できます。
アメリカでは起業家が多く育っていますが、そんな金融環境もその素地にあるのかもしれません。
日本もやっと少しアメリカに近づきそうです。
生かす正しさ
「裁く正しさより生かす正しさ」
先日の勉強会で参加者の1人が教えてくれた言葉です。
「良いか悪いか」を評価しただけで、それで何が残るのか。
それだけでは評価した人間の自己満足しか残らないのではないでしょうか。
会社の中でよくある光景です。
部下の仕事の結果を評価して「良いか悪いか」の判断だけで終わっている上司がいます。
結果判断は誰でも出来ます。
管理能力、指導力の無い上司はそれ以上が出来ません。
本来は結果判断をするとともに、部下に間違いを認識させ、改善する方法を考えさせます。
考えさせることによって部下を教育する。
「生かす正しさ」というのは、上司の能力が試される言葉です。
プレゼントを「あげる人」「貰う人」
春は人にプレゼントをあげたり、また貰ったりことが多い季節です。
バレンタインデー、ホワイトデー、母の日、父の日。
入学、転勤などでも、また会社では得意先の開店などのお祝いを出すこともあります。
プレゼントやお祝いをもらうのは嬉しいモノです。
プレゼントなどをあげた人の多くは、心の片隅でその返礼を待っています。
あげた人は「あげたこと」を忘れないものです。
返礼が無いと「なんで返礼くらいくれないのか」と不満を覚えます。
一方、プレゼントを貰った人は返礼しなければと思っていても忙しく出来ない時があります。
返礼出来ないでいると人の心理は、「返礼出来ず申し訳ない」とズーと心の片隅に思っています。
そしてプレゼントをくれた人のことが常に頭から離れません。
このように「あげた人」と「貰った人」の心理は違います。
もしかするとプレゼントを「あげた人」以上に「もらった人」は気にしているのかもしれません。
そのようなプレゼントを貰った人の心理が分かると、逆に返礼がない間は、あげた自分のことを忘れていないと思うことが出来ます。
返礼ない間は自分のことを気にしてくれている。
そう思えばいいのです。
プレゼントを「もらう人」の心理的負担は結構なモノがあります。
だからプレゼントをあげ過ぎるのもどうかと考えます。
皆さんはいかが思いますか?
叱ることについて
昨日はブラック企業について書きました。
「仕事に対する社員への要求が厳しい企業が、全てブラック企業と言うのはどうなのか?」ということを書きました。
それに関連するのですが「部下の叱り方」について思うことがあります。
私が若い頃あるコンサルタントが部下の叱り方で次のようなことを言っていました。
「部下の間違いを指摘する時、その場で叱らず、時と場所を変えて注意する方がいい。人前で叱られる部下は自尊心を傷けられ素直に聞き入れられない。また時と場所を変えた方が冷静に注意することが出来、部下とも心を割って話せる。その方がいい」というものでした。
当時は「そうだな」と納得したものです。
しかし実際はそうではありません。
後で叱っても叱られる本人はそのことを忘れていたり、他人事のように聞いています。
結局その部下は同じ間違いを繰り返すことが多いのです。
「叱る時はその場で一生懸命叱ること」。これが大事です。
叱ることについては、松下幸之助さんも稲盛和夫さんも土光敏夫さんも、皆さん同じようなことを言ったり書いたりしています。
叱られても部下が納得するのはその言葉の後ろに愛情があるからです。
それが分かるから受け止め、聞き入れます。
松下幸之助さんについて書かれた本の中で、次のようなことがありました。
会社がまだそれほど大きくなっていない時だと思います
ある時、部下が間違いを犯し、それに対し幸之助さんは烈火のごとく叱りました。
叱り終わり部下が下がった後、少し叱り過ぎたかのと反省した幸之助さんは受話器を取り上げました。
そしてその部下の奥さんに電話をして「先ほどあなたのご主人を少し叱り過ぎました。きっと今日はしょんぼりして帰って行くでしょうからお酒の1本でもつけてやってください」と言ったそうです。
部下が家に帰ってみると奥さんはニコニコしてお酒を用意して待ってくれている。
その理由を奥さんから聞いた部下は改めて幸之助さんの言葉を思い出し、そして幸之助さんの気持ちに涙したということです。
部下を叱る時、時には感情的にもなるでしょう。
でも憎くて叱っているのではありません。
その裏に愛情があれば真意は伝わります。
沢山叱って上げて下さい。
ブラック企業
先日ネットニュースを見ていたらユニクロが「ブラック企業」だと言われ、それに対して柳井社長が会見していたのを見ました。
「ブラック企業」とは入社を勧められない労働搾取企業という意味だそうです。
ユニクロが「ブラック企業」だと言われたことに対して柳井社長が反論しています。
「我が社が本当にブラック企業であれば、社員の数はもっと減っていると思う。会社は発展しない。
社員は若いうちは甘やかされず、厳しく育てられたほうが幸せ」との持論を述べています。
「ブラック企業」と言われる会社は実際あるのかもしれません。
でも仕事が厳しいからというだけで「ブラック企業」だと決めつけるのは疑問を覚えます。
逆に、楽な仕事で給料が高い企業は早晩倒産します。
結果従業員は路頭に迷います。不幸にします。
今は頑張る人、辛抱する人が少なくなったのでしょうか。
就職難だと言われながら、健全に経営をしている知人の会社では採用したくても人が来ません。
辛い仕事を避けて、少しでも給料が高く、福祉が完備し環境のいい会社を選択しようとしているのでしょう。
以前テレビで新規オープンするユニクロの店頭の様子が放映されていました。
そこには柳井社長の厳しい叱責している姿も映し出されています。
物凄い緊張感が画面から伝わってきます。
その時私は「ユニクロの社員は幸せだな」と思いました。
厳しく育てられた人はどこの世界でも通用します。
人間として大きくなっていきます。
もしもユニクロが厳しいだけで人が育たない会社であったらこんなにも会社は成長しません。
会社が成長するということはその社員も成長している証拠です。
優れた社長は皆仕事に厳しい人です。
柳井さんの様な社長を応援します。
講座にて
昨夜から札幌市立大通高校で講座を担当しています。
これから7月まで続き、計10回講義することになります。
講座名は「身の丈起業のススメ」で、最終的には参加者各自に事業計画書を作成してもらい、その発表までする予定です。
この講座は「さっぽろ市民カレッジ」として開かれ、一般社会人も参加し、大通高校の生徒と同席します。
ですから参加者は10代から50代。
年代層が違うと同じ言葉も通じなかったりします。
丁寧に話そうと思います。
昨夜の第1回目は10代の生徒を念頭にして「生きがいある人生を送るために」と題して90分話しました。
多くの参加者が熱心に話を聞いてくれましたが、後ろの方に座っていた2名の女生徒はほとんど無関心。
ヒソヒソ話をしたり、寝たり、しまいには化粧道具を出して化粧も始めました。
私は講義をしながら「エッ」と思ったのですが、傍にいる担当教師は気付いても何も言わないのでそのままにしておきました。
講座後のアンケートではその女生徒達は参加理由として「単位のため」とだけ書いてありました。
ヒソヒソ話しても化粧しても講義の邪魔をしないので「まあいいか」と思っています。
ただあと9回の講義の中でその女生徒とがフッと興味持てるような話をしてみたいと考えてみます。
色々工夫します。
今まで他のところで多くの講座を持ちましたが、今回は若干違います。
少し長丁場ですが、これから楽しみです。
不思議な話し
今日は不思議な話を1つ。
先日グループ会社の株主総会があり、その後の会食の時叔父から聞いた話です。
その話は叔父が小さい頃に父親から聞いて、ズーと不思議な話だなと思っていたそうです。
その父親は私の父方の祖父で末吉と言います。
その末吉が生まれた時の話。
末吉が生まれた時、母親はお産が大変なこともあって1度死んでしまいました。
その時父親は「自分の命は10年短くなっていいから、妻を3年間だけで生かせて欲しい」と願を掛けたそうです。
そうすると1度死んだはずの母親は大きな声を上げて生き返りました。
生き返った母親を見て皆は驚きそして喜びました。
生き返った母親の話だと、目の前に白装束を着た逞しい男がフッと現れ、「お前を3年間だけ生き返らしてやる。だが3年経ったら迎えに来る。その印としてこれを与える」と言って持っていた錫杖(しゃくじょう)のような棒で横腹を強く打たれました。
母親はその痛みで大きな声を上げて生き返ったのです。
母親は生まれたばかりの末吉を育て、3年経った時、約束通り死にました。
死んだ母親の体を検めると、その横腹にはそれまで無かった黒いアザがあったそうです。
末吉の生まれは山形です。
山形は羽黒山があり修験者がいるところです。
何となくその結びつきを考えてしまいます。
叔父は92歳ですが、すこぶる元気。
元気な内にまた昔話を聞きたいと思っています。
素直について
「素直」という言葉で気付いたことがあります。
人は素直でなければならないとよく言われます。
でも「素直」になりなさいと言われると、黙って人のいう通りにするということだと思っている人がいます。
これは間違いです。
黙って人のいう通りにするのは、「従順」と言います。
人に逆らわず、考えることを放棄して生きていくことです。
意志の無い奴隷の様な生き方です。
「素直」な人は自分の考えを持っている人です。
自分の夢や大事にしたい考えを持っている人です。
それがあるから生き方にブレがありません。
だから人の話を聞いても言葉を拒否することも言葉に流されることも無く、自分夢や考えにしたがって受け入れます。
今の草食系男子と言われる人を見てそう思いました。
仇を恩で返す
「仇を恩で返す」
これは先日のテレビでコメディアンの欽ちゃん、萩本欽一さんが言っていた言葉です。
このテレビを見た人も多かったと思います。
「恩を仇で返す」ということはあっても「仇を恩で返す」ことはなかなか出来ることではありません。
欽ちゃんがまだ無名な頃、TBSのある番組から干されたしまったことがあったそうです。
普通は「なぜだ!許せん!」という気持ちになってしまいます。
その後欽ちゃんが有名になった頃、TBSから新番組のオファーがありました。
普通は以前の仕返しを考えたりしますが、欽ちゃんは「恩返ししよう」と思ったそうです。
この発想が出来ることが素晴らしい。
そして「恩返し」をすることで自分に運が向いてきたそうです。
嫌な思いをした時、やり返すのでなく、逆にいっぱいの優しい気持ちで返して上げると相手はビックリします。
それによりその人はファンになってしまうのでしょう。
広い大きな気持ちが無ければ出来ないことです。
久しぶりにテレビで欽ちゃんを見た「欽ちゃん世代」の私。
また欽ちゃんが好きになりました。
中小企業金融円滑法
昨日勉強会で中小企業金融円滑化法の話しを聞いてきました。
1年前の24年3月現在に数字ですが、この法律による返済猶予申込件数は327万5千件を越し、金額も92兆8千万円を越しています。
この金額に驚きます。
日本の国家予算に匹敵します。
3月以降この法律が終了したことによる企業倒産を防ぐために、国は「金融機関によるコンサルティング機能強化」「企業再生支援機構等による支援強化」等を進めるようです。
まだこの施策が具体的にどう進められるのか、中小企業支援に財政支出が行われるのか分かりません。
財政再建と言われているのに大盤振る舞いは出来ないでしょう。
法律が切れた3月から今月にかけてはまだ倒産件数が極端に増えている様子はないそうです。
でもこれからが心配です。
特に先ほどの92兆8千億の数字の中には住宅ローンは4兆4千億円あります。
この住宅ローンの返済は中小企業と違い支援の方法がありません。
これも大変な問題です。
中小企業金融円滑法のことは分かっているつもりでしたが、改めて勉強になりました。
ビジネス鞄
先日自宅の納戸を見てみると沢山の鞄がありました。
7個か8個、その他に旅行用の大型鞄が3個。
常に使っているのはビジネス用の革の黒鞄、旅行で携帯する肩掛け鞄位。
残りは処分すればいいのに未練が残り、そしてまたいい鞄を見ると欲しくなる。
困ったモノです。
本来私は好きな鞄を大事に使いこむというのは好きです。
だから飽きないいい鞄を欲しいと思って買います。
先日電車の中で、長年使い込んだ鞄を持つビジネスマンらしき人がいました。
本当に使いこんでいるようで、底の革が擦れ、糸が解けそうな鞄。
そのビジネスマンの身なりはシャキッとしているのですが、それに比べて鞄が貧弱。アンバランスです。
本人はそれには気付いていないのでしょう。
今まで見た鞄の中で特に印象深かかったのが、古くなった抱え鞄。
その鞄には持つところに手の跡がくっきり残り、茶色のはずが全体的に黒ずんでいました。
その人が営業で私のところに訪ねてきた時、その鞄の方に目が行き、気がそぞろになったことを覚えています。
同時にその営業の人の評価も下がりました。
身なりというと洋服・髪型・靴のことが言われますが、仕事の相棒である鞄もその人の評価を決めます。
値段は高くなくてもいいので、ビジネスに適した鞄
大切だと思います。
心の漂白剤
毎日同じような生活をしていると、その生活に慣れている自分がいます。
毎日が安易な生活であっても、毎日が忙しく厳しい生活であっても、それを続けて行くとそれが当り前になります。
厳しくても遣り甲斐がある仕事なら充実しています。
どうせならそんな生き方がしたいものです。
ただ、毎日同じ生活を繰り返していくと、時々心が緩んでくるような気がします。
時として慢心にもなります。
そんな時、自分をあえて別の次元に置いてみる必要があるのではないでしょうか。
例えば毎日掃除で使うタオルは掃除が終わる度に洗い、干して置きますが、それでも少しずつ薄汚れて来ます。
よく洗ってもしみ込んだ汚れはそう簡単に取れません。
そんな時、熱湯消毒したり、漂白剤に浸けてみると真っ白になります。
人間も時には自分をより厳しい環境に置き、心を見詰め直すのがいいのかもしれません。
謙虚で素直な心を取り戻す。
そのための時間が必要です。
少し私の反省を込めて。
72の法則
昨日ある大手証券会社が開いたセミナーに行ってきました。
外国為替相場の見通しについてです。
私は以前から為替には興味がありました。
そのセミナーで2つのことを学びました。
1つは予想は難しいということ。
昨日は日銀の金融政策決定会合が行われ、新しい総裁を迎えて初めての会合ということで注目を浴びていました。
その結果はセミナーの間に出ました。
セミナーの講師はその証券会社の為替のプロです。
セミナーの中で、結果をまだ知らない講師はこの金融政策決定会合について「結果様相はすでに相場に織り込み済みで、ドルに対して円相場に大きな動きはないでしょう。若干円高になる可能性があります」と言ったのです。
ところがセミナー会場を出た時、円相場を確認すると円高どころか前日よりドルに対して3円近くも円安になっていたのです。
如何にプロといえども相場予想は難しいということです。
もう1つ学んだことは「72の法則です」
「72の法則」はアインシュタインが発見したと言われる法則で、銀行や郵便局に預けたお金が2倍になるまで何年かかるかを計算してしまう方程式です。
72÷金利=預けたお金が2倍になる年数
これはお金を複利で運用した時を想定しています。
現在郵便貯金は0.035%の金利です。
この金利を方程式に当てはめると2057年かかってしまうのです。
20年以上前のバブルの時はどうだったでしょう。
当時金利は約8%でした。
そうすると72÷8=9年
わずか9年でお金が倍になったのです。
同じ運用でも金利の違いで結果が大きく変わるとを示す方程式です。
この方程式のポイントは複利ということです。
利息を元金に加えながら増やす方式です。
その都度、利息を受け取り使ってしまう堪え性のない人の元金はそのままで増えません。
やはり節約こそがお金を貯める一番の要因なのです。
昨日のセミナーはためになるセミナーでした。
起業家の経理
今日は「身の丈起業」の経理について書きます。
身の丈で起業する時、大切なのは赤字を出さないこと。
その為、支出となる経費は最小限に抑えます。
自分で出来ることは自分でします。外注に出さない。
その1つに経理処理があります。
会社は個人・法人に関係なく、ドンブリ勘定でお金を管理しているところはすぐダメになります。
また、利益が出れば税金を納めなければなりません。
税金を納めず、それが税務署から摘発されれば小さな会社は信用がガタ落ちになります。
だから、経理処理をしっかりし、決算処理・税務申告もし、納める税金は納めます。
ただ起業を志す人のネックの1つがこの経理処理です。
多くの人は経理の知識がありません。
つい外注に出してしまいます。
税理士さんや会計士さんに頼むと少なくとも月当たり2万円、年間24万円。
決算申告もお願すると年合計30万円弱かかります。
利益がそこそこなのに30万円もかかれば、大変な負担になります。
そこで、「自分経理」が必要です。
誰にも出来きる簡単な経理処理を教えてくれる講座があってもいいのではないかと思っています。
今は簡単で、安い会計ソフトがあります。
「チョットした」知識があれば処理できます。
ただ経理経験の無い人にとっては、その「チョットした」ことが結構大きな壁に思えて来ます。
それを解消し、実践で活かせる講座は従来あまり有るようでなかったと思います。
「税理士さんや会計士さんに頼らない経理をしましょう」となると、そのような講座を開こうとする税理士さんや会計士さんはいなのかもしれません。
先日来社された起業志望者も経理のことを心配していました。
そこで来週その講座を開講出来るか、ある人にお会いして協力いただけるようお願いする予定です。
出来れば早い内に開講したいと思っています。
起業のネックを取り除き、起業を志す人の後押しが出来ればと願っています。
言葉の重み
先日テレビを見ていたら、有名人の「通帳拝見」の様な番組が流れていました。
その中の1人に森永卓郎さんがいました。
その森永さんの通帳残高は1億5千万円を越していました。
ビックリです。
確か森永さんは以前に「年収300万円時代を生き抜く経済学」という本を出し、庶民派の経済評論家として活躍していますので、そのギャップに驚きです。
たまたま森永さんを取り上げましたが、その他にも庶民派を謳いながらそれとはかけ離れた生活をしているコメンテーターや評論家は沢山います。
お金を稼ぐことはいいのです。
ただ、テレビで「円安で物価が高くなり、電気料金が〇〇円上がります。パンが△△円上がり家計に影響を与えて大変です」と言っている言葉にどれほどの真剣さがあるか、現実感があるか疑問に思ってしまいます。
以前にも紹介しましたが、土光敏夫さんは石川播磨重工・東芝の社長、そして経団連の会長を経験し、多くの報酬を得ましたが、そのほとんどをお母さんが創立した「橘学苑」という女子学園に寄付していました。
その分自分の生活は大変質素だったそうです。
クーラーもない古い家に住み、床屋へは行かず自宅で息子さんにしてもらったり、穴とつぎはぎだらけの帽子をかぶっても平気だったそうです。
土光さんは極端かもしれませんが、驕らない生活をしているからこそ、人に対して本音を話すことが出来る。
人が言う言葉の重みはその人の生活から出てくる。
私はそのように思います。
今日も1日いい日です
今日は一日。恒例のように神社・神宮にお参りに行ってきました。
朝7時に娘も一緒に3人で家を出ました。
北海道神宮に着いて、手水をした後、石段を上がろうとした時、若い守衛さんが竹箒で掃除をしていました。
私達に気付いて、手を止め、「おはようございます」と挨拶してくれました。
私達も挨拶をし、そしてお参り。
お参りが終わりまた石段のところに行くと、先ほどの守衛さんが「ありがとうございました」と送ってくれました。
今まで何回も神宮に来ていますが、「おはようございます」「ありがとうございます」という言葉を掛けてくれたことはありません。
守衛さんの言葉が、朝から心が温かくなる気持にしてくれました。
そういえば今日は4月1日。
もしかしたら先ほどの若い守衛さんは「新入社員」なのかもしれません。
新鮮な気持ち、いつまでも大事にして欲しいと思います。
守衛さんにも私達にとっても、きっと「今日も1日いい日」です。
大事な時間
昨日家に帰ると娘から「配偶者ビザが下りた」と報告がありました。
このビザもらうのに半年以上かかっています。
2週間ほど前から娘はビザの最終書類を提出するためにイギリスから帰ってきていました。
ビザが下りたので来月には旅立ちます。
今まではビザの関係があり半年ごとに帰ってきましたが、今度はそう簡単に帰ってくることはないでしょう。
あと半月位。
妻は娘との一緒にいる時間を惜しんでいるようです。
大事な時間を楽しみたいと思います。
良き「出会い」と「出合い」
人との「良き出会い」は予期せぬ時に起こります。
その良き出会いは互いを高め合う関係になります。
出会いとは自分が発している波長と合った人と同調することです。
だから自分が発するモノが無ければ誰とも同調しないのです。
言葉もそうです。
どのような素晴らしい言葉や文章も、自分がそれを受け入れる状況になければ心に入ってきません。
「この世に生れて来たのは自分の魂を磨くためです」という稲盛和夫さんの言葉は出合いです。
それが今の自分の信条になっています。
私は今年の初めから「大事にしたい今日の言葉」という私が作った暦に毎日一言書いています。
毎日一生懸命生きていれば、大事にしたい言葉が見つかるはずです。
ところがこの2日間書いていません。
心に残るような大事にしたい言葉に出合っていません。
それは自分の感度が鈍っているせいだと思っています。
体調が少し悪かったせいかもしれません。
今日から気を引き締めてゆきます。
恩送り
先日来社された人の話です。
その方は私が運営するレンタルオフィスを見せて欲しいということで、事前に電話をもらっていました。
入居希望者かと思ったのですが、お会いしてお話しを聞くと、地下鉄の隣の駅近くで同じようなレンタルオフィスを開きたいとのことです。
隣の駅で開業するので若干競合することになりますが、その人の質問には精一杯答えアドバイスもしました。
オフィス内の写真も沢山撮っていきました。
こう書くといかにも私は寛容な人間のように見えますが、それほどでもありません。
ただ5年ほど前に私も同じように開業を検討する時、あるレンタルオフィスを訪ねました。
そこの運営責任者は快く質問に答えてくれたのです。
開業後も相談に応じてくれました。
そのレンタルオフィスもビル建て替えのため今月いっぱいで閉鎖するそうです。
そのオフィスは「さっぽろチャレンジオフィス」といいます。
運営責任者は山重さんです。
本当に感謝しています。
その山重さんから受けた「思い」を、訪ねてきたその人に渡す。
そんな考えからです。
そしてそれは山重さんへの「恩返し」ではなく「恩送り」
今の起業支援もそのような考えでしています。
これからも多くの人と一緒に起業支援していけたらいいと思っています。
資料整理
ここ2・3日、暇を見つけては資料整理をしています。
その資料は新聞のスクラップ、クリアファイル入れているチラシパンフレット、そして角2封筒に入れてある嵩張る資料の3種類あります。
それだけで書庫の4分の3を占めています。
その資料は20年ほど前からののもで、今となっては必要ないモノがほとんどです。
しかし、忘れていた大事な資料も見つかります。
当時面白いと思った商品情報などは、既に淘汰されたモノもあれば、しっかり生き残っているモノもあります。
また20年前に流行ったモノが今改めて見ると、別の商品として使えそうなモノもありそうです。
教訓―――「いい資料も生すことが出来なければただのゴミ」
資料には2種類あります。
以前に紹介しました「20秒ルール」の様に、20秒以内に見ることが出来る資料・情報。
それともう1つ、何かを検討したり構想してりする時に取り出して使える資料。
この区分けをしっかり認識して、資料・情報集めとその管理をする必要があります
「情報は貯めるばかりでは駄目!生かせてこそ価値がある。」
こんな当たり前のこと。
いまさら実感しています
整理すると書庫の中の資料3分の1になりそうです。
贔屓客
先週の土曜日に何回か行ったことのある近所の寿司屋に行ってきました。
以前にもブログで紹介しましたが、洞爺ウインザーホテルの寿司屋で修行した人が開業したところです。
今回は私達夫婦と娘を連れて行きました。
料理は本当に美味しく、娘は大感激です。
娘の感想では、全て美味しかったけれどその中でびっくりしたのは最後に出た柚子のシャーベットと言います。
味音痴の私でも、確かに味・香りそして舌触り、素晴らしかったと思います。
このお店は他の店より若干価格は高いですが、価格以上の満足を得ることが出来ます。
お店はそれほど大きくはなく、小さな個室が1つ、カウンターは10席位でしょうか。
私達がお店に入った時、個室に1組でしたが、私達の後から3組ほどが入って来て満席。
女将さんから「山地さんはお客様を連れてくる福の神ですね」と言われ大変気を良くしました。
私は人から褒められるとその気になり「そう言われればそうかも}と思っています。
女将さんの一言がお客を喜ばせるのです。
そしてなじみ客になり贔屓客になっていきます。
美味しい料理と、お客を喜ばせる接客。
2つ合わせて繁盛店になっていくのでしょう。
私はこれから贔屓客になろうと思っています。
身丈会
昨夜は「身丈会」の勉強会がありました。
この勉強会は以前に私が開いた「身の丈起業のすすめ」というセミナー受講生が中心となり、勉強したい人達の集まりです。
過去にはネット上で使う写真を上手くとるために「デジカメ撮影のコツ」をプロに教えていただいたり、読書会をしています。
最近は稲盛和夫さんの「心を伸ばす 経営を高める」を読んでいます。
昨夜はその稲盛さんのDVDを見ました。
何年か前にNHKが放送した「知るを楽しむ」という番組の中で、4週にわたって放映された稲盛さんの生い立ち、考え方が稲盛さんの言葉で語られています。
私は過去何度も見ていますが、改めて感動しました。
参加者の中には初めて稲盛さんの声を聞いたという人もいます。
参加者の皆さん15名は食い入るように見て、終わった後は暫く無言でした。
そして皆さんからも感動の言葉をいただきました。
また皆さんからは、このDVDを見てより一層稲盛さんに興味を持ち、すぐにも本を読みたいと思い、勉強したいという気持ちになったと言われました。
参加者の中には既に起業した人、起業したての人、これから起業しようと考えている人がいます。
皆さん積極的な生き方をしている人達です。
だからこの勉強会では私も元気がもらえます。
この勉強会に参加したい人は増えています。
ただ人数の上限は20名位でしょうか。
この勉強会が「起業を志す人達を支援する集まり」であればと願っています。
毎月続きます。
人をけなす人
人と話をしていて嫌だなと思うことがあります。
それはその場にいない人をけなす人です。
聞いていていたたまれなくなります。
「そんなひどい人ではないよ」と言っても独自の判断を変えようとしません。
人をけなす人の心理として、人をけなしながら、それに比べ私は優れていると言いたいのかもしれません。
でもそれは自分の評価を下げるばかりです。
松下幸之助さんの言葉に「人から高く評価してもらうことばかり考えている人は心貧しい人だ。私は人を高く評価する人間になりたい」というのがあります。
自己顕示欲、自我を押さえ、他の人を高く評価し、その人の能力を伸ばす人になりたいものです。
孤独と孤立
新聞にある本の広告が載っていました。
本の題名は忘れてしまいましたが、本の中身の紹介に「1流は孤独を愛し、2流は群れを愛する」「孤独と孤立は違う」というのがありました。
その「孤独と孤立は違う」は言い得ていると思いました。
トップは常に孤独だと言われます。
最終責任を負わされ、決断をしていかなければならない時の心の状態です。
社長もそうです。
ところが時に、勘違いしている社長がいます。
孤立しているのに「社長は孤独なものだ」と自分に言い聞かせているのです。
孤独と孤立はやはり違います
孤独とは1人でいる状態です。
孤立は人から切り離された状態です。
冷徹な決断をする時、社長は孤独な決断をします。
しかしその時、周りには社長に期待する社員がいます。
孤立した社長には期待する社員はいません。
自分のことしか考えない社長は孤立します。
これは肝に銘じて置くことです。
売上最大 経費最少
昨夜盛和塾の例会がありました。
稲盛さんのDVDを見ての学びです。
そのDVDは稲盛さんがまだ若い頃に講演したものです。
その中で「成程!」と思った話をご紹介します。
京セラのある営業部門の損益計算書を使った数字の見方です。
京セラではアメーバー経営を実施しています。
各地の営業部門も単独でそれぞて決算書が作成されています。
京セラ製品を売る営業部門の粗利益は全て売上の10%と決められています。
よって粗利益高を増やすには売上を上げるしかないのです。⇒売上最大。
経費も細かく分類され、水道光熱費も電気、水道、ガスに分けられています。
経費の項目の中に見たことの無い京セラ独自の項目がありました。
それは「売掛金社内金利」「固定資産社内金利」「本社経費」です。
「売掛社内金利」を課すことで売掛金を早く回収する効果があります。
「固定資産社内金利」は自社ビルで営業していても、賃貸で借りるのと同じようにハンディーを課す考え方です。
営業責任者はそれらの経費を少なくする努力によって高い営業利益が生まれます。⇒経費最少。
このような経理の仕組みを作り推進したのは稲盛さんです。
会社の経理の基本的な仕組み作り・運用は会社のトップが作り、それをさせなければ機能しません。
「面倒だから部下に丸投げ」では成り立ちません。
無論経理は外注ではなく、自社でします。
昨夜はアメーバー経営の「サワリ」を勉強出来ました。
怒りと悩み
人はよく怒ったり悩んだりします。
私もそうです。
そんな私も最近は怒らなくなった?と思います。
年を取ったからと言うばかりではありません。
チョット考え方を変えたからだと思います。
「怒ること」の分析が、ある本に書いてあり、その解決方法も記載されていました。
その方法とは、怒る自分を俯瞰的に見て、なぜ起こっているのかをよく見てみるのです。
そうすると「そんなつまらないことで怒っているのか」と思ってしまいます。
そうすると起こる理由が無くなるのです。
これは我慢するのとは違います。
それと同じように悩むということも俯瞰的に見てみると、何かにとらわれているから悩むのでしょう。
それは欲得に絡んでいることが多いのかもしれません。
それらのことが分かると、心が欲得から離れて、少し悩み事が失せてゆきます。
人は皆、聖人君主でないので、全ての欲得から離れることは出来ません。
しかし悩む根本原因が欲得であると分かれば、それを減らすようにすれば悩みも減っていきます。
人間ですから、全ての怒りも悩みも無くすことは出来ません。
それでもそれを減らせればもっと楽しく暮らしていけるでしょう。
これらのことは自分に向けての言葉でした。
顔を見て話を聞く
自宅の私の部屋の本棚を整理していたら、どこからかいただいた「松翁論語・抄」という本が出てきました。
松下幸之助さんが話したことを、江口克彦さんがまとめて書いたものです。
その中に「話している人の顔を見なさい。そして、うなずきなさい。なぜならば、うなずくことによって君の心にその人の話が入り、また話をする人に励ましを与えることになるから」という言葉があります。
時々ありますが、人と話をする時、私と目を合わそうとしない人がいます。
叱っている訳でも怒っている訳でも無く、真剣にこれからのことをどうするかという話をしているのに下を向いているのです。
そのような態度は拒否していると取ってしまいます。
本人に聞くとそういう気持ちでないと言いますが・・・
今の時代、話をしても下を向いたままで聞いている人が多いように思います。
目を合わそうとしないのです。
自信が無いのか分かりませんが、それでは話している人の話す気持ちが削がれていきます。
時には「人の話を聞く時は顔を上げろ!」と怒鳴りたくなります。
顔を見て話すことに関して、もう1つ別の話です。
聞いた話です。
男性は嘘をつく時は相手と目を合わそうとしない。女性は反対に嘘をつく時は真剣に相手の目を見て話をするそうです。
本当でしょうか?
先日「時間を守らない人は相手を大事にしない人」という言葉を見て、なるほどと納得しました。
現代は皆が携帯電話を持っています。
電話すればいいと思うのか、平気で遅れてくる人がいます。
電話くれるのはまだいい方で、電話さえくれない人がいます。
セミナーや講演会で、「まだ来られていない人がいますので暫くお待ちください」と司会者が言っていることがあります。
時間通りに来た人を大事にしないで、時間を守らない人を大事にする。
全て待つ人のことを考えていない行為です。
テレビの番組で沖縄の生活が紹介されることがあります。
「会合があっても遅れて行くのが当り前」「1時間位送れるのは普通」と言っている人がいました。
大らかさを強調したいがために言っているのでしょうが、違和感を抱きます。
そこにあるのは甘え。
孔子の言葉に「君に忠、父母に孝、朋友に信、目下に慈悲」というのがあります。
いくら親しい友にも「信」が無ければ良き友人関係は築けません。
「友達だからそれ位いいだろう」という甘え。
私は「大事にされてない」と思ってしまいます。
20秒ルール
昨日は朝早くから同系グループ会社の今年度の決起大会がありました。
このグループ会社は順調に売上・利益とも伸ばし、全体で従業員350人以上、売上100億円を越し、営業利益も数億円を出しています。
その社長の話しの中でいい話しがありました。
彼が紹介したのは「20秒ルール」です。
これはご存じの方も多いかもしれませんが、私は知りませんでした。
この「20秒ルール」は「何かをする時、20秒以上かかることは面倒だと思い、しなくなること」です。
20秒以内に出来ることは良い習慣となり続きます。
逆に20秒以上かかることは面倒なことだと認識し、それを上手く使えば悪い習慣を止めることができます。
前者の場合は、必要な資料が20秒以内に見ることが出来れば、その資料を生かすことが出来ます。
必要な時にすぐに出てこなければ、その資料は意味がありません。
私の反省----以前は新聞のスクラップを作っていましたが、あまり意味がありませんでした。
必要な時にすぐ出てきません。
後者の場合は、例えば家に帰ってすぐテレビのスイッチを入れ見入ってしまう人は、リモコンの電池を抜いて置き、テレビを見る時20秒以上かかるようにします。
毎日晩酌する人はお酒を抜くため、その日は家にお酒を置かないようにします。
人間は思った以上に怠惰に出来ていて、20秒が我慢の限界の様です。
このルールは自分の生活の中で使っていけそうなヒントでした。
理屈っぽい
フッと思い出したことがあります。
中学生の頃、父と話をしている時、お前の話は理屈っぽいと言われてことがありました。
自分では普通に話しているつもりなのに、聞いている方が「めんどくさい」と思うのかもしれません。
社会人になってからもそんな傾向があったと思います。
自分では筋道を立てて話しているつもりでも、相手にそれが伝わらない。
話す方は単なる自分の思いを理屈付けて主張しているだけなのかもしれません。
結果、相手は聞く気が無くなります。
論理立てて話すということは、聞いている相手が納得する根拠や数字を示し話すことなのでしょう。
「相手が納得するように話す」ことの大切さはこの前のブログでも書きました。
私はこの事に気付くまで時間がかかりました。
ただそのことが分かっても実際に出来ているかというとそうではありません。
今書いているこの文章も理屈っぽいのかもしれません。
相手に分かってもらう、納得してもらうということは難しいことです。
改めて思っています。
本業
成功している会社と成功していない会社
成功していない会社は、変えるべきものを変えず、変えるべきでないことを変えてしまっています。
「変えるべきことを変えず」とは、従来からのやり方にこだわり、過去の成功体験を否定できない状態です。
「変えるべきでないことを変える」とは自社の目的や目標そして理念などは変えるべきではありません。
それを、儲かるからとか、面白そうだからとかの理由で変えてしまう。
今月は3月。
決算月の会社も多いと思います。
私の家具製造会社は2月決算で今日数字が出て来ました。
売上はそこそこでしたが、利益も利益率も目標より高いものでした。
現場責任者の力です。
一方、私の知っている会社は家具製造会社なのに新規事業だと言ってLED照明を売ることも始めています。
でもそれほど売上は上がっているとは思われません。
本業をはずしてはいけません。
新規事業を始めるにしても、自社の技術や資源を使っていけるものでなければ成功は難しいでしょう。
本業を大切に!
改めて思うことです。
理解より納得
先日本屋で「JAL再生」という本を買い、一気に読んでしまいました。
本には稲盛和夫さんのことは勿論書かれていますが、それよりJALがいかにして変わっていったか。
組織として人として、従来の企業風土・概念・意識を変えていく過程での葛藤が書かれています。
倒産した時はJALような巨大企業が再建できると誰も思いませんでした。
それでも、その経営陣や社員達が如何にして再建を成功させていったか。
企業経営に参考になることが沢山書かれています。
私がその中で一番に感じたことは、トップが事業の目的と意義を明確にすることの重要さです。
そしてそれを末端社員まで徹底させる根気強い教育。
この本に植木社長へのインタビューが載っていました。
植木さんが執行役員になり、整理解雇等の諸問題に取り組んでいる時に心の支えになった言葉が3つあると言っています。
1つは「小善は大悪に似たり、大善は非情に似たり」
2つ目は「大義を背負った時、人は強くなれる」
3つ目は「人間として何が正しいかで判断する」
会社のトップが社員に向け発信する言葉は分かりやすく、納得できるものでなければなりません。
往々にして頭のいい社長は理屈で説得しようとします。
社長が話す内容は、社長にとって都合のいい理屈の場合が多いです。
理屈が通っているように思うので社員は「分かりました」と言います。
でも、「理解」しても「納得」していません。
大切なのは「納得」させることです。
社員が「納得」できるのは、人間として正しいことを一生懸命しようとする社長の姿勢であり、社長が社員の幸せを考えていると感じた時です。
「JAL再生」に書かれていたのは、同じ目的に向かっていく中で、トップの言動や行動を社員が「理解」するんでなく、「納得」することの重要性です。
そこにあるのは「心」です。
トップの熱い心が社員を動かしていくのです。
宜しければ読んでみてください。
株・円相場
今、日本もアメリカも株式市場の高騰が続いています。
アメリカは過去最高値を付け、日本の市場も1日で200円以上も上げています。
円相場はそれに対して下がっています。
昔は株が上がれば円が高くなったのですが今は逆の現象です。
アベノミックスが出されてから、円はもっと下がると予想している人が多くなってきています。
現在94円位のが120円、200円。
もっと下がって500円位と言っている人もいます。
もしもそうなれば、日本の経済はガラガラポンが起き、全てが変わるような気がします。
それでもそんな極端な起きないと思っている人はいます。
しかしわかりません。
夏にイギリスに行こうと色々調べています。
イギリスの通貨はポンド。
今は1ポンド140円位です。
でも私が若い頃、ポンドはもっと高かったように記憶しています。
調べてみると1967年は1ポンド1008円でした。
現在は7倍も円が高くなったのです。
逆を言えばポンドが7分の1になったのです。
ドルに対しても、固定相場の時1ドル360円に比べて4倍になったのです。
今後どのような動きになるか分かりません。
通貨価値は各国の動向で相対的に変わります。
ですから、いつ円が一気に下がるか分かりません。
今の日本の株式市場、円相場の動きは思いがけないことで全く逆に動きます。
今後起きうる色々なことを想定して、株や円の動きを予想してみるのは生きた経済の勉強になるのではないかと思っています。
金儲け
今朝の新聞に丸源ビルのオーナーが脱税で逮捕されたという報道が載っています。
丸源ビルは札幌にいる私でも知っている銀座のビルです。
そのオーナーはバブルの頃、総資産1000億円以上と言われたほどの金持ちです。
その金持ちが違法行為をしてまでお金を得る。
それは我欲でしかありません。
このような事件を目にするたびに、若い人達がどう思うかと心配です。
「金儲けすること」=「悪いこと」と短絡的に見てしまうと残念です。
大きなリスクを負って起業した人が、一生懸命頑張ってお金を得て行くことはいいことなのです。
それがこのような問題が起きると、一緒に見られてしまう恐れがあります。
お金に対してもう1つ。
お金はお金に対してポジティブな人に集まります。
お金に対してネガティブな人には集まりません。
概してお金持ちはお金に対してはポジティブです。
それに対して貧乏な人はお金に対してネガティブの様な気がします。
「お金ばかりが人生でない」と言っている人のもとにはお金は集まりません
お金はお金が好きな人のところに集まってきます。
だからと言って我欲の塊になって違法行為をしてでもと思うと、丸源ビルのオーナーの様にお金も名誉も地位も失ってしまいます。
正当な方法で懸命に努力して得るお金を大事にして使う。
そうするとお金は仲間のお金を連れて帰ってきます。
真っ当な商売をしていればそのようにしてお金が増えて行くと思います。
皆さんはいかが思うでしょうか?
報酬制限法
世の中には優秀な人が各分野に沢山います。
とてもかなわないと思う人が私の周りにもいます。
その人達がその才能と努力で結果を出していくことは素晴らしいことであり、多くの人にいい影響を及ぼします。
アメリカではアメリカドリームといって、才能と努力があれば自分の夢が叶うという土壌があります。
それにより過去多くの人が地位と名声と富を得てきました。
ただ、その富が数%のスーパーリッチと言われる人達に集中しているのは問題です。
昨日のニュースでスイスで行われた国民投票で企業幹部に対する高額な報酬や退職金の支払いを制限する提案が、賛成多数で承認されたという報道がありました。
これは画期的なことと思います。
スイスのこの報酬制限はこれから各国に大きな影響を及ぼすのではないでしょうか。
私は、頑張った人にはそれ相応の報酬があっていいと思っています。
ただそれが我欲で富の取り放題、無制限になっていることには疑問を持ちます。
稲盛和夫さんは「自分が持っている才能は、たまたま自分が与えられたもので、それを私物化してはいけない。」と言います。
成功した結果として地位と名声はいくらあってもいいでしょうが、お金はそれなりに制限されるべきです。
自分の才能で得たと富は、そうでない人達へ分け与える役目があります。
そう考えると、スイスの報酬制限は道徳的で先進的な法律だと思っています。
自分を育てる
先週は「人を育てる」「社員を育てる」について書きました。
今日は「自分を育てる」についてです。
自分を育てるは「自分磨き」です。
磨くというと「男を磨く」「女を磨く」という言葉をが浮かびます。
最近は「草食系男子」「肉食系女子」という言葉が流行っています。
「男を磨く」「女を磨く」とは逆の状況の様な気がします。
昔お年寄りに聞いた話です。
男は生まれつき女々しい者。女は生まれつき男っぽい者。
それだからこそ小さい頃、男の子は「男らしくしなさい!」とか「たくましくあれ!」言われて育ちます。
女の子は「女らしくしなさい!」と言われ、「ひな祭り」があり、「御ままごと」「お人形遊び」を教えられます。
最近は男と女の区別は差別につながると思われるあまり「男らしくしなさい」とか「女らしくしなさい」と言われなくなってきました。
その為、男は本来の女々しさが、女は男らしさが表に現れてきたのではないでしょうか。
私は少し古い人間なので、「男らしく」「女らしく」ということは大事にしたいと思っています。
「男らしく」で思い出すことがあります。
私が中学生の時、思春期でおしゃれに気を使っている頃、父親から言われたことがあります。
「男はおしゃれをして、見た目ばかり気にしてはダメだ。
中身のある人間になりなさい。
見た目が良ければそれでいいという女性ではなく、例えば一流のクラブのママ、料亭の女将さん、そんな人に素敵な人だと思われる人間になりなさい。
ママや女将さんは多くの男性を見ているので、見た目でなくその人間の中味を見抜くことが出来る。
そのような女性に惚れられる男になりなさい。」と言ったのです。
父親はその頃はまだ若く元気だったので、色々なクラブや料亭に行って「経験」を積んだのでしょう。
私は未だ一流のクラブや料亭に入ったことが無いので分かりませんが、父親から言われたこの言葉はズーと持ち続けていました。
「自分を育てる」「男を磨く」は大事なことと思っています。
貝原益軒
何年か前、小泉さんが首相の時、施方針演説で「米100俵」の話をしました。
今の首相の安倍さんも施政演説の中で貝原益軒の逸話を紹介しています。
テレビや新聞でも取り上げられたのでご存知の方も多いと思いますが少し紹介します。
江戸時代の学者である貝原益軒はボタンの花を大事に育てていました。
ある日外出しているうちに留守番の若者がその花を折ってしまいます。
怒られると心配する若者に益軒は「自分がボタンを植えたのは楽しむためで怒るためではない」と言ったのです。
何のために植えたかという初心を忘れない。
安倍さんは政治家に対して初心を忘れるず、志を失うなということを言おうとしたのです。
私はこの貝原益軒の話を聞いた時、少し別のことを感じました。
それは益軒の若者に対する優しさです。
過ちを既に悟っている者に、あえて怒る必要はないのです。
それをせず、「ボタンを楽しむために育てている」ということを若者にあえて言うことで、怒る自分の心を別次元に移しています。
怒るということはあまりいい結果は生みません。
また怒らないように我慢をするとストレスになり、ある時爆発してしまいます。
お釈迦様は「怒る自分の心を見ることで怒るむなしさを知りなさい」と言います。
それにより怒りが収まっていくと言うのです。
本当は怒ってもいい状況から、益軒は花を楽しむという次元に気持ちを置き換えることで、怒らないですんだのだと思います。
怒る意味を消しています。
なかなか出来ないことです。
私も見習いたいものです。
特別な存在
「私は褒められると伸びるタイプ」と多くの人が言います。
そう言う私もそうです。
以前、家内に「私は褒められると伸びるタイプなので褒めて!」と言ったことがありました。
その時、家内も「私もそう、もっと褒めて!」と言われました。
自分は褒めてもらいたいのに、人にそれほどしていない。
自分のことばかりに気が行き、人にはそれが無い。
自分は「自己中心的」だと思ったものです。
昔から「自分がして欲しいことを人にして上げなさい」と言われたものです。
子供を育てる。社員を育てる。
同じことが言えます。
どちらもその人が大切な人なんだと思わせることがあってはじめて自信を持ち、行動します。
キャンディーのテレビCMでこんなのがありました。
「私のおじいさんがくれた始めてのキャンディー 。
それはヴェルタースオリジナルで、私は4才でした。
その味は甘くてクリーミーで、こんな素晴らしいキャンディーをもらえる私は、きっと特別な存在なのだと感じました。」
「私は別な存在として認められる」
そう意識するとモチベーションが上がります。
人を育てることは、それほど難しいことではなく、褒めて、特別な存在だということを伝えることなでしょうか。
家内は「特別な存在」なのでもっと褒めて行こうと思っています。
在宅勤務
ネットを見ているとアメリカのヤフーが社員の在宅勤務を禁止すると発表したようです。
このことでネット上では色々な意見が飛び交っています。
アメリカでは在宅勤務が増えていて、05年からの6年間で73%も増加したと言う情報もあります。
日本でも「ノマド」という特定のオフィスを持たないで仕事をする人も増えています。
1人経営の場合は「ノマド」でもいいでしょうが、会社となるといろいろ問題もあるようです。
ヤフーは在宅勤務廃止について「現時点でヤフーにとって何がベストかという問題だ」とするコメントを出しています。
時間と場所に束縛されず、自由に仕事をしたい。
成果を出せばそれでいい。
そのような考えもあるのでしょう。
でも「成果を出させばそれでいい」という考えには私は少し違和感を感じます。
会社の目的はただ単に利益を上がればいいというのではないはずです。
社員に対しても単に成果・結果を出せばいいというのも違います。
以前日本の会社でも採用していた「歩合制」という営業の成果に見合った手当を出すという給料制度がありました。
今でもまだあるかもしれませんが、そのような会社は伸びません。
社員を会社の利益を出すための「道具」として使っているだけです。
会社は社員が働きがいのある職場作りに力を入れ、会社の生産性を上げてこそ永続的な利益集団になれるのです。
そういう意味でヤフーも当り前の会社になったのかと思っています。
IT関連の会社では目新しい、面白い職場環境を作っているところもあります。
でも会社はやはり基本を外してはダメなのだということがこのヤフーの在宅勤務禁止ということで再認識しました。
社員を育てる
昨日は「人を育てる」と題してブログを書きました。
今日は「社員を育てる」について書きたいと思います。
「社員を育てる」は社員教育に似ていますが若干違います。
社員教育は業務上で必要なことを学習させることです。
仕事で使う「道具」を教えるようなもの。
でも仕事をする上で大切なのは「道具」の「使い方」と「考え方」を習得させることです。
お客様が来店した時「いらっしゃいませ」と言うのはマニュアル通りです。
マニュアルにあるからただ言うのと、お客様の目を見てニコッと笑ってするのとでは違います。
なぜお客様の目を見てニコッと笑って挨拶するのかと言うと、本当に来ていただいて嬉しいと思うとそうなります。
嬉しいと思うような社員が生まれるよう育てることが「社員を育てる」と言うのです。
マクドナルドの原田社長がテレビで言っていました。
「若い人がアルバイトでマクドナルドに来るのは給料ばかりでなく、それ以上に自分を成長させてくれることに対する期待があるから」と。
「人として育てられる」ことに期待しているのです。
人を育てると言うと以前にも書いたかもしれませんがお客様へのアンケートの取り方で違ってきます。
お客様サービス向上を目的にアンケートをいただくのだすが、多くのアンケートの質問に「何かご不満、お気づきの点がございましたらお書きください」と言うのがあります。
これはダメな質問です。
お客様がその店のサービス等に満足している時、「何か不満がありますか」と聞かれれば、あえて不満なことを探し出そうとします。
折角満足しているのにあえて不満を生み出しているのです。
お客様が書いた不満事が店の責任者を通して担当者に行き、叱られます。
結果社員のモチベーションは下がります。
それよりアンケートの質問を「ご満足いただけた点をお書きください」とすれば、お客様は〇〇さんの応対が良かったなどとお褒めの言葉を書いていただけます。
それを読んだ店の責任は喜び、〇〇さんを褒めてくれます。
〇〇さんも喜び、より自信を持って仕事が出来るようになります。
これも人を育てる、社員を育てることになります。
自分の仕事に自信を持たせ、やりがいを持たせる。
「社員教育」=「人間教育」なのでしょう。
お伊勢参り
先週末、伊勢神宮にお参りに行ってきました。
昨年もちょうど2月に行き今年が2回目。
末娘と名古屋で待ち合わせをし、親子3人の旅です。
今年も3人でお参りが出来たことに感謝。
外宮には豊受大御神様が祭られて、商売、家内安全など個人的なお願いを叶えていただける神様。
内宮には天照大御神様が祭られ、国レベルのお願い事をする神様。
ともに心をこめてお参りしてきました。
今年は式年遷宮の年。
平成17年から準備が進められ、今年10月頃に天照大御神様が移られる「遷御」が行われます。
お参りの帰りには志摩にも行き、久しぶりに温泉につかり、部屋の窓から見える英虞湾の夕日を見ながら家族3人で談笑。
感謝感謝の旅でした。
男性と女性の違い
昨夜ワールドカフェに参加してきました。
札幌男女共同参画センターが主催する「ワタシもまわりもしあわせにする仕事づくり」という題のカフェです。
参加者はほとんどが女性。男性は2割か3割ほど。
1グループが5~6名ほどで2時間ほどグループ討議しました。
働く幸せという題で話し合われたのですが、話の中で納得したことがありました。
男性と女性の思考と行動が違うことです。
「そんなの当たり前」と言われるは分かっているのですが・・・
男性は考え方も行動も直線的。
1つのことに突き進みがち。
それに対して女性は丸い円の様な考え方。
周りを大事にし、全方位的な気の配りをします。
男性と女性の違いがもとで誤解も生まれることがあります。
「俺がこんなに一生懸命仕事して頑張っているのに、分かってくれよ!」という男性の思い。
「もっと家庭を大事にして、もっと健康を考えて」と全方位的なことを考えてほしいというのが女性。
男性と女性が一緒に生活する上でも、また仕事をする時にもその違いを認め合わなければ上手くいきません。
違いを認め合ったうえで、それを生かしていく。
過去、女性の社会進出意識が今以上に高まっていた時はなかったと思います。
これからどんどん女性が「社会の思考方法」を変えて行くことでしょう。
分かっているようで分かっていなかった男女の違い。
私はまだまだ経験不足です。
子供を育てる
昨夜テレビを見ていたら東京のお母さん達が街角で保育施設を増やすようプラカードを掲げていました。
仕事をしたくても子供を預けるところが無いという切実な思いが伝わってきます。
このお母さん達と子供、そして保育施設について、私の「思いつき」を書きたいと思います。
誤解を恐れずに書くと、働くお母さんは大きく分けると「仕事がしたいお母さん」と、「生活のために働くお母さん」がいます。
まず保育施設には、仕事がしたいというお母さんの子供を優先的に預けることが出来るようにします。
仕事は生活のためにするというお母さんには子供手当を沢山出して上げます。
現在、子供を保育園に預けると、1人につき1カ月20万円近くの公的資金がかかっています。
親が負担する月謝以外にかかっています。
建築費、水道光熱費、人件費等を子供の数で割るとそうなります。
パートで時給1000円、1日8時間、1月22日間働けば給料は17万円近くになります。
手取りは15万円位でしょうか。
であれば15万円を子供手当として出します。
仕事がしたく、月に15万円以上稼ぐことのできるお母さんには保育施設を優先的に提供します。
そうでないお母さんには子供手当を充分にする。
そうすれば今以上の保育園は作らなくて済みます。
また専業主婦が増えれば子供にしても、家に帰ればいつもお母さんがいてくれるという安心感があります。
そして子供手当が充分にもらえるとなると子供を産もうと思う女性も増えるかもしれません。
以上の話は極論、暴論と思われるかもしれませんが、子供を育てるということと、仕事をしたいというお母さんの思いを実現させる1つの方法かと思います。
農業を成長産業に
今朝の新聞の1面に「農業を成長産業に」と書かれていました。
TPP参加の環境作りとして出されたものでしょう。
これは賛成です。
また農業ばかりでなく漁業も成長産業にしてほしいと思います。
週刊ダイヤモンドの資料ですが、漁業に就いている人は22万人。
その内60歳以上が46%、70歳以上は22%と高齢化。
その上、後継者がいるのはわずか18%です。
その衰退の原因は漁業者の平均年収が250万円で低いことにあります。
漁業国として有名なノルウェーとの比較ではノルウェーは平均900万円です。
また、ノルウェーは39歳以下の就業者が全体の40%を占めています。
漁業はノルウェーの基幹産業になっています。
日本の漁業もノルウェーのように成長産業になれるのです。
また、ノルウェーの漁業は株式会社形式がほとんどです。
それに対し日本は大部分が個人経営。
日本では株式会社参入阻害の大きな障害に漁業組合があります。
漁業組合は漁業権の割り当てを管理しています。
漁業権を漁民が権利として持つので、新規参入者が入り込めないのです。
漁民が高齢になり、漁業に出れなくても権利は譲りません。
この構造は農地法で守られている農業と同じです。
漁業も農業も、50年以上前に弱者保護を目的として作られた規制がまだ機能していて、そのため進歩していないのです。
保護産業は成長産業にはなれません。
規制を撤廃してこそ地力が生まれます。
農業と共に漁業も日本の成長産業になれる可能性が大です。
日本より国土が狭いオランダが農産物輸出ではアメリカに次いで世界2位です。
日本は海に囲まれ、領海と排他的経済水域を合わせた広さは世界第6位です。
成長の可能性を広げるには規制撤廃が第一です。
それは政府がする仕事。
今こそ安倍政権の真価が問われます。
経営者体験発表
先週の土曜日に盛和塾の集まりがありました。
東北北海道各地にある盛和塾から選出された経営者の「経営体験発表」です。
昨年に続き2回目です。
発表する経営者の中には70歳を越す女性経営者、38歳の若い経営者など8人の発表でした。
私は審査員として前列に座り、発表者1人25分の持ち時間、8名合計200分真剣に聞きました。
各経営者がいかに苦労して会社を経営しているか、迷った時、悩んだ時の思いが話されます。
経営に向かうその真剣さと努力に、頭が下がるとともに感動のあまり涙ぐむこともありました。
各発表が終わると世界大会等の大会で稲盛塾長の前で発表する人を2名の人を選出しなければなりません。
8人の発表の優劣は付けにくかったのですが、最終的には「フィロソフィの浸透」「学びの実践」「経営数字の説得性」の3点に絞って決められました。
発表会後の懇親会でその2人の名前が告げられました。
その2人は壇上に上がり一言話すのですが、2人とも感極まって声が出て来ません。
色々なことが思い上がってきたのでしょう。
2人の内の1人は私達札幌の仲間の経営者です。
彼も泣いていました。
早速奥さんに報告したそうです。
「今頃社員達と祝杯をあげているみたい」と言っていました。
真剣に経営に向き合う経営者達。
そのような人達と時間を共有できたことに感謝します。
イチロー選手
イチローという選手は彼の生き方で色々なことを教えてくれます。
先日の日経新聞に半ページを割いてイチローのことが書かれていました。
昨年イチローはシーズン途中からヤンキースに入って活躍しました。
その時のことが書かれています。
ヤンキースでプレーをする時、ヤンキースの「ために」戦うというのではなかったそうです。
「何かのため」というのは聞こえはいいですが、それは時には思い上がっているように見えると言います。
誰かを「思い」、何かをすることは、見返りを求めることも無く、そこに愛情が存在するので不幸な結果になることは少ないように思うと言います。
そろそろWBCが始まります。
イチローはどんな「思い」で過去2回のWBCを戦ったのでしょう。
そのイチローも前回の大会では苦しい思いをしたそうです。
今でも思い出したくないという打席があると言います。
決勝戦、対韓国戦。延長10回2死2、3塁の時イチローが打席に立ちました。
イチローはそれまで不振が続き打てていません。
「敬遠ならどんなに楽だろうと思った。この打席で結果を出せなければ、今までの僕はすべて消されると思った。」
彼はそのような恐怖を味わいながら2塁打を打ったのです。
その代償は大きく、胃潰瘍を患い、大リーグで初めて故障者リストに入るということもありました。
「今度どんな場面があっても、あの打席以上のことは無いと想像している」と言いいます。
天才と言われ、また努力の人とも言われるイチローも、悩んで悩んで、時には命を削るようなことを経験して今があります。
そして一流の人は真っすぐで当たり前と言われることを大事にして生きています。
そんなことを思ってこの新聞の記事を読みました。
この記事は永久保存版で仕舞っておきます。
直言
昨夜、起業経営者仲間の会合があり飲んできました。
今朝は少し二日酔いです。
飲んでいると色々な話が出てきます。
参加者の1人Aさんが自分のお店で企画している内容を説明した時、Nさんが「Aさんそんなことを考えるより本業を考えることが大事だ」とズバッと言いました。
楽しい雰囲気が一瞬止まりました。
その時、Aさんは「ありがとうございます。よく言ってくれました」と応えたのです。
それでまた和やかの雰囲気に戻りました。
本音を隠して同調するのはその人の為にならないのです。
Nさんのように正しいことを言ってあげるのは大事です。
それは皆分かっているのですが、間違いを指摘するのは言いにくいものです。
いい顔でいたいと思うのです。
私もその1人でした。
反省です。
ただ、今回のようにAさんが「ありがとうございました」と受け入れてくれたからいいのですが、そうでなければ喧嘩になってしまいます。
相手に話して分かってくれるように話の流れや雰囲気を整えてから言う。
その手順は必要だと思います。
それにしても昨夜の飲み会は楽しく有意義なものでした。
テレパシー
先日電車の中で新卒者向けの合同会社説明会のポスターが貼ってありました。
この時期、就活の終盤なのでしょう。
就職試験の関門の1つに面接があります。
面接試験官になった人なら経験あると思いますが、面接者が部屋に入ってきた時から30秒もたたないうちに、その人がなんとなく分かるということがあります。
試験官がする質問は、最初受けた「感じ」を確認をする作業の様なことになります。
この「感じ」は結構当たっています。
これはテレパシーなのでしょうか。
人は無意識の内にテレパシーで人と通信していると、私は思っています。
1つの例を上げます。
東京渋谷のハチ公前の交差点はスクランブルになっています。
信号が青になると前、斜め右、斜め左から人が押し寄せて来ます。
その数は数百人。
そんな多くの人達がほとんどぶつかりもしないで渡って行きます。
声を出して「私は右に避けますのであなたも右に避けてください」等言わなくてもぶつからないのです。
不思議だと思いませんか?
無意気の内にテレバシーで交信していると思います。
だから、人込みの街でテレパシー使いすぎ、家に帰ってくると「人疲れ」を覚えるのです。
「目は口ほどにモノを言う」と言われます。
テレパシーは存在するのです!?
決断
ソフトブレーン(株)創業者の宋文州さんのブログをいつも読んでいますが、以前にいいことが書かれていたのでご紹介します。
大昔中国に大禹という帝がいました。
彼は治水に優れた業績を残したと言われています。
彼の時代、それまでは洪水を防ぐのに土塁を高くしていました。
しかしその結果川底が高くなり決壊させてしまうことを彼は理解しました。
そこで住民や農地の少ない場所をあえて決壊させ、被害を少なくする方法を提案しました。
しかし決壊させられる場所の住民は反対します。
そこで大禹はリーダーシップを発揮して彼らを説得し実行しました。
決断という漢字はダムの央の一部を無くして水を流す。それは決断の決の字です。
そして政治の政は正しい文化の意味で、治は台を築いて水をおさめる意味です。
政治家はいつの時代も決断を迫られます。
皆にいい顔はできません。
反対者を説得し決断することが重要です。
同じことは経営者実も言えると思いながら、宋文州さんのブログを読みました。
頑張る人が報われる
昨年末の総選挙で政権が変わってから経済環境が変わってきました。
円安・株高で企業の収支が改善してきました。
日本の企業の業績が落ち込んでいたのは企業の努力不足というより、極端な円高に原因があったということになるのでしょうか。
今度日本がクリアしなければならないことはTPP問題です。
私は日本は早くに参加するべきだと考えます。
極端に言えば、日本は貿易によってのみ成り立つ国です。
各企業が努力の末収益を上げ、経済大国といわれるようになりました。
TPP参加に反対する理由の1つに農業問題があります。
日本の農業が壊滅的被害を受けるとJAが中心となり反対しています。
日本の農業は過去、多くの規制で守られてきました。
その1番の規制は農地法です
1952年に施行された農地法は農地改革の成果を維持することが目的のため、農地の売買や賃貸借を制限してきました。
そのため規模の拡大を難しくしてきた。
2010年までの50年間で米農家の生産規模拡大は2倍に満たないのです。
耕作放棄地の面積は40万ヘクタールになり20年間で1.8倍に増えています。
そして農業人口は251万人で65歳以上が6割。
若い人が農業で起業したいと思っても農地法のために出来ないのです。
また、日経新聞の記事によると、JA(農協)がTPP反対の最大の理由は農業保護でなく、共済事業を守るためだとも書かれています。
JAの総事業利益は1兆9000億円(2010年度)あるそうです。
その内、融資や共済といった金融事業が66%を占めています。
一般の保険会社は生命保険と損害保険の兼営が禁止されていますが、共済には兼営規制がありません。
法人税も共済は優遇されています。
日本がTPPに加入すると競争環境を平等にするように求められる可能性が高いのです。
JAグループにとって共済事業は利益全体の4分の1を稼ぎだすところです。
農家が作った農産物を販売したり、農家に農機具を売ったりする農業関連事業よりその比率が高い。
JAのTPP反対論の後ろには共済事業に議論が及ぶのを避けたいとの思いもありそうです。
日本の農業はそれほど非力でしょうか。
野菜は現在関税がほぼないですがほとんどが国産。
日本が不作のときに輸入品が入ってくるくらい。
日本消費者は目も口も肥えているのでいいものを選びます。
力ある農家は安全でおいしい農産物を作り海外にも売りたいと思っています。
牛肉について言うと、アメリカ牛肉輸入規制が1日より緩和されました。
それと一緒に、EUも日本の牛肉輸入規制を解除しました。
おいしい和牛は海外でも人気です。
アメリカ牛肉の輸入が増える一方、和牛の輸出が増える可能性があります。
どこの業界でも頑張っている人と、規制に守られ安穏として頑張らない人がいます。
頑張る人を応援し、頑張らない人には退場していただく。
これからは「本当に頑張る人が報われる日本にならなければ」と思っています。
経営を見るメガネ
昨夜「競争戦略論」の勉強会がありました。
北海道大学の平本教授をお迎えし、講義をしていただきました。
1時間ほどの講義の後、質疑応答。
中身の濃い勉強会でした。
この勉強会については以前にも書きましたが、私が勉強したいという自分勝手な思いだけで、参加者を集め平本先生にお願いに行き開催することが出来ました。
競争戦略というと、30年ほど前にマイケル・ポーターが書いた「競争の戦略」が有名ですが、今回勉強している「競争戦略論」という本はそれも含めた4つの視点で経営分析しているものです。
「ポジショニングアプローチ」「資源アプローチ」「ゲームアプローチ」「学習アプローチ」に分類されています。
この4つのアプローチが業界や経営を見る時の「メガネ」になると平本先生に言われたことが、「そうなんだ!」と腑に落ちました。
次回は来月に開きますが、その時は私が講師役になり皆さんにお話をします。
私の担当は「ポジショニングアプローチ」についてですが、これから徹底的に理解し、それを分かりやすくまとめることになります。
身に付く勉強。
大変そうですが、また楽しみでもあります。
イギリスへ行く
年の8月に開かれる娘の結婚パーティ参加のために今からその準備しています。
イギリスまでの航空券とホテルの手配も親族10人近く行くとなると大変です。
旅行パックを利用することは出来ず、また添乗員もいません。
あえて言えば私が添乗員みたいなもの。
この添乗員は英語は出来ません。
イギリス本島の南に位置するのワイト島というところまでフェリーを使ってまで行きます。
嫁いだ娘と打合せをして進める予定ですが、口やかましい私の妹達が大乗り気で前途多難な予感がします。
私1人の旅行ならどこでも行ける気がしますが、団体旅行となると不安がよぎります。
でもJALにいる知人がバックアップしてくれているので助かっています。
今日はホテル手配のために旅行会社に行きます。
それにしてもやはり英語の勉強しないといけないでしょうか?
税金を支払う
会社経営をして、その結果として利益が出ます。
その利益から法人税を支払います。
日本の法人税額は年間約8兆円位と言われています。
バブルの時でさえ10兆円位でしょうか。
2010年度の法人税を実際に支払った企業は全企業の27%にとどまっているそうです。
残りの企業は赤字です。
また納税された法人税の65%は資本金が1億円を超える大企業です。
日本の中小企業が苦戦している様子が分かります。
ただ、企業の中には節税と称して税金を支払わないようにと、余計なものを買ったり、給料を増やしたりしているところがあります。
そのような会社は内部留保が生まれませんから、何か衝撃があるとすぐ会社が倒れてしまいます。
稲盛和夫さんも「税金は経費として考えよ」と言っています。
支払うべきものとして支払い、確実に内部留保を厚くしていかなければ会社維持は出来ません。
経営者の意識を変えることが第一。
そして税金を支払うことの出来る会社になることです。
酸化と糖化
最近身体の調子がいいです。
半年前から血液検査をする機会が3度ほどありましたが、すべてが基準値以内。
血糖も、尿酸も、肝臓も大丈夫。
以前はいくら節制しても肝臓の数値γ-GTPは基準値をはるかに超す数値でしたが、これも基準値以内です。
何をして数値が良くなったかというと、思い当たるのが炭水化物。
半年以上前から体重を落とそうとして、炭水化物ダイエットを始めました。
ご飯、麺、芋類はなるべく食べないようにするだけです。
体重も落ちましたが各数値も改善されました。
お酒はそれほど節制していないのにγ-GTPが落ちたのにはびっくりです。
だいぶ以前の新聞のコラムに「酸化と糖化」という記事が載っていました。
体が「酸化」して有害な活性酸素が体の細胞を傷つけてしまうというのは知っていましたが、糖化というのは知りませんでした。
「糖化」とは食事から摂取して体内で余った糖分が、体内のタンパク質にベタべたくっついて、タンパク質を劣化させるというものです。
「糖化」が進むとタンパク質が老化物質に変質します。
肌のコラーゲンが糖化してシミやしわの原因に。
血管のコラーゲンが糖化すると動脈硬化。
骨のコラーゲンが糖化すると骨粗鬆症。
現代はいろいろな食品に糖が沢山含まれています。
そんな時代だからこそ、あえて糖を控えることは健康、特に老化防止には大切なことかもしれません。
皆さんも炭水化物ダイエットしてみませんか?
健康にいいですよ。
Mac
昨年末に買ったMacノートを今日から私のメインパソコンとして使います。
MacにWindows8を入れてWindows環境で使おうか、それともOffice for Macのソフトを入れ、ワード、エクセル、パワーポイント使用中心に限ろうかと考えながら、結局Office for Macを入れ、昨日データーを移しました。
若干使い勝手はまだ慣れていません。
deleteキーが電源キーのすぐ下にあるので、押し間違え電源が切れそうになったりします。
また、会計ソフトなどは依然Mac対応でないので、旧パソコンもまだ使ってゆきます。
Macのパソコンを買っていいと思った一つに、one to oneサービスというサービスがあります。
年間9800円の費用で、マンツーマンでパソコン操作を教えてくれます。
これは大変ありがたい。
今回のデーター移動も、本を読んで試行錯誤するより、聞いてその通りしたらあっけなく終わりました。
パソコンが初めての人やwindowsから乗り換える人にとっては優れたサービスです。
アップルストアー独自のサービスのようです。
ビックカメラに行って、Mac購入後のサービスを聞いてもそのようなサービスはありませんでした。
アッップルという会社がソフトもハードも提供して独自の囲い込み戦略だからできるサービスであり、それが成功しているのでしょう。
今週から北大の平本先生を迎えて経営戦略、競争戦略の勉強会が始まります。
優れた戦略を学び、それを実際に参加者各自の経営に生かせることを目的とします。
Macの戦略もいい教材になりそうです。
カニ三昧
先日、今年年最後の新年会がありました。
飲み食いがが一段落した頃、よくあるビンゴゲームの時間。
私は今までビンゴゲームではそれほどいいモノをもらったことが無かったのですが、今回は違いました。
一番最初に「ビンゴ!」だったのです。
どよめきと羨望と嫉妬の視線を浴びながら賞品をもらいました。
箱に入ったモノで、上にカニと書いてあります。
カニ缶かな?と思ったのですが、3杯のカニでした。
ズワイガニ、タラバガニ、毛ガニです。
家で開けて驚きと、戸惑い。
私も家内もそれほどカニは好きではないのです。
誰かに差し上げるにしても生モノ。もしかしたらと思い断念。
次の日から1杯ずつ私1人で食べるのが役目。
昨日やっと最後の毛ガニを食べてホッとしました。
カニは美味しいのですが、殻から身を取り出すのが面倒。
それでも熱燗を飲みながら楽しみました。
カニ好きの人には羨ましがられるかもしれませんね。
最後の新年会で1等賞が当たったので、今年はいいことが沢山ありそうな予感がしています。
情報
今、日本の経済が変わってきています。
新聞や色々な本を読んでも、今後円安の方向は1ドル95~100円位と専門家が言っています。
もしかするともっと進むという人もいます。
円安によって大手企業の業績も大きく改善しています。
日本の企業が韓国の企業に負けていたのは円高の要因があると言われたのも裏付けされたようです。
デフレ経済からインフレ経済。
デフレ経済によってGNPも伸びず、各企業は値下げ合戦で体力を消耗してきました。
でもデフレ経済はお金が無くてもなんとか生きていてる世界です。
インフレ経済になれば生きて行くのが大変です。
頑張らないと置いて行かれてしまいます。
いつか日本は変わると言われてきましたが、今年はその年のようです。
モノの価値が変わります。その時どういう行動をするか。
今は自分の足場を固めるとともに、動き出す時です。
新聞やテレビで報道される情報は既に遅れています。
その前に得れる情報が重要になります。
今度ある会合で、定期的に情報交換をすることにしました。
その人しか知り得ない情報。
たとえ小さな情報でも生きた情報は貴重です。
眼を皿の様に、耳をそばだてながら仕事をする。
これから大事になります。
暴力
今年になって新聞やテレビの報道で暴力問題が取り上げられています。
「スポ根」という言葉が昔に流行りました。
スポーツ選手の根性を「たたきあげる」ことです。
この「たたきあげる」は叩き上げるになります。
叩くは即ち暴力です。
昔の日本の軍隊には「精神棒」と称する堅い樫の木で出来た棒があり、それで新兵をしごいていました。
精神を入れ直すと言ってイジメていたのです。
対等の立場で喧嘩をするのならまだ許せます。
決して刃向えれない、反撃されない状況の中で、「精神を入れ直す」とか「愛のムチ」などと言って暴力をふるう。
ただ「面白くない」という感情の発散でしかありません。
日本のスポーツ界すべてとは言いませんが、いままでシゴキや、暴力があっても見て見ぬふりをして来ました。
子供から大人、それもアスリートと言われる人達の世界まで「愛のムチ」が大手を振っています。
柔道がオリンピックで金メダルが取れなくなってきた原因は、暴力によって生まれた選手の委縮してしまった精神によるのかもしれません。
指導者等の「上の人」はもういらないでしょう。
本来「コーチ」と言われる対等な立場の人が、コーチングという手法で選手をバックアップする。
選手主体の体制に変わらなければならない。
スポーツ界全般が、今回の一連の事件で変わって欲しいと思います。
目を合わせる
先日知人と会った時、猫の話になりました。
私は昔から猫が苦手です。
苦手だということは猫も分かるようで、目が合うとジッと見つめて来ます。
私も見返します。
知人によると、猫はジッと見られると敵だと思うのだそうです。
そんな話の後に、新聞のコラムで京都大学の山極寿一教授の「目を見つめる」ことの話が載っていました。
教授は霊長類研究の第一人者です。
教授によるとサルとゴリラやチンパンジーなどの類人猿とは違うそうです。
普通サルは散らばって食事をとるそうです。
餌の奪い合いになるのを防ぐためです。
ボスにとられないように隠れて食べます。
一方ゴリラやチンパンジーの類人猿は群れの中での上位と下位の区別はなく、順位が低い、例えば子供が上位の個体に近づいて食べ物をねだることは常態化していとのことです。
その時対面して相手の目を見つめることでコミュニケーションをとっているようです。
動物の社会では対面して相手を見つことは敵対行動で、相手を威嚇することに繋がるのです。
類人猿はそうでなく、複数の個体が仲良く対面して餌を食べます。
人間もこの行動特性を引き継いで相手の目を見ることでコミュニケーションをとっているようです。
テーブルを囲んで食事を楽しくとる習慣になっています。
「目は口ほどにモノを言う」とコラムは結んでいます。
でも目は口以上にモノを言うということはあるのではないでしょうか。
だから自信の無い人は目を合わさないように下向き加減に歩きます。
自信ある人は胸を張って歩きます。
だから第一印象で人が分かるということにもなるのでしょう。
教訓
私もこれからは猫と会っても、知らんぷりして目を合わさないようにします。
こども絵画展
昨年の3月のブログに日米の子供達が描く桜の絵の交換展示会の話を書きました。
ワシントンの桜祭りに合わせたイベントとして実施されました。
東京三鷹市にあるSOHO CITYみたかフォーラムの理事長河瀬さんからの依頼で協力し、札幌の子供たちの絵を送りました。
先日河瀬さんから今年も協力を依頼されました。
今年は「日米の子どもたちによる国際交流絵画展プロジェクト2013」という名前で、去年と同様に日米の子供たちの絵を電子画像にして相互に送り、ワシントンと三鷹市で交流絵画展が実施されます。
昨日、昨年協力したお礼としてアメリカの責任者であるカークパトリック氏からお礼のカードとワシントンポトマック河畔のマスコット「パドルザビーバー」の人形、そして缶バッチが送られてきました。
今日私は絵を描いてくれる子供たちが通う絵画教室に打ち合わせに行く予定になっています。
この人形と缶バッチを差し上げるつもりです。
互いに、未だ見ぬアメリカの子供と日本の子供が互いを感じながら絵を描く。
子供たちの夢が広がりそうな気がします。

守・破・離
今朝の日経新聞の「春秋」のコーナーにスポーツ選手のことが書かれていました。
今年の箱根駅伝で去年の惨敗から1年で優勝した日体大と、大学選手権で4連覇を果たした帝京大ラクビー部の選手です。
どちらも毎日、普通の決まりごとをキチンとこなすことで共通していました。
帝京大ラクビー部の生活態度の良さ、礼儀正しさが際立っていると書かれています。
日本電産の永守社長が常に唱えている、6Sと言われる「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」「作法」のままです。
どの世界でも共通することです。
ただこれだけではそれなりの人間には成れても、殻を破り、化けることは出来ないと私は思います。
基本的な6Sを守り、身についた上でそれを破る。
「守・破・離」になります。
人は基本的なことは守りやすいです。
教えてくれる人がいて、言われた通り、それさえしていれば問題ないという安心があります。
しかしそれを破った先にある世界は自分で責任をもって歩まなければなりません。
未知の世界です。
だから多くの人が踏み出せないのです。
逆に言うと、踏み出す人が少ないからこそ成功の可能性が高いとも言えます。
だから破り踏み出そうとします。
でも破れない。
たとえ1つ破っても、その外にまた殻があります。
そのような悩みを背負いながら年老いてゆきます。
歳をとって
歳をとると寛容な人が多いと言われます。
落語の世界でも登場する大家さんや御隠居さんは知識が豊富でモノ分かりのいい人として描かれています。
でも本当はモノ草になり、考えること行動することが面倒になり、投げやりになり、人任せになったところが寛容に見えるだけなのかもしれません。
また人の心には本能があり感情があります。
それを外側から理性で抑えています。
歳をとるとその理性の部分がはがれ落ち、感情がむき出しになってきます。
そしてもっと歳をとり痴呆になると、本能が出てきます。
歳をとっても理性を持ち続けるには、自分が輝くことをし続けることです。
仕事の第1線から抜けても、自分の好きなこと、趣味でもトコトン追求し、人から一目置かれる存在になるのです。
出来ることなら仕事をし続けることがいいでしょう。
そんなことからも、私は団塊の世代には身の丈で起業することを勧めしています。
記憶力アップ
今朝の新聞に「おなかがすくと記憶力アップ」という記事がありました。
東京都医学総合研究室のチームが発見したそうです。
空腹時に血糖値が下がりインスリンの出る量が下ってくると、記憶に必要なたんぱ質が活発に働くそうです。
なので、朝起きて朝食前に勉強するとより効率的に記憶できるかもしれないと書いてありました。
納得します。
私は毎朝4時30分起き、眠い目をこすりながら本を読んでいます。
不思議とその読んだ本の内容が良く頭に残っています。
今までは寝起きで、眠たいまま本を読むので、「一種の睡眠学習法かも?」と思っていたのですが、そうでなく空腹によるものなのですね。
実感していますので、この発見は納得します。
朝はとても静かで、集中出来ます。
皆さんも「朝勉」始めませんか?
論語読みの論語知らず
「論語読みの論語知らず」という言葉があります。
折角勉強してもそれを理解するだけで、それが実践出来ていなことを言います。
先日、長年続く勉強会で学んでいる人と話した時、「〇〇さんは勉強会でいいことは言うけれど、実際の行動はどうなのかね。生かされているとは思えないね」という話がありました。
確かに言われてみるとそう見えます。
本人は気付かず、自分は勉強を生かした経営をしていると思っているのかもしれません。
でも傍目から見れば違うのです。
会社の中で、社長は「こうあるべき論」を説きます。
言っていることは正しいのですが、していることが違っている。
社長が「言行不一致」なのです。
それが社員が言うことを聞かない原因になっているのに、社長はそれに気付かない。
多くの会社で起きていることです。
「毎日の反省」が大切です。
また、社長は常に上の方から見る「俯瞰視点」を持たなければなりません。
自分の言行を客観的にみるクセを付けるのです。
「論語読みの論語知らず」という言葉。
改めて私自身にも置き換えて考えてみます。
競争戦略
色々な会社を見ていて思うのですが、優れた経営をして、しっかりした基盤を築き上げた会社は、初めから確固たる経営戦略を持っていたのでしょうか。
私はそうではないと思います。
創業時は日々の経営の中で「昨日より今日良くなる」「お客様が求めているモノは何か」をコツこと追求していく結果が大きな利益を生み、優れて経営と言われています。
そして会社が少し大きくなってくると、今度経営者は迷います。
どの方向へ進むべきか、新規事業はどうするか、既存事業はどうするか。
そんなん時、「経営戦略の本でも読もうか」と思ったりします。
でも経営戦略の本を読んでも、なかなか自社の経営に生かせるための道具となる「思考」を明確に書いている本が少ないようです。
それは「手法」を書いた単なるHow TO的な本を言っているのではありません。
経営戦略といわれる多くの本は成功した企業の分析をし、優れた点、産業環境の有利さ等を上げています。
素晴らしい先見性や、手法について分析し述べているだけです。
でもそれは「後追いの調査結果」でしかないのです。
具体的に何を持って自社のすすむべき方向を見つけ出すか。
それに近い理論をを学ぶことだと思います。
30年前にマイケル・ポーターが書いた「競争戦略」という本があります。
「競争戦略」という言葉はこの頃から言われるようになりました。
この本のことは以前にも書きましたが、読み直して見ると改めていい本だと思います。
その他にマイケル・ポーターが書いた「競争戦略」を基に、それ以外の戦略も加味し書かれた「競争戦略論」という本があります。
私は今この本に挑戦中ですが、読みやすくいい本です。
自社の戦略に生かせる「思考」が書かれています。
具体的に自社の経営に生かせる戦略を勉強をするには最適です。
一橋大学の青島教授と加藤教授の共書です。
お勧めします。
どん底
昨夜は盛和塾の新年会でした。
新年会では出席者各自から今年の抱負を数字を交えて発表していました。
そんな中、私と同じテーブルに座ったAさんから、「今日やっと解放されました!」と言ってきました。
昨年はAさんにとって最悪の年だったそうです。
Aさんの会社は仕事のミスから何千万の負債を負い、それの返済するために大変な苦労をしたそうです。
自分の給料を何カ月も全額カットし、社会保険も払わず、蓄えも底を突くほどだったそうです。
自分の体の半分は「もうダメだ」、もう半分は「何としてでもやる」と心が揺れ動き、苦悩続きでした。
それを励ましたのは奥さん。
奥さんがいなかったらおかしくなっていたと言います
奥さんに感謝していました。
そのような中、今日大きな売上げが入り、その負債もわずかのところまで来て、目途がついたそうです。
余程嬉しかったのでしょう。
「今日は美味い酒飲むぞ!」と叫んでいました。
会社を経営していれば、大きい小さいはあるにしても、落ち込むことはいくらでもあります。
それでも経営者は果敢に挑戦していくのです。
だからこそ経営者はすごいと思うのです。
自分だけのことを考えれば辞ることはいつでも出来ます。
その方が楽です。
でも従業員、取引先そして家族のことを考えれば頑張れるのです。
頑張った後にこそ、仕事をやり終えた充実感・使命を果たした達成感を味わえれるのです。
それを味わってしまうと、経営者は社長を辞めれなくなります。
1度ならず、何度も落ち込むことがあっても、充実感・達成感があるからまた起き上がれます。
先ほどのAさんは今回のどん底を契機に大きく変わるかもしれません。
頑張れAさん!
葉書
自宅の私の机の上に万年筆用のインク瓶があります。
そのインクの色は「月夜」と「山栗」です。
以前に文房具店で見付けて買いました。
今までインクの色としては黒・青・赤の3色で、せいぜい青がブルーとブルーブラック位でしょうか。
私が買ったインクはパイロットが発売している、「色彩雫(いろしずく)」シリーズにあります。
このシリーズは24色あり、微妙に違います。
名前付けも「朝顔」「松露」「紅葉」等日本の色シリーズになっています。
私は最近葉書や手紙を書くことが少なくなりましたが、書く時はそれなりに気を使います。
相手に自分の気持ちを伝えようとすると、文面を考えるのと一緒に、どのような葉書で、どのような色のインクを使い、ワンポイントの絵を入れるか。切手もどんな切手を貼るかまで考えます。
以前に自分で作った篆刻も押したりします。
それは相手に自分の思いを伝える工夫です。
実際は受け取った人はそれほど思わなくても、出す側の思いです。
そんなことを思う人が増えているのでしょうか、最近は葉書や手紙の「出し方」の本が良く出ています。
文書内容の「書き方」の本は以前からありました。
でも今は如何に印象深い葉書や手紙が書けるかに力点が置かれています。
葉書や手紙は仕事でも大切な営業手段です
葉書1枚で仕事に繋がった事例は沢山あります。
私も経験しています。
その効力は絶大です。
現代は何でもメールで済ませる時代です。
そんな時代だからこそ、1枚でも心込めた葉書出してみませんか?
新刊本
私は時々何か面白そうな新刊本が出ていないか、よく本屋に行きます。
私が買う小説のは文庫本です。
本屋へ行って気付いたのですが、最近の新刊の文庫本は発売と同時に、「テレビ放映決定」という帯がついているモノが多いです。
そしてある作家さんの本に集中していことにも気付きました。
以前は本が発刊され、読んだ人の評判がよく、読者からの要望があってテレビや映画に映像化されました。
ところが今は「発刊即映像化」です。
もしかした「映像化のための小説なのか」とまで思ってしまいます。
内容があり、感動を与えるテレビや映画にはしっかりした放送作家や脚本家がいました。
今はその放送作家の代わりに小説家を使っているのでしょうか。
放送作家と小説家は本来は分けられるべきだと思っています。
小説に感動してもそれを映像で見ると違うイメージに出来あがっていて、がっかりすることが多いです。
テレビのドラマ作成の手抜きと出版社の部数拡大の思惑が一致して、「発刊即映像化」現象になっているのでしょう。
私はテレビのための小説を書いている作家の本は読みたいとは思いません。
読者を馬鹿にしているように思いますし、益々テレビ離れが起きて来そうな気がします。
骨董市
昨日は上京の折、白隠展に行ったことを書きました。
上京したついでに、もう1か所、仕事とは別に行ったところがあります。
それはビックサイトで開催されていた「骨董ジャンボリー」です。
骨董品はテレビの「なんでも鑑定団」の影響で注目されるようになりました。
私は古いもの、特に家具類が好きなので興味を持って行きました。
残念ながら家具類はほとんどありませんでしたが大変面白かったです。
何が面白かったというと、「骨董販売とは究極のニッチの商売だ」ということが実感できたことです。
他の人から見れば捨ててしまうような、汚いレース織の敷物が何万円も。
私が幼かったころ使っていた照明器具や割れた陶器までもが売られていました。
このようなモノも商品になるのです。
欲しいという人がいるから売っているのです。
色々な人がいるのです。
そしてこの骨董市に来るお客さんもユニークな人が多かったこと。
アメリカの漫画ベティちゃんを意識した服装の女性、明治の頃の様な黒い羽織を着た年配の女性、1本歯の高下駄をはいた小父さん。
この小父さんは元々背が高い人なので下駄をはくと背丈が2mを越していました。
多くの人は自己主張の強いオタクっぽい人。
この「骨董ジャンボリー」に出店した骨董店は600以上ありましたが、それで生活しているのですから、商売として十分成り立っているのだと想像します。
ニッチの商売はごく限られた範囲の好みを持つ人にターゲットを絞って成り立つ商売です。
1つの目的のために他を捨てるという競争戦略のトレードオフ、究極の顧客を絞り込む商売を見させてもらいました。
白隠禅師
先週上京した時、「白隠展」に行ってきました。
たまたまある雑誌を読んだ時、渋谷で開かれているのを知り、予定を変えて行ってきました。
若い頃に白隠さんに関する本を読んだこともあり、記憶に残っているお坊さんです。
白隠さんは白隠禅師と言われ、江戸時代中期の臨済宗の禅僧です。
500年に1人の英傑と言われるお坊さんです。
そんな偉いお坊さんの辞世の句が「死にとうない!」です。
これにはいろいろな意味が含まれています。
以前に本でこの辞世の句を読んだ時「凄いな!」と感銘を受けたのを覚えています。
白隠さんは健康にも気を使い、健康の本を出していました。
「軟酥(なんそ)の法」というのが有名です。
一種の自己暗示療法です。
その白隠さんの描く絵も素晴らしい。
達磨や観音様それにおかめの絵は大変ユニークです。
誰にも習わず自己流とのことです。
その絵に一緒に書かれた讃もいいです。
「直指人心(じきしにんしん)、見性成佛(けんしょうじょうぶつ)」というのがあります。
「まっすぐに自分の心を見つめて仏になろうとするのでなく、本来自分に備わっている仏性に目覚めなさい。」という意味です。
また「動中工夫」というのがあります。
これを説くと「動中の工夫は静中に優ること百千億倍」ということです。
今回は、あこがれの白隠さんに触れることのできた時間。
それも偶然に知って行けたこと。
感謝です。
2月24日まで渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムで開催しています。
ご興味のある方はどうぞ
働くということ
「働く」という字は人が動くと書きます。
人が動いた結果が成果になります。
ただし、単に動いていれば成果が生まれるかというとそうではありません。
ブタのしっぽは常に動きまわっていますが何の役にもなっていません。
過去長い間、働く基準を時間に置いてきました。
マルクス経済学では、商品の価値は、商品生産に必要な労働量によって客観的に決まるとする労働価値説を唱えてきました。
決められた時間を働いていればお金がもらえる時代でした。
でも現代では、そのような人は「人手」であっても「人材」ではありません
24時間懸命に働いても、価値があり、売れるモノを作り出せなければ無駄骨です。
働けど働けど我が暮らし楽にならず、ジッと手を見て嘆いても成果が出なければ働く意味がありません。
世の中は日々発展し、人が楽になるモノが生み出されています。
作業時間が短縮されても高い成果が生み出されるようになりました。
結果、働く人はどんどんいらなくなります。
今はそういう時代になっています。
今、働くということは決められた時間動き回るのでなく、成果を出すための工夫でなければなりません。
人が働くということは常に考え、工夫し、行動して成果を出すことです。
ITやシステムで出来ることはそれに任せ、人は常に頭を使うこと。
時間換算する思考から成果探求する思考に変えなければ生きていけなくなる時代です
就職支援が大変という話を聞いて、そのように思いました。
金の卵発掘プロジェクト
先週の金曜日11日に東京帝国ホテルで行われた経済界主催の「経済界大賞・金の卵発掘プロジェクト」の表彰式・祝賀会に出席してきました。
表彰式・祝賀会には千名近くの人が参加しました。
今回の「経済界大賞」は京セラ名誉会長の稲盛さんが受賞され、また「金の卵発掘プロジェクト」の特別賞に私達の仲間の佐佐木絵里沙さんが受賞されました。
佐佐木さんは風船の魔法使いエリサとして札幌・北海道を中心に活躍されてきましたが、この受賞で全国区になりました。
「風船で世界の子供達に絵顔を!」という理念が社会貢献として認められたのです。
壇上にはエリサさんが風船で作ったJALの飛行機が浮かんでいました。
素晴らしい表彰式・祝賀会でした。
仲間の1人としてその会に参加できたこと嬉しく思います。


良きパートナー
会社を経営する時、従業員と価値観が同じというのは大事なことです。
会社を起こし、1人事業から、初めて人を採用する時、色々な思いを抱いて面接するでしょう。
その時、社長としての夢を語り、それに向かって行こうと思ってくれる人、そして性格的にも明るい人を採用しようとします。
それはそれでいいです。
ただもう一つ大事なのは「嫌いだ」という部分も共通した認識が無ければいけません。
人を犠牲にして平気な人、自分だけのことしか考えない人、手段を選ばない人。
残念ながらそういう人はいます。
だからこそ「そのようなことを嫌う」という部分で一致しなければ一緒に仕事をしていけません。
以前にタレントのさんまさんがいいことを言っていました。
夫婦が長く続く要因は好きな傾向が一致することではなく、「ダメ」とか「嫌い」という価値観が一致しないと別れる傾向があると言いていました。
同感します。
「好きもの」はその人の好みですからお互いに認めることは出来ます。
しかし「してはいけないこと」が一致しないと、相手を許せない気持ちになります。
夫婦も社長と従業員の関係も、良きパートナー選びが大切です。
男の生きざま
先日NHKの番組「ファミリーヒストリ―」を見ました。
女優の南果歩さんのお祖父さん「ウンラクさん」が主人公。
番組の中でウンラクさんが口癖のように言っていた言葉が紹介されていました。
その言葉が心に残りました。
ウンラクさんは戦前に韓国から日本に来て軍需品店で武道具を作る仕事に就いていました。
一生懸命働き、その腕を見込まれ、工場の中でも最も高い給料をもらうようになりました。
家族の生活も安定していました。
ところが戦後、進駐軍により武具の生産を停止させられ、職を失いました。
戦後韓国に帰る人が多かった中、ウンラクさん一家は事情があり帰れなかったようです。
日本に残ったウンラクさんは、廃品回収等の仕事をしながら家族を養ったのです。
苦労続きの中、真面目に仕事をし、生き抜いたウンラクさんの言葉があります。
「今が辛くとも努力し続ければ子孫の代で幸せになる」
家族のために真面目に一生懸命生きたお父さんの姿がそこにあります。
ラクして楽しく仕事をしようという風潮の現代。
そういう時代だからこそ、その言葉には貧しくても凛とした生き方する「男の生きざま」を感じ取ることが出来ます。
正月早々いい言葉に出会えました。
年賀状
正月休みが終わり今日から仕事始め。
先ほど会社の新年朝礼も終わりました。
年賀状もいっぱい来ています。
一通一通目を通すと、差出人の人達の顔が目に浮かびます。
しばらくお会いしていない人達にもフッと会いたくなります。
これから年賀状を書きます。
Mac買いました
2日前にMACproというノートパソコンを買いました。
悩んだ末に買いました。
その1週間前には携帯からiphoneに変えました。
初代のiPadもあるので急にApple製品が増えています。
長い間貯めたヘソクリを使うので、熟慮の末の決断でした(少し大げさ?)。
なぜ買ったのかというと、昔から興味があったからです。
MAC独特のデザインが好きだったからです。
興味があったから買うということは、今の私にとって大切なこと。
今年になって、歳と共に物事に興味を失っている自分を知った時、少しショックでした。
以前だと思いついたらすぐ行動し、その場所にすぐ行ったり、試したりしたのに、今は遠のいているのです。
「まあ、いいか・・・」というあきらめの気持ちになりつつあったのです。
でもこの「まあ、いいか・・・」は厳禁です。
MACやiphoneを買うと、沢山の新しいことを覚えなければなりません。
覚えるにも興味がなければ覚えれません。
興味を持つということは全ての行動の最初だと私は思っています。
これからの正月休みの間、MACとiphoneを使いこなせれるよう勉強します。
そして楽しみたいと思います。
御用納め
今日は御用納め。
御用納めとは官庁の仕事納めのこと。
明日が土曜日ということもあり、多くの会社は明日から正月連休に入っていくのでしょう。
今は銀行も31日は休みにしているので、同じように休みます。
私が銀行時代の35年前は31日までびっしり仕事でした。
31日決済の手形が山の様に回ってきます。
お金をおろしに来る人が列をなします。
昼ご飯もとらず頑張り、現金勘定・振替勘定が合って仕事が終わるのは19時頃。
それから帰宅します。
銀行時代の先輩の話では、彼が若い頃は31日の24時を過ぎてやっと仕事が終わたそうです。
その為、前日の30日に年越しを済ませてから31日出勤したとのこと。
今から考えると壮絶な仕事ぶりです。
1つ忘れられず記憶に残っていることがあります
帯広の支店に勤務している時、上司から指示され関連の信組から集金してきたことがあります。
帯広は冬でもそれほど雪が無かったので自転車で行きました。
集金して帰り道、預かった1億円近くのお金を、大風呂敷に包んで自転車の荷台に乗せて帰りました。
1億円近くのお金を預かり、たった1人で大晦日の16時頃、人通りの少なくなって薄暗くなってきた道を自転車を押しながら帰りました。
1億円近くのお金を風呂敷に包んで1人で自転車で運ぶことが出来たということは、余程治安が良かったのですね。
年末になるといつもこの事を思い出します。
円安
昨日の日経平均株価が1万円を突破しました。
また円相場も円安が進み、1ドル85円以上になっています。
政権が変わり、それに対する期待でしょう。
日本のデフレの大きな要因に円安がありました。
過去長い間、日本は「デフレ=不景気」を脱却するために苦労してきました。
でも「デフレ=不景気」と言われながらも、デフレの時代は物価が安く、豊かでないけれど皆それなりの生活が出来て来ました。
デフレ脱却とはそういう生活が出来なくなることです。
物価が高くなります。
頑張って稼がないと生活を維持できなくなります。
デフレは誰にも優しい景気状態。
でもそれは過去に蓄積した財産を食いつないでいるだけ。
それを脱却するということは、それに慣れた人達にとっては厳しい時代になります。
頑張る人とそうでない人。
その差がこれからついて来そうな気がします。
何かを求めようとするなら、厳しいけれど挑戦することです。
その時はぬるま湯から抜け出す勇気が必要。
選択・決断とは何かを捨てること。
今の円安は一時的でまた円高になるかも知れません。
でも、これからの傾向は円安に動いて行きます。
来年は何かを始める時でしょう。
クリスマスパーティー
昨夜、我が家ではクリスマスパーティー。
三女の旦那のダンがイギリスから来、次女が子供2人を連れ来ています。
久しぶりに賑やかなパーティー(夕食)です。
料理はダンが担当しました。
イギリス式のクリスマスパーティーということで、鶏の丸焼き、サツマイモとジャガイモのパター焼き、それとイギリスから持ってきてくれたプラムがいっぱいのプディングという甘いお菓子。
この甘いプディングにブランデーバターを付けて食べます。
食事は色々な香辛料が入ったホットワインを食前酒に始まりました。
最後はこれもイギリスから持ってきてくれたブルーチーズとポートワインで締め。
食事で異文化を満喫しました。
年末から正月にかけては、お節料理等の日本の伝統的な料理になります。
ダンには、ナマス、昆布巻、黒豆などのお節料理を通して日本を感じてもらいます。
また三女にしてもイギリスに嫁ぎましたらから、暫くは日本の正月も味合うこともないでしょう。
いい思い出になると思います。
自己責任
ある人のブログを見ていると、アメリカでの体験が書かれていました。
その人がアメリカで少し危険なスポーツに挑戦しようとした時、その主催者から書類を渡されました。
「もしもケガなどを負ってもそれは自分の責任です」と書かれている書類にサインをさせられたのです。
その時、改めてアメリカは自己責任の国なのだと実感したそうです。
アメリカは何かあるとすぐ訴訟されるので、その為の自己防衛もあるでしょう。
ただもう1つアメリカは、自己責任の国だということも言えます。
何においても自己責任で処理しなければならないようです。
日本では当たり前の「国民皆保険」という保険制度もアメリカでは自分で入らなければなりません。
今問題になっている銃所持問題も「自分の命は自分で守る権利」という自己責任から来ているのでしょう。
それに対して日本人にはこの自己責任という意識が欠如している気がします。
事故があると、本来自分で責任を負わなければならないことも必ず誰かの責任を問います。
自分が一生懸命経営しなければならないのに、上手くいかない時、景気や政治、時には従業員のせいにする経営者がいます。
来年3月に終了する「中小企業金融円滑化法」も自己責任であるべき会社経営に相反する法律のように思います。
また、TPPにも言えます。
TPPの一番の問題は自己責任の有無です。
自己責任社会のアメリカが、過保護の国である日本を真の資本主義社会に引き出そうとする問題提起です。
今度の選挙で日本の政権が変わります。
来年は日本にとって厳しいことが起こりそうな気がします。
「自己責任」
改めて自覚しなければならない心構えではないでしょうか。
報告
昨日は「報・連・相」について書きました。
特に「報告」が重要とも書きました。
それについてもう少し書きます。
会社の中では社長が会社の状況を一番知っていなければなりません。
重要な情報が社長でない別の人が握っていると問題です。
良くある話です。
会社に有能な営業社員がいて、彼がいるおかげで業績がいい。
しかし、会社の方針と相反する考えで、社長の言うことを聞かない。
そういうことがあります。
社長としては辞めさせたいのだけれど、それによって会社の業績が下がるのか怖いのです。
このような状況の原因はやはり「報告」が徹底していなかったからです。
営業で大切なのはまず「営業日報」です。
「営業日報」を通して報告を受け、都度社長は営業状況を把握します。
もう1つ「顧客情報管理表」も作らせます。
1顧客に1つの「顧客情報管理票」を作ります。
この「営業日報」と「顧客情報管理票」でワンセットとして考え、営業報告と情報の共有を図ります。
誰が会社を辞めても困らない仕組みを作ります。
この仕組み作りこそが社長の仕事です。
そしてより重要なのは社長がその「報告」をよく把握する努力をすることです。
決して人任せはダメです。
それをすればまた情報の独り占めが始まります。
結局トップとしての社長の意識の持ち方にかかっています。
報・連・相
「報・連・相」という言葉は皆さんご存じだと思います。
「報告」「連絡」「相談」のことです。
この中で一番大切なのは「報告」です。
だから最初に出てくるのです。
「報告は」下から上に向かって行う伝達です。
「報告」以外の「連絡」「相談」は並列的伝達です。
横のつながりの中で行われます。
「部長が課長に報告しました」とは言いません。
この違いをしっかりしておかないといけません。
時として、単なる「連絡」を「報告」と考え、済ましている人がいます。
この間違いは社会経験が少ない若い人が起業した時、往々にしておきます。
起業して従業員を採用した時、仲間意識を強く持ち、友達の様な関係が生まれたりする時があります。
その結果、仕事の「報告」も「連絡」も「相談」も区別なく仕事が進んで行きます。
コミニュケーションを高める思いだけが先行して、ノリで仕事をしています。
それでも最初の内は勢いで上手く行くことはあります。
でも、満足な「報告」がなければ社長は会社の実態を把握することが出来ません。
「報・連・相」
会社では「報告」が一番重要だということです。
鉄砲と弾を売る
昨夜はサックスのレッスンを受けて来ました。
3年ほど前から近くのヤマハ音楽教室で習っています。
3年経ってもあまり上手くなりませんが、教室に定期的に通うことで続けてこられたのだと思っています。
このヤマハ音楽教室に通う人は日本で約50万人(平成16年)いるそうです。
この数の大きな変動はないようです。
1人当たり月の授業料が7000円とすると単純計算で月売上35億円、年間420億円です。
ヤマハ㈱は楽器を売っている会社です。
最初はその楽器の売上を上げる為に教室を始めました。
その教室の売上が年間420億円にもなっているのです。
商売には「鉄砲を売る商売」と「弾を売る商売」があります。
「鉄砲を売る商売」は1度売ると再購入していただけにくい商品。
例えば家とか自動車等です。
「弾を売る商売」はダスキンの様に少額だけれど購入が長く続く商売です。
ヤマハの商売は楽器という鉄砲を売り、それを練習するための音楽教室という弾も売っています。
鉄砲も弾も売る。
考えればよく出来たシステムです。
私が通っているヤマハ音楽教室はヤマハの店舗の中にあります。
以前は沢山の楽器があったのが今はピアノだけ。
消耗品もほとんど置いていません。
経営方針として楽器より音楽教室に力を入れているのでしょうか。
確かに生徒が使う楽器はヤマハでないメーカーのモノも多いです。
それにしても鉄砲と弾を同時に売る商売はそう多くはないでしょう。
それを見付けると面白いビジネスが生まれるかもしれません。
判断基準
仕事をしていると常に判断が求められます。
前に進むか、止まるか、後ろに下がるか、右に行くか、左に行くか。
仕事ばかりでなく、生活をする上でも判断は求められます。
買うのか、買わないのか。
その判断によって結果が大きく違ってくると思うと決断出来なくなります。
情報を得ようと本を読んだり、ネットで人の意見を調べてみることもあります。
でも最終的には自分で判断し、その結果に対しては自分で責任を負わなければなりません。
この「結果に対して責任を負わなければならない」のを回避して逃げている人がいます。
以前にも書いたかもしれませんが、私は若い頃銀行員でした。
銀行には膨大な量の「規定集」があり、銀行の仕事の判断基準が全て書かれています。
その規定通りに判断すれば、自分の考えと関係なく仕事を進めることが出来ます。
そして規定通り仕事をしていれば、誰からも文句は言われません。
しかし恐いのはこの自分の判断を持たないで規定に従って仕事が出来ることに慣れてしまうことです。
その恐わさを実感したのは、32歳頃銀行を辞めて父の会社に入った時です。
中小企業の会社には規定などありません。
全て自分の経験で得た情報、知識、知恵を使って判断しなければなりません。
自分で判断する能力を失っていた私にとっていつも戸惑いばかりでした。
最初はいちいち他の人の判断を求めなければ仕事が出来ません。
他力依存になっていました。
60歳を過ぎた今頃になって、やっとそれなりの判断基準を持てるようになりました。
判断基準を持てるようになった大きな要因は、どのような結果に対しても責任を持つことが出来ると実感出来たからでしょうか。
今、戸惑いながらも仕事が出来ていること。
自分に対して少し自信が持てました。
心の多重構造
昨夜は今年最後(?)の忘年会がありました。
盛和塾の忘年会で、最初は勉強です。
稲盛和夫さんのDVDを見ました。
いつも思うのですが、稲盛さんのDVDを見る度に気付きを得ることが出来るのです。
今回のお話も「思う」ことの大切さと「思い」が実現するための方法を教えています。
そのお話しの概略を書きます。
小さい頃、家に結核の伯父がいて、離れで寝ていました。
稲盛少年は子供心にも結核は恐いものと思っていつも避けるようにしていたそうです。
でも家で一番結核を恐がり、用心していた稲盛少年は結果結核になってしまいました。
一方、結核をそれほど気にもしなかった兄さんや看病で傍にいた父親は罹りませんでした。
恐いと思った自分が罹ってしまったのです。
また松下幸之助さんの講演を聞いた時に「ダム式経営」の話がありました。
幸之助さんがその「ダム式経営」の大切さを話した後、ある人が質問で「その為にどうすればいいのか」と問いました。
その答えが「必要と思わないといけない」でした。
どちらも「思う」ことが原因であり要因なのです。
将来に対する「思い」を実現するための方法も教えいただきました。
「心の多重構造」という図を使って説明されました。
心にはその核となる「真我」がありその外側に「魂」があります。
生まれてくる時はその「真我」と「魂」だけで生まれて来ます。
生まれると同時に「理性・良心」が取り巻きます。
その後に人間の「本能」「感性」「知性」と多重の構造になってゆきます。
一般的に、人は一番外側の「知性」の部分で考えたり計画を立てたり、そうしようと思うのです。
でもそれでは、その「思い」は実現しません。
常に強い願望を持ち、潜在意識に到達するまで思い続けなければなりません。
そしてその「心の多重構造」の「魂」の傍にある「理性・良心」の部分が間欠泉の様に吹き上がることが大切だと言われます。
「理性・良心」は「魂」からが出て来ます。
ここの部分で思うことはパワーを持っています。
ここがポイントで、「理性・良心」の力を借りた「思い」でなければ成功できません。
以上が「思い」が実現する話の概略です。
チョット説明が上手くなく、また内容が難しかったかもしれません。
もしもご興味をもたれた方がいましたらネット上で「心の多重構造」と検索すれば詳しい説明が出て来ます。
一度ご覧になってください。
使命感を持っている人
人を見ていると惰性で生きている人としっかり使命感を持って生きている人がいます。
惰性で生きている人は、毎日が昨日の繰り返しで、日が流れるままに毎日を暮らしています。
ただジッと次の休みになるまで、当たり障りのない生活をします。
では使命感を持った人と何が違うのでしょうか?
私が考えるに、誰かに期待されいると実感できるかどうかです。
誰かに必要とされているかどうかで使命感が持てます。
家族との生活の中でお父さんへの期待。
仕事でのお客様のあなたへの期待。
上司があなたに託す期待。
折角のそれらの期待があるのに、鈍感さのために見逃している人の多いことか。
その期待や必要とされているという実感は、今少しアンテナの感度を上げることで感じることが出来ます。
これは理屈ではなく「感じ」です。
試してみることです。
その時に「私は家族を幸せにするために頑張る」「お客様の喜びを自分の喜びとしよう」「会社のみんなのために頑張る」という思いが、生きていると実感させ、自分の使命感が持てるようになります。
見回せば周りに自分への期待は必ずあります。
今1度見回してみましょうか。
新しい暦
今日は12月15日、これからが師走の大詰め。
この時期、年賀状そして来年の手帳や暦も用意しなければなりません。
中でも暦は頂き物や市販されている物、他には自分で作る人もいるでしょう。
私も1つ作りました。
毎日自分が見付けだした好きな言葉を書き入れていく卓上暦です。
今までなかった暦だと思います。
見本を人に見せると欲しいと言う人がいますので、30部ほど作る予定です。
こんな忙しい時期に余計な仕事が増やしてしまったかなと思いながら、楽しく作っています。
来年1年間使ってみて、皆さんの感想が良ければ「売り出してもいいか」などと、初夢には少し早い思いを持っています。
さて、これから頑張ります!
予定時間より少し早く
会社で会議をする時、社長は参加者全員がそろった頃に出てくるケースが多いです。
始まる時間より早く席についていることは少ないでしょう。
皆より遅れて、最後に行くことでメンツは保たれると思っているのでしょうか。
私の経験から、そのような会社は全てにスピードが遅いように感じます。
報告を受けるという「受け身体質」になっているようです。
スピード感のある会社は社長が率先して行動します。
そのような社長は、会議が始まる前から準備し、質問事項なども用意し、時間前に席についています。
そうすると参加者全員が緊張感を持って臨めます。
そのような社長は出社する時間も早いです。
そして社長が7時位に出社すれば、部課長も早く出てくるようになります。
それが社員にも伝わり、始業時間より早く出て、仕事の準備をします。
9時に出社して、おもむろに仕事の準備をする会社より1歩も2歩も前に進めることが出来ます。
予定時間より少し早く始める。
これによって仕事の効果は高くなると思っています。
重役出勤などもっての外。
忘年会で考える
昨夜はサッポロビールのビール会がありました。
会場は私共のホテルで開催されました。
今の時期は忘年会シーズンなので、昨夜はホテルもいっぱいでした。
ただ、担当者に聞くと昨年より入りは悪いと言います。
ホテルより安い店で忘年会という傾向のようです。
昔は5000円で料理8品・飲み放題が多かったように思います。
それが4000円、そして3500円。
最近は3000円で料理6品・飲み放題という店も出て来ました。
先日2次会で行ったスナックも、いつもだと3500円で飲み放題なのが、2500円でした。
1店舗だけでは薄利しか出ないので、数店舗経営してトータル利益を稼ごうとしている会社もあるそうです。
でもそうなると、1店舗がこけると連鎖してこけてしまいます。
デフレは生活者にとってはありがたいですが、回り回って自分の首を絞めることになります。
忘年会で酒に浮かれてばかりではいけないと思いながら、今日明日と忘年会が続きます。
選挙について
今、16日に向けて選挙活動が盛んです。
多くの党がスローガンに「景気回復」「TPP反対」が掲げられています。
この2つのスローガンは、私にはどうしても矛盾するように思えてなりません。
今の日本の雇用状況は大変悪く、これが景気を悪くする大きな要因です。
一方、多くの製造業は円高や高税負担、それに電気料金・ガソリン等の高騰などを受け、厳しい状況の中にあります。
日本の国は過去輸出で成り立ってきた国です。
その貿易収支が3年赤字です。
このような国内の経営環境が悪化すると、力ある会社は海外に出て行きます。
自動車各社が100万台の生産を海外に移転すれば日本の雇用は22万人減ると言われています。
22万人は大きな数字です。
「何かを決めるということは何かを捨てなければならない」のです。
いい響きの言葉だけで判断してはいけない。
選挙の演説を聞いてそう思います。
札幌観光大使
昨夜「札幌観光大使」の集まりがありました。
今回は視察・研修会と称して、円山動物園の「アジアゾーン」を見学して来ました。
円山動物園のこの「アジアゾーン」は正式には明日12日にオープンするのですが、その前に観光大使達に見てもらい、告知してほしいとの趣旨です。
「アジアゾーン」は「寒帯館」「高山館」「熱帯雨林館」の3棟で構成され、それぞれの地域にいる動物を展示しています。
展示されている動物はほとんどが観客とガラスで仕切られています。
以前はオリだったのがガラスになっています。
その一番の理由は臭いを防ぐためです。
写真やテレビで見た動物を実際に見た時、その臭いで動物園を嫌いになる子供がいるようです。
本来は、臭いがあっての動物なのです。
普段身の回りにいる動物と言えば、臭いの無いペットにしか慣れていないからでしょうか。
少し違和感を感じます。
ただ、ガラスの仕切りによって良くなったのは動物に極限まで顔を近づけることが出来ることです。
以前はオリだとその前に柵まであり、動物を近くで見ることが出来ませんでした。
でもガラスだとガラス越しに動物と顔をくっ付けることが出来ます。
この「アジアゾーン」には珍しい動物がいます。
アムールトラ、ヒマラヤ熊、マレーシア熊はお勧めです。
レッサーパンダもいて、正月にはレッサーパンダの糞で作ったお守りをくれるそうです。
レッサーパンダは木から絶対の落ちないので、「落ちない」にかけて「合格祈願」のお守りです。
何年かぶりの動物園。たまに行くのもいいですね。
帰宅して
昨夜帰宅しました。
3日間上京し、色々な人に会い、色々なところを歩きました。
1日1万歩以上歩きました。
疲れて家に帰り、さぞや痩せただろうと思って体重計にのったら1キロも増えていました。
動いた分食べたせいでしょう。
今回もさまざまな人にお会いして来ました。
そして多くのことを学びました。
しばらくはそれを整理することになりそうです。
俺は聞いていない
会社の中では、「報告」「連絡」「相談」は大事です。
でも時に、事案によってはその流れからはずれてしまう部署や人がいます。
直接関係しない事柄については知らされないことはあります。
でも、「俺は聞いていない」という上司が時々います。
後で伝える程度で良いとされる内容でも「俺を無視した」という人がいます。
全て知らされないと、「自分の沽券にかかわる」と我慢が出来ないのです。
そういう人がいると会社は動きにくくなります。
仕事と情報は自分で取りに行く。
そういう姿勢でなければなりません。
フッと最近感じることです。
仕事を好きになる
私が主宰しているしている勉強会でのお話しをご紹介します。
その勉強会の教材は稲盛和夫さんの「心を高める 経営を伸ばす」という本です。
今月の勉強会は先週の木曜日に開きました。
15名ほどの方が参加されます。
会社を経営している人は2人ほど、後は起業をしようと考えている人達です。
30歳代から60歳代までさまざまの職業に人が参加します。
「道を切り開く」「生きがいをつくる」「仕事を好きになる」「ひとつのことに打ち込む」「日々新たに創造する」の項目について読み、参加者の感想や考えをお聞きします。
様々な考えと共に経験も披露してくれます。
その中で、看護のお仕事をされている人のお話しです。
最近、病院内の配置変えがあり、彼女は初めて介護病棟の担当になりました。
そこで仕事をしている時「フッ」と気付いたことは、お世話をしている人のおしっこやウンチが汚いものと思えなくなったというのです。
おしっこやウンチが出ると「嬉しい」と思えてしまうのです。
以前は、同じ看護の仕事をしている時、そういう気持ちにならなかったと言います。
介護の現場で、患者さんのおしっこウンチがチャンと出るということは身体がまだ丈夫だという証拠。
それが確認できて嬉しいのです。
自分の仕事に打ち込み、その仕事を好きになっているのです。
私はなかなかそこまでに気持ちななれません。
介護のお仕事をされている人の多くはそうなのでしょうね。
いいお話を聞かせていただきました。
人を育てる
社長の多くが人材不足をよく口にします。
「いいスタッフがいないので困る」と言います。
有名大学卒を新規採用したり、外部から優秀という人を中途採用しても、思った通りの人材に育ちません。
取引先銀行から優秀と言われる元支店長などが来ても、5年持たずに退職します。
そのほとんどの原因は全て社長です。
でも社長はその原因に気付いていません。
社長は自分がいなければこの会社はダメになると思っています。
事実そうでしょう。
しかし人を育てる時、その思いが邪魔をします。
それでは人を育てる為にどのようにするか。
それは社長が「自分は不必要」という状況にするように考え直すしかありません。
いつまでも「自分が一番、俺の言う通りにしろ!」と思っているうちは人が育ちません。
社長が後ろに下がり、「社長がいなければどうする、そしてどうなる」を見、仕事を部下にさせてみるのです。
その時、社長に必要なモノは我慢です。
いつも「俺がいなければ何も出来ない」と思っている社長には「自分は不必要」とすることは辛いですが、それ位しないと人とは育ちません。
社長の言う通りすれば、社員も楽です。
楽な状況では人は育ちません。
社長、社員共に楽な状況から脱しなければ人は育ちません。
新聞の効能
昨日知人が尋ねて来てくれ、しばらく話をしていました。
彼は大学生の就活支援をしている人です。
その話の中で「最近学生は新聞を読まない」という話になりました。
新聞を読む代わりに、ニュースはテレビやネットで済ましている。
彼はそこに就活が上手くいかない原因があると言います。
それは学生が新聞を読まなくなり、それによって知識不足になっている状況を言っているのかと思ったのですが、そうではありません。
新聞を読む時は、だいたい1面からじっくりと見て、目を引く記事があると読みます。
それを経済、国際、企業、マーケット、社会等の紙面を順に見て、読んでいく中で、今まで自分が興味なかったことを見付け出すことが出来ます。
そこで知識の広がりが生まれます。
社説などを読んで色々な考え方を知ることも出来ます。
ところがネットの社会ではこの新聞の様な「一覧性」がありません。
ネットでは興味のある点は深く理解することは出来ますが、それ以外にはなかなか目がいかなくなります。
結果、「多面視点」を持たなくなった学生が多くなったのです。
就活で悩んでいる学生は、この業種しかないとか、この会社しかない等、「一面視点」の志向が強く、それ以外の選択肢を見つけ出す力が不足していると言うのです。
成程と思いました。
私は新聞派で、朝は新聞を読まなければ落ち着きません。
新聞を読んで興味を持ったところを改めてネットで検索して、より深く理解するようにしています。
今はネットのお陰で知識が深く理解出来るようになりましたが、一方浅くても広い情報を得ることが出来る新聞。
新聞の発行部数は年々減少しているそうです。
でもその力はより見直されてもいいのではと考えます。
経営戦略
会社の経営が上手くいくか行かないか、その要因のほとんどが経営者、社長にかかっています。
その社長の倫理観、思考方法、人間性などが大きく影響します。
ただ、会社の経営はそれだけで上手くいくかというとそうではありません。
的確な経営戦略を立て、利益の出る会社にしていかなければなりません。
その経営戦略を学ぶためのバイブル的存在がマイケル・ポーターの「競争戦略」です。
この「競争戦略」は以前にも紹介しましたが、ワタミの渡邉会長が自分の経営に生かしているという話があります。
ただ、500ページにわたるその本は難解で、私も3度読みましたがよく理解できません。
その解説書なるモノも何冊か読みましたが、今一つ。
最近、ジョアン・マグレッタ著の「マイケル・ポーターの競争戦略」という本を読みましたが、これは要約されていてよく理解できました。
経営戦略の本を読んでいく内に、この「マイケル・ポーターの競争戦略」をより実践的に勉強したいと思うようになりました。
そこで知人を通して北海道大学のH教授を紹介され、昨日お会いして来ました。
H教授は経営学が専門です。
H教授に「ポーターの『競争戦略』を学ぶ勉強会を開きたいのですが、ご協力いただけないか」のお願いいをいたしました。
私の話を聞いて、ご協力いただける方向で、話を進めることになりました。
ただ、H教授の話ではポーターの「競争戦略」は翻訳が悪く読みにくい本であること。
それより良い本があると、別の本もご紹介されました。
実際に開催するかどうかは、経営戦略を勉強したいと思う経営者がどの程度いて、集めることが出来るかにかかっていると思います。
今回の勉強会は既に経営し、今後の経営の在り方を学びたいと思う人達を対象にし、共に学び、成長したいと思っています。
人数は10名程度がいいでしょうか。
本を学んだ後は、実際に繁盛している会社と、そうでない会社のケーススタディーを行います。
そこで学んだ「知識」を実践的に生かせる「知恵」にしたいと考えます。
開講するとすれば来年になると思いますが、これからこの勉強会に向けて、そのプランを構築してゆきます。
仕方が無く始める
新しく事業を始める時、やる気満々で始める場合と、仕方が無く始める場合があります。
やる気満々で始める方が成功するかというとそうとも限りません。
私の経験や周りを見ていて、仕方が無く始めた方が成功率が高いように思います。
なぜそうなのか。
やる気満々でやる時は得てして、周りが見えなくなり、勢いだけで突き進むことが多のです。
それが流れに逆行することもあります。
一方、仕方が無く始めた事業は不安が伴いますから、慎重に進みます。
間違いを犯さないようにしながら、将来の目標を見出していけます。
仕方が無く事業を始めなければならないという立場に置かれた時、それを運命と悟ることが出来れば、その流れに素直に乗ろうという思いが生まれます。
それによって「素直な経営」が出来ます。
そしてある期間が過ぎて、振り返ってみると、結果がしっかり残っています。
人は時々「仕方が無いな」と思いつつ始めなければならないことが周りに起きます。
もしかしてそれに挑戦することで、新しい出会いや仕事に結びつくかもしれません。
新しい縁に出会えるチャンスかもしれませんね。
7歳の少年
私の「銘肝録」を見ていると、1年ほど前に切りぬて貼っておいた日経新聞の記事がありました。
それを紹介します。
そこにはハワイ州の知事を務めたジョージ・アリヨシ氏の日本人に対する思いが書かれています。
彼がアメリカ兵として昭和20年に廃墟の東京に来た時のことです。
夕暮れに有楽町を歩いている時、高架下で少年に靴磨きをしたもらいました。
その少年は心を込めて一生懸命にやってくれたので感心し、兵舎に戻ってパンにバターとジャムをいっぱい塗り引き返しました。
少年に「これを君に上げるよ」と言ってパンを手渡しました。
腹ペコだからすぐにその場でかぶりつくと思ったら、その7歳の少年はそのまま風呂敷にしまったのです。
「なぜ食べないの?」と聞くと「家にマリコという3歳の妹が待っていますから」と答えました。
腕白盛りの男の子が、ひもじさを我慢して、妹のためにパンを持って帰ろうとしている。
その瞬間、アリヨシ氏は「物としての日本は壊れたが、日本人の心は失われていない、必ずや日本民族は甦る」と確信したそうです。
「貧すれば鈍する」と言う言葉があります。
この話はそれを否定する情景です。
この記事を読みなおして、日本人として持っている大切なもの。
それを守り続けなければならないと改めて思い、考えさせられました。
居心地のいい店
洋服などを買いに店などに行くと、そこの店員さんは「いらっしゃいませ」と声を掛けてくれます。
今、ほとんどの店舗では、それなりの教育が出来ていますから挨拶だけはしてくれます。
でも、その後の「もう一声」が出て来ません。
お客様によっては、そばに店員さんがいるのが煩わしいと思う人がいます。
店員さんにズーと見ていられるのも嫌です。
一方、放って置かれると「お客に無関心だ」と腹を立てるお客様もいます。
ではどうすればいいのでしょうか。
ある店に行くと、「いらっしゃいませ」の挨拶の後に、「何かご質問などございますか?」と聞いてきます。
その時に「いや、ないです」と応えると、「何かご質問がありましたらご遠慮なくお声をお掛けください」と言って離れ行き、棚の整理など自分の仕事をしています。
そうするとお客としては、自由にしてくた上で、気も使ってくれていると認識します。
そして何かあると気軽に質問することも出来ます。
店員さんとしても、いつ声がかかってもすぐ対応できる体制を取りながら、視線をお客様から離しています。
一声かかって、気配りしてくれていると思える店。
「居心地のいい店」とはそんな店のように思います。
ジャスコンサート
昨夜「上原ひろみザ・トリオ・プロジェクト」がニトリ文化ホールで行われました。
2カ月ほど前から前からA席を3枚買って、家族と行こうと楽しみにしていたのですが、風邪気味なので断念しました。
私の代わりに妻の友人を誘って行ってきたようです。
今朝はまだ早いので、まだその様子を聞いていませんが、楽しかったのではないでしょうか。
夜帰って来てからのにぎやかな声が、寝ている私の耳に入ってきていました。
上原ひとみさんの音楽はじっくり聞いたことがありません。
ただ、以前にテレビの中で、「自分のまえに立ちはだかる壁は、大きなハンマーでぶち壊すようにして進む。そしてそれが楽しい」と言っていました。
そんなパワフルな彼女のジャズピアノを聞きたいと思っていたのです。
また何かの機会もあることでしょう。
それにしても風邪直します。
この連休の内に。
「道」
日本人は何かに付けて「極め」を追求する民族です。
それが突き進むことで新しい何かを見つけ出します。
それが時として「ガラパゴス化」と言われるほど、独自過ぎて他の国で売りにくいという商品作りになってしまうことがあります。
でもその方法は他の国の人との差別化になると私は考えます。
決して悪いことではないのです。
日本は昔から「道」と言う言葉を使って、「極め」を追求して来ました。
柔道、弓道、剣道、茶道等です。
また「商人道」と言う言葉もあります。
昔、儲けると言う行為は卑しいものとみなされていました。
日本人はその儲けると言う行為に「道」という観念を取り入れています。
明治時代、渋沢栄一の「論語と算盤」という本にも表されています。
江戸時代の石田梅岩も「実の商人は、先も立、我も立つことを思うなり」と説いています。
儲かりたいは「欲」
儲けるは「道」
これが「商人道」なのでしょうね。
縁作り
人との出会いは毎日起こります。
何気なく暮らしても出会いはあります。
その出会いを活かすか活かさないか、その人の心持によって違います。
「小才は縁に会って縁に気付かず。中才は縁に気付いて縁を活かさず。大才は袖振りおうた縁もいかす。」と言われます。
振り返ってみれば、私はやっと中才程度でしょうか。
間違えていけないのは袖振り合う「縁」を作ろうとして異業種交流会等に参加し、自分の商売に結び付けようと思うとです。
決して上手くいきません。
「縁」は普段の生活の中で「有意注意」の意識の中で見付けれるものです。
「縁」を使った言葉に「因縁(いんねん)」と言うのがあります。
「因」とは直接的な原因のこと。例えば自分の心の状態のこと。
「縁」とは間接的な原因 のこと。例えば人に会いに行く、手紙を書く、メールをする等、実際に行動することです。
ただ口を開けて待っていても牡丹餅は落ちて来ません。
私が知っている女性起業家はこの「大才」を持っています。
彼女の活躍を見ていればこの「小才」「中才」「大才」の意味がよくわかります。
もう少し行動的にならなければ!
人を悪く言うと・・・
人は誰かを話題にする時、ついその人の評価をしがちになります。
これは慎まなければなりません。
会社内でもよくこれが行われます。
人事評価と言いながら悪口が出て来ます。
人の悪口を言うと、回り回って自分に帰ってくると言われます。
悪口を言うと、自分も誰かに悪口を言われることになるということでしょう。
もう1つ悪口を言わない方がいいという訳があります。
昨日ブログで紹介しました明治の実業家の藤原銀次郎さん言った言葉です。
「人を悪く言うと一種の自己催眠の様なものにかかって、その人を悪く言わなかった時以上に、その人が悪く思える。
反対に人を褒めると褒める以上にその人がいいように思われる。
だからなるべく人を悪く言ってはいけないのだ。」
この言葉を読んで私も思い当たります。
チョットしたことで人を批判的に話すと、その自分で下した評価が頭に残り、そのような見方が強くなってしまったことがあります。
逆にあまり好きでないタイプの人だけれど、あえてその人のいいところを人に話しているだけで、その人に対する好意が生まれたりします。
言霊と言いますが、口に出すと潜在意識の中に刷りこまれていくのでしょうか。
であれば、その作用を良くなる別なことに使うのがいいでしょう。
「美しい言葉」「積極的な言葉」「明るい言葉」
使いたいと思います。
仕事の報酬
仕事を一生懸命するとその報酬が、給料です。
その給料の額は、仕事の内容に比べ少な過ぎても不満が出るし、多すぎても怠惰を生みます。
仕事の成果をお金以外で評価しようという考えから、月間・年間優秀賞を設けて表彰する会社もあります。
如何に従業員のモチベーションを上げるかに経営者は工夫し、苦労しています。
仕事の報酬はもう1つあります。それは仕事です。
明治の実業家である藤原銀次郎さんが言って、土光敏夫さんも口にしていた言葉に「仕事の報酬は仕事」があります。
「仕事の報酬は仕事」と言うと、すぐ過剰労働の強制と取られることがありますが、そう取る人には報酬はお金や表彰でいいでしょう。
でも本当に成長基調にある会社で、明確な目的があり、ベクトルがそろっていると、この言葉が生きて来ます。
仕事にも「見習」「初級」「中級」「上級」「最上級」があります。
その過程を経ながら、難しいけれどやりがいのある仕事をすることになってゆきます。
同時に本人も人間的に成長出来ます。
従業員1人1人の成長を大切にする会社にこそ「仕事の報酬は仕事」という言葉が普通に認識されています。
藤原さんが書いた「愉快に働く十カ条」の中に「仕事の報酬は仕事」が書かれています。
その「愉快に働く十カ条」をご紹介します。
1、仕事をかならず自分のものにせよ
2、仕事を自分の学問にせよ
3、仕事を自分の趣味にせよ
4、卒業証書は無きものと思え
5、月給の額を忘れよ
6、仕事に使われても人には使われるな
7、ときどきかならず大息を抜け
8、先輩の言行を学べ
9、新しい発明発見に努めよ
10、仕事の報酬は仕事である
小さいから楽しいホテルの経営
私は以前メルマガを毎週出して、2年半近く続けました。
6年前に書き終わりましたが、その後メルマガをホームページ上に残して置きました。
この前、久しぶりにそのホームページを見てみると、カウントが2万9千を越していました。
多くの方に見ていただいてるようです。
そのホームページは「小さいから楽しいホテルの経営」と題して、私がホテルの支配人だった時の経験を書き綴ったモノです。
また、Googleで「小さいから楽しいホテルの経営」と検索すると、同じ題名のホームページが色々出て来ました。
驚いたのはあるホテルのホームページの中に私の書いたそのメルマガがそのまま掲載されていました。
ホームページ上に私のメルマガだと謳っていましたのでそのままにしています。
このメルマガは小さなホテルの経営者や支配人のお役にたてればとの思いで書いたメールマガジンです。
ですから、それもいいかと思っています。
宜しければ一度のぞいてみてください?
「小さいから楽しいホテルの経営」
http://www.geocities.jp/shcc_j/
問題とは何?
土光敏夫さんがある本に書いたことです。
「問題」とは何か。
それは目の前にある悩みやトラブルを言うのではありません。
真に自分が取り組むべきことは何なのか、現状にとらわれず「かくあるべき姿」の中に見出した不足分。
それが「問題」だと言います。
毎日に流されることなく追い続ける、明確な「かくあるべき姿」は夢でありビジョンでしょうか。
今、政治の世界では、示されるべき「かくあるべき姿」が明示されず、その問題点も検討されず、自己保身だけの政治家が如何に多いことか。
あんなに長い間放置されてきた特別公債法案、議員数の0増5減案がたった2日間で決まってしまいました。
この何ヶ月間はなんだったのでしょう。
税金の無駄使いの典型です。
1カ月後には総選挙。
私達の意志が反映されるたった1つの手段です。
政治家たちに裏切られてきましたが、それでもこの国を見放さず、見守ってゆきたいと思っています。
車内広告
昨日、札幌の地下鉄に乗って改めて驚いたのは、掲示されている車内広告ポスターの少なさです。
不況だと長く言われ、広告数が少なくなっていますが、昨日見た時は3割程度の掲示しかありません。
普段はほとんどが掲示されている「中吊りポスター」も空きがありました。
今は11月の半ば。
いつもだと年末にかけて忘年会・クリスマスの宴会、ボーナス目当てのバーゲン、お節料理等の広告が多く出される時期です。
今は余程の不況だと改めて認識しました。
でも改めて考えると、こんなに車内広告ポスターが少ない時こそ、掲示価格も安くなっていることでしょう。
そして広告ポスターを掲示すればポスター数が少ない分、目立ち、その効果も高いのではないでしょうか。
ネット社会の現在、広告や告知もネット行われることが多く、一般広告が減ってきています。
でも一方、電車に乗った人には、本を読む人、ケータイを見ている人もいますが、多くの人は手持無沙汰にポスターなどを見ています。
そんな今だからこそ広告の狙い目かもしれません。
1坪の面積
ある本を読んでいたら、土地の面積の単位の成り立ちについて書いてありました。
日本では面積を表す単位として「坪」が今でも使われています。
1坪は約3.3平方メートルです。
300坪で1反(たん)です。
昔は360坪で1反だったそうです。
田んぼ1坪で1人が食べる1日分のお米が収穫出来たそうです。
ですから1反は約1年分のお米を作ることが出来ることになるのです。
昔の人は、人が1日に食べるお米の量で土地の面積の単位を考え、それを「坪」を定めたのです。
ただ人によってお米を食べる量が大いに違います。
戦国時代は1人1日7合食べたと言われ、庶民は5合だとのこと。
若干あやふやなところはありますが。
ところで、1合で2杯になりますから5合でも10杯。
おかずが少なかったので、お米だけで頑張っていたのですね。
現代は1人1.5合しか食べません。少なすぎます。
尚、1反が360坪から300坪になったのは、豊臣秀吉が行った太閤検地の時に、年貢米を多くするために変更されたようです。
大増税です。
改めて日本は「米」が生活の基本だったのだと認識させられました。
縦割りで仕事をする
仕事の割り当てについて考えます。
よく「縦割り社会」と言うとあまり良くない社会と捉えられます。
逆に、「横割り社会」「横断的」「水平思考」と言う言葉はよりよく見えます。
しかし会社において仕事を命じる時は「縦割り」でさせるべきです。
特に若い人を育てるには必要なことです。
調査し、仮説を立て、試行し、失敗を重ねながら成果を上げる。
苦しい仕事から美味しい果実を得るまで全てを任せないとダメです。
そうすることで人が育ちます。
時として、美味しいところだけを上司が得て、辛い仕事を部下にさせるという様子が見える時があります。
それでは人が育ちませんし、仕事に対するモチベーションも持てません。
「縦割り」で仕事をさせる。
改めて考えてみるといいと思います。
京都賞
週末京都に行ってきました。
10日に開催された「京都賞」の授賞式に招待された形で出席しました。
「京都賞」とは1984年に始まり、科学や技術、文化において著しい貢献をした人々に与えられる国際賞です。
「先端技術部門」「基礎科学部門」「思想・芸術部門」の3つの賞が贈られます。
過去にはこの受賞者の中から多くのノーベル賞受賞者が選出されています。
「先端技術部門」では「コンピューターグラフィックスと対話的インタフェースにおける先駆的業績」を評価されてアメリカのアイバン・エドワード・サザランド氏。
「基礎科学部門」には「自らのタンパク質分解を行う自食作用の解明『オートファジー』」に関した研究評価で大隅良典氏。
「思想・芸術部門」では「知的植民地主義に抗う、開かれた人文学の提唱と実践」を評価されてインドのガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク氏が選ばれ受賞しました。
この「京都賞」は稲盛和夫さんが自費で設立した稲盛財団が主催運営し、受賞者にはそれぞれ賞金5000万円授与されました。
授賞式出席者は原則男性はタキシード、女性はドレスの着用と言われていました。
原則はタキシードなのですが、私はタキシードは持っていませんので普通のスーツで行きました。
会場にはスーツの人もいましたが、多くはやはりタキシード。
タキシードやイブニングドレスの人達が集まる授賞式は初めての経験です。
授賞式は高円宮妃久子殿下のご臨席のもと、約1,700名が出席し、開会後、祝典序曲や奉祝能が披露されはじまりました。
厳粛な緊張感漂う式典は約2時間で終わりました。
今回は良き機会を与えられ、普段味わえることのない時を過ごしました。
役割分担
起業したばかりの会社なら、社長が会社そのものなので、社員にも社長の意向は伝わります。
しかし、社員が50人を越してくると、社長の意向・考えは伝わりにくくなります。
また、社長の意向・考えを実践しなければ実績が生まれません。
あるべき姿としては、社長は会社の「理念」「目的」を謳います。
経営幹部は「目的」を追求する為に戦略を練って「目標」を掲げます。
現場のリーダーは「目標」を達成するための戦術を生み出し「方針」を出します。
社員にはこの「方針」に基づき「手順」を考えます。
このようにして会社は動きます。
ただ時として、会社のトップや経営幹部の中には、「目的」や「目標」を出すだけで終わってしまう人がいます。
進むべき方向を示し、ベクトルを合わせ、同時に社員が「手順」を創り出すまでフォローすることが重要です。
「ベクトル合わせ」+「実行」⇒「業績アップ」になります。
挨拶
人と会った時、コミュニケーションの最初は挨拶です。
「おはようございます」「こんにちは」「お疲れ様です」「失礼いたします」
挨拶は全ての基本です。
最近はその挨拶も出来ない人が多いように思います。
家庭で教えられてこなかったのでしょうか。
そんな中で今年の天皇賞の時、優勝したデムーロ騎手が天皇両陛下がいらした貴賓席に来た時下馬し、両陛下に向かって、ひざまずいて最敬礼を行いました。
私は競馬は詳しくないのでわかりませんでしたが、コース内で下馬することは禁止されているそうです。
ですからその行為は審査対象となりましたが、最終的にデムーロ騎手に制裁はされませんでした。
彼はそのルールを知った上で下馬したのです。
私はそれをテレビのニュースで見たのですが、デムーロ騎手の行動に新鮮な感動を覚えました。
彼はなぜそのような行動が出来たのでしょうか。
イタリア人のデムーロ騎手は、昔から騎士道精神がある文化に育ったためかもしれません。
伝統的に守られてきた思想があるのかもしれません。
日本人にはそのような行動は思いつかないでしょう。
最近の日本人が忘れていた大事なモノを教えてくれた気がしました。
人を見たら客と思え
昔「人を見たら泥棒と思え」という言葉がありました。
人に対する不信の表れですね。
もう1つ「人を見たら客と思え」という教えがあります。
自分にとっての自分の周りの人は全てがお客様。
近所の人も友人もいつお客様になるか分かりません。
会社の仕入先の人もいつお客様になるか分からないのです。
それなのについ仕入先の担当者に偉そうな態度を取る人がいます。
ところが、その担当者がその会社の品物を買うとか、お客様を紹介してくれたりすると、とたんに態度が変わる。
傍目から見て「みっともない」です。
江戸時代の商人は常に少し前かがみにして歩いていたそうです。
いつどこでお客様に会うか分からないので、いつでもすぐお辞儀が出来る体制が出来ていたのです。
今はそこまでしなくてもいいでしょうが、それでもいつお客様と会うか分かりません。
その為には普段でも外出する時は恥ずかしくない格好をしたいもんです。
特に人に夢を売る商売や、サービス業に携わる人は気を付けなければなりません。
私も以前、銀行員やホテルマンの時は結構気にしていました。
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」昔の人はいい言葉を残しましたね。
感動の共有
土曜日に雑誌「致知」のAさんとお会いしました。
私が入っている「新現役ネット」という集まりでの勉強会の題材に「致知」を使いたいと思い、その勉強会等のご相談をしました。
1カ月ほど前に、その旨の手紙を「致知」に出していました。
Aさんは土曜日に開催されました「木鶏クラブ札幌」の25周年式典に合わせて来札されましたのでお会いすることが出来ました。
Aさんとのお話しの中でお互いに共通した思いは、「感動の共有の場」の必要性です。
明るく、楽しく、積極的で正しいお思いを持っていても、それを話す相手が周りにいないということがあります。
共感しない人にその思いを話しても、「青臭いね!」とか[甘いんじゃない!」という言葉で切られてしまいます。
歳に関係なく、善き思いを抱き、前向きに生きて行こうとする時、同じベクトルを持った人同士との語り合いは、その人の生き方をより善きものに導きます。
宗教はそれに近いものがあります。
しかし、この勉強会は1つの宗教、宗派から離れた立場を維持します。
善きことを思い、善き行いをすれば、おのずと結果は善きものが得られます。
土曜日はそんな思いを抱きながらAさんとお話が出来ました。
これから仲間と一緒に勉強会の方法を具体的進めてゆきたいと思います。
会議の在り方
会議の在り方について
会議を効率にするために、座ってでなく、立って会議をするという形式が、大分以前マスコミでも取り上げられました。
各事務機メーカーでも、その為の天板の位置が高い会議テーブルも売り出されました。
タバコも厳禁、無駄な話を省き、効率的に結論を出すために考えられました。
今でも実施している会社はあるかもしれませんが、以前ほど聞くことはありません。
中小企業の会社で多い会議の形式は、皆の意見を聞くと言いながら、社長が一方的に話して、結局会議の中では結論が出ないというやり方。
私の会社でも父が現役の時はそうでした。
社長がカリスマ的存在だと特にそうなります。
そんな会議のやり方に異議を唱える形で、先ほどの様な「立って会議」をするという形式が注目を浴びました。
それによって世の中の会議の景色が少し変わった様に思います。
会議は結論出して初めて会議の意味があります。
意見を聞くためとか、情報を交換するとかの目的で会議をするという会社もあるでしょう。
しかしそれは意見交換会、検討会であって、会議とは別ものとしてとらえべきです。
それはブレーンストーミング、ワールドカフェ形式もで行われます。
会議と意味合いを分けることで、「会議は結論を出すところ」という会社内での認識が定着します。
「会議は踊る」ということなないように。
明確なビジョン
カルロス・ゴーンさん。日産の社長です。
ゴーンさんは13年前、瀕死状態の日産を立て直すためにフランスのルノーから社長として送られて来ました。
その経営手腕は凄く、短期間で日産を再生しました。
社長になったその年から業績が急激に良くなりました。
当時、そのことを「下請けに圧力を掛け、徹底した経費削減とリストラによった一時的な業績だ」と評した人も多くいました。
私も「そんなに短期間に良くなるはずはない」と思っていました。
しかし、その後も業績は回復し、成長は続きました。
改めてゴーンさんを見直し、ゴーンさんが書いた「ルネッサンス」という本を買みました。
本を読んで、やはりすごい経営者だと思いました。
そのゴーンさんが日経新聞主催の「世界経営者会議」で講演した内容が昨日の日経に掲載されてていました。
13年間を振り返って「日産が再生出来たのは原価低減やリストラの結果ではない。あるべき姿、ビジョンを描いたから再生出来た。
そのビジョンを世界中の従業員が共有し同じベクトルに向かって行った。
従業員のモチベーションを高め、動機づけするような目標を立てた。
これを維持出来る限り、日産の将来は明るい。」と言っています。
この「世界経営者会議」で稲盛和夫さんも講演されています。
その話の内容を読んでみるとゴーンさんと同じことを言われています。
「リーダーとして経営者は、第1に組織の目指すべきビジョンを高く掲げる。
第2に組織のメンバーとビジョンを共有する。
第3に人間性、フィロソフィが大切。
第4に業績が向上する仕組み作りの能力」の4つ上げています。
全社員が共有出来るビジョンを掲げ、社員とモチベーションを高めながら経営するその姿は2人同じです
。
稲盛さんが常に説かれる「経営の12カ条」の第1項目「事業の目的、意義を明確にする」が何よりも大切なのだということ再認識しました。
少数精鋭
仕事に合わせる。
仕事をする時、暇な時は暇な様な仕事の仕方をしてしまいます。
そしてそれに馴染んでしまうと普通の仕事がきつく感じます。
そのような自分を諌める気持ちのある人はまた回復しますが、そのままダメになってしまう人が多いです。
不景気で仕事が少なくなった時、人を解雇せず仕事をシェアしましょうという考え方があります。
そのような時に起きます。
大事なことは、仕事が少ない時は少人数で仕事をこなし、1人当たりの効率を下げないようにすることです。
その時に余剰となった人には、今まで手掛けられなかった不良在庫処分、製品・商品開発、営業強化また会社内の整理・整頓に振り分けるのがいいでしょう。
景気が回復した時、1人当たりの効率を下げなかった会社はすぐその景気の波に乗れます。
そして業績を伸ばして行きます。
仕事をシェアして1人当たりの効率を下げた会社はそれとは逆に、業績はなかなか回復しません。
「少数精鋭」とは精鋭を少数集めるという意味と、少数にすれば精鋭が育つという意味があります。
不景気で仕事が少ない時代、改めてこの言葉の意味。大事だと思います。
パンのふりかけ
「パンのふりかけ」という商品をご存じでしょうか?
私は知りませんでしたが、昨日ネットのニュースで知りました
ハウス食品が今年の2月に発売した「トーストシーズニング」というものです。
それはシナモンシュガーで、パンにかけて食べます。
ハウス食品は香辛料を中心商品としているので、当初は香辛料売り場に置いたいたそうです。
ところが売り出してみると期待したほど売れません。
そこで、ある営業マンがスーパーにお願いして、それをパン売り場に置いたところ売上が15倍になったそうです。
同じ商品が売り場を変えただけで飛躍的に売れる。
これはどの業界でも共通する事例でしょう。
昔レナウンが消臭効果の高い靴下を売りだしました。
ところが全然売れませんでした。
そこで名前を変え、電車の「通勤快速」を文字って「通勤快足」としたところ爆発的に売れました。
商品そのものは変わっていいません。
商品名を変えただけ、それだけで爆発的に売れたのです。
売る側の固定概念が強過ぎると売り方の選択肢が狭まってしまいます。
売れないと悩んでいる方!
「売り先」「売り方」「売る場所」をもう一度検討してみてはいかがですか?
理不尽なこと
先日、作家の伊集院さんがテレビで「若い人は早いうちに『理不尽』なことは経験するべき」と言っていました。
なるほどと納得しました
同時に、これはとても重要なことだと思います。
世の中全ては自分に都合のいいように動いていません。
また全てがルール通り、決められたように、時には自分が正義と思った通り動いていません。
そして、自分がやりたいと思ったこと、正しいと思ったことが実現出来るとは限りません。
一方、家庭や学校は「理不尽」なことが排除された世界です。
純粋培養な状態で育て、「理不尽」なことは見せようとしません。
でも、そのまま子供が社会に出た時、最初にぶつかるのが「理不尽」なことです。
この世の中は時として「理不尽」なことばかりと思えることもあります。
でもその理不尽さは人を鍛えます。
そしてそれに対する耐性が有るか無いかで世の中の見方も生き方も変わってきます。
草食男子とかオタクと言われる人達はその「理不尽」な世界から逃避しているのかもしれません。
「子供を大事に育てること」と「過保護に育てること」とは似ていますが違います。
私は大事に育ててもらいましたが、過保護ではありませんでした。
改めて親に感謝しています。
ペットを飼っている人
リチャード・ワイズマンという人の本に面白いことが書いてありました。
ペットを飼っている人はペットに似ると言われます。
それを2000人以上の人に対して調査したのです。
その結果、魚を飼っている人は最も幸福観が強い。
犬を飼っている人は最も社交性があります。
猫を飼っている人は最も頼りになると同時に感じやすく、爬虫類を飼っている人は最も独立心が旺盛。
そして寄せられた回答の中には、飼い主とペットの性格がかなり似ているということも示されています。
この類似性はペットとの時間とともに高まっていき、また自分のペットには独特の個性があると思い、それを言いたがるようです。
それと同時にペットには飼い主自身が映し出されることもわかりました。
初めての人と出会って、その人の性格を知ろうとしたらまずペットを飼っているかを質問してみます。
そしてペットは何を飼っているかを確認し、そのペットの性格を聞くのです。
ペットの好きな人は喜んで話すはず。
と言うことはペットの性格からその人の性格も分かってしまうことになります。
ペットを飼っている人はペットのことが話題になれば心を許し、喜んで話してしまう傾向にあるようです。
私はペットを飼っていないの実感がありませんが、面白い実験結果だと思います。
一度ペットを飼っている人に試してみたい気がします。
人事権
会社を経営していると、必ず人事は付いて回ります。
人事・組織作りそのモノは経営ではなく、それに付随するものだと私は思っています。
ところが、その人事・組織をいじくり回しているのを、あたかも経営しているように錯覚している経営者がいます。
本当の経営は何かを知るために、改めて勉強が必要です。
ただ、人事は大切だということは確かです。
そのように人事を・組織をいじくり回す人にとっていい言葉があります。
以前にも紹介しました経団連会長も経験した土光敏夫さんの言葉です。
「人事は神に祈る心境で」と言っています。
「人事は経営者にとって重い負担です。
確かに経営者は人事権を持つがそれは独裁権であってはならない。
神の前に頭を垂れ畏れ謹んで行使すべき権限である。
1人の上位者の判断によって、1人の人間の一生を左右することがあってはならない。
だから関係者を集めて討議し、最後にトップが責任を持って決めるべきである。
その時は神に祈る心境で人事を決するのである。」
ここまで考えて人事をしている経営者は、現在どれほどいるでしょうか。
一度、人事について改めて考えてみては如何でしょうか。
競争力
先日ネットのニュースを見ていたら、衣料品を販売している通販サイトの会社のことが書かれていました。
この会社は急成長していて、以前成功事業例として新聞でもよく取り上げられていました。
そこの社長がTwitterで暴言を吐いてヒンシュクを買っているというものです。
その会社の品物を買うと送料がかかるので、実質価格が高くなり、詐欺みたいだということをある人がネットで書いたようです。
それに対して、「タダで商品が届くとでも思ってるのか?お前のような感謝の気持ちを持たない奴は二度と注文しなくていい。」という社長の反論でした。
私はネットのニュースで見ただけで、詳しいい状況はわかりませんが、社長が絶対吐いてはいけない言葉です。
どんなにお客様から罵声を浴びさせられ、悔しくても口にしてはいけない言葉というのがあります。
その通販会社は衣料品の通販でダントツの実績を上げていたのが、アマゾンもその分野にも入り込み、顧客が奪われているというのが背景にありそうです。
アマゾンは送料が無料というところが強みです。
そのアマゾンに押されて業績が下がって、つい感情的になって発した言葉でしょう。
「ネットでモノを買った場合、買い手がその送料を負担する」というのは今まで当り前のように思われていました。
その当り前の送料負担が無くなれば買い手にとっては実質安くなったようなものです。
以前「Free」という本が評判を呼んでいました。
何で利益を上げるか、その為に何を無料にするかが重要なポイントです。
アマゾンには本の送料を無料というビジネスの形は元々ありました。
送料を無料にしても利益が出る仕組みが出来き上がっていたのです。
しかし先ほどの通販会社にはそれが無い。
通販会社が改めて送料を無料にしても、利益が出るというビジネス形式を構築するのはそう簡単なことではありません。
この業界はある武器を持ってくれば簡単に乗り越えれるという「競争障壁」の低さが、他業界からの参入を許してしまったのでしょう。
勉強になる事例です。
利己と利他
先日知人と話していたことです。
「利己」と「利他」の関係です。
1人で生きている時、自分のことだけを考えて生きていれば「利己」
恋をして人を好きになり、この人を幸せにしようとした時それは「利他」
結婚して相手との暮らしのことばかり考えれば「利己」
子供が出来てその子のためならどんな辛い仕事でも頑張れると思った時は「利他」
しかし妻と子供の家族のことばかり考えていると「利己」
会社を作り、そこの社員のために努力することは「利他」
自分の会社のことしか考えないと「利己」
お客様のために、業界のために頑張ろうとすれば「利他」
このように「利己」が「利他」になったり、「利他」であった行為も視点を変えれば「利己」になっていく。
しかしその「利己」もステージアップされていくと、高い次元の「利己」でドンドン「利他」に近いものになっていく。
「利己」と「利他」
人間の成長とはその繰り返しで作られていくのかと思います。
理屈っぽい話しでした。
共生と循環
昨夜は盛和塾の勉強会がありました。
稲盛さんのビデオを見てそれについて語るのです。
今回は「共生と循環」をメインに話していました。
ビデオは今から20年ほど前、60歳の頃の稲盛さんでしたが、その話す内容は現在とほとんどブレていません。
「共生」とは利己で生きている状態ではなく、他と共に生きている状態です。
そして利他があって自然界は成り立っています。
自然界の生き物は必死で生きていますが、他を踏み台にしてはいない。
また「共生」とは甘やかされる世界ではなく、厳しい世界で生きて行くことです。
それが循環しています。
生きて行こうと一生懸命努力しなければ淘汰される世界。
温室で育てられるのでなく、雑草のようにアスファルトの間からでも伸び上がっていこうとする姿。
厳しい世界の中、他を踏み台にしないでポジティブに生きること。それが「共生」です。
人間も自然界の生き物の1つ。
今回も多くの気付きがありました。
演奏会
昨日は私が習いに行っているサックス教室の仲間と演奏会(発表会!?)がありました。
曲名は「情熱大陸」。
私にとっては高速の指使い。
その日のために、仲間の足を引っ張らないようにと思い、練習しました。
とは言ってもまだまだ、人前でソロ演奏するほどの腕にななっていません。
自分にとってハードルの高い曲をこなすために、時間を見ては練習をする。
演奏会というプレッシャーがあるのでやらざるを得ない。
そのようなプレッシャーがあるからこそ、少しは技術が磨かれているのかもしれません。
毎年1回、今年で3回目になります。
いつまで出来るか分かりませんが、いつかソロ演奏が出来るように夢見ながら楽しんでいきます。
最終講座
昨夜は私が担当している講座「身の丈起業のすすめ」の最終講でした。
最終講では参加者各自が作成した事業計画を発表していただきました。
参加者の皆さんは、私が驚くほどにしっかり事業構想し、それを「事業の目的」「事業の概要」「市場の環境」「事業の将来目標」「事業の課題」「事業の具体的内容」「事業の特色」「販売計画」「仕入計画」「設備計画」「要員計画」別に書き上げて来ました。
その上、資金計画書も書き上げ、5年間の収支予想も算出してきている人もいました。
この事業計画書作成の目的は「事業計画を作るのは大変なこと」という思いを捨てることです。
ですから参加者の皆さんが書いた内容の精度は問いません。
実際に起業する時は、充分調査して書き上げなければなりませんが、今の段階は事業計画書を書くということが大切なのです。
私が今回の講座を担当して驚いたことは、参加者全員が講座を受ける前に自宅でその作業をし、準備して参加した来たことです。
他の多くの講座では参加するだけ、聞くだけで済ます人達が多と聞きます。
ありがたいことに私の講座では過去に担当した講座も含め、多くの人が積極的に学ぶ姿勢を見せ、自宅で自習をして参加されているのです。
担当した講師としては嬉しく、講師冥利に尽きます。
私の「身の丈起業のすすめ」に参加した人達が今後実際に起業するか、またいつするかはわかりません。
でも、もしも私が必要される時はいつでも全力でバックアップしていきます。
今回の講座でも新しい出会いがあり、私自身も成長することが出来ました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。
観の目 見の目
ある本を読んでいてわかったのですが、宮本武蔵の書いた五輪書に「観の目」と「見の目」という言葉が書かれているそうです。
会社である問題を発見して解決していく。
これは経営者の仕事です。
でも問題があってもそれが問題だと気付かない、見慣れてしまって分からない。
そのような注意力の乏しい状態を「見の目」と言います。
大きな問題は、気付くか気付かないか分からないような、氷山の一角の下に隠れていることが多いです。
常に気を配り、身を乗り出して見る目それが「観の目」です。
五輪書には「観の目強く、見の目弱く」と書かれています。
「観の目を強く」は、稲盛さんがよく言われる「有意注意」の言葉と同じでしょう。
考えさせられました。
集合行為論
以前新聞に「集合行為論」という言葉が紹介されていました。
一橋大学の石川教授のが書いた記載記事です。
政治学者のマンサー・オルソン氏が唱えたものです。
この「集合行為論」をTPPを例にして説明します。
TPPで利益を得る人が1億人いて、その利益の合計が10兆円とします。
一方損失を被る人が200万人いて、その損失の合計が8兆円とします。
経済全体としては差し引き2兆円の利益になるのでTPPを勧めた方がよいはずですが、実際にはそうはならない。
それはTPP導入で得るグループ側の利益が1人当たり10万円なのに対し、損するグループは1人当たり400万円になります。
TPPで得するグループは「世論調査」で賛成と答えても、霞が関まで行って「TPP賛成!」と叫ぶ行為はしません。
しかし損をする側のグループは400万円の損がかかっているわけで、交通費を掛け、丸1日仕事をせずとも、そのような行為をします。
ここではTPPを例に出しましたが、政治・経済そして社会問題等においてこの論理は成り立ちます。
マスコミにも取り上げられていることはつい大多数の意見のような錯覚をしますが、実態は違うことがあります。
「集合行為論」
そんな論理があるということを知っておくと、新聞やテレビを見ても、今までと違った別な見方が出来ると思います。
利益とリスク
「利益」と「リスク」は前向きの経営をする時、常に付きまといます。
経営者はこのバランスを考え経営します。
恐がってばかりでは、利益を得れる仕事が出来ません。
だからと言って、準備も段取りもしないで、濡れた丸木橋を下駄で渡るような経営は谷底へ真っ逆さまです。
稲盛和夫さんは「自分は怖がりで心配性だ」と言っています。
だからと言って恐がってばかりいた訳ではありません。
ご存じのように企業を拡大し世界に冠たる会社を作りました。
恐がりの人が慎重に検討して決断・実行することが大切なのです。
私も父から言われていました。
「見通しの立たない仕事はするな!」と。
当り前のようですが、実際には思いだけが先行して事を始め、失敗するケースが多いのです。
ソフトバンクの孫さんがアメリカのスプリント・ネクステル社を買収しました。
その買収金額は巨額で不安視されています。
それでも孫さんは過去の3回の買収で成功した実績から、4回目も成功しますと言いきっています。
しっかり見通しが立っているのでしょう。
ぜひとも成功してほしいと思います。
ちなみに、孫さんも若い頃は稲盛さんの盛和塾に入って勉強していたそうです。
事業計画書2
2日前に事業計画書についてこのブログで書きました。
事業計画書には2種類あって、新しいことを始める時の「新事業計画書」と、同じ事業の中で次年度または中長期計画を立てる「事業計画書」があります。
私はどちらの事業計画作りも経験していますが、その内容は会社トップの経営姿勢、意欲が反映されます。
私が事業計画作りで鍛えられたのは、不可能と思われる目標数字の達成を求められたことです。
自分なりに市場環境を調べ、マーケッティングも行いその結果出た収益予想数字では通らないのです。
それより高い数字が求められます。
そうなると、もう一度計画内容を見直さなければなりません。
求められる目標数字から逆算して、単価を上げることが出来るか、客数を上げることは出来るか、仕入値を下げる可能性はあるのか等の見直しを、これでもかと思われる位します。
その時ツイ弱気になり、数字を作り上げてはいけません。
出来もしない数字を書いて「紙に描いたボタ餅」になってはいけません。
その数字の具体的な裏付けが無ければなりません。
そのようなことをしているうちに、鍛えられました。
もしもトップが単に優しいだけの人では、そうはならなかったと思います。
時には無茶苦茶と思われる要求をされることがありますが、拒否せずまず受けてみること。
そこからまた新しい展開が生まれます。
「おまえが出来ないことを他の人が出来たとしたら悔しくないか!」
こんな言葉をよく言われたのを思い出します。
旅行会
この土曜日・日曜日に、ある銀行の親睦会の旅行会に行ってきました。
銀行が主催するこのような旅行会に参加するのは初めてです。
参加者は20名ほど。ほとんどの人は初めてお会いした人達です。
旅行先は小樽周辺。
企業訪問先は小樽ワインの北海道ワイン工場、余市のニッカウィスキー工場、小樽市内の田中酒造。
全てアルコール関係の企業ばかり。
興味深い話が聞け、珍しいお酒も飲めました。
工場見学 ― 試飲コーナ ― 販売店。
これはどこの見学も同じ流れです。
お陰で沢山のお酒を買ってしまいました。
宿泊は朝里川で一泊。
同室の人は初めてお会いした人。
知らない人と2人で同室というもはあまり経験はありませんでした。
それでもお話しをしていくと、とても興味深い話を聞かせていただきました。
立地のいいところに病院を建ててそれを医者に貸すというビジネスを中心に経営しているそうです。
初めて聞くビジネスです。
親しい人と一緒に行く旅行もいいですが、このように知らない人の中に入り、旅行するのもいい刺激を受けます。
美味しいお酒と料理。それに知的刺激。
楽しい旅行会でした。
事業計画書作成
昨夜は講座「身の丈起業のすすめ」の4講目の日でした。
今回は実際に事業計画書を書いていただく作業を中心に進めました。
「事業の目的」「事業の概要」「市場の環境」等を1つ1つ書き方を説明しながら書いていただきました。
その講座で少し驚いたことがありました。
昨日の講座に参加する前に、既に事業計画書を記入してきている人が多かったのです。
先週の講座で、事業計画書の重要性と書くことはそれほど難しくないことを話し、書き方も説明しました。
参加者の皆さんはそれだけで書上げてきたのです。
ですから今回は自分の書いた事業計画書を確認、修正しながら私の話を聞いていました。
熱心に起業について学ぼうとしている姿勢が見られます。
事業計画書というものは、私も過去に何十回として書きましたが、書き慣れるとそれほど難しいものではなく誰でも出来ることです。
ただその経験が無いと、いつまでも「大変そう!」というイメージが付きまといます。
今回簡単ですが、実際に自分の事業についての架空の事業計画書を書くことで、それが少しでも払しょく出来たらいいと考えています。
この講座も来週の1講で終わりです。
次回は参加者各自から作成した「事業計画の発表」する日です。
最後なので少し寂しい気がしますが、どのような事業計画発表になるか楽しみです。
長所のみとらば可なり
「人はその長所のみとらば可なり。短所を知るを要せず」
これは江戸時代の儒学者萩生徂徠の言葉です。
同じようなことはよく言われることです。
人は長所も短所もあります。完全な人はいません。
それが分かっているのに、人はつい他人の短所ばかりに目が行きがちです。
会社の中にもあります。
ついその人の欠点ばかりに目が行き、本来の能力を見ようとしない。
それが行き過ぎると減点主義的に人事評価をしてしまいます。
結果その人を使いこなせずいると、お互いに不幸です。
上に立つ者の度量の大きさが必要と言われるのは、こんな時にも表れてくるのでしょう。
父の文章
昨日、会社の女性社員から「書類を整理していたら会長が書いた文章が出て来ました」と手渡されました。
父は2年前に93歳で亡くなりました。
その文章は「創業の思い出」という題名で書かれています。
24歳の時、父親(私の祖父)から「親元から離れて事業の稽古をしてみよ」と言われてから、苦労して創業していった姿が書かれています。
読んでその中で特に考えさせられたことがありました。
父は当初は「セメント瓦」の会社を創業しました。
大変な苦労をした末、初年度から多くの利益を出しました。
今で言うと1億円近くになったようです。
父は喜び勇んで帳簿一切を風呂敷に包んで父親のもとに報告に行きました。
どんなに喜んでくれるかと思って帳簿を見せ報告したところ、父親はそれに目もくれず「困ったなア」と言って頭を抱え込みました。
その姿に私の父は困惑しました。
後で分かったことですが、父親は当時としては驚異的多額な利益が若い経営者を慢心させ、経営を甘く見ることを心配した為だったのです。
言葉に出さなかったけれど、「おごるな!」と諭したのです。
このやり取りを読んで、「多額の利益を出した父も凄いけれど、その父親(祖父)も凄い。」と思います。
自分の身内をほめるのはおかしいですが、素直にそう思います。
残念ながら父が書いたこの文章は途中で終わっています。
父の経営経験を書いた文章は私の教科書です。
探せばまた出てくるかもしれません。
父は死んでからも色々な形で教えてくれています。
「スペシャリスト」と「ゼネラリスト」
よく「スペシャリスト」と「ゼネラリスト」という言葉が使われます。
専門職の人を「スペシャリスト」と言います。
総合職の人が「ゼネラリスト」です。
「ゼネラリスト」は広い範囲の知識が求められます。
一方「スペシャリスト」は専門の深い知識が求められます。
しかしその深い知識を求めるということは、それに関連する知識・情報も追求し学ばなければなりません。
それを避けては本当の「スペシャリスト」「職人」とは言われません。
それは深い井戸を掘るのに似ています。
深い井戸を掘るためには、幅の狭い穴では無理です。
周りを広げ、幅を広げていって、初めて深い井戸が掘れるのです。
それと同じです。
一時的には「オタク」と言わる専門職も、そのままでは行き着くのは浅い穴を掘るだけで終わりです。
幅を広げるのに他の分野の勉強もします。
結果「ゼネラリスト」に近い「スペシャリスト」が生まれ、リーダーとしての力も発揮できます。
ノーベル賞を取られた山中教授の話を聞いてそんなことを考えました。
数字に弱い
数字に強い人とそうでない人がいます。
私は元銀行員ですがどちらかというと数字に弱い方です。
暗算などは苦手です。
私の父は結構数字に強かったようでした。
家具製造会社を経営していた父は、レストランに行って、そこのテーブルを見て「これはナラ材を〇〇石(こく)使っている。石単価は△円なので材料費は◇◇円だろう」と算出していました。
(石とは、木材を、尺貫法における体積を表す単位。木材の量を計るのに使われました。)
父は商売に関するモノをすぐに数字に置き換えてしまう習慣がありました。
これは経営者にとって大切なことです。
経営者の中に「私は数字に弱く、全て会計士さんにお任せしています」という人がいますが、それでは経営者失格でしょう。
経営判断の根拠は数字です。
例え数字に弱くても、数字から逃げてはいけません。
弱くても数字で物事を見るようになると慣れて来ます。
それが出来なければ、どんぶり勘定の経営しか出来ず、つぶれてしまいます。
一方、数字に強いと自認する人もいます。
彼らは数字に自信があるがために、数字だけで経営判断をしようとする人も多いです。
現場にも出ず、社長室で経営しようとします。
仕事は現場で起きています。
数字を自分のモノにすることは大変重要なことですが、その割合は経営中では2割くらいでしょうか。
数字は経営基礎素養として大変重要です。
数字は経営に欠かせられないものですが、それが全てではないということを良く認識して経営して行かなければなりません。
ほめて伸ばす
子育ての本や会社の人事教育のに関する本に「ほめて育てる」という言葉がよく出て来ます。
その人のやる気を出すために使われています。
確かに子供はテストでいい点数を取り、親や先生にほめられるとその気になります。
次も頑張っていい点数を取りほめられようとします。
その内に子供は勉強が楽しくなり、学力も上がり優秀な学生と言われるようになります。
ここまでは順調でいいのです。
でもほめられて育てられた子供には欠点が生まれます。
最大の欠点は失敗を恐れることです。
失敗しそうな事は極度に嫌います。
そして親や先生に気に入られる様な事や無難な道を探します。
そこにチャレンジ精神は育ってきません。
優秀だけれど自分の枠からはみ出すことが出来ないのです。
このほめて育てるという方式を会社の人事で使っているところがあります。
やはり間違えています。
決められたことしか出来ない人間を育ててるだけで、何かの挑戦しようとする人は生まれません。
それでは褒めることはすべて悪いかというとそうではありません。
大事なのは結果をほめるのでなく、一生懸命頑張ったことをほめるのです。
挫折した子供の方が伸びると言われます。
会社でも、失敗を恐れず何かに挑戦した人は評価されるべきです。
懸命に頑張った結果、失敗しのであればその努力は認めてあげるべきです。
失敗を恐れ、何もしない人間より何倍も評価されるべきです。
失敗したことはとがめても、挑戦したこと、頑張ったことが評価されるとまたやる気が出ます。
人はほめられて伸びます。
でも、ほめるところを注意してほめましょう。
最後の1冊
昨日はこのブログで「本の出会い」について書きました。
良き本に出会える、気に入った本に出会えるのと同じように、あまりしっくりこない本を買うこともあります。
その良き本も、そうでない本もいつの間にかドンドン溜まります。
今まで何度か処分して来ましたが、まだ溜まっています。
蔵書として保管したくても、そのような保管する場所がなければ処分するしかありません。
60歳を過ぎたら身の回りを整理しようと思っていたのですが、溜まるばかり。
ブックオフにも何度か出しました。
これから本格的に処理していこうと考えています。
まず50冊以内に抑え、最終的には自分の手元に置く本を10冊以内するのが目標。
その時10冊に絞るとすれば、残す本はどの本になるか。
そして究極的には最後の1冊はにしたい。
「その時の本はどの本なのか」と考えています。
この10冊の本、そして最後の1冊を選んでいく過程で、自分のこれからの「生き着くべき場所」の方向が見えてきそうです。
まずは50冊選定にかかります。
出会い
出会いには、人との出会い、モノとの出会い等があります。
折角の出会いがあってもそれを「良き出会い」と感じられる感性を普段から磨いておかないとダメです。
出会いの中で私が大切にしているのは本との出会いです。
今の私があるのは良き本との出会いがあったからだと思っています。
私が30歳代の初め頃まで、あまり本を読んでいませんでした。
家に帰ると酒を飲んでテレビを見て寝るだけ。
ある時、私の部下と話をしていると本の話が出ました。
彼は多くの経済小説を読んでいるようでした。
話を聞いて私は奮起しました。
「私も読もう!」と思い、手始めに城山三郎さんの本を片っ端から読みました。
次は松下幸之助さん、本田宗一郎さん、土光敏夫さんに関する本も読みました。
安岡正篤さん、中村天風さんの本も読みました。
そして稲盛和夫さんの「敬天愛人」という本に出会い、稲盛さんを師と仰ごうと思い、盛和塾に入塾しました。
本で人生が変わりました。
そんなこともあって私は暇があれば本屋をのぞきます。
古本屋見も行きます。
お陰さまで時々良き出会いがあります。
今日もどこかの本屋に行こうかと思っています。
会社広報
私の友人のSさんが「会社広報」の仕事を始めました。
「会社広報」とは自社から発信したい理念や商品・情報を的確に伝えることです。
「会社広報」は大手の会社では力を入れていますが、中小企業は必要だと思ってもそこまでする余裕がありません。
Sさんの仕事は中小企業向けの「会社広報」のアウトソーシング事業です。
中小企業や起業したばかりの会社では、いくらいいモノを作り売り出しても発信能力が無いため売れず、挫折することが多いと思います。
Sさんは以前、大手リース会社の広報室長として活躍した実績があり、その経験とノウハウを生かした仕事が出来ます。
広報として一番効果があるのは、新聞・テレビ・雑誌などのメディアに取り上げてもらうことです。
取上げてもらうためにメディア向けに書く文書とプレスリリースと言います。
Sさんはその書き方、そしてメディアへの戦略的PRを手がけてくれます。
北海道の中でも、札幌はまだメディアとの接点はあります。
でも地方になるとそれは少なく、商品が表に出て来れず、いい商品が埋もれていることが多いはずです。
Sさんの様な「会社広報」専門の人が出て来て、中小企業・起業家の事業を支援してくれることは必要なことです。
私のレンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」もSさんと契約し、オフィスに入居されている会社の「会社広報」の支援を依頼する予定です。
起業成功者が1人でも多く出てくるのを支援するためにも、Sさんの力を借りることにしました。
隠れ家
昨夜は久しぶりに友人が属しているバンドの演奏会に行ってきました。
懐かしい曲を聞かせてもらいました。
その演奏場所はいつものライブハウスと違い、ある設計会社の中にありました。
地下鉄の駅から1~2分のところにある5階建の小さなビルですが、その5階エレベータを降りたとこと全てがジャズバーになっています。
ここは毎日営業しているわけではなく、ビルオーナーが自分のバンド仲間を集めて演奏したり、時々演奏会場として貸しているようです。
20坪程でそれほど広くはありませんが、流石設計家が作っただけあって素敵なところでした。
天井高さは5メートルはあり、壁・天井はコンクリートそのまま。
でも、その形状は深く波打って、音響が反響しないよう造られています。
バーカウンターもあり、テーブル椅子もオーダー家具の様です。
オーナーのTさんとは初めて挨拶しましたが、私と同じ高校の1年先輩。
64歳です。
ご自分もエレキギター等の楽器を演奏そうするそうです。
しっかり会社を経営しながら、自分の生き方を楽しんでいるのです。
以前にもご紹介しましたが、自分で「漁師番屋」を持つ60歳代の男性と同様、このTさんも「隠れ家」をもっているんです。
自分なりの「隠れ家」、私もまた欲しくなりました。
夢を叶えるために
今、起業支援の講座を開いていますが、その時、常に意識してお話しているのは、1歩踏み出す勇気です。
自分の夢をどんなに素晴らしく語ってみても、踏み出さなければ何の意味もありません。
夢を描くことは大切です。
願望を強く心に描き続け、イメージを明確にし、真剣に思い続けなければなりません。
「そうなればいいな・・・」という漠然と思っているだけでは、想念にもパワーが伴わないために、潜在意識への働き掛けが弱くなってしまいます。
そうなると自信や勇気もみなぎらず、信念も揺らいでしまい、些細なトラブルやアクシデントでも「自分には無理だ、ダメだ」と思いこんでしまいます。
一方、夢を持ってイメージさえ行えば潜在意識に到達し、願望が叶うと錯覚している人がいます。
確かに、鮮明なイメージを繰り返していけば潜在意識に到達し、願望を叶えさせようとします。
しかし、それには願望を目指した行動をしなければ、いつまでたってもその人の人生は変わりません。
行動こそが重要なのです。
これは講座で話しながら、自分に言い聞かせていることです。
色について
人にとって「色」は大変大きな影響を与えるモノだと感じます。
黄色を見ると楽しくなります。
赤い色を見ると血が湧くようになります。
青い色を見ると冷静になれます。
緑を見ると心が癒されます。
この色を上手く使うと自分の心をコントロールすることが出来ます。
以前聞いた話ですが、ある女優さんが自分の家を造る時、最後までこだわったのは自分の部屋だったそうです。
そして最終的に自分の部屋のドアの色を真紅にしました。
仕事に行く時、部屋で準備し、「出かけるぞ!」と部屋を出る時、その真紅のドアを見て自分を奮い立たせるのです。
やる気で出かけるための工夫です。
我家はそこまで「色」にはこだわって造っていませんんが、1つ緑が見える窓があります。
居間の窓から見えるお隣の庭。
最近手入れされないせいか、色々な木が密集し、私の敷地までせり出すほどです。
でも、そのうっそうとした木々の緑がまるで山の中にいるような思いにさせてくれます。
それこそ「借景」です。
周りに緑が少なくなっているこの近辺。
休みの日にその窓の傍で、ゆっくりした時間を過ごすことは、心地よいものです。
妻が東京に「出張」している間、1人時間を楽しみます。
歩合制
仕事、特に営業には歩合制というものがあります。
その制度は今はもう少なくなってきていると思います。
「契約を取る為には何でもアリ」とか、取引後はアフターサービスが置き去りにされる等、その制度の欠陥が指摘されてきました。
歩合制にはもう1つ心理的な問題もあります。
その心理が、昨日紹介しました「その科学が成功を決める」という本に書かれていました。
実験結果があります。
公園のゴミを拾ってもらうのに、AとBの2グループに分けました。
Aグループには謝礼としてかなりの額のを、Bグループにはごく少額を払うと約束。
1時間後に、自分はどれだけ仕事を楽しんだかを参加者全員に採点を頼みました。
結果10点のところAグループは平均2点、かたやBグループは8.5点で、Bグループの方が断然楽しんだそうです。
高い報酬をもらったAグループの心理は「報酬が高いということは嫌な仕事だ」と無意識うちに判断してしまう。
一方、Bグループは「報酬が少ないのはきっと楽しい仕事なんだ」と思う。
実験の結果からみると、やる気を出して仕事を楽しむ為には多すぎる報酬はマイナス効果になりかねないのです。
ニンジンを鼻先にぶら下げられても、それほど成績は上げられないのです。
仕事は報酬ばかりでなく、楽しく、やりがいの有る内容でなければ続けられません。
仕事が終わった後に、思いがけず小さなプレゼントをもたったり、その仕事を褒めてもらう方が満足度が高いのです。
経営者にとって大事なポイントです。
都市伝説
最近読み出した本があります。
リチャード・ワイズマンという人が書いた「その科学が成功を決める」という本です。
「成功する自分をイメージする方法はむしろ逆効果!」
「子供の知能や才能をほめて育てると、とんでもない結果を招く!」等。
今まで一般に言われ、信じてきた「常識」を否定することが書かれています。
この本の中で改めて驚いたことが書かれていました。
以前別の本で読んだことですが、「イエール大学の目標達成研究」というものがあります。
これは1953年にイエール大学のある研究チームが学生に面接し、うち3%の学生に人生で達成したい目標を書き出してもらったところ、20年後にはそうでない学生と大きな差がついたというものです。
自己啓発本などで良く取上げられていますので、ご存じ人も多いと思います。
私も目にしました。
ところがこの実験が実際に行われてという形跡はないのです。
アメリカのビジネス雑誌の記者がこの研究について追跡したのですが、その証拠も証言も得られなかったようです。
この実験・研究は都市伝説だったのです。
このように自分は信じていたけれど、そうでなかったということはよくあることかもしれません。
時には「天の邪鬼」的な見方も大切です。
この本はゆっくり読んでみます。
琴似B級グルメ祭
昨夜も飲み会でした。
集まったメンバーは銀行支店長、保険代理店社長、IT会社社長、デベロッパー会社専務、染色会社取締役そして私の6名。
皆さんは仕事がそれぞれ違いますが、私達が住む琴似に関連した仕事をしている人達です。
皆さんに集まっていただいたのは、小さいながら「異業種交流」を図りたいと思ったからです。
話の中では琴似における起業支援の話も出て来ました。
琴似の街にはマンションがドンドン出来て人口密度が高くなっています。
琴似で仕事をしている人、起業しようという人達も増えています。
彼らの仕事の成功を支援・応援するのです。
その1つに、琴似限定の「B級グルメ祭(仮称)」を来年開きたいという話が出ました。
参加した6名がそれぞれの立場で協力し、これから賛同者を集め行けば出来そうだという思いで盛り上がりました。
場所はJR琴似駅前の広場という案も出ました。
「楽しいこと」は人を引き寄せるはずです。
現在は思いだけが先行していますが、夢を膨らませて、形を作ってゆきたいと思っています。
私も出来るだけ参加して協力して行きたいと思っています。
国民の義務
昨夜、親しい人達と食事会をしました。
その時に出た話です。
国民の義務についてです。
憲法で定められている国民の義務は「教育」「勤労」「納税」です。
現在の日本にはこの国民の義務を果たしていない人達が沢山います。
国民の権利は「生存権」「教育を受ける権利」「参政権」です。
この権利は日本ではおおむね守られています。
重要なのは国民としての義務を果たすことです。
国民が権利は主張するが、義務を果たさないと国は滅びます。
生活保護受給者は戦後の混乱期に200万人を超えていたのが、現在はこんなに裕福なのに209万人を越しています。
戦後の混乱期は本当に多くの人が餓死をする位苦しい時でした。
現在そのような人はほとんどいません。
本当に必要な人に支給されるべきなのですが・・・
暑い夏の日、ヘルメットをかぶりながら、交通整理をしている「棒振りさん」がいました。
その「棒振りさん」は私より年上だと思います。
道行く人に優しい声を掛けながら誘導している。。
その姿を見るとつい、「お疲れさま」と声を掛けてしまいます。
「汗水たらして頑張っている人がこの日本を支えている」
私はそう思っています。
オータムフェアー
先週の土曜日に札幌の大通公園で行われている「オータムフェアー」をのぞいてみました。
のぞいてみようと思ったのですが、その人の多さに巻き込まれ、身動きが出来なくなり、その流れに身を任せたまま、やっとの思いで抜け出しました。
すごい人の多さです。
「オータムフェアー」では道内各地の美味しい産物を使った料理を提供しているようです。
食べることが好きな私も、このすごい数の人の中では、挑戦する意欲も失せてしまいました。
それにしてもすごい数の人です。
提供されている料理の価格は決して安いものでありません。
それでも延々と並んでいるのです。
テレビで紹介された料理などは特に人気が高いようです。
私達夫婦は早々に大通公園を離れ、別のレストランで昼食を取りました。
帰りに丸井今井が経営する「キタキッチン」に寄ってみました。
ここは常に道内の特産品を売っていますが、ここも常に人でいっぱいのところです。
道内各地の海産物、肉・乳製品、野菜が売られています。
私も含め、食べる事にお金を使う人がいかに多いことか。
グルメ番組の影響なのでしょう。
統計上、毎年上がっているエンゲル係数を物語っているように思います。
身の丈起業のすすめ
昨夜からご近所先生講座で「身の丈起業のすすめ」を開講しました。
来月の19日まで5回あります。
受講者の皆さんは物事に前向き、積極的な方々ばかりで、良き人達との出会いでもあります。
この「身の丈起業のすすめ」は今回で4回目になります。
毎回同じような講座内容の項目で進めるのですが、受講者の受講姿勢によって話す内容は大分変わってきます。
講座を開講する度に思うのですが、教えるというのではなく、教えられるという思いを常に再認識させられています。
これからの講座、楽しみにしています
勉強会
昨夜からまた勉強会を始めました。
これから月1度の勉強会になります。
題材は稲盛和夫さんが書かれた、「心を高める、経営を伸ばす」という本を1項目ずつ読んで、話合います。
話合うことで、理解が深まるし、心に残ります。
「こうあるべきだ」と自分で言えば、その言葉が自分を縛り、自然と「そのようにしよう」と行動します。
この勉強会のメンバーは「身丈会」と称する、「身の丈起業のすすめ」という私の講座を受講した人達の集まりです。
これから楽しみな勉強会です。
技術職の会社
数多くの会社の中には、資格や技術を看板に経営しているところがあります。
会計事務所や法律事務所、その他にインテリアコーディネーターや設計会社。
先日の盛和塾の例会でも国際特許事務所の社長が経営体験を話していました。
その事務所は250名の従業員を抱え、弁理士免許を持っている人が200名以上います。
そこで疑問に思うのは、資格や技術があれば自分で独立した方が実入りがいいはずでは?
私の身近の会計事務所でも独立志向の人が多いと言われています。
独立せずその会社で仕事をするというのは何かあるはずです。
それは会社に魅力があるからです。
この会社に働いていて良かったと思えるからです。
それはやはり経営者の人格、経営方針そして従業員を大切にしている会社だからです。
しっかりした経営理念やフィロソフィがあって、それを守り追求する姿勢こそが会社の魅力になります。
私の会社は家具工場も経営していますので、家具の修理にも興味があり、その実態を調べたことがありました。
そうすると、札幌ではほとんどが個人経営。従業員も多くて3人程度。
なぜ会社を大きくしないかと聞けば、従業員に修理技術を教えると、すぐに独立してしまい、自分の競争相手になってしまうからだと言います。
一方、東京には従業員200名以上、年間30億円以上売上を上げている修理専門会社もあります。
やはり経営者の器量の違いでしょうか。
はんこの大谷
先週の13日に盛和塾札幌例会が開催され、2名の経営者による経営体験発表が行われました。
その中で新潟に本社がある株式会社大谷の大谷勝彦さんのお話しは大変素晴らしく心に残りました。
そのお話しを少し紹介したいと思います。
株式会社大谷は「はんこ屋」さんです。
お母さんが始めた3.6坪のお店を日本一の「はんこ屋」にしました。
現在全国に「はんの大谷」として展開しています。
私はお話しを聞いて、その業容拡大の素晴らしさばかりでなく、その生き方に感銘を受けました。
若い頃に原因不明の難病にかかり、命は長くないと医者に言われながら、何度も手術を繰り返していました。
医者に、放射線治療を2度も受けて生きている人はいないとまで言われました。
それでも新潟一、日本一の「はんこ屋」になるという夢は持っていたそうです。
ある時、最愛の娘さんが交通事故に会い、生死をさまよった時、自分の命と引き換えにしてでも助けたいという思いになりました。
幸いに娘さんは助かりましたが、その時難病を抱える自分に対する母親の愛情の深さを改めて知ったそうです。
そのようなこともあり、株式会社大谷では弱者に優しい会社を目指し、積極的に障がい者を雇用するようになりました。
そして、その障がい者を雇用していく中で、彼らの親もまたその子供達の将来を大変心配しているの知ったのです。
それから大谷さんは障がい者にハンコ作りの職を手に付けさせ自立させる。そして一生面倒をみることを決意しました。
その為にも日本一の「はんこ屋」になるとしてのです
会社の経営理念の中に「社会福祉に貢献する集団を作る」と書き加えました。
また、この度社長を降りる時受け取った退職金2億円以上も障がい者のための施設作りに使われるそうです。
この大谷さんの話を聞いて稲盛さんの言葉です。
随分前に大谷さんにお会いしたことがありましたが、その当時は病弱であったので、今お会いして見違えるほどの元気ななっています。
「善きことを思い、善きことを行えば、善き結果が生まれる」見本のような生き方です。
「大きく美しい利他の心」と評していました。
大谷さんのお話しは自分の生き方をもう一度問われるような話でした。
札幌発寒のイオンにもあるそのお店にも行ってみようと思います。
週末の3日間
今日は休み明け。
いつもと違い少し疲れています。
金土日曜日の3日間にわたって、外で過ごしたことが響いているのかもしれません。
金曜日は盛和塾で稲盛さん達と鮭遡上観察。
土曜日は友人達が我が家に集まり、11時から庭でバーベキュー。
6時くらいまでの飲みっ放し。
日曜日は始めてのパークゴルフを経験。
全て大変楽しかったです。
でも長い間外にいるというのは、身体に応えます。
最近は会社内で仕事をする方が多いせいでしょうか。
私が営業マンだった頃はほとんど毎日外回り。
毎日のことなので慣れたのでしょうし、また若かったのでしょう。
疲れを感じた思いはありませんでした。
それにしても、体力不足、運動不足を感じる3日間でした。
もう少し外に出るようにしまします。
稲盛和夫さんを迎えて
13日14日に開催されました盛和塾札幌例会が終わりました。
稲盛さんを13日に空港へ迎えに行き、一緒に回転寿司の「はなまる」さんで寿司を食べたのは一番の思い出になりました。
稲盛さんが最初に注文したのはサンマのお寿司。
「私はこれが食べてくしょうがなかった」と言って、2皿を食べます。
回転台の傍に座っていた稲盛さんは「あなたも食べなさい」と言われ、同じサンマのお寿司を取っていいただきました。
話は難しい話しは無く、世間話。
楽しい時間を過ごしました。
ただ、緊張と楽しさ、嬉しさの中で舞い上がり、写真を取るのをすっかり忘れてしまい後悔。
でもありがたいことに、その時、向かい側のカウンターに同じ盛和塾の仲間がその様子を写真に撮ってくれていました。
感謝!
例会での経営体験発表会の様子は後日改めて書きます。
素晴らしい経営者達が沢山いました。
13・14日はすっかり稲盛さんのミーハーになった2日間でした。

稲盛和夫さん来札
今日は稲盛和夫さんが来札し、例会が行われます。
これは盛和塾の塾長例会です。
札幌で塾長例会が開催されるのは4~5年ぶりになります。
全国ばかりでなくアメリカや中国からも参加者があるそうで、600名を超える塾生が集まります。
今日は午後から例会、懇親会があり、明日はツアーを組んでいます。
今日明日、稲盛さんの傍でお話しが聞けるのが楽しみです。
私はこれから稲盛さんをお迎えに千歳空港に行きます。
例会などの様子はまた報告します。
計画は予定ではない
昨日のブログで土光敏夫さんの言葉を紹介しました。
私は以前から土光さんを尊敬していて、若い頃は土光さんの本を読んでいました。
その中の1冊を再読いると「成程!」ということが書いてありました。
これを紹介します。
「計画とは『将来への意思』である。将来の意思は、現在から飛躍し、無理があり、実現不可能にみえるものでなければならない。
現在の延長線上にあり、合理的であり、実現可能な計画は、むしろ『予定』と呼ぶべきであろう」
これを読んで、自分が今まで、この「予定」と言われるモノを「計画」としてきたことを反省させられます。
「予定」であれば、特別努力をしなくても達成出来るものです。
土光さんは続けて書いています。
「計画は自己研鑽の場を作る高い目標を掲げ、何が何でもやり抜く強烈な意志の力によって、群がる障害に耐え、隘路を乗り越える過程で、心の人間形成が行われる」とも言っています。
やはり強い経営者としての心構えを感じます。
社長の仕事
私達の周りには日々色々な情報が流れ込んできます。
毎日読む新聞の他にテレビ、ラジオ、ネットのからの情報など様々です。
その中から必要な情報を取り出すのですが、時として偽りの情報もあります。
また偽りではないのですが、発信者にとって都合のいい事実だけをつなぎ合わせた情報もあります。
それを見抜くのはなかなか難しいものです。
そのようなことが会社経営していても起きます。
競争している企業は時として、相手を意識して、あえて誤った情報を発信し、混乱させたりします。
会社内では営業から上がってくる情報が疑わしいこともあります。
経営者は常にそのような情報から経営判断をしなければなりません。
しかし、そのような誤った情報から判断すると、誤った決定をすることになります。
それでは経営者はどうしたら良いのか。
会社の中にいてはダメです。
毎日自分の足で歩き、得意先や仕入先、銀行等から直接情報を取りに行きます。
それは決して営業に行くわけではありません。
色々な人から話を聞き、情報仕入れと情報判断能力を高める為です。
一方残念ながら、経営数字だけを見れば経営が出来ると思っている経営者がいます。
部下から上がってくる情報を充実させようとして、社長の足や耳の役目をする「社長スタッフ」なるものを作る社長がいます。
しかし、会社内に長くとどまっている社長に「優れた社長」はいません。
自分が得た情報と、部下から上がってくる情報を突き合わせて、その結果より良い決定がなされます。
社長がそのような行動をすることで、自分なりの判断能力が高まると、分析能力も高まります。
色々な情報を「裏から見る能力」も高まります。
石川島播磨重工や東芝の社長、経団連、臨時行政調査会会長を歴任した土光 敏夫氏の言葉があります。
東芝の再建に入った時に言ったそうです。
「社員諸君にはこれから3倍働いてもらう。役員は10倍働け。俺はそれ以上に働く」
やはり社長は会社の中で一番働く人です。
連帯保証人
仕事をしていると、多くの人との間に交流が生まれます。
その中で仕事以外にでも依頼事を受けることがあります。
私は出来るだけその意向に応じたようと思い努めています。
ただ絶対応じないのは保証人です。
特に連帯保証人。
元銀行員ですからその怖さはよくわかりますし、若い頃から父に「他人の保証人だけにはなるな!」と言われてきました。
この保証人は親子の間でもしてはいけません。
この事は以前にもブログで書きました。
例えば起業する時、資金が足りないので銀行から借り入れします。
その時、連帯保証人として父親に受けたもらおうとします。
父親は「息子だから仕方がない」との思いがあり受けます。
息子の事業がうまく行けばいいのですが、ダメだった時、息子は勿論、父親まで財産を無くしてしまいます。
父親が保証人にならなければ、たとえ息子がダメになっても、父親は無傷ですから息子の生活を支援することが出来ます。
起業支援しようとするなら保証人とならず、資金提供の方がいいのです。
借入の話のついでに。
連帯保証人は連帯債務者とも言われ、お金を借りた本人、債務者と同様に扱われるということです。
よく分からないでハンコを押すと、とんでもないことになります。
旅と旅行
朝晩が涼しくなり、札幌は秋の気配を感じます。
それと同時にどこか「旅」に出たくなります。
学生時代はしょっちゅう「旅」に出ていました。
「旅行」でなく「旅」です。
私の理解では「旅行」は「行き先」「出発・帰宅日」は決まり、宿泊先まで決まっていること。
「旅」は「行き先」も「日程」もアバウト。
帰る日も決めていない。
そんな「旅」にあこがれ、バック1つぶら下げて色々なところへ行きました。
そんな「旅」も帰るところがあるから「旅」と言えるのです。
帰るところがなければ「旅」ではなく「さすらい」になります。
若い頃は「さすらい」にも憧れましたが、やはり帰るところがなければ寂しいです。
今はもう「旅」することも無くなりました。
せいぜい妻と「旅行」することぐらいでしょう。
でもそれはそれで楽しいものです。
今年の秋は紅葉を見に京都にでも行こうかと思っています。
違憲状態
私はあまり政治絡みの話はしたくありませんが、今日は特別。
新聞等では総選挙が近いと報道されています。
1票の格差が違憲となっているにもかかわらず、それを是正することもせず、ただ解散、総選挙へまっしぐら。
すべての政党が同じようです。
議会は立法府です。
法律を決める立法府が、最高裁判決を無視し続けているのです。
総選挙してしまえば後は何とかなると思っているのでしょうか。
もしも総選挙がこのまま行われると、すぐに違憲として裁判所に提訴されるでしょう。
結果、選挙が破棄されます。
総選挙には700~800億円の選挙費用がかかると言われます。
700~800億円の税金が無駄になるかもしれないのに、議員たちは平然として自分達の都合だけで推し進めています。
選挙が無効とされた時には、かかった費用を全て、衆院議員全員に損害賠償として請求しなければならないでしょう。
株式会社に置き換えてみると、会社経営に不正がった場合、それを決定した取締役は株主から責任を追及され、損害賠償を請求されます。
当り前のことです。
今後の動きを注意深く見てゆきたいと思います。
楽あれば苦あり
以前にユダヤ人と日本人の違いについて書きました。
今日もその流れになります。
日本には「苦あれば楽あり」という言葉があります。
これは「苦しくても我慢をして頑張ればいいことがある」という教えです。
中国にも人間万事塞翁が馬(じんかんばんじさいおうがうま)ということわざがあります。
これは「楽の後に苦があり、苦の後に楽があり。それは繰り返す」という教えです。
ユダヤ人は逆です。「楽あれば苦あり」だけ。
これは「好調な時こそ将来起きるリスクに対して対処しておかなければならない」という教えです。
ユダヤのことわざが日本と中国のことわざと違うのは、ユダヤ人の教えは「苦の後に楽があるとは限らない」ということです。
「好調」な時こそ努力して、その「好調」をより伸ばしておかないとダメ。
「苦」は何も意味が無いのです。
これは会社の経営にも通じるところがあります。
好調の時こそ、次の1手を打っておかなければならないのに、その上に胡坐をかき、努力を怠り、苦しくなってから頑張る。
そのような姿を諌めている言葉の様に思います。
琴似神社の銀杏
9月の3日4日は琴似神社のお祭でした。
4日は本祭りで神輿行列が出ます。
例年のごとく私も裃行列の1人として参加しました。
行列に参加するために琴似神社に集まり準備を終え、境内で待っていた時の話です。
境内には大きな銀杏の木があります。大人が3人で手を広げても届かないくらい太い木です。
よく見ると実を沢山つけています。
行列に参加する人達の話しでは、この銀杏の実は素手で触ってはダメだそうです。
ウルシと同じような成分があり、実を触った手でおしっこをして、オチンチンが腫れたという実体験を話した人もいました。
神主さんの話では銀杏の実は臭く、特に拾っていいないとのこと。
欲しい人が拾っていく程度で、大部分は処分に困り放置していそうです。
「勿体ない!」
琴似神社はパワースポットと言われているところです。
そこで生った銀杏の実はパワーがあるかも?
「ご利益(りやく)の物語」を作って売り出せば神社の利益にもなりそうです。
今度機会があったら宮司さんに提案してみます。
採用しない人の基準
今、若い人の就職難がよく話題にされています。
就職試験に受かる為、如何にしたら面接に通るかのテクニックばかりを指導している学校まであります。
一方会社側は、如何にしたら「良い人材」をとろうかと考えています。
でも、なかなか「良い人材」はとれません。
特に中小零細企業には「良い人材」その者が来ません。
採用の結果、「何でこんな人間を採用してしまったのだろう」という後悔が起きることも多いものです。
それでは「良い人材」が来ない中小零細企業の採用方針を少し変えてみたら如何でしょうか。
「良い人材」とは逆に、「こういう人間だけは採用しない!」という最低基準を決めておきます。
たとえば「挨拶が出来ない」「協調性が無い」「感謝の気持ちが無い」等、日常的、常識的なことが出来ない人間は採用しないとするのです。
そうすることで「採用したくない人」のレベルは維持されます。
このような採用方法は一見後ろ向きの様ですが、時としてそのような人の中から優秀な人材は見つかるものです。
「採用しない人の基準を決める」という採用方法。
試してみる価値はあります。
安全はタダでない
「日本人は『水と安全はタダ』と考えている」というのは、30年以上前に出版された「日本人とユダヤ人」という本に書かれています。
例えばお金が沢山あるとして、住む場所をどこにするかというと、日本人は庭付きの広い一軒家を買って暮らしたいと思います。
一方ユダヤ人はお金が沢山あればホテルに住みたいと思います。
ホテルは一番安全な場所だからです。
ユダヤ人は安全にお金を使います。
その日本人も世の中に不安が増すにつれ、警備保障でという仕事が生まれ、安全を買うようになりました。
水もペットボトルで買うようになりました。
それでも最近まで原発については安全と思っていました。
しかし爆発で安全でないということが認識されました。
大変なお金がかかるということも分かりました。
また、「脱原発」によって安全を買うと、そのコストは高いものになります。
これから日本人はそれを理解して、高くても安全を買っていかなければならないと認識することになります。
もう1つ安全を買うための負担があります。
それは経済にも及ぶということです。
高い電気料によるコスト負担に耐えられなくなる中小製造業者が増えると予想されます。
力のある中企業・大企業は高コストから逃れ、海外移転するかもしれんせん。
その結果失業者が増えます。
これが一番大きい安全に対するコストです。
日本人はそれに耐えれるでしょうか。
これからその分岐点を迎えます。
レストラン
今日は9月1日。
妻と琴似神社、北海道神宮にお参りに行きました。
帰りが7時過ぎだったので、朝食をとるため「ローヤルホスト」に寄りました。
行ってみると結構混んでいました。それも年配者ばかり。
若い人は1組くらいで、他は50歳以上の夫婦か単身の人達。
私達のようにたまには朝食は外で食べようということでしょう。
以前にはマクドナルドやモスバーガーに行きましたが、そちらは若い人がほとんど。
朝食代の違いもあるのでしょうか。
私達夫婦も2人で暮らしていると、たまには家事労働から妻を解放してあげようと外食をする回数が増えます。
そんな時、居酒屋などではなく、家庭料理の延長上にあるようなレストランなどは重宝します。
1人1500円位で、静かに食事が出来るといいですね。
これからシニアの単身者、夫婦向けのレストランは開発の余地がある気がします。
誰かが何かをしてくれる
現在の日本は近来大震災や大災害を経験し、また長い不況の中にあります。
そのような中においても、多くの国民の生活は平和で、平穏に暮らしています。
それは過去多くの人達の努力のお陰で成り立っている平和です。
でもそれが行き過ぎてしまったのか、多くの人が何かに挑戦する、頑張ることをしなくなりました。
自分が出来ないその思いを、テレビでオリンピック等のスポーツを見て、自分以外の人が挑戦し頑張っている姿に感動しています。
自分がしない分、他人を通して感動しているのです。
自分は何もしなくても、「誰かが何かをしてくれる」のを待っています。
いつの間にかそうなっているのです。
日本は世界で一番の社会主義国と言われるくらい、手厚く国民は守られています。
いつの間にか挑戦心が薄れています。
先日の新聞に「1万社起業へ支援」という記事が掲載されていました。
起業を促すために数百万程度の小口の助成金制度を創設するというものです。
これも甘えを助長するモノだという気がします。
国や自治体からのお金に頼らず、苦労して自分が出来る範囲でお金を集め起業する。
そのような心意気が無ければ、起業は成功しません。
一度でも補助金のうま味知ると、何かある度に「補助金目当ての心」が生まれます。
補助金が出る事業を探したりします。
今、起業時に本当に必要なのは「マンパワー」の支援です。
友人やメンター・コーチになる人達とのネットワーク作りこそが大切です。
下手なお金の支援は起業家の心を堕落させてしまいます。
「誰かが何かをしてくれる」という思いを排除することこそ、起業する時に必要な心意気に繋がります。
変化
昨日長男一家が帰京しました。
7月末から始まった子供達家族の夏休みはやっと終わりました。
帰った後の家の中はゴチャゴチャのまま。
「孫は来て嬉し、帰って嬉し」の心境です。
また、深夜にはイギリスにいる3女からメールが来て、28日無事婚姻届を出し、向こうの家族中心の結婚パーティーも終わりましたとの報告がありました。
名前が変わっていました。
私の周りはどんどん変化して行きます。
私もまた何か始めようという気になっています。
1万人の節電宣言
先日電車に乗った時、車内に「1万人の節電宣言」というポスターを見ました。
これは札幌ばかりでなく各地でも行われていることのようです。
何気ないポスターですが、フッと嫌なイメージが湧きました。
これは私がへそ曲がりだからでしょうが・・・・
今、日本中「節電キャンペーン」に取り組んでいます。
このポスターもそのキャンペーンの1つでしょう。
ただ、このキャンペーンが戦争時の「贅沢は敵!」とか「欲しがりません勝つまでは」の国を挙げてのキャンペーンとダブってきます。
勿論、私は戦後生まれですから、直接は知りませんが、そのイメージに近いものを感じてしまいます。
一旦何かが起きた時、皆がその同じ方向に一気に流れて行く危険性を感じてしまいます。
勘違いしないでください。
節電は大切だと思います。
ただ一つの意見ばかりに、自分も周りも強制されるような風潮になりつつあるのが良くないのです。
日本人は何かあると一致団結する国民性があります。
もしかすると、そのような国民性を利用しようという人が出てくるかもしれません。
「1万人の節電宣言」はその風潮の流れを測る「サンプル」の様なものに思えてしまいます。
私の思いすごしかもしれませんが。
日本航空の再建
昨夜盛和塾札幌の例会がありました。
例会では時々スピーカーを招いてお話を聞きます。
今回は日本航空北海道地区支配人の藤田克己氏を招いて「稲盛塾長と歩んだ再生への道」と題して話していただきました。
旧日本航空が破綻した主な原因は①永続的経済成長を前提とした拡大主義、②国策会社としての認識等を上げています。
破綻後日本航空の再生が決まり、稲盛さんが会長就任しました。
稲盛さんが会長就任後、日本航空は劇的に変わって行きました。
まずは人員整理が始まりました。
止むを得ず人員を21000人減さなければならなかった。
支配人自身も多くの人に辞めてもらいましたそうです。
中には同期もいて、辛い思いも語っていました。
再建出来た大きな要因として①フィロソフィの確立②部門別採算制度の2つを上げています。
「京セラフィロソフィ」を基としたフィロソフィの浸透を徹底するために、初めは社長以下130人の役員から経営の12カ条、6つの精進等の勉強会を開きました。
勿論講師は稲盛さんです。
そのような勉強会を下部組織まで浸透させてゆきました。
そして「JALフィロソフィ」を作ったのです。
藤田支配人の話によると、札幌支店では毎朝「JALフィロソフィ」を読んでいるそうです。
この「JALフィロソフィ」は40項目あります。
「京セラフィロソフィ」は78項目ですから若干少ないです。
しかし、やはりサービス業としてのJALらしく、「1人1人がJAL」「尊い命をお預かり仕事」「最高のバトンタッチ」「スピード感を持って決断し行動する」の4項目が加えられています。
スピーチの最後に今後の課題として①JALフィロソフィ―の浸透と②利益が出た時の気の緩みを上げました。
藤田支配人の話しを聞くと、日本航空の中でのフィロソフィを中心とした勉強会は大変内容が濃く、私達盛和塾生の企業以上のものを感じます。
近い将来、きっと彼らが目指す「世界最高のサービスを提供する航空会社」に選ばれるでしょう。
私も楽しみにしています。
第2回番屋で遊ぼう会
土曜日、銭函にある漁師番屋で遊んできました。
「番屋で遊ぼう会」と称して去年に続いて2回目です。
今回は20名の人が集まり、夕方4時から8時ころまで賑やかに大宴会。
海にせり出した10坪程の広さのベランダの上に大きな炉端があり、そこで鮭のチャンチャン焼き、烏賊、サンマ、イワシの丸焼き、ホッキ貝の殻焼きを食べ、小屋の中には刺身の大きな舟盛り。
用意した生ビールは30リットル、差し入れの「田酒」等の日本酒やワイン。
参加費は3500円。参加者した皆さんは大満足です。
灯台の光、遠くに見える町の灯、夜の海を見ながらの宴会はいいものです。
この漁師番屋は知人のKさんが所有し、気が向いた時グルメ亭を開き、料理を用意してこのような宴会をしてくれます。
この漁師番屋の入口には「グルメ亭」という看板はありますが、営業しているわけではありません。
Kさんの隠れ家です。
この「番屋で遊ぼう会」に集まった20名は、20代から70代、職業もバラバラの男女です。
私の関係している2つのグループの人達に声を掛け集まっていただきました。
この会は来年も開く予定していますが、大好評なので参加希望者が増えそうです。
私も楽しみにしています。
脳ドック
昨日「脳ドック」に行ってきました。
予約を入れてから2カ月待っての検査です。
決して安い金額ではありませんが人気があるようです。
私は過去「脳ドック」も「人間ドック」も経験はありません。
会社の健康診断だけです。
最近、年と共に物忘れが多くなり、「脳ドック」位は受けてみようかという気持ちで受けました。
MRI検査の他に胃カメラ、血液検査等しましたが、肝臓、腎臓、胃共に問題ありませんでした。
以前の健康診断より良くなっている位です。
心配だった肝臓のγーGTの正常値になっています。
ここ3カ月で5Kほど減量したせいかもしれません。
今回診察を受けた医院にはドック受診者用の休憩控室が用意され、1人に1部屋のゆったりした部屋があてがわれます。
検査に3時間ほどかかりますが、各検査を受ける合間はその部屋でゆっくりすることが出来ます。
最後には食事も出されました。
病院もサービス業なのですね。
私が時々行く整形外科の病院の受付は事務的で冷たくニコリともしません。
本当は行きたくないのですが、家から歩いて3分のところにあるので仕方が無く行っています。
誰かが「病院ミシュラン」なるものを作れば、病院もサービス業との認識が高まるかもしれません。
伊那食品工業
昨日知人から「今日の夜、山地さん時間ありますか?」と聞かれ、飲み会かなと思ったのですが違いました。
「カンブリア宮殿という番組知っていますか?」
「もちろん知っています。」
「それならもしも良かったら今晩放映するので番組見てもらえますか?」とのこと。
その理由は「私の娘が嫁いでいる先のお父さんが出るんです」
そのお父さんというのが伊那食品工業の社長塚越寛さんです。
伊那食品工業という名前は知っていましたが、詳しくは分かりませんでした。
でもテレビを見て素晴らしい会社だというのが良くわかりました。
働く人のほとんど多くが幸せを感じています。
伊那食品工業は寒天を製造している会社です。
寒天を応用した商品は多く、「かんてんぱぱ」という名前が売れているようです。
その名前は、モノに疎い私の妻でさえ知っていました。
この会社は48年間連続して売上を伸ばしています。
急激な売上増を求めず、「年輪経営」を謳っています。
急激に大きくなった木は年輪の密度があらく、嵐に倒れてしまう。
しかしゆっくり大きくなった木は密度がしっかりしていて、簡単には倒れないのです。
だから「売り過ぎない」がモットー。
またもう1つのモットーが「作り過ぎない」です。
いいものを着実に作って売っていく。
1人のお客様を大事にするということで商品の廃番も出さないようにしています。
商品の研究開発は盛んに行われていますが、新製品として出すのは年間数点で、多くはストックされ、将来の戦略商品となります。
「年功序列」「終身雇用」を実施しているこの会社の塚越さんは、「会社が永続することによって皆を幸せになる」と言います。
会社が永続すると、社員は勿論、仕入れ先、取引先、お客様が幸せになるのです。
それを別な言い方で塚越さんは「利益は健康な会社から生まれるウンチ」と言います。
その意味するところは、売上が上がり、粗利益が出、その中から社員の給与や福利厚生等を十分にし、その他の支払をしていく。
それら大切な支払をした後、残ったモノが会社の利益でそれはウンチみたいなもの。
「会社の目的は利益ではなく、社員の幸せでありそして関係する人達に喜んでいただくこと」なのです。
この塚越さんの話を聞いて、これからの新しい経営者像が見えました。
のれん分け
2日前に「俺のイタリアン」という店について書きました。
また、その経営者の坂本孝さんのこともご紹介しました。
昨日、その坂本さんが経営しているVALUE CREATE株式会社のホームページを読んでいて「成程!」と思ったことがありましたので改めてご紹介します。
坂本さんが自社のホーページ上にメッセージを書いています。
その中で、新しく飲食業を選んだ理由を次のように書いています。
「世の中の多くの事業は、一般には強くて大きくなければ勝てないと言われていますが、飲食事業に限っては『小さくても勝てる』業種なのです。
例えば、30坪の小さな本屋の隣に1000坪ものブックセンターができてしまったら勝てる可能性はありませんが、10坪しかない居酒屋の隣に100坪の居酒屋チェーン店があったとしても勝てるのです。
なぜならば、同じ原材料であっても味やサービスなどでそれぞれの付加価値を提供することができるからです。」
これを読んでセブンイレブンを日本に入れた鈴木敏文さんの言葉を思い出しました。
「大型ショッピングセンターが近所に出来たから小さな店は太刀打ちできない」という考えを打破したいと思ってセブンイレブンを日本に入れたと言っていました。
規模が小さくても勝てる業種や方法があるということを教えてくれています。
坂本さんはまた飲食業を始めた第一の理由を上げています。
「私は誰もが成長と共に独立できる土俵を作ることが夢でした。
いわゆる『のれん分け制度』です。
そこで、のれん分けがしやすい業種は何かと考えたときに、『飲食事業』というひとつの答えが浮かびました。」
これも「成程!」と思いました。
この「のれん分け」という制度は昔から日本にありました。
今で言えば、親方がする「起業支援」です。
でも今の日本ではあまり聞いたことがありません。
坂本さんは「のれん分け」という考えで、「起業支援」をしようとしています。
自営業をする人は1980年代以降減少しています。
総務省の資料によると80年代初め940万人だったのが、今年の6月で564万人と、この30年で4割減少しています。
坂本さんがしようとしている「のれん分け」はこの自営業者を増やすことになるのです。
坂本さんのメッセージを読んで、「のれん分け」も「起業支援をする」1つの考え方だと考えさせられました。
眼力
昨日2人の人から新しいビジネスプランの説明を受けました。
詳しくは説明するわけにはいけませんが、1つは「生命保険+葬儀」
もう1つはコンサルト関連です。
それぞれの話しを聞いてみると、「成程!」という仕組があります。
どちらも自分の周りにある当り前のことが、商売のネタになっています。
日本マクドナルドの創業者の藤田田(デン)さんの言葉があります。
「凡眼には見えず。心眼を開け!好機は常に眼前にあり!」
目を凝らしても見えないのはモノを見る眼力が無いため。
見て、聞いて、調べる。
その繰り返しが眼力を高めるのでしょう。
俺のイタリアン
私はよく、武沢信行さんが書いている「がんばれ社長!」のメルマガを読んでいます。
昨日のメルマガに書かれていた内容を紹介します。
そこに書かれていたのは「俺のイタリアン」というお店です。
ご存じの方もいるのかもしれませんが、私は全然知りませんでした。
そのお店は、本格的なイタリアンのお店にもかかわらず、ほとんどの席がカウンター席。
シェフはミシュランのお店などで修業した腕の確かな料理人。
カウンター席の為、お客の回転が良く、その為本格的イタリアンを安い料金で提供出来ているようです。
その一例として、私は飲んだことがありませんが、かの有名なドンペリが1杯1000円です。
1日7杯限定ですが驚きの値段です。
一般的な飲食店では原材料費30%、人件費 30%で設定されます。
しかし「俺のイタリアン」では原材料費を45%、人件費25%で計70%もコストがかかります。
高コストですが、回転率の高さによって1店舗の売上げは月間で1000万円、15%~20%の営業利益が出ているようです。
すごくいい数字です。
この「俺のイタリアン」の他に「俺のフレンチ」という店も展開しているそうです。
そしてこの経営者が「ブックオフ」創業者の坂本孝さんだそうです。
坂本さんは稲盛和夫さんが主宰する盛和塾の塾生の1人です。
ブックオフの社長の時から各地で行われる盛和塾の例会にはほとんど顔を出していました。
その坂本さんは「ブックオフ」から離れた時、一時意気消沈しているように見えました。
それが暫くして、「坂本さんが飲食業に進出したようだよ」という話を聞きました。
その店が「俺のイタリアン」だったのです。
坂本さんは今69歳。
その歳に驚きです。
私が「もう歳だから」と言ったら笑われそうです。
「俺のイタリアン」はぜひ一度は行きたい店です。
今度上京した時の楽しみがまた増えました。
琴似商店街
私が住み仕事をしている琴似という街は北海道で2番目に古い商店街と言われています。
一番古いのが狸小路です。
琴似の街は35年ほど前に地下鉄のターミナル駅が出来てから賑やかになりました。
琴似生まれの私にとって、小さい頃のことは私の懐かしい思い出ですが、若い人達にとってはもう昔話になっています。
人口も増えました。琴似だけの人口は分かりませんが、琴似のある西区全体では21万人以上に人達が住んでいます。
その西区の中心が琴似で、またその中心が琴似栄町通(通称は琴似本通り)の商店街です。
この商店街は他の地域の人からは大変賑わっていると言われます。
商店街を歩いていて気付くのは、琴似本通りに並ぶ店の様子です。
賑わっていても、空き店舗はあります。
その空き店舗が多いのは、地下鉄琴似駅からJR琴似駅に向かって歩いて行く右側です。
700mの間に5件ほどありますが、左側には空き店舗がほとんどありません。
不景気なので、他の地域の商店街では空き店舗ばかりで困っているということですから、琴似はまだいい方ですが、それでも右側は多いのです。
この傾向は昔からそうです。
左側の並びは太陽が当たります。
反対に右側は当たりにくいのです。
人は太陽が当たる方を歩くようです。
同じ商店街でも、通りの右か左かで商売に大きな影響が出ます。
北海道は雪が多いところです。
陽のあたるところは雪が溶けやすい。
また歩く人も、陽を身体に受けると温かくなります。
必然的に人の交通量が増えます。
雪が降るところでは、店舗を出す場合、陽のあたる場所とそうでない場所、見極めが大切になってきます。
イギリスの教育
今、イギリスに興味があり、「古い家と家具にこだわるイギリス人」という本を読んでいます。
その中に子供の教育について書かれています。
少し紹介します。
イギリス紳士や貴族の性格形成に伝統に深くかかわってきたのは幼少期から青年期にかけての教育です。
7,8歳になるとプレパラトリー・スクール、13,14歳になるとパブリック・スクールに進学するようです。
その10年間余りの教育で、紳士、貴族になる為の人間的基礎教育が仕込まれます。
子供達は幼少期から両親や家族と離れ、寮生活をします。
寮生活そのものが厳しく、寂しい孤独に耐える教育になります。
食事も粗食で、スパルタ式の訓育の日々です。
上級生からのシゴキや、イジメにも耐えなければならないそうです。
その中でたくましい自立心と、強健な肉体が同時に作られていくのです。
イギリスでは昔から、選ばれた子供へのエリート教育が行われてきました。
この様なエリート教育に対して良い悪いの評価は別にしても、将来の国を背負うリーダーを育てる教育になるでしょう。
子供は小さい頃に教えられてことがその人格形成に大きく影響します。
イギリスの教育は、日本に一時あった、ゆとり教育とは正反対の教育方針です。
日本の底力
今朝の日経新聞の一面に「シャープ主要事業売却」と大きく載っていました。
シャープの存続がどうなるか気になります。
10年ほど前でしょうか、シャープの液晶パネルの亀山工場はブランドでした。
この工場で生産された液晶テレビは大変な人気。
私もどうせ液晶テレビを買うなら「シャープの亀山工場製」と思い、買った覚えがあります。
また吉永小百合さんがその宣伝をし、益々ブランド力が高まりました。
確か当時、最新鋭のアメリカの戦闘機に装備されている液晶もシャープ製だったという記憶があります。
そんなシャープがこんなに落ち込んでしまった。
また、ダントツの売上と利益を出していた任天堂も急下降しています
ついこの間まですごい勢いだった携帯電話のノキアも苦しんでいると言われています。
急激な消費動向変化についていけなくなっているのです。
旧来の大企業が衰退しているのと反対に、ここ10年でベンチャー起業の会社が売上を伸ばしています。
日本でもこれからドンドン新陳代謝が進みそうです。
大企業に勤めているからと言って安心なんかできません。
一方、それでは日本の企業は全て力を無くしているか、中国・韓国の企業に太刀打ちできないかというとそうでもないのです。
サムスンは液晶や半導体など多くの分野で日本を凌駕しています。
しかしあまり知られていませんが、サムスン電子が使っている半導体や液晶を製造する機械は例外なく日本製です。
韓国で製造されている主要製品の機械はほとんどが日本製です。部品もそうです。
ですから現在の対韓国の貿易収支も黒字なのです。
日本の底力はまだまだだ強いのです。
でもいつまでもその力があるか分かりません。
重要なことは、会社は新規事業に挑戦し、その為に企業内起業家を育てること。
これから多くの新しい力が必要です。
今こそ起業家育成が必要な時なのです。
盆休み
盆休みが終わって今日から出社です。
昨日まで妹一家が来ていて、その入れ替わりに長女一家が来ました
次女と子供は2週間前から来ています。
今度の日曜日には長男一家が来ます。
最盛期には10人以上になりそうです。
暑い東京から涼しい北海道に逃げて来ているようです。
10人以上となると食事が大変。
6人掛けと4人掛けのテーブルを並べます。
私は時々孫と遊ぶ以外は自分の部屋に入り込んでいますが、家内は大変そう。
寝る場所はありますが、布団や枕をそろえるのも大変。
私の仕事は先週もしましたが庭でジンギスカンを振る舞い、皆とビールを飲むこと。
大変そうな家内もにぎやかのことが好きです。
暫くは楽しくにぎやかに暮らします。
「Jimdo」
「Jimdo」というソフトをご存じでしょうか?
ホームページを作るソフトです。
昨日知人が来社して話している時にこのソフトの話しが出ました。
彼女はそのソフトの存在は知っていたのですが、あまり使ったことがありませんでした。
最近必要があり使ってみると、その簡単さと内容の濃さに驚いたそうです。
私はこの「Jimdo」を使って2つほどホームページを作っています。
以前はホームページビルダーを使っていましたが、「Jimdo」が断然使いやすい。
その上無料。
このソフトの凄さに感激した彼女は「Jimdo」の勉強会を立ち上げる予定です。
そしてゆくゆくはサロンみたいなものを作る考えもあるようです。
勿論私も協力します。
第1回目の勉強会場は私の事務所になる予定です。
ブログやFacebookが盛んに使われていますが、やはりしっかりしたホームページは仕事をする上で基本です。
勉強会が楽しみです。
頑張っている人
今日は頑張っている起業家を紹介します。
Aさんは3年ほど前に私のレンタルオフィスに入られました。
起業して、家庭と仕事場を分けたいとの思いがあったようです。
当初は個人事業主でしたが、オフィスに入居後法人化しました。
お仕事内容は私も詳しくはわかりませんが、ネット上で商売をしているようです。
法人化して暫く順調に業績も伸びていたのですが、ある時、急に原因不明の病気にかかり、入院してしまいました。
入院は3カ月近くに及びました。
退院してきた時は伸びていた業績は急降下していました。
Aさんは一時オフィスを出てまた自宅で仕事をしようかとも思ったそうです。
それでも家庭と分けたいとの思いで、オフィスに残りました。
そして個室よりは比較的価格が安いブースの席に移りました。
それからAさんは頑張りました。
業績をアッという間に回復し、暫くするとアルバイトを雇うようになりました。
またオフィスに入居していた別のIT関連の仕事をする人達とも連携して仕事を広げていきました。
そして1年ほど前に、入居していた別の2人と一緒に私のレンタルオフィスを出て、同じヤマチビルの3階に共同で部屋を借りました。
当初は20坪ほどの部屋でしたが、急激に雇用者が増え、今は40坪の部屋に移っています。
3社共同で1部屋を借りています。
Aさんは5人の部下がいます。
また他の2人も同様に業務を拡大しています。
私のオフィスで、互いに良き出会いがあったようです。
ここで少しAさんの生活行動を紹介します。
Aさんは180センチメートル以上あり、筋肉質のスポーツマンタイプ。
なかなかいい男です。
夜寝るのは10時。
起きるのは午前2時で、睡眠時間4時間です。
それで十分だと言います。
2時に起きて、運動をし、本を読み、そして家族の朝食、お弁当まで作ります。
会社には徒歩30分位かけて通い、9時から仕事をし、4時には退社します。
彼は家庭を大事にし、子供と遊ぶ時間をとるのです。
人一倍頑張り、仕事と家庭を両立させ、自分の健康にも気を配る。
これからどこまで大きくなるか楽しみな人です。
ジャズ演奏
昨日友人から「今夜ジャズのセッションがあるけれど行かない?」とお誘いを受けました。
5000円の入場券だけど、招待されたので、一緒に行こうということです。
最近、夜は出歩かない私ですが、折角のお誘いですので行くことにしました。
そのジャズ演奏の紹介文面は次の通りです。
「日本を代表する、最高峰のJazzギタリスト矢堀孝一。カシオペアのキーボーディスト大高清美。16歳の天才ドラマー平陸。最強のトリオでお届けする至高のジャズをお楽しみ下さい。
ゲスト: Kristin Berardi & James Sherlock(ボーカリストKristin BerardiとギターリストJames Sherlockによるオーストラリアの若手人気デュオ)」
ジャズを聴くのは好きですが、あまり曲名も知らず、いわんや現代の有名な演奏者も知らない私がこの紹介文を見ても「ああそう」程度です。
本当にジャズが好きな人にとってはすごいメンツの様です。
2時間余りの演奏。
最初はオーストラリアの人気デュオのムーディーな曲。
その後は耳が痛くなるほどのギターとドラム、エレクトーンの演奏。
曲名も演奏の良さもわかりませんが、音楽に浸ったというか、音の浸った時を過ごしました。
終わって帰る時、不思議とフッと元気になった気がします。
色々考えることが多く、意気が少し下がっていた時、何かパワーをもらった気がします。
生の音楽はいいモノですね。
これから努力して、夜な夜な出かけるようにしようと思っています。
自分の心を自由にする
以前読んだ本の中に、ダーウィンの言葉が紹介されていました。
「どんなに気に入った仮設でも、事実がそれに反すると証明されれば、すぐそれを放棄するために、いつでも自分の心を自由にして置くように努めてきた。」
これは自分に自信が無いと言えない言葉です。
自分が考え、主張していた仮設を他人が間違いだと証明した時、それを素直に認める。
それは事実を追求する科学者にとって必要なことでしょう。
しかしそれでも認めることは難しいこと。
一時的にでも自分を否定してしまうことになります。
エライ先生だと、なお難しいことでしょう。
今、世の中には思いもよらないことが多く起きています。
それらの専門家や先生たちは自説にこだわり混乱が起きています。
原発問題ばかりでなく政界、経済界でも起きています。
と言いながら、わが身に振り返ってみれば、「自分がそうなのではないか」ということに気付きます。
「自分の心を自由にする」とは、深く学ぶと共に人間性の成長によって生まれるのでしょうか。
修行が足りません。
歯医者
先週末に歯を抜きました。
十分気を付けていたのですが残念です。
掛りつけの歯医者は私の従兄弟です。
彼はまじめな性格で1人1人の患者を丁寧に治療しています。
治療もしますが彼のいいところは、歯の磨き方を時間を掛けて何度も教えてくれます。
歯の磨き方に合わせて色々な歯ブラシも用意してくれます。
それは私ばかりでなく、患者皆にしているようです。
その為、医者は彼一人ですから1人当たりの治療時間がかかり、決して効率いい経営とは言えないです。
でもその患者中心の考え方は多くの人に支持されています。
勿論私の家族もお世話になっています。
今の歯科医院の数はコンビニより多いと言われています。
競争が激しく、廃業するところもあると聞きます。
従兄弟が経営する歯科医院は昔の歯科医院の様な大儲けは出来ていないようですが、しっかりファンを作っています。
歯科医院はリピーター産業です。
そして広告宣伝も、割引することの必要ありません。
1人1人の患者を大事にしていけば、何年にもわたりお客様になってくれます。
当り前のことをすれば堅実に経営出来ます。
私もこれから今まで以上に通うようにします。
信頼のおける掛りつけの歯医者を持つことは、歳をとっていく者にとって大切なことですから。
子供の旅立ち
昨日知人Aさんが来て色々な話をしました。
その話の中で、彼の子供の話しが出ました。
今年高校を卒業した18歳と中学3年生の男の子2人です。
その18歳の息子さんが7月から1人で中国に行っているそうです。
今は語学学校に入っていますが、将来は大学に行く予定です。
息子さんの将来を高校生の時から父と子でズーと話し合っていたいました。
Aさんは息子さんにこのようなことを話していたのです。
「私の息子なのでそれほど優秀でない。東大や京大に入れるわけではない。だからと言って他の大学に行っても大したことが身につくわけでない。
それより世界に目を向けて将来世界を相手に仕事をするためのことをしよう。
これからはやはり中国だ。
最初は中国語を学び大学に行き、人脈を作り、起業するための準備をするべき」
そのようなことを話合ったそうです。
Aさんは「私のプレゼンテーションが良かったから息子もその気になった」と言っていました。
奥さんはやはり母親として色々心配したそうですが、最終的には納得してくれたそうです。
この話を聞いて感心しました。
まず、父が子供とそこまで話し合っている親子はいるだろうかということです。
子供の将来を心配しない親はいません。
でも子供の将来に対する親の気持ちをプレゼンしている親がいるでしょうか。
長い時間を掛けて話合う親子関係に感心。
また素直に父親の話を聞いて、決断した息子さんにも感心です。
そのようなお兄さんの行動を見ていた中学3年生の息子さんも、「それじゃ僕はどこの国に行こうかな」と話しているそうです。
親離れ、子離れが出来ていいて、それで強く結びあっている親子関係。
人の子供ながら何年か後のことが楽しみになってきます。
個人競技者
昨日からテレビや新聞で内村航平選手の個人総合金メダルの報道が続きます。
スポーツの選手を見ていて、いつも思うことがあります。
個人スポーツの選手は精神的により強いモノが無ければ優勝できないのです。
スポーツには大きく分けて個人と団体があります。
団体スポーツの代表は野球、サッカー、バスケット等あります。
チームの中にスターが出て来ます。
その彼もチームがあってのスターであり、競技に臨む時の困難さ、プレッショーも皆で共有出来ます。
ところが個人であればそれを全て自分1人で受けて、孤独に打ち勝ち、競技をするのです。
技術ばかりでなく精神的な強さが必要になります。
残念ながらその重圧に負けたのは柔道選手達でなかったでしょか。
私が高校生の時、毎年冬になるとクラス対抗のスキー競技会がありました。
私はたまたま、アルペン競技の中の大回転の選手に選ばれたました。
練習を何回かし、練習では参加メンバーの中でベストタイムを取りました。
しかし、いざ本番の時、皆の注目を一身に集めていいるという意識による緊張、逃げれない孤独。
2本目のポールをくぐったところで、スキーの金具がはずれ、コースアウト。
その思いは今でも忘れません。
もう1つ個人競技者と団体競技者の違いは「誰のために頑張るのか」という思いです。
団体の場合「1人は皆のために、皆は1人のために」という気持ちで自分以外の人のために頑張ることが出来ます。
個人競技の場合は自分しかいません。自分のために頑張るしかないのです。
自信過剰なほどの自信をつけなければ精神的に勝てません。
そのコントロールが大変です。
でも今回のオリンピックを見ていて気付いたのですが、メダルと取った体操や水泳、体操の個人の競技選手達はインタービューで最初に感謝の言葉が先に出てきています。
「応援してくれた家族、仲間そして日本の皆様に感謝します」
個人競技の選手もやはり自分以外の誰かのために頑張り戦うという気持がモチベーションを高めたのでしょう。
1人で仕事を始めた起業家もそうです。
起業は孤独の中で仕事が始まります。
自分の思いを叶えるために起業したのですが、「誰かのために」という思いが無ければいい結果を出せません。
それに気付いた時、自分1人のためばかりでなく、最初に家族のため。その次にお客様の為となっていくのでしょう。
オリンピックはこれからも続きます。
男女サッカーも応援しますが、個人競技者にエールを送ります。
両親の思いで
日街を歩いていて、ブックオフに何気なく立ち寄りました。
フッと目に入ったのが「父母への手紙」という本でした。
立ち読みしたのですが、素敵な両親の思い出が語られていました。
その時、自分の父母との思い出は何があるだろうかと思ったのです。
居るのが当り前のように存在した両親。
何不自由なく育ててくれたことが当り前のように思っていた自分。
両親が死んで1年2年経ちます。
来月は母の1周忌です。
沢山あるはずの母との思い出、思い返してもあまり出て来ません。
なんと親不孝な息子だと思いながらも思い出すと、ありました。
私は物心ついた時には既に左の耳が聞こえていませんでした。
右の耳はチャンと聞こえます。
その左耳治療のため母は私を色々な病院に連れて行きました。
この病院なら直るかもしれないと聞いたらすぐ連れて行きました。
母に手を引かれて市電に乗って札幌医科大学病院、バスを乗り継いで北大病院など覚えています。
分厚いドアの検査室に入って検査をしました。
耳が聞こえなくなった原因はストレマイシンという薬の様です。
私が生まれたのは8月。母乳が出なかった母は、粉ミルクを飲ましてくれました。
母の話しでは、作り置きしたミルクが、8月の暑さで悪くなってしまい、それを飲んだ私はお腹を壊したそうです。
医者にに見せるとすぐストレマイシンが打たれのです。
それが左耳が聞こえなくなった原因のようです。
母が私が高校生の頃、そのことを話してくれ、謝っていました。
小さい頃から左の耳が聞こえませんが、右はよく聞こえるので、ほとんど不自由は感じませんでした。
人は皆、耳が2つ付いているけれど、そのどちらか1つしか聞こえないものだと私は思い込んでいました。
勿論、障害者だとの自覚はありません。
母が年老いて私と住むようになってある時、何気なく「すまないね」「ごめんね」と言いました。
80歳を過ぎても私の耳のことを気にしていたのです。
「全然気にしてないよ。大丈夫だよ」と言っても申し訳なさそうな顔をしていました。
そして悲しそうでした。
昨日はそんなことを思い出しました。
親はありがたいものです。
母の写真に合掌しました。
公平・自由な情報公開
今テレビをつけると、どの放送局もオリンピックの報道や番組ばかりです。
日本選手の活躍に一喜一憂して、私も結果が気になってしまいます。
でも楽しいオリンピックが開催されている一方、世界や日本では以前と同じように事件、事故が発生し、重要な動きや決定が進行しています。
新聞はその扱いは小さくても、まだ報道されている方です。
テレビではオリンピックの報道が中心となり、その他のニュースがカットされています。
テレビ局にとって「何が大切か」というと、国民が喜ぶものを提供することなのでしょう
テレビの報道は国民が喜びそうなものを提供する大衆迎合主義(ポピュリズム)と言われても仕方がないでしょう。
日本では現在色々な問題が起きています。
原発再開やオスプレイの配備、TPP等が問題提起され、今後の動きが不透明です。
これらの重要な問題に対して私達が賛成反対を言う時、その情報はほとんどがマスコミから得ます。
でも私にはそのマスコミの報道がどうしても公平に情報提供をしているとは思えないのです。
私も原発再開には疑問を持っています。
オスプレイの安全性も不安です。
TPPによる農業の衰退も心配です。
でも本当に私達が得ている情報は、賛否の根拠となる公平な情報でしょうか。
どこかに、「その問題を騒ぎ立てて、報道として思い面白いものにしよう」という意図が隠されているように思います。
一方に偏った情報が多いようです。
パソコンを使えば情報を得ることも出来ますが、多くの国民はテレビや新聞で報道された情報だけを鵜呑みにしています。
原発に関連する放射能も「危険!危険!」ばかりが先走って入るように思います。
過度に心配するあまり、それによる別の弊害の方が心配になります。
今の日本では、もしも原発賛成などというと「非国民」と言われそうな雰囲気です。
私が中高生の頃アメリカやソ連、それに中国は大気圏の核実験をしていました。
その放射能が偏西風に乗って世界中にばら撒かれ、先生に外出する時は帽子をかぶるようにと言われました。
毎日のように自衛隊の戦闘機がその濃度を測るために飛んでいました。
その頃と比べて今の放射能濃度はどうなのでしょうか。
その頃の放射能と今の放射能の比較報道が公平に提供され、その上でどうするかを考えていいはずです。
その放射能を浴びた私達「団塊の世代」は元気なのです。
「米ソが大気圏内核実験を繰り返していた1960年代までは、たしかに東京における放射性セシウムの降下量は、今回の福島の事故が起こるまでの1000倍以上の数値だった」という情報もあります。
勿論だから放射能があってもいいと言っているわけではありません。
ただ、過剰に敏感し過ぎるには弊害が多く、もしかしたら誰かに誘導されているのではないかという気がします。
オスプレイ問題にしても、TPP問題にしても、反対の意見や情報ばかりです。
賛成意見やその根拠情報がもっと出てしかるべきです。
一方の意見が大勢になり、それによりもう一方の意見の根拠となっている情報を黙殺する。
そのことで、もしかしたら本当のことを隠して、間違った結論を出すことになる恐れがあります。
より公平・平等そして自由な情報の公開を求めます。
専業主婦
先日テレビを見ていたら、専業主婦と共稼ぎ主婦との比較論議がありました。
最近は専業主婦というと少し肩身が狭い感じがします。
女性がドンドン社会進出することは大賛成です。
その目的が生活費を得る為とか、自分のしたいことを実現するためとかいろいろあると思います。
一方専業主婦の人は皆裕福かというとそうでもありません。
それなりの理由があります。
専業主婦もいいと思います。
ちなみに私の妻は専業主婦です。
先日のテレビで保育園に通う園児にかかる公的負担額は1カ月約20万円かかると言われていました。
年間240万円かかるのです。
私の子供は5人いたので、もしも保育園に通わせていたら年間1000万円以上の公的負担になっていたのです。
妻と話したことは、私達は年間1000万円以上の公的負担を受けずに子育てをしたということ。
それなりに社会貢献したことになります。
妻は「子育てする専業主婦はもっと評価されてみいいのだ」と言っていました。
見方は色々あって、1つの方向から見ると専業主婦は共働き主婦と比べ楽してと思われがちですが、別の見方をするとそれなりに評価せれます。
最近思うことの1つにこのように一方的意見ばかりが先走って、「結論ありき」の議論が多いように思います。
この事については明日書きます。
強く元気な人
今、私は起業する人達のお手伝いをしています。
起業しようとする人達は全て積極思考の人達です。
起業することは少なからずリスクを負うことになりますが、それでも自分の夢を追って行こうとする人達です。
下手な雇用支援をするより彼ら彼女らを支援する方が、日本が元気になり、雇用が生まれます。
日本では変な傾向があります。
貧乏な人の意見が正しくて、金持ちの意見はそうでないようです。
これは私の思い違いかもしれませんんが、テレビや新聞を見ていて思います。
国民の意見として取り上げるのも裕福でない人達です。
国の施策も、貧乏な人、弱い人を大きく捉えられて、その対策の予算が沢山付きます。
私はあえて言いたいのです。
元気な人、強い人、お金持ちと言われる人達にもっと支援をするべきと。
今の日本は、そのような人達の意見も取上げられず、またその力を発揮できない風潮にあります。
元気な人、強い人を支援し、その力で沈んだ日本を浮上させ原動力にしていかなければなりません。
金持ちは金持ちになるノウハウやパワーがあります。
それを発揮させるべきです。
弱い人、貧しい人、可哀そうな人への配慮は大事ですが偏り過ぎては日本は浮き上がれません。
元気な人、強い人、金持ちの存在を広く知らしめ、公的にも今以上に支援し、日本の推進力になってもらわなければなりません。
中学、高校生たちに「俺たちもなりたい」と言われる存在になれば、元気な若者も生まれるかもしれません。
「いたずら」と「イジメ」
昨日知人が来社しました。
彼女は中学校の養護教諭です。
今は北海道の学校も夏休みなり、尋ねて来てくれました。
そこで問題になっている「イジメ」の話が出ました。
大津のいじめ問題が起きてから、北海道の教育委員会が教員の行動をチェックしているそうです。
このいじめの話しをしている時思ったのですが、「イジメ」は本来は元々「いたずら」の延長にあったよう思います。
今はそれが度を外して犯罪になっているのです。
イジメている人間も、この「境」「けじめ」が分からないなって犯罪行為をしているのかもしれません。
例えば小さな落とし穴を掘って、友達を落としたりするのは「いたずら」として、私もしていました。
仕掛けた方も仕掛けられた方も笑える程度です。
それを少し大きな穴にし、特定の人間を落としてばかりいるとそれはイジメになります。
そしてその穴に特定の人間を落とした上で、埋めてしまう行為は犯罪です。
子供の「いたずら」ではもはやありません。
犯罪が学校で行われたなら警察に任せるのが当り前です。
大津のいじめで警察が入っていますが、もっと早い時点であっていいです。
これからは学校といえども犯罪が許される聖域ではありません。
昨日話をした養護教諭も言っていました。
学校では先生の手の負えないことが起きていると。
今後はもっと地域社会と学校が連携し合って、子供たちを教育することが大切でしょう。
「いたずら」と「いじめ」と「犯罪」の区別がつかなくなってきた例は大人でもあります。
何年か前に、男性が大きな落とし穴に埋もれて死んでしまったことがありました。
仕掛けたのは友人と死んだ人の奥さん。
殺すつもりはなく、いたずらのつもりが犯罪になってしまいました。
大人もその「境」「限度」「程度」「加減」が分からなくなっているのでしょうか。
「何のために」「誰のために」
今日ロンドンオリンピックが開会します。
このオリンピック参加のために日本を出発する選手のインタビューをテレビで見て、「あれ!変だな」という思いを抱きました。
「自分の力を精一杯出し、オリンピックを楽しんできまます」
「このオリンピックを最後に引退するので、精一杯頑張って楽しんできます」というのがありました。
平常心でいようという思いから出た言葉でしょうが、それは変です。
彼ら彼女らとオリンピック出場をかけ、メダルを取ろうと懸命に戦った人達に失礼です。
そして結果「一生懸命頑張ったから、たとえメダルが取れなくても仕方がない」という気持ちが見えてきます。
昨日のネットのニュースの中で、なでしこジャパンの宮間主将の言葉が紹介されていました。
「試合前の控室で選手が涙した主将からの言葉」と題しています。
そのまま紹介します。
「キャプテンの言葉に奮い立った。試合前のロッカールーム。円陣を組んだ選手の輪の中で宮間あやが言った。
『ここに立てるのは選ばれた18人だけ。大切な思いや大切な人たちがいて、私たちは戦っている。
ここからの6試合、お互いのために戦おう』
五輪メンバーに選ばれることのなかった選手たち、バックアップメンバーとしてチームに帯同しながらピッチ
には立てない選手たち。日本から応援してくれる人たち、スタジアムに駆けつけ、熱い声援をくれる人たち。
すべての人たちのために、18人全員が力を合わせて戦う。
『特に考えていたわけではない』という挨拶だったが、『円陣を組んで、みんなの顔を見て、ここに立てている
幸せを感じたし、その思いをみんなで共有したかった』と宮間は言う。
佐々木則夫監督は『ロッカールームでの宮間のコメントが格好いいというか、素晴らしくて。僕もジーンと
来て涙を流しそうになったぐらいだった。選手も結構、涙していた』と明かす。
主将の熱いメッセージに
チームはあらためて一丸となり、集中力を高め、五輪初戦に臨んだ。」
何事にも言えることですが、一生懸命頑張るにしても、戦うにしても、「何のために」「誰のために」が明確になっていいる人こそ勝利をものにすると私は信じています。
開会式前の男女のサッカーの勝利!
嬉しいですね!
「プライベートカンパニー」と「パブリックカンパニー」
盛和塾の話しをもう1つ。
先日、盛和塾札幌例会があり、そこでアインファーマシーズの大谷社長の「我が経営を語る」の話を聞きました。
その話しの中で「これは!」と思うことがありましたので紹介します。
アインファーマシーズという会社はドラッグストアーの「アインズ」」を全国展開しています。
しかし、この会社の収益の大部分は調剤薬局です。
「門前調剤薬局」に特化し、その調剤薬局の数は日本で一番多く、売上も1500億円、経常利益140億円という規模になっています。
大谷社長は1981年に創業しましたので、31年ほどで東証一部上場の会社にしています。
この会社の特徴はM&Aを繰り返して規模を拡大したことです。
その目的は成長拡大のスピードアップのためです。
この大谷社長が特に力点を置いて話したのは次のことです。
起業し、ある程度売上が上がった時、その後会社は「プライベートカンパニー」に進むのか「パブリックカンパニー」を目指すのかを明確にしなければならないということです。
それを明確にすることで進むべき目標とその手段が全く違ってくるのです。
大谷社長は早くからパブリックカンパニーを目指しました。
そのスピードを上げる為に、M&Aで事業を積極的に展開し、そしてファイナンスによる積極的な資金調達を進め、東証1部上場も果たしました。
勿論、「パブリックカンパニー」でなく、自分の会社は「プライベートカンパニー」で行くというのもいいです。
いけないのは、どちらともつかず経営することだと大谷社長は言います。
確かに私の父の経営方法を振り返ってみると、口にする言葉は「パブリックカンパミー」を目指しているのですが、実際の経営は「プライベートカンパニー」そのものでした。
結果経営パワーが分散してしまいした。
「プライベートカンパニー」を選ぶか「パブリックカンパニー」を選ぶか、起業家にとって大事な選択と言えます。
足るを知る
2日間、先週開催されました盛和塾世界大会のことを書きました。
今日はその最後になります。
世界大会の時の経営体験発表者の話です。
稲盛さんが「常に切磋琢磨して、昨日より今日、今日より明日良くなるように努力しなければならない」言います。
また時に「足るを知りなさい」とも言われます。
それは相反することで矛盾することではないかとと稲盛さんに問うたことがあったそうです。
それについて稲盛さんはこう話されました。
「あなた、だからダメなんです。理解していません。
『足るを知る』と言うことは、現状に満足しなさいと言っている言葉ではありません。
上手く行かない時、文句言ったり、愚痴ることなく、『感謝する』という意味です。
感謝しながら、常に誰にも負けない努力をし、心を高め、会社を向上させることは大切なことです。」
私もこの話を聞いて「成程!」と理解できました。
今、「足るを知る」と言う言葉を使って、現状に甘んじている若者が多いように思います。
必要なのは、足るを知って感謝しながら、努力する向上心ではないでしょうか。
稲盛講話
昨日は、先週開催されました盛和塾世界大会で最優秀賞になった回転寿司「花まる」の清水さんのことを書きました。
今日はその世界大会での稲盛さんの講話内容を紹介します。
講話は「人と起業を発展に導くもの」です。
最初にJALの再建についてです。
その再建成功の要因は
①フィロソフィが力を発揮し役員、幹部、社員が変わった。⇒意識改革
②アメーバー経営による管理会計システムの導入⇒組織改革
そして3つ目はサムシンググレイト。
社員が懸命に努力している中で、人の力以上の天の助けと言われるモノを感じました。
サンスクリットの格言で、そのモノを紹介しました。
「偉大な人物の行動の成功は、行動の手段よりもその心の純粋さによる」
そして稲盛さんはその上で言います。
事業の成功を達成する時、正しく、美しく、優しい心でなければなりません。
ただし、正しく、美しく、優しいだけでは経営になりません。
経営者はそれを土台にし、「凄まじいまでの闘争心」を持たなければ成功出来ません。
そしてその闘争心を正しく美しいい魂でコントロールすること。
だから意志が弱い人はダメです。
自分が立てた目標をやり遂げる強い意志がなければなりません。
鬼のような上司が必要なのです。
「一生懸命したから・・・」を許したのではダメなのです。
優しい上司が、時には鬼にも成らなければいけません。
美しい心が羅針盤で、闘争心をコントロールして事業は成功します。
1時間半ほどの講話時間でしたが、特に心の残ったのは以上の話でした。
盛和塾世界大会
先週は18日から20日まで上京しました。
主な目的は盛和塾世界大会参加です。
日本中、世界中から4000名近くの塾生が参加し、2日間にわたり開催されました。
メインは8人の経営者の「経営体験発表」と、稲盛さんの「塾長講話」です。
発表された各経営者の体験内容は、聞く多くの塾生に感動を与えました。
その中でも、今回は私達札幌の塾生から初めて選ばれ、発表した人がいました。
その塾生は札幌と根室で回転寿司「花まる」を経営している清水鉄志さんです。
清水さんの体験発表は以前に練習を兼ねた勉強会で、同じものを2度ほど聞いていましたが、その都度涙が出ました。
以前にもブログで紹介したかも知れませんが、改めて少し紹介します。
小さい頃から赤面症の少年だった清水さんは、あえてそれを克服するために、専門学校を出てから上京して落語家になろうとしました。
でも断られ、すぐあきらめました。
その後は浅草の喜劇劇団に入りましたが、26歳の時に故郷の根室に帰りました。
根室に帰っても26歳の彼には就職先は無く、仕方が無く東京でアルバイトしたスナックの経験を生かし、スナック経営を始めました。
スナックは5名ほどの従業員、年間売り上げ3千万円程度だったそうです。
スナックを経営しても、小心の彼はお客に愛想も言えず、サービス業は向いていないと、回転寿司店に転向しました。
しかし寿司も握ったことも無い彼が始めた回転寿司は、案の定それほど売上が上がりません。
清水さんは若い頃から「なぜ人間は生きるのだろう」「なぜ仕事をするのだろう」と悩んでいましたが、その頃は特に悩みました。
そんな時稲盛和夫さんの経営講話テープに出会いました。
そのテープを聞くとその内容に引き込まれ、トイレに行くのも食事をするのも惜しくなり「取り憑かれたように聞き狂った」そうです。
それが1カ月ほど続きました。
その様子に周りの人達は気味悪がったようです。
そのテープこそが稲盛さんが今私達に教えてくれている「フィロソフィ」なのです。
その後清水さんは盛和塾に入り、毎日フィロソフィを経営に取り入れる努力を続け、今は従業員500名、年商30億円の会社にしています。
彼の目標は100億円の売上です。
清水さんの話を聞いて、稲盛さんは「感動しました。このようにフィロソフィを使って、経営を改善し、素晴らしいい経営をされている。学ぶべきことが多くあります。
また、小心で赤面症でイジメられた子が、このような仕事を成したことが素晴らしく、子供のイジメ問題にも生かすヒントがあります。」と話していました。
そして、私達の予想通り清水さんは栄えある「最優秀賞」に輝き、稲盛さんから表彰状と記念品をいただきました。
清水さんの話は、聞いた4000人に感動を与えたのです。
聞いたいた私も涙が止まらず、こっそり拭くのに苦労しました。
清水さんの話が終わると、盛大な拍手が続き、その拍手が鳴り止みません。
司会者が制止するほどでした。
今夜は盛和塾札幌の例会があります。
きっとその話題でまた盛り上がることでしょう。
家具作り
この連休は久しぶりに家具作りに精を出しました。
新しく庭が出来たので、そこに置くベンチを3台。
グリーンのベンチが2台、真っ赤が1台。
グリーンのベンチは風景に溶け込みますが、真っ赤なベンチは目立ちます。
陽の光に当たってその赤がまぶしい位。
赤を見ると元気が出ます。
久しぶりの家具作りだったので、大変疲れました。
1日中、中腰になったり、しゃがんで作業をするので、普段使っていない筋肉が悲鳴を上げます。
それでも頑丈なベンチが出来ました。
知人達と庭でバーベキュ―をする時、活躍しそうです。
その翌日も続けて家具作り。
妻から依頼された妻専用の本棚。
前日の作業の疲れが取れないまま頑張りました。
これも完璧な造り。
私は経営者より職人に向いているのかと改めて思った連休でした。
明日から盛和塾の世界大会が横浜で行われます。
私も参加して、今度は知的刺激を受けて来ます。
夢が無い子供達
今の若者や子供に夢が無いとよく言われます。
確かに、「その日楽しく暮らせればいいや」という思いで生活している若者が多いようです。
そして将来に対して夢が無いようです。
私より古い時代には「末は博士か大臣か」という言われ、上昇志向が高かったようです。
私の団塊の世代も、若い頃は何かを探しに旅に出ました。
世界放浪の旅と称して鞄一つを持って貧乏旅行に出るのが流行りました。
何かを見付けた人もいたし、見付けれなかった人もいました。
それでも何かを求めていた分だけ上昇志向がありました。
しかし、今の多くの若者にそれほどの思いは無いように思います。
それの要因には、よく言われるようにモノの豊かさがあるようです。
私の子供の頃はまだ日本中に貧しさが残っている時代でした。
欲しいモノがあっても、買ってくれません。
何度お願いしても買ってくれません。
それで欲しいモノはお年玉や神社のお祭の時にもらうおこずかいを貯めて、1年2年がかりで買いました。
結果、そこまでしても欲しいと思う気持ちが育ちました。
私達より貧しい人達は、お腹いっぱい食べたいと思ってそれを夢見て頑張りました。
一方、今の子供達は小さい頃から品物も食べ物も欲しいと言えば買ってくれました。
欲しいモノはすぐ手に入る、その繰り返しの中で、「何としても叶えたい」という気持が育たず、夢を持つ喜びを失っていたのかもしれません。
それでは、自分の子供だけ我慢させようと思っても、仲間外れにされては可哀そうという親心から、やはり買い与えてしまいます。
人を幸せにしようとしてモノを開発し進歩してきた世の中なのに、それによって人が将来に対しての夢を失って行く。
矛盾した世界です。
必要なのは物質社会から精神社会。唯物論から唯心論。
今子供の教育に必要なのは精神教育。
しかし精神教育と言うとするすぐ「軍国主義」と言う言葉が返ってきます。
偏った思想が教育現場に残っています。
この風潮を無くすことは大切です。
そうすれば今のイジメも少しは無くなることでしょう。
そして今、改めて生きる為の「哲学」を学ぶことも大切のように思います。
イジメについて
今、新聞等で大津市のいじめ自殺のことが大きく報道されています。
イジメは昔からありましたが、昔は表に出て来ませんでした。
私も今になってみれば「あれがイジメだったのか」と思うことがあります。
高校の同級生の中でいつもニコニコして、誰から何を言われても笑っていた男子がいました。
その彼に冗談を言ったりしてからかったこともあります。
でも私は冗談だと思っても、彼にとってはそうでなかったのかもしれません。
私がなぜそう思うのかというと、彼は卒業以来1度も高校の同期会・同窓会に出てきたことがありません。
高校時代は彼にとっていい思いではなかったのかもしれません。
彼は以前新聞に大きな病院の児童心理学の医局長として紹介されていました。
イジメはイジメている方は意識していなくても、イジメられている方はしっかり分かります。
昨日のブログに「畑仕事」と題して書きました。
その中で従姉妹の孫ことも少し書きました。
彼は皆が嫌うダンゴ虫、いも虫等をせっせと集めて喜んでいました。
私の子供の頃は昆虫をとって遊んだりしましたが、結構残酷なことをしました。
アリを踏み潰したり、アリの巣に花火を仕掛け、爆発させたり。
タレントのたけしさんが小さい頃、蛙のお尻からストローを入れお腹を膨らませた爆発させたという話は聞きましたが、さすがにそれは気持ちが悪く出来ませんでした。
子供は何も知らない、無垢と言われながら、残酷なのかもしれません。
でも小さな虫をいじめながら、これ以上してはいけないといことを学んだような気がします。
時としてそれが歯止めが利かなくなって、小動物をいじめたりするようになってくるおかしな人が出て来ます。
子供が小さい頃に、弱いものをイジメたらいけないと思う気持ちと、イジメる快感を得る「境」があるのかもしれません。
その時に「誰が、どのように教えたか」が大切な分岐点になります。
先ほど紹介しました従姉妹の孫は、皆が嫌がる虫を可愛いがります。
彼はきっと優しい大人になることでしょうね。
畑作り
先週末、妻と一緒に従姉妹が作った畑に行ってきました。
札幌市内の住宅地の中、200坪程度の宅地に畑を作り耕しています。
4年ほど前から素人で始めたそうで、今はハマり込んでいます。
野菜と花々。その畑の隅に小さな家を立てています。
庭が良く見える大きな窓があり、台所、風呂、トイレそれに泊まれる小さな部屋もあります。
家の中から見た景色がまたいい。
可愛いその家がまた風景になっています。
彼女が普段住んでいるのはそこから15分位のマンションです。
別荘かわりにして、暇を見付けてはここへ来て野菜作りにいそしんでいます。
時折孫も連れて来ています。
私達が行った時にも来ており、土をいじり、穴を掘り、虫を集めていました。
ダンゴ虫、てんとう虫、青虫まで。
孫は虫を嫌がりません。
子供にとっても土をいじることはいいことです。
私の子供頃は夏になれば、川へ泳ぎに、また昆虫採集。
土に穴を掘ってはミミズやアリを観察しました。
暑いのも忘れて遊びまわりました。
今はその頃とは環境が変わってしまい、多くの子供はそのような遊びは頭にも浮かべられないでしょう。
可哀そうな気がします。
従姉妹はこの歳になって、初めて自分が打ち込めるものを持てて嬉しいと素直に喜んでいます。
彼女も60歳を過ぎ、子育てが終わった今が本当に自分らしい生き方を見付けてたようです。
私達夫婦はこれから畑作りを始めるところ
いい先生が傍にいて心強いかぎりです。
あきらめる
今朝出勤前にテレビを見ていると、太平洋を37日間漂流した船長の本のことが紹介されていました。
題名は「あきらめたから、生きられた」
その題名を聞いてアレッ!と思いました。
普通は「あきらめず生きるぞ!」と思い続けたから生きれたと考えます。
それが逆なので、つい耳を傾けました。
船長の石川さんの船が航行不能になり、潮に流されました。
交信も出来ず、何も出来なくなった時、あきらめたそうです。
考えたのは「出来ないことはあきらめる」
出来ないことをあきらめなかったら助からなかった。
「出来ないことはあきらめる」と考えると、逆にその時に自分で可能な出来ることを探します。
自分でルアーを作り魚を獲ることもしたそうです。
無理をせずいたから助かった。
普通人はあきらめず、頑張らなければならないと思っています。
仕事でも「ネバーギブアップ」
その為に、誰にも負けない努力をします。
しかし突然自分の周りにあった大事なモノが無くなった時時、頑張り続けることが出来るでしょうか。
例えば、アスリートが事故で足を失ってしまってはもう競技は出来なくなります。
いくら頑張ろうとしても出来ません。
それをあきらめずにいると、どうしても事故を起こした関係者に対する恨みや憎しみになり、出来ない環境にある自分が嫌になってしまうでしょう。
逆に「もう足はないのだ」とあきらめれば、また別の生き方が見つかり、生き生きとした人生が送れます。
パラリンピックの選手達はその経験をしている人達だと思います。
私達の年代である団塊の世代もそうです。
若いつもりでも、歳をとり若い時と同じ体力が無くなり、第一線から離れています。
それでも負けず嫌いの人は頑張ろうとします。
でも、年とともに無くなる体力はどうしようもありません。
歳をとり、体力も記憶力も落ちてきたということを良く認識し、あきらめること。
出来ないことはあきらめると、出来ないことで悩むことが無くなります。
そうするとストレスを感じず、その時に自分で出来ることを探し出すことが出来ます。
いつまでも昔のことをあきらめず、放そうとしなければ、新しいことを掴むことは出来ません。
どう頑張っても出来ないことはスパッとあきらめ手放す。
そうして新しい可能性を追い、それを掴む
何かを放さなければ新しいものを掴むことは出来ないのです。
そのような考えは、歳をとっていく私達60歳以上には必要ではないでしょうか。
こんど石川拓治さんが書かれた「あきらめたから、生きられた」を買って読みます。
経営理念
起業して始めた会社が「成功する」ためのお話しです。
起業して一生懸命努力していくと事業も拡大して行きます。
ところがあるところまで行くと止まって、落ちて行く人がいます。
その原因はいろいろあります。
その内の1つを紹介します。
起業する目的は様々でしょう。
単に社長になりたかったとか、お金を儲けるとか、異性にもてたいというのもあるかもしれません。
その動機は不純でいいのです。
勿論初めから世の中のためになる事業を起こそうと思う人もいます。
その数は少ないでしょうがいます。
それは素晴らしいことです。
でも最初は金儲けしたいという気持で始めてもいいと私は思います。
ただその思いのままで仕事が拡大していくとある壁にぶつかります。
仕事がうまく行くと、社長はもっとお金を儲けたいと考えます。
そうするとつい儲かりそうだと思い、本業以外に手を出す人がいます。
これが壁になり、つまづきになります。
例えば家具の製造業が儲かりそうだからと、福祉介護の仕事したとします。
福祉介護の仕事は全く家具の仕事と関連しない世界です。
福祉介護の世界に参入することで、資金、戦力は分散されてしまいます。
以前紹介しました「弱者の戦略」は一点集中戦術に徹しなければなりません。
これに反することになります。
このような失敗をして学ぶことは、会社の目的が金儲けだと、間違いを招くということです。
会社の目的を利益第一だと、つい本業以外の仕事に手を出してしまいます。
それを防ごうとした時、会社の目的がもっと別の志の高いものでなければならないと気付きます。
その時初めて会社の存在理由が明確になります。
そして本業の仕事に戻ります。
そうなれば一度落ちた業績も格段に伸びていくでしょう。
起業当初、起業のエネルギーとなる「金儲けするぞー」という思いは必要です。
でも、そだけではどこへ飛んでいくか分かりません。
エネルギーは目的には成り得ません。
会社の目的となる「理念」作りは必要です。
最初は無くても、壁にぶつかって必要だと気付きます。
起業した時、お飾りで目的や理念を作ることがあります。
でも本当に苦労した時に作った目的、理念こそが本物になります。
庭仕事
今日と明日は畑仕事をする予定です。
今週、私の小さな庭に黒土が入りました。
樹木や野菜を植える予定です。
妻から午後には腐葉土を買って来るよう指示されています。
隣地境界と西日が入る窓にはそれそれにポールを2本立て、上部でもう1本のポールとつなげています。
これに網を掛け、そこにつる草をはわせる予定です。
本当はつる草の代わりに、春にゴーヤを植えてゴーヤチャンプルも楽しもうかと思っていましたが、時期的にはもう遅いようです。
ゴーヤは沖縄で出来る南国のモノと思っていましたが、北海道でも生るのですね。驚きました。
もう夏なので、植えるモノも限られています。
今日これから畑を耕します。
カルチャ(文化)という言葉はカルティヴェート(耕す、培う)から来ているそうです。
2日間文化的生活です。
弱者の戦略
起業した人が私の周りに多くいます。
今朝も朝早くからオフィスに来ていた起業家と話をしました。
業績を聞くと、「今は新規が増え過ぎて・・」と嬉しそうです。
それを聞くと私も嬉しくなるし、「頑張れ!頑張れ!」と声を掛けたくなります。
起業家の中でもうまくいかない人も時折います。
上手くいかない原因の1つに目標作り、販売計画にあります。
大きな会社を相手にするような営業をしていると、ただ消耗するだけで売上も利益も上がりません。
やる気いっぱいの人はつい自分より大きな会社、強い会社を意識し、同じような商品を売り、同じ顧客を獲得しようとしますが、なかなか上手く行きません。
目的は「日本一の会社になる」でもいいのですが、だからと言って初めから自分より強い会社と闘ってはいけません。
ランチェスターの法則で言う「弱者の戦略」で行くべきです。
小さな地域や部分的なところで一番を目指すことです。
これは起業家ばかりでなく、中小企業の経営者にも言えます。
私のグループ会社の中でも昨年整理したところがあります。
競争相手の会社が大量生産、大量販売、低価格の規模の大きさでシェア―を広げてゆきます。
それに太刀打ち出来なくなったのです。
相手企業は「強者の戦略」で戦い、私のグループ会社はそれに引き込まれてしまいました。
規模の大きさ、資金的にも差があり、回復する見込みがないとして整理されました。
「弱者の戦略」を見出して経営戦略の方向転換をすれば良かったのでしょうが、それには規模が大き過ぎました。
その業界が拡大するにつれて、各会社は生産規模の拡大し、大量生産、大量販売、低価格に向かいます。
それについてこれなければ負けてしいます。
業界が拡大し、それに伴い生産性を上げている時、ある時点で今後「強者の戦略」で行くか、「弱者の戦略」で行くか決めなければならない時があります。
それを決める要因は資金力、組織力そして人材です
その選択時期を見逃すと会社は衰退の方向に行きます。
「弱者の戦略」に興味がある方はランチェスター戦略を勉強するといいですよ。
哲学
新聞の広告欄を見て思うことがあります。
「〇〇をすれば一瞬にして変わる」とか「この本を読めばあなたの人生が変わる」ような本が多くなったのではないでしょうか。
世情に不安を抱いている人を励ます、あるいはその不安感に付入るというような色々な考え方があります。
啓蒙書として、著者の主催するセミナーやサークル・組織への入り口として書かれているものもあります。
また同じ著者が似たような本を何冊も出します。
これ一冊で一瞬にした変わるのなら、それ以上の本は書かないと思うのですが、似たような本が出て来ます。
不思議です。
政治の不安、経済の低迷、その上震災等心配な世の中。
どうしても、それに負けない自分に変えたい、強くなりたいという思いは強くなります。
私もそうです。
そんな時、父の家を整理していたら、物置から私が大学生の時に買った本が出て来ました。
40年ほど前に買った岩波書店の「哲学」18巻です。
箱カバーは黒く汚れていましたが、中に入っている本は全く汚れていず、きれいなまま。
学生時代に読みましたが、あまり理解できず、途中で断念しました。
それを紹介しますと「①哲学の課題」「②現代の哲学」「③人間の哲学」「④歴史の哲学」「⑤社会の哲学」「⑥自然の哲学」「⑦哲学の概念と方法」「⑧存在と知識」「⑨価値」「⑩論理」「⑪言語」「⑫科学の方法」「⑬文化」「⑭芸術」「⑮宗教と道徳」「⑯哲学の歴史Ⅰ」「⑰哲学の歴史Ⅱ」「⑱日本の哲学」
この中で興味あるのは「⑧存在と知識」「⑮宗教と道徳」です。
現代の様な混沌とした時「哲学」という言葉に引かれています。
当時の哲学はマルクス思想の影響を受けているはずです。
文章は難しく書いています。
18巻全部を読む気力はありませんが、好きな巻をゆっくりと読んでいきます。
学校教育
最近若い人と会うと、どうも「打たれ弱い」という感じがしてなりません。
強く言うと、いじけ、反発します。
優しく言うと甘えます。
特に男性がその傾向が強いように思えます。
最近はセクハラの他にパワハラという言葉を聞くようになりました。
会社の上司がその立場を利用して理不尽なことで部下をいじめる。
これはパワハラです。
でも、叱咤激励もパワハラとなる可能性があります。
目標に向かって頑張っていく時、1人違う行動を取れば注意をし、時には叱ります。
私はこれはパワハラだとは思いません。
しかし今の考えでは受けた側がそう思えばパワハラと認定されがちです。
会社はその目的・目標を共有した人達がそれを達成するために頑張るところです。
その競争相手は世界中にいます。
そこには相手を蹴落としてでも、何が何でも勝ち抜き、生き残ろうとしている「つわもの」がひしめいています。
優しいだけの会社では生き残れません。
先日のテレビで日本体育大学の女子学生の集団行動の練習風景が流されていました。
監督から怒られ怒鳴られ、時には人格否定さえ受けながら、懸命に頑張っている姿を見て感動した人も多かったと思います。
見方を変えればパワハラです。
でも彼女達はパワハラと感じていないようです。
これは受ける本人の意識の問題です。
叱られることに慣れていない人が増えています。
この原因の多くは小学、中学、高校の教育でしょうか。
全てが平等という教育環境で育ち、叱られることも無く、社会生活とはかけ離れた、まるで試験管の中で純粋培養されたように教育を受けます。
しかし社会に出れば、学校の様にはいきません。
不公平、不平等の世界です。
結果パワーに抵抗力のない若者が潰れていきます。
子供時代に、叩かれても、転んでも、「何クソ!」と起き上がって行ける、そんな逞しい子供が育つ教育が大切だと考えます。
鹿の角と革
昨日相談にのって欲しいと来客がありました。
エゾシカの角や革を使った商品作りについてです。
エゾシカの角はナイフの柄やハンガーラックなどに使われることはあっても、ほとんどが捨てられているそうです
。
鹿革もあまり利用されていません。
相談者はその利用方法として、角を輪切りにしてアクセサリーやお守りを作ろうとしています。
話を聞いていくと、誰がターゲットなのか、どの様に売っていくのかが決まっていません。
そこは大事なところです。
お客様が買いたいと思うような価値、意味づけを明確にしなければ買ってくれません。
また売値、その材料費・手間賃の計算は?となるとまだ出来ていません。
不要として捨てられる角や革の再利用を考えるのはいいのですが、思いばかりが先行しているようです。
起業を考える、新製品を作るという時、自分の思いが強ければ強いほど、意識してそれを押さえなければなりません。
お客様は本当に欲しがるのか、欲しがるとすればどのような人か、男か女か、中高校生か、それとも既婚者か。
欲しいと思われる人を絞り込み、その人をイメージして商品作りをしなければ、売れず単に自己満足だけで終わってしまいます。
相談者は改めて商品作りを企画するようです。
ところで鹿の革の再利用についてですが、「なめし」の技術は北海道には無いようで、本州の業者に依頼しないとダメだそうです。
今北海道ではエゾシカ肉の商品化を進めています。
それに伴い生まれる革の利用も自分達で出来るようにしなければなりません。
早くその技術を導入して革の製品・商品作りしていかなければなりません。
それによって、エゾシカを使った北海道産物の育成になります。
鹿革の中に、フェルトのように肌触りがいいセーム革があります。
眼鏡拭き、レンズ拭きに使われます。
私の個人的な希望ですが、このセーム革で作られた、デジカメ入れの袋が欲しいと思っています。
今のデジカメは小さく携帯に便利です。
でも鞄に入れて置くには擦りキズが心配です。
専用のカメラケースもあるのですが、固くてかさばります。
そこでフェルトのように柔らかく、破れに強いセーム皮で作った信玄袋に入れると鞄の中でも邪魔にならず使いやすいはず。
そんなセーム皮で作られた「デジカメ袋」があればすぐ買います。
1500円位がいいところかな?
シンプルにする
仕事をする上で求められることの1つに、シンプル志向があります。
核心は何かを求めたり、肝心なことをするために、余計なことを省きます。
より効率を求めてゆく過程で行われています。
組織をピラミッド式からフラットにしてトップと現場の距離を短くする。
内に抱えていた部門を切り離してアウトソーシングにしする。
工場の生産性を上げる為、機械化を高め人手を省いたり、人が歩く歩数を少なくする工夫をします。
そこには求める数字化した成果目標がなければなりません。
それにより、より生産性、経営効率を高めてゆきます。
一方、シンプルにする、省く、という行為を間違えて使っている人がいます。
「面倒だから省く」が始まりです。
「面倒なことはやめて簡単にしようよ」という言葉で、大切なこと、肝心なことを避ける経営者が言います。
「シンプルにする」「余計なことを省く」という行為と似ているように見えますが、真逆です。
楽をしようと思って行う行為は単なる怠惰です。
そのような経営者の会社は衰退の方向に向かって行きます。
もう1つ省くというと、日本の風習・慣わしがシンプル化しています。
結婚式を挙げる人が減ってきたり、挙げても仲人を立てる人はほとんどいません。
葬儀も以前と違って家族葬が増えています。
生活の行事もそうです。
季節の行事は変わってきました。
正月はしますが、おせち料理は作らず、買ってきます。
お餅もそうです。
ひな祭りや端午の節句、お彼岸やお盆、月見。
そこには日本の文化があるのですが、多くが省かれてきています。
日本人でありながら、日本の文化を知らない人が多くなっています。
どんどんその傾向にが強くなり、知らない人ばかりにありそう。
いつしか、餅つきや月見などは文化財的行事というようになってしまうのでしょうか。
私の手元に「すまいの歳時記」という講談社が出版した本があります。
昭和60年に発行され250ページもあります。
日本の伝承行事が詳しく写真付きで書かれています。
改めて知る日本の文化が描かれています。
それでいて読むと懐かしい気持ちになります。
毎年12月28日には親戚大勢で行われた餅つき。
お彼岸に母が作ってくれた牡丹餅、おはぎ。
9月の月見には兄とススキを取りに行き、母が作ってくれた団子をお供えしました。
懐かしく思い出します。
2振りの刀
昨日、会社に刀鑑定士さんをお呼びしました。
父の形見の刀が2振りあり、その鑑定のためです。
父は祖父から引き継いだものですが、どのような経緯で当家に引き継がれているか分かりません。
山地は元は四国の讃岐の出身。
昔は海賊だったかも。
刀の1振りは備前長船倫光で、1振りは無銘です。
私達は無銘の方は江戸時代の道中刀でないかと思っていました。
でも、鑑定士さんの話ではともに室町時代の刀でないかということです。
俗に言う古刀です。
無銘の刀がなぜ無銘かとうことも教えてくれました。
元々、刀身が長かった刀の柄の部分を切り落とした時、銘が入った部分が無くなったのではないかということです。
その証拠に刀の波紋が柄のところまでつながっています。
室町時代の後期は戦国時代に入ります。
戦場では短い刀の方が戦い易かったようです。
その為に刀を短くしたのです。
今回の鑑定はあくまでも簡易的なもので、正式には協会に提出して鑑定してもらわなければなりません。
ところで刀の所有届け出はどこにすると思いますか?
私は銃刀法の関係から警察かと思っていました。
実際はその地域の教育委員会に届け出し登録証をもらわないとダメです。
幼いころこの刀で兄とチャンバラごっこをして、刃をボロボロにしてしまいましたが、今は研ぎに出されきれいになっています。
この刀は兄が引き継いでいきます。
いつか、この刀が我が家に伝わっているそのいきさつを調べてみたいと思っています。
カンブリア宮殿
昨夜テレビ東京の「カンブリア宮殿」を見ました。
稲盛和夫さんが出演していたからです。
私はいつも10時過ぎには寝るのですが、10時から始まり11時30分まで眠気も飛んで見入ってしまいました。
稲盛さんがJAL再建に取り組んだ当初、JAL幹部には倒産したという意識がまだなく、会議中そのような幹部におしぼりを投げつけたとうエピソードも紹介されていました。
私達に見せる温和な姿とは別の、仕事に向かう時の真剣な厳しい姿勢が見とれました。
番組の中で、JALの植木社長が稲盛会長はひと時も漫然と時間を過ごしている姿を見たことがないと言っていました。
時間があれば常に書類に書き込みをしながら、真剣に読んで姿を見て、「会長は50年近く、このように誰にも負けない努力をしてきたのだ」と悟ったそうです。
司会者の村上龍さんが言った言葉で「稲盛さんは6年前にカンブリア宮殿に出演いただいて、その時に語っていたことと全然ブレが無いのですね」という言葉が心に残りました。
この稲盛さんのブレないフィロソフィこそが京セラ、KDDIを作り上げ、JALを再建している原動力だと思います。
盛和塾で話されていることと同じことを今JAL再建で実証しているのです。
稲盛さんは私達に良く話していることがあります。
「これだけ皆さんに私の全てを教えているのだから、会社が成功しないわけは無いのですよ」
この番組の中で経費削減の姿が紹介されていました
その1つに、パイロットが鞄を引っ張りながらバスで出勤しているのです。
私はその姿を見て「ヘエ・・」と少し驚きました。
このようにバスや電車で会社へ行くというのは普通は当り前のことです。
でも以前はCAはタクシー、パイロットはハイヤーで送り迎えが当り前でした。
パイロットがホテルに宿泊する時も、会社と組合の取り決めで、部屋の広さがが20㎡以上なければならず、ツインやダブルの部屋を1人利用という形で宿泊していました。
私が東京のホテルの支配人をしていた時、ホテルはCAの定宿でした。
パイロットやCAがそのような待遇を受けているのを知っている私にしてみれば、少し驚きでした。
番組の最後に村上龍さんが書いた文章があります。
「オーラがすごかった。『神様』と話しているような気がしてきた。日本で、最後に残った経営の神様だ。ただし、JALが本当に再建できたのかどうか、現時点では私にはわからない。業績改善のおもな要因はコストカットであり、成長に転ずるには乗客や路線を増やさなければならない。巨大企業の体質がたった2年で変わるのかという疑問も残る。
サバイバルは本物なのか、答えが出るのは5年後だろう。」
村上さんが言うようにJALの本当の再建はこれからでしょう。
楽しみにしながらその経緯を注目して行きます。
God Bless Japan
パソコンは今や仕事では欠かせない存在です。
以前、日本で売られているパソコンのほとんどが日本製でした。
今は海外勢に圧倒されています。
その中でも台湾のメーカーも頑張っています。
アスース(ASUS)という台湾のパソコンメーカーがあります。
以前私もそのノートパソコンを買ったことがあります。
安いにもかかわらず、故障も無く快適に使っていました。
そのアスースのことが、昨日見たネットのニュースの中にありました。
フェイスブックの会員の中で反響があった話です。
いい話なので紹介します。
フェイスブック会員の1人がある写真を紹介しました。
アスースのパソコンの基盤に小さな文字で「God Bless Japan(日本に神のご加護を)」と印刷されてました。
日本は去年の大震災で被害を受け、多くの犠牲者が出ました。
それに対しての台湾の人達の思いは深く、すぐに支援の手を差し伸べ、多くの義援金も集まり日本に送ってくれました。
「1日も早い復興を」と願ってくれる台湾の人達の思いがこの言葉にあります。
そのことを知ったフェイスブックの会員達からは「ありがとう感激です」とか「感動しました」というコメントが多く寄せられたそうです。
アスースの会社では日本から問い合わせがあるまでこの事は知らず、同社の技術者が独断で行ったことで、誰か特定できないとのことです。
そして会社としては日本の1日も早い復興を願ったその行為に対して黙認するそうです。
アスースの社是は「技術革新やイノベーションの創出と並び、謙虚、誠実、勤勉」。
この行為は会社の理念が従業員に浸透している証拠でしょうか。
今の日本では、自分のことばかり主張する姿をを良く見かけます。
私もそうかもしれません。
でもこのアスースの従業員が行った「誰かのために何かをする」「誰かのために幸せを願う」という行為は感動します。
素敵な行為です。
この話は忘れている「何が大切なことか」を改めて教えてくれました。
消費税増税
昨夜やっと消費税増税法案が衆議院通過しました。
いろいろ意見もありますが私は消費税増税賛成です。
昨夜のテレビの街頭インタビューで聞くと反対する人が多いようです。
誰でも自分の生活が苦しくなるのは嫌です。
「消費税増税についてどう思いますか?」と聞かれれば、嫌だと言う人が多いのは当り前です。
ただ将来のことを考え、子供・孫のことを考えれば消費税増税も仕方がないと思えます。
日本の国民負担率は40%以下です。
国民負担率とは国民所得に対する「国税+地方税+社会保障負担」の割合です。
日本の40%以下に対して、デンマークの国民負担率は世界で一番高く、70%以上ということです。
しかし、デンマーク国民は、自分達は世界で一番ハッピーだと思い、幸福度調査をするとデンマークが1位で、日本は90位だそうです。
安心した生活をするにはそれなりに高負担になるのは仕方がないのです。
ただ一方、増税反対の人達が言うように、国の支出を削減するという改革も大変重要です。
これなくしては国民が苦労して負担してもそれが自分達に還元されず、訳の分からないところに流れていく。
この恐れもあります。
これを改革するには国レベルばかりでなく地方でも改革が必要になります。
大阪の橋本市長がその口火を切って改革しようとしていますが、北海道・札幌はまだその気配が見えません。
私の高校の同窓生は道庁を退職後、道庁の外郭団体に役員として入り、67歳まではその身分は保障されているそうです。
その外郭団体は必要な団体か、そうではないのかはわかりません。
必要な外郭団体はあるでしょうが、整理すれば多くの団体が整理されます。
この「天下り」というシステムはデンマークなどではどうしているのか興味があります。
日本のシステムを変えるには、国民の意識も変えていかなければダメでしょう。
「総論賛成、自分に関する各論は反対」では何も前に進みません。
これからは国民も1人1人痛みを感じながら改革しなければなりません。
その痛みは、これからの日本を背負う「若い世代」のため、現世代が負わなければならない痛みです。
車道の自転車
最近、自転車が車道を走っているのを良く見かけます。
歩道を走ってはいけないという道路交通法が徹底されたためでしょうか。
そのことが自動車に乗っていいるとよくわかります。
私も接触しないよう、より慎重な運転に努めています。
でも時々車道を逆方向に走っている自転車に遭遇します。
自動車は左側走行なのに、その自転車は右側走行しています。
向こう側から走ってくるとビックとします。
特に自動車が左折する時、右走行してきた自転車は「直行優先だ」と思っているのか突っ込んで来ます。
何度も驚かされます。
車が右折する時は直行する自転車が優先だとわかっているので違和感はありませんが。
自転車は軽車両だと法律で定義されています。
自転車が自動車と同じ車道を走る時は、当然ルールを守らないといけません。
中国に行った時、自動車も自転車も人も皆、交通ルールは無視です。
赤信号でも道路を渡ってしまいます。
慣れればルールがない中での知恵が生まれるのでしょう。
思うほど事故が無いようです。(もちろん日本より格段に多いですが)
でも今の日本の自動車と自転車の関係は、ルールを守る自動車とルールを知らない自転車が混然となって車道を走っているのです。
もしかしたら中国以上に怖い状態なのかもしれません。
「自転車にも免許を!」と私は言いたいです
自動車と同じ車道を走るからには、自転車に乗る人はルールを知った上で車道を走らなければなりません。
自転車に乗っている本人はそれほど危険を感じなくても、自動車を運転している方が危険を感じています。
万が一の時は自転車の方が被害が大きく、責任のほとんどは自動車を運転しているの方に来ます。
それは不公平です。
互いにルールを守り、互いに思いやりを持つことで本当の自転車と自動車の共存が成り立つのです。
野生動物を食べる
昨日交流会があり参加して来ました。
この交流会は札幌市の外郭団体が主宰しているご近所先生講座の講師達の交流を図るための会です。
ついたテーブルに興味深い講師がいました。
その人は女性のハンターです。
狩猟の鉄砲射ちです。
彼女の講座は「野生動物をいただく」という食に関しての話。
彼女は、駆逐のために止むを得ず射殺したシカなどの野生動物は、射殺するだけでなく美味しくその命をいただかなくてはいけないと言います。
開いたその講座は残念なんがら受講者が少なく8人位でしたと笑っていました。
面白そうな講座なので、私がその講座の開講を知っていたら受講したと思います。
講座の中では実際に焼いた鹿肉やドライソーセージなどの加工品を食べたりするのです。
ハンターになるには大変な手続きが必要で、免許の維持にもお金と手間がかかるそうです。
そのようなこともあってか、ハンターになる人が最近少なく、高齢者が現役引退して行く中、ハンター人口が減少しているようです。
彼女は今度「ハンターになりませんか?」という講座を開講する予定です。
昔から鉄砲に興味のある私も参加したいのですが、チョット無理かなと思っています。
鉄砲には散弾銃とライフルがあり、原則最初許可されるのは散弾銃しか認められないようです。
10年位の経験があって初めてライフルが許可されます。
彼女もまだ散弾銃です。
ライフルは威力があり、その弾の飛距離は4キロくらい飛んでしまうそうです。
間違えた方向に撃つと、山を越えて被害を発生させる恐れがあります。
実際そのようにして飛んできた弾でトラクターに穴が開いたという例もあるようです。
うっかりミスの多い私にはやはり無理かもしれません。
日本の神話
最近本屋に行って気付くことがあります。
妙に伊勢神宮や出雲大社等に関する本が目に付きます。
コーナーが出来ている本屋もあります。
また、それに伴ってか古事記・日本書紀について書いている本も多く見かけます。
平成25年は伊勢神宮の「式年遷宮」の年に当たります。
20年ごとに社殿を造り替える行事です。
また同じ来年は出雲大社も社殿を作りかえる60年ぶりの「本殿遷座祭」の年です。
そのような行事とつながっての伊勢神宮、出雲大社、古事記、日本書紀の流れになっているのでしょうか。
先日私も、「古事記と日本の神々」という本を買って読んでいます。
読むと沢山の神様が出て来て混乱しています。
でも今年伊勢神宮に参拝に行ったこともあり、興味深く読んでいます。
「日本の神話を知ることは日本という国を知ること」
そのように思い、楽しみながら読んでいます。
2つの飲み会
また飲み会の話です。
昨夜は友人と琴似にある「雪峰」という寿司屋に行きました。
ここは私のホテルの和食レストランで責任者をしていた女性が嫁いだ人の嫁ぎ先です。
「食事に行きますよ」という約束もしており、友人を誘って行ったのです。
「いらっしゃいませ」と迎えたくれたのは「新女将」。
私の顔を見て少しビックリしたようで、でもにこやかに席に案内してくれました。
こじんまりしていますが、手入れされたお店の雰囲気。
初めてお会いしたご主人に挨拶。
さわやかで、真面目そうなご主人。
お似合いのご夫婦です。
食事はコース料理を依頼し、さっそく日本酒で乾杯。
ご主人は高級ホテルで有名なザ・ウインザーホテル洞爺の和食店でも腕をふるっていました。
出された料理は大変美味しく、また酒が美味い。
ご主人や新女将さんとの話も弾み、酒がすすみました。
2時間ほど居て「次回は家内をつれてくるよ」と言って店を出ました。
同じ頃、その家内は東京から遊びに来ている私の妹と2人で近くのおでん屋に行っているはず。
友人を誘ってそのおでん屋に行くと、元気なおばさんが2人いました。
酒を飲むと元気に明るくなる2人です。
周りのお客さん達と盛り上がっていました。
私と友人はその隣で、静かに焼酎を飲むだけ。
確かこの前私がボトルキープし、封も開いていない少し高めの焼酎のビン。
既に3分の1になっていました。
私と友人は2人を残して早めに帰りました。
「たまには旦那のいないところで憂さを晴らすのもいいかな」と少し寛大な気持ちで1人帰りました。
経営は数字ではない
「経営は数字だ」という言葉をよく見・聞きします。
確かに経営する時、数字を押さえることは大切です。
数字は経営にとってGPSであり羅針盤です。
しかし大切なのは動かす「動力」です。
数字をいじくって、数字を見ていれば経営が出来ると言っている社長がいます。
組織をいじって経営改善をしようとする社長がいます。
でもそれだけではダメです。
経営は熱い情熱と、向かうべき方向を明確に示し、社長が先頭に立って進まなければいけません。
戦争になぞらえて「社長が先頭に立って討ち死にしたらどうなる」と言う人がいます。
経営は戦争ではありません。
経営で死ぬことはありません。
数字や組織をいじくって、それが経営だと思っている原因の一つに、経営の勉強会があります。
特にいけないのが起業者向けの勉強会です。
官庁関連が主催する講座の講師が不思議と「士業」の人が多いのです。
中小企業診断士会計士、税理士、時には司法書士です。
弁護士もいます。
そのような講座では主にビジネスプラン・事業計画書の書き方、マーケッティング等を中心として進められます。
勿論ビジネスプラン・事業計画書作りやマーケッティング理論は大変重要です。
でも時としてそれが中心となると、起業者は「経営=数字」と認識してしまいます。
熱い情熱を持ち自分の夢に向かっていく充実感、それを支える「正しい考え方」を教え、納得してもらうことが第一。
その後に数字の説明です。
起業し仕事を始めるとトラブルにあいます。
欠かせない教えのは、多くの人に起こるトラブルの紹介とそれを解決する考え方です。
1例を上げれば、起業して初めての仕事を受け嬉しくてつい細かい支払条件を詰めず売上を上げることの夢中になる人がいます。
その場合支払時にトラブルが発生します。
昔私が父から教えられ実行してきた1つに「後の喧嘩先にせい!」です。
「後で起こるだろうもめ事は、先に済ましてから始めよ」の意味です。
支払のことでお客さんとトラブルを起こしている起業家が私の周りでもいます。
このような実際の経営に即した話は経営者でしか話せません。
また経営は「続けること」が大切だということも教えます。
どんな素晴らしい業績を上げている会社も、落ち込むことがあります。
それを我慢して経営し続けた結果業績が伸びていくのです。
失敗した起業者の多くが、この1度の挫折であきらめてしまっています。
「経営は数字でない。熱い情熱だ!」
財産価値
昨夜はまた飲み会でした。
私が声を掛けたメンバーはビール会社、染物会社、都市開発会社の部長・専務達です。
それぞれ全く違う業種の集まりです。
共通点は「酒が好きだ」です。
飲みながらそれぞれの業界の色々な話が聞けて大変有意義な会でした。
その中で都市開発の会社の専務の話があります。
今、札幌の琴似駅近くに40階建のマンションを建てています。
来年の秋頃の完成予定です。
今までにも既に30階建、40階建のマンションを建て数年経っています。
それらのマンションはJR駅やイトーヨーカドー等と空中回路で繋がり、雨や雪に悩まされることなく、電車に乗れたり買い物にも行けます。
またスポーツジム、本屋、各病院にもつながって、便利この上ない立地です。
この数年経ったマンションも現在空室はなく、中古物件として売りに出されても新築当時とほとんど同じ価格で売買されているとのことです。
財産価値が下がらないのです。
普通マンションは中古になれば2~3割ほど下がるものですが、そうではないのです。
現在建築中のマンションはまで売り出しはされていません。
でもこのような好条件なので、すぐに売り切れる見込みとのことです。
財産として下がらなければ投資物件として購入する人もいるでしょう。
現に以前立てた2つのマンションの購入者は北海道以外の東京や大阪などの本州の人が多いらしいです。
特に首都圏や関西で大地震が発生するかもしれないという中では、避難先として購入を考える人もいるのではないでしょうか。
そして現在銀行からの借入固定金利が1%を切っている中で、投資物件としても魅力的です。
日本の経済が、近い内にデフレからインフレに転換すると言われています。
インフレになればマンションの財産価値が上がり、一方借入金額は相対的に低下します。
購入にはいい時期です。
お金に余裕のある方、購入を考えてみてはいかがですか?
精神的・身体的健康
昨日は金曜日に開催しましたフォーラムの主催者と後援者へ挨拶に行きました。
主に歩きでしたが、3ヶ所回って「疲れたな-」と思って、携帯に付いている歩数計を見ると1万歩越え。
2時間で3ヶ所回っての1万歩は運動不足の私にとってきつく、疲れが足にきました。
その後、打合せ、勉強会、懇親会と続き、帰宅が11時半。
寝不足気味で起床。
今朝寝不足の頭で考えることがどうもマイナス思考になっているのに気付きます。
朝そんな状態で妻と話した時の話題。
365日休みも無く朝から晩まで働き、睡眠時間も4~5時間位でも益々元気な人。
一方、仕事がきつく過労死する人。
前者の人はどちらかというと経営者、後者は雇われている人が多いでしょうか。
昨日会ったある若い経営者は、今月東京に進出するために自分の居場所を移すと言っていました。
近い将来アメリカにも拠点を作ると夢を語っていました。
この若い経営者は365日朝から夜遅くまで働きます。
それでいて元気。
夢や目標を持ち、それに真剣に向かっている人は、傍目から見て働き過ぎであっても、身体的・精神的に健康です。
それは現在・過去の成功した経営者の皆さんに言えることでしょう。
今朝は身体的にも精神的にも鍛えなければと思った朝でした
SOHOリレーフォーラム2
前回のブログで、「SOHOリレーフォーラムin札幌」が今日開かれます、と書きました。
そのフォーラムが15日金曜日に無事終わりました。
フォーラムは定員100名の参加者が集まり、最初主催者代表で日本政策金融公庫の村山廣治氏の挨拶。
続いて基調講演。
基調講演をしていただいたのは「SOHO CITYみたかフォーラム」理事長の河瀬謙一さんです。
河瀬さんのお話しの第1のポイントは「お金を掛けず起業、そして必ず1年目から黒字を目指す」です。
その為にはどうするかが語られました。
また続いてのシンポジウムでは3人のSOHO事業者のお話です。
それぞれなぜ起業を目指したか、それにより今はいかに充実した仕事をし、生活をしているかが具体的に語られました。
フォーラムに引き続いて「ワンコイン交流会」です。
コーヒーやソフトドリンク、ドーナッツや菓子を用意して、気楽に交流が出来るようにしました。
交流会だけでも80名近い人が集まり、皆さん熱心にご自分のお仕事を語ったり、新しい知遇を得ようと名刺交換をしていました。
予定の1時間半がアッという間に過ぎてゆきました。
フォーラムは1:30から始まり、交流会18:00まで4時間30分間続きました。
多くの方が最後まで交流していただいたことをうれしく思います。
振り返ってみれば、このフォーラムを開催するに、多くの方々のご協力がありました。
なかなか決まらなかった主催者に日本政策金融公庫さんと札幌市男女共同参画センターさんがなっていただいたこと。第一に感謝です。
会ったことも無い人間が突然尋ねて来て「今度札幌で開催するSOHOリレーフォーラムin札幌の主催者になってください」とお願されたのに、それを受けていただいたのです。
この時は本当にうれしかったです。
主催者が日本政策金融公庫さんと札幌市男女共同参画センターさんに決まったお陰で、その後の後援者や協力者もスムーズに決まりました。
お忙しい中、札幌まで講演に来ていただいた河瀬さん、忙しいお仕事の中、時間を割いて参加いただいたシンポジストの佐佐木絵里沙さん、大田実さん、市村夕鶴さん。
ありがとうございます。
佐佐木さんは10頃から会場に来て、風船で飾り付けもしていただきました。
フォーラムの司会進行は日本政策金融公庫の今里所長にしていただきました。
会場の設営・後片付けは札幌市男女共同参画センターの菅原さんを中心にしていただきました。
皆さんに心から感謝致します。
1年前に依頼されて企画したフォーラム。
私にとってこのフォーラムが最初で最後だと思います。
大変いい経験をさせていただきました。
関係の方々に改めて感謝いたします。
SOHOリレーフォーラム
今日は「SOHOリレーフォーラムin札幌」の日です。
去年の今頃「来年のフォーラム、今度は札幌でやって」と言われて、「いいよ」と簡単に応えての開催です。
気軽に「いいよ」と言ったものの、私は過去にフォーラムなど企画したことは無いのです。
準備を進めるうちに大変だということが分かりました。
色々な人達にお世話になり、助けていただき、ほんとに皆さんのおかげで何とか開催にこぎ着けることが出来ました。
「段取り八分」のつもりで準備して来ましたので、無事終わると思います。(願いを込めて)
私はもうこのような経験をすることも無いと思いますので、今日のフォーラムを楽しみたいと思います。
北海道神宮祭
今日から北海道神宮のお祭りが始まります。
今日が「宵宮祭」。その後「例祭」「渡御」と3日間続きます。
私が子供の頃は北海道神宮は札幌神社と言われ、札幌市内の学校は休みになった記憶があります。
地元の会社も共に休みになり、皆でお祭を楽しみました。
今でもそうですが、札幌神社から離れた中島公園に何百という夜店が立ち、サーカスが興行を打ちます。
私も親に連れられサーカスを見に行った記憶があります。
その時、「悪いことをすると『人さらい』に合い、サーカスに売られてしまうぞ」と親から言われたトラウマがあります。
逃げるとこも出来ず、朝から玉乗りなどの修行をさせられ、出来なければムチで打たれる。
その時からサーカスが恐いモノに思えて、サーカスに行ったことがありません。
こんな話は今の若い人達には分からないでしょうが、私の同世代の者の中には同じようなことを言われた人が結構多くいるのです。
不思議です。
先日私が参加したビール会の会員の中に、琴似神社と手稲神社の神主さんがいます。
その神主さんの話では、昔は札幌神社のお祭りには札幌市内の神社から応援に駆け付けたそうです。
今は北海道神宮には人手も充実していて、それはもうないそうです。
でも「宵宮祭」だけは出席し、行事に参加するとのこと。
「宵宮祭」は単なる前夜祭と思っていましたが、神様を迎える大事な行事のようです。
先日まで行われたYOSAKOIソーラン祭りは北海道神宮祭の露払いの様なのもに感じます。
週末はお参りに行ってきます。
寿司屋再開
昨夜、毎月開かれるビール会に参加して来ました。
サッポロビールのホールで美味しいビールを飲みました。
その時その会の最中に、ビール会の会長が私のところに来て「今度再開することになりました」言われました。
会長は3月まである寿司屋のご主人でした。
故あって寿司店を閉めてしまったのです。
この寿司屋のことは以前のブログでも書きました。
大変美味しく、よく出前を頼んでいました。
閉店の時は妻と「無くなると淋しいね」と話していたのです。
そのお寿司の店を再開するというのです。
出資者がいてその人の力で再開するのです。
年齢は会長は私より上で、65歳を越していると思います。
その会長が目を輝かして話をするを見て、こちらも嬉しくなってしまいました。
経営に対する熱意は年齢に関係ありません。
WHOの定義では65歳を過ぎると高齢者だそうです。
日本には当てはまらないではないでしょうか。
会長が3月に店を閉め、会の皆さんにそのことを話してから少し寂しそうでしたが、それでもへこたれることなく、再開に向け努力するその姿は私達の手本です。
真面目にそして懸命に過去仕事をしてきた姿を見ている人がいたのです。
その1人が今回出資してくれた人なのです。
何かに挑戦して懸命に頑張る姿は、誰かが必ずどこかで見ているはずです。
昨夜家に帰ってそのことを妻に話したら、妻も喜んで「開店したらすぐ食べに来ましょう」と言っていました。
私も楽しみにしています。
一番の応援は美味しい寿司を食べに行くことです。
そして食べることは私の得意中の得意。
応援しますよ。
頑張れ会長!
競争の戦略2
今、M.E.ポーターの「競争の戦略」という本を読んでいます。
このことは去年の5月にもブログで書きました。
読みこなすのに難しく、この1年間、何度も挫折しそうになりました。
それでも何とか続け、今3回目の読み返しです。
3回目になってやっと少し楽に読めるようになり、若干ですがその内容も理解が出来るようになりました。
最近、本屋に行くとこの「競争の戦略」の解説本を多く見かけます。
この本で例題とされている会社がアメリカのそれも昔の大企業を取り上げています。
私にとってはそれも違和感を覚えたものでした。
でも、経営の原理は同じ。
中小企業にも十分生かせる手法が書かれています。
この本に書かれている、他社に打ち勝つための3つの基本戦略があります。
それは「コストのリーダーシップ」「差別化」「集中」です。
ただ、この戦略を使う時、重要なポイントがあります。
3つ戦略のうち2つ以上を同時に主目標にして上手く行くのは稀であるということです。
この戦略を実行するには、全力投球の心構えと組織面での支援体制が必要になります。
その時、戦略の主目標が2つ以上になるとぼやけてくるのです。
これは重要なポイントです。
「コストを下げ、商品の差別化を図り、それに集中しましょう」という謳い文句が良く目にします。
謳い文句としては分かりますが、実行するとなると進みません。
コスト下げと差別化は全く相反するものです。
大切なことは「経営のポイントを外さないこと」です。
完全に理解するのは難しいでしょうが、これからも気長にこの本を読み続けてゆきたいと思っています。
採用の時
週末、知人が経営する居酒屋へ行ってきました。
お店は居酒屋というよりモダンな割烹店という感じです。
知人は3年ほど前に開業して、1人で頑張っています。
忙しい時は時々奥さんが手伝いに来て、2人の優しさからとても居心地のいい店です。
料理もそれなりに工夫し美味く、その料理のほとんどは手作りと言っています。
そのような店も最近はお客様が少なくなり、いろいろ悩んでいるようです。
その為「思いっ切って今度チラシを2000枚ほど撒こうと思っています。」と言います。
それも来客数を増やす1つでしょう。
そのような来客数を増やす時、しなければならないことがあります。
受け入れ態勢を整えること。
当り前のことですがなかなか出来ないのです。
1人で起業し、1人でお店を運営していて、商売の最初の転換期は「いつ人を採用する」かです。
それが社員でもアルバイトでも同じです。
身の丈で経営するということは余計な経費を削減すること。
起業した最初は、1人で運営することはいいのですが、いつまでもそれが出来るわけではありません。
お客様が増える時、人手が必要になります。
その時期を見誤ると、折角業績が伸びる時なのに止まってしまいます。
先ほどの知人の店の様に、広告のチラシを入れるとする時は、チラシを撒く前にそれを十分整えなければいけません。
それをすることなく、従来のままの体制では、客が逃げていきます。
ビールや焼酎は頼んで3分位で出てこないとダメです。
5分過ぎると遅いという気持ちになります。
折角来たお客様を不満もって帰させては逆効果です。
「待たせること」はお客様がお店を敬遠する切っ掛けになります。
以前も紹介しましたが、1人で運営するイタリアンレストランが私の家の近くにあります。
人を連れ食べに行きました。
料理の量も多く、また大変美味しく満足だったのですが、出てくるのに時間がかかりました。
3人で行ってスパゲッティーを3種類頼んだのですが、3皿出てくるのに40~50分かかります。
そうなると、美味しいのでまた行きたいと思うのですが、なかなか足が向きません。
人を初めて採用する。
身の丈起業において、この「採用の時」を見定めることは、チョットした覚悟と勇気がいりますが大切なことです。
帆船模型
今ちょっと考えていることがあります。
それは帆船模型作りにチャレンジしようかということです。
皆さんもテレビで見ている出ようが、全長120センチ以上もある大型の帆船です。
私は20年ほど前に50センチほどの大きさの帆船を作ったことがあります。
完成するのに3年近くかかりました。
毎日は出来ませんし、休日にしたのでその位かかりました。
模型を作るのは大変細かな作業と根気と集中力を要します。
細く薄い板を一枚一枚貼り付け、最終的なは細い木綿紐をロープに見立てて、張っていく作業も結構大変でした。
そんなこともあり躊躇しているのです。
それでもやろうかなと考えているのは、細かい作業に熱中出来る自分の「集中力」を確認したいからです。
最近、困難なことや面倒なことを避けようとする自分を見ることがあります。
集中力も落ちて来ているように感じます。
今一度自分の興味を持っているものでその集中力を確認したいのです。
始めれば120週にわたってキットが送られてきます。
完成出来るかな?
今日明日で決めようと思います。
地域戦略
3日前から続いて書いています経営戦略の続きです。
今日は「地域戦略」について書きます。
どこで店を開くは大変重要です。
その選定として、「狙う客層を決めて、それに即した場所を選定する」と「場所を決めてからそれに合った客層を決める」方法があります。
本来は前者がベターです。
多くの場合テナントとして入ります。
その時、「賃貸料」と「場所」の兼ね合いで出店場所決定がなされると思います。
そうすると、先ほどの「場所を決めてからそれに合った客層を決める」ことになるのです。
その客層へどう売るかの「客層戦略」については昨日書きました。
今日は出店する場所をどう選ぶべきかの1つのポイントを書きたいと思います。
ただし、ここでは「料理やコックが腕に自信があり、辺鄙なところでもお客様を呼べるという」話は別です。
一般的には場所と賃料を見比べて決めます。
しかしその営業結果は賃料通りの結果しか出てきません。
それを良く理解しておくべきです。
賃料は固定費です。
高い賃料だと損益分岐点が高くなります。
賃料は収入の10%以内に収まるのが理想です。
ですから賃料は安いに越したことはないのです。
もう1つ別の見方をします。
坪当たり賃料4万円と2万円の場所があったとします。
札幌では札幌駅直結している札幌ステラプレイスに入っているお店が4万円だと聞いています。
同じ札幌駅周辺の別のビルが2万円だとします。
予算から考えれば、同じ札幌駅周辺なので2万円という選択が多いと思います。
でも客数はその場所の賃料に比例します。
4万円の店をA店、2万円の店をB店とします。
A店もB店も設備・内装の投資は同じ作りと仮定。
客数は賃料に比例するとして単純計算すると、A店はB店の倍の来客があることになります。
その結果売上は倍になります。
賃料が高い分、売上も高くなります。
ここでもう1つ見るべき数字があります。
それは人件費です。
パートを使っても人件費は固定費に近い経費です。
A店もB店も人数は同じだとします。
B店は暇な時間があり、従業員は手持無沙汰です。
A店は休む暇なく働きます。
そうすると1人当たりの労働生産性が全く違ってきます。
また、A店もB店も作りが同じなので、光熱水道費も若干しか違いません。
B店は客寄せのために常に広告宣伝しなければなりません。
A店は常にお客が来てくれるので広告費はほとんどかかりません。
A店はB店と比べて、賃料以外のコストはほとんど変わらず、それでいて生産性・経営効率は高いのです。
結果、賃料が高いA店の方が高い利益を得ることになります。
ただ、この理屈は分かっていてもなかなか4万円の賃料を払う決断がつかないものです。
その決断をすぐつけることが出来るのは東京で5万6万の賃料などを経験している業者です。
「札幌ステラプレイス」の場所の賃料を「安い」と判断出来る業者です。
その為いい場所で、賃料が高いところには東京の店が多いのです。
この理屈が分かっているからです。
成功経験がない地元の業者はそこで負けてしまいます。
このように考えると、「何を売るか」「誰に売るか」そしてそれに見合う価格帯が明確である経営なら、高賃料の場所は高い売上が保証されていると見ることが出来ます。
やはり昔から言われているように「1に場所、2に場所。3・4が無くても5に場所」になってしまいます。
客層を絞り込む
昨日は経営戦略について書きました。
8つの戦略、①商品戦略 ②地域戦略 ③客層戦略 ④営業戦略 ⑤顧客戦略 ⑥組織戦略 ⑦財務戦略 ⑧時間戦略です。
その中の「何を売る」の商品戦略は説明しました。
今日は「どのような人に売る」の「客層戦略」について書きます。
昨日の様に居酒屋を例にします。
店主に「どのような人に使っていただきたいですか?」と尋ねると、「どなたにも喜んでいただけるお店にしたいと思いますます」と言う人が多いです。
でも、このような店を目指すなら大変多くの費用と時間がかかります。
資本力のあるチェーン店などがとる戦略です。
資本も少なく、小さく起業した居酒屋ならお客様を絞り込むことです。
そのお客様層に「集中する」こと。
札幌にあるそうですが、阪神タイガーズのファンばかりが集まる居酒屋があり、いつも阪神フアンで混んでいるそうです。
阪神ファンは不思議で、勝っても負けても気勢を上げ応援します。
そしてファンを辞めらません。
私の知人にも阪神フアンがいます。
北海道に日本ハムが来て、彼も日本ハムのファンになりましたが、阪神は見捨てれないと言います。
阪神・日本ハム戦では阪神側に座って応援しています。
その阪神フアンに絞った店にしています。
これは野球ばかりでなく、サッカーやその他のスポーツや趣味の世界でも同様なことが出来るはずです。
また、知人から聞いた話です。
ある居酒屋は「〇〇高校の同期会指定」になっています。
同窓会でなく同期会です。
同じ時に高校を卒業した仲間は大学や就職でバラバラになっています。
しかし60歳位になると昔が懐かしくなる時です。
同期会の幹事から同期一同に「毎週〇曜日の19時から△△居酒屋で同期会やっています」と声を掛けておきます。
あの人に会いたいと思う人、時間が出来たから顔を出そうと思う人、東京からの旅行を計画する時、ついでだから顔を出すよう組んでみようと思う人。
最初は参加者も少なかったそうですが、歳をとるにつれ増えています。
また別の知人が、以前ある街でスコッチウイスキーのシングルモルトが好きな人達だけが集まる会を開きました。
好きな人は、高くて珍しいモノも飲みたいのですが、なかなか手が出ません。
それが会費1万円で、10名集まれば10万円になります。
手が出なかった美味しいウイスキーを味合うことが出来るのです。
その会はドンドン人気が出て、とうとう店を作りました。
会員は50名と決め、それ以上は増やさず、欠員が出た時しか入会できません。
どうしても行きたければ会員の同伴者としてしか入店出来ません。
その客層はその街の経営者・政治家達等のそれなりの地位の人達が入り、その会に入るのが1つのステータスのようになりました。
この店は儲ける為に始めたのではなく、楽しみを広げるという、経営とは若干違いますが、それでも客層を絞り込む点では参考になる話です。
このような実例は沢山あります。
「小資金で起業する」「身の丈で起業する」はランチェスター戦略でいう「弱者の戦略」を応用することでしょう。
経営戦略
昨日は、これから世界は「弱肉強食」の時代になっていきそうだということを書きました。
それではこれからどうすればいいかというと、個々人が人に頼らず、打ち勝つ力を持たなければならないのです。
坐して待つだけでは何も生まれません。
経済で言えば、起業を志す人が増えることです。
リスクを感じながら前向きに生きようとする人が増えることです。
このような起業家が増えることが日本が元気なっていく将来への保証といえます。
折角高い志を持って起業したからには事業が成功しなければなりません。
ただ、残念ながら私の周りでもやっと起業したのに事業が滞っているて悩んでいる人がいます。
そのような人達が共通している点があります。
それは「どこ」で「どのような人」に「何を売っている」かが明確でないのです。
分かっているようでいて、問い詰めるとあやふやになってしまいます。
経営するにはポイントがあります。
その1つに、ランチェスター戦略の専門家竹田陽一さんの経営戦略を参考にするといいです。
竹田さんは経営戦略を8つに分けています。
①商品戦略 ②地域戦略 ③客層戦略 ④営業戦略 ⑤顧客戦略 ⑥組織戦略 ⑦財務戦略 ⑧時間戦略です。
この中で大事なのは①~⑤まで。
その中でも①②③は重要です。
先ほどの「どこで?」は地域戦略。
「どのような人に?」は客層戦略。
「何を売る」は商品戦略。
例えば飲食店を例にあげてみます。
何を、誰に売るが決まれば、その場所が決まります。
逆にその場所が先に決まっていれば、誰に売るかを決めなければなりません。
でも、その「誰に」とか[どこで」の前に、「何を売る」かが明確になっていなければいけません。
最初に大切なのは「何を売る」かです。
単に刺身や焼き魚や煮物を売ってもそう簡単に売れません。
「売物」がそのようなどこでもあるものでは勝てません。
本当の「売物」は別にあります。
例えば、魚の新鮮さを謳うなら「毎朝直接市場から仕入れている」とか、「特定の漁師から毎日送ってくる」を売り物にします。
「料理の質の高さ」なら調理人の経歴を謳い文句にしてもいいでしょう。
また手作りの良さを訴えるなら、自作の燻製、栽培した野菜。
器も自分で焼いた皿や碗で提供するのも「差別化」になります。
自分の強みをトコトン調べつくして、「差別化」を図ること。
この「差別化」が大切な商品なのです。
弱肉強食
今、ツナ缶が値上がりしているそうです。
海流の変化が原因だとか、外国でのツナ需要が高まり、各国のカツオなどの漁獲量が増えているとも言われています。
BRICsといわれる、ブラジル、ロシア、インド、中国等の人口が多い国の経済発展とともに、食需要が急激に高まっています。
マグロやサーモンの魚類ばかりでなく、肉、乳製品、ワインなどの需要が増えて、国際価格が高くなっていると言われます。
以前は食料輸出国だった中国は今は完全に食糧輸入国になっています。
現在食糧を輸出している国はアメリカやカナダ、オーストラリア等の大国が中心です。
一方日本はご存じのように食糧輸入国です。
農業を支援しても日本の食糧自給率は益々低下しています。
その中で日本が豊かな食生活を遅れているのは、過去の経常収支黒字よる対外的資産の蓄積、また円高による物価安のお陰です。
潤沢なお金で安く海外から必要なものが買えています。
その日本の経済は現在株安、債権高、円高というアンバランスな状況にあります。
いつ崩れるかわかりません。
日本の経済のバランスが崩れた時、一気に円安になる恐れがあります。
その時、食料品をはじめ物価は高騰するでしょう。
また日本ばかりでなく、世界中がギリシャやスペインの経済危機が高まると、世界経済へのい影響が甚大なモノになります。
私が心配するのはこれを契機に、世界中は少ない食料品や資源を奪い合う「弱肉強食」の時代に突入するかも知れないということ。
資源のある大国は排他的な政策や方針の「モンロー主義」をとるかもしれません。
世界は日本人が目指している「人に優しい国作り」とは真逆の「弱肉強食」に向かっていくのです。
また、食糧・資源を求めた戦争も起こる恐れも感じます。
優しいだけでは日本は「弱肉」になってしまいます。
6月の今月はギリシャの選挙、日本の消費税問題などがあり注目しています。
週末
この週末は久しぶりに家でゆっくりしました。
2週続けて週末は旅行していたので、のんびり出来ました。
土曜日には妻と一緒にホームセンターに行き、バジルなどの香草類や花を買って庭に植えました。
今年の春夏は庭作りに精を出す予定です。
一般に人は、北海道・札幌は緑が多と思われがちです。
確かに山や公園には緑があります。
しかし残念ながら住宅地の中には本当に少ないのです。
現在住んでいる家のそばはまだ多い方ですが、新興住宅地は樹木がほとんどありません。
なぜか北海道の人は「邪魔だ」と言って、平気で木を切ってしまします。
10年ほど前まで住んでいた東京・町田の家の方がよほど木々や花に囲まれていました。
私の部屋の窓からはプラタナスの並木、我が家の庭のサルスベリの木、隣の家の大きな木々が見えまます。
夏の暑い日にも、その木々を通して吹く風は涼しいそよ風となり、部屋の中に入ってきます。
フッと花の香りも含んでいました。
余程東京の方が緑に囲まれた生活でした。
今住んでいる家の庭も少し緑を増やしたいと思います。
以前住んでいた家では、自分で庭の小道にレンガを敷き、畑を作り、6人掛けのベンチと椅子も作りました。
今年はまたそれに挑戦してみます。
土を触ることは健康にいいと言われます。
無理をしない程度に楽しみます。
不思議な偶然
昨日は1日なので、いつものように北海道神宮と琴似神社に参拝に行っていきました。
いつもは朝、会社に出る前の7時頃に行っているのですが、今回はたまたまお昼前になってのお参りでした。
琴似神社のあと北海道神宮にお参りし、駐車場に向かうところでバッタリ知人の女性に会いました。
その人は1年半ほど前に起業相談に来られていました。
彼女はその後占い師として起業され、忙しく仕事をしていました。
ところが1年ほど前にご主人が急に亡くなり、力を無くされ、仕事も中止するという連絡をもらっていました。
元気になったら連絡するということでした。
私も時折、元気になったか気になっていました。
その彼女と神宮の駐車場でお会いすることが出来たのです。
お互いにびっくりです。
彼女も1日には毎月お参りに来ていたそうで、その日もいつもは朝に来るのがたまたま遅くなったそうです。
偶然が重なりました。
話しているそこに車が止まり、「山地さん」と声を掛ける人がいました。
その人は起業した彼女が「ホームページを作ってくれる人を紹介してください」と言われ紹介した人です。
ですから、たまたま偶然が重なり、神宮という「その場所」で「その時」に3人がそろったのです。
偶然という以上に不思議な感じがしました。
ご主人が亡くなってから1年ほど経ち、今はだんだん力を取り戻して、近い内に仕事を再開するそうです。
今年の春には息子さんとお嬢さん共に一流会社に就職が決まり、ホッとしていると言っていました。
彼女の占いはよく当たるそうです。
でも彼女は知っている人を占うことはしないと言っています。
ですから私も占ってくれません。
私は占いに興味がある方なので、本当は占って欲しいのですが・・・・
ウッドデッキ
先日、我が家にウッドデッキが出来ました。
業者に依頼し10日間ほどかかって作ってもらいました。
家は3年ほど前に出来たのですが、庭は手付かずで、土のまま。
毎年夏には草がボウボウになっていました。
思い切って今年は庭改造に取り組みます。
その手始めとしてウッドデッキです。
最初「ウッドデッキの材料を何にするか」から考えました。
良く聞くのは、作ったけど5年位でシロアリにやられボロボロになった。作らない方がいいという話です。
従来は主に杉や松で作り、それに防腐剤を塗ったものが多かったです。
材料価格は安いのですが、メンテナンスが大変。
毎年防腐剤を塗るにしてもウッドデッキの裏面は無理です。
それより少しいい材料はレッドシダー材でしょう。
それでも10年持ちません。
最近は新建材として、木の粉とプラスチックの粉を混ぜ固めた材料が使われるようになっています。
耐久性があり、いいように思いますが、夏の太陽に照らされると熱くなり裸足では歩けないそうです。
やはり私は自然の材料にこだわりました。
結果、見付けたのは「ウリン」という木材です。
これは南洋材ですが重くそして硬く、また防腐に優れ、30年間メンテナンス無しでも持つそうです。
これに決めました。
30年持てば充分です。
30年も経てば、もうウッドデッキは必要なくなっている頃でしょうから。
これからは来客用の駐車場の舗装をし、木や花・野菜を植えます。
早速、休日には近くの大型ホームセンターに妻を連れていくよう言われています。
これからは外での仕事が増えそうです。
老人の武器は挫折
新聞やテレビで新藤監督が亡くなられたという報道がなされています。
この監督の映画はほとんど見たことがありません。
小さい頃「原爆の子」と「第五福竜丸」という映画を見たきりです。
その印象は暗く、強烈でした。
子供にとって原爆の恐さと共に、拒否反応が生まれたのでしょう。
その監督が100歳近くまで映画を撮る度に、そのエネルギーには驚かされました。
その監督の言葉があります。
「老人の武器は挫折です。
年をとると、若さがどんどん削り取られるが、その末に残るものがある。
挫折を乗り越えるため試行錯誤を重ねてきた心の転機です。
これこそ、老いたるものの力であり、これで若い人に対抗できる」
このように言い切れる自信は、その挫折から生まれたものなのでしょう。
一般の人も、歳をとるということは、いろいろな挫折を味わうということです。
それが肥やしにしてきたか、ただ避けてきたか。
それによって結果が違ってきます。
人はつい困難なことを避け、傷付かず、挫折を味わない安易な道を選ぼうとしがちです。
しかし何もしなければ何も生まれません。
そしてそれは不満な結果しか生みません。
若い頃に多くの挫折を経験すれば、それは必ず自分の糧になり成長の力です。
沢山恋をし、沢山失恋し、何かに挑戦して失敗を繰り返す。
若い内はいくら失敗してもまた取り戻すことが出来ます。
新藤監督ほどではありませんが、ある程度歳をとって来るとそれが良くわかります。
4つの事業選択肢
先日のセミナーに参加しました
その要約です。
講師は「起業支援ネットワークNICe」 代表幹事の増田紀彦さんです。
その演題は「起業を不滅にする4つの事業選択肢」
4つの選択肢とは
「従来マーケットに従来商品・サービスを提供」⇒現状維持
「新規マーケットに従来商品・サービスを提供」⇒新規開拓
「従来マーケットに新規商品・サービスの提供」⇒深耕工作
「新規マーケットに新規商品・サービスの提供」⇒新規事業
この4つです。
自社の今後の発展のため、どの選択肢を選ぶか、それが重要なことです。
そしてその為の必要な能力として
1・何を止めるかの「決断力」
2・何をやるのかの「洞察力」
3・決めたことを行動に移す「実行力」
この3つを上げ、その循環を示しました。
この分析はたいへんシンプルで、分かりやすいです。
経営者はこれを常に現状改革のためのツールとして身に付けておくことが重要でしょう。
知っているだけでなく、実際に使ってみて初めてその効果が分かるものです。
これにもう少し加えるとすれば、マイケル・E・ポーターの「競争の戦略」に書かれている「コスト」「差別化」「集中」というキーワードも入れるといいでしょう。
久しぶりにいいお話が聞けました。
今、大切なこと
今朝の新聞にパナソニックの本社人員を半減すると載っていました。
その他のソニーやシャープ等の家電業界も大変です。
日本航空も再建途中ですが、一度倒産しています。
一流会社に勤めれば安心という幻想がドンドン崩れています。
それでも「一流大学を卒業し、一流会社に入る」という志向はまだまだあります。
公務員志願者が増えているのはその安定を求めてでしょう。
でも皆が公務員になれば、誰が税金を作りだすのでしょうか。
私も5人の子供の親です。
子供達が安心で楽しく暮らせてくれればと願うと、安定志向に行きがちです。
しかし、これからはそうは言っていられません。
1人1人が自立した生き方をしていかなければ、生き残っていけません。
これからは今までの様な「優しい社会」から、「厳しい社会」に方向転換していくのですから。
たとえ今、就職し安定した生活であっても、いつどうなるか分かりません。
それに備えるには勉強でしょう。
その勉強は単に資格を取るためのものではありません。
生きる為の心構えを作ることであり、自信をつけること。
何があっても家族を養っていけること。
その為に今何をするか、良く考えてなければなりません。
身体に自信のある人は、「いざとなれば土方でもやるぞ」と体を鍛えることでもいいでしょう。
今まで身に付けた仕事の経験・知識・人脈を使って起業することもいいでしょう。
目的を持ってその勉強をすることです。
一番いけないのは「自己満足だけの勉強」です。
これによって付けた資格などが逆に自分で壁を作り、それ以上のことを考えられなくさせます。
大切なのは人格向上のための勉強、次に習慣を変える為の行動。
考えが変わり、行動が変われば、結果も変わります。
変わっていく自分が自信を持ち、新しきことへ挑戦して行きます。
今こそ、真っ当な考えを身に付け、行動する時です。
帯広
週末に帯広に行って来ました。
メインはある会のフォーラムが開催されたので、それに参加するためです。
当初は日帰りで行ってこようと思ったのですが、夫婦で行って来ました。
帯広は私が銀行に入り、社会人として第1歩を踏み出したところであり、結婚したところです。
本籍もまだ帯広にあります。
35年ほど前に帯広を出てから、私は2~3回行ったことはありましたが、妻は1度もありません。
そこで懐かしがっていた妻も同伴することにしました。
折角なので日帰りでなく1泊に変更して。
私がフォーラムに参加している間、妻は帯広の街を散策。
フォーラム終了後はその懇親会参加を免除していただき、妻と昔懐かしい店に行きました。
独身の頃、妻を連れて行った炉端焼きの店です。
記憶とipadで店を見付けました。
建物は木造で、地震が来たら一発でつぶれてしまいそう。
店の中は当時のままで炉端の周りにカウンター席があるだけ。
天井・壁・柱は煤と油で真っ黒。
カウンターも椅子も昔のままので、黒ずんでいます。
時間とともに作られたその雰囲気はとってもいいのですが、残念ながらお客様は少なかったです。
お客様は1組だけ。
昔は大変盛況でした。
魚を焼く名物叔母さんが人気者でした。
聞くところによると2年ほど前に亡くなったそうですが、亡くなる直前まで炉端の前で魚を焼いたそうです。
店にいた1組の人とも話しましたが、2人は恋人同士とのこと。
昔の自分達のことをフッと思い出してしまいました。
私達と同じ美男美女のカップルでした・・・・。
街の中は今でも残っている店、とうに無くなっている店。
そのように昔の店を探して歩くと、35年の月日の長さを改めて感じました。
思い出探しのいい旅でした。
1冊の本
私の机の上にはいつも1冊の本があります。
「心を高める、経営を伸ばす」という稲盛和夫さんの本です。
その本の表紙を開いたところに、稲盛さんのサインと言葉が書いてあります。
その言葉は「敬天愛人」です。
今から10年ほど前になるかもしれません。
稲盛さんが札幌に講演に来られた時、一緒に回転寿司のテーブルについて昼食をとりました。
緊張のまま食事が一段落した時、目の前に座っている稲盛さんにこの本とペンを出し、サインしてくださいと申し出ました。
快く書いていただいたのがこの言葉です。
それをきっかけに他の人達もあわててサインをもらっていました。
この昼食会は全く偶然に参加できました。
事務局から当日稲盛さんと一緒に昼食を取りたい人は連絡くださいという通知がありました。
盛和塾に入会したばかりの私は無理かと思いながら申込しました。
後日、以外にも承諾の返事が来たのです。
当日昼食場所に行ってみると、同席する人は8名程度。
事務局に聞いてみると恐縮し遠慮する人が多かったようですとのこと。
大変ラッキーでした。
昼食会場はいつも行列が出来る回転寿司の「はなまる」さん。
その社長の話では、従業員は皆、稲盛さんファンだとのこと。
忙しいのに入れ替わり立ち替わり稲盛さんのところに来ては注文を聞いていました。
その回転寿司のネタに生のサバがありました。
当時寿司ネタのサバは〆サバしかありませんでした。
後で社長から聞くと、稲盛さんを喜ばせる為に従業員が築地からその朝直送で仕入れたそうで、結構高かったようです。
その社長はニコニコして話していたので暗黙に了解していたのでしょう。
今でもこの昼食会のことは詳細なことまで覚えています。
その時一緒に撮った写真と、このサインと言葉が書かれた本は私の宝物です。
何かあるとこの本を取り上げ読んでいます。
人の採用2
昨日に書きました「人の採用」についての続きです。
「人は採用したけれど、使いこなせられない」について、私の経験も含めて書きます。
まずこれから人を採用する時は「何をさせるのか」「どのような能力を必要とするのか」「考え方が自分に合っているのか」「どんな人を採用したら楽しく能率的に仕事が出来るか」等を具体的に決めておくことです。
そして特に必要なのは「自分の夢を語り、それに賛同してくれる人」を採用することです。
採用する人が社員でなく、例えアルバイト・パートでもそうです。
採用した後も常にコミュニケーションをとります。
それも仕事の上でのコミュニケーションです。
間違いを犯すのはここです。
仕事中、仕事に関係ない他愛も無いことを話題にしてはいけません。
「無駄話も潤滑液だ」と言っていては、仕事の中に遊び心が広がってしまいます。
それをする時は、休み時間や仕事が終わった時。
ONとOFFをはっきりさせることです。
ただ、多くの会社では残念なことに、この社内の「けじめ」を破るのはトップがほとんどです。
自重しなければなりません。
朝礼は毎日します。
例え社員やパートが1人でもします。
昨日の状況を確認し、その日の仕事の目標を指示します。
また、毎日会社で起きたできごとを題材に、自分達がするべきこと、向う方向を示すべきです。
勿論、社長の将来にわたる夢を語ってもいいのです。
そして社員からの共感を得、ベクトルを合わせていくことに力を注ぐべきです。
会社の中が仕事を一辺倒では人間関係がギクシャクすると言われる人がいますが、会社は仕事をするところです。
仲良しクラブではありません。
ただし誤解してはいけないのは、トップたる社長が常に神経をピリピリさせていなければならないということではありません。
優しさは大切です。
仕事がしやすい環境を作り、社員達の健康管理も社長の仕事です。
ただ「優しくする」ことと「甘やかす」とは違います。
ここを外すと絶対ダメです。
社長の心得
「トップたる者、社員に好かれようと思ってはダメ」
社長は孤独で寂しいもの。
それは社長の宿命。
それから逃れ、社員に迎合しようと思った時、社長失格です。
優しさを持ちながらも、会社の向かうべき方向を示し、時には嫌われようと叱咤激励します。
社員に好かれようと思った時、社長たり得ないものだと知ってください。
人の採用
起業している人と接していて気付いたことがあります。
起業家が頑張って仕事を増やし、事業拡大する時、1つの壁にぶち当たるようです。
それは雇用です。
初めから人を採用して起業することもあるでしょうが、私の周りには1人で起業する人が多いです。
仕事が順調に伸び出すと、人手が欲しくなり人を採用します。
社員かアルバイトかパートかですが、どちらにしてもその人達を使って事業を拡大させます。
ここに壁があるのです。
採用した人をどのように教育し、仕事をさせ、成果を上げるか。
多くの若い起業家は人を採用すると、仕事をしてもらおうと思うあまり、優しく接そうとします。
特に自分より年上の女性を採用すると、言いたいことも言えず遠慮して話します。
時として「そんなの出来ません」とか「自主性に任せてください」とか言われると、言い返せないのです。
過去に人の上に立つ経験が無いと、よりその傾向が強くなります。
結局社長が人を使いこなせず、自分1人で仕事を背負ってしまうのです。
その結果、売上は伸びず人件費等経費だけが増える。
事業も行き詰まってしまいます。
若い起業家が落ちいる最初の壁であり、関門です。
その為どうするか。
それについては明日述べます。
血肉化する
昨日のブログでは盛和塾の話しを書きました。
申し訳ありませんが今日も盛和塾の話です。
昨夜勉強会があり、また稲盛さんDVDを見、お話しを聞きました。
その中で稲盛さんは「盛和塾に入って業績が良くならなければ意味が無い」と言っています。
「盛和塾で勉強しているけれどもそれを活かして企業の業績が良くならないのはなぜなのか」
その根本は「フィロソフィ―をいくら知識として持っていても意味がありません。血肉化しなければならない」のです。
「頭の中で知識として持っているだけではフィロシフィというものは使えません」
私もそうですが、本を読んだり人の話を聞いて、それを理解し納得しても自分のものになっていると思っています。
でもそうではいないのです。
実行しなければ自分のものにならないのです。
稲盛さんは「実行して初めてそれが血肉化する」と言うのです。
皆さんは当り前と思われるでしょうが、私はこの稲盛さんの話を聞いて、改めてそれに気付かされました。
稲盛さんの言葉を実行し、血肉化してこなかったのではないか
軽い言葉の理解だけで終わっていたのではないか。
「血肉化する」
改めて挑戦したいと思います。
京都研修旅行
木曜日から日曜日まで京都・奈良に旅行に行っていました。
そのためなかなか書く環境になく、今日は「久しぶりのブログ」という気持です。
旅行のメインは京都山科にある京セラ経営研究所訪問です。
札幌から22名の仲間と訪問し、稲盛和夫さんが過去の社員向けに語った教育DVDを見ました。
今、私達が稲盛さんから聞いている話は、盛和塾を作ってから経営者向けに話してこられたモノです。
今回はそれとは別に、実際に仕事に即した社員に話しているのです。
でもその話は私達経営者達に話している内容と同じです。
ただその表現方法が違うだけです。
私が見たDVDは稲盛さんが48歳と49歳の時のもので、どちらも「主事技術師昇格者教育」での講話です。
それは50歳前の人が話すには内容が濃いのです。
京セラの業績についても触れられています。
48歳の時の講話では「昔は夢のように思っていた1000億円の売上が達成した」と話し、翌年の講話では「1500億円の売り上げ」と言っていたのです。
物凄い急成長の時の元気のいい稲盛さんです。
講話は主事になった人向けにリーダーについて語っています。
「リーダーは完全でなければならない。
パーフェクトな考え・人間性・性格が求められます。
リーダーは私心を捨てて集団に尽くすこと。
集団のために損な役割を引き受ける勇気が必要」
実際に稲盛さん自身がそんな生き方をしていました。
この頃は既に「京セラフィロシフィ」が作られていたようです。
このDVDを見て驚いたのは、この頃と現在私達経営者に話す内容と同じなのです。
ブレていないのです。
この研修の夜はコンパ。
夜の6時から12時まで続きました。
その時も全て経営について語り合います。
年は違いますが、同じ経営者同士、経営上の悩みや問題点を話し、それに対して意見が出る。
経営問答です。
今回も大変中身のある研修旅行でした。
子供の教育
私は時々流れてくるソフトブレーン㈱の宋 文州さんのメールマガジンを読んでいます。
宋さんの意見は的確で納得できることが多いのです。
先日のメールマガジンに子供の教育のことが書かれていました。
宋さんの子供が北京から休みに日本に遊びに来て、帰る時「北京に戻りたくない」と言ったそうです。
息子さんは3年前から北京のインターナショナルスクールに行っています。
なぜ日本の学校に入れなかったかと言うと、宋さんの教育方針に合わないからです。
日本の学校は「優しさ、思いやり、平等、公正等」があり、一般論で言えば中国の学校より日本の学校の方がいいのです。
しかし、宋さんは「日本の学校には競争およびこれに伴う挫折の体験が少なく、当然その挫折から立ち直るための体験や教育もできません。」と書いています。
続けて「私の子供が中国の学校を嫌う理由の一つは先生の乱暴さです。
子供の前で間違った宿題をバリバリ破ったり、勉強できる子とできない子への態度が全然違ったりします。
最初に日本の学校を経験した息子にとってどれもショッキングな話で、おまけに給食が不味いです。」とあります。
「また1年に1度の運動会も競争に意欲満々の上、何らかの項目に勝てそうな生徒を選んで、入場式や試合に参加させますが、意欲がなく弱い子は席に座って応援することになります。
どうしても嫌だったら学校に来なくてもいいと言われる始末です。」
私はこの宋さんのメールマガジンを読んで納得できるものがあります。
団塊の世代の私の小学校の時は人数が多く、全て競争です。
勝ち負けは当り前。
「負けて悔しければ頑張ればいい」ということを学びました。
レイモンド・チャンドラーの小説に「男は強くなければ生きていけない。しかし、優しくなければ生きていく資格がない」というセリフがあります。
最初に強くなければダメなのです。優しさが先ではないのです。
転んで傷つきながら自分で立つ。
それを余計な優しさから抱き起したり、転んでも痛くない床を敷いたりすることの無いように。
私の子供はすでに成人しています。
これからは、かわいい孫に本当の優しさで接したいと思っています。
恐いお祖父ちゃんになるかも?
会社への評価
会社を経営していると業績の浮沈は少なからずどこの会社でも経験しています。
ある事業に投資し、思惑が外れて巨額の借金を背負うこともあります。
取引業者の倒産で代金回収ならず、苦しい資金繰りに悩まされることもあります。
経営者が「それは○○のせいだ!」と大きな声上げても誰も相手にしてくれませんし、助けてくれません。
全て自分の責任です。
それが時として業績が特段に伸び、世間から注目される時、マスコミや評論家の第3者は、「上手く時流に乗りましたね」とか「たまたま○○のお陰で良くなったのですね」と評します。
その経営者そしてその従業員が懸命の努力をして獲得した成果なのにそれを評価する声があまり出ません。
素直に素晴らしいと評価して欲しいと思います。
今朝の新聞に日本航空が2000億円以上の営業利益を達成したと報道されていました。
でも、やはりその要因はリストラであり、更生法適用による制度面での支援効果が大きいと書かれています。
日本航空を稲盛さんが再建を引き受けた時、それに関して色々な本が出ていました。
それは、例えリストラをし再生法定が適用されても再生不可能だと書かれていました。
「JAL再生の嘘」とか「日本航空・復活を問う―元パイロットの懐疑と証言」等の本があります。
1週間前のテレビに稲盛さんが出演した時、司会者から「日本航空が再建出来たのはリストラの効果が大きかったのでしょう」と言われました。
それに対して稲盛さんは「それは可哀そうでしょう。再建が始まる時、皆さんは不可能だと言われていた。それが再建成功したら、リストラのせいだとか、更生法が適用されたからだと言う。それでは苦労し、頑張った従業員があまりにも可哀そうです」とハッキリ言っていました。
先日の盛和塾の勉強会に札幌の日本航空の幹部も参加していました。
彼らは常にLALフィロソフィ―を携帯し何度も何度も読み返しているそうです。
以前と意識が180度変わったと言います。
マンダラ的発想
先日のブログで「土俵の真ん中で相撲をとる」について書きました。
土俵際に追い詰められるような経営をしてはいけないということです。
それとは逆に、仕事の余裕が出くると不安で仕方が無いという若い社長が私の周りにいます。
真面目に仕事に取り組んで行くと、時間に際限なく仕事をするのでしょう。
私は残念ながらそのような経験はなく、取り組めるそのバイタリティを羨ましく思いました。
そのようなバイタリティがあるところは、事業が順調に伸びている会社の社長に共通しています。
しかし時に、その仕事一筋の熱心さの陰で犠牲になっているモノも見受けられます。
そしてそのことに気付かず、取り返しがつかないことも起きます。
大きな病気になったりとか、家庭が崩壊していまったとか、仕事関係以外にネットワークが無いとか起きます。
直線的は発想だと、仕事がうまくいってから、次家庭のこと。その後は健康について考えようと思ってしまいます。
「仕事が上手く行かなければ家庭も上手くいかないし、精神衛生上も良くない」と言います。
そのような脅迫観念に陥ってしまいます。
しかし忙しいという仕事を改めて省みると、無駄な仕事が多いことに気付きます。
今必要ないことをしたり、人に任せれられるモノを抱え込んだりしています。
私はそんな時「ブタのしっぽ」を思います。
「ブタのしっぽ」については以前にも書きましたが、せわしなく動き回っているけど何の役にも立っていない意味です。
「肝心な仕事はなんなのか」を考えてみる。
この歳になって思うのです。
当り前のことですが、人生において大切なのは「仕事」ばかりではありません。
それと同等の重さで「家庭」「健康」「社会的貢献」「人格形成の勉強」等があります。
直線的でなく、マンダラ的発想でそれらをこなしていかなければなりません。
頑張る起業経営者の皆さん。
自分の人生を大切に!
間違って買った本
今朝アレッと思うことがありました。
私は休みの日は朝風呂に入ります。
風呂に入って本を読むのが楽しみです。
1時間弱半身浴で汗をかきながら本を読むのです。
今朝も昨日買った直木賞作家の池井戸氏の本を読んだのですが、5~6ページ読んだところで、「アレッこれ前に読んだことあるぞ」と気付きました。
途端にその本の粗筋が頭に浮かんできました。
そうなるともう読む気がしなくなります。
実はその3日前に買った浅田次郎氏の本も読み出して暫くたってから、「これ前に買った本と同じだ」ということに気付きました。
同じことが続けて2度起きたのです。
少なからずショックでした。
ボケたかなと思ったのですが、読み出してすぐに「読んだことがある」と気付いたことはボケていない証拠。
ボケていたらそのままそのことを気付かず、読み続けていたはずです。
そう自分に納得させています。単なる勘違いなのだと。
それにしても浅田次郎氏の本は最近出版された文庫本なので「既に読んでいることはおかしいな?」と思いました。
本の裏を見ると出版社は文芸春秋で「第1刷2012年1月10日」と書いてあるのです。
ところがその横のページに「2009年1月徳間文庫刊」とあります。
私は以前にこの徳間文庫で読んだのです。
がっかりです。
折角新しい浅田次郎氏の本が読めると楽しみにしていたので、裏切られた気がします。
それにしても同じ本を3年後に別の出版社で出すとは驚きです。
このようなこと当り前なのでしょうか。
余程浅田次郎氏の本が人気があり、このようなことが起きるのでしょうか。
どちらにしても迷惑な話です。
これからは十分注意して買います
土俵の真ん中で相撲をとる
昨夜は盛和塾の勉強会でした。
京セラフィロソフィの中にある「土俵の真ん中で相撲を取る」についてです。
以前に別の勉強会でもこのことを学びました。
しかし参加する人によって話す内容は全く違うものになります。
昨夜の参加者は社長、それも経験豊富な社長たちの話が印象的でした。
「土俵の真ん中で相撲をとる」とは余裕のある仕事・経営をしなければならないということを意味しています。
しかし、どこが土俵際であるのか、もしかしたら真ん中と思っていてもそれが土俵際であったりします。
捉え方がその社長によって違うのです。
時には自分の都合でその土俵が広げてしまうこともあります。
資金繰りも仕事も先を見通して、余裕ある仕事をする社長。
一方、資金繰りはうまく行っているし利益も出ている。
しかし、余裕のある仕事が不安で仕方が無いという社長。
この社長は急上昇をしている会社が巡航高度になり、その速度が遅くなることに不安を覚えます。
また、早く仕事を切り上げることに抵抗があり、終電間際まで仕事をすることを常としています。
この両者の社長のタイプ。
どちらが良いということはないですが、前者は会社の形が出来あがっている2代目社長に多いタイプ。
後者の社長は馬力があり、急成長し続けている会社です。
起業する社長はこのタイプでなけばダメです。
勘違いして前者の様な社長のマネをしては失敗します。
また、「余裕」と「楽する」を勘違いしてもいけません。
どちらにしても「土俵の真ん中で相撲をとる」は仕事を進める上で大切な心構えです。
失業について
先日新聞にILO報告として、「長期失業、先進国で増加」という記事が載っていました。
先進国の失業者のうち失業期間が1年以上の[長期失業者]の割合は37%に達したとあります。
長期失業で求職への意欲を失い、労働市場から完全に退出してしまう人が増えています。
日本の失業率は4.5%、その中でも若年層(15~24歳)における完全失業率が年平均で9.8%に達しています。
学生の中には、景気が良くなれば求人が増え改善されるだろうという期待で、就職浪人をする人もいます。
しかし現状はそれほど楽観視されない景気動向です。
また今後景気に関係なく失業率は増えていくと私は思っています。
文明度が高まり、各分野の技術水準が向上すれば、それに従って失業者は増えていきます。
15年ほど前パソコンが急速に普及しましたが、その前は会社の経理の仕事を6~7人で処理していました。
それがパソコン導入で1人で処理できるようになりました。
営業マンは日報作成や顧客管理表作成などで夜遅くまで仕事をしていましたが、パソコン導入で簡単に出来るようになり生産性が高まりました。
勿論工場の方は技術改善、効率アップを図り、ロボット化により、働く人の数は激減しています。
ホワイトカラー族、ブルーカラー族ともに人は余ってきました。
家庭も私が小さかった頃と今を比べれば、格段に生産性が高くなっています。
専業主婦の数が減ってきています。
技術革新とともに、色々な分野で人が余って来ているのです。
ただ、どうしてもマンパワーが必要な分野があります。
それは身体を使う仕事。
農業、漁業、林業、サービス、介護の仕事です。
しかし、その業種は人気が無く、就職希望者はまだまだ少ないようです。
募集を掛けても人が来てくれないと嘆いている経営者が多いのです。
マスコミが失業問題を取り上げる時、大企業のリストラや臨時雇用問題をクローズアップしています。
しかしこれは1企業の問題ではなく、今後技術革新が進むにつれて、ますます増えていく現象としてとらえなければなりません。
そうでなければ単なる大企業バッシングや感情論で終わってしまいます。
これから今以上に人手が余って来ます。
その中で、自分を生かす選択は3つあります。
1つは自分を高めて「人手」ではなく「人材」に変えていくこと。
もう1つはマンパワーを必要とされている分野に積極的に参加していくこと。
そして自分で好きなことを仕事を見付け起業していくこと。
これからは益々、「人生に前向きな人だけが生き残れる」そんな時代になっていきます。
電気料金
昨日知人が来社され、色々話をしをしました。
気付くと10時半から途中昼食をはさみ2時間半。
政治・経済・宗教まで及びました。
今までその方とはそこまで深く話したことはありませんでした。
大変楽しい時間でした。
その中での話を1つ紹介します。
現在夏場に向けて電力不足が心配されています。
その中でも夏場の電力が一番足りない関西電力の対応が批判されています。
当初16.5%供給が不足すると言われたのが、15%に訂正されたりして、不信感が募っています。
原発問題、そして電気料金の値上等で、電力会社の対応不足に批判が集中しています。
しかし考えてみると、家庭用料金は電気事業法に基づいて経済産業大臣の認可制になっています。
監督官庁は本来、料金申請がある時は専門的知識を持ってその申請を審査し、適正であるか判断することのできる専門家集団のはずです。
しかしここへきて、経済産業省の対応を見ると、電力会社の収支内容の把握、需給状況の根拠付けは一切出来ず、
監督官庁としての役目も責任も放棄しているのがはっきりしてきました。
全て電力会社任せです。
良く言われるように、電力会社とは「ズブズブ」の、もたれ合い関係だったのです。
また電力関連の学者や専門家といわれる人も知識不足勉強不足です。
もしもそのような人達がいれば、第三者委員会の様なものを立上げ、電力会社に対して対抗出来ているはずです。
今、マスコミは電力会社批判に集中しています。
しかし本来は上手く責任逃れしている経済産業省の、今までの認可行政を明らかにする方が本筋だと思います。
ここで批判を受けることを覚悟して書きます。
電力料金値上げは国民にとっては大変です。
一方電力会社も電力を上げなければ経営が成り立ちません。
電力会社は公共的事業ではありますが、民間企業です。
民間企業が赤字を避け利益を出すことは当り前のこと。
そのことを批判しては資本主義は成り立ちません。
値上げ申請の内容が正当かどうかを国民に知らしめるのは電力会社の責任ではありません。
認可する経済産業省の責任です。
「地震・津波・電発の爆発・放射能⇒電力会社は悪者」になっています。
私は殿様商売をしてきた電力会社は好きではありません。
でもあまりにも感情的なマスコミの報道も扇動的的でおかしいです。
今年の夏は暑くなりそうな予報です。
本州の皆さん! 夏の間涼しい北海道に来ませんか?
仕事もはかどりますし、北海道の経済も活性化するかもしれません。
日本の個人金融資産
昨日のテレビで、フランスの大統領選挙、ギリシャの総選挙の結果がEUの経済に大きな影響を与え、また混沌とした状態なることが懸念されると報道しています。
そして、それの影響で日本の株がまた下がり、円も上がり傾向です。
普通は経済が悪く、貿易収支が赤字、デフレ不景気であればその国の株も通貨も下がるはずです。
ところが日本の円だけが高いままというのは不思議で異常なこと。
「異常なことは長く続かない」という言葉があります。
今の円高期間は少し長いですが・・・
ただ、このような異常な状態は必ず修正されます。
多くの経済評論家は、1~2年位の間に日本の経済は大変革が起きると予想しています。
そしてそれに備えてかか、富裕層の資産の海外移し替えが多くなっているそうです。
それが急激に進行すると銀行の預金の減少⇒国債購入資金減少になり、日本の国債への評価へも影響されます。
そんな動きに対しての牽制でしょうか、これに関する税制が出来ました。
2012年度税制改正で、海外資産の課税が強化され、違反者は懲役刑まであります。
海外に所有する総資産が5千万円(預金、株式、不動産など)を超える個人を対象としており、その資産を把握し、課税するのが目的です。
その背景には、日本人の海外資産が増え、申告漏れが増加していることが理由です。
違反した場合は1年以下の懲役です。
結構厳しい法律です。
富裕層でない私達には関係ないのですが、金融資産の海外への移し替えは日本経済への影響が大きいと思います。
日本の個人金融資産は、1400兆円と言われています。
しかし船井財産コンサルタンツの資料によれば、これには個人事業主の事業性資金も含まれているとして、個人の資産という概念から、差し引いて考えるべきだと指摘しています。
こうした見方では、個人金融資産について2009年の全国消費実態調査結果を基に試算すると、それは672兆円になります。
このうち負債は206億円であり、これを差し引いた正味金融資産は466兆円だとしています。
この金融資産が海外に移っているのです
日本の国債が近い内に1000兆円を超す勢いです。
その時言われるのは、「1400兆円の個人金融資産があるから大丈夫だ」です。
船井財産コンサルタンツの資料を見ると、それの根拠もあやふやになります。
以前、外国に金融機関が豊富な日本の金融資産を狙っていると言われたことがありました。
まさに今それが現実になっているように思われます。
不思議なキリスト教
昨日でゴールデンウイークも終りました。
札幌はあいにく雨続きで外出がままなりませんでした。
でもお陰で本が読めました。
読みかけの本も入れて6冊。
それなりに充実した休みでした。
その中でいつもは読まない宗教的な本も読みました。
「ふしぎなキリスト教」という題名で、副題として「日本人の神様とGODは何が違うか?」となっています。
この副題に引かれて読みました。
キリスト教とユダヤ教のつながり、それを意識して生まれたイスラム教が興味深く書かれています。
キリスト教もユダヤ教もほとんど同じで、違うのはイエス・キリストがいるかどうかだと著者は書いています。
そして副題の「日本の神様とGODは何が違うのか」についてです。
ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も1神教です。
神様は1つしか存在しないという考えです。
一方、日本では神様は沢山います。
「八百万の神」といわれるくらいいます。
日本人からすれば、神様が沢山いてなぜいけないのかと思います。
元々原始宗教は神様が多かったのです。
この本の中では、日本人にとって神様は仲間みたいのものと解説しています。
その付き合い方の根本は仲良くすること。
大勢と仲良くすると自分の支えになり、ネットワークが出来ます。
この考えは日本人が社会で生きていく基本になります。
そうすると日本人から言うと1神教が不思議になります。
ユダヤ教などの1神教は、人はGODが創造したもので、その関係は主人と奴隷の関係。
GODは人間と血がつながらない全知全能で絶対的存在なのです。
だからGODは怖い存在で、怒られると滅ぼされてしまうこともあると考えるのです。
GODを信じるのは安全保障のためです。
GODが素晴らしいことを言っているから信じるのではなく、自分達の安全のために信じるという考え方です。
この本はその他に「イエスは神なのか人なのか」とか[精霊とは何か]等興味深いことが書かれています。
宗教本というより、「宗教解説本」という位置付けでしょうか。
15万部売れているといわれている本です。
宗教が読みやすく書かれています。
ご興味がありましたらどうぞお読みください。
自殺について
内閣府から自殺に関する資料が公表されました。
「自殺に対する成人の意識調査」です。
それによると4人に1人は自殺を考えたことがあるということです。
特に20代が一番高く28.4%いるそうです。
実際に自殺者も増加していて、日本では8年間連続して3万人を超えています。
原因を雇用問題などの社会環境の悪化と言う人もいます。
それもあるでしょうがそればかりではないと思います。
私が若い時には哲学的な自殺という風潮がありました。
そして実際に自殺について考えた人は多かったように思います。
どこまで真剣に考えるかは別に、大人になる過渡期にぶつかる成長へのステップだったのでしょう。
だからと言って自殺を勧めているわけではもちろんありません。
ただ、「生と死」を考える時期は成長段階にはあるはずです。
確かに生活に悩んで苦しんで、結果自殺を選ぶ人はいます。
それを防ぐための方策の色々考えられています。
防ぐために私が一番いいと思うのは、幼い頃に地獄について教えることです。
強烈な絵を見せられ、語って聞かされると、夜が怖くなるくらいショックを受けます。
「悪いことをせず、いいことをしなさい。そうしないと地獄に落ちるぞ!」
「自殺すると地獄に落ちるんだぞ!」と教えるとその怖さを一生忘れません。
私も小学生低学年の頃、祖父から地獄の絵を見せられ、語って聞かされたことしっかり覚えています。
それは大人になっても理屈抜きで恐いモノだと思っています。
それが怖くて、たとえ自殺を考えても実際には出来なくなるはずです。
自殺すると、今以上に苦しく辛い地獄に行ってしまうかもしれない。
そう思うと自殺の抑止力になります。
「トラウマになるから子供の精神上良くない」という人がいるかもしれませんが、それ位の強烈な思いを感じさせないと後々後悔することになります。
最近「絵本地獄」という本が売れているそうです。
小さい子さんがいるお母さんはぜひ読んで語って上げて下さい。
それも大事な子供を守ることだと思います。
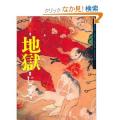
北海道の春
今日はゴールデンウイークの中日。
そして1日です。
いつものように神宮・神社にお参りに行って来ました。
朝6時30分頃家を出、琴似神社、北海神宮に参拝して来ました。
今朝は春の陽気ですが、日中は25度近くになり、天気予想では7月中旬の気温だそうです。
1カ月前の4月1日はまだ雪があり、寒かったのを思えています。
琴似神社には「さつき」か「つつじ」か分かりませんが、花がもう咲いています。
梅も桜もまだなのにです。
本州では3月に梅、4月に桜、5月に五月「さつき」や「つつじ」の順に花が咲きます。
北海道は5月に咲く花が、梅・桜より先に咲きます。
と言うよりこの1~2週間の間に一斉に花々が咲く勢いです。
これからが北海道が一番花に囲まれ、輝く季節なのかもしれません。
ついこの間まで「もう北海道は嫌だ」と言っていたのが、「やっぱり北海道はいいね」と、心が高揚する季節です。
今は朝の8時。
今日も気持ち良く仕事を始めます!
ゴールデンウイーク
今日からゴールデンウイークが始まります。
私にとって休みが多いと正直困ってしまいます。
するべき仕事がまるまる1週間延びてしまいます。
相手があることですから仕方がありません。
そこでこれから「連休中何をしようか」を考えることにします。
1つは先日買ったカメラの操作を熟知すること。
2つ目はいつもと違う毛色の本を読むこと。
3つ目は新しい曲をしっかり吹けるようになること。
今のところこれ位しか考えつきません。
そう言えば今日これから妻と娘3人で札幌近郊の藻岩山に登ります。
登るといっても麓まで車で行き、ロープウエーで山頂まで。
全然運動になりません。
目的は頂上にオープンしたレストランで食事をすることです。
見晴らしがいいということですので楽しみです。
その娘も来月早々イギリスに旅経ちます。
暫く会えなくなるので、いい思い出を作ろうと思います。
また夫婦2人の生活になります。
やはりこの連休は娘中心になりそうです。
これからの日本
昨日神田昌典さんの本を読みました。
ご存じの方も多いと思いますが、神田さんは経営コンサルタントとして多くの本を書き、コンサルタントとしても活躍している人です。
久しぶりにその神田さんが「2022-これから10年活躍できる人の条件」という題名の本を出されました。
その本には、神田さんは暫く癌と闘って生還したこと、そしてその後それまでの考え方見方が変わったことが書かれています。
日本はこれから数年のうちに、明治維新・敗戦と同じような、またはそれ以上の変革が起きると予想しています。
そしてその中で希望を捨てず自己変革をして生き抜くことが書かれています。
ご興味があれば読んで見てください。
その中で私が興味を持ったことがありました。
人口動態に基づく経済予測で名高いアメリカエコノミストであるハリー・S・デント氏の予想が紹介されていました。
そのデント氏の予測を神田氏が単純化して「景気は46歳~50歳の人口の増減によって決まる」と言っています。
この年代は人生で最もお金を使う年代であり、節約したくても出費を抑えられない。
子供は大きくなり、住居費、教育費をはじめとして様々な費用が一番かかる世代です。
どの国でもこの世代が多くなる場合、景気はよくなり、少なくなる時は景気が悪くなる。
たいへんシンプルな説ですが、過去に照らし合わせてみると無視できない精度があります。
デント氏はこれからの日本を予想しています。
日本がこれから若手の人口が少なくなります。
団塊ジュニアが40歳~50歳の層を過ぎてしまう2020年以降の日本の経済について「国も人もいずれは死んでしまう」と言っています。
最近はこの神田さんばかりでなく大変革が起きると予想する本が多く出版されています。
読んで単に付和雷同することは危険です。
それでも真剣にこれからの動きを読み解く材料となるでしょう。
もしもよければ神田さんのこの本をゴールデンウイークに読んでみませんか?
特に若い人にはいいかもしれません。
社会保障費削減
今、消費税増税論議が盛んです。
政府が言っている消費税増税の話は社会保障費と一体改革という言葉が伴います。
この意味を間違えて理解している人はいないでしょか?
先日テレビに野田総理が出て、若い人達との討論会がありました。
その中で総理は「増税したお金はすべて社会保障費に回します」と言っていました。
でも、社会保障との一体改革とはそのことを意味しているのではありません。
あれだけを見ていると「社会保障費が足りないから増税で賄う」というふうに取られてしまいます。
本来は増税をし、同時に社会保障費も見直し、それを削減し、日本の財政改革をするという意味です。
消費税増税があまりにもクローズアップされて、社会保障費削減問題が表に出て来ていません。
政治家は、この社会保障費削減にふれた途端、次期選挙で落選するということを恐れているのでしょう。
論議を後回しにしています。
しかし、もしも増税が決まった後に、「それでは次に社会保障費を削減します」と言われると、国民は増税以上の反発をします。
することが後先になっています。
日本の今年度の予算96兆円。
それに対し、税収は42兆円程度。
足りない54兆円は国債という借金です。
消費税を5%アップさせても10兆円程度です。
まだまだ足りません。
法人税は現在10兆円弱。
これを倍にしても10兆円増えるだけ。
しかし現在、法人税30%の他に、地方法人特別税を含めると40%の負担になる会社は、増税にした途端海外に逃げていきます。
また、経済を復興させ税収を増やそうとしても難しいです。
あのバブルの時でさえ税収は70兆円に届いていません。
そして、その時の税率は今より高く、所得税最高60%(今40%)、法人税50%(今30%)でした。
その高い税率があり、バブルの時でさえ70兆円に届いていないのです。
将来バブルの時と同じことが起きるとは思えません。
財政改善には支出を下げることしかありません。
日本の社会保障費は29兆円ほどになり、税収の70%以上を占めています。
ただ、この社会保障費を見直すとなると、「弱者いじめ」「格差拡大」等の批判を受けます。
しかし、どのようにしても税収の7割以上も占めている社会保障費を見直さないと日本は潰れてしまいます。
総論では賛成と言う人がいても、自分のこととなると反対になります。
難しいことですが、これから日本の大人1人1人が現状を認識して覚悟をしていかなければ、将来今の子供達から馬鹿にされます。
「こんな日本に誰がした!」と言われない行動が大人に求められています。
金融政策決定会合
今週はチョット気になることがあります。
北朝鮮の軍創建80周年が今日で、その動向が心配されることもあります。
それとは別に、景気動向の転換期になりそうなことが起きそうです。
先日買った雑誌「エコノミスト」に「日銀と円安」という特集が載っていました。
それには、「4月24日~25日に開かれるアメリカの連邦公開市場委員会で追加緩和観測が退けば、相対的に日本の金融緩和姿勢がクローズアップされる。そうすれば円買いの動きは抑制され、円安トレンドに戻る」と書かれています。
日銀の金融政策決定会合が今週の27日に開かれます。
その時、「追加緩和策はある」と多くのエコノミストは予想しています。
今の1ドル80円は異常に高いと言われています。
もしも円安トレンドに向かうとすれば、経済的に大きな変化が起きます。
経済活性には良い動きです。
しかし、物価は上がります。
デフレだからなんとか生活出来ていたのが、一気に苦しくなります。
輸入品が高くなり、特に石油、LPGの価格が上がり、電気料金は急激に上がるでしょう。
円安により貿易収支が一時的に悪化し、経常収支まで赤字になることも考えられます。
今の消費税増税問題にも影響を及ぼすかもしれません。
それでも日本の景気回復の転換点になるかもしれません
27日の日銀の金融政策決定会合の内容に注目したいと思います。
「士業」について
大分前からですが、テレビを見ても電車に乗っても弁護士事務所の宣伝が多くなったように思います。
特に最近は目立ちます。
以前は弁護士と言えば犯罪を起こした時とか、会社の仕事上必要な顧問弁護士とか、一般庶民とは遠い存在でした。
これほど個人的に必要とされるようになったのは、やはりサラ金問題が切っ掛けだったのでしょう。
あまりにもの暴利を貪ってきたサラ金業者を悪者に、それに対抗する正義の味方的存在でした。
また、その時期と、弁護士を大量に輩出しようとして新司法試験制度が始まった時期と重なります。
しかし今は、弁護士飽和状態とも言われ、他の弁護士事務所に間借りしている「イソ弁」と言われる弁護士も増えています。
新規事業をしようと起業を志す人の中には何か資格を得ようと、試験を受ける人が多いと思います。
司法試験はその中でもトップレベルの難しい試験です。
8000時間以上勉強しなければ合格しないと言われています。
1日8時間勉強して1000日、3年弱かかります。
勿論、勉強してからといって必ず受かるわけではありません。
司法書士試験は4000時間、税理士試験は5000時間勉強しなければならないとされています。
また例え、その試験に受かり「士業」に就いたとして、すぐ仕事があるわけではありません。
既にいる数多くのライバルを押しのけて、自分の仕事を獲得していかなければ生き残れません。
「士業」についてもやはり競争は激しいのです。
せめて弁護士業界のように、サラ金問題が起き、新しい仕事先が生まれるのなら、仕事の範囲が増えるわけですから、新弁護士も仕事も生まれることになります。
しかしそれ以外の「士業」は大変です。
起業を志す時陥りやすのは、安易に「何かに頼ろうとする気持ち」
「資格を取ればなんとかなる」「フランチャイズチェーンに入れば商売がうまくいく」という気持ちはタブーです。
資格試験を受けようとする人の中に、時々そのような人がいます。
起業の時は、挑戦心と、1人で生き抜く力。
やはりその人の志しかないのでしょう。
「士業」についても、従来がら顧客とされる人達以外の新しい分野を探し出して仕事を作る。
これから世の中が大きく変化していく時を迎えると思います。
その時こそ、その変化に注目していくことです。
悲観思考と楽観思考
人の思考に悲観的思考と楽観的思考があります。
どちらかというと悲観的思考をする人が多いのではないでしょうか。
日本は長い間デフレ、不況が続き、人の心もより一層悲観的思考が占めるようになっています。
昨年の大震災や災害が起きるともっとその気持がより強くなります。
今日のニュース番組で、太陽の活動が停滞期に入り、地球は温暖化でなく冷たくなり、ミニ氷河期になると報道されていました。
300年前にも同様な状況になり、その時大飢饉が起きたそうです。
また最近、日本中の各地で大地震がいつ起きてもおかしくないという情報が流され、また富士山がここ数年で大爆発を起こし、首都圏が活動停滞するという話もあります。
数年前はそんな話は週刊誌で興味本位に掲載されていた、信憑性が疑われる程度の情報でした。
ところが昨年大震災が起きてから、それらのことがテレビや新聞で堂々と取り上がられ、将来の不安が益々高まっていきています。
また、日本の経済ももうそろそろ国債暴落、ハイパーインフレの恐れがあると言われています。
ここまで悲観的要素が溢れてくると、悲観的にならざるを得なくなってきます。
これに対し自分1人の力はあまりにも非力に見えてしまいます。
だからと言って単にそれらのことに目をつぶり、楽観的に生きればいいかというとそうでもありません。
今必要なのは、悲観的のことに備えをしつつ、その変化を受け止める柔軟な発想を作り上げていくこと。
個人が出来ることはそれしかないのです。
万が一、日本のどこかでまた大震災が起きたら、日本は大変なことになります。
精神的にも経済的にも耐えきれないほどの痛手を負うことになるかもしれません。
その時はもはや、国や自治体に頼ることは出来ません。
助けてくれません。
自分の力で生き抜くり力が求められます。
大げさに言えば、これからは益々個々の人間の力が試される時になりそうです。
私達が今必要なのは「悲観的に備え、楽観的な発想をする力」ではないでしょうか。
今日は自戒を込めて書きました。
「デジカメ操作術」講習会
昨夜は私の事務所で「デジカメ操作術」の講習を開きました。
定員一杯の20名近くの人が集まりました。
当初は10名も集まるかなと思ったので、正直驚きました。
これほどの人が集まるのは「デジカメは持って使っているけど、ついているその機能はよく知らない」と実感している人が多いという証ではないでしょうか。
私のその1人です。
また参加者の中にはインターネット上で商品を紹介する時、写真を取るけど「イマイチ」と思い参加した人もいました。
講師は溝口さんというプロのカメラマンです。
講座は最初溝口さんがデジカメの機能などを説明し、その後質問形式で話を進めました。
また溝口さんの写真を見ながら、撮る角度の重要さも教えていただきました。
角度1つで全然違うのです。
商品を撮る、人物を撮る、花を撮る、夜景を撮る、そのポイントも教えていただき、もの覚えが悪い私も、何となくわかりました。
実際は何枚も何枚も写真を撮り、時にはオートでなくマニュアルで撮ることで習得していくのだということも教わりました。
今後何回かこのデジカメの講習会を開きます。
これから季節も良くなるので、一度皆で写真を撮りに出かけたいと思います。
そしてそれをプロジェクターなどで映し、溝口さんから講評をいただくという進め方も考えています。
今日は札幌も天気が良さそうなので、カメラをぶら下げて出かける予定です。
自らを追い込むⅡ
昨夜は盛和塾の勉強会がありました。
京セラフィロソフィの「自らを追い込む」についてです。
同じこの項目についての勉強は以前もここで紹介しました。
今回は以前の参加メンバーと違いほとんどが経営者です。
改めて別の見方、考え方で勉強することが出来ました。
「自ら追い込む」と「追い込まれる」とは違います。
今回の勉強会でも、始めは混同していました。
「追い込まれる」というのは受け身で、それを解決するにはあらかじめ段取りをするなどで対処できます。
毎日の仕事上ではこのような状態は良く起きます。
「自ら追い込む」とは自ら高い目的に向かって行かざるを得ない状態に自分を置くことです。
そうすることでその目標に向かって必死にになって実行しなければならなくなります。
やらざるを得ない、逃げ道のない状況の中で仕事をするうち、自分でも驚くほどの成果が生まれる。
それを「自ら追い込む」ということと稲盛さんは言っています。
会社の目的である経営理念、ビジョンという頂上に向かって、垂直登攀をする。
無理と思われることに挑戦する。
社長のその姿を見て部下がついて来る。
そのことが社長の経営に対するあるべき姿勢なのでしょう。
成長する会社
昨日は同系会社の株主総会がありました。
株主総会と言っても、同族ですので出席者は10名以下です。
その会社は従兄弟が社長をしていますが、先期は売上100億円を突破しました。
その社長が以前から目標にしていた数字でしたので喜んでいます。
営業利益も利益率は10%とはいきませんが、それなりに出ています。
その成長の要因は何かというと「留(とど)まらない」ことです。
彼は常に新しい何かを求め、それに挑戦します。
挑戦して、うまくいかなくても頑張ります。
それでも見通しが立たないと思えば、思いきって止めます。
事業を止めるという行為は、作る時以上にエネルギーを使います。
それでも色々挑戦して、事業を拡大してきました。
成長しない会社の多くは事業を止める時の不安があるために、挑戦するのに躊躇します。
いくらいいことを考えても、始めなければただゼロです。
そして誰がが先にしたのを見て、「本当は俺も考えていたのだけれど」と言ってもそれは犬の遠吠えです。
この社長の仕事の進め方は私とは若干違います。
でも会社を発展させ、従業員を幸せにするという考え方は同じ。
やり方は違っても同じ頂きを目指すのであればいいのです。
この会社がこれからどう変化していくのか楽しみです。
勉強しない学生
昨日来社された方とお話したことです。
その方は大学で就職カウンセラーの仕事をしています。
「最近の学生は勉強しないですね。それより常識的なことが分かっていない。」と言うのです。
例えば2万円の洋服が2割引きになっているという話している時、その2割引きはいくらになるかが分からない。
%の計算が出来ないのです。
大学で仕事をしているけれど、あまりにも大学生の程度が低くなったと嘆いていました。
誰でも大学行くことが果たしていいことなのか。
誰でも平等に大学に行けることが、その本人にとってもいいことなのか。
今朝の日経の一面に「勉強しない学生」という内容の記事が載っていました。
日米の大学生の学習時間がグラフで示されています。
1週間当たり16時間以上勉強する学生の割合は、アメリカは4割ほどですが日本は1割以下。
逆に1時間から5時間勉強する学生はアメリカが1割強ですが、日本は5割以上。
全く勉強しない学生はアメリカは0に対し、日本は1割います。
以前にもブログで書きましたが、40年ほど前、私はアメリカの大学に行っていたが、その大学生の勉強時間は生半可のものでありませんでした。
授業も2回欠席すると、落第。
テストもある点数以上取らないと落第。
ですから毎日勉強をしっかりしています。
(私はその時正式な学生でなかったのでそんなに勉強しませんでした。念のため)
その状況を見て、日本とアメリカの差は益々つくなと思ったものでした。
今は当時以上の違いかもしれません。
昨日の話でもう1つ。
前の話に繋がることですがが、今の日本人の指向は「面白い」ものばかりを求めているのではないかということです。
「楽しい」というならいいのです。
ダメなのは、ただ「面白い」ものです。
「楽しい」という言葉は、何かを努力した結果でてくる言葉です。
それは次に繋がり、モチベーションを高めることになります。
しかし「面白い」はただそれだけの感情。何も残りません。
人間の最低の欲求を満たすだけです。
テレビを見てもグルメ番組、お笑い番組、報道番組の面白いネタ探し、そしてセンセーションで大衆を煽る報道。
それらはマズローの法則の最低の「生理的欲求」を満たすだけ。
それ以上にならない日本人。それを助長するマスコミ。
もうそろそろ、その状況から抜け出さなければならないとの思いです。
昨日の2人の話の結論は、「このままでは駄目だ、変えなければならない」と思う人が、地道に周りの人1人1人に、語っていくことしかないのだ、ということでした。
昼寝の効用
毎日仕事をして、特に内勤の仕事の場合、午後は眠たくなります。
皆さんも経験あることでしょう。
眠たいのに無理しても仕事の効率は上がりません。
私の場合これはテキメンです。
書類を読んでも集中できず、本を読んでは瞼が重くなり、何をしても中途半端。
そこで多くの方が昼寝を勧めます。
私も出来るだけ昼寝をします。
私の場合、会社から自宅まで徒歩10分という距離ですので、ほぼ毎日自宅で昼食を取ります。
本当に恵まれた仕事環境です。
なので、昼寝が十分できます。
時間は10分から15分程度。
これ以上寝ると寝起きが悪いです。
私が以前、東京のホテル支配人時代も昼寝はしました。
その時は自宅には帰れませんので、昼食後ホテルの邪魔にならない片隅に椅子を置いて10分ほど寝ました。
昼寝時間は長くなると、かえって体がだるくなます
また夜、目がさえ、夜更かしの原因になります。
早く寝て、早く起きる。
早く起きた分だけ、午後は15分位昼寝をする。
そうすると早寝・早起きの習慣が付きやすくなりますよ。
手抜き仕事
今から何年か前に、建築物の耐震問題が起きました。
当時は設計の段階で不正が行われ 建て直しなどが行われました。
建築に関しての不正は偽装設計ばかりでなく、工事現場でも起きます。
元請けのゼネコンから不当に安い価格で請負う工事業者の中には手抜きをする会社もあります。
材料等はゼネコン指定があり、変えることは出来ませんが、工事人数を減らすことをします。
鉄筋工事では、鉄筋同士を番線と呼ばれる針金で結びます。
10カ所結ばなければならないところを、7本で済ましてしまいます。
コンクリートを型枠に流し込む時も、手を抜きジャンカ(空洞の様なもの)を作ってしまいます。
私の家の隣では昨年11月からアパート工事が始まりました。
今年の3月に合わせて完成するつもりだったのでしょうが、2月に工事がストップ。
「なぜ?」と思っていたのですが、先月の終り頃、工事会社の人が来ました。
折角、内装まで進んだ建物ですが、壊して建て直しするそうです。
理由を聞くと、1階のコンクリート部分の強度が設計の半分しかなく、震度6で倒壊するという検査報告があったとのこと。
確かに、その建物を良く見てみると、コンクリート部分にはジャンカはあるし、異物も挟まった状態です。
そして特にダメだったのはコンクリートそのモノです。
私は隣ですので、工事をしているのを毎日興味深く見ていました。
その1階部分のコンクリートを流し込む時、「アレッ!」と思ったのです。
12月末の雪の降る、気温零度以下の時にその工事をしたのです。
そして養生もしないでそのまま年を越しました。
私も以前は住宅会社の帳場として現場で働いていましたので分かりますが、コンクリートが固まる時、気温が低いと中で水分が凍上し、コンクリートがボロボロになってしまいます。
冬場の工事では事前に足場を組んでブルーシートで囲みます。
ジェットヒーターなどを使って、その中にあるコンクリートが零度以下にならないようにします。
北海道で冬に家を建てる時の常識です。
ところがこのアパートはそれをしない。
私がそれを見た時、「今はコンクリートの性能が良くなって、養生などしなくてもいいのかな?」と思っていました。
でもやっぱりダメだったのです。
そのことをたまたま私の家に来た施主会社の人に言ったところ、建築検査会社依頼をし調査したのです。
結果、先ほどのように耐震性がないことが分かりました。
今回はたまたま施主が分かって調査を入れましたが、普段はそんなことしません。
今建物を壊しています。
勿体ないです。何千万ものの損失です。
今はデフレ時代。
建築ばかりでなく、色々ところでコスト削減という名目で手抜きが起きていると思います。
考えなければならないことは、自分の財産を守る為にも、買う時は「信用」というものが重視することです。
生産者側も将来、劣悪品の代名詞がデフレ時代に作られた製品「デフレ製品」というレッテルが張られないようにしなければなりません。
また、こんな時代だからこそ、信用を重視する会社が将来に向かって生き残れると信じています。
SOHOリレーフォーラムin札幌
先週末に「SOHOリレーフォーラムin札幌」の大筋が決まりました。
このフォーラムは8年ほど前に東京三鷹市から始まり、今回札幌での開催が10回目になます。
このフォーラムは起業を志す人、そして起業したSOHO事業者を支援することを目的としています。
そして、起業を志すひと・SOUO事業者、そしてそれを支援する人達が連携することも目指します。
フォーラム後も支援者とのつながりがによって、SOHO事業者の事業が成功することも願っています。
このフォーラムは6月15日(金曜日)13時から始まります。
主催は日本政策金融公庫と札幌市共同参画センターの共催。
後援は札幌市、札幌商工会議所、札幌信用金庫、北海道新聞社、北海道セールスレップ協同組合、それと私のレンタルオフィスの札幌オフィスプレイスです。
第1部は、講演者は東京三鷹で起業者やSOHO事業者を支援している、「SOHO CITYみたかフォーラム」理事長の河瀬謙一さんにお願いします。
第2部は、既に起業しSOHO事業者になっている3名の人に起業体験発表をしていただきます。
その1人は、今札幌を中心にバルーンアーリストとして活躍している「風船の魔法使いエリサ」さん、佐佐木絵里沙さんもいます。
このフォーラムは勿論参加費は無料です。
定員は100名で、受付は先着順になります。
今月中にチラシを作り、5月から申込受付を始めます。
受付開始頃のまたこのブログでお知らせします。
このフォーラムの後は参加希望者だけで「ワンコイン交流会」をします。
会費500円で、コーヒーやドーナッツを食べながら起業を志す人、SOHO事業者との交流を図ります。
これから告知活動で忙しくなりそうです。
そして今からお願い致します。
6月15日の午後は時間を空けておいてください。
多くの方のご参加をお待ちしています。
最近の料理
昨夜ある会合がありホテルで食事をしていました。
その時に料理の話がでました。
最近の料理を見ると、日本料理とかフランス料理、イタリア料理等の範ちゅうから外れた料理が多くなって来たように思います。
世界中の料理が日本に入ってきて、日本人はそれを積極的に取り入れたてきたました。
もしかしたら日本人ほど各国の料理を抵抗なく食べる国民はいないのではないでしょうか?
日本に長く住んでいた中国の知人と以前食事の話をした時、中国人は家庭ではほとんど中華料理ばかりを食べていると聞きました。
「今日は中華料理、明日はフランス料理、その次はイタリア料理・メキシコ料理・タイ料理・インド料理」と食べ歩かないそうです。
日本人が各国の食べ物を好きなように食べることが出来るのは日本が経済的に豊かだという証拠でもあります。
その日本人の中に、大分以前から「マヨラー」と言われる人が出て来ました。
何でもマヨネーズを掛けて食べます。
また、普通辛くて食べれない料理も好んで食べる人がいます。
彼らは何でも好きなように食べているうちに、舌が麻痺してきたのではないかと疑ってしまいます。
日本人が本来持っていた微妙味付けの料理に対する繊細な味覚が失われてきたように思います。
「冷たいそうめんを喉ごしで食べる」「微かな柚子の香りのする薄味の煮物」等、その良さが分からなくなってきたようです。
折角のそのような料理に、マヨネーズを掛けたり、タバスコを入れたりしてしまう人がいます。
「何でも有り」の料理の世界です。
味覚がおかしくなっているのではないでしょうか。
このようなことの原因は、子供の頃から「食育」がしっかり成されてこなかったからでしょう。
カツオ、昆布、煮干しなどで出汁を取り、本来ある日本の味付けを家庭で口にしてこなかった子供が多かったのではないでしょか。
料理を作る側も食べる側も、基本の味を知る舌作りが大切だと私は思っています。
微妙な味付けで、素材本来が持っている味を味合う日本料理。
もっと見直されていいはずです。
今晩は美味しい煮物やお浸しを肴に日本酒を飲むのもいいかも・・・
自分へのご褒美
テレビで若い女性が「自分へのご褒美」ということで、洋服を買ったり、美味しいものを食べに行っているのを見ました。
頑張った自分へ、自分でねぎらうこと。
ご褒美はやはりモノが多いです。
美味い酒を飲む為に、その1日所懸命仕事する。
勉強して合格すれば、自分に高価な時計を買う。
以前読んだイザヤ・ベンダサンという人が書いた「日本人とユダヤ人」に同じようなことが書いてありました。
私の記憶では「ユダヤ人は週末に恋人と一緒に美味しいレストランで食事をすることを予定に入れ、それに向かって1週間、懸命に仕事をする」と書いてありました。
ただこの「自分にご褒美を出す」がともすれば、ついつい自分に甘くなり、大したことないことでもすぐ褒美を出すことがあります。
これでは逆効果でしょう。
また、具体的な楽しみを作り、自分の欲を原動力にして頑張ること、これは我欲です。
我欲は即効性がありますが、本当の喜びでには結びつかないはずです。
刹那的に感じることもあります。
本当の喜びは自己満足より、他の人から受ける評価でしょう。
本当の自分へのご褒美は自分で自分を褒めるより、他の人から褒められる方が嬉しいものです。
マズローの法則の4段階目の「承認の欲求」がこれに当たります。
稲盛和夫さんが言う、人のために行うという「利他の心」
これを追求することは、それの見返りが無くても、結局「自分へのご褒美」になるのでしょう。
最終的にはこれに行きつくと思います。
日本の自殺
以前にも書いたかもしれませんが、今年の文芸春秋の3月号に「予言の書『日本の自殺』再考」という論文が掲載されました。
これは37年前の1975年に同じ文芸春秋に掲載されたものです。
当時、高度経済成長を遂げ、繁栄を謳歌していた日本に対し、内部崩壊の危機を警鐘する論文でした。
3月号はその再度の掲載です。
その論文には日本そのものが自己崩壊の道を進んで行くといく内容が書かれています。
古代ギリシャやローマ帝国がたどった大衆迎合の政治と同じ道を進んでいると書いています。
内部崩壊を通じて日本が自殺していくのです。
「パン」と「サーカス」がはびこった古代国家と同じ道をたどる。
古代ギリシャやローマ帝国の末期では、大衆は大土地所有者や政治家に「パン」を求めました。
彼らは大衆の人気を得る為に無料で「パン」を与えました。
働かず「パン」が保障された大衆は、時間を持てあまし、今度は娯楽を求め、そこに「サーカス」が登場します。
大衆はドンドン際限なく「パン」と「サーカス」を求めていき、ついに経済は破綻し文明も崩壊して行きました。
日本も同じような道を進むのでないかと危惧し、37年前に「日本の自殺」という論文が書いているのです。
今の日本では、37年前に予言されたその論文と同じようなことが起きています。
昨日「新・日本の自殺」という論文が掲載されている文芸春秋5月号が発売されました。
そこには「シュミレーション国家破綻」という副題がついています。
消費税増税導入が失敗し野田政権が瓦解、日本の国債が暴落し、年金、雇用、給料等全てが破綻していく姿がえがかれています。
6月末までに消費税増税法案が成立しなければ、日本の財政再建の能力はないとみなされ、日本のソブリン格付けを引き下げるという可能性が書かれています。
ソブリン格付けとは国債などが元金・利息ともに返せるかのランク付けです。
国債に対する評価が低下すると金利が上がります。
現在日本の国債の金利は1%程度です。
3月の国会答弁で日銀の白川総裁は「2%上昇したら日本に金融機関の損失は18兆円になる」と答えています。
不安を煽るつもりはありませんが、今後の日本、これから向かう方向、見極めていく必要はあります。
またよろしければこの文芸春秋を読んでみるといいと思います。
盛和塾世界大会
今朝、今日のブログは何を書こうかと思っていた時、メールである知らせが来ていました。
私も入塾している盛和塾の世界大会が毎年横浜で開かれます。
3000名を越す世界の経営者達が集まります。
その大会で稲盛和夫さんや3000名の経営者の前で8名の人が「経営体験発表」をします。
その1人に私達と同じ盛和塾札幌の塾生が選ばれました。
事前に各地でその選考が行われ、選ばれた上での出場です。
その人は清水鉄志さんといい、回転寿司の株式会社はなまる社長です。
清水さんが選考される時、私も参加していましたが、その「経営体験発表」は大変感動的なものでした。
やはり最終的に世界大会に出場出来たのだと納得してしまいます。
清水さんという人は、過去20年ほどの間に売上1億円程度の会社を30億円にも伸ばし、その上経常利益が10%にもなる高い利益率にしました。
「花まる」という回転寿司店は根室と札幌に10店舗以上あります。
その中でもJR札幌駅に隣接するステラプレイス6階にあるお店は一番の売上です。
開店から閉店まで行列が出来ています。
30分待ちは早い方です。
8年ほど前に開業して以来ズーと続いています。
そのお店は60席ほどしかないのに、年間売上は5億円になります。
これは驚異的な数字です。
清水さんは会社躍進の原動力は稲盛和夫さんの教えと教えてくれます。
稲盛さんの教えを忠実に守り、社員を大事にし、会社を発展させて来ました。
その姿は稲盛さんの教えの正しさを私達に示してくれます。
清水さんは会社発展のお礼を込めて、稲盛さんの前で「経営体験発表」をしたいというのが強い思いでした。
それが叶うのです。
先週の土曜日に私のホテルで清水さんの結婚祝賀会(再婚)と世界大会出場を願う会をしました。
本当に親しい仲間同士の会で、大変楽しい会でしたが、今となればそれが前祝いとも言えます。。
7月に行われる盛和塾世界大会で、どれほど多くの人達に感動を与えれるか、今から楽しみです。
子供を生む
私には今4人の孫がいます。
これからまだ増えるでしょう。
その孫達が成人を迎える20年後、私は80歳を越しています。
その頃の日本はどうなっているかという不安、これは皆さんも持っていると思います。
その頃日本の国勢が3流に転落していた時、子や孫らは大変苦労すると共に、そのような国にした年寄達を恨むでしょう。
そして、働く自分達の人口が少なく、年金をもらう沢山の年寄達のために自分が社会保障費を支払うなんてとても考えられないでしょう。
今、日本人にとって、増税等で国の収入を増やすより、欲を押さえ支出を減らすことが大切です。
そして同様に人口を増やすことも重要です。
残念ながら今、子供を生むより、自分の生活を大事にしたいと思っている若い人達も多いようです。
子育てに使うお金より、自分達の生活をエンジョイしたいと思っている人達が多いです。
日本の子育てをする環境は欧米と比べ低いのは確かです。
しかし、それを単に言い訳にしているだけだと私は思います。
私の兄弟は4人、妻も4人兄弟です。
私の子は5人です。
今から比べれば生活環境は悪かったと思います。
交通手段、通信環境はまだ不十分で、家庭内の電化製品も少なく、家事にかかる時間は今の2倍も3倍もかかりました。
そしてカツカツのお給料で子育てをしました。
妻は5人の子供を育てました。
子供が生まれると将来のため限られた給料の中から1人1人の進学資金を貯めました。
その為、生活は贅沢出来ず、家族旅行もあまりしなく、外食も月に1度くらいのマクドナルドに行くのが楽しみでした。
豪華に海外旅行に行くことは勿論ありません。
グルメな料理を食べたこともありません。
でもその節約のおかげで、子供達は大学や専門学校に行くことが出来ました。
ただ、入学金と授業料だけは親が払いましたが、教科書・教材費や交通費はアルバイトで支払わせました。
そのおかげでしょうか、皆早くから自立心が身に付いていたようです。
子育てをすることは大変ですが、かけがえのない素晴らしい経験です。
お金や物で替えられないものです。
そして子供が成長するとともに、一緒に親も人間として育っていきます。
自宅に貼ってある東京にいる孫達の写真を見るとそんなことを思い、こんなことをツイ書いてしまいました。
マクロを目指す
今の政界を見ると、国民新党が分裂し、民主党も内紛状態です。
自民党も一枚岩ではありません。
日本が大変な時に何をしているのか、国民が皆そう思っていることです。
政治家が1人1人言っていることは確かに正しいのです。
消費税にしても、郵政問題にしてもそうです。
正しいことを言っても意見が違っています。
問題はミクロの世界で論争に終始していることです。
目の前ことだけだけしか見えていません。
ミクロの世界で正しくても、マクロでみると間違いということが数多くあります。
政治、経済、国防、教育、国の根幹にかかわることの大筋は、ミクロから離れてマクロで論議しなければなりません。
時には、目先のマイナスも踏み越えて進まなければならないこともあります。
国民に関わることは1つ1つ大切です。
しかし、それにとらわれては国を存亡の危機に貶めることになりかねません。
政治家は国のすすむべき方向を真剣に考え、それを国民し示します。
そして非難を受けつつも、それに進んで行く勇気と力がなければなりません。
この事は全ての世界でも言えることです。
経営にもミッション、ビジョンというマクロが求められます。
会社のすすむべき方向と価値を示し、従業員と共に仕事をする。
目先の損得だけで経営していくと、あらぬ方向に行って取り返しがつかなくなります。
どの世界でもトップに立つ者には、必要なのは倫理観、正義感であり、勇気と行動力。
貧すれば鈍す
日本の言葉に「貧すれば鈍す」というのがあります。
「貧すれば窮す」ともいわれます。
「貧乏になれば礼節を忘れる」という例えです。
ここで私は貧乏を軽蔑しているのではありません。念のため。
世界中を見ると、貧しい国では犯罪が多いです。
食べていくために起きることです。
小説「レ・ミゼラブル」でもパンを盗んだ主人公が19年も牢獄に入ったというのもあります。
それでは貧乏は「悪」なのでしょうか
「貧すれば鈍す」の逆に、裕福になったら精神が高くなるのでしょうか。
色々調べたのですが「貧すれば鈍す」の反対語がありません。
決して裕福になったら精神意識が高くなり、人に優しく、悪いことはせず、皆幸せになるかというとそうではありません。
どちらかというと、裕福になればより欲が生まれ、精神は「貧」する傾向にあります。
日本には「 貧なれど卑ならず」という言葉もあります。
「武士は食わねど高楊枝」という言葉もあります。
貧しさに負けない精神の高さを表しています。
以前にもブログで書きましたが、城山三郎氏の小説で、国鉄総裁だった石田礼助氏を主人公にした「粗にして野だが卑ではない」というのがあります。
租・野・貧に負けない「精神の高さ」を語っています。
日本人はどちらかというと「清貧の思想」のように、過去の日本では、貧しさに負けない高い精神を保って来ました。
日本人のその高い精神を保つには、なまじっかモノにあふれた豊かな時代ではなく、少し貧しい方がいいのかとさえ思われてきます。
今の日本人は豊かです。
その豊かさと共に「鈍」になってきて、「卑」にもなってきているように思います。
そのような日本人の考えはそう簡単には変わらないでしょう。
それでも過去日本人の考えが大きく変わった出来事があります。
それは明治維新と敗戦です。
共に黒船だったり、戦争という外部要因によってです。
日本人ばかりでなく、ギリシャを見ても人間には自浄能力があまり無く、外圧でしか変えられないようです。
日本にもこれからそう遠くない時にその強烈な外圧が起きそうです。
その時は価値観が変わっていくのでしょう。
考え方も変わっていくと思います。
今それを受け入れる準備が必要です。
難しいかもしれませんが、私もその心構えを築いていきます。
馴染みの寿司屋
先月の30日に、いつも出前を頼んでいるお寿司屋さんが閉店するという案内をいただきました。
私の父母がその店のお寿司が好きで、生前は何かある度に出前を頼んでいました。
いいネタを使い、少し高いのですが美味しいので、私たち家族も大ファンでした。
そのお寿司屋さんが先月の31日で閉店するという葉書は、前日の30日に届きました。
もう少し早く知らせてくれれば、もう一度食べたかったという気持ちです。
ただ、閉める寸前に告知をする、そこにそのお寿司屋さんの思いがあるように思います。
3月31日の区切りのいい日に、後腐れなくスパッとやめる心意気があるように感じます。
今は普通のお寿司屋さんが生き延びていくのは難しい時代なのかもしれません。
美味しい回転寿司、出前寿司がシステム化された経営でドンドン増え、従来からあるお寿司屋さんは生き残る余地がほとんど無くなっています。
地方で、回転寿司も出てこないような街で営業するか、超高級路線で差別化を図るかの方向しか残っていないでしょう。
もっと以前に回転寿司を手がけるという方法もありました。
でも回転寿司が出現し、それが勢いがついてきた時、従来の寿司店は「回転寿司の寿司は寿司ではない」と見下してきたところがありました。
今、その回転寿司にお客さんを奪われてしまったのです。
どの業界でもそうでしょう。
従来のやり方だけに固執すれが「ゆでガエル」になってしまいます。
それにしてもあのお寿司屋さんが閉店したのは誠に残念です。
外国人
昨日から我が家に若いイギリス人が来て、しばらく滞在する予定です。
娘の知人の男性です。
我が家に帰った時、彼に話をしました。
私は欧米人が好きでないと。
私が彼に「欧米人が好きでない」とあえて言ったのは、日本に来ながら日本語を使わず、英語やフランス語を使い通そうとする人が多いからです。
日本人は外国に行くと一生懸命英語や現地の言葉を使おうと努力します。
食習慣でもそうです。
日本人は蕎麦を食べたり、味噌汁を飲む時音を立てます。
それを欧米人はマナー違反だとか、エチケットがないとか言い、自分の国の習慣を押しつけます。
日本人は欧米に行き、食事する時は慣れないフォークナイフの使い、音をたてないよう努力にします。
互いにその国を訪問するのだから、その国の習慣や食べ物・言葉を理解するように努力するべきです。
その国を本当に理解するにはそれらがベースになるのです。
とイギリス人の彼に日本語で言ったのですが、あまり理解していなかったようです。
ただ、そのように欧米人が自分の文化・習慣を押しつけてくるというのは、日本人の「舶来主義思想」が残っていて、素直にそれを受け入れてしまうからなのでしょう。
欧米人には甘いです。
一方アジアやアフリカの人達に対しては逆です。
先月看護師国家試験の結果発表されました。
その試験にインドネシア人とフィリピン人の計415人が受験し、47人が合格しました。
合格率は11・3%で、昨年度(4%)に比べ大幅に上昇したが、依然低い合格率にとどまっています。
日本人も入れた全体の合格率は90・1%です。
外国人にとっては難しい日本語を、日本人受験生とほぼ同じレベルでの読解力を求めてきます。
47人が合格したというのは、異国の地で、異国の言葉を覚え、余程努力した結果度と彼女らに頭が下がります。
ここで思うのです。
どうして日本人は同じアジアの人に対しては高圧的な態度になるのかと。
彼女らは日本の足りない分野を補って働いてくれる人たちです。
より考慮されてしかるべきと考えます。
以上述べてきたのは、多分に私の単なる思い込みなのかもしれません。
ただ、国によって区別するのではなく、各国の人達が互いに相手を理解しようとし、尊重することが本当の交流が生まれると信じています。
私もこれから海外に行くことも多くなるかもしれません。
その国をじっくり味わってきたいと思っています。
「金融円滑法」再延長
今、国会では消費税法案でもめています。
その方に気が取られている内に「金融円滑法」の再延長になっていました。
4月1日から来年まで延びたのです。
以前にこのブログで「金融円滑法」について批判的に書きました。
今回の再延長で、本来整理されるべき企業が生き延びて、ただ債務を増大するだけにすぎないと私は考えています。
日本リサーチ総合研究所のレポートがあります。
昨年の9月現在で「金融円滑法」による返済猶予を受けている債権件数は累計で228万件、金額で63兆円になっています。
利用している企業の半数は2回以上利用しているリピーターです。
「金融円滑法」を利用しても企業が倒産した件数は、2011年度で194件、前年の23件に比べ急増しています。
その倒産原因のほとんどが「販売不振」です。
企業の根本に原因があり、単に資金繰り緩和で解決できることではないようです。
「金融円滑法」が施行された時、期待される2つの役割がありました。
1つには優れた技術やノウハウを持っている企業が、市場環境等の急激なショックで一時的に資金繰りに陥った中小企業救済
2つ目は中長期的な視点から経営改善できるようにコンサルティング指導をすること。
この1つ目の役割は、市場環境の一時的に急激なショックを受けた中小企業救済のためです。
決して、その企業固有・個別の技術力低下や競争力の低下などの「構造的リスク」に対してではないはずです。
しかし利用の半数がリピーターという実態は、「構造的リスク」を抱えている企業の利用がほとんどということを示しています。
また金融機関にとってこの円滑法は、債務者の区分を「不良債権先」を「正常先」として扱ってよいとするもので、銀行は貸し倒れ引当金を積む必要がないのです。
そのためその融資先企業の「構造リスク」が改善されないまま、「金融円滑法」の再延長は「隠れ不良債権」の増加につながることになります。
そうなるとこの円滑法が切れた時、恐ろしいことになります。
自見金融担当大臣は再延長は今回限りと明言しています。
そうなると2009年始まった金融円滑法は来年3月に切れるまで、起こるべきだった企業倒産が一気に起きることになります。
それは新たな社会不安を起こすことになるかもしれません。
そしてその場合、信用保証協会付きの融資は代位弁済されますが、それはすべて財政負担、国民の負担となってきます。
このように見てきますと、国民新党の亀井さんが中小企業救済のためと思って強引に始めたこの法案は、負の増大を招いただけなのかもしれません。
つくづく「小善は大悪に似たり」そのままのとの思いがします。
親は鞘(さや)
数日前、私が良く読んでいるブログに書いてあったこと、読んで私なりに考え感じることがありました。
そのブログには、ある人の子供が成長するにつれ生活態度がおかしくなり、悩んでいるという相談を受け、そのブログの筆者が自分の体験を踏まえて書いていました。
相談をした人は、いっそのこと「勘当だと言って追い出した方がいいのか」と考えているようでした。
その筆者も同様に子供の問題で悩んだ経験を書いています。
私は子供が5人居ます。
子育ての間は色々ありましたが、子供達はしっかりと育ったと思っています。
でも最近子供達に聞くと、時に横暴な父親のために布団の中で泣き、兄弟で慰め合っていたとのことです。
私としては、「厳しかったかもしないが横暴ではなかった」と思っていますが・・・
親は親として悩み、子は子として悩む。
子供が小さい頃は「お父さん、お父さん」と慕ってくれても、成長するにつれ、自我が芽生えると共に、反発心が生まれ、最初の大人である親に反抗するのでしょう。
親は親で「なぜいうことを聞かないのか」と怒ります。
でも、その時ツイ「勘当だ!家を出ていけ!」と言ってはいけないのです。
そのブログの筆者は「親は鞘(さや)です。子供が帰れる鞘は残していおかなければなりません」と書いていました。
私はこの「親は鞘なんだ」という言葉に改めて気付かされました。
(この「鞘」は「元の鞘に納まる」という言葉からきています。)
子供が大人になり、どのような生活をしても、いつか困った時、悩んだ時、帰って来れる親元があるのだということ。
子供がいつでも帰って来れるよう、親としていつでも迎えるという心意気で居れること。
今回ブログでその大切さを知らされました。
送別会
昨夜は長年勤務していただいた取締役部長の送別会がありました。
身近の人達だけ、9人が集まりましたが、いい送別会でした。
部長は私より2歳ほど若いのですが、60歳をもって退職するということです。
私はこの部長とは30年の付き合いがあり、退職するということがまだ実感として感じることが出来ません。
銀行員から父の会社に入り、本部勤務の時に出会いました。
私は入社時はほとんど新入社員状態で、色々教えていただきました。
特に経理実務に関しては徹底的に指導されました。
当時はパソコンも無く、全てが手書きで決算書まで作りました。
そのおかげで今、どの決算書を見ても内容を把握できるようになりました。
その部長が送別会の時、挨拶をしたのですが、いつも冷静である彼とは違い、涙ながらに心境を語ったのが今でも私の心に残っています。
部長は本部勤務が長く、私の父が社長・会長であった時、常に傍にいた人でした。
父は亡くなる半年前まで、することが無くても会社に出てきました。
父がいつまでも元気であるためという思いで、部長を中心とした会社の人達が送り迎えから、散髪にも車で送って行くくらい、私達家族以上に世話をしてくれました。
部長はあいさつの中で、「会長が朝、事務所のドアを開け、片手を上げ、おはよう!という声が懐かしい」と泣いてくれました。
父が2年前の11月に亡くなり、母も昨年の9月に亡くなった頃から、彼は会社を辞める気持ちでいたようです。
事務所の人の話によると1年ほど前から時間を掛け、会社の書類の分類・整理を完璧にしていたそうです。
元々生真面目な人です。
自分が辞めた後のことまで時間を掛けて整理したようです。
今の社長である兄も、公私ともに部長に頼ってきたところもあり、大変残念そうです。
今さらに、「父は多くの良き人材を育ててきた」との思いがします。
宇宙に働く2つの力
2日前にブログで書いていました稲盛和夫さんの話で、「大事にしてほしいことの3つ」の最後の3つ目の言葉を紹介します。
「宇宙に働く2つの力を得る」です。
このようなことを書くと、スピリチュアルだったり、宗教じみていると思われるかもしれませんが、我慢して読んでみてください。
宇宙はビックバンから始まって、今でもどんどん広がっています。
そのような宇宙には「成長させる力」と「調和させる力」があります。
宇宙には無生物に至るまで、森羅万象あらゆるものを進化発展する方向へと導いていくような強い力が存在すると考えても良いのではないでしょうか。
宇宙に同調する美しい心を持って努力すれば、必ず成長発展して行きます。
しかし1つのものだけがどんどん成長発展を遂げ、肥大化していくと宇宙はバランスを失ってゆきます。
そこに「調和の力」が働きます。
宇宙にはあらゆるものを成長発展させる力と、あらゆるものの調和を保つという力、2つが備わっていると考えられます。
この2つの力を生かすことで成功を収めることが出来、その成功を長く維持することが出来ます。
必死になって努力する人は成功をするように宇宙は約束しています。
上手くいかないのは努力不足だけ。
次に企業が大きくなっていくと人は傲慢になり、最後には他をおとしめてでも、自分だけが儲かればいいと思うようになっていきます。
そこで「調和」が大切になってくるのです。
相手に良かれかしと願う「利他の心」、温かい思いやりをベースとした経営を行うならば、それは宇宙に働く「調和する力」と同調し、その成長発展を維持することが出来るのです。
稲盛さんはこの2つの力を図に表し、「極楽界」「波乱万丈界」「地獄界」「植物界」であらわしています。
ここに添付しましたので参考までご覧ください。

政治不信
私のブログではあまり政治のことは書かないようにしています。
人には色々な考え方があり、何が正しいかなど明確なものは無いと思うからです。
ただ最近思うことがあり、書くことにしました。
今、国会は消費税増税でもめています。
これは大変重要な問題です。
でもこれには触れません。
私が気になるのは「郵政民営化見直し」です。
郵政問題についても賛否両論があると思います。
これにも触れません。
ただ私が不満に思っているのは、2005年に圧倒的国民の賛成で信任された法案が、いつの間にか政争の具にされ、変更されようとしていることです。
法案の見直しが政党の思惑でなされたとするば、あの時の国民の意思はどうなるのでしょうか。
当時の小泉首相に対しても好き嫌いの意見があります。
郵政問題がその1つにあるのでしょう。
郵政選挙と言われたあの時ほど、1つの法案に対して国民の意思が反映されたことは過去あまり無かったのではないでしょうか。
あの時の選挙の結果が民営化反対でも、それが国民の意見であればそれでもいいのです。
ただ選挙で確認された国民の意思を変更するのであれば、どさくさにまぎれてするのではなく、再度国民にそれを問うべきなのです。
政治には時には駆け引きもあるでしょう。
しかし、民意を無視する態度こそ、政治不信になるのです。
この政治の世界は正しいことより、政治家の損得の世界そのものの様な気がします。
大変残念です。
思いは実現する
昨日は盛和塾勉強会での稲盛さんの言葉を紹介しました。
昨日は「謙虚にして奢らず」のことを書きました。
今日は「思念は業を作る」「思いは必ず実現する」ということについて書きます。
稲盛さんは次のように言っています。
「『思念は業を作る』ということは『思い』が原因を作るということです。
その原因が発現して現象としてあらわれてくるものが結果であり、物事が実現することです。
『思いは実現する』と言いかえることが出来ます。
世の中に出ている成功哲学のどれを見ても『思いは実現する』という教えがあります。
これは人々を成功へ導く鉄則となっています。
善きことを思えば善きことが起こり、悪いことを思えば悪いことが起きます。
しかし我々現代人はこの『思う』ということにそれほど偉大な力があるということを理解していません。
それで平気で心の中で悪いことを思ってしまっても大丈夫だろうと考えます。
それが間違いで、思っただけで原因を作ってしまうのです。」と稲盛さんは言っています。
私はこの「思う」ことにの大切さは、私の経験からも本当だと実感しています。
稲盛さんの本やDVD、時にはご本人から、「考え方の大切」さ、「思う力」を教えたいただた時から、私の考え方・行動が少しずつ変わったきたことを感じています。
そして今の自分は、10年前の自分とは違う自分の様な気がします。
謙虚にして奢らず
昨夜、毎月開かれる盛和塾の例会がありました。
今回は昨年12月に録画された稲盛和夫さんのDVDを見ました。
盛和塾で何を学ぶかという題名で話されました。
以下その内容を自分なりに解釈して書きたいと思います。
盛和塾というフィールドに入れば、ぜひ経営者として大成してほしいし、企業を大きくし、従業員を幸せにしてほしい。
それではどうすればそれが出来るか。
それには大切な3つのことがあります。
1つは「謙虚にして奢らず」
2つは「思念は業を作る。思いは必ず実現する」
3つは「宇宙に働く2つの力を得る。」「成長させる力」と「調和させる力」
今日は1つ目の謙虚にして奢らずについて説明します。
人間は自分を分かっているようで分からないもの。
知らず知らずに初心を忘れていきます。
そして知らぬうちに奢り高ぶっていくことがあります。
素晴らしい業績を上げていながら、いつの間にか没落していった人達の多くは、「謙虚にして奢らず」を忘れてしまったからです。
また分かっていても本当に理解していなかったのです。
自分がある程度成功した時、人間は知らず知らず、「自分は素晴らしい才能がある」と奢り高ぶってしまいます。
でも、その時こう思うのです。
「自分がそれを成し遂げたのは確かにその才能があったからではあるが、たまたま自分にその才能があっただけで、もしかしたら自分でなくても良かったはずである。」
「自分はたまたま与えられ、それを演じているだけにすぎないのだ」
「自分という存在がたまたまその役割を与えられただけなのだ」
そう思うと自分の才能を私物化してはいけないのです。
才能はたまたま与えられたと思うことが大切です。
稲盛さんは昔のことを反省してこう続けました。
京セラが利益20億円程になった時、社長である自分の年収は数百万円で1千万円にはなっていませんでした。
もっともらってもいいのではないかという迷い生まれたと言っていました。
その時そうではない。たまたま自分に与えられた才能を私物化してはいけないと思ったそうです。
私は今回の話で「謙虚にして奢らず」という言葉の意味をより深く理解できたように思いました。
誰でも知っている言葉です。
私はこの言葉を単に「自分の欲を押さえ我慢をすること」と理解していました。
稲盛さんのこの話で「謙虚にして奢らず」とは「我慢をする」といのではなく、自分という「存在」そのものと向き合い、たまたまそれを成し遂げることが出来た才能に感謝し、私物化することなく、利他の心を持つということだと気付きました。
この考えを本当に自分に置き換えていくまでには、少し時間がかかると思いますが、改めて勉強し習得していきたいと思います。
格安航空券
先日航空券をインターネットで予約しました。
2カ月弱前で新千歳から関西空港までJALで予約したのですが、9800円でした。
安過ぎてびっくり!
往復でも2万円を切っています。
あまりにも安いので、念のため同じ日同じ時間で新千歳―羽田をチェックしました。
13000円位です。
関空の方が距離的にも遠いのに3000円近くも安い。
考えてみると、格安航空会社の影響でしょうか。
格安航空会社「ピーチ・アビエーション」今月1日、新千歳-関西空港間に就航しました。
1日3往復で、25日から4往復となります。
ピーチをチェックすると、同じ日で6280円と8380円です。
この2つの金額は予約変更が出来る出来ないの違いのようです。
JALの9800円よりは確かに安いです。
このピーチはまだ新千歳―羽田は飛んでいません。
その為、この間を飛ぶ他の航空会社はその影響を受けていなく、それほど安くなっていないのでしょう。
ただ私は若干の金額に違いであれば、JALに乗ろうと思います。
稲盛さんが会長をしているということもありますが、格安航空はどうしても時間が一定でありません。
平気で1時間位遅れます。
予定を組んでいる人には使いづらいです。
それでも飛行機を利用する側にとって選択肢が増えることはいいことです。
ここまで格安航空会社が表に出てくると、心配な航空会社があります。
それはエアドゥです。
北海道民のためにとして立ちあがったベンチャーの航空会社でしたが、現在はANNの傘の下に入ってしまい本来の創業当時の考えと違った経営方針になっています。
本来は今の格安航空会社的な経営を目指したはずです。
その点スカイマークは上手く対応しています。
格安航空会社と伍して戦っていけると思います。
JALもこれから格安航空会社を作るそうです。
これから益々競争が激しくなるとともに、私達にとっては選択肢が増え、より行動し易くなるのではないでしょうか。
今後新幹線新設問題も絡んでくるかもしれません。
ながい坂
今まで色々な小説は読んでいましたが、山本周五郎の本は何となく敬遠していました。
重たそうで暗そうな印象でした。
そんな思いを持っていたのですが、たまたま書店で手にしたのが「ながい坂」という長編小説です。
500ページが上下巻で、1000ページの長いものです。
この小説を読み終わっての感想は「感動」でした。
上巻を読んでいる時は、やはり重たく暗く、「やはりそうか」という思いを持ちながら読んでいました。
途中でやめようかとも思った位でした。
それが読み続けていくうちに、引き込まれていきました。
この小説を読まれた方も多いと思います。
下級武士の家に生まれた少年が、初心を貫き通すその姿を描いています。
平侍の長男であった阿部小三郎がある時父と釣りに行きました。
ところがいつも使っていた小さな橋が壊されていました。
それは、ある上役の都合によってあまり意味も無く壊されました。
小三郎はその理不尽さに憤りを持ったのです。
それが小三郎の志の原点となりました。
その後、彼は武道・勉学に励み、その才能から若き藩主に見い出されていくのです。
ところはその成長の過程では潔癖であるがゆえに、父・母・弟の生き方に反発を覚えます
そして阿部家を捨て名門三浦家の名跡を継いでゆき、三浦主水正(もんどのしょう)となります。
藩の中に騒動が起き、藩主引き下ろし騒動がある中、主水正は常に藩全体のこと、領民のことを考えたブレない考え方と行動を貫きます。
平侍から上に昇っていき、最終的に城代家老になる過程では、やっかみや反発を受けながらも信念を通し続けるその姿に、ついに周りの人達も認めていくのです。
自分の出世を望んでいたのではなく、藩のため領民のためという思いで生きて、最終的には藩主から望まれてなった城代家老も退く思いを胸にして、この小説は終わっています。
男として凛として生きているその姿に感動しました。
まだ読んでない方はお勧めします。
元気になれる小説です。
もうすぐ春
北海道・札幌は昨日の最高気温が5度、今日もその位になりそうとの予想。
やっと雪解けも始まり、春を感じるようになりました。
それでも札幌での桜の開花予想は5月4日頃。
まだ1ヶ月半もあります。
雪のある北国の人は5カ月ほど雪に囲まれ暮らします。
春が来るのをひたすら耐えて待ちます。
この「ひたすら耐えて待つ」という思いは、年をとるにつて強くなってきました。
幼い頃は雪が降ると喜び、スキーやスケート、かまくら作りと楽しいことがいっぱいあり、雪が降ると嫌だという大人の気持ちが分からなかったのもです。
今、大人になりその気持ちが良く分かります。
この耐えて春を待つ心が北国の人の忍耐強さを作っているのかもしれません。
この耐える気持ちが大きい分、春を迎え草木に若葉が芽生え、花が咲きだすと喜びが爆発していましそうです。
冬の間、春になればあれをしよう、これをしようと計画を立てます。
私も沢山の計画があります。
それがどれほど実行し目的が叶うか。
春を迎えるということは、本当の意味での新年を迎える気持ちになります。
春よ来い♪早く来い♪
子供の絵
昨夜、絵画教室に行き、子供の絵をいただいてきました。
2週間ほど前にお願いしていました。
4歳から11歳までの子供の絵25枚です。
これは「ポトマック河畔の桜寄贈100周年記念」の事業の一環として日米の子供の絵を集めて、互いの国で展示するというプロジェクトに賛同いただいものです。
東京で創業・起業そしてSOHO事業者へ支援活動している河瀬謙一さんからの依頼です。
河瀬さんのおじいさんは造園家で、100年前に当時の東京市長の依頼で桜の苗木をポトマック河畔に植えたとのことです。
河瀬さんがワシントンへ行った時、その桜が取り持つ縁でアメリカ人と知り合い、今回のプロジェクトが立ち上がりました。
日米の子供達の絵とメッセージを交換し日米の交流をさらに深めることを目的としています。
ただ実際に絵を送るとなると大変なので、それぞれの国で絵をスキャンして、データーとして相手国に送ります
それをプリントアウトして自国の子供の絵と一緒に展示します。
展示はワシントン・ポトマック河畔で行われる「桜祭り」の期間3月24日から4月15日までです。
展示場所はワシントン「桜祭り」会場に設営されるテントの中。
日本では三鷹市の市民協働センター等で展示する予定です。
札幌でも子供の絵を集めてくれるよう河瀬さんから依頼された時、正直戸惑いました。
私の周りにその対象となる子供がいないのです。
知合いのお母さんたちにお願いしても描いてくれる子供はいなく、集めるのが難しかったです。
小学校にお願いと考えましたが、募集期間が2週間ほどしか無くそれも断念。
それでインターネットで札幌の絵画教室を探し、その1つのリボンハウスの先生にお願いしたところ、ご協力いただけたのです。
集めるのにチョット苦労した分、昨夜25枚もお預かりした時は大変うれしかったです。
25枚の子供達の絵は皆明るく、個性的で楽しいものです。
見ていても見あきません。
暫く私の部屋に飾っておきたい位です。
子供達の絵が海を渡って、ワシントンの桜祭りの会場で、見知らぬアメリカの人達に見てもらえるという思いは想像するだけで楽しくなってしまします。
描いた子供達もそのような思いで書いたのでしょう。
その思いを届ける為にも、これから丁寧に荷作りし送ります。
篤志家
篤志家という言葉ご存じでしょうか?
「とくしか」と読み、社会奉仕・慈善事業などを熱心に実行・支援する人を意味します。
ボランティアに似ていますが、私の解釈では、お金持ちがする慈善事業という意味に理解しています。
その1つに、昔、それなりの地位や財産を得た政治家や財界人が、有望な人間を見出し、書生として自分のところで育てました。
生活に必要なものや学業に関する費用は全て負担します。
それを偽善という人がいますが、私はそうではないと思います。
才能ある人を見出し、その才能を生かし育て上げることが、国の将来のために重要だと思っていたのです。
昔は有能がありやる気があっても、経済的理由でその能力を発揮できない若者が多くいました。
有能な人を世に送り出すために、その篤志家と言われる人はそのような行為をしました。
今と違い、社会福祉も充実していず、貧富の差が大きい時代でした。
その時代の社会体制を問題にする人もいるかもしれませんが、ここではあえてそれは取り上げません。
篤志家と言えば、アメリカでは鉄鋼王と言われたカーネギー、日本では大原美術館を作った財界人の大原孫三郎、政治家では小沢一郎を書生と受け入れ政治家に育てた田中角等、昔は沢山いました。
勿論今でもいるのでしょうが、今はそれに代わる色々な制度があり、機関があります。
昔程、篤志家という人は多くはいないでしょう。
今、人を支援するということでは起業に関してもそうです。
社長などの経営経験者がその経験を生かし、支援する人がいます。
山あり谷ありの苦労を乗り越えた経営経験を生かして起業支援をしようとします。
多くの場合それは無償で行われます。
起業支援を仕事とはしません。
一方、起業支援を仕事とする人もいます。
この仕事の難しいのは、起業を志す人が、支援してもらうのにお金を出すか、ということです。
起業を志す人は、実際に起業する時、少しでも「持ち金」を持って始めたいと思います。
支援を受けることにどの程度お金を出すことが出来るか。
お金を出して支援を受けても成功出来るかどうかは保証されません。
起業支援が単独で事業と成り立つかどうかここが難しいところだと思います。
東京にはそれなりに需要はあるかもしれませんが、札幌の様な地方では難しいです。
支援と言えば経営コンサルタントもいます
経営コンサルタントは事業支援です。
会社は資金がそれなりにあり、コンサルタント料を支払っても十分ペイする事業だと思うからお金を出します。
同じ支援でもここが違います。
そして起業支援の難しさがあります。
起業支援には新しい仕組み作りが重要です。
何かいい仕組みが出来ないと起業支援を仕事ととする人は出て来ません。
起業支援体制が出来ないと、起業家が生まれません。
起業が成功出来る起業支援、それを支える「支援を事業」として成り立つ体制作り。
大事なことだと思います。
お中日
今日はお彼岸のお中日。
朝9時に家を出発、途中で花とお供え物の牡丹餅を買ってお寺へ行きました。
私の家のお墓はお寺の納骨堂にあります。
外にお墓がある人にとって北海道での春のお彼岸大変です。
お墓まで除雪をして、それからのお参りですから、お墓参りは体力勝負になります。
その点、屋内にあると大変気軽に行け、楽なものです。
妻と二人で花を供え、供物を上げ、お参りします。
般若心経を唱えて終わりです。
お経を唱えている時、去年なくなった母が「おまえの般若心経上手だね」と褒めてくれたのを思い出しました。
母に何かあると褒めてくれました。
60歳を過ぎている息子の私に「いい男になったね」とも褒めてくれました。
私は褒められて伸びるタイプです。
母は私の応援団でした。
そんなことを思い出させてくれたお墓参り。
お墓参りから帰っていま、言いしれぬ充足感を味わっています。
七福神
先日「京都七福神」の色紙をいただきました。
私が運営するレンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」に入居されている会社の社長さんからのプレゼントです。
その方は名古屋で経営コンサルタントとして活躍されている方ですが、毎年正月には顧客40名ほどと一緒に「七福神」廻りをするそうです。
また、その年の干支にちなんだ神社仏閣も廻ります。
今年は龍にちなんだ所を廻ったそうです。
その社長は、人の運は努力で引き寄せることが出来ると信じています。
一生懸命努力することも大切ですが、運が良くなると言われていることをしたり、良いと言われる場所を巡ったりすることも重要だと思っています。
私もこの社長と同じ考え方ですので、よく理解できます。
でも、全く信じない方もいますので、無理強いはしません。
ただ運が良くなると言われることは、お金が掛らないのであれば素直にすればいいと思っていますが。
いただいた京都の「七福神」の色紙は大きな色紙で横46縦38センチほどあります。
各お寺で御朱印を頂いてあり、各寺ではそれぞれの神名が記されています。
京都の「七福神」巡りは色々あるようですが、今回いただいたのは「都七福神」と言われるものの様です。
薄い金色の色紙に黒墨で書かれた神名と御寺名それに赤い御朱印が鮮やかに七神あります。
昨日木製パネルを買ってきて、それに真っ赤な毛氈を張りました。
そして、それに色紙を取付けました。
なかなか目立ち、オーラが出ているようです。
来週レンタルオフィスの目立つところに貼りたいと思います。
皆さんの仕事が益々盛業であるよう願って。
率先垂範
昨夜は久しぶりに盛和塾の勉強会に出席してきました。
若い新会員の経営者が増えて、大変活発な論議が交わされました。
この勉強会は稲盛和夫さんが書かれた「京セラフィロソフィ」の本を教材に行われます。
今回は「率先垂範する」の項目です。
以前開いていた私の勉強会でも「京セラフィロソフィ」を学んでいました。
同じ「率先垂範する」という項目も参加者と一緒に議論しましたが、今回は経営者ばかりなので、それとは別の意見を聞くことが出来ました。
自分が創業したばかりの会社であれば、人手も足りなく、当り前のように自分が中心になって仕事をします。
その時は「率先垂範」ということは頭にありません。
それは自分が働かなければ会社が成り立たないのですからです。
自動車修理工場の社長が言っていました。
会社がある程度規模が大きくなってきた時、どの時点で工場の現場から離れるか、すなわち作業着の「つなぎ」をいつの時点で脱げばいいのかと悩んだそうです。
経営者は現場ので皆を引っ張って行くと同時に社長としての仕事もあります。
いつまでも現場に入って、時給1000円の人と同じ仕事をしていてはダメなのです。
社長として時給1万円、10万円、時には100万円の仕事をしなければなりません。
「率先垂範」は会社の規模によってもそのやり方は違います。
現場に入ることばかりが「率先垂範」でもありません。
また、創業者と2代目とはやり方も考え方も違うという意見もありました。
創業者は自分が先頭に立って引っ張っていかなければならないという覚悟が最初からあります。
しかし、2代目は現場は知らなくても、作り上げられた体制の中で経営するという環境があります。
そこに「率先垂範」の考え方の違いがあります。
他に、「率先垂範」は「矢面に立つ勇気」という意見もありました。
「率先垂範」という言葉は理解していたつもりでいても、このように話合ってみると深い意味を持っていることに気付かされました。
盛和塾の塾長でもあります稲盛和夫さんはJAL再建のために、経営計画を作りながら、全国の現場に行き、管理職や社員と会い、意思の共有を図っています。
これも勿論「率先垂範」です。
私はJAL再建を進める稲盛さんの行動そのものが「率先垂範」の姿かと認識しています。
鞄
私は若い頃から「いい鞄」が欲しいと思っていました。
私が鞄を意識したのは、映画007ジェームスボンドが持っていたアタッシュケースでした。
何か洗練された、スマートなビジネスマンが持つ鞄というイメージを抱きました。
007の映画が上映が始まると、アタッシュケースの大ブームが起き、皆が様々なアタッシュケースを持っていたように記憶しています。
その頃銀行員だった私も早速買いました。
物持ちのいい私はいまだにその鞄は持っています。ただ、今は道具入れとして。
私にとて「いい鞄」とはなかなか明確に定義できません。
価格は高くても、使い易く、所有している満足感があり、長く使え、長く使うほどにより愛着を増す鞄。
自分にとって究極な鞄というものにはなかなか出合えません。
高いからいいかというと、そうではありません。
鞄は男性も女性もこだわる人が多いと思います。
私の妻も気に入ったバックとか鞄は買います。
ブランドモノとか高いモノではないのですが、気に入ると買ってしまいます。
男性の場合、鞄はビジネスで使うことが多いのではないでしょうか。
鞄を見ると結構その人の性格が見えるようです。
使い古し、ヨレヨレで、手の跡がくっきり見える鞄を持っている人は、こだわりの強い人なのか?
そのような人は結構ピシッとスーツを着ているのですが、その鞄とのアンバランスが違和感を感じます。
ルイビトンなどのブランドのアタッシュケースなどを持っている人もいます。
でもビジネス用としてはどうかと思います。
お客様が引いてしまうのではないでしょうか。
鞄は長く使うと、古くなって良くなるのと、単に汚くなるのとがハッキリしているモノです。
私は革の鞄が好きです。
手垢が付かないようにマメに拭くとか、表面が擦れてきたらオイルを塗るとか手を掛けます。
今の鞄は結構気に入っています。
これからも長く使っていけそうですが、時折浮気心が出ます。
いい鞄があれば買いたいと思いながら、街を歩くことが多いです。
鞄はやはり相性ですね。
電車の中で
地下鉄に乗っていて思うことがあります。
電車の中で本や新聞・雑誌などを読んでいる人を、札幌と東京で比較すると、圧倒的に東京が多いです。
札幌は東京の3分の1以下かもしれません。
東京の電車の中では何かを読んでいる人の多くは男性でした。
また、その中でも新聞を読んでる人が多かったように思います。
札幌の電車の中で新聞を読んでいる人はほとんど見かけません。
乗っている時間が短いからなのでしょう。
電車の中で男性が読むものは、新聞に次いで漫画が多いです。
東京にいた頃、朝電車に乗ると漫画を読んでいる男性が如何に多かったことか。
「出勤前の大事な時間に頭を漫画状態にしてどうするのだ!」といつも思っていたものです。
札幌で最近目にするのは、電車の中で常に携帯とにらめっこしている人が多いことです。
この前電車に乗った時、私の両サイドの若者はともに携帯をいじっていました。
女性と男性です。
ちょっとのぞいてみると、女性の方は一生懸命メールを打っているようでした。
男性はゲームです。
以前にも電車の中で男性がゲームを一生懸命しているのを見かけました。
昔は漫画、今はゲームなのでしょう。
ただ何となく思うのは男性は享楽的な生活、女性は堅実な生活を求めているようです。
これは単に私の誤解と偏見からなのかもしれませんが・・・
現在はこれからますます激動の時を迎えそうです。
真剣な生き方をしなければ、時代に淘汰されます。
楽で享楽的な生活から抜け出さなければダメです。
男の子!もう少し頑張ろう!
キャバレー
昨夜は飲み会がススキノでありました。
久しぶりのススキノでした。
飲み会は、サッポロビールのビール会でキャバレーで開催されました。
札幌には以前3ヶ所のキャバレーがありました。
その内の2ヶ所は既に無く、昨日行ったのは最後に残った「クラブハイツ」というキャバレーです。
私は初めて行ったのですが、客席400席という大きなところで、定期的にショーなどがあり、華やかなところです。
残念ながら昨日のビール会は予算上ショーを見れる時間帯ではありませんでしたが・・・・
キャバレーというところはご存じのように、きれいなドレスを着た女性がそばに座って、いろいろな話し相手をしてくれるところです。
華やかさを売り物にしているところです。
キャバレーは19世紀頃からからフランスで始まりました。
フランス語で、ダンスやコメディショーなどのパフォーマンスをする舞台のあるレストランやナイトクラブの事です。
キャバレーは文化の香りのするところでもあります。
フランス・パリのキャバレーは、昔ピカソ等の芸術家のたまり場でもあったそうです。
今でもパリには「ムーラン・ルージュ」や「クレイジーホース」などの高級キャバレーもあります。
数年前には函館である女性が中心となり、昔あったキャバレーを懐かしみ、1日だけ再現しようと奮闘している姿がテレビで放映されていました。
その彼女もキャバレーは文化の香りがするところと話していました。
昨夜は仲間とビールを飲み・騒ぎ、文化の香りは無かったかもしれませんが、札幌には1か所位はこのようなキャバレーはあってもいいと思います。
8時頃には終わり、仲間と離れて1人、大通まで歩いて行きました。
地下通路を通らなず、駅前通りを歩きました。
心地よい風に吹かれて文化の香りを感じながら?帰りました。
孤独死
最近新聞やテレビの報道で「孤独死」がよく取り上げられています。
何週間も発見され無かったケースも多いです。
寂しい思いをされて無くなった人もいたでしょう。
この孤独死の事が私達夫婦で話題に出ました。
子供達が家を出て、夫婦2人その後1人になった時、やはりそうなるのかもしれません。
私達が話したのは「夫婦2人で暮らし、その後1人は暮らす」というのはその人の生き方だということです。
可哀そうだから老人ホームの様なところで暮らす方がいいと言われても、本人にとっては独自に暮らしたいと思う人も多いはずです。
私は「孤独死」という言葉も好きではありません。
それは周りの人が付ける言葉で、本人にとってはひっそり死んでいくという感じの人もいるかもしれません。
昔話です。
あるところに仲のいい夫婦がいました。
ある寒い冬の夜、道に迷った旅人が一晩の宿を求めて来ました。
心優しいその夫婦はその旅人を家の中に入れ、精一杯のもてなしをしました。
翌朝天気も晴れ旅人が旅立つ時、こう言いました。
「私は神様です。あなた達2人は心優しさしい人です。お世話になったお礼に何か望みをかなえて上げよう」と。
夫婦は考えました。
そしてこう言いました。
「特に欲しいものはありません。ただ出来ることであれば、夫婦一緒に死なせて欲しいのです。」
神様は分かったと言って家を出ていきました。
それから何年も経ち、2人は年老いてきました。
ある日庭に出ていると、お爺さんが急に倒れ死んでしまいました。
それを見ていたお婆さんは「神様にお願いしたことを思い出し、もうすぐ私も死ぬのですね」と言いた時、倒れ死んでしまいました。
2人の死んだところに2本の樫の木が生えました。
このような昔話を聞いたことがあります。
私にとっての理想的な死に方かなと思って覚えていました。
今、社会的問題になっている「孤独死」を揶揄するつもりはありませんが、別の考えもあるということを書いてみました。
グズの効用
先日知人と昼食を食べていた時、彼から「グズの効果」という言葉を聞きました。
それは、「何もしない」とか「何も出来ない」という状況で、世の中が勝手に動いた結果、得をしたということを言うそうです。
成程と思います。
その話を聞いて、20年以上前にのバブルがはじけた時の出来事を思い出します。
バブルがはじけて拓銀が倒産・消滅した時、ある銀行の頭取が言いました。
我々はバブルの時、うまい儲け話にも手を出さず、投機もせず、堅実に経営をしてきた結果このように生き残れたと胸を張って言っていました。
その時私は「そうではないだろうな」と思っていました。
バブルの時、他の銀行ではおいしい話しが来て、儲かる事業にも手を出していました。
そうしなければおかしいという風潮が当時はありました。
ただ、したくても力が無いため、そのようなおいしい話が来ない銀行もありました。
先ほどの銀行はそれに近い立場でした。
またそれに向かって挑戦するという思いも無かったようです。
でも、結果それが良かったのです。
バブルがはじけて、他の銀行が傷付いていたのに対して、ほとんど無傷でした。
私はこの銀行も「グズの効用」の結果だと思っています。
結果オーライだからいいのでしょう。
ただ一般には「グズの効用」は「棚ボタ」即ち「棚から牡丹餅が落ちてきた」に近い、ラッキーということだけです。
先ほど紹介した銀行の様な事はそれほどあることではないのです。
勿論、何もしないのがいいということではありません。
でも「グズの効用」を期待している人が世の中には結構います。
何もしなくても、「その内良くなる」と思っている人が多いです。
「成り行き任せ」なのです。
でも現在、世の中は猛烈な勢いで動いています。
今こそ行動の時です。
これからは「グズの効用」を期待するのではなく「行動の効用」を求める時です
行動を起こした人が多くのものを得られる時代になると思います。
復興で頑張る人
今朝の朝刊に「にぎあう杜の都」という記事が掲載されていました。
それによると昨年12月の全国10都市平均の百貨店売上高が前年同月比0.9%増となる中、仙台市は10%増と突出していたと書かれています。
また仙台で一番の繁華街の国分町も賑わっています。
賃貸住宅も沿岸部からの転居者等の需要増で部屋が足りない状態だそうです。
仙台に色々なお金と、人が入って来ています。
以前にもブログで紹介しましたように、2週間前に私も仙台に行って来ました。
仙台は駅前からアーケードの商店街が驚くほど延々と長く続いています。
またそのアーケード商店街は横にも広がって続いていました。
街中を3時間ほど歩き廻ったのですが、驚いたことに、どのアーケード街も人が多かったのです。
駅から離れたところに三越や地元のデパート藤崎があります。
そこにはブランドショップが軒を連ね、人が沢山いました。
札幌の繁華街のススキノやアーケード商店街の狸小路と比べても断然人が多かったです。
人が集まり、お金を使い、消費が高まるということは、一番の復興です。
儲けられる時に商売を一生懸命頑張る。
そしてお金を回す。
そしてもっともっと頑張る人が出てくる。
雪が解けると震災復興事業がより活発になり、仕事を求めて全国から会社も人も集まります。
1年後は仙台と同じように活気ある町が増えているでしょう。
「頑張る」は「我を張ることだ」とか、「頑張るいう言葉は簡単に使うべきでない」とか「頑張るという言葉は飽きた」と否定的に言う人がいます。
そんな言葉を聞くと、「ここだ頑張らなければいつ頑張るんだ!」と言いたいです。
「頑張るべき時」に「頑張る人がいる」から復興が成るのです。
私はこれからも頑張る人を応援します!
サービスの深さと広さ
サービス業に必要なのは「気配り」とか「心配り」と言われます。
しかし「心配り」「心に添う」と「気配り」「気働き」とは少し意味合いが違います。
「心配り」や「心に添う」はサービスの深さ、「気配り」や「気働き」はサービスの広さを意味しています。
どちらも大切です。
サービスの深さと広さを持って、一流のサービスであると言えます。
私のホテルの和食堂はお陰様でいつも混んでいます。
昨日も知人と昼食を食べに行ったのですが、やはり混んでいました。
それでも何とか空いているカウンターに座って食べました。
4・5人で食事する時は、何日か前に予約を入れなければ入れません。
料理も美味いのですが、その女性店長がいいのです。
彼女の動きを見ていると、作業をしながら周りを見ています。
そして自分も動きながら、上手く部下も使います。
3人前の仕事をしています。
また、心配りもあり、お客様が欲していることを察知する能力が高いです。
彼女のファンのお客様も多いです。
特に年配の方の人気は高いものがあります。
この女性店長は以前にもブログで書きましたが、今月いっぱいで辞め、結婚します。
次期店長が誰になるか分かりませんが、同じ仕事をする人はそういないでしょう。
和食堂の営業にも影響が出るかもしれませんが、それは仕方がありません。
彼女が結婚する相手は小さな和食のお店を経営しているそうです。
まだ行ったことは無いのですが、料理の評判がいいと聞きます。
彼女がそこの女将さんになれば、料理、サービスとも優れたお店になって行くことでしょう。
彼女の幸せを心から祈っています。
近い内にそのお店に行こうと妻と話しています。
単調な生活
昨夜は久しぶりで近くの馴染みのおでん屋に1人で行きました。
本当に久しぶりで半年ぶりになります。
振り返ってみると、お付き合いや会合で飲みに行くことはあっても、自分から1人で飲みに行くということは最近はほとんど無くなりました。
「面倒だ」と思ってしまうのです。
その久しぶりに行ったおでん屋の主人は私と同じ年で、私のそんな話をすると、「私もそうなんです」と言います。
最近気力が落ちて、やる気が無くなってきたと言います。
私と似たところがあり、これは「男の更年期」だという意見で一致しました。
ある人が言うには男の更年期は幅広く、40から60歳代まであるそうです。
私達はそれより若干遅れているのかもしれません。
気力が落ちているのは、更年期なのかもしれないけれど、もしかして単なる年による衰えなのかもしれません。
そこで考えました。
今の自分の単調な生活を変えてみようかと。
起きる時間から、その後の会社に出かけるまでの行動は毎日ほとんど同じです。
会社へ行っても同じような仕事が続きます。
会合がなければ、帰宅時間も同じ時間。
寝る時間も決まっていれば、それまでの行動も同じ。
「単調な生活」こそが気力減退の原因なのかもしれません。
自分で決めた通りの生活をすることは「楽」なのです。
「楽」だから精神的にそれに委ねてしまいます。
しかし、その「楽さ」が問題です。
そこでこれから、毎日の行動を能動的にいじり回してみようと思います。
「楽」な生活を変化させ、刺激的で「楽しい」生活にしていくのです。
楽しいは喜びに結び付きます。
これからは「気力」ばかりでなく、「喜力」も大事ではないかと思います。
マインドコントロール
今、テレビや新聞ではオセロの中島知子さんの報道ばかりです。
そこに出てくる「マインドコントロール」という言葉が注目されています。
大分以前に事件を起こしたオウム真理教問題では、頭が優秀な人ほど「マインドコントロール」にかかりやすいと言われました。
自分は大丈夫だと思う人ほどかかるそうです。
このマインドコントロールを使った事件としてはオウムの様な宗教関係団体はよく出てくる話です。
また第二次世界大戦時、ドイツのヒットラーが独裁政治を行った時も集団マインドコントロールを使ったと言われています。
このヒットラーはこの心理的操作を使った兵器を考えていたと伝えられています。
ネットであるページを見てみると、ヒットラーの言葉として「近い将来、我々は『究極兵器』を持つようになる。
かつて私は、それを細菌かウイルスだと考えて諸君に話したことがあったが、今では、もっと強力なものが見えている。
『心理兵器』や『意志兵器』がそれだ。『特殊な電磁波』を媒体として、我々自身の意志をそのまま兵器にする。
それは敵に命令し、少なくとも敵を無力化させ、我々の望む通りに動かす。
軍隊に限らず、人類全体をそのようにできる。」と言ったそうです。
このマインドコントロールが最終的に兵器までに発展するとなると怖いものがあります。
逆にこのマインドコントロールを使って自分改造ということも可能です。
「セルフマインドコントロール」とは自らの心の働きをコントロールすることが出来るモノです。
「思い通りにできない」「止めたいのに止めれない」等のネガティブ思考を思った通りにできるというポジティブ思考にすのです。
この方法は本を読んだだけで、自分で作り上げるということは難しいと思います。
やはり専門の人に指導を受けるのがいいのでしょう。
しかし、ここではやはり指導者を冷静に選ばなければなりません。
そうでなければ、その人のマインドコントロール下に置かれ、また不幸な立場になってしますからです。
今回の中島知子さんの事件を見ても、人間の心って、自分が思っているほど強くないのだなと改めて感じました。
1人暮らし
私は先週から1人生活をしています。
というのも、妻が東京の子供たちのところをめぐり回っているからです。
ちょうど節句にも重なり、それぞれの家を泊まり歩いています。
妻にとっても久しぶりの1人旅行なのです。
妻がいないため、この土日は1人で家にいました。
妻が旅行する前は、「あそこで外食し、あそこで飲みに行こう」と思っていました。
でもいざ1人になると、「今日は家にいよう」とか「出歩くの面倒だな」と思って結局、出不精のまま。
運動の散歩以外外出しませんでした。
家にいてサックスを吹いたり、本を読んだり、夜は1人酒。
食事は妻が作り置きしてくれたモノを温めて食べるだけ。
食器などは食べたらすぐ洗うので汚れません。
たまには1人もいいものです。
ただ、振り返ってみると、この土・日に人と話したのは、1度コンビニに買い物に行って、店員さんと「お願いします」「ありがとう」しか話していません。
たまにの1人暮らしはいいですが、本当に1人で暮らすというのは、話す人が居ないということです。
こんな当たり前のことが実感されます。
これから10年20年の間に、本当に1人になることも現実問題として考えられます。
色々考えさせられる土日でした。
妻が旅行に行くにしても、いいところ1週間ぐらいがいいところかな?と思っています。
平等について
平等について考えてみました。
平等という言葉は1つの観点だけでは捉えられない言葉の1つです。
平等には大きく分けて「結果平等」と「機会平等」があると思います。
「結果平等」とは、今の生活水準を他の人と平等になるように求めることです。
人より低い水準であると、自分も同じ水準に上げるように求めます。
「機会平等」とは人間として差別されることなく、同等に機会が与えられる環境です。
身分差別などなく教育を受けることが出来るとか、同等に安全が守られるとかです。
貧乏の家に生まれたから平等でないというのとは違います。
金持ちの家に生まれる、貧乏の家に生まれるこれは「宿命」です。
その与えられた「宿命」を背に負い、同じ人間として頑張る機会を平等に与えられている中で、頑張れる人と怠ける人では結果が違います。
頑張らなかったその結果が不平等になっているのにかかわらず、それを「平等にしろ!」を主張すれば、それは本当の平等とは言えないと思います。
頑張っても怠けても、結果同じ待遇であればそれこそ不公平です。
今必要なのは「機会平等」を沢山作って頑張る人を増やすことです。
「結果平等」は頑張っても出来なかったを人を救済するものであるべきです。
身障者であったり、頑張ったけれど病気になってしまった人です。
頑張った人の生活救済は絶対必要です。
繰り返しますが、怠けた人も頑張った人と同じ生活を許すということが不平等です。
生活保護支給額が、年金支給額より多い。母子家庭所得より多いというのも、同じ観点から問題があります。
今の日本は「結果平等」が特に大きく取り上げられています。
それより必要なのは「機会平等」で、その重要さを唱える時です。
夕張市美術館
2~3日間のテレビのニュースを見ていて「なぜ?」と思うことがありました。
今年は日本中、例年にないほどの豪雪です。
北海道の岩見沢や夕張などは雪で苦しんでいます。
そんな時、夕張市の美術館が雪のために倒壊したとの報道がありました。
幸いに美術品の多くが地下にあったそうで無事だったようです。
ただ、このニュースを見て最初に「?」と思ったのは、「夕張市に美術館があったのだ!」です。
そしてテレビの報道ではその中に、ピカソやシャガールの版画や、佐藤忠良さんの作品が沢山あり、529点が運び出されているのがテレビで映っていました。
そこでまた疑問が。
夕張市は2007年に事実上破たんして、財政再建団体に指定されました。
日本中から支援の声が上がりました。
夕張市も職員を減らし、縮小財政の中で頑張ってきたはずです。
ところが、そんな夕張市に美術館があり、その中にピカソやシャガールの版画や佐藤忠良さんの作品があるとは信じられませんでした。
借金返済のためにそのようなものは処分していたのではないかと思っていたからです。
それらの美術品を売るだけで、億のお金が入ってくるはずです。
残しておいたのには「大事な美術品、市民の財産」という思いもあるでしょう。
しかし借金で苦しい会社は存続のために第一に必要ないものをすべて売り払うことが常識です。
倒産しそうな会社が美術品を大事にしている話は聞いたことがありません。
倒産したらいの一番に売り払われます。
夕張市はとっくに倒産し、借金減額をお願いしている立場です。
なぜ美術館の地下に「お宝が隠されていた」のか不思議です。
今のところこの事を「おかしい」いう報道はまだありません。
これからこのことが問題視されるのではないかと思っています。
もしも問題されなければ、それこそ「おかしい」ことです。
「善・悪」と「好き・嫌い」
事柄を判断する時、第一に「損・得」で決めるのは良くないと言われます。
「善・悪」の善いことか悪いことかの判断で決めるべきです。
この事はよく理解されていると思います。
ただ、その時1つの問題があります。
「好き・嫌い」という感情の問題です。
人間にとって、この「好き・嫌い」の判断基準はどうしても先に立ちます。
会社の経営者として考えてみます。
経営判断、商品開発、人材活用等では、「善・悪」が最初に来、次に「損・得」を考え、その「適正・不適正」の判断基準にします。
一般的にはそのようなことがいいと言われています。
しかし実際は、時として「好き・嫌い」が最初に来ることが多いのではないでしょうか。
もしかすると、ほとんどの経営者はそうなのかもしれません。
常に自分の感情を押さえて経営判断することは不可能です。
精神的に参ってしまいます。
では感情中心の「好き・嫌い」で経営したらどうなるでしょうか。
一時的にはその経営者の優れたアイディアなどで時流に乗り、上手くいくこともありますが、すぐ墜落してしまいます。
これが多くの優れた若手経営者の失敗の原因の1つだと思います。
「善・悪」だけで経営すれば精神的に参り、「好き・嫌い」で判断すれば経営がうまくいかない。
どうすればいいのか。
私が思うには「好き・嫌い」の感情と「善・悪」理性的判断が近づくように努力することが大切だと考えます。
「善・悪」の認識が、自分の「好き・嫌い」の感情に近づけば、なんのストレスなく適正な判断が出来るのでしょう。
経営者としての勉強は人間形成と言われるのはそう言うことです。
稲盛和夫さんが言われる「心を高める・経営を伸ばす」という考えに一致します。
結婚について
昨日のブログでは親子同伴の受験生のことを書きました。
今日も若い人についてを書きます。
私の会社にも独身の人が多いです。
話を聞くと、なかなかいい人に巡り合えないようです。
でも話を聞いていると、独身が長い彼ら彼女らが結婚できない大きな理由があるように思います。
彼ら彼女らの共通する気持ちは「結婚して幸せになりたい」です。
この「幸せになりたい」がネックです。
自分の幸せを求めると、「この人と結婚して大丈夫か?」「この人の両親はどんな人か?」という不安を感じてしまいます。
結婚してもうまくいかないのではないかと思ってしまいます。
この不安があると、それを乗り越える余程のことがなければ結婚に踏み切れません。
一方結婚が出来る人は、自分の幸せより相手の幸せを考える人です。
「好きなこの人を幸せにしてやろう!」とか「私がこの人を支えて上げる!」という思いが強いと、不安などなくなります。
人を好きになればそのような気持ちになります。
独身が長い人は、人を好きになるのが憶病なのかもしれません。
昨日私のホテルの女性社員が結婚すると聞きました。
結婚してホテルを辞め、彼が経営する和食・飲食店を支えるそうです。
「私がこの人を支えて上げよう!」という気持ちが大変強いようです。
彼の幸せが自分の幸せなのです。
また昔、ホテル勤務していたある女性は、絵描きのご主人のために一生懸命に働き、支えていました。
ご主人の才能を信じていました。
ご主人が個展を開くという時は、自分のことのように喜んで、周りの人に案内チラシを配っていました。
「愛する人のために」という思いが、結局自分の幸せも掴むことが出来るのでしょう。
現代の受験生
昨日も書きましたように、先週末24・25日は仙台に行っていました。
その日は東北大学の試験日だったようです。
その日はチェックインの時からフロントカウンターに人が並び、ホテルマンが3人対応していましたがなかなか進みません。
朝食時もレストラン前に延々と並びます。
6時30分から開店しますが、行列が一段落したのは8時頃、その頃になってゆっくり食事が出来ました。
普段でさえ稼働率が高い言われる仙台市内のホテルも、受験生と重なり大混雑でした。
その受験生を見ると、親と同伴の子供が半分以上、もしかすると3分の1近くいたのかもしれません。
そして男子がお母さんと同伴というのも多かったです。
女子とお母さんより多かったかもしれません。
それはビックリするより、若干気持ちが悪いとう感想です。
お母さんが手続きからホテル側との交渉まで全てし、男の子は後ろで当然のことの様にそれを見、ただ「ボー」としているだけ。
普通は高校生ぐらいになると、お母さんと一緒に歩くのも恥ずかしいという気持ちになるものではないでしょうか。
このような子が1人で大学生活をして、社会に出て就職出来るのか。
まず無理でしょう。
そのような人間は、たとえ優秀な大学を出ても、面接時にその本質を見抜かれ落とされます。
それにより就職難と言われるのかもしれません。
でもそれは就職難ではなく、自業自得です。
逆にそのような甘い若者が多くいる時、1人で道を切り開いていく気概のある若者にとっては好機です。
私が宿泊したホテルで、1人で来ている男の子何人かに声を掛けると、快活に返事をし受け答えをして来ます。
「試験頑張ってね」と言うと、明るく「ありがとうございます」と答えます。
こんな当たり前のことが新鮮に感じてしまう。
少し世の中おかしいですね。
経営体験発表会
昨夜仙台から帰ってきました。
本来は14時頃に家に着いているはずでした。
しかし千歳空港が吹雪のため、千歳上空まで来てまた仙台に引き返し。
その後再度飛んで18時に過ぎに無事到着。帰宅は20時。予定より6時間遅れました。
それでも帰れて良かったです。
前のブログでも紹介しましたが、仙台では盛和塾会員による経営体験発表が行われました。
10人の発表者の中から2名を選出し、盛和塾の世界大会での発表者を選ぶものです。
札幌からは回転寿司「はなまる」の清水社長が自ら希望され出場しました。
札幌からは塾生20名以上が応援。
結果、ダントツ(私の感想)で清水社長が選ばれました。
しかし、それ以外の9人の社長たちの経営体験も大変な勉強になりました。
それぞれの会社の発展の変遷、会社経営の中で社長としての苦労、そしてその時出会った稲盛哲学。
様々の経営体験を聞くことが出来ました。
その話の中では、今まで私が知らなかった稲盛さんの言葉も紹介されていました。
その中の1つ。
稲盛さんはこう話されたそうです。
「浜松市からホンダ、ヤマハ、スズキのバイク会社が生まれました。
なぜ浜松のような小さな町からバイク会社が3社も生まれたのか。
それは本田宗一郎さんの様なハチャメチャな人間でもバイク会社が出来たのだから、自分も出来ると思った人がいたからです。」
稲盛さんが言いたかったのは、「自分でも出来ると思ったから出来たのだ」ということです。
自分を信じることが成功の原動力になるということを示しています。
その他に「チャンスはピンチの顔をしてやってくる」と言う言葉もあります。
各社長達は自分達の経営の中に稲盛さんの教えを取り入れ、忠実に守って発展してきました。
その中でも「はなまる」の清水社長の話は感動的なものでした。
清水社長は自分の赤面症を克服しようと上京し、落語家志望、浅草での喜劇劇団。
その後根室に帰りスナック経営、その後回転寿司を始めました。
そして、業績不振の時に出会った稲盛さんの経営テープ。
何十巻もあるそのテープ20万円出して買い、食事も忘れ、寝るのも惜しみ、トイレは走って済ませ、朝から晩まで何十日も聞いたそうです。
周りから「おかしくなったのでは」と思われたそうです。
その経営テープを切っ掛けに盛和塾に入りました。
稲盛さんの教えを経営に生かし、売上は20倍になったそうです。
稲盛さんはいつも言っています。
「私がこれほど手の内を見せているのだから、私の言う通りにすれば誰でも成功するのです。」
その成功例が、清水さんをはじめとする多くの経営者が盛和塾にいます。
「経営は数字ではなく社長の人格形成」と言う教えその通りです。
身の丈起業のすすめ
昨夜は「ご近所先生講座」「身の丈起業のすすめ」の最終講座が終わりました。
この講座はいつも気を張って準備をし、話をしますので、5回の講座が終わった後は興奮状態が続きます。
講座が終わり、家に着くのは9時を過ぎてからです。
寝るのは10時か10時30分ですので興奮状態のままでは寝れません。
特に昨夜は最終日でしたのでボルテージが上がりました。
いつもはお酒を飲んで、興奮を少し冷ましてから寝るのですが、昨夜はお酒を用意するのを忘れ興奮状態のまま就寝。
なかなか寝付かれませんでした。
今日は寝不足です。
でも今回の講座でも多くの人との出会いがありました。
感謝の気持ちです。
1人でも起業を志す人が生まれればと思います。
その時はまた一生懸命支援していきます。
今日はこれから仙台に行って来ます。
日曜日に帰る予定です。
仙台では復興バブルが起きていると言われています。
色々見てきます。
葛飾北斎
テレビの話です。
昨夜10時からは始まった、NHK「歴史秘話ヒストリア」の題名は『いつだって負けずギライ~葛飾北斎 横町のオヤジは世界一』でした
興味深く見ました。
葛飾北斎については皆さんも良くご存じでしょう。
北斎は90歳で亡くなったと言いわれています。
その晩年の言葉があります。
「天我をして五年の命を保たしめば 真正の画工となるを得(う)べし 」と行ったと言われています。
毎日筆を取って描いているけれど、まだまだ上手くならないと、死を前にして嘆きます。
「天があと10年の間、長生きさせてくれたら、いや天があと5年の間、長生きさせてくれたら、必ず本物といえる画工になり得たであろう」と言って死んだのです。
その道を極めれば究めるほど、不十分さ未熟さを実感するということでしょうか。
この言葉を聞いて思い出した言葉があります。
江戸時代に武士道について書かれた本「葉隠」の中にあります。
現代文に訳されています。それをご紹介します。
「人間の修行には段階がある。
修行の初期ではものにならず、自分でも下手と思い、人も下手と思う。この分ではまだ用には立たない。
中の位は、まだ用には立たないが、自分の下手さも他人の不十分さもわかるようになる。
上の段になると、全てを会得して自慢も出きるし、人がほめるのを喜び、他人の不十分さを嘆く。こうなればものの用に立つ。
その上の上になると知らん顔をしている。そして人も上手だと見えることが出来る。だいたいのものがこの段階までである。
その上にもう一段飛び越えると、言うに言えない境地が広がっている。その道は深く入れば入るほどついに果てしもない無限の世界だとわかって、これで良しという思いも無くなり、自慢心も起こさず、卑下する心も無く進んで行く道である。」
北斎はこの「その上にもう一段飛び越えた境地」になっていたのでしょう。
この葉隠の文を読むと、今の自分はどの段階なのか、いつも考えさせられます。
人の評価
何かを評価する時、別のモノと比較してしまいます。
モノを買う時、「同じ値段ならこれよりあれがいい」と比較してしまいます。
比較と言えば、競争もそうです。
学生時代は勉強でもスポーツでも「あいつには勝ちたい」「あいつだけには負けたくない」という気持ちがありました。
仕事上では、他社との競争する時は、商品、価格、品質等比較します。
誰にも負けない努力をするとなると、泰然とした気持ではなく、比較し、競争心があります。
このように仕事中心でモノを考えるようになってきたせいか、私は人を見る時も比較するようになっていたようです。
それを指摘してくれたのは娘です。
この間夫婦と娘3人で旅行している時に言われました。
自分では意識していなかったのですが、人を比較して評価していると言うのです。
テレビを見ていても「タレントのAさんよりBさんがいい」とか「この役者と比べたらあの役者はまだまだ」と言っています。
テレビで言っている内はまだいいですが、それが私は自分の家族に対しても比較して評価していたようです。
本来は他と比較ではなく、1人1人その個人として評価されなければいけません。
そうでなけれが評価されたその人間は辛いものがあります。
私はそれを良くわかっているように思っていたのですが、そうではなかったようです。
そのような相手の思いを知らず、一生懸命に教えた上げているつもりでも、単に他との評価を話しているしかないということがあるのです。
大いに反省しました。
「負うた子に教えられ」ではありませんが、娘も大人になったと改めて感じました。
先日の旅は、そんなことも話し合い、教えられたいい旅でした。
美味い漬物と酒
昨夜は友人とススキノで飲みました。
その友人とは久しぶりの飲み会。
彼の知っている店に行きました。
その店は漬物会社が経営しているということで、漬物を使ったメニューがほとんど。
素朴な陶器に7種類、15種類盛られた漬物をはじめ、漬物の入ったさつま揚げ、各種の漬物を肉で巻いた串もの等、漬物会社ならではのメニューばかりです。
漬物にはやはり日本酒。
その店は日本中から漬物に合う日本酒を集めていました。
でも、私はやはり北海道の地酒です。
月曜日にもかかわらず店はほぼ満席。
それも女性が圧倒的に多いのが驚きでした。
「漬物を肴に酒を飲む=おじさん」のイメージですが、店の作りはシックで落ち着いているにもかかわらず、モダン。
間接照明だけの、ほのかな光が雰囲気を作っています。
以前聞いた話ですが、「薄暗いろうそくの光は女性をきれいに見せる」らしいです。
その考えが店作りに行かされているのかもしれません。
「漬物を中心としたメニュー+日本酒」の店は初めての体験でしたが新鮮でした。
そして独自な戦略があると思います。
この店は札幌市内に2店あるそうですが、まだ増えるでしょう。
もしかすると、アメリカのニューヨークやフランスのパリ等で展開すると、評判を呼ぶのではないでしょうか。
漬物は塩辛いですが発酵食品でもあります。
健康という切り口でも受け入れられることも充分考えられます。
今日のブログは美味い漬物とお酒の話でした。
お伊勢参り
昨夜遅く旅行から帰りました。
11時を過ぎていました。
出発の金曜日は5時に起き始まる強行軍でした。
今回の旅は初めての「お伊勢参り」です。
東京に住む末娘と名古屋で合流し、3人旅でした。
やはり伊勢神宮はすごいですね。
何がすごいて、規模もそうですが、精神的にも圧倒される荘厳さが溢れているところです。
今回は内宮そばにある、神社会館に宿泊しましたがこれが大正解でした。
ここに宿泊すると、希望者には朝6時30分から1時間30分ほど、専門のガイドさんが内宮を案内してくれます。
大変寒かったですが、空は晴れ渡り、ほとんど人がいない静かな内宮を歩く時、石の1つ1つ、木々の一本一本の存在を感じ、別世界にいるようでした。
来年は式年遷宮ということで、もうすでにその工事は始まっていました。
来年の10月頃に内宮は移られるそうですが、その時は新旧の内宮が存在するという珍しい時だそうです。
内宮の他に外宮、月讀宮、月夜見宮、倭姫宮、猿田彦神社を廻り参拝し、翌日はセントリア空港へ向かう時に熱田神宮にも参拝しました。
今回の旅は今までのお礼の気持ちを込めたお参りツアーです。
内宮に参拝し神宮会館に戻った時、冬靴の底に挟まれている玉石を見付けました。
可愛らしい玉石で、今回の自分への土産になりました。
運のいい人と付き合う
仕事で成功するためには「運のいい人」と付き合うこと。
これは非常に大事なことです。
私が運営するレンタルオフィスに入居された起業家同士が、1年ほど前に出て、この同じビルの上の階で共同事務所を作りました。
3人がそれぞれが独立した会社を作りながら、互恵の関係で共に会社が発展しているようです。
3社にはそれぞれ社員もいるので、最近は事務所も狭くなり、春には倍の大きさの事務所に移るようです。
この3人の起業家は明るく前向き、プラス思考の人達です。
運のいい人同士が付きあっている姿です。
一方、独りよがりで、愚痴っぽい人も私の周りにはいます。
その人はやはりあまり運がいいように思いません。
でも、そのような人に引き寄せられていく人がいます。
仕事がうまくいかず、精神的に疲れている時に引き寄せられていきます。
つい愚痴を言い出したりすると、そのような人同士が結び付いてゆきます。
本人達は意識していなくても三毒(愚痴、妬み、怒り)に犯されていきます。
人はいつも積極思考、プラス思考、明るく元気とは限りません。
心が落ち込む時があります。
その時こそ十分注意しなければなりません。
「魔が差す」時なのです。
悪魔に入りこませる隙を見せてはいけません。
上手くいかない時は、上手くいっている人が羨ましくなってしまうことがあります。
そのような時、上手くいっている人を避けがちになりますが、避けてはいけません。
その時こそ、その人のマネをし、その人について行こうと思うことです。
その内にきっと運が開けてくるはずです。
色々な人と付き合っていると、「なんであの人の仕事がそんなにうまくいくの?」と思う時がたまにあります。
その人は運を沢山持っているからです。
いま一度、自分の付き合いを見直して見ることは大事なことです。
ところで明日から伊勢神宮に行って来ます。
初めての「お伊勢参り」です。
パソコンを持って行きませんので、帰ってからその報告したいと思います。
またオークションに参加しました
昨夜、またYahooのオークションに参加してしまいました。
今までの私の入札仕方は、「ある程度この金額以内なら落札するけれど、それ以上になったらあきらめよう」という思いで、最初から金額は確定していました。
ですから、一度入札金額を入れれば翌朝落札したかどうかを確認するだけでした。
(なぜかオークションの落札最終時間が夜中の23時24時が多いです)
ところが昨日のオークションに出品されたモノは以前から欲しかったものだったので、若干違いました。
ツイ熱くなってしまいました。
はじめは「この金額以下でなら買おう。それ以上ならあきらめる」と思っていたのですが、やはり気になり落札最終時間1時間前に状況確認をしてしまったのです。
そうすると私の入札金額より千円高い金額で他の人がリードしています。
アッと思った時はすぐにそれ以上の金額を再度入札していました。
そうなるともう気になって寝れません。
30分前、15分前、10分前、5分前、3分前と確認すると少しずつ上がって行きます。
最終的には私が落札したのですが、当初入札した金額より若干高いものでした。
それでも市販されている金額よりズーと安かったです。
終わったのはいつも寝る10時をとっくに過ぎ、11時過ぎ。
少し興奮して寝付けず、今は少し寝不足気味です。
オークションは何回か経験ありますが、これには自制心が必要です。
あまり深みにはまらず、また機会があれば参加したいと思っています。
藤田田(でん)さん
街中を歩くといつもお客様が多いのはマクドナルドです。
マクドナルドの経営状態もいいようで、2011年12月期の連結決算は営業利益が前期比0・2%増の281億円と過去最高利益だということです。
マクドナルドという会社の名前を聞くと私は「藤田田さん」を思います。
藤田田さんはもう既に亡くなっていますが、日本マクドナルドを創業した人です。
以前に読んだ本のことで記憶は不確かですが、東大生の時に藤田商店を立上げ雑貨を扱っていました。
その藤田さんはマクドナルドが日本進出するという話を聞いて、直接交渉に行きました。
その時は既に三菱商事などの大手商社が交渉中でした。
それを押しのけて小さな藤田商店がその権利を勝ち取ったのです。
普通に考えれば、大商社の三菱商事が相手だと初めから勝ち目がないとあきらめてしまいます。
全く劣勢な状況の中、取りに行き、実際に取ってきたというのだから驚きです。
昔、この事を知った時、藤田さんの可能性の限界を知らない思考に脱帽しました。
私には全く考えられない思考です。
その藤田さんを尊敬した人が孫正義さんです。
孫さんは高校生の時、これからどのような分野が成長する分野か、意見を聞きに藤田さんを訪ねました。
勿論一介の高校生が有名な社長を訪れてもそう簡単に会ってくれません。
何度も断れながら、やっとの思いで会うことが出来、コンピュータが成長産業だと教えられたそうです。
その後アメリカに渡りITの勉強をし、人のネットワークも作り帰国しました
帰国後会社を立ち上げました。
孫さんはソフトバンク設立前に「ユニソン・ワールド」という会社を創業しました。
朝礼の時、社員・アルバイト2人の前で、みかん箱の上に立ち、会社を「10年で年商500億の会社にする」と宣言しました。
これを聞いた社員とアルバイトの2人はその可能性を信じることが出来ず、翌日から出社しなかったそうです。
社員たちは、こんな大ホラ吹きの社長の会社は将来が不安と思ったのでしょう。
でも現在は売上3兆円 利益が5200億円の会社にしています。
2人には自分の可能性をどこまでも信じているという共通点があります。
孫さんはソフトバンクがある程度成功した時、藤田さんを食事に招待して、高校生の時相談にのっていただいたお礼をしました。
残念ながら藤田さんは当時のことは忘れていたようです。
でも2人は意気投合して、その後藤田さんはソフトバンクにコンピューターを500台注文したそうです。
2人を見て思うのは「大器は大器を知る」ということでしょうか。
想像力
想像力は起業家には欠かせない要素です。
自分の夢を描くのも想像力が必要です。
また、自分が目指すモノを考え、それを具体的に描き、そしてそれに数字を入れ、組織や仕組み作りに置き換えて、全体像を作り上げていく。
それが事業計画の在り方です。
しかしともすれば、自分の思いだけが強過ぎて、こんな会社にしたい、お客様がいっぱい入る店にしたいという思いだけが先行している起業家がいます。
マクロ的な視点だけの人です。
ミクロの視点で見る想像力がなければ、思い描くような会社や店を作ることは出来ません。
マクロ的視点で、自分の憧れる人、会社、店を目指して夢の実現に向け努力することは大切です。
しかし、それを成功させるためには、表面的でない、実務的な仕組み作りが重要です。
例えばお店を開く場合。
この時も想像力が必要です。
どのような年齢層、タイプのお客様が来るのか、
お客様が来たらどのようにお迎えするのか、
声掛けはどのような言葉を掛けるのか、
そのお客様が着て来たコートはどうするか。
濡れた傘はどうするのか。
お客様を席までどのように案内するか。
最初にお客様に出すモノは箸と水とおしぼりか。箸置は必要か。
オーダーも通し方からそれをお客様に提供するまでの流れに無駄と漏れは無いか。
その他色々あります。
大事なことは、お客様が来店して、お帰りになるまでの流れを想像できるかです。
この想像力が出来なければ、開業してからアタフタします。
折角いいのものを提供しても充分な満足を与えられません。
お客様が来店されてからお帰りになるまでが「ワンパックの商品」です。
想像力は経営者にとって不可欠な要素です。
プロの世界
以前にも書いたかもしれませんが、私の趣味はサックスを吹くことです。
3年前からサックスを始めました。
若い頃から興味がありましたが、なかなか踏ん切りがつかず挑戦していませんでしたが、フッとしたキッカケで始めました。
休みの日などはよく家でサックスを吹いています。
なかなか指が動かず、ミスも多いのですが、ナベサダやMALTAになったような気分で拭いています。
時折CDで一流のサックス奏者の演奏を聴きます。
そのテクニックはやはりすごいです。
また、ものすごいテクニックを使わない童謡なのどの曲を演奏しても、心が引かれてしまいます。
真似したくなってしますが、全然違うものになってしまいます。
一方インターネットのユーチューブで流れている普通の人の演奏を聴くこともあります。
それなりに上手いのですが、どうしてもそれなりモノのです。
楽譜どおりに間違いなく演奏するのですが、それだけです。
すごいという気持ちが湧いてきません。
勿論「素人だから」という思いを持って聞くこともあるからかもしれませんが、それだけではないようです。
ここがプロと素人の違い、一流とそうでない人との違いなのでしょう。
習い事の世界では、一流の人と普通の人との違いは歴然としたものがあります。
それは普段あまり親しみがない分野でも何となくわかります。
クラシックバレーにしても、ビアノにしても、バイオリンにしても、またお茶の点前にしても違います。
何が違うのかと聞かれてもうまく言えませんが、違うということはハッキリしています。
その道で究めようとしている人が、「何が違うか」が分かれば、「コツを掴んだ」と言うことになるのでしょう。
その為には練習量の多さも大切でしょうが、理解力、表現力を育て、鍛えることも大切です。
極端に言うとその分野における総合力、人間力までいくことになるのだと思います。
1つのものを究めることはどの世界でも大変なことです。
一流のプロと、アマチュア、趣味の世界は違います。
私はズーと趣味の世界で楽しんでいきます。
起業家の悩み
昨日、身の丈起業講座があり、その時若い女性から質問されました。
起業する時、起業しようとする分野の研究を一生懸命するべきか、経営の勉強を一生懸命するべきかと言うことです。
私は、起業しようとする分野の研究をするべきだと話しました。
その後気付いたのですが、多くの人が起業しようとする時、同じようなことを考えているのではないだろうかと。
起業して社長になると、色々な事が起きることを想像して、「経営の数字はどのように見ればいいのか」「人の採用はどうなるだろうか」とか思い悩んでしまいます。
勿論起業することは社長になることですが、社長になる前に、起業する仕事をとことん市場調査し、販売方法、販売経路、仕入れ方法、投資計画等詰めることが沢山あります。
極端に言えば、会社の経営方法は後でいいのです。
必要に応じて会計士や社会労務士の人にお願いしてもいいのです。
それより、いかに儲けるかを考えることが大事。
ただそれも、起業を志す人にとってはわからないのが当り前。
私が当然と思っていることが間違えています。
そういうことを改めて認識し反省させられた質問でした。
兄弟姉妹
昨夜は食事会をしました。
久しぶりの兄弟姉妹会です。
兄と私の連れ合いも参加して6人でした。
親が元気な時は、親に会いに子供達や孫が集まり、子供同士、孫同士の仲が深まります。
でも親がいなくなると、その求心力も無くなってしまいます。
兄弟姉妹というものは、親がいて繋がっている関係かと、改めて思います。
意識して会うようにしないと会うことがなくなります。
特に遠く離れていると、疎遠になりがちです。
それは物理的に仕方がないことでしょう。
そんな疎遠になるところを少しでも防ぐ意味で、人が亡くなったあとに49日法要、100日法要、1周忌、3周忌と、親しい人同士が会うための「仕組み?」があるように思います。
法要は強制的に兄弟姉妹を集め、親から「仲良くせよ!」言われている気がします。
昔の人はそんな思いで仕組みを作ったのかもしれません。
私達はそのような「仕組み」を別に作れました。
兄とは同じ札幌で仕事も一緒でいいのですが、妹2人は東京方面に住んでいます。
なかなか札幌へ来る理由や機会が少なくなります。
そこで私の家のすぐ裏にある、父達が住んでいた古い家を妹たちの「別荘」としてのです。
「別荘」と言って名前だけですよ。
そうすると、妹達家族が大好きな北海道、札幌に来る口実が出来ます。
「兄弟は他人の始まり」と言われます。
でも、兄弟姉妹が仲良くすることは亡くなった両親が喜ぶこと。
これからも皆が頻繁に集まり遊ぶことになりそうです。
履物について考える
今日は履物について書きます。
地下鉄を利用する時などはよくエスカレーターを使います。
特に登りの時、前の人の靴に目が行きます。
また電車に乗っている時も、前に座っている人の靴に目が行きます。
特に意識しているわけではないのですが、そうなります。
靴を見て思うのはその人の性格です。
素敵な服を着ている女性も、靴が汚れていれば幻滅。
ヒール部分がはがれているのを気付かず履いている人は少しだらしがない人。
靴の先がぶつかったりして白くなっている人はそそっかしい人。
勿論これは私だけの思い込みですが、いつもそう感じてしまいます。
靴などの履物に関しての話は多いです。
昔、ラジオで永六輔さんが話していたことです。
一流の料理屋さんには下足番という人がいます。
お客様が玄関先で履物を脱いで上がると、下足番がそれを預かります。
年季の入った下足番は、下足札を使いません。
それでいて、お客様がいくら多くても間違いがありません。
また年季の入った下足番は、お客様の履物を見て、お客様の身分、性格、好みが分かるそうです。
別の話です。
何かで読んだ話ですが、昔、剣の修業をしている武士が永平寺に入り教えを乞おうとして訪れました。
入山制限が厳しい永平寺では誰でもそう簡単に入れなかったそうです。
許可するお坊さんは、その人の人なりを一瞬で見抜き、許可不許可を与えたそうです。
その武士は修行を積み、武士としても人としてもそれなりの人でした。
それでも断られてしまったのです。
何度行ってもダメでした。
その武士はなぜダメなのか考えました。
結果判ったことは、自分が履いている右の下駄が斜めにすり減っていたことです。
足を挫いていてそうなっていたのです。
武士は下駄を新しくし、再度入山の許しを乞いました。
すると今度は許されたそうです。
心のあり方が履物に表れるという話です。
私はこのような話を聞いていたせいか、靴に目が行くようになったのではないかと思います。
ちなみに私の靴は私が磨いています。
私が靴を大事にしているという訳でなく、してくれる人がいないだけです。
新婚の時はしてくれたのですが・・・
企業人講話
昨日札幌市内の公立高校へ行ってきました。
1年生向けの「企業人講話」の講師としてお話しました。
今年2年生になり、これからの進路を決める上で民間企業人の話を聞くという趣旨の様です。
母校も含めて高校の校舎に入ったのは卒業以来です。
まず驚いたのは、すれ違う生徒のほとんどが「こんにちは」と声を掛けてくることでした。
私の高校時代そんなにチャンとあいさつしたかと思ってしまいます。
この高校は公立高校にもかかわらず「普通科」の他に「デザインアートコース」があります。
公立で「デザインアートコース」がある高校は、北海道では他にないのではないでしょうか。
案内された校長室には、「写真甲子園」や「はんが甲子園」に出品し優秀な賞を得た作品が飾られています。
「講話」は体育館の様に大きな講堂で話しをしました。
時間になると1年生が自分の椅子を持参して入ってきます。
講堂には最初、椅子がなかったので、昔の様に「体育座り」をするのかと思っていました。
今回の講話の依頼は去年から話がありました。
私は今まで大人向けに起業に関する話はしてきましたが、学生や高校生への話は初めてです。
「何を」「どのように」話をすればいいか大分悩みました。
結果、やはり起業・創業への関心を持ってもらうような話をしました。
「起業・創業は自分達にも出来るかもしれない」「将来社長になるのもいいな」と思ってもらうよう話をしました。
話が伝わったかどうか分かりませんが、50分間の講話の最中、居眠りをしている生徒はほとんどいなかったようなのでそれなりに納得しています。
日本には社長が270万人、就業人口中3.5%が社長です。
昨日話を聞いてくれた1年生は320名ですから、その3.5%の約12名は計算上社長になるはずです。
何人でも私の話を聞いて、社長になると思ってくれた生徒さんがいれば嬉しいです
10年後20年後どうなっているでしょうか
廃用症候群
前回は「東日本大震災から見た誰もが暮らしやすい仮設住宅」という講演の話を書きました。
今日はその続きになります。
大震災が起き、それを逃れて最初に入るのが第1次避難所です。
その次に仮設住宅に入る人が多いようです。
講演をされた菊地氏は理学療法士ですので、住民の健康状態にも関心を持って対応したそうです。
その中で健康だったお年寄りが体調を崩していくケースが多くみられまたと話していました。
そのような症状は「廃用症候群」といいます。
「廃用症候群」とは、何かの事情で身体を使うことがなくなると、筋肉が萎縮し関節が固まってしまう状態のことです。
そしてその症状は意外と速く進行してしまいます。
何もしないでいると筋力低下は、1週目で20%、2週目で40%、3週目で60%になって行きます。
また、この筋力低下を回復させるためには意外に長くかかります。
1日間の安静によって生じた体力低下を回復させるためには1週間かかり、1週間の安静により生じた体力低下を回復するには1か月かかると言われています。
災害を受け避難した人達は、気力も体力も落ち込み、何もする気が無くなっています。
何もすることも無く、体育館などでただ横になっていることが多くなります。
でも、手伝いをしてくれるボランティアの人達が来てくれます。
食事なども作ってくれます。
洗濯もしてくれます。
若い人達はまだ外に出歩くことが多いでしょうが、お年寄りや障害者は動くことがほとんどないようです。
「廃用症候群」になりやすいのはお年寄りや障害者です。
この「廃用症候群」にならない為の仕組み作りも支援活動に組み込まれる必要があると思われます。
何もしない状態が続くと、若い人も身体ばかりでなく精神的にも弱くなります。
食事作りや洗濯などは日常的なことは自分達でするようにします。
支援する側は、避難した人達が自分達の出来る仕事を作って上げ、生きがいを見つけるサポートに力を入れるようにするのです。
本当の復興とは自立して、元の生活、それ以上の生活が出来るようにならなければなりません。
その為の支援こそが本当の支援です。
無条件で優しいばかりがその人のためでは無いと思います。
言うのが辛くても、時には「叱咤激励」も必要かもしれません。
仮設住宅
昨夜は「北のユニバーサルデザイン協議会」のセミナーに行って来ました。
セミナーの題名は「東日本大震災から見た、誰でもが暮らしやすい仮設住宅とは」
札幌市で介護センターの所長をし、現地に5回ボランティア活動に行った菊地氏が講師です。
彼は理学療法士でもあります。
理学療法士として見た仮設住宅で暮らす不便さを話してくれました。
彼が撮った写真で見ると、仮設住宅はお年寄りや身体が不自由な事ばかり。
また、寒地に建つ住宅としても不十分でした。
お風呂では浴槽のフチが高く、足を持ちあがるのが大変。
また家中が段差だらけです。
床には畳がなく、窓も1重のため結露がひどい状態。
今、それは後工事で解消されつつあります。
地震国日本では、万が一の時には何万棟という数の仮設住宅が必要となります。
阪神大震災の時も同じ問題がありました。
今後も大きな地震が起きると予想されています。
こらからも必要とされる仮設住宅は、住む人のことが考慮される「ユニバーサルデザイン思想」に基ずいた設計がなさらなければならないと感じました。
また、仮設住宅の建築コストは1戸当たり400万円かかると言われます。
少しかかり過ぎです。
あらかじめコスト計算された設計に基づいて概算も用意しておく必要もあります。
今のままでは建築業者の言うがままの工事費がかかります。
時には「火事場泥棒」的に儲けている業者もいるかもしれません。
仮設住宅は法律では2年の使用です。
阪神大震災の時は特別5年でしたが、それでもその後は多くが廃棄されます。
改めて書きますが。建築費は1戸当たり400万円、撤去に100万円かかるのです。
廃棄されてはもったいない話です。
その費用が無駄になる事を考えれば、一部は仮設住宅を建てるより、民間のアパートを斡旋し、その費用に充てる方がいいのではと考えます。
災害への備えは、そのところまで考えると復興の費用も、スピードもが早いはずです。
このセミナーは色々考えさせられるお話を聞くことが出来ました。
今日は節分
今日は節分。
子供が小さい頃は、節分の日はなるべく早く家に帰りました。
夜遅くまで外にいると鬼になると子供達に言われるし、また家長として豆撒きをしなければなりませんでした。
北海道で撒く豆は落花生です。
本来は大豆なのでしょうが、東北以北はほとんど落花生の様です。
雪国なので、豆が雪に落ちても食べれるようにと思ったからでしょうか。
我が家では落花生の他に、小袋の飴やチョコレートも入れ、撒きました。
家中の電気を消し、窓や玄関も開け、また念のためトイレの蓋も閉まっているかを確認して始めます。
私が豆を撒くと、子供達は床に這いずりまわって、豆、飴、チョコレートを取り合います。
小さい子はお姉ちゃんたちに先に取られ、泣きべそをかきながら豆を探します。
豆撒きが終わると、それぞれ子供達がどれでけ取ったかを比べ合い自慢会。
小さい子は勿論少ないのですが、お姉ちゃんたちが自分のを分けて上げ、最後は皆満足で終わります。
豆撒きは長女が高校生になっても続けていました。
親になった私の子供達も、節分には自分の子供に同じことをすることでしょう。
豆撒きは子供たちの大きな声と笑いで鬼を追い出してしまいます。
今私達は夫婦2人の生活。
もう豆撒きはありません。
今日の夜も会合があり遅くなる予定です。
鬼にならないようにします。
今日は帰ってから夫婦二人で北北西に向かって恵方巻を食べる予定です。
本屋について
先日、馴染みの本屋に行きました。
その前に行ってから10日位しか経っていないのに、店の中が全く変わっていました。
いつも真っ先に行く新刊コーナーもいつものところにありません。
本を探すのに大変苦労しました。
そこで、本屋はなぜ本の位置変更するのだろうかと素人ながら考えました。
1、販売本の種類を増やすため。
2、ある種の本を隠すため(アダルト本等)
3、万引き防止のため。
4、本を分野別に分類するため。
5、店員さんが単に変化を求めたから。
等考えました。
一番可能性が高いのは「店員さんが単に変化を求めたから」だと邪推?します。
どちらにしても、行きつけの本屋の本の位置を変えられるのは常連としては困ります。
どこにどのような本があるか、というのがすぐ分かるから行きつけになるのです。
以前、仕事で色々な街に行きました。
その街に行くと、仕事の合間に必ず本屋を探します。
そして本屋に行くとその地域だけの、普段出会えない本を見付けることがあります。
また、本屋に置いている本の種類によって、その街に住んでいる人の様子が感じられます。
会社の多いところはビジネス書。
学生は多いところは漫画やIT関連の本(学術書も少し)
住宅地では趣味やグルメ本。
私の独断ですが、その街に本屋があるか無いか、また本屋の規模によってその地域の住民の「民度」が分かると思っています。
本屋はその地域の「民度」をはかるバロメーターだと思います。
そして本屋はその地域の「知識発信所」だとも思っています。
時として、ある本との出会いでその人の人生が変わることがあります。
そう考えると本屋の存在意義は高いモノです。
現在、本はアマゾンで簡単に買えます。
でもやはり本屋は私にとって無くてはならないものです。
それにしても行きつけの本屋の本の配置に慣れるまでしばらくかかりそうです。
今日は一日(ついたち)
今日は1日(ついたち)。
今朝は5時に起き、琴似神社と北海道神宮へ行き参拝してきました。
朝早かったこともあり、1日にしては参拝者は少なかったです。
北海道神宮で参拝すると、参拝する横にまだ「撤下塩(おさがりしお)」がありました。
いつもは既に無くなっているのですが、今月は珍しくありました。
他の参拝に来ていた人達も喜んでいただいて行きました。
勿論私も。
今月2月は私にしては予定が結構入っています。
中旬には妻と伊勢神宮にも行く予定です。
神社や神宮で参拝する人を見ていると、ズーと熱心に祈り続けている人がいます。
何か心配事があるのでしょうか。
一度奇妙な参拝者を見たことがあります。
梵字のたすきをした人がお経を読んでいるのです。
参拝口の端の方で小さな声でお経を読んでいました。(確かお経だと思います)
神教と仏教とは何かつながっているのでしょうか。
神宮寺というものが奈良時代に建てられています。
日本の宗教の大らかさを垣間見た様な気がしました。
何にしても1日に神社に参拝に行くというのはいいものです。
益々清々しい気持ちになります。
パワーをたくさんいただいたような気がします。
今月もいいことが沢山ありそうな予感がします。
さあ、今日も頑張ります!
自分の成長 他人の成長
アメリカの会社GEの元最高経営責任者ジャック・ウェルチの言葉があります。
「リーダーになる前は、成功とはあなた自身が成長することだった。
ところがリーダーになった途端、成功とは他人を成長させることになる」と言っています。
本当にそうです。
仕事で優秀な成績を上げた人が起業して社長になった時、一生懸命稼ぎます。
しかし、それより大事なのは、いかに従業員に働き・稼いでもらうかです。
その時、優秀な成績を上げた社長は往々にして、自分の尺度で人を指導しようと思います。
同じレベルの仕事を要求します。
勿論時には厳しい指導も必要です。
ただ、自分が仕事を通して成長した過程を、そのまま他人に背負わせてはいけません。
部下が自分と同じことが出来ないことが許せないと思うと、人は育ちません。
重要なポイントは、自分の狭い許容量を自覚し、一度、部下のレベルまで下がって見ることも必要です。
「なんでそんなことで悩んでいるのか」という上から目線でなく、共に考える「共感」「共有」の気持ちが無ければなりません。
そのような中で人は育ちます。
いつかその部下が社長の右腕となる人に成長するかもしれません。
自分の成功だけを願う「利己」から他人の成長を願う「利他」の心にならなければ人は育ちません。
「良きプレーヤーは良き指導者にあらず」と言われます。
素晴らしい活躍をした野球選手も優秀な監督になるとは限りません。(勿論例外もあります)
自分を管理することは出来ても、他人を管理をする事の難しさ。
成功した会社の経営者が必ず通ってきた道です。
海陽学園
今朝の新聞に海陽学園のことが掲載されていました。
大分以前の報道で、変わった学校が出来たということは知っていました。
その第一期生が今年高校部を卒業するということです。
Wikipediaによると2006年に全寮制の中高一貫制男子校として設立され、トヨタ自動車やJR東海、中部電力などの中部地方の有力企業が中心となり設立され、開校しました。
「将来の日本を牽引する、明るく希望に満ちた人材の育成」を謳い、イギリスのエリート育成校「イートン校」の日本版です。
この高校の寮には教員の他に各企業から男性若手社員が派遣され、生活を共にしています。
寮での生活は厳しく、携帯電話・ゲームは禁止、テレビも寮に一台のみ。
その厳しい生活になじめず1期生は120名中20名が転校したそうです。
大手企業各社から派遣された社員は「フロアーマスター」として生徒と生活を共にします。
「企業の協力をもとにしたキャリア教育」がこの学校最大の売りです
日本の教育は戦後一貫して「平等」という言葉のもとで、このようなエリート教育は避けられてきました。
教育に関しては色々な考え方があり、ともすれば論争の元になりがちです。
ですからここではあまり深入りしません。
ただ、私はこのような教育もあっていいと思っています。
差別教育と思う人もいるでしょうが、区別教育だと思います。
職人を養成する学校があってもいいと思います。
芸術家を育てる学校もいいです。
今までは考えられていた「平等」という言葉は、「同一」と混同されていたように思います。
金太郎飴の様な人を作ることが平等ではありません。
私の友人で一般企業の幹部社員から転身して公立高校の校長をしている人がいます。
彼の話では学校の中では一般社会と違った常識があると言っていました。
将来、社会を担っていく子供たちに正しい思考、判断力、生きる力を身に付けさせ、送り出していくのも学校の役目です。
今年初めての卒業生を出す海陽学園。
3月には有名大学に何人入ったかなどの基準で評価されるでしょう。
でも、どの大学に何人入学したかより、その後どのような仕事を成したのかが大事です。
この学校の本当の評価は10年後、20年後になって出てくるものでしょう。
話すより聞く
昨夜は久しぶりに妻と2人、自宅でお酒を飲みながら食事をしました。
子供たちの話や、亡くなった両親の話しが中心でした。
妻は私と2人で話をする時は自由に意見を言い合います
でも私以外の人とはあまり自分の意見を言いません。
昔からそうです。
意識してそうしているわけでは無いようです。
でも結局人からは、話を良く聞いてくれるとても「いい人」と思われています。
確かに「いい人」なのです。
一般的に、聞く事に徹していると「いい人」だと思われるようです。
コミュニケ―ションの基本は、「話す」より「聞く」ことだと言われます。
自分の意見を言うより、聞く側に立つことで、その人の評価が上がるようです。
カウンセラーの仕事もひたすら「聞く」事に専念する仕事だと言われます。
合コンの時も、しゃべる人より人の話を黙って聞いている人の方がモテるそうです。
話をしている人にとって、相手が黙って聞いているのであれば、自分を理解してくれていると思ってしまいます。
反対に聞く側はどうでしょう。
「聞く」というのは意識しなくても耳に入ってくる状態です。
そのような時は、時折大事な言葉をも流してしまうことがあります。
本当は「聴く」というように、注意して聞き耳を立てる状態でなければならないのでしょう。
「無意注意」ではなく「有意注意」でなければなりません。
妻は人の話をチャンと「聴いて」います。
私の場合、自分を振り返ってみると、私は話す方が多く話し過ぎです。
自分の意見ばかり押し付けているようです。
ですから「いい人」とは思われていないでしょう。
今日書いたことは他の人に向かって言うことではなく、自分への自戒です。
でもなかなか直りません・・・
自力で生きる術(すべ)
数日前に日本の貿易収支が赤字になったと新聞報道があり、このブログでも取り上げました。
若干その続きになります。
日本は長い間、給料も上がっていません。
私の若い頃は毎年10%以上ベースアップしていたと思います。
現在日本の役員・社員の平均給与は400万円程度と言われています。
しかし、中小企業の平均は300万円でしょうか。
今は給料は上がらなくても、デフレだから何とか生活が出来ています。
これがインフレになると大変なことになります。
先日ある本を読んでいた時に紹介されていたことです。
日本を代表するトヨタ自動車の従業員の平均給与は年間580万円だそうです。
やはり大企業です。
その給与を1ドル80円で計算すると、72,500ドル。
アメリカの代表するGMの平均給与は38,000ドル。
2倍違います。
韓国の自動車会社と比べると5倍違うとも言われています。
トヨタの給与が高過ぎると言えばそうですが、日本を代表する会社がこの位もらっていなければ、それ以下の会社の給与はもっと低くなります。
ただ、トヨタの様な輸出企業にしてみれば、海外の企業との競争の中、高い人件費、高い法人税、高い製造コストを考えると海外移転が一層進めざるを得なくなります。
そうすると益々貿易収支が赤字になり、2~3年後には経常収支まで赤字なる恐れがあります。
そうなると円安⇒インフレです。
生活する上で大変厳しくなります。
これからは各自が自力を付け、お金を稼ぐ術を身に付けなければなりません。
昨夜から「身の丈起業のすすめ」という講座を始めました。
以前にもこの講座のことは紹介しました。
今回で3回目の講座になります。
身の丈でもいいから起業し、自分でお金を稼ぐ方法を学ぶというものです。
15名の参加者のうち男性は5名、女性が10名です。
女性の方がよりパワフルな考えで将来を見据えているのでしょうか。
参加者の期待に応えるよう5回の勉強会、頑張りマス!
人たらし
ある本に「デキる起業家はモテます」と書いてありました。
なぜかというとそれは、人の心をつかむのが上手だからです。
「なるほど!」と思います。
◆人を喜ばせるのが上手い。
◆人の話をしっかり聞く。
◆気配りが出来る。
◆人の良い面を見付けるのが上手い。
◆些細な心の変化に敏感に対応できる。
◆落ち込んだ時には勇気付けてくれる。
このようなことをされると、その人を好きになってしまいます。
「人たらし」の名人です。
そしてこれはそのまま女性の心をつかむプレーボーイ(最近は言わなくなりましたが・・)のテクニックです。
女性の場合は男性より、より繊細な心配りが出来ると思います。
以前当社にいた女性の常務は多くの社員から、そしてお客様から好かれ、信頼されていました。
彼女はまさにこの行動そのものを意識無くこなしていました。
その上、数字に強く、頭の回転も早く、物事の状況をつかむのに優れた人でした。
ですからその常務と打合せをしても話の展開が早いのです。
また話をしていても、気配りがあるので、心がなごみ、何でも気楽に話してしまう気になってしまいます。
まさに「人たらし」の名人でした。
最近は男の人でも女の人でも自己主張が強く、自己アピールばかりする「バリバリ」の人が多いようです。
頭の回転も良く、能力も高いのですが、「いまいち」と人がいます。
そのような能力の高い人がこの「人たらし」を身に付けると「大化け」するはずです。
でも残念ながら、頭がいい人は往々にしてそれに気付かないのです。
「素直であれば分かるのに」と最近感じています。
ストーカー心理
先日街の中を歩いている時、フッと思ったことがあります。
人の成功心理とストーカー心理が似ているのではないかと。
人の脳は錯覚と現実との区別が出来なくなることがあります。
過去に起きた出来事も、いつの間にか自分を美化するような思い出にしてまうことがあります。
そしてそれが本当にあったと信じてしまうのです。
ストーカーは人を好きになった時「自分がこれほど相手のことを好きなのだから、相手も自分のことを好きなはず」という思い込みに陥ります。
相手の行動や思いは全て自分に都合のいいように解釈します。
このような妄想による思い込みを心理学的には「妄想性認知」というそうです。
昔あったテレビドラマの「101回目のプロポーズ」の主人公の武田鉄矢はストーカーの1人だと思います。
この「妄想的認知」をストーカー等の犯罪に使うのでなく、成功するための手段に使っている人はいるのではないでしょうか。
「自分は成功するのが当り前」「失敗などするはずがない」「失敗したことがないから反省もしたことがない」「いくらうまくいかなくてもネバーギブアップ」と思う人は時々います。
意識しなくてもそのような心理状態でいれるのです。
一見無神経で自己中心的な人に見えるかもしれませんが成功者に多いパターンです。
一般の人はそのような心理状態になるため、「ツイている!」とか「おまえは出来る人間なのだ!」言って自己暗示を掛けたりするのでしょう。
一方、ストーカーと言われる人はその心理になりやすい人なのです。
その心理を犯罪ではなく正しい方向に持っていけば、成功者と言われる人になれるのではないでしょうか。
人は1人1人性格も性向も違います。
そして人から欠点と言われる自分の性格・性向も時として、プラスに生かせて長所と変換することが出来ます。
先日歩きながらそんなことを思いました。
若い社長達
昨夜は稲盛和夫さんが主宰する盛和塾札幌の総会・新年会がありました。
まずは総会をし、新年会が始まりました。
会が盛り上がってきた頃から、司会から指名を受けた者が今年の抱負を語ります。
会社は違っても同じ稲盛哲学を学ぶ者同士と言うこともあって、自社の数字を具体的に上げながら話をしていました。
最近は30代40代の若い社長達が多くなりました。
彼らは勢いがあり、力強い宣言も出ました。
その中である若い社長が新製品を紹介をしました。
その会社は北海道中標津町(なかしべつちょう)にある「株式会社標津羊羹本舗」と言う会社です。
中標津というところは北海道の東の方に位置して、根室に近い町です。
車で5~6時間かかるので、盛和塾の勉強会に参加する時は仕事に合わせ泊りがけになります。
その中標津から札幌まで盛和塾の勉強に来ているので、経営に対する意気込みは大変なものです。
その彼は地元の乳製品と和菓子と組み合わせた新製品開発を続けてきました。
その思いの結果「牧場まんじゅう『みるく』」というお菓子を作りました。
新年会に参加した人達に配られました。
私も食べましたが、大変美味しかったです。
見た目は普通のまんじゅうですがその案は濃厚なミルクの味がし、餡とミルクが絶妙にマッチしています。
機会がありましたら是非食べてみてください。
千歳空港でも売っているそうです。
この会社は通信販売もしていますが、このまんじゅうは新製品なのでまだ売られていないようです。
株式会社標津羊羹本舗HP:http://shibetsuyoukan.com/
今日のブログは何か宣伝になってしまいましたが、若い社長が頑張るその勢いに押されて書いてしまいました。
これからも若い社長たちを応援して行きます。

買い手の気持ち
人がモノを買う時、何がその決断を促すのでしょう。
多くの人は無駄なモノを買わないようにしようと思います。
価格の高いものであれば、本当にいいモノなのか、宣伝していることは本当なのだろうか、愛着を持ち長く使えるだろうかを考えます。
「買って後悔しないのか」が大きなポイントです。
その為に雑誌を見たり、インターネットでそのモノの評価を探したりします。
モノを買うのとは違いますが、先日は「食べログ」での投稿が問題になりました。
となるとインターネット上の評価もあまり当てになりません。
やはり身近の知人の評価を一番信頼することになります。
同じようなモノを買ったことがある人に聞くことで、そのモノへの評価が大きく左右されます。
しかし、もしも知人の中にも買った人がいなければ、どうします?
最終的には「エイ!ヤー!」と言って思い切って買ってしまうのかもしれません。
皆さんもその様なことは経験したことがあるのではないでしょうか。
モノを買おうとする時、多くの人はそのように悩んでいます。
ところが今度自分が売り手になった時、その買い手の思いを忘れている人が多いようです。
お客様は悩んで悩んで買うその気持ちを思いやることなく、接客している人がいます。
折角高いモノを買おうとしているのに、安いものをすすめたり、その店の売り筋を押しつけたりします。
悩んでいるお客様がお店に来た時は、その気持ちをそのまま受けることが大切です。
「なかなか決められないですよね。」と一言言葉を掛けて上げるだけでお客様の心をつかむことが出来ます。
「あなたの味方」「あなたの良きアドバイザー」という思いをお客様が感じていただければ、仕事はスムーズにいきます。
お客様はモノを買う時、自分は「間違いない選択をした」と思いたいのです。
その時「いい選択をしましたね」と背中を押してくれる人が欲しいのです。
お客様が買うか買わないか迷っている時は、買う気持ちが8割以上あるのです。
その時あなたの判断は間違いないですよと言っていもらうと安心して買います。
勿論その時売り手は、本当に知識と経験が豊富でなければ信頼は得られません。
このようなのとはすべての商売で言えます。
なじみの店とは良きアドバイザーがいる店であり、結果、足しげく通うことになるのでしょう。
形見分け
母が昨年亡くなり、形見分けをしました。
父が亡くなった時、私は父の時計とネクタイをもらいました。
服やシャツ等は寸法が合わず使うことが出来ません。
母の形見分けはどちらかと言うと妹たちの管轄なのかもしれません。
それでも私も形見分けとして茶道の茶碗を2個もらいました。
形見分けするというには意味があると私は思っています。
単なる財産分けではないです。
亡くなった人を忘れないためのものです。
いつも身に付けて、時あるごとにその人を思い出すためのものです。
父が使っていた時計はハッキリ言って私の趣味ではありません。
金色のその時計よりは、その前に私がしていた手巻きの腕時計の方が好きです。
でもあえて、いつも手首に巻いています。
少しシミの付いた使い古しのネクタイも使っています。
父のことを忘れなければ父も喜ぶでしょう。
そして、何かあった時、父はどう考えたのだろうかと思うことが出来ます。
父は欠点もありましたが、人間としても事業家としても尊敬していました。
ですから、何かあった時その腕時計に触ると、父の考えに立ちかえるキッカケになります。
形見を身に付けるのはそのためです。
いつも父に見られているようです。
母の形見分けは、やはり女性のものばかりで身につけるものはありませんでした。
それでもお茶碗をもらいました。
今度は母を偲ぶためにも、お茶をたててみようと思います。
2つありますから1つは自宅、1つは会社に置いておきます。
茶筅を回し、ゆっくりお茶を味わってみます。
母は生前、時々私がたてたお茶を、「お前がたてるお茶は美味しいね」と言って飲んでくれました。
やはり形見はその人を思いやる品物なのですね。
日本の貿易収支
昨夜は3人の仲間の勉強会をしました。
その中で日本の経常収支や貿易収支のことを改めて学びました。
その勉強の内容少し紹介します。
2011年度上期の経常収支は前年同期比46.8%減の4兆5196億円に半減しました。
東日本大震災の影響で自動車などの輸出が急減速して、貿易収支が赤字になったのが大きかったようです。
2011年上期は、自動車などの製造業の混乱で輸出が伸びなかったのと、原発停止に伴い、火力発電所の燃料の需要が増加したことが大きな要因です。
その為貿易収支は1兆2517億円の赤字になりました。
前年同期は4兆145億円の黒字です。
日本は貿易立国で、貿易収支は常に黒字でそれなりの伸びがあると、私は思っていました。
しかし、実際は違います。
経常収支の主なものは貿易収支と所得収支、それと赤字となっている経常移転収支とサービス収支の合計です。
経常収支は過去増加傾向にありました。
しかし肝心の貿易収支は、ほぼ毎年減少しているのです。
伸びているのは所得収支です。
2000年と2010年を比較してみます。
経常収支は12兆8755億円が17兆1706億円になり4兆2951億円の増加です。
貿易収支は11兆3719億円が7兆9789億円で3兆3930億円の減少です。
それに比べ所得収支は6兆5052億円が11兆6977億円となり、5兆1925億円の増加です。
所得収支とは外国から得た利子・配当や賃金などと、外国へ支払ったそれらなどの差額です。
また、2010年度の貿易収支が7兆9789億円だったものが、2011年の上期だけですが1兆2517億円の赤字になったということは大変なことです。
原発が停止になり、東京電力だけで燃料輸入が8000億円膨らむとなると、日本の9電力会社合計では何兆円にもなるのでしょう。
そして、企業も海外移転が急増しています。
これからは貿易収支赤字が続くのかもしれません。
所得収支のおかげで経常収支は黒字を保ちますが、所得収支は一部の個人や会社の収入で、あまり世の中に回ってきません。
国際価格が上昇している燃料価格も円高のお陰でまだ押さえられていうほうです。
1ドル100円位であったらもっと大変のことになっています。
昨夜の勉強会は良き社長を目指す社長の勉強会でした。
社長として日々の自社の経営ばかりでなく、世の中の動向、特に日本経済の先行きについても感心を持たなければなりません。
時にはこのような勉強会も必要だと考えています。
起業仲間
先日飲み会がありました。
私はいつも飲み会が多いのですが、この飲み会は以前私が講師をした「身の丈起業のすすめ」を受講された方々です。
皆さんはまだ起業はしていませんが、起業に興味ある人達です。
色々な話が出て盛り上がる中で、ある人の特技が分かりました。
書が上手く、書道4段ということです。
そこでその特技を生かして週末起業をしたらいいという話になりました。
色々なアイディアが出ました。
それを「ビジネスプラン」にするということまでなりました。
参加者は皆起業に興味を持っていますから当然です。
それで来月くらいには再度私の事務所に集まってビジネスプランを作り上げることになりました。
この書道をする女性のように、人知れず何か優れた特技や才能を持っている人は多いと思います。
それを本人に気付かせ、引き出して上げることが大切です。
以前にもブログで紹介しましたが、同じ「身の丈起業のすすめ」に参加していた女性は小説内容を紙芝居にして来ました。
起業したいと思う人は何かに挑戦している人です。
趣味を深めたり、興味あることを勉強したりしています。
飲んでいた同じ仲間の男性は私と同じ62歳ですが、韓国語に挑戦していて、日常会話は大丈夫だそうです。
その会話力で、観光ボランティアや韓国に行くツアーに同行してお手伝いをすることも出来ます。
色々なことに興味ある人達と共に酒を飲み、お互いの起業を応援する、そんな仲間作りはこれからもして行きたいと思っています。
もしかしたら近い内に皆で韓国旅行もあるかもしれません。
世界の政治経済
最近、経済関連の本を何冊か読んでいます。
欧州の経済混乱、アラブの春と言われる民主化運動、イランや北朝鮮の核問題、勿論日本の肥大化する国債高など世界中に経済を混乱させる爆弾を抱えています。
その状況の中で書かれている本の内容は様々です。
日本に関して言えば、今後益々円高になり1ドル50円台になるという人もいれば、逆に一気に円安になり150円位になるという人もいます。
それぞれの理論には裏付もあり、それぞれ納得させるものがあります。
ただ今の世界情勢をみると、どの予測を持っても思いがけない、想定外のことが起きる時代です。
ホルムズ海峡がイランにより閉鎖れれば、この海峡を通る石油タンカーは止まる恐れがあります。
日本の石油の80%はこの海峡を通っています。
一番影響を受けるのは日本です。
現在、ドイツ・アメリカ・日本の国債が買われているという報道がありますが、この海峡で紛争が起きれば日本の株も円も国債も一気に下がる恐れがあります。
中国の経済も落ち込んでおり、また情報としては共産党と人民軍との確執も表面化しているという話も聞きます。
また、日本の国債発行額が1000兆円を超えるとなると、海外からの国際評価が低下し、金利アップになるかもしれません。
何か一つの波紋が世界上の政治・経済を震撼させることも起きえます。
今、私が一番気をもんでいるのは日本の国債発行の増加です。
今年は世界中で大統領の選挙があります。
日本も総選挙があるという予想もあります。
選挙の時は政治家は「〇〇をします。□□もします。」とお金の出る話ばかり出してくるのではないでしょうか。
日本の税収が40兆円ほどしかないのに、支出は80兆円以上。
それにプラスして支出を増やすことになるのか。
もうそろそろ政府や役所頼りはやめなければなりません。
国民が1人1人自立する気構えがなければ、いつでも政府や役所に「オンブに抱っこに肩車」のままです。
社会保障費用も年間75兆円のうち40%が赤字国債で賄われています
40%と言えば30兆円です。
消費税を5%上げても10兆円の税収にしかなりません。
これからは社会保障費も聖域ではなく見直しされる必要があります。
優しいことはいいことだと思われてきました。
でも、そろそろ現実を見据えて、厳しいことを言い、指導する政治家が出てこないと、近い内に日本もデフォルテになるかもしれません。
心しておかなければなりません。
限られた情報の中でも、刻々と変わる世界情勢と、日本の政治・経済を見て、自分なりの予想を立てるのはいい勉強になると思います。
鹿の角
先日知人が来社し、鹿肉の缶詰をいただきました。
売られているのは一部の道の駅だけだそうです。
1缶600円ほどと少し高いです。
その知人はあるところから鹿肉を利用した商品開発、販路開拓等を任されています。
来社された時、相談が1つありました。
鹿の角の利用法です。
鹿の角を使った刀掛とかは映画で見たことがありますが、それ以外で利用したモノはあまり見かけません。
ただ漢方薬としては鹿の角は利用されています。
鹿茸(ロクジョウ)と言って強壮、強精、長寿の薬として使われます。
成長途上の柔らかい角を干したもので、角が伸びきると薬効がなくなってしまうそうです。
しかしこれも薬事法上の問題もありそう簡単ではありません。
簡単なのはアクセサリーでしょうか。
北海道土産を目指して開発するのが、より現実的かと意見がまとまりました。
角の先を切ってアクセサリーにしたモノはもう既にあります。
そしてそれは鹿の角1本から1つしかとれず非効率的です。
鹿の角を輪切りにして数多く作れるものを考えました。
検討の結果2つほどアイディアが生まれ、今度それを試作することにしました。
まだアイディアの段階ですので、ここで書くことはできません。
製品化した時はお知らせします。
北海道は鹿の害が多く50万頭以上いると言われ、鹿による森林・農業被害が増えています。
北海道庁も駆除するように計画を立てていますが、なかなか達成できていません。
ハンターの数が足りないのが原因です。
計画的駆除が出来るようになれば、鹿肉を食肉流通の載せれるようになるようです。
ハンター育成はそう簡単ではありませんので、これからハンター学校の設立も必要になってくるかもしれませんね。
3女の帰国
ホンジュラスに行っていた3女が帰ってきました。
青年海外協力隊として2年間行っていましたが、無事任務終了して帰ってきました。
ホンジュラスでは視覚障がい者のための職業訓練校でマッサージの指導などをしてきました。
娘の後の後任者は日本の青年海外協力隊からは派遣されていないそうです。
でも、現地の人をそれなりの指導員として育ててきたようで、暫くは大丈夫だろうと言っています。
帰って来た時娘が私に「これからしばらくはお父さんの身体を直して上げる」と言ってくれました。
私の体は昔から硬く、前屈しても手が床に届きません。
年とともにより硬くなっていました。
その身体を3日前から1回1時間30分ほどかけて指圧をしてくれます。
その指圧はとても痛いのです。
でも我慢です!
2回治療をしてくれていますが、何となく体が軽くなったようです。
これから針や灸の治療もあり、少し不安もありますが、しばらくは素直な患者でいようと思っています。
授業料の高かった指圧・針・灸の専門学校へ行かせたお返しを8年ぶりにやっと受けています。
今月の末にはまたイギリスに旅立ちます。
もう充分自立してしてくれていますので心配はしていません。
それまでの間は娘の治療を受け、楽しいお父さん気分を味わいます。
誠実な応対
昨日のブログで小売店や飲食店での応対について書きました。
今日もその続きを書きます。
お客様への応対は目の前にいるお客様ばかりではありません。
お客様が目の前にいなくても、お客様への心使いは持ち続けるべきだと考えています。
バックスペースに戻った時とか、食事をしたりする時に、あるお客様の話になったとします。
その時に〇〇様と言えるか、せめて〇〇さんと言っているか。
つい〇〇と敬称を付けなく呼び捨てにしていることがあります。
それを目にしても上のものは注意せず、時には経営者自身がそのような話し方をすることがあります。
論外です。
お客様サービスが大切とか、顧客第一と会社の謳い文句にしていながら、経営者がお客様を呼び捨てにしては示しが付きません。
顧客第一は会社の建前としか受け取りません。
経営者・トップが常に有言実行してこそ、社員が見習うものです。
先日、知人の税理士さんが毎月送ってくれる「事務所通信」にいいことが書いてありました。
大丸創業者の下村彦右衛門が残した「主人心得の巻き」というものが紹介されていました。
「自分が規則に反しておいて、下の者に規則を守らせようとするのは、とんでもないことであり、そういうことはすべきでない。」
「主人たるものは、自分の方から誠実さをもって人を使うことが大切である。
主人は不誠実な気持で人を使っておきながら、奉公人には誠実を尽くさせようということがあってはならない。」
このように昔から経営者の心構えの大切さが問われて来ました。
小売店、飲食店のサービス評価は会社の経営者の姿をそのまま映すのでしょう。
私語の無い店
小売店や飲食店へ行った時、私語のない店はいい意味の緊張感があり、私は好きです。
逆に、店員の愛想が良くても、客から離れると店の隅の方で同僚と笑いながら何かを話しているのを見ると幻滅してしまいます。
大事なことは笑顔はお客様に提供し、店員同士はあまり笑顔で話し込まないことです。
店員同士が私語も無く、てきぱきと仕事をし、受け答えする時だけに笑みを浮かべるのは見ていて気持ちがいいものです。
このように店は最近少なくなりました。
店員同士がペチャクチャ喋っている店は、お客様が少ない店です。
お客様が少ないから暇で喋っているのか、そう言う店だからお客様が来ないのか。
どちらにしてもオーナーや店の責任者の責任です。
知人が経営する回転寿司店は常に行列が出来るほど混んでいます。
そこではほとんど私語しているのを見たことはありません。
勿論そんな事をしている状況でもありませんが。
そこでは社員教育が徹底していて、常にお客様に注意が注がれ、例えば疲れたからと言って、少しでも壁に寄りかかると叱責されます。
有意注意が徹底されています。
若い頃よく行ったバーもバーテンダー同士の私語はありませんでした。
お客様が手持無沙汰にしていると、スーと近寄り話し相手になってくれ、1人になりたい時は、飲物を作る時以外はソッとしてくれます。
常にお客様の機微を感じ取っていました。
残念なことにこのバーは昔、火事になり無くなりました。
これからは自分が気に入る「お店」や「バー」を探してみようかと思っています。
自分だけの居場所作りです。
ところでどなたか、いい「バー」知りませんか?
お客様が求めているもの
「江戸と上方の大工仕事を比べて、古くはこんなたとえ話があったそうだ。
『江戸は100人の手間がかかっているようでいて、じっと見ると80人の手間しかかけていない。
上方は100人のようでいて実は150人の手間がかかっている』」
これは今朝の日経の春秋に書かれていたものです。
江戸は見てくれにこだわり、上方は人の目の届かないところまで手を抜かず、仕事をするということを言っています。
上方の大工の方がいいということです。
私はこの春秋を読み始めた時、最初江戸の大工の方がいいと書いているのかと思って読み進めました。
でも、そうではなく上方の大工がいいという話になっていました。
私はどうしても生産性や効率性を頭に浮かべてしまうせいか、つい江戸の大工の方がいいと思ってしまったのです。
その時代、その人の考え、環境によって、この江戸の大工と上方の大工の評価は1つではないように思います。
宮大工と普通の大工とは求められるののが違いますから、別の次元の話になるでしょう。
モノを作る時、手を抜くことはダメですが、手を掛ければいいというものでもありません。
お金を気にせず、いくらでも手間を掛けることは出来ます。
しかし、経済性を考えた時には、如何に生産性を高めるかというのも大切なものです。
より良いものをいかに高率良く低コストで生産するか。
手間を掛けて、人件費が高くなり、コスト高になっても求めれてているのものが同じであれば、人手を掛けただけ無駄になります。
20年ほど前に中国の合板製造会社に視察に行きました。
幅広い機械で丸太をかぶらむきのように薄くはいでいました。
機械1台にかかっている人は5~6名位。
同行した日本の製造会社に人に聞くと、日本では2名位で作業するそうです。
中国の工場側の説明では、丁寧に仕事をしていると言っていましたが、単に人海戦術だったのでしょう。
人手を掛ければいいというものでもありません。
今は中国でも効率を求めて、以前のようではない様です。
求められている者が何なのか芸術性なのか、職人技なのか、それもと低価格なのか。
これを受ける側が整理して、お客様と折衝しなければ、お客様が満足できるものを作ることは出来ません。
時としてこれがトラブルの元になります。
北海道の雪道
北海道の冬は雪道のため車の運転が大変です。
2~3年前までは結構除雪が行き届いていました。
昔のように車の車輪が雪道のワダチに埋まって動けないということも少なくなりました。
雪道から抜け出すためのスノーヘルパーの使用回数も少なくなってきました。
ところが昨年くらいから札幌市の除雪予算が削減されたのか、除雪・排雪の回数が少なくなっているようです。
メイン道路はいいのですが、少し脇道に入ると除雪が不十分です。
昔のように雪道のワダチがひどくなっています。
その為か最近は4WDの車が増えています。
私の車も4WDですがワダチに入っても抜けれないということは無くなりました。
これから北海道に住む人にとって4WDの車は必需品なのかもしれません。
そんな北海道の雪道ですから、それなりのドライバーの心得があります。
雪道で埋まっている車があれば、車を後ろから押して脱出させたり、雪で狭くなった道路で対向車と出会った時は譲って上げたりします。
不便だからこそ「お互いさま」という気持ちが生まれ、優しい気持ちになるのだと思います。
雪道の埋まった車を後ろから押す時は、空回りする車輪が巻き上げる雪がもろに当たり、押す人は雪だらけになります。
それでも文句言わず押します。
皆見知らぬ人同士ですが、脱出出来た時は皆が笑顔になり、「良かった、良かった」と言って別れます。
私は今までそれが当り前だと思っていましたが、考えてみるとすごく優しい人達だったのです。
最近雪道が良くなり、そういう機会が少なくなったせいか、マナーが悪いドライバーが増えたように思います。
狭い道を我先にと進む車もいます。
その車が仕事の車で、会社の名前入だったらどうでしょう。
その運転手は気付かないのかもしれませんが、私の会社は「このような乱暴な運転をしていますよ」と悪宣伝しているようなものです。
逆に優しい運転をして、道を譲ってくれた時は軽く会釈をして行くと、その会社の名前を見て「いい会社だな。今度買う時はこの会社にしよう」と思ったりします。
会社の経営者もこのことに気付き、運転マナーを徹底している会社もあります。
北海道の雪道は色々の事を教えてくれます
妻の仕事場
多くの男性にとって家庭は安らぎ・憩いの場所だと思います。
仕事から疲れて帰って来た時、家に電気が付いていて、冬の夜は家中が温かく、子供の声がします。
独身男性が結婚したいと思う要因となる家庭への憧れです。
家庭が安らぎ・憩いの場所だというのは、私達男性にとってそれが当り前でと思っていました。
昨夜久しぶりに妻と食事に出かけ、そのような話をした時、意外な返事が来ました。
「妻にとっては家庭は仕事場でもある」というのです。
私の妻は専業主婦です。
共働きの夫婦では違うのかもしれません。
この思いは専業主婦の言葉なのかと思います。
妻にしてみれば、夫が仕事で家にいない間、掃除・炊事・洗濯・子育てと仕事ばかりです。
夫は仕事が終わり疲れたと帰ってきて、安らぎ・憩いを求めても、妻はまだ仕事体制です。
最近の優しい夫は食事の後かたずけなどしてくれるのかもしれませんが、私も含めある程度の年以上の人はあまり手伝いません。
「妻の仕事場は家庭だ」という視点は、妻から言われて改めて認識させられました。
この認識がないと軋轢が生まれます。
安らぎ・憩いを求めてくる夫と、まだ仕事体制の妻とは気持の上で差が生まれます。
この差を夫が理解して上げることが大切です。
そしてその仕事場から解放させてあげることです。
一番は外出させてあげることでしょう。
夫婦一緒に外出したり、友人と遊びに行く環境を作ることが解放させることになるのでしょう。
私達夫婦は結婚30年以上経ちますが、昨夜は新しい発見がありました。
若干?遅すぎましたけれど。
魔法使いの少年
昨日の新聞にACジャパン(旧称:公共広告機構)の広告が載っていました。
見た方も多いと思います。
「魔法使いの少年」という題名で文章が掲載されていました。
「押しボタン式の信号が赤に変わり、私は車を停めた。
『間が悪いな・・・』
その時突然、魔法を掛けられた。
横断歩道をわたり終えた男の子が、こちらに向かって、ていねいに頭を下げたのだ。
少年の『ありがとう』のおじぎは、私を、対向車の人を、一瞬にして笑顔に変えてしまった。」
この文章はACジャパン作文コンクールに応募してきた作文だそうです。
「魔法使いの少年」という文章は読む人を一瞬にして優しい気持ちにさせます。
このように信号をわたってお辞儀をする子は実際私も見たことがあります。
でもこの作文を書かれた人の様なピュアな気持ちが無かったせいか、これほど感動的な思いはしませんでした。
家庭の教えなのか、学校の教育なのか判りませんが、そのように教えてもらったことを、実行しているのでしょう。
教える側は教えてその通りさせる。
子供は理屈より、教えられた大切なことを実行する。
これが教育の基本です。
小さい頃に教えられたことは、その人格形成に大きな影響を与えます。
私も小さい頃、祖父から地獄の絵を見せられ、「悪いことをすると地獄に落ちるぞ」と言われ、夜は怖くて寝れなかったことを覚えています。
その後悪いことをすると地獄に落ちるという思いは常にありました。
「成功への9ステップ」などの本を書いたジェームス・スキナーさんは本の中に、6歳の頃母親に連れられて元ヘロイン中毒者のところに連れられて行かれたと書いています。
1回その悲惨な実態を見てしまえば、麻薬などに魅力を感じたりすることは無くなると書いていあります
これは母親の子への教育の1つです。
小さい頃に学んだことはその人の人生に大きな影響を及ぼします。
「鉄は熱い内に打て」と言われます。
改めて小さい頃の教育の大切さを教えられた新聞広告でした。
椅子が届きましたが・・・・
昨年末にオークションで椅子を買ったことをブログで書きました。
その椅子が5日に届き、ワクワクした思いで梱包を解くと、椅子の脚がねじ穴を中心に大きく割れていました。
届くのを楽しみにしていただけにショックでした。
販売会社に「善処願います」とメールをしたのですが、いまだ連絡がありません。
宅配便会社にも電話したのですが、何度電話してもつながりません。
椅子が壊れた原因は配達の段階で起きたと推測します。
椅子の梱包はしっかりされており、販売会社は充分な処置をして発送したと思います。
ネット上で見る写真も脚が割れているようには見えません。
配送中に落としたりして、大きな衝撃が加わったようです。
ですから販売会社へのメールも非難じみたような事は書かず、事実を伝え、どうするかを尋ねたのです。
それでも連絡がないのです。
改めてその会社がネット上で書いている取引の取り決めを見てみると、「家具が破損した時は送り返してください。代金と送料は後で返金します」と書いてあります。
この一文が書いているので返事もくれないのでしょうか。
ネット上で売買をする時、このようなトラブルはよくあるでしょう。
だからこそ顔が見えない分、いかに信頼を得るよう努力を続けなければ、商売は長く続きません。
売った後のアフターフローこそが、次へつながる重要な顧客管理になります。
このようなトラブルはありましたが、私はこれからもいいものがあればオークションで買い物をするつもりです。
この椅子は縁あって私のところに来たので、返却するつもりもありません
割れた脚は今日これから修理するつもりです。
実は私の趣味の中には「家具修理」もあります。
この程度の脚の割れはほとんど判らない程度に直すことが出来るはずです。
これから直す作業が楽しみです。

Simple is best
昨日知人が来社されお話をしました。
その中で、昨年は大変忙しかったという話になりました。
でも、その人の話では忙しいだけで、それに流されただけのようでした。
自分のために人が知人を紹介してくれるということが多くあったそうです。
その折角の話を無駄に出来ないと思い、色々な人に会に行ったけれど、結局それだけで終わって仕事には結び付きませんでした。
紹介してくれた人は本当にその人のためと思ったのでしょうが、結局振り回されてしまったのです。
このような事は私も数多く経験しました。
自分の為だと思ってくれている人の好意を断れないのです。
しかし限られた時間を無駄にしては仕事の成果は得られません。
まだ読んでいませんが「断・捨・離」という本が売れているそうです。
モノを「断・捨・離」することは出来ますが、人を「断・捨・離」することはそう簡単ではありません。
特に自分のことを心配してくれる人を切ることはできません。
そんな時大事なのは自分が何が重要なことなのか、何をしたいのかを明確にすることでしょうか。
それを簡潔にし、人に伝える力をつけることです。
自分を支持してくれる人に、今自分が求めていることを明確に伝え、それに沿った協力を依頼することです。
往々にして方向違いの支援をしてくれているのは、支援してくれている人が悪いのではなく、お願いをする自分の考え方、希望、ベクトルが明確でないからです。
年の初めに当たって、「断・捨・利」のごとく、頭の中にある思いを整理し、仕事を単純化することを始めるといいのかもしれません。
仕事の能率が上がります。
それにより自分の仕事を人に伝えやすくなります。
仕事にも「Simple is best」の考えは大事なことと思います。
仕事始めにあたって
今日から仕事始め。
久しぶりに事務所に来てみると、年末掃除をしたこともあり、いつもの朝と違い新鮮な気持ちになります。
年末に生けた花も蕾からきれいに満開になっていました。
真新しい1年を感じます。
それと共に、色々な人が言われているように、今年は大変革の年なのかもしれません。
大変革は決して楽なものではありません。
逆に苦痛を伴うものです。
でもその辛さに耐えなければ取り残されていきます。
昨日の続きが今日明日とは続かないのです。
理屈では分かっていても、今までの社会環境が激変するのに耐えられるか。
これは各個人にかかってくると思います。
企業そして国など、誰かが何とかしてくれるという思いは捨てなければなりません。
今朝の新聞に換金困難な外貨を売り付けられて被害を受けている高齢資産家の記事がありました。
昔から欲得で被害を受けた話はありました。
そのような自己防衛が出来なく、警察や国民生活センターに泣きつくのは、甘えでしかありません。
これからは多くのことを自分の責任で選択し、進まなければなりません。
もう人のせいにはできません。
若い人達の就職難が新聞等で取り上げられていますが、一方外国人の企業採用が大幅に増えています。
外国人の多くは必死に勉強し、経験を増やしキャリアをアップさせています。
「誰かが何かをしてくれる」のを待っていないのです。
これからは自己責任を問われる時代になるのではないでしょうか。
日本はありがたいことに今まで「おくるみ」に包まれ、守られてきました。
でもこれからは、世界中が大変革していく中で、日本だけ特別に守られる環境ではなくなります。
「おくるみ」から抜け出し、これから迎える厳しさに耐えれる身体作りをしていかなければ、取り残されていきます。
今年は私達1人1人が自立していく覚悟の年だと思います。
2つの回転寿司店
今、末娘が帰ってきています。
久しぶりの帰郷です。
東京では毎日質素な食事らしく、帰っていてすぐに「お寿司食べたい」と言いました。
それを聞いて親としては、「よしわかった。すきなだけ食べなさい」と言って近くの回転寿司店に連れて行きました。
行った回転寿司店は少し変わっていて、寿司が乗っている回転台の上にはほとんどと言うか全然お寿司がなく、席も前にあるタッチパネルを押して注文する方式になっていました。
注文した寿司は回転台の上に設置されたレールの上を走る舟に乗って運ばれてきます。
これはもはや回転寿司店でなく注文寿司店です。
指定された椅子に妻娘と一緒に座り、早速タッチパネルを操作し、好きな寿司を注文しました。
とりあえず15皿ほどを注文しました。
4~5分経ってからウニ、サンマ、シャコ、サーモンは流れてきました。
しかし後はいくら待っても流れて来ません。
しびれを切らして店員に話そうとすると、妻と娘が「いいからもう少し待とう」と言われ、そこにあるガリを食べ、お茶を飲んで我慢していまいた。
結局30分経っても流れてこなかったので店員さんに、「30分経っても4皿しか流れて来来ません。待ちきれないのでオアイソしてください」と言って席を立ちました。
店員さんは「そうですかすみません」と言って、皿を数え伝票を切るだけ。
この系列の回転寿司店は美味しいので評判だったのです。
でも私はこの店には2度と行かないと思います。
機械化して効率的にと思ってタッチパネル式にしたのでしょうが、お客様側に立ったサービスではなく、運営側に立ったサービス思考に問題があるように思います。
私達と同じような思いをしたお客も他にいたのではないでしょうか。
残念な気持ちです。
満足にお寿司が食べれなかった私達は次の日(昨日)別の美味しいと評判の回転寿司に行くため、札幌駅まで出て行きました。
ここはいつもお客が並び、必ず1時間ほど待たされるとことですが、昨日は運よく30分位で入れました。
前日食べれなかった分を3人で好きなだけ食べました。
ここはネタは新鮮で大きく、いつ来ても満足出来るお店です。
そこには職人さんや店員さんの活気ある声が響き渡り、その声につられお客も明るい気持ちになります。
2つの回転寿司店に行き、「飲食店もサービス業」という思いを改め納得させられました。
人が第一です。
美味しい寿司の中でも一番うまかったのは「タチの軍艦巻き」。(タチは鱈の白子)
機会があればぜひご賞味ください。
朝打三千暮打八百
私の部屋には10年以上前から禅宗のお坊さんが書いたと言われる「書」を掲げています。
それには「朝打三千暮打八百(ちょうださんぜんぼだはっぴゃく)」と書かれています。
禅宗の言葉で、朝から晩まで警策(警覚策励の略)という樫の棒で肩を叩かれまくります。
私は禅宗でもなくまた、座禅の経験もありませんがこの言葉が気に入って掲げています。
それは自らを鍛えることを意味しています。
自分の心はほおっておくと悪さをしかねない。
常に自分に厳しくあらねばならないという教えです。
この正月の間、つい気が抜けがちになります。
今年のするべき目標をもう少し詰めて考えなければならないのが進んでいません。
やはり「朝打三千暮打八百」は私に必要な言葉と、今改めて思い知っています。
お正月
昨日は元旦でした。
元旦は「何もしてはいけない日」と言われていました。
その為何もしませんでした。
いつもするラジオ体操もブログ書きも。
私の小さい頃、大晦日にいくら遅く寝ても、元旦の朝は父に起こされ、「若水汲み」をさせられました。
年の最初の水を男の手で汲み上げ、それでお雑煮を作ったりお茶を飲んだりするのです。
本来は井戸水を汲むのでしょうが、私の小さい頃は水道栓をひねれば井戸水が出てきましたからそれほど苦ではありまません。
今は完全に水道水なので若水という感じは薄くなりました。
元旦はお雑煮やお節料理を食べ、初詣に行く以外は家にいてテレビを見たり本を読んだりして過ごします。
「元旦には買い物をしてはいけない」と親から言われました。
「1年の計は元旦にあり」といわれるように、元旦からお金を使うと1年間お金ばかり使うことになると言われました。
また、「1年の計は元旦にあり」と言われるなら、元旦から習い事や勉強をすればいいのですが、そのようなことはしてはいけないことになっていました。
事始めは2日なのです。
2日に書き初めをすると字が上手になると言われています。
初めてお風呂に入る初湯も2日です。
元旦からお風呂に入ってはいけないと言われました。
色々な元旦のに決めごとは我が家だけの決まり事なのかもしれませんが、1年に1日くらい普段と全く違う生活というのも本当にお正月らしくていいものです。
このような我が家の決まりごとも私の子供達の代では薄れていっているようです。
昔は2日が「初売」「初荷」の時でした。
今は元旦からスーパーが開いています。コンビニもあります。
便利なのは良いですが、だんだん正月らしさが薄れていくのが少し寂しいです。
大晦日
今日は大晦日ですね。明日は正月。
とは言え、私のところは今年母が無くなったので正月はありません。
また、子供たちも皆東京だったり海外だったりで、今年の大晦日は夫婦2人だけです。
今まで必ず子供がいたり父母がいて、正月を迎えていましたので今年は少し寂しいです。
でも、久しぶりに夫婦2人もいいものです。
大晦日になるといつも子供の頃を思い出します。
お正月が明日に控え、お年玉が楽しみな上に、大晦日の夜はご馳走が出ます。
子供の頃はお寿司や刺身などはめったに食べれなく、甘いチョコレートもたまに買ってくれても、1枚を4人兄弟姉妹で分けて食べました。
それが大晦日だけは特別でした。
すき焼き、刺身、それに子供たちにはチョコレートがまるまる一枚、ゆで卵が1つ、羊羹や口取りのような甘いモノが載ったお皿が1人1皿ずつあたりました。
それが嬉しかったことを今でも思い出します。
母は子供たちが大好物なモノを年を越す大晦日だけは特別に用意してくれたのです。
1人1枚のチョコレートなんてこの大晦日だけしかもらえませんでした。
大事なチョコレートは、少しずつ口に入れ、決して噛まず、舐めるようにして食べました。
そんな子供たちの様子を母はニコニコして見ていました。
その母も9月に見送りました。
今年の大晦日は妻と二人で、父母に感謝しながら、そして子供たちの来年の幸せを思いながら過ごそうと思います。
仕事納め
昨日は私の運営するレンタルオフィス「札幌オフィスプレイスの」仕事納めでした。
15時から私の事務所で納会をしました。
10名以上の人が集まり、皆が持ち寄った飲み物や食べ物をいただきながら、色々な話が出ました。
同じオフィスにいてもなかなか顔を会わせる機会がなく「やあ、久しぶりですね」という言葉が出ました。
皆さんの話を聞いていると、仕事が順調な人が多く、私も嬉しくなってしまいます。
最近私の顔を見て大黒様みたいだといってくれる人が何人かいます。
ただ単に太って丸顔だからなのでしょうが、私のレンタルオフィスに入居されている人達を支援する立場としては、こらからもより強力に入居者の事業の成功を支援・応援していきたいと思います。
来年度はどのような支援の仕方があるか、この正月休みにじっくり練っています。
「うだつ」が上がる年
今日は28日で私の事務所でも仕事納めです。
昨日、年末の挨拶ということでレンタルオフィスに入っている人が来ました。
実家が愛知県だそうで、正月も結構温かいそうです。
時には雪のない正月にあこがれる私としては羨ましくもあります。
その彼と話をしていると「今年から来年にかけては『うだつ』の上がる年ですね」と言われました。
「うだつ」とはご存じのように、屋根にある隣家との境界に取り付けられた土造りの防火壁のことです。
それなのに「今年から来年にかけて『うだつ』が上がる年」とはどう意味かと聞きました。
彼の話では「うだつ」は「兎辰」と書き、今年がうさぎ年で来年は辰年です。
うさぎ年の時はうさぎが飛び上がるように変化の多い年で、辰年は龍のごとく伸び上がって行く年ということだそうです。
今年は確かに色々なことがあり過ぎました。
世界でも日本でもどちらかと言えば、悪いことが多かったです。
来年こそは良い年になって欲しいと思います。
龍のごとく大きく伸び上がって欲しいものです。
ただ彼の話では登り龍もあるけど、下がり龍というのもあると言います。
是非とも来年は登り龍で、良いことが沢山起きることを願います。
オークションで買いました
昨日久しぶりにYahooオークションの家具を見ていたら、以前から欲しいと思う椅子があり、それを見て、すぐ入札しました。
入札締切期限は昨夜の12時でしたが、その前に入札をしてすぐ寝ました。
以前は欲しいと思うものを入札締切ギリギリまでチェックしていたのですが、ツイ熱くなり自分の見込み額を越して入札したということもありました。
それを教訓に、自分が買っていいと思える最大の金額を入れたら、それっきり見ないようにしています。
今朝パソコンを開いてチェックして見ると、運よく落札出来ていました。
自分が見込んだ金額より1万円以上安かったです。
落札したのはカンディハウスが取り扱っているスエーデンのSWEDESE社LaminoCHAIRセットです。
この椅子は勿論中古ですが上代価格の4分の1以下ではないでしょうか。
この椅子は50年以上続く世界でも人気の椅子です。
いい家具は長く使えます。
「時間に磨かれて良くなる」は私の持論です。
建物や家具、そして万年筆など消耗品でないモノはほとんど、手を掛ければ時間と共に、味わいあるものになります。
古くなると汚くなるという人がいます。
それは手入れをせず大事にしないからです。
自分が気に入ったものは手入れをします。
「時間に磨かれたモノ」はいくらお金を出してもすぐには作れません。
今までオークションで買った家具は10個ほどです。
全部中古です。
買った家具を雑巾で磨き、大きな傷は修理し若干塗装もします。
グラグラしたサイドテーブルを承知買ったこともありましたが、しっかり修理したので今はビクともしません。
でも、補修や塗装などはあまり手を掛けると折角の味わいが無くなってしまいます。
今、問題が1つあります。
今回買った椅子を置くところです。
どこに置こうかと悩んでいます。
家に置きたいのですが、椅子だらけになりそうです。
妻の同意が得れるか心配です。
優しい妻ですから許してくれるとは思いますが、とりあえず私の事務所に置こうか考えています。
ボディーアクション
「ポジティブに生きましょう」「積極的思考を持ちましょう」とよく言われます。
そのように生きることはとても大事なことです。
でも、人はいつでもそのような生き方が出来ているかというと、そうでもありません。
時として、落ち込んだり、自信を無くしそうになることもあるでしょう。
ネガティブな気持になったことが無い人はほとんどいないのではないですか?
人の心は弱く、すぐ落ち込みます。
でも、大切なのはそれを長く引きずらないことです。
各分野で成功している人達はその落ち込んでいる自分を早く立て直すことが出来る「方法」を知っています。
例えば、元気がなくなったらとんかつを食べるとか、神社に行ってお参りをするとか、マラソンをするとか、仲間とどんちゃん騒ぎをするとか、それぞれ自分だけの「アクション」を持っています。
もう1つ気持ちを切り替える簡単な「ボディーアクション」もあります。
人と話していて気持ちが重たくなったとか、チョット元気がないけれど、これからお客様のところに行こうとする時などに使うと効果的です。
人によっては指をパチン、パチンと数回鳴らすとか、鉄腕アトムのように両腕を肩のところまで上げてガッツポーズをするとか、人によって違います。
誰かのマネをしてもあまり効果はありません。
自分に合った「ボディーアクション」を見付けるのです。
私が最近見つけた自分の「ボディーアクション」は両手の掌を1分間位上に向け、その後に合掌するのです。
手のひらを上に向けていると両手にドンドンとパワーは入ってくるような感じがします。
両手に入ってきたパワーが合掌することで身体に回って行きます。
これはイメージの世界です。
そして私がそう思うからしているだけです。
それで気分がスッキリするのであればいいのです。
このように、裏付は無いけれど自分が信じる「ボディーアクション」を持っているといいですよ。
皆さんは、何か自分だけの「ボディーアクション」をお持ちですか?
電車を待つ時
昨日も外出をしました。
休みの日はなるべく外に出るようにしています。
昨日は街中に出る為、地下鉄に乗りました
電車に乗る時はいつも、チョット違和感を感じます。
ここ5~6年位前から感じています。
電車を待つのに、前から順番に並んで待つのですが、私より前に並んでいる人が、広い間隔を空けて立っているのです。
最前列の人は黄色い前線より1メートルほど後ろに立ち、次の人も2人分くらい空けて立っています。
その後ろに立つと、3人しかいないのに長い列になってしまいます。
もう少し詰めて並べばいいのにと思います。
いっその事、その空いているところに入ってしまおうかとか、「前に詰めてください」と言おうとか思うのですが、気の弱い私はまだ言っていません。
ただただ「なんなんだろう」と思ってしました。
私が勝手に前の空いているところ入っても何とも言わないのだろうか、入ったら怒るのか、怒っても何も言わないで我慢しているだけなのか。
「詰めてくださいと言ったらチャンと詰めてくれるのか、それとも無視されるのか。
何も予想がつきません。
人は自分以外の人に関心がなく、周りが見えていないのでしょうか。
自分の行動を俯瞰的に見ることが出来ないのでしょうか。
それで他人との関係がうまくいくのでしょうか。
極端に言えば何か重要なことが欠落しているのではないかとしか思えてしまいます。
利己主義と個人主義とは違います。
利己主義とは自分のことだけを考え、他人の事には無関心でいること。
個人主義は自分を大切にするためにも、他人への関心があり、他人の生活も認め、自分と他人の関係を俯瞰的にみることが出来ることです。
この違いが明確でないがために自分だけしか「居なくなって」います。
結果自分を大切にしなさいという考えが、個人主義ではなく利己主義になってしまうのです。
クリスマスイブ
今日はクリスマスイブです。
なぜか25日のクリスマスよりイブの方が嬉しいく思います。
サンタからのプレゼントへの思いがあったからでしょうか。
私の一番思い出のあるクリスマスはと問われれば、中学生の時、クラスだけで開いたクリスマスパーティーでしょうか。
中学生ですから47年前。半世紀前の大昔の話です。
何かの切っ掛けでクラスの教室でクリスマスをすることになりました。
その準備はすべて生徒たちだけでしました。
金額は忘れましたが、1人1~2百円位集めて費用分担。
飾り付けする人、お菓子を買う人、バックグランドミュージックを録音する人、会の運行を企画する人、それぞれ分担です。
私はバックグランドミュージック担当でした。
何日も前からテープレコーダーにクリスマス用の音楽を録音しました。
あの頃はクリスマスが近づくと頻繁にラジオからクリスマス音楽が流れていました。
ラジオにテープレコーダーのマイクを近づけ、その曲を録音するのです。
音を立てると吹き込まれてしまうので、静かにして録るのですが、時々ドアを閉める音が入ったりしました。
そんな雑音入りの「ホワイトクリスマス」「ジングルベル」「きよしこの夜」などのクリスマス音楽をリール式のテープレコーダーに録音しました。
24日は午前中からクラスの窓に暗幕を張ったり、クリスマスの飾りの星などを金銀の紙を折って作り、それを貼ったり準備します。
クリスマス会は午後1時から始まり、クラスのほとんどが出席したと記憶しています。
お菓子を食べ、ジュースを飲み、全員が芸をします。
踊りを舞ったり、歌を歌ったり、手品、皿回しなど多彩です。
うまい下手は別にして皆で盛り上がりました。
4時頃には終わり、クラス皆が名残惜しく帰って行ったことを覚えています。
クリスマスパーティの時は勿論担任の先生はいましたが、ほとんどが生徒が企画し準備し楽しみました。
24日は既に学校は冬休みです。
その学校でそんなクリスマスパーティ開催を許してくれた学校は寛大だったと思います。
当時の学校には校則などはありましたが、それ以外は結構自由にさせてくれる大らかさがあったと思います。
そんな中で学校生活が出来たこと、今でも心に残る思い出となっています。
聞くところによると今は宗教上の理由で、学校でクリスマスパーティーをしてはいけないということになっているそうです。本当でしょうか?
がんじがらめの環境では、自主性も、発想もそれと行動力も生まれてこなくなるのではないかと思います。
我慢をする時
最近新聞やテレビを見て思うことは、今の日本の財政がいつまで持つかということです。
日本の国債が943兆円を越してもうすぐ1000兆円になろうとしているのに、お金の出る事ばかり決められて、削減がほとんど進んでいません。
札幌では新幹線が函館から札幌まで延長になることが決まりそうだと盛り上がっています。
その費用は2兆円を超すそうです。
八ッ場ダムも建築継続が決まりました。
社会保障のお金も増えていきそうです。
毎年半分近く借金をして組む予算では2~3年で日本も破綻すると言う人がいます。
その可能性がドンドン高くなっています。
政治家は耳触りのいい話をします。
お金のかかることも簡単に「わかりました」聞いていきます。
国民に我慢しなさいと言った政治家はほとんどいません。
小泉元首相が米百俵の話をして我慢を強いたぐらいでしょうか。
来年は、もしかしたら衆議院の選挙があるかもしれないと言われています。
また、来年はアメリカ、ロシア、フランス、韓国の大統領選挙があります。
それぞれの国で、国民に甘い言葉を言い続ければ、お金が出ていくばかりです。
戦争の時はインフレ、平和の時はデフレと言われています。
イラク、アフガニスタンからアメリカ兵が撤退すれば、平和になり益々世界中がデフレになります。
インフレの時と違いデフレの時の政策は「小さな政府」「緊縮財政」が条件です。
なのに皆、相変わらずお金をばらまくインフレ時と同じ政策をとっています。
まるで大王製紙の元会長がギャンブルにのめり込んで行ったのと同じです。
悪いこと。直さなければならないと思いながら、ズルズル流され、目が覚める時は刑事事件になり拘置所に入れられた時です。
日本もズルズルと流され、気付くと経済が破たんし、全てのか金がストップしてしまう時です。
日本に個人資産が1400兆円を越すと言われていますが、70%が高齢者が持っています。
収入のない高齢者は、万が一の時その資産を使って生活するようになりますから、個人資産が一気に無くなることも予想されます。
早く「国民が国から何かをしてもらう」のではなく「自分達が何をするべきか」を真剣に考えていかなければなりません。
今は、「誰が悪い」と人のせいにするのではなく、「してもらう生活」から自立して、不自由・不便でも我慢していく時だと思っています。
そうでなければ子供・孫に対して申し訳がたないでしょう。
同士といえる支援者
起業する時、1つのアイデアだけ会社を始める人がいます。
でも、アイディアだけでは無理なのです。
アイディアがありそれを具体的に作り出し、それを売って利益を得る。
これが1サイクルです。
アイディアだけではいくら優れていても単なる絵空事。
そのようなアイディアだけを持っていて、後で誰かがそれに似たようなアイディアでヒット商品を出すと、「実は以前から私が考えていたことなんだ」という人が時々います。
それは何の意味も持ちません。
実際に素晴らしいのは思い付きのアイディアだけで終わるのではなく、それを具体的に製品として作り出し、それに付加価値を付けて商品として売り出すこと。そして実際に売れることです。
昨日東京の知人が来社されました。
色々のお話しの中で、いま彼女が商品化に取り組んでいる製品について語ってくれました。
「キエルーフ」という布製品でこれは制菌と消臭の二つの効果があるそうです。
これをバンダナやハンカチ等の商品にしていますがまだ需要が出てきていません。
知人の女性はこの「キエルーフ」の性能・効能に共感し、これを開発した会社の支援をするために、新しい商品を開発しようとしています。
新しい商品を探るため、色々な会社を訪問しているのです。
話を聞いていると、何とかこの会社を成功させたいという意気込みが感じられました。
1つのアイディアを考え出し、製品にすることは何とか1人でも出来ます。
しかし、それを商品として売り出し、収益が上がるまでは大変です。
1人で起業し、資本も人もいない中、いくら頑張っても限度があります。
すぐれたアイディアがで製品化しても、多くの起業家が挫折していく例は多くあります。
それは付加価値のある商品になっていないからです。
必要なのは先ほどの女性のようにその製品に惚れ込んで、一緒に広めてくれる同士を作って行くことが大変重要になってきます。
単なるコンサルタントではなく、一緒に広げていく同士と言える支援者が必要なのです。
昨日は起業者にとって支援者がいるということの重要性をを改めて感じました。
繁盛する店
一昨日、昨日と望年会が続いて、今日が今年最後になりそうです。
昨日は知人夫婦と牡蠣の専門店で食事しました。
この店は以前にも紹介したことがありますが、いつも混んでおり、予約しなければ入れないところです。
昨夜も70席ほどがいっぱいでした。
この時期は飲食店にとっては書き入れ時です。
どこの店でも入っているはずですが、全然入っていないところもあります。
何が違うのでしょうか。
昨夜の店はメニューも工夫が凝らされ、お客を飽きさせない内容になっていました。
そして知人を連れて行くと、皆が喜ぶ工夫があります。
昨夜私たちの給仕をしてくれた女性は機知に富む対応をしてくれました。
生牡蠣を1セット頼むと、人数に合わせて1つ増やしてくれたり、日本酒を「盛っきり」で頼んでも勢い良く入れてくれます。
その時「一言」言うのです。
「人数に合わせて1つサービスしておきました」
「盛っきり」で入れる日本酒もグラスから溢れさせ、受けの升にもギリギリまで入れてくれます。
その時一言。「本当は升の中間まで入れることになっているのですが、特別です。」
お客は得をしたという気持より、「特別」にしてくれたことがうれしくなります。
このようなサービスはその女性だけがというのではなく、きっと店の考え方としてその位のサービスを認めているのでしょう。
店の考え方と、それをサービスとして接客する人との意思の疎通がうまくいっているからなのでしょう。
美味い料理とお酒、それに自分は特別と思わせるサービス。
これが繁盛するこの店の重要ポイントなのでしょう。
素直にお願いをする
半月ほど前、千歳空港へ向かう電車の中で感じたことです。
朝一番に飛行機に乗ろうという人達で込み合う電車です。
札幌駅の1つ手前の琴似駅から私は乗ったのですが、ある若い人が座席に荷物をのせ2人分を占有していました。
私は天の邪鬼ですから、そういうのを見るとあえてそこに行って「すみません。座らせて下さい」と言うのですが、その横に空席ありましたのでそこに座りました。
札幌駅では、多くの人が乗り込んで来ました。
でも先ほどの若い人は知らんぷりで寝た振りしてしています。
立っている人も多くいたので、お節介でもある私は「席を譲って上げたら?」と言おうとしました。
でもその時「ちょっと待て!」という言葉が私の頭に浮かびました。
「私が言うことではない。座りたいと思っている人が自分で言えばいいのでだ」と。
それで暫く見ていました。
誰1人「すみません。席譲ってください」と言った人はいませんでした。
寝た振りの若い人も譲ろうとしません。
立っている人達は、時折彼の顔を冷たく見つめるだけ。
それを見ていると可笑しくなってきました。
して欲しいのに、して欲しいと言わない。
ただ相手が気付いて譲ってくれることだけを期待している。
人がしてくれるのを待っているのか。
素直に「済みませんお願いします」と言って、「はい。どうぞ」といえいる関係がいいのです。
もう1つ。以前私が経験したことです。
込み合う電車で吊革につかまっている時、ある駅でお婆さんが乗って来て、私の傍に立ちました。
その前に座っている若い人が友達とおしゃべりして気付いていないようです。
それでお節介の私は「すみません席を譲ってあげませんか?」聞くと、その若い人達はすぐ立ち上がり、どうぞと快く譲ってくれました。
お婆さんは申し訳なさそうにしながら座りました。
普通はここで終わりなのですが、続きがあります。
その後3つくらい後の駅で、先ほどの若者が私のところに来てこう言いました。
「先ほどはありがとうございます。気付きませんでした。教えていただいて良かったです。」と言って降りて行きました。
彼らが近づいてきた時、文句言われるかと思ったのですが、その逆です。
ビックリするとともに、「嬉しいな」という気持ちが湧いて来ました。
この時はお節介して良かったと思いました。
そして素晴らしい若者がいるモノだと、その日1日楽しかったことを覚えています。
今でも時々その時のことを思い出し、あの若者はいま何をしているのかと想像が膨らんでゆきます。
残念なレストラン
この土曜日と日曜日は久しぶりに夫婦2人でデートしました。
時間を気にせず、ゆっくり街を歩き、買い物をし、食事をしただけですが楽しい時間でした。
考えてみれば結婚して間もなく子供を授かり、5人の子育てが終わた頃から、両親と同居し、2人を見送るまでは、時間を気にせず2人で出歩いたことはほとんどなかったように思います。
このデートは運動も兼ねていましたので、1万歩歩きました。
運動も兼ねてはいますが、お昼は美味しいものを食べのも楽しみです。
土曜日は札幌中島公園を歩き、そこにある古い歴史的建物のレストランで食事しました。
あえて名前は出しません。
東京生まれの妻は、長年札幌に住んでいますが、この建物には一度も行ったことがないので、見学と食事をするのを楽しみにしていました。
結果は「ガッカリ」でした。
建物は明治天皇、大正天皇、昭和天皇も宿泊された迎賓館ですので素晴らしいものです。
「ガッカリ」なのはレストラン。
古い建物の1室をレストランに利用していて、テーブルには白い布クロス。
レストランの広さに比べテーブルと椅子が多く、狭く感じましたが雰囲気は良いです。
私達が入った時、お客は4名だけ。
出されたメニュー表はA4判の白黒コピー、それも何度も使われたようにヨレヨレ。
料理内容は道産牛を使ったステーキセットや白いカレーライス、スパゲッティ位です。
私はステーキセット、妻はスパゲティを頼みました。
ステーキセットはワンプレートで出されてきました。
ステーキといってもカルビ焼きの様なもので、それにサラダとライスだけ。
一瞬「アレッ!」と思いました。
これで1200円!?
スパゲティは味が薄いけれど普通並み。
ガッカリというより残念な気持ちになりました。
もっとメニューやサービスに工夫を凝らすと、もっとお客様が増えるはず。
これほどの歴史的建築物でレストランが出来るということは物凄い差別化が出来ること。
それを生かし切っていないことが悔やまれます。
サービスは1人しかいません。
その彼に聞くと、運営は民間会社だということです。官庁かと思ってしまいました。
翌日の日曜日は札幌の街中にあるホテルのレストランで食事しました。
入店待ちのお客がいて20分ほど待たされて入りました。
ここの料理、サービスとも素晴らしいものでした。
土曜日のレストランとほぼ同じような料金で、焼き立てパン、サラダ、肉料理、デザート、コーヒーまで、満足する内容でした。
このレストランが、先ほどの歴史的建物で営業すれば、予約しなければ入れないほどの人気が出ることでしょう。
レストランやホテルは「第1に立地、第2に立地、何は無くても立地」と言われる位、営業する場所に影響されます。
でも最終的にはやはり人間力です。
同じ場所で営業しても、運営する人間が違えば「月とすっぽん」ほどの違いが出ます。
今思い返しても残念です。
あの歴史的建築物のレストラン、チャンスがあれば私が経営したい位の思いにさせられました。
三浦知良さん
先日の新聞に三浦知良さんの手記が載っていました。
三浦さんは皆さんご存じのように日本のサッカーの有名選手です。
現在は横浜FCに所属し、日本の最年長プロサッカー選手。
私はサッカーには興味がなかったのですが、三浦選手だけは知っていました。
絶頂期の若い頃、彼がシュートを入れると、「カズダンス」を踊っていました。
テレビでそのシーンを見て「軽薄な奴」と思っていました。
(フアンの皆さん。申し訳ありません。)
その彼が半年前のテレビで、自分の肉体をベストに維持するために、、毎日自分に課しているトレーニングが半端でないのを見ました。
そして今回の手記を見て、改めて凄いと感心しています。
その手記を紹介します
今回の手記の題名は「サッカー人として」です。
「横浜FCはJ2の18位に終わった。これが現実、力不足。
『こんな成績ですみません』。こう言いがちになるけれど、僕はそういう言葉は言いたくないし、これまで使わないようにしてきた。
ふがいない成績をたたかれ、罵声を浴びても仕方がない。
ただ、プロが『ごめんなさい』と発言すべきなのは、自分が怠け、努力をせず、いい加減に日々を送ってきた時のはずだ。」
「結果を認める。責任も負う。でも謝るのは少し違う。謝るべきことのないよう、常に自分の出来ることはすべて毎年してきたつもり。だから僕のサッカー人生に『すみません』の文字は無い。
では謝るより何をするのか。
『さらに自分を高めていくしかない』と、いつもそこへ行き着く。」
この手記を読んで改めて三浦さんの真摯で求道的な生き方を見た思いです。
やはりプロとはそういう人でなければならないのでしょう。
簡単にごめんなさいというのは素直に見えますが、単に「努力しなかった自分を許して下さい」の意味でしかないのです。
経営者もそうです。
会社を倒産させ、「ごめんなさい」では済みません。
どこまで真剣に経営に向き合うか、その姿を三浦さんが示してくれたように思います。
その三浦さんが先の手記の最後に「『いつまでやるの?』『ボロボロになるまで』―――。
じゃあ肉体も精神もボロボロになるまでやって、その後生きていけんのかなとも思うけれどでも、それで楽しんだよね」
ここまで生き抜ける精神力に本当に脱帽です。
高くても売れる
「100円のコーラを1000円で売る方法」という本が新聞の広告欄にのっていました。
この本は読んでいませんが、以前読んだ「球場のビールはなぜ800円でも売れるのか」と同じような内容でしょうか。
改めて商売の原点を考えてみました。
売れないから安くするのか、それとも最初から安くしないと売れないと思うから安くするのか、どちらにしてもモノの売値が安くなっています。
でも100円のコーラが1000円で売れるのはなぜ。
800円でも球場では生ビールが飛ぶように売れるのはなぜ。
それは当り前のことですが、お客様が高くても欲しいと思うからです。
夏に山を登って行くと頂上付近に茶店があり、冷たいジュースやコーラが地上の何倍も高い値段で売られています。
スキーをに行ってヒュッテで食事をしようとすると、温かい豚汁が結構高い値段で売られています。
これらは必要とされているところに、必要とされるものを出すから高い値段で売れるのです。
言われてみれば当り前のこの事ですが、それを忘れ工夫をするのを怠って、売れない売れないといって言っているように思います。
以前のブログで「てんびんの詩」というビデオの話を書きました。
天秤棒商売は商売の原点です。
必要とされる場所に必要なモノを天秤棒に吊るして運び、それを売り、その代金で新しく商品を仕入れ、それを必要とするところに運び売ります。
その利ザヤの積み重ねで持ち金を増やし、店を構えることが出る商人も出るようになりました。
天秤棒商売の発祥の地、近江八幡市の観光ガイドにこのことが詳しく書かれています。
要約しますと、近江八幡は天正13年に豊臣秀次が八幡山に城を築き・開町した事に始まります。
城主の秀次は、理想に燃えて町づくりに励みましたが、秀吉により清州(きよす)の城主に移された後、切腹させられました。
それは近江八幡が開町後わずか10年目のことであり、八幡城は廃城の悲運に見舞われました。
城下の商人達は、城主からの庇護(ひご)やその他の特権を一挙に失いました。
ゼロからの再出発です。
彼らは肩に天秤棒をかつぎ、あるいは商隊を結成して全国に行商に出かけ、新しい市場を独自で開拓しなければなりませんでした。
こうして近江八幡は町人を主体とする町に生まれ変わって行ったのです。
近江商人が取り扱った商品は最初の頃、畳表、蚊帳、数珠などの地場産品だと言われます。
それらを関東で売りさばき、その代金で現地の紅花(化粧品の原料)などを仕入れ、それを京都に持ち込んで売りさばきました。
さらにその代金で京都の古着を買い入れ、全国各地に売り歩き、その代金でまた、土地の産物を仕入れるという商売をしました。
これが「のぼり天秤」「くだり天秤」と言われる無駄の無い往復商売です。
必要なところに必要なモノを運び売るのです。
やはりこれが商売人の原点ですね。
世の中、来年に向かい激動が予想されますが、この商売の原点を忘れず、広く日本・世界を見渡すことで新しい商売の道筋が見えてくるように思います。
「どこで」「誰が」「何を」必要としている、今改めて見直してみてはどうでしょう。
的確な情報
昨日も忘年会でした。
風邪もお陰様で良くなり、連日続く宴会も何とかこなしています。
昨日の会場はいつもだと予約しなければ入れないようなところでしたが、空席が結構目立っていました。
今は忘年会シーズンのはずです。
聞いてみると震災の影響で忘年会を控えている人が多ということでした。
震災の人達を思う気持ちは分かりますが、もう私たちは普段通りの生活をしていいと思います。
心のどこかに忘れてはいけないものを抱えながら、一方でするべきことをして、復興する力を発揮しなければならないのです。
テレビなどを見ていると震災被害のその後の報道があります。
しかし、東北経済復興はどうなっているのでしょうか。
知りたいと思っていました。
知人からの話では仙台は復興のお金や人が集まって、経済が対前年で120%の伸びだと聞きます。
ホテルの予約も取れず、繁華街では人であふれ返っていると言います。
それでは福島市はどうなっているのでしょうか。
仙台市より被害の大きかったところですが、その後の復興状況・経済状況が良く分かりません。
来年2月に何人かで仙台に行くことになりました。
その時に幹事が呼びかけた「文句」が「復興著しい仙台を見に行きましょう」でした。
それに対してメンバーから不謹慎だという声がありました。
幹事は恐縮していましたが、私は問題ないと思います。
事業をしている者は経済の動きに敏感でなければなりません。
被害者の心を思いながらも、一方で事業者としての仕事もする、その両立は可能です。
景気や事業の話をするのを押さえる必要はないです。
もうそろそろ、報道ももっと公平で的確な情報を伝えて欲しいと思います。
いまだにフィルターを通した情報ばかりのように思えています。
学生と資格
昨日の日経新聞に学生と資格について特集が書かれていました。
就職に有利だということで資格を取る人が増えています。
昨年10月にリクルートが大学4年と大学院生758名に資格の有無を尋ねたところ、7割の人が「ある」と答えたそうです。
定番の運転免許が一番多いですが、TOEICや簿記などのビジネス系の資格も多いです。
資格を取る学生が増えているのは、就職での武器として使えるからとい考えが大きいようです。
学生にしてみると、履歴書の資格欄が真っ白だとそれだけで落とされてしまうという不安があるようです。
そのため、就職業界に詳しい人の話では、将来のキャリアプランを明確に描けない学生にとって、資格を取ること自体が目的化していると指摘されています。
その傾向に対して企業側は冷めた目で見ているようです。
面接の時、なぜその資格を取ったのか、どう生かすつもりなのか、その質問にきちんと説明できないと、自分に自信がないから資格を取ったのでゃないか、逆にマイナス点になる時がると、ある面接官は言っています。
ユーキャンという会社はテレビで、資格があれば今のみじめな人生がばら色に変わるというイメージ広告を出していました。
罪な広告です。
下手な資格を取る位なら、いっそ1人旅に出たらどうでしょう。
1~2ヶ月間、1人で外国旅行してみるのです。
出来なければ国内でもいいです。
貧乏旅行をしてみると、人の温かさが分かります。
色々な人に出会って見聞が広がり、その人間性も高まるはずです。
1人旅の1番の収穫は自信が生まれることです。
もう1つ学生にしてもらいたいのはカーネギーの「人を動かす」という本を読むことです。
この本の事は以前にもブログで書きましたが、極端に言うと人生が変わります。
何回も読み返し、自分のものにすると、その人の考えが変わります。
しっかりした考え方が出来た人間ならば、企業側も喜んで採用します。
一層、大学の就職支援の一環として、学生に「人を動かす」の本を読ませ、その感想文を書かせるなどした方が、実のある支援になるように思います
運をつかむ
以前読んだ本に面白いことが書いてありました。
「人生を変える7つのサイン」というものがあるそうです。
1.リストラ、仕事の行き詰まり、売り上げの急減
2.自分や家族の病気、事故
3.お金トラブルや破産
4.人生の退屈感
5.物事の完了
6.男女関係、人間トラブル
7.他人のライフワークに触れた時
この多くは人生における衝撃(ショック)ですが、4番目の「人生の退屈感」や5番目の「物事の完了」は幸せな転換です。
確かに自分が何か始める時は、何かが自分の周りで起き、それに急かされるようにして始まることがほとんどです。
その時は「する時が来た!」と言って、すぐに動き始めることです。
それによって自分の運をつかむことになります。
運を逃す人は往々にして鈍感な人です。
また素直でない人です。
折角のサインを見逃してしまうか、たとえ分かっても素直にそれに従わないかです。
形は違い、状況も違うかもしれませんが、チャンスは皆平等に来ると私は思っています。
そしてそのチャンスは人それぞれに合せられた「オーダーメイド」です。
ですから人のチャンスを見て羨んでもそれはあなたには合いません。
今の自分だけに適したチャンスが来ます。
運は「年末ジャンボ」ばかりではありません。
運が来たらしっかり捕まえて人生のステージアップをはかりましょう。
後の喧嘩、先にしろ!
今日は起業家の話をします。
起業する時1人で始める人は多いと思います。
しかし1人で始めると孤独を感じ、仲間を見付けようとします。
異業種交流会や、サークルなどで人との出会いなどを探します。
そんな時自分の考えに賛同してくれ、自分の仕事の助けになる人が見つかることがあります。
これはラッキーなことです。
それでその人と共同経営者という形をとる人がいます。
以前にも書きましたが、共同経営者等の形を取ると、ほとんど成功しません。
起業家が始めた事業を共同経営者が牛耳るという形が多いからです。
起業家が自信がないあまり、共同経営者に頼り過ぎるからです。
自分の足りない部分を補うのに人を入れるのはいいことです。
ただし、その時は職務の分担を明確にすることです。
そして経営に関する分野は決して任せてはいけません。
どんなに自分が不得意だと思っても、経営に関する仕事は手放してはダメです。
もう1つ、共同経営者にならなくても、それぞれが会社として共同して仕事を進める協力関係を築くことも出来ます。
この時は「どのような仕事を」「どのように進め」「利益分配はどうするか」「契約は〇年〇月までとして、その後見直す」等の業務契約書を作るべきです。
最初は単に仲良しの仲間意識で始めると、当初は良いと思った内容でも、だんだんと不満を抱くようになります。
結果、感情のもつれを招くこともあります。
起業家は、この世の中、全て契約で動くということを良く認識してください。
最初に面倒でも決めごとをしておけば後が楽になります。
「後の喧嘩、先にしろ!」です。
5感
数日前、妻が父や母の遺品を整理していて、昔の写真を見付けました。
父や母がまだ独身時代の写真でした。
父も母も驚くほどいい男いい女で、成程、だから私が生まれたのだと納得しました。
私が小さい頃に亡くなった母方の祖父は、今の私にそっくりだというのもびっくりしました。
写真というのは画像で記憶を残しておくもの。
記憶を残すと言えば、音もそうです。
NHKラジオの「日曜あさいちばん」でラジオ体操の後、流れてくる「音にあいたい」のコーナーというのがあります。
リスナーが「この音を聞くと懐かしい過去を思い出す」と音をリクエストするというのものです。
「朝の港の市場のにぎわい」とか「稲を刈って皆で脱穀機を使っている時の音」等、実際自分が聞いた時の音が流れるのではないのですが、その時に似た声や音を聞くだけで、過去の1場面を思い出すものです。
味覚も、食べていると懐かしい味に出合い、おふくろの味を思い出すかもしれません。
嗅覚も記憶を思い出すことがあります。
ふと流れる臭い、また特別臭いはないけれど、空気の香りを嗅いで、甘酸っぱい青春時代を思い出したりします。
人間の五感の中で、過去の記憶を知るものと言えば、視覚、聴覚、味覚、嗅覚でしょう。
その4感は過去をたどる方法を持っていますが、触覚だけは無いようです。
何かを触って昔を思い出すということは無いように思います。
逆に言うと触覚は触って初めて感じることが出来ます。
触感は5感の中で「現実確認」出来るただ1つの感覚なのかもしれません。
他の4感のは先に述べましたように、過去のものと現実が交錯する時があります。
物を買う時、触って確認するというのが通常行われてきました。
特に女性は触らなければ決して買わないと言われていました。
ところが今は、洋服や、靴をインターネットで買う人が増えています。
触らないで買っているのです。
パソコンの画面を通して、写真や商品説明だけで買っているのです。
そう言う傾向は益々増えていくことでしょう。
良さそうに思う、より感覚的な判断で購入するという感覚的購買が増えていくのでしょう。
もしかしたらこれからのマーケティングも変わって行くのかもしれないですね。
休日で、寝て頭が朦朧としていた時に思いついたことを書きました。
少し支離滅裂だったかもしれません。
健康第一
ここしばらく体調があまり良くなく、この1週間はちょっと大変でした。
折角の2回あった亡年会も何とかこなしたような状態でした。
いつもだと、大いに飲み食いして、2次会にも行ったかもしれないはずでした。
体調と思考は同調するようです。
どうしても体調が悪いと思考もマイナスに向かいがちです。
「健康な体に健康な精神が宿る」というのは本当です。
健康な身体を保つ方法は年と共に変わってくるようです。
若い頃のつもりで薄着でいると風邪をひく。
バイキングに行っても飲み食いする量は限られている。
年を自覚するということは、健康を守る原点なのかもしれません。
今日明日は静かにして暮らします
約束は守る
先日の日経新聞「春秋」の中に書いてあったコラムを読んでの感想です。
「この1週間、のどに骨が引っ掛かったような感覚が抜けない。前沖縄防衛局長の不適切発言に関してである。あの暴言を明るみに出したメディアは正しかったのか」というものです。
なぜこのコラムが気になったかと言いますと、メディアがメディアの報道方法に対して自己批判しているからです。
メディアが自己批判するというのはあまりありません。
前沖縄防衛局長が発言した内容は暴言です。
「沖縄県知事は『口が汚れるからコメントしない』と吐き捨てた。こちらも紙面を汚したくない。
気になるのは1点、暴言がオフレコの場で出たということだ。
オフレコとは、発言を記事にしないとの約束を前局長と記者たちが前もって交わしたという意味だ。そしてその約束が守れなかった。」
「前局長の発言をはじめに報じた琉球新報は、発言を沖縄県民に伝えることを優先した。
『報道には公共性、公益性がある』。そんな考え方も良く分かる。それでも腑に落ちないものが引っかかる。
過ちかもしれないが、約束はしてしまった。
ならば、相手が官僚、政治家であれ、守る。そう言う原則を貫くことも大切ではないか」と書いています。
昨日のブログでも約束は守るという話を書きました。
報道の自由さを尊ぶのか、約束を守るという信義を重んじるのか。
その内容の重大さにもよるのかと思います。
またその重大さの判断も人によって違います。
でも、記者たちにしても、約束を守るという基本的なことが成されなければ、内輪の話を聞ける環境になかったと思います。
異論はあると思いますが、私もこのコラムに書いた内容に同調します。
約束は守らなければなりません!
小さな約束
今日は「約束」について書いてみたいと思います。
皆さんも私も、過去多くの人と約束をしたことあると思います。
そして、守れた約束、守れなかった約束、忘れてしまった約束、守れないのにしてしまった約束等あったはずです。
人の信用はその約束を守る人か、平気で破る人かで大きく違います。
人間ですから時として忘れてしまうことはあります。
そのことで、私が若い頃伯父から言われたことがあります。
「おまえが憧れの彼女とやっと最初のデートが出来る時、その日と時間場所は忘れないはず!約束を守るか守らないかは、約束事にどれほど真剣に意識を持っているかどうかにかかっている」と。
約束には「大きな約束」と「小さな約束」があります。
彼女とのデートは「大きな約束」です。
仕事でもお客様訪問時間も「大きな約束」です。
商品の納品・発送日、支払期日の厳守等、仕事の上では数え切れないほどの約束事だらけです。
「小さな約束」は子供と遊ぶ約束だったり、友人に「○○を貸してあげるね」のようなものです。
つい忘れてしまうことが多いです。
でも「小さな約束」は約束した人が忘れても、約束してもらった子供や友人は忘れません。
人の信用とは意外にこの「小さな約束」を守れるかどうかにかかっているようです。
仕事上などの「大きな約束」は忘れたり守れなかったら大変です。
だから「大きな約束」は誰でも守もるのが当り前になります。
でも何気なくした約束はつい忘れてしまう人が多いです。
「今度一緒に飯食おうよ」と誘ったり、「今度遊びに行きます」と言ってもつい忘れてしまう。
そのような約束は別れる時の常套句になっているようです。
でもそんな時、本当に食事誘いの電話があったり、遊びに来てくれたりすると、「アッこの人忘れていなかったんだ!」という小さな感動が生まれます。
このように「小さな約束」を守る人ほど、他の人と比較して信用度は高くなります。
自分の信用を高める方法として、あえてこの「小さな約束」をたくさんして、それを1つずつ果たしてみたら如何ですか?
「マメな男性は女性にモテる」というのも、そういうことにあるのかもしれません。
皆さん、もう一度身の回りを見回して、忘れている「小さな約束」ありませんか?
奥さんに「今度指輪買ってあげるよ」と言ったの忘れていませんか?
(アッ!それは私です!)
自立した生活
私は毎朝、起きて出勤するまでの時間はある程度決めて行動しています。
ですから、大体同じように時間に家を出ます。
多くの人も同じ出勤状況ではないでしょうか。
人によっては、起床から出勤までの時間内に毎日運動したり、本を読んだりする時間を取って、それを習慣づけている人もいるでしょう。
私は最近起床時間が遅くなり、5時50分起床し7時過ぎに出勤しますが、その間2つの事を必ずする習慣があります。
毎日決められたことを必ず行う人は、それをすることで安心を得ます。
それにより自分の毎日のモチベーション維持にも役立っています。
毎日自分の責任を果たしています。
一方、そのような束縛を嫌う人がいます。
決められたように生きるのが辛いと思う人がいます。
好きな時間に起きて、好きな時に働いて、好きなことをすることに喜びを持つ人です。
そのような人には普通のサラリーマン的生活は耐えられず、ドロップアウトしていきます。
勿論、人として自由に生きるべきで、どちらが正しいかと比較してもあまり意味がありません。
自由な生き方をする人の中には、小説などの作家となり、自分のペースで仕事をしている人もいます。
芸術家の中にもそういう人もいます。
そのような生き方をしてもそれなりに結果を出し、責任を持った生活が出来ればいいのです。
生き方は自由です。
ただ、その結果につについては自己責任を負うべきでしょう。
その結果貧乏になったから、誰かに頼らなければ生きていけないというのでは意味がありません。
自分に厳しく、懸命に頑張っている人が多くいる中、自分に優しく安易な生き方をしている人もいます。
どのような生き方をしようと、人として自立できる生き方こそが大切です。
最近思うことです。
盛和塾台湾開塾式
昨日まで辛かった風邪も、お陰様で少し良くなって来ました。
今日は先日台湾で行われた「盛和塾台湾開塾式」の様子を書きます。
会場は台北の「圓山大飯店」で行われました。
ここはグランドホテルとも言われ、台湾でも由緒あるホテルです。
開塾式は2日の14時から始まりました。
2時間ほど台湾の塾生の自己紹介があり、それに引き続き稲盛さんの話。
今回の題名は「人生について思うこと」でした。
人生をいかに生きるかです。
以下は稲盛さんが話した中で私がメモした内容です。
人は自分を管理する時「健康管理」「知的管理」「心の管理」をしなければなりません。
人は運動したりする「健康管理」や、英語等を勉強する「知的管理」は良くしますが、「心の管理」をする人は少ないのです。
でもこれがとても大切なことです。
心の思った通りのことが自分の周りに現象となって現れてきます。
有名な英国の思想家ジェームス・アレンもその著書の中で「心の中に生えた雑草を刈り取り、きれいな花を植え、花園を造らないければなりません」と書いています。
人生とは「運命という縦糸」と「因果という横糸」が紡ぎ出すものです。
また人間には「真我」と「自我」があります。
「真我」とは愛と誠との調和に満ちたもので、「真・善・美」という言葉で表すことのできるものです。
「自我」とは本能に基づくもので、自分だけ良ければ良いというものです。
「憎悪」「嫉妬」「強欲」「虚栄」「猜疑心」「自己愛」などと表現されます。
この「自我」を如何に抑えるかが大切です。
でも、これはモグラたたきのように、いくら叩いても出てくるものです。
何度も叩きながら、少しでも「真我」を追い続けるそのプロセスこそが人格を高めることになるのです。
その他にも西郷隆盛の言葉を書き遺した「南州翁遺訓」に書かれている「自分を愛することは間違いの第一なり」という言葉も紹介していました。
約1時間30分ですが、皆真剣に聞き入っていました。
ただ、今回の講演は中国語と日本語の同時通訳でしたので、どこまでうまく中国語に翻訳されて伝わったかという心配はあります。
というのは、中国語の日本語への翻訳が怪しかったものですから疑ってしまいます。
この講演の後、会食になったのですが、この時に私の声が出なくなってしまいました。
14時から17時30分までの間の3時間30分の間です。
自分でビックリしてしまいました。
気温は15度位の、この時期台湾でも寒い日でした。
それなのに天井から冷風が流れ込んで来ていましたので、それにやられたのだと思います。
知りませんでしたが、台湾ではホテルも、車も勿論家庭にも暖房設備はないそうです。
今回の旅は大変実りあるものでしたが、風邪をこじらせたのが大変悔やまれます。
風邪引きました
今月の1日から昨日まで台湾・台北に行って来ました。
この間ブログが書けませんでした。
第1日目は8時発の飛行機に乗る為4時30分起き。
時間的にどうしてもブログは書けませんでした。
日本出発前から喉の調子がおかしかったのですが、2日目は完全に風邪をひいてしまい、その上行事が8時過ぎから始まり、ブログ書けず。
風邪は出発前の夜3時間ほどしか寝れなかったせいだと思います。
風邪は咳がひどい上に、とうとう声まで出なくなりました。
今回は初めての台湾旅行でした。
その目的は盛和塾の台湾塾開講式に出席するためです。
台湾の塾生が160名に対して、日本から300名近くの人が参加し、札幌からも10名ほどの人が行きました。
大変楽しい旅行でしたが、風邪のためそれが充分エンジョイ出来なかったことが残念です。
今日もまだ本調子でないので、ここまでにします。
この旅行についてはまた改めて書きたいと思います。
年をとって思うこと
60歳を過ぎ、考えるようになりました。
年をとるということは?
年をとる意味は?
赤ん坊としてこの世に生まれ、育ち、20歳を過ぎた頃が人間として一番人生を謳歌する頃でしょう。
もしも許されるなら、その元気な20歳代のままの身体で、70歳80歳まで生き、ある時寿命で死んでいくというのが理想的。そう思う人が多いのではないでしょうか?
今、アンチエイジングとか若さを保つための健康食品、化粧品が大変売れています。
60歳の女性が30歳代に見られて、喜んでいるのもテレビでよく見ます。
いつまでも若く元気で行きたいと誰でも思います。
では、なぜ神様は死ぬまで20歳代の身体的状態のままにしてくれなかったのか、それを少し考えてみました。
それはこの世に生まれ、愛情を沢山注がれる赤ん坊の状態から、年をとってシワだらけになり、腰も背中も曲がり、目も耳も悪くなり、時には人に助けてもらわないと生きていけない状態の老人になって死んでいきます。
その意味を考えてみました。
可愛いだけの赤ん坊。
小学生・中学生のやんちゃ盛り。
高校生から20歳代の思春期は人を愛するようになり、
30歳代から仕事を通して世の中の役に立ち、
40歳50歳代は物質的・精神的な蓄えをし、
60歳代はこれからの人生を人のために生きようと考え、
70歳以上は過ぎた自分の人生を振り返り、反省と満足を感じながら死んでいく。
これらすべてが人間として生きる意味であり、それが人間の修行なのかと考えます。
人から愛される時があり、人を愛する時があり、人のために頑張る時があり、人からお世話を受け生きる時がある。
若い頃は麗しいく、人から羨ましがられた美貌の人も、シワだらけになり悲しむ人になるか、
顔はシワだらけでも、心は凛として、すがすがしい生き方をする人になるか、
これら全てが人生であり、修行だと思えば生き方が変わってきます。
死ぬ時、どんな生き方をしたか。
それが大切です。
それを、人知れず自分だけで納得していけばいいのでしょう。
自立する
最近思うことがあります。
優しさは無責任を伴うのではないだろうかと。
「優しさ」=「甘やかし」の形が多くなっているように思われます。
公的なものを見てみると、社会保障というのがあります。
23年度の社会保障の予算額が約29兆円になります。
毎年2兆円増えています。
この内4割が国債でまかなわれているということです。
福祉という名の下では、その増額にはなかなか反対できず、膨らむばかりです。
でも、もうそろそろ限界に来ています。
増税でという話もありますが、成立も、またそれだけでは処理できないほどに支出が膨らんできています。
ヨーロッパの国債市場の混乱が日本にも影響を及ぼす勢いです。
日本の銀行が買い支えている日本の国債も先行き不安です。
いつ日本がギリシャの様になるか分かりません。
その可能性がはあります。
その時、国債でまかなわれている予算分は一気に消滅してしまいます。
日本はこれから高齢化が益々進み、福祉、介護の業界が伸びると言われています。
予算削減で福祉、介護の予算がカットされてしまうと、補助金も大幅に減額され、この業界が大きなダメージを受けるかもしれません。
勿論他の業界もそうです。
入ってくるお金で生活するという当り前のことに戻る時が必ず来るでしょう。
最初に書きました「優しさ」というものは、余裕があるから出来るものです。
余裕がなくなれば、人の事は構っておられず、自分が生活することが優先されます。
現在の「優しさ」の下の「豊かさ」は、過去の先人たちの苦労の末、作り上げた「豊かさ」です。
私たちの生活はその上に成り立っているのです。
そして今、私達が作っているのは借金です。
将来への子孫へただ単に苦労を作っているだけなのです。
来年は変動の年と予測されています。
経済的にも厳しく、私たちの周りの様子も変わって行くはずです。
今こそ、自立し、将来の子孫たちから「ダメな世代」と言われない生き方をしなければならないと考えます。
自力をつける
今、ヨーロッパではギリシャ問題から発して、ヨーロッパ全体が揺れています。
アメリカも経済が弱体化して、ドルが安くなっています。
中国もいつバブルが弾けるかという心配もあります。
日本もデフレ経済から抜けきれず、その上1000兆円近い国債も不安材料です。
日本も世界も経済がどうなるかという不安があります。
来年は大変革の予感があります。
一方、私達の生活はどうでしょうか。
景気が悪く、モノは売りにくく、給料は上がらなく、生活は大変だと言いますが、それでも毎日の生活では悲壮感も無く、楽しく生活している人が多いでしょう。
iphonが売り出されると爆発的に売れ、今はiphonをはじめとするスマートフォーンは一般携帯電話の台数を追い越して行きました。
日本人はまだまだ豊かです。
でも、確実に不況は深まっています。
リストラ、会社整理も増えています。
今まで600万円、700万円の年収をもらっていた40代50代の人が、リストラになり就職難に遭遇しています。
年収300万円ほどの職業には付きたくないと思っても、仕事がなければ就職しなければなりません。
就職先があればまだいい方かも知れません。
40代50代の人には就職先はそうありません。
そんな時、自分の無力さを知ることになるかもしれません。
自分の力を付ける為に勉強をすることは大切です。
でもその勉強が、ただ資格を取りたいとかいうだけでは意味がありません。
そんな資格を取っても、同じ資格の人は掃いて捨てるほどいます。
自分に力を付ける、すなわち自力をつけるには、資格は二の次だと思います。
一番大切なのは生活力があるかどうかです。
会社勤めていると、会社に頼ったり、肩書きや資格にこだわる人が多いようです。
でも、それではこれからの時代は生きていけません。
いっそ就職で苦労する位なら起業した方がいいでしょう。
その時、何かを当てにする気持、頼る気持を捨てていないとダメです。
これから自力が高い人しか生き残れなくなるかもしれません。
「誰かが何かをしてくれる」と思うから当てが外れるのです。
自力をつける勉強は精神力を高めつことかもしれません。
発想法を鍛えることかもしれません。
また、ネットワークを広げる活動かもしれません。
自分に足り無いものを加えるか、また自分のいいところを伸ばすのか。
自力をつけるということはそれそれ人によって違います。
今は早くこの事に気付き、行動する時だと私は思います。
コバンザメ商法
今朝テレビを見ていたら、売れているモノに乗っかる商法が紹介されていました。
よく言われる「コバンザメ商法」です。
この方法は起業家や小資本の会社が参入するのに適しています。
テレビで紹介されていたのはスマートフォーンに使われる、ペンや手袋等です。
スマートフォーンの画面にメモをするペンは従来からもありました。
でも紹介されたペンは、より細か文字が書けるなど、操作し易いペンでした。
もう一つは手袋です。
普通は手袋したままではスマートフォーンの画面を触っても操作できませんが、紹介された手袋は右手の指先に伝道糸を使っており、手袋をはめたまま操作出来るものです。
これも今、爆発的に普及しているスマートフォーンに追従し、乗っかった「コバンザメ商法」です。
私が以前に見たことがある「コバンザメ手法」で感心したのがあります。
それは八百屋なのですが、大手スーパーの駐車場近くに、バラック建ての様な簡単な建物をつくって営業を始めました。
営業を始めると、その八百屋に大変多くのお客さんが行くようになりました。
スーパーの野菜売り場より新鮮で美味しそうな野菜を売っています。
また、八百屋のお客さんはスーパーの駐車場を使っていますので、八百屋は駐車場を用意する必要がありません。
その内にその八百屋の周りに、魚屋が出来、その他スーパーのお客さん相手のお店が出来始めたのです。
もう一つ別な「コバンザメ商法」です。
結構、人の出入りの多いビジネスビルの正面玄関の片隅でレンタルボックスの店を開き、繁盛しているところまがありました。
レンタルボックスとは30センチ角程の箱を沢山用意し、そのボックスをレンタルします。
自分でアクセサリーや小物を作った人はそれを借りてそのボックスに入れて展示販売するのです。
この店もビルに出入りする客を当てにした「コバンザメ商法」です。
「コバンザメ商法」に似たような手法として、「ツイている人」に乗っかるというのがあります。
これは聞いた話です。
あるタクシーの運転手で成績が上がらず悩んでいました。
そんな時に、成績のいい運転手はどういう行動をするか知りたいと思ったそうです。
翌日からその成績のいいタクシーの後を追いかけるようにしました。
成績のいいタクシーは車を走らせていると、すぐ道端で手を上げるお客さんをキャッチするそうです。
そうすると、その後ろを走っているタクシーも不思議とタクシー待ちのお客さんに出会うようになりました。
これは「コバンザメ手法」というより、ツキのある人のマネをするとツキが回ってくるということでしょうか。
お金をかけず、確実に利益を出す。
「コバンザメ商法」は起業する人が「どこで」「どんな」商売をしたらいいか考える1つのヒントだと思います。
固定費
昨夜は2回目の社長講座を開きました。
題材にしたのは売上です。
売上とは何から成り立つのでしょうか?
突然聞かれると戸惑うでしょうが、売価×数量です。
当り前のことです。
でも当り前のことですが、これを良く踏まえないと前へ進めません。
次に売価構成はどうでしょうか?
売価=仕入単価+粗利単価です。
それでは粗利は何から構成されているでしょうか?
粗利=固定費+利益です。
経理を知っている人には、こんな簡単な事と言われてしまいます。
会社は最終的にはこの利益を上げることが目的です。
そしてその為に重要なことは固定費をいかに下げるかにかかってきます。
特に起業したばかりの人にとっては、思うほど売上が上がらない中で粗利を増やすことは難しいことです。
そうすると粗利の中の固定費部分を少なくすることが利益を増やすことになります。
ところが、分かっていても固定費を増やしている人がいかに多いことか。
特に男性がそうですが、見栄を張ってしまうのか、余計なものを買ったりします。
お金がなければ自宅で起業し、パソコンも机も今まで使っていたモノを使います。
電話も自宅のものを使います。
必要に応じてレンタルオフィスも使ってもいいかもしれません。(レンタルオフィスを運営している私としては積極的に使って欲しいですが・・・)
でも少し余裕が出てくると、そのところが甘くなります。
ついビルのオフィスに入ったり、事務員を置いたりします。
折角の儲けがそこで消えていきます。
起業を志す人、起業する人は特に固定費をかけないことを十分念頭に入れて起業すること。
あらかじめ将来に向かっての事業計画の中で、利益がいくらになったら従業員を雇い、オフィスを借りるかの計画を作っておきます。
それを達成するまで決して手を付けないという覚悟は必要でしょう。
照明のカバー
朝、出勤前に腹を立てることがありました。
昨夜から我が家の食堂の照明が、スイッチ入れてもすぐ5秒ほどで消えてしまうという現象が起きていました。
このような時は私の出番です。
台の上に上がり、その照明のカバーを外そうとしたのですが、外れません。
カバーに貼っている説明書きの通りしても外れません。
5分位経った頃でしょうか、急にイライラしてきました。
「業者に来てもらいましょう」という妻の言葉にも従わず「こんなの私でも出来る!」と言いつつ、「このヤロー!」と照明のカバーに毒ついていました。
やっと1か所は外れたのですが、あとは外れません。
イライラが募り、つい力を入れました。
カバーが割れました。
でも割れても外れません。
とうとう思い切って引っ張ったらバラバラになってしまいました。
「やっぱり業者に頼めばね・・・」と妻の言葉。
今度は腹が立ちました。
妻の言葉にではありません。
こんなカバーを付けた照明器具メーカーです。
割れたカバーを見てみると、内側に小さな黒い矢印があり、それの部分を突起物に合わせると外れるようになっています。
そんなの中を見なければわかりません。
カバーを付ける時はそれに合わせて付けるのでしょうが、外す時も分かるように、外側にハッキリ印を付けるべきです。
そう言えば大分前ですが、以前に住んでいた家でも同じようにカバーを割ったことがありました。
学習していない私も悪いのですが、こんな使い勝手の悪い製品をつくる方がもっと悪いです。
見てくれが良くても、使い勝手の悪い商品の1つが照明器具のカバーだと思います。
そうは思いませんか?
そして皆さんはこのような経験はありませんか?
近い内に業者に来てもらいます。
それにしても高い蛍光灯交換になりそうです。
講演会3
昨日に続き22日の講演会のお話を書きます。
福島大学教授白石豊さん、天外伺郎さんに続き、今日は西田文郎さんのお話です。
西田さんも数多くの本を書いています。
私も5冊ほど読んだことがあります。
西田さんは「能力開発の魔術師」と言われ、「スーパーブレイントレーニングシステム」を開発し、ビジネス界、スポーツ界、教育界に大きな影響を与えているメンタルトレーニングの国内第1人者です。
西田さんは西田塾の塾長ですが、その西田塾に入塾する費用は1人88万円です。
高いか安いかはその内容でしょう。
西田さんは「大した内容は無いのです」と言う割には、過去何千人という人が入塾しています。
以下は西田さんの言葉です。
成功には、社会から評価される「社会的成功」と人間力を高める「人間的成功」の2つがあります。
その2つの成功を得ることが本当の成功と言えます。
その成功を得る為に大切なのを脳の仕組みを知ることです。
人間の脳は成功いう概念が本当であっても、錯覚であっても肯定的にとらえてしまうのです。
この錯覚を利用して自分の夢を達成させてしまうことが出来ます。
西田さんのこのような思いから「アホの会」が出来ました。
「でっかくて非常識な夢」を描くことが出来るのはアホしか出来ません。
お互いの夢を高める為の会です。
この「でっかくて非常識な夢」を描き行動することは、白石さんが話した「ゾーンに入る」、天外さんが話した「フローに入る」と同じ意味を持っています。
やはり3者同じように人の夢を達成させるには、心理即ち脳に繋がってくるのでしょう。
西田さんはマズローの法則についても言っていました
皆さんもご存じのようにマズローは「生理的欲求」「安全の欲求」「社会的欲求」「自我欲求」「自己実現欲求」の5つの欲求段階説を唱えました。
しかし西田さんによるとマズローは最後にもう1つその上の欲求があると言いたかったそうです。
それは「積極的無欲」だそうです。
一生懸命に人間を磨きあげていく最後の姿でしょうか。
その反対が「消極的無欲」で、何もしないでただ生きている状態です。
西田さんはその最後の「積極的無欲」を得るには 人を喜ばせる「他喜力」が必要だと言っています。
その「他喜力」は稲盛さんが言う「利他の心」と同じようなものでしょう。
今回の講演会ではいいお話しを6時間近くにわたり聞きました。
そして皆さんが話された内容はすべて共通しているように思いました。
「本当の事は1つなのだ」という思いをさせらてた講演会でした。
講演会2
昨日は予定通り講演会に行ってきました。
開始時間より1時間早く行き、前列から3列目に席を確保。
この講演会は1000名近くの人が集まりました。
確かに4名の講師陣の顔ぶれを見れば入場料5000円は安いでしょう。
白石豊さん、天外伺郎さん、西田文郎さん、土屋公三さん。
この講師お1人でもそれくらいのお金を払って人は集まるはずです。
最初の講師は福島大学教授の白石豊さんです。
白石さんはサッカーの岡田監督のチーム作りをワールドカップ終了まで関わり、また阪神の下柳選手、日本ハムの田中賢介選手等アスリートのメンタルトレーニングの指導をしています。
以下は講師の先生のお話で、私が特に「成程!」と気になったことです。
白石さんの話です。
メンタルトレーニングの目的は簡単に言えば「肉体のリラックス」と「精神の集中」をいかにするかです。
自分の力を120%出ている状態を「ゾーンに入る」といいます。
その為には自分の枠を超えるほどの目標をもつことが大事。
そうすることで自分の枠を壊してしまう。
日本ハムの田中選手は枠を壊すほどの目標を立て、その為にどうするかを決めて、実行するといいます。
言葉で書くと簡単ですが、実行することがなかなか普通の人に出来ないことなのです。
天外さんの話し。
天外さんはフロー理論を話しました。
フローとはwikipediaでは次のように説明しています。
「人間がその時していることに、完全に浸り、精力的に集中している感覚に特徴づけられ、完全にのめり込んでいて、その過程が活発さにおいて成功しているような活動における、精神的な状態をいう。」
これは白石さんが話していた「ゾーン」と同じ意味です。
天外さんは以前ソニーの上席執行役員でした。
ソニーは創業以来フロー理論で成長していたのに、アメリカ式の成果主義の考えを取り入れたことでダメになったと言います。
フローに入れば奇跡が起きます。
いつも何か、知らない人がサポートしてくれます。
自然現象がサポートしてくれます。
宇宙がサポートしてくれます。
天外さんはそのフローに入る入口を教えてくれました。
①崖から飛び降りると思われる位チョット無理と思われることに挑戦する。
壁を超えないとフローには入らない。
②ワクワクした遊び心を持つ。
自分が楽しいこと、仲間が楽しいと思えることをする。
正しい・正しくない、良い・悪いの判断でするとそのワクワク感が生まれない。
③目標をしっかり持つこと
時には目標を持つだけでフローに入ることが出来ます。
などです。
この他にもフローに入る色々な入り口があるそうです。
気が付いたらドンドン良くなっていて、知らない内にフローに入っていたということもあります。
西田さんのお話などは、明日書きます。
講演会
今日は半日、講演会漬けの予定です。
この講演会は知人の事務所の開業30周年行事として開かれ、4人の講演者が登壇します。
1人は「スーパーブレイントレーニングシステム」を構築した株式会社サンリの西田文郎氏です。
数多くの本を出されています。私も良く読んでいます。
2人目は元ソニー上席常務で宇宙や人間の成り立ち根本法則などの本を多数出している天外伺朗氏。
3人目はメンタルトレーニングで有名な福島大学教授の白石豊氏。
4人目は土屋ホームという北海道ではトップクラスの住宅会社を創業した株式会社土屋ホールディングス取締役会長の土屋公三氏です。
この4人の人達は単独公演でも多くの人を集めることが出来る程の人達です。
それが4人纏めての講演は今まで聞いたことがありません。
入場料が5000円ですから充分その価値以上のものがあると期待しています。
このブログを見た方の中にも、講演会に行く方はいるかもしれませんね。
13時から始まって18時30分までの5時間30分になります。
1人1時間位のお話でしょうか。楽しみです。
ただ心配なのは、昨夜少し早い忘年会があり、寝不足なことです。
それでもしっかり聞き耳を立て、目を開いてお話を聞いてきます。
明日のブログでこの講演会の内容を書くことが出来ると思います。
歯について考える
昨日はセミナーに行ってきました。
「歯科治療の可能性を考える」という題名です。
知人からの紹介でしたので、あまり興味はありませんでしたが参加してきました。
しかし、考えてみると私も60歳を過ぎていますので、これから深刻な問題になるはずです。
今のところ入れ歯はなく、不便はないのですが将来は分かりません。
セミナーの内容はMTC(エム・ティ・コネクター)という新しい入れ歯の紹介です。
このセミナーはインプラント治療や従来の入れ歯の欠点から入りましたが、これが長かったです。
そのため予定時間をドンドン延長して話が続いたので途中退席してしまい、肝心のその効能はあまり聞けませんでした。
そのセミナーの中で興味ある話がありました。
入れ歯用の安定剤と言われるものは年間700万個売られているそうですが、その箱に注意書きとして「連続使用しないでください」と書かれているそうです。(私は確認していませんが)
歯茎に良くないそうです。
ちなみに、このMTCでは安定剤は使わないとのこと。
またインプラントも治療費が高い上に、治療が難しく治療後のトラブルが多いそうです。
この講演を聞いて思ったことは今ある歯をいかにして残すかです。
その為には歯医者の主治医をもつこと。
いい歯医者が傍にいることは幸せなことです。
私も幸せなことに、従兄弟が歯医者、兄嫁の実家も歯医者です。
今は従兄弟の方に行っていますが、これがいい歯医者です。
歯の治療も無駄なお金を使わせない方法を考えます。
その上必ず、歯の磨き方を指導してくれます。
何回行ってもその都度歯磨き方法をチェックしてくれます。
従兄弟のおかげで、虫歯はなく、歯槽膿漏もありません。
時々歯のチェックをしてもらいに行きます。
虫歯にならないようにと、治療と同じように歯磨きの指導をここまで徹底して教えてくれる歯医者は、今まで会ったことがありません。
その為か、患者さんは多いのですがあまり儲かっていないようです。
でも彼のおかげで助かっている患者さんは多いはずです。
私は毎日、3種類の歯ブラシを使って歯磨きをしています。
これからも歯を大事にします。
美味しいものを食べるためにも!
手帳
あと10日で12月になります。
これから年末にかけて忙しくなります。
私は先週は行事、特に夜の行事が多く、週末は少しダウンしてしまいました。
金曜日の夜、土曜日1日は何もしないでただボーとしているだけでした。
自分の年齢の事をいうつもりはありませんが、若い時と同じようなビッチリ詰め込む予定は少し無理かもしれません。
でも年末となるとやはり忙しそうです。
年末と言うともうそろそろ来年の手帳を準備しなければなりません。
私はマンダラ手帳を10年ほど前から使っています。
ありがたいことに、毎年ある方からプレゼントされます。
使って思うことは、「これを使いこなすと人生もビジネスも変わるぞ!」ということです。
確かに使ってみて私の考え方は変わりました。
仕事の方法も変わりました。
この手帳は深いものがあります。
私の周りにも使いこなしている人が多くいます。
私もより深く使いこなそうと思うのですが・・・・
今は自分なりの使い方でいいと思っています。
手帳を使う時、書くことが楽しいと思わなければ続きません。
無理をせず、自分なりの手帳にしていくうち、絶えず傍にある相棒の様なものになります。
この時期は来年の予定を今から決めて、書き入れていこうと思います。
自分のしたいこと、行きたいところ、なりたいこと。
そう考えると来年が楽しみになります。
昔聞いた落語のセリフにいいのがありました。
少しうる覚えですが、「貧乏だけれど俺たちにも手つかずの来年がある」と言うのです。
金持ちも貧乏人も、皆平等に「手つかずの来年がある」というのは楽しくなるセリフで、覚えていました。
皆さんも新しい来年の手帳を手にして、楽しい予定を書き込んでみませんか?
ブータンからの義援金
今日本にブータン国王夫妻が来日しています。
ブータンという国はGNH=国民総幸福という指標を掲げています。
世界中からその考え方への共感の声が上がっています。
日本人にとっても国民総幸福という考え方への共感と親日的ということから各地では大変な歓迎を受けています。
東北の大震災にはブータンは寄付を募り、100万ドル(約8000万円)の義援金を送ってくれました。
ブータンという国の年間平均所得が15万円という人々が100万ドルを送ってくれたということは、驚くべきことです。
国税庁の「平成22年分 民間給与実態統計調査」によると、平成23年(平成22年12月31日現在)の日本の平均年収は412万円です。ブータンの27倍以上になります。
その国から100万ドル送られたということは日本の所得換算で考えれば2700万ドル相当になります。
日本円で21億6000万円に相当する額です。
日本がかって1つの国にこれほどの義援金を贈ったことはあるでしょうか?
ODAのように国が税金を出すことはありますが、義援金として集めて送ったことはありますか?
勿論お金ばかりではありません。
震災が起きた時、すぐに国王自ら、死んだ日本人に対して祈りをしてくれるということもうれいしいことです。
お金持ちの国から100万ドル200万ドルいただくより、何倍も嬉しいです。
今回のブータン国王夫妻の来日によってそれらの事はマスコミから紹介されました。
もしかして、来日されなかったら、報道されず、これほど多くの日本人に知れなかったのではないでしょうか。
もしもそうなら、日本人はブータンの人々の優しい思いを知ることはなかったのです。
そして日本人は恩を感じない国民と思われたかもしれません。
そう考えると、そのことを事前に知らせなかった国やマスコミの怠慢だと思います。
ブータンの幸福度を報道し、それを日本でも広めていと考えるマスコミは、他の国の人々からの支援・援助も細かく報道するべきです。
そうすることで人の優しさ・ありがたみが分かり、今度何かがあったら真っ先にお返ししようという気持ちにさせます。
それにしても、ブータンで何かが起きた時、日本人が21億円相当のお金をすぐに義援金として集め、送ることが出来るでしょうか?
その分自分の欲望を押さえて出来るでしょうか?
他国で何かが起きた時、日本人1人1人がその国の人々に対して、すぐに何かをすることこそが本当の友好になるのです。
国がするのではなく、その国民がすることこそが大切です。
今日ブータン国王夫妻は帰国されるそうです。
ブータンへの関心が高くなり、日本人の旅行客が増えると予想されているようです。
機会があれば私も行きたいですね。
一緒に行きませんか?
ワールドカフェ
昨夜は「ワールドカフェ」を私の事務所で開催しました。
「ワールドカフェ」は最近注目されているフリートーキング形式のアイディア発想法です。
4名のグループに分かれ、会話をしながら、広げられた模造紙に落書きでもいいので、ドンドン書き込んで行きます。
「ワールドカフェ」は1995年にアメリカで開発されたものです。
会議室で議論していて、いいアイディアが出なくても、場所を変えてスターバックスなどのカフェでコーヒーを飲んで話している時、思いもよらないひらめきが生まれるという経験はありませんか?
心理学的にも、人は飲み食いすると警戒心が薄くなり、お互いの胸襟を開いて話をするようになります。
「ワールドカフェ」はその効用を積極的に取り入れたアイディア発想法です。
この勉強会の仲間は、以前私が「身の丈起業のすすめ」を主宰していた時参加していた人達です。
そして新しいことに挑戦するのが好きな人達です。
「ワールドカフェ」を開くに最低人数は12名からですが、昨夜は欠席者が多く8人でした。
そのため本来の方法では運営できませんでした。
それでも、それらしく話し合いを楽しみました。
運営を準備した人達が大変凝っていて、事務所にボサノバの音楽を流し、コーヒーマシンで入れたてのコーヒーを用意。その他の飲物もあります。
サンドイッチやお菓子等の沢山の食べ物も用意し、その上ウエイターエプロンも持参していました。
私もエプロンを着せられました。
本当にカフェのような雰囲気を出しての「ワールドカフェ」でした。
題材は「札幌観光」としました。
この「ワールドカフェ」を進めてみると、確かに色々なアイディアがどんどん出てきます。
びっくりするほどです。
そしてメンバーの中でイラストの上手な人がいて、皆から出てきた話を模造紙の上に絵にして描いてゆきます。
これは良く分かりやすく、話が盛り上がります。
昨日は本当のトライアルでした。
ただ「ワールドカフェ」が面白いということが分かっただけでも、次回何か検討する時には使えます。
楽しい勉強会でした。
模造紙に書いた内容を写真に撮り載せています。

団塊の世代
昨夜も飲み会でした。
高校時代の同級生3人で語り合い、遅くまで飲みました。
私以外の2人は共に高校卒業以来初めての顔合わせでした。
始めはぎこちない話も、酒がすすむにつれ、盛り上がってきました。。
3人の話は、最初はこの年齢からでしょうか、身体の不調の話から始まりましたが、やはり話の中心は仕事に移って行きます。
彼ら2人の話を聞いていると、まるで映画のドラマを聞いているような興味あふれる話でした。
特に空調工事の仕事をしていた友人の会社人生はサイパンから始まり、日本・世界の各地で仕事をしました。
青函トンネル工事も空調関連を受け持ち、その仕事の中心となり完成させました。
ある事故が発生した時は、彼を中心として救助し、人命救助の表彰も受けています。
私たちは62歳。
現役から身を引いて振り返った今、みんな頑張ってきたと胸を張って言えます。
みんなは、良き夫だったかは分かりませんが、良き父であり、素晴らしい職業人だったのです。
これからの人生まだまだ時間があります。
どのように生きるか。
今までとは違う人生でしょうが、これからもまた誰かのため、何かのために生きていくことだと思います。
団塊の世代はまだ頑張ります。
偶然ではなく必然
昨夜は京セラフィロソフィ勉強会の打ち上げがありました。
いつも勉強している私のオフィスで、1人1000円相当の「自分が飲みたいモノ」「食べたいモノ」を買い、持ち寄ってのパーティです。
勉強会は約1年半、18回続きました。
参加する皆さんは出席出来る時はそれぞれ違う訳で、昨夜初めて顔をあわせた人同士ということもありました。
この勉強会は私にとって自分のための勉強会でした。
私が主宰して、参加した人同士が互いの考えを述べ合いながら、新しい考えも取り入れていく、その過程が勉強でした。
そしてこの勉強会で知り会えた人同士、知り会えたことは偶然ではなく必然でなかったかと思っています。
最近私は全てのことが必然で起きると感じるようになりました。
起きてしまったことはすべて正しい。
そう思えば、後悔することも少なくなってきます。
年と共に考えが変わったというより、良い人との出会い中から、その感謝の気持ちが芽生え、偶然ではなく必然だと思わせたのかもしれません。
今は1年半、毎月続いた勉強会が終わるという淋しさはあります。
それと共に、何とか1年半続けれてこれたという満足もあります。
来年度にはまた何かテーマを見付けて、勉強会を開始したいと思います。
どなたか興味ありそうなテーマがありましたら教えて下さい。
「君の椅子」プロジェクト
今朝は朝食会と称した勉強会がありました。
毎月開かれる勉強会ですが、今月は「君の椅子」についてのお話でした。
「君の椅子」という活動は「誕生する子供を迎える喜びを地域の人々で分かち合いたい」という思いから、2006年に始められました。
小さな椅子1つ1つに名前と生年月日・シリアルナンバーが刻まれ、生まれた赤ん坊にプレゼントされます。
現在は北海道の東川町、剣淵町、愛別町が参加しています。
今日の講師は元北海道副知事で現在財団法人北海道文化財団の理事長をしている磯田憲一さんです。
磯田さんは「君の椅子」プロジェクトの代表でもあり、また旭川大学の客員教授でもあります。
磯田さんは数年前、大学のゼミの時に学生から「子供が生まれると花火を上げる町がある」という話を聞きました
そこで旭川では何が出来るかと考えたそうです。
旭川⇒家具の街⇒子供の誕生を喜ぶモノは何?⇒子供の椅子とつながったそうです。
「君の椅子」の「君」という呼称を付けた理由は、赤ん坊と言えども1人の人間として人格も人権もあることを強調したかったからです。
現代は悲しいことに子供への虐待やイジメ、それによる自殺が増えています。
そのような事がないようにとの思いで、子供へ「君の椅子」をプレゼントするプロジェクトが誕生しました。
「生まれてきてくれてありがとう。君の居場所はここにあるからね」というメッセージが込められています。
このプロジェクトは最初は旭川市からと思ったそうですが、人口が多く予算の問題で、旭川市は参加しませんでした。
そこで近くの東川町が最初で、その後愛別町、剣淵町が参加しています。
生まれて100日経った頃に町長やグループの代表が訪問して手渡ししています。
2006年から始まってますが、毎年デザインが違います。
色々な一流のデザイナーと家具職人が作る手作りの椅子です。
ある3人の子供がいる家庭ではデザインの違う椅子が3つあり、それぞれが子供の居場所になっているそうです。
このプロジェクトの延長で今検討されているのは、3月11日の東北大震災が発生した日に生まれて来た子供達へ椅子を送る「希望の君の椅子」計画があります。
今計画進行中です。
現在「君の椅子」プロジェクトでは3つの町がプレゼントしていますが、個人的にプレゼントとしたいという声も日本中からあり、「君の椅子倶楽部」というものが出来ました。
それに参加すると可能です。
ご興味のある方はホームページを見てください。
「君の椅子」プロジェクトのホームページ
http://www.asahikawa-u.ac.jp/page/kiminoisu_project.html

航空会社
先日の新聞にJALの中間業績が掲載されていました。
私は平成22年2月に稲盛さんがJAL会長に就任してから、JALに関する新聞記事が出ると切り抜き、保管しています。
今年の4月から9月までの中間営業利益が1061億円となり、今期の目標営業利益757億円をすでに突破したようです。
その為、今期通年営業収益を1400億円に上方修正しました。
ANAの中間営業利益は501億円ですから、JALの1061億円は如何に大きいか分かります。
そのJALも格安航空事業に参加すると言われています。
稲盛さんは格安航空事業(LCC)に参入したことについて次のように述べています。
「低料金でお客様を乗せるLCC事業は厳しいと思っていました。でも、LCCの勉強もしないといけない。ジェットスターからお誘いがあったので、主導権を持つのではなくて、勉強を兼ねて参入を決めました」
どちらかというと格安航空事業には否定的です。
先日上京した時、いつもはJALを使うのですが、いろいろ事情がありスカイマークを利用しました。
スカイマークを使って第一に思ったことは、「遅れる」ということです。
千歳空港発が45分遅れ、最終的には1時間遅れになりました。
また帰りの羽田発も10分遅れが20分遅れです。
電光掲示板に表示される各航空会社の出発予定時間が、スカイマークだけが遅れた時間で表示されています。
今回の私はビジネスではなかったので、少しくらいの遅れは気になりませんでした。
でも、時間で動くビジネスマンにはこの遅れは致命的です。
1時間も遅れると仕事になりません。
この時間の不確かさはお金では換えられません。
やはりJALなりANAを利用する方が確実だという思いになります。
格安ということはそれなりの覚悟が必要でしょう。
スカイマークからは「出発時間が遅れたことに対し、心よりお詫び申し上げます」というアナウンスが流されますが、その声が空々しくなるほど、遅れは多いです。
逆を言えば、安くて時間に正確であれば格安航空会社は伸びるのでしょう。
これからの航空会社の競争に興味があります。
社会貢献
昨日帰札しました。
今回の上京は3日間で、11日は多摩市にあるココリアホールで「SOHOリレーフォーラム」に参加してきました。
「SOHOリレーフォーラム」の基調講演は株式会社ソーシャルプランニングの竹井善昭氏です。
竹井氏はマーケッティング・プランナーとして活躍され、最近は社会貢献活動、ソーシャルビジネスに特化されています。
「社会貢献でメシを食う」という本も出され、今回の講演はその同じ題名です。
社会貢献する組織としてはNPOが代表的なものでしょうか。
日本には1万5千ほどのNPOの団体がありますが、その内人件費を支払い、利益を出している団体がどの程度あるでしょうか。
いくら社会貢献だといってもそれでメシを食べることが出来なければ意味がありません。
竹井氏の講演でも紹介されましたが、アメリカにあるNPOのCEOの年収は3千万円を超す人が多くいるそうです。
またNPOへの寄付を集める専門家であるファンドレイザーが活躍しています。
彼らの年収も8百万円はあります。
アメリカでは「社会貢献でメシが食えている」人が多いのです。
日本のNPOも「社会貢献で飯が食える」ようにならないとダメだと竹井氏は言います。
私も以前からNPOもしっかり利益を出さなければならないと思っていましたので、竹井氏の意見には同感です。
ただ、疑問が残るのです。
「社会貢献」とは何でしょうか?
竹井氏は「社会貢献」とは社会問題を解決することと説明しました。
でもNPO等の非営利団体だけが「社会貢献」をしているのではないのです。
社会に貢献をしてそれに対してお金が支払われる。
それは民間会社も同じなのです。
人が困っていることを改善する。その中には社会的問題もあります。
それを解決することで利益をもらっています。
その貢献が高い分、多くの利益をもらっています。
昔、松下幸之助さんは電気製品で豊かな生活を国民に贈りたいということで、「水道哲学」という考え方で経営しました。
これこそ「社会貢献」です。
会社の経営をしてきた中で私が学んだことは「価値のないものは売れない」ことです。
人が喜ばない、社会が受け入れないモノは売れません。
もしかして日本のNPOの人達の中には、価値あるモノを提供できず、対価が少ないことの逃げ道として、言葉だけ「社会貢献をしている」と言っているように思います。
どのようなことでもしっかり稼ぐようにしなければなりません。
講演の中でも学生の話が出ていました。
就職試験の時将来は「社会貢献をしたい」という学生が多いそうです。
会社の担当者によると、学生はその「社会貢献」は実際どの様な事なのか、何か良く分からず言葉だと言います。
私は会社を経営し「社会貢献」を目指す人を応援します。
君主論
皆さんは「マキャベリスト」という言葉や「君主論」という本をご存じでしょうか。
少し年配の人なら若い頃読んだかもしれません。
10月にNHK教育でマキャベリの「君主論」を取り上げていました。
それを見て、読んでみようと興味を持ちました。
私の若い頃もマキャベリの「君主論」は仲間の話の中に出てきましたが、読もうという気がしませんでした。
「目的のためなら手段を選ばない」という考えが、若い頃の私は反発を覚えて嫌っていました。
マキャベリを信奉する者をマキャベリストと言います。
権謀術数主義者という意味と同意語になっています。
マキャベリとは15世紀末から16世紀初頭に活躍したイタリアの外交官で、「君主論」を書きました。
ノンキャリア外交官だったマキャベリが、当時の権力者へ向けた就職のための論文だったと言われています。
現在もこの「君主論」を愛読書にしている経営者や政治家も多いそうです。
私はこの「君主論」はまだ読みかけですが、気になる言葉があります。
「残酷さと慈悲深さとについて、敬愛されるのと恐れられるのとではどちらが良いか」についてです。
マキャベリは、始めに「君主は慈悲深く、残酷でないという評判を得るようにしなければならない」と言います。
しかしこの慈悲深さを誤用してはならないとも言います。
「思慮と慈悲心とによって自らを抑制するようにし、あまりに他人を信用して不用心になったり、あまりにも他人に不信感を抱いて耐えがたいような存在になったりしないようにするべきである」
そして「恐れられるより愛される方が良いか、あるいは反対か」と問うています。
それに対して「両方であることが望ましいと答える人がいるが、それは難しい。
したがって、両者のうちどちらかが良いかとなれば、愛されるより恐れられる方がはるかに安全である」
この文章を読んだ時に思ったのが稲盛さんが良く言われる「小善は大悪に似たり、大善は非情に似たり」という言葉です。
最初は「真・善・美」を大事にする稲盛さんと「目的のために有効ならば、手段を選ぶべきでない」と言う権謀術数主義のマキャベリは正反対のように思いました。
全く逆の行動をとる人かと思っていたのですが、もしかしたら考え方は似ているような気もします。
2人を比較して読んでみようと思っています。
「会社を倒産させないためには手段を選ばない」というところは現代の経営でも重要なところです。
「君主論」は面白そうです。
自力をつける経営
起業家が起業を志したきっかけは色々あると思います。
お金を稼ぎたい。贅沢したい。好きなモノを買いたい。思い通りに人を動かしたい。世の中を良くしたい。
様々あります。その動機がどうであれ起業することはいいことです。
起業しようとすると、今はそれを支援する団体や制度は沢山あります。
起業・創業資金の貸出も容易に受けることが出来ます。
インキュベーション施設も充実しています。
ただ最近フッと思うことがあります。
起業して実業の世界に入って行くと、守ってくれる人はいません。
最初は社長になって目標に向かっていく自分を夢描いていますが、しかし実際は自力で、誰にも頼らず、汗をかき、涙を流し、時には這いずり回りながら登って行くこともあります。
その時必要なのは「根性」です。
「根性」という言葉は最近聞かれ無くなりましたが、同じ意味で「ネバーギブアップ」です。
誰にも頼れないからこそ大切です。
30年以上前は、現在のように起業の環境が整備されていなく、起業する人達は、知人にお願いしてお金を集め、足りなければ銀行に事業計画書を提出し、承認受ければ自己保証でお金を借ります。
経営指導してくれるところは銀行とか商工会議所くらいで、実際は周りにいる経験者や先輩たちに教えを請うて、学んでいきました。
事業計画書の書き方は銀行に行って教えてもらい、商売の仕方は他社の見よう見まねでやりました。
市場調査とか、マーケッティング等分からなくても商売を伸ばしてきました。
経験しながら自力をつけ事業を拡大してきました。
それに対して現在のように起業の大切さが言われるようになって、国などの「官」が起業に対するいろいろな環境を整備してきてくれました。
極端に言えば手取り足とり教えてくれ、支援してくれます。
インキュベーション施設も安い料金で入居出来、そこではマネージャーがいて相談ものってくれます。
しかし、先ほども書きましたように、実業の世界は昔と変わらず厳しいものです。
その厳しさを知らずにインキュベーションから出た途端に、風邪をひいて倒れてしまうかもしれません。
実業の世界では自力がモノを言います。
勿論「官」のサービスを利用してもいいのですが、早くそこから脱した方がいいと思います。
実業に入ったら民間のネットワークを使うことです。
自分の周りに作るのもいいです。
また、既にある民間の起業支援ネットワークに入るのもいいでしょう。
私も入っていますがNICeという団体があります。
「つながり力で、日本経済と地域社会の未来を拓く!」を合言葉に起業家を支援しています。
起業した人同士、またそれを支援する人とのネットワークです。
そのようなところが、昔のように先輩や経験者に相談し、教えてもらえ、起業家同士は互いに助け合いながら、成功を目指していける世界をつくるのではないでしょうか。
この団体も「官」ではなく一般社団法人格で頑張っています。
周りにも同じような団体やネットワークがあるかもしれません。
「民」の力で自力ある骨太の経営を目指しましょう!
人との付き合い方
先週の土曜日に、卒業した高校の同窓会がありました。
母校札幌西高は二中と言われた時も含め、来年で100年になります。
久しぶりに同期の友人たちと会い、楽しい時間でした。
この同窓会には毎年出席していたのですが、今年は用事があり欠席する予定でした。
ところが前日に20年会っていない友人から電話があり「明日の同窓会出るんだろう?」と言われ、懐かしさのあまり「うん。いいよ」と言ってしまったのです。
色々調整して参加しましたが、久しぶりに会った友人や思いがけない人に会い、出席した良かったです。
このような会が選挙時に行われると、いつもは顔を出さない人が挨拶をして回ります。
1票でも獲得しようという思いでしょう。
私の知らない人がそれをする分には気にしないのですが、それが知人だと、私は逆に反発してしまいます。
普段は協力的でないのに、自分の都合のいい時だけ出てきて宣伝するのは嫌われます。
これは仕事でもそうです。
自分の都合だけで仕事をする人がいます。
普段はほとんど協力もせず、顔も出さないのに、新製品が発売されたり、新しい仕事をする時だけ入り込んでくる人がいます。
このような行為は逆効果です。
本人は気付かず一生懸命なのでしょうが、私は引いてしまいます。
そうではなく、いつもから参加し協力的な人が、仕事ではあえて自分が参加している会やネットワークを利用しようと思わず、正攻法で仕事をしている人もいます。
そのような時は逆に、支援・応援しようと、参加メンバーがその人に代わって応援メッセージを出して行くのではにでしょうか。
これはその人の性格が「積極的」「消極的」ということではなく、「利用出来るものは何でも利用しよう」と思うか、「大事にしたいモノは大事にする」かのどちらかです。
人でも、集まりでも、ネットワークでも、自分の仕事の利用だけを考えている人は、はじかれてしまいます。
何でもそうですが、仕事のためと思いながら付き合うか、本当に好きになって付き合うか。
それによって人生の楽しさが違ってくるように思います。
ギター製作
私の事務所にはいろいろな方が訪ねて来られます。
先日、知人が起業家のAさんを連れて来て、紹介していただきました。
知人はお世話になっている人で、いつもいろいろな情報を教えてくれます。
今回連れて来られたAさんはギター製作にて起業を志しています。
Aさんが作るギターはアコースティックではなく、エレキギターです。
今回はギター製作をするAさんと、同じく木を扱っている私の家具会社との連携が出来ないかとの思いで紹介してくれたのです。
Aさんは今まで自宅でギター作りの作業をしていましたが、手狭になり場所を探しています。
私の工場の片隅を借りてと作業をしようと思っていたようです。
しかし、これから冬を迎えるに当たり、私の工場は断熱工事はされていないので、冬は寒く、とてもギター製作のような繊細な作業ができる環境ではありません。
ただ、ギター製作をする時必要な、塗装の相談や木の切削等については協力できるはずです。
現在、団塊の世代の人達を中心に再度楽器演奏に挑戦し、第2の青春を謳歌しようとしている人が多くなっています。
その人達は結構お金もあり、自分が気に入ったものにはお金を出します。
そのような人向けにオーダーメードのギターを提供しようというのがAさんの考えです。
Aさんによると、ギター制作で使用している木材は外国産だそうです。
日本の木ではいい楽器が作られないと言われています。
でもそうでしょうか。
北海道には豊富な木材があります。
多くの種類の木材がある北海道は、ギターをはじめとする道産材を使った楽器が製作される環境にあると私は思っています。
各民間企業や工業試験場・林産試験場との研究で解決されるはずです。
ゆくゆくはいろいろな種類の楽器を作る職人集団として広がっていけば、北海道の道産事業として注目されるようになるのではないでしょうか。
紹介してくれた知人もそれを期待して支援しています。
現在、楽器製作する学校は北海道にありません。
そのため道外に出て行って、学びそのまま北海道に戻らない人が多いようです。
でも、その人達を受け入れてくれる事業が北海道にあれば、学んだのち戻って来てくれます。
そのようなためにも、今回のようなギター製作するAさんを支援し、応援していうことは大切なことです。
私もこの起業家Aさんを支援していきたいと思います。
自分はどの山に登るのか
昨夜若い起業家が2人集まり、社長講座と称した勉強会をしました。
以前にたまたま、その1人と話をしていて、「私社長になります」と言ったことがきっかけで始めました。
この勉強会は少人数がいいので、志の高いもう1人の起業家も誘いました。
この勉強会は私が教えるというより、2人がそれそれ考えてもらい、自分で結論を出していく形式で進めたいと思っています。
社長として経営していく上で、最終結論は自分が出さなければなりません。
その結果は全て自分で責任を負うことになります。
ただ社長として結論を出す時、考え方を間違えると折角の努力が無駄になるか、見当違いの方向に進むことがあります。
起業したばかりの時は軌道修正をする「人」「場」があれば判断の助けになるはずです。
この勉強会はそのような思いで月2回ほどのペースで開く予定です。
また、この勉強会に参加する私も含めて3人は、ここで話し合った秘密事項は他言しないという約束を立てました。
だからこそ本音の話が出来る「場」になると思っています。
昨日は自分が向かうべき目的は何かを知るために、「自分はどの山に登るか」について話し合いました。
経営をする時、ただ一生懸命頑張ろうという思いだけでは前に進みません。
エベレストに登るのか、富士山に登るのか、札幌近郊の手稲山に登るのか、それとも2時間ほどで登れる三角山に登るのか、それを決めなければ心構えも、装備も、組織も違ってきます。
最初からエレベストを目指す人もいるでしょう。
近くの三角山を上り、次に手稲山、そのうち力を付けて富士山を制覇する人もいます。
どの山を目指してもいいのです。
大事なのはどの山を目指すのが自分にとっていいのかを知ることです。
昨夜この重要性を話し合い、それぞれの向かうべき目標について語ってくれました。
次回はこの向かうべき山を具体的に考え、披露することが宿題となりました。
この勉強会が今後どのように展開するか、私も試行錯誤で進めますが、しっかり2人をフォローしていこうと思っています。
そして今後が楽しみです。
ルミネ開業で考える
最近有楽町にルミネがオープンしたとテレビ等で報道されています。
今は大変なにぎわいだそうです。
以前は西武が入っていたのですが、経営不振のため撤退した後にはいってきました。
西武有楽町店が入居したのは1984年で有楽町センタービル(マリオン)に阪急デパートと並んで開業しました。
開業当時はバブルの頃で物凄いにぎわいでした。
それが1991年頃バブル崩壊と共にデパートの人気が下がりはじめました。
デパートの時代が過ぎ、とうとう西武有楽町店は去年12月に閉店しました。
その建物を引き継いでのルミネの開業です。
建物の外観等の大幅な変更はせず、そのまま内装を変えてだけのオープンの様です。
このルミネ有楽町店のにぎわいは一時的かもしれませんが、ルミネは若い人達に人気のある会社なので、案外長く人気が続くと思われます。
このように経営や運営がうまくいかない店やホテルが、経営者が変われば一気に良くなるという話は良くあります。
勿論、投資コストが違います。
100億円かけて作ったデパートも、その投資に合ったほども収益が出なければ撤退します。
しかしそれを引き継いだところが20億円で買収し運営すればそこそこの収益でも十分成り立ちます。
今は積極的経営をする企業にとって、いい物件を相当安く買収し事業展開する絶好のチャンスなのかもしれません。
ただ投資効率ばかりでなく、人の経営手腕で変わることも多いのです。
株式会社ミスミという会社は現在三枝匡氏が会長です。
三枝氏は以前「V字回復の経営」や「戦略プロフェッショナル」等の本を書き、私も熱心に読んでいました。
その三枝氏が2001年に請われて株式会社ミスミ入ってから、同社は凄い勢いで業績が回復し、現在優良企業になっています。
また、ハンバーグのマクドナルドも現在の原田泳幸氏になってから業績が回復して、過去最高利益を出しています。
日本マクドナルドは藤田田氏が創業して業績を拡大していきましたが、藤田氏が亡くなってから業績が低下してしまいました。
その後原田氏によって業績は回復したのです。
同じ場所で、同じ会社で、なぜ人によって業績が変わるのかを考えることが大切です。
私が若い頃ある部門の責任を負わされていましたが、業績が良くありませんでした。
その時父に言われました。
「お前に代わって誰かが責任者になり、業績が良くなったとしたら、どうする!悔しくないか?」と。
「だから頭を絞って絞って考え、方策を考えろ!」と言われました。
その時会社経営も運営も「人による」ということが良く理解できました。
最後の1つ
私は今、シンプルな暮らしに憧れています。
身の回りの物が片付かないこともあり、その思いが強くなっています。
本も、手元に置く本とオフィスに置いている貸出用の本、そして売却する本と整理しましたが、まだ整理しきれない本が残っています。
そんな時「究極最後に手元に残す1冊はなんなのだろうか」と思いました。
それも絞れていません。
稲盛さんの本なのか、ドラッカーの本なのか、カーネギーの本なのか。
また、身の回りにあるモノをそれぞれ1つ最後に残すとすれば何なんだろうとも考えてみました。
万年筆も7~8本あります。
モンブランの万年筆と使いなれたプラチナの万年筆が残ります。
気に入った椅子も30年前に買った「ねむの椅子」か、使い古した松本民芸のキャプテンチェアーか。
靴もリーガルのウイングチップか、履きなれたウォーキングシューズか。
そんな風に自分の周りにあるモノを絞り込んで行くと、自分は何が好きなのか、どんな生き方をしたいのか、何に憧れているのか等が整理されてくるように思います。
江戸時代は持家の人はほとんどいなく、狭い長屋などで暮らしていたと言われています。
いつでも引っ越しがしやすいように、生活に必要な道具は、碗1個、箸1本、鍋釜1つ等、今では考えられないほど少なかったようです。
それでもそれなりに満足した生活をしていました。
勿論、それを現代にそれを当てはめようとは思いません。
生活様式が違います。価値観が違います。
現代は江戸時代ほどのモノのない生活は出来ないと思います。
でも、一方最近「断捨離」とか「シンプルライフ」とかの風潮は広まっています。
気に入ったモノだけに囲まれて暮らしたいという考えです。
その傾向はもしかしたら、モノを捨てることばかりでなく、煩わしいことも捨ててしまいたいという思いもあるのかもしれません。
何にも拘束されない自分らしい生活への憧れなのかもしれません。
私は特別煩わしいモノをもっているわけではありませんが、「究極これだけあれば満足」というものだけというシンプルな生活に憧れています。
神様の女房
昨日、前から読もうと思っていました「神様の女房」を読みました。
以前には同じ題名のテレビも見ました。
松下幸之助さんの一生が夫人のむめのさんの目を通して書かれ、とても興味深く読みました。
世間では経営の神様と言われている人が、悩み、時には怒り、ちゃぶ台をひっくり返したり、夫婦喧嘩もよくしていたというのは、どこでもいる夫婦にうつり親しみを感じます。
しかし生活の中でも仕事においても[筋を通す生き方」を貫いた夫婦でした。
世間的な常識は守るけれど、おかしいことはおかしいと自分の筋を通します。
これは幸之助さんもむめのさんも同様です。
本の中の抜粋を少し。
幸之助さんが自転車商会で丁稚の時に学んだことが紹介されています。
その自転車商会のご主人のお兄さんが目の見えない人で、その人を自宅から店へ連れてくるのが仕事でした。
その道すがら、その人から教えられた事です。
幸之助さんの言葉です。
「目の見えへんの人には、目の見えへん人にしか見えない世界がある、とよう言われた。
親切や、と自分で思ってる人に限って親切なんかやない、とかな。
そらそうやな。でもな、もっと言うたら、どんな人にもその人にしか見えない世界がある、ということなんや。
それを理解して、人と接することが出来るかどうか。いつでも相手に敬意をもって接する、いろんなものの見方があるということを理解しながら、接することが出来るかどうか、ということや。
実は人というのはそれをよう見とるんやと思う」
この言葉は幸之助さんが「聞き上手」と言われ「耳学問をしてきた」ということに通じます。
そして体の弱い幸之助さんが、人を生かした経営をしてきたという、幸之助さんの考えの根本にあったことではないでしょうか。
またむめのさんの言葉もいいのがありました。
「普段着とよそゆき、という考え方があるやろ。家では汚い格好をして、よそへ行く時はきれいな格好をする。
でも、よくよく考えてみれば、それは、本末転倒ではないやろうか。
ほんまなら、普段を大事にすることが、大切やということや。
たまにかっこええことをしても、それはほんまもんやない。
毎日しゃんとするから、それは意味を持ってくる」と言っています。
「普段を大事にする」ということは「目から鱗が落ちる」ような思いがしました。
むめのさんによるとその例として
「例えば、家に部屋がある。一番日当たりのいい、きれいな部屋を客間にする人がいてはる。
客人にとってはうれしいことやろうし、見栄張れるかもしれんが、これも本末転倒やと思う。
一番いい、使いやすい部屋は、自分達で使う部屋にするのがええはずや。
お客さんの部屋は、少々日当たりが悪うても、むしろ、落ち着ける部屋にする方が大事やと思う」
見栄を張ることではなく、毎日の自分達の生活が基本なのだということです。
同感です。
住みやすい環境を作りながら、しゃきっとして生活をする。
これもシンプルライフに通じるところがあります。
手の届く贅沢
日常、生活している中で、自分のお気に入りというものがあります。
身の回りにあるものの中で、私が気に入っている物の1つに酒器があります。
酒器も色々な種類がある中で、どうしてもその器に手が行きます。
ところがその気に入った器に限って、割ってしまうのです。
先日も続けて、大事に使っていた猪口を2つ、ウイスキーグラスを1つ割ってしまいました。
普段使いのグラス等はもう10年以上も使っても割れていません。
不思議なものです。
その気に入ったウイスキーグラスは3000円弱の価格です。
すごく高いものではないと思うのですが、家内からは「そんな高いグラスなの?」と言われてしまいます。
昨日そのグラスを購入した酒器関連を販売している女性が来社しましたので、改めて1個買いました。
彼女と仕事の話をしていると、最近の傾向を話してくれました。
お客様の中で少し高いものを買う人が増えているそうです。
インターネットで販売しているのですが、北海道の人より西日本の人の方がそういう傾向が高いとのことです。
バブルの頃の様に、ただ高いモノが売れたのとは違い、今は自分が気に行ったののなら若干高くても買おうとする人が多くなったのでしょうか。
ヒット商品のキーワードの一つに「手の届く贅沢」があります。
生活はシンプルにして、本当に自分の気に入ったものだけを使って暮らしたいという傾向があるようです。
私は早速買ったグラスでウイスキーを飲みました。
高いウイスキーではありませんが、他のグラスで飲んだ時より美味く感じるものです。
昨夜は少し「手の届く贅沢」を楽しみました。
会社対応
会社の対応の差は何によって起きるのでしょうか。
会社の市場占有率が№1№2№3に位置付けされるのは、その商品・サービスの良し悪しによって決められるのでしょう。
そして会社の対応はその順番で決まってくるように思います。
ホテルでも№1№2№3では価格も違うしサービスも違います。
デパートでも銀行でもその順位によって対応が違います。
そんなことをなぜ気にしたかというと、先日警備保障会社と契約した時の経緯がありました。
私の家は両親や娘と5人で暮らしていましたが、今は両親がなくなり、娘も上京して夫婦2人で暮らしています。
家の裏側は人目も無く、不用心なこともあり、ホームセキュリティをしてもらおうと思いました。
早速パソコンから警備保障会社3社にパンフレット送付を依頼しました。
依頼した翌日の午前中にS社から「パンフレットを持参します」と電話がありました。
その日の午後にはA社から同様な電話がありました。
C社からは後でパンフレットだけ送られてきました。
パンフレットを依頼したのですから、C社の対応でいいのです。
でもS社やA社の様に電話をもらい「見積もします」と言われると「お願いします」という気持ちになります。
2社から見積を取るのであればC社からももらおうと、C社の札幌支社に電話をしました。
「見積を依頼したいのでお出でいただきたい」と申し入れたのですが、忙しいので家の図面をFAXして欲しいと言われました。
その電話の対応で私はC社から見積をもらうのも止めました。
その対応によってセキュリティを依頼する先としては不安を感じます。
結局2社から見積を取り、金額の安い方と契約し、今はセキュリティも始まり安心な生活が出来ています。
この3社の対応を比べると、占有率1位のS社と2位のA社は若干の差はありましたが、ほぼ同じようなサービス対応でした。
3位のC社は違っていました。
価格から言えばC社がきっと最安値を出してきたと思います。
でも対応の良し悪しがセキュリティの良し悪しに繋がっているはずです。
会社とは良き人が集まれば良き会社になるとは限りませんが、良き会社は良き人を育てると思います。
良き会社かどうかは、やはり経営者の良し悪しでしょうか。
中国の経営者
昨夜ある会合があり京都から盛和塾事務局の人が来て話をしました。
その時話に出たのが稲盛さんの普段の姿です。
稲盛さんは私たちに対しては思慮深く、優しい指導者というイメージですが、実際の仕事では常に研ぎ澄まされた刀の様に触れると切れるような厳しさがあるそうです。
会社で稲盛さんから呼ばれるのは叱責の時がほとんどで、会長室に向かう取締役たちの足取りは重いといいます。
現在79歳でもその厳しさは変わらないようです。
JALの経営再建でもその強い仕事への思いは変わらず、それによって来年3月の決算でも良い収益予想が見込まれると言われています。
その稲盛さんが主宰する経営者の勉強会「盛和塾」の開塾が、今中国で立て続けに起きています。
稲盛さんの経営手腕に対しての評価が高くなってきているせいかと思いますが、重慶、広州、青島、無錫、大連に作られています。
先日の大連での開塾式では800名の中国の人が参加申込したそうです。
開催日の1週間で一気に200名増えるほどの勢いでした。
中国の盛和塾は勿論中国の人が自主運営することになりますが、今回の開塾式参加も含めての参加費用は1人5万円だそうです。
私はその金額を聞いて驚きました。
5万円を日本の価値換算すると50万円ほどします。
50万円のお金を払い勉強会に参加する人とはどういう人でしょうか。
日本ではそれほどの金額を支払って2日間の勉強会に出席する人はあまりいません。
中国には富裕層が増えていると言います。
確かにそういう人もいるでしょうが、50万のお金を支払ってでも商売、経営に対して真剣に考えている経営者がいるということでしょう。
この大連の開塾式に参加した私たちの仲間が驚いていたのは、30代の経営者が多かったことです。
そしてその若い経営者達の目の輝き・意欲が日本人と全然違っていたそうです。
12月には台湾で開塾式があります。
今度は私も参加しようと思っています。
どんな意欲のある台湾の経営者に会えるか楽しみです。
SOHOリレーフォーラム

「SOHOリレーフォーラム」というのがあります。
これは9年前に東京三鷹市で始まったフォーラムです。
毎年場所を変えて日本の各地域で開催されてきました。
今年はまた東京に戻り、11月11日に多摩市で開催されます。
私も参加しようと思っています。
このフォーラムは全国のSOHOの人達同士の連携を深めるということを目的として、バトンタッチ形式で引き継がれ、各地で実行委員会を設立して開催されます。
来年は札幌で開催する予定で、私が実行委員会を立ち上げて取り組むつもりです。
先にも書きましたが、今年は東京の多摩市で行われ、多摩信用金庫が主催となって開かれます。
来年の準備のため、札幌でも銀行の協力が得れるかと、銀行と信金にその趣旨を話しました。
銀行も信金も同じ金融機関なので仕事内容は同じものかと思っていましたが、違いました。
信金の方が中小企業、零細企業、創業・起業に対しての支援体制が良くできています。
創業支援やビジネスマッチング業務をする部門を持ち、対応しています。
一方、昨日話をした銀行の方はあまり創業や起業については関心がなく、もっぱら貸し付けを増やそうとする目的が見え見えでした。
創業・起業支援の部門もありません。
以前にも書きましたが、本来銀行というところは起業家を育て、企業の拡大を支援していくことで、預金を集め、融資してきたはずです。
しかしそれは昔の話なのかというのを今回実感しました。
信金の方が地元の起業家を育てようという思い強いようです。
銀行や信金の協力がもらえるかどうかはこれからですが、11月には実行委員会を立ち上げていく予定です。
じっくりと実行委員会の中でフォーラムの企画を練ります。
まずは札幌らしい「テーマ創り」が手始めでしょうか。
これからまた、途中経過なども書いてゆきたいと思っています。
日本の高齢化
昨日の新聞に2010年実施の国勢調査の数字が掲載されていました。
日本の人口が1億2535万人。5年前より37万人減少しています。
しかし、外国人を含めた日本の総人口は逆に0.2%増えているそうです。
1億2535万人の0.2%は約25万人です。
日本の人口減が37万人なので、外国人は5年間で62万人増えていることになります。
この現象は良い悪いは別にしても私は驚きました。
5年間に62万人も増えたのです。
また日本の高齢化も進み、65歳以上の人は5年前より357万人増えて2924万人になったそうです。
それは総人口に占める割合が2.8ポイント増えて23%の割合になります
これは2位のドイツ・イタリアの20.4%をダントツに引き離しています。
この2010年に調査した時は、まだ団塊の世代が含まれていな時です。
2015年、2020年に調査する時は急激な増加が見込まれるずです。
過去5年で65歳以上の人が357万人増えたのですから、10年後はその倍以上になるでしょう。
団塊の世代のことを考えて750万人増えるとなると、日本総人口が2010年と同じとしてもその割合は35%になります。
この数字を見てみると改めて若年層に対して申し訳ないというより可哀そうな気がします。
現在は60歳定年から63歳・65歳と定年が延長になって行く傾向にあります。
元気な人は60歳を過ぎても仕事をしていいのですが、一方それが就職難の若年層の就業機会を奪うことにもなりかねません。
そう考えるとこれから高齢化社会が進む世界では、働き方を変えていかなければならないのではないでしょうか。
「定年になったからこれから気楽に遊ぶ」という考えは捨てて、自分のために働くという「身の丈起業」が必要になってくるように思います。
若い世代に負担をかけず、またその仕事を奪わないためには、新しく仕事を作っていくことです。
年金をもらっても不足する自分の生活費の足しにするくらいの仕事の程度でもいいのです。
ボランティアではなく、しっかりとお金をいただける仕事をするのです。
これから高齢化が進む日本では、今までの生き方・考え方を変えていかなければ、生きていけない社会になってしまいます。
高齢者も誰かに頼り、当てにするのでなく自分で何かを始める時ではないでしょうか。
「家業」と「事業」
起業を志す人と話をしているとそれぞれ夢を語ってくれます。
しかし実際に起業して暫くたつと、現実問題に直面していつの間にか夢や志を失ってい人が多いです。。
会社を起こして「事業」として発展するか、「家業」として終わるかは、持っている夢の大きさと内容によります。
ただ間違わないでください。ここで私は「事業」が良くて「家業」が悪いといっているわけではありません。
身の丈で起業し、自分の趣味を生かし、生甲斐と家族の生活を維持できればそれが自分の夢というのもあります。
それはとてもいいことです。
街の商店街には「家業」と言われる八百屋、米屋、酒屋、魚屋等があります。
親から引き継いで立派に「家業」としてお店を運営しています。
それが人々の生活を維持し地域に貢献しているのです。
もう1つの「事業」とは、企業が始めた商売を規模を拡大していく経営の事だと私は理解しています。
最初は「家業」と言われるものから始まって大企業になっていくことはあります。
その違いは持っている夢や目標の大きさとそれを見失わないことではないでしょうか。
例えばラーメン店をAとBがそれぞれ起業したとします。
AもBも起業した当初は一所懸命がんばります。
共にそれなりの売上や利益が出てきました。
1年ほど経つとAは毎日のラーメン店の運営にも慣れてきて、家族も喜び満足しています。
それ以上に拡大する気はありません。
一方Bの方は満足していません。
起業した当初から夢はラーメン店ではなくラーメン事業に乗り出したという思いがありました。
1店舗目を出す前から、どの時点で2店舗目を出すか、100店舗を達成するにはいつまでに、どのように進めるか。
その資金、人材、出店地等の思いを持っています。
勿論、具体的には1店舗目の店が予定の売上と利益が出てから次に着手します。
今の成功に満足しないで常に次を考えています。
「事業」を起こす人を「事業家」と言います。
経営者とはまたちょっと違うかもしれません。
常に商売、事業を拡大するために、意識は仕事のことばかりで、これでいいとは思わない人です。
このような人が事業を拡大して、パナソニックやホンダ、京セラなどの大企業にして、多くの雇用を生み、税金を支払っています。
生活密着の「家業」も必要。そして、国を発展させる事業家も必要です。
今の日本には「事業家」を志す人がより必要かと私は考えます。
日中友好映画祭北海道応援団
以前にもこのブログで紹介しましたが、昨日「日中友好映画祭」があり、行ってきました。
日本ではまだまだ中国映画は認知されていません。
それでも東京では「東京国際映画祭」の正式イベントとして、2008年より「東京・中国映画祭」が開催されてきました。
今月の24日に中国映画関係者が来道して、昨日の25日はオープニングセレモニーの後映画上映、18時過ぎからレセプションパーティーが開かれました。
30日まで中国映画週間として札幌市内の映画館で12本ほど上映されます。
この映画祭に私が参加したのは知人に誘われてです。
大分以前に札幌で映画祭を開くことが決まったのですが、中国映画がまだ日本人に認知されていないため、あまり盛り上がっていなかったのです。
それを知った人が中心となり「日中友好映画祭北海道応援団」をつくり団員を募集しました。
会費1万円でしたが100名の予定人数をオーバーする人が集まったそうです。
参加者の中には数年前より農業を始め、今では農産物に付加価値を付けて新しい商品として売っている人。
北海道の海産物の中でも美味しいものを掘り起こしている人。
アメリカの西部劇に出てくる馬(サラブレっとではありません)を飼育し、乗馬体験、映画の乗馬指導などをしている人。
起業をお手伝いしている若い人等バイタリティに溢れた人達が参加していました。
参加した人達に共通しているのは「面白そう」とか「楽しそう」だから「応援してやろう!」という思いです。
外に向かって行動する人達です。
ですから話をしていて大変楽しかったです。
誰かのために行動するという人達は話をしていてパワーを感じます。
回り回って自分のためになることであっても、最初に人のために動くことは大切です。
昔、生命保険の契約高日本でトップという女性の話をテレビで聞いたことがあります。
その人は保険のセールスはほとんどしなかったそうです。
知人の商売のお手伝いばかりしていました。
車が欲しいという人には知人のディーラーを紹介し、高級服地の販売があるといえばどこかの社長を紹介したりしていたのです。
その内にお世話に合った人達がその保険セールスの女性のために代わって、保険の勧誘や紹介をしてくれるようになったそうです。
それが日本トップの獲得数に結び付いていったのです。
人が喜んでくれることを一生懸命することが、いつか自分に帰ってくる「タライの水」現象でしょうか。
仕事に成功している人の多くはこのような人達です。
長所と欠点
人には欠点が多くあります。
そして自分の欠点を思い浮かべれば、すぐに何個も出てきます。
それに比べ長所と言うとなかなか出てきません。
私は社会人になった若い頃、周りの人から色々欠点を指摘されることが多かったです。
私は素直?なので人の話をよく聞く方でした。
ですから言い易かったのだと思います。
私は素直で真面目に一生懸命欠点を直そうと努力しました。
少しは直ったかもしれませんが、それと同時に自分に対しての自信も無くなったように思いました。
小さい子供の頃は「良いこと」「悪いこと」を教える為にも、指摘して教育していくことは必要です。
しかし社会人になれば長所を伸ばすことに力を入れて教育するべきでしょう。
そして特に30歳を過ぎた人間には欠点を直そうとしても無理です。
無理なことに力入れるより長所を伸ばすことです。
私も起業する人達に言うのは、自分の良いところを見付けて、それを意識して伸ばすようにすることが起業を成功させるコツだと言います。
起業した時会社はまだ小さく、「個人=会社」の形が多いです。
その時は欠点を振り返るより、自分・自社の良いところを伸ばすことに力を入れることで、収益はどんどん上がります。
会社の実態が「個人=会社」の時はそれでいいです。
会社が大きくなり、その実態が「個人≠会社」になった時、長所を伸ばすとともに、欠点を拾って直すことに意識を変えなければなりません。
過去には折角大きく成長してきた会社が、不正営業行為やアフター体制の不備等のため、会社が無くなってしまった多いう例が多くあります。
個人のレベルでは長所を伸ばすことに力を入れ、会社が個人経営のレベルと超えた時は欠点を無くし、コンプライアンスを守らなければなりません。
会社のトップはその切り替えをどこでするか、その判断がとても重要なのです。
その時に会社の理念や使命が明確に作られるのでしょう。
保険について
先週朝食会があり、今日はその時のお話を書きたいと思います。
朝食会は毎月第3火曜日朝7時30分~8時30分の1時間、私の事務所で開いています。
今回は「あなたが知らない保険。あなたの保険は大丈夫?」と題しての話でした。
1時間ほどの短い時間でしたがよく分かる話していただきました。
今は昔の様な1社の保険だけを取り扱うことは少なく、広く各社の商品を扱えるようになっています。
それによって、お客様の年齢、生活状況・環境に合わせた組み合わせが出来るようになりました。
「死亡した時、家族に残すお金」「長生きをすることで必要なお金」等その人にとって必要なお金はそれぞれ違います。
保険はその組み合わせで、その人の収入と目的に合わせた組み合わせが出来ます。
簡単にですが具体的な仕組みもを教えたいただきました。
話の中には保険の裏話もありました。
相続でも保険が生かされる話です。
講師が実際に扱った事例です。
ある人が5000万円のお金を持っていました。
相続人はA、B、C3人いるけれど、自分が死んだ時は面倒をよく見てくれるAに全て残したいと思っています。
その思いで遺言書を残しても、全てのお金がAにはいきません。
BやCから請求があれば法定相続分は支払われてしまいます。
ところがAが受取人指定の5000万円の生命保険に一括入金して契約すると、死亡した時は5000万円の保険金は全額Aに行くそうです。
保険金は相続対象にはならないそうです。
ただ、Aは相続できなかったBやCとはもめるでしょう。
結果お金ばかりでなく争いの種まで残していてしまうことになりますが、そうゆう手段もあるということです。
病気疾患で保険に入れない場合の話です。
病気疾患で保険に入れなくても、2年間経過すれば保険会社に拒否権が発生しなくなり、その病気で入院しても保険金が出るそうです。
この事は保険約款に書いてあることです。
勿論、約款に「隠し通せば」とは書いていませんよ。
保険のコンサルタントというプロは各保険会社にとらわれず、自由にお客様の立場でお金・保険のプランを組んでくれます。
各生命保険、損害保険の全ての会社の商品を知っている人はいないと言われるくらいその種類は多いです。
自分に合った保険選びはプロと相談するのがいいのではないでしょうか。
機会がありましたら気軽に相談してみてはいかがですか。
ものごとをシンプルにとらえる
今日で「京セラフィロソフィ」の最終項になります。
78項「ものごとをシンプルにとらえる」です。
稲盛さんは次のように書いています。
「私たちはともとすると、物事を複雑に考えてしまう傾向があります。
しかし、物事の本音を捉える為には、実は複雑な現象をシンプルにとらえ直すことが必要なのです。
事象は単純にすればするほど本来の姿、すなわち真理に近づいていきます。
例えば、一見複雑に見える経営というものも、つきつめてみれば[売上を極大に、経費を極小に]という単純な原則に尽きるのです。
京セラの[時間当たり採算制度]も、この単純化してものごとをとらえるという考え方をベースにしています。
いかにして複雑なものをシンプルにとらえ直すかという考え方や発想が大切なのです。」
また、稲盛さんは技術者としての観点で続けて書いています。
「技術者は実験をした時、その現象の中から本質的なもの真理をつかみ取ろうとするものです。
それが発明、発見につながります。
実験をしていれば複雑な現象が起こります。
その現象をそのままにしないで、その源は何かを見ていくことが必要なのです。
エジソンのような有名な技術者や科学者は複雑な現象をシンプルにとらえる直感力というか、分析力を持っていると思います。
会社の中で社内会議でも『これは複雑な話です』と言って、複雑な話をより複雑に説明する人がいますが、これはダメです。」
私も本を読んでいて感じることがあります。
翻訳本で多いのですが、書いてある中身が何度読んでも分からないというものがあります。
本の中身が深いもので、私の理解力が及ばないということもありますが、それにしても「もっと簡単に書けないか!」と思うこともあります。
稲盛さんはシンプルに見る為にはどうすればいいかということも書いています。
それは心を静めることだと言います。
「雑駁な感覚では、複雑な現象をシンプルにとらえることなど出来ません。
「心眼を開く」と言われるように、落ち着いた目でものごとを見ると、その神髄が見えてくるのです。」
確かにそうかもしれません。
経営する時、基準を損得で判断しようとすると、複雑な絡み生まれてきます。
正しいか、そうでなきかで考えるとシンプルに判断できます。
稲盛さんは最後に
「会社でも経済界でも、また政治の世界でも、リーダーとなれる人は皆、物事をシンプルにとらえる才能を先天的に持っている人だと思います。
またそうでなければリーダーにはなれないと私は考えています。」
以上で京セラフィロソフィは終了しました。
この勉強会は時期を見てまた再度開催したいと思っています。
ダブルチェックの原則を貫く
今日は「京セラフィロソフィ」77項「ダブルチェックの原則を貫く」です。
これも稲盛和夫さんが書いた「稲盛和夫の実学」という本の中でも紹介されています。
これについて稲盛さんは次のように書いています。
「人は誰しも単純なミスを起こすことがあります。
また、してはならないと知りながらも、つい魔が差したように不正を行ってしまうことがないとも限りません。
こうしたミスや不正を防ぐためには、複数の部門や人が関わるダブルチェックのシステムが働くようにする必要があります。
物品の購入における受入部門と検収部門という複数部門によるチェック、公印の捺印における捺印者と保管者という複数の人によるチェック、数字の計算における2者検算等はその代表的なものです。
特に金銭関係や、物品の管理においては、このダブルチェックを徹底し、ミスや不正を未然に防止する体制にしておかなければなりません。」
会社におけるお金の不正行為はよく聞く話です。
正直に言うと、私どもの会社でも昔ありました。
稲盛さんも書いているように、これはマネジメントの責任です。
不正が出来ないようなシステムにしなかった経営トップの責任です。
このシステムが出来ていれば人を罪人に陥れることはなかったのかもしれません。
このダブルチェックの中で、特にお金に関することは最重要でしょう。
実印や銀行印は本来社長が押すものですが、多忙のため経理部長などに任せている場合が多いです。
その経理部長が1人で全て出来るようにすると不正が起きる温床を作ります。
金庫を開ける人、印鑑箱の鍵を開ける人、そして押印する人と分けておけば間違いが起こることは少ないでしょう。
仕入もそうです。
ホテルなどではコックに仕入れを任せると、仕入れ業者と組んで差額を作り、ピンはねするという話は昔よく聞きました。
ホテルの調理長をすれば、家が建つとまで言われたことがあります。
今はほとんどのホテルでは調理場から発注依頼を購買係に出し、購買係が発注し、品物の検品は調理場でします。
分業制にしています。
このシステムをつくってもそれを運用する責任者の選任は大切です。
必ずルールを守るという人に任せなければなりません。
自分の都合に合わせてルールを変えるような人には任せられません。
例えば、交差点の信号のところで、すき間を縫って平気で渡ってしまう人と、全然車が来なくても信号を守る人がいます。
平気で渡ってしまう人には任せてはいけません。
どんなことがあっても信号が変わるまで渡らない人こそシステムの管理責任者や金庫番に最適です。。
これは私の経験の中で得た経営管理の重要なポイントです。
1対1の対応の原則を貫く
今日は「京セラフィロソフィ―」の76項「1対1の原則を貫く」について説明します。
この項と次回書きます「ダブルチェックの原則を貫く」は経理に関して書かれたものです。
稲盛さんは「1対1の原則を貫く」について次のように書いています。
「ものごとを処理するに当たっては、どんぶり勘定でとらえるのではなく、ひとつひとつ明確に対応させて処理することが大切です。
たとえば伝票なしで現金や物を動かしたり、現金や物の動きを確認せずに伝票のみで処理するというような事があってはなりません。
売掛金の入金チェックにしても、どの売上分をどの入金分で受け取ったかを個々に対応させながら1対1で消し込むことが必要です。
また、生産活動や営業活動においても、[総生産]や[総収益]と言った、いわゆる収益とそれを生み出すために要した経費を正確に対応させ、厳密な採算の管理を行うことが必要です。」
この事は稲盛さんが書かれた「稲盛和夫の実学」の中で詳しく説明されています。
この本は稲盛さんが書いた他の本とはちょっと違っています。
多くの本は人として、社長としての考え方や生き方を説いていますが、この本は実務に書かれています。
まだお読みでない方は是非お読みください。
話を戻します。
どのような会社でも作った製品が納入される時、必ず納品伝票が付いています。
それに先方から受領印をもらって初めて売上として計上されます。
必ず物と伝票が共に動きます。
現金の入出金もそうです。
現金が入出金する度に、出金伝票や入金伝票が起票されそれには相手の名前や適用が記入されています。
一時的に現金を出さなければならない時も、仮伝票を起票します。
たとえ社長だからといっても勝手に持ち出してはダメです。
この1対1の原則を守ることは企業の透明性を高め、不正を防ぐことになると稲盛さんは強調します。
それに関する1つの話を上げています。
ある大きな会社で決算月の3月に予定していた売上や利益が達成できない。
そこで取引先に「うちの売上が立たず困っている。3億円をそちらから売上を立てもらえないか」と頼むそうです。
品物はないのに取引先に仕入伝票を発行してもらい、自分のところは納品伝票を立て、出荷したようにします。
4月の半ばくらいになると、返品伝票を切ってなかったことにします。
架空の売上が上がり、また品物が無いので経費も発生せず、売上は100%利益になってしまいます。
それは粉飾決算です。そのようなことは絶対あってはならないのです。
不正の温床を作らない為にもこの「1対1の対応原則を貫く」は重要なことです。
そして経営者トップがそれを実践して示していかなければならないことは当然のことでしょう。
製品の語りかける声に耳を傾ける
今日は昨日に引き続き「京セラフィロソフィー」の紹介をしたいと思います。
75項目「製品の語りかける声に耳を傾ける」です。
これについて稲盛さんは次のように書いています。
「問題が発生した時や、仕事に行き詰まった時には、その対象となるものや事象を真剣に、謙虚に観察し続けることです。
たとえば、製造現場では、あらゆる手を尽くしても歩留まりが思ったように向上せず、壁にぶち当たることがよくあります。
そんなときは、製品や機械、原材料、冶工具に至るまで、工程全体をすみずみまで観察し、素直な目で現象をじっと見つめ直すことです。
不良品や整備の悪い機械があれば、その泣き声が聞こえてくるはずです。
製品そのものが解決のヒントを語りかけてくれるのです。
先入観や偏見を持つことなく、あるがままの姿を謙虚に観察することです。」
稲盛さんはこの項目について19ページにわたりご自分の思いを説明しています。
その中には製品開発・完成までの苦しい思いなどがあるのか、過去の製品製造について詳しくその工程が書かれています。
「製品の語る声に耳を傾けて製造すると、手の切れるような製品を作ることが出来る」と書いています。
やはり仕事に真剣に打ち込むと、自分の作る製品に限りない愛情が生まれないのです。
そして「自分の製品を抱いて寝たい」と思うに位にならないと、いい製品は出来ないのです。
また「調和の感覚のない人間に不良品や異常は発見できない」とも書いています。
整理・整頓・清掃は口やかましく言うそうです。
机の上に書類が斜めになって置いてあると、「机はスクエアなのだから、辺に平行におかなければバランスが取れず、気分が悪いでしょう。四角いところには四角であるように、辺をそろえておきなさい。」
即ち稲盛さんは四角の机の上にものがバラバラ置かれているのを見て、それに違和感を覚えないようでは、いい製品というものを理解することも出来なければ、それをつくることも出来ないと言うのです。
私も新入行員時に言われたことを思い出しました。
壁にかかっている絵が傾いていることに誰も気付かず、直さなかったことを支店長は叱りました。
絵が傾いていても、それに何も違和感を感じないことを指摘したのです。
そのようなことにさえ気付かないと、お客様への心配りもおろそかになり、そしてお金のミスも招くと言っていました。
「製品の語りかける声に耳を傾ける」ためには、繊細と言われるほどの心配りと愛情が欠かせないことなのでしょう。
手の切れるような製品
昨夜は「京セラフィロソフィ勉強会」を開催しました。
今回は18回目で最終回になります。
これで78項目の勉強が全て終わりました。
今回学んだのは次の項目です。
74項「手の切れるような製品を作る」
75項「製品の語りかける声に耳を傾ける」
76項「1対1の対応の原則を貫く」
77項「ダブルチェックの原則を貫く」
78項「ものごとをシンプルにとらえる」
今日は74項の「手の切れるような製品を作る」について説明します。
稲盛さんはこれについて次のように書いています。
「私達が作る製品は、『手の切れるような製品』でなくてはなりません。
それは、たとえばまっさらなお札のように、見るからに鋭い切れ味や手触りを感じさせる素晴らしい製品のことです。
製品には作った人の心が表れます。ラフな人が作ったものはラフなものに、繊細な人が作ったものは繊細なものになります。
たくさんの製品を作って、その中から良品を選ぶというような発想では、決してお客さまに喜んでいただけるような製品はできません。
完璧な作業工程のもとに、1つの不良も出さないように全員が集中して作業にあたり、1つ1つが完璧である製品作りを目指さなければなりません。」
続けて、「手の切れるような製品」について稲盛さんは経験の中から次の様なことを書いています。
「半導体のパッケージを作ろうとしてある技術者にリーダーとなってもらい、研究開発を始めました。
半導体パッケージの開発は今まで誰も経験したことのないほど過酷な作業でした。
苦労の末やっとそれらしきものが出来あがると開発リーダーが私のところにサンプルを持って来ました。
苦心惨憺して作ったことは分かっていたのですが、それを見た時どことなく薄汚れているように映りました。
薄汚れていはいたのですが、製品自体は半導体パッケージとしての特性はすべて満たしていました。
それでもそれを見た時、『なるほど性能は間違いないが、これでは駄目だ』と言いました。
リーダは『なぜですか特性は全部満たしています』と言い返します。
それでも私は『見てみろ。薄汚れているじゃないか』と答えました。
大変苦労して出来上がったのですから、彼は気色ばんで食ってかかりました。
『あなたも技術者なのだから、理論でものを言うはずでしょう。それを薄汚いとはどういうことですか!
薄汚いことと製品の特性とは関係ないはずではありませんか。感覚で判断するなんて、おかしいじゃありませんか。』
『測定の結果特性は立派に満足していると君は言うけれど、これだけ変色しているということは、スペックも何とか合格ラインにのったというようなサンプルであって、最高の出来栄えとは言えないはずだ。
本来、立派な特性を備えているものは、見た目も美しいものであるはずだ』と私は彼に説明しました。」
「最高の出来栄えであるものは見た目も美しい」ということが、稲盛さんが言う「手の切れるような製品」なのです。
この稲盛さんの話と先日亡くなったアップル社のスティーブ・ジョブズ氏の行動とが重なります。
スティーブ・ジョブズ氏は、Macintoshにはシンプルな美しさが必要だと考え、基板パターンが美しくないという理由で、設計案を幾度となく却下した。
また、同じく美しくないという理由で、拡張スロットの採用を拒否したり、みすぼらしいフロッピードライブのイジェクトボタンをなくさせ、オートイジェクトを導入させることも行わせた。(ウぃキぺディアより)
ジョブズ氏はMac製品の美しいデザインに執着を持って取り組んでいたのです。
より良い製品とは美しくて手の切れるほどのものなのです。
稲盛さんは野球選手にもたとえて、優れた投手は投げるフォームも美しいと言います。
そう言えばイチローのプレーする姿が美しいのも、それに通じるモノがあると思います。
下請会社
昨夜は盛和塾の勉強会があり、稲盛さんのDVDを見てそれについて討論をしました。
1993年に石川の開塾式での講演です。
18年前で稲盛さんも60歳頃なので若々しく、話の内容も当時の京セラの経営内容を具体的に話していました。
その中で特に私が興味を持ったことを紹介します。
稲盛さんは「商品の売値は『買った人』が喜び、『売った人』も喜ぶ値段が最適の売値です。」と言います。
京セラは下請会社として仕事をして来ました。
京セラは創業時から松下電器の下請としてセラミック製品を納入していましたが、絶えず値引きを求められていました。
値引きをしても次回はもっと値引きするように要請されます。
仕舞いにこれ以上出来ないというと、損益計算書の提示を求められ、そこに利益が出ていれば、その分安くするように求められたそうです。
私だったら「そこまでさせられることはない」と言って穴を捲くってしまいます。
稲盛さんはそのような値下げ要請がある中で、松下電器が本当に求める最低の金額を聞き、たとえとても出来そうもない価格でも受けることにしました。
そしてその最低の価格を売値として、その中から京セラとしての利益を出す努力をしました。
結局「売値は使う人の価値で決まる」ということです。
しかしその売値で利益が出てくれば、先に書いた「買った人」が喜び、「売った人」も喜ぶ最適の売値になるのです。
一般的に言えば下請会社は立場的に弱者です。
その為、つい下請から離れ完成品を売る業態へ変更したいという気持ちになりがちです。
稲盛さん盛和塾の塾生経営者からそのような相談をされることが多いそうです。
その時稲盛さんは下請会社は下請会社で利益を出すように努力しなさいと言います。
慣れない完成品を売る会社にしようとするから倒産していまう会社が多いのです。
先ほどの様に松下電器の下請会社となれば値引き攻勢がありますが、一方松下電器にしてもそこまで突っ込んで京セラと仕事をしていれば、簡単に他社に乗り換えることは出来なくなります。
お互いに相手の存在を認めざるを得ないのです。
下請けだから利益が出ないということも無いのです。
先ほどの様な松下電器とのやり取りの中で値引きを依頼されても、京セラは経常利益を10%以上確保してきていたのです。
下請会社という会社は多いと思います。
稲盛さんは京セラは下請会社だとハッキリ言います。
でも京セラの経営は下請会社でも工夫と努力で利益が出せる会社にすることが出来るということを教えてくれます。
やはり利益が出ないのはこの工夫と努力が不足しているからなのでしょう。
蓄電池
東日本の大震災後、原子力発電の賛否など電力問題がクローズアップされています。
日本中で夏場には節電に努めました。
それと同時に蓄電に対しての関心が高くなっています。
今朝の新聞に「蓄電池の性能が高くなってきている」と書かれています。
トヨタ自動車は連続走行距離が100kmに迫る次世代電池を試作しました。
マツダは電池の容量を2倍近くに増やせる電極材料を開発。
NECは20年間持つ長寿命の住宅用蓄電池を可能にしました。
今まで電気を蓄電することが難しかったたのですが、ここへきて飛躍的にその蓄電性能が伸びてきました。
そうすると今まで電力会社が発電しても無駄にしていた電気を蓄電しすることが出来ます。
家庭で発電した電気も蓄電することが出来、家庭で使う電気の自給自足が可能になるかもしれません。
また、世界中で進められている電気自動車の普及も早まるでしょう。
そうなると、世の中の様子がガラリと変わります。
ガソリンの需要が急減し、産油国も別の産業を改めて構築していかなければならなくなります。
ガソリンスタンドの数も大幅に無くなるでしょう。
ポケベルが出てきてフィーバーしましたが、一時的なもので終わりました。
PHSの出現により無くなってしまいました。
そのポケベルで大きな利益を上げた会社も今は既にありません。
PHSも携帯電話が出てきてから、同様な流れです。
私はこの高性能の蓄電池が出てきたことによる世界に与えるショックは、ポケベルやPHSの盛衰どころの比ではないくらい大きいと思います。
産業構造も生活環境も大きく変わります。
世の中で大きな動きがある時は、このことによる影響を早くから察知して、自社の経営方針を見直すことが大変重要になってきます。
自社の強さと、新しい動きをどう結び付けるか、それを考えるのがトップの仕事です。
高性能の蓄電池は世の中を変える可能性があります。
その時の自分の生活がどのようになっているか想像してみるのも楽しいのかもしれません。
運の違い
今日は「運には違いがある」ことを書きたいと思います。
最近たまたま人と運の話をしていて思ったことです。
人が何か運が良くなることを一生懸命しても、思い通りにならないことがあります。
それは人のマネをしているからです。
人マネをしても、うまくいかないものです。
でも、それが分からなくて無理をしている人がいます。
時として人は成功して人の体験を本で読み、それをマネしようとします。
その人の考え方を学ぶのは良いのですが、その人の経験をマネすることはできません。
どうしてもその対象があこがれの人であればあるほどマネをしたくなります。
でもその通りにはなりません。
羨ましがっても、それはその人の運です。
同じにはなりません。
私も最近納得してきたことですが、その人にとっての運はその人のやり方をしなければ付いてきません。
別な人のマネをしてその人と同じような運を得ようとしても無理です。
自分のやり方をすることが大切です。
自分のやり方を探す為には素直になることです。
まず素直になること。
そして本当に自分が好きなことを見付けること。
好きなことが見付からなければ、今やっていることを一生懸命すること。
それをすれば、その人だけの良い運が付いてきます。
また欠点を直したり、足りないものを加える努力より、自分の長所を伸ばしたり、楽しいことをすことの方がより運を呼び込むと思います。
また、良き運は気付かない内に訪れていることが多いのです。
気付かない内に訪れている運を無くさないようにするために、常に感謝の気持ちを持つこと。
運がいいと思うことと、運がいいと口に出すことが大切です。
そんなことをしているうちに、その人だけの良き運が集まり、それが蓄積し、より高い運を連れてくるようなります。
人と違った、自分だけの、自分に合った運が付いてきます。
早くそれに気付いた人が幸せになると私は信じています。
社格
昨日のテレビや今朝の新聞報道で九州電力の問題が取り上げられています。
自社が設置した第3者委員会が出した結論を、気に食わないからと言って無視して、勝手に作った報告書とはあきれてしまいました。
日本国民のほとんどが憤慨していると思います。
外部の調査委員会が作った調査を無視するのは、まだ理解できます。
自社が選定した人が中心となった第3者委員会の結論を無視してしまうことは、自己否定につながることで、電力問題を別な面から混乱に陥れることになります。
日本にある9つの電力会社は九州電力と同じよなう体質があると思います。
9社とも誰に対しても強い立場にある会社です。
それは電気料金は認可制ですが、その料金の裏付になるコスト計算は掛った分をそのまま計上しています。
普通の会社は合い見積を取り、少しでも安く購入しようと努力します。
でも電力会社はほぼ言い値で購入するそうです。
そうすることで、納入業者に対してより優位に立てます。
また官庁に対しては天下り先として優遇されます。
電気の購入者である一般企業や個人に対しては、電力の競争相手がいないので国が認可した金額がそのまま通ります。
本来一番頭が上がらないはずの顧客に対しても頭を下げる必要がないのです。
民間企業で日本の電力会社ほど強者の立場でいれる会社は世界中にないのではないでしょうか。
「お陰様」いう謙虚の心のない会社が存在することはもう許されない時代になってゆきます。
発・送電の分離などの電力の自由化を本格的に進めなければ弊害は無くならないと思います。
現在のような形で電力会社が存続し、今回の様な九州電力のような対応が許されていると、「金儲けだけが目的」みたいに企業経営全体が思われ、そのような不信感が若い人達に広がるのを恐れます。
九州電力のホームページを見ても明確な経営理念が見つかりませんでした。
経営者が心を高める努力をすることで、「人格」が上がるとともに会社の「社格」が上がります。
「貧すれば鈍する」にならないように。
日中友好映画祭
昨日琴似の街を歩いていると偶然知人と会い、「お久しぶりですね」と挨拶をしただけで別れました。
夕方にその彼から電話がありました。
「偶然山地さんに会って、山地さんなら興味を持つ話がある」と言うのです。
その話は「日中友好映画祭」のことです。
私はあまり映画に興味はないのですが、面白そうな話でした。
「日中友好映画祭」は、中国では北京と上海、日本では東京と札幌の2カ所で開催されます。
昨年までは東京と上海だけだったのだそうですが、今年北京が加わり、日本で東京ともう1カ所を選定しようというとなりました。
色々な都市が候補に挙がったのですが、結局札幌になりました。
折角札幌で開催されるのだからこの映画祭を盛り上げようと勝手連的に応援団というのが立ち上げられました。
応援団長は帯広の後藤健市さんという方で、帯広屋台村創立に係わった人です。
先にも書きましたが私は映画にはそれほど興味はありませんが、勝手に応援団を作り勝手に応援するというのに興味を持ちました。
今月の24日・25日に行事があります。
先ほど申し込みしました。
何事も、何がキッカケになるか分からないものです。
だからと言って目先のことばかり考えていてはチャンスを逃します。
大事なのは「面白そう」と興味を持つことだと私は思っています。
面白ければ結果何が無くてもそれで満足します。
それにもし、プラスαが付いていればラッキーです。
そんなことの繰り返しから、人とのつながりやチャンスをつかむことが出来るのです。
その為には「行動」です。
動かなければそのチャンスに出会えません。
私は最近この「行動」が鈍くなってきていると自覚していました。
昨日の偶然の出会いから、面白い話を聞き、行動のキッカケが得ることが出来、知人に感謝しています。
日中友好映画祭についてはまたお伝えします。
社長になる
先日、生命保険の仕事をしている人が来社されました。
保険の仕事をしている人同士が集まって、1つのグループを作り共同で運営しています。
昔と違い現在は1人でどの保険会社の商品を扱ってもいいようになっています。
生命保険ばかりでなく損害保険も取り扱えるそうです。
来社いただいた彼に、今度私が属しているサークルで保険に関した話をしてもらおうと思っています。
彼の名前を仮にAさんとします。
今日はこのAさんのことを書きたいと思います。
Aさんは大学の建築科を出たので最初に就職したのは建築会社でした。そして建築現場に入りました。
1つの現場が終わればまた新しい現場。その都度組む業者仲間はほとんど同じ人同士。
そのような仕事が続きました。
暫くそのような生活をしていると、何か物足りなさを感じるようになってきたそうです。
新しい出会いが欲しいと思うようになったのです。
そしてそんな時にフッと思い出したのは、「若い頃からの夢は社長になること」。
その夢を叶えるには今の生活では実現出来ないと思い、改めて営業マンになろうと思ったのです。
それで、一大決心をして社長に辞表を提出しました。
社長は営業が希望なら配置転換すると言ってくれたそうですが、別のところで自分を試したかったのです。
営業の仕事は沢山あります。
その中で選んだのが保険の仕事でした。
保険の仕事は、働けばそれなりに収入は増えますが、手を抜くと減ってしまいます。
彼は手を抜くと収入が減ってしまう保険の仕事を選んだのです。
それは歩合給制だからです。
彼の話では、「普通の固定給の営業では、収入が安定している。自分は怠け者なので、その上に胡坐をかく生活になる」ことを恐れたそうです。
Aさんは28歳の時に会社を辞め、現在は32歳です。まだ若いです。
私は最近若い人から「将来は社長になる」という声を聞くことがほとんどなくなりました。
久しぶりにリスクを背負い「社長になる」と起業を志す若い人にお会いすることが出来ました。
これからも見守り、支援して行きたいと思っています。
交流の場
今日は私も会員になっているビール会があります。
以前にも紹介しましたが、これはサッポロビールが愛飲者を増やすために作ったサッポロビールを飲む会です。
本来は母が亡くなって49日もたたないでこのような会に出るのははばかれますが、今回のビール会の幹事が私になっており、また会葬のお礼も兼ねて出席することにしました。
ただ、明日は会社の健康診断の日です。前日は禁酒しなければならないらしいです。
日のめぐりが悪いですね。
この西サッポロビール会は50年の歴史があります。
私の父も会員でした。その後私が引き継ぎました。
会員のメンバーは私より年配の人が多く、私はズーと若い方です。
参加されている多くは既に現役を引かれ、皆さんは月に1回開かれるこのビール会を楽しみにしています。
それなりに楽しい会です。
ただ、先にも書きましたが、若い人が少ないのです。
飲むだけの会では本当にビールが好きな人は入会しますがそれ以外はあまりいません。
若い会員が少ないという点では他の会でもそうです。
ロータリークラブやライオンズクラブは入会していることがステータスシンボルの会でした。
その会でも若い人がいないと聞きます。
その理由は年配の人が退会しないからです。
どのような会であれ、人脈を広げ、それを仕事に生かすことを目的に入会します。
30年以上前だと、現役の社長たちが中心となり、その社長同士の交流の場でまた商談の場でした。
そのような会であれば、皆が参加したくなります。
ですからその頃は入会規則も厳しいものでした。
そうなると益々その価値が高まります。
しかし今はその現役だった人達も仕事を離れ悠々自適に生活しています。
そして入会している会に出席することが楽しみになってきます。
こう言っては申し訳ないのですが、もう「老人会」になっているのです。
そこに入会した若い人は、その会では下の位置にいるので、いいように使われます。
ローターリークラブやライオンズクラブのように奉仕活動をするところではそれが顕著にあらわれ、若い人達に負担が多くなります。
益々若い人は入りません。
会則では退会年齢が書いてないところがほとんどです。
今の若い人達は新しい交流の場であり、商談の場を求めています。
その入会の目的からも、現役の社長の少ない会には入らないでしょう。
今後そのような会は消滅していくのでしょうか。
それを防ぐには退会年齢を明確にして、活性化していくことしか生き延びることが出来ないように思います。
現在は新しい交流会や商談を目的とした会等が出てきました。
ただ、必要かどうかは別にして、ロータリークラブやライオンズクラブに代わるステータスクラブはまだないようです。
ステータスクラブはやはり高度成長期の産物だったのでしょうか。
オトン
昨夜、昭和歌謡のライブに行ってきました。
私の友人がギターとボーカルをするというので、妻と行ってきました。
この友人の事は前にも書いたかもしれませんが、大手旅行会社の取締役までして60歳の定年できっぱり仕事を辞め、趣味の音楽の世界に入り込んでいます。
彼はこのバンドではギターを弾いていますが、時にはジャズバーでウッドベースも弾き、また尺八はプロ級です。
ボーカルとして訓練のためボイストレーニングにも通っています。
時折尺八の先生として私たちの母校の邦楽部にも指導に行っているそうです。
なかなか忙しそうです。
この昭和歌謡のバンドは夏には北海道各地で演奏活動もして来ました。
昨夜はOtone(オトン)という雑誌の取材も入って、盛んに写真を撮っていました。
そんなこともあり、昨日のバンドメンバーは特に力が入っていたようです。
バンドメンバーは2人の若い女性の他はおじさん(オトン)です。
まだ現役のおじさん、既に自由の身のおじさん、立場は違いますが趣味の世界に生きる元気なおじさん達です。
Otoneという雑誌は40~50歳代をターゲットにしている北海道の雑誌なので、取材ターゲットとしてはこのバンドはピッタリです。
昨夜のライブ会場は30席位のバーで行われましたが、50名程が集まりビッシリ。
窮屈な思いで2時間近く座っていましたが、スカスカのライブより窮屈なライブの方が盛り上がります。
そのほとんどが年配の女性。
こちらの方も元気で、大きな掛け声出て、和気藹藹のライブでした。
何においても、何かに熱中できるものを持つことは人生を幸せにするのだと再認識しました。
帰り道、妻とは「私たちも元気でいれる70歳までの10年間どう生きるかだね」と話しながら帰りました。
休日の過ごし方
先月も今月も連休が続きます。
連休の過ごしかたは皆さんはどうされているのでしょうか?
私は出不精なので家にいて、本を読んだり、サックスの練習をしたり、またなにがしら用事があり、1日が過ぎてゆきます。
運動もあまりしません。その為体重が増える兆しがあります。
そのような状況を心配した妻が強制的に朝のラジオ体操、休日は1時間の散歩を指示しました。
素直が取り柄の私はそれから体操は毎朝ほとんど欠かさずしています。
散歩も昨日・一昨日しています。
私は毎朝「している」ことが2つあります。
このブログを書くこととあることをしています。
この事は口外していませんのでここでも書きませんが、10年以上欠かさずしていますので、私は結構「根気がある」と自認しています。
なので今回のラジオ体操も長く続くのではないかと思います。
昨日も妻と散歩をしましたが、私たちは歩きながらよく話をします。
不思議と散歩していると、普段家で話すこととは別の話題が出てきます。
目に入る家並から、人の様子から、また流れる風に季節を感じながら思いつくままに話をします。
楽しい散歩をするポイントはただ1つ。決して喧嘩しなこと。
その為、私は妻が話したことは否定しないことと決めています。
昨日の散歩では妻がなんとなく思い描いている楽しい話しを聞きました。
その描いている思いはなかなかいいものです。
そんな話も散歩しながらだから出てくるのでしょうか。
健康のために始めた散歩は身体のためばかりでなく、心の健康のためにもなっています。
この年になって改めて2人でいることのありがたさを感じています。
今日は取り留めのない話しでした。
銀行の使命
最近街を歩いて気付くのはティッシュ配りをする人が極端に少なくなっていることです。
いつもは秋冬は風邪のシーズンと重なるのでポケットティッシュは助かります。
ティッシュ配りが少なくなったのは消費者金融会社の配布が減ったためでしょう。
一時、消費者金融会社は飛ぶ鳥を落とすような勢いがあり、業績を拡大していました。
私がまだ銀行員だった頃、消費者金融はサラ金と言われていました。
そして同じお金を貸すとしても銀行はサラ金と明確に線引きをして、独善的に区別していました。
しかし、消費者に近い立場で融資をするという点ではサラ金の方が優れていました。
昔の銀行は消費者に対して融資をするとすれば、住宅ローンや自動車ローン、割賦販売の手形発行位のものでした。
消費者に身近なことからサラ金の方が広まっていきましたが、同時に高金利や過剰な返済取立で社会問題になりました。
その頃でしょうか、サラ金が個人相手で利益を出しているのを見て、銀行もやっと個人融資を本格的に始めました。
銀行では一般企業への融資が減る中、新しい収入源として個人融資にも力を入れるようになり、そして最近はサラ金と言われた消費者金融会社を系列傘下に置くようになりました。
そのような変遷の中、銀行が本来持っていた使命感が薄れているように私は思います。
以前、銀行は会社・経営者をに対して、金融支援や経営指導と共に精神的なフォローをしていました。
たとえ今お金が無くても、銀行の支店長はその経営者の人格や志に期待をし、色々な形でフォローしていました。
経営の仕方が悪ければ親身になって相談にのりました。
しかし、バブルが弾けて、銀行の経営そのモノが危なくなった頃から、銀行は自分のことだけを第一に考える様になりました。
「貸しはがし」等が行われる頃になってから、銀行には使命感が無くなりました。
もしかしたら、今、銀行は既に銀行ではなくなり、サラ金と言われた昔の大きな消費者金融会社に変わっているのかとさえ思えるほどです。
現在のように先行き不安が広がる中、起業に挑戦しようとする人は少なくなっています。
それでも起業に挑戦する人はいます。
今大切なのは起業しようとするその志を抱く人を支援することです。
長く支援し続けることが出来るのは銀行だと思っています。
北海道や札幌市などの公的機関は起業するまでは支援しますが、起業してしまえばそれまでというところがほとんどです。
起業に必要なお金を貸し、その後利益の出る会社にするために具体的な支援をすることが出来るのは銀行が最適です。
人を育て、会社を発展させるという使命感を銀行が持ってくれれば、新しく成功する多くの起業家が生まれると思います。
マヤ暦
昨日知人たちとランチを食べました。
色々な話の中で「マヤ暦」のことが話題になりました。
マヤ暦では周期的に世の中は変わり、2012年の12月21日に人類は滅亡するという予言です。
ホゼ・アグエイアスという人の著書『マヤンファクター』によって2012年12月21日に「新しい太陽の時代」が始まるとされたことで広まったらしいです。
昨日の話題では人類が滅亡するというより「大変革が起こるのではないか」という話になりました。
今年になり世界中で地震や天候による大災害が起き、中東で起きたジャスミン革命から始まった政治変革があり、経済もヨーロッパ、アメリカでのでフォルテの恐れがあり、経済の大変革が起こる様相です。
中国でも「いつ」「何が」起こるか分からない状態です。
政治では世界中の多くの圧政政府が倒されています。
経済も資本主義そのモノの弊害に苦しんでいます。
今年中にギリシャでフォルテが起き経済の変革が始まるかもしれません。
この変革の時期とマヤ暦の「新しい太陽の時代」が重なれば、「なるほど」と言うことになります。
このマヤ暦についてある人の解釈では2012年12月21日でなく、今年の10月28日だという人もいます。
このマヤ暦の話を聞くと1999年ノストラダムスの予言を思い出す人もいるでしょう。
何も起きませんでした。
ですから今回のマヤ暦も天変地異が起こらないと思います。
でも、今、何か世界中で新しい変革が起きつつあるだろうという予感はします。
私はそれも良い方向へ向かうことになると思っています。
一時的に今までの「考え方」や「やり方」と違うことになるかもしれません。
資本主義そのものが否定され、別の考えが生まれてくることになるかもしれません。
それは共産主義、社会主義、資本主義等の政治的なものでなく、生き方の問題になるのではないかというものです。
このようなことを気心が知った者同士で好きなように話してきました。
結構当たっていると思っています。
見える化
昨日のニュースと言えば小沢一郎氏の裁判がありますが、やはりアップルのスティーブ・ジョブ氏が亡くなったことでしょう。
私のパソコンはwindowsですが、昔からアップル社のパソコンへの憧れはありました。
操作が慣れているwindowsから離れないまま来てしまいました。
アップルのパソコンに憧れてた要因はそのデザイン性です。
そのデザインを創り出したのはスティーブ・ジョブ氏です。
ジョブ氏は優れた経営者ですがそれよりデザイナーとしての凄さでしょうか。
デザインでも「明確なビジョン」があり、それに沿わないものに対しては完全に拒絶し、理想を追い続けたと聞きます。
ジョブ氏が目指すのは「宇宙に衝撃を与えるほどのもの」を作ろうとしていたそうです。
やはりスケールの大きさは人と違います。
成功する起業家はジョブ氏程ではないにしても「明確なビジョン」を持つ人が多いです。
「明確なビジョン」は「見えるか化」されるまで具象化しなければなりません。
「見える化」されたビジョンは人にも容易にプレゼンテーションが出来ます。
「見える化」されるようになったら、それを寝る前に布団の中であたかもその情景が達成したかのように思い描きながら寝ると、不思議とそのようになるものです。
それは潜在意識の中で、心も体も達成したかのような錯覚が起き、それが実現化の原動力になっているように私は理解しています。
また、その「見える化」されるビジョンなり構想は、今の自分に「分相応か?」を自動的に自己チェックしているようです。
例えば今年収300万円の人が、1年後1億円にするんだと思っても、心のどこかで、「そんなバカなことはないな」と思っています。
そのように自分が信じられない様なビジョンや思いは「見える化」しません。
スティーブ・ジョブ氏はiphoneを世に出しましたが、以前から彼のビジョンの中にはポケットに入るコンピューターとしてiphoneが「見える化」されていたのかもしれませんね。
やはり凄い人です
クマ出没
今朝テレビをつけると札幌市内にクマが出没しているとの報道です。
それも朝の3時頃北海道神宮の鳥居を横切って行ったとの警察官の目撃情報があります。
この地域は札幌でも高級住宅地です。
最近藻岩山にクマが出没したとの情報がありましたので、そのクマなのかもしれません。
北海道のクマは羆(ひぐま)で本州の月輪熊とは大きさも凶暴さも違います。
クマと言えば私が独身時代帯広に勤務したいた時、山が好きで土曜日半ドンの時はその夜から近くの山に入り、山小屋に1泊して朝、登ります。
ほとんどが単独行でした。
夜、山の麓の駅に着き、タクシーで山の近くまで行きます。
1人で山に登るので、一番怖いのはクマです。
タクシーの運転手に「最近クマの情報ありますか?」と聞くと「最近は聞かないけれど、クマにも足があるからな...」と言ったのは忘れられません。
なので今回のクマ出没の話を聞いて改めて、「クマにも足がるから」と当り前だけれど納得しました。
最近クマが民家の近くに出没するという報道が多いです。
私の家内はそれを聞くたびに「可哀そう」と言います。
自然の中で暮していればいいのが、山に餌が無くなり餌を求めて降りてくるのです。
昔はクマと人間はそれぞれが住み分けしていました。
近年になり、山の木々の手入れがなされず、山が荒れ、木の実も少なくなっています。
その上、人間がクマの餌のキノコや山菜を採りに山に入ります。
山登りやハイキングで山に入って、ごみを持ち帰らないとクマはそのゴミをあさり、それで美味しさを知ります。
元々クマは憶病なもので、人間に近づかないかったのが、ゴミで美味しさを知ったクマは人間に近づいてくるようになりました。
クマ除けの鈴を鳴らすとクマは逃げるはずのが、逆に近づいてくると聞きます。
餌を求めてです。
クマにとって「人間=美味しいものがある」となります
クマ出没の原因のほとんどは人間にあります。
それでも迷い込んだクマはやはり射殺されるのでしょうか。
なお可哀そうになってしまいます。
過去北海道は開発・開拓という名のもとに自然破壊してきました。
今朝は色々考えさせられる朝でした。
質の高さ
2010年にチュニジアで大規模な反政府運動が始まりました。
ジャスミン革命と言われています。
それを契機に世界中で反政府運動が広がっています。
当初は弾圧をうけた国民の抗議行動で、非民主国家で起きているものと捉えられていました。
しかし先週からアメリカでもウォール街占拠等のデモが始まり、全米に広がっています。
このデモの相手は国民の1%の超富裕層で、「自分達は99%」というスローガンを掲げています。
あるホームページでは次のような数字が紹介されていました。
トップ1%のアメリカ人が国富の40%を所有している。
トップ1%のアメリカ人が年間国民総所得の24%を得ている。
トップ1%のアメリカ人が国内の株式、債券、投資信託の半分を所有している。
格差は日本の比ではありません。
またマイケル・サンデル教授の「これから正義の話をしよう」ではアメリカ大企業のCEOの平均報酬と労働者平均報酬の差は1980年で42倍であったのが、2007年には344倍になっていると紹介されています。
また、その本にはアメリカ、ヨーロッパ、日本の一流企業のCEOの年間平均の報酬も紹介されています。
アメリカは1330万ドル。それはヨーロッパの660万ドルの約2倍、日本の150万ドルの9倍です。
現在行われているアメリカのデモの大きな要求は雇用です。
9%を超す失業率。日本は4%台で、その2倍です。
各報道ではこれから世界の経済情勢は、益々厳しくなっていく可能性があります。
日本も同様に経済がより悪くなり、失業率も高くなる可能性があります。
8月に私の運営するレンタルオフィスから退室された人が、昨日訪ねて来てくれました。
彼は起業し頑張っていましたが上手くいかず、いったん断念して就職先を探していました。
昨日は就職が決まりその報告に来てくれたのです。
就職先は2件ほどありましたがその1件に決まりました。
就職難で心配していたのですが、短期間に良く見つけたものだと感心しました。
やはり彼には採用されるだけの「人として質の高さ」があったように思います。
概して起業を志す人は志の高さがあります。
会社を経営していく中で苦労も勉強もします。
それにより人の質も高まっていきます。
起業して苦労したことは決して無駄ではないのです。
彼は就職しましたがまだ起業の志は持っているようです。
起業の時はまた私のレンタルオフィスに入ってくれると言ってくれます。
私も出来るだけの応援をし、また入居するのを待ちたいと思います。
不渡手形
知人のHさんは毎月「さんかく通信」という手書きの便りをFAXで送ってくれます。
経理の仕事をしている彼女は、その仕事に関した出来事の紹介や考え方を書いてくれます。
今回で73号となっていますので6年以上続いています。
私は毎月この「さんかく通信」を楽しみにしています。
今回の通信の最初に「銀行取引停止猶予処分」のことが紹介されていました。
手形などが資金不足で期日に引き落としされない時は不渡りとされ、それが半年に2回あると「銀行取引停止処分」になります。
今回は東日本大震災で被害を受けた会社の救済目的で、従来の様な不渡手形としてでなく、「東日本大震災の災害による資金不足」として手形取立者に返却されるそうです。
対象は岩手・宮城・福島の3県の被害を受けた会社です。
普通は1度不渡りになった手形は再度銀行に取立依頼できないのですが、この場合は支払する会社の資金の目途が立てば再び取立決済が出来ます。
ですから2度不渡りを出しても銀行取引にはなりません。
この処置により被害を受けた会社は助かります。
震災の被害を受けた会社にとっては朗報です。
しかし問題なのは、その手形が引き落としになる事を見越して資金繰りしていた取引先の会社です。
その会社には特別に救済があるわけではなく、自助努力しかありません。
もしかするとその会社が不渡りを起こし、倒産するかもしれません。
勿論、「東日本大震災の災害による資金不足」理由の不渡手形になっても債務・債権関係は変わりません。
ですから債権者から債務者へ直接請求は出来ます。
手形取引のルールが変更されるということは大変なことです。
昔から手形という制度があり、そのルールは厳然と守られてきました。
その厳然と守られるという事実に基づいて信用が生まれ、商売が成り立って来ました。
しかし今回の様な処置がなされると、ルールに従い仕事をしてきた会社が、自己責任が及ばないところで倒産するなど納得出来ないでしょう。
そのような「東日本大震災の災害による資金不足」による不渡りとして手形が返された会社に対して、ルール変更を決めた銀行協会が各銀行に対して、特別融資をするなどの処置はあるのでしょうか。
大きな仕組みの中で成り立っていた世界が、何かの都合でルール変更が起きると、それが些細と思われたことでも大きな影響を及ぼすことになるということを今回の不渡り猶予問題で考えさせられました。
ノーベル賞
今週はノーベル賞週間だそうです。
この時期になると、7年前に北欧旅行した時、訪れたストックホルム市庁舎を思い出します。
そこはノーベル賞の受賞会場です。
新聞には今年のノーベル賞生理学・医学賞の最有力候補はips細胞を作製した山中伸弥京都大学教授だと報じられています。
また同時に、物理学賞の候補として青色発光ダイオード開発で知られる、カルフォニア大学の中村修二教授も上げられています。
2人とも今までのノーベル賞受賞者と比べて格段に若いです。
山中教授は49歳、中村教授は57歳です。
山中教授がips細胞を作製したのが2006年45歳の時です。
また中村教授が青色発光ダイオードを開発したのが1993年40歳の時です。
大学を卒業したのが22歳であれば、社会に出てから20年から25年でノーベル賞級の発明をしたのです。
私にとってみればその時間の短さは驚異的です。
勿論時間をかければ生まれるものでもありませんが。
山中教授のIPS細胞は病気を根本的に直す期待があり、中村教授の青色発光ダイオードのおかげでLEDが私たちの生活の分野で当り前に使われています。
2人の発明で私たちの生活が大きく変化しています。
山中教授と中村教授は傍目からの感想ですが、正反対のような性格に思えます。
山中教授は一時ウツやノイローゼになったといわれるくらい繊細な人。
中村教授は発明に対する不当評価に対して会社や、司法とも闘い続けてきた人。
性格は正反対ですが、どちらも「成功する人生の方程式」の通りに生きています。
人生の成功=考え方×熱意×才能
人類の為という高い志、誰にも負けない熱い思いを抱き、天才と言われる才能を生かし切ったその評価がノーベル賞候補者として認められたのでしょう。
お二人と同じように頑張っている若い発明者が日本にまだまだ多くいるのだろうと思います。
頼もしい限りです。

真直ぐに
昨夜NHKで「神様の女房」が放映されました。
来週・再来週と3週続く予定です。
この番組は松下幸之助さんの奥さんのむめのさんを主人公にしています。
1週間ほど前に同名の本を買い読もうとしているうちにテレビの方が先になってしまいました。
この本は高橋誠之助さんという人が書きました。
高橋さんは松下家の執事として20年間職務についていて、幸之助さん、むめのさんの臨終にも立ち会ったそうです。
常に幸之助さん夫婦の傍にいて、見て聞いた「人間松下幸之助」が書かれているそうです。
テレビを見てからゆっくり本を読んでみようと思っています。
昨日のテレビの中で幸之助さんのお姉さんが幸之助さんの性格を語る場面がありました。
壁にかかっている絵でも机の上にある書類でもまっすぐでなければ気が済まない性格と言っています。
キチンとした性格、曲がったことが嫌いな性格を表しています。
このようなキチンとした性格は京セラの稲盛和夫さん、日本電産の永守重信さんも同じようなことを言っています。
皆さんは仕事で大事なのは整理・整頓・清掃・清潔と言い、永守さんは作法・躾も入れ6つの「S」を経営の基本にしています。
私が新入社員で銀行に入った時、その支店長も銀行のロビーに飾られている絵が少しでも曲がっているとすぐ直します。
そして行員全員に「なぜ絵が曲がっていることが気付かないのか」と叱ります。
気配りが足りないことを叱るのです。
若い頃の私は整理整頓が苦手で、支店長から直接注意されたことがあります。
その時に「山地君、若い内から整理整頓に気を付けなければダメだ!年をとるとめんどくさくなりがちだから、もっと酷くなるぞ!」と言われたことを覚えています。
それから意識して気を付けるようにしています。
他から見れば不十分でしょうが、少しは良くなった方だと思っています。
身の回りを整理整頓する5Sや6Sはシンプルライフと繋がっているのでしょう。
身の丈創職
昨日ある学校でお話しをして来ました。
出席した人達は20代から50代くらいまでの人達でした。
今回は再就職支援事業の一環の様です。
何回か講演の経験をすると、前に立ち、話しているうちに出席した人達の意気込みが分かるものです。
聞き耳を立て真剣に聞く人と、いやいや出席している人、さまざまいます。
今回は真剣に聞いてくれる人が多く、私も熱くなって話をしてしまいました。
今回話をしたのは「身の丈創職」というテーマでした。
私は別に「身の丈起業」という講座も開いています。
創職も起業に近いものがあります。
「創職」とは就職しても、その仕事が自分の「天職」とは思えなく、一念発起して自分の仕事を新しく作り出すことです。
作り出すことは起業に似ています。
それまでの仕事の経験を応用し、極端に言えばこれまでの日本にはないような新しい仕事を生み出すこと。
そして自分で肩書を創り出します。
経営コンサルタントの経験を生かし「キャリア& マネーアドバイザー」
インターネット関係では「ウェブプロデューサー」や「アプリケーション・ソムリエ」
精神科の医者と連携してアロマオイルを用いてマッサージをする「メディカルアロマテラピスト」等があります。
それ以外に私が提案したのは、既にあるのかもしれませんが次のようなのもです
・マンションのベランダ専門の「ベランダガーディナー」
・親子の相性を専門に見る「教育運命鑑定士」
・儲かる会社・オフィス作りを目指す「オフィス専門風水師」
・思い出の家具をよみがえらせる「家具のお医者さん」
・パソコンや情報が苦手なシニア向けの「シニア専門旅行アドバイザー」
・家でパソコンを作ったら叱られるお父さん向けのプラモデル製作ルームを作り、その運営をする「プラモデル・アドバイザー」等があります。
このような肩書は付けた者勝ちです。
早く肩書きの付いた名刺を作り、人に配り、マスコミの記者クラブで配布すれば、ニッチな世界の専門家としてテレビ局から声がかかるかもしれません。
このように書いてみますと創職と言ってもやはり自分で仕事をするわけですから、身の丈起業に近いものがあります。
これからは「身の丈起業講座」の対象を創職を目指す人にも広げていく方が現実的かと思っています。
講話後に今回出席した人から建設的な質問も多く、話をした者として満足しています。
3人ほどの人からから私の事務所を訪問したいとの申し出がありました。
喜んでお迎えします。
今回も良き出会いがありました。
定点観測地点
2日前にMiceの「企業セミナ」に参加した時のことを書きました。
その時は「北海道遺産」について書きました。
同じセミナーの中で、別の講師からもいい話がありましたので紹介したいと思います。
その講師は道内大学の准教授です。
仕事で中国や韓国に行くことが多く、中国には年に2回程行って、行くと必ず立ち寄るところがあるそうです。
それは本屋です。行くその本屋は同じところに決めています。
1週間ほど前に中国から戻り、その時に感じたことを話してくれました。
准教授は観光に関して研究をしており、本屋では中国の観光雑誌なども買ってきます。
震災前に行った時、観光に関する雑誌や本はほとんどが日本の観光地を紹介するモノが中心で、北海道も注目されていました。
しかし今回行って驚いたのは、日本に関する観光の本は1冊しかなく、ほとんどはアメリカ・カナダ観光に関する雑誌や本に変わっていたのです。
今、中国人の海外観光の目は既に日本からアメリカ・カナダ・ヨーロッパに向いていています。
もしかしたら、震災が落ち着いたら日本に観光客が戻ってくるだろうという期待も叶わないかもしれません。
この状況は生の情報です。
いずれ新聞やテレビでも取り上げられるかもしれませんが、生の情報が早く入手できるということは重要です。
早めに対応が出来、現実的対処が出来ます。
情報を手に来入れるには現地に行き、人に会うことは大事です。
それと同時に自分だけの情報を得る場所が必要です。
それは自分で決めた「定点観測地点」を作ることです。
今回のセミナーで情報を話してくれました洵教授も、本屋という自分の「定点観測地点」を持っていました。
そこで売られている雑誌や本の変化で、日本への観光客が減少するだろうという予想を立てたのです。
昔ある雑誌の編集長もテレビで「定点観測地点」を持っていますと話していました。
自社の週刊誌が発売される時は、繁華街のある売店の前に半日ほど立っていて、売れ行きを見ていたそうです。
週刊誌の発売数などは後で集計されることですが、それは何日も後です。
遅い情報は役に立ちません。
自分で発売日に「定点観測地点」で確認した状況と、後で発表される売上状況とは変わらなかったそうです。
生の情報をいち早く得て、次号の記事構築に生かしたそうです。
最近札幌市内で通行量調査がされていますが、これも定点観測でしょう。
このように定点観測について書いていますが、現在の私は「定点観測地点」を持っていません。
せいぜい地下鉄に乗る度に、広告ポスタ―の枚数増減や、その業種を注意して見ている位です。
私も改めて自分なりの「定点観測地点」を作りたいと思っています。
3割バッター
今朝の日経新聞の「春秋」に将棋の羽生さんと大リーグのイチロー選手のことが書かれています。
羽生さんの王座戦連覇が19で終わり、イチロー選手の200本安打記録が10で切れてしまいます。
それに対して「記録はいつか途切れる。途切れてこそ二人の輝きが増す」と1ファンとして筆者は結んでいます。
私もこの2人には、常に挑戦するストイックな生き方に憧れみたいなものを抱いています。
この「春秋」の中に長嶋茂雄さんの言葉も紹介されていました。
3割バッターを評して「だいたい世の中で7割ミスをして、3割だけうまくいゆけば評価されるなんて商売は他にありますか?」と言っています。
私も最初は「なるほど」と思ったのですが、でもそうではありません。
一般の人は、ひとはうまくいっている会社や人を外から見て、常勝を羨ましがります。
でも実際は違います。
一見成功し続けているように見える会社や人も、その陰では7割以上の失敗を繰り返した上の成功なのです。
会社等は時として1割の成功率ということもあります。
発明王エジソンが電球を発明するまで1万回の失敗があったと聞きます。
失敗したところを表に見せなだけです。
野球のバッターも7割の失敗があって生まれる3割です。
その上野球の場合年間144試合ズーと挑戦し続けています。
また、試合以外でも個人トレーニングを重ねた上での3割です。
どのような世界でも100%うまくいくことはありません。
失敗を繰り返して、挫折を乗り越えて1~3割の成功を手に入れます。
またそれは1度きりではなく、その成功を積み重ねるのです。
ある程度の年齢になった時、自分の人生を振り返って見て、「一生懸命やってきたな。私は運が良かったな」と思うのです。
最近の若い人と話すと、運をつかむことばかりに気がいっているようで、本来自分のするべきことを一生懸命しているのかと疑問に思うことがあります。
一生懸命していれば運は後からついてきます。それは真実です。
それを早く知った人が成功すると私は信じています。
北海道遺産
昨日はMiceアカデミーの「企業セミナー」に出席して来ました。
ところで皆さんはMiceをご存知でしょうか?
正直言って私はよく分からず参加しました。
Miceとは企業等の会議(Meeting)、企業等が行うインセンティブ旅行(Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議(Convention)、イベント、展示会・見本市(Event/Exhibition) のことで、Miceはその頭文字からきています。
多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどを取り込もうとする活動です。
ホテルや商業施設等の観光関連企業が中心となって啓蒙・教育の活動を進めています。
今回の「企業セミナ―」は「プロフェショナルなホスピタリティを提供するための知識や心構えを北海道ならではの『食のもてなし』も検証しながら学習する」とありましたので、Miceのことをよく分からず参加申し込みをしてしまいました。
セミナー時間は9:30から16:30までの長丁場。
最近はこのように長い時間セミナーを受けていないので眠たくなるかと心配しましたが、なんとか大丈夫でした。
ただ参加者は20歳代の若い人達が中心でしたので、チョット場違いな感じがしました。
セミナーは昨日と来週火曜日の2回あります。
講師の中には知人の社長や高校の同級生がいたり、お互いに気を使うところがあり、別の刺激を受けました。
昨日のセミナーは4講座でした。
その中で「まちづくり事業」を主に活動している知人社長の話が特に興味がを持ち聞きました。
話の中で、「まちづくり事業」を行う時そのアプローチの手法を説明してくれました
その順番は「まちの魅力や資源を掘り起こす」⇒「まちの価値をみんなで守り育てる」⇒「まちの魅力や価値を広く発信する」⇒「まち作りからビジネスを起こす」となっています。
「まちづくり事業」の1つは、その社長も中心となって進めている「北海道遺産運動」です。
「北海道遺産運動」とは次世代に残したい北海道の宝物を掘り起こし、地域で守り育て、活用していき、その中から新しい魅力を持った北海道を創造する道民運動です。
今登録されているのは「自然遺産」「歴史遺産」「文化遺産」「開拓遺産」「産業遺産」「食文化」に分類され、合わせて52項目があります。
遺産と言うと「世界遺産」が有名ですが、「北海道遺産」は1997年から構想が始まり、2001年に正式に設立されました。
私もこの「北海道遺産」の話を聞いて、自分が住んでいる場所にも、気付かないだけで素晴らしいものがあるのかもしれないと「自分遺産」を思い浮かべてみました。
自分が大切にしたく、自慢に思うものを再確認してみたのです
小学生の時、遊んだ発寒川や琴似神社、昔ながらの細い路地等を上げてみました。
でも本当に「自分遺産」にしたいモノはもう無くなっていました。
私が卒業した小学校・中学校・高校の校舎既に建て替えられ、住み慣れた実家も既になく、夕日が映えていたサイロとポプラ並木も無くなりました。
改めて月日が経ったことを認識するとともに、経済成長の中、世の中の急激な変化の中で環境が激変し、大切なものが失われてしまったことを再認識しました。
2度と手に入らない大切なモノは「守る」という意識がが無ければ守れないのです。
「北海道遺産」に選定された遺産も、「守る」運動が生まれたことによって将来も守られるでしょう。
何もしなければ、きっと消えていってしまいます。
現在の遺産を次世代に引き継ぐのは「大人」に課せられた責任なのですね。
挑戦
今月の初め頃、雑誌「致知」の広告が日経新聞に掲載されました。
読まれた方もいると思いますが、とてもいい文章でしたので、それを切り抜き、私の[銘肝録]に貼っています。
今日はそれを紹介したいと思います。
生涯を小中学生の教育に捧げた東井義雄先生からうかがった話として書かれています。
「ある高校で夏休みに水泳大会が開かれた。
種目にクラス対抗リレーがあり、各クラスから選ばれた代表が出場した。
その中に小児マヒで足が不自由なA子さんの姿があった。
からかい半分で選ばれたのである。
だが、A子さんはクラス代表の役を降りず、水泳大会に出場し、懸命に自分のコースを泳いだ。
その泳ぎ方がぎこちないと、プールサイドの生徒たちは笑い、ヤジった。
その時、背広姿のままプールに飛び込んだ人がいた。
校長先生である。
校長先生は懸命に泳ぐA子さんのそばで『頑張れ』『頑張れ』と声援を送った。
その姿にいつしか、生徒たちも粛然(しゅくぜん)となった。」
私はこの文章を読むたびに少し涙ぐんでしまいます。
「イジメは良くない」と叱るのでなく、校長先生が自ら背広のまま飛び込み励まします。
A子さんに手を貸さず、「頑張れ」「頑張れ」と励ます姿に感動します。
また、それより「イジメかもしれない」と分かっていても、逃げることなくリレーに参加するA子さんの心意気の素晴らしさ、そしてそれを支えている親・家族の姿が浮かんでくるようです。
精神的にも肉体的にもハンディーを負った人達を差別することは人間として、してはいけないことです。
それを分かった上で、A子さんのような人を育てることも大事かと思います。
ハンディーを追った人は自他「障害者」との認識を持っています。
優しくすることも、されることも当り前と思っている部分があります。
でも優しさは時としてその人の力も殺いでしまいます。
人の可能性はハンディを乗り越えたところにあります。
それを思い知らされたのが韓国で行われた世界陸上「男子400」です。
それに出場した両足義足のランナー、オスカー・ピストリウスさんです。
パラリンピックのような障害者だけの競技会でなく、世界一を競う世界大会に挑戦して立派な成績を残せたことが素晴らしいことです。
両足義足のランナー、オスカー・ピストリウスさんが世界陸上に出場すると知った時は驚きでした。
でも、障害者でも健常者と対等に戦えることを証明しました。
彼の挑戦が、それに倣う多くの障害者アスリートを生んで行くのでないかと期待しています。
経験則を重視する
今回は「京セラフィロシフィ」勉強会最後の項目「経験則を重視する」です。
これについて稲盛さんは次のように書いています。
「企業での技術開発やものづくりには経験則が不可欠です。理論だけではものはできません。
たとえばセラミックスの場合、原料である粉体を混ぜて成型し、高温で焼けば出来あがるということは、勉強さえすれば誰でも理解できます。
ところが、粉体を混ぜるということがどういうことなのかは、実際に自分で手を染めて苦労してやってみないと決して分かりません。
液体や気体なら完全な混合が出来ますが、粉体はどこまで混ぜたら混ざったと言えるのか、それは経験則でしか分からない世界です。
この経験則と理論がかみ合って初めて、すばらしい技術開発やものづくりが出来るのです。」
この「経験則を重視する」は前項の「現場主義に徹する」とつながっています。
私は「経験」というと職人の世界を思い浮かべます。
学校も満足に出なかった人が、職人の世界に入り、下働きから始まり、叱られ、怒鳴られ、時には叩かれながら身体で基礎を覚え、仕事の技を盗むよう習得していきました。
それは理屈なしで会得していく姿です。
身体に染み付いた経験を通して、その世界の本質を知っていくのです。
一方、今は情報や知識を得ようとすればインターネットで簡単に手に入ります。
何かをするにしても、その作り方、使う道具も図解で紹介され、簡単なことは出来てしまいます。
この簡単に出来てしまうところが、落とし穴で、それで全てを知った気になってしまうことです。
また、自分は頭がいいと思ってる人は、動く前にどうしても物事を頭で考えます。
そしてそれを基準にして判断しようとしがちになります。
そこに経験で生きてきた人との対立が生まれます。
起業して会社運営をする時、往々にしてこのようなことにぶつかるケースがあります。
起業する人は得てして自分に自信があります。
自分の考えることだけが正しいと思いがちです
そのような経営者に必要なのは、「謙虚さ」です。
自分より経験のある人を素直に認める「素直さ」なのかもしれません。
稲盛さんが言うように「経験則と理論がかみ合った」状態にすることは、起業した会社が発展する大事な基本ポイントの1つです。
現場主義に徹する
今日は72項目の「現場主義に徹する」についてです。
稲盛さんは次のように言っています。
「ものづくりの原点は製造現場にあります。
営業の原点はお客様との接点にあります。
何か問題が発生した時、まず何よりもその現場に立ち戻ることが必要です。
現場を離れて机上でいくら理論や理屈をこねまわしてみても、決して問題解決にはなりません。
よく、『現場は宝の山』と言われますが、現場には問題を解くためのカギとなる生の情報が隠されています。
絶えず現場に足を運ぶことによって、問題解決の糸口はもとより、生産性や品質の向上、新規受注などにつながる思わぬヒントを見つけ出すことが出来るのです。
これは、製造や営業に限らず、すべての部門に当てはまることです。」
会社は優秀な人材を求めて人を採用します。
優秀な人は大学で勉強し、研究し、それを実際の仕事に生かそうとします。
ところがこのような人間が得てして陥りやすいのは、やり方さえ知っていれば簡単に出来る、と錯覚してしまうことです。
しかし実際にやってみると、うまくいかず、理論上出来ることでも実際はそうならないものです。
勉強して身に付けた知識と、現場で実際にやってみて得た経験の2つをあわせもって、初めて「できる」といえます。
知識が経験を経て知恵が生まれ、能力が高まるのです。
この事は従業員ばかりでなく経営者自身にもいえることです。
時として経営者が現場に入って、現状を把握し、問題点を見付けなければなりません。
稲盛さんも社長の時は、作業服を着て工場に入り作業状況を確認していました。
また必要であれば、工場内に社長の机があってもいいのではないでしょうか。
社長の現場主義の姿勢を見せることと、実際に現場に足を運ぶことが出来ることになります。
ソフトバンクの孫さんの言葉で「信じるな!疑うな!現場で確認せよ!」というのがあります。
その通りですね。
必要な時必要なだけ購入する
今日は「必要な時に必要なだけ購入する」について書きます。
これについて稲盛さんは次のように書いています
「物品や原材料を購入する場合、大量に買えば単価が下がるからと言って、安易に必要以上のものを買うべきではありません。
余計に買うことは無駄使いのもとになります。
たとえ一時的に大量に安く購入できたとしても、これによって在庫を保管するための倉庫が必要となったり、在庫金利が発生したりといった余分な経費がかかってきますし、さらには製品の仕様変更などの理由で、全く使えなくなってしまう危険性もあります。
やはりメーカーはメーカーに徹し、ものづくりそのもので利益を上げるということに専念するべきです。
必要な時に必要なだけ購入するという考え方が大切です。」
この事は以前の[健全資産の原則を貫く]でも述べたことですが、一見まとめ買いは安く上げるコツのように見えますがそうではありません。
大量に買って在庫が発生するとなれば、その為の倉庫が必要になります。
その上、決算ごとに棚卸をしなければならず、人件費もかかり、使う見込みのないモノは廃棄処分をしなければなりません。
結果として、最初は安く買ったように思うけれども後々目に見えないロスが出てきます。
京セラでは今でも、必要な時に必要なだけ購入する「当座買い」を実施しているそうです。
会社で利益が出ているように見えても、もしかしたらそれは在庫に化けているのかもしれません。
健全な経営をする為にも在庫を少なくする経営は重要です。
倹約を旨とする
今日は京セラフィロソフィの「倹約を旨とする」について書きます。
稲盛さんは次のように書いています。
「私たちは余裕が出来ると、ついつい『これくらいはいいだろう』とか、『なにもここまでケチケチしなくても』と言うように、経費に対しする感覚が甘くなりがちです。
そうなると、各部署で無駄な経費が膨らみ、会社全体では大きく利益を損なうことになります。
そしてひとたびこのような甘い感覚が身についてしまうと、状況が厳しくなったときに、改めて経費を締め直そうとしても、なかなか元に戻すことはできません。
ですから、私たちはどのような状態であれ、常に倹約を心がけなければなりません。
出ていく経費を最小限に抑えることは、私たちにできる最も身近な経営参加であると言えます。」
その後続けて書いています。
「人の考えは変わります。
ある時期には素晴らしい考え方を持って経営をし、その事業もうまくいき、人生も順調にいった。
けれど成功して環境が変わるにつれて、その人の考えも変わり、次第に堕落していく。そしてせっかく成功させた事業を失敗させ、会社を潰してしまう。
経営者が持つ考え方は変化します。それによって経営状態も変わっていくのです。」
稲盛さんはこのように書いた上で「現在は過去の結果、将来は今後の努力」と書いています。
また稲盛さんは自分のことについても書いています。
自分は貧乏性なのか贅沢はできないと言います。
昼食をとる時、吉野家の牛丼が好きで、よく運転手さんと行くそうです。
吉野家から名前入りの専用のどんぶりをもらっているくらいです。
最近の話ですが、稲盛さんは現在JALの会長として、月曜日~金曜日まで東京暮らしです。
滞在先はホテル。
ホテルにはレストランも沢山あるのですが、それよりコンビニ弁当も食べるそうです。
東京で盛和塾の会合があり、塾生がホテルまで送ろうとした時、彼らは稲盛さんが途中でコンビニに入り、弁当などを買っていくのを目撃しました。
塾生の中には寿司やレストランの社長もいて、夕食などの差し入れをしたいと申入れしたそうですが、それも断ったそうです。
稲盛さんほどになれば贅沢してもいいように思いますが、意識してそれを避けているようです。
稲盛さんは最後に「経営者は10年はおろか、20年も30年も40年も会社の繁栄を維持していかなければなりませんから、努力を延々と続け、その間わずかでも慢心することがあってはならないのです」と書いています。
以前ウォルマートに関する本を読んだ時も、ウォルマートの役員でさえ飛行機はエコノミー席、2人連れであればホテルはツインルームと規定で決められているそうです。
「倹約を旨とする」は如何にトップ経営者が実践しなければならないことかが良くわかります。
採算意識を高める
今日も昨日に引き続き「京セラフィロソフィ」について書きます。
69項目の「採算意識を高める」についてです。
稲盛さんは次のように書いています。
「京セラでは、アメーバ単位で[時間当たり採算制度]を実施し、職場での仕事の結果が誰にでもわかるようになっています。
社員1人1人が経営者の意識を持って、どうすれば自分達のアメーバの[時間当たり]を高めていけるかを真剣に考え、実践していかなければなりません。
常日頃、鉛筆1本やクリップ1つにいたるまで、ものを大切にしようと言っているのはこうした思いの表れです。
床にこぼれ落ちている原料や、職場の片隅に積み上げられている不良品が、まさにお金そのものに見えてくるところまで、私たちの採算意識を高めていかなければなりません。」
「採算意識」とは「原価意識」のことです。
「採算を合わせる」ということは即「利益を得る」という意味にとられがちですが、そうでななく、常に「原価を考える」ということであって、このことが採算を向上させる鍵になるのです。
大切なのは仕事をしていく中で、原価がどうなっているかを考えることで、それをせずに経営がうまくいくはずはないのです。
そのことを稲盛さんはレストランで食事した時を例にして説明しています。
「ホテルのレストラン食事をするとします。
レストランの中は閑散としていて、何人もウエイトレスやウエイターが手持無沙汰で立っています。
数少ないお客様が千円から千五百円位のを食べているようだと、頭の中ですぐ計算します。
従業員の人件費、レストランの売上を計算し、『これじゃ採算は合わないな』となります。
このように自分の仕事は勿論、色々な場面で一瞬一瞬で原価意識を持って物事を考えることが出来るか、それともただ漫然と見ているだけか、これによって経営は大きな違いが出て来ます」と言っています。
稲盛さんが書かれたような事は私も良くします。
居酒屋、ラーメン店、カレー店に入った時、そこの平均客単価と席数・回転率等を計算し、材料費、人件費、テナント料などを差し引いてどの程度利益があるかを大まかに計算します。
もしも採算が合わないとすれば、なぜ長年営業することが出来るのかを考えてしまいます。
もしかしたらアパートなどの別の収入源があるからなのか等とも想像します。
また、私がこの店を任せられたらどのようにして改善するかも考えます。
店構え、雰囲気、サービス、メニュー改良等によってどのように売上が伸びるか考えます。
好き勝手な考えが出来るので楽しいです。
料理が出てくるまで、このように考えるだけで頭の体操になり、経営のヒントを得ることが出来ます。
目標を周知徹底する
昨夜は毎月行われている「京セラフィロソフィ」勉強会の日でした。
今回は「目標を周知徹底する」「採算意識を高める」「倹約を旨とする」「必要な時に必要なだけ購入する」「現場主義に徹する」「経験則を重視する」の6項目を勉強しました。
今日は「目標を周知徹底する」について書きたいと思います。
稲盛さんはこれについて次のように言っています。
「目標を達成するためには、その目標が全員に周知徹底されていなければなりません。
つまり全員が目標を共有し、自分達のものになっていることが必要なのです。
営業部門でも製造部門でも、当月の[売上]や[総生産]、[差引売上]・[時当たり]などの数字が全員の頭にしっかりと入っていて、職場の誰に聞いても即座にその数字が口をついて出てこなければいけません。
京セラの[アメーバー経営]と[時間当たり採算制度]では、目標を全員に周知徹底し、共有化を図ることによって1人1人の参画意識が高められ、これが一丸となって目標達成に向かうエネルギーとなるのです。」
一般的に経営者は幹部社員に対しては自分の考えを話しますが、そうではなく全社員に対して語りかけることが必要なのです。
また、経営者は皆に目標を周知徹底させるばかりでなく、現状や結果も全て報告することが大切です。
時として、幹部社員にその部門の目標売上・利益高・利益率等を質問すると、少しお待ちくださいと言って、資料を見る者がいます。
論外です。
とっくに頭に入っていて、その部門の部下たちと数字を共有していなければならないのです。
そのような幹部は結構いると思います。
京セラの場合はアメーバー経営をしていますので、アメーバーのリーダは経営者意識を持たなければ務まりません。
その為、経営者意識が浸透し易いのだと思います
最終的には経営者も従業員も共同経営者的意識を持つことが大切です。
やはりそこには、経営者や従業員が共有できる会社の理念があれば可能になるのではないでしょうか。
宇宙船地球号
今朝は私の事務所で朝食会と称した勉強会がありました。
毎月第3火曜日、出勤前の7時30分から1時間ほど開きます。
今回は「宇宙船地球号は、今」という題名でのお話をしていただきました。
以下はその受け売りです・
「宇宙船地球号」という言葉は1951年頃にバックミンスター・フラーが用いた言葉で、「宇宙船地球号操縦マニュアル」という本を書きました。
この中では「宇宙船地球号はあまりにも見事にデザインされた発明」であり、「船内で生命を繰り返し再生出来るように、実に驚くべきデザインとなっている」等と地球をとらえています。
後にアメリカの経済学者のケネスEボールデンは「宇宙船地球号」は「無限の蓄えはどこにもなく、採掘するための場所も汚染するための場所も無い」と言っています。
即ち、再生出来るのではなく有限の存在だと言っているのです。
また、「エコロジカル・フットプリント」という言葉をご存じでしょうか?
ウィキペディアでは「エコロジカル・フットプリント」(ecological footprint:EF)とは、地球の環境容量をあらわしている指標で、人間活動が環境に与える負荷を、資源の再生産および廃棄物の浄化に必要な面積として示した数値です。
通常は、生活を維持するのに必要な一人当たりの陸地および水域の面積として示されます。
これは「宇宙船地球号」は有限のものであることが前提になっています。
日本人の現在の様な生活レベルを全世界の人が維持しようとすると、地球が2.4個必要であり、アメリカのレベルだと9.5個必要になるのです。
如何に地球に負荷を掛けない生活をしていかなければならないか。このままでは人類は滅亡してしまうという警告です。
「便利さ」を追求した結果です。
「不便」を知ること。「不便」を楽しむこと。そのような心構えがこれからは必要で、そのことを子供たちに教育していくことが大切ではないかと思います。
北海道はこれから冬を迎えます。
完璧な除雪、ロードヒーティングで雪を溶かし家の周りに雪が無くなるという快適さより、必要最低限の除雪、ロードヒーティングを使わず、出入りする道は狭くても生活することが出来ます。
また、北海道の車が全て4WDの車であれば、少しくらいのワダチ道でも楽に走れます。
福島の原発事故と今日の勉強会の話はつながります。
私たちは早急に自分達の生活を見直す必要があるのです。
優しさとは
昨日のブログで母のことを書きました。
母親はどの人にとっても優しい人です。
私の母も優しい人でした。
と言ってもいつも傍にいて、色々してくれるという人ではありません。
父が商売をし、兄弟4人の他に住み込みの若い人の食事の世話などをしていましたので、休む暇なく働いていました。
小学校の頃、学校帰りに雨が土砂降りになった時、多くの他の子は母親が迎えに来てくれましたが、私の母は1度も来てくれず、ずぶ濡れになって走って帰ったことがありました。
母は「迎えに行けずごめんね」と言ってくれました。
小学校の修学旅行の時、見送り・迎えに来てくれる他の親を見ながら、「僕にもお母さんも迎えに来てくれればいいのに」と思いました。
そんなことは叶わず、仕方が無いことと判っていましたから、それ以上の不満な気持ちは持ちませんでした。
母が優しい人だというのは判っていましたから。
「構ってくれなかった」ことが、今になってみれば良かったと思っています。
一方、今の親子関係を見てみると、優しさが溢れているように思います。
その上、過保護になり、子供の生きる力を削いでいるように見えます。
ある情報によると、現在日本の引き籠りの子供の数は百万人になるそうです。
その原因の多くは親の過保護によると言われています。
ある中学生の子供が女の子を好きになったのですが、フラれそれが原因で引き籠りになりました。
過保護のあまり、子供が転ばないように親が守り、転んでその起き上がることを教えてこなかったのです。
その為一度の挫折で心が折れました。
ある子は、ねだったモノを親が買ってくれなかったからといって自殺しました。
それまでは、欲しいと言えば何でも買ってくれたのに、急に買ってくれなくなり、それが自分への愛情が無くなったのだと錯覚したようです。
子供が小さい頃は少額のモノなので買えますが、子供が大きくなり欲しいモノの金額も高くなると、それをいつまでも続けることはできません。
それを愛情が無くなったと思ってしまったのです。
「優しさとは何か」を考えさせられます。
人は時として、受け止める相手のことでなく、自己満足で愛情や優しさを表現しているのではないでしょうか。
本当の愛情があれば特別に表現しなくても伝わるものです。
優しさも度が過ぎると悪になるのでしょう。
「小善は大悪に似たり」の言葉を思い返しています。
順番
今月13日から昨日までブログを止めていました。
13日の朝に母が亡くなり、なかなか書く気にもなりませんでした。
仮通夜を2夜し、昨日、告別式・忌中引も終わりました。
一段落した思いです。
昨年の11月に父が亡くなり、その一周忌が終わる前に母も旅立ったわけです。
寂しい思いはありますが、同時に私たち子供の役目を無事に果たしたという思いはあります。
昔、読んだ本の中に書かれていた良寛さんの話を思い出します。
ある時、良寛さんは婚礼に招待され、祝辞をお願いされました。
その時「爺・婆が死に、父・母が死に、子が死ぬ」と話したそうです。
出席者からは「婚礼の目出たい時に死ぬなどと言うことは不謹慎だ」と非難されました。
でもその真意は「人はいつかは死にます。爺・婆、父・母が死んで子が死ぬという順番が幸せ。それが逆になり、子が先に死ぬことは親にとって耐えれれない悲しみ。」と言うことです。
母もそれなりの葬儀をし、送り出して、その順番が守れたことに満足しています。
親が死んで満足していると言うと不謹慎かもしれませんが、そう思っています。
母は私たち夫婦と同居し、最後は家で看病されながら亡くなりました。
私たち夫婦、兄弟で相談し、母が死ぬ時は病院でなく、自宅で死なせたいという思いした。
往診の医者とも確認していました。
そして、最後は苦しまず、静かに息を引き取りました。
2人の親を送り出し、今は寂しいですが、新しい生活が始まります。
ここ2年程、ほとんど外出せず親の面倒を見てくれた妻に感謝し、これからは彼女を家から解放させて上げようと思っています。
妻は絵が好きです。結婚前は絵描き志望でした。
これからは自由に絵を描かせて上げます。
私が彼女のパトロンになります。
彼女が描く、明るくあたたかい絵が楽しみです。
意見を言う
人と議論をする時、皆さんは自分の意見を言う方ですか?それとも聞く方が多いですか?
これは人の性格にもよるのかもしれません。
一般的に人の意見を聞く耳を持つのがいいと言われることが多いです。
「人には口は1つ、耳は2つある」
だから人の話を聞くことが大切だというのを聞いたことがあります。
私も暫くは「そうだな」と思っていました。
でも最近疑問に思っています。
社長は社内会議ではあまり意見を言ってはいけません。
社員の意見を聞いて、最終判断をするのが社長であって、自分が喋っては社員の本当の意見が出てきません。
社長は聞く側に立たねばなりません。
しかし、社員等が1人の参加者という立場であれば違います。
「物分かりが良い」ような顔をして、意見を聞くだけでは参加する意味がありません。
また「おかしい」と思うことがあるのに、「この辺で意見を言うのはとどめておこう」と思うのもおかしいです。
それは「利己の心」があるからだと思うのです。
これ以上追及すると嫌われるからという気持ちは、相手に対する気配りのようですが、保身から出る態度です。
「嫌われたくない」「しつこいと思われる」等、自分が大事だから出てくるのです。
勿論、言い方も大切です。
反発されるような言い方で、喧嘩を売る人がいますが、それは自己顕示欲が強い人でそれもやはり利己です。
相手に分かってもらう言い方をして、自分の主張をはっきり述べることが大事です。
この「意見を言う」という話で思いだすのが、「葉隠」に書かれた話です。
会議の場でその間違いを指摘できなかったけれど、会議の後、如何に相手にその間違いを判ってもらおうという状況が書かれています。
「葉隠」は江戸時代の武士社会における心得を書いたものです。
以前にもにもご紹介したかもしれませんが、そこには「人に意見を言う時は相手が聞いてくれるよう工夫をするべきである」と書いてあります。
例えば帰り道に待ち伏せをして、その人が来たら偶然に会ったそぶりをし、一緒に帰る道すがら「そう言えば、先ほどのの〇〇は△△した方がいいと思うよ」とそれとなく自分の意見を言うのです。
相手が素直になっている時に言うことで、聞いてくれることがあると言うのです。
本当に相手のことを考える「利他の心」があれば相手も判ってくれます。
人に意見を言うこと1つとっても、昔から苦労しているのですね。
決断力
ある本の中に「逡巡(しゅんじゅん)は惑(まど)いを生み、惑いは恐怖を呼ぶ。」と書いてありました。
決断出来ないでいると、迷って、それが恐怖につながり、結局何も出来ないでいる状態のことです。
人が何かを決断する時、常に「どうしようか」と考えます。
特に自分の人生が変わるかもしれない時はそうです。
一歩を踏み出す勇気はそう簡単ではありません。
でも、必要な時必要な決断をすることが出来なければ、後で後悔します。
ですから誰であれ、決断をしなければならないのです。
もしかしたら、生きていくことさえ出来ないかもしれないのです。
それでは決断する勇気はどうしたら出来るのでしょか
それを作るいい方法があります。
身近のたわいもないことで訓練するのです。
たとえばレストランに入った時、何を注文するかすぐ決める人と、いつまでも迷っている人がいます。
そういう時こそ訓練の時です。
料理選びのその決断で後悔することであっても大したことではありません。
決断する訓練なのです。
訓練としては「メニューを見たら10秒以内に決める」と自分で決めておくのです。
注文して、それが意に添わないものが来ても、後悔しないのです。
「決断して全てが上手くいくはずはない」ということもその訓練で勉強します。
決断するという行為そのものの訓練のためです。
それでも、決断できないのなら、「メニューの最初に出てくるものを注文する」と最初から決めておくのです。
そうすると、機械的に決断することが出来ます。
慣れないうちは「決断するぞ!」と意識します。
でも色々な場面で他愛もないことでも決断を訓練していくと、大切な決断も容易に出来るようになります。
決断出来ない理由は、後で後悔したくない、損をしたくない、という思いからです。
でもこの世の中は5分5分です。フィフテ・ィフィフティです。
そのことがわかりさえすれば、決断は怖くありません。
決断が思ったことと、たとえ違っても大したことはないのです。
今の日本では余程のことがなければ、間違えた決断で命が無くなるということはありません。
独立するか、起業するか等の決断する時などは、余程検討して調査しているわけですから、その成功率は5分5分以上に成功率は高いのです。
昔ある人から聞いた話です。
「出来ると信じて始めたことは6~7割は既に成功している」と言うのです。
疑心暗鬼と言う言葉があります。
疑いの心でいると暗闇に鬼がいると思ってしまう心の状態を言います。
それでは「信心来喜」はどうでしょう。
この言葉は私が勝手に作った言葉ですが「信ずる心で行えば、喜びがやってくる」と言う意味です。
この世の中は決断だらけです。
「私は決断力がないな」と思った人がいましたら、どうぞ今度レストランへ行った時、思い出してやってみてください。
いい訓練になりますよ。
読書
最近私は意識して本を読むようにしています。
年のせいにしたくはありませんが、年と共に読解力が落ち、その内に流し読みになり、簡単に頭に入りやすい本しか読まなくなりました。
10年ほど前まで東京にいた時は、仕事に関する本も電車の中で読み、トータルでは今の3倍は読んでいたように思います。
私は風呂の中でも1時間ほどは本を読みます。
以前は難しい本も風呂の中で読んでいましたが、今は小説ばかりです。
風呂の中では本が濡れると思われますがそんなことはありません。
本を持つ手が濡れなければ大丈夫です。
以前読んだ雑誌の中で、ある経営者が新しい事業を勉強する時は、それに関する本を5冊ほど買い、主に風呂の中で読破したと書いてあったのを覚えています。
その人は風呂の蓋をテーブル代わりにし、その上に本とか筆記具を置き読んだそうです。
汗がたっぷり出ますのでタオルと飲み水は必要です。
風呂の中の読書は他のことに気を取られることなく、読書に集中出来るからいいのです。
その経営者の話によると、新しいことを勉強しようとすれば、それに関する本を5冊も読めば大体分かるそうです。
最近の私は少し小難しい本を読むと、なかなか頭に入らず苦労しています。
そんな時に最近気付いたのは、要約を書き留めるという作業がいいということです。
これは風呂の中では出来ませんので机に向かってします。
本を読み大事なところをマーカーで印をつけ、2度目そこのところを意識だとしても、それほど頭に残りません。
ところが少し面倒ですが大事なところを書き留める作業をすると、自然と頭の中で前後の文脈をつなぎ合わせ、その意味するところを理解するようになります。
勿論、全ての読書にこの方法は必要ありません。
読み飛ばしてしまって、要点だけを捕まえてしまう本もあります。
どちらにしても本を読むという行為をしなくなると、益々読むのに苦労するというのが実感です。
読む習慣をつけることこそが大切だと最近痛感している次第です。
生甲斐ある経営
昨日は美味しいランチを食べてきました。
以前にも何回かご紹介しています、予約をしなければ、なかなか入れないお店です。
ご一緒したのはサッポロビール会の仲間です。
仲間と言っても、私より年配者です。
ビール会の中では62歳の私でも若い方です。
普段は私はお陰様で多くの会合に参加することが多いいのですが、その参加者のほとんどは若い人達が多く、私はどちらかというと年上です。
時として偉そうなことを話すことが多いのですが、ビール会のように、私より先輩の人達がいる場所ではお話を聞く側になります。
昨日も取り留めのない話しの中でも色々な人生の話を聞かせていただきました。
食事をした店は私がお連れしたところでしたが、お連れした2人はその料理内容に大変満足されたようです。
食事の内容は写真を見ていただければ分かるかと思いますが、見栄えも良く、美味しく、とても1000円とは思えない内容です。
調理人はその料理を提供するために、前日の夜に仕込みをし、ほとんどが手作りです。
出来あいのモノはほとんどありません。
ですから夜は営業していません。ランチだけのお店です。
予約客がメインですから、その分だけ作るので無駄がありません。
メニューも1種類のみ。
食後にコーヒーを頼むと、300円ですが、美味いコーヒーと共にフルーツのデザートが出ます。
この店は年配の男性が2人だけで運営しています。
経営的には沢山儲かっているとは言えません。
席数は15席ほどしかありませんので、ランチだけの1日の売上は15名~20名で2万円位です。
休みなく営業していますので、1カ月間30日でも最大60万円程の売上です。
材料費や家賃を考えればそれほど手元には残らないはずです。
それでも、それ以上手を広げず、今の形を続けていくようです。
手を抜かない料理を提供し、お客様が喜ぶのを生きがいにしているようです。
そして私のように感激したお客様が自分のブログやツイッタ―で紹介とか、口コミで広がります。
たとえ沢山儲けなくても、途切れずお客様が訪れ、喜び、それに生甲斐を感じることも素晴らしい経営だと思います。
昨日お連れした2人も早速お店の名刺を手にしましたので、近い内にどなたかと来店するでしょう。
益々込み合うお店になるのは良いのですが、予約しにくくなるのがちょっと心配です。



起きていることはすべて正しい
昨日のブログでは「運と愛嬌」について書きました。
この「運」とか「ツキ」とい言われて、人の反応は2つに分かれます。
「運」とか「ツキ」の話を聞いて、大きくうなずく人と「そんなの!」と思ってしまう人です。
まず、「そんなの!」と否定してしまう人は、頭のいい人、自信がある人に多いです。
自立心があるのですが、もう一つ素直でない人が多いようです。
自信があるから人の話を聞こうとしません。
そして大きな失敗、辛い思いをしたことの経験がない人です。
「俺だって辛かったことぐらいある」と言っても自分の持っている力で乗り越えられた人です。
それだけ実力がある人ではあります。
一方、大きくうなずき肯定する人は、辛い思いをした時、自分の力ではとても乗り越えられず、神様や仏様にお祈りしたり、周りの人に助けを求めた経験のある人です。
そして、その中から這い上がった時に、「ありがたい!」と思い、神様や仏様に感謝し、周りの人に「お陰様で助かりました」という謙虚な気持ちが生まれます。
その時に自分の力以外の何かの力で克服することが出来たという思いが生まれます。
先ほどの「運」や「ツキ」を否定する人には、周りの人に助けられたという感謝と、「おかげさまで」という謙虚な気持ちが無いのだと思います。
事業で大成功した経営者の話を聞くと、異口同音に「私の力ではありません。運が良かったからです。ツキもありました。そして皆さんのおかげです」と言います。
謙虚な気持ちだけで言っているかというと、そうではなく、本当にそう思っているようです。
本当は、その人にもそれなりの力があるのですが、山あり谷ありの事業をしてくる中、倒産寸前に行った経験の中から這い上がった時、「神の手」とか「サムシンググレイト」に助けられたと言います。
また、そのような人の心の状態は「起きていることはすべて正しい」という思いです。
この言葉は勝間和代さんの本の題名にもなっていますが、このように思える人が成功するのです。
昨日ある人から手紙をいただきました。
差出人は起業を志し、会社設立したばかりの女性です。
ところがこれからという時に、ビジネスパートナーとの意見の相違と離反、またご自分も大きな病気の疑いも見つかり、以前私のところに相談に来られた時、思わず泣き出したのです。
でも昨日の彼女からの手紙には、これから前向きに生活し、仕事の準備も進めていくと書いてありました。
その上、この一連の出来事が自分にとって何かを示唆しているのではないかと書いています。
このマイナスと思われることさえ、良くなる為に必要なことと思っているようです。
起きてしまった辛いことを悔やむのでなく、前向きに「起きていることはすべて正しい」と思える人は今まで以上に強くなれる人です。
私はこれからも彼女の起業を支援し、成功出来るようを一生懸命お手伝していきたいと思っています。
運と愛嬌
昨日テレビを見ていましたら、松下政経塾のことが特集として取り上げられていました。
松下政経塾はご存知の方も多いと思いますが、1979年に「新しい国家経営を推進していく指導者育成が、何としても必要である」との松下幸之助氏の思いによって設立されました。
日本の政財界に多く人材を輩出していて、今の野田総理もこの松下政経塾出身者です。
勿論、この松下政経塾に対する批判も多いです。
「政治家養成機関として、ほかにライバルがいないから目立っているだけ」とか「エリート意識が高くて一般人を理解しないタイプも多い」とか言う評論家もいます。
ただ、このテレビの特集を見ていると、現代の日本に若い人達を指導者として育成する機関が無い中、特異で興味ある教育機関だと思っています。
私は現在、京セラの稲盛和夫さんが主催する盛和塾に入塾したいますが、それは稲盛さんが経営者として、人として尊敬するからです。
稲盛さんを知る以前は、松下幸之助さん、そして土光敏夫さんを尊敬し、お二人に関する本は数多く読みました。
ですから松下政経塾が創立されたことは当時既に社会人になっていた私も知っていました。
その頃から興味を持っていました。
昨日のテレビの中で松下幸之助さんが入塾時に重視してい項目が紹介されていました。
それは「運と愛嬌」です。
野田総理も第一期生として入塾試験を受けました。
論文試験等の後、面接がありました。
幸之助さんの面接の時、「あんたには『運と愛嬌』がありそうだから選んだ」と言われたそうです。
同じ「運と愛嬌」があるという理由で入塾選考で選ばれた人は多かったようです。
テレビでその話を聞いて、以前に幸之助さんが言ったか書いたことで「人事面接では必ず運がいいかどうかを聞くようにしている」と言ったのを覚えています。
また、幸之助さんの言葉を纏めた「松下幸之助発言集」の8巻の題名は「強運無くして成なし」にも運のことが書かれています。
「一番偉いのは運の強い人だと思う。頭が良く金もあり、社交が上手であっても、突然ころっと死んでしまっては何もならない」と書いています。
「運」と「愛嬌」は人を成功に導いてくれる馬車の両輪みたいなものでしょう。
「愛嬌」がある人は「運」が付いてきます。「運」が付けば人生が楽しく、楽観的になり、笑顔も出て、益々「愛嬌」が良くなります。
今回のテレビで松下政経塾と幸之助さんが紹介されたこともあり、暫く本箱に眠っていた「松下幸之助発言集」10巻を久しぶりに読破してみようと思っています。
ペースメーカー
2日ほど前のブログで「ドリームプラン・プレゼンテーション」について書きました。
その時に表現力不足から「ドリームプラン・プレゼンテーション」を批判するような内容になったかもしれませんが、本意はそうではありません。
その企画や目的は良いのです。
ただ時として、それに適さない人にとって辛い結果になる恐れについて書いたつもりです。
例えば起業して会社経営したいと思っても、その人の性格から言って、無理だと思われる人が時々います。
私は「身の丈起業をしましょう」「無理をしない起業をしましょう」と日頃言って、起業家が1人でも多く生まれればいいと願っています。
それでも、この人は無理だという人はいます。
そのような人には「あなたは起業家に向いていません」とその理由も述べて、はっきり言ってあげる方がその人にとっては大切なことです。
全ての人にとって良いということはありません。
改めて起業について言えば、会社の規模の大小はあるにしても、多くの人はそれなりに起業は出来ると思います。
しかし起業しても全ての人が成功出来るわけではありません。
勿論、成功の程度は人によって違います。
その成功するために大切なのは、起業の時に抱いた夢を持ち続けて、仕事をし続けることです。
時には自分の性格や考え方を変えることも必要です。
そしてその成功をサポートしてくれる人が大切です。
怠惰な気持ちになった時、叱咤激励してくれる人。
苦労して目標を達成した時、褒めてくれる人。
悩んだ時、その話を聞いてくれる人。
そのような人が「アドバイザー」「コンサルタント」「コーチ」「メンター」なのでしょう。
ただもう一つ、より起業家に密接に傍にいてくれる人が必要だと思うのです。
あまりそこまで手厚くすると過保護になってしまうかもしれませんが、「ペースメーカー」という存在もあっていいかもしれません。
ウィキペディアでは「ペースメーカー」とは「陸上競技や自転車競技など中長距離競走において、ある走者に先行、あるいは伴走してその速度を主導する者」と「心臓に対して電気刺激を与え鼓動を促す医療機器」と説明しています。
起業家にとっての「ペースメーカー」とは、私のイメージでは常に心臓に刺激を与え続けるように、起業家に常に刺激を与え続けれる人です。
「アドバイザー」に近い存在ですが、より起業家に近い位置にいます。
少なくても毎日接点を持ち、刺激し続ける人です。
私の知っているところでは、そのような「ペースメーカー」的な仕事をしている人はあまりいないのではないかと思います。
起業を成功させるには「夢・目標を持ち」「正しい考えを身につけ」「強い意志で努力をし続ける」ことです。
私はその環境作りが本当の起業成功支援かと思っています。
琴似神社のお祭
昨日は地元の琴似神社の秋まつりでした。
毎年9月3日4日行われ、4日が本祭りです。
私はここ数年裃を着て神輿行列に参加しています。
今、各地に被害をもたらしている台風12号の為、3日は大雨、4日も午前中までは雨だったのですが、神輿行列が始まる時はほぼ雨も上がり、無事行列することが出来ました。
今回の台風が大きく、北海道に影響を及ぼす可能性がありましたので、私は3日ほど前に神社に、台風の影響で中止になった場合のことを尋ねました。
その時の回答が、「過去のお祭で雨のために神輿行列が中止になったことはありません。」でした。
それでも万が一の時はということで、その時の対処法を教えてもらいましたが、行列本番時は神社の人が言い切った通り、行列は中止になりませんでした。
琴似神社の神様は「霊験あらたか」と改めて感じました。
そう言えば誰かが「北海道神宮以上に琴似神社はパワースポットとして凄いところ」と言っていました。
今年も無事に神事に参加できたことは氏子の1人として嬉しく思っています。
ドリームプラン・プレゼンテーション
昨日「ドリームプラン・プレゼンテーション」の支援会に参加してきました。
知人誘われての参加でした。
今回のプレゼンターは2名。支援者などが20名ほど。
プレゼンターは自分の夢を語ります。
「ドリームプラン・プレゼンテーション」とは株式会社アントプレナーセンターの福島正伸氏が進めているものだそうです。
昨日このプレゼンテーションに参加して感じたのは、夢を語るのは良いのですが、その根拠や裏付がなく、現状と将来の姿が混在したような話でした。
特に「何のために」「誰のためにの」「どのように」という観点が抜けていました。
思いあまり、私はこの事と、数字の裏付けはどうなっていますか?と主催者に質問しました。
その回答として、改めて「ドリームプラン・プレゼンテーション」の目的が話されました。
「ドリームプラン・プレゼンテーション」はいかに楽しく感動する夢をあきらめない為、そして人間として成長することを支援するものとのことです。
事業計画等の数字を考える前の段階、胸が「ワクワク」する段階がこの「ドリームプラン・プレゼンテーション」だとのことです。
確かにそうです、私が起業する人達に話すのも、最初は自分の「ワクワク」する夢を膨らますことが大切で、誰かにその夢を潰されないために守ることは大事だといいます。
その次の段階ではその夢を実現するために充分数字の裏付けをして行かなければなりません。
起業を夢見る時は「楽観的に」、それを事業として計画する時は「悲観的に」、そして実行が決まり、会社設立して時は「楽観的に」するのがポイントです。
この夢を見る時の段階がこの「ドリームプラン・プレゼンテーション」なのでしょう。
夢を創り出すことは大切です。
日本人は「遂行能力」はあるが、「目的をつくる能力」は他の国の人より劣ると言われます。
ですからこの「ドリームプラン・プレゼンテーション」はいいことです。
ただ、このプレゼンテーション後はどうなるのかという疑問が残ります。
夢を膨らませてもそれを実行するための力が無ければ無意味です。
もしかすると、それ以上に害があります。
あまり否定的なことは書きたくないのですが、私の若い時に言われたことと重なってきます。
私が学生時代「あなたの生きがいは何ですか?」とか「あなた探しをしなさい!」という風潮がありました。
多くの文化人、インテリゲンチャ―という言われる人が、雑誌やテレビで話していました。
その中でも寺山修二氏の言葉に特に若者に影響を与えました。
寺山氏の言葉に「わたしの存在そのものが質問なのだ。その答えを知りたくて生きてるんだ。」というのがありました。
大変哲学的です。
それに感化された若者たちは、「自分探し」の旅に出た人も多かったです。
海外1人旅も増えました。私もその1人でした。
その経験から何かを見付けて成長して人もいましたが、多くの「フーテン」も生み出しました。
職を転々として、30歳40歳になっても「自分探し」をしていた人がいました。
私はその時の現象と今の「ドリームプラン・プレゼンテーション」がダブってきています。
これも「自分探し」みたいなものです。
ただ違うのは、「自分探」しの旅は誰でも出来ますが、起業をする人は誰でも成功出来る訳ではありません。
本当に夢があり起業したいと思う人が成功します。そしてその裏付けがあり、遂行能力がなければなりません。
起業しても成功しなければ起業の意味がありません。
「ドリームプラン・プレゼンテーション」を見ていて、思ってしまうことがあります。
もしかしたら、プレゼンテーションをしている人の中にはただ単に現実逃避して、夢の中で生きようとしている人もいるのではないかと。
もしもそのよな人達がそれに気付かずいることは不幸なことです。
勿論、この「ドリームプランプレゼンテーション」を通して成長する人もいるでしょう。
しかしそうでない人の方が多いと思います。
もしもその運動を推進するのであれば、そのプレゼンテーションの後も、それを事業として数字に置き換え実現するかどうかまでフォローしてあげなければ無責任です。
夢を膨らませるだけ膨らませて「後は知らないよ」では問題があるように思います。
私も起業成功を応援する1人として、危惧しているところです。
利己について
今日は先日読んだ本の中に書いてあった言葉を紹介したいと思います。
その本は文庫本で植西聰氏の「ヘタな人生論よりイソップ物語」です。
その本の最後に書いたある言葉を紹介したいと思います。
良いことが起こるようにするために大事にしたい6つの言葉です。
1・「喜与思考」:人に喜びを与えようとする心。愛情、善意。
2.「尊重思考」:相手の立場でものを考える心。思いやり、共感能力。
3.「楽観思考」:どんなことでもプラスに考える心。
4.「快生思考」:自分自身を大切にする心。快適に生きようとする気持ち。
5.「上昇志向」:現状に満足することなく、夢や願望を持つ心。向上心、探究心。
6.「行動思考」:願望達成や生きがいの創造に向かって積極的に考え行動する心。情熱、信念。
これらはよく言われる言葉ですが、纏めて見ると成程と思います。
この中で「喜与思考」や「尊重思考」は利他の心ですが、「快生思考」は自分が快適に生きようとする事なので、利己な考えなのかというとそうかもしれません。
利他の心が大切だというのはその通りですが、自分のことも大事にすることを忘れてはならないと思います。
私はこのブログで過去何度も利他の心の大切さを書いてきました。
しかし自分を大切にすることも大事です。
「燃え尽き症候群」という言葉をごぞ存じでしょうか?
これは一定の生き方や関心に対して、献身的に努力した人が期待した報酬が得られなかった結果、感じる徒労感または欲求不満になる状態と言われます。
人に尽くしても、それが義務であったり、責任感ばかりであって、それが自分にとっても良きことと思えることでなければ「燃え尽き症候群」になってしまいます。
「快生思考」というより、自分を喜ばせる「喜己思考」という言葉の方がいいのかもしれません。
利他の行為が自分にとって本当の喜びとなることにならなければ、「してもらった人」も嬉しいとは思わないはずです。
先に紹介した6つの言葉も、自分が幸せになることが最終的目的です。
「滅私奉公」ではいけないのです。
今日は自分も大切ということを書きました。
本の整理
今日は本について書きたいと思います。
本を読む量は60歳前から減りつつありました。
仕事に関する本ばかりでなく、小説を読むのも少なくなりました。
仕事に関する本は、なかなか頭に入っていかなくなったため。
小説などの本は面白かっただけで終わり、読み終わった本は読み返すことも少なく、冊数だけが積み上がってゆく無駄という思いがありました。
1年ほど前から本の整理をしています。
理想は手放すことの出来ない数冊の本だけを手元に置き、あとは処分したいと思うのですが、なかなか出来ません。
それでまずは、家にある本を「売却する本」と「残す本」に分けました。
「残す本」の中でも「手元に置く本」と「閲覧用の本」に分けました。
会社の私の部屋に本棚を2台用意し、そこに起業の人に役立つような業務関連本や自己啓発本などを置いています。
そして私が運営するレンタルオフィスの人達や勉強会に参加する人達がいつでも借りれる状態にしています。
そのようなこともあって、最近は本を選ぶのも慎重になっています。
本の整理をしていた時、1つ発見がありました。
以前に買って読みかけの「競争の戦略」が出てきました。
この本は「いい本だ」と言われたので買ったのですが、難しく途中で断念した本でした。
「最近読解力が低下している」と自覚している私は、あえてこの本に再挑戦しました。
やっとの思いで読み終りましいたが、読んだだけでそれほど中身を理解しているとは言えません。
そこで「理解力が低下している」と自覚している私はこの本を「どこまで理解出来るか挑戦しよう」と思い、ノートにまとめながら再度読み返しています。
予定では10月の末までにはノート取りは終わる予定です。
身辺を整理し、シンプルに暮らす事を目指して本の整理を始めましたが、その中で改めて昔のいろいろな本を読み返しています。
「私は結構いい本を買って読んでいたのだな」と自分を褒めながら、新しい発見を楽しんでいます。
運をつかむ習慣
昨日のブログでは、溜まった雑誌を整理していて早稲田大学の野口さんのコラムを見付け、それを紹介しました。
今日も雑誌「プレジデント」に書いてあって「成程!」と思った話を書きます。
その「プレジデント」では「運をつかむ習慣」という特集をしていました。
そこに京都大学の藤井教授の「解明!運が無い人は、なぜ運が無いのか」という題で「運がいい人」「運が悪い人」について書いてあります。
藤井教授は「認知的焦点化理論」というものを唱えています。
それは人が心の奥底で何に焦点を当てているか、そこに注目した心理学です。
「ある人が物事に向き合う時に、どの位他人のことを配慮できるかという観点から、人を分類したものです。
そのような研究の中から利他的な人ほど得をし、利己的な人ほど運をつかむチャンスを失い、益々損をするという法則を導き出しました。
一見気が利くタイプなのに評価が上がらない人は、自分の心の幅、つまり潜在的な配慮範囲が少し狭く、利他性が低いことに原因が潜んでいるのかもしれないのです。
利己主義者は、正直者を出し抜いて一時的には得をしますが、長い目で見れば必ず損をする運命にあります。
それは人間社会には『互恵不能原理』『暴露原理』『集団淘汰原理』という3つの原理があるからです。
『互恵不能原理』とは自分の損得ばかりに焦点が合っている利己主義者は『お互いさま』で成り立っている人間社会で、最終的に『嫌な奴』として村八分されてしまうことです。
『暴露原理』とは人間には利己主義者を見分ける能力がきわめて強力に備わっているということです。
表面的にごまかしても、利己主義者であることはすぐにバレてしまいます。
人間は進化の過程で『悪者を見破る能力』を異常に発達させてきました。
それが出来なかった人は、誰かに騙され生き延びることはできませんでした。
騙されない能力を発達させてきた子孫だけが生き延びているのです。
だから見破ることが出来る遺伝子を受け継いでいるのです。
『集団淘汰原理』とは利己主義者が支配する社会は社会ごと自滅し淘汰されることです。
これは企業もそうです。全社的に利己的体質が過剰になれば、やがては会社自体が崩壊することになります。」
この話を読んで、『利他であるか』『利己であるか』によってその人の運命が決まるということが理論的に書かれ納得しました。
私が納得出来るのは、私の周りにもそのような事例があるからです。
私の父はそれなりに事業を成功させました。
その父を支えたのは、父の母、即ち私の祖母と妻即ち、私の母でした。
その二人とも稀に見る利他の人でした。
父は時として利己のところもあったかもしれませんが、それを補うに余るほどの利他の人に守られていたのです。
京セラの稲盛さんも常に利他の心の大切さを説いています。
私も改めて、自戒してみます
円高のおかげ
昨日は今まで溜まった雑誌の整理をしました。
雑誌の気になった特集などは読み終わってからスキャナーでパソコンにいれ、またipadとも同期させて必要な時に見れるようにしています。
6月の週刊ダイヤモンドに早稲田大学の野口悠紀雄さんの「超整理日記」というコラムがありました。
今回は「貿易赤字は継続する。輸出立国時代は終焉」という題名でした。
貿易収支が4月に赤字となり、5月に赤字が拡大していると書いてあります。
LNG等の発電燃料の輸入が増えたためで、赤字は今後も継続し、赤字の定着は日本の経済構造が大きく変化することを示していると書いています。
それを裏付けるように、昨日(30日)に財務省が発表した8月上旬の貿易統計速報によると、貿易収支は3545億円の赤字となったようです。
前年同期は201億円の黒字でした。
今年度は 輸出が前年同期比7.6%増の1兆8523億円に関わらず、輸入は同29.7%増の2兆2068億円となったのです。
これは一時的なものではないようです。
野口さんは「原子力発電に制約がかかったことが、貿易赤字定着の本質的な原因」と書いています。
そして「これまでの『日本の輸出立国』は『原子力発電は絶対安全』という神話の上に築かれたものだ」と指摘しています。
また円安・円高の問題についても書いています。
円高によって日本の製造業は国内から国外に生産拠点を移す時代になってきました。
製造業界は円安・円高に左右されない体制になりつつあるます。
そして円高問題も円高によるマイナスが言われていますが、円高によって輸入品が安いということも、よく認識しなければなりません。ただ海外旅行がしやすくなっただけではありません。
それは原油価格にも表れていると野口さんは指摘します。
原油価格は09年1月初めの1バーレル34ドルから11年4月末の121ドルまで4倍近く上昇しました。
しかし日本の輸入単価は2.15倍にしか上昇していないのです。
これは円高のおかげです。
日本人は円高のおかげで石油価格高騰の影響から守られていたということはあまり評価されませんでしたがとても重要なことです。
しかし、このような状況の時に円高から円安へ移ると、貿易赤字が益々拡大し、原油輸入単価上昇などにより、全ての物価に影響してきそうです。
デフレだから低収入でも生活出来た環境も、激変し大変な時代になるかもしれません。
新首相選出後の注目
昨日民主党の代表選挙で代表が決まり、今日首相が決まる予定です。
新首相にはこれから山の様な難題が待ち受けています。
その中で私が注目しているのは、景気回復、復興財源確保の動きです。
首相に選出されるだろう野田さんは、新聞によると復興増税に前向きと報道されていました。
既に国会で承認された特別公債法案と共に復興資金として復興増税は実施されるのでしょうか。
注目しています。
またもう一つ注目しているのは、昨日もブログに書きましたが特別公債法案が承認され、赤字国債が発行されます。それが日銀が買い取りをするかどうかです。
現在日銀が国債を買うのは法律で制限されています。
財政法第5条に「すべて,公債の発行については,日本銀行については,日本銀行にこれを引き受けさせ,また,借入金の借入については,日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し,特別の事由がある場合において,国会の議決を経た金額の範囲内では,この限りではない」
多くの政治家はこの「特別の自由がある場合において、国会の議決を経た金額な範囲ではこの限りでない」を根拠に、国会で議決し日銀に買い取らせようとしています。
法律でそれを禁じているのは過去の苦い経験があるからです。
戦後に行われた国債の日銀買い取りにより、ハイパーインフレが起きたことが教訓になっています。
しかし、経済評論家も含めて多くの人が、日銀買い取りによってインフレを起こし、デフレ脱却と、円安誘導を目論んでいるようです。
アメリカも量的緩和QE3を実施しようという機運があります。
QE3も中央銀行による国債を買うことです。
これによりドル安になる可能性があるそうです。
こうなると国債の日銀買い取りによって円安にしても、QE3が実施されればドル安になり、円安は相殺されてしまいます。
ドルも円も安くなるということはどういうことになるのしょうか。
私のような素人では良く分かりませんが、基軸通貨のドルが安くなり、円も安くなるということは、相対的にユーローが高くなるのではないかと考えます。
でもユーローも不安材料があります。中国の元も同様です。
結果通貨安の連鎖になればどうなるのでしょうか。
年末までに何か大きなことが起きそうな予感がします。
政治と経済
今日は民主党の代表選挙があります。
民主党代表が次期首相になるのでしょう。
私は以前、政治に関してそれほど熱心ではありませんでした。
今もそうです。
でも今、政治と経済が今まで以上につながりが強くなったのを見て、「自分の仕事に関係ない」とも言えない時代になってきているのではないでしょうか。
勿論以前からも、政治と経済は一体のものでした。
しかしバブルの時などは、経済一流、政治三流と言って、経営者は政治と一線を引いた立ち位置にいたように思います。
そこには政治的主義・主張が無く、商売となればどこの国に対しても、政治的トラブルを避け、「頭を低くして」入って行きました。
政治の主義・主張とは無関係に商売第一で仕事をしました。
それが「エコノミックアニマル」と言われた一因でもありました。
しかしバブルが弾けてから、GDPは伸びず、デフレ経済の中、経済は三流にまでなりました。
民主党政権になってからの政治の不安定さ、それによる国民生活の影響は大でした。(だからと言って自民党がいいと言っているわけではありません。)
そして今回の大災害を契機に、今ほど政治動き1つで日本の経済、国民生活が大きく影響されそうな時はないように思います。
私は、「増税」と「国債の日銀引き受け」を注目しています。
もしも政治が誤った方向に行って、不安材料が増えてくると、国民はより一層自己防衛体制に入るかもしれません。
企業や富裕層の海外逃避が増える可能性は大です。
最近の報道では、個人の普通預金が増えているそうです。
収入が少なくなっているのに貯蓄思考が高くなっているのです。
それも自己防衛の一つかもしれません。
今日の民主党代表選挙を注目しています。
消費税について
今は新聞テレビでは民主党代表選挙を取り上げています。
5人の候補者から色々な政策が発せられています。(不十分な気がしますが)
その中で増税についても賛成反対の意見があります。
ただ、どの候補者もいずれは消費税増税も仕方が無いと思っているようです。
モノを買うと消費税が含まれている内税方式が多いですが、消費税が増税されると必ず販売価格が高くなり、消費が下がるというのは充分予想されることでしょう。
スエーデンなどのような25%の消費税が掛けられると、大変高いのもになります。
税金と言うと「取られる」というイメージがあります。
ですから、「高いのは嫌だ」となります。
でも少し考え方を変えてみてはいかがでしょうか。
日本でこれから引き上げられる消費税は明確に社会保障の目的税とされるでしょう。
そして、今まで社会保険料を払っていたどうかは関係なく、老後は誰でもが保障されるのです。
その財源は勿論消費税です。
社会保険料を払わなくなるので、個人も法人も可処分所得が増えます。
人々は将来の不安から貯金していたお金も、今の生活や遊びに使えます。
貯金に当てられていたお金が消費に回りますので、経済も活性化します。
個人の貯蓄高が下がりますから、また別の問題も発生するかもしれませんが、それは今は考えません。
要は消費税を老後の安定した生活のための「天引貯金」として考えて見るのです。
今から7年ほど前にフィンランドとスエーデンに福祉施設を回るツアーに参加したことがあります。
どちらも福祉国家ですが、フィンランドは22%、スエーデンは25%の消費税でした。
日本人から言えば高額な税率です。
それぞれの国の人に、「消費税の税率が高く不満ありませんか?」「消費税率を低くするという政治家がいたら当選間違いないのでは?」と聞いてみました。
回答した皆さんは皆「今の税率でいい」と言います。
低くするという政治家は落選すると言います。
「今の税率によって将来の自分の生活が保障されている。税率が低くなって将来の生活に不安を持ちたくない」という思いです。
ただ、どちらの国も税金の使い方のチェックは大変厳しいです。
スエーデンのある福祉施設を見学した時、そこは民間の会社が運営していますが、その運営内容、公的支給金、補助金等の使い方のチェックは10箇所の機関が行うそうです。
国、州、市、町等の色々な分野の機関がチェックしています。
入居者の満足状況もその評価に入っていて、本人・家族の満足も重要視されます。
日本の場合このチェック機関が不十分で、税金の流れが明確でないところに不信感があります。
将来は国や都道府県、市が本当に信頼されるための仕組みをつくらなければならないでしょう。
そうすれば消費税は「天引き貯金」という考えに対しても賛同してくれる人も増えるのかもしれません。
能力を未来進行形でとらえる
今日は「京セラフィロソフィ」67項の「能力を未来進行形でとらえる」です。
これは私がとても納得した内容のものでした。
稲盛さんは次のように書いています。
「新たな目標を立てる時は、あえて自分の能力以上のものを設定しなければなりません。
今はとても出来そうもないと思われる高い目標を、未来の一点で達成するということを決めてしまうのです。
そして、その一点にターゲットを合わせ、現在の自分の能力を、その目標に対応できるようになるまで高める方法を考えるのです。
現在の能力を持って、出来る、出来ないを言うことは誰でもすることです。
しかしそれでは新しいことや、より高い目標を達成することなど出来るはずはありません。
今は出来ないものを何としても成し遂げようとすることからしか、高い目標を達成することはできないのです。」
この中の「未来の一点で達成するということを決めてしまうのです。」という言葉は、ワタミ創始者渡邊さんは「夢に日付けを入れなさい」という言葉に似ています。
ただここで言っているのは、今の自分が持っている可能性を信じなさいというです。
どうしても今の自分だけを見つめてしまうと自信がなく、将来の可能性を見出そうとしないところがあります。
人間の能力は未来に向かってどんどん伸びて行くことを前提にして、自分の人生を設計することです。
それを、将来のある期限を決めて努力することで、能力が開花し、可能性も広がるのです。
稲盛さんはこの体験を京セラ創業時に体験したそうです。
創業時は松下電器や東芝にセラミックを売込むにしても、既に他の会社と取引をしており、そこに入り込むにはそう簡単でなったそうです。
そこでより強く依頼すると、「これは作れるか?」と出してくるのは、他のセラミックメーカーが「これは難しい。うちでは作れません」と断ったものばかりでした。
稲盛さんはそれを断ると仕事がないので、出来ますと言って注文を取ってきたのです。
その上、3カ月後に試作品を納品する約束までしました。
会社に帰って研究者に話すと皆は「稲盛さんそれは無理です」と口をそろえて言います。
その時に稲盛さんは「われわれの能力を未来進行形でとらえよう」と言い始めたのです。
試作品が出来あがるまで毎日文字通り命がけで難しい実験を繰り返し、議論を繰り返しました。
その時に唯一信じられたのは「自分の能力を未来進行形でとらえる」ということだけだったのです。
京セラはそのような仕事の繰り返しをしながら、特許等の技術を積み上げていったのです。
私も時として自信をなくしてしまう時があります。
でも、この「能力を未来進行形でとらえる」という言葉を知って、自分を信じるということこそ、基本であり、能力向上の原点である。そう考えています。
健全資産の原則を貫く
今日は昨日に引き続き「京セラフィロソフィ」66項の「健全資産の原則を貫く」について書きます。
これは昨日に紹介しました「日々採算をつくる」と同様経理に関する話です。
「京セラでは不良資産を発生させることを厳しく戒めています。
必要な時に必要なだけ買いいれること、必要なものだけをつくることが原則です。
余分なモノを買ったり、余計なモノをつくったりすると、不良在庫を発生させ、無駄な経費を使うことになります。
しかし、万一不良資産が発生した場合には、ただちにこれを処理することです。
一時的には損失を出すことになりますが、目先の数字にとらわれず、勇気を持って不良資産を処理しなければなりません。
これをせずに問題を先送りすると、さらに大きな損失につながります。
経営は常に健全な資産状態で行われる必要があるのです。」
製造業の場合、受注生産であっても、作り置きや余分に作ってしまったモノが発生しがちです。
それを売れるかもしれないからと言って在庫にして置くと、仮に売れる物でも2~3年経つと売っても二束三文にしかならなりません。
稲盛さんは言います。「そのような不良在庫や不良資産は、経営者自身が棚卸をして、不要なモノはなるべく消し、落とすようにしなければなりません。
ここで大切なことは、不良資産を落とすというのは、自分の都合によってすモノのではありません。
利益の出ている時に、利益を少なく見せる為にしたり、利益が出ない時にはしないということではなく、利益がどうであれ、常に健全な資産だけを残すようにするべきです。」
また不要在庫を抱えないために、「当座買い」の必要性も説いています。
私たちは会社でもまた個人でも、安い時に買っておこうとしてり、大量に買えば安くなるので買ったりします。
しかしそれでは無駄が多く出、結局は高いものについてしまうのです。
この事について稲盛さんは書いています。
「当座買いは、一般的には高くつくだけで常識的に反するやり方だと思うことでしょう。
ところがそうではありません。それは実に合理的な買い物の仕方なのです。
なぜなら、当座買いは高くつきますから、必要な分だけしか買いません。
人間というのは面白いもので、必要ギリギリの数しかないと思うと、どんなものでも実に丁寧に、大事に使うようになります。
ところが、それが倉庫に山ほどにあるとなると、どうしても粗末に使ってしまいがちです。」
確かに私の会社でもビス一本大事に使っているかというとそうではありません。
落としても拾おうとしません。拾うより生産性と高める方がいいという方便を使います。
ギリギリしかビスや材料が無ければ、落とすようなミスをしないようになり、より真剣に作業をし、製品もオシャカに成る率も低くなります。
「当座買い」をするという考え方は改めて考えてみる方法だと思います。
日々採算をつくる
今日は「京セラフィロシフィ」65項の「日々採算を作る」について書きます。
これについて稲盛さんは
「経営というものは、月末に出てくる採算表を見て行うのではありません。
細かい数字の集積であり、毎日の売上や経費の積み上げで月次の採算表がつくられるのですから、日々採算を作っているのだという意識を持って経営にあたらなければなりません。
毎日の数字を見ないで経営を行うのは、計器を見ないで飛行機を操縦することと同じです。これでは飛行機ははどこへ飛んで行き、どこに着陸するのか、分からなくなってしまいます。
同様に日々の経営から目を離したら、目標には決して到達できません。
採算表は1人1人の毎日の生きざまが累積した結果であるということを忘れてはなりません。」
毎日毎日数字を意識して経営をすることの重要性を指摘しています。
また稲盛さんは月次決算書のことも書いています。
月次決算は必ず作ること。そして締め日から10日以内に出来あがることを強調しています。
それ以上遅くなると、前月の決算書を使って、今月の経営を進めることが出来ません。
また、「採算は経営者の意思で作られる」とも書いています。
勿論それは粉飾決算を言っているのではありません。
「経営者が一生懸命に頑張っていても、採算がただ成り行きの数字だとすると、経営者の意思が伝わりません。
先月は悪い決算で利益が出ませんでしたという場合、『私は努力したのですが、なぜかこうなってしまったのです。』ということは通りません。
経営者は自分の意思で、売上を上げたり、経費を下げたり、工夫を凝らしたりすることが出来ます。」
以前稲盛さんの話を聞いく機会がありましたが、その時決算書について話をしてくれました。
出張などに出る時は厚い決算書を持ち、電車などの中でそれを見るようにしているそうです。
数字を見ていると、「何をしているんだ」とか「良くやっているな」とその部門の人の顔が頭に浮かんで来るそうです。
常に数字を見る習慣の大切さも話していました。
売上を極大に、経費を極小に
昨夜、8月の京セラフィロソフィ勉強会をしました。
今回で16回目になります。
今回は「売上を極大に、経費を極小に」「日々採算をつくる」「健全資産の原則を貫く」「能力を未来進行形でとらえる」の4項目を勉強しました。
いつものように、これから4日間はその内容について書きたいと思います。
今日は「売上を極大に、経費を極小に」についてです。
稲盛さんは京セラフィロソフィ―に次のように書いています。
「経営とは非常にシンプルなもので、その基本はいかにして売上を大きくし、いかにして使う経費を小さくするかということに尽きます。
利益とはその差であって、結果として出てくるものにすぎません。
したがって私たちはいつも売上をより大きくすること、経費をより小さくすることを考えていればよいのです。
ですから[原材料費]は[総生産]の何パーセントでなければならない、とか[販促費]はこれ位必要だといった常識や固定概念にとらわれてはなりません。
売上を極大、経費を極小のための努力を日々創意工夫をこらしながら粘り強く続けていきことが大切なのです。」
この「売上を極大に、経費を極小に」と言われると、皆さんはそんなの「当り前だ」と言うと思います。
昔から「入るを量って、出を制する」と言われます。
でも、言うは易くて行うのは難いのです。
よくある話ですが、高い売上目標の数字を立て、それに見合う経費も計上した計画を立てました。
結果は「売上目標」は達成できませんでした。でも「経費の目標」だけは達成しました。
勿論、利益は減です。
このように売上アップの目標を立てると当り前のようにその分の経費も計上することが間違いなのです。
売上アップの計画を立てても、経費はそのまま変えないというのが本当だと稲盛さんは言います。
その時、その時、必要に応じて必要なモノを買えばいい。
泥縄式でいいと言います。
本来は泥縄式は、行き当たりばったりで準備が出来ていないという悪い意味で使われますが、この場合はこの考え方がいいと言います。
私の経験でも、計画を立て準備万端で始めてから、買う必要のなかったモノが沢山出てきたということがありました。
このいい典型です。
また稲盛さんはこの「売上を極大にし、経費を極小に」を追求していく中で、京セラ独特の「アメーバ経営」を生み出しました。
「アメーバ経営」というのは、売上から原材料などを差し引いた「付加価値」を社員の全労働時間で割り、1時間当たりいくらの「付加価値」を作り上げたのか、その指標で経営することです。
この「アメーバ経営」は稲盛さんがJAL再建する時、京セラフィロシフィと共に持ち込んで再建しているものです。
「売上増⇒経費増」という「常識」を否定することが大切なのです。
「エゴ」と「パッション」
昨日のブログでジェームス・スキナ―氏のセミナー事業の事を書きました。
今日はお知らせが来たセミナー案内にいいことが書かれていたのでご紹介します。
以下は案内書に書いてある内容の要点です。
「豊かな人生を手に入れる2つの鍵があります。
その2つの鍵は「エゴ」と「パッション」です。
人は所有欲があり、私のお金、私の家、私の服、その他に地位、名誉、能力等もあります。
所有すること自体は悪くないのですが、問題は所有することで自分の不足感を埋めようとしたり、不安を埋めようとしたり、自尊心を満たそうとすることです。
そうすることで、自分のモノを攻撃された時に、自分が攻撃されたと勘違いしてしまいます。
この勘違いは「エゴ」によるもので、成長を妨げる大きな原因でです。
成長する人は『自分の』という部分に執着しません。
所有する事で満たされた感情は、同時に失うことへの巨大な恐怖を生みます。
所有することで安定の欲求を満たせば、手放すことへの恐怖が生まれます。
また「エゴ」と密接なのは欲です。
欲にも2つの種類があります。
1つは「エゴ」から出た、自分の欠乏を埋める為の欲
もう1つは「パッション(情熱)」です。
「パッション」は愛、貢献、成長といった欲求に基づいています。
「エゴ」は恐怖、欠乏、不安、苦しみ、迷い、疲労に満たされています。
「パッション」は喜び、好奇心、愛、創造、共有、インスピレーション等尽きないエネルギーに満たされています。」
ここに書かれている「エゴ」は「利己心」、また、「パッション」は「利他行」に置き換えることが出来ます。
自分でない人のために行う行為は『熱い思い』から生まれます。
日本では大災害や政治、経済の不安などでこれからどうなるかという時代に、「エゴ」「利己心」また「パッション」『利他行」について考えてみる時なのかもしれません。
そして改めて自分の原点に帰ってみることが大切な気がします。
セミナー
最近ある会社からセミナー受講案内書が送られてきました。
ジェームス・スキナー氏のセミナーです。
ジェームス・スキナー氏は「7つの習慣」という本の著者のコヴィ―博士から、日本での事業の承認を受け、本の翻訳と共にセミナー事業を展開しました。
その後その事業を売却し億万長者になりました。
自身も「成功への9ステップ」を書きベストセラーになりました。
彼は「7つの習慣」での事業と同様に「成功への9ステップ」のセミナーをも展開しています。
このセミナーは参加費が10万円以上し、その他に宿泊費が別にかかります。
会場は千葉の鴨川のホテルなので、交通費など入れると20万円近くになります。
それでも今までに1万人以上が受講したそうです。
実は私も4~5年前に参加しました。
150名以上集まり、3泊4日のハードでユニークなセミナーでした。
朝の9時から夜中の2時ころまで延々と続きます。
確かにいいセミナーでした。
今回の案内は、そのジェームス・スキナー氏の新しいセミナーで「人生の飛躍」という題名で開催されます。
6泊7日のロングランのセミナーです。
会費は1人40~100万円もします。
私は参加するつもりはありませんが、改めてこんなに高い料金でも100人以上の人が参加するのだと驚いています。
ただ、セミナーとはその価格に比例して内容が充実しているという話は聞いたことがあります。
「成功への9ステップ」のセミナーを体験した人の中には、熱烈なジェームス・スキナーファンになったり、事業がうまく行ったという口コミから1万人以上の人が受講したのでしょう。
今回の「人生の飛躍」も前のセミナーがベースにあるのでしょう。
一般的にはセミナー料金は高くても5万円以内という「常識」を超える今回のセミナー。
セミナー案内をもらって改めてこの集客のシステムに興味を持ちました。
「番屋で遊ぼう会」
先週の木曜日に番屋で遊んできました。
新現役ネットという団体の夏の企画でした。
その新現役ネットの会員の1人が銭函の浜に「番屋」を持っています。
「番屋」とは「漁師番屋」で本来は漁師が漁の準備をするための小屋です。
ただこの「番屋」は個人が自分で楽しむ為に作った「男の隠れ家」的なものです。
作ったAさんは元公務員で定年後は民間の会社で働いていますが、自分の夢であった「番屋」を自前で作ったのです。
銭函の駅から歩いて7~8分位のところで、函館本線の線路と海の間の狭いところに建っています。
「銭函グルメ館」と称する番屋は「グルメ館」だからといって営業しているわけではありません。
平均月に1度程度、Aさんが気が向けば開いてくれ、気の合った仲間同士が飲み食いするところです。
そしてそこではAさんが自分で作る漁師料理を食べさせてくれます。
夕方の6時頃から始まるということで5時30分頃に行くと20ℓの生ビールが用意されており好き勝手に飲んで、海を見ながら料理が出来るのを待ちます。
まずは海の傍まで突き出したベランダの上でホッケのチャンチャン焼き、ホッキ貝のバター焼き、サンマ焼き、イカ焼きが続きます。
海の沖を見るときれいな夕日が見えます。
1時間ほど経つと今度は「番屋」の中に入り、舟盛りの刺身を肴にシャンペンで改めて乾杯。
海鮮焼きそば、たこ飯などが続きもう食べきれないほどの料理が続きました。
自分のするべき仕事を成し遂げ、自分の好きな生き方
料理などは準備からAさんが1人でこなし、大変のお世話になりました。
今度何かの特別の仲間が集まっての飲み会にはまたこの「銭函グルメ館」を使わしていただきたいと思っています。




守成は創業より難し
昨日は2代目経営者のことを書きました。
今日もその続きになります。
昨日のブログでは、2代目は心して経営しなければならないと言う内容のものを書きました。
創業者と2代目に関する言葉として、「守成は創業より難し」という言葉があります。
これは中国の古典の貞観政要に書かれていて、徳川家康も読んだと言われています。
現在も多くの経営者が読んでいます。
「守成は創業より難し」の意味は、その事業を守り抜く2代目、3代目は創業者より大変で、難しいということを述べています。
創業者は無手勝流であっても自分の思い通りの会社を作り上げることが出来ます。
部下はみな自分の子供のように思えます。
少し位我儘を言っても許してもらえます。
そして創業者として尊敬されます。
一方2代目はその創業者と常に比べられる立場です。
少しでも業績が悪くなれば非難されます。
そのような会社を維持し、発展させるには本当に実力が必要になってきます。
もしかしたら創業者以上に人格的にも高いものが求められます。
宋文州さんのメールマガジンに書かれていた場面があります。
ある会社の創業記念パーティ時、真っ先に年老いた創業者がヨロヨロした足元でお客様のところを1人1人お酌して回った時、宋さんは感激したそうです。
それに比べ後継者は・・・・。
そして宋さんはこう書いています。
「創業の苦難を乗り越えた人の身に染みついた感謝は、言葉が少なくてもその表情や体から滲みだすのです。
2代目は経営がもっと良くなることがあってもこの感謝の気持ちはないと思います。
恐怖と苦難と闘って僅かな勝算にかけて生き残ったことを通じて、人は感謝の本当の意味を知るのです。
『怖かった!』、『助かった!』という呟きの後にだいたい『ありがとう。』と続くのです。」
2代目3代目が会社を守成するのは大変です。
その2代目3代目に抜けがちなのは、その本当の「ありがとう」ではないかと思っています。
創業者は会社を作り、山あり谷ありの中、苦しかったことや辛かったこと、そして「怖かったこと」の経験の中、生き延びた時、「お陰様で」とか「ありがとう」という言葉が心の底から湧き出てきたのです。
そのような経験から発せられる「ありがとう」の言葉は大変重いもので人に感動を与えます。
お店でモノを買って「ありがとう」と言う言葉とは、その重みが全然違います。
うわべだけの言葉は、時として薄っぺらく感じます。
後継者は自分で意識して、早くに本当の苦労をするべきでしょう。
その中から這い上がり、心から発せられる言葉を使えるようになれれば、創業者を超える経営者になれるのではないでしょうか。
2代目経営者
新しく経営者になるには起業してなる場合と、引き継いでなる場合があります。
専務や常務が先代の社長を引き継ぐ場合は、長年先代社長と共に経営をしてきているので、経営を知っています。
この場合は特に問題はありません
社長の息子が引き継ぐ場合、特に経営経験が無い中で引く次ぐ時、いろいろ問題があります。
経営の基本はその会社の根幹を早く学ぶことです。
普通、最初から社長として入るより、部長とか常務とかの肩書きで入るのが多いと思います。
入社した時大事なことは、最初は現場に入って朝から晩まで誰よりも働くことです。
そして謙虚な気持ちで仕事をすることです。
なまじっか管理部門に入れたりすると「頭でっかち」になってしまいます。
稲盛和夫さんも2代目社長の心得として「まず親の代からの経営幹部たちに仁義を切りなさい」といいます。
一席設けて「至りませんが、また社長の器ではないかもしれませんが、将来社長のお役割を務めさせていただきます。」とお願いし、1人1人にお酒を注いで回るのです。
この謙虚さが無いと誰からも見向きされなくなります。
稲盛さんは「爺殺し」という言葉も使います。
「爺殺し」とは気軽に年配の方にすり寄っていって、いろいろ相談を持ちかける人のことです。
人間というものは不思議なもので、厚かましくヒョイヒョイやってくると、最初は無礼だと思っていても、その内アドバイスするようになるということです。
このテクニックも謙虚さが無いと使えません。
私も父の会社に入社した時心したことです。
過去の私の仕事の中で、それなりに実績が出た時はほとんどの場合、年配の良き相談者なりパートナーがいました。
ある意味、私も「爺殺し」が上手かったのかもしれません。
親から引き継いだ2代目3代目経営者が一番ダメなのは、現場の仕事を軽く見て、経験程度で終わり、外部活動にいそしむことです。
人脈を磨くと称して、青年会議所やライオンズクラブ、ロータリークラブに入る人が多いです。
そこに入っても遊びを覚えるだけ。
そして、なまじっか良き人脈や情報を得ると、それにこだわり仕事を進めてしまおうとします。
でも、そのほとんどが失敗します。
現場が良く分からず、なかなか皆から信頼を得られない時、ついスタンドプレーをしてみたくなります。
でも、経営の原理原則・基礎が出来ていない時に、小手先で経営するような事を知ってしまうと、取り返しがつかなくなります。
2代目3代目は最初からある程度の地位を与えられます。
自分も周りも将来は社長になると思っています。
だからこそ、何度も書きます「謙虚さ」が大切です。
「謙のみ福を受く」の言葉通りです。
「お金を使わない」ということ
昨日は「生き金」と「死に金」について書きました。
今日もお金に関して書きます。
人は何かの目的でお金を貯めます。
「10万円貯めて一眼レフカメラを買おう」と思い、1年後貯まった10万円でカメラを買います。
でも、カメラを買った後はお金が残っていませんから、何も買えません。
もしも10万円のカメラを買わず、今度は20万円のパソコンを買おうとしてまた貯めると、結果20万円のパソコンでも、10万円のカメラでもどちらもでも買うことが出来るようになります。
また、何も買わず50万円のバイクを買おうとまたお金を貯めると、50万円までのモノなら何でも買えるようになります。
私が何を言いたいかというと、「お金を貯めるということ」は「可能性を広げる」ということです。
お金が入ればすぐ使う。少し溜まったらまたすぐ使う。
このようなことをしていては自分の可能性を潰しているようなものです。
ある経営者は起業時に自己資金を現金で積み立てていったそうです。
預金するのでなく、現金を手元に置いたのです。
不用心ですが、お金を実際に確認して、お金を貯めているということを意識すると共に、お金があるが故の誘惑に惑わされない意志の強さも育てたのです。
その起業した会社は上場までしました。
以前にも紹介した話ですが、「貧乏人」と「普通の人」と「お金持ち」の考え方です。
グラスにジュースが入れられた時、「貧乏人」は満杯になる前に飲み干してしまいます。
「普通の人」は満杯になって飲み干します。
「金持ちの人」は満杯になっても飲まず、溢れ出るジュースだけを飲みます。
だからいつもグラスにはジュースが満たされています。
お金があるということは可能性を持っていることです。
1千万円あれば、「いつでも海外旅行に行ける」「大概の車ならいつでも買えるぞ」「高いレストランだって行けるぞ」と考えることが出来ます。
でもしません。
お金持ちの年配者がお金を使わないのは、将来への不安心理と共に、いつまでも「出来る」という可能性を保持したいという同じ心理からきているのかもしれませんね。
「生き金」と「死に金」
お盆休みの間は兄弟たちが集まり、86歳の母を中心に話をしたり、食事をして過ごしました。
そして小さい頃のことを色々思い出されることがあります。
父は私が生まれる前から起業し、会社を経営していました。
私が小学生の頃には、既に家にテレビがあり、車もありました。
よそから見ればリッチな生活をしているかと思わますが、実際は家に風呂はなく、銭湯通い。
食事も質素で、時々朝食につく卵は1人1つあたらず、2人で1個。それでよく喧嘩をしました。
毎日朝食には目玉焼きを食べていた友人がうらやましかったことを覚えています。
バナナやチョコレートも年に1回か2回しか食べれませんでした。
私と同年代の人達の中には、同じような経験をした人が多かったと思います。
父のお金の使い方を思い返してみると、無駄なお金は使わず、会社でも家庭でも質素だったようです。
子供たちにも無駄なお金は使わせませんでした。
でも仕事で「ここ一番」という時は思い切って使いました。
お金には「生き金」と「死に金」があります。
そのお金を使うことで大きな効果が生まれる使い方が「生き金」
無駄に、単に欲望だけで使われるのが「死に金」です。
経営者にはこの金銭感覚がしっかりしていないと儲かった利益も使い方を間違えてしまいます。
会社強化のために内部留保を厚くし、将来の投資に備えるか、それとも税金支払うのが嫌だからと言って無駄な経費を使ってしまうのか。
この違いで10年後が違います。
ある人から聞いた話ですが、その人のお姉さんは欲しがっていたモノを買ったとたんにそれに興味を示さず、買ったモノを包装紙に包んだままにして置いて置くといいます。
これはそのモノが欲しかったというより、欲しいと思った欲望に負けて、買うという目的が達成した時、興味が無くなってしまのでしょう。
斉藤一人さんは、お金について言っています。
「『お金が好きだ。好きだ。』と言っている人がお金が入るとすぐモノを買うのは、お金が好きなのではなく、モノが好きであったり、買うことそのものが好きなだけ。
そのような人は、本当はお金が好きではないのです。
本当にお金が好きなら、お金を使ったりしません。
お金持ちがお金持ちなのは、お金が好きでお金を使わないからです。」
何も使わなければ単なるケチですが、本当のお金の価値を知っていれば、「生き金」として使えるでしょう。
私の父が質素な生活の中、テレビを買ったり、車を買ったりしてのは、新しいことに興味があり、テレビで新しい情報を手に入れる、車でお客様サービスをすると、それは「生き金」だったのでしょう。
盆休みに思い返したことでした。
お盆
今日は8月16日。
私の盆休みも今日までです。
札幌の温度は急に下がり、今日の最高気温の予想が24度です。
やはり「盆が過ぎると秋」というのが本当のようです。
盆にはご先祖様が家に戻ると言われます。
それなのに昔からの習慣で、札幌ではお墓参りをします。
ご先祖様を迎えに行く行為なのでしょうか。
東京の人に「お盆にお墓参りする」と話すと不思議がられませす。
東京の方では迎え火を焚きご先祖様をお迎えします。
北海道では迎え火を焚きませんが、お墓参りをすることで直接お迎えに行くことになるのでしょか。
今年は父の新盆でした。
その為、お参りに来ていただいたお客様も多かったです。
父のことを話すことも多く、その為か、ここ2晩、父の夢を見ました。
どんな夢か覚えていないのですが、父を身近に感じられます。
お盆は家族そろって亡くなったご先祖様のことを思い出し、一緒に過ごす時なのかもしれません。
この4日間ほとんど外出しないでいましたが、そんな盆休みも良かったと思っています。
政治家と官僚
お盆休みで家にいることが多いと、孫と遊ぶことと本や新聞を読むことがになります。
新聞では毎日、新しい総理選出問題が取り上げられます。
私はあまり政治的な話をするのは好きではありませんが、その仕組みには以前から疑問を持っています。
それは政治家と官僚との関係です。
民主党は政権をとる前、官僚依存脱却、政治主導と言っていました。
それで結果、政治主導は取れませんでした。
自民党時代の安倍さんから菅さんまで1年おきくらいで首相が変わり、閣僚はそれ以上に変わっています。
その中で本当に政治主導が取られていたらどうなっていたでしょうか。
首相が変わるたびに考え方、方針が変わっています。
そのような状況の中、現実問題として政治家に代わって官僚が行政間や外国との関係を維持しながら行政を仕切ってきていました。
首相がこう度々変われば仕切らざるを得ない状況になってしまうのではないでしょうか。
外国政府高官にとっても政治家とのパイプも作れず、より官僚頼りにならざるを得なくなっています。
アメリカは大統領制をとっていますので、高級官僚は大統領と共に変わります。
アメリカの職業公務員が昇進出来るのは課長までです。
行政・政治の仕組みが日本と違います。
同じ内閣制をとるイギリスにおいては首相に任期はありません。
議会の信任があり、選挙のたびに国民の支持が得られれば、いつまででも続けることは可能です。
私は政治の仕組みはあまり詳しくはないのでここまでにしますが、どちらにしても首相が簡単に変わる日本の政治の流れこそが強固な官僚体制を作った原因だと私は思っています。
その官僚体制は地方の行政組織まで浸透し、各地域でも上席の公務員は自己保身に向かっているきらいもあります。
では「公僕」という言葉は遠い昔に忘れられてしまったのでしょうか。
そうではなく国民のために、市民のためにと思っている公務員の人達は多いと思います。
私の知人の公務員も市民活動にも熱心です。
ですからここでは一般の公務員と高級官僚とは一緒に論じるつもりはありません。
ただ、何時になったら本来の政治主導の日本になるのか、もはやそれは無理なのか、最近は少し諦めの心境になっています。
ネットでの評価
昨夜は久しぶりに兄弟妹で食事会をしました。
妹たち家族がお盆に合わせて来てくれ、兄夫婦も一緒になっての宴会でした。
宴会をしたのは、自分達のホテルではなく、ネットで調べた料理店です。
ネットでモノを調べることが出来るということはとても便利ですが、逆にその評価が簡単にされ公表されるという恐ろしさもあります。
料理の格付けとしてはミシュランの星付けが有名です。
権威付けされたところが評価することで、その信用性が高くなります。
もう一つ信用が高いのは知人からの口コミでしょう。
概ね知人紹介はそれなりに納得出来るものです。
私が最初にネットなどで評価される経験と言えば「旅の窓口(現楽天トラベル)」でした。
ネットでホテルに居ながら集客が出来る便利さと、その評価がネットによって広がるという恐ろしさを体験しました。
ネットは顔が見えない分本当のことなのか、陥れる為のものなのか見ている人には判断できません。
ただ書かれていることが本当だと思ってしまいがちです。
私は支配人をしている時、こまめにお客様評価を見て、その都度丁寧な返事をすることに心がけました。
今も楽天トラベルを見てホテルを予約する時は、やはりそのホテル評価を見てしまいます。
見る時、ホテルからの返事も見ます。
その返事の内容がいつも同じ文面ばかり使っているのをときどき目にします。
それによって「このホテルはお客様の声に真剣に取り組んでいないな」と思ってしまいます。
ホテル支配人の顔が見えない分、お客様もホテルの回答の仕方だけで評価してしまうことがあります。
これは心しておかなければならないことです。
ネット上のお客様とホテルとの受け答えを、別のところから第三者のお客様が評価するのです。
便利になった社会だからこそ見えないところまで気を配る配慮が求められます
企業の公的負担
最近のテレビ、新聞の報道では、菅総理がやっと退陣すると同時に増税論議が再燃しています。
その中で気になるのは企業に対する課税です。
やはり会社経営にをしている者として増税は辛いです。
「税金も経費の一部としてとらえなさい」と稲盛和夫さんは言われます。
その税金で日本人の生活が成り立っています。
それではその企業の公的負担はどの程度あるのでしょうか?
昨年の6月に経済産業省がまとめた資料によると、日本の企業の負担率は50.4%でアメリカやイギリスより高いのです。
アメリカは42.8%、イギリス41.6%、オランダは31%になっています。
日本の公的負担の内訳は国税と社会保険料の事業主負担あわせて31.8%、地方税が18.6%です。
また法人税負担の純益に占める比率(実負担率)を見ると、アメリカは27.8%、イギリスは22.4%に対して日本は35.5%です。
こうして見ると日本の企業が果たしている貢献度はそれなりに評価されていいモノだと思っています。
このような高率負担をしている企業に対しての増税論議が生まれることが、企業経営する側からしてみると残念な気がします。
経営者はリスクを覚悟し起業し、自分の全てを掛けてその事業に打ち込み利益を出します。
経営者は経営の全責任を負いますので、借入にしても個人保証を求められ、もしかすると全ての財産を没収されます。
そのようなリスクを負ってまでも自分の夢をかなえる為に努力した結果が会社の純益です。
その汗の結晶から「経費とみなそう」と高率の公的負担をしながら頑張っているのに、それより高い負担を平気で求めるというところが納得いかないところです。
これ以上の負担が高まると、力ある企業は、「静かに」公的負担の少ない国々へシフトしていくことでしょう。
企業は生き延びる為には、あらゆる努力をします。
タイなどの国々ではそのような企業の誘致を積極的にはかっています。
金の卵を産むガチョウからもっと卵を産まそうとして、殺してしまう行為に似ている思いがします。
経費の節減
朝、会社に車で行き、地下の駐車場に入っていくと、ここ最近駐車場の照明が消えています。
朝、担当の人が来て、駐車場のシャッターを開けるのですが、照明を点けてくれません。
以前はそうでなかったのです。
仕方がなくヘッドライトを点け進みます。
昨日担当者に、暗くて「事故る」可能性もあるので照明をつけてくれるよう依頼しました。
担当者は「経費節減のため8時からしか照明は点けません」と言いました。私はいつも7時頃行きます。
私は「事故る」可能性を考えると、電気代の方が安いよと言ったのですが拒否されました。
彼の経費節減をするという信念は強く、それはいいことでもあり、私はそれ以上言えませんでした。
私の父は現役の時、経費の節減について口うるさく、その伝統は会社の中に残っています。
電気については勿論、裏紙利用、長電話禁止等ありました。
ただ目に付く経費については口うるさいかったのですが、時間等の見えない経費には少し無頓着だったかもしれません。
照明についても無駄な照明は消した方がいいのです。電力不足の時の今は特に大切なことでしょう。
でも、サービス業等お客様商売のところでは、それも限度があると思います。
あるホテルの社長は電気料金節約のために、日中お客様が少ない時ロビーの照明を3分の1程度にするように指示しています。
ですからそのホテルに行くと、常に暗いイメージしかありません。
「ホテルは少し暗い方がゴージャスに見える」とその社長は言いますが、それならそれなりの照明計画に基づいて設置されれば良かったのですが、お客様の目には単に「節約」としか見えません。
参考までに以前私が調べた電気料に関しての数字を教えします。
事務所などの照明で使われている長い蛍光灯は1台40Wが2本付いています。
5年ほど前に北海道電力で調べまたところ、電気使用料は蛍光灯1台当たり1時間使用して1円30銭でした。
10台設置されているところでしたら、13円、10時間で130円。
これを「高い」と思うか「安い」と思うかです。
経費の節減と営業効率、商品アピール等を考え、経営トップが総合的に判断することは大事です。
原発と日本の将来
日は少し皆さんに賛同いただけそうも無いお話を書きます。
昨日ある会合がありその時、原発問題が話題になりました。
原発廃棄し、自然エネルギーに転換していかなければという話が出ました。
今原発に対して大変敏感になり、世論は原発廃棄の方向に向かっています。
私は孫が3人います。
子供や孫のことを考えると、安心と安全を確保してやらなければなりません。
今回の原発事故で被害がこれ以上広がらないよう願っています。
と同時に孫たちが成長した時、日本がどうなっているかを心配します。
安心と安全と一緒に話すことが多いですが、安心と安全は違うものです。
国として安全を追求すれば際限なく追求出来ます。
それと共にコストがかかります。
コストがかかればその負担を強いられて、豊かで安心な生活が出来なくなります。
時として安心と安全は反比例の状態になることもあります。
原発問題を考える時、私もその危険性は十分認識しています。
その原発を今廃棄した場合、それに変わるモノとしては、火力発電になるでしょう。
太陽光・風力・水力といってもすぐには原発に変わることは出来ません。
火力発電に頼るとなると大量の石油や天然ガスを輸入しなければなりません。
読売新聞に載っていた中部電力の試算では、原発を火力発電に変えると1日当たり2~3億円の負担増になるとのことです。
それは年間で700億以上の石油や液化天然ガスを輸入しなければなりません。
それが全国の電力会社で起これば何千億円の輸入増になります。
法政大学小峰教授によると、「日本の貿易収支は30年以上黒字でしたが、震災後の4、5月は赤字になりました。
ただし所得収支は依然として大幅な黒字でしたので、経常収支としては黒字でした。
しかしその黒字幅は2月は約1兆3千億円から5月には4千億円まで減少しました。
今後原発の代替のために石油や天然ガスの輸入が増えると、それが経常収支の赤字を促進する可能性があります。」
経常収支が赤字になるということは日本全体が資金不足になり、一層の国債発行に結び付いてゆくことになります。
貿易で成り立っている日本の経常収支が赤字に転向するということは、日本経済の衰退になります。
会社倒産し、失業者が増え、生活は厳しいものになります。
それは安全を手に入れましたが、安心な生活を失ったことになります。
今、一度冷静になって原発問題を考える必要があると思います。
数年前秋葉原通り魔事件がありました。
あの時マスコミが取り上げ、問題になったのは「タガ―ナイフ」でした。
マスコミの論調で、その「タガ―ナイフ」があの事件を起こしたような風潮になったことを覚えています。
実際はナイフが悪かったのではなく、それを使った男が悪いのです。
その男の背景に問題があったのです。
原発も危険なものです。
ナイフと危険の度合いが違うと叱られるかもしれませんが、問題が発生すると人はどうしても「モノ」に目が行きがちです。
本質は別にあります。
今日は否定されることを覚悟して、もっと冷静にも一度原発問題を考えてみたいと思い、あえて書きました。
2人の社長
昨日ある会社の会長が私の事務所に顔を出してくれました。
そこで出た話は、身近にいる社長たちの話でした。
その中で、それなりに実績を上げている2人の社長の話が中心となりました。
A社長は積極的経営です。仕事の関連、人的つながりを生かし、数多くの会社、事業を展開しています。
コンサルタント会社との繋がりも強く、そのアドバイスも積極的に受け入れています。
会社の数、その事業数は私達では掌握出来ない数です。
また、その展開のスピードも早いです。
良しとして作る時は、アッという間に作ります。
逆に見込みがないと思えば、即座に撤収し躊躇しません。
利益もしっかり出し、売上も100億に近いでしょう。
一方B社長は慎重な人なので、確実な経営をしています。
3社を経営し、それぞれでしっかり利益を出しています。
3社の売上はA社長ほどでありませんが、利益率は大変高いです。
新規事業はしたいのですが、慎重過ぎてなかなか上手く展開できません。
A社長の会社もB社長の会社も売上も高く、しっかり利益も出しています。
私達で話したのは、どちらの社長の会社がこれから、さらに伸びるだろうかということでした。
結論としては、どちらも経営としてのやり方が違うだけで、どちらも将来も伸びていくだろういうことです。
ダメになる時はやはりその社長の気力が落ちた時でしょう。
その時誰にバトンタッチするか。
あるメールマガジンに建築家の安藤忠雄さんの話が紹介されていました。
経営を車の運転になぞらえて書いています。
概略は
「車の運転はノロノロ運転していたら、つい眠くなってぶつかってしまいます。
でも時速150キロで走っていれば居眠り運転なんかしないでしょう。
これは大企業でも、小さな会社でも同じで、リーダーは目標を明確にして、それに向けて可能な限り全力疾走していれば、緊張感があるからそんなに失敗しないと思うんです。
やっぱり居眠りができるような中途半端な走り方では駄目です。」
先ほどの経営論議についても、経営のやり方は色々ありますが、最終的には社長によって決まるのです。
最終的には、真剣さがなければ、今いくらいい会社もこれから衰退して行きます。
安藤さんの言葉は、稲盛和夫さんが言っている「強烈な願望を心に抱く」「誰にも負けない努力をする」「経営は強い意志出来ます」に通じるところがあると思います。
初心忘れるべからず
皆さんは、ご自分が社会に出て初めてお会いしたお客様、営業して初めて受注したお客様を覚えていますか?
また、起業して初めてのお客様は覚えていますか?
ある本の中であるフリーライターのことが書かれていました。
彼は毎月4~6本の連続原稿を抱えて大変忙しいそうです。
その内のA社の1本だけは安価であるにもかかわらず、どんなに忙しい時でも、最優先で取り組むようにしているそうです。
その理由が述べられていました。
「独立した時、丸1年間仕事がなく満足な生活が出来ませんでした。
そんな時、信用も実績もまるでない私に定期の仕事をくれたのがそのA社でした。
A社からの仕事がなかったら今の自分はなかった。それを思うと恩を仇で返すような事だけはしたくはありません。
たとえ安価であっても、誠心誠意仕事をやらせていただこうと思っています。」
この心構えは素晴らしいですね。
この話を聞いて感心しても、実際に自分達はどうでしょうか?
「初心忘れるべからず」
良く言われる言葉ですが、なかなか実行できないものです。
苦労した時に助けていただいた人や会社に対して、今でも感謝の念を持ってその仕事を続けているでしょうか。
これは起業して成功する人と失敗する人の分岐点でもあります。
多くの支援者・応援者を作る人。
その場限りの応対で、振り向けば支援・応援してくれる人が誰もいない人。
お客様を大切にし信頼という財産を築きあげる人
その時の損得で生きる人
自ずと成功者と失敗者は分かります。
私の場合は新入社員で銀行に入り、営業で最初に定期預金をいただいた方の事はすっかり忘れています。
若い頃の私は、全く成っていませんでした。
やっと20年前くらいからは、最初のお客様のことは良く覚えています。
今はその方との仕事のつながりは特にはありませんが、それでも少しその人に関係するような事があれば、お願いしたり、お客様を紹介したりします。
些細なことですが、それが自分なりの筋の通し方だと思っています。
食と旅
テレビを見ていつも思うのは、皆さんも同じだと思いますが、食に関することではないでしょうか。
そしてテレビや雑誌の特集で一番人気があるのは食べ物に関するものでしょう。
次が旅特集。
この旅と食べ物はつながりがあります。
旅をしてその土地の美味しいものを食べるのが旅をする目的という人もいるでしょう。
今はほとんど旅はしませんが、私も若い頃は暇さえあれば色々なところへ行きました。
行き先をガイドブックで見て観光名所や景色を調べそこへ行くのが目的でした。
貧乏だったこともあり、何かを食べたいとはほとんど考えませんでした。
旅先で食べると言えば、立ち蕎麦だったり、パンをかじったり、時にはラーメン屋や定食屋で贅沢するぐらいでした。
旅をして帰ってくるとチョット空しさを感じることがありました。
それは1人旅が多かったせいもあり、旅先での人との触れ合いがなかったことです。
その土地の生活を知り、人とふれあうには、その土地のものを食べれるべきでした。
そうは思っても、また旅に行く時も貧乏旅行でしたので、やはり美味しモノは食べなかったです。
食べ物と言えば、世界で一番人気がある日本食と言えば寿司でしょう。
多くの外国にも寿司屋が増えています。
でも昔は違いました。
生の魚を食べる日本人はゲテモノ喰いと見られていました。
私の学生時代、欧米人から日本人は「醤油臭い」と嫌われるという話を聞いたことがあります。
そのにおいを消すため、欧米人と会う時は牛乳を飲んで臭いを消しなさいと何かに書いていました。
同じようなことでが日本でもありました。
韓国の人がホテルに宿泊するとキムチの臭いがひどく、部屋の換気が大変だったと言われました。
当時はまだ、多くの日本人にはキムチは未知の食べ物でした。
それが経済の発展と共に、外国へ行く日本人が増え、また日本を訪問する外国人も増える中で、食に対する興味が高まりました。
そしてその国の独特な食べ物に対する理解も深まりました。
その国の食べ物を知るということは、その国民を身近に感じることにもつながります。
日本人はまだ若干欧米志向がありますが、それでもアジアに対しての興味が深くなったのは、食に対する理解があったからだと思います。
タイのトムヤンクン、ベトナムのフォー等食べてその国行きたいと思うのかもしれません。
食と旅が人々の交流を生むきっかけになっています。
日本の食事の内容が万国から取り入れているのを見ると、日本は世界でも一番外国に対して開かれている国ではないかと思います。
日本に住む中国の知人に以前聞いたことですが、彼の毎日の食事はほとんどが中華料理だと言っていました。
日本人のように、朝はアメリカンブレックファースト、昼食は餃子定食を食べ、夜はワインとスパゲティというよな食事はしません。
その中国人も多くの人が海外旅行を楽しむようになっています。
これから中国も旅と食を通じて開かれる国になって行くのかもしれません。
新盆
今週末から旧盆が始まります。
今度は父の新盆になります。
お盆に少し早いですが、今日お坊さんが来てお参りをしてくれます。
お盆の時期は忙しそうで、早々と来るのでしょう。
お盆には人が集まります。兄弟、親戚達が集まり、お墓や仏前で昔話をしたりします。
そう意味でお盆はご先祖様が子孫同士が仲良くするために戻ってくる日なのだと思っています。
今、私の家には娘と孫、お盆には妹たち一家5名、その後には息子達一家が来ます。
私は母と同居しているので皆母に会いに来るのです。
人には故郷が懐かしいという気持ちがあります。
若い頃、その地を離れて外国などに行くと、ホームシックにかかったりします。
故郷が恋しい、家が恋しいと思うのでしょうが、本当は母親が恋しいのだと思います。
ホームシックというよりマザーシックなのかもしれません。
今来ている孫達を見ていても、父親が仕事のため東京にいて、ここにいなくても、母親がいれば何の問題も無く暮らしています。
そのかわり母親が見えなくなると不安がいっぱいです。
やはり母親が全てであり、故郷なのです。
確か武田鉄矢の「母に捧げるバラード」の中にも出てくる言葉です。
今私は故郷に暮らし、仕事をし、母と一緒です。
日常はそれが当り前と思っていますが、考えてみると幸せなことです。
これから、お坊さんが来ますので仏壇を掃除します。家内に言われましたので。
「札幌オフィスプレイス」
昨日は私が運営しているレンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」のビール会でした。
入居している人達とOBの人も参加しての会でした。
それぞれ入居している人同士、仕事内容は違うのですが皆さん仲がいいです。
食べたり飲んだりしながら、互いに情報交換します。
新しい事業を始めた人の話を聞き、またロシアに機械輸出している人は、最近の円高のため、円が上がったり下がったりの報道を聞くたびに一喜一憂するという様子を話します。
そのロシア貿易をしている人は、半年前までレンタルオフィスにいたのですが、業務拡大のため出て、札幌駅近くに事務所を構えています。
その彼から1つの提案がありました。
私の住んでいる琴似でロシアとの交流拠点を作らないかという話です。
ロシアと日本の間には北方領土問題があり、正式な国交はありません。
その為、隣国なのに中国や韓国のような盛んな経済交流はありません。
新千歳空港からウラジオストックまで50分位の近さなのに、飛行機料金は8万円もするそうです。
まだまだ遠い国のような感があります。
北海道は日本の中では北国ですが、ロシア、ウラジオストックの人から見ると南の国です。
ロシア人から見れば魅力的なところです。
そのような中で札幌市内にロシアと交流の拠点を作るのは貿易や観光の仕事をする人にとっては魅力的な話ではないでしょうか。
この札幌オフィスプレイスはさまざまな思いを抱いた人たちの集まるところです。
その中で何か新しく大きな仕事が生まれる可能性も秘めています。
私もこれからが楽しみです。
男性と女性の性向
毎日ブログを書いていると、書いたことを再度書くような事があるかもしれません。そんな時は申し訳ありません。
今回もそうかもしれません。
ここ数日の間に起業を志す男性と女性にお会いしました。
この2人ばかりでないのですが、男性と女性の考え方の違いを改めて考えました。
大分以前、ホテルの支配人をしている頃、取引業者を訪問した時に教えていただいたことがあります。
その会社の総務社員はほとんどが女性で男性部長が管理しています。
その部長の話です。
女性に仕事をしてもらう時、何をいつまでに、どのようにするかを教えると、女性はその仕事を真面目に一心不乱に深く取り組む性向があります。
男性にそのような仕事をさせると、根気が続かず、タバコを飲んだり、他のことをしたりして能率が上がりません。
今度は女性にあるプロジェクトを任そうと方向を教え、それを取りまとめるように指示すると、1つのことにこだわり、1つずつ指示を仰いできてなかなか計画がまとまりません。
一方男性は漠然としながらも、その全体像をつかみ、色々な人に会い、資料を調べ、大まかな計画を作り上げることが出来ます。
男性は浅くても全体を広く見渡すのが得手。
女性は決められたことを深く追求するのが得手という性向があります。
勿論、全ての男性・女性がそうだというのではありません、その傾向があると言っているのです。
起業する時はこの二つの性向が求められます。
男性は出来るだけ集中力を持って完璧にこなすことに心がけ、女性はなるべく広く全体像をつかみ、ポイントがどこにあるかを知れるように努力すると、起業の成功は高くなります。
自分にそれが出来なければ補佐役を付けておくのも方法でしょう。
最近、起業する人とお話しすると、そんな思いをします。
ワールドカフェ
昨夜は私のオフィスで「北のユニバーサルデザイン協議会(NUDA)」のミーティングがありました。
1人1000円以上の飲物・食べ物をそれぞれが持ちこんで、お酒を飲みながらのミーティングでした。
それぞれが思い思いに買ってきたので、同じものが重なったりしますが、ワイン、ビール、日本酒、紹興酒などのお酒は美味しく飲みました。
そのミーティングの中で、ある人が「ワールドカフェ」が今流行っているという話をしました。
「ワールドカフェ」とは1995年にアメリカのアニータ・ブラウン氏とデイビッド・アイザックス氏によって開発・提唱されました。
知識や知恵は、会議室の中で生まれるのではなく、人々がオープンに会話を行い、自由にネットワークを築くことのできる「カフェ」のような空間で生まれるという考えです。
「ワールドカフェ」ではお菓子や飲み物が用意され、食べながら飲みながらディスカッションするのです。
その運営方法は、グループごとにコーディネーターがいて進行して行きます。
飲み食いしながらというと、営業担当者がお得意先を食事や飲みに誘ったりするのは、飲み食いすることで心理的に解放される、本音の話が出来ることを期待して設けられているようです。
人同士は食べることで、緊張関係が無くなると言われます。
このようなことを考えていけば、昨日の私たちのミーティングも「ワールドカフェ」と言えるのかもしれません。
アイディアを出すための手法はブレーンストーミングやKJ法など昔から数多くありました。
インターネットで見ると良く分からないものもあります。
例えば
・10分間で3つ以上のアイデアを引き出す「Scamper」
・技術的な視点からアイデアを引き出す「USITオペレータ」
・多様な観点でアイデアを引き出す「6観点リスト」等
グループでアイディアを出す作業をすることの一番の効用は、アイディアを出すことも大事ですが、それより皆が同じ方向へ向かって作業をすることそのものが重要だと思います。
そこには一体感が生まれ、そしてその結果に対する共同の責任感も生まれます。
会社で飲み会をすることもただ飲むのでなく、そこで会社の問題点を話し合い、その対策を考える場にしていくことも広い意味の「ワールドカフェ」なのではないでしょうか。
コミュニケーションの専門家からは「酒飲みのたわごと」と言われるかもしれませんが、「飲みケーション」は大事なコミュニケーションだと思います。
「楽しむ」という言葉
もうそろそろ夏の甲子園が始まります。
北海道からも2校が出場します。
その1校の選手がテレビのインタービューに応えている時、「オヤッ!」と思った言葉がありました。
甲子園出場を果たしたその選手は「勝っていきたいと思いますが、それ以上に思いっきり楽しみたいと思います。」と話していました。
私は「楽しみたい」という言葉に反応したのです。
ここしばらく「アスリート」とか、「達人」についてのブログを書いていたからでしょうか、この「楽しみたい」という言葉に違和感を覚えました。
「リラックスした気持ちで試合に臨め」という思いから、指導者がそう話したのかもしれません。
しかし、勝負の世界は何よりも勝つという意識以外の意識を持った時はもう既に勝てないはずです。
以前、有名なへアーメイクの人の講演で聞いた話です。
その人は大きな大会に何度も挑戦したけれど、優勝には届かず、その度に一生懸命練習をして次の大会に臨みました。
それでも夢は叶わなかったそうです。
ある時、人から「本当に優勝する気が無いから優勝できない」と指摘され気付きました。
その時に気付いたのは執念の有無です。
一生懸命頑張ろうと思っていたけれど、何としてでも優勝するのだという執念が無かったのが原因だと気付きました。
勝ちにこだわった、絶対優勝するのだという執念を持ち続け、翌年優勝することが出来ました。
この度の女子ワールドカップに優勝した、「なでしこ」も優勝にこだわったと聞いています。
最近は「頑張る」より「楽しむ」という方が時代に合っているのでしょうか。
癒しを求める風潮の中、頑張っている人に「そう気張るなよ」と評する雰囲気があるように思います。
癒しもいいのですが、「頑張る時はどんなことがあっても頑張る」という切り替えが大切です。
「ON・OFF」「メリ・ハリ」「けじめ」を持つことです。
先ほどの北海道を代表する高校、どこまで頑張れるか注目して応援します。
論語の言葉
昨日は私が運営するレンタルオフィスに3社が新しく入りました。
私のところのような小さなレンタルオフィスに同時に3社入るのは珍しいことです。
起業を志す人が増えているのでしょうか。
私の事務所には起業を志す人や、既に起業した人が顔を出してくれます。
起業の目的はそれぞれです。
障害者を支援しようとして起業する人、自分の得意を伸ばしたい人、お金を稼ぎたい人さまざまです。
最初はお金を稼ぐことが目的でもいいです。
でもそれだけでは、つまらなくなり、ある程度まで行けば満足し、仕事をする意欲がなくなってしまいます。
やはり仕事をする意味、意義を考えて生きていかなければ、死ぬ時、自分の頭をなでて死ねないのではないでしょうか。
(「自分の頭をなでて死にたい」とは懸命に仕事をして、誰にも認められなくても自分だけは満足して死にたいという松下幸之助さんの言葉)
先日浅田次郎さんの本を読んでいましたら論語の言葉が紹介されていました。
「富を貴(たつと)きとは、それ人の欲するところなり。其の道を以(もつ)てこれを得ざれば、処(お)らざるなり。」
金持ちや高い身分には誰でも憧れる。だが、自分の信念とは違った方法でお金持ちになったり、身分が高くなったりするのであれば、決してそういうものになりたくない、という意味です
続いて
「貧と賎とは、これ人の悪(に)くむ所なり。其の道を以てこれを得ざれば、去らざるなり」
これは誰だって貧乏は嫌だし、卑しい階級に生まれ育つのは嫌だ。しかし自分自身の信念を持って、自分がこれは正しいと思って行った結果、自分が貧乏をしていたり、卑しい階級に貶められたりしているのであれば、あえてその場所を去る必要はない、去るべきでないという意味です。
自分の信念を貫く大切さを説いています。
ここに書かれている「道」とは人としての道のことです。
人は時として自分の欲望から「其の道」を外れてしまうことが多いです。
偉そうに書いていますが、私も信念を持つことの大切さは分かっても、それを持ち続けるのは困難な時もあります。
さまざまな誘惑や欲望に遭遇した時、この孔子の言葉は萎えそうになる自分の心を支えれくれそうです。
この言葉も私の「銘肝録」に記入しました。
人間の修行
昨日はアスリートについて書きました。
アスリートもそれを究めていくと達人と言われるでしょう。
大分以前に紹介しました、江戸時代に書かれた「葉隠」という本の中に、達人と言われる人が述べた言葉がありました。
それを紹介します。
ある剣の達人が老後に行ったことがある。
「人間の修行には段階がある。
修行の初期ではものにならず、自分でも下手と思い、人も下手と思う。その分ではまだ用には立たない。
中の位はまだ用には立たないが、自分の下手さも、他人の不十分さも分かるようになる。
上の段になると、全てを会得して自信も出くるし、人が褒めてくれるのを喜び、他人の不十分さを嘆く。こうなればものの用に立つ。
その上の上の上になると知らん顔をしている。そして人も上手だと見ることが出来る。だいたいの者がこの段階までである。
その上にもう一段飛び越えると、言うに言えない境地が広がっている。その道は深く入れば入るほど、つい果てるともない無限の世界だと分かって、これで良しという思いもなくなり、自慢心も起こさず、卑下する心もなく進んで行く道である。」
この中では「人間の修行」と書いていますが、江戸時代の武士が書いた本ですから剣の修行に近いイメージでしょう。
しかし、現代ではスポーツ、芸術、職人の技術を磨くということばかりでなく、「人間としての成長」そのものを述べているととらえることが出来るでしょう。
稲盛さんも言われている、人として「魂を磨く」に通じるものを感じます。
私はこの葉隠れの文を読んだ時、その上の上の上という人がいて、またそれを飛び越えている人がいるということに感心しました。
同時に、「それに比べてわたしは・・・」と思ってしまいまうのです。
全てのことは奥が深いということです。
上っ面だけですべて分かっているつもりになっている自分への諌めです。
ただ、達人にはなれなくてもその達人を目指す生き方こそが大切なのかもしれませんね。
アスリートにとっての「利他の心」
最近私は「利他」と「利己」について書くことが多いです。
勿論、稲盛さんの考えを受けてのことだと思います。
先日、スポーツニュースを見ていて気付いたことがあります。
それは、運動選手は「利他」など考えるのだろうかと。
優れたアスリートは勝つために懸命な努力をして相手を倒し、勝ち進みます。
苦しい練習も勝つために耐え抜きます。
そこに「利他の心」というものはあるのでしょうか。
勝つために自分を中心に考え、もしかしたら相手のミスを喜ぶような気持ちが生まれたりしないのでしょうか。
「利己な心」だけで占められてしまわないのでしょうか。
どのような事をしてでも相手に勝つという気持ちが、間違えるとドーピングなどの不正行為をしてしまうかもしれません。
自分が一番強い、一番すごいのだという気持ちはアスリートにとって必要な心構えです。
そこには「利他の心」を持つということは無理なのかもしれません。
そのようなアスリートが現役を引退し、一般社会で生活する時、ものすごいギャップを感じるのではないかと思います。
自分は優れた人間だ、特別だという思いで一般社会に入って行くと、はじき出されてしまいます。
私はアスリートの世界は詳しくなく、よく分かりませんが、協会や支援団体の周りの人達がアフタフォローをしてあげなければ、本人がその間違いに気付くことは難しいと思います。
一般社会に出ると、ただの普通の人で、そこで別の結果を出さなければ淘汰されてしまいます。
「利己」から「利他」へ心を切り替えてあげるのです。
考え方や道しるべをしっかり教えてあげれば、努力することを知っている人達だけに、一般社会でも成果を出すことが出来ると思います。
以前に何かで読んだ話です。
ゴルフのタイガー・ウッズは試合の時、最終ホールで相手がそのパットを入れつと、自分に追いつく状況でも「入れ!」と念じるそうです。
普通は「入るな!」と念じるはずです。
それを「入れ!」と念じるのは、自分が精神的に強くなれるからだそうです。
相手のミスで得る勝利は、本当に自分が強いわけでない。
自分が強くなるためには相手のパットを入れてもらい、それ以上に自分が頑張ることで本当の強さになるのだと言うのです。
余程自分に自信のある証拠でしょう。
そんなタイガー・ウッズも女性問題を起こして苦しみ、成績も低迷いています。
人は現在の環境によって心の持ち方が違ってきます。
稲盛さんの経営の勉強会「盛和塾」に柔道家の山下泰裕さんや元日本サッカー監督岡田武史さんも入っています。
新しいスポーツの指導者には教育者としての使命もあるのでしょう。
夫婦の形
私は今、母親と同居しています。
母は病弱でそばに誰かがいなければならない状態です。
その為、常に妻が付き添っています。
ですから、妻はほとんど外出が出来ないので、夜に付添いさんが来てからスーパーに行くのが楽しみの様です。
そんな妻にはいつも感謝ばかりです。
先日永六輔さんの夫婦に関する言葉をネット上で見つけました。
10代の夫婦は「セックス夫婦」
20代の夫婦は「愛で結ばれる夫婦」
30代の夫婦は「努力して夫婦」
40代の夫婦は「我慢の夫婦」
50代の夫婦は「あきらめの夫婦」
60代の夫婦は「感謝の夫婦」
夫婦は年とともに形が変わっていきます。
子供が生まれる前、生まれた時、子供を育てている時、子供が巣立った時、それぞれ夫婦の関係が違ってきます。
いつまでも愛で結ばれてばかりでいれません。
私も振り返ってみればそうでしたが常に、夫婦っていいモノだという思いはありました。
永さんの言葉の中に「信頼の夫婦」と言うのがあってもいいかと思います。
私はいま60歳を超えましたので「感謝の夫婦」になります。
確かに感謝の日々です。
良く熟年離婚と言われることがあります。
男性が定年を迎える頃に離婚を決意するのは50代、ちょうど「あきらめの夫婦」の時です。
もう少し頑張れば「感謝の夫婦」になったかもしれません。
この永六輔さんの言葉を妻に話したら、「あなたは40歳代の時は我慢し、50歳の時はあきらめていたの?」と言われました。
「アッ不味い!」と思い、決してそうではなく、常に感謝していましたと、弁明はしましたが、余計なことを言ってってしまったと後悔。
これからも感謝の日々だが続くと思います。
コヴィ―博士と稲盛さん
昨日「プレジデント」という雑誌を買いました。
今回は「7つの習慣」を書いたコヴィ―博士と稲盛和夫さんの対談、そして「運をつかむ習慣」という標題になっていました。
この本は発売日に近くの本屋に行ったのですが売り切れており、少し遠くの本屋に行きました。
いつもだと数冊あるはずなのですが、1冊だけ残っていて、かろうじて買えました。
今回の「プレジデント」は、運をつかむという標題もいいのですが、それよりコヴィー博士と稲盛さんとの対談の方に興味がありました。
コヴィ―博士は「7つの習慣」、稲盛さんは「経営の12カ条」を基本思考に据えてお話ししています。
2人とも「素晴らしい人格」を持つことの重要性を説いています。
その中で興味ある話しがありました。
コヴィ―博士の話です。
「アメリカ建国200年の時、200年間で成功した人々を調査しました。
すると、最初の150年と後の50年で大きな違いがあることに気が付いたのです。
最初の150年に成功した人達に特徴的だったのは、誠実、謙虚、勇気、勤勉といういわば人格主義でした。
後の50年では、もっと表面的なスキルやテクニックが重んじられていました。
私は人格主義こそ重要だと考えています。」
また、稲盛さんは
JAL再建のためにフィロソフィ―を共鳴してもらおうと、幹部を集めて徹底的にリーダー教育を行ったこと。
また、立派な考え方や人格が無ければ、いくら戦略や手段、方法を考えてもいい結果は生まれまないことを言っています。
その話を聞いてコヴィ―博士は「エンパワーメントの好例です」と言います。
エンパワーメントとは「現場の裁量を拡大し、自主的な意思決定を促すとともに、行動を支援すること。現場の責任感とモチベーションが高まる。」ことです。
私はいつも稲盛さんの本を読んだり、話を聞いたりしていますがエンパワーメントとは気付きませんでした。
確かに稲盛さんの言っていることの結果は、まさにエンパワーメント作りそのものだと思いました。
ただ、それはあくまでも結果であって、先に経営者の人格形成があっての流れです。
今回の「プレジデント」には「運をつかむ習慣」の中で、京都大学の藤井教授が「利他の心を持つ人」はツイている人生を送り、「利己の心を持つ人」はツキから見放されるということを論理的に解明しています。
これも興味ある内容です。
宣伝するわけではありませんが、ぜひ読まれるといいですよ。
会社を起業した時
昨日起業した人が来社され、今後の会社運営についてお話をしました。
以前にも書いたと思うのですが、起業する時、1人でするか別の人と組んでするかという選択肢があります。
1人より2人で起業するメリットは高いです。
互いに夢を語ることでモチベーションを維持し、励まし合いながら目的に向かって仕事を遂行していくことが出来ます。
ただ、その時に注意することは、その立場と責任分野の明確化です。
社長が2人いてはダメです。
社長、専務と名称を分けても時として専務の方が声が大きいとお客様から逆転して見られます。
また社長がその立場を充分意識しないと、専務に頼り切ってしまうこともあります。
そうなると社内でも益々混乱してきます。
お金と人事権だけは社長が最終管轄すること、これがポイントです。
次に大切なのは、連携でしょう。
任せっ放しではダメです。責任分野以外だからという気持ちで立ち入らないのもダメです。
社長は最終責任を取らなければならない立場です。
遠慮することはないはずなのですが、口を出さないということが見受けられます。
よく言われる言葉ですが、「ホウ、レン、ソウ、ダ」です。
報告、連絡、相談、打合せです。
ついでながら書きますと、会社に必要なのはその他に「ポパイ」です。
ポリシー、パワー、イノベーション。
これらを合わせて「ポパイのホウレンソウ」です。
改めて書きますが、会社経営する時、連携、特にトップ同士の連携が重要になってきます。
分かっているだろうでは決してうまくは行きません。
また起業した時は、あせらず確実に仕事を進めることです。
効率を求めては基礎が出来ません。
確実に進めれば1+1=2になります。
あせると1×1=1なのです。
最初は1つずつ「足し算」のように仕事を進め、実力が出てきた時こそ「掛け算」のように加速度を付けます。
トップ同士が連携しないと1-1=0になってしまいます。
昨日来られた方々はこの点はしっかりしていそうなので上手く行くはずです。
その会社の成功支援はこれからも続けていく予定です。
物忘れ
私は最近物忘れがひどくなって言います。
先ほど聞いた相手の名前が忘れてしまったりします。
もうそれは物忘れと言うよりボケかと思ってしまいます。
以前に脳トレーニンングの道具を買って試しまいたが、すぐ飽きてしましました。
昨日の新聞にその物忘れのことが書いてありました。
ある調査によると40~60代の男女600人のうち「物忘れが多くなった」と答えた人は8割を超えています。
また、私と同じように脳トレーニングの商品を買った人が25%、まだ持っていないが興味があるという人も27%いるという結果が出ています。
その新聞には、物忘れを防ぎ、脳の活性化をさせる方法が紹介されていました。
1.家事や雑用を進んでこなす。――これにより脳の前頭葉を鍛え、思考の持続力を養う。
2.目を良く動かし、耳からの情報を取る。――パソコンなどの画面から離れ、脳を刺激する。
3.仕事に時間の制約を設け、集中力を高める。――ダラダラ続けていると発想が切り替えられない。
4.活動を広げ「余計なこと」からヒントを得る。――ワンパターンの生活から脱し、発想を豊かに。
5.「報告書」をまとめ「ブログを積極的に書く。――情報を消化し、脳に刻み込む訓練をする。記憶力を高める。
6.意識して長い話しをする。単語だけで済ませない。――前頭葉を使って試行を組み立てる力を鍛える。
7.過度な運動と「腹八分目」を心掛ける。――脳の大敵である生活習慣病に用心する。
私はこの中で5番目の「ブログを書く」というのに目が行きました。
毎日ブログを書いていることで、少しは脳の活性化に役立っているのかと思います。
「ブログを毎日書くぞ」と思い始めてから今月末でちょうど1年になります。
この他にも今挑戦していることがあります。
500ページの少し難解な本に挑戦しています。
昔したようにノートを作り、理解度を高めています。
人は年と共に安易な方に流れていきます。
自分に「無理を掛ける」ことが無ければ退化していきます。
脳が退化しないように、チョットした背伸びがいいようです。
ハンカチを使う
今、日本中が大震災による原子力発電の停止等の影響で節電意識が高まっています。
クールビズ、スーパークールビズを着る人、扇子や団扇の利用者が増えているそうです。
またエアコンをあまり使わず、扇風機を使おうと思う人が電気店に殺到しているという報道もあります。
節電は省エネになり、無駄を省くことになります。
節電、省エネに関して、これを改善すればと思うことが最近ありました。
それはハンカチです。
トイレに行くと手を洗います。
洗い終わるとハンカチで手を拭きます。
でも今のトイレ内には回転式のタオルや、ペーパータオルが設置されています。
最近はエアータオルというものがあります。
ハンカチを持ってこない人が多いせいなのか、それらを設置しているトイレが多くなっています。
それらはすべて電気を使い、木材資源を使います。
ハンカチを使えば必要ないものです。
「マイ箸を持ちましょう」というより「ハンカチを持ちましょう」の方がより省エネ・省資源効果が高いです。
それなのに最近の若いはハンカチを持っていないようです。
彼らはペーパータオルもエアータオルも設置されていないところではトイレットペーパーで拭いています。
ひどい時は手を洗わず出ていきます。
ハンカチは西洋人(古い言い方ですが)にとっては鼻をかむ時に使います。
ティッシュペーパーはあまり使わないと言われています。
それに比べ日本人は如何にふんだんにティッシュペーパーを使っていることか。
私も鼻をかむばかりでなく、テーブルが汚れたらティッシュペーパーで拭き、汗が出てきたら傍にあるティシュペーパーで拭きます。
それらはすべてハンカチや布巾、タオルで済ませば必要ないのです。
知らず知らずのうちに無駄使いをしてきたのです。
節電、省エネ、省資源と言われている今こそ、もう一度生活を見直して、ハンカチ持参、身の回りに布巾やタオルを置くようにしませんか?
それに気を付けるだけで違います。
最近は素敵な柄のハンカチやタオルがあります。日本手ぬぐいも伝統的なものから可愛いものもあります。
それらを楽しみながら始めましょう。
優しいということ
昨日のお昼12時で、テレビの放送がアナログからデジタルに変更されました。
アナログとデジタルの仕組みは分かりませんが、画面がきれいになりました。
この告知キャンペーンは8年ほど前から「耳にタコが出来るほど」見たり聞いたりして来ました。
それでも「テレビ受信者支援サンター」には昨日1日で9万件以上の問い合わせがあったそうです。
私はこの数に驚くとともに興味を持ちました。
それは「なぜ今頃に問い合わせをしたり、苦情を言ったりするの?」という思いからです。
電話をした人は、テレビを見ていてテレビの画面が映らなくなって電話をしたのだと思います。
それなら今まで「耳タコ」になるくらい、テレビでデジタル移行を告知しているのを見ているのに、なぜ今頃になってあわてたり、苦情を言うのでしょうか。
そのために9万件の電話を受ける為のオペレーターを配置しなければなりません。
是非ともその理由を聞きたいものだと思います。
人は本来、自分の生活、テリトリーを守るために敏感になります。それは自己防衛本能から来ます。
テレビのことと同一のレベルで書くことではないのですが、人間は将来自分の生活やテリトリー、極端に言えば命に関係するには必然的に敏感にならざるを得ないと思います。
そして将来起きることが予想される問題に対して予め対応するようになっています。
いまさらでもないのですが、イソップ童話の「アリとキリギリス」に例えられる通りです。
私の住んでいる北海道は寒い冬の準備は秋には済ませています。
昔は石炭を石炭庫に一冬分用意し、冬に食べる野菜や魚は保存食にし、漬けものも漬けます。
それをしなければ死んでしまうからです。当り前のことです。
自己防衛のため、その備えは誰の責任でもなく自己責任で行います。
今の日本は色々な意味で優しくなっています。それに甘えて、本来自分がするべきことさえ放棄しているような風潮が見受けられます。
会社を経営の場合それは即倒産です。
社長は先を見て常に手を打ち、最善の方法を考え対処します。
死に物狂いで対応しまます。
経営状態がいいように見える会社でも、「対応力がある」社長と、「その日暮らし」の社長との差は1~2年で結果は出てきます。
世の中には制度融資とか、補助金だとかの優しい制度があり、そればかりを頼るとやはり会社の力は落ちてきます。
優しい世の中だからこそ、強く生きるのは難しいですが、これからは強く生きる会社しか残って行けないのです。
苦しい時は私の背中を見なさい
今は日本中「なでしこジャパン」の話で持ちきりです。
テレビでも色々な番組で取り上げられています。。
私もつい見入ってしまいます。
その中で「私の背中を見て!」と澤選手が言ったことが紹介されていました。
その話を聞いて感動した人もいるでしょう。
この言葉は今回のワールドカップで言われた言葉でなく、北京五輪の時に言われた言葉です。
試合の最中に宮間選手が走りきれなくなった時に、「苦しい時は私の背中を見なさい」と澤選手にに声をかけられ、最後まで背中を見て走ったといいます。
余程、自分に自信が無いと言えない言葉です。
また同時にリーダーとしての自負心を感じさせます。
過去、背中を例えにして言われてきた言葉が多いあります。
「子は親の背中を見て育つ」という言葉のその1つです。
子供は親から言葉で言われるより、親の行動を見て判断します。
昔は子供も多く、また親たちは忙しく、子供を構う暇はありませんでした。
必然的に子供は自分の回り、環境を見て育つしかありません。
親を尊敬する人として見たり、また時には反面教師としてその生き方を見て育ちました。
職人の世界では「背中で教える」とも言います。
昔の職人は弟子に手取り足とり教えたりしませんでした。
弟子たちはその職人の仕事のしぐさ、たち振る舞いを見て、技を盗み、勉強し、自分のものにしてゆきました。
今は言葉が多過ぎるのかもしれません。
言われないで感じる方が学びは多いと思います。
昔、私は「背中に哀愁を漂わせた男」にあこがれたこともありました。
寡黙でいて、全ての苦しみや、悲しみ、寂しさをじっとお胸に収めている、映画に出てくる高倉健さんの姿です。
今の私は、語り過ぎるきらいがあり、哀愁とは無縁のところにいます。
そう意味では寂しさを感じています。
値決めは経営
先日開かれた「京セラフィロソフィ勉強会」の続きです。
今日は経営についての話になります。
今まで、京セラフィロソフィに書かれていることは、「考え方」、「生き方」についての記述が多かったのですが、この項からは経営について述べられています。
今日は「値決めは経営である」についてです。
この事はとても大切なことで、稲盛さんは要文と説明を36ページにわたって説明しています。
「経営の死命を制するのは値決めです。値決めにあたっては、利幅を少なくして大量に売るのか、それとも少量であっても利幅を多く取るのか、その価格設定は無段階でいくらでもあると言えます。
どれほどの利幅を取った時に、どれだけの量が売れるのか、またどれだけの利益が出るのかということを予測するのは非常に難しいことですが、自分の製品の価値を正確に認識したうえで、量と利幅との積が極大値になる一点を求めることです。
その点はまた、お客さまにとっても京セラにとっても、共にハッピーである値でなければなりません。
この一点を求めて値決めは熟慮を重ねて行われなければならないのです。」
価格はお客様との交渉で決まります。
お客様は少しでも安くと思い、自分達は少しでも高く売りたいと思います。
合い見積もりを出しながらお客様は値引き交渉をします。
それをそのまま受けては利益が出ません。
だからと言って自社の価格を押し通せば他社から買ってしまいます。
その為、値決めはお客様が喜んで買ってくれる最高の値段を決めることなのです。
そして、それは経営トップの仕事なのです。
営業が何の知恵も働かせず、お客様にただ言われるまま、他社より安い値段を提示して注文を取ってくることでは、経営は成り立ちません。
また、お客様が喜んで買っていくれる最高の値段で決めても、その値段で経営はうまく行くかというと、そうとは限りません。
問題は、売値が決まったら、その中でどうやって利益を生み出していくのかということです。
既に決まった売値で利益を出せるかどうかは、今度は製造の責任になります。
稲盛さんはこの事をご自分の著書「稲盛和夫の実学」でも述べていますが、「売価還元方式で原価を決める」という「売値ありき」という考えをしなければなりません。
京セラでは「原価+利益=売値」という原価主義はとっていないそうです。
稲盛さんは京セラという会社は下請け会社だと言います。
これほど大きな会社でも、大手の電機会社の部品を注文生産して作ります。
その時、先方から言われる価格で決められることが多いのです。
「原価主義」の考えでは利益が出ません。
「売価還元方式で原価を決める」ためには経費の見直し、材料の値下げ交渉、それでも限界があればVA(価値分析)を行い、設計そのものから見直し、利益が出るような設計に変えていくこともします。
ただ単に材料をたたいて買ってコストダウンを図ればいいという甘い考え方では限界が来ます。
そのように値決めは営業から製造、設計までつながるからこそ、「値決めは社長の仕事なのだ」と稲盛さんは言うのです。
この「値決めは経営」という言葉は、改めて経営の深さを知らされた言葉でした。
反省ある人生を送る
今日も「京セラフィロソフィ勉強会」で学んだことを書きます。
今日は第62項「反省ある人生をおくる」についてです。
この事について稲盛さんは次のように書いています。
「自分自身を高めようとするなら、日々の判断や行為が果たして『人間として正しいものであるかどうか、奢(おご)り驕(たか)ぶりが無いかどうか』を常に謙虚に厳しく反省し、自らを戒めていかなければなりません。
本来の自分にたち返って、『そんな汚いことをするな』『そんな卑怯な振る舞いはするな』と反省を繰り返していると、間違いをしなくなるのです。
忙しい日々を送っている私たちは、つい自分を見失いがちですが、そうならない為にも、意識して反省をする習慣をつけなければなりません。
そうすることによって、自分の欠点を直し、自らを高めることが出来るのです。」
「反省」と言うと「改めて言われるまでも無い」と思われる方もいるかと思います。
また、「そんなきれいごとを言っても」と思うかもしれません。
そのような思いに対しても稲盛さんは次のように書いています。
「われわれ人間は肉体を持って生まれてきたために、自らの肉体を維持しなければなりません。
毎日食事を取り、水を飲み、睡眠を取らなければ生きていけないのです。
それゆえに、人間はもともと己を守ろうとする心、すなわち利己的で欲望に満ちた心を持っているわけです。
本来この肉体を維持していくために、神様がくれた心なのです。
だから何も手入れしないでそのまま放っておけば、人間の心は必ず利己的で強欲なものに満ち満ちてしまいます。
そこでこの項目にある『反省』ということが大変大事になってきます。」
「偉そうなことをお話ししていますけれども、この私とて、まだまだ不完全な人間なのです。すきあらば悪さをする、自分の欲望を満たそうとする、普通の人間です。
ですから当然、間違いも起こします。それでも悪いことは悪いこととし、常に反省を繰り返し、今より悪くならないように努力しようと思っています。」と言っています。
ただ、反省をしても、自分を卑下したり、傷を付けるようなことをしてはいけません。
反省をして自分がダメだったと思ったら「神様御免なさい!」と言ってお仕舞にするくらいでいいのです。
中国に「謙のみ福を受く」という古い言葉があるそうです。
心の手入れをするという意味でも反省することは大切です。
小善は大悪に似たり
昨日に引き続き、京セラフィロソフィ―勉強会で学んだことを紹介します。
「小善は大悪に似たり」です。
これについて稲盛さんは次のように書いています。
「人間関係の基本は、愛情を持って接することにあります。しかし、それはもう盲目の愛であったり、溺愛であってはなりません。
上司と部下の関係でも、信念も無く部下に迎合する上司は、一見愛情深いように見えますが、結果として部下をダメにしていきます。これを小善と言います。
『小善は大悪に似たり』と言われますが、表面的な愛情は相手を不幸にします。
逆に信念を持って厳しく指導する上司は、煙たいかもしれませんが、長い目で見れば部下を大きく成長させることになります。これが大善です。
真の愛情とは、どうであることが相手にとって本当に良いのかを厳しく見極めることなのです。」
「小善は大悪に似たり」という言葉は仏教からきた言葉だそうです。
稲盛さんは私達に語る時は「小善は大悪に似たり。大善は非情に似たり。」と言います。
私はこの言葉を聞いた時、昔の私の体験を思い出しました。
北海道帯広市で銀行員だった頃、営業の部門は定期預金を集めてくるのが主たる業務でした。
彼らは得意先係と言いました。
当時の支店長は大変厳しい人で、担当者に毎月3000万円の預金を集めるのがノルマとして与えました。
毎日100万円集める勘定になります。そう簡単ではありません。
ボーナスが出る時期は定期預金獲得の一番の時です。
官庁にボーナスが支給された日は、夕方から官舎を定期預金依頼をして回ります。
その日は支店長は、7時8時頃に帰ってくる得意先係を入口のところで待ち、100万円の定期預金を獲得しているかチェックしました。
獲得していなかった人はもう一度営業に行かせます。
8時以降に官舎を廻ると、「夜遅い!常識を考えろ!」と怒られることもあります。
水を掛けられることもあります。
最後には100万円獲得できなくても、10時頃になってやっと入れてくれます。
当時の得意先係は皆、大変苦しい思いをしました。
そこで鍛えられた得意先たちはその後、転勤していった先でものすごい活躍をし、支店長までなった人が多かったです。
そんな厳しい支店長でしたが、私には私的に大変お世話になった人でもありました。
私が結婚した時、いろいろなことがあり、結婚式が出来ませんでした。
そんな私達を哀れに思ったのか、支店長が指示し、銀行の人達が企画して銀行の2階の会議室で結婚式をしてくれました。
急に「明日の日曜日に結婚式をする」と言われ、なにも用意していない私達は、家内にスーツを買い、私は普段のスーツで出席しました。
銀行の2階の窓を暗幕で覆い、キャンドルサービスから始まりました。
出席者は50名ほどの銀行員の仲間だけです。
私達がひな壇に行くと、そこには支店長と次長が座っています。
皆の前で婚姻届に私達二人がサインをし、支店長と次長が保証人のサインをしてくれました。
その結婚式のことは今でも忘れません。
仕事では大変厳しい支店長も、仕事を離れればとても愛情深い人でありました。
「小善は大悪に似たり。大善は非情に似たり。」という言葉は私にとって身にしみている言葉です。
純粋な心で人生を歩む
昨夜は毎月行われる京セラフィロシフィ勉強会でした。
今回もまたその内容を紹介していきます。
今日ご紹介するのは「純粋な心で人生を歩む」についてです。
この項目で稲盛さんは次のように書いています。
「古代インドのサンスクリット語で『偉大な人物の行動の成功は、その行動の手段によるよりも、その人の心の純粋さによる』と言うある聖人の言葉が残されています。
純粋な心とは言い換えれば、物ごとを行う時の動機が純粋であり、私心がないということと同じです。
またそれは、人間として何が正しいのかということとも共通しています。
純粋な心を身につけることによって、私達は間違いのない人生を歩んで行くことが出来ます。
純粋で私心のない心、すなわち人間として高い見識や見解を判断基準として物事を決め、人生を歩めば、その人の人生に大きな潤いと素晴らしい結果をもたらすのです。」
続けて稲盛さんはこれを経営に当てはめて書いています。
「持っている技術、あるいは経営手法、経営計画、そのような物が優れているから成功するのではなく、経営者の心の純粋さが成功をもたらすことになります。」
この心の純粋さが大切だという考えは前に紹介しました「動機善なりや、私心なかりしか」ということにもつながっています。
この項目で二宮尊徳の生き方を紹介しています。
ご存じのように二宮尊徳は鍬1丁、鋤1丁で貧しい農村を豊かな農村に変えてゆきました。
彼は人を評価するのに、その人の動機が善であるかどうかを判断基準にしたと、内村鑑三が書いた「代表的日本人』に書かれています。
時として人は「純粋な心」と言うと、「そんなきれいごとを言ったって」と思う人がいます。
勿論、人は利己の塊です。
でも、だからこそ、それを押さえる為の努力をし、心を磨くのです。
「純粋な心」や「動機善なりや」という思いを追求していくからこそ、1段1段と心がステージアップしてゆくのではないでしょうか。
心を整える
今朝は朝食会と称しての勉強会がありました。
今回は「ヒプノセラピー」についての話です。
ヒプノセラピーをご存じでしょうか?
これは「催眠療法」といわれ、催眠誘導という手法を使って、普段閉じている潜在意識の扉を開け、潜在意識の中に注意を向けていく心理療法です。
始めに「ヒプノセラピー」の説明を受け、その後実際に「ヒプノセラピー」の体験をしました。
最初は自分の自己暗示の強さを知るために、両目を閉じ、両手を出し、右手に重い辞書を置き、左にヘリウムの入った風船を結びつけるイメージをしていきます。
そうすると、その内に実際に右手が下がり、左手が上がっていくのです。
人によってその差はありますが、実際に両手の位置が違ってきました。
次は紙に大きな十字を書き、その上に糸のついた5円玉を右手でぶら下げ、十字が交差する付近に5円玉を空中で静止させます。
その後、頭の中で上下と唱え、目を上下させるのです。
その内に5円玉が上下に揺れ出します。
右左と意識しても同じように起きます。
参加者の中にはびっくりする位揺れている人がいました。
最後に本番の「睡眠療法」の体験です。
講師の声を素直に聞き、身体を順々にリラックスさせてゆきます。
そして、講師の声によって自分のイメージを膨らませてゆきます。
今日は朝日が出る海岸をイメージしました。
その内に催眠状態に入ってゆきます。
15分ほどの体験でしたが、それでも頭がすっきりして、気力も湧いたような気がします。
これは自然な音、例えば川のせせらぎ、風のそよぐ音、波の音などをBGMにして1人でも出来るそうです。
仕事の中で、「精神的に疲れたかな」とか、思い悩んだ時にしてみると効果がありそうです。
講師の話では21日間、毎日朝起きたばかりの時、寝る前にすると効果があると言います。
ただその時に使ってはいけないのは否定的な言葉です。
肯定的な言葉、そしてing(進行)的な言葉を使うことがより効果的になります。
イメージするモノは人によって違うそうです。海の他に花園、山もいいそうです。
男性は「たき火」などが合う人もいるとのこと。
私は「たき火」が好きなので今度はこれでしてみようと思います。
自分の「心を整える」方法として勉強になりました。
なでしこジャパン
今朝起きたら「なでしこジャパン」が世界一になっていました。
昨夜から気になっていたのですが、寝てしまいました。
それでも気になって少し早く起きました。
今朝は感動の朝です。
背の高さ等の身体的ハンディがあるのを乗り越えての勝利です。
スポーツでは身体的ハンディはその結果に決定的な差が出ます。
アメリカとの身長差は平均で10cm位あり、また、アメリカは世界一の実力があると言われていたので、戦う前から日本不利と予想する人もいました。
前にも書きましたが、駒大苫小牧高校が高校野球で優勝した時も感動しました。
その時も、北海道の高校は雪国なので、そのハンディーのため甲子園で勝つことは困難だと言われ、北海道の人達もそう思い込んでいました。
でもその思いを跳ね返して優勝したのです。
その後プロ野球も日本ハムが日本一になりました。
皆が超えるのが難しいと思いこんでいるハンディを、ものともせずに乗り越えて勝ち取った勝利は、その練習の努力ばかりでなく、精神的なタフさ、プラス思考の重要さを再確認させられました。
人はどうしても自己保身をする本能のため、マイナス思考をするようになっています。
だから出来ない理由を作りたがります。
それはダメだと思ってもそう考えてしまいます。
そんな時にこのようなハンディーを乗り越えての世界一になったという事実は、人の弱い心に勇気を与えてくれます。
スポーツの凄いところは、困難を乗り越え勝利を掴んだ人達の生き方が、それを見ている人に感動を与えることです。
理屈抜きの感動は「そんなの出来ないよ」という思いを打ち壊してしまう力があります。
それはどんな本を読むより影響が大きいです。
今朝は私も大きな感動と勇気をもらいました。
それにしてもすごいな「なでしこジャパン」
幸せの価値判断
ある時、AとBの2人がそれぞれラーメン店を開店しました。
開店当初はともに一生懸命に仕事をし、それなりにお客が入っていました。
それから3年後、Aは5店舗のラーメン店を展開しています。
まだまだ拡大を考えています。
一方、Bは相変わらず1店舗の店で仕事をしています。
これは1つのモデルケースとして取り上げました。
このAとBが創業したのはラーメン店ですが、それが居酒屋でも回転寿司でも同じことが起きます。
その違いの大きな要因は、簡単に言えばAとBの考え方の違いです。
Aは常に仕事のことを第一に考え、将来の自分の夢を明確にし、それを追いかけます。
Bはそれなりに仕事をしますが、自分の生活が出来ればそれで満足し、家族との生活、趣味、友人関係を大切にします。
Bがそのような仕事をするのは、Aの様な仕事ぶりが出来ず、諦めたからなのではありません。
単に分相応な生活志向なのです。
どちらの考え方も良い悪いの価値判断は出来ません。
自分が満足で出来ればそれでいいのです。
Aのような人はリスクを恐れず大きな仕事をし、店舗や雇用を増やし、税金を多く支払い、影響力が大きくなります。
Bのような人は身の丈の仕事をし、家族を守り、1市民として生活していきます。
起業を志した時、どちらの生き方を選択するか、決めておくことは大切だと思います。
間違えていけないのは、Bの人のような考えで仕事をしていたが、いつの間にかAの人のように大規模な経営が出来るようになるということはほとんどありません。
またAのような考えの人は、元々Bの人の様な生活をしたいと思いません。
A、Bどちらも自分の生活に満足すればいいのです。
一番良くないのはそこそこの努力しかしないで、他の人の成功を羨むだけでは、事業も失敗してしまいます。
そこには3毒(怒る、妬む、愚痴る)しか生まれません。
自分の幸せを「どこに置くか」ということがとても大切です。
最近、ラーメン店、居酒屋、回転寿司の流行っている店をや、逆にお客がそこそこの店に行く度に、思うことでした。
商売のコツ
私は浅田次郎さんの本が好きです。
浅田さんの本はほとんど読んだと思います。
浅田さんの本にはいい言葉が多く書かれています。
最近改めて読んだ「人は情熱が無ければ生きていけない」という本に、商売のヒントが書いてありました。
浅田さんのお父さんの言葉として紹介されています。
「なんだって早くすませちまおうとするな。手順よくやるのが一番早えんだ。」
「いっぺんにあれこれやるほどおめえは利口じゃねえ。ひとつひとつ片付けろ」
これは、仕事の基本です。
効率を求めようと短兵急に物事を進めると大事なことを忘れてしまいます。
一足飛びにしようとすると、ミスばかりが続きます。
また、地道にコツコツするばかりが仕事でないことも教えています。
「足し算をしているうちは銭は残らねえ。掛け算を覚えなければダメだ。」とも言っています。
不動産についても述べています。
「不動産の値打ちは手離れの良さ。思い立った時にすぐ売れるものが一番。いくら上等だって売れねえものは、持っていねえのと同じ。」
「土地や家は生きものじゃねえんだから、愛着なんざ持っちゃならねえ。たかがクソたれて寝る場所じゃないねえか。」
私は今まで土地に関する仕事もして来ましたので、この不動産に関する言葉は至言です。
仕事と離れ、将来も売るつもりが無ければ、愛着持てる場所を選びそこに住むのもいいでしょう。
それでも、万が一、住宅ローン返済が出来ず、売却せざるを得ない時はあります。
その時、高い価格で売れるか、安くしても売れないかは大きな違いです。
浅田さんのお父さんは商売で成功し巨額の財産を作り上げた人だそうです。
その商売の達人は自分の息子にお金を貸したり、残さなかったけれど商売のコツを教えたのです。
それが今、すごい財産になっていると浅田さんは語っています。
この言葉も私の「銘肝録」に書き入れておきました。
ビジネスでのプレゼント
私の事務所に来られる人の中で、時々プレゼントを持参する方がいます。
特別なことがあっていただくのではないので、プレゼントやお土産とは違う「心遣い」なのでしょう。
「ビジネスではない」という意思表示なのかもしれませんが、初めていただいた時は戸惑いました。
3年ほど前から、その様なことをしてくれる人が「出現」したように思います。
それまでは仕事で来られた方からモノをいただくことは、ほとんどなかったように記憶しています。
私は人からモノをいただくと、つい「何をお返しすればいいのだろう」と思ってしまいます。
モノをいただいて直ぐに返すのもオカシイし、時間がたち過ぎるのも気になります。
ただ、モノをいただくということは、決して相手に不快な気持ちは持ちません。
ビジネスで初めて人に面談する時、これはいい方法なのかもしれません。
反対に自分が誰かに手土産的に持参する時のことも考えます。
プレゼント内容は工夫することが大切です。
金額的に相手に負担を与えない程度のモノ。
選んだ理由付けのあるモノ。
選ぶ時はこの2点に気を付けた方がいいでしょう。
私も上京する時、時々お土産にしているものがあります。
近くのカナダ人が経営する店で売っているメープルシロップです。
本場のメープルシロップにこだわって、美味しいころと、価格がそれほど高くないところがいいです。
最近は別の店で売っている「山わさびの醤油漬け」とか、「ハスカップのジャム」等の北海道的なモノも選んでいます。
ただ私はプレゼントとは人に差し上げるのはいいですが、いただくのは少し「申し訳ない」という思いが起き、苦手です。
損得で考えればもらう方が嬉しいはずなのですが、不思議ですね。
ボランティア活動
昨日は「サポスポ起業家交流会」のランチ会がありました。
毎月第2水曜日12時から開かれています。
毎回スピーチがあり、また参加者の近況報告などを行います。
昨日は60歳代の起業家が行って来た、東北復興支援ボランティアの報告でした。
行く前は体力的にキツイのかと心配していたそうですが、大丈夫のようでした。
今回のボランティアは札幌市社会福祉協議会が中心となり、日本旅行が主催した3泊4日のパックツアーです。
1泊目と3泊目はフェリー泊、ボランティア活動も実質2日間というものです。
今回行った先は大槌町でヘドロの撤去が中心だったそうです。
大槌町は約15,000人の人口のうち1割に当たる1500人が死亡・行方不明と大被害にあったところです。
大槌町の周りの宿泊施設は、自衛隊、警察や各救援隊使用のため、ボランティアの人達は大槌町からバスで3時間かけたところのホテルで宿泊します。
そのホテルも震災のためお客が急減しているとのこと。
ボランティアの人達の宿泊そのものが助けになっています。
3時間かけて現場に行きますので、現場での作業は4時間ほどしかないのですが、60歳を越した参加者にとってはちょうど良かったと言っています。
このツアーは毎週3ツアー出発しています。
私も行きたいと思うのですが、頸椎ヘルニアやぎっくり腰のため、参加することで逆に迷惑をかけてしまいます。
このボランティア報告会が終わってから、ランチ会参加者の1人が発言しました。
偶然にもその方はこの大槌町出身者で、親戚たちが被害を受けいまだ行方不明者もいるそうです。
その話にボランティアに行った人も驚きました。縁なのでしょうか。
最後にその大槌町出身者の人が「心からお礼を言います」と言ったのが大変印象的でした。
法人税
先月私の会社の税務申告をし、税金を払いました。
払ったと言っても大した金額ではありません。
それほど利益が出なくてもしっかり税金を支払わなければならなりません。
でも税金を支払う時は「取られる」といった気持になります。
「取られる」という気持ちから、節税や脱税をしようとする人もいます。
先日話を聞いた社長は10年間利益がほとんど出ない決算を見せてくれました。
税金を払いたくないためです。
社長の給料も低くして、必要なモノは会社経費で落とすようにしていったそうです。
売上1000万円以下の別会社を作り、消費税も支払わないようにしたこともあったそうです。
でも、それはすぐ止めたそうですが。
会社経費で何でも落とすようにすると、会社の中の公私混同がつかなくなります。
その社長は年間飲み代だけでも300万円以上使ったそうです。
起業したばかりの社長は税金を支払いする時、「俺は税金を支払う事の出来る会社にしたのだ」と満足するでしょうか?
それとも「なんでこんなに努力して稼いだお金を、国や道・市は理不尽にもたくさん取って行くのだろう」と思うでしょうか?
ほとんどの人は後者だと思います。
そんな思いからすぐ「税金を少なくしよう」と思うのでしょう。
その為、先ほどの会社の社長のように利益がほとんど出ないようにするのだと思います。
しかしいくら節税の為だと言いながら利益を出さないようにし、税人を支払わなければそれは内部留保も出来ないということです。
先ほどの社長もやっとそこに気付きました。
今は考え方を180度変え、税金を支払いながら内部留保を増やそうとしています。
内部留保が無い会社は何かあるとすぐ資金に行き詰まり倒産になります。
会社が倒産するのは売上や利益が無いからではなく、お金が回らななくなるからです。
税金を必要経費として考えなければなりません。
そして内部留保を確保することに努力しなければ、基盤も作れないし、成長も望めません。
税金を支払うことで少しでも世の中の役に立っているという考え方を持つことで、会社経営の意義も見えてきます。
一方、本当に役立つ税金の使い方ををして欲しいとは思いますけれど・・・
自分を馬鹿と言える
昨夜勉強会があり、参加してきました。
「我が経営を語る」という題名で、40代の経営者が過去の経営方法を赤裸々に語っていました。
彼は有能な人です。
大学受験は半年の間に集中的に勉強をし、国立大学現役入学を果たしました。
1日16時間勉強したそうです。
また、社会人になってからも、ある会社に入社したばかりの頃、新規工場のコンピューターシステムを1人で作り上げたという大変優秀な頭脳と、情熱・熱意がある人です。
その彼が独立し15年間会社を経営をして来ましたが、その経営は利己的であったこと、愚かな経営をしてきたことを皆の前で、経営数字を披露しながら語りました。
当時、自分は間違えた経営をしているとは思っていなかったそうです。
しかし、その間違えに気付いたのは大幅な赤字に落ち込んだ時です。
このままではダメだと思った時に、「己を生きる」という言葉に巡り会えたと言います。
一生懸命に生きるという意味です。
その時に彼は「会社は経営者の考えでで変わるのだ」と思いました。
それと同時に過去の経営を反省しました。
数多くの社員が自分の経営者としての至らなさから辞めてゆき、特に新入社員として入社しながら3カ月ほどで辞めていった人を思い、「その人の人生を狂わせてしまった」と反省します。
それ以降彼はまず、社員のために、次は顧客のために、社会のために会社は存在するのだと、会社を位置付けしました。
彼の話を聞いて私がまず思ったことは、「この人は凄い」ということです。
自分の失敗や馬鹿さ加減を人前で披露できる事はそう簡単に出来ません。
どうしてもいいカッコをしたがるものです。
最近の若い社長は特にそうです。
でも、一度自分を馬鹿だと言い切れると、もう怖いものはありません。
失敗を恐れなく突き進んで行けます。
彼には高い能力と情熱があります。
それに今度は真っ当な、堂々とした考え方が加われば、稲盛さんがいう人生の成功方程式に則って行けます。
力のある40代の経営者が素晴らしい考え方を携えて経営して行く。
これからの彼の会社の発展が楽しみです
「体力」「気力」「知力」
土曜日・日曜日は家にいて何もせずにいましたが、常に身体がだるく、眠たく、本もあまり読みません。
テレビを見てもつまらなく、ただボケーとしていました。
原因は4日間上京し、その内2日間は1日中歩き回ったせいでしょう。
日頃身体を動かさず、怠けていた証拠です。
今朝はやっと普段通りの生活が出来そうです。
考えるに「体力」「気力」「知力」は皆連動しているのでしょうか。
若い頃は体力があるまま、行動しました。
ところが60歳を過ぎると体力を温存することばかり考えているように思います。
私は学生時代4カ月間ほどアメリカに行きました。
2カ月はオクラホマ大学の学生寮で生活し、2カ月間はアメリカ中を1人旅をしていました。
今思い返せば、旅の間は「体力」だけが頼りでした。
当時は少しも疲れたとも思わず、毎日グレイハウンドバスを乗り継ぎ、気の向くままにアメリカ中を回りました。
安ホテルに泊まり、食べるものは固くなったパンと缶詰、ジュースが中心の食生活。
それでもあれを見たいとブロードウェーでミュージカルを見、これをしたいとデンバーでスキーをし、あのジャズを聴きたいとニューオリンズへと、したいことへの「気力」は続きました。
それも「体力」に自信があったからでしょう
若い時に「体力」を使い、思いのまま活動・行動をすることによって、多くのものが蓄積されてゆきます。
それで何が出来たかという具体的なモノは無くても、大げさに言えば今の自分の原型が出来たように思います。
「知力」については私の場合、年を取るにつれ、少しずつ加わってきたように思います。
「元気」であること、「体力」があることは全てのベースです。
今回はそのことを改めて知らされました。
今一度「体力」作りをしなければと思っています。無理をせずに
社会起業家
今回の上京中はいろいな人と会いました。
その中でも、ある人とNPOや企業の活動、その為の起業について話をする機会がありました。
NPOは非営利活動団体だと言うことで、「利益を追ってはいけない」と誤解している人がいます。
ボランティアに近い活動をし、その活動原資は寄付金や補助金に頼ることだと思っている人がいます。
しかしそれではどんな素晴らしい活動をしても資金が続かなくなり、活動を中止し、NPO自体も有名無実化してしまいます。
結果サービスを受けていた人達に迷惑をかけることになります。
今はNPOでも事業型NPOとして社会起業家が注目されています。
Wikipediaによると社会起業家は事業成功による社会貢献を目的としていることから、「株式会社や有限会社の事業形態をとることもある。」と書かれています。
またWikirediaでは「ビジネスの起業家は、儲けと自分にどの程度報酬があったかで、その実績を計るのに対し、社会起業家は、社会にどれだけの強い効果を与えたかを成功したかどうかの尺度にしている。」と書かれています。
お金もうけではなく、社会的に役立つことを第一義に考える。お金は必要だが利益の最大化を求めない。社会的価値を創造する。それが、社会起業家なのです。
でもここまで来ると、一般の企業が目指すものと同じに見えてきます。
マイクロソフトのビル・ゲイツ、アップルのスティーブ・ジョブスはITによって世界を変えた人です。
最近ではFacebookを作ったマーク・ザッカーバーグも、社会価値を創造するということから、社会起業家と言えるのではないでしょうか。
NPOとか社会起業家というくくりで表現することで、一般企業家とあえて違った活動をしているように見えますが、ともに社会貢献が目的のはずです。
社会貢献をして利益を得ます。
人々に喜ばれる製品やサービスを提供できないところは売れず、必ず潰れます。
以前にも紹介しましたが、各企業の経営理念は社会貢献をうたっています。
パソナグル―プの経営理念は
「社会の問題点を解決する」
「私達は「人を活かす」ことをサービスの原点とし、常に高い志と使命感を持ち、新たな雇用インフラを構築し、さらなる雇用創造に挑戦し続けることを使命とする。」
オリエンタルランドは
「自由でみずみずしい発想を原動力にすばらしい夢と感動ひととしての喜びそしてやすらぎを提供します。」
ダスキンは
「経営理念を大切に、人に社会に『喜びのタネまき』を。
ダスキンは、利益追求のみならず、世の中の人に喜ばれる「喜びのタネまき」を実践し、地域の人々と喜びを分かち合い、物も心も豊かな暮らしに貢献することで、継続的な企業価値の向上を実現します。」
皆、社会貢献をしてうたい、その活動をして利益を得ています。
利益を得ているからこそ、継続して顧客への製品・サービスの提供が出来ます。
そして、その価値を求める多くの人達が増える為に、会社の規模が拡大して行きます。
NPO、社会起業家、一般の企業家の活動目的はそれ程大きな違いはありません。
ともに社会貢献をして、しっかり利益を出すことが大切なことだと思います。
多分、多くの人達とは意見の相違はあるでしょうが、私はそう思います。
盛和塾世界大会
昨日帰札しました。
今回の上京は盛和塾の世界大会に参加するのが目的でしたがそれ以外に色々な人に会い充実した約1週間でした。
盛和塾の世界大会では2日にわたり8人の経営者による「経営体験発表会」があり、各経営者がそれぞれ、感動の発表でした。
「東京の医療法人愛生舘 小林武彦さん」「熊本の株式会社ヒライ 平井浩一郎さん」「大阪の太陽ファスナー株式会社 馬淵健司さん」「鳥取の寿スピッツ株式会社 河越晴皓さん」「石川県の株式会社ぶどうの木 本昌康さん」「兵庫県の株式会社フジタ精米人 藤田覚さん」「京都の日本クリニック株式会社 小嶋享子さん」「新潟の株式会社佐文工業所 佐藤銀次郎さん」
この中で特に驚いたのが鳥取の寿スピッツ株式会社の河越晴皓さんの話です。
話を聞いていると、北海道小樽にある「小樽洋菓子舗ルタオ」がこの河越晴皓さんの会社なのだということです。
ここのお菓子は美味しいということで評判になって、北海道土産として高い人気があります。
でも私は「ルタオ」は北海道の会社が興したお菓子会社だとズーと思っていました。
大会に参加していた札幌の仲間も私と同様に驚いていました。
驚きと同時に少し寂しさを感じました。
落下傘のようにその場に舞い降り、アッという間に北海道を代表する会社にしてしまうその手腕の凄さと、なぜ同じことが北海道人が出来なかったのかという寂しさです。
あまり地元根性を出し過ぎる考えは良くないのは分かっているのですが・・・・
その他に兵庫の「フジタ精米人」と言う会社の仕事内容に驚きました。
この会社は精米を中心に成長してきましたが、今は「ご飯」を売っているということです。
自社精米したお米を自社で炊き、それをレストランや寿司飯にして寿司店に業務用として販売しているのです。
どのようなレストランや寿司屋が使うのかはわかりませんが、「ご飯くらい自社で炊けば」と思います。
でもこれも商売になるのです。
思いもつかないところに需要が生まれるのだとつくづく考えさせられました。
利益率1%という薄利多売の会社ですが、それを5%までに持っていっているのはこの藤田社長の手腕です。
この会社は、年商31億円、従業員31名の会社です。
利益率5%ですから1億5千万円でしょうか。
盛和塾世界大会では稲盛経営者賞が発表され、最優秀賞は東京の小林武彦さんが選ばれました。
ここ数毎年のように大会に参加させていただきますが、いつもものすごいパワーを感じ、エネルギーを受けています。
これほど真剣に会社経営している人達がいるという思いは、社長は孤独だと言われる中、連帯感を生んでいるのではないでしょうか。
この大会には70人ほどの日本航空の職員も参加し、話を聞いていました。
また、来年も参加したいと思っています。
展示会で
昨日はビックサイトに行ってきました。
今、ビックサイトでは「東京国際ブックフェア」「国際電子出版EXPO」「文具・紙製品展」「オフィス機器展」「オフイス家具EXPO」等全部で11の展示会が同時に開催されています。
私は「東京国際ブックフェア」「国際電子出版EXPO」から廻り始めました。
「ブックフェア」は既成の出版会社が直接本を展示販売するのが中心のアナログ世界。
反対に「電子出版EXPO」はデジタルの世界。
特に「電子出版EXPO」はハード・ソフトと共に150社が集まり、書籍・雑誌・コミックのデジタル化に伴う新しい事業も見れました。
見れましたと言っても、私にはハードは理解出来ても、ソフトとなると、それをどのように使うかも含めて理解出来ないことが多かったです。残念ながら・・・・
次は「文具・紙製品店」。
こちらの方は自分の使い勝手、好き嫌いで選ぶことが出来るので興味を持って回ることが出来ました。
欲しいものも多くありましたが、この展示会では買うことが出来ず、これもまた残念。
ビックサイトで開催されている展示会は、先ほども書きましたが11です。
2時から5時までブックフェア、電子出版、文具を廻っただけで、私は力尽きました。
歩き廻ったため足が痛くなり、それと一緒に気力もなくなってきました。
改めて、「体力」と「やる気」は比例するのだと再確認しました。
展示会場内は歩けないほどの人の多さです。
その中で、ひときわ人が集まっているところと、そうでないところがあります。
大きいスペースを確保している大手企業は人集めは上手いです。
しかし小さい店だけれど、人集めしているところは、店のトータルコーディネートが良くて、周りの店と明らかに違う雰囲気を出しています。
結果そうなったのか、それとも意識してそのように創作したのか分かりませんが、そこにも展示した会社の意欲が見えます。
この展示会は10日日曜日まで行われています。
入場券はインターネットからでも手に入ります。
ご興味ある方は行かれてはいかがですか?
友人
昨日までの2日間「盛和塾世界大会」がありました。
この時の話は日を改めて書いてみたいと思います。
ただ、1日目が終わり、3500名が一堂に会しての懇親会がありました。
その様子は「壮観」という言葉がピッタリでした。
この懇親会の後、札幌から来た人同士の2次会が場を変え、横浜中華街の店で行われました。
懇親会で飲み食いしたのに、また飲み食いしたのです。
その店で参加者20名程で盛り上がっていましたが、そこに同じ盛和塾に参加していた中国の人達も加わり、にぎやかな会になりました。
中国人の1人は貴州省から来ていて、茅台酒(マオタイしゅ)を作る会社の社長です。
茅台酒とは高粱(こうりゃん)を原料とした白酒で、500mlで15,000円もする高いお酒です。
度数は50ほどありますが美味しく、私は好きです。
その社長は盛んに中国貴州省に来るよう盛んに誘っていました。
ベンツやBMWで 出迎えに空港まで行くと言っていました。
その時は皆酒を飲んでの勢いで盛り上がりました。
もしかしたらこれから新しい人のつながりが出来るかもしれません。
昨日盛和塾の世界大会が終わって、その後18時から高校時代の友人と会いました。
東京近郊に住んでいる彼と会うのは2年ぶりです。
上京したらなるべく会うようにしているのですが、なかなか出来なく、2年ぶりとなりました。
彼と私は全く性格も考え方も違う人間です。
それでいて、とても信頼できる友人です。
何かの題材で話し出すと、互いに違う見解で、話が延々と続きます。
意見は違うのですが、不思議と対立することはありません。
お互いに尊敬する部分を持っているからなのかもしれません。
彼と話をして改めて思ったのですが、人には同じ志を持ち、同じ方向を見続ける友人を持つことは大切。
しかしそれと同じように、自分と価値観が違い性格も違う友人を持つことも、自分をに直すには大切なことです。
ただ、なかなかそのような友人を持つことは難しいです。
意見が対立してしまう人とはそう簡単に仲良く出来ません。
でも、対立の中にその人に人間としての尊敬できる部分を見つけ出せば出来るのかもしれません。
私にそのような友人がいることは大変幸せなことです。
昨夜友人と別れる時、ともに60歳を過ぎているもの同士。
今度会う時はいつになるか、また元気でいるのか。
互いに思い合いながら別れました
道を究める
新聞を読んでいましたら今度の日曜日10日から大相撲7月場所が始まると書かれていました。
大震災報道で途切れてしまった大相撲の八百長問題もいつの間にか治まったようで、7月場所からNHKも放送を復活するそうです。
八百長問題は以前から相撲の世界ではあったという話を聞きます。
あるテレビ番組で貴乃花親方が出ていました。
その時、司会者から「現役時代に八百長問題は身の回りで見、聞きしたことはありますか?」と問われ、親方はないと答えていました。
自分は相撲のことばかり考え、自分の相撲を取ることで精いっぱいだったと言っていました。
確かにあの現役時代の姿は「相撲道」を究めようとする気概があったように思います。
今の親方の体型は身体を絞った結果80kg減量したそうです。
それも意思の強さを感じます。
日本人は色々な世界で「道を究める」ことに熱中し、精神修養までに高めていこうとする傾向があります。
柔道、剣道から始まって空手道、プロレス道等あります。
会社経営にもあるのかと思ってインターネットで「経営道」と検索すると、「日本経営道協会」という団体が出てきました。
経営を精神修養的なとこまで高めようとするようです。
私は道を究めるということは、個人的な行為だともいます。
相撲にしても柔道剣道にしても、個人競技です。
競技では個人がストイックに生きようとする生き方と、それによって個人の競技結果が良くなることでその価値があります。
一方経営は個人競技ではありません。
いくら社長がストイックに生きようが会社成長が伴わなければ何も意味がありません。
そこが違います。
ただ、社長は個人のことはどうであれ、会社や従業員のことを、お客様が良くなるように考えるところに価値があります。
稲盛和夫さんが経営を教える盛和塾では一見「求道的」に見られがちですが、社長が会社のトップとしての心構えを持ち、高い志を抱くのは、会社、従業員、お客様のためなのです。
そのような教えの言葉に「心を高める、経営を伸ばす」があります。
明日から横浜で盛和塾の世界大会があり、約3600名の塾生が参加する予定です。
私も勉強してきます。
公平な判断
昨日テレビで原発のニュースを見ていたら、傍にいた妻が「福島の第2原発はどうしたのかしら?」と言いました。
今、第1原発では事故処理が大変な状況です。
その事故によって日本中の原発が地震などの天災に弱いとみなされ、稼働停止されている原発が多くなっています。
1000年に一度の大災害にも耐えられるのかということで問題になっています。
今回の1000年に1度の災害で第1原発は大事故を起こしまいたが、第2原発の方はそうではなかったはずです。
このことをインターネットで調べてみますと、東京電力が発表している7月2日付の「福島第二原子力発電所 プラント状況のお知らせ」では「1~4号機は冷温停止中です」と安全に安定してことが書かれています。
そうすると今回の1000年に1度の大災害にも耐えれた原発だったとの見方も出来るのではないのでしょうか。
第2原発は第1号原発に比べ新型であるという情報もあります。外部電源の確保がキーポイントだったという情報もあります。
第1原発の被害を強調するあまり、第2原発のことをあえて報道しなかったのかどうかわかりません。
勿論、だから原発が安全だと言っているわけではありません。
ただ日本人が原発反対・推進を判断する時、その公平な判断材料が必要です。
それが意識的ではないにしろ、一方だけの話ばかりが強調されてしますと、本当の判断が出来ません。
現代は情報が溢れていると言われます。
だから公平な判断が出来ると思っています。
しかしそれは錯覚なのかもしれません。
入ってくる情報の量が多い方に人間の判断が偏ってしまいます。
人間の心が極端から極端に簡単に移ることは、歴史上でも明らかです。
「軍国主義から平和主義」、「過激学生運動からノンポり学生」「石油ショック時の買い占め現象」等がありました。
情報を集めて分析する時、今までは「右派・左派」等の「水平的思考」に気を取られていました。
もう一つ「垂直的思考」で深く知ることも必要。
また「老人・若者・子供」「社長・課長・社員」等の「上下思考」でモノを考えることも必要かもしれません。
天の邪鬼的に常に色々な切り口から物事を観察する力こそが、情報過多言われる時代に必要だと改めて感じています。
人を雇用する時
昨日知人が来て話をしていきました。
彼の会社は最近は忙しいらしく、嬉しい悲鳴を上げているとのこと。
ただ、ある人から面白い仕事の話があり、それを受けたいのだけれど、時間がなく悩んでいるようでした。
彼の会社でも、今まで1人で仕事をしていたのですが、最近はアルバイトを1人雇っています。
そのアルバイトをうまく使えば時間は取れるはずです。
問題はアルバイトをどのように使うかです。
起業した人が初めて人を雇用した時、その人を十分に活用し切れていないのをよく見受けます。
それは社長の「遠慮」と「任せることの面倒さ」に大きな原因があるように思います。
「遠慮」とは「こんなことを頼んでいいのか」という思いです。
優しい社長はアルバイトも「同士」として扱い、上から指示することに躊躇するのです。
また「任せることの面倒さ」とは人に任せると、指示する時間がもったいないとか、仕事の遅さに我慢できないくなり、つい自分でやった方が早いと思ってしまい、自分で仕事を抱え込んでしまいます。
結果アルバイトの人は雑用しかしなくなります。
社長が自分の時間を作るということは如何に人に仕事を託していけるかどうかにかかっています。
起業家が成長する時ぶつかる最初の関門です。
これを越せなければ、いつまでも1人社長から抜け出れません。
ところで、急ぎの仕事を頼む時は、「忙しい人に頼みなさい」とい言われるのをご存じでしょうか?
普通は「時間があり暇そうな人に頼む」と思われると思います。
でも、忙しい人は仕事をこなす手順、時間管理が優れていて、多くの量の仕事を処理します。
一方、暇そうな人は時間管理も仕事の手順も考えたことが無く、行きあたりばったり的な行動をするので、仕事の目途が立ちません。
起業家は仕事の規模を一段階上に上げる時、人を採用します
その時、自分が作り上げてきた時間管理能力や仕事の手順を、遠慮なく如何に教えることが出来るか。
それが重要。
最初それに時間がかかってもいいから、そこに重点を置くことで、その後の仕事の速さが違ってきます。
ここが肝要な点です。
過保護
昨日のブログにも書きましたが、15歳以下の人口が減少しています。
そして子供1人1人が大切にされます。
子供が1人いるとその両親、両親の親達、合わせて6人の大人がかかりきりになります。
子供は精神的にも物資的にも満たされて育ちます。
その生活環境は整備され、転んでも怪我をしないようにされます。
公園で何かに器具を使って怪我をすると、すぐに取り外されたりします。
過保護の一言です。
その結果生活対応力のない子供が育ちます。
転んだら、パッと手が出て怪我を防ぐと言う、自己防衛本能さえも無くなっている子供が増えているそうです。
ある小学校では近年低学年の児童が転倒して顔面打撲や骨折等が多くなっているとのことです。
昨日そのようなことに関するセミナーがありました。
転倒防止運動のために開発された「ハニカムマット」についてのお話でした。
このマットはウレタンで出来た、数種類の形や硬さがあります。
それを並べてその上を子供が飛び歩くことで体のバランスを保つようにするというものです。
実際に小学校で実用研究されそのデーターが集まり有効との結論が出たそうです。
これから体育の授業で取り入れる学校も増えるかもしれません。
このマットによる訓練は大切な教育の1つだと思います。
しかし、このような対応は、現象面の解決に重点が置かれているように思います。
もっと根本のところを見直さなければ本当の解決になならないと思います。
転ばないように気を配るのでなく、転んでも身体を防ぐ方法を身に付けさせ、自分で起き上がる方法を考える力を付けさせる。
そんな当たり前のことをすればいいのですが、お節介な大人が多すぎます。
子供は怪我するのは当り前。子供同士でぶつかって、転んで、起き上がってまた転ぶ。
遊びの中で自然と身に着くモノ。
私も3人の孫がいます。
夏には東京から遊びに来ます。
その時は厳しいお祖父ちゃんでいます。いや、いるつもりです。
それにしても私の小さい頃は2階から階段を転げ落ちたこと何回あったことか。
それでも泣いただけで、怪我もしませんでした。
ただ、今、頭の回転が悪いのはその時の後遺症かもしれませんが・・・
ホテル住まい
今朝の新聞に国勢調査の内容が掲載されていました。
65歳以上の人が全人口の23%――世界最高
15歳未満の人が13%――世界最高
と言う見出しです。
また労働人口(15歳~65歳)は2005年からの5年間で300万人減少しています。
札幌市の人口が200万人弱なので、ものすごい数だということが分かります。
これはこれから労働人口は益々減少してきます。
また、1人暮らし世帯が急増して全世帯の3割を超えているとのことです。
これらの数字は経済が益々縮小化していきそうな気にさせます。
私は高齢者が増え、1人暮らしが増えているというのを読んで、別の新しい暮らし方があるのではないかと考えています。
以前にノーマン・S・ハイナーが書いた「ホテルライフ」という本を読み、刺激されました。
住む場所として、戸建て、アパート、マンション、老人ホームなどがありますが、この本により「ホテル住まい」と言う考えがあるというのを知りました。
「ホテル住まい」をした人として私が記憶しているのは、日本オペラの草分けと言われた藤原義江さんが帝国ホテル、映画評論家だった淀川長治さんがホテルニューオータニで暮らしたというくらいで、お金持ちがすることと思っていました。
でもそうではなくて、これからもっと一般的で別の「ホテル住まい」を考えてみると、新しい新規事業も生まれてくるのではないでしょうか。
勿論、「ホテル住まい」運営はホテルの副業として始めるのです。
一般のホテルの部屋と違えて、簡単な自炊設備を備えたウイークリーマンション的なものですが少し豪華に。
サービス内容はホテルサービスと同じで、応対は全てフロントで行います。
必要に応じてベットメイクからクリーニングもします。
食事のルームサービスもします。
長期滞在するわけですから、ホテル側も料金は格安にしても十分見合う利益が生まれます。
今は結婚をしない40,50代の人達が増えています。
40歳代から上の年代のプチリッチな人をターゲットとして、安全で便利なホテル生活を提供するのです。
仕事が忙しく掃除洗濯できない人、身体が丈夫でなく健康に不安を抱いている人、街の真ん中で暮らしたい人、安全に気を配る人等「ホテル住まい」をしたいと思う需要は多いと思います。
「あなたはどこに住んでいるの?」と聞かれて「〇〇ホテルです」と答えるって少し素敵でないですか?
「パーフェクト」と「ベスト」
昨夜、経営者が集まっての勉強会があり、私も参加してきました。
経営者が集まってですから勿論経営についての話が中心です。
その中で特に議論したことは、「パーフェクト」な仕事と「ベスト」な仕事の違いです。
昨日より今日、今日より明日へ向かって向上する時に使うのは「ベター」という表現でしょう。
「より良くなる」というのは大事な心構えです。
ただ、仕事をする上で「ベター」な仕事では許されないのです。
製品・商品として完成されていなければお客様の満足は得られません。
「前回の商品よりいいでしょう」と言っても買ってくれません。
勉強会では、その完成された製品を目指す時、「ベストを尽くす」というのがいいなのか、「パーフェクトを目指す」というのが本当なのかこれが論点になりました。
「ベストを尽くす」という言葉はいいように聞こえますが、時として「ベストは尽くしました」が結果、出来ませんでしたという言い訳にもなります。
ある会社で目標数字の達成が難しかった時、社長が幹部に「何とか目標達成をしたいので頼む」と言った時、幹部が「ベストを尽くします」と答え、社長は満足しました。
しかし、目標は達成できませんでした。
社長は幹部に目標達成出来なかったことを責めました。
それに対して幹部は「ベストは尽くしたのですが・・・」といいます。
社長は「ベストを尽くす」という言葉を承認したのですから、それ以上は責めることはできません。
「ベストを尽くします」と言われて、「それじゃベストを尽くしてくれ」と言うのは社長失格です。
社長は「必ず達成してくれ」といい、幹部も「必ず達成します」と言うのでなければならないのです。
目標達成と言う「パーフェクト」を目指すのです。
製造業の製品もそうです。
「ベスト」を目指してもハネ品が出ます。
その場合100個の製品を作るのに、ハネ品を予想して110個分の材料を用意します。
2~3個のハネ品が出て、7個分の材料が無駄になります。
利益が減ります。
パーフェクトを目指すとすれば、100個分の材料しか購入しないことになります。
そこに「1個も無駄が出来ない。」「1個もハネ品を出すことはできない。」という、本当の真剣さが生まれます。
「ベスト」と「パーフェクト」の違いは「本当の真剣さ」が生まれるかどうかではないかと思います。
「ベスト」にはまだ甘えがあります。
「パーフェクト」と言っても完璧なことはそう簡単にできないでしょう。
しかし目指すモノとして最初から甘さのある「ベスト」より、完璧な「パーフェクト」を目指すことが大切だと思っています。
タフな精神と体力
最近夏風邪が流行っているそうです。
私も2週間程前、あるセミナーで話を聞いている時、肺か気管のあたりの調子が悪くなり、咳ばらいが多くなり、少し周りの人に迷惑をお掛けしたかも知れません。
熱も無く、のども痛くなく、空咳が出る程度でした。
3日後あたりから夜の咳がひどくなり、寝れない日が続きました。
咳は日中はほとんど出ません。
病院へ行き、薬で何とか寝れるようになりなしたが、まだ少し出ます。
今までの私の風邪は鼻から始まったのですが、今回は全然前兆もなく始まりました。
身体が年と共に少しずつ変化しているせいなのかもしれません。
私の風邪とは別ですが、私達の周りの病気が、従来と違った病原菌が多くなりました。
私が小学生の時とは大きく違っています。
環境の変化と、医療が進み、それに耐えうる、より強力な耐性病原菌の増殖があるのでしょうか。
抗生物質の多用にその原因があるかもしれません。
それも人間の快適な生活を求めての結果です。
本来の免疫力で回復したものが、簡単に抗生物質を使用することがありました。
勿論、現在病気で苦しんでいる人達を指しているのではないのです。
世の中豊かになると快適を求めていきます。
それが満たされることで、あわせて体力・体質が変化し、弱体化すると言われています。
もっと言うと、人の精神もそうでしょう。
豊な生活は精神も甘やかします。
もっと耐性のある精神を作る努力をしなければ、体も弱く、精神も弱く、体力さえない日本人が増えて行きます。
それを少しでも防ぐために、もっと自分に課する生活をした方がいいのかもしれません。
だからと言って急激な変化は身体に良くありませんので少しずつ。
朝早く起きる努力をするとか、毎日運動するとか、辛いけれど帰宅後毎日1~2時間は本を読むというような「怠惰な本能に抵抗する行動」から始めてもいいのかもしれません。
これから大きく変化することが予想される日本。
そこではタフな精神と体力が必要とされそうな予感がします。
経験を生かす
小説を読んでいましたら「青春」「朱夏」「白秋」「玄冬」という言葉が出てきました。
人生を四季に当てはめた中国からきた言葉です。
「青春」は10歳代、「朱夏」は20歳~30歳代、「白秋」は40歳~50歳代、「玄冬」は60歳代以上となります。
60歳以上を「玄冬」と一括で括られているのは昔の寿命を考えてのことでしょう。
今なら10歳以上加算してもいいのかもしれません。
この言葉に似たものが論語にも載っています。
子曰わく
吾十五にして学に志す――「志学」(学を志す)
三十にして立つ――「立身」(独立をする)
四十にして惑わず――「不惑」(まよわない)
五十にして天命を知る――「知天命」(天命を知る)
六十にして耳順(した)がう――「従耳」(人の言葉を素直に聞く)
七十にして心の欲する所に従って、矩(のり)を超えず――「不超矩)(思うままにふるまっても道はなずれない)
この孔子の言葉の中ではやはり、自分の世代の「六十にして耳順がう」はピッタリでしょう。
この年になると物事を知ったかぶりして、自己主張が強くなり、人の話を聞かない世代なのです。
それを克服した時こそ、「七十にして心の欲するところに従って、矩を超えず」とした境地になるのでしょう。
それを克服しなかったら、普通の口うるさい年寄になる・・・
ただこれからのことを考えると、70歳以上の人達の力が必要かと思うことがあります。
この度の大震災の被害は大変のもので、これからは今まで以上に経済にも大きな影響が出てくることでしょう。
復興資金のために増税や国債発行、もしかして日銀が国債購入引き受けなどになったら、ハイパーインフレ・スタグフレーションが起きるとも言われています。
今までの生活基盤が崩れていくこともあるかもしれません。
そのような時に必要なのは「経験」ではないでしょうか。
今回の災害に近い経験をした人達は70歳・80歳代でしょう。
それ以下の人達は知らないのです。
今は戦後ほとんどゼロから始まった日本を立て直してきた人達の知恵が必要になってくると思います。
経験と知恵を年配者から受け、若い人達がそれを生かして復興する。
そのような形が「一丸」となってということです。
今の政情を見ると、「一丸」という言葉と程遠いので本当に残念です。
これからの動きが大変気になるところです。
来訪者
私の事務所には多くの人達が訪ねて来てくれます。
色々な情報を持ってきてくれる人もいます。
私の部屋は一度に10人以上の人が来られてもいいほどの椅子やテーブルがあり、打ち合わせや会議が出来ます。
多くの人達が来てくれますが、気が付くといつの間にかその人の顔ぶれは変わっています。
フッとそういえばあの人は最近来なくなったけれど、「どうしたのだろう?」とか「何かあったのかな?」と思うことがあります。
そんな時思うのは「私が何か悪いことを言ったかな?」とか「悪いことをした?」と考えてしました。
勿論、私の話が面白くなくてそうなっているのだとは思うのですが。
訪れてくれる人とお会いしていつも「いい話を聞かせてくれた」と思うのです。
人と話をしているうちに、思いがけないヒントやチャンスを得ることがあります。
その人がそれを直接言って入れたわけでなく、一緒に話をしていると、自分の頭の中が整理されてそれが生まれてくるようです。
お話をしたいと思う人は楽しい人。話をしていて胸がワクワクする人です。
そしてそのような人は私の話を導いてくれます。
自分では相手の話を聞いているつもりですが、いつの間にか自分が好き勝手に話しているのです。
自分で気付かない部分を、その人と話をするうちに、導き出されてくるようです。
身近にそのような仲間を作ることは大切ですが、自分がそのような人になれることがより大切だと思います。
人の良さを引き出してくれる人こそ、本当のメンターと言えるのでしょう。
動機善なりや。私心なかりしか
今日も「京セラフィロソフィ勉強会」の続きを書きます。
今日は「動機善なりや、私心なかりしか」についてです。
これについて稲盛さんは次のように言っています。
「大きな夢を描き、それを実現しようとする時『動機善なりや』ということを自らに問わなければなりません。
自問自答して、自分の動機の善悪を判断するのです。
善とは、普遍的に良きことであり、普遍的とは誰から見てもそうだということです。
自分の利益や都合、格好などというものでなく、自他ともにその動機が受け入れられるものでなければなりません。
また、仕事を進めていく上では『私心なかりしか』という問いかけが必要です。自分の心、自己中心的な発想で仕事を進めていないかを点検しなければなりません。
動機が善であり、私心がなければ結果は問う必要はありません。必ず成功するのです。」
この「動機善なりや、私心なかりしか」という言葉は、私が稲盛さんの勉強会「盛和塾」に入って最初に学んだことです。
この言葉は稲盛さんが、今のKDDI(第二電電)を創業する時に「これだけの事業を始めるからにはもっと自分を駆り立てる何かが必要だと思い、考えを思い巡らせていた時に浮かんだのがこの言葉だったのです」と言っています。
稲盛さんは第二電電を創業しようと思い立った後6カ月間、毎夜寝る前に「動機善なりや私心なかりしか」と自問自答したそうです。
「おまえは第二電電を創業し、通信事業を手掛けたいと言っているが、その動機は善なりや、そこに私心はないのか」と問い続けたのです。
ここで言う「善」とは良いこと、正直なこと、人を助けること、優しさ、思いやりある心、美しいこと、さらに言えば、純粋な心という意味だと説明しています。
人は誰でも私心はあると思います。それは人間としての生存本能として、自己防衛的なものが必要だからです。
ですから稲盛さんはそこまで捨てろと言っているわけではありません。
良く思われたいと思う「見栄」とか、有名になりたいという「名誉」とかで判断することがあってはならないと自己点検したのです。
私は過去そこまでの判断を求められたことは記憶にありません。
しかし、企業は益々社会に関連する仕事をすることになります。
自分のことばかり考えていれません。
企業人として、自分の襟を正す上でこの「動機善なりや、私心なかりしか」という言葉は、常に念頭に入れておかなければならないでしょう。
夢を描く
今日も「京セラフィロソフィ―勉強会」で学んだことを書きます。
「夢を描く」についてです。
稲盛さんはこの事について次のように書いています。
「現実は厳しく、今日一日を生きることさえ大変かもしれません。しかし、その中でも未来に向かって夢を描けるかどうかで人生は決まってきます。
自分の人生や仕事に対して、自分はこうありたい、こうなりたいという大きな夢や高い目標を持つことが大切です。
京セラをまず西の京で一番、その次に京都で一番、それから日本一、世界一の企業にしたいという大きな夢を創業時から描き続け、努力を重ねてきたことによって今日があるのです。
高く素晴らしい夢を描き、その夢を一生かかって追い続けるのです。それは生きがいとなり、人生もまた楽しいものになっていくはずです。」
この「夢を描く」は前項の「心に描いたとおりになる」の続きになります。
「心の思い描いたとおりになる」なら、夢を描かなければ勿体ないのです。
そしてその夢は、楽しく、明るく、希望にあるれた夢を描くべきです。
稲盛さんは続けて次のように書いています。
「夢は事業を行っている経営者の場合は、もっと現実的に企業経営の目的だとか、また業績数値といった具体的なモノを思い浮かべる方がいいと思います。
例えば、こういう売り上げにしたい、こういう利益にしたい、こういう雰囲気の会社にしたい、そのようにリアルな数字や目標をはっきり描くことも必要です。
そのような夢や目標を描き続けていけば、その通りの会社が出来るはずだと私は信じています。」
私は以前聞いた西田文郎さんの講演会の話を思い出します。
西田さんは「NO1理論」等の本を出し、多くのアスリートのメンタルケアをしている人です。
西田さんは次のようなことを言っていました。
「アスリートたちはトップを目指して努力します。オリンピックなら金メダルを目指します。
彼らはトップでなけれな意味が無いと思っています。1位と2位の差は大きなものがあります。
2位3位までは何とか人の記憶に残りますが、それ以下だと皆同じ無名の人とみなされてしまいます。
しかしビジネスの世界では1位を目指して努力して、たとえ1位にならなくても十分評価してくれる世界です。
ビルゲイツにならなくても世界で100番でも十分すごいことです。」
西田さんは、アスリートの世界の方が厳しい世界だと言っていたのです。
まだビジネスの方が、自分の努力で達成される成果でも十分評価される世界です。
どちらにしても「夢を描く」ことの大切さは同じです。
心に描いたとおりになる
昨日のブログに続き、「京セラフィロソフィ勉強会」での内容を書きます。
今日は「心に描いたとおりになる」についてです。
「心に描いたとおりになる」という言葉を聞くと、「引き寄せの法則」を思い出す人もいるでしょう。
稲盛さんは次のように書いています。
「ものごとの結果は、心に何を描くかによって決まります。『どうしても成功したい』と心に思い描けば成功しますし、『出来ないかもしれない、失敗するかもしれない』という思いが心を占めると失敗してしまうのです。
心が呼ばないものが自分に近づいてくることはないのであり、現在の自分の周囲に起っているすべてのものの現象は、自分の心の反映でしかありません。
ですから私達は、怒り、恨み、嫉妬心、猜疑心など否定的で暗いものを心に描くのではなく、常に夢を持ち、明るく、きれいなものを心に描かなければなりません。
そうすることにより、実際の人生も素晴らしいものになるのです。」
稲盛さんは、従来から人生の成功方程式(=「考え方」×「熱意×「能力」)を説いています。
その中でも特に「考え方」の重要性を言っています。
まさに「人生は心に描いた通りになり、心に描いた通りのものが現象としてあらわれる」のです。
この事は「思念は業(ごう)を作る」とお釈迦さまが説いておられ、また中村天風さんも「ゆめゆめ暗い想念を抱いてはならない」と言っているのです。
ただ、今、良いことを思えばすぐに良いことが起こるかというとそうではないのです。
稲盛さんは「因果応報」の辻褄(つじつま)は大体20年~30年スパンで起きると言っています。
思い返してみますと確かに、私も20年ほど前から考え方が変わって、今があるように思います。
風船はヘリウムや水素等の気体をたくさん入れれば大空へ飛んでゆきます。
二酸化炭素やラドン等の重たい気体を入れれば全然飛びません。
また何も吹き込まなければ、それはただのゴム袋です。
同じように、良い考え・良い思いを取り入れると、自分の人生も大きく羽ばたいてゆきます。
この項ではこの事の大切さを説いているのです
一日一日をど真剣に生きる
昨夜は毎月行われる「京セラフィロソフィ勉強会」の日でした。
今回も5項目を読み、話し合いました。
「一日一日をど真剣に生きる」「心に描いたとおりになる」「夢を描く」「動機善なりや私心なかりしか」「純粋な心で人生を歩む」です。
今日は「一日一日をど真剣に生きる」について書きます。
稲盛さんは本に次のように書いています。
「人生はドラマであり、1人1人がその主人公です、大切なことは、そこでどういうドラマの脚本を書くかです。
運命のままにもてあそばれていく人生もあるかもしれませんが、自分の心、精神というものを作って行くことによって、また変えていくことによって、思い通りに書いた脚本で思い通りの主人公を演じることも出来るのです。
人生というのは、自分の描き方一つです。ボケっとして生きた人と、ど真剣に生きた人では、脚本の内容はまるで違ってきます。
自分というものを大事にして、一日一日、一瞬一瞬をど真剣に生きていくことによって、人生はガラッと変わって行くのです。」
稲盛さんは続けて書いています。
「たった一回しかない人生を無意味に過ごすことぐらいもったいないことはありません。天地自然はこの宇宙で必要だったからこそ我々を存在させていると私は考えます。この宇宙に我々は必要である、自分は大切な存在なのだと、まずは信じるべきでしょう」
私はこの「自分は大切な存在、必要な存在なのだ」と認識することがとても大事だと考えます。
自分を卑下したり、無意味に自信をなくしたりする必要はないのです。
胸を張って生きていく存在なのです。
その点をしっかり認識して、そしてそれをは自分の子供達にこの事を伝えるのです。
自分の存在意義を教えることは命を大事にすることであり、また他人の存在を認めることになります。
私も1日が終わり今日はど真剣に勉強したか、仕事をしたかと問うてみる。
今日は満足出来る日だったと思える日は何日あるだろう。
残念ながら忙しかったけど、何をしたか分からない日が多かった気がします。
毎日目標を定め、意識を持って生きる、すなわち「有意注意」な生き方こそが、ど真剣に1日1日を過ごしていくことなのでしょうか。
1人思考
先日の日曜日に高速料金1000円が終了になりました。
私は列車とかバス・飛行機で旅行することが多く、車で旅行することはほとんどありません。
ですから高速料金1000円が終了してもあまり影響はありません。
終了間際では高速料金1000円終了で商売に影響があるという声をテレビのニュースで放映されていました。
ほとんどが「どうしようか」という声を拾ってばかりです。
それは高速道路を使って旅行する人達によって潤っていたお店や旅館の人達です。
この制度が始まった時も同じように「どうしようか」という困った声もありました。
その時は一般道路沿いで商売をする業者の声です。
フェリー会社や鉄道関係も影響を受けました。
今回はその逆パターンです。
テレビ等の報道は報道対象をフォーカスし過ぎる為か、センセーショナルに取り上げがちです。
それを見た人がそれに影響され、自分の意見を変えてきます。
しかし、全ての事には表と裏があるということを捉えていかなければ、本当が見えなくなります。
温暖化のせいだと言って、サンマが獲れなくなり漁民が大変だと報道されても、もしかしたら別の魚が取れているかもしれません。
本来東北では獲れない鯛が豊漁だとのニュースもあります。
暑過ぎて野菜がダメだと言って野菜農家が困っても、果物の糖度が高くなり果物農家は喜びます。
私はテレビ等の報道を見る時、意識して裏読みをするようにしています。
「天の邪鬼」と言われるかもしれませんが、そうしなければ本当のことが見えて来ないのかもしれません。
これはテレビばかりでなく全ての情報に言えることでしょう。
情報社会において受け身であるということは大変危険なことなのかも知れません。
その為に必要なのは知識を増やす勉強よりは、「1人思考」することなのかもしれません。
その時は、昔から言われている「価値基準」に照らし合わせながらするのです。
「損得よりは善悪」「真面目に生きる」「人を愛する」「利己より利他の心」等、親から教えられ、昔から言われていることを基準に考えています。
そうすると、自分なりの考え方を持って情報に向き合うことが出来ます。
つまらない情報に踊らされないために1人思考の時間を取ることは大事だと、最近特に感じています。
商売する場所
昨日は仲間が集まって、知人のレストラン開店のお祝いをしました。
少人数でしたが楽しい会でした。
このレストランは開店してからまで1月も経っていないのですが、順調な売上を上げているようでした。
このオーナーは約1年間、自分の気に入った店舗を探すのに時間をかけたそうです。
札幌の大通に面した1階にあり、中心部から少し離れていますが、周りには大きい病院や会社も多く、昼食を中心に繁盛しています。
このレストランが入居する前もこの場所にはイタリアレストランが20年以上続いたいたそうです。
それなりの売上があったのですが、諸事情があり閉めたのを居抜きで借りました。
私の経験から言って、場所には運気があると思っています。
一見いいような場所でも、いろいろな店が入居しても潰れていくところと、繁盛して居続けているところがあります。
その違いはわかりません。でも、場所を決める時、以前の店の入退去状況を調べてみるのは大切だと思います。
ただ、いい場所として言われているのは銀行のあとです。
そこは商売繁盛すると言われています。
金庫というお金が集まる場所は商売がうまく行くということらしいです。
そのような例は何件か知っていますが、私が知っている限りでは、確かに商売がうまくいっているようです。
商売に方角とか運気とか言っても「迷信」と言う人もいますが、どこの国でもそれなりに信じられてきました。
先ほどの開店したレストランは「円山惣菜」という名前で、お惣菜も販売しています。
料理は契約農家で作られた野菜、その多くは有機野菜、オーナーはソムリエでもありますので、ワインも選ばれたもので、有機ワインも取りそろえています。
このレストランは小さくて落ち着きがあり、料理も美味いです。
知人の店だからというのではなく、本当にまた人を連れてきたい場所です。
私の隠れ家にしたいので、あまり教えたくありませんが・・・・
札幌市中央区大通西16丁目3-6アーバンコート札幌1F 「円山惣菜」
宜しければ行ってみてください。
マスターはイケメンです。
復興資金
今朝の新聞に「東北3県に復興基金」という見出しが載っていました。
数千億円のお金を国から自治体に渡し、自治体はそれを支援対象者に出資や融資の形でなく、返済不要の支援金として出すそうです。
被災した企業や個人が市町村を通じて申請し、支援金を受け取ることになります。
やっと出るのかという思いがします。
被災した人達が本当に復興したと思うのは、被災者という名称が外れ、自分のするべき仕事を成してこそ思えるのではないかと考えます。
特に多くの企業が再生して地域産業が復活し、雇用も生まれて、早く元の生活、それ以上の生活が出来ることが重要です。
また、今回の復興支援金は直接申請者に渡されることが大切です。
なぜかというと、良くあることですが、支援と言って自治体は財団やNPOに丸投げしてしまうことが多いからです。
中に入った財団やNPOの団体が支援金を「中抜き」させてはなりません。
財団とかNPOという「非営利団体」という衣を被った利益団体が存在するのは事実です。
自治体は忙しいという理由でお金を出しただけで仕事をしたつもりになります。
この事はつい最近もこのブログでも書きました。
今回の資金ばかりでなく、これから多くの復興資金がつぎ込まれます。
企業を再生し、地域活性に役立つことを願い、これからも起業家、経営者支援に多くの資金が使われることを注目して見てゆきたいと思います。
時間管理
昨夜のセミナーは久しぶりに「良かった」と思えるセミナーでした。
周りの人達にも声をかけ参加してもらいましたが、皆さんも満足した様子でした。
それは「時間倍増セミナー」と題して、有限会社がんばれ社長の武沢さんが主宰しました。
講師は3名。
1人は武沢信行さん。日刊メールマガジン『がんばれ社長!今日のポイント』の作者で、全国3万人を超える経営者が読んでいます。
2人目は佐藤幸枝さん。一冊のマンダラ手帳だけで仕事も家庭も健康も経済も何もかもが見事にマネジメントしているマンダラ手帳の達人。
3人目は佐藤等さん。ドラッカーブーム以前からドラッカーを信奉するドラッカリアンで、「実践するドラッカー[思考編]」「実践するドラッカー[行動編]」等の著者。
この3人が3様の時間管理を話されました。
武沢さんはの話では、時間を作ることは、仕事を減らすことに気付いたと言います。
マイケル.E.ポーターの「競争の戦略」にある「何をしないかを決めること」という言葉があります。
武沢さんは時間を生む為、仕事の選別をしました。その選別基準は4つあります。
①自分の理念・価値観に合致しているか。
②自分の情熱レベルに合致しているか。
③自分の得意(競争)レベルに合致しているか。
④自分の利益レベルに合致しているか
の分野で現状の仕事を1~5までの点数を付け、その重要度を確認したそうです。
それにより無駄な仕事を見出し、それを切り捨て、今は自分の得意な仕事に特化しています。
佐藤幸枝さんは自分のマンダラ手帳を見せながらその活用方法を教えてくれました。
特に「時間は塊としてとらえる」という考え方は納得する言葉でした。
自分の人生を全て手帳で管理しているような感がし、時間を有効活用している様子が分かりました。
佐藤等さんはドラッカリアンとしてドラッカーの言葉の引用をからめての話でした。
「計画とは時間を割り付けること」という言葉も印象に残りました。
「時間を塊としてとらえる」のは佐藤幸枝さんと同じですが、その塊を2時間とするのだそうです。
ドラッカーが言う仕事の成果を上げる能力も紹介してくれました。
①時間を管理する
②貢献を重視する
③強みを生かす
④重要なことに集中する
⑤成果の上がる意思決定をする。
そして時間の管理とは時間からスタートすることで、決して仕事からスタートしないそうです。
仕事が入ってきたら時間を埋めるのではなく、あらかじめ自分で時間をコントロールし、予定を先に決めることです。
また「非生産的な時間を破棄する」ために取る方法は「止める」か「任せる」だと言います。
「任せる」でいい方法は「丸投げ」です。
「丸投げ」すると相手から質問してくるから教えやすく、時間がかかりません。
そうでなく手取り足とり教えると、受け身で聞くので、不完全になるのです。
最初に書きましたように今回のセミナーは「身になる話し」が聞けました。
そしてこの話を実践することが重要だと思います。
そのことは講師の皆さんも口をそろえて言っていたことです。
私も今日から始めます。
講座「身の丈起業のすすめ」
昨夜は私が担当しています講座「身の丈起業のすすめ」の最終講でした。
5回講習のうち最終講ではグループごとの「事業計画発表会」でした。
前回に参加者を4グループに分け、それぞれで1つの事業を決め、事業計画書を書いてもらいました。
昨日はその「事業計画」発表会でした。
この「事業計画」発表の目的は、「ビジネスプラン」とか「事業計画」と聞くと、とても自分には出来ない遠い世界のことのように思っている人に、「それほどでもない」と思わせることです。
実際に発表された「スープカレー店」「家庭農園」「喫茶店」「エコツアー会社」の「事業計画書」はそれそれ自分達の思いが込められたものでした。
このようにグループ単位で事業を考えることによって、「事業を考えることは楽しいこと」を実感してもらうことです。
実際にそのグループメンバー同士が意見を出し合うことで、互いの考え方を学び、事業計画を書き上げることで、次回に自分の事業を作ることが出来ます。
あるグループには経理経験者もいたので、周到な事業計画書を作り上げていました。
この事業発表を聞いて、共通して思ったことは、お客様の絞り込みが不十分である点です。
これは事業計画を立てる上で一番大切なことです。
しかし、このことはいくら講義で話しても、理屈として分かり、「そうか」で終わってしまいます。
でもこのように実際に事業計画を立てたあと、指摘されると、そのことが納得できるはずです。
この「身の丈起業のすすめ」という講義は今年の1月2月にも行い、今回で2回目です。
また来年の冬にも開講したいと思っています。
それにしても「人に教える」ということは、「人から学ぶ」ことでもあると今回も教えられます。
楽しい講座でした。
ルールを守る
セミナーや講演会に出席して、いつも気になることがあります。
それは定時になっても始まらないことです。
その内司会者から「まだ遅れている方がいらっしゃいますのすので、少々お待ち下さい」とのアナウンスがあり、5分、10分遅れで始まります。
遅れてくる人は時間を守るというルールに違反した人。
努力して時間を守った人が、守らなかった人のために待たされる。
それを優しさという人がいます。
そうでしょうか?
大分前になりますが、ある大企業の講演会の時のことを思い出します。
例のごとく定時になっても始まらず、司会者からの案内も無い時、突然講演者の永六輔さんが演台の前に立ち、これから始めますと話し出しました。
その時、あわてて司会者が出てきましたが、永さんはそれを無視して「時間になったら始める。それがルールです」の様な事を言ったのを記憶しています。
その言葉を聞いて拍手が起きました。
参加者の気持ちを代弁している思いがしました。
ルールを守るのは当り前。
守る人が損をして、守らない人が得をする。そんな社会になって来たのかと思います。
地下鉄そばの自転車置き場に置く人と、置いてはいけない地下鉄入り口周辺に置く人。
運動会の場所取りもルールを守る人、守らない人。
ゴミ出しのルールを守る人、守らない人。
色々ありますが、ルールを決めても守らない人に対する罰則が無いものだから、守らない人が得をする。
そんな社会に日本がなって来ました。
ルールを守ることは本来人間としての倫理観です。
倫理観の欠如でしょうか。
テレビで沖縄には「沖縄時間」があると言っていました。
始まる時間が定時より1時間遅れるのは当り前だそうです。
「いいじゃないの」という大らかさという考えもあります。
「許すことも優しさ」という考えもあります。
私は残念ながら馴染めません。
そんな人と約束をしようと思いません。
北の国と南の国。
経済に置いて南北問題があります。
その原因の一つにその気質にあるのかとまで思ってしますのは考えすぎでしょうか。
平均寿命100歳
先日テレビを見ていたら「平均寿命100歳時代が来る」という番組が流れていました。
途中から見たのですが、長寿を促す遺伝子が見つかり、100歳寿命も可能だとのことです。
その遺伝子は老化要因を抑える効果があり、アメリカでは既にそのサプリメントも売られ、大変な人気だそうです。
その番組では、あるアメリカ人はそれまで食事に気を付けていたけれど、そのサプリメントが出てからはそれを取れば平気だと、好きなモノを食べるようになった様子が映されていました。
平均寿命が100歳という現実は充分予想されることです。
ある統計では、日本は1900年の男女の平均寿命は44歳。
それが1999年には81歳になっています。
約100年で37歳延びたのです。
勿論、新生児や幼児の死亡率が減少したことも要因ですが、確実に平均寿命は増えています。
今後本当に平均寿命が100歳になるかどうかは別にしても、元気な高齢者が増えることは確かです。
今、年金問題から退職年齢の引き上げが論議されていますが、年金の問題ではなく、もっと別な観点からこれを論議しなければ、何もしない高齢者が増えるだけで、社会問題化する可能性があります。
単にボランティアや趣味に生きるだけでは、勿体ない。
60歳からの起業を謳う本も多く出ています。
私も60歳以上の人達の起業がもっと出てもいいと思っています。
アントレプレナーというと若い人の起業と思いがちで、現に公的支援もその考え方のようです。
60歳以上の起業は身の丈でいいのです。
自分の好きなこと、身の回りで興味あることから始めます。
そして万が一、将来事業が大きくなった時は、若い人に引き継ぐことで、高齢者の仕事は終わります。
60歳から新しいステージに立ち、事業を立ち上げ、それを社会に残していく。
小さくても多くの独立した人達が活躍する社会。
そんな高齢者社会なら、若い人達にも喜ばれ、参加意識が高盛ると思います。
「高齢者の増加⇒公的依存の増加⇒若い人への負担増⇒高齢者厄介者」という考え方にならない方策が長寿社会には必要です。
手堅い経営
昨夜は経営の勉強会がありました。
その冒頭に、幹事を代表してある製造会社の社長のあいさつをしました。
内容はその業界の現状を話です。
その会社はコロッケを中心に製造会社して、コロッケの製造としては国内で1,2位の生産量を上げています。
この震災よる影響で多くのモノが値上げしているようです。
フェリーの料金が大幅に値上げし、小麦粉などのコロッケ原材料も値上げしてきているそうです。
そのコストだけで1億円以上の増になるそうです。
それは1億円以上の利益が飛んでしまうことです。
また、コロッケ製造は冷凍管理が必要な製品なのにで、電力15%削減は影響が大きいそうです。
工場で15%削減しようとすると20%以上の削減を目標にしなければ達成できない数字。
しかし、工場は1回動き出すと簡単に止められないので、15%削減を守ろうとすると、生産量が大幅に下がる可能性があります。
ただこの会社は北海道が主力なので、この15%削減の対象から外れます。
それを武器に、7月に本州で始まる15%下電力削減に向け、他社工場の生産減を北海道で補うような営業をかけているようです。
それにしても今後、各分野、業界で物価の値上げが予想されます。
今までデフレで苦しんできて、インフレ期待がありましたが、急激にその現象が起きるかもしれません。
勉強会では稲盛和夫さんのDVDを見ての話し合いが中心でした。
15年以上前のDVDでしたが、その当時も今と同じように不況で、それを克服する方法について語っていました。
毎日毎日その日1日を懸命に仕事をしていくことが重要と稲盛さんは言います。
そうすれば明日につながり、次につながるのです。
それを一足飛びに、来月や来年のことを考えるからダメになると言います。
また、稲盛さんは自分のことを石橋をたたいて渡る、とても「ビビり」の性格だと言います。
だから1歩1歩ずつしか進めなかった。
それが手堅い経営になったそうです。
その様な経営をしていると不況時にも強い会社になります。
過去不況の時に京セラは伸びたそうです。
不況に強いということは、好況時ももちろんいいわけですから、京セラは増収増益の積み重ねが今を作っています。
毎日を懸命に努力する事こそ、経営の原点です。
当り前のことですが、心に止め置く言葉になりました。
日本とアメリカの農業
先日の新聞に「農地に流れ込むマネー」と題した記事がありました。
それによるとアメリカイリノイ州では1エーカー(約4000㎡)が8000ドル(65万円)の農地の出物があり、その売買のことが書いてありました。
8000ドルとは10年前の2倍の価格です。
その記事では「そんな高値では農業は採算が合わないと断った」とあります。
1坪を3.3㎡換算とすると、この農場は坪当たり540円です。それが高いのです。
それに対して日本の農地の価格は農水省の資料では、平成20年度全国の農地の平均売買価格は10a当たり田:144万円、畑:100万円となっています。
10aは1000㎡ですから約303坪。
坪あたり計算をすると日本の農地の場合、田:4750円、畑:3300円になります。
日本の平均農地価格はイリノイ州の畑と比べ6~9倍の価格です。
勿論日本の農地は簡単に売買は出来ません。
農地委員会の許可が無ければ売買が出来ませんし、そう簡単に許可されません
日本の農地は規制が多すぎる上に、アメリカとこれほどの価格差があるのです。
単に輸入規制をして農業を守るということがいつまでも続くのかと改めて考えさせられました。
アメリカの農業は「量」で日本の農業は「質」だと言われますが、それも限度があります。
日本の農業でも「量」、生産性を高めていくことは重要な方向性ではないでしょうか。
そして競争原理も必要です。
守りばかりだと衰退します。
衰退しているもう一つの例が林業だと思います。
林業は営林署などで国に管理された為、自然は残りましたが、山は荒れてしまいました。
木材価格も高く、外国モノに押されています。
この分野も見直しが必要です。
今の日本は色々な分野で、競争規制をし、守られた過保護社会の社会なのです。
製品の転用
今朝テレビを観ていたら面白いモノが紹介されていました。
それは「シュレッダーハサミ」です。
テレビをご覧になった方もいるかもしれませんが、それは私にとって「なるほど」と思わせる製品誕生でした。
刃物の街、新潟県三条市にあるアーネストという会社の製品です。
その社長の話では、最初は「刻み海苔」を作るために作られたハサミでしたが、あまりブレイクしなかったそうです。
その同じハサミをシュレッダーとして売り出したところ、100万本も売れて大ヒットしているそうです。
確かに文房具コーナーに行くとこの商品は大体置いてあります。
そのシュレッダーに転用した経緯は「お客様の声」からだそうです。
あるお客様から「私のところではシュレッダー代わりに手軽に使えてとても便利」との言葉です。
それをヒントに「刻み海苔」用ハサミを「シュレッダーハサミに」転用しました。
製品に手を入れることなく、「使い方を変える」だけで、売れたのです。
昔、レナウンが発売した「通勤快足」という大ヒットした靴下がありました。
これも最初は違う名前で売られていましたが、売れ行きはよくありませんでした。
それを「通勤快足」というネーミングに変えた途端、大ブレイクしました。
これも製品はほとんど変わらす、名前を変えただけです。
仕事熱心な経営者は、自社製品を一番知っているという自信を持っています。
しかしそれは一方向からしか見れない固定概念を生んでいるのかもしれません。
常に柔らかい頭を持つための努力は必要です。
私も時々使っているモノをご紹介します。
知っている人も多いと思いますが「オズボーンのチェックリスト」です。
下記に紹介しますので、頭を柔らかくするために皆さんも使ってみたらいかがでしょうか?
記
オズボーンのチェックリスト
◆転用したら?
現在のままの新しい道は?
◆応用したら?
似たものはないか?真似は出来ないか?
◆変更したら?
意味、色、動き、臭い、形を変えたらどうなる?
◆拡大したら?
大きくする、長くする、頻度を増やす、時間を伸ばすとどうなる?
◆縮小したら?
小さくする、短くする、軽くする、圧縮する、短時間にするとどうなる?
◆代用したら?
代わりになる人や物は?材料、場所を変えられないか?
◆置換えしたら?
入れ替えたら?順番を変えたらどうなる?
◆逆転したら?
さかさまにしたら?上下左右、役職を逆にしたら?
◆統合したら?
合体、混ぜる、あわせたらどうなる?
事業の顧客は誰?
昨日のブログで「身の丈起業のすすめ」という講座について書きました。
どのような起業でも大事なのは何を、誰に、そしてどのように売るかを押さえることが大切です。
会社経営とはそれを競い合うもので、それが収益に結びつきます。
言われるまでも無く、当り前のことです。
でもNPOは少し違うのかもしれません。
すべてのNPOがそうだと言えば叱られるかもしれませんが、「誰に」という顧客が一般企業と違うようです。
NPO法人にとっての顧客は官庁なのかもしれません。
昨日、ある団体のNPO法人化についての話し合いがありました。
その話のメンバーの中に、既にNPO法人を立ち上げ活躍している人がいました。
彼は、国・北海道・札幌市等の補助金事業については大変詳しく、彼のNPO法人でも今まで多くの事業に参加し、実績を上げています。
彼はその事業の申請方法も、認可されるポイントも熟知しいて、申請して8~9割は認可されると言います。
彼のNPO法人は完全に補助金事業に特化して活動しています。
そのようなNPO法人にとって、顧客は官庁です。如何に事業を獲得するかの工夫は官庁との良好な関係にかかっています。
NPO法人は補助金事業を受け、その事業を実施します
それに参加してきている人達には、「それなり」にこなせばいいと思っている人もいます。
特別素晴らしい結果が出なくても、その事業の目的さえ果たせればいいのです。
極端に言えば参加者はお客様ではないのです。
例えば就業支援事業の場合、何とか認可を受けて、パソコン教室を事業として開始し、参加者を集めます。
参加者はある意味、行かざるを得ない状態で参加する人が多いです。
事業を開催する側も事務的に時間をこなす様な教え方でもいいのです。
すべてのNPO法人がそうだと言いませんが、多くの法人が補助金事業に主力を置いているようです。
そしてそれが収益の大きな源泉です。
私は補助金事業に関わったことがありませんので、このよう状況は若干違和感を感じます。
民間企業が汗水たらして稼いだお金が税金としてこの世の中の役に立っているはずです。
その税金を使った補助金事業でまた収益活動をしているということに違和感を感じました。
官庁は補助金事業を行えば仕事した気になり、それを受ける側は官庁への申請をいかにうまく通すかに力点を置きいて、事業を獲得し、その事業で開かれる就業支援講座に参加すればお金がもらえるから参加する人がいます。
NPO法人も官庁職員も税金を支払っていると言いますが、その元は民間企業が作りだした利益から支払われた税金です。
だからと言ってNPO法人がダメだと言っているわけではありませんが、なんとなく釈然としません。
また、補助金事業頼りにしているのはNPO法人ばかりでなく、一部の民間企業もあります。
どちらにしても、私とは違う次元の話のように思えてきました。
立つ位置
今日は朝からスープカレーを食べました。
なかなか美味いスープカレーでした。
このカレーは昨夜の講座「身の丈起業のすすめ」の受講生からいただいたものです。
昨夜の講座は「事業企画書」の作成で、受講生を4~5人のグループ分けにして、それぞれで具体的な事業を決め、それの企画書と収支計画書作りを行いました。
その中の1グループで「スープカレー店」を企画することになったのです。
他のグループでは「家庭農園経営」とか「エコツーリズム会社」等面白い業種を企画しています。
来週が最終日で、各グル―プからそれぞれの事業企画をプレゼンテーションしてもらうことになっています。
身の丈起業で起業しても、他の起業と同じように成功しなければなりません。
起業しても同じような業種の会社や店は数多くあります。
例えば「スープカレー店」もそうです。
札幌には有名な店も多くあります。
その中で生き抜くためには、最初に自社の「位置づけ」を決めておかないといけません。
いくら美味しいモノを出していると言っても決めるのはお客様。
客観的に「特段に美味い」「美味い」「普通」の中で「普通」なのに、作る側が「特段に美味い」と思いこむと失敗です。
また、「美味い」程度の店は結構あります。
そうすると今度は所得や年齢等で対象層を絞り込んでいかなければなりません。
例えば高齢者が多い地域でしたら、思い切って「デイケアセンター」的な集まりの場を提供すれば、昼食をはさんで人が集まるお店になるでしょう。
ただ、店の回転数が悪くなりますので、その対策は必要ですが。
また、集客方法についてもその対象層を絞り込むことでやり方が違ってきます。
起業する時大切な事は色々ありますが、その「立つ位置」を客観的に認識することは、つい忘れがちになりますが特に重要なことだと私は考えます。
自然のモノ
今年の夏は電力不足から暑さ対策が色々報道されています。
着る物ではクールビズ、スーパークールビズと簡易服装が推奨されています。
また機能性肌着も各メーカーから発売されているようです。
良く見てみると吸汗性が高い、接触時の冷感が高い、また消臭・抗菌防臭性が高いとか謳われています。
確かに従来の綿製品では、汗でべた付き少し不快感はありました。
今年はその機能性肌着などが沢山売れていくのでしょう。
ただ私は、従来からの綿製品にこだわりたいと思っています。
機能性肌着はほとんどがナイロンやレーヨンの化学繊維で作られています。
それが肌に直接触れるのですから、あまり体にいいとは思えません。
それより綿や麻の自然の素材を使って、織り方も縮みの様にし、ゆったりした下着の方が体にいいように思います。
現代は機能性を求めるあまり、化学製品が多過ぎるように感じます。
住宅も以前は壁紙は漆喰塗りや板張りでしたが、今はビニールクロス貼りがほとんどです。
床材は数年前まで、何とか自然材のフロアーでしたが、これも現在は化学シートで覆われています。
確かに安く、傷は付きにくくなりましたが、部屋の中は天井・壁・床全てが化学製品で出来あがっています。
そんな中、自然のモノに引かれて行くのでしょうか。
昨日、起業家の集まりである「サポスポ起業家交流会」があり、そこで木材のセミナーがありました。
秋田杉 青森ヒバ 木曽檜をはじめ、クルミ材、外国産のクルミ材であるウォールナット等の説明を受けました。
特に杉やヒバ、檜にはフィットンチッドという物質が含まれており、それは癒しの効果があるそうです。
森林浴をすると気持が良くなるのもその成分の効果だとのこと。
木は傷付き、腐るものですが人に癒しを与えます。
木の住宅は、湿度が高い時は室内の湿気を吸収し、空気が乾くと湿気を発散させるそうです。
このセミナーで自然に囲まれる生活の良さを改めて認識しました。
日本では今年は檜が不足するそうです。
全国の神社の建て替え時期が重なってきた為とのこと。
以前は台湾檜も輸入されていましたが、今は輸出禁止だそうです。
益々、人間と自然について考えさせられました。
半額北海道
昨日若い起業家が来ました。
起業家といっても既に5年経過しています。
彼の名前は柵山 充さんで、22歳の大学生の時に起業していますから今は27歳でしょうか。
株式会社ネクストシェアを経営し、「コツコツ開拓くん」という商品で各企業の販路拡大の手伝いをしています。
5年の会社経営の間には紆余曲折がありましたが、めげずに頑張っています。
昨日来社されたのは新規事業を始めるとの報告でした。
その事業は「共同購入型クーポンサイト」の「半額北海道」の立ち上げです。
ご存じの方も多いと思いますが、「共同購入型クーポンサイト」とは、例えばあるレストランでは、5000円のディナーコースを出していて、これに対し100人のユーザーが購入したいと手を上げた場合、店舗側が50%引きの2500円で提供するようなイメージです。購入はクレジット決済によって行われ、最低購入者数を満たした時点で取引成立となります。
現在アメリカ発の「グルーポン」が先行していて、大きなシェアを持っています。
「半額北海道」の本体は「半額東京」です。
「半額東京」の主要株主には堀江貴文さんがいます。
堀江さんはご存じの通称「ホリエモン」です。
現在は有罪が確定したので、収監待ちの状態だそうです。
「半額北海道」は今月の18日に正式に立ち上げします。
その時は堀江さんも来札して記者会見をするそうです。
ただし、収監前という条件付きですが・・・
「半額北海道」という新規に事業を立ち上げることは大変なことだと思います。
先行する競合会社と戦いながら、参加企業・店の勧誘や、購入希望者増加のための告知活動等やることが沢山あります。
それでもこれは、若い起業家がより成長するための重要なステップだと思います。
私も出来るだけ支援は続けていき、成功することを祈っています。

他知る、自知る
今朝出勤前につけたテレビで興味深いことを紹介していました。
外国人にとって、日本の「折りたたみ傘」がお土産として人気があるとのことです。
軽くて、小さいのに丈夫ということでお土産の定番になっているらしいです。
その番組では、折りたたむということに焦点を合わせて外国人に喜ばれるものを紹介していました。
日本の「折りたたみ携帯」も「キュート」らしいです。
「折りたたみ物干し」も外国人にとっては驚きの様です。
観光客が持っている「折りたたみ式の地図」も人気があります。
アメリカ人が言うには、アメリカでも日本の布団がたためるということで使う人が増えていると言っていました。
日本人にとって当り前のモノが、外国人にとっては興味あるものに映るのです。
その逆も言えます。
人は毎日の生活の中で当り前と思われることが、他人にとっては面白いモノ、興味深いモノに見えることに気付かないのです。
異業種交流会に出席するということは、この自分と違う人の考えや、行動を知ることと同時に、気付かない自分の良さも発見することなのです。
異業種交流会と言えば自分の商売に結び付けようと思って参加する人が多いのですが、折角の発見の機会を見逃しています。
異業種交流会は「他知る、自知る」機会のなのです。
(「他知る、自知る」は私の造語)
外国人との接点を持つのも大切です。
英語学校で行われる、部外者も参加出来るパーティーなども新しい出会いの場ではないでしょうか。
その異業種交流会や、外国人とのパーティの交流の場に立った時、大切なのはやはり「素直な心」でしょう。
それが無ければ、話の中に飛び込んで行くことが出来ません。
そして話を聞き、相手を知ることが出来ません。
出会いの場を多く持つことは仕事ばかりでなく、人生を豊かにしてくれるはずです。
北海道観光
札幌はライラックが満開で、昨日までライラック祭りがおこなわれていました。
ライラックは別名リラとも言います。
花言葉は「白色は年若き無邪気さ青春の喜び」、「紫色は恋愛のはじめての喜び」だそうです。
北海道は今、春真っ盛り。多くの花が咲いています。
「YOSAKOIソーラン祭り」も8日から始まります。
その後北海道神宮祭そして7月には「サッポロ・シティ・ジャズ」「カルチャーナイト」と続きます。
北海道の観光行事が目白押しです。
その北海道も震災後から観光客が激減し関係者は大変な思いをしています。
しかし、一方これからは北海道の観光が回復する可能性も大です。
震災の影響が少ない北海道ということで、海外、特に台湾・中国からの観光客が戻る気配があります。
また、震災のため電力不足が懸念され、今年の夏の暑さ対策として、北海道への国内観光客増加が見込まれます。
北海道庁は「COOL北海道」というキャンペーンを掲げて活動しています。
宿泊施設の夏の予約状況は数字を掴んでいないのでわかりませんが、伸びていると予想しています。
今朝の新聞に西武ホールディング社長の話が載っていました。
「節電を迫られる今夏は長期休暇や平日休暇を導入する企業も多く、予約がすごい。7月分は軽井沢が現時点で前年比4割増で、箱根も2割多い」と話しています。
そのことからも北海道も観光客の増加は十分見込まれます。
北海道に来る修学旅行も前年より増ているという話も聞きます。
北海道に本格的な夏を迎える頃、景気のいい話が増えてくることを期待しています。
シンプルライフ
今、私はシンプルライフにあこがれています。
ドミニック・ローホーさんが書いた「シンプルに暮らす」を読みました。
下重暁子さんの「持たない暮らし」も読みました。
共に必要なモノしか持たないし買わないという考えです。
時々は私も思いっ切って周りにあるモノを全て捨てるくらいに整理をして、身も心もリセットしていと思います。
シンプルに暮らすとはモノが無いこと。本当に気に入ったものだけを傍に置く。
必要のないものなら、たとえ高いものでも捨ててしまう。
そしてモノを買う時は、必要と思えるものを選び、熟考して買います。
傍に置くモノは飽きの来ないないものだけを置きます。
そうすれば今、私の周りにある本や、家電、道具などは一気に3分の一くらいになってしまいそう。
食べるものも、本当に美味しいものを食べます。
それも量は多くは食べない。
ドミニック・ローホーさんの「シンプルに暮らす」にも書かれていましたが、沢山食べてしまうと、本当に美味しいか分からなくなってしまうのだと思います。
バイキング料理で食事をした後の感想は、沢山食べて満足したけれど、何が美味しかったか良く分からなかったと思うことがあります。
それは食欲を満たすために多くの量を食べた為です。
美味しい松坂牛を食べ放題で食べて、美味しいと思うでしょうか。
それより1枚の肉を、落ち着くレストランで友人とゆっくり味わいながら食べる方が、本当の肉の味が分かるのでゃないでしょうか。
「必要なモノを必要な分だけ」というシンプルライフはエコな生活でもあります。
シンプルライフは安物を買いませんから、お金はかかるかもしれません。
洋服も、限られた同じような服を着ますから、コーディネート力が必要でしょう。
それでも自分がシンプルに暮らすことは、素直な本当の自分を表現することになるのかもしれません。
60歳を過ぎたらそろそろ、周りを整理していかなければならない年代です。
私も少しずつ始めていこうと思っています。
ただ、1つのネックは、私の貧乏性です。捨てるということに抵抗があります。
これを乗り越えることは大変です。
乗り越えることに努力していますので、これから本当のシンプルライフへの道が開かれると思っています。
少年よ大志を抱け
北海道に生まれ育った者にとって、クラーク博士の「少年よ大志を抱け」という言葉はなじみ深いものです。
この言葉を聞くたびに胸が高まる思いがします。
特に若い時は「無限な可能性がある」という思いはしましたが、同時に無限に何もないということも知らされたように思います。
私もこの言葉を知ってから、自分の「大志」とは何かを求め続けてきたように思います。
このクラーク博士の「少年よ大志を抱け」に続く言葉があります。
「しかし、金を求める大志であってはならない。利己心を求める大志であってはならない。名声という、つかの間のものを求める大志であってはならない。人間としてあるべき全てのものを求める大志を抱きたまえ。」
となっています。
これを読むと、尚のこと大志とは何かと悩んでしまいます。
いっそ「大志」を「野心」に置き換えてもいいのかもしれないと思います。
「お金を求める大志であってはならない」とか「利己心を求める大志であってはならない」とのクラーク博士の考えには反するかもしれませんが、若い内は「野心」を持っていくべきだともいます。
そうでなければいつまでも「大志」とか「使命感」とか追い続けるだけで、何もしない人生になってしまいます。
私がそう感じたのは40歳代のなった頃からです。少し遅かったです。
「野心」を持った人は年齢を重ねても精神がいつまでも若いです。
そういう人は年を取っても老いは認めようとしません。
老いを認めた時から老いは始まるのかもしれませんん。
時のは「労害」といわれますが・・・
人は生まれた時から死ぬまで、何かをするために生まれてきました。
新約聖書の中に「われらはこの世に何も持たずに生を受け、また、何も持たずにこの世を去って行く」とありますが、死ぬ時は生まれた時持っていた肉体さえもこの世に置いて行かざるを得ないのです。
それならばこそ、この世に生れて来た意味を知って、「野心」でもいいから、何かをやって見ることが大切。
何かをして一生懸命生きて行けば、その中で心が磨かれ、「野心」が本来の「大志」に変わって行くのではないかと考えます。
肯定思考に変える
日常生活や仕事の中で、うまくいかないことが時々起きます。
何事でもうまく行けば、肯定的に考え、うまく行かなければ否定的に考えてしまいます。
しかし、一方では肯定的な考え方を持たなければ成功しないとも言われます。
実際に仕事をしていて、なかなか芽が出ないと、どうしても「もうダメかもしれない」と思ってしまいがちです。
いくら、「肯定的に考えないと成功しない」と言われても、否定的な考えばかりで、肯定的な考えは浮かんできません。
言葉に出して肯定的になろうとしても、頭の隅で、「そうじゃない。うまく行くはずはない」という否定の思いが強くなります。
それではどうすればいいのか。
1つ方法があります。
私もしていることですが、問題ある事柄から一旦離れ、別のこと、それも小さくて実行出来ることを始めます。
たまっていた雑用や、身の回りの整理をしてみるのです。
1つずつ解決していくにつれて、小さな自信が生まれます。
この小さな自信の積み重ねが大切です。
この小さな自信を多く持つことで、改めて問題に対した時、以前より自信を持って肯定的な考え方が持てるようになります。
この肯定的な考え方が出来るようになると、積極的な行動を取り始め、その行動の中から少しずつ成果が生まれ出します。
否定的な考えをしている時、それを肯定的に変えようと意識すればするほど、否定的な考えが強くなるようです。
別なことで自信を付けることは、自分の頭を誤魔化しながら、いい方向へ導く1つの方法です。
のめり込んでいたことから一度離れてみると、のめり込んでいた時に気付かなかったことが見えてくることがあります。
凝り固まった頭の思考を切り替える1つの方法です。
逆命利君
近頃テレビ・新聞では内閣不信任等の記事でいっぱいです。
民主党内では菅陣営か小沢陣営かで議員が行ったり来たりしているようです。
そんな時「面従腹背」という言葉が浮かびました。
「面従腹背」とは、うわべだけ上の者に従うふりをしているが、内心では従わないことを意味します。
まさに今の政界はそのような世界なのかもしれません。
この「面従腹背」に似ているけれど、意味が全く違う言葉があります。
それは「逆命利君」です。
中国の「説苑(ぜいえん)」に書かれて言葉です。
「命に従いて君を利する、これを順(じゅん)となし、命に従いて君を病ましむる、これを諛(ゆ)となし、命に逆らいて君を利する、これを忠と謂(い)い、命に逆らいて君を悩ましむる、これを乱と謂う」
「逆命利君」は「名に逆らいて君を利する、これを忠と謂う」のことです。
私がこの言葉を知ったのは、大分昔に佐高信さんの「逆命利君」という本を読んだ時です。
上に書いた言葉はその本からの抜粋です。
この本によれば「逆命利君」は住友の初代総理事、広瀬氏が良く使った言葉だそうです。
そして「逆命利君」という小説はその現代の住友商事に実際にいた人物を主人公にした経済小説です。
興味ありましたら是非読むのをお勧めします。
「面従腹背」のように、従っているようでいてそれに反するような行為をする人が多い世の中で、「逆命利君」は意味のある言葉のように思います。
逆を言えば、上に立つ者は部下からの忠言はきちんと聞かなければならないということも意味しています。
トップとナンバー2との間もそのような関係が必要とされます。
会社が収益を上げるということ
このブログの中で、何回かお金を稼ぐことに関して書いてきました。
また何日か前には、会社の中に評論家やコメンテーターは要らないとも書きました。
民間企業で働く以上は収益を上げる、すなわち如何にお金を稼ぐかが問われるべきです。
勿論その前に人々に喜ばれるザービス・モノを提供することが前提です。
先日盛和塾からの会報を読んでいましたら、稲盛和夫さんが日本記者クラブで話した内容が載っていました。
題名は「日本航空の再建及び日本の再生について」です。
その中で、紹介されていたことです。
JALは幹部を集め、意識改革セミナーという勉強会を定時後や休日に1カ月以上にわたって集中的に行いました。
時には稲盛さんも講義を行い、どういう意識を持たなければならないか、どういう使命感と考えを持たなければならないかということを話しました。
セミナー後は缶ビールとつまみを買って侃々諤々の議論をしたそうです。
その中で稲盛さんがびっくりしたことが書かれていました。
「JALの幹部達が、企業が利益を出すことに対して、罪悪感に近いものを持っているということ。航空運輸業は安全が何よりも大事であり、利益ということを口にすることでも卑しい思いがするという幹部が沢山いました。」
幹部が企業経営という考え方を持たないからこそ、JALは破たんしたのでしょう。
大企業と言われる会社の幹部にはそのように利益を出すことに罪悪感を持った人がいるのでしょうか。
断言できませんが、マスコミ、特に新聞社の中にはそのような考えを持った人達が多いかもしれません。
どうしても、新聞報道を読んでいると、しっかり稼いでいる会社より、「お客様のため」との口実で利益も出ず、苦しい経営している会社の方を評価して取り上げていることが多いようです。
利益を出し、従業員を雇い、給料を払い、税金を支払います。
従業員に支払った給料からも税金が源泉徴収されます。
会社が出した利益から税金が支払われ、今の日本を動かす源泉になっているのです。
如何に「お客様のため」とは言っても、利益を出さない会社は決して評価されないと私は思います。
この事を忘れると、お客様のためと言いながら、単に自己満足だけで、何も生まれません。
最近気になることでした。
パートナー
今日はパートナーについて書いてみます。
パートナー探しと言えば結婚でしょうか。
良き伴侶を得ようとしますが、よき伴侶とは何かという問題があります。
しかしほとんどの人は理屈で考えるより、心・感情で相手を選びます。
その結果、結婚してから思わないことも起きるのです。
要は「心構え」だと思います。
三輪明宏さんが言っていました。
「恋愛は夢。結婚は現実。結婚式は夢から現実への儀式です。」
結婚式はこれから始まる現実生活への「心構え」の儀式なのでしょう。
もう一つ重要なパートナーは会社で言えば社長に次ぐナンバー2の人です。
一般的には副社長や専務という地位にあるかもしれません。
時には参謀的な役割をしますが、参謀は指示命令権を持たないですから、厳密には違います。
昔の武将で言えば秀吉と弟の秀長の関係。
現代では本田宗一郎と藤沢武夫、松下幸之助と高橋荒太郎・井植歳男等の関係でしょうか。
パートナーとしての心得は参謀の心得に似ています。
司馬遼太郎の本「坂の上の雲」で東郷平八郎が参謀である秋山真之に対し、参謀たる者の心得を説いています。
「参謀の要務というのは、円転滑脱として上と下との油にならなければならない。功名を断じて顕してはいけない」
即ち上下間に入って円滑になるよう油のような役目をし、決してトップに代わって名を上げようと思わないことです。
野心のあるパートナーと組むと会社が乗っ取られてしまします。
会社でも社長とパートナーとしてのナンバー2との関係も結婚と同じように「心構え」が必要なのです。
有能なナンバー2ほど野心が強いと思われます。
経営者はコメンテーターではありません
世の中では毎日のように事件・事故・災害が発生しています。
新聞、テレビではそれに対しての評論やコメントが多く出ています。
専門外のタレントまでもがコメンテーターとして評論し、それなりの影響を与えています。
彼らは「良いか悪いか」「○○だからダメなんだ」ということは言えますが、それならどうするのか、具体的に適合性ある解決策があるのかというと出てきません。
扇動的発言は多いかもしれませんが、責任ある発言はあまり見受けられません。
一方、起業、会社経営となるとそうはいきません。
起業する前は第三者的な発言で、「これはいけない」とか「こうするべき」とか言えても、実際に起業し会社を経営するとそれだけでは済みません。
実際に行動し、結果に対して責任を負わなければなりません。
起業する時に最初に意識変革しなければならないのはこの点なのかもしれません。
サラリーマンの時は、評論家やコメンテーターのように経営陣のやり方を批判しても、周りからはそれなりの考え方を持っていると思われました。
しかし、実際に重い責任を負って実行するかとなると、そうはいきません。
その境目が重要なのです。
日本人総コメンテーターと言われる今、付和雷同に流されず、自分を見失わない考え方と具体的行動のあり方を身に付けておかなければならないと考えます。
そのような訓練をするのも起業準備とも言えます。
経営者は常に現実問題に直面し、それに対するベストまたはベターな解決策を考え、行動し、最終責任を負っています。
常に真剣勝負の世界なのです。
技術・技能を売る商売
昨夜はある英語学校のパーティーに参加してきました。
知人もいて楽しいパーティでした。
参加していた外国人講師は6~7人ほどです。
学校の経営者と話をしたところ実際の講師数は23名ほどで、その人件費を支払うのが大変とこぼしていました。
この学校の仕事は会話教室の他に、翻訳や同時通訳や来日者のアテンド等があるそうです。
しかしその仕事の請負金額は年々下がっていると言います。
同時通訳などは以前1時間5000円で請け負っていたのが、今は980円とのこと。
信じられないほどの低さです。
その理由を考えてみました。
以前は今と比べ、外国語を話す日本人が少なかったので、通訳や翻訳という仕事が重宝されました。
しかし今、来日して日本語を話せる外国人も増え、また外国語を話せる日本人が増えました。
英語などの教材の開発・販売や、外国語教室の増加などもそれを後押ししているのでしょう。
英語を学ぶ人が増えると、一方では通訳などの報酬額が減るという相反する作用が起きています。
このような状況が生まれるのは技術・技能を扱っている他の業種で起きやすいものです。
以前私も関心がありました家具修理の仕事もそうです。
ある高い技術を持った人が会社を作り、社員にその技術を教えて家具修理の業務を拡大しようとしました。
その経営者は一生懸命になって全ての技術を教えたのです。
しかし、技術を習得した社員は勤めるよりは独立してもっと稼ぎたいと思い、自分で家具修理の仕事を始めました。
そのような社員が増えることで結果、競争相手が増え、収益も下がって行きました。
技術系の会社で、その技術で商売をする会社では起きがちな問題です。
その為、経営者は競争相手を作らない為、社員を少なくし、結果規模の小さい経営になってゆきます。
勿論、技術で商売する会社の全てがそうかというとそうではありません。
数は少ないですが、しっかり管理システムを作り、従業員100名以上、売上何億という会社も存在します
そこには経営者の思想があります。
最終的にはその経営者の考え方にかかっています。
今度改めてこの事については書いてみたいと思います。
モノを買う口実
昨日は琴似神社の春祭りでした。
琴似神社のお祭は春と秋の年2回あります。
秋は本祭りと言って2日間続きますが、春は1日です。
昨日は金曜日ということもあってか凄い人出でした。
綿菓子やチョコバナナ等の出店が1kmは無いと思いますが何百mも続いています。
昨夜は知人との飲み会が琴似であり、帰ろうと店を出ると身動きが取れないほどの人です。
3m以上の幅のある歩道には人が溢れ、はみ出して車道を歩く人も多くいました。
これほどの人出を相手に、出店の売上は凄いものだろうと予想します。
出店で売っているモノは決して安いものでなく、綿菓子など600円もしています。
材料のザラメは10円もしないでしょうからほとんどが利益です。
それでもみんな喜んで買って行きます。
なぜでしょうか。
お祭の日は特別の日だから、「少し高くてもいい」という「自分に対する口実」が成り立つからだと考えます。
楽しいことなら尚のことです。
観光旅行へ行って、今日は特別だからと言って土地の美味しそうなものや少し値の張る旅館に泊まったりします。
それも特別だからと言いう「自分に対する口実」があるからお金を出すのです。
商売を考える時、お客様に特別だからという口実を作らせる仕組みを作るのも1つのセールステクニックなのです。
それにしても、出店で売られている食べ物は不衛生な気がします。
チョコバナナを売っているお兄さんは、くわえ煙草をしながらチョコバナナを作っていました。
その煙草の灰が落ちそうにいなっていました。
最後まで見ていませんでしたが、きっと落ちたでしょうね。
益々私は出店では食べ物を買いたいとは思いません。
それでも良く売れているのには、改めて感心します。
喫茶店+〇〇
昨日、知人と四方山話していた時に出た話です。
彼はパソコン教室を各地域で開き、また個人指導も行っているそうです。
1か所の場所を教室にしているのと違い、毎日東奔西走しています。
移動するだけでも時間がかかります。
と言って教室を持つとそれだけで固定費がかかり、生徒集めも大変です。
それならば何かとコラボすればと考えました。
それは喫茶店です。
彼はコーヒーも好きな人で、喫茶店経営も夢にあったそうです。
コラボの内容は、その喫茶店の一部を壁で仕切ってパソコン教室にするというものです。
喫茶店は、昼はランチで忙しいですが、2時以降は暇になります。
その間帯に生徒数人がノートパソコンを持ち込んでレッスンを受けるのです。
喫茶店がパソコン教室とコラボした形です。
備え付けのデスクトップは用意しません。
しないのは投資コストがかかることと、その場所が飲食の個室利用として使われることもあるからです。
また、生徒側も自分のノートパソコンを持ち込んで学ぶ方が、自宅でもそのまま復習も出来ます。
喫茶店は考えて見ると色々なモノとコラボできます。
「喫茶店と+ペットショップ」、「喫茶店+床屋」、「喫茶店+針・灸・指圧」等。
そう言えば、私の系列会社が今度「喫茶店+家具+住宅」の新形態カフェを展開するとの計画も聞きました。
自社が建てた南欧風の建物に自社で輸入した家具を並べ、コーヒーを出します。
そこがショールーム兼カフェです。
一時はドトールやスターバックスで個人経営の喫茶店が淘汰されたかのように思われましたが、そうではないのです。
これからは喫茶店の新しい業態が生まれてくるかもしれません。
「人相」と「店相」
今、若い人を中心に占いが流行り、占いサイトや、占いのテレビ番組は人気あります。
姓名判断、手相などがありますが、「人相」というのもあります。
「人相」は人と会った時受ける「感じ」に似ているのかもしれません。
私も過去に人事採用で何百という数の人と面接しましたが、その人の第一印象で、多くの評価が決まったように思います。
店舗にも「人相」と同じように「店相」というのがあるようです。
流行らない店に行くと、何となく寒々として、活気が無いのが分かります。
逆に、流行っている店に行くと、何となくほのぼのしていたり、楽しかったりします。
そこの働く人達のサービスや気遣いもあるのでしょうが、それとは別に店そのものから受ける「感じ」が違います。
「人相」では福耳と言って大きくて耳たぶの豊な耳が良いとされます。
鼻は大きくて小鼻が張っているのがいいそうです。
店にも同じことが言えるのかもしれません。
昔聞いた話ですが、あるところにお客があまり入らない家具店があったのですが、その店は毎月のように赤字続き。
その店長は一生懸命営業をし、顧客管理にも力を入れていたのですが、店先にはお客様がいません。
社長は思い切って、店長を変えました。
新しい店長は若い上に、前の店長ほど営業力はありませんでした。
でも、気配りのある人でした。
新店長が最初にしたことは店の掃除です。
徹底的に店を磨き上げ、毎日暇さえあれば掃除、窓ふきをしていました。
そうすると内装はほとんど変えていないのに店が明るくなって来たました。
「店相」が良くなったのです。
その明るくなった「店相」に引かれてお客様が徐々に増え始めました。
そして、その店の売上もそれに比例して伸び、黒字になって行ったそうです。
人も店も人を引き寄せる「気」があります。
その「気」を上げる為にすることは、人も店も同じなのです。
流行っている店は確かにいつもきれいに清掃されています。
売上が伸びなくなったら、店先に「打水をしなさい」と言われます。
それも「気」を上げる一つなのでしょう。
ABC分析
ABC分析というのはご存知でしょうか?
販売会社や飲食関連の会社なら良く使われる商品販売管理法です。
私も以前和食堂の店長をしていた時は、販売会議でこれをもとに売上検討をしていました。
飲食店を例にすると、ABC分析とはメニューごとの売上を計算し、総売上に占める割合(売上高構成比)を算出します。
その結果、全体の75%を占める商品がA商品。 全体の20%を占める商品がB商品。 最後の5%を占める商品がC商品となります。
Cグループの商品は「死に筋メニュー」であり、メニューから外されます。
常に新メニュー開発されますが、このABC分析の結果で、残るメニューと外されるメニューが出てきます。
効率を求めるチェーン店は特にこの傾向が強いと思われます。
私は今は飲食関連から離れていますので、わかりませんが今も使われていると思います。
以前はとてもよく使われていましたが、今考えるとその弊害もあったように思います。
居酒屋に行ってそのメニュー表を見た時、多くの居酒屋のメニューは代わり映えしない、どこも同じように思えるのです。
極端に言えば「つぼ八」のメニュー表を「いろはにほへと」に持っていっても分からないくらい似たメニュー内容です。
それはABC分析によってもたらされた「現象」だと考えます。
各飲食会社はABC分析をして、売れ筋のAランクBランクのメニューを残し、Cランクのメニューをリストから外してゆきます。
そうすると必然的に各飲食店や居酒屋のメニューが似たものになってしまいます。
結果お客にその店自体が飽きられてしまうことになります。
これは飲食店や居酒屋がマンネリ化に陥るパターンです。
そうなると、その店としてはメニュー以外の立地やサービスで競争になってきます。
今はサービス競争の時代とも言われます。
今まで当り前だと思っていた手法が、知らない間にその店の独自性や、特徴を取り去っていたのです。
それならば逆を行って、それほど数多くは売れないけれど、こだわりを持っているお客様がいるようなメニューを残していけば、他にない特徴あるメニュー構成になるのではないでしょうか。
時には変わったメニューのある飲み屋に行きたいと思うのは私ばかりではないと思います。
皆さんはいかがですか?
紙芝居
小さい頃紙芝居を見た人も多いと思います。
私も紙芝居屋が来ると見に行きました。
でも紙芝居のおじさんは飴を買わないと傍で見せてくれません。
私の親は飴を買うお金をくれなかったので、しかたがなく遠くから見るしかありませんでした。
そのためストーリーはあまり分かりませんでしたが、それでも拍子木の音が聞こえると飛んで行きました。
昨夜はその紙芝居を久しぶりに見ました。
昨夜は以前私が講師をした「身の丈起業のすすめ」に参加した人達が集まっての読書会でした。
参加者のうち5人が自分の紹介したい本をそれぞれのやり方で感想を話してくれます。
その中で特にHさんという女性の話しは驚きでした。
彼女の読書感想は10枚上の紙芝居形式にしてものです。
彼女が本を読み、それから紙芝居形式に絵を創作し描いたのです。
本の中に出てくる人物の心理的描写まで描かれて、すばらしいの一言でした。
読書感想を紙芝居にしようとする発想力、絵に描く想像力・創作力は大変素晴らしい才能です。
このように身近にいる人が思いがけない才能を見せてくれると、驚きより感動になります。
現在彼女は普通のOLとしての仕事をしています。
その才能を生かした仕事はしていなようです。
それを生かす機会が無かったのか、本人がその気が無かったのか分かりませんが、何とかしてその才能を生かしてあげたいと思いました。
読書会ではその他に、ある女性は自分が投稿して掲載されている本を紹介してくれたり、また別の女性は演劇の演出家という別の顔を見せてくれました。
昨日の読書会は従来考えていたものと違う、新しい刺激を与えてくれました。
これからもこの読書会に参加したメンバーから刺激と気付きがもらえること、楽しみです。
論語と算盤
昨日ブックオフでのことを書きましたが、その時買った本が「富を築く100の教え」という本です。
これは渋沢栄一の子孫の渋澤健氏が書いた本です。
なぜこの本を買おうかと思ったのは、これから富を築こうと思ったわけではなく、この本は渋沢栄一が書いた「論語と算盤」の言葉の説明だったからです。
この「論語と算盤」は私が35歳頃に買って読んだ本で、今本棚から出してみると、少しカビ生えています。
この本は私に会社の経営とは素晴らしい仕事であるということを教えれくれた本です。
私は小学校・中学校と学校教育の中で、働くことは尊いけれど、お金を稼いだり、儲けようとする行為は悪いことと教えられました。
金持ちは、何かズルイことをしてお金を稼いだからそうなったと思っていました。
学生時代は反体制の運動も少ししました。
そのような人間も社会人になり、仕事をしていく時、お金を稼ぐことは大変な事。ズルイことをしてそう簡単に稼げるものでないと分かってきました。
そんな時にこの本に書かれていた、道徳に基づいた経済活動があるとことに気付かされました。
そこに書かれていた一文です。
「道徳上の書物と商才とは何の関係が無いようであるけれども、その商才というものも、もともと道徳をもって根底としたものであって、道徳と離れた不道徳、詐瞞、浮華、軽佻の商才は、いわゆる小才子小利口であって、決して真の商才ではない。故に商才は道徳と離れるべからざるものとすれば、道徳の書たる論語によって養えるわけである」
今、私は稲盛和夫さんから「経営の教え」を勉強していますが、最初に「経営の根幹にある正しい考え方」を教えてくれたのはこの「論語と算盤」でした。
改めて読みたいと思っています。
参考
渋沢栄一は1840年、今の埼玉県で生まれ、27歳の時、幕臣として遺欧使節の一員として先進諸国の近代的産業や経済制度を見聞してきました。
後に第一国立銀行、王子製紙、日本郵船等の会社を興した明治大正時代の財界人
新商売
先日、古本屋のブックオフに行き本を見ていたら、ある人が本棚の本に小さな機械を当てて何かを読み取っていました。
こまめに一段ずつそれを繰り返しています。
「何をしているのですか?」と聞くと、「いや別に」と言って作業を止めます。
また、もっと以前、ある人は携帯電話画面をチェックしながら本を確認していました。
聞いても教えてくれませんでした。
私が想像するに、ブックオフの100円本の中からインターネット上で高く売れる本の仕入れをしているのかと思います。
確かにインターネット上で本を探すと、アマゾンでも古本も売っています。
アマゾンが直接売っているのではないようですが、そこで売られている古本は、それなりの値段で売られています。
時として絶版になっている本などは定価以上の価格になっていることもあります。
先ほどのブックオフで古本を探している人が直接ネット上で販売している人もいるでしょうが、どこか専門に古本を買い取りしている業者からの依頼で探しているのかも知れません。
この古本を古本屋から購入して商売になるというのも新しい発想だと納得します。
ブックオフは本の内容の価値で販売価格を決めるより、システムで売る会社なので、ブックオフが存在して初めて成り立つ仕事なのかもしれません。
ならば、ブックオフが専門部署を作り、ネット上で人気のある古本を調べ、全国の自社店舗から探し出させれ管理し、ネット上で販売する方法もありそうな気がします。
世の中の仕組みを興味持って見てみると、新商売のネタは沢山あるのですね。
ただそれに気付けるか、気付いてもそれを商売に結び付けることが出来るか、ここが分かれ目です。
身の丈起業のすすめ
先週の木曜日から市民講座を担当しています。
今年の1月にも担当しましたが、「身の丈起業のすすめ」という題名でお話しています。
毎週1回開き、5講で終講となります。
講座の最終目標は簡単なビジネスプラン作り、それのプレゼンをすることです。
ですから私が話をするというより、参加者に考え、書いてもらうことが多くなります。
参加者は定員の20名。
このような起業のセミナーなどでお話しする機会は多いですが、いつもは圧倒的に女性が多く、男性は1割いるかどうかでしたが、今回は男性12名、女性8名で男性が多いのです。
ほとんどの参加者は実際に起業を考えている人が多いように感じます。
私は今が起業をするチャンスだと思っています。
日本は長い不景気で大企業が贅肉を落としている時、すき間産業を興すチャンスです。
その上、今年の秋・冬頃から今回の大震災の復興に向け、かってないほどのお金とモノが動き出します。
その時を捉えて、今から何をしてらいいかを考え準備をしなければなりません。
復興に向け日本だけでは物資が足りなくなる事も予想されますから、海外からの輸入も増えるかもしれません。
日本経済が復活し出すと、今以上に円高になる可能性もあります。
そうすると益々輸入品が増えるはずです。
建築部門では人と物が不足する事も考えられます。
起業を志す人も、既に起業した人も今が仕事を伸ばすことのできるベストチャンスです。
私は震災の復興に参加することが、企業人として復興支援になるのだと信じています。
この「身の丈起業のすすめ」の講座の中でもそのことは強調して話をしてたいと思います。
人生の成功方程式
今日は京セラフィロソフィの55項目「人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力」についてです。
この考え方は「人生の成功方程式」と言われ、フィロソフィの根幹になっている考え方です。
これについて稲盛さんは次のように言っています。
人生や仕事の結果は、考え方と熱意と能力の3つの要素の掛け算で決まります。
このうち能力と熱意は、それぞれ零点から百点まであり、これが積でかかるので、能力を鼻にかけ努力を怠った人よりは、自分には普通の能力しかないと思って誰よりも努力した人の方が、はるかに素晴らしい結果を残すことが出来ます。
これに考え方がかかります。
考え方とは生きる姿勢であり、マイナス百点まであります。
考え方次第で人生や仕事の結果は百八十度変わってくるのです。
そこで能力や熱意と共に、人間としての正しい考え方を持つことが何よりも大切になるのです。
稲盛さんは福沢諭吉の言葉も紹介しています。
思想の深遠なるは哲学者のごとく、
心術の高尚正直なるは元禄武士のごとくにして、
これにく加わうるに小俗吏(しょうぞくり)の才をもってし、
さらにこれに加わうるに土百姓の身体をもってして、
初めての実業社会の大人(たいじん)たるべし。
※小俗吏:悪賢いともいえる程の頭の切れる才能を持った明治時代の下っ端役人
福沢諭吉の言葉も、哲学者や元禄武士のような「考え方」を持ち、悪賢いと言われるほどの「能力」を持って、頑強な土百姓のような身体に例えられる「熱意」があれば、経営者として大成すると言っています。
稲盛さんは常に「考え方」の重要性を説いています。
「考え方」こそが人生を決め、運命を決めると言います。
宿命は変えることは出来なくても、「考え方」で運命は変えることが出来ます。
「才子才に倒れる」といいますが、私の周りでも高学歴で頭の回転もいいのですが、あまりパッとしない人はいます。
逆に不器用でそれほど目端が利く事は無い「鈍」な人でも、その考え方と熱意で大成した人もいます。
私もどちらかというと「鈍」な方ですので、稲盛さんが言われるこの「人生の成功方程式」で救われました。
今はもしかしたら「鈍」な方がいいのかもしれないなどと、自己満足で、自分を慰めています。
成功するまで諦めない
今日は昨日に続いて京セラフィロソフィの内容を書きたいと思います。
昨日は「見えてくるまで考え抜く」でした。
今日は始めた事業を「成功するまで諦めない」について書きます。
稲盛さんはこの事について次のように言っています
成功するかしないかは、その人の持っている熱意と執念に強く関わっています。
何をやっても成功しない人には熱意と執念が欠けているのです。
体裁のいい理由を付け、自分を慰め、すぐに諦めてしまうのです。
何かを成し遂げたいときには、狩猟民族が獲物を捕らえる時のような手法を取ることです。
つまり獲物の足跡を見付けると、槍一本を持って何日も何日も追い続け、どんなに雨風が吹こうと、強敵が現れようと、その住みかを見付け、捕まえるまでは決してあきらめないというような生き方です。
成功するには、目標達成に向かって粘って粘って最後まであきらめずにやり抜くということが必要です。
ここで言う成功とは会社を大企業にさせ、上場するということではありません。
「自分が目標とする規模まで到達すれば、成功したと考えてもいいと思います。」と稲盛さんは行っています。
また「成功するまで諦めない」為には土俵の真ん中で相撲をとっていなければ出来ません。
松下幸之助さんが言う「ダム式経営」と同じことです。
人的・資金的に余裕のある経営を行っていなければなりません。
この「成功するまで諦めない」という言葉と、以前紹介しました「成功の反対は失敗ではない。妥協である」という言葉と連動してきます。
色々な理由を付け目標を下げてしまうのは妥協であり、それで生まれたものは妥協の産物で成功とはいえないのです。
「言うは易しく、書くのも易しいです。」
しかし、「するは難しい」ことは私の経験からも良く分かります。多くの妥協をして来ました。
簡単なら誰でも成功しているはずです。
でも、確かに「あきらめず続けて成功している人」もいるのです。
大事なのは「ここ一番」という時、諦めないで続けるか、妥協してしまうのか。その時背中を押してくれるのがこの言葉ではないかと思っています。
見えてくるまで考え抜く
昨夜は毎月第3火曜日に開催しています「京セラフィロシフィ勉強会」の日でした。
今回のテーマは「見えてくるまで考え抜く」「成功するまで諦めない」「人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力」です。
今日は「見えてくるまで考え抜く」について説明します。
この事について稲盛和夫さんは次のように書いています。
私達が仕事をしていく上では、その結果が見えてくるというような心理状態にまで達していなければなりません。
最初は夢や願望であったものが、真剣にこうして、ああしてと何度も頭の中でシュミレーションを繰り返していると、ついには夢と現実との境が無くなり、まだやってもいないことまでもが、あたかもやれたかのように感じられ、次第にやれるという自信が生まれてきます。
これが「見える」という状態です。
こうした「見える」状態になるまで深く考え抜いていかなければ、前例のない仕事や、創造的な仕事、いくつもの壁が立ちはだかっている様な困難な仕事をやり遂げることはできません。
また、稲盛さんは「見えるまでシュミレーションを繰り返すことで、完成品や到達した理想的な状態が見える。それも白黒でなくカラーで見えるまで寝ても覚めて考え抜く」と言います。
それは稲盛さんが言う「楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する」の「悲観的に構想する」の時に行うことなのかもしれません。
優れた経営者は自然とそれを行い、頭の中に理想とする形や、状態が出来あがっているようです。
例えばアップル社の社長スティーブ・ジョブズ氏はデザインに対しては完璧主義的な考えを持っていると聞きます。
自分の頭に理想とするモノがありそれを追求するのでしょうか。
またソフトバンクの孫社長は新発売される携帯電話の最終選考を自ら行い、決めるそうです。
そこにも孫氏の頭にある理想的の携帯電話の姿があるのでしょう。
一般的には会社の製品開発は、それなりの要望が満たされた製品であればそれで良しとされます。
それは稲盛さんが言う「手の切れるような製品」とはかけ離れたモノです。
最終判断者の経営者が真剣に考え抜かず、またシュミレーションも行わず、ある程度で「妥協」したモノであるため、そこそこの製品どまりなのです。
「作ったものが売れない」原因は「見えるまで考え抜く」をしてこなかったところにあります。
そこに気付かなければ、会社の発展は望めないのでしょう。
家具製造会社である私の会社のあり方も反省されるところです。
正しい判断
昨夜勉強会があり参加してきました。
講師はKCCSマネジメントコンサルタント㈱の明比常務さんです。
明比氏は長年京セラに勤め、稲盛さんの元で多くの経験をされてきました。
KCCSマネジメントコンサルタント㈱は主にアメーバー経営の手法をもとに、経営指導している会社です。
この勉強会で多くのことを教えられましたが、特に印象が強かったのが「成功の反対は失敗ではない。妥協である」という言葉です。
これは私の経験からも納得出来る言葉です。
自分の目標を立て、それに向かって邁進するけれど、思い通りにならない。
その時、もうひと踏ん張りすれば成功出来るのに諦めてしまう。そして目標を下げてしまう。
それが妥協です。
会社の年間売上目標があり、それに向かって全社で努力するけれど、リーマンショックや震災の影響で売上が思うよう行かなくなる時があります。
その時、社長はどうするのか。
自分達の力が及ばない外部要因で目標が達成できないとなると目標を下げてしまうのか。
それとも何としてもあきらめずより頑張るのか。
後者が成功をつかむのであり、前者は「妥協」した為、達成できなく終わってしまう。
この「妥協」を一度してしまうと、安易に繰り返すようになります。
それが成功の反対は「妥協」ということになるのです。
もう一つ印象に残っているのがあります。
それは正しい判断をしようとする時、何を持って正しく判断するかの基準についてです。
結論から言うと、判断する時、「自分が損をする」「自分が大変な思いをする」方を基準にして選べば良いのです。
そうすることで、概して正しい判断が出来ることになります。
確かにそうですね。
人は物事を判断する時、正しいということより、気持ちのどこかで、自分が「損をしないように」「楽が出来るように」と思いがちです
そうするとその基準が自分の損得でしか判断が出来ないということです。
自戒を込めて、今度何か判断、決断を求められた時、意識してこの事を思い出すと、的確な判断が出来るのかもしれません。
仲間作り
昨日は起業家の人達と花見をしました。
この仲間は「サポスポ起業家交流会」のメンバーです。
「サポスポ起業家交流会」は以前にもブログでも紹介しましたが、厚生労働省管轄の雇用能力開発機構北海道が起業家を支援するために作られた「北海道創業サポートスポット交流会」が母体です。
雇用能力開発機構は事業仕訳の対象になり、残念ながら1年ほど前に「北海道創業サポートスポット交流会」は廃止になりました。
しかし折角集まった起業家同士の交流会を無くすわけにはいかないと、会員有志によって引き継がれた起業家の集まりが「サポスポ起業家交流会」です。
交流会の目的は「会員相互の交流親睦を図り、起業、経営に係る情報交換や最新情報の共有等のためネットワークを形成し、起業、経営に関して更なる発展・拡大に寄与すること」としています。
会員の業種も様々で、起業した人、これから起業をしようとしている人達が集まっています。
これから起業を考えている人には、会員が経験者としてその仕事の情報を教えてくれます。
定期的に月1回の例会があり、また隔月で講師を呼んでの勉強会もあります。
例会は12時からランチ会として雇用能力開発機構北海道の部屋を借りて開催しています。
時折会員同士の親睦をはかるために花見、ビール会、パークゴルフ等も企画しています。
昨日の花見はその最初の親睦会でした。
参加者は居酒屋、不動産、行政書士、占い鑑定士、刃物研ぎ等の経営者が集まり1時~5時位まで、途中でメンバーのお店に場所を移しながら、飲み食べ続けました。
段取りは全て居酒屋さんご夫婦にしていただき、手羽先、ステーキ、そして10ℓの生ビール、白ワインと豪華な内容でした。
起業した人達の多くは真剣そしてに一生懸命仕事に向かっていきますが、時として迷ったり、悩んだりします。
そんな時に、打ち解けて話の出来る仲間、それも異業種の仲間を持つことはとても大切なことです。
異業種交流会で知遇を受けても、打ち解けて話が出来る仲間になるまではそう簡単ではありません。
この「さぽすぽ起業家交流会」にはその打ち解けて話が出来る仲間作りの環境があります。
それは自分以外の人のために「何かをして上げよう」という気持が会員の中に溢れています。
私も会員の1人として、これからも活動に積極的に参加して行きたいと思っています。
このブログを読まれご興味をもたれた方、入会をお勧めしますよ。
「サポスポ起業家交流会」ホームページ
http://kigyouka.jimdo.com/

行動パターン
昨日ある人と話していた時に「人の行動パターン」について考えさせられました。
そのAさんは絵を描くのが好きな人です。若い頃は絵描きを目指していました。
Aさんの話では、絵を描きだすと全てが見えなくなると言います。絵の対象である花なり、人物に全てが注がれます。
「これはどう見ればいいのだろう」「どのような表現が良いだろう」と対象に全神経が注がれるのです。
食事を取るのも忘れ、寝るのも惜しんで描いてしまいます。
「しなければならない」という思いでするのでなく、そうなってしまうそうです。
絵を書いている時は中断されることを嫌う訳です。
一方、別の知人Bさんは1つの仕事をしている時、フッと別のことを思い浮かべてしまい、それもチェックしながら仕事をします。
時には同時に複数の仕事を進めることもします。
Aさんとは反対に、Bさんは1つのことをし続けることに苦痛を感じてしまいます。
あることをしている最中に、別のことが気が行ってしまうのです。
本を読む時も同時に数冊を読むことが出来ます。
Aさんは絵を書き始めると周りが見えなくなるので、そのせいかあまり気が回りません。
Bさんは良く気配りが出来、、場の空気も読むことが出来ます。
AさんとBさんはそれぞれの「行動パターン」が違うのです。
どちらが優れているかかという問題ではありません。
強いて言えばAさんはスペシャリスト、Bさんはゼネラリストと分けることが出来ます。
それぞれの役割があります。
大事なのは自分はスペシャリストな要素が多いのか、ゼネラリストとしての要素が多いのかを知ることです。
単なるあこがれから、ゼネラリストがスペシャリストになろうとしても、苦労が多いです。
勿論その逆もそうです。
自分が1つのことをし続けるのが出来ないと悔むことは無いです。その人はゼネラリストなのです。
そのような生き方をすればいいのです。
経営者はほとんどがゼネラリストの傾向が多いでしょう。
自分を正しく知り、それを生かせば順風に乗れます。
憧れだけで違う方向に行くと、苦労だけ多く、実を結びません。
昨日のAさんとの話で、改めて自分を知ることな大切さを認識しました。
思考方法
会社を経営する時、社長は会社のトップとして決断を迫られる時があります。
「進むべきか引くべきか」「始めるべきか止めるべきか」、事業を展開する時、最終判断は二者択一で決めなければならないことばかりです。
その折衷案はありません。
事案に対して、社内で色々な議論を戦わせて可能性を探り、さまざまな条件の中で最終決めるのは社長です。
社長の究極の仕事は会社のトップとして二者択一の決断を下すことです。
極論を言えば社長の仕事はそれしかないのかもしれません。
全ての責任を負って決断を下します。だから孤独なのです。
時折、それを避け、部下に決断を丸投げする覚悟のない社長がいます。
社長失格です。
このように、二者択一で決めなければならないのは、最終判断です。
ところが日常の活動、それは日常生活の中でも仕事上でもそうですが、上記とは逆になりますが、安易に「白か黒」か、「右か左」かを二者択一で決めてしまうことが多すぎるようです。
あの人は良い人、あの人は悪い人で人を判断する人がいます。
二者択一で裁判官の判事のように有罪・無罪の判断しかしないのです。
そして人はそのような思考に慣れてしまうと複雑な多様性のある思考が出来なくなります。
単純回路、短絡回路だけになってしまいます。
また、現代のように数多くの情報が氾濫し、情報が多過ぎてしまうのも、それの原因かもしれません。
現代社会では安易な二者択一でしか考えなくなってきているように思い、少し危惧感を思えます。
それを防ぐには自分で意識して「二者択一以外の道はないか」と考えるしかないのです。
例えば道が二つに別れていたら右と左以外に進む方法はないかと考えます。そうすると右と左の間の藪の中を通った方が近道かもしれないのです。
人を「好き嫌い」で「いい人か、悪い人か」と見るのでなく、別の面からみると、自分と同じで、普通の人だと判断出来ます。
頭を一捻りするクセをつけるといいのです。
この「二者択一思考」と「多様性の思考」を共に身に付けなければならないのは社長・経営者なのだと思います。
二つの思考方法をその場に合わせて使い分けて行くことも身に付けなければならない能力です。
話を聞いてもらうために
人の話を聞く時、素直に聞く人と、斜に構えて聞く人、全く聞く耳を持たない人とさまざまです。
それは耳に栓をするとか、耳を塞ぐとかしているからです。
もしかしたら、その人は本当はいい話しをしているのに「何となく嫌な人だから」とか「あまり大したことのない人だから」とかの理由があるのかもしれません。
でもそれはもったいない事です。
それに似たような話です。
私の若い頃、好きな歌手がいてその歌が好きだったのですが、ある時その人がスキャンダルを起こしたため、その歌も聞きたくないと思ったことがありました。
その時友人から言われたのが、「歌が良ければその歌っている人間がどうであれ、関係ないはず。良い歌は良い歌なんだから。」と
それと同じように、話している人に対しての先入観を持たずに、「いい話しかもしれない」と話を聞く姿勢は必要なのです。
そうでなければ耳触りのいい話しか聞かず、自分の考えがますます狭くなってしまいます。
自分と考えが違う人の話も「成程」と思える心の広さも必要です。
一方、逆に話す人間の立場に立てみれば、「自分の話を聞いてもらえない」というのも問題です。
特に経営者として話す力は重要です。
大切な話をしても伝わらない。それでは人は動きません。
社員や得意先、銀行などに話をする時、信用して聞いてくれるかどうか、そして行動してくれるか。
人を動かすことので来る経営者が成功します。
聞かない人が悪いのではありません。聞く耳を持たせるように努力しなければならないのです。
人が話を聞いても動かないのは、その経営者の考え方、姿勢が大きく原因してきます。
耳を傾けてくれるだけの話の内容と共に、人としての考え方がしっかりしていなければ、社員も得意先も銀行も聞いてくれ、動いてくれません。
経営者は普段からの行動が信用されるかどうかにかかっています。
素晴らしい経営者、成功する経営者は、良い話しをするより前に、耳の栓を抜いてあげることが出来る人なのです。
自分に自信を持たせる
「恐れ入りますが・・・」という言葉で声を掛けられることがあります。
私もホテル時代では良く使っていました。
その時の意味するところは「申し訳ありませんが」とか「恐縮しますが」ということでしょう。
恐縮の意味も考えだすと難しいものになってきます。
「恐れ入ります」は辞書によると
「相手の優れている点に、すっかり感心して、まいってしまう」
「相手のあまりのひどさに言う言葉もないほどにあきれる」
「目上の人に迷惑をかけたり失礼なことをしたりして申し訳ないと思う」
「 相手の行為をありがたいと思う」等があります。
1つの言葉でこれほどの意味がるのです。日本語って難しいものだなと思います。
この中で最初に紹介しました「相手の優れている点に、すっかり感心して、まいってしまう」ということについて考えたことがあります。
この気持ちは神様や自分の憧れる人に対して持つ心です。
ところが、日常生活で、自分より目上の者、金持ち、地位の高いものに対して、常に「恐れ入っている」人がいます。
あまり「恐れ入る」と心が卑屈になります。卑屈な心になると、自分が出せなくなります。
そういう人は時として、目下の者、地位の低い者に対しては、高飛車に出ることがあります。
このような人を見て、私も自戒します。
ただ、この様に恐れ入ったり高飛車に出るのは、その人に自信がないからでは、と考えます。
自分の行動指針や生き方が定まっていないことが多いのです。
それを「自分の立つ位置が分かる」と表現出来るかもしれません。
それは実際より良く見せようとか、最初から叶わないと思う気持ちを排除しなければ出来ません。
「あるがままの自分」を認めるところから始まるのではないでしょうか。
「良いところ」も「悪いところ」も自分の存在を認めることです。
自分に自信を持たせる良い方法があります。
それは、肩の力を抜き、お腹に少し力を入れ、胸を張り、顔を上げて歩くと、不思議に元気が出てくるものです。
特に、心が弱くなった時は効果てきめんです。
私のパソコンのデスクトップ画面に入れている言葉です。
「腹に力を入れ!」 「胸を張れ!」 「顔を上げ!」 「さあやるぞ!」
宜しければお試しください。
楽しい生き方
昨夜、知人が出るバンドのライブを聞きに行ってきました。
ライブハウスは20人程しか入らない狭さですが、ほぼ満席の状態で始まりました。
私の同級生ですから61歳。バンドメンバーでは年齢として彼が一番上で、その他に40代50代の人達7人構成です。
曲は「昭和歌謡」と謳って懐かしい歌が10曲ほど続きました。
私の知人は大手旅行会社の取締役を定年で辞め、今は音楽を生きがいにして活動しています。
高校時代はフォークバンドを結成し、ラストライブでは札幌市民会館をいっぱいにしました。
大学時代に尺八を始め、今ではプロ並みの腕前です。
また10年以上前から、仕事の合間を縫ってウッドベースを始めました。
これもメキメキ腕を上げ、旅行会社に在籍中から、週末はジャズバーでベースを引いていました。
彼は定年前から定年後は音楽に没頭すると宣言し、定年を楽しみにしていました。今はその通り音楽漬けです。
昨日のライブには彼の奥さんも来ていました。
奥さんとも話をしましたが、その時の話がまたいいのです。
「毎日私は幸せです。彼が練習といって午前中は尺八、ギター、ベースを演奏してくれるんです」と嬉しそうに話をしてくれました。
彼にはこんな大ファンがそばにいて応援してくれているのだからこそ、人生を謳歌出来るんだと感じ入りました。
自分の夢を共有してくれる人がいてこそ、大きく育つのです。
この7人のバンドメンバーは、大手ゼネコンの設計部長のピアニスト、英語とフランス語の教師のドラマー等現役の仕事を持ちながら音楽活動をして人達です。
本来するべき自分の仕事をこなしながら、自分の趣味を生かす生き方をしています。
外国の大企業の経営者や政治家の中には、趣味でピアノやバイオリンなどを上手に弾く人が多いと聞きます。
また昔の日本の経営者の中にも小唄、長唄、能、茶等に造詣が深い人もいました。
「仕事+〇〇」と仕事以外に何かを持っている人は、人間的な魅力があります。奥行きのある人の様に思います。
定年後の生き方についてはボランティアという生き方も、起業という生き方もあります。
趣味に没頭し生きるのもいいのかもしれません。
このバンドの様に有料で演奏会をすれば、それなりの収入も入ります。
久しぶりに生バンドを聞いて楽しい夜でした。

仲間で起業
昨日は「良き仲間」というテーマでブログを書きました。
今日はその「仲間」つながりで書きます。
起業する時、1人起業もいるでしょうが、何人かで起業することも多いでしょう。
兄弟、友人等のつながりで起業する方が心強いと思います。
仲のいい友人と起業する時、初めはいいのですが、ある程度起業が順調に進んだ時、リーダーシップの問題が起きます。
誰がリーダーなのかということです。
普通は社長がリーダーだというのが常識ですが、そうでない場合もあります。
多いのが「仮社長」です。「当面は仮に社長、専務、常務で行こう」ということで起業を始めてしまうことが多いです。
共同責任で始めると、責任の所在、権限の所在が不明になりがちです。
仲間で起業して成功した例はワタミ創業者の渡邉美樹さんでしょうか。
また、資金も多く出し、ビジネスアイデアも提供したのに、人の管理が嫌だということで、社長なのに重要な仕事を人任せにする人がいます。
重要な仕事を人に任せると「権限」と「権力」が知らぬ間にその人に移って行ってしまいます。
規模は違いますが、以前アップルのシティーブ・ジョブズは自分が採用したジョン・スカリー(元ペプシコ社長)に追い出されてしまったことがありました。
ナンンバー2を選ぶ時は能力よりは、その人に「人間性と忠誠心があるか」が重要なポイントになります。
兄弟で起業する時は、長男・次男の序列がありますので比較的リーダーシップは取れます。
しかし、兄弟だからということで甘えも生まれる余地もあります。
兄弟だからそこ、それも許さないリーダーシップを発揮しなければならないのです。
社長というトップは孤独なものです。
それを覚悟し、「甘えたい」とか「頼りたい」という気持ちを捨てなければ、成り得ないのが社長という仕事でしょう。
良き仲間
現在日本はデフレ、不景気それに震災の影響で経営が大変な会社が多くなっています。
そんな状況の中、知っている札幌のある家具製造会社が倒産してしまいたした。
不景気のため仕事が減ったのが原因ですが、それ以外に大きな要因があったように思います。
それは厚生労働省が雇用対策として打ち出している「雇用調整助成金」です。
これは「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。」というものです。
そしてその条件は「売上または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること。」です。
それにより従業員を休業させた場合、休業中の従業員に支払った賃金の三分の二は国が補てんするというものです。
先ほどの家具製造の会社社長は従業員の給料の三分の二が補てんされるというところに目が行ってしまったようです。
生産・売上が下がっても三分の二も給料を国が支払ってくれるのだからということで、生産・売上向上の努力をするより、いかに効率よく補助金・調整金を得るかに関心が行ってしまったのです。
そのような状況だと必然的に会社は縮小し、倒産するのは目に見えています。
しかし、伝え聞くとその社長は「甘い誘惑に負けてしまった」と言っていたそうです。
国は失業者対策と言って色々な施策を出します。
しかしそのほとんどの施策には「お金」が付いてきます。
「緊急人材育成事業」というものは失業者が職業訓練期間中月当り10万円のお金が支給されます。
これも真剣に訓練を受けに来ている人と、お金目当てだけの人がいるそうです。
会社にしても個人にしても今は大変な時代です。
頑張っても頑張っても一向に良くならないと、つい安易な方に引かれて行ってしまいがちです。
でもどこかで踏ん張っていかなければなりません。
1人で出来なかったら仲間を作ってでも頑張らないとダメです。
仲間について斉藤一人さんが本に書いていました。
「渡り鳥は逆Vの字になって飛びます。先頭を飛ぶ鳥は疲れるので、時々交代します。逆Vの字になるのは前を飛ぶ鳥の羽ばたきが後ろを飛ぶ鳥の浮力の助けになるからです。お互いに助け合っています。
飛ぶ鳥は助け合うけれど、オンブしている鳥はいません。ぶら下がっている鳥もいません。助け合うけれどそれぞれが独立して飛んでいます。そう言う仲間でなければなりません」と書いていました。
今本当に必要なのは、傷をなめ合う仲間でなく、互いに切磋琢磨して頑張れる仲間をもつことなのでしょう。
そういう意味でネットワーク、勉強会などの仲間作りは大切です。
休日に働く
今日で長いゴールデンウイークも終わります。
途中2日休みを取れば10日間にもなります。正月休みより長かったのではないでしょうか。
明日から仕事で、すぐに元の仕事ペースに戻らない人もいるでしょう。
一方、この皆が休みの時期に仕事をしている人も沢山います。
その人達のおかげで、休日を満喫出来たということもあります。
「休日こそ稼ぎ時」の人でも、家族がいる人は子供と遊ぶことが出来ないという思いはあります。
恋人がいる人は休日を一緒に過ごすことが出来ません。
私も以前ホテルの仕事をしている時は同じような経験をしましたので、その時の気持ちはわかります。
昔のことになりますが、私の場合子供達はどう思っていたかと考えてみました。
私も一緒に遊んでやることはあまり出来ませんでした
でも、そのことで文句を言われたことはありません。
もう諦めていたのだと思います。
私はあまりいい父親でなかったと思っています。
それでも、その分子供たちは自分達で楽しむことを見付け、遊んでいました。
少し言い訳じみていますが、今思い返してみると、全てが満たされているより、少し不便苦痛がある方が子供は精神的に成長するのではないかと思っています。
子供にとって全てが思い通りになって育つと、成長してから辛いものが多く感じるようになってきます。
私の子供たちは早くから家より外の世界に興味を持っていました。
既に皆、私達夫婦から巣立って行っています。
それでも時々遊びに来ます。
このゴールデンウォークの時期に、夫がヨーロッパへ出張に行っていると言って長女が遊びに来ています。
同じように休みなしで働く人がここにもいました。
競争の戦略
大分以前に読みたいと思って買ったけど、まだ読み切れていない本が有ります。
今まで多くの本を買いました。
良い本だと思って買ってみたけれど、読み始めると詰まんない本は、途中で止めてしまうことはあります。
それとは違って、読んでみるとやはり良い本で、読みこなしたいと思っても、読み切れない本。
私にとってその本はM・Eポーターが書いた「競争の戦略」です。
500ページ近くあるその本は、内容も難しく1ページを読んで理解するのに相当時間がかかります。
読むのに時間がかかり、本の3分の2ほど読み終わって見ると、最初のページの内容をすっかり忘れています。
読解力がないせいなのですが、素晴らしい本だというのは分かる分、忸怩たる思いがあります。
そこで今考えているのは、この「競争の戦略」を読みこなしたいと思っている人同士が集まる「読書会」を立ち上げです。
1人で読みとおし理解するのが難しくても、何人かでそれぞれが補いながら読むほうが、理解度が高くなると思います。
現在色々な経営に関する本が出版されていますが、その内容の多くは、この「競争の戦略」に書かれている内容の様に思います。
この本はワタミ創業者の渡邉美樹さんが座右の書として何かで紹介していたことがありました。
ある本で、この「競争の戦略」は「競争戦略の抽象的な概念論を展開しているのではない」と紹介しています。
原典のサブタイトルは「業界及び競合を分析するための技法」となっていて、方法論の解説に主眼を置いている本だそうです。
つまりビジネスで実際に使える手法とその活用方法が書かれているのです。
この1冊を読みこなせば、自分にとって新しい経営戦略法が見えてくるかもしれません。
近い内に参加者を募集して立ち上げたいと思っています。
その時は宜しくお願いします。
フランス料理店
昨日も外食をしました。
今回は86歳の母も含め総勢6名で、フランス料理店に行きました。
その店は山の上にあり見晴らしが良く札幌の街が一望です。
母の日も近いことですし、食事の目的は母を喜ばせることでした。
ランチメニュ―なのでセミコースの料理でした。
なかなか美味く2時間ゆっくり食事をしました。
その昼のお客は私達6名の他に2名のお客、計8名だけ。
店は山の上にあり、ほとんどが予約客なのでしょう。
「8名で儲かるのかな?」という疑問が起きました。
1名2800円のランチが8名で売上22400円。
材料費率30%として粗利益は15680円です。
夜も営業していますので、少なくても同じくらいの金額があれば1日31360円の粗利益になります。
月25日営業とすれば月間78万円近くの粗利益です。
運営を家族だけでしているとする、人件費がかからず、何とか店の運営は出来るのではないでしょうか。
以前読んだ「餃子やと高級フレンチではどちらが儲かる?」という本を思い出しました。
読んだ方も多いでしょう。
フランス料理店と餃子店では限界利益率(粗利益率)が違います。
フランス料理店は客単価を高めて、限界利益を高くしなければ商売が成り立たちません。
逆に餃子店では客単価が低く、限界利益率が低いので、客数を増やさなければ成り立たない。
この本は会計について書かれており、結論としてどちらが儲かるとは書いていません。
ただ限界利益率を高くしなければならないフランス料理店は固定費がかかるということが理由です。
そうすると、先ほどのフランス料理店では、最大の固定費である人件費が家族ということで、成り立っているのかもしれません。
勿論、紹介しましたフランス料理店が本当に家族経営しているかはわかりませんが・・・・
2800円のランチはランチといて考えれば高いです。
そう頻繁にいけませんが、環境と美味しさで考えると決して高くはありません。
機会があればまた行きたいと思うレストランでした。
レストランの名前は秘密にして置きます。
食中毒事件
昨日は久しぶりで妻と娘とで食事に行きました。
いろいろ事情があり、一緒に外食するのは半年ぶりです。
その店は喫茶店風のレストランで結構混んでいました。
注文をしてから暫くすると、スプーン等が入った籐製の箱をもってきたのですが、その時一緒に注文レシートを置いて行きました。
まだ、注文した料理が来ていないのにです。
一般的には料理が来てから持ってくるものですが、効率を図ってのことなのでしょう。
料理がおいしかった分、心配りがなく残念。
料理と言えば今、食中毒問題でユッケや生肉が問題になっています。
連日焼肉会社の社長はただただ、頭を下げ謝っています。
この一連のテレビ報道を見ていて、一方的なバッシングにはどうしても疑問が残ります。
勿論、ユッケを食べ死亡した人、重い病気になっている人は可哀そうですし、焼き肉店またその社長はその責を責められて当然です。
でも、一方的にこの店や社長だけが間違いを犯し、悪いのでしょうか。
今朝の日経新聞で生肉に関しての記事が掲載されていました。
現在の国の基準では、以前起きた生食レバーによるO157食中毒事件が発生したこともあり、2007年以降生食用として出荷されている肉は、馬肉と馬レバーのみということです。
即ち、現在は生食用肉として牛肉は認められていないのです。
そうすると、この食中毒を起こした店ばかりでなく、生肉を出している全ての店が、認められていない生肉を出していたことになります。
あるテレビでは「調理場で細菌検査をしてい無い」と指摘しますが、定期的にしたとしても毎日、またその都度に検査するんは無理です。
食中毒を起こした「焼肉酒家えびす」は平成10年に設立し、まだ12・3年しかたっていません。
この間に20カ店以上の店を展開してきました。
この会社の社長はテレビで見る限りまだ若い人です。
短時間に会社を急成長させた中には無理もあったのかもしれません。
しかし、それでもこの社長に経営の力があったことは確かです。
この事件の記者会見でも弁解も言わず謝っている姿も真摯にうつります。
あまりこの社長をかばうと、皆さんに非難されるかもしれません。
でも、優れた経営者がつぶれて行くのは大変残念に思っています。
この事件の責任を全て取った後は、是非再起して欲しいと願う気持ちいます。
職住一体
連休が続くと家にいることが多くなり、運動不足になります。
ふだん運動することない私は尚そうです。
そこで雨が降らない日は1時間散歩することにしました。
散歩道はなるべく普段通らないところを歩きます。
歩きながら発見や再発見があります。
昨日も歩いていると、1階がお店、2階が住居式の建物が結構ありました。
商店では「店舗+住居」が当り前でしょう。
飲み屋さんもそのような形態があります。
この形態でお店をもつことで、住居費を削減し、通勤費・通勤時間を無くして、費用・時間効率が良くなります。
でも最近このような形で店を持つ人が少なくなっているようです。
店と住宅を違う場所に構え、通勤しています。
「仕事と生活は別」という考え方なのでしょう。
確かに「仕事場と生活の場を別に持つべきだ」という考え方で、私は起業者向けのレンタルオフィスを運営しています。
しかし、お店をもつ場合は別です。
お店の運営には家族のお協力が必要です。アルバイトを雇うことはズーと後で考えるべきこと。
昔に読んだ邱永漢(きゅうえいかん)さんの本に書いてあったのを思い出します。
邱さんは台湾生まれの87歳になる経営コンサルタントです。
日本がバブルの頃大変影響力のある人でした。
邱さんの本の中で自分が最初に会社をもった時、事務所が夜には住居になったと書いています。
その頃は結婚したばかりですが、奥さんも同じ事務所で仕事をし、社員が帰った後に、事務机で夕食を食べ、寝る時は事務机を合わせてベットがわりにし、その上に布団を引いて寝たそうです。
事務所には台所も、トイレも付いており、風呂は銭湯があります。
邱さんは「中国人はそのようにするのが当り前で、それによってお金を節約した」と書いてありました。
そして「なぜ日本人はわざわざ別のところにアパートを借りるのか」とも書いています。
今の時代、事務所で生活するというのは大変でしょうが、「職住一体」も起業したての頃は考えてもいいのではないでしょうか。
起業したての頃は事業費も生活費も出処は一緒です。
また、起業したての頃は1日中仕事漬けになります。
「職住一体」によって足腰の強い経営体質が作られると思います。
言葉の意味
昨夜、テレビを見ていたら、字を書くのクイズがありました。
その中で叫ぶという字が出題されました。
この「叫ぶ」という字を良く見ると、「1」を抜くと「叶う」という時になります。
何か関連があるのでしょうか?
昔の歌の詞に「『若い』ていう字は『苦しい』ていう字に似ているわ・・・・・」というのがありました。
こじ付けなのでしょうが、結構流行った歌でした。
漢字にはそれぞれ語源があります。
それとは別に、こじ付けであっても、納得出来る解釈もあります。
ご存じの人も多いと思いますが、これも昔に聞いた話を紹介します。
親という字は「木の上に立って見る」と書きます。
即ち、「べったりと子供の傍にくっ付いて、箸の上げ下げまでうるさく言わないようにして、少し離れて自主性をもたせるようにする。
万が一の為に木の上から身守っている。」という親への諌めを意味しています。
「成程」と理解しました。
このような言葉の解釈は沢山あるでしょう。
漢字に興味を持って、それらの言葉の意味を探すのも面白いのかもしれません。
それだけで1冊の本が出来るかもしれません。
最後にもう一つ。
これも昔ある飲み屋のお婆さんに聞いた言葉です。
「嬶(かかあ)」とは奥さんや母親を呼ぶ時に使われました。
今はほとんど使われません。
この意味するところは、そのお婆さんが言うに「女は若い頃は可愛いと思っていても、年をとるとともに『鼻につく』ようになる。そうなると『嬶』と呼ばれるんだよ」ということです。
確かに、女性は母親になれば逞しくなり、力のない旦那なら強くならざるを得ないでしょう。
少し女性を蔑視している意味合いが含まれています。
幸せなことに、今のところ私の妻は「嬶」にはなっていないようです。
プライド
昨日は5月1日でした。
毎月の事ですが1日(ついたち)は琴似神社と北海道神宮にお参りに行くことにしています。
お参りして思うのですが、神様の前だと「素直」な気持ちになれます。
手を合わせながら、素直に「ありがとうございました」というお礼を述べます。
そして自分の心を見通して、わかっていたければという気持ちになります。
Something Great(サムシング・グレイト)の前では素直になれます。
お寺に行くと仏様の前でも同じでしょう。
そうすると、毎朝、神棚の前でお参りをする時も、素直になれる時なのかも知れません。
生活の中で素直になれる「時」をもつことは大切だと思います。
昔、「敷居をまたげば、男には7人の敵が居る」と言われました。
その為、人は自分の身を守ろうとします。
その1つの武器が「プライド」ではないでしょうか。
それがあることで、「負けないぞ」という競争心が生まれ、より良くなろうという向上心の元になります。
ただ、「プライド」は自己成長にとって欠かせない要素の1つですが、一方、人の話を「素直」に聞けない要因の1つでもあります。
時としてその「プライド」を捨てることも必要です。
その「プライド」を捨てることができるのが、神仏の前なのかと思います。
神仏の前なら「プライド」を捨てて「素直」になれるのです
「素直」は自己成長の重要な要素です。
「プライド」を持つこと以上に人間としての成長に必要なのです。
勿論、人それぞれですから、神社にお参りに行かなくてもいいのです。
でも、「素直な心」を意識できる機会を、自分の生活の中に多く持つことは、自己成長のための「環境作り」なのだと思います。
1日1快
昨日は「自分褒め」ということで書きました。
今日もそれに近い話しをします。
昨日読み終わりました城山三郎さんの本の中に「1日1快」という言葉が書いてありました。
この言葉は城山さんの造語です。
「一日一善」に似ていますが、その意味するところは、1日に1つでも、爽快だ、愉快だと思えることがあれば、それで、『この日、この私、生きた』と、自ら慰めることができる」ということです。
1日1日を大事に生きることを教えてくれています。
1日が終わる時に、1つでもそう思って床につけることは幸せなことです。
一日の終りに反省をし、それを改善に結びつけます。
それと一緒に楽しかったこと、自分が成長したことも喜びと感じることが、自信の蓄積になります。
その為、寝る前は心を乱すような事をしてはいけないと中村天風さんの本に書いてありました。
インドのヨガの達人の教えだそうです。
奥さんと喧嘩したまま寝るとそれが寝ている時に、蓄積となり、精神的にも肉体的にも良くないことなのです。
逆に、寝る時に、楽しく、自信に満ちた思い出、将来の夢を思い描きながら寝るとそれが実現するそうです。
毎日日記を書いていればそれに近いことができるのかもしれませんが、三日坊主の私は日記は続きません
せめて寝る前に、1日を思いめぐらす時間を持とうと思います。
寝る前はとても大切な時間なのだと、最近実感しています。
自分褒め
頑張るという言葉について考えてみました。
「頑張れ!」「頑張る!」は人に対しても、自分に対しも良く使います。
気分がいい時に、「頑張れ!」と言われると「よし頑張るぞ!」と思います。
そうすると少し頑張ることが出来ます。
しかし元来頑張るということは、困難を乗り越えていく行為です。
本当は辛い行為です。
ですから、気分がいい時は最初は頑張ってもそれが続かないことが多いのです。
人は楽しくなければ頑張れないと思います。
楽しく頑張れる方法は何か?というと、褒められることではないでしょうか。
同じ仕事をしている仲間同士褒め合うのも1つです。
もしもそのような褒めてくれる人がいなければ、自分を自分で褒めるのです。
頑張って成長したことが「楽しい」と思えることが大切なのです。
「子供がある日、急に勉強をし出すという時は、勉強が楽しいと思える時です」と聞いたことがあります。
親が褒める⇒勉強する⇒成績が上がる⇒皆に評価される⇒嬉しい⇒勉強する⇒より成績が上がる⇒勉強が楽しくなるのです。
大人の世界も同じです。
以前にもブログで書きましたが、昔ホテルの支配人をしていた時、業績が良くない中、一生懸命考え、企画し、営業していました。
自分が頑張らなければと思い、頑張りましたが、結果がなかなか出なく、誰も評価してくれません。
そんな時、「自分くらいは自分を褒めてあげよう」と思いました。
自宅から駅までの間10分間、小さい声で自分を褒めながら歩きました。
あまり大きい声だと変な人だと思われますので注意しながら褒めました。
そうしていく内に、頑張っている姿は神様も見てくれるのだと思う気持ちになりました。
その内、成果が出て、ある時から急激に業績は良くなりました。
そうなると歩きながら、自分褒めの他に「ありがとうございます」という言葉も自然に出てくるようになりました。
頑張るということは困難に向かうことで、それだけを取り上げれば辛いことですが、それをどのように「楽しいこと」に置き換えていくか。
それが出来るかが成功する1つの要因だと信じます。
遺言師
先日知人が私の事務所に来ました。
久しぶりなので話が大変はずみ、楽しかったです。
暫く会わないうちに彼は、新しい仕事を始めていました。
それは「遺言師協会」です。
この「遺言師」という言葉は既に商標登録したそうです。
人が亡くなって問題が起こりのはその後の処理です。
「お金」と「モノ」の処理についてです。
その為、それに関することすべてを請負う専門家集団がこの「遺言師協会」です。
一般社団法人として設立し、行政書士、司法書士等の「士業」の人達が中心となって運営されます。
ゆくゆくは各地の「士業」の人達との連携で広めていくそうです。
私の知人は「士業」の人ではありませんが、この設立の中心となって活動しています。
彼は少なくても2年に1社の勢いで事業を興したいと言っています。
起業したいと思ってもなかなかその夢が実現できない人が多いのに、何が違うのでしょうか。
彼を見ていると、まず行動的です。自分が考えたらすぐ行動します。
そして、何にも興味を持ちます。
彼と一緒に中国旅行へ行った時、朝の5時前から北京の街を1人で歩き回り、皆が起きてくる頃には「一仕事終えた」感じでいました。
何事にも興味を持ち行動的な彼だからこそ、新規事業を立ち上げことも出来るのでしょう。
そして何より、そのフットワークの良さからネットワークも広いのです。
人を巻き込んで仕事を作り上げてしまいます。
彼はゼロから事業を立ち上げるのが好きなのです。
彼が言うには、経営は誰かに任せて、事業を立ち上げに専心したいと言っています。
彼のような人と組むことで、事業を立ち上げ、会社経営出来るとなると、1つの起業支援でもあります。
そう言う意味でも彼は貴重な人なのです。
話を聞いて私も刺激を受けています。
何か始めましょうか!
心の余裕
先日テレビを見ていたら、日本テレビ恒例のチャリティ番組「24時間テレビ」の今年のマラソンランナーに徳光和夫さんが決まったとありました。
今年は大震災の後なのでまた寄付金も多く集まることでしょう。
人は何か災害などがあると支援・応援しようと立ち上がります。
そのことはとてもいいことなのですが、もっと日常的に生活の中にいる不自由な人を助ける行為は、もっとあってもいいのかと思います。
私はユニバーサルデザインの団体の活動に参加しています。
その活動の中で思うことは、あまり「福祉!福祉!」と大上段に構えて取りかかることよりも、日常生活の中で自分が出来ることをすだけで、住みやすい社会になっていきそうな気がします。
電車の中でお年寄りや体の不自由な人に席を譲る時も、自然としている人がいます。
私が電車に乗っている時、若い男性が友達と席に座って、話をしていました。
ある駅でお年寄りが乗ってきました。
するとその1人が友人と話をしながら、本当に自然に「どうぞ」と言って立ち上がり、そのまま話を続けています。
席を譲ったという意識を持たせないほどの自然な仕草でした。
冬の雪道、滑る歩道、それも坂になって登れないお年寄りに、自然に手を貸してあげる若者。
決して、特別なことではありませんが、全てが自然に日常的に出来る「心の余裕」を感じます。
昨日も紹介しました城山三郎さんの文章にもそのような情景が書かれていました。
城山さんが電車を待って駅のベンチに座っていると、隣に50歳前後のがっちりした体格の男性と、その母親らしき人がいました。
その前を盲目の夫婦が盲導犬を連れて歩いていました。
2人そろってトイレに向かったのですが、そこには「清掃中」の札が出ていました。
その時となりの男性が立ち上がり、駆け寄って事情を話したのですが、夫婦は困惑してしまいます。
その男性は意を決したようにトイレの中に行き、清掃作業員に話を付け、2人を案内しました。
段差があるので、その段数まで教えて戻ってきました。
戻ってきた男性は母親に「目が見えるんだから、できることはしなくちゃね」
うなずく母親になお照れくさそうに「こんなことぐらいしか、出来ないんだ」とつぶやく。
城山さんは「私は拍手をしたかった。これまた心をこめた拍手、熱い拍手を」と書いています。
日常出来る、人への優しさ。それをするにも最初は勇気がいります。
それが自然に出来、そのような人が多くなれば「福祉!福祉!」ということも少なくなるのではないでしょうか。
大器晩成
色々な人とお会いして、特に若い人にお会いして感じるのは、余裕の無さです。
余裕は楽をするとか、手を抜くとは違います。
力を少し貯めていざという時に使うことを意味します。
勿論なりふり構わず突進することも大切ですが、その時もどこかに気持ちの余裕が必要かと思います。
トップになることを第一に考えて突き進むのもいいのですが、後ろにいて、力を蓄える時期も必要です。
昨日読んだ城山三郎さんの「無所属の時間で生きる」という本を読んでいた時、「どん尻が一番」というのがありました。
昔の上海での話。中国人とスコットランド人との混血児の騎手が、混血児であるため、これはという馬に乗せてもらえず、毎度のレースで「どん尻」でした。
ところが彼はくさりもせず、むしろ逆転の発想で生きていました。
「『どん尻』であることが素晴らしいことでした。私にはレースの全貌が見えたのです」と言います。
つまり一番後から眺めることを重ねたおかげで、レース展開が読め、ライバル全員の行動が分かるようになったというのです。
そうしているうちに、彼を買う人が出てきて、いい馬に乗せてもらうと、12レース中10レース優勝してしまい、英雄になり、戦後は香港に移り、第二の人生もまた成功しています。
人生、不遇続きの中でもくじけることなく、何かに気ころがけていさえすれば、いつか報われる日が来るという訳です。
普通、人は弱い者で、「どん尻」になると自分を卑下し、やけっぱちになりがちです。
もう人生が決まってしまったような錯覚に陥ります。
「どん尻は素晴らしいものでした」と言える余裕は、「大器晩成」型の人が持つ心構えでしょうか。
最近「大器晩成」という言葉は語られなくなりました。
若い内は、すぐにトップになるより、力を蓄え後ろからじっくり着実に進む生き方もいいのではないでしょうか
多柱戦略
先週の土曜日にある講習会の講師として参加してきました。
起業した人と2代目経営者の勉強会です。
私は先月と今月の2回を担当しました。
今回の勉強会では、それぞれ経営の立場から課題を提示していただき、それについて皆で考え、述べ合う形式をとりました。
提示された課題を少し紹介します。
「目的と目標を自社でどのように掲げていけばいいのか」
「自分の仕事をどのように世間に知らせることができるのか」
「売上優先になり、利益が少ない現状改革」
「自社にある2部門を活用して新規事業開発の方法」
等です。
それぞれの問題に対して参加者から多くの意見が出ました。
この勉強会で私が心掛けたのは、一方的に私が話す事より、参加者それぞれが自分の考えをまとめ、発表し、同じことで悩む経営者同士の連帯感を作ることでした。
批判するような意見は出ませんでした。
この課題の中で参加者から出た意見を紹介します。
それはあるコンサルタントの人から聞いた話だそうですが、新規事業を考える時、「多柱戦略」するべきという考えです。
新規事業を検討する時、「利益が出る」とか「儲かる」とかの考えで事業を考えると、成果が上がりません。
自社の強みを分析し、会社を支える柱となる事業を開拓するのが多柱戦略なのです。
確かに基盤のしっかりした会社の事業展開は、「多柱戦略」が生かされています。
私も関係している住宅会社は、自社系列に家具製造会社、家具・インテリアショップ、結婚相談所、広告IT会社等展開しています。
それぞれが結婚⇒家具購入⇒住宅購入と繋がり、それらの会社の広告を一本化する広告会社があります。
この「多柱戦略」という言葉はGoogleで検索しても出てきませんが、新規事業展開の時の1つのセオリーなのかも知れません。
善意と優しさの連鎖
昨日本棚の横に誰かが置いたか季節外れの本がありました。
それは「34丁目の奇跡」というサンタクロースと称した人の物語。
雪も無くなり、やっと春が来たのにいまさらサンタクロースでまあるまいと思ったのですが、薄い本なのでアッという間に読んでしまいました。
この本は既に読まれた方も多いかと思います。
60年以上前に、ニューヨーク34丁目のデパートを舞台にし、世界中に感動させた映画のもとになった本です。
そのあらすじは、ある老人ホームにクリスという名の、自分をサンタクロースと信じている老人が主人公です。
アルバイトで始めたデパートのサンタクロース役が本当のサンタクロースの様で大評判を呼び、人々の優しさを引き出し、奇跡を起こす物語です。
アルバイト先であるメイシ―百貨店で、子供やお母さん達からプレゼントの相談を受けた時、メイシー百貨店にない物は、例えライバルであるギンベル百貨店でも教えてしまう。
なぜだかクリスは、おもちゃはどこにあるかがすべて分かっているのです。
その行為が問題になりそうな時、お母さん達からライバル会社であるにもかかわらずお客様のために情報を提供してくれるという「本物のクリスマス精神ですわ!」という多くのお礼のメッセージが届けられました。
そのお客様のためならライバル百貨店の商品でも紹介するという行為が、新聞で評価され、メイシ―百貨店社長は喜びます。
また、そのライバルであるギンベル百貨店の社長は「メイシー百貨店は今やモテモテだ。お客様第一の親切な店ということでね! すると、うちのイメージはどうなる? 儲け第一のがめつい店だ! 負けてはおれん! 今後は、お客様のご希望の品が切れていたら、メイシ―百貨店にお出で下さいと申し上げろ!」とはっぱをかけます。
親切の連鎖の始まりです。それが新聞・雑誌、コメディアンのネタにまで取り上げられます。
ライバル関係である宝飾店のティファニーとカルチェの間でも同じような現象が起きます。
人の「善意や優しさの連鎖」が奇跡を起こす物語です。
この本の最後は、この主人公はサンタクロースを称したため、精神異常者にとして裁判にかけられますが・・・
3月11日起きた大災害に日本中、世界中の人が救援の手を差し伸べています。
そしてそこにも同じような「善意と優しさの連鎖」が起きています。
結果、きっと日本でも奇跡が起きるのでしょう。そう信じます。
この本は季節外れの本でしたが、私には的を得た、考えさせられる本でした。
有言実行でことにあたる
今日は「京セラフィロソフィ」の52項目「有言実行でことにあたる」を説明します。
稲盛さんはこのとこについて下記の通り説明しています。
世の中ではよく「不言実行」が美徳とされていますが、京セラでは「有言実行」を大切にしています。
まず自らが手を上げて「これは自分がやります」と名乗りを上げ、自分が中心になってやることを周囲に宣言してしまうのです。そう宣言することで、周りと自分の両方からプレッシャーをかけ、自分自身を奮い立たせるとともに、自らを追い込んでいくことによって、目標の達成がより確実になるのです。
朝礼やミーティングなど、あらゆる機会をとらえて進んで自分の考えを皆の前で明らかにすることにより、その言葉で自らを励ますとともに、実行のエネルギーとするのです。
昔、「男は黙ってするモノだ」と言われ、事前に話してすると、吹聴しているようで「自分だけ良いかっこしている」と言われたりしました。
しかし実際は稲盛さんが言われるように、自分の言葉に責任をもつ為にも有言実行は大切なことなのです。
稲盛さんは次のようにも言っています。
「例えば『今期の売上はこれだけにします。利益はこれだけ出します。』と社員に公言する。すると自分の言った言葉が『言霊』となって自分に返ってきます。
その言葉は自分の中にこだまして、それを実行するためのエネルギーを生み出すのです。
つまり、有言実行とは、言葉を実行のエネルギーに変換するという作業だと私は考えています」
今回の勉強会でこの「有言実行でことにあたる」を読み、参加者の意見を聞いている時、参加者の中から、自分の将来の目的や夢、そして、実際に起業している事を話してくれる人が数人いました。
それも熱く語ってくれました。
あえて自分の夢や目的・目標を口にすることで、自分にプレッシャーをかけているのが良く分かりました。
その点自分を振り返ってみると、まだそれが出来ていません。
若い参加者から学んだ時でした。
自らの道は自ら切りひらく
ここ数日続いています12回「京セラフィロソフィ勉強会」の続きです。
今日は「自らの道は自ら切りひらく」について説明します。
これに関して稲盛さんは下記の通り書いています。
私達の将来は誰が保証してくれるものでもありません。
たとえ今、会社の業績が素晴らしいものであったとしても、現在の姿は過去の努力の結果であって、将来がどうなるかは誰にも予測が出来ないものです。
将来にわたって、すばらしい会社にしていくためには、私たち1人1人がそれぞれの持ち場・立場で自分達の果たすべき役割を精いっぱいやり遂げていくことしかありません。
誰かがやってくれるだろうという考え方で人に頼ったり、人にしてもらうことを期待するのではなく、まず自分自身の果たすべき役割を認識し、自ら努力してやり遂げるという姿勢をもたなければなりません。
「中小企業を経営していると誰でも分かっていることですが、どんなに困ることがあっても、誰も助けてはくれません。「独立自尊の精神」というものが必要です。」
「オーナーはそれが分かりますが副社長、専務、常務、取締役、部長、課長はそうではありません。社長が何とかしてくれるだろうと考えてしまいがちです。」
うまくいっていない会社は「独立自尊の精神」が足りないのです。
京セラではアメーバー経営をすることによって独立採算で各部門がで運用され、自分達の稼ぎは自分で稼ぎそれ以上の利益を残して会社に貢献する体制となっています。
また京セラではその貢献に対してお金などで報いず、皆から賞賛され、会社から表彰されるだけのことです。
私は以前ラジオで聞いた話ですが、人の心理として「女性は愛されることを求め、男性は尊敬されることを求める」そうです。
お金がもらえれば嬉しいですが、それだけであれば本当の喜びとはならないのではないでしょうか。
自分が誰かのために貢献できたという思い、それを正当に評価してもらえる事により、それを喜びとして感じるのではないかと思います。
明日は「有言実行でことに当たる」について説明します。
12回「京セラフィロソフィ勉強会」3
今日は京セラフィロソフィにある「闘争心を燃やす」について書きます。
この「闘争心を燃やす」について稲盛さんは次のように書いています。
仕事は真剣勝負の世界であり、その勝負には常に勝つという姿勢で臨まなければなりません。
しかし、勝利を勝ち取ろうとすればするほど、さまざまな形の困難や圧力が襲いかかってきます。
このような時私達はえてして、ひるんでしまったり、当初抱いていた信念を曲げてしまうような妥協をしがちです。
こうした困難や圧力を跳ね返していくエネルギーのもとはその人の持つ不屈の闘争心です。
格闘技にも似た闘争心があらゆる壁を突き崩し、勝利へと導くのです。
どんなにつらくても、「絶対に負けない、必ずやり遂げてみせる」という激しい闘志を燃やさなければなりません。
経営者の中には勝ち気で負けん気が強く、闘争心があり、ボクシングやレスリングなどの格闘技が好きだという経営者が多いです。
しかし稲盛さんは誤解していいけませんと言っています。
闘争心というのは「相手を打ち負かす闘争心」ではないのです。
「例えば路傍の草木を見ても、夏の暑い盛りなど、まるで競い合うようにして生きています。陽の光を少しでも沢山浴びようと精一杯葉を伸ばし、一生懸命炭酸同化作用を行い、養分をたくわえ、来るべき過酷な冬を耐えて、再び春を待つのです。雑草でさえ全てが一生懸命に『生きよう、生きよう』と努めています。
「そのような草には、隣に生えている草を打ち負かそうとなど思っていません。ただ、自分が陽を浴びようとして精一杯葉を伸ばしているだけなのです。周りの草も同様に、必死で生きようとしています。」
「実際に、一生懸命に努力した者、誰にも負けないような努力をした者が、世の中に適応して生き残り、努力しなかったものは絶えていく、この適者生存こそが自然界の掟なのです」
私は稲盛さんが、闘争心を草木に例えたことで良く理解できました。
弱肉強食の様に相手を食べなければ自分が生き残れないという世界ではないのです。
闘争心は脅威から自分達を守るためと、自分の「怠け心」との闘争に必要なのでしょう。
稲盛さんが掲げている経営の12カ条の8項目に「燃える闘魂」というのがありますが、それも同じ意味を持っているのだと思います。
12回「京セラフィロソフィ勉強会」2
今日は昨日に引き続き「京セラフィロソフィ」の中の「真の勇気をもつ」の紹介です。
稲盛さんはこの事について下記のように言っています。
仕事を正しく進めていくためには勇気が必要です。ふだん私達は、周囲の人から嫌われまいとして、言うべきことをはっきり言わなかったり、正しいことを正しく貫けなかったりしてしまいがちです。
仕事を誤りなく進めていくためには、要所要所で正しい決断をしなければなりませんが、その決断の場面では、勇気というものが必要となります。
しかしそこでの勇気とは蛮勇、つまり粗野で豪傑と言われる人が持っている勇気とは違います。
真の勇気とは、自らの信念を貫きながらも、節度があり、怖さを知った人、つまりビビりをもった人が場数を踏むことによって身に付けたものでなければなりません。
「社長として毎日仕事の中で『こんな問題があります』『あんな問題があります』と部下から相談を受けますが、その時に勇気がなければどうしても安易な解決法を選んで取り返しのつかないこともあります。」
「企業経営していくためには『勇気』は不可欠なのです。」
ただ、稲盛さんは「勇気」は「蛮勇」ではないと言っています。そして経営者には「怖がり」という資質が必要だとも言います。
「お金を借りるにしても、事業展開するにしても何をするにしても小心で、最初はビビってしまうようなタイプの人が、経験を積んでいく、つまり「場数を踏む」事で度胸を身に付けていく。このような人こそが真の勇気を持った人とい言うのです。」
私は昔に父からこれに近いことを言われたことがあります。
「濡れた丸木橋を下駄を履いて走るな!」
これは99%落ちる可能性があるのに、状況を認識しないで行動するということです。これは勇気があるとは言えません。
でも、こういう人は時々みかけます。
またその逆に、「石橋を叩いても渡らず、叩き過ぎて壊していまう人」は慎重過ぎて、結局一歩も前に踏み出せない人の例えです。
私は勇気を出すというのは、常に意識して持っていなければならない「心構え」だと思います。
特に今は、いつ何が起こるか分からに時代だからこそ、経営者に必要な資質なのではないでしょうか。
12回京セラフィロソフィ勉強会1
昨夜、毎月開催しています「京セラフィロソフィ勉強会」をしました。
20名ほどの参加者で下記の5項目を学びました。
①「楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する」
②「真の勇気を持つ」
③「闘争心を燃やす」
④「自らの道は自ら切りひらく」
⑤「有言実行で事に当たる」
今日は「楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する」について書きます。
稲盛さんは次のように書いています。
新しいことを成し遂げるには、まず「こうありたい」という夢と希望を持って、超楽観的に目標を設定することが何よりも大切です。
天は私達に無限の可能性を与えているということを信じ、「必ずできる」と自らに言い聞かせ、自らを奮い立たせるのです。
しかし、計画の段階では「何としてもやり遂げなければならない」という強い意志を持って悲観的に構想を見つめ直し、起こりうるすべての問題を想定して対応策を慎重に考え尽くさなければなりません。
そうして実行段階においては、「必ずできる」という自信を持って、楽観的に明るく堂々と実行していくのです。
京セラは過去、常に新しいことに挑戦して今の姿があります。
その京セラでも、幹部を集めて新しいアイディアを話し、意見を聞いても、「身の程知らずなことを、資金も技術も無いのに、とんでもないことばかり言いだすのだから」という顔で見ていました。
稲盛さんは「最初、頭のいい部下をブレーンとしてそばに置くということはいいことだと思いましたが、ある時『どうしてもおかしい』と気付き、それ以来、新しい仕事についての話をする時には、そう言う賢い人間を呼ばないようにしました。そのかわり、ちょっとオッチョコチョイで、すぐに私の尻馬に乗って『社長それはいいですな』と、訳もわからずにおべんちゃらを言うタイプの人間を集めて話をするようになったのです」
「無茶なことを言っているように聞こえるでしょうが、実際、物事を考え、成就させるには、そのように楽観的に考えることが大切なのです」
「その次に計画を立てる時には違います。楽観的で、明るいだけの人間に任せっぱなしにするのは危険この上ないとのです。」
「計画を練る時はちょっとニヒルなところがあって、冷やかにモノを見るような人間にさせなければなりません」
「そのような人間は『それはあまりにも無謀です』『うちにはこういう技術がありません』『ああいう設備がありません』等、次から次へとネガティブな事を言い出します。そのようなマイナスの要件を全部列挙させるのです。そして、それらの条件を、全部、自分の頭に叩き込んで行きます。難しさを十分理解してから計画を練り上げていくのです」
「どこでどういう障害があり、どんな問題があるかが分かったら、今度はまた楽観的な人間に選手交代させて、彼らにその計画を実行させます」
「一度やると決めたらどんなに苦しい目にあっても、それは承知の上だ、と自分の逃げ道を無くし、前向きに仕事を進めていくのです。これはベンチャーを成功させるための絶対条件だあると言ってもいいと思います。」
このように稲盛さんは書いています。
私の経験でも、会社の中で誰かが新規事業を考えた時、否定的に話すのはほとんどが頭のいい人です。そのように頭にいい人が言うものですから、止めてしまいます。
その繰返しで、いつまでたっても新規事業が成り立たなかったという場面を見てきました。
私は、起業する人達に言っている事は、自分の夢を膨らましている時は人に話さないこと。
話すなら、「いいね!いいね!」と肯定的に賛同してくれる人だけ。
決して頭が良く、優れた人に話してはダメです。ほとんど否定されます。
その人が一目置くくらい頭のいい人なら尚更です。
結果いつまでも起業はできません。
この稲盛さんの言葉は皆さんの周りを見ると同じようなことが起きているのではないでしょうか。
会社のトップが会社の成長を望むなら、考えを改めるポイントだと思います。
LED照明
今朝、朝食会に出席して、今戻りました。
この朝食会では食事をしながら毎回講師の話を聞くことが出来ます。
今回はLED照明の話でした。
LED照明についてはご存じの人も多いと思います。
LED照明は今節電と言われ、改めて注目されている照明です。
ただ、私も知っているつもりでしたが、今日の話を聞いて「なるほど」と思うことも多かったです。
ここでLEDのメリットとデメリットをご紹介します。
メリット
1.長寿命
4~5万時間の寿命。5万時間とは1日24時間点灯したままで6年間使える計算になります。
2.低消費電力
40Wの白熱電球はLEDでは4Wの相当し、10分の1です。
3.紫外線が少ない
紫外線は衣料品や絵画の退色を促します。
4.スイッチオン・オフの繰り返しに対して強い
蛍光灯は頻繁にスイッチの入り切りをすると寿命が低下しますが、LEDは影響しません。
5.蛍光灯の様なチラつきがない
LEDは直流電流なのでチラつきがなく、目にもいい。
6.低温の環境でも点灯、照度に影響がない
蛍光灯は低温に弱いですが、LEDは-20度でも問題なく点灯。業務用冷凍室に向いています。
7.水銀の不使用
LEDは蛍光灯のように水銀ガスを使っていないので環境に良い
8.割れに強い
LEDはポリカーボネートを使用しているので割れに強く、地震等の衝撃にも耐えれます。
9.熱くない
熱を発さないのでやけどの心配はありません。
デメリットも紹介します。
1.価格が高い。
40Wの蛍光灯タイプで1万円程度します。
2.大きさに問題
ハロゲン球タイプではまだ対応出来ません。
3.調光が難しい
白熱球のような調光は難しい。
4.演色性に劣る
白熱電球のような赤い色は苦手。
5.点光源
光が点光源なので、広い面を照らすのは苦手。
6.蛍光灯と取り替えるとき簡単な工事必要
蛍光灯は交流なので、直流のLEDに変更する時、器具に簡単な工事必要です。
私はこのLED照明の特徴で一番気にいっているのは長寿命なことです。
私が以前ホテルの支配人をしている時、高い位置に取り付けられた「袖看板(壁に取り付けられた)」の蛍光灯交換で大変な思いをしました。
蛍光灯の寿命は1年ほどで、毎年看板の蛍光灯取替工事が必要でした。
日本経済がバブルの時ですが、その看板の蛍光灯交換工事の費用が1回120万円もしました。
蛍光灯は1本1千円位のモノですが、クレーン車などを使うのでそれくらい請求されました。
その頃このLED照明なら少なくても10年以上は切れることなく、結果1千万円以上経費が浮いたことになります。
これから看板の照明はLEDが当たり前という時代なのでしょう。
1人の日本人技術者が発明した青色LEDにより、このような照明が当たり前になりつつある技術の進歩の速さに改めて驚いています。
犠牲の上での安穏
若い頃私は毎朝シャワーを浴びていました。
朝に熱いシャワーを浴びると身体がシャキッとして「仕事をするぞ!」という臨戦態勢になることが出来ました。
今はその習慣も無く、夜ゆっくり風呂に入って疲れをとるようになりました。
私の風呂時間は長く1時間くらいは当り前。
半身浴で汗を流しながら本を読むのが好きです。
以前は勉強のための本が中心でした。
1時間弱、集中して本が読めるこの時間は貴重なモノでした。
今はまたその元気も無くなり、小説の本を読むことの方が多くなりました。
昨日1冊の本を読み終わりました。
「タッポーチョ太平洋の奇跡」という題名です。
俳優竹内野豊さんが主演する映画「太平洋の奇跡」の原作です。
この映画は見ていませんが以前から興味を持っていました。
本屋に行くと映画の題名の本とその横に私が読んだこの本が並んでいました。
日本人を主人公にしてアメリカ人が書いてあるということで興味を持ち買いました。
私は戦後生まれですが、学校で戦争の話を先生から聞いた時、戦争の悲惨な話の1つとして、サイパンが玉砕し、全ての日本人は戦死か、崖から飛び降りたりして自殺し、誰も助からなかったと教えられました。
そのため、この映画の広告を見て「生きていた人がいたのだ」とびっくりしました。
この本を読むとその生き残った数は多く、アメリカの収容所には軍人民間人合わせて1万人以上がいたと書いてあります。
この本を書いたアメリカ人ドン・ジョーンズ氏はもサイパンの戦いに参加し戦った1人です。
その人が敵国である日本の1大尉を主人公にして本を書いたのは、余程主人公である大場大尉の戦いぶりに感動したからなのです。
ですから本の中では、大場大尉が降伏して来た時、アメリカの将校たちがその戦いぶりをたたえて、パーティーを開いたほどでした。
この本は大場氏の検証のもとで書かれたので、事実に近いものでしょう。
アメリカ人のドン・ジョーンズ氏はこの本の中で「日本人は何百万という善良な人達が国のために見事に戦いました。その中には優れた兵士だった人達がたくさんいました。彼等はたいていの国なら国民的英雄とされるような勇敢な戦功を立てました。それなのにこの国では無視されてい、認められていません」と書いています。
私は戦争を賛美しませんし、戦争は反対です。
ただ戦争が起きたことは事実であり、そしてそこで国のために戦った人がいたということも事実として忘れてはいけないと思いました。
戦争はいけないモノだというだけで事実に蓋をしてしまのは疑問です。
サイパンは玉砕で誰も助からなかったと教えられれば、最後まで戦い抜いたその戦いの意味は何だったかと悲しい気持ちになります。
今の原発もそうですが、誰かの犠牲の上で安穏とした生活が出来ている今を思い、自然と頭が下がりました。
ギャンブル商売
先日「なぜ韓国はパチンコを全廃出来たのか」という本を見付け、買いました。
新書版で昨年12月に売りだされた本です。
私は以前からパチンコをはじめとするギャンブルに対して色々な疑問を持っていました。
私も20代から30代の初めまでパチンコに行っていました。
それほどの金額をかけたことはなかったのですが、よく行きました。
そこに習慣性を感じていましたが、何かの切っ掛けで止めていました。
ギャンブルは競輪・競馬・競艇が法的に許されています。
パチンコも非合法的に現金化することも黙認されています。
私は競輪・競馬・競艇は経験ありませんが、したいとは思いません。
しかしそれを生きがいにしている人もいます。
私の同系会社の社員の中で、パチンコに溺れ、借金をし、自己破産・離婚に落ちた人もいます。
そのような自分の人生を貶めるのは自分自身の問題もありますが、依存症が高いというのも事実です。
パチンコはマリファナより依存性が高いという人もいる位です。
そのパチンコは日本ばかりでなく、韓国でも盛んでした。
2006年当時までパチンコ店は1万5千軒、非合法も入れれば2万軒あったそうです。
それを2010年に全廃したのが韓国です。
パチンコによって人生をダメにした人たちの多さが問題になり、マスコミ・政府・警察が本腰を入れて撲滅しました。
その経緯・内容が書かれたのが紹介した「なぜ韓国はパチンコを全廃出来たのか」という本です。
これから読み始めますが、なぜ日本でそれが出来ないかも書かれているようです。
パチンコはギャンブルが盛んなアメリカ・ラスベガスにはありません。
それは人為的操作ができる機械は、本当のギャンブルとはみなされないからだそうです。
パチンコも含めてギャンブルは公的認可があるものはお咎めがなく、認可されないモノは警察につかまってしまいます。
ギャンブルという行為そのものは同じなのにです。
公的機関が認めれがOKというのは何となく、前近代的感覚です。
ギャンブルによって人の人生が破壊されるのであれば、それは良くないものです。悪いものです。
「のめり込まない程度なければ娯楽だ」というのはナンセンスです。
「マリファナは後遺症が少なく、少しなら気分転換になる」という論理と同じです。
パチンコなりのギャンブルは、商売として考える時、儲かるからする仕事なのでしょう。
善悪で考えればしてはいけないものです。
それにより、多くの人が不幸になるようなものは、パチンコメーカーやパチンコ店が儲かるだけで、陰で泣いている人、家庭が多くいるはずです。
「良いこと」か「悪いこと」かを考えれば、日本でもパチンコは全廃するべきでしょう。
また、東京や大阪で考えられている「カジノ構想」なんて問題外だと私は思っています。
これからの働き方
先ほど息子の嫁と孫が帰京するので千歳空港まで送ってきました。
結構混んでいましたが、若干観光客が少ないようでした。
特に外人客はほとんど見ませんでした。
2日前にベトナムから帰ってきた兄の話では、飛行機に乗っていた人で日本で降りたのは兄達2名のみ。
また入国カウンターでもほとんど人はいず、連絡電車の中では1車両に2人だけという状態す。
いつもは多くの外国人でごった返しているところも、閑散としたものだったそうです。
先日の新聞では3月の外国人入国数は例年の半分くらいと言われていますが、現状は10分の1以下なのかもしれません。
その煽りで、先日北海道の観光バス会社が倒産しました。
今後ホテル・旅館など観光関連産業でも倒産の話は出てくるでしょう。
これも原発事故の風評被害と言えます。
そうするとこれも、被害補償の対象になるのでしょうか。
震災被害の他に、原発による風評被害の大きさは計り知れないものがあります。
この問題もしっかり線を引かなければどこまでも被害補償が増え続けます。
東電では保証し切れず、国の補償になるでしょうが、いくら増税しても追い付かない状態も予想されます。
現在の経済は、ある業界だけが単独で成り立つモノでなく、全ての業界が結びついています。
そのため今は直接被害は受けていなくても、必ず回り回ってきます。
これから被害を受けた人達への援助をしながらも、自分が生きる為に、なりふり構わず仕事をしなければならない時代になってゆきます。
今までの様な「癒し」の時代から、経済成長時の様な「モウレツ」な時代に逆行し、そのような働き方をしなければ生きていけなくなるような気がします。
今こそしっかり儲けることを考える時です。
素直・謙虚・感謝
昨夜も勉強会がありました。
今回のテーマは「素直」「謙虚」「感謝」について考えるものでした。
参加者は30代、40代、50代、60代の20名の会社経営者でした。
参加者の中には名の知れた会社の経営者もいて、皆さん本音で話されました。
「素直」でいる為には「謙虚」な心でなければならない。その状態でいると「感謝」の心が生まれるのですが、理屈で分かってもなかなか出来ないものです。
ある経営者は部下に「素直」さを求めながら、「素直」でない自分を発見すると言います。
また、ある経営者からは人を採用する時、「素直」な人間を採用しようとする。それを見るポイントの1つは両親や祖父母に対する考えである程度判断するという人もいました。
「素直」は「迎合」と違います。人の意見に左右される「優柔不断」を言うのでもありません。
「謙虚」は「自己主張しない」という訳でもありません。
起業家は会社を起業した時、自分の力を信じ、自分の考えをやり通す意思の強さが求められます。
アスリートは傲慢な位、自分の力を信じ、金メダルをとるために努力し、有頂天になり天狗と言われるくらい頑張って初めて獲得出来るものだと思います。
そのような選手育成をしてきたのは欧米のコーチです。
日本は逆に選手が練習努力の結果、自信を持ってきたところで、「傲慢になってはいけない、謙虚であれ」と諭すと、選手は力を発揮できなくなってしまいます。
結果、力を出しけれず敗退していったことがありました。
人は頑張る時、なりふり構わず頑張って、壁にぶつかった時初めて、「素直」「謙虚」「感謝」の心を持つことの大切さを知るのではないでしょうか。
人は一本調子で伸びていけません。ズッコケてしまいます。
階段の途中で踊り場があるように、自分を見つめる時それを知るのです。
「感謝」について話があった時、ある若い経営者が自分の父親である社長と考え方の違いで、いつも衝突していた時のことを話しました。
言い争いをした後、それでも父親に対し「感謝」しなければならないという気持はあったので、何とかその「感謝」の気持ちを持とうと、1日1000回「お父さん感謝します」と唱えたそうです。
右手にカウンターを持ち、数えながらしました。
それでもなかなか感情的にはそうならなかったそうです。
でも今は「感謝」しているそうです。
「感謝」の気持ちを持つということ1つとっても、色々な事例が紹介されました。
この勉強会は大変有意義で、考えさせられ、経営者同士が本音で話し得る会です。
来月は予定があり残念ながら参加できませんが、今後とも続けて参加していこうと思っています。
ストーリーとしての競争戦略
やっと「ストーリーとしての競争戦略」を読み終わりました。
厚い本なので、時間がかかりました。
この本は一橋大学大学院国際企業戦略研究科の楠木建教授が書いたもので、週刊東洋経済で特集も組まれたくらい注目された本です。
競争戦略という専門書ですので、私には少し難しいところもありましたが、大変興味を持って読みました。
その内容を一言で言えば「優れた戦略というのは思わず人に話したくなるような面白いストーリーを持ったもの」です。
優れた戦略ストーリーで事業を展開している会社としてトヨタ、デル、アマゾン、セブンイレブン、マブチモーター等の企業戦略を詳しく解説しています。
成功しているこの様な会社のやり方をマネしようとしても、成功出来るものではありません。
根本的・本質的なところでマネできないため、表面的にマネをして失敗していく企業の例も取り上げています。
楠木教授はこの本の7章で戦略ストーリーの「骨法10カ条」を上げています。
1.エンディングから考える
2.「普通の人々」の本性を直視する
3.悲観主義で論理を詰める
4.物事が起こる順序にこだわる
5.過去から未来を構想する
6.失敗を避けようとしない
7.「賢者の盲点」を衝く
8.競合他社に対してオープンに構える
9.抽象化で本質をつかむ
10.思わず人に話したくなるような話をする
この10カ条を読み興味をもたれたら、ぜひこの本を一読ください。
なるほどと思われることが書かれています。
単に物珍しい、人が思いつかないだけでは新規事業にはなりません。
すぐマネされてしまいます。
この本は、追随されない新規事業構築のため(そう簡単ではなりませんが)の参考本だと思います。
「女性起業」を支える男性
起業する時、1人起業もあるし、気の合う人と立ち上げることもあります。
起業時に人と組むというと往々にして、男性同士が圧倒的に多いのではないでしょうか。
時として男性と女性が組むこともあります。
それでも、男性が主になり、女性がサポートする立場なりがちです。
でも、女性が主で男性がサポートするのもいいのではないでしょうか。
男性と女性の関係は友達、恋人、夫婦がほとんどですが、仕事仲間としての「ペア」があってもいいと思います。
それも、女性の仕事をサポートする形です。
今まで、事業を興す、会社経営をするというと男性中心の世界でした。
私もそのような古い考えを持っていました。
でも、最近は女性の進出が多くなりました。
女性だから気付く、生活に密着した事業は掘り起こせば多くあるのです。
以前にもブログで書きましたが、マムプレナーという起業には、男性のパートナーは必要と思います。
家庭の中にいることが多かった女性が事業の世界に入っていく時、そこはまだ男性社会です。
女性の強みである、押しの強さ、それは時には図々しさになってしまいます。
本人は気付かないのですが、それは嫌われます。
それをフォローするのが事業社会経験のある男性が最適です。
夫婦という関係が一番でしょう。恋人同士というのもいいでしょう。
でも全く恋愛抜きのビジネスパートナーというのもあるかもしれません。
ただ、パートナーとなる男性を選ぶのはそう簡単ではないでしょう。
「幸運な巡り合わせ」が一番かもしれません。
その為には自分の夢を発信して、多くの人の話・考えを聞きながら探していくのです。
そして選ぶ男性のポイントは自己主張しない薬味のような存在の人です。
例えば胡麻。
胡麻は主役では無いけれど、振りかけたモノを食べると香りがし、その存在がしっかり分かります。
そのペアは、演じる役割は違うけれど「同じ夢を追う同志」です。
これから多くの女性をフォローする男女のペア―起業が増えていくような気がしますし、それは1人で起業するより成功率が高まる一つの方法かもしれません
経営の12カ条
昨夜は勉強会に参加してきました。
今まで何度もご紹介しています、稲盛和夫さんが主宰している「盛和塾」です。
今回は、昨年10月に中国の青島市で行われた、「稲盛和夫経営哲学青島国際フォーラム」での講演をDVDで見ながら学びました。
テーマは「経営の12カ条」でした。
「経営の12カ条」は経営の原点としていつも私達に教えていただいているものです。
それを今回、中国の経営者向けに説明したものです。
「経営の12カ条」については既に知っている方もいると思いますが、改めて紹介します。
「経営の12カ条」
1.事業の目的、意義を明確にする。
(公明正大で、大義名分の高い目的を立てる)
2.具体的な目標を立てる。
(立てた目標は常に社員と共有する)
3.強烈な願望を心に抱く。
(潜在意識に透徹するほどの強く持続した願望を持つ)
4.誰にも負けない努力をする。
(地道な仕事を一歩一歩、堅実にたゆまぬ努力を続ける)
5.売上を最大限に、経費は最小限に。
(入るを量って出を制する。利益を追うのではない。利益は後からついてくる。売上が伸びても、安易に経費を増やさない)
6.値決めは経営。
(値決めはトップの仕事。お客様も喜び、自分も儲かるポイントは一点)
7.経営は強い意志で決まる。
(岩をも砕く強い意思が必要)
8.燃える闘魂。
(経営はいかなる格闘技にも勝る激しい闘争心が必要)
9.勇気をもって事に当たる。
(たとえ儲かっても卑怯な振る舞いがあってはならない。脱税、粉飾などはもっての外。)
10.常に創造的な仕事をする。
(今日よりは明日、明日よりは明後日と常に改良改善を絶え間なく続ける。創意工夫を重ねる)
11.思いやりの心で誠実に。
(商いには相手がある。相手を含めてハッピーであること。皆が喜ぶこと)
12.常に明るく前向きで、夢と希望を抱いて素直な心で。
(苦しいときこそチャンス。笑う門には福来る。ただ、謙(虚)のみ福を受く)
この12項目を2時間近くにわたり、稲盛さんは具体的に説明していました。
昨夜の勉強会ではDVDを見終わった後、1項目の「事業の目的、意義を明確にする」の副題「公正明大で大義名分の目標」とは何かについてそれぞれの意見を述べ合いました。
私の解釈を少し述べます。
起業を志す人は最初はこのことにはあまり拘らなくてもいいのではないかと思います。
多くの起業人は「公正明大で大義名分のある目標」を目指して起業したのではありません。
「金を儲けたい」とか「贅沢したい」から始まっていると思います
最初はそれでいいと思います。
ただ、人を雇い、事業が少し大きくなってくると、壁にぶつかります。
「仕事をしてもうまく行かない」とか「従業員が言うことを聞いてくれない」、「やる気が無くなってきた」等困難に陥った時、「なぜ仕事をするのか」「何のために一所懸命になるのか」自問するようになります。
その時こそ「公正明大で大義名分のある事業の目的や意義」を作り上げるのが大切だと思うようになります。
形ばかりの経営理念を作っても、魂が入っていなければ空念仏になってしまいます。
ところで、「目的」と「目標」の違いが分からない人がいますので、私なりの若干解釈を書きます。
「目的」は「なぜ?」を問い、「目標」は「何を?」です。
「目的」は「なぜ生きるのか」「なぜ一生懸命頑張るのか」を明示するもの。「目的」はなかなか到達できないモノです。
目標は「いつまで、何を目指すのか」です。「今年の売上目標は1億円」等のように達成出来るものです。
興味をもたれたら、この経営の12カ条をプリントアウトして時々見られたらいかがですか?
私はこの「経営の12カ条」を目のつくところに貼っています。
チョットした時にヒントなり、生きる力をもらっています。

統一地方選挙
昨日は統一地方選挙でした。
皆さんは投票に行きましたか?
私の選挙区では知事も市長も現職が勝ち、道議、市議もほとんど現職が当選しました。
その中で、昔市議だった人が道議に当選しました。
彼は20年前札幌市議として活躍していましたが、市長選に落選してから消息が分かりませんでした。
ところが今回、道議に立候補していました。
組織も無く、お金も無く、ポスターは単色の名前だけのものでした。
忘られた名前の人で、私は正直当選は難しいだろうと思っていましたが150票差で当選しました。
今回の選挙で番狂わせはそれくらいでしょうか。
私は選挙のたびに思うのですが、投票者も立候補者も目指すものは「利益誘導」です。
今回も大震災に対する復興という名のもとで、お金を出すという公約を掲げて当選した候補者がほとんどです。
東北・関東は大変な被害で金銭的、人的支援は必要なところですが、北海道は函館や釧路の港周辺、その他牡蠣養殖業者には被害が出ましたが、比べるほどのものではありません。
風評被害にまでお金を出すと言っている候補者がいましたが、北海道に風評被害はほとんどありません。
選挙の度に、国民・地域住民の声を反映するという名のもとに、お金を出してきました。
国にしても地方自治体にしても莫大な借金を負っているにもか関わらず、社会的美名のもとでお金がばら撒かれてきました。
選挙民は一般論では赤字・借金解消を唱えながら自分のことになれば補助金や予算付けを求めます。
本当に将来の国や自治体のことを考える候補者が、「今まで出してきたお金はカットします」と言えばいいのですが、落選するでしょう。
耳触りが悪くても、本当のことを言う候補者を応援する風潮が生まれなければ、益々日本の再生は難しくなると思います。
特にこの大震災による復興のもと莫大なお金がつぎ込まれますが、本当に必要なところに出しながら、「私のところは大丈夫。自立できる!」という意識を持たなければ、疑似被害者が際限なく増えていく懸念があります。
国・自治体の議員、そして国民が自立していかなければこれからの再建は難しいと私は考えます。
「正義」の話
昨日からハーバード大学教授マイケル・サンデルさんの「これからの『正義』の話をしよう」を読み始めました。
結構厚い本でいつ読み終わるか分かりませんが面白そうです。
読んで最初に出てきた「正義」の話は2004年に発生したハリケーンにより被害を受けたフロリダで起きたことを取り上げています。
ハリケーン直後、あるガソリンスタンドでは1袋2ドルの氷が10ドル、小型の家庭用発電機が通常150ドルで売っているものを2000ドルで売っていました。
避難して入ったモーテルが、いつもは1晩40ドルが160ドル請求されました。
これらの商行為に対して、マスコミから「他人の苦境や不幸を儲けの種にしている」と非難されました。
しかし一部の経済学者はその非難を検討違いと論じました。
その根拠は、「価格は需要と供給によって決まる」と主張し、公正な価格などは存在しないというものです。
その上、氷や飲料水、発電機などが高くなったおかげで、こうした商品やサービスの消費が抑えられた。
また遠隔地の業者にとってハリケーン後、最も必要とされている商品やサービスを提供する機会が増えると言います。
その論理の中で市場価格の公正さを訴えています。
アメリカでは、不当に高く売っていると非難する人と、市場価格は当り前と思う人が混在してます。
でもどちらかというと、例え災害時でも、市場価格は高くても公正な価格だと言う人が多いようです。
一方、日本で起きた今回の大震災後、モノの不足は取上げられましたが、価格が異常に高くなったという報道は無かったように思います。
それなりに納得する値段で売られていたようです。
ここに日本人とアメリカ人との価値観の相違がみられるのではないでしょうか。
「正義」という言葉も違ってくるのかも知れません。
アメリカ人の価値観が特別というより、日本人の価値観の方が他の国と違っているのではないでしょうか。
「これからの『正義』の話をしよう」という本を読み始めたばかりですが、改めてこれほど価値観が違っている国同士が対等に商売をする大変さが改めて分かります。
アメリカなどの海外の国々は、大震災に遭遇した日本に、それなりの人道的援助はしてくれますが、この弱みに付け込んで商売をすることにいささかも躊躇することはないでしょう。
日本製品に取って代わる製品を出し、日本のシェアを奪っていくでしょう。
日本で必要とするモノも、これからはそれなりの高い価格で提供してくるかもしれません。
それも彼らの概念では「正義」なのでしょう。
厚い本なので、いつ読み終わるか分かりませんが、面白そうな本です。
自己抑制力
経営者は立てた目的・目標に向かって従業員の先頭に立って進んでいかなければなりません。
そして「その目的の意味するのは何か」、「目標を達成した時何が変わり、その後どうなるか」を示さなければなりません。
しかし経営者は実務の上では従業員に指示し、企画、生産、営業等の担当者に業務を任せます。
会社の目的・目標が明確にされ、それをどのようにするかは各部署の担当責任者が受け持ちます。
ところが時々担当責任者が、自分の部門のことを中心に考え過ぎて、部門間に不協和音が聞こえて来ることがあります。
そのままだと業務のスピードが落ち、目的・目標とは違う方向へ向かって行くことになりかねません。
それを防ぐため、その時は経営者自身が入り込んで調整していかなければなりません。
経営者は最高権限者です。
自分がすべて決定していけるのですが、それでは部門責任者に任せている意味がありませんし、従業員が育ちません。
経営者はその時「良き助言者」でなければならないと思います。
「俺の言うことを聞け!」という権力者ではなく、また何でも知っている「知恵者」でもありません。
「自分はすごいだろう」ということを示す「権力者」や「知恵者」はいりません。
「なぜ目的・目標に向かっていかなければならないのか」その為に「今、何をしなければならないのか」の手掛かりやヒントを示し、従業員に考えさせる努力が必要です。
「これはこうするのだ」とか「このやり方はダメだとか」と答えを出してはいけません。
勿論、緊急時には経営者が即決しなければならない時もありますがそれは別です。
人として、会社として大切な原理原則は守りながら、「なぜ」「どうして」そして「今、何をやる」を考えさせなければ、従業員の成長、そして会社の成長・発展はありません。
一時的、単発で終わる会社は、それがありません。
そして一番重要なことは経営者が会社の中で一番学び、人間として経営者として成長することです。
私の周りにいる経営者の中でも、会社が成長しているところの経営者は大変勉強家です。
本を読み、人の話を聞き、それを試してみる素直な人が多いです。
勉強しても「知恵者」になってはいけません。言いたいのを押さえる自己抑制力も必要になってきます。
私はこのブログを書いていながら、この自己抑制力が足りない自分を認識しています。
まだまだです。
「居酒屋ミーティング」
昨夜、「居酒屋ミーティング」を開催しました。
この「居酒屋ミーティング」というのは、私の事務所を居酒屋にして、お酒を飲みながら四方山話をしましょうという飲み会です。
参加メンバーは私が運営するレンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」に入居している人達が中心で、外部からのゲストもお呼びします。
昨夜は参加者12名位ほどで、18時から20時の予定でしたが21時過ぎまで続きました。
参加費は無料、ただし自分が食べたいもの飲みたいものを持参ということでしたが、十分過ぎるほど集まりました。
でも全て完食。
私は家内にお願いし2重箱のツマミを作ってもらいました。
普段は同じオフィスにいてもなかなか話をする機会がないものです。
この「居酒屋ミーティング」で普段話す機会がない人同士打ち解けて話が出来ます。
人の心理として、飲み食いをする時は普段の防御の鎧を少し下ろすそうです。胸襟を開いた話が出来ます。
また、居酒屋と違って周りがうるさいわけでなく、また時間も好きなだけ、お酒が無くなるまで話せます。
参加メンバーを少し紹介します。
英語の特許を専門に翻訳している女性、グラフィックデザイナーの女性、バルンアートをする女性とそれをヘルプする男性、広報マネジメントをする男性、記帳代行業の男性、建築設計の男性、IT業務の男性そしてその奥さん等です。
各分野で仕事をしている人が参加していますので、色々の話しが聞けます。
参加者メンバー同士で新しい仕事を始めた人達もいます。
この「居酒屋ミーティング」は今まで5,6回はしたでしょうか。
これからはもう少し頻繁にし、外部からのゲストも増やし、より多くのそしてより深い交流が出来る機会を作りたいと思います。
来月は札幌でも桜が咲きます。
その時はまた花見と称して飲み会を企画します。
今度は居酒屋かどこかになるでしょう。


「利益を出す」ということ
私は会社の経営数字の中で一番注目しているのは経常利益率です。
稲盛和夫さんが主宰する「盛和塾」で良く言われるのは、「最低でも10%以上の経常利益率が無いとダメだ」ということです。
半分近くの税金を払って、その利益を内部留保して資本基盤をしっかりしておくのです。
そうすると簡単に倒産しません。
今回の大震災でも復興に活躍しているのは長年蓄えた内部留保の多い会社です。
今朝の新聞に重機メーカーのコマツが今回の震災に対してブルド―ザ―や油圧ショベルなどの建築機械を約1000台送っているそうです。
コマツの社長は「こういうときは儲かる、儲からないじゃない。支援は売り上げや利益に優先する」と言い切っています。
そう言うコマツも12%の利益率があり、多くの内部留保があるから出来るのです。
また、支援するまで行かなくても、自社の立て直しがすぐ出来るのも、資金的に余裕がないと出来ません。
儲かっていた大手の企業はすぐに着手しています。
もうけ過ぎと言われていた企業が復興の中心になってきています。
この震災を見て、海外の企業は「日本の企業はもうダメ」と「日本はずし」が検討されましたが、それを跳ね返しているようです。
企業は一生懸命商売をして利益を出すのが一番。
でも、利益が多くなると誘惑も多くなります。
銀行などから土地購入や投資話があったり、「どうせ税金で持ていかれなら」と従業員の給料をドンドン上げたりする会社があります。
一時的に儲かっているかもしれず、それを散在しては企業としての永続性が失われてしまいます。
しっかり仕事をし、しっかり儲け、無駄使いせず蓄える。
そんな当り前のことが出来ているかどうか、今、企業もそして個人も問われています。
震災後の商売
大震災後3週間を過ぎ、まだ1万人以上が不明者で、原発事故解決も先行きが見えません。
それを心配しながらも、商売をする者は今後どうするかを考えなければなりません。
大震災に対する自粛と言われて、歓送迎会や花見が中止になっています。
それにより私のホテルも影響を受けています。
東北の「南部美人」という酒造メーカーの社長は「花見や歓送迎会は中止しないで、東北のお酒を飲んでください。それが復興支援になるのです」と訴えています。
それを受けて、東京の小売店では東北のお酒コーナーを設けたそうです。
でもそれにより、逆に他の地方の日本酒メーカーが影響を受けるかもしれません。
家具インテリア販売の「ニトリ」は、2012年2月期決算予想を震災の影響で連結純利益が13%減になると新聞掲載されていました。
震災の影響で売上が振るわないことが大きい要因のようです。
私は復興で家具が売れるかと思ったのですがそうではない様です。
もう1つ新聞に掲載されていた記事で中古オフィス家具の買取り価格が上昇しているというのがありました。
これは震災の影響で企業が予定していたオフィス移転を見合わせたために、中古家具の供給が減少したためということです。
中古オフイス家具への需要は増えても供給が少なくなっているのです。
以上のように例を少し上げましたが、震災後の商売の動きは、従来と違って一律ではないようです。
今までは大きなデフレといった景気の動向予測によって概ねその方向で各分野動いて行きました。
でも今後はインフレに備えなければならないかもしれません。
震災後は経済の流れが変わり、それぞれ仕事の分野ごとに動きがマチマチになって来るのではないでしょうか。
今こそ自分の仕事が関連している分野の動きを再度調査する必要があります。
単に従来の予測基盤で予測しても、違っているかもしれません。
震災特需を期待していても、そううまくは行かないかも知れません。
逆に思わないところで商売が良くなることもあります。
先ほど紹介しました私のホテルでも歓送迎会は減少していますが、減少するだろうと予想した宿泊が伸びています。ビジネス客が増えています。
その要因は今調べています。
北海道の経済は東京商工リサ―チ北海道支社によると3月の道内企業倒産は前年同月に比べ25%増加しました。
この数字にはまだ震災の影響を受けたものではないそうです。
その影響を受けるのはこれから3~6カ月後に出てくるようです。
再度足場を固めながら、状況判断に神経を使い、好機を探してゆかなければ、生き延びれません。
本当に大変なのはこれからです。
集団プラナリアの法則
「集団プラナリアの法則」というのをご存知ですか?
小阪裕司さんの「仕事心にスイッチを!」という本の中で紹介されていました。
もしかすると小坂さんだけが使っている法則なのかもしれませんが。
プラナリアとはミジンコみたいな原生動物で、頭を切ってもまた生えてくるそうです。
「集団プラナリアの法則」とは会社の頭と言われる重要な人間を切っても、またそれに相当する人間が育ってくるというものです。
これはよく経験することです。
会社の№2とか3と言われる人が会社を辞めていく時、経営者は不安を抱きます。
その為、その人間が経営者の意見と違っているのが分かっていても、辞められるのを恐れて何も言えなくなってしまう事があります。
その内会社の中が滅茶苦茶になり、衰退、倒産してしまいます。
本当は思い切ってそんな人間を切ってしまっても新しい人材が育って来るものです。
それより今までの№2や3の陰に隠れていた優秀な人間が、表に出てきて力を発揮するかもしれません。
これに似た法則で「2:6:2の法則」というものもあります。
どんな団体でも優秀な人は2割、普通の人が6割、ダメな人が2割いるというものです。
この法則は不変的なモノで、先ほどの「集団プラナリアの法則」とは逆に、ダメな人2割を辞めさせて、優秀な人2割と普通の人6割で運営しても、いつの間にか2:6:2の割合になってしまいます。
どうしてもダメな人間2割が残ってしまうのです。
そんな時良い言葉があります。
アメリカの経済学者シュンペーターの言葉です。
「しっかりした組織は『ドリーマー(夢見る人)』、『ビジネスマン(実務家)』、『嫌な奴』の3種類の人間から成っている」
「嫌な奴」も組織には必要という考えです。
組織を組み替えることは大切なことですが、それが経営ではありません。
組織をいじくりまわすことを重要な経営者の仕事を思っている人がいます。
それは違います。
今まで紹介したように、会社には「ダメ人」や「嫌な奴」はいるものとして考えるべきです。
結局、今いる従業員を引っ張っていく経営者の手腕に経営の成否が掛かっているのです。
是非ともその点は外さないようにしましょう!
マムプレナー
マムプレナーという言葉を知っていますか?
以前に読んだ浜口隆則氏と村尾隆介氏が書いた「誰かに話したくなる小さな会社」の中で紹介されていました。
アメリカでは主婦から起業家に転身するケースが多く、そう言った人達をアントレプレナーとは別に「マムプレナー(お母さん起業家)」と呼んでいます。
どうしてマムプレナーが多いかというとその理由の一つが「主婦や女性の目線で世の中を見ることで社会の不便や不満がより見えやすいということです。
またもう1つもっと現実的な理由は、80年代にアメリカでは不景気のため失業者が増え、男性達がどんどんクビになっていました。
その時に何とかしなければと立ち上がったのが子供がいるお母さんたちでした。
子どもを抱えているのに、路頭に迷うわけにはいかないので、お母さんが頑張ってスモール・ビジネスを始めたのです。
今はインターネットという道具がありそれを駆使して、子供が昼寝をしているうちに仕事をするのです。
このような話を聞くと、確かに私の周りの女性で頑張っている人の多くは子供がいる女性です。
以前受け持った講座「身の丈起業のすすめ」を受講した女性の中にも子供がいる人が4~5人いました。
「マムプレナー」という言葉は日本ではまだメジャーな名前にはなっていませんが、着実に増えていると思います。
日本は不景気の中での大災害。元気を無くしていく男性に代わって女性、それもお母さんが起業していくケースが増えていくと思います。
だだ、私の知るところでは、他の起業家支援の様な「マムプレナー」への公的機関からの起業支援はまだ無いようです。
家庭で出来る業種探しのポイントは何か、「マムプレナー」として起業した時、気を付けなければならない事項は何か、仕事をする上でのネットワーク作りも必要になって来ますのでその構築方法等、他の起業家支援と違うバックアップ体制が必要です。
これも「身の丈起業」の1つです。
私も機会があれば「マムプレナー」への支援策をまとめてみたいと思っています。
これから問われること
テレビ、新聞等では連日原発事故の報道が盛んです。
先行き見えない予測を聞かされて、暗い気持ちになってきます。
それと共に、経済の予測も芳しくありません。
今回の大災害・大事故によりこれほどの不幸と苦労を強いているものは何かを考えてしまいます。
その意味まで考えてしまいます。
豊富なエネルギーを生む為の原子力発電の問題点が、エネルギーの使い方を問うているように思います。
人間はもっと謙虚でなければならないと諭されます。
3月11日を起点に1人1人観点を変えていかなければならないのかもしれません。
幸いにして被害の少ない北海道に住んでいて、今それほど生活苦を感じていなくても、近い将来感じざるを得なくなると思います。
原発問題に目途がつけば復興が本格化するでしょう。
その復興事業に期待する企業もあるかもしれませんが、それで日本の経済が良くなるわけではありません。
復興のための増税が決まれば、消費税だと税率を1%引き上げる場合、2兆円超の財源が確保されると言われます。
復興資金だけで少なくても20兆円以上になるわけですから消費税は10%の増税になります。
1年で一気にとはならないでしょうから、5年にかけての2%の特別増税になるかもしれません。
増税により消費は一気に下がることが予想されます。
それが所得税に変わっても大変な増税になります。資産の海外移転などが起こるかもしれません。
景気が一気に下がる中で、経営者はどのような経営をすればいいのでしょうか。
自分だけ儲かるということはなかなか難しいと思いいます。
その時どのように生き、仕事をするかが本当に問われるのではないでしょうか。
悲観的に話をするつもりまありませんが、現実をしっかり見つめていかなければ、右往左往することになります。
これから復興資金調達のために国会などで集中して議論されることになります。
その動きに注意をしながら、個人としては自分がするべきことをする。
何をするべきかこれから問われてゆきます。
交差点にて
私が仕事しているビルの近くに交差点があります。
その交差点を通るたびに考えさせられることがあります。
交差点は幅が10m以上ある大きな道と5mほどの道が交差しています。
大きい道路を横断する時は、ほとんどの人は信号を守ります。
しかし5メートル幅の道路は信号を無視する人が結構います。
信号待ちする人を見ていると色々な人がいます。
「どんなことがあろうと青になるまで渡らないぞ!」としている人。
「隙あらば赤でも渡っちゃえ!」とする人。
「右見ても左見ても車は来そうにないけど・・・渡ろうかな、どうしようかな」と悩んでいる人。
皆さんはどのタイプですか?
ただ私は赤信号でも躊躇しないで、渡ってしまう人は好きではありません。
そのような人は決まりごとも平気で破ってしまう、自分勝手な人の様な気がします。
躊躇して、それでも渡る人はそれなりに規則を意識している人でそれほど問題でもありません。
また、はるか遠くを見ても車が来ないのに待ち続けるのも良いのですが、少し頑固かも。
心配なのは、信号があるのに気付かず、渡ってしまう高齢者。
周りの人が止めてあげなければ危ないです。
それと、子供連れのお父さんやお母さんはどんなことがあっても赤信号を渡ってはいけません。
子供に「規則は守る」ということを教えるのと、危ないことをしてはいけないということを身をもって教えないといけません。
以前聞いた話ですが、高齢者と子供は遠近感を感じにくいそうです。
だから、子供が急に車の前に飛び出すのは、車が近くに来ていても遠くだと錯覚してしまうからです。
大人が車が来ないだろうと思って渡っても、子供はそうはいかない。
親は信号を守ることで、子供が1人で道を渡る時、自分勝手に判断して飛び出さないよう教えることが大切なのです。
赤信号なのに子供の手を引っ張って渡っているお母さんを見ると「あなたは子供を交通事故に合わせるつもりですか!」と言いたくなります。
以上は信号を渡る時いつも私が思うことです。
大分主観が強すぎるかもしれませんが・・・
福島原発
昨日は少しfacebookの勉強をしてみました。
その時、以前に買った週刊ダイヤモンドで特集していました「フェイスブックの旅」も参考にしました。
一段落して、ほかのページをパラパラとめくっていましたら、東京電力の広告ページが掲載されていました。
それは5ページにわたり、カラーで福島原発の安全性を謳っているものでした。
この週間ダイヤモンドの発売日が1月29日ですから、今回の大災害・大事故の直前の様なものです。
そこでは主には福島第二原発が中心に書かれていますが、第一第二原発とも安全性を強調していました。
特に「非常時でも確実に電源を供給するディーゼル発電機」という項目では、原子炉水の冷却の重要性が書かれていて、今の事故がそこにあるのを改めて認識させられます。
東京電力と日立GEニュークリア・エナジーとの取り組みも強調され、現場責任者の写真も載っていました。
2人の姿が明るく誇らしげに写っています。
時間を戻せるとするならこの時に戻り、原発の安全性をより高めてもらいたかったと、写真を見ながらつくづく思います。
しかし時間は戻せません。
起きてしまったことは全力を挙げて処理してもらわないといけません。
震災による復興が日本経済に大きな影響があると言われているのに、さらに原発事故による観光産業、農水産物の輸出停止などでさらに大きな打撃が予想されます。
ネットのニュースでアメリカコロンビア大学の教授が「日本は今後貧しい国になるだろう」と予測したそうです。
しかしながら、そうはならないでしょう。
日本人がこの災害に遭遇し、見せた大きな力、一つの方向を見つめる一体感は、たとえ経済が一時的に落ち込んでも、それ以上の復興を成すと思います。
その為には、それぞれの人が1人1人、改めて自分の成すことを一生懸命しなければ良いのだと私は信じています。
facebook勉強会
昨夜、face bookの勉強会があり参加してきました。
facebookは始めたばかりでその仕組み、操作方法、その効果がほとんど分からない私にとって、大変いい勉強会でした。
この勉強会を主催したところは日本創造教育研究所(日創研)というところです。
この日創研という団体を知りませんでした。
ここの理念は「共に学び 共に栄える」です。
中小企業の活性化を願い創設され、1万社の会員がいるそうです。
「経営コンサルタント」、「人材教育」、「人事システム」を中心に活動しています。
経営の勉強する団体としては広く認知されているようです。
facebookの勉強は実質1時間30分ほどで、概略の説明で終わってしまいました
ですから本当に概略しか分かりませんでした。
でも講習料は無料ですから仕方がありません。
参加者が60名も集まりました。
ほとんどがfacebookの告知だけで集まったのですからその効果は大変なモノです。
facebookの勉強会に参加し興味を深くしました。
特にfacebookの「ノート」と言われるのはビジネスでの応用が期待されるシステムです。
ただ、私の場合、ここで知った知識と出来るかということは別です。
有料にしてでも、時間をかけて勉強したいものだと改めて思いました
今後も時間をみて勉強します。
理念
今、「企業理念」について調べています。
改めて今の「会社、社長、従業員」との関係を見ると、昔と変わってきました。
(株主も関係者に入ってくるでしょうが、中小企業の場合は株主=社長がほとんどですので、この際は株主を除いて考えます。)
昔は会社=社長で一体のモノでした。そしてそれに対して、従業員が対する対立関係にありました。
従業員が一生懸命働くのは生活のためで、働きに応じて賃金が支払われました。
社長は会社は自分と同一と考え、会社が豊かになることは社長個人が豊かになることでした。
そのような状況では、会社の理念を唱えても、従業員にとっては単なる念仏でしかなったのではないでしょうか。
今でもそのような会社はありますが、じきに衰退していくでしょう。
成長する強い会社は、社長も従業員も、共に目指す事の出来る企業理念、経営理念があります。
ダスキンには「人に社会に『喜びの種まきを』」、京セラとJALには「全従業員の物心両面の幸福を目指す」、セントラルスポーツには「0歳から一生涯の健康づくりに貢献する」等分かりやすい理念があります。
今の成長している会社の「会社、社長、従業員」の関係は、社長も従業員も会社の中の一員として機能し、共に共通理念を目指す関係だと思います。
職責は違うけれど同士の関係なのです。
そのように向かうベクトルが同じであれば大きな力が発揮されます。
同じベクトルを目指すと言えば、今の日本でしょうか。
日本の多くの人達が、被災者のために、災害地復興のために、そして日本のために自分達が出来ることを一生懸命努力しようと行動に移しています。
現在原発で400人の人達が不眠不休で戦っているのも日本のためなのでしょう。
自衛隊、消防署、警察、ボランティアの人達も同じベクトルに向かって戦っているのです。
方向性が同じ人達の力が集まれば大きな力になります。
そのことを今改めて知らされた気がします。
参考
「面白法人KAYAC」のホームページ上に上場企業の経営理念が紹介されています。
http://www.kayac.com/vision/philosophy
言葉使い
昨日、知人が「札幌オフィスプレイス」に訪ねてこられました。
用件はオフィスに入居しているAさんにお客様を紹介しようとしたようです。
ただ、その時に知人が話した言葉が妙に引っ掛かかりました。
「Aさんに○○というお客さんを紹介してやろうと思ったんです」と言いました。
私が気になったのは「○○してやる」という言葉です。
これはあまりいい言葉でありません。
完全に上から下へ見下した言い方です。
私は小さい頃、親に向かって「わかったよ。○○してやるよ」と言ったところ、父親に烈火のごとく叱られました。
「○○して上げる」と言いいなさと、何度も叱られました。
もっと丁寧な言葉は「○○して差し上げる」でしょうが。
そんなこともあったせいか「○○してやる」と言う言葉が気になります。
日常生活で気になるといえば、敬語・謙譲語を使う時です。
「ビジネスマナー意識調査」という調査によると言葉使いに「あまり自信がない人」が62.5%、「まったく自信がない人」が13.7%と、2つを合わせると、76.2%の人が言葉使いや話し方に「自信がない」と答えています。
4人に3人は言葉使いや話し方に自信がないと思っているのです。
私も気付かぬうちに間違えた言葉を使って、先ほど自分が感じた様なことを、他の人が感じているのかと思います。心しなければ。
敬語や謙譲語と関係ありませんが、チョットした言葉使いで違うものもあります。
小椋圭さんの歌詞で「もうと思えば下り坂。まだと思えばも上り坂」と言うのがあります。
言葉が1つ違うだけで、全く違うものになります。
言霊とはよく言ったものだと思います。
被災地の復興
今朝、朝刊を見ていましたら、宮城県名取市で「ゆりあげ港朝市」が再開されたと掲載されていました。
理事長の桜井さんという方が仲間を集め、新潟や北海道の取引先社長に協力をもらい再開したそうです。
また、テレビを見ていましたら、津波の被害を受けた洋服店が、海水に濡れた洋服や靴下を一度水で汚れを落とし、安い価格で売り出していました。
買う方も商品のことは承知の上で、まだ濡れた服を買っています。
どちらも多くの人達が購入していました。
この報道を見て、思ったのは「起業魂」「経営者魂」を持った人達が立ち上がったのだと。
皆を元気にしよう、不足し、不自由しているものを提供しようと、本来商売人経営者がいつも心掛けている動機で始めたのです。
ボランティアも大事ですが、このように商売を再開し、立ち上がろうとするバイタリティある人達を支援することは地域活性化の基本だと思います。
一方では不明者捜索がまだ続いていますが、新しい再生の芽生えを育て、広げていかなければなりません。
先ほど紹介しました朝市のように、今回の被害地で商売を再開する人達に、全国の経営者が協力し、物資の供給することが、経営者がするべき「助け」のように思います。
現在、国は不景気で就職できない人達に手厚い支援支給をしていますが、今回の災害で被害にあい、多くのものを失ったけれどやる気のある経営者を支援する方が多くの雇用が生まれます。
経営者同士の支援は私達経営に携わる者にとって身近のことに思います。
これからは寄付だけでない、自分で出来ることを探してみます。
ピンチがチャンス
今回の地震で被害を受けた人達はまだまだ、大変な生活を強いられ、毎日毎日、その日1日を生きるのに懸命なのでしょう。
将来の不安もあります。
それでも少しずつですが、そのような人達への救援の手は広がって来ました。
もう1つ、この地震で起きた大事故は原発事故です。
毎日気になりテレビを見ていますが、その報道に一喜一憂して、なかなか先が見えません。
今後どの程度期間で放射能の発生を止め、封印されるのか分かりません。
この原発の事故処理の対応に日本中はもとより、世界中も関心を寄せています。
世界では化石燃料にかわる新エネルギーとして、既に原発導入している国、また検討していた国が数多くあります。
日本はその中でも優秀な製品・技術を保持していると評価されてきました。
今回の日本の原発事故は、その処理いかんによって世界の原発開発の機運が一気に落ち込んで行く可能性があります。
でも、原発に対して素人の私が言っても詮ないのですが、日本の持っている全ての技術を使い、この事故をこれ以上広げず、処理することで、改めて日本の原発技術に対する評価が高まるのではないかと思います。
一時的には今回の原発事故問題で、原発に対して安全性を疑問視する傾向になるでしょうが、それに変わるものがなければ、再び原発設置の話が出てくることもあります。
その時こそ、事故処理を無事に対処することができた日本の出番が改めて生まれて来ると思います。
勿論今はそのようなことを考える時ではなく、早く処理をしなければならなりません。
しかしいつの日か、この大事故を教訓として、「ピンチがチャンスに変わる」時が来るのを、私は期待しています。
平成維新塾
いつもは朝のうちにブログを書くのですが、今日は9時から勉強会があり先ほど戻ってきました。
その勉強会は「北海道倫理法人会青年部」が主催する「平成維新塾」です。
12名ほどの若手経営者を中心とする勉強会で今日から毎月1回行われ、計5回予定しています。
私は1回目2回目を担当してお話しをします。
参加者は皆倫理法人会の会員ですので、経営に対する基本的な考え方はよく理解しています。
私はこの勉強会で心がけている事は、教えるというより、学びたいと思っています。
若い経営者中心ですが、それなりしっかりした考え方をもって経営している人が多いです。
私はたまたま稲盛さんの勉強会に入って教えられたことが少し多いだけで、それを紹介する役割だと思っています。
参加者のほとんどの人の「望み」は、人に必要とされる会社、人になることと言います。
そのやり方が違うだけで、向う方向は同じです。
来月も同じメンバーで勉強会を行います。
その時は参加者それぞれが「経営についてのテーマ」を最低1つ持って参加してもらいます。
そのテーマを発表してもらい、それぞれについての意見交換をします。
私も参加者の1人として「経営に対するテーマ」をもって持っていきます。
次回の勉強会が楽しみです。
紅型染作家
以前にもご紹介したかも知れませんが、「紅型(びんがた)染」をご存じですか?
「紅型」とは沖縄伝統の染物で琉球王朝時代からの伝統あるものです。
昨日、その紅型染物の展示会に行ってきました。
作家は山本ふじのさんです。
山本さんとは、私が月一回開いている「京セラフィロソフィ勉強会」で知合いました。
展示物はタペストリー中心ですが、その明るい色調と独特な構図。
魚のバラクーダ、ヒガンサクラ、マブヤー(魂)等が彼女独特の世界観で描かれ、見あきない魅力ある染物です。
山本さんは今札幌在住ですが、数年前まで沖縄で活躍していました。
沖縄では「りゅうぎん紅型デザイン公募展」(現「りゅうぎん紅型デザインコンテスト」)で平成16年度の大賞に輝いています。
山本さんは今月31日にフランスに旅立ちます。
フランス人とパリ郊外に暮らす予定だそうです。
彼女の才能がフランスの地でより大きく開花し、芸術の国で認められるような予感がします。
この展示会は30日までです。
ご興味がある方は是非この機会にご覧になってください。
そして彼女と話をしてみてください。
きっとその世界観に引き込まれてしまいますよ。
ふじの紅型染工房=「反映する庭―II」 『沖縄のファブリック伝統工芸びんがたの世界展』 ■開催期間:2011/3/23~2011/3/30 ※日祝定休
■ 10時~19時 ※月曜 12時~18時
■ 会場 札幌アリアンス・フランセーズギャラリー
(札幌市中央区南2条西5丁目10-2南2西5ビル2F)
■ 入場料 無料
■ お問合せ 011-261-2771

「デフレの正体」を読んで2
昨日に引き続き、藻谷浩介氏が書いた「デフレの主体」の中で、私が特に注目しているものをご紹介します。
デフレの主な要因は生産者人口の減少と高齢者激増です。
その中で高齢者問題について改めてご紹介します。
藻谷氏は過疎地域の代表として青森県を取り上げ、首都圏との比較しています。
2005年から2015年の10年間に青森では65歳以上が2割増え、75歳以上は4割近く増えるという予測になっています。5万5千人以上も増えるのです。
増加した75歳以上の1割が特別養護老人ホームや老人保健施設といった収容型の介護施設に入るとします。
そうすると、施設定員を10年間に5500人分増やさないといけません。
施設数では何十箇所にもなります。
また、増加した75歳以上の人のうち要介護認定を受ける人が仮に3割にとどまっても、絶対数では10年間で1万6千人人以上の需要増です。
ヘルパーを数千人単位で増やさなければなりません。
その後団塊の世代が75歳以上になる2025年あたりでは、介護福祉の需要が大爆発という事態が現実化しています。
一方、首都圏1都3県では2005年から2015年の10年間で65歳以上は45%増えます。
75歳以上は63%増、154万人の増加です。
このうち1割が収容型老人施設に入るとすれば、15万人、施設数で言えば数千か所作らなければなりません。
また3割が要介護となると50万人弱。ヘルパーも何万単位で増やさなければなりません。
団塊世代が75歳を超える25年にはさらに凄まじい福祉需要の爆発が起きます。
以上のような予測を藻谷さんは書いています。
これらの数字は人口から予測したもので、どんな予測データーより確実性が高いものです。
2015年はもうすぐです。
しかし、今回のような大災害が起き、その復興資金が20兆円30兆円と言われる中で、高齢者のための予算がどこまで組み込まれるか分かりません。
復興の方が優先事項です。
そうなれば、高齢者は今以上に自立していかなければなりません。
「年を取ったから...」というだけで休んではダメです。人を当てにしてはいけません。
高齢者同士で手をつないでいくのもいいです。
ただ、お互いの傷を舐め合う様な事はやめましょう。
65歳まで働きたいという人が多いそうですが、70歳くらいまでは頑張りましょう。
65歳から高齢者と言われるそうです。
私も何年かすると仲間入りです。
でも私はいつも言いますが、カッコいい年寄になりますよ。
「デフレの正体」を読んで1
10日程前ですが、「新現役ネット北海道エリアグループ」の朝食会でお話しをしました。
その内容は「『デフレの正体』を読んで」でした。
この本は藻谷氏が書いてベストセラーになり多くの人が読まれていると思います。
この中で特に注目したところをご紹介したいと思います。
この本の副題は「経済は人口の波で動く」です。
藻谷氏はこの副題のように、日本経済低迷の大きな要因は「高齢者人口の激増」と「生産年齢人口の減少」と指摘しています。
「生産年齢人口」とは15歳から65歳までの人口を言います。
例えば首都圏1都3県では、2000年から2005年の間に106万人も人口が増えています。
しかし生産年齢人口は最大22万人減少しています。
人口が増えているのに生産年齢人口は減少しているのです。
一方この間に65歳以上は118万人増加しています。
2000年から2005年の間の全国の65歳以上の増加は367万人ですから、3人に1人は首都圏民です。
首都圏では「生産人口の減少」と「高齢者の激増」の同時進行が起きています。
東京都だけを見れば「生産年齢人口」は1万人増加していますが、しかし65歳以上の増加は39万人。
1万人の増加は65歳以上39万人増の前に飛んでしまいます。
「生産年齢人口」は2000年から2005年の間、実数での減少日本一なのは大阪府です。その次が北海道3番目は埼玉県。
日本で一番「65歳以上の高齢者」が増えているのは東京都。
日本で一番「生産人口」が減少しているのは大阪府です。
なぜ高齢者が増えることが経済的に問題なのかというと、高齢者はお金を使わないところにあります。
ある程度のものは所有しまたそれほど贅沢はしない世代です。
それでいて日本の金融資産の80%近くは60歳以上の世代が持っていると言われています。
外国から稼ぐ金利配当が、外国に支払う金利配当を超えた分を所得黒字と言います。
この所得黒字はバブルの頃は3兆円程度でした。それが2007年は16.3兆円と5倍以上に増えた。
その多くは輸出企業とその企業の株主になっている高齢富裕層の財布に集中しています。
日本では地域格差と言われていますが、世代格差の方がより問題だと思います。
それでいて高齢者は弱者のように扱われています。
身体的には弱者かもしれませんが、金銭的には弱者世代ではありません。
勿論、高齢者にもお金がない人もいます。でもそれはどの世代でも格差はあります。
藻谷氏も書いていますが、日本で今必要なのは、高齢世代から若い世代への富の受け渡しが行われなければなりません。
このような状況がありながら、北海道の多くの市町村では、首都圏から退職者の移住計画を進めています。
しかし、一時的に人口が増えても、その退職者はすぐに高齢者になり、将来は福祉介護の対象者になります。
その分市町村の負担は増えます。
それでいながら、その移住者はほとんど税金を納めません。現役の時は首都圏で地方税を納税したでしょうが、退職後はしません。
将来自治体の負担になるのがわかっていながら、目先の人口増加だけに目がいっているように思えます。
明日はこの続きとして、高齢者の激増によって社会的にどのよう影響を与えるのか、またこの「デフレの正体」から抜粋したいと思います。
これから
経済の今後の予測は常に「流れ」の中で行われます。
しかし今回のような大災害は、今までの予測など吹っ飛んでしまう程のインパクトがありました。
福島の原発が処理されなければ何も進まない現状です。
逆にどんどん現状も、将来予測も暗いものになっていきます。
地震復興への莫大な予算組み、そして放射能による健康不安・食料品の不安、それによる観光客の激減。
既に、その影響はすごい勢いで拡大しています。
大震災というと大正12年に起きた「関東大震災」があります。
この大震災は第1次世界大戦後の不況下にあった日本経済にさらなる負担を負わせ、後の昭和恐慌に向かって行きました。
同じ不景気下で起きたこの大震災は日本経済に大きな打撃を与えるはずです。
私は経済学者ではありませんので、データーに基づいた予測は出来ません。
ただ、経営に携わる者として、常にリスクを考えます。
一部に震災復興景気の話をする人もいますが、一部の土木や建築関連の会社が少し良くなってもそれほどの効果が期待できるでしょうか。
国内の消費は減少し、食料品関連の輸出も減るでしょう。
輸出黒字から赤字になっていくかもしれません。
でも、だからと言って、黙って「仕方がない」と言い訳を言ってもどうしようもありません。
「このような大震災の時に不謹慎」と怒られるかもしれませんが、経営者や起業家は早く手を打ち、飯のネタを探す工夫を始めなければいけません。
1人1人の小さな工夫、努力の積み重ねでやっていくしかありません。
北海道にも海岸を中心として被害はありました。
それでも東北と比べてまだまだ恵まれています。
「もう年だから」、「まだ若過ぎるから」とかいう言い訳はやめて、今こそ何かに挑戦しましょう。
今こそ、北海道から発信して行く時なのかもしれません。
反作用の法則
「すべての作用は、それと同等の反作用を伴う」という物理の法則があるそうです。
人の人生にも言えるかもしれません。
過去に苦しい思いを抱きながら、懸命に頑張った人には良き事が起こるのです。
逆に怠惰な楽な生活をしていると、悪く辛い状況になってしまいます。
それでは今幸せであるということは、将来辛いことになるのではないかと思われるかもしれません。
「万事塞翁が馬」という言葉もあります。
でも、それについて三輪明宏さんが「正負の法則」の中で言っています。
苦労して頑張った人ほど、幸せが訪れた時には、例えそれがささやかなことであっても、苦労しなかった人の何倍もの幸せや充実感を感じることが出来ます。
また、逆に今が幸せな境遇であったとしても、それに甘んずることなく努力を続け、人間としての向上を目指すことで、負の方向には行かず、さらに良い方向に導かれていくのだ言います。
今は何に付け、大震災にあわれた人のことを思います。
この法則からいっても、大震災を経験した人達は、この苦労があっても、いつかきっと良き幸せな生活ができるようになるでしょう。
また、幸いにも災害に当たらなかった私達も、その幸せに感謝し、災害にあった人達のために行動し、また自分の仕事をしっかり頑張ることによって、より良いステージに上がっていくのだろうと思います。
私は、日本はこれからは良き新しい時代を迎えるのだろうと信じています。
11回「京セラフィロソフィ勉強会」5
今日は「京セラフィロソフィ」の47項「信念を貫く」について書きます。
「仕事をしていく過程には、様々な障害がありますが、これをどう乗り越えていくかによって結果は大きく違ってきます。
何か新しいことをしようとすると、反対意見や色々な障害が出てくるものです。
そのようなことがあると、すぐに諦めてしまう人がいますが、すばらしい仕事をした人は、すべてこれらの壁を、高い理想に裏打ちされた信念でもってつき崩していった人達です。
そうした人達は、これらの障害を試練として真正面から受け止め、自らの信念を高く掲げて進んで行ったのです。信念を貫くには大変な勇気が必要ですが、これがなければ革新的で創造的な仕事は出来ません。」
稲盛さんは、江戸時代のキリシタンが自らの信仰・信念に殉じたこと、明治維新の時、錦の御旗を掲げてそれを信念とした人達等を例にして信念の強さを説いています。
そして「自分はこういう目的、信念がある。それを貫くために、自分は命をかけて戦うのだ」という大義目名分を持ってほしいと言っています。
リーダーこそ真の勇気を持たなければならないのです。
会社の経営者は従業員が10人、20人でも社員の生活を守っていかなければなりません。
不景気の中、会社をしっかり経営し、従業員の生活を守るだけでも、社会的に大変貢献していると言えます。
自分や従業員を脅かす、例えば暴力団のような者が来たら、けんかなどしたことのないような気弱な経営者でも、勇気をもって立ち向かわなければならないのです。
経営者には勇気、忍耐、努力が必要ですが、特に勇気は非常に重要です。
勇気を持って、信念を貫くと言えば、1週間前に起きた大震災に向かって立ち向かい、努力している人達がいます。
「俺が行かなければ」と言って志願して原子力発電所に向かった、あと半年で定年を迎える59歳の東京電力の男性がいます。
自衛隊、消防署、警察等の多くの人達が、自分や家族を犠牲になるのを覚悟して戦っています。
今私達は、信念を持つことに重要さと、その崇高さを見て、感動しています。
そして今私達は「何のために生きているのか」まで問われているのです。
11回「京セラフィロソフィ勉強会」4
今日は「京セラフィロソフィ」46項の「もうダメだというときが仕事のはじまり」について書きます。
「ものごとを成し遂げていくもとは、才能や能力というより、その人の持っている熱意や情熱、さらには執念です。
すっぽんのように食らいついたら離れないというものでなければなりません。
もうダメだと、というときが本当の仕事のはじまりなのです。
強い熱意や情熱があれば、寝ても覚めても四六時中そのことを考え続けることができす。
それによって願望は潜在意識へ浸透していき、自分でも気付かないうちに、その願望を実現する方向へと体が動いていって、成功へと導かれるのです。
素晴らしい仕事を成し遂げるには、燃えるような熱意、情熱を持って最後まであきらめず粘り抜くことが必要です。」
稲盛さんはこのように言いその後、「経営においても、普通ならあきらめてしまうものを、粘って成功させるという戦法が必要です。
ただ『もうダメだというときが仕事のはじまり』ということは、そもそも余裕ある経営をしていなければ言えないことなのです。」とも言います。
稲盛さんはよく「土俵の真ん中で相撲をとる」という表現で、余裕ある経営をしなさいと説いています。
俵に足が付いてから「まだ頑張ります」と言っても、本当にもう後がない時が多いのです。
会社が好調の時、慢心し、新しいことを始めようとしない。しかし、業績が悪くなると急に儲かる新規事業はないかとあわててしまう経営者は多いのです。
一方、起業したばかりの人にも言っています。
起業したばかりではそんな余裕ある仕事はできません
仕事がうまくいかないと、お金も無い、車も無い、人も無い、と言って自分で限界を作っている人がいます。
自分で限界を作ってしまうから出来ないのです。無一文でも出来ます。
稲盛さんは最後に「私は先ほど余裕がなければダメだと言いましたが、余裕がなくても裸一貫までは頑張ることができます。」と言いきっています。
私も、振り返って見ますと、意識しないうちに自分で限界を作っていました。
性格的なモノなのかもしれませんが、どうしても先行きのことを考え過ぎてしまうことで、そのリスク対策を考え、いつの間にか自己防衛的な意識の中で、限界を作っていたようです。
「もうダメというときが仕事のはじまりは」私にとっても改めて考えさせられた項目でした。
11回「京セラフィロソフィ勉強会」3
今日は「京セラフィロソフィ」の45項「開拓者であれ」について書きます。
「京セラの歴史は人のやらないこと、人の通らない道を自ら進んで切り開いてきた歴史です。
誰も手掛けたことのない新しい分野を開拓していくのは容易ではなく、海図や羅針盤も無い状態で大海原を航海するようなものです。頼りになるのは自分達だけ。
開拓するということは大変な苦労が伴いますが、半面これをやり遂げた時の喜びは何物にも代えがたいものがあります。
このような未踏の分野の開拓によって、素晴らしい事業展開が出来るのです。
どんなに会社が大きくなっても、私たちは未来に夢を描き、強烈な思いを抱く開拓者としての生き方を取り続けなければなりません。」
と稲盛さんは書いています。
続けて稲盛さんは自分の人生を振り返って見ると、田んぼのあぜ道の様なぬかるみを歩いてきたようなものだと書いています。
フッと横を見ると「舗装されたいい道」があり楽に行けるだろうと思います。
「舗装された道」とは専門家が教えてくれる道、あるいは皆が通っていく道です。
でも自分はそのような道を通ろうとは思わない。
自分は研究者なのだから何か新しいことを開発しなければならないのです。
大勢の人が通る道にはもう何も残っていない。
あぜ道の方は泥まみれになるかもしれないが、ヘビやカエルに出会い新しい発見があり面白い。
そのあぜ道を歩く時、人が通った道ではないので、時として道に迷うこともあります。
その時に唯一無二の羅針盤となったのはこの「京セラフィロソフィ」でした。
私は「開拓」という言葉を聞くと、北海道民として気になる言葉です。
屯田兵や開拓民の末裔としての現在の私達は、決して忘れてはいけないのに、忘れてしまいそうな言葉です。
開拓者精神とはリスクを乗り越えて挑戦する心の有り様です。
リスクを避け、楽な生き方を求めている自分達へ発せられたような今回の大地震。
これで目が覚めたような気がします。
11回「京セラフィロソフィ勉強会」2
今日は京セラフィロソフィ44項目にある「チャレンジ精神を持つ」についてお話します。
「人はえてして変化を好まず、現状を守ろうとしがちです。
しかし新しいことや困難なのとにチャレンジせず、現状に甘んじることは、既に退歩が始まっていることを意味します。
チャレンジというのは高い目標を設定し、現状を否定しながら常に新しいものを創り出していくことです。
チャレンジという言葉は勇ましく非常にこころよい響きを持つ言葉ですが、これには裏付けが必要です。
困難に立ち向かう勇気とどんな苦労もいとわない忍耐、努力が必要です。
自分達にはとてもできないと言われた難しいものをつくるというチャレンジの連続が、京セラを若々しく魅力ある会社にしてきたのです。」
稲盛さんはこの言葉に続いて、
「チャレンジとは格闘技にも似た闘争心を伴う戦いを意味します」とも言っています。
経営の12カ条8項に「燃える闘魂」というのがありますが、それと同じものです。
ですから、このチャレンジ精神は「闘争」であり、もう一つバーバリズム(野蛮主義)と表現することも出来ると言いいます。
歴史における文明の興亡を例に取り上げています。
ローマ帝国がほろんだ一つに好戦的なゲルマン人の侵攻がありました。
蒙古民族の元はヨーロッパの文明人を攻めました。
文化レベルの高く知識も豊富な文明人が勝つだろうと思いますが、実際はより強い闘争心を持っている野蛮人が勝ったのです。
会社もそうです。
歴史もあり、高学歴の人が多い会社より、野蛮と言われるほどの闘争心を持つ会社が新しい分野や事業に果敢に挑戦し、勝利するのです。
マンネリ化した会社の多くは「確実に経営する」という名目の上で、チャレンジを忘れ衰退していくのです。
ただ稲盛さんは「チャレンジも軽々しく挑戦すればとんでもない大失敗を招いてしまいかねません。
どんな障壁に当たろうとも、それを乗り越えて努力を続けていくというタイプの人でない限り、チャレンジしてはならないと私は思っています。」と言っています。
下手にチャレンジをすると大やけどを負うかもしれません。
だから無理することは無いのです。
しかしチャレンジを忘れた会社は衰退して行きます。
闘争心を持ち続ける会社のみが勝ち続けるのです。
11回京セラフィロシフィ勉強会1
昨日毎月定例の京セラフィロソフィ勉強会を開きました。
1.「人間の無限の可能性を追求する」
2.「チャレンジ精神をもつ」
3.「開拓者であれ」
4.「もうダメだというときが仕事のはじまり」
5.「信念を貫く」
この5項目を勉強しました。
今日は「人間の無限の可能性を追求する」について書きます。
仕事において新しいことを成し遂げられる人は、自分の可能性を信じることのできる人です。
現在の能力を持って「出来る、出来ない」を判断してしまっては、新しいことや困難なことなどできるはずはありません。
人間の能力は努力し続けることによって無限に広がるのです。
何かをしようとする時、まず「人間の能力は無限である」ということを信じ、「何としても成し遂げたい」という強い願望で努力を続けることです。
ゼロからスタートした京セラが世界のトップメーカーになったのはまさにこの事の証明です。
常に自分自身の持つ無限の可能性を信じ、勇気を持って挑戦するという姿勢が大切です。 人の能力は進歩します。
毎日運動をすれば次第に身体は丈夫になるし、学力も勉強すればどんどん向上します。
「自分には無限の能力がある。それを伸ばせなかったのは、自分が今までその能力を向上させるように努力してこなかったからだ。それならば今からでも能力を磨いていこう」と思うことが大切です。
稲盛さんは自分の可能性を追求することの1つとして第二電電(今のKDDI)を設立した時のことを書いています。
設立の時、そのよりどころとしたのが「京セラフィロソフィ」でした。
「京セラフィロソフィ」を唯一の武器として携えて挑戦しました。
京セラ幹部には「私は電気通信の知識も技術も何もない。そんな男が電気通信事業で采配をふるって成功するなら、『京セラフィロソフィ』が正しかったことの証明になるだろう」と言いました。
稲盛さんは現在日本航空再建に取り組んでいます。
そこでも「京セラフィロシフィ」を携えて頑張っています。
日本航空のホームページ上では「企業理念」と、「JALフィロソフィ」が掲げられています。
稲盛さんは現在も身をもって実践しているのです。
宜しければご覧ください。
JALグループ企業理念:
http://www.jal.com/ja/corporate/rinen.html
自分は何ができるか
今朝の日経新聞の「春秋」にアメリカのケネディ大統領就任演説の言葉が紹介されていました。
「国があなたのために何かをしてくれるのを問うのではない。あなたが国のために何ができるかを問うて欲しい」
今こそ、その言葉は今の日本人への言葉として胸に迫ってきます。
災害にあわれた地域の回す為でしょうか、コンビニのおにぎりが無くなっています。
ガソリンもその他の物資も不足しています。
私の会社への材料入手も困難になってきています。
大変ですけれど仕方がないです。
不足だと文句を言ってもどうしようもないです。
東京方面では電力不足のため「計画停電」をすると言われていました。
ところが、それが計画通りにならないと言って、東京電力はマスコミから「無計画停電」と非難されています。
でも、今の大災害の時、関係者は一生懸命に命を賭けてやっているはずです。
これほどの災害を目にして、経験の無さからミスも多いでしょう。
もう、そのミスを責めるのは暫く止めませんか?
今はミスを責めたり、足引っ張りするより、少し不便になっても我慢をして、より良くなる為にどうするかの提案を出す方が、今必要の様な気がします。
今後東京での電力不足はすぐには改善されないだろうと予想されます。
今後夏を迎えるにあたって、益々電力不足が問題になります。
東京電力に文句言っても仕方がありません。
仕事に支障が起きるので、もしかすると大手企業は東京脱出するかもしれません。
東京から飛行機で1時間30分の北海道・札幌に拠点を移す事も考えられます。
個人も脱出するかもしれません。
また、今後食料を考えると、どこかに家庭菜園を借りて野菜作りをするかもしれません。
これから自分で出来ることが周りに沢山あるはずです。
そして、もしかするとそれが仕事に結びつくかもしれません。
今こそ文句を言うより、自分達は何ができるかを考える時です。
これから世の中の流れ、仕組み、環境が大きく変わります。
前を向いて生きていきましょう。
今するべきこと
今日は月曜日。
特別な月曜日の様な気がします。
今朝からテレビの放送はほぼ通常な番組構成になっています。
札幌に住んでいる私にとって周りは通常生活です。
しかし、実際は違います。
被災者たちと共通の痛みは持てませんが、連帯感は持てます。
それ相応の物質的、精神的、金銭的の負担も覚悟しなければなりません。
昨日の菅総理大臣の国民へのメッセージを聞いて、私は同感です。
かってなかったほどの未曾有の大災害を受けた日本、その為に日本中一致団結をして克服していこうというメッセージです。
言うまでも無いことですが、私たち1人1人は自分の立場で一生懸命仕事をすることが第一、そして必要な支援は積極的にするべきです。
きっと増税が審議され決まるでしょう。
今まで受けていた生活も不自由になることもあるでしょう。
仕事面でも環境が大きく変わるかも知れません。
例え環境がどう変わっても対応ししっかり仕事をこなして利益を上げ、納税をする。
利益を上げなければ、納税が出来ません。
納税こそが最大の被害者への貢献だと思います。
逆に、税金で助けられてはいけません。
これがまず経営者としてするべき第一の心構えではないでしょうか。
祈りと感謝
連日の地震報道を見るたびに被害の大きさに驚くばかりです。
2晩明けたにもかかわらず、いまだ被害の全容がわかっていない状況。
テレビを見て思うのは、ただただ、一人でも多くの人たちが助かる事を願うだけです。
飲み物も、食べ物もない生活を強いられている人たちがいます。
被害にあった人達を夜も寝ず助ける人達がいます。
食品や毛布を提供する会社がいます。
私は祈ることと、普通の生活ができる幸せに感謝するだけです。
大災害
昨日発生した大地震・大災害は広い範囲にわたり、発生時から全てのテレビ・ラジオはその報道ばかりです。
今日になると益々その被害の大きさが報道されています。
昨日地震発生当時は札幌で震度3だったそうですが、私はその時街の中を歩いており、気付きませんでした。
会社に戻ると大地震のことを知らせれびっくりしました。
この大地震の報道を見ている時、悲惨な事を知ると同時に、別のところで起きているだろうニュースが全て遮断されたようになっていることが不安になります。
被害にあわれた人は大変気の毒です。
私たちが出来る事はするべきです。
妻は義援金を送りましょうと言っています。
でもそれとは別に世の中は動いています。
その報道されていない起きている事を知るには、やはりネットの力はすごいです。
ネットで知ることが出来ることの便利さを改めて認識しました。
そして今後この大災害を契機に日本はどうなるだろうかと考えます。
菅政権は国会解散や総辞職など出来る状態では無くなるでしょうし、与野党一致して予算を作っていかなければならなくなります。
また、円高から一気に円安になる可能性も大きいです。
今まで日本は円高で吸収していた世界中の物価高も、円安によって一気に押し寄せ、デフレからインフレになる転換期になるかもしれません。
それでも景気が回復しなければスタグフレーション(景気停滞の中の物価高)になる可能性もあります。
今年になってまだ3カ月、その3カ月の間に世界中で政変、物価動向、天候、そして大天災が起きています。
これから何が起こりるか分かりません。
以前にもブログで書きましたが、まずは自分を守る、自己防衛策を考えておくことが大切だと思っています。
人を助ける前に自分の足場をしっかり固めなければならのいのです。
今その時だと思います。
セールスのポイント
昨日来社された方とお話をしていて思った事です。
営業マンにとってセールストークの最初の一言と1枚のチラシとが大切なのではないでしょうか。
セールスをしたいことを一言で話せる「キャッチコピー」、それと相手の心を「ガシッ」と掴むモノが必要です。
特に相手が忙しい人で、やっと会えた人にセールスする時こそそれが必要です。
相手の心を「ガシッ」と掴むものは、A4サイズの紙に書かれたチラシ1枚。
儲かっている会社の社長は忙しい人が多いです。
そのような人に長々話をすると「もういいよ」と言われてしまいます。
それこそ1分で概略が説明できることが必要です。
それと、儲かっている会社の社長にお話しをして、「ガシッ」と相手の心を捕まえる言葉は、「会社が良くなります」「利益が出ますという」言葉です。
それは「会社が良くなる」「会社に利益が出る」のであって、社長個人の儲け話ではありません。
会社のことを懸命に考えている社長にとって、第一は会社です。
時として、セールスのポイントをそこで間違えてしまう営業マンがいます。
自分自身の儲けのことを考えている社長もいるでしょうが、健全な会社の社長は自分のことをさておいてでも、会社のこと、社員のことを考えます。
セールス用の書類も3種類用意します。
1枚目は図やイラスト中心の一目で分かる「概略書」。
2枚目は裏付けとなる大まかな数字の書かれた「裏付書」
3枚目は詳しい「説明書」です。
一番大事なのは1枚目の「概略書」です。
2枚目の「裏付書」や、時として詳しい「説明書」から入ろうとする人がいます。
それは間違いです。
相手が見た瞬間に「面倒だな」と思ってしまっては、もう聞く耳を持ちません。
「概略書」で見せ、興味を持ってもらったら、その「裏付書」で数字説明します。
営業マンがいくら「いいですよ」と言われても、数字的裏付けがないければ信用しません。
時としては2枚目の「裏付書」の説明までにして、止めておくのも方法です。
本当に興味を持ってもらうのに、後日まで少し時間を置くのもいいでしょう。
興味を持っていただいた時に「説明書」で詳しい話しをし、シュミレーションなども行います。
「概略書」を見せて、相手が興味を持たなければ、サッサと帰ってくるべきです。
お互いに時間の無駄です。
「相手が興味を持たなければサッサと帰ってくるのがいい」とは、神田昌典さんも言っています。
粘ってセールスするより、アッサリと帰ろうとする方が、相手にインパクトを与えます。
「そんなにアッサリ帰るなよ。少し説明していけよ!」という気持ちにさせます。
あまりテクニックに走ってはいけませんが、それも人間の真理です。
セールスも少し工夫をすると違いが分かります。
以上は元営業マンであり、今は営業を受ける立場からの考えです。
言葉について
今日は私が書いている「銘肝録」を読み返していて、いい言葉がありましたのでご紹介します。
誰かの言葉です。(私ではないと思います)
「気配り」とは自分が傷つかず、相手に気に入られるために神経を使うことです。
相手によって気配りの程度も態度も違ってきます。
「心配り」とは相手を傷つけず、相手により良くなってもらい、突き詰めれば生きる勇気を与える為に神経を使うこと。
それは思いやりとなって表面に出てきます。
「心配」とは自分の目的にストレートに神経を使うこと。
「配慮」とは自分の目的を果たすために、ヨコに神経を使うこと。
「自由」とはお互いに認め合うルールを守った上で、フリーにプレーすること。
自由とはお互いに厳しいもの。
「勝手」とはお互いに自分だけが認めるルールでプレーすること。
「心が広い」とは自らの利害に対し、マイナスやダメージがあること、不利なことに対しても寛容で許すこと。
「正義感」とは自らの利害関係のないことに対しても「許さん」という強い信念を言います。
自らの利害に対して許さないという心情や感情を持つことは「正義感」でも。「心が広い」のでもありません。
単に「心が狭い」人なのです。
また、どんな時でもニコニコしている人は「心が広い」のではなく「お人好し」にすぎません。
以上の様に、言葉とは似ているようでも、その意味するところが全く違ってきます。
最後に紹介しました「心が広い」「心が狭い」「正義感」「お人好し」の内容説明は、よく自分が陥るところで、意識しています。
感謝
東京から里帰りしていた娘と孫が、昨日帰りました。
同じく東京から私と同居する母の様子を見に妹が来ていましたが、昨日帰りました。
途端に急に寂しくなっています。
私ども夫婦が両親と同居して1年3カ月。
昨年は父が亡くなりましたが、母は元気です。
昨夜、妻とこの1年3カ月を振り返って話をしました。
私も妻も共に感じているのは、兄弟姉妹同士がより仲良くなっているという実感です。
両親が病気がちになり、一昨年より私共夫婦が同居することになりました。
その時から、兄や妹たちは両親を見舞いに私の家を訪れるようになりました。
以前両親が元気な時は、兄弟姉妹が一堂に会することなど2・3年に1度あるかどうかでした。
それが今では毎月のように東京から妹たちが来てくれ、札幌に居る兄も含め両親を囲んで懇談をしたり、食事会をするようになりました。
両親にとって一番の願いは兄弟姉妹が仲いいことです。
親である私も同様に、自分の子供達皆が仲がいいことが嬉しいです。
今の状況から振り返ってみれば、全てが必然のように思います。
兄弟姉妹がより仲好くなっているのは、両親が私たち子供に残してくれている最後の宝物なのかもしれません。
今改めて両親に感謝しています。
「寛大」と「寛容」
今朝、なぜかイラつく自分に気付きました。
何となくで、特別理由があるわけではありません。
人に好まれる性格は寛大な人、寛容な人です。
人は自分には寛大な心、寛容な心がなくても、他人にはそれをを求めます。
人には優しさを求めるのでしょう。
この「寛大」と「寛容」の意味は似ています。
でも、若干違います。
辞書によると「寛大」とは度量が大きく、思いやりがあり、むやみに人を責めないこととあります。
「寛容」とは心が広くて、よく人の言動を受け入れること。他の罪や欠点などをきびしく責めないことです。
この2つは似ていますが、その反対語を調べてみると、その違いが分かります。
「寛大」の反対語は「偏狭(へんきょう)」です。
「偏狭」とは自分だけの狭い考えにとらわれること。度量の小さいことを意味します。
「寛容」の反対語は「厳格」です。
「厳格」とは 規律や道徳にきびしく、不正や怠慢を許さないことです。
仕事をする時、上司が「寛大」で「寛容」な人だと、いい上司と評価されます。
それでは会社のトップはどうあるべきでしょうか。
私は「寛大」であっても、「寛容」であってはいけないと思います。
「寛大」でありながら「厳格」であるべきです。
トップが「偏狭」な心の持ち主では誰もついてきません。
しかし仕事に対して優しすぎると会社はつぶれます。
「寛大」な心を持ちながら、仕事の上では「厳格」に処理するトップこそ、部下から信頼され、ついていこうという気持ちにさせます。
優れた経営者は、特に若い頃「カミソリ」と言われるくらい厳格な人は多かったです。
そのような経営者は自分にも厳しかったのです。
「寛大な心」を持ちながら「厳格」な仕事。
今朝改めて認識した言葉でした。
自己防衛
今朝の朝刊にまた大臣辞任が大きく載っていました。
最近私は新聞を読むと、政治のところは飛ばしてしまいます。
ゴタゴタした今の政争ばかりの政治に興味が持てません。
政治に興味を持たなければならないのは分かっていますが、何にも出来ない自分の非力さを思うと、読んでまたイライラするだけ。つい避けてしまいます。
国民は政治に対する自分の意思表示を選挙でしか表せられません。
貴重な1票とい言われながら、1票の格差裁判で是正勧告されても改善されないまま。
世界中が大きく変化しつつある今、日本政治の体らくぶりにあきれている人は多いと思います。
政治家一人一人はテレビなどでいいことを言うのに、やっていることは違います。
物価問題、雇用問題、為替、その他多くの経済に関する問題もこれからどうなるか分かりません。
デフレと言われながら、一気にインフレが発生するかもしれません。
それは景気が悪いのにインフレになる「スタグフレーション」という最悪の状況になる可能性が高いと思われます。
私が学生時代は世の中の不条理を正すとして学生運動も盛んでした。
政治に皆が関心を持ち参加していました。
その後も「草の根運動」としてありましたが、それも今では一部の人達の動きでしかなくなったように思います。
私たちはこれからは自己防衛を考えなければなりません。
自分達の仕事を守る為、自分達の財産を守る為、それは家族を守る為です。
国や地方自治体に依存しても、期待できるほどの施策が出てくるとは思いません。
藻谷氏の「デフレの正体」をよると、今後大きな問題に1つは高齢者問題があります。
高齢者の増加に対して国や自治体の対応の遅れは既に起きていますし、今後爆発的に増える将来に対するプランもありません。
若い世代は今後も収入も増えず、苦しい生活を強いられるかもしれません。
でも、これからは誰かが何かをしてくれることに期待は出来ません。
やはり自分で稼ぐ道を作ることが重要です。
無理をしない、身の丈で出来る小さな起業で別収入の道を作るのです。
周りを見渡せば自分しかできないことがあると思います。
自分の将来は自分で保証するしか無いのです。
春よ来い!
北海道・札幌はまだまだ冬。雪が解けたと思ったらまた雪。
春近くなると三寒四温と言われますが、まだ四寒三温です。
それでもこの雪も今月の終りには無くなっていると思います。
北海道の春は花々が一斉に咲きます。
梅も桜も一緒です。
東京の方では梅が三月の初めに咲き、四月には桜が咲きます。
北海道は梅も桜も一緒に咲きますから、小学校の教科書に梅が咲いて、その後に桜が咲くと書かれていても理解できませんでした。
ですから恥ずかしながら、私は高校の頃まで梅と桜の区別が出来ませんでした。
北海道や東北の雪国の人にとって春は特別の様な気がします。
雪がなくなり、一斉に花が咲き、鳥が飛び交う様子は、心理的にも、視覚的にも人の心を開放的にします。
何かいいことがありそうな予感を持たせてくれます。
四月は入学式・入社式、会社の決算も新年度を迎えます。
一月が年の初めなのに、三月決算、四月新年度というのは日本の風土になっています。
それは日本人の基本生活様式になっているのでしょう。
来月は四月です。
今年の初めに「今年の目標」を立て、「やるぞ!」と思ったのに上手く言っていない人へ
四月に向け私と一緒に再度挑戦の計画を立ててみませんか?
一月より四月は心理的にも、環境的にも実行に移せ易い時を迎えます。
寒い一月に立てた計画も、寒い冬の間に凍えている人もいるのではないでしょうか?
春を迎え、浮き立つ気持ちの時こそ再チャレンジの時です。
今年は年初めから色々なことがあました。
政治や経済は憂慮することが沢山あります。
そんなのを言い訳にしないで、今こそ改めて自分の足場を固めてみたましょう!
これは自戒の意味も含めての提案です。
カンニング問題について
今、盛んに報道されているカンニング問題について色々なお考えがあるでしょう。
私はどう考えても騒ぎ過ぎのように思います。
たかがカンニングでしょう。
確かにカンニングは悪いことです。悪いことをしてはいけないし、すれば罰せられます。
だからカンニングが見つかったら叱られるのは仕方がありません。
しかしそれが警察に訴えられる事は異常です。
大学側は「警鐘」と言いますが、「見せしモノ」です
私が高校生の頃、恐がりでカンニングはしたことがありませんが、周りでは結構していました。
先生に見つかれば、「コラッ!」と怒られ、せいぜいれ0点にされてしまう程度でした。
今回の問題はカンニングペーパーの代わりに携帯電話を使っただけのことです。
それが見つからず4大学でしてしまったのです。
別の見方をすれば、如何に大学の監視体制が甘かったかが問われるべきです。
カンニングをする人間がいるから監視人がいる。大学はカンニングの存在を知っていたのです。
そしてITを使ったカンニングは韓国や中国で盛んに行われていることは分かっていたはずです。
大学にはIT関連の専門学科もあり専門教授もいるはず。
その大学が自分の甘さを棚に上げ、被害者になろうとしている。
私と同じような気持を持っている多くの人達が、京都大学に抗議の電話をしている報道されています。
また、大学よりひどいのはマスコミです。
毎日トップニュースで取り上げる問題ではないはず。
カンニングをした学生の祖父のところまで行って取材しているのをテレビで放映して、見るに堪えませんでした。
カンニングは悪い事だけれど犯罪ではありません。
しかしマスコミが騒ぎ立て、学生を犯罪人に仕立て上げ、彼の将来を潰しているような気がして尚がありません。
学生は誰も気付かないカンニングの方法を考え、訓練し、実行した。
したことは悪いことだけれど、その能力をいい方向に導いてやれば、素晴らしい才能を開花するかもしれません。
その学生は父親を高校3年生の時に亡くし、一浪の彼はこれ以上母親に迷惑を掛けてはいけないと思い、思いあまてカンニングをしたと言われています。
親を思う子供に悪い子はいません。
大学やマスコミにはもう騒ぎ立てるのはやめてもらいたいです。
そして学生の将来を考えて上げて欲しいです。
私と同じ様に考えている人は多いと思います。如何でしょうか?
感謝
今朝早くから同系会社の事業計画発表会にオブザーバーとして行って来ました。
最初に社長からのあいさつです。
この会社はグループ合わせて社員が260名。この発表会に参加者は170名ほどです。
そこで社長が第一に「感謝」という言葉の説明です。
親に感謝、家族に感謝、お客さまに感謝、取引先に感謝、仲間に感謝することの大切さを説いていました。
そして「感謝」の反対は何かと問いました。
それは「当り前」です。
誰かが何かをしてくれても、してくれるのが「当たり前」という気持ちでは何も生まれません。
それを一所懸命説いていました。
いい話でした。
ただこの会社の社長は「感謝」の反対は「当たり前」と言いましたが、私は「無視」だと思います。
この「無視」は大変怖いのモノです。
「無視」には感情がありません。
人がしてくれた好意を受け止める感情が無いのです。
だから「無視」しているのです。
「当り前だ」と思う感情があるだけまだましです。
無感動という人は多いように思います。
悲しい話しを聞いても、悲しいと思わない。それより思わないのでなく、思うことが出来ない。
だから人も痛みを自分の痛みとして感じることも出来ない。
そのような人は精神的に問題があるのではなく、成長の途中で何か欠落してきたように思います。
それは無駄と思えるような事をしてこなかったのではないでしょうか。
小さい頃なら「おままごと」のようなして、人と触れあう。
友達と喧嘩して、痛い思いをして、泣いて、そして仲直りする。
思春期なら沢山恋をして、失恋して、その痛みが分かるようになること。
損得でもなければ、学力が上がることでもない。
色々遊びを通してこそ人間力が育つと思います。
今私のところに東京から小さい孫が遊びに来ています。
これからうんと遊んで欲しいし、思春期には沢山失恋して欲しいと思います。(まだ早いかな?)
明日、明後日は遊び相手しなければなりません・・・・
私も頑張らねば!
焼肉を食べて
昨夜、娘達と焼肉店に行きました。
私は焼肉を食べに店に行くことはほとんどありません。
せいぜい行くのはジンギスカンの店です。
以前に焼肉店に行ったのは8年前。それも娘達に誘われて。
それでも末娘がアルバイトしていた焼肉店に行くことになりました。
食事する前に娘がお世話になったお礼の為、お店の責任者の方にご挨拶しましたが、その後はすごい勢いで食べます。娘達が。
私はサーロインやカルビを食べただけでもうお腹いっぱいになって箸がすすみません。
それでも娘達にせかされて、少しずつ食べました。
勿論ホルモンも食べました。
タンとかミノしか名前はわかりませんが、ホルモンといっても結構な値段がするのですね。
私の中学生時代でも 周りの大人達はホルモンを食べながら焼酎を飲む人が多かったです。
ただその頃のホルモンは安いものの代名詞のようなもので、肉とホルモンの価値ははっきり分けられていたように思います。
ホルモンの語源は大阪弁で、「放るもの(ほおるもの)」から来ていると言われています。
それが今は、ホルモンが肉と匹敵するようになるなんて...と思ってしまいます。
時代が変わればモノの価値も変わります。
昔に「猫またぎ」と言われ、猫も食べずにまたいで行ったと言われるマグロの大トロもそうです。
エキセントリックというものも評価が変わりました。
その意味は奇抜なとか奇妙なという意味で、昔そのような格好をした人は変人と言われました。
それは今はいい意味で使われます。
人の評価もそうかもしれません。
出る釘は打たれると言われていましたが、出る釘が評価されることも多くなりました。
焼肉から他のところに飛んで行き過ぎました。
昨夜は肉をたくさん食べ過ぎたせいか身体がほてり眠れませんでした。
やはり肉は体を温める食べ物なのでしょうか。
今日は少し寝不足です。
街の歩道にベンチを

昨日札幌市西区の土木センターに行ってきました。
私が住み、仕事をしている琴似の街の歩道にベンチを置くことについて相談に行きました。
ベンチを置きたい理由があります。
以前にもブログで書きましたが私の父は昨年11月に亡くなりました。
93歳でしたが、亡くなる6カ月前までは毎日会社に行きました。
行きましたというより行かせました。仕事好きの父が元気でいる為にです。
普段は車で送り迎えしました。
休みの日は父と母と私共夫婦が付いて会社近くのホテルヤマチまでコーヒーを飲みに歩きます。
歩くのは健康の為です。
歩く距離はそれほどはなく、私が普通に歩いて10分かかりません。
でも父があるくと30分位かかります。
ゆっくり歩くのと、途中休み休み歩くためです。
その時気付いたのは街の中に休む場所がないのです。
仕方がなく、人の家の花壇やスーパーの裏階段等に座って休みます。
ベンチがあってもいいのに1つもないのです。
その頃から「この街にベンチを置きたい」と思うようになりました。
父が亡くなって、今改めてなって「街にベンチを置く」ことを考えています。
最初はホテルヤマチの前の歩道に置きたいと思っています。
ベンチの形も名前も決めました。
そんな思いで土木センターを訪ねたのですが、簡単に「ダメです」の一言で終わりです。
何か出来る方法が無いかを聞いても「ありません」しか返ってきません。
琴似の街の歩道幅は3m以上あり、その上ロードヒーティングされています。
それほど邪魔になることはないと思います。
視覚障害の方に聞いたことがありますが、上からぶら下がっているのは怖いけれど、下にあるモノは杖で分かるのでそれほど問題は無いと聞いたことがあります。
街にベンチがあると、そこに座りお話が出来ます。高齢者や妊婦の人達も休むことが出来ます。
街の中に居る人の滞留時間が長くなります。
そうすると商店街にとっても活気が出てきます。優しい街づくりになります。
そのような話をしても無駄でした。
でも何とかして街の中にベンチを置くことが出来る方法を考えたいと思います。
どなたかの街でその実例があるというようなお話がありましたら、ぜひ教えてください。
これからしばらく戦略を練ってみます。
エリート教育
先日テレビで学校教育のことが取り上げられていました。
日本の教育と韓国・発展途上国の教育の比較がされていました。
現在の日本は、韓国の受験競争、中国の国策としての教育と比較するとひ弱に見えます。
日本では個人の自由や平等を謳うがため、学習能力が下位か中位の子供のレベルに合わせて教育がされ、それが平等だとしています。
その番組でのその件に関してもいろいろ意見が出ていました。
私も下位や中位の子供のレベルに合わせるのが平等だとすれば、「それなら上位の子供はどうするのか」と思います。
環境がそれなら、上位の子供は下位や中位の子供たちに合わせることになってしまいます。
そして折角の能力がある子供の芽を摘み取ってしまうことになります。
勉強の嫌いの子供や学校の授業についていけない子供たちでも、絵がうまい、手先が器用という子供はその方面で優れた力を出せばいいのです。
一定の枠にはめることが平等という考えは大変危険です。
その危険な状況が現在の日本の教育だと思います。
子供が持っている素晴らしいその能力を生かしていける教育をしなければ日本将来は大変なことになります。
今までの教育は、個性を大事にと言って好き勝手なことをさせ、弱者に合わせることが平等だというモノでした。
日本でも昔はエリート教育というものがありました。
しかし、それが戦後教育の中で、差別を生むいうことで否定されてきました。
私は今改めてエリート教育が必要と考えます。
エリート教育を受けた人間がいて上昇指向の国が出来ると思います。
今日本にリーダーと言われる人が少なくなっています。
リーダーとはリスクに向き合える人です。
エリート教育の中にはリーダーとしての考え方、心構えも教えられます。
このまま折角の能力ある人達が埋没し、日本が衰退していってしまうのは残念と思うのです。
挑戦心
今月22日に発生したニュージランド地震で多くの日本人も被害にあいました。
彼ら・彼女らは何かに挑戦しようとする人達で、志を抱いた貴重な人材です。
テレビや新聞の報道で知る不明者の夢を聞くたびに、私は涙ぐんでしまいます。
その中でも平内好子さんは高校の校長先生を退職し、第2の人生にチャレンジしようとする私と同じ61歳です。
毎日の報道を見聞きして不明の日本人の無事を祈るばかりです。
皆さんも気付いているでしょうが、被害にあわれた日本人のうち圧倒的に女性が多いのです。
このような災害が発生した時に、不謹慎なのかもしれませんが、どうしてもその男女の比率に目が行ってしましたす。
私も学生時代にアメリカオクラホマ大学の米語学校に行きました。38年前です。
その時同じ学校にいた日本人は6人、そのうち女性は1人でした。
その学校からアメリカの大学に入学出来るので、それに挑戦する人もいましたが、私も含めそれとなく来てしまった人が多かった気がします。
その点、今の人達の方が目的意識があります。
ただ、私も古い人間だからでしょうか、今の若い男性にはもう少し挑戦心を持ってもらいたいと思います。
最近外国へ行くのを嫌がる若い男性が多いと聞きます。
一般には、ひ弱な若い男性を「草食男子」と言っています。
「草食男子」を言われて、「僕は平和主義者だから」と言う人がいます。
平和主義者だから争わないそうです。
でも違います。
究極の草食男子で平和主義者はガンジーです。
徹底した非暴力主義を唱えてイギリスに抵抗してインドを独立に導きました。
「平和主義=競争回避」ではないのです。
「草食男子」は若い人ばかりでなく、私たち団塊世代も言えるかもしれません。
自分の世界を守ることも大事ですが、何かに挑戦し、誰かの為に何かをする生き方こそが素敵で、カッコいいと思います。
団塊世代の皆さん共に頑張りましょう!特に男性!
カーリング体験会
昨日カーリングを体験してきました。
私が属している「新現役ネット北海道エリアグループ」が企画し実施しました。
8名の方が集まり、カーリングの1チームが4名ですのでちょうど2チームが出来る数でした。
2時間ほどの時間でしたが、普段使わない筋肉を使うものですから結構きつかったです。
特に体の固い私は前かがみになってストーンを離す姿勢が辛かったです。
カーリングの始まる前に、準備として係員が氷面の処理をします。
それは大きな霧吹きのようなモノで霧状の水を撒き、氷面に氷の粒を作ります。
その処理をすることで氷の滑りが全然違います。
氷の上に出る時は片足の靴の底にスライダーという滑るカバーを付けます。
カーリング専門の靴には片足はスライダーになっていますが、体験者には特別にスニーカーに被せるカバーが用意されています。
このスライダーがある為にストーンを投げる時、ストーンと一緒に滑ることができるのです。
スライダーは右利きの人は左足に履きます。
このスライダーを付けて歩くだけでも大変。
使われてないい筋肉に力が入って、リンクを1周するだけで脚が突っ張ってきました。
その後ストーンを投げる姿勢の練習、実際にストーンを投げる練習、ミニゲームまで体験しました。
そのミニゲームの中で点数の数え方も学びました。
以前に机上で教えてもらったことはありますが、実際にゲームを体験すると一発でわかります。
「ゲームをした」と書きましたが、実際のゲームは40メートルも長い先にあるハウスという丸い輪まで投げるのですが、私たちはとても届きませんので10メートル位の距離でしました。
10メートルでも思うようなところに投げれませんし、止まりません。
体験して初めて、40メートル先の数センチ単位のポイントに止める技術の高さを認識しました。
この体験会の間中、ズーと北海道カーリング協会の指導員が付いて教えてくれます。
このカーリング体験は札幌では美香保体育館で土曜日の18時から行われていいます。
体育館の入場料大人580円(65歳以上140円)だけで予約しないでも出来ます。
指導員の方は、指導料も支払っていないのに、申し訳ないほど丁寧で手取り足取り教えてくれました。
2時間の体験だけでも、カーリングの面白さを知りました。
今度テレビでカーリングを見るのが楽しみです。



先見性
私は札幌生まれで札幌育ち。
途中東京や帯広等へ行きましたがまた戻り札幌在住です。
卒業した高校は札幌西高です。
この高校は「西高山」という山を持っています。
高校の敷地に山があるという訳ではありません。
車で20分ほどのところにあります。
公立高校が山を持っているというのは珍しいのではないでしょうか。
山を持つ経緯を以前先輩から聞いたことがあります。延べ11万6000坪の広さがあり、これを管理しているのが札幌西高会です。
定期的に山に入り、下草刈りなどもしているそうです。
この「西高山」を札幌西高が所有した経緯は、昔「札幌二中」と言われたころ夜間高校に通っていた生徒たちの支援の為に始めたと聞きました。
当時の先生と全生徒が一緒になって山に入り、主にカラマツを植えたそうです。
それは電気が普及すれば電信柱が必要になると考え、その供給にとカラマツを植えました。
しかし今、電信柱はコンクリート製です。
私の住んでいる琴似は地下ケーブルになり、電信柱さえなくなっています。
今西高山にある木は使い道がなく、ただ管理だけ行われているとのこと。
カラマツは建築材や家具材に適していません。
カラマツは製材にすると「暴れる」と言われるくらい狂うためです。
良かれと何十年後のことを考え、山を購入して準備しても、予想もしない現実でその通りにはなりません。
昨日「北海道・札幌の生きる道」という講演会を聞いてきました。
その中で20年後50年後のことが語られていました。
人口減少によって引き起こされる経済的ダメージが中心でした。
20年後50年後は私はどうなっているか分かりませんが、子供や孫のことを考えると心配です。
でも講演を聞いた後で、「西高山」のことを思い出しました。
その教訓として、あまり先のことは考えない方がいいと思い直しました。
悲観的になったり、喜んでみたりしてもあまり意味がありません。
講演する人は色々数字を示しながら悲観的・楽観的に見解を述べるのが仕事です。
それより私たちは、目の前にあり、今するべきことを認識し、確実に成し得ていくことが大切です。
その積み重ねによって先が見えてきます。
今日一生懸命頑張れば明日が見えてくる。
明日一生懸命頑張れば1週間後が見えてくる。
1週間頑張れば、1カ月後が見えてくる。
1ヶ月頑張れば1年後が見えてくる。
1年後が見える、その程度の先見性でいいように思っています。
如何でしょうか?
財布の中身
今日は金曜日です。
週末だからという訳ではありませんが、牡蠣の専門店で知人夫妻と食事(お酒も)をする予定です。
この牡蠣の店は私の高校の同級生が経営している店で「開(ひらく)」という店です。
牡蠣料理を中心に美味しい料理が食べれます。
この店に関しては色々な物語があり、今度ご紹介します。
私は食事会や飲み会は良くあります。
誘われたり誘ったりです。
その代金はほとんど自腹です。
お金が沢山あるわけではないのですが、それなりのお金は用意しています。
私の奥さんは優しいので「足りなければ言ってください」と言ってくれます。嬉しい限りです。
彼女が言うには「お金がないから」という理由で大事な付き合いをしないのは良くないと言います。
給料が少ない若い頃から、子供5人にお金がかかるのにそのように言ってくれていました。
私は若い時「年齢に応じたお金を常に財布に入れておきなさい」と人から言われたことがあります。
20代は2万円、30代は3万円、40代は4万円、50代は5万円。
年に応じてお付き合いする人のレベルが違ってきます。
現役で仕事をしている時は、その位のお金を常に持っていなければいけないと言われました。
「毎月のお小遣いが2,3万円なのに、いつも財布に3万円とか4万円を入れておくことなんか無理です。」と言う人もいるでしょう。
でも、仕事で事を成そうとしているなら、その位のお金を持っていなければ、急に大事なお付き合いが発生した時「お金がないので」とは言えません。
「クレジットカードがあるでしょう」と言うかもしれませんが、割り勘で支払いになった時どうしますか?
お金が常に財布に入っているからといって、必要なければ無駄遣いしなければいいのです。
それ位の自己管理が出来なければ何も出来ません。
それなりのお金が財布の中にあるだけで、気持にも余裕が出来ます。
初めてお会いした人でこれから親交を深めていと思った時は、「これからお食事いかがですか?」とか「今晩美味しいお料理を出す店にお連れします。」と言えます。
それをきっかけに大きなチャンスが生まれることもあります。
仕事に関係した接待と認められれば後からでも会社請求出来ます。
それも財布にお金があればのことです。
もう一度お財布の中身チェックしてみてはいかがですか?
贈り物
昨日私が運営するレンタルオフィスに入居している女性から「たんかん」を1箱いただきました。
皆さんは「たんかん」という果物をご存じでしょうか?
私は知らなかったのですが、箱の中に「奄美ブランド果実」とありました。
無農薬・有機栽培で育てたと書いてあります。
オレンジのような形ですが、食べると全然酸っぱくなく、甘くその上大変ジューシーで大変美味しいです。
その「たんかん」をオフィスに入居している皆さんに食べていただこうと、箱ごと置いておいたのですが、私が食べ過ぎたせいでしょうかアッという間になくなりました。
私のところには時々贈り物が届き、その都度皆さんと食べます。
贈り物の多くはきれいな包装紙に包まれていて、私は破るのがもったいなく、カッターナイフなどを使いきれいに剥がします。
さてその剥がした包装紙はどうするかというと、結局きれいにたたんで捨ててしまうことが多いです。
それならバリバリと破いて、中身を出してもいいのでしょうが、なかなか心理的にそうは出来ません。
この日本人の心理について書いてある本があります。
「政治と秋刀魚」という題名でジェラルド・カーティス氏が書いた本に
「プレゼントをもらえばアメリカ人は包み紙を破って中身を出す。
日本人は中身だけが大事ではない。包装紙を丁寧に取って折りたたんで、箱を破らず中身を出す。
要するに日本人にとっては、全部が『中身』である。」と書いてあります。
読んでなるほどと納得しました。
映画などではアメリカ人はプレゼントをもらうとその場で破いて中身を確認し、喜びを表します。
もしもその時、それをきれいに包装紙を開いて、5分も10分もかかって開けたのでは、目の前に居る送り主がイライラしてしまうのかもしれません。
日本人は受け取っても開けずそのまま持って帰り、後から開けます。
包装紙も含めた全部が「中身」だからなのでしょう。
結婚式や法要の時、祝儀袋や不祝儀袋を出す時も、袱紗に包んで出さないとマナー違反だと言われます。
だた、最近日本のこの独特な感情は薄れてきているのかもしれません
ダメという訳ではありませんが少し考えるところです。
スピリチュアルについて
昨日来られた女性と話をしていると「スピリチュアル」の話が出てきました。
「スピリチュアル」は英語で霊的という意味です。
私は昔から怪談話は嫌いでしたが、スピリチュアル的な事には興味がありました。
人は自分が良く理解できなくても、何か自分の世界と違う世界の存在を意識しているのでしょうか?
勿論「俺はそんなの信じない」という人もいるでしょう。
でも大きなことを成した人達はそれなりにそれを信じていました。
松下幸之助さん、稲盛和夫さん、土光敏夫さんもそうです。
書かれた本の中にあります。
「スピリチュアル」は宗教と結びついているところもありますがそれとは違うイメージもあります。
昨日話をした女性は自分では霊を見ることはできないけれど、存在を信じていると言います。
霊は見えなくても、自分の周りに起きていることがそれを信じさせているのです。
その女性が師事している方は霊的感化を受けて絵を描きます。
それも200号を越すような絵を描きます。
その先生も自分では霊を見ることはできませんが、近くの北海道神宮の林の中で撮った写真には、無数の白く輝く球が浮いていました。
それは精霊だそうです。
そのような写真を沢山取っています。
「原因」と「結果」の法則を書いたジェームスアレンは毎朝裏山に1人で登り暫く瞑想に耽っていたそうです。
そこで神と交信をしていたと言われています。
それを家に集まる人々に話をしました。その内容はトルストイや仏陀にも及んだといいます。
ジェームスアレンの本はスピリチュアル的なこともありますが、人としてどう生きるかの教えがあります。
久しぶりに読んでみようと思っています。
制服について考える
昨日銀行に行く用事があり、ロビーに座ってあらためて気付いたのですが、最近銀行の女性行員は制服を着ていないのですね。
地元の北海道銀行、北洋銀行ともに制服が廃止になっています。
私服で仕事をしています。
今は制服廃止の傾向なのでしょうか。
以前はどの銀行も女性行員は制服を着ていました。
私が北海道銀行に勤めていた大昔、森英恵デザインの制服を着ていました。
制服廃止は銀行の業績低迷が続いたため、経費削減が大きな要因なのかもしれません。
でも最近その制服も北海道銀行では4月から復活するという話もあります。
制服着用の目的は何でしょうか。
「制服を着ていないと行員とお客さんの区別がつかない」というお客様側の意見もありますが、制服着用の目的は別のところにあると思います。
制服の代表は軍隊です。
その他警察、消防士、鉄道員・駅員、病院の医師や看護師、ホテルマン等で、その姿を見てすぐ判別できます。
私はその判別できること以外に、制服着用には大きな意味があると思います。
それは帰属意識です。
同じ制服を着ることで、仲間意識、統一感、ロイヤリティ等が生まれます。
軍隊や警察、消防は特にそれが求められる仕事です。
企業でも以前は女性は制服を着ているところが多くありました。
特に日本が高度成長期はそうでした。
「金太郎飴」と揶揄されますが、同じ考えを持ち、同じ方向に向かって頑張る時、制服というのはその一体感が生まれやすいのです。
男性も統一性を持つために、同じネクタイをするというのもありました。
それも統一感を持つには有効です
現在私が入会していますビール会も赤いネクタイ着用が義務です。忘れると罰金を取られます。
これも仲間意識保持が目的です。
統一感がなく困っている会社は、制服までいかなくても、チョットした遊び心的発想でネクタイくらいから始めてみると、思いがけない効果があると思います。
如何でしょか?
経営者と事業家
今日は「経営者」と「事業家」ついて書きます。
特に事業家について最近考えることがありました。
「経営者」と事業家」との違いについて明確な規定はありません。
ただ経営者がある程度成功すると、時として「私は事業家だ」と言う人がいます。
そう言う経営者は現場から離れてしまっている人が多いです。
事業家という人は「私は大所高所から世の中の動きを見て事業を展開する」と言います。
ただ起業したばかりの人には「事業家」は関係ありません。
起業した人はあくまで経営者を目指して欲しいです。
私がイメージする事業家は西武創業者の堤康次郎氏、東急創業者の五島慶太氏、現在では孫正義氏でしょうか。
経営者は松下幸之助氏、土光敏夫氏 本田宗一郎氏、稲盛和夫氏です。
経営者は会社に利益を生みだし、従業員の幸せを追求し、社会貢献を目指します。
事業家はいかに効率良く資金活用するかを考え利益を追求します。どちらかというと投資家に近いものがあります。
資金が10億円以上あるなら事業家としての活躍もあるでしょう。
先ほども書きましたが、中小企業の経営者が事業家と言う時は、会社が順調に行っている時が多いです。
その時は自分は現場から離れ、現場責任者に経営をさせ、自分は仕組みを作ったり、会社組織を変更することで
会社を動かしていると認識しています。
私は世の中に事業家という人も必要だとは思いますが、中小企業社長はあくまでも経営者を目指すべきです。
投資話で失敗するのは会社が順調に行き、自信が生まれてきた時に起きます。
経営者から事業家という甘い誘惑につられている時です。
会社に経営理念が存在し、社長が確実にその履行をしているかどうかで会社の発展がはかられます。
その時は基礎がしっかりしているので、甘い誘惑には誘われることはありません。
目指すは「事業家」でなく「経営者」です
ご近所先生講座最終回
今月の17日は「ご近所先生講座」の最終日でした。
オリエンテーションと5回の講座を振り返ってみると、講義前の準備が結構大変でした。
でもその準備をし、いかに分かりやすく話をするかを考えることが私の勉強になりました。
やはり「人に教えることは自分が学ぶこと」と実感しました。
「ご近所先生講座」の最終日は4回目の講座の時に作った起業事業を3グループから発表をしてもらいました。
Aグループは「たまり場」、Bグループは「ほおずきランプ」、Cグループは「定食屋+コーヒー」の事業をテーマに代表者によるプレゼンテーションです。
「たまり場」は事業目的を「人の心と体を癒し、人と人をつなぐ『町の保健室の様な場所』の提供」と定義づけています。
そしてその視点は「心」「人」「体」の3点に置き、商品やサービスを考えています。
「ほおずきランプ」は講座参加者の中に実際に趣味で「ほおずきランプ」を作っている人がいて、その製品を売り出す方法を考えています。
この事業の目的は「ほおずきランプで人の心に感動を与えたい」です。
作られた作品を見ましたが、本当にほおずきの中から放たれる赤い光が郷愁をそそり、優しい気持ちになります。
これは外国人向けのお土産としても可能性がありました。
「定食屋+コーヒー」の店は実際に北海道留萌市で起業したいという現実的な事業です。
この事業の目的は「地域に食の夢を与え、老若男女が集い、食事が出来、地域住民とのコミュニケーション及び食育の場・空間の提供」です。
この事業で起業を希望している人は、実際に留萌に土地があり、漁業、農業関連に親戚や知人がいることで、良い素材を安価に仕入れることができる環境にあります。
この3事業はまだこれから練られていかなければならないところはありますが、それぞれ考えられたユニーク視点もあり、面白い内容でした。
今回の「ご近所先生講座」は「身の丈起業のすすめ」がテーマなので、その目的は「起業はそれほど高い壁があるわけではなく、事業計画も、実際に作ることで作り方が身に付く」ということを知ってもらうことでした。
最終日に3グループの事業発表を聞いてその目的は何とか達成したのではないかと思っています。
今このブログを書きながら、自分が勉強になったことと、新しい良き縁が生まれたことを感じています。
潜在意識にまで透徹する強い持続した願望を持つ
京セラフィロソフィの中に「潜在意識にまで透徹する強い願望を持つ」という項目があります。
これについて稲盛和夫さんは次のように説明しています。
「高い目標を達成するには、まず『こうありたい』という強い、持続した願望を持つことが必要です。
新製品を開発する、お客様から注文をいただく、生産の歩留まりや直行率を向上させるなど、どんな課題であっても、まず『何としてもやり遂げたい』という思いを心に強烈に描くのです。
純粋で強い願望を、寝ても覚めても、繰り返し繰り返し考え抜くことによって、それは潜在意識にまでしみ通っていくのです。
このような状態になった時には、日頃頭で考えている自分とは別に、寝ている時でも潜在意識が働いて強烈な力を発揮し、その願望を実現する方向へと向かわせてくれているのです。」
続けて
「私がここで強調したいことは『強く持続した願望を持つ』ことであり、言い換えれれば、それは『私は人生をこう生きたい』『私は会社をこうしたい』ということを、強く、継続して思い続けることです。そうすることによって、はじめて潜在意識までに願望を透徹させることが出来るのです」と言います。
潜在意識についての説明もあります。
稲盛さんはそれを自動車を運転する時のことを例えに説明しています。
昔に運転を習いたての頃は、右手でハンドルを持ち、左足でクラッチを踏み、左手でギアチェンジを入れます。
そのように教えられやっても手足がバラバラになってうまくいかない。
それは顕在意識でしているからです。
それが免許を取り、運転に慣れてくると、意識しないで運転が出来るようになります。
それはもう潜在意識で運転をしているからです。
ですから潜在意識まで「願望」を落とし込むことは誰にでも出来ることなのです。
繰り返し繰り返し覚えさせるようにして潜在意識までに落とし込むのです。
そうすると、常に潜在意識の中に「願望」があるので、思いがけない場面で潜在意識が働き、素晴らしい着想を得ることも出来ます。
以前に紹介しました
「新しき計画の成就はただ不屈不撓の一心にあり。さらばひたむきにただ思え、気高く強く、一筋に」という言葉に表されてきます。
勉強会ではこの「潜在意識にまで透徹する強い持続した願望を持つ」を読んで、皆さんに自分の「願望」は何かを聞きました。
「願望」とはただ単に「したい」とか「欲しい」というのでなく、そう簡単に達成できないが、自分の人生をかけても叶えたいと思うものです。
なかなかそこまでの思いを抱いている人は多くはないと思います。
でも、勉強会に参加している数人の人が素晴らしい「願望」を持っていました。
その「願望」に対する思いも語ってもらいました。
その熱意に私も大変感動し、影響を受けました。
そしてこの勉強会参加者の意識レベルの高をさ改めて再認識しました。
公私のけじめを大切にする
昨日に引き続き、「京セラフィロソフィ勉強会」で学んだことを書きます。
「公私のけじめを大切にする」についてです。
このことに関して稲盛さんは
「仕事をしていく上では、公私のけじめをはっきりしなければなりません。
プライベートなことを勤務時間中に持ち込んだり、仕事の立場を利用して取引先の接待を受けたりすることは厳に慎まなければなりません。
勤務時間中の使用電話の受発信を禁止したり、仕事を通じていただいたものを個人のものとせず、みんなで分けあっているのもそのためです。
これは、ささいな公私混同でもモラルの低下を引き起こし、ついには会社全体を毒することになってしまうからです。
私たちは、公私のけじめをきちんとつけ、日常のちょっとした心の緩みに対しても、自らを厳しく律して行かなければなりません。」と書いています。
この文章が書かれたのは大分以前のことなので、電話のところでは携帯電話の現在と事情がちょっと違っているかもしれません。
でも「モノ」も「時間」も公私混同を諌めています。
仕事上の立場を利用して得るモノ、お中元やお歳暮も個人でもらってはいけないのです。
「役得」を厳しく諌めています。
身近なモノで言えば以前は「マイレージ」のことで各会社で問題になりました。
出張の多い社員は結果マイレージが貯まり、家族旅行で使う。
一方、総務や経理部門の様に出張の機会の少ない部署の社員にはそれがありません。
そこに格差が生まれました。
これも「役得」です。
今は個人の「マイレージ」も会社に移すことが出来るようになったそうです。
会社のトップである社長の問題もあります。
以前中小企業に多かったと思いますが、社長の個人的な事を社員を使ってさせることが多く見受けられました。
社長個人的な用事を社員にさせるのです。
残念ながら私の会社でもありました。
中小企業の社長は苦労して会社を作ってきたことがある為か、どうしても会社=社長個人と見てしまいます。
しかし、それでは社員に対し公私混同はダメだと言っても全然意味を持ちません。
それによって会社内で不正も起きるようになります。
「公私のけじめを大切に」とは社員に対する以前に、会社のトップである社長に問われている項目です。
フェアプレー精神を貫く
毎月行われています「京セラフィロシフィ勉強会」を今月も15日に開きました。
毎回熱心に参加している方が多いです。
今回は「フェアプレー精神を貫く」「公私のけじめを大切に」「潜在意識にまで透徹する強い持続した願望を持つ」の3項目について学びました。
今日はその最初の「フェアプレー精神を貫く」について説明します。
最初に稲盛和夫さんは
「京セラは「フェアプレイ精神」に則って正々堂々とビジネスを行っています。したがって、儲ける為に何をしても良いとか、少しくらいのルール違反や数字のごまかしは許される、という考えを最も嫌います。
スポーツの世界でも、反則やルール違反のないゲームからさわやかな感動を受けるのは、フェアプレー精神に基づいているからです。誰であっても、矛盾や不正に気づいたら正々堂々と指摘すべきです。
私たちの職場が常にさわやかで活気があふれるものであるためには、1人1人がフェアなプレイヤーであるとともに、厳しい審判の目を持つことが必要です。」と書いています。
人というものは「フェアプレー精神が必要だ」「正々堂々として生きよう」と言われればその通りだとほとんどの人が思います。
しかし少し時間がたつと気持ちが薄らいできて、儲け話が持ち込まれると「少しぐらいは」と心がふらついてしまうという心理も稲盛さんは指摘しています。
その為には全社員が審判の目を持ち「悪いことは悪い」と指摘する風潮を会社に作る必要があります。
しかし、たとえ間違いを見付けても、人はそれを指摘するのは難しいものです。
また、時には人を陥れて自分をいい格好にしようとする人もいます。
そういう人がいるので、かえって「自分の人格が疑われては大変だ」と考えてしまいます。
そのような時、その指摘が理にかなっているか、誹謗中傷なのかを判断する方法を稲盛さんは書いています。
「『○○さんはけしからん』とただ誹謗するのではなく、『○○さんはこう言うことをやっておられますが、あれは我社にとって問題なのではないでしょうか。ぜひ正していただきたい』と建設的な提言として発言されているかを判断材料とします。」
判断基準に「損得」置くのではなく、「正しいか、そうでないか」に置くこと。
そしてそれを上下関係なく指摘できる会社の雰囲気作りがトップの仕事なのでしょう。
明日は「公私のけじめを大切にする」について書きます。
PEST分析
昨日は「新現役ネット北海道エリアグループ」の朝食会がありました。
朝食会では参加メンバーが講師となり、自分の専門分野の話をすることになっています。
今回は元銀行支店長で、今はビジネスコンサルタントをされている人が担当です。
題名は「PEST分析で将来を見通す」です。
私はこれまで「PEST分析」という言葉を知りませんでした。
私と同じように知らない方に少し説明します。
「PEST分析」とはマクロ視点で、外部環境を洗い出し、「政治的」「経済的」「社会的」「技術的」の観点からその影響度や変化を分析する手法のことです。
PESTとは、政治的(P=political)、経済的(E=economic)、社会的(S=social)、技術的(T=tchnological)の頭文字を取った造語です。
今回の話の要点は、日本はこれから益々「成長経済社会」から「成熟型経済社会」に移行していいくということ。
「成熟経済社会」の特徴は「モノの充足感のある社会」です。
話の中でその「成熟型経済社会」のビジネススタイルは「好縁ネットワーク」を構築して、それを生かすことだと言います。
「好縁ネットワーク」とは彼が作った造語です。(なかなかいい言葉だと思います)
それは企業、個人に関係なくそれぞれの資源を活用して新しい事業を展開するためのネットワーク作りが重要だと言います。
その視点を「政治」「経済」「社会」「技術」の各方面から見てみるのです。
その4つの視点は密接につながって世の中は動いています。
藻谷浩介氏が書いた「デフレの正体」という本を読むとそれが良くわかります。
就業者人口が日本で一番減少しているのは大阪府。高齢者人口が一番増えているのは東京と書かれています。
そうであれば消費傾向は減少が予想されるのです。
そうなれば大都会と地方の格差というのも見直してみなければなりません。
経済影響も大きくなります。
社会動向と経済、そしてそれに対する政治の政策が密接に絡んできます。
講師は最後に自分もその好縁ネットワーク作りを進めていると言っていました。
これから新しいビジネスが生まれる可能性を示唆するお話でした。
日本航空
昨夜は経営者勉強会「盛和塾」の例会がありました。
この例会は毎月1回行われます。
今回は昨年12月に行われた東日本地区合同例会のDVDを見ました。
それは稲盛和夫さんが「日本航空の現状と課題・盛和塾に思うこと」と題してお話していました。
日本航空の再建については、先日テレビ東京の番組で「ガイヤの夜明け」で取り上げられていました。
また、日本航空をベースに書かれたと言われる山崎豊子さんの「沈まぬ太陽」もテレビ放映されていました。
「ガイヤの夜明け」を見ていると日本航空の各部署に貼られていたスローガンに注目しました。
「新しき計画の成就はただ不屈不撓の一心にあり、さらばひたむきにただ思え、気高く強く一筋に」です。
稲盛さんの話では、会長として日本航空に行き最初に感じたのは日本航空の「官僚体質」そのものでした。
毎月の実績の把握もままならず、また幹部社員であっても経営に関する数字に関しての関心はほとんどなかったそうです。
現在日本航空では幹部教育と共にアメーバー経営を導入して、幹部・社員の意識変革そして数字で話が出来る環境整備をしています。
4月~9月の前期実績は、売上はほとんど変わらないのに営業利益は前年より2000億円プラスになりました。
その間、円高による燃料費減少の追い風もありましたが、コスト意識の浸透も大きな要因と見られています。
稲盛さんのお話と共に、この例会時に盛和塾メンバーの1人が話したエピソードが心に残りました。
それは彼がタイから帰国するJAL便の中の出来事です。
ある若い人達が大きなカバンを機内に持ち込み、収納棚に入らなくて、それを少し小柄のCAが苦労して収納しようとしていました。
彼はそれを見かねて手伝いをしたのですが、結局は入らず別預かりになりました。
その後先ほどのCAが彼のところに来て、「ありがとうございました」と言って袋に入ったキャンディーをくれました。
彼は受け取りそのままにしていましたが、暫くたって口が寂しくなりキャンディを食べようと袋を開けると、そこに先ほどのCAからのメッセージカードが入っていました。
カードにはお礼と、今後ともご利用下さいとの言葉がありました。
彼は嬉しくなり、自分の名刺の裏に「がんばってください。応援します」と書いて、別のCAに渡してもらうよう依頼しました。
暫くたって少し年配のCAとカードをくれたCAが一緒に改めてお礼に来ました。
その年配CAによるとカードをくれたCAはまだ経験が浅いが、先ほど名刺の裏に書いた彼からのメッセージを読んで泣いたそうです。
お客様の励ましの言葉に感激したのです。
それであらためて挨拶に来ました。
それを聞いて彼も感動するとともに、日本航空は変わったと実感し、そして今後より良くなると思ったそうです。
この彼の体験談と稲盛和夫さんの話しを聞いて、私も日本航空の業績回復するのを期待します。
「弱者」とは
最近「弱者」と言う言葉が多くなり、新聞テレビでも盛んに取り上げられています。
「生活弱者」、「身体的弱者」、「教育弱者」等色々言われます。
しかし、「弱者」とは簡単に言って欲しくない言葉だと私は思っています。
傍目から見たら大変な「弱者」と思っても、本人は自分のことを「弱者」だと思っていない人もいます。
また、本人の努力不足なのに自分は「弱者」だと言う人もいます。
私は「弱者」と言う概念は多分に観念的なモノだと考えます。
今、話題の「選択の科学」という本を書いたのはシーナ・アイエンガーさんは、小さい頃から目が不自由ですが、コロンビア大学の教授で、多くの研究をしています。
(この「選択の科学」という本もとても素晴らしい本で、お勧めします。)
本を読んでみると彼女は素晴らしい科学者で、自分は眼が不自由ということは本の中では書いていません。
シーナ・アイエンガーさんンは自分を「弱者」だとは思っていないはずです。
お会いしたことはありませんが、「五体不満足」を書いた乙武 洋匡さんもテレビで見ても、自分を卑下したところは見えません。
高齢者を弱者だという人もいますが、私はただ年を取ったのだと思っています。
高齢者の中には身体の不自由な人もいますが、それはどの世代でも同じです。
逆に高齢者は金融資産を一番持っている世代です。その点から言えば若い人の方が「弱者」です。
シーナ・アイエンガーさんは「選択の科学」の中に次のことを書いています。
「保守的な政党が自由放任主義的な経済政策を志向するのに対して、リベラルな政党は大きな政府と社会計画を志向する」とあります。
本当に弱者といういわれる人もいますが、「弱者という名に隠れた怠け者」もいます。
全てをごちゃ混ぜにして一言で「弱者」という風潮に疑問を持っているこの頃です。
自己表現
自分をどう表現するかということは、この社会で生きていく時、とても大事な要素です。
自分の考えていること、思っていることを人に伝えることは大切な「技術」です。
人によってその表現方法は違います。
今、担当している講座「身の丈起業のすすめ」に参加している人の中に、漫画を描くのが得意という人がいます。
それも素晴らしい「技術」です。
絵や図を描いて自分の考えていること、言いたいことが表現できます。
以前に家具の仕事で中国へ行った時、交渉中に先方のデザイナーが目の前で万年筆で描く椅子のイラストが、口で説明する以上に訴えていました。
単なる線なのですが、その線が定規で書いたのと違って生きています。
パソコンで書かれたイラストより訴求カは高いのです
描いたそれだけでそのデザイナーの凄さがわかるようでした。
描くばかりでなく、話をして自分の言いたいことを伝える時も、人によって違いが出てきます。
皆さんにも経験あると思います。講演会で聴衆を惹きつけて話しをする人と、そうでない人。
同じ日本語を話しているのですが、その違いは大きいです。
この話す能力は経営者にとって重要な「技術」の一つです。
会社の方針、社長の考えを末端のアルバイト、パートの人達まで伝えるのは、ただ話すだけではダメです。
伝達能力が問われてきます。
私の知り合いの社長は小さい頃「どもり」でした。
それを直したくて、彼は高校卒業後東京へ行き噺家になろうとしました。
しかしある噺家を訪ねたのですが断られ、仕方がなくその後浅草の劇団に入って演劇を経験しました。
それにより「どもり」は治ったそうです。
彼は数年後北海道に戻り、いくつかの会社を経営し、現在は有名な回転寿司の社長になっています。
その社長の話を聞くと、朴訥とした話し方の中に引き込まれてしまいます。
それは「間」であり、そして声の強弱だと思います。
私は演劇をいう自己表現を経験して得た「技術」だと思います。
そういう意味でも、演劇など人前で自己表現を訓練することは、自己形成をする上で1つの方法かと思います。
「今更」という気持ちを持つ人も多いかと思いますが、機会があれば挑戦してみましょう。
私も機会があれば・・・・・・
命をかける
私は稲盛和夫さんのことを、何かあるごとに話をしたり、書いたりしています。
このブログでもご紹介していることがあります。
また、稲盛和夫さんは経営者の為の勉強会「盛和塾」を主宰しています。
その「盛和塾」が発行している会報があります。
先ほど4年前の会報をパラパラと読んでいましたら、ある文章が掲載されていました。
稲盛さんが創業した京セラには「全従業員の物心両面の幸福を追求する」という経営理念があります。
その作られた背景には、昭和35年に入社した高卒社員11名の反乱がありました。
その会報にその時の1人が状況を、高卒社員の1人の立場で書いてあります。
その時の状況は、時あるごとに稲盛さんから聞いていましたが、それがもう一方の当事者から書かれているところに大変興味を持って読みました。
この反乱というのは昭和35年に入社した社員が中心となって、業務改善を会社に求め、稲盛さんと団体交渉し、それを受け入れなければ全員会社を辞めると迫ったものでした。
稲盛さんからは、「要求を飲むことは今すぐには出来ない。将来はそのような会社にする。それまで待ってくれ。出来もしないのに今ですぐに出来るという嘘は言えない」と言われたそうです。
3日3晩続き、1人1人説得されて行き、最後の残ったこの筆者も稲盛さんから「お前、そこまで言っても分からんのかよ。騙されてみる勇気はないのか!」そして最後に「もしも俺が裏切ったら、刺し殺してもかまわん。」と言われたそうです。
最後まで折れなかった彼はその一言で納得し、仕事をし続けました。
京セラは成長し、約束通り業務も、待遇も改善されました。
彼は後には四国セルラー―電話㈱の専務取締役までになりました。
京セラの創業当時、そしてその後も厳しい仕事環境だった様です。
それに対して、皆さんからは「良い」「悪い」の判断もあるでしょう。
しかし、トップとして、命をかけて真剣に仕事をする姿勢があってこそ、社員を引っ張っていく力が発揮され、社員もついて行くのでしょう。
今でも、小さくてもそのような社長はいます。仕事に命をかけている経営者はいます。
そのような会社が成功する会社なのではないでしょうか。
数字に興味を持つ
昨夜も4回目の「身の丈起業のすすめ」講座でお話ししてきました。
今回は実際に事業計画書を作成する作業が中心でした。
今まで経営に携わったことのない人達にとって、事業計画書作りとはとても大変なように思っているはずです。
しかしひな型に合わせて実際に書いてみると「思ったほどではない」と分かった様子です。
この講座を通して知っていただきたいことの一つはこれです。
「こんなふうにになればいいな」と思っていたことを事業計画・ビジネスプランとして書くことで、より具体的な形になります。
また収支計算の方法も最初はそれほど難しく考えず、平均単価×販売数量×営業日数で売上を算出し、材料費はざっくりした比率でいいので粗利益まで出してみます。
このように計算することに対しての抵抗を無くすことによって、日常生活の中でも自然数字に落として考えるようになります。
例えば居酒屋に行って大まかな席数を数え、そこの平均単価と大体の客数、席の回転率をかけ合わせると大体の売上が見えてきます。
衣料品店に行っても同じように計算できます。
このようなことが自然と出来るような癖になると、いつしか数字に強い人と思われるようになります。
また、そのように数字に置き換えてモノを見る癖が経営する基礎的感覚を鍛えます。
次週はこの講座の最終日で、グループごとに作った事業計画書を発表することになっています。
楽しみです。
「習う」
現在、趣味や勉強の通信教育や教室が盛んに宣伝されています。
資格を取って就職に有利になるようにとか、趣味の世界を広げたいという思いからなのでしょう。
私は「習いに行く」ということはあまりしていませんでした。
若い頃、人に教えを請うことが面倒臭いと思っていた時期がありました。
20歳頃フルートに興味を持ち、吹き始め、独学で吹けるようになりました。
しかし、ある程度までしか上達出来ません。
また自分勝手に吹いてたので、人と演奏するということが出来ませでした。
独学の限界を知りました。
2年ほど前に、以前から興味があったサックスを吹きたいと思い、今度は独学ではなく教室に通い始めました。
週1回の割合でサックスを習いに行っています。
習うという意味は「見習う」ことから始まり、「ナレるまで」するということだそうです。
昨夜もサックス教室の日でしたが、上手くなるには如何に練習が必要かとつくづく納得しました。
習っている曲のある部分がどうしても吹けません。
先生の後について吹くのですが、どうしてもうまく出来ません。
「私は音楽センスが無いからかな?」とか思ったりします。
でも、2年前の初心者の時、当時とても吹けないと思われた曲も今は吹けるようになっていることを思えば、ただ単に練習不足しかないのでしょう。
60の手習いですが、若い先生を「見習い」、「ナレる」まで練習することが上達の秘訣ですね。
近い将来ステージの上でジャズでも吹いているかもしれません。
これもカッコいい年寄になる為の挑戦です。
CoCo壱番屋
昨日読んでいたメールマガジンと起業家向け瓦版に偶然「CoCo壱番屋」創業者の宗次徳二氏のことが掲載されていました。
瓦版では講演会での話の内容が紹介されていました。
宗次氏は「経営は難しくない。不況だからと言って、特別な事をする必要は無い。マーケティングをする必要はない。コンサルタントなどを雇う必要は無い。
経営者に必要なのは簡単なこと。それは、朝から晩まで365日休まず徹底的に働くこと。交流会などには決して出ず、私利私欲は一切捨て、現場に居続けること。つまり経営に身をささげること。
その覚悟を持って30年間働き続ければどんな3流経営者でも成功出来る」と言います。
「経営者が休むことは罪悪だ」とすら言っていたそうです。
また、メールマガジンでは宗次氏の朝起きのことが書いてありました。
始業時刻の三時間前までなら"普通の早起き"、四時間以上前で"超早起き"になるらしいです。
宗次氏は2時に起きていたそうです。
朝起きは私の周りにも居ます。4時起きて会社に5時出社するという社長がいます。
私は6時起床して7時30分出社です。
以前は5時起きでしたので少し怠けています。
最初に紹介しました宗次氏の講演会で話された休みなしで働くという姿は私の父がそうでした。
父親に遊んでもらったという記憶はあまりありません。
常に仕事でした。
休みなしで働くと言うことは傍目から見ると辛いように思いますが、本人はそれが充実した生活で、何より楽しいと思えているようでした。
逆に仕事をしないで遊びに行くことが辛いように思うのかもしれません。
本当に仕事に没頭した人だからこそ「経営者は休むことは罪悪だ」と思えたのでしょう。
「誰にも負けない努力をする」と言う稲盛和夫さんの言葉が浮かんできました。
「他慢」する
ネットワークについて2日前にこのブログで書きました。
「ネットワーク作りはITも大事だけれど、結局は人に会うことです」と書きました。
昨日来られたAさんはまさにそのような人です。
お歳は60歳代半ばと言っていましたので私より少し先輩です。
時々私のところに情報を持って来てくれます。
Aさんは会計会社の部長さんですが毎日外出されているそうです。
Aさんは毎月会計会社主催のランチ講演会の企画・集客もこなしています。
その講演会には40~50名ほどの人が常に集まり、もう7年ほど続いています
講演会の目的は各参加者同士の交流が目的です。会計会社の宣伝はほとんどありません。
Aさんは日頃お客様ばかりでなく知人、そして新しい出会いを求めて色々なところに出入りしています。
その時訪問した会社やお店の新製品、告知したい情報等を受け、別のお客様を訪問するとその商品のチラシを渡したり、宣伝をしてあげています。
自社の宣伝するより、ほかの会社の宣伝をするのです。
その会社の社長さんはきっと他の人を通して、Aさんが宣伝してくれるのを知り喜ぶはずです。
Aさんはそれをすることで、人と人との橋渡しをしているのでしょう。
先ほど紹介しました講演会の集客も、Aさんを慕って集まってくるのでしょうか。
それは結果会計事務所の顧客獲得にも結びついています。
Aさんが電話をくれる時「いい情報がありますよ」と言います。
それが色々な会社の宣伝や情報なのです。
自社でない他の会社の宣伝を一生懸命するその姿はいいモノです。
自分を自慢するのでなく他人を良く言うことの方が、話してくれる人の評価を上げます。
他人を自分のことのように自慢する言葉として、「他慢する」を造語します。
「決める」とは?
今までこのブログで書いてきたことですが、何かを始める時に大事であり、第一にしなければならないのは「それをすると『決める』ことだ」と言ってきました。
しかし、経験上したいと思っていても、いつの間にか挫折してしまうことが多のではないでしょうか。
また、以前に紹介しましたWish listに「したいこと」「会いたい人」「食べたいもの」「行きたいところ」等を書いてもなかなか望みが叶わないことを感じるのではないでしょうか。
私の周りでタバコを吸っている人が「禁煙するぞ」と誓っても、なかなか禁煙できず、何回も誓っていは挫折していた人が数人いました。
でも、最近ピタッと止めました。それ以来一本も吸っていません。
なぜ急に禁煙が出来たと思いますか?
それは、1人は狭心症、1人は肺がんと診断され、そのまま吸い続けると死んでしまいますよと言われたからです。
死ぬと言われた時、タバコを止めると本当に「決断した」のです。
それまでは、タバコは心臓に悪い、肺がんの元になると言われても、他人事だったことが、自分にに置き換わった時「決断できた」のです。
何かを始める時、「決断をする」ということは、「出来たらいいな」程度の思いで始めても、それは決断とは言いません。
本当に新しいことを始めるということは、それまで親しんできた習慣や楽しみや時間を捨てることであり、その覚悟が無ければ成功しないのではないかと思います。
タバコも吸った時の満足感や充足感を捨てなければ、タバコは止めれません。
その満足感や充足感以上の重要なことが起きた時止めれたのです。
肥っていても痩せれないのは、食べる満足に浸っているからです。
このまま太ると命にかかわると言われると食べる制限はするようになるでしょう。
何かに挑戦する時大切なのは、決断する前に本当に今楽しんでいる時間や事柄を本当に捨てる勇気があり、実行出来るかを認識し、そこに集中することが成功・失敗の大きな要因になります。
私がなかなか痩せれないのもそこに原因がありそうです。
ネットワーク
最近私もFacebookを始めました。
周りの人達も始めている人が多いようです。
その他にmixiやTwitter等があり、簡単に人とのつながりが持てるようになりました。
インターネットにつながり、情報発信や逆に享受することが簡単に出来るようになりました。
このようなITを使ったネットワークを知っていると知らないとでは、生活の上でも仕事の上でも大きな差が出てきます。
使える人と使えない人との差はますます広がるかもしれません。
ただ、注意すべきはITでのネットワークに依存し過ぎてしまわないようにすることです。
時々若い人で見かけるのは、仕事している中で、IT上でのネットワークへの依存度が高い人は、あまり伸びていないように思います。
いまさら言うことでもありませんが、ITは道具として使うべきです。
私の周りの活躍している起業家たちは、ITを駆使する一方、良く動きます。
何かあるとすぐ人に会いに行きます。会って、直接情報交換を行います。
その方が情報の中身が濃く、早い結果が出ます。
人とのつながりも、より強いものになります。
「素直で」、「明るく」、「行動的で」、「物怖じしない」人が仕事の上で成功しています。
最近出不精になった自分へ反省を込めて書いています。
元気な?年寄
昨日地下鉄に乗った時のこと。
私と同時に足の悪い70歳くらいのお婆さんが乗り込みました。1人は杖をついていました。
その時シルバーシートには女子高生が座っていましたが、すぐ立ち席を譲りました。
お婆さんたちは遠慮しながらそこに座りました。
そこまではいいのですが、向かい側の普通シート席が空いた時、お婆さんたち2人はスッと立ち上がり、そちらのシート席に移ってしまったのです。
シルバーシートが空きました。
先ほどの女子高生は勿論、誰も座りません。混んでいるのにも関わらず。
お婆さんたちがそのままシルバーシート席に座ってくれたら、向かいの空いたシート席には若い人が座ることが出来たはずです。
自分達はまだシルバーシートに座る年でないと思ったのでしょうか。でも少し周りに迷惑をかけています
電車の中で席を譲ると言うと、以前に小さい子供がまだ50歳代の女性に席を譲ったのを見かけました。
その子にとっては50歳代の女性はお婆さんに見えてしまったのでしょう。
譲られた女性は最初びっくりしましたが、笑いながら「ありがとう」と言って座りました。
周りにいた人達は微笑ましく見ていました。
2年前に中国北京に行った時、私も地下鉄の中で、席を譲られました。
びっくりしたのですが、好意にしたがって座りました。
中国に詳しい人に聞くと、中国は年寄りに優しい国だということです。
私も年寄に見られたのですね。(その時まだ60歳になったばかり)
今、私は還暦も過ぎていますので、日本でも何時席をを譲られるか分かりません。
心の中では「まだまだ元気なんだぞ」と思いながも、その時はニコッて笑い、「ありがとうと」言って座ろうと思います。
いい年寄になりますよ。
自分に適した事業の探し方
昨夜は3回目のご近所先生講座「身の丈起業のすすめ」がありました。
今回は「自分の適した事業の探し方」についてお話していました
1回目、2回目の時は「自分の好きなこと」「自分の素晴らしい素質を見付けること」をテーマに自問自答してもらいました。
大切なのは「自分がしたいこと」を見付けることです。
今回講座で使ったツールは森英樹さんが書いた「起業のネタ」という本にある「フォーカストライアングル」を使いました。
自分の持っている希望や能力を掛け合わせて専門分野を絞り込む方法です。
言葉ではなかなか説明しにくいです。
添付しました図を見ていいただくと、黒字のところが自分の希望や能力、青字のところが掛け合わせて考えられる事業となります。
この講座「身の丈起業のすすめ」の目的が、自分のしたい事業を見つけ出し、簡単でもいいから事業計画まで書けるようにすることです。
今回はそれをもとにして自分の適した事業は何かを探り、実際に事業計画書の書き方までお話しました。
参加者で同じ様な業種の人同士3グループに分け、それぞれで具体的な事業選定をします。
勿論、仮定の事業計画ですから細かいところまではいいのですが、実際に事業計画書を書くことが重要なのです。
本来は1人1人自分の事業を考え、事業計画書を作るのでしょうが、最初からそこまで挑戦するにはハードルが高いのでグループで作ることにしました。
次週は具体的に事業計画書を書くことをします。

1人起業
昨日私のレンタルオフィスに入居されている起業家が「お話があります」と言って来ました。
3月いっぱいでレンタルオフィスを出たいと言うこと。
よく話を聞くと、同じく入居されているもう1人の起業家の人も一緒で、この同じビルで共同の事務所を持つということです。
以前にこのオフィスを出ていったOBの人も含め3名が一緒です。
その話を聞いた時「良かったですね」と言い、本当にそう思いました。
私は「起業家が成功するためのオフィス」と称してレンタルオフィスを運営しています。
ですからそのようになっていることが嬉しいのです。
今までも多くの起業家が業務拡大のため「巣立って」行きました。
今回の様に同じレンタルオフィスの仲間同士でネットワークが出来、出て行ったのは2例目です。
今回申し出てこられた起業家は1年ほど前に入居され、業績が良くなってのを機に会社設立をしました。
その直後病気をされ3カ月ほど入院していました。
退院後オフィスに出て仕事をしていたのですが、入院中に業績が急激に悪くなったそうです。
一時は「オフィスを出て自宅で仕事をしよう」と思ったそうですが、「家庭と仕事は分けたい」との思いでそのままオフィス利用をしてくれました。
彼は頑張り、最近は業績も回復し、アルバイトも雇うほどになっていました。
1人起業の時一番辛いのは病気です。
自分が病気になれば即、業績悪化に結びつきます。
彼の場合は大変な努力をして業績回復、またそれ以上にしています。
今度共同の事務所を持ち、気心の知れた仲間を持つことは、精神的な事ばかりでなく、仕事の上でも協力関係が生まれるのではないかと期待しています。
3人で共同事務所にしますが、会社名はそれぞれ今のままで、当面は事務所を共同運営することになりそうです。
1人起業をする時、私が運営するレンタルオフィスを利用するのもいいですが、仲間が出来たら、彼らの様に起業家同士で共同事務所を持つのも新しい起業拠点作りの方法かもしれません。
彼らとは同じビルの中ですから、今後とも交流が続きます。
これからはOBとして私たちの勉強会や飲み会などの催しものに参加してくれるはずです。
北海道神宮にて
昨日は2月1日。月の初めということで北海道神宮と琴似神社にお参りに行ってきました。
私の父が昨年末亡くなったので暫く喪に服していた為、神宮、神社ともお参りに行っていませんでした。
身内に不幸があると神棚さえ触れることが出来なくなります。
ですから昨日は今年初めてのお参りになります。
神宮に朝7時頃に行くと人も少なく、お参り後フッと横を見ると、まだ撤下塩(おさがりしお)が残っていました。
撤下塩というのは神宮で神前にお供えした塩で、それを少しずつ袋詰めされたものです。
人気がありいつもはすぐ無くなってしまいます。
冬の、そして雪が降っている神宮、神社ともモノクロの印象でした。
人も地味目な装いで、落ち着く色合いです。
日本の伝統的な文化は結構モノクロの世界ではないか思えてきました。
そのモノクロの世界に巫女さんの赤い袴が映えてくるのでしょう。
土門拳の写真もモノクロだからこそ迫力があるのかもしれません。
そんな風に思いながらお参りしていると、すれ違う人同士が知らない人でも自然と「おはようございます」と言葉が出てきます。
朝早く神宮や神社にお参りに来ていいと思うことの1つが、自分が素直になれるということでしょうか。
毎月1日にはお参りに来ていますが、そればかりでなく、仕事をして、疲れて来た時も行きます。
それは自分が素直でなくなっている時なのかもしれません。
「なら」と「しか」
仕事でも家庭でも人を注意する時は気を使います。
時には自分の気持ちをぶつけたりします。
それが必要な時もあります。
松下幸之助さんも稲盛和夫さんも叱る時はしっかり叱ったと言っています。
尊敬する人から叱られたら、叱られることさえ嬉しくなることもあるでしょう。
しかし、多くの場合はそうではないのかもしれません。
昔の私は感情のまま怒ったことが多かったと思います。
叱ると言うより怒っていたのです。
それでは反発されるだけです。
叱る目的は、その人が間違いを認識して正して欲しいから叱るはずです。
しかし実際は叱られた人は「そんなに怒らなくてもいいのに」とむくれてしまいます。
今の私は年なのでしょうか、それほど怒らなくなりました。
叱る時は、その人がその時に起こした背景・状況を把握するように努めています。
そうすれば、それが起きた理由が理解出来ることもあります。
その間違いを起こした本人が「自分が間違えていたな」と思うように諭してあげる話し方が有効なのです。
その時に使ういい言葉があります。
これはある雑誌に載っていたのですがご紹介します。
何かあった時「君なら出来るはずだ」「これは君にしかできないはずだ」と言ってあげるのです。
本人に期待していることを伝える言葉としては、大変的確な言い回しと思います。
叱る時も「君らしくないね」と言ってあげるといいですね。
このような叱り方によって、叱っている人も心穏やかになっていけるのです。
言葉一つで人は変わります。
教えられる
今朝末娘が今春上京したいと言う話を聞き、許しました。
中学生の頃から歌手になりたいと言って、何時も歌ばかり歌っていました。
自分の夢を叶えたいと言うのです。
私は以前(もしかしたら今も)「こうあるべき」という型にはまった考え方をする人間でした。
結果自分の殻から脱皮出来ず悩んだこともありました。
そんな私からすれば娘が歌手になりたいなどという話は論外でした。
私と娘の葛藤がありました。
でもその葛藤や悩みの中から気付いたのは、私の考えが変わってきたことです。
「愛するということは自分の庇護のもとに置き、自分が正しいと思うことをさせることではない」ということにやっと気付きましいた。
「何をいまさら」と思う人も多いかもしれませんね。
今の私は5年前の自分と随分変わったように思います。
それは娘のおかげです。娘から教えられたのです。
勿論心配は心配です。
でも、自分の夢をつかみたいという思いを抱くようになった娘の気持ちを大事にしたいと思います。
娘はこれから私の見知らぬ人達のお世話や恩を受けながら成長していってくれると思います。
私は今から見知らぬ人達に「娘をよろしくお願いします」という気持ちになっています。
今日はプライベートな事を書いてしまいました。
東国原英夫氏
昨日東国原英夫氏の講演を聞いてきました。
主催は札幌商工会議所の新春特別講演会として「元気な地方が日本を変える」というテーマでした。
開演より1時間ほど早く着いてしまったのですが、既に100人ほどの人が並んでビックリしました。
商工会議所が主催し、会費5000円もするので、ビジネスマンの人が主体で、会場にはもっとゆっくり来るだろうと思っていました。
並んでいたのは私と同じか、それ以上の年配の女性が多かったのです。
開演時には満席になるほどの盛況でした。
通路には報道関係者、3社ほどのテレビカメラもあり、これからの動向が注目されている東国原氏の発言への関心の高さがうかがわれました。
東国原氏の話の内容は題名とはかけ離れ、漫談でした。
初めから最後まで笑い声が溢れていました。
小学6年生の時、政治家とお笑い芸人になろうと思ったこと。
ツービートの漫才を見てビートたけしさんに弟子入りしたこと。
宮崎県知事になるまでのいきさつ等を話しました。
この講演の中で山本五十六の話が出てきました。
東国原氏がたけしさんの付き人をしている時、たけしさんが教える姿に山本五十六の言葉 「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじ」が浮かんだそうです。
この山本五十六の言葉はよく知られた文句ですが、確かに人を育てる時に指導する側が心すべき言葉です。
講演は1時間30分間、ほとんど笑いっ放しで終わり、地方の話も国の話もまた自分のこれからの動向に関しても話しが無く、少し肩透かしを食らった感じでした。
そのため報道関係者は早々といなくなってしまいました。
山本五十六の言葉でもう一つ有名なモノがあります。
ご存じの方も多いと思いますがご紹介します。
男の修行
「苦しいこともあるだろう 言いたいこともあるだろう 不満なこともあるだろう 腹の立つこともある
だろう 泣きたいこともあるだろう これらをじっとこらえてゆくのが 男の修行である。」
ご近所先生講座
昨夜は2回目の「ご近所先生講座」でお話をしてきました。
講座名は「身の丈起業のすすめ」で今回は「自分の素晴らしい素質を知りましょう」というテーマで進めました。
講座の内容を概略書きます。
どのような人でも素質や才能はあるものです。
本人はそれを知らないだけです。
起業家にとって、それを知り、どう自分の起業に生かせるかが重要になってきます。
今回はそれを知る為の作業「自分の棚卸」をしました。
その作業の前に「自分時間の棚卸」もチェックしました。
「自分時間の棚卸」とは現在の生活を見直して、その中から有効時間を作る作業です。
起業を志す時、必要なのは時間です。
ですから時間を生み出すことが重要になってきます。
生活を見直すと思いがけなく時間が生まれるものです。
この時に心するべきは、新しいことを始めると言うことは、今までのやり方を「捨てること」と認識することです。
今までの安易な生き方を止めなければ、新しい一歩は踏み出せれません。
この時間の棚卸の後に「自分の棚卸」の作業を行いました。
これはマトリックス図を作成します。
横軸の上には今まで所属した学校や会社名を入れます。
縦軸の左端には業務内容、例えば学校でしたらクラブ名、社会貢献活動、得意学科など。
会社でしたら営業、経理、総務、人事、企画、広報、生産現場、所得免許等を書き、それぞれ交差するところで過去に何を経験したかをどんどん書き入れてゆきます。
この作業をしているうちに忘れていた得意なことや経験が思い出され、それが今考えている起業の立ち上げに生かせれるのです。
次回の講座は来週です。その時は「自分に適した事業探し」をする予定です。
「自分時間の棚卸」と「自分の棚卸」の表を添付しましたので宜しければお試しください。


ツイている人と付き合う方法
世の中で「ツキ」というと肯定する人と否定する人に分かれます。
私は「ツキ」を信じる方です。
それでも他力本願的な思いではないつもりです。
自分の出来る努力をした時、巡ってくるモノだと思っています。
ご存じのように「幸運の女神は前髪しかない。来たなと思ったらその前髪をつかむのだ。その女神が過ぎ去ってから捕まえようとしても後ろ髪が無いので行ってしまう」と言われます。
幸運の女神がいつ来てもいいように備えていなければなりません。
その備えが一生懸命勉強することであり、仕事することです。
もう一つ「ツキ」を得るには「ツキ」のある人とお付き合いすることだと思っています。
ある本にその方法が書いてありました。(出典は忘れてしまいました)
ツイている人と付き合う方法
◆物事を強気に考え、相手と付き合う習慣を身に付ける。
◆情熱を吹き込め。情熱以上の説得力はない。
◆NO1のイメージを持ち、いつもNO1のイメージで語りかけよ。
◆リスクには進んでチャレンジせよ。相手はリスクなくして進歩なしを知っている。
◆一貫性を持って接すること。一貫性は継続的能力の現れであると相手は知っている。
◆自分のすべてをさらけ出してはいけない。相手には見苦しいだけだ。
◆いかなる弱みも見せるな。長所だけを見せよ。
◆夢を見続け、夢を語り続けること。夢のない人間は相手にされない。
◆相手は不満をいう人間は弱いと知っている。絶対に不満や言い訳を口にするな。
◆人の噂話はするな。ゴシップは信用されないどころか不信感を与えてしまう。
◆100%自信のない話しはするな。99%では0%と同じ。
◆謝るような事はするな。謝罪する人は、約束を守らない人と同じとみられる。
◆親密すぎる交際は避けろ。親密性は信頼を失う。節度ある付き合いを心掛けよ。
以上です。
この内容に「そうだ」納得する部分と、「いや違う」と言う人もいるでしょう。
私は「100%自信のない話しはするな。99%では0%と同じ。」と同じようなことを、昔に父から言われました。
「確実でない話をして、それが違っていたらお前は完全に信用を失ってしまうぞ」と。
その時きっとあやふやのことを言ったのだと思います。
「100%確実でなければならない」というのは少し厳しすぎると思いますが、確実性の高い話でなければならないでしょう。
ツイている人と付き合うのは私の経験から行っても正解です。
モノの考え方が違ってきます。
「ツキ」のことについては今後またこのブログで書くこともあると思います。
未だ木鶏たりえず
今朝の日経新聞に林原が私的整理を申請したと書いてありました。
この会社のことは詳しくは分かりませんが、私は以前から林原という会社に興味を持っていました。
というのも、この会社の社長林原健氏は大分以前に日経新聞の「私の履歴書」に1カ月間、その履歴と一緒に考え方も書いてありました。
それを読んで感銘し、記事の切り抜きも取ってあります。
林原健氏はソニー創業者の井深氏との親交があり、その影響を受けて研究に力を入れたようです。
今朝の記事では林原単体での売上は280億円で純利益が1億円とありました。
この利益額はあまりにも少ないです。利益率は0.3%しかありません。
稲盛さんが私たちに言う「経常利益10%」とは大きな差があります。
林原という会社は研究に力を入れてきて、その分利益を圧縮してしまったのでしょうが、あまりにも利益率が低すぎると思います。
利益率が低いということは内部留保も少ないということで、常に倒産の危険性があります
また、新聞によるとこの会社は過去10年間以上にわたって売上を水増しし、損失を隠してきたと書かれています。
林原健氏の「私の履歴書」を読んで憧れたこともありましたので、このことに関してはショックを受けました。
フッと「未だ木鶏たりえず」という言葉が浮かびました。
相撲の双葉山の連勝記録がストップした時、彼が師事していた安岡正篤氏に「イマダモッケイタリエズ」と電報したと言われています。
双葉山と林原健氏を同列で論じることはおかしいのですが、それなりに努力して実績を残していても、思わぬ気の緩みで、踏み外してしまう「はかなさ」を感じてしまいました。
毎日毎日コツコツ積み重ねていっても、何かの切っ掛けで踏み外すことはあるのだと思います。
自戒の意味も込めて、やはり必要なのは「毎日の反省」なのかもしれません
カッコいい年寄
昨日知人Aさんが訪ねてきました。
私より7から8歳年上の方です。
Aさんは今本を書いているそうで、その内容は高齢者の生き方の「あるべき姿」を書きたいそうです。
Aさんの頭にある理想の高齢者は稲盛和夫さんや三浦雄一郎さんです。
Aさんは自分の周りの人達が高齢者を年寄扱いしすぎることに不満を持っています。
年寄扱いされる「シルバーシート」も要らないし、「車の枯葉マーク」も要らないと言います。(バスなどの優待券は別だそうですが)
その話を聞きながら思ったのですが、元気な高齢者は皆さん現役の人が多いようです。
そしてその現役の仕事が人から一目も二目もおかれる内容です。
人は他の人から評価されることに敏感になり過ぎているように思います。
自分の生き方を貫き、自分に自信を持つこと。
「するは自分の責任。評価は人の勝手」の気持で生きることは年齢に関係なく大切です。
年を取ると「人間が丸くなる」と言われていましたが、本当は違います。
年を取ると、自己主張が強くなり、人と合わせることや妥協するのが出来なくなります。
それは特に現役の仕事を離れて時から起きるように思います。
現役を離れると自分に対する評価が下がります。
その下がることに対して不満を持ちます。
「俺はすごかったんだぞ」「今だって負けないのだ」という気持が強くなります。
そのような気持ちになるのは仕方が無いことなのかも知れません。
でもカッコ悪いです。
私は今年の誕生日で62歳になります。高齢者と言われる65歳までもうすぐです。
私はカッコいい年寄を目指しています。
それは自分の生き方は自分で決め、周りの評価を気にせず、そして自分がこの世に役立つことをすること。
抽象的な表現になりますが、「凛として生きる」姿こそカッコいいと思います。
まとまったパワー
私が以前に読み、抜粋した文章を紹介します。
誰が書いたか今は分かりませんが、「自分の力を出し切る」方法です。
多くの人は自分が描く目標や夢を持ちながら、思うようにならないと悩んでいる人は多いのではないでしょうか?
元々自分にはその為に必要な全てのツールを身体的にも、精神的にも、技術的にも持っているのに、思うようにならないということは無いでしょうか?
それは本来持っている自分の力を出し切れず、あっちに少し、こっちに少しと使い、まとまっていないのです。
それは私の解釈では「器用貧乏」と言われる人です。
色々な力があるために、色々なことをさせられ、また自分も好んでするのだけれど、いつの間にか単なる便利屋になっている状態です。
それを「散在したパワー」と言います。
一方「まとまったパワー」と言われるものがあります。
これは自分の才能や、知識、スキル、心などを雪だるまのようにまとめてくれ、目標や夢を達成させてくれる力になります。
そのまとめるものは自分の心です。
次が具体的に「自分の心をまとめる」方法です。
①具体的で明確な目標を立てる
②毎日、その目標を心の映画館の中で上映させる。
③意思の力よりもイマジネーションを生かす。
④他人の意見に心を開く
⑤成功は直線的でなく回り道をしながらやってくるものだと理解する。
⑥温かいまなざしで自分自身を見守る。
イメージし易く、具体的で、明確な目標を常に保持する為、手帳等に書き、常に見て確認する等の行動が、目標達成を推進させる力になるでしょう。
幸福と快楽
私は先週の木曜日から「ご近所先生」の講師をしています。
2月17日まで計5回開きます。
テーマは以前にもこのブログで書きましたが、「身の丈起業のすすめ」です。
この勉強会の目的は、他の起業講習会とは違います。
マーケティングも資金調達も話しません。
「起業は自分の身の丈に合った規模で始めること」「起業したからは絶対赤字を出してはいけないこと」を中心に進めて行きます。
起業は誰でも出来ます。でも起業は成功しなければ意味がありません。
起業したいと思う人の中には「何かをした行けれど、何をしてらいいか分からない」という人が意外と多いのです。
第1日目はまず自分の欲しいもの、したいもの、合いたい人、行きたいところなど自分の好きなモノを書く出すことを中心に行いました。
ご存じの方も多いと思いますが「Wish List」といわれるものに書き出します。
この「Wish List」に自分の欲望を書き出すことは、1人でも出来るのですが、拘束された時間、決められた15分間に書き出す方が、頭を絞って無理やりでも出すことが出来ます。
人に見せる必要はありませんので、自由に書いてもらいます。
それが2回目以降に起業の事業を探す手掛かりになります。
この「身の丈起業のすすめ」の目的のもう一つは、自分の「幸福」探しです。
起業の最初は「Wish List」で自分の欲望を書きだしたり、目的がお金儲けであっていいのです。
何も目的も持たず、変化のない、そして面白味のない人生より、何か目的を持って生きる事が大切です。
ボランティアという活動もありますが、ボランティアはそれほど責任がありません。
支障ある言い方かもしれませんが、ボランティアは「時間がある時にする」「自己満足」「上から目線的」なところがあります。
同じように人に喜ばれることをするなら、起業して会社を興します。
人は利益が絡むと、無責任では出来ませんん。お客様第一に徹します。
起業は最初は欲望・快楽を求めるもいいのです。
それが仕事をしていく中で、働く意義を見付け、自分の会社が人の役に立つとを知った時、「快楽」では無く「幸福」を感じれるようになるのです。
一流と言われる多くの経営者は会社経営を通して社会的貢献をしていると認識しています。
「金儲け」⇒「快楽」⇒「幸福」でいいのです。
いい車に乗るとか、美味しいものを食べるとかの欲望を満たしても、本当の「幸福」は味わえません。
「幸福」は人の為に生きていると思え、潜在意識にまで到達する満足にあります。それは決して優越感でもありません。
身の丈でいいから、人の為になることを起業を通して成し、その結果自分の本当の満足を得ることも大切な生き方かと思っています。
有意注意で判断力を磨く
今日は「有意注意で判断力を磨く」について説明したいと思います。
このことについて稲盛さんは次の様に言っています。
「目的を持って真剣に意識を集中させることを有意注意と言います。
私たちはどんな時でも、どんな環境でも、どんな些細なことであっても気を込めて取り組まなければなりません。
最初は非常に難しいことのように見えますが、日頃、意識的にこれを続けていると、この有意注意が習慣になってきます。
そうなれば、あらゆる状況下で気を込めて現象を見つめるという基本が出来ていますから、何か問題が起きても、すぐにその核心をつかみ、解決出来るようになります。
物事をただ漫然とやるのではなく、私たちは、日常どんな些細なことでも真剣に注意を向ける習慣を身に付けなければなりません。」
この「有意注意」は意識して意を注ぐという意味です。
反対語の「無意注意」は、どこかで音がしたから反射的にフッと振り返るような意識の使い方です。
この「有意注意」という言葉は稲盛さんが中村天風さんから「研ぎ澄まされた鋭い感覚で迅速な判断をするためには、どんなに些細だと思えるようなことでも、常に真剣に考える習慣を付けなければならない」と教えられたそうです。
私の知っている経営者はこの「有意注意」の教えを実践しています。
彼は人の話を聞く時は、常に意識を集中して、身体を前のめりになって聞きます。
会社で部下と取り留めのない話を聞く時も、前のめりになって真剣に聞きます。
そうすると最初は大変疲れたそうです。
でも最近やっと習慣的に出来るようになったようです。
このように「有意注意」を習慣付ければ経営者にとって大きな力になります。
そのような経営者を稲盛さんは「どんな些細なことでも、ど真剣に考えるような人は、感覚が研ぎ澄まされていますからいつでも迅速に、的確な判断が下せるようになっています。ですから、問題を聞いた瞬間に『あ、それはこうすればいい』と分かるのです。』と言います。
優れたトップには自然とこの「有意注意」を身に付けています。
例えばある会社で、トップの自社工場視察があった時、事前に工場を清掃し、整理していても、トップが工場を巡回すると簡単に問題点を見付けたり見抜いたりします。
私もこの「有意注意」という言葉を大きな紙に書き貼っているのですが、意識しないと「無意注意」の状態になっていることに気付きます。
私も改めて今後、より意識して生活してゆきます。
大胆さと細心さをあわせもつ
今日は「京セラフィロソフィ」38項目の「大胆さと細心さをあわせもつ」について書きます。
稲盛さんはこう書いています。
「大胆さと細心さは相矛盾するものですが、この両極端をあわせもつことによって初めて完全な仕事が出来ます。
この両極端をあわせもつということは「中庸(ちゅうよう)」をいうのではありません。
ちょうど綾を織りなしている糸のような状態をいいます。
縦糸が大胆さなら横糸は細心さというように、相反するものが交互に出てきます。
大胆さによって仕事をダイナミックに進めることが出来ると同時に、細心さによって失敗を防ぐことが出来るのです。
大胆さと細心さを最初からあわせもつのは難しいことですが、仕事を通じて色々な場面で常に心がけることによって、この両極端を兼ね備えることが出来るようになるのです。」
「中庸」とは儒教の言葉で「偏らない心」「とらわれない心」のことです。
常に判断を求められる経営者は「真ん中」という訳にはいきません。
私は以前から常に「溢れるばかりの熱い情熱を持ちながら、時として冷徹な判断が出来る」経営者があるべき姿と思っていましたので、この稲盛さんの言葉に触れた時、得心しました。
また、「両極端」ということについて説明があります。
「この『両極端』とは、資本金以上の投資を決める大胆さと、わずかな額の投資でも逡巡し、考えに考えた後で結局行わないというような細心さだけではありません。
ものすごく情が深く、優しい人間性を持っていながら、時にはズバッと社員の首が切れるという冷酷さ、非情さということもあります。
大胆でなければならない時に大胆さを出す、細心でなければならない時に細心さを出すという具合に、それぞれの性質を状況に応じてうまく機能させる能力が無ければなりません。」
この両極端な状況で常に判断を求められるのが経営者です。
また「京セラフィロソフィ」の本の中には米国作家F・S・フィッツジェラルドの言葉が紹介されています。
「第一級の知性とは、両極端の考えを同時に持ち、かつ、それらを正常に機能させることのできる能力である。」
時々この「大胆さと細心さ」を間違えている人がいます。
よく似ていますが全く違う言葉として「放漫と小心」です。
それは無責任で、よく判断もせず博打みたいな投資をし、自己保身のためにいつもビクビクすることです。
この違いも心しなければならない事だと思います。
利他の心を判断基準にする
今日も昨日に引き続き「京セラフィロソフィ」勉強会について書きます。
今日は「利他の心を判断基準にする」です。
稲盛さんは
「私たちの心には『自分だけが良ければいい』と考える利己の心と、『自分を犠牲にしても他の人を助けよう』とする利他の心があります。
利己の心で判断すると、自分のことしか考えていないので、誰の協力も得られません。
自分中心ですから視野も狭くなり、間違った判断をしてしまいます。
一方、利他の心で判断すると『人に良かれ』という心ですから、周りの人みんなが協力してくれます。
また、視野も広くなるので、正しい判断が出来るのです。
より良い仕事をしていくためには、自分だけのことを考えて判断するのではなく、周りの人のことを考え、思いやりに満ちた『利他の心』に立って判断するべきです。」
と言っています。
人は「利他の心」と聞くと、「経営は競争社会で勝ち抜くことだ。『利他の心』と言っては会社が倒産してしまう」と思う人が多いと思います。
稲盛さんもそれについて言っています。
「私が利他とはそのようなものだという話をすると『何をきれいごとを言っている。
お前だって商売人ではないか。10%以上の利益率でなければ儲かっているうちには入らないなどと言って利益を追求していながら、一方では人を助けよとは矛盾も甚だしい。
人を助けながら経営をやっていいたら、10%の利益など出るわけがないと言う人がいます。」
それに対して
「利他の心の究極は自分の命を犠牲にして相手を助けることです。
でも、それでは命はいくらあっても足りません。
誰もが皆この現世に生まれ来て、1回しかない貴重な人生を必死で生きています。
だからこそ、この世では森羅万象あらゆるものが共生し、共存していかなければなりません。
自分の生き、相手も生かす。つまり地球にある生きとし生けるもの、全てのものが一緒に生きていけるようにすること、それが利他なのです。そういう意味で、決して矛盾していないはずです。」
稲盛さんは「利他の心」を話す時「小善は大悪に似たり。大善は非情に似たり」ということも話します。
「利他と言ってつまらない善をなすことがかえって相手を悪くする。時には非情と言われる利他の仕方がある」と言います。
また、稲盛さんは「利他の心」を話す時、「利己の心」は神様が人間に与えてくれた生存の本能であると認めています。
しかし人が共生、共存するためには「利己の心」を放置するのでなく、「利他の心」で生きることの大切さを言っているのです。
常に創造的な仕事をする
昨夜は久しぶりの「京セラフィロソフィ」の勉強会を開きました。
今回で9回目になりますが、まだ「京セラフィロソフィ」の本の3分の1が終わったところです。
今回は
項目36:「常に創造的な仕事をする」
項目37:「利他の心を判断基準にする」
項目38:「大胆さと細心さをあわせもつ」
項目39:「有意注意で判断力を磨く」
の4項目を勉強しました。
今日は「常に創造的な仕事をする」について説明します。
与えられた仕事を生涯の仕事として一生懸命行うことは大切ですが、ただそれだけで良いということではありません。
一生懸命取り組みながらも、常にこれでいいのか、ということを毎日毎日考え、反省し、そして改善、改良していくことが大切です。
決して昨日と同じことを漫然と繰り返していてはいけません。
毎日の仕事の中で、「これでいいのか」ということを常に考え、同時に「なぜ」という疑問を持ち、昨日より今日、今日より明日と、与えられた仕事に対し、改善、改良を考え続けることが創造的な仕事へとつながっていきます。
こうしたことの繰り返しによって素晴らしい進歩が遂げられるのです。
このように稲盛和夫さんは書いています。
一般の中小企業の社長は、目覚ましい発展を遂げた大企業を見て、「うちもあのようになりたいもんだ。でもそのような技術も、人材も資金もない。しょせん無理な話だ」と思っている人は多いはずです。
稲盛さんはそれに対して、「会社を発展させる画期的な技術をどこからでもらってくることが出来ると思っているのではないか」
「同じことを繰り返さない。昨日より今日、今日より明日、明日より明後日と小さな工夫の積み重ねがその源」と言っています。
さらに、「こんな事で本当に会社を立派に出来るのだろうかと思えるほどの小さな努力を、時間をかけて続けてい行くことによって、何年か先には企業の中に技術が蓄積されていくのです。」とも言っています。
トップの仕事こそは、小さくても改善、改良、工夫の積み重ねを常に考えながら仕事をし続ける事が出来る環境作りなのかもしれません。
新現役ネット
今朝は7時30分から「新現役ネット北海道ネットワーク」の朝食会があり帰ってきたところです。
1月なので、今年度の行動計画を皆で話し合いました。
毎月の第3火曜日の朝食会は定例会とした上で、その他の行事を検討しました。
行事予定は今月の新年会から始まり、2月はカーリング体験 7月は「カルチャーナイト」への協力、8月には銭函で地曳網体験を予定しています。
「新現役ネット北海道ネットワーク」のメンバーの数はまだ少ないのですが、環境問題の専門家、経営コンサルタント、また、カルチャーナイトの事務局長等様々の技能・能力を持った人達が集まっています。
8月に地曳網の体験が出来るのも、メンバーの中に銭函の浜に番屋を持っている人がいるから出来るのです。
この会の活動に参加した、改めてネットワークから得ることのできる可能性を実感しています。
参考
新現役ネットホームページ:
http://www.shingeneki.com/ 新現役ネット北海道ネットワークホームページ:
http://shingeneki.jimdo.com/ カルチャーナイトのホームページ:
http://www.culture-night.com/
代理セールス
昨日は私の父の49日の法要でした。
アット言う間の49日間だったような気がします。
お寺で法要を上げ、その後ホテルで会食です。
身内だけの会食でした。
ホテルは私共のホテルです。
その時の「なるほど」という事がありました。
叔母の1人が「ここの青山(店名)の懐石料理が美味しいのよね。だから良く友達を連れてくるの。今日も美味しいわ」と言ってくれたのです。
また、1人の女性が「以前来た時は美味しくなく、それからは来ていなかったけれど、今日のお料理は美味しいわ」
「調理長が変わったのかしら」と言いました。
その話を聞いた別の叔母が「今度私の集まりはここでするわ」と話は料理、ホテルの評価が上がる一方でした。
私は味覚音痴ですが、確かに美味しいと思います。
特に天麩羅は揚げ立てで、こごみ、タラの目、フキノトウ、鱈の白子の天麩羅でした。
季節はまだ冬ですが、冬と春の季節感が出ていました。
この会食は身内だけですから、自分のホテルのことを話しているわけです。
自分のホテルだとの思いなのか、それだからこそなのか、いつもこの女性たちはホテルに対しては、厳しい見方をしています。
美味しくないモノは美味しくないとハッキリ言います。
その中で、料理に対して高い評価が出たので、これは嬉しい思がしました。
また、最初に美味しいと言ってくれた叔母の話を聞いていると、ホテルのどの営業マンより説得力があり、確実に新しいお客様を連れてくるほどの影響力がありました。
その時ホテルの支配人はその話を知りません。知らないところで、お客様がホテルの宣伝をしてくれているのです。
どのような仕事でも同じです。
「口コミ」と言いますが、「いい口コミ」をしてもらうか、「悪い口コミ」になってしまうか、それはその店側の思い一つです。
お客様に「いい口コミ」をしていただけるように、店側が工夫をする事が大事です。
「口コミ」になる話題を提供するのです。
お客様を自社の代理セールスマンになっていただけるようにするのです。
先ほどの会食の時、サービスする女性は天麩羅をただ出すだけでなく一言言っています。
「季節の天麩羅です。今日は特別に、少し早いですが春のフキノトウ、こごみ、タラの目、それにタチの天麩羅です。珍しいと思いますよ」
それを受けて女性たちから「凄いわ。タチの天麩羅ですって」「フキノトウが食べれるなんて」という話題になっていきました。
今回は身内の話でしたが、「口コミ」の影響の大きさを改めて目の当たりにした思いでした。
サプリメントアドバイザー
60歳を過ぎると、身体のことが気になります。
膝の為にはコンドロイチンやヒアルロン酸がいいとか、青汁が身体をきれいにするなど、健康食品やサプリメントがテレビで宣伝されています。
気になるボケ防止にはイチョウの葉がいいとか言われます。
でも、それらを宣伝を見て、その都度買っていては大変な金額になるし、医学的に本当に効くのか分かりません。
私は頸椎ヘルニアになっていますが、コンドロイチンがいいと言う人がいますが、医者はコンドロイチンを飲んでも消化されアミノ酸に分解されるだけと言います。
そんな時、身近に医学的に相談できるアドバイザーがいれば助かります。
これから高齢化社会を迎える時、健康にお金をかける人は増えると思います。
そんな風に思っていると「サプリメントアドバイザー」という人は既にいるのがわかりました。
「日本サプリメントアドバイザー機構」という団体があります。
詳しく内容まではわかりません。
ただ、供給側の立場でなく、ぜひとも使用者の立場になってアドバイスして欲しいと思います。
「サプリメントアドバイザー」がどのような形で仕事をすれば、その中立性を守り、本当に消費者の体質、症状、不安に対処することが出来るかが大切です。
私の自身が必要としていますので良く分かりますが、今後将来性がある仕事ではないかと思います。
これから何か新しく仕事を始めようと考えている人は一度検討されるといいのかもしれません。
参考
「日本サプリメントアドバイザー機構」:
http://www.jcna.jp/index.html
大器と言われる男
今日は私が若い頃に読んだ言葉を紹介します。
「大器と言われる男は皆自分を生かし抜いた。
たった1回の人生、無駄に生きてはなるまい。
輝かしく生きることだ。
自分を生かすとは好きなことを見付けること。
つまり正しく自分を知ること。
人生は勝ち負けの観点で仕分ければ勝たねばならない。
しかし、勝敗以外に自己を生かしきればそれこそ無敵の境地となる。
好きなことが見当たらなければ、現在やっている仕事を好きになることだ。
自分の好きなこと、得意の分野、やりたいことを社会のニーズに結び付けられた時、楽しさは無限である。
世に認められる。それこそ生きがいを感じる時である。
大器に欠かせないのは信念を持つこと。
信念があれば途中の苦しみも、ものの数ではなく、外部事情が揺れ動いても、腰もフラつかず、自分の生き方が出来る。
自分は自分で自分の運命を保証していけば良い。誰も保証してくれない。
誰かが保証してくれると思うから当てが外れる。
働きは天に貸す。天に貸せば貸し倒れが無い。」
この言葉は30代の頃に大きな紙に手書きし、額に入れて飾っていました。
暫くぶりで見つけまた部屋に飾っています。
改めて見てもいい内容だと再認識しました。
ご近所先生オリエンテーション
昨夜「ご近所先生」のオリエンテーションがありました。
私の担当講座は「身の丈起業のすすめ」という起業に関する講座です。
受講生13名で、その内昨日のオリエンテーションには7名の方が参加されました。
20代から60代の、いろいろな経験のある方々です。
これから5回にわたって講座を開きます。
この講座は「何を起業するのか」というところから始めます。
最初は「起業はしたいが、自分に何が出来るのか分からない」人に、自分探し、自分の棚卸の作業を通して、忘れている自分の能力や才能を見つけ出し、「自分の好き」と結びつける起業を探ります。
最終的には簡単に作れるビジネスプランの作製法を学び、今後何かあった時、苦労なくビジネスプランが作れるようにします。
そしてこの講座の最大の主旨は決して無理な起業をしないことです。
起業には上場を目指すような「メガ起業」もあるでしょうが、今回の講座は自分の身の丈にあった、無理をしない起業を目指します。
私はこの講座が楽しみでした。
それは新しい人達と巡り合えることです。
私は「縁」(えにし)を大事にしています。
過去振り返るとその「縁」のおかげで如何に充実して、楽しい人生だったか。
これからは、多くの「縁」ある人から受けた恩を返すのでなく、次の人に恩を送っていこうと思います。
その為の「縁」作りです。
この講座はたまたま私が先生ですが、教えられることが多いと思います。
これからその為の勉強が大変そうですが、それも楽しんで行こうと思います。
福の神
今月は1月なので、皆様は新年会に参加する機会が多いのではないでしょうか?
私も昨夜は宴会でした。
今は宴会が終わるとまっすぐ家に帰ることが多くなりましたが、もう少し若い頃はは2次会3次会と遅くまで飲み歩きました。
2次会3次会は1人の時や数人の時と様々です。
スナックに行くと、暇そうにしているところもあります。
そこでしばらくお酒を飲んでいると、お客が1人、2人と少しずつ増えてくきます。
いつの間にかママさんは忙しくなっています。
そんなことが何回か起きている時、冗談交じりで「私が来るとお客を連れてくるようだね。」と言うとママさんは「山地さんはまるで福の神みたい」と言ってくれました。
「福の神」と言われると、人間はその気になります。
「私が行くお店は繁盛するよ」と話すようになりました。
私は単純な人間なので、自分で言っているうちに、自分は運のいい人間だと思い込むようになりました。
また、何か外出の予定がある時、いくら雨が降っていても私が出掛ける頃には雨が止む。「私は晴れ男だ」と言うようになりました。
私の妻も、私が仕事で悩んでいる時「お父さんはついている人だから、何をやってもうまく行くよ」と言ってくれます。
こんなお話を書くと「そんなの思い込みだよ」と言われるかもしれませんが、それでもいいのです。
思い返すと、私は「あなたは福の神よ」と言ったママさんが素晴らしいと思っています。
スナックでもレストランでも、どのようなお店でも、お客様商売をしているならば、この言葉を使うとお客様は喜ぶはずです。
例えばレストランで、常連のお客様に「○○さんが来るといつもお客様が多いです。○○さんは福の神かもしれませんね。」と言えば、お客様は喜びます。
そして、レストラン側もそのように言っていると、本当にお客様1人1人が福の神のように思えてきます。
言霊って本当です。
言っているうちに本当にいいお客様ばかりが集まる店になります。
店はチョットした「優しい言葉」で儲かる店に変わることもあるのです。
宜しければ試してみませんか?
夢計画
昨夜、「夢計画の会」を開きました。
参加者は10名でした。それぞれ仕事も個性も違う人達ですが、和気あいあいの雰囲気で進みました。
今までこのブログで「夢計画の会」のことはお知らせしてきましたように、計画書の形式はマンダラ形式です。
会の最初に私から書き方を説明したのですが、説明の仕方が悪かったのか、なかなか理解されませんでした。
でも、実際に書き出すと、皆さんそれほど問題なく書き上げた様です。
計画を書く時に気を付けなければならないのは、
①具体的に書くこと
②達成可能なのとを書くこと
夢計画と言っても、自分が実現できると認識できるモノでなければいけません。
③意欲が持てること
④数字で表すこと
例えば「ダイエットの励みます」より「10キロ落とします」の方が目指しやすいです。
⑤期日、期限を決めます。
例えば「家族旅行します」より「8月に家族旅行をします」と書くと、実現性が出てきます。
この書き上げた計画を実現するためには書いただけではダメです。
自分の手帳に落とし込みます。
年間計画は年間計画欄に、毎週行うことなら月間計画欄に、毎日行うなら、週間計画欄、に書きます。
そして、毎日絶えず作った計画表と手帳をにらめっこして進捗状況を確認します。
私は今日から計画表の書き写しをしてゆきます。
計画書が出来ましたので、今年こそは計画を実行して成果を上げてゆきたいと思っています。
計画を実行する上で大切なのは継続力です。
今年は私の継続力も試されることになります。
相互依存
今日マンダラを使った「夢計画の会」があります。
その準備の為にマンダラ関連の本を読んでいましたら、なるほどと思うことが書いてありましたのでご紹介します。
ある会社にA君、B君、C君の3人が入社しました。3人とも気力・体力・能力ともに同じような青年です。
A君は「新入社員なので、上司の指示・命令は確実にこなす。1日10件の飛び込み訪問など言われたことは必ずやる。それは社員として当然やらなければならないことだからね。」と言います。
B君は「僕は与えられた目標を達成することが絶対だと思う。だから上司が飛び込み訪問10件と言っても必ずその通りしなくてもいいと思う。その代わり目標が達成できなければ1日20件でも30件でも飛び込み訪問をする。目標達成の為なら何でも利用する。手段も選ばない。」と言いいます。
C君は「僕も目標達成のために全力を尽くす。しかし、自分の目的のことばかり考えていても、相手は思うようにはいかないと思う。だから目標達成のためにも、お客様や周囲の人達との関わりを大事にしてゆきたい」と言います。
この3人の1年後はどうなったと思いますか?
A君は上司の指示・命令を守り、日報もきちんと書いていました。しかし成績は思うように上がりません。
「とにかく言われたことはちゃんとしているのにどうしてなのだろう」と思います。
B君は「目標を達成する」為に頑張り、あらゆるものをその目標達成に利用して、成績は常にトップでした。
上司の評価も高かったのです。
しかし1年を経過した頃より、周囲の人達との関係がギクシャクし、顧客との間でもトラブルが増えてきました。
それと同時にB君の成績も落ちてきました。
C君は人との関わりを大事にし、常に、お客様とのお互いの関係性を重視し信頼を築いてきました。
それには時間がかかり、最初はそれほど目立つ成績は上げれませんでした。
でも「お客様の為に自分が出来ることはなんなのか」を考えて仕事をしていましたので、信頼を得ることが出来、成績は安定し、徐々に伸びて行きました。社内でもいい人間関係を築き、上司からも深い信頼を得ることが出来ました。
3人の考え方、行動を改めて見てみます。
A君の行動の原則は周囲の人や第3者に依存した考え方、思考なのです。
上司の指示命令さえ守っていればいいという、守ることが目的になっています。これは「他者依存」なのです。
B君はA君のように他者から影響されてはいけないと、自己を頼りに仕事をしました。それで成績も上げることが出来ました。
しかし落とし穴は、自分の目標達成を最大の目的としていたことです。
お客様や周りの人達の利益より自己利益を優先したことです。
そして自分は間違っていないと思ってしまいます。これは「自己依存」です。
C君は自分の仕事は「相手がいての自分」と考え、その関係を大事にしました。他者だけでも、自己だけでもなく、その関わりで成り立っていると考えました。これは「相互依存」です。
お客様は自分の為にしてくれる人を好みます。そしてそのお返しに仕事が生まれます。
3人の行動は極端すぎるかもしれません。
しかし、私の経験から見て、腑に落ちるモノがあります。
過去に私はA君だったり、B君だったりしました。
今はC君の考え方、行動がいい生き方だと考えます。
起業するとB君のような人が成功すると思われがちですが、本当に成功する人はC君のタイプです。
「利他の心」ですね。
今日の「今年の夢計画作り」の中でもこの考えを盛り込んで行きます。
悪魔の観念
私は学生時代に大学の懸賞論文のコンクールに応募したことがありました。
その時の題名が「悪魔の観念と経済学」です。
奇妙な題名ですが当時は真剣に書きました。
図書館に閉じこもり1カ月位かけて書き上げたと記憶しています。
この論文の大筋は
悪魔という観念を持っていた人と持っていなかった人との行動認識の違いです。
キリスト教やユダヤ教等は神と悪魔を認識する二元論です。
仏教にもお釈迦が様が悟りを開く禅定に入った時に、瞑想を妨げるために現れたとされる魔神が、マーラ(魔羅)と言われ存在しました。
仏教が日本に伝来してきた飛鳥時代には、そのマーラの観念は入って来ませんでした。
なぜなら、日本に仏教を導入した理由は、国家統一が目的だったので、二元論なマーラの観念は必要なかったのです。
元々の日本の宗教にも悪魔の観念はありませんでした。
神道の中でそれに近いと言われるものはスサノオでしょうが、悪魔ではありません。
日本は本格的にキリストが入ってくる明治時代まで悪魔の観念が無い一元論の世界でした。
悪魔の観念が有るか無いかで何が違うかというと、起きた出来事を環境や制度が原因とするか、個人の責任とするかということです。
「貧乏な人」を例に上げれば、経済制度の問題として発生した「人」なので、社会としてそれを救済することが必要だと考えるのは二元論者。―― そこから社会保障制度の考えが生まれました。
貧乏はその本人が一生懸命働かないからだと、その「人」の責任とするのが一元論者です。
椅子取りゲームで9個の椅子を10人で争う時、椅子が9個しかないのが問題で、1人が脱落するのだと言うのが2原論者。
一生懸命勝ち取らなかったその人の努力が足りないからと言うのが一元論者です。
このブログを読まれた方の中には、この論理の展開に異論がある方も多いと思いますが、昔若い時に書いたものです。お許しください。
現在は色々な思想、思考方法があり、一概に日本人だから一元論者とは言えません。
第二次世界大戦後はそれまでとは極端に違った考え方が日本に入り込み、そう簡単ではなありません。
ただ、日本人の基調は「自分を見つめる」と言う、自分を内省する傾向はあると思います。
それが日本人の良いところであり、それが日本の活力の源だと思っています。
夢計画
札幌は連日雪が降っています。
今雪かきして来ました。いい運動になります。
この3連休もどこも出ず、家にいます。
こんな雪が続き日は暖かい家の中から降る雪を見ているのがいいです。
そして、今年の自分計画の準備をしています。
11日に希望者が集まって、「夢計画の会」を開きます。
会といってもそれ1回のみです。
この「夢計画の会」では、参加者がそれの自分の今年の計画を作るのが目的です。
計画を1人でじっくり作るもいいでしょうが、私のようにすぐ他のことに興味を持つ性格の人は、じっくり作り上げるのが苦手です。
そんな私が同じようなことで悩んでいる人達に呼びかけ、決められた時間内に計画を一気に書き上げるのです。
2時間あれば書き上げることが出来ると思います。
この計画は人に見せる必要はありませんので、皆で一緒に書いても内容は教えなくていいのです。
ただ、「こんなことすれば面白い」とか「こんなところに行きたい」など差し障りのないことは話しながら楽しく進めます。
実際には今回が最初ですのでどうなるか分かりませんが、楽しい会になりそうです。
計画の形式はマンダラの表を使います。
私は毎年マンダラ手帳を使っていますので、書き上げた計画はこの手帳に記入し、絶えずチェックしながら計画を達成させるつもりです。
今年もいい年になりそうです。

自分を律する
仕事上で人を指導をする。子供の教育をする。
人は色々な場面で教える立場になります。
その時の自分の有り様はどうなのか。
以前にブログで紹介しました潮田健次郎氏の「寝ていて人を起こすな!」の心構えが大切です。
もう一つ私の「銘肝録」書いてある文章を紹介します。
これは「がんばれ社長」の武沢信行氏が5年程前に自身のブログで紹介していた文章です。
天台宗大阿闍梨 酒井 雄哉氏が書かれた「超人の教え」に書かれています。
「正しいことは正しい、悪いことは悪いという物差しを子供に持たせることは親の責務である。
親や近隣の人に挨拶する、目上の人に礼儀正しくする。いわゆる躾と言われるものは特にそうだ。
辛く苦しいことでも、とにかくやらせる。時には叩くこともする。
焼け火箸と同じことで痛さで分からせることは最も心に残る。
言葉だけで言っても、それを実感出来ないからだ。
実感出来ないものは知識として記憶できても、行動や知恵にはならない。
ただ言うまでもないことだが、親や大人が子供を自分の感情のはけ口にしているような場合は、何の教育にもならない。
むしろ何をされようと大人の言うことなど聞くものかと思うようになり、逆効果である。
それにまつわる、ある親子の話。
子供が仏壇においてあったお金を盗んだ。
それに気付いた父親は「ならぬことはならぬ、ならぬと言え」に従い、子供に厳しい罰を与えた。
季節は真冬。庭には雪が積もっている。
息子を庭の井戸端に連れていくと『お前は人としていけないことをした。よって戒めとして、この井戸の水を十杯かけてやる。
しかし、そんな息子に育てたのは親であるわしの責任でもある。
お前に水をかぶせる前にまずわしが罰をうける』と言うやいなや、氷のように冷たい井戸水を桶で、頭から十杯かぶった。
それを呆然と見ていた息子は、途中から泣き出し自分の非を詫び責めた。
父親は自分がかぶり終わると「次はおまえの番じゃ」と言って、桶にたっぷりの水を続けて三杯、息子の頭から浴びせた。
四杯目からは、形ばかりの水の量。そして五杯でやめた。
相手を厳しく叱るとは、同時に自分自身のあり方への深い内省を伴わなくてはならない。
「子供に言う前に、親として叱るだけの事を自分が出来ているのか。自分のあり方はどうだったのか」そこには自分に向ける厳しさが不可欠である。
そうしたものがあってこそ、初めて相手に深く伝わる。単純に厳しく叱ることが愛情だということを言う人がいるが、そこのところをよく気をつけなければならない。
相手が、愛情から出た行為であることを認め、受け入れてくれなければ何の意味もない。」
私はこの文章を読む度に涙が滲みます。
自分が親から受けた恩。
そして、自分が親として子を叱る時の心構え。
また、部下を叱る時も自分はどうなのか。
考えさせられる文章です。
私は気持が落ち込んでいる時など読むと元気になれます。
企業理念
企業理念については、改めてい書くまでもなく大切なモノです。
でも、例え素晴らしい企業理念があっても作りっ放しでは作った意味がありません。
それに血肉を付けるのは社長です。
3年ほど前の新聞の切り抜きを見付けました。
それは「サマンサタバサジャパンリミッテド」社長の寺田和正さんの「仕事術」の記事です。
この記事には企業理念について書かれています。
寺田さんの言葉です。
「やりがい、プライド、良い報酬、そして信頼」が企業理念です。これを社員と共有することがとても大事です。
その為には言い続けないといけません。起業して今年で17年(当時)。分かってもらえずあきらめている自分に気づいて、ハッとすることがあります。
理念の共有は恋愛と似たところがあります。「いつも一緒に居るのだから分かるでしょう」。
これは会社でも通じません。
人は突如、伸びることがあります。200回言っても分からない人が、次からは2回言えば、うち1回は分かるようになることもあります。
社会が淡白になってきましたから、これれ迄以上に、繰り返し理念を語ることが重要です。
当時私はこの「サマンサタバサジャパンリミテッド」という会社は、女性に人気のファッションを作り出す会社だとは知っていました。
ただ、その時は若い社長がたまたま流行に乗って伸びただけかなと思っていました。
でもこの新聞記事を読んだ時、私の間違いに気付きました。
辛抱強く社員と理念の共有に心がけている姿は、感銘を受けました。
同社は現在は284億円の売り上げの会社になっています。
華やかな仕事も地味な仕事も、見た目ではなく、経営の基本は同じと改めて認識した記事でした。
サマンサタバサジャパンリミテッド:
http://www.samantha.co.jp/index.html
理解と納得
私は今まで多く人達にお会いし、教えや指導を受けていました。
祖父祖母、父母、学校の先生、そして社会人になると教育担当の先輩、上司から教えや指導を受けました。
小さい頃一度だけ父から殴られたことがありました。
今でも覚えていますが、母が入院している夏の暑い日に、お手伝いに来たおばさんの財布から5円盗んで、家の向かいの店でアイスキャンディを買い食いしました。
友人達が皆アイスキャンディを食べているのが我慢できなかったのです。
なぜ見つかったか分かりませんが、父からひどく叱られ、「悪いことは悪い!」と殴られました。
殴られながら叱られたそのお陰で、その後2度と悪さはしていません。
今考えると、父は自分の子供が盗みをするということにびっくりし、「ここで叱り、直さなければ!」という気持ちだったのだと思います。
入院していた母もきっと悲しい思いをしたのでしょう。
叱られ殴られても、自分が悪いことしたということも分かっていました。だから納得しました。
銀行に入っても色々な人に教えられました。
以前にもブログで書きましたが、入行して間もない頃定期預金係の窓口担当している時、あるお客様から帯付きの100万円の束を受け取りました。
数えたのですが1枚足りません。
2度3度数えても足りません。自信のない私は、自分の間違いかもしれない思いながら、お客さまに確認したところ、「そんなはずはない!」と言われそのまま100万円の定期預金証書を作りお渡ししました。
業務終了後改めてお金を数えると、1万円足りません。やはりあのお客様です。
そのことを上司に話したところ、ひどく叱られると思ったのですが、「自分に自信を持って仕事をしなさい」と言葉丁寧に指導されました。
いつもは厳しい上司ですので、怒鳴られるかと思っていたのです。
それが優しく指導してくれたのです。
思い返すと、きっと厳しく叱ると益々私が自信を無くすと思ったからなのでしょう。
「理解する」と「納得する」とは違います。
今紹介しましたように、殴られても納得できます。
言葉丁寧に叱られても納得します。
誰に話をするにしても納得されなければ意味がありません。
一生懸命話していても、相手が「理屈は分かります。でも・・・」と言う人がいます。
これは聞く相手が悪いのではなく、話している方に問題があるのです。
頭のいい人がよく陥るのがここです。
理論武装して、相手がら反論できないくらい言いくるめても、納得しないことが良くあります。
納得には言葉だけでなく、「相手を思う気持ち」が大切です。
時には言葉が無くても、後ろ姿で教えるということも出来ます。
有能な若い経営者が会社運営で空回りしている時、このような状況に陥っているのが多いです。
「相手を思う気持ち」があれば、例え叱り倒しても分かってくれます。
松下幸之助さんは部下を叱る時は真剣に叱れと言っていました。
幸之助さんは部下を叱った後に、奥さんに「今日ご主人がしょんぼり帰るかもしれないけれども、何か美味しいものを食べさせてあげて」と電話することもあったそうです。
そのような部下を思いやる気持があればそこ、叱られた人は、より一所懸命頑張るのでしょう。
その時は「納得」が「信頼」に変わるのです。
御用始
私は今日から仕事始めです。昔の言葉では御用始です。
年初めに会社に来ると、年末清掃していたこともあってか、清々しい気持ちになります。
私は個人的には喪中ですが、会社は法人ですからそれに関係なく、正月飾りや鏡餅を飾っています。
例年は仕事始の朝は北海道神宮と琴似神社に参拝に行きますが、今年は行けず少し寂しい気持ちです。
1月は正月休みや祝日があり、実質働く日は15日程しかありません。
新年会などの行事もあり、アッという間に過ぎて行きます。
しっかり予定を立て管理して行かなければ日が流れて行きます。
年の初めには人から「今年の抱負は?」と聞かれることが多いでしょう。
皆さんはその時すぐに答えられますか?
1月は1年の「目標」を明確にしするのに最適な時です。
その「目標」は自分の「目的」である「夢」につながるモノだと、より頑張れます。
大分以前に新聞の広告に書かれていた言葉です。
「夢を失ってはいけない
夢が無くても死にはしないが
もう生きてはいけない」
私も年の初め、自分の夢の再確認をしようと思います。
本屋にて
私は先月の29日からほとんど家から出ず、冬眠状態でした。
昨日久しぶりに外出し、近くのTSUTAYAに行ってきました。
ここのTSUTAYAは北海道で一番大きいい規模でCD・DVDレンタル、文房具、本屋、コーヒーのスターバックまで入っています。
TSUTAYAが出来て最初に行った時不思議に思ったのが、ここの本屋は立ち読みOKどころか、椅子まであって座って読むことが出来ます。
最近はそのような本屋も増えているのでしょうが、ここはスターバックスの中に本や雑誌を持ち込むことも出来ます。
コーヒーを飲みながら、何冊ものの雑誌をそばに置いている人もいます。
コーヒーを飲みながら読むので、もしかしたら本にコーヒーがこぼれるかもしれません。
それでも店側は許しています。
私はこのTSUTAYAの本屋には時々どのような本が出ているか見に行きますが、本はあまり買いません。
私は決して潔癖症ではないのですが、どうせ本を買うなら人の読み跡が残っているような本は買いたいと思いません。
本屋がなぜこのようなことを許して入れるかと言うと、再販制度のせいでしょう。
売れ残っても出版元に戻すことが出来るから、本が汚されても店側は困らない。損害は出ないからでしょう。
損得から言えばこのような商売もあるのかもしれません。
でも私はこのような商売は好きではありません。
商売人は自分の商品を大事にし、最高の状態で売ることが心得です。
商品を好き勝手に使われ、汚されても平気でいれること自体が問題です。
再販制度が無く、全て自分の損害になるとすれば決してそんな事は許さないはずです。
たとえ再販制度の下で商品を預かっていたとしても、預かる限りはそれを大事に管理する義務もあるはずです。
この本屋ではそれもありません。
このような仕事をしていると社員の考え方が荒廃してしまいます。
TSUTAYAという大手の会社ですから倒産は無いと思いますが、普通の会社や店だとそうなります。
自分の扱う商品こそが自分の「飯の種」だということを分からせることが重要な社員教育ではないでしょうか!
本屋にとって再販制度というのは好条件の制度です。
その好条件の制度を間違えた使い方をすることで、自分の首を絞めることにもなりかねません。
マシュマロテスト
今日はお正月3日目です。
昨日の2日に娘が買い物に行ったのですが、ものすごい人出だったそうです。
2日は初売りでにぎわったのかも知れません。
正月と言えばお年玉ですね。子供たちも欲しいモノを買いに行きます。
でも子供の中には欲しいモノを買わず貯金する子もいます。
ところで「マシュマロテスト」というのをご存じでしょうか?
これはアメリカの心理学者ウォーター・ミッシェルが1960年代に行った「誘惑と戦い、それに屈するかそれとも勝つか」を研究したものです。
その内容というと
少年を1人ずつ別室に連れて行き、美味しそうなマシュマロを見せます。
その少年に「マシュマロを1つ上げる。これは君のモノだけれど今食べてはいけないよ。おじさんが戻ってくるまで我慢出来たらご褒美にもう一つ上げる。
おじさんがいない時にどうしても食べたかったらベルを鳴らしなさい。すぐ戻るからね。でもそうしたらマシュマロは1つしか食べれないよ。わかったかい?」と言います。
マシュマロはとても美味しそうで、少年は益々食べたくなります。
「1個でもいいから今すぐ食べたい。でも食べたら美味しくて、またもう一つ食べたくなるのではないか。そうすると悔しくなる。」と心が揺れ動きます。
少年達は自分が今すぐ欲しいマシュマロを食べるか、我慢してもう一つもらおうとするかの思いの間で、激しい心の葛藤が起きています。
この実験の結果は70%の子供が途中でベルを鳴らしマシュマロを1個もらい、30%の子供たちが自制力を発揮して15分間待ち2つもらいました。
この実験から10年経った追跡調査によれば、我慢できた子供達は、我慢できなかった子供達に比べて、強い友情で結ばれ、困難な状況に適切に対処する力があり、行動上の問題も少なかったそうです。
成人後の追跡調査でもこの自制心のある人達は、喫煙の経験率が低く、社会経済的地位が高く、修学年数も長かったという結果が出ています。
以前もブログで「貧乏な人」「普通の人」「金持ち」のお金の使い方をジュースを飲む時を例えて書きました。
貧乏な人はジュースがグラスに満たないうちに次々飲み干します。
普通の人はジュースがグラスに一杯になってから飲みます。
金持ちはジュースがグラスに一杯になっても飲まず、グラスから溢れてきたジュースだけを飲みます。
だからいつもジュースがいっぱいあるのです。
このジュースの話とマシュマロテストとは、共通する点が多いですね。
正月休み
今日は1月2日。事初めの日です。
元旦は何もしてはいけない日で、習い事などは2日の今日から始めると言われています。
私のブログも今年初めてになります。
昨年末父が亡くなったので、喪中のため正月は無いことになっています。
年末せっせと喪中はがきを出したので、年賀状はありません。
神棚も触ってはいけないということで、掃除もしていません。
勿論お供え餅も、正月飾りもありませんので、正月と言っても雰囲気はテレビの中だけで、普通の連休のような感じです。
やはり年末バタバタして掃除をし、正月飾りをし、元旦は神社に行く行為そのものが正月のでしょう。
今年は静かな正月なので、思いのほか本が読めています。
400ページ弱程のハードカバーの本をじっくり読んでいますが、今年だからこそ読めるのでしょう。
2~3冊は読みたいと思っています。
それと今年はお酒をほとんど飲んでいません。
年末に体調を崩した事もあるのでしょうか。
今年は少し健康に気をつけようと真剣に考えています。
細木数子さんの占いの本によると今年の私はいい年のようです。
でも、健康があってこその仕事であり、遊びです。
今年も多くの体験をし、いい年である様に頑張ります。
今月の11日には今年の「夢計画作りの会を」開きます。
今年の計画をその時間内に一気に作り上げるのが目的です。
マンダラ形式を用いた計画書作りになります。
1人でダラダラと作って中途半端なモノを作るより、決められた時間内で、お互い刺激を受けながら一気に作り上げてしまいます。
作った自分の計画は、見せ合う必要はありません。(見せたい人は勿論いいです)
一気に作り上げてしまうと楽で、後でまた状況に合わせて修正していくことが出来ます。
10名以内のメンバーがちょうどいいかもしれません。
今のところ4名参加ですのでまだ余裕があります。
参加したい人はどうぞ連絡ください。
今年もいい年の予感がします。
貧・瞋・痴
今日は大晦日です。
年の終りに1年を振り返ると何があっただろうか。
私は後悔することが大いです。
夜にはお寺で除夜の鐘が108つ打たれます。
煩悩を払うために打たれ、その煩悩が108つあると言われています。
その中心になるのが「貧・瞋・痴(とん・じん・ち)」です。
ご存じのように人間にある3欲で、仏教の言葉で「貪欲(とんよく)」「瞋恚(しんに)」「愚痴(ぐち)」のことです。
人はこの煩悩から逃れることはできなく、それを犯しては反省して悩みます。
西遊記にもこのことが語られています。
「貪欲」は「むさぼること」で人間の「欲」を表しています。 これは猪八戒。
「瞋恚」は人間の「怒り」を表わし孫悟空。
「痴」は「愚痴」で 真理が見えず理解出来ない為に不満を持つ事を表して、沙悟浄。
そして三蔵法師は自分自身のことです。
人間は常に3欲から離れられないのです。
稲盛和夫さんも、勝間和代さんもこの3毒についてそれぞれの本に書かれています。
ただ、この3欲は全く良くないかというとそうではなく、これが人間が生きていく上での大切な条件でもあります。
これがあったからこそこの世の中が発展してきたとも言えます。
今、私は「利休にたずねよ」という本を読んでいます。
この本は第140回直木賞作品で山本兼一氏の著書です。
その中にもこの3毒について書かれています。
利休の言葉として「人は誰しも毒を持っておりましょう。毒あればこそ、生きる力も湧いてくるではありますまいか」
「肝要なのは、毒をいかに、志にまで高めるかではありますまいか。高きを目指して貪り、凡庸であることを怒り、愚かなまでに励めばいかがでしょうか」
「それは3毒の焔を一段高い次元に昇華させることになる。」
これは山本氏が利休の口を借りて語っていますが、私は得心しました。
私は今の日本は3毒に満たされているように思っていました。
自分勝手な事を主張し人のモノを欲しがり、人に対して怒ってばかりいて、愚痴・妬みばかり口にしているように見てきました。
そのため3毒を否定してきました。
しかし3毒は、志を高次元に高める為に人間に許された力なのかもしれません。
私の亡くなった祖母が言っていた「下見て暮せ。上見て励め」の上を見て頑張る人が沢山出てこなければならないのが今の日本なのかもしれません。
3毒は人間生存に必要なモノで、それを生かす生き方が大切なのです。
ただそれが過ぎれば大きな悩み、煩悩、そして罪になります。それを理性によって押さえる為に、いろいろ学ばなければならない。
年の終りにそんなことを考えています。
私の業(ごう)
昨日午後から私の体が変調をきたし、寝ていました。
今朝もまだ本調子ではないようです。
私は以前から年末に家の内で何かが起こると警戒していました。
私の家では年末になると誰かが倒れたり、骨を折ったりして病院に行ったりしていました。
昨年も12月30日に母が倒れ救急車で運ばれました。
今年も皆で「気をつけようね」と言ったのに、私が病気に掛かってしまいました。
このようにブログが書けるのですから、それほどひどいモノではありません。
昨日のブログでパワースポットのことを書き、その中で業(ごう)のことを書きました。
私の家で毎年のように年末に起きていたトラブルは、その業が無くなる通過点なのかと思います。
業が無くなり、まっさらな新年を迎えることが出来るのかもしれません。
軽い病気程度で済めばありがたいことなのでしょう。
それにしても来年こそは体調管理に気を使うことが大切だと実感しています。
パワースポット
最近パワースポットのことがテレビや新聞で取り上げられています。
明治神宮にある加藤清正の井戸がパワースポットとして評判だそうです。
日本の究極的なパワースポットは伊勢神宮でしょうか。
伊勢神宮には多くの人が参拝し、今年は過去最大の参拝客数だそうです。
「パワースポットに行けば良いことが起こると」いう思いを抱いて行くのでしょうが、ここでいつも不思議に思うのは伊勢神宮で毎日働いている神主さんや神官さんは毎日いいことばかり起きているのか?ということです。
伊勢神宮周辺で商売している人達は皆、商売が上手く行き、悩み事もなく幸せに生活しているかと思うのでしょうか?
きっと世間一般と同じように、いい人もいれば悪くなる人もいる。幸せな人もいれば、不幸せな人もいるはずです。
それじゃパワースポットへ行くことは無意味なのかというと、そうではないでしょう。
ご利益はあると思います。
ただそのご利益は受けた人によって、色々な形に変えて現れるのではないでしょうか。
パワースポットに行っても宝くじが当たる人もいれば、恋人と別れる人もいるかもしれません。
商売している人は取引先と上手く行かなくなるかも知れません。
そのような状況は受けた人それぞれがそれをどのように受け、対処するかによって良くも悪くもなります。
パワースポットへ行くことはそのような機会を与えてくれるきっかけになったのかも知れません。
パワースポットへ行って恋人と結婚を願ったししても、結果別れてしまうこともあります。
それは結果良かったということもあるのです。より素晴らしい人が現れるために必要なことだったのかもしれません。
取引先と上手く行かず商売が無くなっても、実はその取引先が仕事上のネックだったのかもしれません。
結局、自分の身に起きたことをどのような心で受け入れるかが重要になってきます。
何年も前に、京セラの稲盛和夫さんは、京セラがファインセラミックスの人工膝関節を、許認可を得ずに販売したということでマスコミに叩かれたことがありました。
既に認可を受けていた人工股関節を、医師の人達からの強い要望により、膝関節に応用したという事情があった様です。ですから稲盛さんは言いたいことが沢山あったようです。
それを師事していた京都の円福寺西片擔雪(たんせつ)老師に話したところ、「それが生きているということです。災難に遭うのは、過去につくった業(ごう)が消える時です。 稲盛さん、業が消えるんですから、喜ぶべきです。 今までどんな業をつくったか知らんが、その程度のことで業が消えるのなら、お祝いをせんといかんことです」と言われたそうです。
稲盛さんはこんなに苦しい思いをしているのに、お祝いしなさいと言われてその時は「ムッ」としましたが、後で考えるとその通りで、その言葉は最高の教えだったのです。
そう思うことで気持が切りかわり積極的な対策が出来たそうです。
どのような時でも、起きたことをどのように受け入れるべきか、その心の有り様が大切なのです。
パワースポットに行って気持が良くなればそれで良しとし、何かがあっても良きことと受け止めることは開運につながるのかもせません。
私は今まで伊勢神宮に入ったことが無く、今年は行こうと思ったのですが、事情があり行けませんでした。
来年こそは私も伊勢神宮に行こうと思っています。
より良い運をいただきに。
起業について
私のところに起業を志す人がよくいらっしゃいます。
起業を志す人達はそれなりの自信があり、目算があり頑張ろうとします。
現在は起業するにとって環境はいいと私は思っています。
今の日本のような縮小経済の時は隙間が生まれます。
その隙間を見付けて起業する事は出来ます。
最初は小さい事業でも、時として大きな事業に変わることもあります。
ダスキンにしても、ヤマト運輸にしてもそうです。
ただ一方、縮小経済というのは全ての分野で、100の需要が90、80になって行くことです。
ですから、例えば居酒屋で起業をしようとすれば90,80になった市場で客の奪い合い、低価格競争に巻き込まれてゆきます。
その様な状況で起業するなら、新しいサービスやアイディアを作りだし、参入していかなければ勝算はありません。
好きだからというだけで参入し、従来と同じ商品・サービスしか提供できなければ、すぐ撤退することになります。
起業が経済を活性化すると言うのは、新しい分野の開拓、新製品開発、新しいアイディア発想があって、そこに新しい需要が生まれるから、起業の意味があるのです。
この新しい分野の開拓、新製品開発、新しいアイディ発想は、良く練られなければなりません。
どうしても独りよがりになりがち、我田引水の考え方に陥ります。
その時こそ、自分の周りにそれを評価してもらえる人のネットワーク作りが必要です。
何でも批判する人や何でも褒める人は外します。(ここがポイント)
そのネットワークがそのメンバー同士のフォローアップの場になれば大きな力になります。
私の仕事はそのネットワーク作りの手伝いをする事かと考えています
マンダラ手帳
クリスマスも終り、今年も残り少ないです。
来年の目標計画を立てている人も多いのかもしれませんが、今年の目標計画は達成しましたでしょうか?
過ぎ去ってしまったことを思い返しても仕方がありませんが、来年の計画を立てる時、今年の結果はどうだったかは、どうしてもチェックしておかなければなりません。
私も今しているところですが、如何に未達の事が多いことか。
私が使っている手帳はマンダラ手帳です。
ご存じの方も多いと思いますが、中心核を持った3×3の9マスのマトリックス=マンダラチャートが使われています。
人生計画やビジネス計画がマンダラチャート式になっています。週間計画もです。
その人生計画に今年の目標計画が書くようになっています。
その計画のページには「健康」「仕事」「経済」「家庭」「社会」「人格」「学習」「遊び」の8項目があります。
マンダラ手帳のいいところは8項目が全て同等に重要だという考えがあることです。
以前は自分が計画を立てる時、計画の順番は「仕事」が最初にあり、次に人とのつながりの「社会」がありその後に「家庭」や「健康」等が続きました。
「仕事」の2つくらい後に「家庭」がありますが、それではいつまでたっても家庭を顧みることは出来なかったのです。
マンダラ手帳の考えは「仕事」も「家庭」も「遊び」も全て同等に大切だということです。
マンダラ手帳はいい手帳だと思いますが、問題は計画を書いても未達成が多いことです。
これは手帳に問題があるのではなく、私に問題があります。
「仕事」「学習」ばかりでなく「遊び」や「健康」さえも未達が多いのです。
「食べ過ぎない」「飲み過ぎない」「体重を○○kgにする」は全然だめ。
これから来年の目標計画を立てるのですが、また同じ目標を掲げるかどうか悩んでいるところです。
公私混同
私の会社は家具工場です。
木の端材が沢山出ます。
ある時、1人の社員が器用に木の端材でお地蔵様をカッターナイフ一つで彫っていました。
工場では昼休みの他に10時と15時に15分ほどの休憩時間があります。
彼はその時間にコツコツ掘っていたのです。
そのお地蔵様は高さ3cm×幅1.5cmの大きさで、とてもかわいくて、1つもらいました。
それをストラップとして携帯に付けていると、大変評判がいいのです。
(運もいいのです)
作ってくれた彼は趣味でイラストも書き、造形感覚も優れた人です。
図面も下絵も無しで、小さな端材に直接カッターナイフで彫り込んで行きます。普通の人には出来ない才能です。
彼の普段の仕事はNCルーターのオペレーターで、図面通りに機械で木を刻む仕事です。
その仕事は慣れれば彼でなくても誰でも出来ます。
彼の本来持っている才能を生かす仕事ではありません。
そして、彼の才能を生かす仕事は今の工場にはありません。
一方、彼は自分の才能を特別なモノと思う気持ちは持っていないようでした。
私は普段から彼のイラストや彫刻を見ていましたので、その造形感覚や技術の高さは素晴らしいモノがあると思っていました。そして才能を別な方面で生かすことが出来ればと考えていました。
半月前に私の持っているお地蔵さまを見た人が欲しがりました。一緒にいた人も欲しがり、結局合計10個ほど欲しいということになりました。
彼の才能を求めてくれる人がいて、それもお金を出してでも欲しいと言う人がいるのです。
金額は支障があって言えませんが、それなりのものです。
彼に依頼しました。仕事ではなく彼の趣味の延長としてです。(勿論マージンは取りませんよ)
ここで問題が起きました。
私は彼の副業として、自宅でお地蔵様を作ることは問題ないと考えています。
社内規定にも副業を禁止する項目はありません。
しかし彼の直接の上司は筋が通らないという主張です。
彼に仕事を依頼するのは会社を通すべきだと言うのです。
公私混同というのです
私の考えは違います。
会社は社員1人1人と向き合い、その人それぞれの特性を生かす努力をしなければならないのです。
しかし残念ながら会社にその特性を生かす仕事が無いのなら、その特性を生かす方策やチャンスを考えるべきと考えます。
社員は会社の所有物ではありません。
そして万が一にも、将来その社員が会社を離れることがあっても、自分の才能に気付き、それを生かせる術を知っていれば仕事は色々あるのです。
人を生かすということについて考えてみました。
このお地蔵様を写真添付しました。宜しければご覧ください。
そしてお地蔵さまのご感想もいただければ嬉しいです。


物忘れ
最近は物忘れが激しくなってきました。
さっき会った人の名前を忘れる。2階に来て何をしに来たか忘れる。さっき喧嘩していた原因も忘れる。
ただ、痴呆症状とは違うとは思います。まだ食事をしてかどうかくらいはわかりますから。
このブログは毎日書いていますが、最近「サア書こう」と思って書くと、「あれもしかしたら前に同じこと書いたことがあったかも」と大変不安になります。
もしかしたら既にその症状が起き、読んでいただいている方々には、「前と同じことを書いている」と思われているかもしれません。
もしそうなら申し訳ありません。でもまたあるかもしれませんので今からお詫びしておきます。
年を取ると物忘れが進み痴呆になっていくのかと思います。
自分の両親と同居していましたから良く分かります。
以前私は物忘れがひどくなり、もしかしたらそのまま痴呆につながるかという不安がありました。
医学的にそうなのかは分かりませんが、今はなったとしてもそれを受け入れることにしました。
周りの人には迷惑を掛けるかもしれませんが、痴呆になるということは神様が長生きした人へ与えたご褒美なのかも知れません。
年をとり、人の顔も忘れてしまったとしても、本人にとっては何の不自由も無いのです。
食事をしたのを忘れて、また食べたても、食べるだけ元気の証拠です。
痴呆になると今しかなくなるようです。
過去のことを忘れ、将来の不安もありません。
そして死ぬ不安も無くなるのではないでしょうか。
年をとって毎日その日にだけを生きるのもいいかと思います。
私もいつか来るその日の為に、覚悟と身辺整理をしようと思っています。
今年の少ない日を数えながらそう考えています。
アイディアについて考える
昨日知人と話していての話です。
その知人が運営している会では、時々メンバーが集まり今後の会の運営などについて話し合いをするそうです。
ある日、同じように話し合いをしていた時、メンバーの1人が自分のアイディアを披露し、それについて皆で話をしていたそうです。
その後、その会に参加していた別のメンバーがそのアイディアを使って仕事をしているのがわかりました。
一言断りを入れていればまだ良かったのですが、それも無かったそうです。
読んでいる皆さんにも同じ様な経験があるかと思います。
私も経験があります。
された人間はしっかり覚えていますが、した本人は「真似た」と思っていないのかあまり気にしていない様子です。
意識して「真似た」わけではないと言っても、会社の仕事絡みだと大変のことになります。
お金が絡みますから。
札幌の知られたある会社は、噂ですが他社のアイディアを勝手に使いっているというものがあります。
だからその会社の人の前ではアイディアなどを話しをするものでないという話です。
ここで考えさせられたのは、アイディアを勝手に使って仕事をした人が悪いのかということです。
もしかするとアイディア考えた人はアイディアを考えついただけで、それをすぐ仕事に生かせなかった。
もっと言えば出来なかっただけとも言えます。
考えたらすぐそれを仕事に生かせば良かったものを、それを人に披露するだけでそれ以上すすめれなかっただけではないでしょうか。
私も色々アイディアを考えることはあります。しかしなかなか仕事に結びつけることは出来ません。
しかしだからといって、それを誰かが勝手に使われると面白くはありませんが、しかし自分に出来なかったことを他の人がしたのだから良しとしようと思っています。
本当に自分でそのアイディアを守りたいなら特許で保護すればよいのです。
ただ、個人レベルで言えば、仲間作りが大切です。
アイディアを考えた人も、それを使いたい人も、お互いに「使わして下さい」「いいですよ」と言える風通しのいい関係が大切ですね。
「大人の学校」
昨夜「大人の学校」の忘年会に参加してきました。
前日も別の忘年会でしたので少し疲れ気味で参加しましたが、実際に始まると、その疲れを吹き飛ばす楽しい会でした。
この「大人の学校」は私の知人のSさんが今年始めた文化教室的な勉強の場です。
「大人の学校」の運営理念は「私たちは大人の学校の運営を通して、参加者一人一人がより充足感に満ちた生活を送り、仲間の輪を広げることができるよう、お手伝いをします。」
講座は「カーリング」「バルーンアート」「話し方教室」「ギター教室」「カラーセラピー」「ひょっとこ踊り」等10講座以上あります。
長年勉強して経験もありながら、それを生かす機会が無いのが現状です。
でも、1人では出来ないけれど、仲間が集まれば出来る等ことがあります。
志ある人達が集まったのがこの「大人の学校」です。
生徒集めは講師は勿論学校としても熱心に告知活動をしています。
この「大人の学校」は北海道のお笑い芸人の集まり「北海笑事」も応援しています。
若い人達がビックになるのを夢見て頑張っています。
昨日の忘年会会場もその北海笑事が運営する「北笑ダイニング」というステージ付きの居酒屋で行われました。
この「大人の学校」校長のSさんはその人柄でしょうか、色々な人と人とを結びつけるのが上手な人です。
1人1人の力を発揮させることが出来る人です。
このような人がいてこそ個人の力を発揮できる場が生まれるのだと思います。
今、志を持っていながら、その機会を見いだせることが出来ずいる人にとって、Sさんのような人が多く出てくることが、元気な世の中を作っていくことになるのだと感じます。
それにしてもこのSさんはお酒が飲めないのに、飲んだ人以上に陽気になり会を盛り上げていました。
人を喜ばすことが本当に好きな人なんですね。
クリスマスカード
昨日知人から桐の箱に入ったお線香が送られてきました。
父の霊前にということです。
お線香の贈り物は最近TVのコマーシャルでも見ますが、実際に送られてきた時は「へー」という驚きと、気を使っていただいた感謝の気持ちが伝わってきました。
贈り物と言えば私が還暦を迎えた時、妹から桐の箱に入った5合瓶のお酒と徳利・お猪口の酒器セットをもらいました。
その桐の箱とお酒の瓶、徳利・お猪口には私の名前が入っています。
これをもらった時も「へー」と驚きました。
何かを送る時、相手に感動を与えるモノを考えるのは結構大変です。なかなか見つかるものではありません。
送ると言えば、今は年賀状を書いている人も多いと思います。
年が明けると多くの年賀状がきます。それぞれ考えられ、工夫されているものも多いです。
でも相手に感動を与えると年賀状は少ないです。
私が以前ホテルの支配人をしていた時、出していたのは年賀状の他に、クリスマスカードです。
その切っ掛けは、ある年のクリスマスの前日に仕事で親交のある人から届いたクリスマスカードです。
思いがけないカードに驚き感激しました。
日本ではクリスマスカードを出す習慣がほとんどないので、いただいた時は驚き、喜ばれるはずです。
お仕事でお世話になっている人にクリスマスカードを送ると大変喜ばれ、その効果が大きいことは経験上分かります。
今年はもう遅いかもしれませんが、来年は思い切って年賀状でなくクリスマスカードを送るといいですよ。
その効果は驚くばかりです。
ぜひ仕事に生かしてください。
若者よ広く遊べ!
私は現在61歳、もうすぐまた1つ増えます。
61歳のおじさんから「今の若い者は!」と言うつもりはありません。
ただお節介にもつい口に出してしまいます。
若い内は固まらない方がいいです。固まらないで欲しいのは頭、考え方です。
色々な情報に囲まれて、全て知っているような錯覚になってしまうからでしょうか、若者なのに頑固な人が多いように思います。
若いうちは広く実体験を通して、経験知識等を身に付け、その上で取捨選択すればいいのです。
若者の特権を使えばいいのです。
沢山恋をして、失恋もたくさん経験すれば人の痛みも分かります。
マージャンやパチンコしてお金を無くせば、お金の有難味を知るかもしれません(逆もありますが)。
国内旅行や外国に遊学して知識と知人と、経験を増やせば一生の財産になります。
音楽にのめり込み、楽器に熱中するのもいいです。
勿論勉強も大事ですが、若い時でなければできないことを経験することが自分の可能性を広げるのです。
若い内は浮気性でいいのです。
その内その人間の考え方が作り上げられてきます。
1つのモノだけに集中するのはその後でいいのです。
以前にも紹介したかもしれませんが、ある人は定期的に各分野の本や雑誌を買うそうです。
倫理、哲学、政治、経済、科学、文芸、芸能、美術等の広い分野の本を一気買いし、読みます。
時にはエロ本も買うそうです。
そのようにして自分の考え方を偏らせないように努力しているのです。
流石に私はその真似はできませんが、その大切さは常に意識しています。
無責任な多くの情報に惑わされず、自分なりの判断する基になるのは、そうした経験の積み重ねの上にあります。
若者のことを書いてきましたが、若者ばかりでなく、頭が固くなってくる年配者も同様なのかもしれませんね。
学び合い
昨日は「ご近所先生企画講座」の研修会がありました。
この「ご近所先生企画講座」というのは札幌市が主催する勉強会です。講師は一般の市民です。
自分の得意分野を教える講座です。
今まで人に教える経験の少ない人に、講師として進行の工夫を教える研修会です。
この講座は「教える」ではなく、共に「学び合う」がポイントです。
「教える」は一方通行です。
「学び合う」は相互通行です。
講師という立場で話をしますが、講座に参加する人達もそれなりの経験を持っており、その見識を知るのも勉強なのです。
共通のテーマを講師という立場の人が進行役になり、参加者同士が教え・教えられながら理解を深めていく。
そういう勉強会は楽しいモノだと思います。
その為の講座の基本的な考え方があります。
1.共通の目的を明確にする
到達目標、計画、手順を知る
2.物理的環境を整える
机の並べ方、使う備品の習得
3.共通の体験をする
共同作業体験、結果や感想の交換
4.個人の特性を知る
相互認識、受講動機や期待の共有
5.円滑な関係性を持つ
基本ルールの設定、緊張緩和、コミュニケーション環境整備
このような相互通行的な講座で特に大切なことは、最初にルールを明確にすることです。
発言した内容を否定から始めないと言うことです。
ある人が話をした時、すぐ「いや違う」と誰かが反応すると、そこに反発の場が出来てしまいます。
反発の流れが出来ると互いに否定し合います。
例え自分と違う意見を言っていると思っても、一度それを肯定するのです。
「いや違う」と言うのでなく、「そうですね。そういう考えもありますね」と相手の話を受け入れるのです。
その後自分の意見を言う時も「ただ、こういう考え方もありますよ」といって反対意見を述べると、それほどの反発は生まれません。
これは私の経験から書いています。
今度の講座は1月中旬から始まります。楽しみです。
「起業家寺子屋」
以前から私は起業を志す人を応援・支援するレンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」を運営しています。
そこには一生懸命自分の夢を追う人達がいます。
私が応援・支援する人は「札幌オフィスプレイス」に居る起業家ばかりでなく、それ以外の起業家にも成功してほしいと願っています。。
勉強会や交流会も「札幌オフィスプレイス」の人達ばかりでなく、外部の人の参加も多くあります。
起業を志す人達向けのホームページを11月頃から始めてきました。
やっと正式なロゴも決まり、正式開設になりました。
「起業家寺子屋」がその名前です。
昔、寺子屋では手習い・読み方・そろばんなどを教え、子供たちは学問や商売の基礎をそこで身に付けました。
「起業家寺子屋」も経営者としての「基本的な考え方」を伝えて行きます。
起業し事業を拡大して行く時、「基本的な考え方」を充分身に付けていないと、壁にぶつかり止まってしまいます。
そして、その原因が分からず挫折する人がいかに多いことか。
私は先生という教える人ではありません。どちらかというと伝道師です。
今まで多くの人達、とりわけ父や稲盛和夫さんから学んだことを伝えていくことが、私の仕事だと思っています。
受けた恩の「恩送り」です
「起業家寺子屋」のホームページは作ったばかりです。
ホームページを見られ、何かご提案やご指摘があれば教えてください。
「お問い合わせ」というページがあります。
そこからご意見等をいただければ大変うれしいです。
起業を志す人達に必要とされるサイトにしたいと願っています。
「起業家寺子屋」ホームページ:
http://www.kigyoka-terakoya.com/
「お金がある生活」と「モノがある生活」
昨日ある人と「お金がある生活」と「モノがある生活」について話しました。
お金があっても使わずにいる生活と好きなモノを買って満足する生活を選ぶとすると、どちらがいいかというものです。
私もその人もお金があっても使わない生活を選びました。
普通、金を稼ぐ目的は、欲しいモノを買いたい、美味しいモノを食べたい、好きなところに行きたいからお金を稼ぐのでしょう。
そうするともっと高いモノを買いたい、もっと美味しいモノを食べたい、行きたいところが増え、益々頑張って稼ぎます。
そうすればお金が回り日本の経済が良くなってきます。
それでは、お金を稼いでも使わず貯めておくことの何がいいのかというと、お金があれば何でも買えるという「可能性」です。
いつでも買えるという「心の満足」なのです。
必要なモノ以外は、いつでも買えるけど買わない。
本当に必要なモノは、以前にもこのブログで書きましたが、気に入ったのを「一点豪華主義」で買うだけ。
お金があっても使わない、モノ以外の楽しみ喜びを見出せば、よりその傾向は強くなります。
今の日本はそんな気持ちを持った人が増えているのかもしれません。
だから日本の中でお金が回らず、経済が浮上しないのかもしれません。
企業も同じです。
稼いで、その上借金をして、次から次へと事業拡大をしていく会社と、しっかり内部留保を充実させていく会社があります。
どちらがいいかは一概に言えません。そして極端であってもいけません。
会社は適正な利益を出すことが基本です。
事業拡大してもそれに伴う経常利益が10%程度生まれていればいいのですが、3%・5%では自転車操業になります。
個人がお金を貯めているのと同じように、会社もある程度の内部留保が有るか無いかによって、経営者の心の余裕が違います。
お金があれば、嫌な仕事を断ることが出来ます。嫌な人に頭を下げる必要もありません。
会社が投資しなければ益々経済活性化しませんが、個人も会社も今は自己防衛を考える時かもしれません
今は、先を見分けていく力を蓄え、蓄えた力とお金を「一点豪華主義」的に使う時期をうかがう時です。
高齢化社会
知人が主催するセミナーに行ってきました。
「ほっとけない介護セミナー」と題し、介護の現状の勉強です。
私も親と同居し、86歳の母親の世話をしています。
と言っても主に妻がしてくれています。感謝
2008年9月末のデーターがあります。
65歳以上の人口は2,877万人。そのうち要支援・要介護認定者は462万人で、6.2人に1人の割合になります。
これから2年ほど経つと団塊の世代が65歳に突入してきますので、この割合が急増します。
在宅介護の場合、要介護度に応じて介護保険から給付される支給限度額が決められています。
在宅サービスにかかった費用が限度額以内の場合に自己負担は1割です。
限度額を超えると超えた分が全額自己負担です。
限度額は月額で「要支援1」の49,700円から「要介護5」の358,300円です。
この額でも不十分と言われています。
一方、別のデータとして2006年度の社会保障給付費は89兆円を突破しています。
その内訳は高齢者関係費が69.8%です。
それに対して育児支援など児童・家庭関係費は4.0%と驚くほど少なく、この比率はここ数年ほど固定しています。
私は61歳で数年で65歳になります。
高齢者となった時、自分のことを考えれば手厚い介護体制を願いますが、この数字を見ると、児童や若年層に対しての支援体制を充実していかなければ、日本の将来が不安です。
先日北海道大学の山口教授が話したことが日経新聞掲載されていました。
「団塊の世代は食い逃げするな」という趣旨で書かれています。
恵まれた環境で定年まで過ごし、金銭的にも豊な団塊の世代は若者へ寄付などを通じて助けるべきであると言っています。
確かに団塊の世代は学園紛争で燃えながら、就職難など経験せず、高い初任給を受け、結婚すれがマイホームパパになり、好景気を経験し、それなりの財産も作ってきた世代です。
定年になったからといって、単に自分の趣味なりの私生活に埋没するのでなく、世の中で恩返しする活動をしなければ罰が当たります。
私も罰が当らないように頑張ります。
成功する人
昨日「札幌オフィスプレイス」に入居されている女性起業家とお話しました。
彼女はパフォーマーとして順調に成功しつつあります。
彼女を見ていると成功する人の見本のように思います。
いいところは素直、行動的、物おじをしないの他に、決して人の悪口は勿論噂話もし無いところです。
仕事に関しては、寝る間も惜しんで打ち込んでいます。
それでも悲壮感はなく楽しんでいるようです。
彼女の周りには担いでくれる人が多くいて、営業をせず、ほとんどが紹介によって仕事が増えています。
成功を願うなら彼女を研究するといいでしょう。特に女性は。
私は以前、成功する人の条件として、自立心があり、どのような困難も切り開くほどの精神力のある人だと思っていました。
でも、時々そのように見えるの人が壁にぶち当たって苦労しています。
それは自分に自信がある人、過去に失敗の少なかった人、挫折したことのない人に多いようです。
逆に自分に自信のない人は素直に人の話を聞こうとします。
素直ということは情報の受け口が多いということ。
失敗したことのある人は、慎重になります。
これも人の話を聞こうとします。
挫折したことのある人は、人の痛みが分かるので優しくなれます。
物事はそう簡単ではないと思うかもしれませんが、結構単純な理由で成功を手にすることが出来る私は思っています。
良いモノを使い続ける
モノを買う時、何を基準で買いますか?
私は何かを買う時、少し高くても、長く使え、飽きの来ないモノを選びます。
特に、万年筆や腕時計、カバン等の耐久品は少し無理しても、気に入ったモノを買いたいと思います。
そのかわり数は1個から2個程度でいいのです。
家具などは以前もブログで書きましたように、少し高くても10年20年使い込んで、味が出てくるような家具を選びます。
安いだけのモノだと、使い捨てのイメージがあり、結局お金の無駄であり、ゴミを作ることになります。
以前何かに書いていたフジマキジャパンの藤巻幸夫さんが書いた文があります。
「私は『モノは心』という考えがあって、使い捨てにせず、使い続けたいと思うし、だから選ぶ際の基準は大切。
総合すると『色×素材×機能性×ブランドの顔×デザイン』を重視し、その上で価格を考慮に入れます。」
同じようにモノにこだわった文章を書いているのが元NHKアナウンサーでエッセイストの下重暁子さんの「持たない暮らし」という本です。
そこには「私自身は『シンプルに暮らす』とは、モノを捨てることではなくて、『物を大切にすることだ』と思っている。
最初は私はモノを捨てることばかり考えた。しかし、それでは解決できない。行きついたのは、モノを大切にする、モノの命を使いきることだと気が付いた」と書かれています。
良いモノを長く使う事によって、同じようなモノを何度も買わず。簡素に暮らす。
必要なモノしかないシンプルな暮らしに、今私はあこがれています。
これからの年末の大掃除を前に、無駄なモノの多さに驚きつつ考えたことです。
0.07秒
「0.07秒」と聞くと、「スポーツ競技会の1位と2位の秒差?」と思うのではないでしょうか?
先日の新聞に掲載されていた数字です。
新聞よると、中部電力のある変電所で瞬間的に電圧が低下し、周辺の半導体工場などが被害を受けたそうです。
その電圧低下した時間はわずか0.07秒間。
0.07秒間の電圧低下は、普通の生活レベルでは全く気が付かない変化です。
そのたった0.07秒の為に各工場に大きな被害が発生しました。
東芝の四日市工場ではこの為に1~2月の出荷量が2割減になるそうです。
工場では10億分の1m単位の精度の装置を再調整するため復旧に数週間かかるとのこと。
その工場で作られるフラッシュメモリーの供給が減少するという見込みで、スポット取引価格が前日より高くなり、一方東芝の株価は下がりました。
それほどの影響を与えました。
その他の工場でも影響が大きく、補償問題に発展する可能性がるそうです。
それぞれの工場では万が一のトラブルに備えてバックアップ装置も設置していました。
東芝でも雷などの供給電圧低下に備えて、装置を設置していたそうですが、今回は想定を上回るのどの急激な低下だっそうです。
私達の日常生活や仕事では、これほどの精密さを求められることはありません。
だからこそこの報道には驚きました。
仕事の上で「間違いのない仕事をする」「完全主義を貫く」と努力しても、他者の影響や天災でどうしようもないことが起きます。
その時、余裕のない仕事をしていれば、それが致命傷になることがあります。
稲盛さんが云う「完全主義を貫く」という言葉と共に「土俵の真ん中で相撲を取る」という言葉が頭に浮かびました。
土俵の真ん中で仕事をしていれば、天災に会ってもそれに対処できる余裕があるから生き延びれます。
それにしても、これほどのミスも許されないほどの電力体制が基盤にあってこそ、日本のハイテク産業が存在するということも再認識しました。
日本はすごい!
起業を志す人
先週の金曜日に起業を志す人が来られました。
パソコン操作が得意ということで、パソコン教室を経営したいと考えているようでした。
お話を聞いて感じた問題は、それに伴う計画が無く、ただ起業して教室を開きたいという気持ちだけが先行していることでした。
勿論、これから起業をしたいと思う時、最初に夢が必要です。その夢を思う情熱が、計画を進める原動力になります。夢をドンドン膨らませることは大切です。
その時陥りがちなのは、夢を具体的に数字に落とし込んで行くのを後回しにしがちなこと。
夢を持ちそれを追い求めていく時、同時に数字で考える「癖を付ける」ことがどうしても必要です。
その数字は最初は大まかなモノでいいのです。
このことは以前も書いたと思いますが、単価、客数、稼働率、材料費率、諸経費割合、人件費、利益等は頭に浮かべながら判断しなければなりません。
それが無ければそれこそ「砂上の楼閣」や「書いただけの牡丹餅」になってしまいます。
多くの成功している経営者は常に頭に数字を置いて判断しています。
数字のない計画は「何の意味も無い」と言い切ります。
相談に来られた人にはそのことを話しました。
その上で、パソコン教室を開くからと言って今すぐに勤めている会社を辞めるのでなく、「週末起業」を勧めました。
時間の空いた時に、個人指導をしながら、どの程度の顧客がいそうなのか、レッスン料は幾ら位だったらいいのかを知りながら、独立の自信を確かめることです。
少し偉そうに言いますが、今まで経営者や起業を志す人に数多くお会いしていまので、会った瞬間に起業家として向いているかどうか分かるようになりました。
100%ではないのかも知れませんが、高い割合で分かります。
しかしだからと言って、起業家に向いていないと思う人には直接「向いていない」とは言いません。
勿論、勧めもしません。
難しいところです。
どう話すのかは言えません。
これから相談に来られる人がいますので。
モノを売る
商売に限らず、アイディアを練ったり企画を立てたりするのが好きな人がいます。
彼ら、彼女らは、時々ユニークなモノを考え出します。
それに惚れ込んで特許まで取ってしまうこともあります。
私もそういう人の一人です。
今まで特許や実用新案の申請もしました。
一時はこれで商売になると思い込んで一生懸命になったこともありました。
実際はそれほどのことはありませんでしたが。
モノが先にあると、販売対象や販売方法をその後に考えることになります。
時として、その時の足かせが商品そのモノにあることに気が付かないことがあります。
どうしてもその特許を取ったモノがいいモノだという自負心から、販売対象やそのルートを狭めてしまうようになります。
「優れた職人は優れた経営者になれない」と言われます。
それは自分の製品を作品のように思いこみ、販売しても売れない時、お客に対して「その良さがわからない客だ」と思いがちになります。
それと同じようにモノが先に立ってしまうと販売しにくいものです。
いいモノだから売れるわけではないのです。
これは私の反省でした。
私が作ったのモノは趣味的なモノでしたので、売れなくてもそのままにして時が過ぎています。
もしも本当に売ろうとするなら、そのモノにこだわらない別の人とタッグを組むのもいい方法だと思います。
昨日私のところに仕事の相談に来られた女性も、ご自分の考えられた商品をどのように売るかの話でした。
彼女の商品も特許申請中です。
彼女の話を聞いていると私と同じように、商品への自負心を持っています。
その商品に対しての思い入れがある分、売り方にもこだわりを持っているようでした。
確かにいい商品ですので売れると思います。
私がアドバイスしたのは商品と一緒に、自分も売ること、自分をブランド化し、先生と呼ばれる形を作ることでした。
名刺の肩書きも今までない面白い「○○コンサルタント」「△△アドバイザー」を名乗って売ることで、「モノ+ブランド」の商品が出来、売りやすくなるはずです。
狭い分野の専門家として特化することで、小さなブランドが出来ます。
最後に私のアイディアを紹介します。
一つは「木楽な定規」と言って取っ手の付いた定規です。
これは札幌市の「札幌デザインコンペティション」に入選しました。
もう一つはお尻の滑らない「防滑座椅子クッション」で、これは実用新案を取りました。
写真を載せましたのでご興味があればご覧ください。



平等と公平
「平等」と「公平」、これについては色々な考えがあります。
最近課税に関しての新聞報道が多くなり考えてみました。
「平等」「公平」の考えは人によって違いますが、私なりに書きたいと思います。
「平等」とは人間の基本的な権利。
「人間として」、「日本人として」、「1人の会社の社員として」属する中で差別されることなく均等に扱われるものです。
「公平」とは、偏りがなく取り扱われることでしょうか
よく言われることですが、「一生懸命頑張った人間が報われ、そうでなかった人間はそれなりに処される。それが公平だ」と。
確かにそうだと思います。
会社でも、社員としてのスタートラインに立った時は平等です。
しかしその中で頑張った人とそうでない人の待遇は違ってくるはずです。
会社の「利益の8割は2割の社員にて作られる」と言われるのに、その2割の人間が他の8割の人間と同じ給料であれば、その人達は退職し他社に行くか独立してしまいます。
頑張った人にはそれなりの待遇をする、それが公平でしょう。
問題になるのは、その待遇の高低の度合いです。
頑張って利益を出した社員は給料を沢山もらって当り前。
頑張ったけど結果が出せなかった人は「次は頑張って給料たくさんとるぞ」と思います。
それほど頑張らなかった人はそれなりの給料で満足します。
しかしその差が大きくなると「それは取り過ぎだ」と不満も大きくなります。
人それぞれの立場で公平感は違ってきます。
その時、重要なのは社長の判断です。また、日頃の社長の行動も大切です。
なぜかというと社長が自分のことばかり考えている社長だと、その判断に対しても賛同されません。
常にトップに立つ者が常に社員の立場に立っていると知っている時初めて、社員に理解してもらえる公平性が生まれます。
トップが自分を律して経営をする姿が大切なのです。
改めて今の日本を見てみると、現在法人、個人に対しての課税が問題視されています。
減税・増税どちらにしても、関係するところから不平不満が出てきています。
平等の上に立った公平をどのように示すのか、日本の政治家の力量が問われています。
大変心配ですが見守るしかないのでしょうね。
女の6感
男性と女性。
今、若い男性は「草食系男子」が多いと言われています。
一方女性は「おじさん化」してきています。
なぜかと考えたら、学生時代に聞いたことを思い出しました。
「男は元々女っぽいもの。女は元々男っぽいもの。それが大昔から分かっていたから、男に対して『男らしくしろ!』と言われ、女性は『女らしくしなさい!』と言われて育ってきました。
それが男女平等の現在、『男らしく』とか『女らしく』と言われなくなったために、男性は女っぽく、女性は男っぽくなって来ています」というものです。
その為、現在はユニセックス化された社会になって来ているのでしょうか。
私の周りで元気なのは女性です。そしてオピニオンリーダーも女性が多くなりました。
女性の感性を生かした商品作りは重要なマーケッティング手法の一つです。
テレビ等のコメンテーターも女性が多くなりました。
男性と違った、女性の感性が重要視されているからでしょう。
その女性には「女の6感」があるそうです。
以前に雑誌に「サトウワカバ」さんが書いたものです。ご紹介します
1.女性の眼力は騙せない――視覚
2.女の耳は地獄耳 ――聴覚
3.女は裏読みの天才 ――嗅覚
4.女の舌はわがまま ――味覚
5.百聞は一触にしかず ――触覚
6.女の心を知らずして ――六感
これを読んで「へ― ―」と思いました。
男は理屈で考えがちですが、改めて女性の感性の凄さを認識しました。
以前読んだ「女がわからないでメシが食えるか」という本がありましたが、これも私に衝撃の本だったことを覚えています。
「いまさら何を言うか!」と怒られそうですが、商売を考える時、第一に女性を知ることが大切ですね。
笑い
「笑う」と言うと色々な笑いがあります。
「大笑い」「微笑み」「含み笑い」「ニヤッと笑う」「ヘラヘラ笑う」と色々の言い方があります。
同じ「笑い」でも、笑った本人の思いと受けた側の思いが違うことがあります。
本人は「微笑んだ」つもりが相手は「ニヤッと笑った」と取るかも知れません。
笑うことは一つの意思表示なのですが、誤解を受けることがあります。
ただ、何時も笑っている人にはイイ事が起こります。
本当です!
もう一つ笑いについて、中国の言葉をご紹介します。(発音は分かりません)
開口便笑
笑古笑今
凡事付諸一笑
その意味は
開口便笑:人に会ってはまず笑おう。
笑古笑今:昔を笑い、今を笑う。
凡事付諸一笑:何事も笑って対応することだ。
何事においてもクヨクヨせず、笑い飛ばしてしまう。
自分の失敗も「笑い話」として笑い飛ばすことが出来る人は、何よりも強い心の持ち主になります。
また、元気が無い時はまず、鏡に向かって自分に笑いかけると、本当の微笑みが生まれます。
そして、少し力が湧いて来ます。
よろしければ何かの時にお確かめください
齊藤佑樹投手
早稲田の斎藤佑樹投手が北海道日本ハムと仮契約しました。
ドラフト会議で交渉権を獲得してから、北海道では齊藤フィーバーに沸きました。
新聞では昨日の仮契約の報道と同時に、その経済効果が58億円に上る推計が掲載されていました。
この数字は北海道未来総研が算出したものです。
その前提は斎藤投手が一軍で先発ローテーション入りし、道内の試合に11試合登板が条件になっています。
11試合全部が満員になれば、観客数は46万2000人になり、グッズ購入や宿泊代などの波及効果があり、その総計が58億円だそうです。
斎藤投手の契約金は1億円ですから大変な投資効率の良さです。
日本ハムは今季パリーグ優勝は出来ませんでした。
少し元気が無いところですが、来季は斎藤投手で盛り上がることを期待されています。
2006年に初優勝した時、北海道は元気になりました。
経済効果もあり、優勝という事実が道民を元気付けました。
あの頃は新庄選手がいました。
新庄選手が日本ハムを引っ張って行ったと言ってもいいくらいです。
1人の効果の高さを知りました。
斎藤投手は新庄選手のようにチームを引っ張っていくほどの実績はありませんが、魅力ある投手です。
北海道の経済は以前低迷状態です。
その中で、新庄選手や斎藤投手は暗い中のロウソクのようなものです。
暗闇に灯の点ったロウソクが一本あれば、皆その光に引かれて行きます。
そして、そのような光を少しでも多く点すことが出れば世の中は明るくなります。
斎藤投手ほどではないにしても、私たちも自分達が出来る範囲で小さなろうそくを点していくが、大切ですね。
本気で夢や目標やを目指す。
今朝の新聞を見ていたら、手帳の高橋の新聞広告が掲載されていました。
サッカーの岡田前監督の写真も載っていましたので岡田さんの文章かもしれません。
読んだ方も多いと思いますが、とてもいい文章でしたので紹介します。
「夢や目標を本気で目指すと、全てが変わる。
運は誰にでも流れている。それをつかむか、つかまないかだ。
明日死ぬと思って今やれることをやり尽くす。
それがだめなら仕方がない。その開き直りが自信につながる
ここまでダッシュと思ったら、最後まで全力で走る。
1m手前で力を抜いたせいで負けることもある。
プレッシャーは重力のようなもの。重量がないと筋肉も骨もダメになる。
重力があるから自分が強くなる。
人にどう思われてもいい。日本中の人に批判されてもいい。
最後に家族が信じてくれればそれでいい。
スランプや失敗が続いても、調子が良かった過去を振り返ってはいけない。
今つまずいたいるのは、もっと高い場所に行こうとしているからだ。
本当にどうしようもない状況に陥ったら、こう思う。
ここが分かれ道だと。ここで投げ出すか、踏ん張れるかだと。
どん底に落ちてはじめて気づくこともある。
危ない危ないと言ってリスクを避けてばかりの社会は、人の生きる力を弱めている。
夢なんてなんだっていい。
どんなに小さなことだっていい。
その一歩で、また次の夢が見えてくる。
まずは一歩を踏み出すことだ。」
如何ですか?
チョットした啓蒙書より何倍も勇気が出てきませんか?
この文章も私の「銘肝録」の収めておきます。
職業観
昨日に続き、父の葬儀で感じたことを書きます。
父の葬儀を通して多くの人達のお世話になりました。
病院で死に、看護婦さんには父の身支度をしていただきました。
知人の葬儀社に連絡すると夜の8時過ぎにも関わらず、車で自宅まで運こび、お坊さんには10時頃枕経を上げていただきました。
11時には「死に化粧」と続きました。
納棺の時は納棺師が来て、父が来ていたスーツを着せて整えます。
この間家族はただ見ているだけです。
告別式後は火葬場です。
札幌に新しく出来ました火葬場です。
ここはPFIで運営されています。
その為かホテルのロビーのような豪華で明るい作りになっていました。
迎えてくれた係の人達はほとんどが女性で優しい応対です。
火葬場にこれほどの女性が働いているのかと思うほど多いのです。
応対も良くサービス業との印象です。
この度の葬儀を通して特に感じたのは、葬儀という不祝儀にこれだけの人達が職業として選び、働いているということ再認識しました。
他人の死にここまで携わり、それを通して社会貢献をしています。
人が嫌がることを一生懸命こなし、感謝されている仕事です。
人は自分の職業を選ぶ時、華やかで給料が高く、カッコいい仕事を選びます。
銀座のOLを選ぶか、火葬場の仕事を選ぶかと言えば、ほとんどの人は銀座のOLを選ぶでしょう。
火葬場の仕事を選んだ人は「仕方がなく」とか「給料が高いから」という理由だったのかもしれません。
それでも私は無条件で頭を下げ感謝します。
係の女性の手首にしっかり数珠が捲かれていたのは印象的でした。
色々考えることがありました
昨日父の法要が終わりました。
先月の29日に亡くなり今月2日に通夜、3日告別式そして繰上法要でした。
今日のブログは、亡くなった翌日の30日からブログを書くのを止めましたので5日ぶりです。
葬儀は社葬にて行われました。父の関係者、会社関係を中心にお参りをいただき、花輪だけで200台以上届きました。ありがたいことです。
この葬儀の中で色々ありました。
北海道のお通夜には子供親戚が葬儀場で一晩過ごします。
皆でお酒を飲みながら死んだ父の想い出話をしました。
夜遅くなた頃、父のお棺のところで父の顔を見ながら、私の息子と甥が酒を飲み「お祖父ちゃんと一緒に酒を飲みたかった」と話しかけ、「お祖父ちゃんを尊敬していた」と言います。
従兄同士で酒が飲め、息子にとって親戚と一晩遅くまで飲みながら話し合えたのはいい経験だったようです。
そして私も息子の本当の気持ちを聞くことが出来ました。
昔はワンマンで怒ってばかりいた私に「お母さんが可哀そう。普通だったらとっくに別れているはず。大事にしてほしい」と涙を流しながら言ってくれました。
優しい息子の一面を見ました。
昨晩妻にそのことを話したら大きな声で笑っていました。嬉しそうに。
また、愚痴一つ言わずに、私の父と母の介護をしてきている妻をいつも見ている末娘は「お母さんを尊敬している」と言いました。
それも妻に話しました。
いつも突っ張っている末娘の言葉に驚きながらも嬉しそうでした。
父の通夜の晩は飲み過ぎて、翌日は少し二日酔いでしたが、死んだ父が最後にくれた、私にとって忘れられない一夜でした。
反省について
ある本を読んでいましたら、反省することの大切さが書かれていました。
松下幸之助さんも寝る前に反省したそうでした。
寝る前がいいようです。
ワタミの渡邉美樹さんもそうだそうです。
以前に稲盛和夫さんと食事をしている時(数人です、2人ではありません)、「昨夜猛烈に反省したのです」と話されていたのを思い出しました。
稲盛さんの書かれた「六つの精進」の三項に「毎日の反省」と書かれています。
反省する時、気を付けなければならないことがあります。
反省とは自分を省みる(かえりみる)ことです。
決して自分を責めることではありません。
これは言葉で分かっていてもなかなか出来ません。私もそうですから。
1日を振り返ってみた時、自分の至らなさを思い出すと、恥ずかしさの為に大声を出したくなります。
そして、「なんて自分はダメな人間だ」と自分を責めてしまいがちになります。
人間は感情がありますからそれは仕方がありません。でも、それで終わってはいけません。
大切なのは、その後です。
「省みる」ことです。「今日失敗した原因は何だったのだろうか」「どうすればよかったのだろうか」と考えるのです。
失敗を次に生かせる。これがホントの反省です。
先ほどの「六つの精進」の最後の6項に「感性的な悩みをしない」とあります。
これは反省しても、自分を責めてはいけないということも示しています。
何事でも成功している人は寝る前に必ず反省しているそうです。
私も今日から寝る前に反省を始めます。
ただ、反省することが沢山ありすぎて、寝れなくなるのでは・・・
ご近所先生企画講座
先週の26日に「ご近所先生企画講座」を受け持つことが決まりました。
「ご近所先生企画講座」とは札幌市の外郭団体が主催する「さっぽろ市民カレッジ」の一つです。
今回私が担当する講座名は「身の丈起業のすすめ」です。
25日に募集締め切りして13名の受講希望者がいるそうです。
どのような人が受講するか分かりませんが、私が想定しているのはシニアの人、主婦の方々です。
子育てが終わり、それぞれ自分の責任を果たした人達が、新しい人生に再チャレンジする時、趣味に生きるのも、ボランティアもいいでしょうが、起業するというのも一つの道だと思っています。
それも今後の生活に支障をきたさない程度の投資で出来る、自分の身の丈に合った起業です。
講座は来年1月の下旬から週1回、5回で終了です。
講座では私が主にお話ししますが、私が教えるというより、受講者が自分の持っている能力や才能を再発見して、新しい一歩を踏み出す手伝いをする内容にしたいと考えています。
最終的には数人のグループに分け、簡単なビジネスプランも作成して発表します。
受講者が1人で慣れないビジネスプランを作るより、数人のグループになった方がより面白いアイディアも生まれます。
1月から講座が始まりますので、これからその準備も始めます。
新しい出会いが生まれるのを、今から楽しみにしています。
中国人について
昨日のブログでは「サポスポ起業家交流会」を紹介しました。
今日は先日そこで行われましたスピーチの内容を書いてみます。
スピーカーは同じ「さぽすぽ起業家交流会」メンバーの能味さんです。
能味さんは8年間木材関連の会社の駐在員として中国、主に大連に駐在していました。
その間、数多くの中国人との交流もあり、中国語も堪能な人です。
その能味さんのスピーチ内容を紹介します。
『中国人の一生』
1979年より始まった「1人っ子政策」が現在でも依然と存在していますが、その弊害も出てきています。
政策が出来た頃は、1人以上生むとその両親は多額な罰金を課せられたり、職場を追放されたりしました。
その子も大きくなり、大学に進学します。受験は競争が厳しく清華大学が最高峰です。(昔は北京大学が一番だったはず)
以前は学生時代から卒業後の就職が決まっているという高待遇でしたが、現在は自分で就職先を探さなければならなくなりました。
大学を出ても就職できなければ、苦労して大学に入れてくれた親への顔向けが出来ないので、地方出身者は故郷には帰らないそうです。それが「蟻族」と呼ばれている人達です。
上手く就職出来ると今度は会社の厳しい縦社会が待っています。
上司の補助的仕事を上手くこなさなければならず、連日の会議、接待の準備・接客に追われます。
上司に嫌われたら出世は望めません。
次は結婚です。
結婚する時は住むところが重要です。
以前は、最初は安いアパートに住んで、お金が貯まったらマンションを買ったそうですが、今はマンションが無ければ結婚しない人もいるそうです。
近年は都市部での不動産価格の高騰により、市内では住居が買えず郊外に住む人も増えました。
住宅ローンを組んで親と同居するのも多いようです。
定年後は年金生活です。
子供が親の面倒をみるのが一般的で、老後は子供に養ってもらうのが理想です。
しかし、今までの「一人っ子政策」の為、今後親を養うことが出来なくなるかもしれません。
『教育文化』
学校では道徳の時間と同じように、中国共産党の授業があります。
テレビでゴールデン時に放映されるドラマでは悪役は大体日本人。
それでいて、金八先生が放映され、日本アニメも人気があります。
音楽では香港、台湾のアーティストや日本の浜崎あゆみも人気があります。
『季節の行事』
「春節」:旧暦の正月。中国で一番大事な行事。
「元宵節」:旧暦の1月15日。日本の鏡開きの様なモノ。お湯に浮かべたあん入りの団子を食べます。
「国際労働節」:5月1日メーデー。1週間休みになります。
「端午節」:旧暦の5月5日。ちまきを食べます。日本のような「男の子の日」ではありません。
「中秋節」:旧暦の8月15日。日本のお月見と同じ。家族で食事をします。月餅を送り合います。
「国慶節」:10月1日。建国記念日。1週間休みがあります。
その他に「情人節」はバレンタインデー、「国際愚人節」はエイプリルフール、「生誕説」はクリスマスがあります。
中国人はメンツを重んじる国民性で、人前で叱責を受けるのを極端に嫌います。
人とのつながりを大切にするが、他人は信用しません。
家族、友人、顧客との会食は大切にします
「割り勘」という習慣はありません。
大筋のお話は以上ですが、能味さんはもっと興味深くお話しされました。
私の文章力が貧弱で、うまくお伝え出来なかったのが残念です。
ただ、能味さんの話で、隣国である中国人を知るいい機会になりました。
参考
能味さんの会社のホームページ:
http://www.lovewood.ecnet.jp
サポスポ起業家交流会
札幌に「サポスポ起業家交流会」という起業家の集まりがあります。
これは雇用能力開発機構北海道センターにありました創業サポートスポットの交流会が元になっています。
創業サポートスポットは起業家育成の為に作られたものですが、「事業仕訳」の結果廃止になりました。
廃止になっても、折角出来た起業家同士が気軽に情報に情報交換出来る場は無くしたくないという気持ちから、名称を「サポスポ起業家交流会」として今年4月に再スタートしました。
今年度1年は雇用能力開発機構のご協力も得れました。
現在「さぽすぽ起業家交流会」は30名以上の会員がいます。
月に1度のランチ会を実施し、また隔月で1時間ほどのスピーチもあります。
会費も無く、本当に手作りで、起業家同士の交流、そしてこれから起業を志す人の支援応援をしています。
特徴的な事は、ここには各業種の起業家が集まっていますので、これから起業しようと考えている人にとっては、同業種の先輩から直接情報を得ること場になっています。
会員同士の協力も強く、お互いに仕事応援も行われています。
経営者同士の勉強会や異業種交流会はありますが、「さぽすぽ起業家交流会」のように会費無料で、会員同士がお互いに協力し合う会は他にあまり知りません。
ただ、今心配なのは来年度4月以降、雇用能力開発機構の協力はなくなりますので、どのような運営をしていけばいいのかが問題です。
ただ、この会の意義を感じている人達は多くいますので、どのような形であっても存続されていくと思います。
勿論私も協力して行きます。
雇用問題ばかりでなく、雇用を生む為にも起業家が成功する環境作りこそ重要な施策だと思いますが・・・
先日、「サポスポ起業家交流会」であった中国問題に対するスピーチの内容が大変面白いかったので、明日はこのスピーチについて書きます。
参考
「サポスポ起業家交流会」ホームページ:
http://kigyouka.jimdo.com/
決めたら実行する!
最近年を少しとり、偏屈になったせいか、街に出て周りを見ると、決められたことを守らず、破っても平気で、、注意すると逆に怒られることが多いように思います。
赤信号で渡ってはいけないのに、平気で渡ってしまう。
自転車を置いてはいけないところに平気で置いてしまう。
歩きながら煙草を吸ってはいけないと言われているのに、平気で吸ってしまう。
それをしているのは大人がほとんど。
折角、学校で信号を守りましょうとか、自転車を決められたところに置きましょうと言われても、大人が守らないから「守らなくてもいいんだ」となってしまう。
怖いのは子供が赤信号を無視することです。
医学的に老人と子供は車が横から来るのを見た時に、遠近感がうまく判別できなく、飛び出してしまうことになりやすいそうです。
赤信号なのに母親が子供の手を引きながら渡ってしまう。
子供を交通事故に合わせる為に訓練をしているようなものです。
日本人の中に、決められた事は守るというモラルの欠如なのでしょう。
法律で罰せなければ守らないとは残念なことです。
会社でもそうです。
会社には理念や目的が必要と言われます。確かに大切です。
しかし、それを作って朝礼で唱えるだけでは身に付きものではありません。
行動に落とし込んで初めて自分のものになるのです。
特にトップがそれを実践してこそ社員が見習うのです。
経営理念の中に、「お客様を第一とします」というのをよく見ます。
言葉だけでなくそれを実践することは結構大変なことです。
「お客様第一」といいながら、「会社第一」になっているのではないでしょうか?
そのような決めごとと実際が違うと、社員の誰ひとり経営理念など守ろうとしません。
何かある度に経営理念に立ち戻って判断の基準にする習慣がなければ、無意味です。
無意味どころか、いろいろな決め事も同様な行動んになり、ご都合主義がはびこってしまいます。
だからこそ経営理念作りは社長の仕事なのです。
自分がそれをどのように実践していくか、それを実践していく覚悟を持って作らなければなりません。
決して社員に作らせるとか、コンサルタントに作ってもらうものではないのです。
そして、「決めたら実行する」ということを習慣化しましょう。
介護福祉
現在92歳の父と85歳の母と同居しています。
2人とも病気持ちで足も弱く、またともに認知症です。
父は肺気腫で酸素が必要なので在宅酸素を設置しています。
以前から夜中に救急車を呼ぶのがよくありました。
先日の日曜日にも、夜中の2時頃苦しみ出し、「救急車を呼べ」と叫びましたが、酸素を調整して何とか治まりました。
でもまた4時30分頃苦しみ出し、また「救急車を呼べ」と叫びます。
仕方がなく、救急車を呼び、私の妻が伴って札幌市立病院に行きました。
3時間後落ち着いたので、私が迎えに行き自宅に戻ってきました。
22日の月曜日は私も妻も寝不足フラフラでした。
その月曜日の昼ごろにまた苦しみ出しました。
会社にいた私に妻から電話があり、どうしたらいいか聞いてきました。
半日前に救急車を呼んだばかりでまた呼ぶわけにいかず、一般病院に入院することを考えました。
しかし、父の主治医は訪問専門の医者で病院を持っていません。
ですから急に入院させると言ってもそう簡単ではないのです。
受け入れ先を探すのが大変でした。
やっとの思いで近くの病院に入院させることが出来ました。
その病院からも「しばらくしたら退院してください」と言われています。
自分に介護を必要とする両親がいて、初めて自宅介護の大変さを感じています。
早い内に老人ホームや療養型病院に入れてしまえば楽なのですが、我儘な父のことを考えると、きっと孤独になり寂しい思いをすると考え在宅介護を選びました。
老人介護は現実の問題として目の前にあり、そして何年かごには自分がその対象になるという事実に、今向き合ったいる最中です。
理念と目標
企業にとって業績の浮沈はつきものです。その都度経営者を中心にしてそれを乗り超えます。
しかしいくら努力しても、なかなか業績が回復しない時があります。
その対応の一つに人件費削減も検討することもあります。
従業員を減らすのか、ワークシェアで従業員を減らさず1人当たりの賃金を下げるのか。
従業員を減らすと、景気回復した時すぐそれに対応出来ません。
景気回復した時、改めてを採用して訓練することになるので、タイミング良く生産を上げることが出来ません。
ワークシェアをすれば従業員を減らすことが無いので、景気が回復した時すぐにそれに対応できます。
ベターな方策と言えます。
しかし、ワークシェアを取った時一番の問題は生産性・効率の低下でしょう。
先日玉川大学の研究結果が新聞に掲載されていました。
最初に金銭報酬が与えられて課題に取り組んでいたところ、報酬が無くなった際には、本来楽しめる課題もやる気が失せてしまうという心理実験です。
給料が急激に減少しても同じようなことが言えるでしょう。
「成果報酬の減少はやる気も減少させる」ということです。
いくらやりがいのある仕事をしていても、給料が低下した時、本来の生産性・効率を維持することが難しいのです。
ワークシェアをしても生産性・効率を低下させないために必要なのは何でしょうか?
それは「会社に明確な理念があるかどうか」だと私は信じています。
そしてその理念が従業員全員で共有しているかです。
この会社が「何のために存在する」のか、「何を目指して頑張る」のか、それを普段から共有出来ている会社は強いのです。
一時的に給料が下がっても、それを乗り越える力は出てきます。
勿論、業績回復した時は、経営者は従業員の苦労に応える待遇改善をしなければなりません。
稲盛和夫さんは過去に、不景気で京セラの業績が低下した時とってきた方法がこれです。
不景気に力を蓄え、景気が回復した時は一気に拡大させる。
だから「不景気もまた良し」と言えるのでしょう。
現在、不景気だからこそ従業員が共有できる理念・目標の重要性を再確認しています。
対応力
今朝の日経新聞に三菱商事や丸紅が来春に20代の全社員に海外経験を義務付ける新制度を導入するそうです。
語学や実務研修などを名目にして半年間から2年間派遣されます。
先日、テレビを見ていたら、ある番組でキリンビールでは、自己申請し選ばれた人が、海外に行って現地調査と称して現地の生活を体験するのが放映されていました。
ただし条件として、現地にある自社の出先には近寄ってはならないのです。
自社に出入りすることで、派遣社員の自立する気持ちが萎えるのを防ぐためです。
このような大手企業の社員教育の方針は「内向き志向」の若手社員へ教育なのでしょう。
新聞等で若者が外国に行く割合が減少していると話題になっています。
冒険やチャレンジするより、現状の居心地良さを享受してしまう安定志向、癒し志向が日本の社会の中に広がっているのでしょう。
20年ほど前までは、自腹で海外に行く若者が多くいました。そこで何かを学んで帰ってきました。
勉強でなくてもいいのです。観光、見聞、遊びでいいのです。
そのように海外に行くのを「遊学」と呼んでいました。
現在は企業が経費をかけて「遊学」させているのです。
私も学生時代少しの期間アメリカに「遊学」しました。
アメリカ中を1人で回り、いろいろな人に会い、いろいろな経験をしました。
毎日何が起こるか分からない、ハプニングばかりでした。
その都度、何とか対処しながら、アメリカを網羅している「グレイハンドバス」でアメリカ中を回りました。
若い頃はあまり思わなかったのですが、今になって分かったのはアメリカで都度対応しているうちに「対応力」が作られたように思います。
そして、それが私の「思考」や「行動」の基になっています。
今、大手企業が若者を海外に出すのは、韓国のサムスンの影響だそうです。
サムスンが以前からこのような制度で若手社員を育て、それが現在の戦力になっているのです。
現在の「遊学」は五木寛之さんの小説「青年は荒野をめざす」の現代版ですね。
知識より体得を重視する
京セラフィロソフィ勉強会5項の「知識より体得を重視する」について書きます。
「『知っている』ということと『出来る』ということは全く別です。
たとえば、セラミックを焼成する時の収縮率の予測1つを取ってみても、この事実はよく分かります。
文献などで得た知識に基づいて、同じ条件で焼成を行ったつもりでも、実際に得られる結果はその都度違ってくるということが良くあります。
本の上での知識や理屈と実際に起こる現象とは違うのです。経験に裏打ちされた、つまり体得したことによってしか本物を得ることはできません。
このことは営業部門であれ、管理部門であれ全く同じで、こうしたベースがあってこそ、初めて知識や理論が生きてくるのです。」
稲盛さんは続けて言います。
「専門家を雇ったりする時がありますが、専門家の言うことも知識として言っている場合と、実体験を通じて行っている場合と、分けて聞かなければなりません。」
確かに私の経験でもあります。
経営コンサルタントと称する人が、本当は経営のことは学問、知識でしか知らず、実際に経営したことが無い人がどうして、社長の孤独や苦しみを知ることが出来るのかと思う時があります。
中小企業の社長は銀行から借り入れをすれば、連帯保証人にならなければなりません。
会社にもしもののことがあれば、会社ばかりでなく自分の全財産も差し押さえられるかもしれないのです。
そのような身体を張って経営をする社長に経営指導する人はそれなりの経験がなければ説得力がありません。
このような事を書くと支障があるかもしれませんが、私が疑問に思っている事があります。
インキュベーションマネージャーという仕事があります。
その人達は起業家を支援し指導するのが仕事です。
しかし、インキュベーションマネージャーの中には、官庁の職員が研修に行ってその資格を持ち、インキュベーション施設で働いている人もいます。
経営経験、ましてや起業経験が無い人が、講習を受け研修をしただけで、起業家にどんな指導が出来るのでしょうか!
建前論だけ話して指導するのでは意味がないどころか、時には害になります。
この稲盛さんの「知識より体得を重視する」を読んでこのことが特に気になりました。
バランスのとれた人間性を備える
今日は「京セラフィロソフィ」の中の「バランスの取れた人間性を備える」について書きます。
稲盛さんは言います。
「バランスの取れた人間性とは、何事に対しても常に「なぜ」という疑問を持ち、これを論理的に徹底して追求し、解明していく合理的な姿勢と、誰からも親しまれる円満な人間性を併せ持った人のことをいいます。
いくら分析力に優れた合理的な行動を貫くスマートさを備えていても、それだけでは、周りの人々の協力を得ることはできないでしょうし、逆に皆からいい人だと言われるだけでは、仕事を確実に進めて行くことはできません。
私達が素晴らしい仕事をしていくためには、科学者としての合理性と共に、「この人の為なら」と思わせる様な人徳を兼ね備えていなければなりません。」
稲盛さんが云うバランスのとれた人間というのは「両極端な考え」を持つということです。
それは決してどっちも付かずという中庸ではないのです。
優れた経営者とは、従業員に対して溢れふばかりの愛情を持ちながら、時としては冷徹な判断の出来るをする人です。
経営は「愛情」と「数字」だと私は思います。
従業員を愛する人間性を持ち、向う目標に対しては常に数字で追いかけて行く。
現在いくらの数字で、目標に対してはいくら足りない。その足りない数字をどのように埋めていくか。
それを詰める時は常に数字です。
時々見受けられることですが、
上司が中途チェック時、目標未達の部下に「目標までいくら足りない?」と聞くと部下は「○百万です」と答える。
上司が「出来るか?」と聞くと部下は「頑張ります」と答えます、
それに対して上司は「それじゃ頑張ってくれ」と言っておしまい。
そのような情景は良く見ませんか? バカバカしい情景です。
結果、月末になると部下は「申し訳ありません。達成できませんでした。」となります。
本来は部下が「○百万円足りない」と言った時、上司は目標達成出来るか確認し、達成できないとなると、いくらの数字なら達成できるか数字で答えさせなければなりません。
その数字も互いに詰めて行くのです。そうでなければ先の見えない経営になってしまします。
単に「頑張ります」「頑張れよ」では会社ごっこです。
明日は「知識より体得を重視する」について書きます。
それで、先日開いた京セラフィロソフィ勉強は一段落です。
私心のない判断を行う
今日は、16日に開催した「京セラフィロソフィ」勉強会で学んだ3項目「私心のない判断を行う」について書きます。
稲盛さんが書いています。
「何かを決めようとする時に、少しでも私心が入れば判断はくもり、その結果は間違った方向へ行ってしまいます。
人はとにかく自分の利益となる方に偏った考え方をしてしまいがちです。
みんなが互いに相手への思いやりを忘れ、「私」というものを真っ先に出していくと、周囲の協力も得られず、仕事がスムーズに進んで行きません。
また、そうした考え方は集団のモラルを低下させ、活動能力を鈍らせることにもなります。
私たちは日常の仕事に当たって、自分さえよければという利己心を押さえ、人間として正しいか、私心をさしはさんでいなないかと、常に自問自答しながら物事を判断していかなければなりません。
端的に言うと「自分というものを無にして物事を考える」、もっと極端に言えば、「自分を犠牲にして物事を考える」ということ、これば、私の言う「私心のない判断を行う」という意味です。」
稲盛さんはよく言う言葉があります。「動機善なりや私心なかりしか」
第二電電(現在のKDDI)など、多くの事業を始める時、常に繰り返し自問自答したそうです。
結果自分に都合のいい判断をせず、客観的に正しい判断をすると、それが物事とを成功せることになるのです。
一方人間は本能として自分を守ろうというものがあるのも事実です。
その本能を押さえて、自分というものを除いて考えた時に相手も喜び、自分も喜ぶという最良の解決法がスッと見つかる時があります。
稲盛さんはこの項目の最後、経営者向けに「トップに立つ者が私心に満たされ、間違った判断をすれば、会社の将来に大きな禍根を残すことになります。」と言っています。
経営者に必要な能力の一つに、自己管理能力があります。
経営者が起業の時頑張って、会社を大きくすることに努力した結果、会社が安定すると、それを自分の所有物のような気持ちになり、公私混同が始まり、業績が傾いてきた事例は大変多いです。
「私心のない判断をする」は経営者の重要な心構えです。
「本音でぶつかれ」
今日は「京セラフィロシフィ」の中の「本音でぶつかれ」について説明します。
責任を持って仕事をやり遂げて行くためには、仕事に関係している人々が、お互いに気付いた欠点や問題点を遠慮なく指摘あうことが必要です。
物事を「なあなあ」で済まさず、絶えず「何が正しいか」に基づいて本音で真剣に議論していかなければなりません。
欠点や問題に気付いていながら、嫌われるのを恐れるあまり、それらを指摘せずに和を保とうとするのは大きな間違いです。
時には口角泡を飛ばしてでも、勇気を持ってお互いの考えをぶつけ合っていくことが大切です。こうした中から、本当の意味でお互いの信頼関係も生まれ、より良い仕事ができるようになるのです。
「本音でぶつかれ」とはよく聞く話です。もう一方、「和を尊しとせよ!」とも言われます。
日本人はオブラートに包んだ言い方が良しとされます。
しかし、遠まわしに言うものだから逆に誤解されてしまいます。
現在のような外国人との接点が多い時代、直接的な言葉でなければ話が通じません。
稲盛さんが言いたいのは
真剣に仕事をし、会社の経営理念ある「全従業員の物心両面の幸福を追求する」を実行するには、言うべきことを言わなければならないのです。
個人的な感情で可哀そうだからとか、言いにくいからだとかで、するべき報告を会社にしなかった為に、重大な問題が発生することもあるのです。
稲盛さんはこの言葉の最後に
本音を丸出しで議論する中にもルールがあります。
まず、相手の欠点をあげつらったり、足を引っ張り合うような事は当然いけません。
例えそれが事実であっても、そのような言動はご法度です。
必ず「みんなの為に良かれ」ということに立脚した本音でなければならず、建設的でポジティブな議論でなければなりません。
明日は「私心のない判断を行う」を書きます
第8回「京セラフィロソフィ」勉強会
昨日は8回目の「京セラフィロソフィ」勉強会を開きました。
「土俵の真ん中で相撲を取る」「本音でぶつかれ」「私心のない判断を行う」「バランスの取れた人間性を備える」「知識より体得を重視する」の5項目を勉強しました。
今日より5日間に分けてご紹介して行きます。
今日は「土俵の真ん中で相撲を取る」についてです。
稲盛さんは次のように説明しています。
「これは常に土俵の真ん中を土俵際だと思って、一歩も引けないという気持ちで仕事に当たるということです。
納期というものを例にとると、お客様の納期に合わせて製品を完成させると考えるのではなく、納期の何日も前に完成日を設定し、これを土俵際と考えて、渾身の力を振り絞ってその期日を守ろうとすることです。そうすれば、万一予期しないトラブルが発生しても、、まだ土俵際までには余裕があるため、十分な対応が可能となり、お客さまに迷惑をおかけすることにはありません。
このように私たちは、常に安全弁を置きながら、確実に仕事を進めていく必要があります。」
もう一つ例として、中小零細企業の経営者の中には、売掛金の回収が遅れたり、手形の期日が迫ったりすると、常に金策に追われている人がいます。
金策に走り回って、何とか手形を落とすと、そこで満足して、何か大きな仕事をしたような気になっている。
手形は落ちて当然であり、経営者はなにもいいことをしたわけではないのです。
それなのにあたかも自分はいっぱしの事業家であるかのような顔をする。
この姿は映画「男はつらいよ」の中に出てくるタコ社長のようなものです。
稲盛さんは自分の学生時代のことも書いています。
大学生の時はガリ勉で、試験日の1週間から2週間前には、どこからも出題されてもいい様に勉強を終え、満点が取れるように備えたことも紹介しています。
私のように試験の直前になって徹夜勉強するのとは雲泥の違いです。
しかし、私も社会人になり、数多くの経験の中から、余裕をもって仕事をすることの重要性はよくわかりました。
「段取り8分」です。よく言われていました。
「準備をしっかりすれば8割方出来た様なモノ」という意味です。
準備の重要性を表した言葉です。
明日は「本音でぶつかれ」について説明します。


葬儀業界
昨夜、盛和塾札幌の例会がありました。
今回は「我が経営を語る」と題して、葬儀社「セリオむすめや」社長の三澤さんのお話しでした。
お話を聞くと、葬儀社といえどもサービス業として努力されています。
葬儀と言えば、縁起が悪いと捉えられがちですが、人は必ず死ぬことになっています。
「セリオむすめや」の社員はそれを後ろ向きに捉えるのでなく、積極的営業をしているそうです。
各地域の町内会との交流、ゲートボール大会やパークゴルフ、時には旅行会のお手伝いもするそうです。
また、「セリオむすめや」は色々なアイディアを出し、お客様サービスをしています。
その一つは「セリオメール」というものです。
知人に不幸があると、皆さんは喪主宛てにNTTの弔電を打つことが多いと思います。
NTTの弔電には色々な種類があります。
刺繍付きとか漆塗りとかあり、数千円と結構高いものになります。
「セリオむすめや」では葬儀をしていただいたお客様への弔電を自社HPからメールで受け、それを専用の台紙に付け、ご遺族に届けるものです。
台紙もいいモノを使いますが、全て無料です。
このようなサービスは「セリオむすめや」だけのサービスの様です。
将来このようなNTT弔電に代わる「メール弔電」を各葬儀社で用意し、それにアクセスして利用することが出来れば革新的なサービスになりそうです。
「セリオむすめや」では「私小説」と題する遺言書の様なモノを用意しています。
自分の「プロフィール」「子供・学生時代の思い出」「現在の思いや近況」等を書き、その他「介護の希望」や「葬儀の方法」等のこれからのことも書くようになっています。
勿論、財産のことも書きます。
これを一冊書くと自分を棚卸をするようです。
現在の日本の死亡率は人口当たり0.75%位で、札幌・全国でも同じような数字だそうです。
これから高齢化社会を迎え、ゆくゆくは1%になるでしょう。
私も近いうちにこの「私小説」で自分を棚卸してみたいと思っています。
参考:
「セリオむすめや」HP:
http://www.musumeya.co.jp/index.html
ゲーテの言葉
今日はゲーテの言葉をご紹介します。
この言葉は私の名刺の裏面に書かれていて、私への諌めの言葉でもあります。
◆人間一人でいるということは良くない。
仕事を一人でするというのは特に良くない。
むしろ彼が何かを成就しようとするならば
他人の協力と刺激が必要なのだ。
◆今日をダラダラと無為に過ごす。
明日も同じこと。
そして次の日はもっとグズグズする。
ためらいの一つ一つが、それぞれの遅れをもたらし
日々のことを後悔しつつ日が暮れていく。
おまえは本気でやっているのか?
一瞬考えてみるといい。
思い切りの良さには、才能と力と魔術が内在する。
ひたすら没頭するれば、心に火が点る。
始めるのだ!
そうすれば、その仕事は完成する。
如何でしょうか?何か力が漲ってきませんか?
事業を成功せさせる為の順番
今日は起業・事業を成功するために大切なことを書いてみたいと思います。
それは順番です。
まず起業する時、どのような事を事業として考えなければならないのか。次のことを順番に考えます。
①明確な理念
「何のために」「何をするのか」の目的を明確にさせることが第1です。
②この理念を実現する概念(コンセプト)の明確化
「どんな方法で」、「どんな規模で」、「どのような人と」、「どのように」実行するかを作り上げます。
事業が成功するにはまずこの「理念」と「概念(コンセプト)」の2つが、人々を奮い立たせ、満足させるような精神性や正当性を保持していなければなりません。
この為にだったら一生懸命頑張ることが出来るという「理念」「概念」は、例え苦しい時でもそれを支えるバックボーンになります。
③次に、この「理念」と「概念」を成功させるための「ストーリー」を想定します。
この「ストーリー」を考える時、大切なのは、成功の結果が「理念」「概念」から外さないことです。
注意することは、始める時、往々にして「入り易いところ」を選んでしまうことです。選らばないように!
安易に「入り易いところ」を選んでしまうと、目的と違ったもの、妥協の積み重ねになってしまします。
結果それが挫折につながりかねません。
起業・事業を進めて行く時、成功させるためにいくらこの順番を守っても結構大変です。
事業計画書を作り、そこにこの「理念」や「概念」を記載しても、動き始めるとこの事を忘れ、一般的・常識的な事に流され、行動しがちです。
「なるほど、この『理念』や『目的』を達成するためにはこれをやるのか」という象徴(シンボル)や仕組み作りが必要です。
例えば、会社の「クレド」を作り定期的にそれを従業員に徹底させるとか、成功した時の会社の姿や、社員の生活環境の変化を見える様に示すなど、全社員が共有できる象徴(シンボル)や仕組み作りです。
こう考えると事業を成功させるためには最初が大切です。
起業家・事業家の自分の思いを明確にし、具体的行動まで落とし込むことが出来るかどうかが重要になってきます。
西サッポロビール会
昨夜、月に1度開かれる西サッポロビール会がありました。
この会はサッポロビールを飲むのが目的の会で、参加しても気張らず大変気軽な会です。
サッポロビール側としては自社ビール販促の一環でしょうが、始まりは明治41年、北海道で生まれたビールを道内に広めるために発足されました。当時の発足人は、現在の北海道大学の教授たちでした。
現在も札幌を中心として各地で開かれています。
この会には私の父も参加していました。私はそれを引き継いだ形です。
昔はこの会に入ることがステータスシンボルで、地元の有力者が中心でした。
しかし他の会と同様に、年々会員は高齢化し、「元現役」の人達ばかりの会になっていました。
61歳の私が下から2番目に若いという超高齢の会でした。
最近若い人達を入れて活性化しようという機運が高まり、昔の様なハードルを設けず、広く参加者を集めましたところ、この1年の間に10人ほどの若い人達(30歳代40歳代)が入会しました。
そこで気付いたのですが、利害関係なく、ただビールを飲むだけが目的の会で、年の離れた人達の交流は双方にとって意味あるモノのように思います。
若い経営者にとって仕事から離れ、年配者と交流することで人生の知恵を学び、年配者は若い人から、今の新しい情報を聞くのにビールは口を滑らかにします。
メンバーの中には地元琴似神社の宮司さんもいます。
琴似神社の祭典にはこのビール会の人達がその主だった氏子として運営しています。
地元の年配者と若い人の交流が生まれることで、地元で働く人達の応援団が出てきそうです。
これから益々楽しみです。

「葉隠」1
最近「葉隠」を読んでいます。
現代訳されたののですが、20年ほど前に読んで、そのご本棚に仕舞いっ放しでした。
少しカビ生えた本ですが、再読しています。
「葉隠」という本はご存じの方も多いかもしれまし、以前にも紹介したかもしれませんが、改めて紹介します。
江戸時代元禄の頃、佐賀鍋島藩士山本神右衛門常朝という武士の言葉を、その弟子が書き残したものです。
この「葉隠」という本の名を聞いて、「武士道とは死ぬことと見つけたり。」という言葉を思い出す人もいるでしょう。(特に年配の方は)
「葉隠」に書かれているこの言葉を戦時中、軍部などが利用して若者を死地に駆り立てたことを知っている人にとっては、「葉隠」と聞いただけで嫌悪感を持つ人もいます。
でも真意は違います。
常朝は続けて行っています。
「死ぬというのは、死ぬか生きるかという2つに1つの選択の場に立たされたならば、ためらわず、死ぬ方(不利な方)を選べということ。そこに腹を据えて進むこと。それで失敗したら犬死だというのは都会風のもっともらしい理屈にすぎない。2つに1つの選択で、こちらにすれば必ず成功するなどというのは不可能なことだから、なんとか死なずに済む様な理屈を付けるだろう。その結果失敗すれば、命が惜しさに、ああした腰抜けだということになる。失敗して犬死するのはきちがいであって恥ではない。それが武士道というものだ。」
要するに、ものごとを判断する時、自分の利害や損得で決めてはならない。しかしその欲求は捨てにくい。自分が損しないような理屈をつけたがる。それを防ぐのにその逃げ道を塞ぐということです。
そして、たとえそれで死んでも私利私欲のための失敗でないから恥ではないのです。
「葉隠」に書かれている言葉は、人生訓として現代社会に通じる内容が豊富に書かれています。
これから時々、ご紹介して参ります。
ご都合主義
昨日のテレビでは、中国船衝突事件の映像をYoutubeに投稿したとして、海上保安官が逮捕されたとういう報道がトップでした。
この問題に関しては、いろいろな考えをお持ちの方もいるでしょうが、街頭インタビューでは大方が海上保安官に同情的な報道でした。
私もそうです。「よくぞ流してくれた」という気持です。
でも、よく考えてみると流してはいけないと言われた映像を流したこと自体は間違いでしょう。
彼と同じような行為をした海上保安官は他にいませんでした。したかったけれどそれを押さえたというところでしょうか。
私たちはどうしてもテレビや新聞報道を見て情報を得ると同時に、その判断まで依存してしまっている自分がいるのに気付きます。
もう一度自分の価値基準を明確にしなければ判断基準の軸がズレて来そうです。
9月に鈴木宗男元議員は色々な違反行為で最高裁で有罪が確定しました。
最高裁で有罪が確定すれば罪人です。本人がいくら検察の「国策捜査」だと言っても罪は罪です。
本来は無視されるものです。
それでも彼を支持する人は北海道の十勝地方を中心に数多くいます。
また政界にカムバックすると言っています。
同じ9月に島田紳助氏が女性マネージャ暴行事件で損害賠償1000万円有罪判決が東京地裁で出ました。
この報道は新聞では小さな記事しか取り上げられず、テレビではほとんど取り上げられなかったのは人気者だからでしょうか?
これらの事件の他にもホリエモン問題もあります。
それらの事件は昔だと「悪いことは悪い」とされました。
「良いことは良いこと」「悪いことは悪いこと」とする判断基準はしっかりしていました。
しかし現在は「それはそれ」「これはこれ」というご都合主義的な判断で動いています。
楽しければいい、面白ければいい、儲かればいい、の判断です。
大人が「良いことは良いこと」「悪いことは悪いこと」という行動を示さなければ、子供も価値判断が狂ってきます。
雨の日に平気で他人の傘をさして帰ったり、他人の自転車を勝手に乗り捨てたりします。
彼らは傘ぐらいとか自転車を借りただけという気持ちで、悪いとは思っていません。
大人と同じご都合主義です。
大人はもう一度日常生活から見直さなければならないと思います。
車が来ないからと言って赤信号で渡ると、それを見ている小さな子供が真似をし、もしかしたら赤信号で渡り、車にひかれてしまうこともあります。
もう一度価値基準、判断基準を見直し、大人としての真っ当な生き方がしたいものです。
TPP問題について考える
APEC閣僚会議が今日から始まります。
それに合わせ菅首相がAPECの場でTPP参加表明するかどうかが問題になっています。
TPP問題は連日テレビや新聞に取り上げられ皆さんの方が詳しいのかも知れません。
このTPPに加盟した場合、安い輸入農産品の為に日本の農業が壊滅的打撃を受けると、農業関係団体が猛反発し、反対運動を起こしています。
しかし新聞等を見ていると、TPP加入しなければ日本の経済が一層ダメージを受けうことは明確との論調です。
TPP参加に反対にしても賛成にしても、農業に対してはそれなりの対処が必要という点では一致しています。
ここで疑問があります。
農業対策と言えば補助金や所得補償など税金を使って保護することが意見の中心です。
しかしもっとその前に、日本の農産物が輸入品より高い上に、決して農家が裕福でない原因を考えることが必要です。
日本の工業製品の流通経路は20年ほどの間に大きく変わりました。
多くの分野で問屋制度が無くなり、製造者と消費者の距離が縮まりました。
流通システム変更で、途中の1次問屋2次問屋などの部門が淘汰され、結果として製品・商品が安くなりました。
今、農業でも流通システムの見直しも重要課題ではないかと考えます。
米を取り上げ、その流通を見ると、生産者から農協が米を集めて、同じ農協グループに持って行き検査をします。
その後「米穀価格形成センター」で価格を決めて、次は米穀卸業者を通して消費者に渡ります。
現在は農家から直接消費者や米穀卸業者に売る経路もありますが、まだ僅かです。
いろいろ理由はあるでしょうが、米が流通する時、中間マージンを取るところが多すぎます。
この改革に手を付けなければ本当の農協改革になならないように思います。
現在のように全ての産業に効率化が求められている時代に、農業だけは昔から特別でした。
その原因は政治から始まって農協問題もあります。ここでは詳しくは述べません。
ただ、以前聞いた話ですが、農家人口が減少しているのに農協職員は増えていると聞いた時、違和感を覚えました。
勿論、これだけで農業問題が解決するわけではないと思いますが、新聞テレビの論調で誰もこの流通問題を取り上げているところが無いのも不思議な気がします。
禁煙について考える
今朝の新聞に禁煙に関する記事が掲載されていました。
10月のタバコ値上げを機に禁煙を始めた人のデーターです。
1カ月後には5人に1人、20%が脱落していったそうです。
1カ月しか経っていないで調査ですから、3カ月後はもっと多くなっていることでしょう。
なぜそう言えるかと言うと、私は2回禁煙に挑戦した経験があるからです。
3日目、3週間目、3月目がなぜか転換点です。その転換点の時に、何か大きな誘惑が発生します。
過去私は1日3箱、60本くらい飲んでいた時もありましたが、現在は煙草は吸ってはいません。
10年以上前に2回目の禁煙で止めました。
今思えば1回目の禁煙が失敗した理由がわかります。
「止めよう」としたからです。
「止めよう」と意思の力で努力しても、夢の中まで出てくるタバコの誘惑につまづいた時、元に戻っていました。
2回目の禁煙が成功したのは「止めよう」としなかったからです。
禁煙成功のポイントを教えましょう。
①風邪をひいた時などを利用して、ニコチンの少ない煙草に変えます。
②ニコチンの少ない煙草に少し慣れてきたら、家にたばこを買い置きしないようにします。
③家にいて煙草が切れたら、「買いに行くの面倒だと」自分に言い聞かせて、少し我慢します。決して止めるのではないのです。
④3カ月経ったらタバコの本数を減らすのに、シガレットケースを買います。それにタバコを10本入れ「1日これですまそう」と思います。
⑤「1日10本ですまそう」と思っても、そう簡単に出来ません。10本以上吸ってもいいのです。
⑥吸いたい時、タバコを買わず、人から貰うようにします。ここがポイントです。タバコは決して止めるのでなないのです。ただ自分で買わず人から貰うようにします。
私はよく部下から貰っていました。
⑦いつもタバコを貰ってばかりでは悪いので、その分以上のタバコは買ってあげます。この頃になるともう1日4~5本くらい。家では吸わなくなっています。
⑧いくらタバコを買って上げているからと言って、もらいタバコは気が引けます。その内もっと本数は減ってゆきます。
その頃になると、たばこの魔力から解き放たれ、吸うのも吸わないのも自由という気持ちになり、心を操られていたタバコからの開放感を感じれるようになります。
こうなれば成功したようなもの。
後はいつ止めるかを決めるだけになります。
どうです?参考になりましたか?
よろしければ個別指導して上げますよ!?
100万円を手にする
今日のブログのテーマは「100万円を手にする」としました。
今月100万円が欲しいと思った時、くじに当たって手にすることも、仕事で稼ぐことも、もしかして金持ちの伯父さんからもらうこともあるかもしれません。
どの方法を取っても100万円を手にするという結果は同じです。
このブログを読まれている皆さんはほとんどの方が「仕事で稼ぐ100万円」が大切と思うのですが・・・。
でも最近の風潮はその100万円を手にする為の過程よりも、手にすることだけに興味が集中しているように思われます。
特に若い人達に多いように思われます。(年寄りの若者批判かな?)
仕事で黄金のような価値のあるものを手にするためには、その過程で血のにじむような努力を経て、何回も何回も試行錯誤を繰り返さなければなりません。
その努力を省いて目の前に黄金があってもそれは単なる金属の塊なのかもしれません。
勿論、価値ある黄金ですから捨てはしませんが、棚ボタは嬉しくありません。
あえてこの話をしたのは、起業した人達に間違えてほしくないと思ったからです。
起業の目的が当初は金儲けでもいいのです。その目的を達成するために汗水流す過程、行為が重要です。
その結果、お金ばかりでない何かを得て、次のステップの時は別の新たしい目的・目標を目指すようになるはずです。
そういう意味で起業時に他人から多額の投資を受けたり、補助金を受けたりすることは以前から疑問に思っています。
起業当初は本業で稼ぐお金こそ価値があるのです。
会社に力を付け、目標・目的が出来てから、他からのお金を利用して大きくなるべきです。
起業時は力を分散しないことです。本業に集中です。
「知っている」ことと「出来る」こと
現在は当り前のようにインターネットを使って情報を得ることが出来ます。
簡単に情報を得ることで、いかに便利になったか毎日実感しています。
それでもパソコンが使えない人もいます。
パソコンを使える人とそうでない人との情報格差はますます広がって行くのでしょう。
その使えない人の為に代わって、パソコンでモノの購入や申込等をしてくれる人の存在も、商売として成立するようになるのかもしれません。
ただ、最近気になるのは、簡単に情報が手に入ることで怠惰になってきている自分です。
怠惰な自分を見て後悔することも多くなりました。
以前は、一つの情報を得る為に、時間を掛け、お金を掛けました。人にも会いに行きました。
例えばある情報を持っている人に会いに行くという行為は、電車で行くとすれば、電車の中での吊広告に面白い情報が書かれていたり、途中久しぶりに友人にあったとか、情報をもらう為に初めて会った人と気が合い長い親交が得られたなどプラスアルファがあります。
一つの情報を得る為に掛けた手間暇によって、目的以外のモノを得ることが出来ます。
行動するということは、目的以外の大切なことが得られることなのです。
それによって別の意味で豊かになっていきます。
以前ある教育者から聞かされた話があります。
今の子供たちは、周りに情報が溢れているから、色々な事を知っています。
例えば「お料理は出来ますか?」と子供たちに聞くと、した経験は無くても「出来ると思います。」と答えます。
「お裁縫でハサミはうまく使えますか?」と聞くと、した経験は無くてもまた「出来ると思います。」と答えます。
この話を聞いた時、実際にした経験が無いのにもかかわらず、知識としてしているだけで、出来ると思っていることへの怖さを感じました。
現在の情報社会では大人も同じような状況ではないでしょうか。
情報をインターネットで知っただけで自分は何でも知っていると思い、何でも出来る様な気になっていないでしょうか。
「体得」とは文字通り「体を使って得る」ということです。
今私達が必要なのは外に出ることです。
自宅で仕事をしたり、内勤の仕事が多い人は意識して外に出ましょう。
そしてリアル体験をしましょう。
それにより知識が深まり、人としても厚みが増します。
今日のブログは自戒の意味で書きました。
誤りを正すのに、はばかることなかれ
仕事をする時、常に決断が求められます。
素早く決断し実行する。その結果決断が間違えていればまた方向転換する。
経営はその繰返しです。
ダメなのは間違えているかもしれないと思っても、変えようとしないことです。
「朝令暮改」はいけないとか理由を言いながら、本当はカッコ悪いとか、面倒だとかの気持ちが変える決断を阻害しています。
昔は「朝令暮改」はダメだと言われましたが、経済環境の変化が激しい現在はしてもいいのです。
以前にも書きましたが、東京でホテルを開業した時、宿泊稼働率は大変悪く、20%台で低迷していました。
そこでそれまでのやり方を止めました。それからは新しいことへの挑戦の連続でした。
他のホテルがしていないことをするのは勇気が必要でした。
そのような時、若い頃父に言われた「間違いを正すに、はばかることなかれ」ということばが常に頭にありました。
間違えていると思えば、方針を大きく変えることが重要です。
最近もありました。
今運営しているレンタルオフィスも計画当初は必要以上にお金をかけたように思います。
でも、オープン後は思ったほどの入居がありませんでした。
その時すぐに運営方法を変え、コストのかからない仕組みに変えました。
規模小さいので苦労なく出来ました。
でも今思うと、「そのままも何とかなるだろうからと変えず続けていよう」と思っていたら、とっくに運転資金が無くなり、閉鎖していたでしょう。
私は自分の夢を実現しようとすると、どうしても「構え」から入って行って行く傾向にあります。
一般的に、男性はその傾向の人が多いのではないでしょうか。
でも実態と違っていればすぐ変える勇気は常に持っていましょう。
時としてカッコ悪く見えても、わかる人は理解してくれます。
「職のミスマッチ」って何 !
先日の新聞に「職のミスマッチ拡大」と大きな見出しで記事が掲載されていました。
「職のミスマッチ」とは企業側の仕事と、探す人の希望がかみ合わない状況のことです。
新聞によると現在企業の収益改善で採用意欲が持ち直しているにもかかわらず、完全失業率が5%台で高止まりしています。
北海道苫小牧にあるトヨタ自動車北海道では期間従業員の募集を始めたそうです。
それも北海道外から100名。
北海道で募集しても集まらないからです。
失業率5.5%の北海道の人はなぜ応募しないのでしょうか。
確かに期間従業員は正社員とは違って将来の不安はあります。
しかし、仕事がなければ家族を養うために頑張るべきではないでしょうか。
例えどこかの正社員になっても、会社によってはいつ倒産するかわからない不安定さは同じです。
政府はミスマッチ対策とし「トライアル雇用奨励金」や「ジョブサポーター」も増やしています。
雇用に関しては以前にもブログで書きましたが、どう考えても働く側に甘えがあると思います。
単に能力がなくて高望しているのに、税金を使って甘やかしているにすぎません。
科学ジャーナリストの喰代栄一氏の本に同感できることが書かれていました。
「この社会では、自分の好きなことを仕事にしている人達だけによって支えられているのではない。
辛い仕事や、社会の必要に応じて、それを仕事にしている人達が沢山いることを忘れてはいけません。
その人達の努力によって社会が支えられ自分が支えられていることを忘れてはいけません。
その人達の努力によって社会が支えられ、自分が支えられていることを理解せず、ただ自分の好きな事をしたいというレベルでは、単なる駄々っ子にしかすぎません。」
日本は戦後豊かさを求めて私達の先輩は努力し、頑張ってきたはずです。
結果それがモノの豊かさがあふれてくるとともに、日本人はひ弱になり、甘くなってきました。
そしてそれを正そうとすると、時として非難されます。
1人の人間として自立でき、「人から何かをしてもらう」人間ではなく、「人に何かをして上げれる」たくましい人間が多く生まれること、それが日本にとって今大切なことです。
今日は非難めいたことを書いてしまったと少し反省しながら終わります。
「学ぶ」とは
今朝の新聞に教員免許更新制度についての記事が記載されていました。
民主党が廃止を含めて見直しをしていた教員免許更新制度が存続されそうです。
先生は教員免許更新の為には講習を30時間以上受けないと失職してしまいます。
廃止を見込んで早々と講座を中止した大学が多く、講習先探しで先生達が大変という記事です。
私はここでこの制度について意見を述べるつもりはありません。
私が気になったのはその講習を受けた先生達の反応です。
文部科学省によると教員免許更新制について「児童生徒への質の高い教育の提供」への効果が「全くない」「あまりない」と考える先生が54.4%ありました。
質の高い教育の提供への効果が「とてもある」「ややある」と答えた先生は24.1%でした。
私はその講習の内容はわかりません。機会があれば知りたいもと思います。
私はこの記事を読んで思ったのは
先生は子供達に教える人。でも、講習を受ける時は生徒になるということです。
いつも「教える立場」の人が「教えられる立場」になることはとても大切なことと考えます。
学校でいつも子供たちに言っていることを「教えられる立場」になった時出来ているのか。
出来ていなかったら何が原因なのか。
そういう意味でこの制度は意味があると思います。
講習を受けた先生の9割が内容について「良かった」と評価しているのも理解出来ます。
ただ、記事の中に「最新の知識技能の習得への効果が『有る』『無し』が40%と分かれた」と書かれているのが少し疑問があります。
どのような内容の講習であれ「無し」は無いはずです。
どのような講習でも全て身になります。
内容が良くなければそれなりに反面教師として受け止め、自分の授業に生かせばいいのです。
先生は子供に教育する人です。授業の受け方も身をもって体験し、それを自分の授業に生かせば今までより以上の授業が出来るのではないかと考えます。
「自分の立つ位置をずらしてみる」ことはどのような立場の人でも必要なことです。
違った考えが生まれます。
人はそれがなかなか出来ません。でも機会があれば積極的に受け入れればいいチャンスなのです。
平成の坂本龍馬
昨日「目指せ!平成の坂本龍馬」というテーマの話を聞いてきました。
西川りゅうじんさんがコーディネーターとなり、格闘家のニコラス・ペタセ氏、全国龍馬社中会長の橋本邦健氏との談義です。
なぜ、北海道で坂本龍馬のテーマの話がされるかと言うと、ご存じの方も多いかもしれませんが、龍馬は北海道開拓を真剣に考え、おりょうさんにも「エゾ語」を勉強するよう勧めたそうです。
また、龍馬が死んで途絶えそうになった坂本家を継承したのが画家の坂本直行さん。
坂本直行さんは北海道に住んで絵を描き、その絵は先日ブログで紹介しました「六花亭」の包装紙に描かれています。
「六花亭」は十勝に坂本直行記念館も造りました。
坂本直行さんは北海道民にとってはなじみ深い画家です。
この談義の中で西川りゅうじんさんが話されたこと、興味深いことをご紹介します。
日本は「大変」な時代になっています。
この「大変」という字は「大きく変わる」と書けます。
変わるという字を英語で言うと「CHANGE」(チェンジ)と書きます。
この「CHANGE」のGのTを取ると「CHANCE」(チャンス)になります。(本当はTではないかも)
このGから取ったTは「TABOO」(タブー)で束縛と言う意味です。
すなわち大変な時は「CHANGE」の時。
その時、色々な「TABOO」を取り除くことで、「CHANCE」が生まれると言っています。
なるほどと感心しました。
近年日本では起業家の数は減少しています。
談義では「起業家よ立ち上がれ!」という思いで話は進められました。
龍馬が言った「世に生を受けるは 事を成すにある」も話に出てきました。
人に感動を与える仕事は国を元気にするのです。
孤高の人
「孤高の人」という言葉を見て、新田次郎と結びつきますか?「週刊ヤングジャンプ」を思い浮かべますか?
それとも全然わかりませんか?
この小説は加藤文太郎という登山家を主人公にした新田次郎さんの山岳小説です。
私は学生時代に小説として読みましたが、今の若い人は漫画で読んだのかもしれません。
私はこの小説を読んで山に憧れ、山登りを始めました。
それもこの主人公を真似て1人で。ただし、低い安全な山ばかりです。
加藤文太郎は常に1人で山を登ることを信条として、毎日の訓練の為、会社に行く時も石を入れたリュックサックを背負って歩いて通いました。
彼は当時の登山会からは異端児扱いされていましたが優れた登山家でした。
孤独を愛し、常に単独行で山を登っていた彼は、最後に知人と一緒に雪山に登りました。
そして、初めてパーティを組んだその登山で遭難し、亡くなりました。
「孤高」とは辞書で調べると、「俗世間から離れて、ひとり自分の志を守ること。また、そのさま」とあります。
最近私の父を見ているとフッとこの言葉が浮かびました。
父は20代から事業を始め、それなりのグループ会社を作り上げて来ました。
子として見ていると、父は常に仕事ばかりで、子供達を遊びに連れて行ってくれたことは少なかったように思います。
仕事の上では、社長としての判断が求められる時は、いつも自分の信条を押し通してきました。
その関係かもしれませんが、父の周りには仕事関係の人がほとんどで、親友という人もいなかったと思います。
社長は孤独であり、時として情に負けない、厳しい決断をしなければならないこともあったはずです。
そんなことの積み重ねで、自分とそれ以外に人達との間に距離が生まれていったように思われます。
現在92歳になります。半年前まで会社に来てました。
勿論現役ではありません。
最近は会社に行くことが生甲斐でした。
会社のスタッフは、誠にありがたいことに、「会社に出てくることが元気の基」と言ってサポートしてくれてました。
その父も最近は一気に元気を無くして、寝ていることが多くなりました。
そんな父を見ていると「孤高の人」という言葉が浮かびました。
俗世間から離れてはいませんでしたが、自分の生き方を貫いた生き方に共感しています。
最近元気がないのが寂しいです。
「六花亭」という会社
今朝も神社に行ってきました。
毎月1日朝出社前に北海道神宮と琴似神社のハシゴです。
1日以外でもフッとその気になれば神社に行きます。
朝の参拝者と昼間の参拝者は若干違うようです。
朝の参拝者は会社の団体が多く、毎月1日参拝を行事としてお参りに来る人達。
昼間の人達はお願い事やお礼に来る人たちでしょうか。
私はそんな風に見ています。
お昼にお参りに行くと境内にある六花亭の茶店に寄ります。
ここは無料で参拝者向けにほうじ茶と「判官さま」という蕎麦饅頭を焼いた出してくれます。美味いです。
無料だからではなく、ほうじ茶は香ばしく、焼いた蕎麦饅頭も美味いのです。
時には行列が出来るほど。
六花亭が無料で配る対象者は毎日何百人にもなるでしょう。
宣伝費と言えば言えますが、それにしても饅頭やお茶代、それに店の維持費や人件費と考えると大変な出費です。
そして一度始めてしまえば、そう簡単に止めれないのに始めてしまっている。
会社の明確な方針がなければ出来ないことです。
六花亭は昔「白いチョコレート」で大フィーバーした会社です。当時発売したのは帯広千秋庵の子会社の「ふきのとう」という会社名でした。
その「白いチョコレート」が大フィーバーした為、札幌千秋庵とトラブルが発生しました。
止む得ず千秋庵という名前を捨てて六花亭としました。
私はその当時銀行の帯広支店に勤務しており、毎月六花亭の小田社長宅に伺っていました。
毎回社長夫人からお茶をたてていただき、美味しいお菓子をご馳走になりました。
その頃ちょうど社名変更の時で、その事情について詳しく話を聞きました。大変だったみたいです。
そのことは今日は触れません。
その社名が変更になった頃からでしょうか、六花亭では文化活動を積極的に進め、店内で音楽の演奏会や落語会を開き、各地に美術館も作りました。
北海道神宮の茶店もその一つかもしれません。
今の六花亭の繁盛ぶりを見ると、帯広千秋庵から名前を変えたことが大きな飛躍のきっかけだったのかもしれません。
接客の心得
私は以前ホテルの支配人等を経験してきました。
如何にお客さまに喜んでいただくかを考えるのが支配人の仕事です。
大切なのはお客様の気持を知ることです。
その為に「目配り」「気配り」「心配り」を持つことです。
「目配り」とは自分の周りにも目を向けられる余裕。
「気配り」とは相手がしてほしいと思うことを言われる前にする事。
「心配り」とは相手を喜ばそうとする意思と行動。⇒心で相手の心を見る。
この中で一番大切なのは、「心配り」です。
昔聞いた話ですが、東京のある大きなホテルのことです。
外国人のお客様が多いそのホテルである時、ホテルスタッフの中で誰が一番お客様に人気があるかコンテストをしたそうです。
ホテルの総支配人たちは英語がうまく、ホテル経験が長いAさんが一番人気だろうと予想しました。
しかし結果は圧倒的にBさんでした。
総支配人たちは驚きました。なぜかと言えばBさんは英語もあまり上手くない上、ホテル経験も短いのです。
お客様に聞くと、そのBさんが人気があったのは、上手くない英語を一生懸命使って、お客さまに喜んでいただける為に声を掛け、常にお客の為のことを考えているのを感じたからだそうです。
一方Aさんも評価されていますが、Bさんと比べれば英語がうまい分余裕があり、一生懸命さが伝わらなかったのです。
お客様はBさんには「心配り」を感じたのでしょう。
大きなホテルにはコンシェルジュがいます。
ホテル西洋銀座のコンシェルジュの多桃子(おおのももこ)さんが、ある雑誌に書いていました。
「コンシェルジュはお客様の心に寄り添い、その方の気持ちになって考える姿勢が第一歩で全てです」と。
私は、この文章を読むまでは、「心配り」が一番大切かと思っていましたが、「心を寄り添う」という思い方がより素晴らしいサービスが出来ると思い直しました。
この「心を寄り添う」とは、自分を捨ててお客様の心と自分の心を同化させた思いのことでしょうか。
このようなサービスが出来れば素晴らしい仕事が出来るはずです。
忘れずにいたい私の大事な言葉の一つです。
雪国北海道
昨日タイヤ交換に行ってきました。
先日の初雪が思ったより積り、急いで交換に行きました。
混んでいるかと思ったのですが、タイヤ交換のお客は私だけ。
暫く雪の予想がないから、皆さんはゆっくりしているようです。
毎年雪道は気を付けます。車を運転する時も歩く時も。
私が高校生の頃、北海道が内地(昔北海道の人は本州のことをそう呼ぶ)と比べ、雪が多いから移動にも時間がかかる。
だから北海道経済は遅れていると、大人達が言っていたこと覚えています。
でも、それはちょっとおかしい。「スエーデンやノールウェーという国は北海道より北にあっても国として栄えているのに」と不思議に思いました。
その頃大人達は雪国ということでハンディーを感じている振りをしていたのでしょうか。
そのような自信のないハンディーを振り払ったのは、2004年夏の甲子園で駒大苫小牧高校の優勝でした。
それまで初戦敗退が続いた時、何時も言われたのが「雪国で練習が出来ないせいでしょう」という言葉でした。
それが優勝したのですから、そんなこ言葉は一気になくなりました。
この優勝は北海道民に自信を与えたと思います。
その後日本ハムも日本一になり、雪国によるハンディーという言葉は無くなりました。
今はもう聞かれません。
逆にその雪を使って何か産業に生かそうという試みが生まれています。
自信を取り戻すにはチョットした切っ掛けで出来るのですね。
ブタのしっぽ
今朝フト思いだした言葉です。
「ブタのしっぽ」
知っている方も多いと思いますが、「無駄な仕事をする」という意味の例えです。
「ブタのしっぽ」は絶えず、絶えず動き回っているが何の役にも立っていません。
以前私はこの言葉を頭に置いていたのです。「ブタのしっぽになるな!」
すっかり忘れていました。
今朝思い出したのは、最近肝心な仕事をしないで、余計なことばかりしている為でしょう。
今日からまた「ブタのしっぽ」にならないように仕事をします。
今日のブログは私の決意表明です。
チャレンジ精神とは
今日は私の銘肝録に書き留めている言葉として、ホンダ創業者の本田宗一郎氏が言った言葉を紹介します。
チャレンジ精神についてです。
「無我夢中でやるのがチャレンジ精神だと思ったら大間違いだ。失敗して痛い目にあって、苦しさも、悲しさも、大変さも、怖さも分かった。もう、自分を奮い立たせないと情熱は出てこない。それでもやる。それが本当のチャレンジだと思う」
「何かに挑戦しようと思いやってみましたが失敗しました。」はチャレンジ精神ではなく、失敗して、もう駄目だと思う時、それでも挑戦することがチャレンジ精神だと言うのです。
この言葉を知るまで私は誤解していました。
新しいことに挑戦し失敗したら、また別な事を挑戦する。次々新しいことに挑戦する。それをチャレンジ精神があると思っていました。
そうではないのです。
挑戦して挫折しそうになっても、挑戦し続ける姿こそチャレンジ精神というのです。
皆さんも「一生懸命やっているけれど、結果が出ない。もうダメかもしれない。」と思った時があると思います。
それを乗り越えてきたはずです。
昔に聞いた話ですが、人間は人生の中で「倒産」「大病」「刑務所に入る」の経験があると成功するというのです。ただし「刑務所に入る」時の罪は破廉恥犯ではありません。
これらも人生において大きな挫折の一つです。
それを乗り越えようとするところにチャレンジ精神があるというのです。
私の父を見てもわかります。その人生の中で仕事を拡大している時、いつもアップダウンの繰り返しでした。
辛い時は「人が出来て、自分が出来ないはずはない!」と言って自分を励ましていました。
そしてそれには及びませんが、私も今まで沢山の挫折を経験してきました。
これも皆さんもあることでしょう。
振り返って見ると、その挫折という節目がったからこそ今の自分があると思っています。
モノ作り日本
私は小学校か中学校の時授業で「資源の少ない日本は原材料を輸入し、それを加工して製品にし、輸出して成り立っています。」と教えられました。
皆さんもご存じの様に、近年日本の製造会社数が減少しています。外国から購入した方が安く、日本で作っても価格的に太刀打ちが出来ず、倒産・廃業してい行くからです。
円高は物価が安くなり、消費者にとっては恩恵になりますが、会社側にとっては死活問題です。
先日の報道では大手製造会社は円が1ドル70円になっても耐えれる体制作りを進めていると書かれていました。
過去の円高では、会社側のコスト削減や生産効率を高めることで克服してきましたが、これからはそのような手段だけでは解決できず、海外に移転して行く会社の数が急激に増加することが予想されます。
今朝の新聞でアメリカの経営者が日本経済について述べていました。
そこでは「日本は最先端的なモノ作りを国内にとどめなければならない」と忠告しています。
30年ほど前、ソニーが韓国でテレビ製造に力を入れ、技術移転をした結果、サムスンという会社が生まれました。同様のことが中国でも起きています。
結果現在それが日本に大きな影響を与えています。
現在私は起業する人達を支援・応援していますが、個人レベルの起業ではITやサービス業の業種がほとんどです。製造業を志す人は少ないです。
政府は、これから日本はITや観光に力を入れましょうと言っていますが、それが従来の製造業が生んだ富にに匹敵する富を生むとは思いません。
今必要なのは、現在必死に日本で頑張っている製造業、特に海外に移転できない中小企業を支援して育てていかなければなりません。このままでは益々倒産・廃業が増えます。
イタリアでは中小の会社が海外に売る仕組みを政府が中心になって作っている言われています。
現にイタリアの家具製造会社は大手会社は少なく、中小の会社が製造部門別に存在し、数社が共同生産をすることで一つの製品を作り上げています。
日本も中小の会社の製品輸出に力を入れるともに、国内では消費者も地産地消の意識を高めて日本の産業を育てていかなければなりません。
円高で安いからいいだけでは、将来自分達の生活を狭めることになりかねません。
また起業について考える
新聞に最近日本では起業を志す人が減っていると出ていました。
一方アメリカでは新たな起業ブームが起きているとのこと。
国民性が違うからでしょうか。
日本とアメリカの起業に対する考えの違いは、何百年間の歴史が生んだ国民性によるものと私は思います。
アメリカは新天地を求めて来た人たちの子孫です。
国や何かから束縛されるのを嫌う独立志向が強いのかもしれません。
一方、日本は江戸時代から士農工商の身分制度があり、自分の立場や地位を守り続けることが求められ、特に商人は丁稚奉公から始まり終身奉公することが求められていました。
独立するといっても「暖簾分け」という程度だったのでしょう。
その風潮・考えが現在まで続き、日本人の起業に対する考え方になっていると思われます。
その為日本人にとって、急に「独立せよ!起業せよ!」と言われてもそう簡単に切り替えができないのです。
個人の頭の切り替えばかりでなく、世間もです。
まだ、会社勤めが良いと選択されます。
このように起業に対する国民性が違うと言っても、やはり起業は大切です。
「起業と技術革新こそが繁栄をもたらす」とアメリカの大学教授が言うように、日本で起業を志す人が減少していくと日本の将来が不安になります。
前にもブログに書きましたが、起業を志す人を増やには、起業で成功した人をクローズアップするべきです。
身近に起業に成功した人がいれば憧れます。
その為には成功者を増やすために皆で支援・応援する体制が必要です。
起業を支援するのではなく、起業した事業が「成功する」ように支援することです。
私も微力ながら努力しているつもりですが、周りにいる同じ考えの人達との協力は不可欠です。
多少なりとも利害関係を意識している人もいますが、それを乗り越えて起業家を支援・応援することが今重要です。
日本で広範囲にそれを進めている民間の団体はインターネットサイトの「起業SNS」や「NICe]ではないでしょうか。
これから益々その役目は重要になってきます。
お辞儀をする
先週末、整形外科のリハビリ―で治療を受けていた時のことです。
70歳くらいの男性が治療が終わり室を出ていく時、出口のところで中に向かって深々とお辞儀をしました。
誰にというのではなく自然としたのでしょうが、私はハッとして感動を覚えました。
私なんかしようと思っても照れくさくて出来ないことを、自然とするカッコ良さを感じます。
もう一つ、ずいぶん前んになりんすが、自宅の2階から何気なく外を見ている時でした。
道路を挟んだ向かいの家で、灯油の給油を終えた作業員が玄関の郵便ポストに給油済み書類らしきものを入れた後、道路に出たところで家の方に向いて深々とお辞儀をしました。
この時もエッと驚き、そして感動しました。
この瞬間に「この会社はいい」と思いました。
雪のないところに住んでいる人はわからないかと思いますが、北海道のほとんどの家には屋外に灯油タンクが設置されており、定期的に給油する契約になっているところが多いです。
留守中でも給油していくので、先の作業員は留守の家に向かってお辞儀をしたのでしょう。
彼は会社の方針でそのようにしているのかもしれません。
パフォーマンスと言う人もいるかもしれませんが、「ありがとうございました」との気持ちを持ってのお辞儀は
素晴らしいです。
会社がいくら指導してもしない人もいますが、彼のお辞儀を見ていると「ありがとうございました」の声が聞こえそうなお辞儀でした。
いつどこで誰が見ているか分かりません。
1人の作業員の行動一つでその会社の評価が変わるだろうこと実感しました。
私の家の灯油も彼の会社にしようと思ったのですが、私のところは親戚の燃料屋さんに頼んでいるので残念ながら出来ませんでした。
自らを追い込む
今日は「自らを追い込む」について書きます。
京セラフィロソフィの30項目に掲載されています。
稲盛さんは次のように話しています。
「困難な状況に遭遇しても、決してそこから逃げてはいけません。追い込まれ、もがき苦しんでいる中で、『何としても』という切迫感があると、普段見過ごしていた現象にもハッと気付き、解決の糸口が見つけられるものです。
火事場の馬鹿力いう言葉があるように、切羽詰まった状況の中で、真摯な態度で物事にぶつかっていくことによって、人は普段では考えられないような力を発揮することが出来ます。
人間はえてして易きに流れてしまいがちですが、常にこれ以上後に引けないという精神状態に自らを追い込んでいくことによって、自分でも驚くような成果を生み出すことが出来るのです。」
この「困難から逃げてはいけない」とは、経営者として大切な心構えです。
社長の「地位」と「待遇」がいいのは、会社の全ての責任を負うことへの報酬です。
最後まで戦うのは社長です。
昨日㈱ビジネスバンクの浜口社長が来社されました。
その時の話を紹介します。
今の経営者はすぐあきらめてしまう人が多い。
どんなうまくいっている様に見えるいる会社でも浮沈の時はあります。
それがわかっていない。
浜口さんの会社もそうですし、私の会社もそうです。
そこを頑張ったから今があるのです。
底を這いずりながら頑張り、そこから復活すると人間が変わります。より強い経営者になれます。
今、起業家に必要なのはここです。
壁にぶつかった時こそチャンスと思うのです。
そこを乗り越えれば起業が成功するのです。
そして私が思うに、目先が利き、賢そうな人は、物事がうまくいかず困難なことにぶつかると、そこを避けてすぐ違うことをしようとします。
楽な方楽な方に行こうとします。でも結局行き止まりになります。
稲盛さんはこの「自らを追い込む」の説明の最後に書いています。
「私は社員にも『神様が手を差し伸べてくなるほど。一途に頑張るのだ。そうすればきっと啓示がある』と言ってます」と
私は今まで「頑張る」という言葉についてこのブログで何回も書いています。。
でもやはりこの言葉が重要です。
頑張れ!頑張れ!
率先垂範する
今日は京セラフィロソフィにある「率先垂範する」について書きます。
稲盛さんはこのことについて次のように書いています。
「仕事をする上で、部下や周りの人々の協力を得る為には、率先垂範でなければなりません。人の嫌がるような仕事も真っ先に取り組んでいく姿勢が必要です。
どんなに多くの、どんなに美しい言葉を並べたてても、行動が伴わなければ人の心をとらえることはできません。自分が他の人にしてほしいと思うことを、自ら真っ先に行動で示すことによって、周りの人々も付いてくるのです。
率先垂範するには勇気と信念がいります。これを常に心がけ実行することによって、自らを高めていくことも出来るのです。上に立つ人は勿論のこと、全ての人が率先垂範する職場風土を作り上げなければなりません。」
稲盛さんは経営者に対しては「リーダーたるもの、自ら最前線で仕事をしなければなりません。その後ろ姿で部下を教育するのがリーダーというものだ」と言います。
そして、会社のトップたる経営者は最前線に立って指揮を執るのがいいのか、後方に居て大局を見て指揮するのがいいのかについても言っています。
後方にいる経営者は「私は楽をしているのでない。全体を見る為に後ろにいるのだ」と主張しますが、それは自分が苦労をしたくない、楽をしたいからそう言うのです。
また一方、前線に居てばかりでは全体の動きを見切れないこともあります。
ですから、最前線で社員と一緒に苦労しては、後方に取って返して全体を見るようにするという具合に、臨機応変に行ったり来たりすることが必要です。
最後に稲盛さんは「社員の先頭を切って自分も仕事をし、苦労するという勇気が大切」と言っています。
よくあるのですが、経営者は会社が大きくなり、社会的地位も高くなると動かなくなる傾向にあります。
極端な時は社長室から一歩も出ず、全て報告させそこで方針を出すこともあります。
稲盛さんが言うように率先垂範をするという信念を持ち、現場に出ていく勇気が社長たる経営者には必要なのですね。
「渦の中心になれ」
19日に開催しました「京セラフィロソフィ勉強会」の内容をブログで紹介します。
昨日から紹介していますが、今日は「渦の中心になれ」について書きます。
稲盛さんは次のように言います。
「仕事は自分一人ではできません。上司、部下をはじめ、周囲にいる人々と一緒に協力し合って行うのが仕事です。その場合には、必ず自分から積極的に仕事を求めて働き掛け、周囲にいる人々が自然に協力してくれるような状態にしていかなければなりません。これが『渦の中心で仕事をする』ということです。
会社にはあちらこちらで仕事の渦が捲いています。気が付くと他の人が中心に居て、自分はその周りを回るだけで、本当の仕事の喜びを味会うことが出来ない時があります。
自分が渦の中心になり、積極的に周囲を巻き込んで仕事をしていかなければなりません。」
この話を読んで納得する人は多いでしょう。
そして起業を志す人はまずこのような人でなければ、成功は望めませんし、その前に起業しない方がいいでしょう。
私は35年ほど前(大昔ですね)新入行員として銀行で仕事をしている時、上司から言われたことは忘れません。
「山地君 君は良く人の話を聞き、素直だけれど、いつまでもそれではいけない。自分の意見を持ち、それを主張することも大事だ。」と。
新入行員だった頃は、人の話を黙って聞き、素直に従っていけば、「楽」だったことを覚えています。
頭を使うことが必要ないからです。
自分で考えず、ただ上司の言うままにしていれば、お怒られることも無くそこそこ仕事が出来ました。
でも、仕事はだんだん面白くなくなりました。
上司の言うとおりでした。
あの頃を思い出すと「渦の中心」になっていたのは飲み会の時ぐらいでしょうか。
「渦の中心で仕事をする」時大切なのは謙虚な心でしょう。
周りを引き込み仕事をする時は、年配の人や上司もいるかもしれません。態度や言葉使いに気を付け、その人達に彼らの重要感を意識させながら、仕事を進めることは大切です。
「俺について来い」的な行動は、後ろを振り返ると誰も付いては来ていません。
心するところです。
第7回京セラフィロソフィ勉強会
昨夜19時から7回目になる京セラフィロソフィの勉強会を開きました。
16人で活発な意見交換もあり有意義な勉強会でした。
今回のテーマは「物事の本質を究める」「渦の中心になれ」「率先垂範をする」「自らを追い込む」の4つです。
今日から4日間それぞれのテーマごとに書いていきます。
「物事の本質を究める」
稲盛さんはこう書かれています。
「私たちは1つのことを究めることによって、初めて真理や物事の本質を体得することが出来ます。
究めると言うことは1つのことに精魂込めて打ち込み、その核心となる何かをつかむことです。
1つのことを究めた体験は、そのほかのあらゆることに通じまます。」
完全主義を貫き、真面目に一生懸命仕事に打ち込む事を四六時中やっていれば物事の本質が究めてくるのです。
そして物事を究めれば全てのことに通じるのです。
また、真面目に一生懸命に働くことは、禅宗のお坊さんが、座禅を組むだけでなく、掃除、炊事も一つの修行としてこなしているのと同じように、修行と考えることも出来ます。
私は経験がありませんが、芸事や技術を師匠の下で教えていただく時、最初は掃除や、炊事等の雑用を命じられ、長い間黙々とこなしているのと似ています。
芸事や技術を習得する前に、どんなことも一生懸命こなすことが出来なければ、何を教えても所詮中途半端に終わってしまうということなのでしょう。
ある時稲盛さんがテレビを見ていると、1人の宮大工さんが大学の教授と対談していました。
その宮大工さんは大学の教授がタジタジとするくらい素晴らしい話しをしていたそうです。
その宮大工さんは小学校を出てからずっと宮大工をして努めてきた人なので、学問的知識はありません。
でも「宮大工という仕事を究め」「一芸に秀でる」ことは、単に素晴らしい建物を建てることが出来るだけでなく、自らの人間性を素晴らしいものに作り上げることに通じると稲盛さんは思い至ったそうです。
勉強会に参加した人の中にも紅型職人の女性がいますが、その彼女もこのことはよく理解できると言っていました。
稲盛さんはこの「物事の本質を究める」の最後に経営者も「自分の一生、このまま終わりたくない。もっといろんなことをやりたい」と思うなら、仕事を好きになり、今日よりは明日、明日より明後日と創意工夫を重ね、それを長く続けることが大切と結んでいます。
究めると言うことは、大小はあるにしても、その道の専門家になることです。その中で人間として磨かれ、自分の人生が豊かになっていくことになるのでしょう。
明日は「渦の中心になれ」について書きます。

NPOでもしっかり利益を稼ぐ
私の知人のAさんはNPOを運営しています。
昨日彼から色々話を聞き、相談も受けました。
NPOの世界も以前と比べ、国や北海道、札幌市の補助金事業は減少して、その事業を獲得するのに競争が激しくなってきているようです。
そうなると、小さな規模のNPOでは競争に負けるケースが増えてきます。
Aさんは色々な補助金事業の申請書を出して忙しそうですが、なかなか実績に結び付いていません。
その彼に話したのは、NPOの活動の中に「実業」で稼ぐことを勧めました。
NPOについては詳しくないので、間違えているかもしれませんが、利益を上げることは許されているはずです。
その活動範囲を外さなければいいと思います。
その時、障害になるのがNPOで働く人の意識です。
稼ぐという意識です。
NPOの仕事は補助金事業の調査活動であったり、指導する立場でした。
どちらかというと、事業の認可をもらうと、教えて上げるという立場になります。
それが今度は実際に商売をするという「実業」に取り組む時、商売の姿勢が持てるかということです。
稲盛和夫さんは商売の原点は「夜鳴きうどん」といいます。
同じ屋台を引いて商売をするにしても、でも人によって利益の出し方が違ってきます。
材料費を高くても美味しいうどんを売ろうとするか、安くして沢山売ろうとするか、その為に如何に安く材料を入手するか。
売り方にも工夫が必要です。
お客様が喜ぶことを実際にしてお金をもらう。
そういう、「手もみ商売」が出来るかということです。
これからNPOで起業しようと考えている人もいるかもしれません。
その時いつでも「手もみ商売」が出来る人が成功すると思います。
「手もみ商売」というとあまりいいイメージを持たれないかもしれません。
でも私は「手もみ商売」が好きです。
「手もみ商売」は商売の原点だと思います。
今度「手もみ商売」について書いてみたいと思っています。
小善は大悪に似たり
先日、日経新聞の社説に「企業の倒産先延ばしは長く続かない」という題名で企業倒産のことが書かれていました。
2010年度上半期の企業倒産件数が前年同期に比べて15.2%減少しました。
その背景には、「中小企業金融円滑法」があります。
これは亀井静香前金融担当大臣が肝いりで作ったもので、「企業が借りているお金の期限が来て返済猶予を求めた場合、銀行はそれに応じる努力をせよ」とういうものです。
昨年12月の施工から今年6月末までに同法に基づく猶予は累計で39万件を超え、総額13兆4000億円程度になっています。
私はこれを読んだ時、「大変なことだ!」と思いました。
企業が生き延びたのですからいいように見えますが、本当によかったのでしょうか。
一時的に資金が足りない程度ならいいのですが、今後猶予を受けた会社のどのくらいが再生出来るでしょうか。
単なる倒産の先延ばしなら、ただ負債が膨らむだけです。
2回3回と返済猶予を繰り返しても、事業計画の練り直しがうまく出来ていない企業があると書かれています。
本来は、先行きの見込みがなければ、その時点で倒産させた方が、その会社の損害が少なくて済むかもしれません。
ある時耐え切れず、返済猶予の会社が一気に莫大な借金を抱えて倒産することになれば、事業主の再生不可能になるばかりか、日本中にパニックが起きるかもしれません。
弱者に優しく思えた法律が、当人ばかりでなく他も引き込んで禍を広げることになりかねません。
昔、私が銀行員だった時、当時支店長に言われたことがあります。
「人にお金を貸すということは、貸すことで良くなることもあるが、貸した為によりダメになることもある。
貸さないのもその人の為ということもある」言っていたのを思い出します。
銀行は「傘が必要な時に傘を貸さず、必要ない時に貸そうとする」と言われます。
確かにそんな一面もあります。
しかし、銀行がこれ以上貸してはいけないと思っても、法律で貸し続けろと言われれば貸さざるを得ません。
それが企業の傷口を広げるとわかっていてもです。
今、改めて思います。
「小善は大悪に似たり」です。
優しいことが良いことばかりではないのです。
お客様に選ばれる仕事
駅前や繁華街にタクシーが長々と列をなして並んでいます。
「流し」ではなかなかお客が捉まらないので、捉まりやすい駅や繁華街に集中するのでしょう。
私の住んでいる地下鉄駅周辺にも、決められたタクシー乗り場以外のいたるところにタクシーが並んでいます。
ひどい時には交差点にも駐車しています。その為渋滞が起きて大変迷惑しています。
時々タクシー協会の取り締まりが入りますが、入るとその時だけはいなくなりますが、またすぐ違法停車です。
このようなタクシーの現状がある一方、私の知り合いのタクシー会社社長は、タクシー業界の不振は政府の「自由化」が原因だと言います。
「自由化」によって価格破壊が起こり、新規参入が増え、それまでの秩序が壊されてしまったと。
私は違うと思います。
それはこの業界がいつまでも変わろうとしないところに問題があります。
国の認可制で新規参入を防ぎ、既存の権利を保持することばかり考えてきたところに問題があります。
それを打ち破っているのはMKタクシーくらいでしょうか。
タクシーが本当にお客のことを考えれば、今みたいな料金は設定しないはずです。
自分達の会社の経費・利益の積み上げでタクシー料金が設定されています。
初乗り(1.6㎞)が650円は高すぎます。
高い料金を設定して、乗車率が悪くなり、結果売上が下がっています。
200円のハンバーガーを600円で売っているような感じです。
お客様が正当と思われる金額を見つけ出して売らなければ売れません。
これから高齢化が進むと、足となるタクシーが手軽に使えれれば、乗る人が増えるはずです。
初乗りが200円か300円になれば、乗車率が格段に高くなります。
タクシー乗り場で、エンジンをかけたままで長時間待つことも必要なくなります。
時間と燃料が浮いた分利益になります。
また運転免許を返上した高齢者に、特典としてタクシーの割引券を上げ、需要を掘り起こすことも出来ます。
如何に使うお客様のことを考えるか、考えている会社は発展します。
そうでない会社は衰退していくでしょう。
現在他の業界ではそんなことは自明の理です。
それが出来ていないところそれがタクシー業界と思っています。
そのようなところに気付いているのがMKタクシーなのかもしれません
新規参入する時狙う業界は遅れている業界と言われています。
もしかしたらタクシー業界はこれからの商売かもしれませんね
5年後の日本
昨日講演会があり、行ってきました。
札幌は東京などと違って、そう頻繁に専門家の話は聞けません。
ですから、私は講演会がある時はなるべく業種にこだわらず聞きに行くようにしています。
昨日の講師は斉藤精一郎さんでした。斉藤さんは皆さんご存じのように経済学者で、テレビにもコメンテーターとして出ています。
このイベントの名称が「卸・小売連携フォーラム」ということで、斉藤さんの講演題名は「地域商業の活性化と小売・卸の役割」です。
でも話のほとんどは日本の経済全般の話でした。
現在の日本の状況は改めて説明するまでもありませんが、不景気・デフレの真っ最中です。
斉藤さんの話を纏めると
◆日本経済の下降は20年前から始まりました。
20年前の1989年の日経平均株価が39000円だったのは20年経って2009年末で10540円4分の1。
土地の価値も4分の1
◆日本のGNPは20年間で0.7%の伸び。アメリカは2.6%の伸び。
◆日本の給料は20年前、平均年収は403万円が現在406万円でほとんど伸びはない。
◆日本の給与は世界的に見てまだ高い。より下がる可能性が高い。
◆日本は12年前頃よりデフが始まった。
◆国債はもう1000兆円を超える。
◆日本は高齢化が進むので消費は増えない。高齢者は貯蓄はあっても年金以外の収入がないから。
◆ベルリンの壁が無くなってから、世界中が市場経済になった。結果どこで作っても、どこで売っても良くなった。
日本の製造業は海外で作り、海外に売るようになっている。
日産のマーチはタイで、トヨタのカローラす全て海外生産すると発表している。
◆日本はあと5年で再生する方法を探さないとどうなるか分からない。
◆日本に残された時間は無い。
以上の斉藤さんの話を聞いて悲観的とは思いません。
今大切なのは、日本人は真正面から日本経済の現状を認識し、自分が何が出来るかを考えなければならないとことに来ています。
もう国が何かをしてくれることを待っている暇はないのです。
大手企業は自己保存の為に海外へ出ていきます。
これからは金持ちも資金を海外へ移していくでしょう。
私たちはこれから誰かや何かに頼るのではないく、自立出来る力が必要になって来ます。
これからは起業家が活躍する時代だと、私は確信しています。
リーダーシップについて考える
昨日のテレビでは夜遅くまで、チリの落盤事故で閉じ込められた33名が全員救出されたことが放映されていました。
69日間、地中に閉じ決められ極限状態で生き延びてきました。
最後にリーダー格のウルスアさんが救出されると大歓声が上がりました。
極限状態の時に人を纏めるとのは大変難しいことです。
ウルスアさんはリーダー格としてそれを成し遂げました。
ただ、テレビを見ていて、ある解説者が言った言葉が気になりました。
「このようなリーダーは国民性ですね。外国では『俺についてこい』的なリーダが多いですが、日本のリーダーには協調性が求められるので、日本人がこの状況になった時は違うかもしれませんね」と言ってました。
私はその話を聞いて「違う」とテレビに向かって叫んでいました。
この問題を会社を例にしたなら、会社が順調な時は社長は仕事を各部署の責任者に任せ、会社全体を見、会社の目的目標の共有をはかっていればいいのです。
しかし、会社存亡の危機の時は、社長が先頭に立って指揮し、全社員と共に生き残りをかける行動をとります。
外国人だろうが日本人だろうが関係ありません。
それは落盤事故が起きて、生きるか死ぬかの時、全てのリーダがとる行動と同じです。
国民性の問題ではありません。
テレビを見ていて、チリのピニェラ大統領の行動も注目していました。
救出時間が24時間近くかかったそうですが、大統領はその間中現場に居続けました。
勿論大統領としての立場、人気取り等の気持もあったのでしょうが、「現場に居続けることがリーダーとして重要なことだ」ということを再認識させられました。
昔、私が銀行員だった頃、営業担当者は毎月3000万円の定期預金を獲得しなければなりませんでした。
1日最低100万円以上になります。
目標が達成で難しい月は、各自の目標を達成しないと帰社しても、銀行に入れてくれません。
支店長はシャッター越しに「もう一度行って来い」と言って再び営業に行かされます。
夜10時頃まで帰れません。
営業担当者が営業している間は支店長も帰りません。色々仕事をしながら待ちます。
当時私はまだ営業担当でありませんでしたが、支店長を見て、「待つのも大変だ」と感じていました。
大統領と支店長とでは立場もその時の状況も違いますが、リーダーとして「じっと現場に居続ける」重要さは同じです。
良く見聞きするのですが、社員にきつい仕事を言いつけておきながら、自分は用事があると言って、会合やゴルフに出かける社長が多いのです。
話を聞くと「そんなこと当り前」と思うことでも、自分を振り返ると出来ていないものです。
最後にもう一つ、このチリ落盤事故で本当に素晴らしかったのは、6名の救助隊です。
最初にテストも無くカプセルに乗り、33人を全員助け出した後、最後に地上に出る。
本当に勇気がなければできないことです。
色々な事を考えさせられる救出でした。
でも本当に良かったですね。全員救出されて
経営と占い
昨日、起業家の集まりがありました。
そこで占いで起業を志すSさんという女性に会いました。
Sさんは60歳。長年会社に勤めてをしていて、4年前に今後のことをある占い師に見てもらったところ、占い師に向いていると言われたそうです。
本人はびっくりして「自分は霊感も無いのに」と思ったのですが、その占い師は「霊感は必要でない。占いとは長年に渡り研究されてきた統計学です」と言ったそうです。
その占い師に就いて4年間占い全般を勉強し、今度独立を志しています。
「経営と占い」と言ってすぐ思い出すのは、今は有名になった家具販売会社N社の社長です。
小さな家具店が、30年ほどの間に全国にチェーン展開するようになりました。
その会社が快進撃を続けている頃、「あの社長には女性の占い師がついている。重要な案件を決定する時相談して決めている」という噂がありました。
本当かどうかわかりません。
「社長が占い師話の聞いて経営するとは!」としかめっ面する人が多いかもしれません。
私は占い師に相談してもいいと思っています。
社長は大変孤独です。会社の最終的判断は社長がしなければなりません。
専務や常務達と相談出来ても決断は社長です。
その時、占い師に自分の運や流れを聞いて決めるのもいいのではないかと思います。
昔から大きな会社の社長に占い師が付いていると噂は聞きます。
そのような占い師で、有名なのは以前よくテレビに出ていたHさんとも聞きます。
あの有名な安岡正篤さんも易学に精通していました。
社長にとって、占い師をコーチやメンターとしてとらえると、受け入れやすくなるもかもしれません。
先程の起業を志すSさんも「占いによって、その人の進むべき良き方向を示すお手伝いが出来ればいい」と言っていました。
恋愛占いだけをする占い師になりたくないとも言っていたので、経営者の相談相手になって行く方法もあると思います。
キャッチフレースも「経営者の為の占い師」と明確にすることで、社長の心を捉まえるが出来るのではないでしょうか。
結構不安を感じている社長は多くいますので商売にはなると思います。
願望と欲望とうは違う
起業を志す人と話をすると、起業する動機がお金を稼ぎたいと多くの人が言います。
お金を稼いでどうするのと聞くと、しばらく言葉がありません。
もしも実際に1億円稼いだとして、1億円で何をしたいのかわかっていないのです。
本来は「○○をするために1億円が欲しい」となるべきです。
強いて聞くと「ブランドの服を着れるようになりたい」「フェラーリに乗れるようになりたい」「3つ星レストランに行きたい」等あります。
それは単なる欲望です。
願望と欲望は違います。
「Wish List」と言うものご存知でしょうか?
これはアメリカのバーバラ・アン キプファーさんが書き、宇宙飛行士の向井千秋さんが日本に紹介したモノです。
この言葉の通り、自分が欲しいものを数多くこの「Wish List」に書いていくのです。
バーバラ・アン キプファーさんは6000個の望むモノを書きたそうです。
私も興味があり、自分がこれから進むべき方向を決めるに、「何をしたたいと思っているのか」をはっきりさせる為に書き出しました。
自分の「欲しいもの」「買いたいもの」「行きたいところ」を一生懸命書いたのですが100個も出てきません。
書いてから、この「欲しいもの」「買いたいもの」「行きたいいところ」は今の自分でも何とかしたら叶えてしまうものだとわかりました。
そしてこれは単に欲望をリストアップしていることではないかと気が付きました。
「Wish List」を否定しているわけではありません。
自分自身の欲望を解離して、自分を確認することはいいのでしょうが、それが目的になってはいけません。
昨日知人と話をした時、稲盛和夫さんが経営の12カ条に書かれている「強烈な願望を心に抱く」について私の考えを聞かれました。
願望とは何かということです。
稲盛さんの考えとは違うかもしれませんが、私は「願望」とは明確な「目的」「目標」ではないかと私なりに答えました。
この「目的」と「目標」については以前にも書きましたので、改めて説明しませんが欲望とは違うのです。
私の死んだ祖母が言っていた「下見て暮せ、上見て励め」は自分の欲望を押さえて、その上で明確な「目的」「目標」を持って、人の為、会社の為に努力することだと理解しています。
改めて、起業を志す人は、高い「志(こころざし)」を持って、起業してほしいと思います。
新聞休刊日
今日は朝刊が来ていません。休刊日でした。
私は休刊日の時思うのですが、各新聞がいっせいに休刊とは不思議な気がします。
独禁法違反ではないのでしょうが、購読者の考えも聞かず、ある時突然「休刊日を設けます」と一方的に言って始まった記憶があります。
私の記憶ではその頃学校の週休2日制が始まり、官公庁も同様に始まりました。
当時は詰め込み教育の弊害や日本人が働き過ぎだと言われた時代です。
そして新聞社は「新聞配達少年」を表に出し、「彼らにも休みをあげる」為に休刊日を始める様な事を言った気がします。
今は状況が変わりました。
「新聞配達少年」は減り、中高年の人達に変わりつつあります。
彼らは、アルバイトです。休刊日があるとお金がもらえませんので、困ります。
現在は24時間営業の店も増えました。
デパートでも昔は休館日があったのが、今はありません。
皆一生懸命働いています。
情報社会の現在、ネット情報によりテレビや新聞を見ない若者が増えています。
特に新聞の購読者層が減ってきています。
その様な中でも新聞社は購読者が一番望む休刊日廃止はしていません。
駅売りのスポーツ新聞は休刊日がありません。
昔、新聞はマスコミの王様でした。
早く、購読者の方に降りてこないと、裸の王様になって、最後には新聞が無くなることになりかねません。
そうなると新聞を毎日楽しみししている私はまた困ります。
元気がない時は
今日は3連休最後の日。明日から出勤の人が多いでしょう。
休み明けは休みボケになりやすいと言われます。
また普段でも気が乗っている時とそうでない時があります。
そううつ病ではなくても、元気な時と落ち込んでいる時があります。
私もそうです。
頑張らなければならない時に、気が乗らないことがあります。
多くの人がそれに悩んでいるからでしょう。色々な人がそれの対処方法を教えてくれています。
昔、元気の代表だった長嶋茂雄さんは常にポジティブで、落ち込むことなどないと思っていましたが、日経新聞の「私の履歴書」にそのために努力していたことが書かれています。そのままご紹介します。
「大学4年間、私は自分が何をしたら周りの人が喜んでくれるのか、自分をどう表現したらいいのか、そればかりを片時も忘れずに考えていた。私は人生は表現力だと思っている。プレー以外のどんな時でも観客の全ての視線を引き付けようと意識した。見られる方がいつも集中して、さらにプラスアルファの力が生まれるものだ。」
「人生は表現力だと思う」と言う言葉は納得しました。
元気のない時に、元気でいるように見せることで、いつの間にか元気になっていることがあります。
会社で社長が元気なかったら社員も元気をなくします。
社長は元気でなくても、元気を演じるのです。
もう1つ言葉を紹介します。アメリカの女優のジュリア・ロバーツさんの言葉です。
「心の中ではいつも不安があります。期待される演技が出来なかったらどうしよう。番組を降ろされるかもしれない等という不安です。でも、何時も自信にあふれている『ふり』をすることに心がけています。そして自信に満ちた態度で『やれます』と挑戦を引き受けること。そしてそれを証明するために努力すること。その繰返しでやがて『ふり』だった自信が体験によって本物の自信に変わっていく。」
経営者は良き俳優になって演じることが必要です。そして自信ある経営をし続けなければなりません。
読書不足
最近読書不足を痛感しています。
「それなら読めばいいのに」と思われるでしょうが、少し難しい本だと前に進みません。
以前より読む速度が遅くなっています。
その上、読んだあとからドンドン忘れていく。
現在61歳ですが、60歳を境に変わってきたように思います。
以前は小説の本をよく読みました。
城山三郎さんの企業小説や司馬良太郎さんの歴史小説、宮城谷昌光さんの中国歴史小説は好きです。
これらの本は自分の人生観を変えた程に中身の濃いものでした。
最近の小説の本は読んでも、どうしてかそれほど「血沸き、心躍る」様な本に当たりません。
私が変わったのか、小説全般の傾向が変わったのか。
それでもこの連休に頑張って本を読んでいます。
今読んでいるのは玉岡かおるさんの「お家さん」です。上下巻のボリュームがあります。
戦前金融恐慌で没落した「鈴木商店」の話を、商店の「お家さん」と呼ばれた女性から見た盛衰記です。
なかなか面白いです。
人間の頭は常に「プットイン」と「プットアウト」を繰り返していかないと、頭がボケます。
今、再挑戦しようと思っているのがM.E.ポーターの「競争の戦略」です。
以前読んでいたのですが、途中で挫折しました。
この本を改めて読破しようと思います。
以前読んでいて「いい本」だとはわかるのですが、私には難しいのです。
読んでもまたすぐ忘れるのです。
でも、何回か繰り返して読んでみようと思います。
最近少し自信を無くしている自分を「オーバーホール」をしてみます。
頑張ります!
身近の起業家の復活
私はレンタルオフィス「「札幌オフィスプレイス」を運営しています。
ほとんどが起業したばかりの人達です。
最近オフィスで嬉しいことがありました。
仕事がうまくいかず一度退室した人が、また入居しました。仲間が戻ってきたのです。
以前退出する時、必ず戻りますと言っていました。
再入居してからの彼の仕事振りは以前とは全然違います。
以前は昼ごろ出てくることも多く、ある程度自由な仕事ぶりでした。
今は、朝は9時前から出社し、仕事をし、帰りは遅いようです。(私が先に帰ってしまっているので良くわかりませんが)
オフィスでは朝にコーヒーを落します。入れたてのコーヒーを飲みながら話を聞くと、頑張っている様子が分かります。
もう1人、彼は順調に業績も伸ばし、会社も個人会社を法人化したのですが、法人化した直後病気になってしまいました。
2ヵ月も入院している間に業績は極端に低下したそうです。
収入も不安定になり、退院後はコスト削減の為一旦オフィスを出て自宅で仕事をしようと思ったそうですが、家には小さな子供がいるので、やはり仕事の環境を考えてオフィスに残りました。
それから5ヵ月程経った昨日、人を1人入れたいのでブース席を1つ借りたいと申し入れありました。
落ちた業績を盛り返し、前にも増して仕事が順調のようです。
私はあまりお手伝い出来ませんでしたが、大変嬉く2人で喜びました。
起業し、成功して業務拡大の為、私のオフィスを出ていく人達が増えています。
嬉しい限りです。
この2人もいずれは業務拡大の為出ていくことでしょう。
これからも起業家が成功するように支援していきます。
主電源は切らず
明日から3連休の人が多いでしょうか。
休日の前の日だからといって、飲みに行ったり、夜遅くまで遊びに行ったりするのでしょう。
私も休日の前日の方が、休日より浮き浮きした気持ちになります。
そんな私も「主電源は切らず、何時でもボタン一つで立ち上がる状態に心を保つ」ように心がけています。
いつ会社で何が起きるか分かりません。
知らない人に会い、その人から重要な話が聞けるかもしれません。
ある物を見て、それが自分の仕事のヒントになるかもしれません。
「常在戦場」なのです。
優れた経営者は「常在戦場」の状態です。
「人はいつも気を張っていてはストレスになってしまうから、オン・オフに切り替えたらいいよ」と言う人がいます。
その通りです。でも主電源は切らず、スイッチは自動感知式になっていなければなりません。
優れた経営者は仕事のことを常に考えるのが好きなのです。
逆に仕事から切り離されるのと、ストレスになるのかもしれません。
いつも主電源が入っている人は、酒飲んで騒いでいても、楽しくゴルフをしていても、何かを見たり感じたりすると、自動的にスイッチのボタンが入ります。
決して意識しているのでなないのです。
そう言えば私もいいアイディアが思いついた時、頭の中で「パッチン」という音がします。
ボタンの音だったのかも?
ノーベル賞受賞
昨夜7時のNHKのニュースを見ていたところ、「ノーベル化学賞受賞者日本人2名」とアナウンサーが叫んで始まりました。
また、そのうちに1人が北海道大学の鈴木章名誉教授だとのこと。
北海道人として「地元北海道大学からノーベル受賞者が出るとは!」という驚きと嬉しさがありました。
新聞には最近、工学や化学を専攻する人が少ないとか書いてありましたが、このニュースを見聞きして若い人、特に北海道の若い人が自信を持って、頑張ってほしいという気持ちになりました。
現在「『頑張れ』という言葉はあまり使ってはいけない」と言う人がいます。精神的に追い詰められている人に使うと、もっと追い詰められていくからと言います。
そのような考えもあると思いますが、それが強調され過ぎているからでしょうか、今の若い人達が頑張らなくなっています。
頑張れと言うことに関して、2年前同じノーベル化学賞を受賞した下村脩さんも、昨年7月日経新聞の「私の履歴書」に書かれています。
読まれた方もいるかもしれませんが、その文を紹介します。
「ノーベル賞を受けた翌年の2009年3月、日本に一時帰国して、日本化学会などが主催する講演会に招かれたときのことだ。講演後のパネル討論の場で、会場の若い参加者から私への質問が出た。おそらく研究者かその卵であろう。『研究で成果が出ず、行き詰ったときはどうすればいいか』という問いだった。
ちょっと考えた後、こう言った。「がんばれ、がんばれ」。つべこべ言わずに努力をしなさいという、突き放したような言い方に、ひょっとしたら聞こえたかもしれない。もう少し丁寧な答え方をしようとも思ったのだが、私が言いたかったのは、結局はこの「がんばれ」という単純な言葉に尽きるのである。」
「『やりたかったことをやっていて行き詰ったらどうするか』と、聞かれたこともある。この質問の真意が私にはよく分からない。すぐにあきらめたり、ほかのことに移ってしまったりするのは、それはそのことが本当にやりたかったことにはならないのではないだろうか」
どんな世界でも頑張らなければ報われない。
目的に向かって「頑張れ!」「頑張れ!」のエールは今、改めて必要な事だと思います。
逆説的に言えば、頑張らない人が多いから、少し頑張れば成功できる時代かもしれません。
ほっかいどうにできること
昨日、日本経済新社主催で「ほっかいどうにできること」という題名のセミナーに出席してきました。
基調講演は日本ハムファイターズオーナーの大社啓二氏、続いてグーグル名誉会長の村上憲郎氏の話があり、その後釧路公立大学長の小磯修二氏、植松電気の植松努氏、知床羅臼町観光協会事務局長の三浦里紗氏を交えたパネルディスカッションと続きました。
今後の北海道をそれぞれの立場で話され、興味深いものでした。その中でも特に興味を持ったことを書きます。
グーグルの村上さんはやはりグーグルのことを中心に話されました。
皆さんもご存じだと思いますが、グーグルのミッションは無料でサービスを提供することで、収入約2兆円のうち97%が広告収入、3%がサーバーの利用収入です。
グーグルの一番の課題はコスト削減、その中でも電気量の削減には力を入れています。
サーバー使用と発生する熱を冷やすための電気量は莫大なモノです。
そのサーバーは全てぐグーグルが自前で作っているそうです。
そのサーバーの設置場所は、札幌ドーム球場の大きさ位あり、それが何か所にも分かれています。
データーが膨大に増え続けるので、それに合わせてサーバー設置もこれから限りなく増えていくそうです。
ユーチューブの登録でさえ、1分間で24時間分が登録されています。
電気の品質のことで、アメリカと日本を比較する数字が示されました。
年間の平均停電時間はアメリカが9時間に対して日本は4分というデータがあり、日本の電量事業者の優秀さを強調していました。。
パネルディスカッションの中で興味あったものを若干紹介します。
植松電気の植松さんからの話です。植松電気は建設機械の会社ですが、今はハイブリッドロケットの開発で有名になっています。
現在1年のうち300日は講演に出かけて、日本中の経営者達とも話をしているそうです。
その中で感じたことは
①現在日本では経済の構造変革が起きており、本州の起業には危機感が高まっている。従来のスタイルを変えようとしている。しかし北海道の企業にはそれがない。
②北海道は行政に依存した経営スタイル。自分たちで考えない。
③してもらう気持ちが北海道経済低迷の敗因である。
釧路公立大学長の小磯さんは地域経済研究の専門家です。その立場からの発言です。
グーグルの村上さんが九州大分県出身と言うこともあり、小磯さんから九州と北海道を比較しての話がありました。
九州は県が7つあり、7人の知事が互いに競い合っています。北海道は1人の知事です。
そこに地域の競争原理が働くころと働かないところが生まれ、経済格差にもなっています。
今、北海道は競争の仕組み作りが必要と指摘しました。
また、若い人の地方からの流出についても話しがありました。
東京の人口の割合は全国の9.9%にもかかわらず、学生人口の割合は25%にもなり、各地方から若い人材が東京に集中し、そのまま戻らない現状も示されました。
その他にもいろいろ興味深い話がありましたが、このセミナーの状況は近いうちに日経新聞の全国版に掲載される予定です。
よろしければご覧になってください。
参考
植松電気:http://uematsu-electric.fte.jp/
人の「質」
以前にも書いたかもしれませんが、人にとって重要なのは、どんな才能より人としての「質」です。
「質」の良い人は、何をやってもうまくいきます。何があっても周りの人が応援してくれます。
私が考える「質」が良いとは
1.親孝行であること
2.真面目であること
3.卑しくないこと
4.謙虚であること
5.約束を守ること
この「質」がベースにあって、明るいとか、行動的だとか、頭の回転が良いとかが付加されて、その人の能力が高まるのです。
この5項目のうち「卑しくない」と言うのは、品格の問題でもあります。
城山三郎さんが書いた小説で「租にして野だが卑でない」と言うのがあります。
国鉄総裁であった石田禮助氏の生き方を書いたものです。
自分の損得から離れた生き方をした人です。この小説は私の好きな小説の一冊です。
先日私のレンタルオフィスを先日退室していった人がいました。
私のレンタルオフィスには起業を志す人、起業した人が多くいます。
退室していった彼もその一人でした。
色々相談に乗りながら、励ましもしたのですが、うまく行かず退室しました。
出る2,3日前まで相談にのっていたのですが退室の日、私の会社のポストに鍵を入ただけの、言葉もない別れでした。
一言「お世話になりました」の言葉があり、「頑張ってね。またいつでも相談にのるよ」と言ってあげたかったのです。
寂しさを感じました。
「一言の大切さを自覚しないと、間違えた方向に行く」事を分かって欲しいと思っています。
セールスマンがもたらした情報2
昨日に引き続きセールスマンから教えてもらった情報について書きます。
今日はセールスマンの情報でコストが削減された話をします。
ホテルの運営コストとしては、水道光熱費の占める割合が高いです。
その水道料金と、電気料金が安くなった例を書きます。
ある日水道料金が安くなるということで「水道節水コマ」のセールスマンがきました。
それはシャワーの根本に取り付けるもので、それを付けることにより、シャワー口から出るお湯の勢いは変えず、20%ほど水道料が減ると言うのです。
これはいいと思いました。
ご存じのように宿泊されたお客様はほとんどの方がお風呂やシャワーを使います。その量は大変の量です。それが減るのであればコスト削減になります。
しかし、その「水道節水コマ」の料金は1個1万円もしました。小さな鉄の塊が1万円もするのです。
そのセールスマンは収支予想も出してきて3年で元が取れますと言います。
私はその商品は断りましたが、こういう「水道節水コマ」があると知り、暫くいろいろ探しました。
2年後に1個1500円の「水道節水コマ」を探し出しました。はじめのとは違いますが、節水の能力は高いものでした。
2~3カ月で元が取れました。
もう一つ水道の料金下げの話です。
あるセールスマンがきて、「当社のノウハウを使って水道料金を安くします。安くなった水道料金の3割を手数料としてある期間支払って欲しい」と言う話しです。
その内容はクーリングタワー方式で冷房しているビルは、水の気化熱で冷房するのですが、その冷房で使われた水道水は本来空中に散布されますので、下水道としては流れません。
でも現状では上水道として使った水の量と同じ量が下水道に流れたとして計算され請求されます。
上水道量も下水道量も同じ量としてみなされ料金を支払うことになっています。
たとえ「クーリングタワーに使われて下水に流していない分」があると言っても、通りません。
それをそのセールスマンはノウハウを使って必ず安くしますと言いました。
私も一時はその気になったのですが、自分で調べてみることにしました。
東京都の水道局に直接行って聞きました。
水道局の職員は1枚の申請書を出してきて、「これに記入して提出すれば、クーリングタワーに入る水道の量を測るメーターを取り付けます。その分は下水道料金から引きます」との話です。
たった紙1枚でで水道料金が削減できたのです。メータの代金は数万円支払ますが、安いものです。
これにより年間50万円ほど安くなったと記憶しています。
電気料金が削減になったのも、同じセールスマンからの情報です。
これも直接東京電力に行って相談しました。
そうするとそこの職員は「それは深夜電力契約のことでしょう」と言いました。
そして前年度の使用電力データーを「深夜電力契約」をした場合のシュミレーションに落とし込んで料金を調べました。
そうすると年間で100万円以上の削減できるのです。驚きです。
勿論その場ですぐに深夜電力契約に変更しました。
ビジネスホテルの場合は宿泊するお客様中心の営業ですので、電力を使う時間帯は夜です。
その夜に使用される電気単価が安くなれば料金が下がるのです。
考えてみれば当たり前のことです。
結局下水道料金も電気料金もセールムマンには依頼しなかったのですが、彼らの情報のおかげで合わせて150万円以上のコストを削減することが出来ました。
ぜひ情報源としてセールスマンを活用しましょう。
私が4年ほど前に書いていたメールマガジンをまとめたホテル経営に関するホームページがあります。
もしもご興味がありましたらご覧ください。
「小さいから楽しいホテルの経営」http://www.geocities.jp/shcc_j/
セールスマンがもたらした情報1
昨日は「訪問セールスマンは情報源」ということで書きました。
今日は具体的にセールスマンから得た情報の内容等を書きます。
一番印象に残っているのは「旅の窓口」です。
以前は宿泊客は旅行エージェントや特約企業からの送客が中心でした。
そのような送客状況の中で、12~13年ほど前、「旅の窓口」の営業部長と部下が尋ねてきました。
色々話を聞いたのですが、当時インターネットを使って宿泊予約をするなどほとんどなく、せいぜいホテルのホーページを見てメール予約をしてくれる程度でした。
私は「旅の窓口」の営業部長の話を聞いても、ピンとこず、その時は加入するのを断りいました。
その後2カ月ぐらい経った時、あるホテルの支配人と話していて「旅の窓口」の話が出ました。
そのホテルは既に加入していて、結構送客があるという話でした。
私はその話を聞いて早速旅の窓口の担当者を呼んで、すぐ加入しました。
その効果はすぐ現れ、宿泊稼働率はどんどん伸びて行きました。
その後ホテルのインターネット宿泊の割合は30~40%になり、大きな収益源になりました。
今はほとんどのホテル・旅館が加入インターネット宿泊予約をしていますが、当時はまだ加入ホテル・旅館の数が少なく、ホテル間の競争はありませんでした。価格もそれほど下げないでも売れました。
インターネットの宿泊予約システムはホテル側にとって使いやすいものでした。
ホテル側が「旅の窓口」に提供する客室数はホテル側で自由に決めることが出来、提供客室数の増減もいつでも出来ます。
提供価格も自由に上げ下げできるというホテル側にとっては画期的な仕組みでした。
送客手数料も1件当たり6%と当時の旅行エージェントの10~20%と比べると大変低いのです。
また、今もそうだと思いますが、旅行エージェントに提出する客室数は旅行エージェントに決められ、価格も一度決まれば変えることはできません。
そして、お客様が混んで客室が足りなくなた日でも、旅行エージェントにでした客室は、返して欲しいといっても返してくれません。
当日になって売れなかった客室は返されますが、その時は機会損出になって売れ残ってしまうこと多かったのです。売り価格も自由にはなりません。
そのような状況でインターネット予約システムが出現したので、やっとホテルにとって自分の「商品」を自分が自由に販売できることが出来るようになったのです。
このインターネット宿泊予約システムの最初が「旅の窓口」でした。
「旅の窓口」は最初に始めたこともあり、圧倒的な集客力を持ち、大きな利益を上げました。
親会社の日立造船は「旅の窓口」を楽天に売り、大きな利益を得ました。
最初に私のホテルに来ていた営業部長は小野田さんで、「旅の窓口」を立ち上げた人です。
「旅の窓口」が売却された時会社を辞め、別のインターネット宿泊予約会社「ベストリザーブ」を設立しました。
今思ってもあの時、ホテルに小野田さんが来なかったり、来ても会わずにいたら、インターネット宿泊予約に乗り遅れていたはずです。
早く加入したことで、後から加入したホテルより優位になったのは確かでした。
訪問セールスマンは情報源
皆さんの会社に良くセールスマンが訪問しませんか?
ほとんどの会社は「セールスマンお断り」でしょうか?
今は私のところに来るセールスマンはほとんどいませんが、以前東京でホテルの支配人をしていた時、毎日何人か来ました。
セールスマンはホテルのフロントに来るので、来たらほとんど会いました。
会う理由の一つは、そのセールスマンは明日お客になるかも知れないからです。
ですから、お客さまと同じように対応します。言葉使いも気を付けました。
もう一つの理由はセールスマンが売り込みに来る商品の話しの中に情報があるからです。
時には詐欺みたいな話もあります。
でも、私はセールスマンが持ってくる情報から、宿泊稼働率を少なくても30~40%上げましたし、電気料金、水道料金も合わせて年間150万円削減しました。
セールスマンからもたらされる情報を聞いて、「この話はあれとこれを組み合わせたらどうか」とか、「これによって別の問題が解決するかもしれない」とかすぐ考えるのです。
セールスマンは良く話を聞いてあげると、その後も来ます。
その多くのセールスマンは、来る時また何か情報を持っています。
私が外に情報を得に行くより、セールスマンからもたらされた情報の方が多かったかもしれません。
明日その情報で得したことを、もう少し具体的に書きます。
富士メガネ
富士メガネという会社をご存じでしょうか?
北海道の人ならほとんどの人が知っていると思います。
私はそこで眼鏡を作ってもらい、昨日出来あがりました。
この会社は北海道ばかりでなく関東・東北も含め68店舗の店を有しています。
安売りメガネ店でなく、サービスも良くそれなりの価格の眼鏡を売っています。
眼鏡を入れた紙袋の中に「海外難民視力支援ミッション」と書かれたチラシが入っていました。
海外の難民に眼鏡を送る活動が書かれています。
その活動の始まりは創業者の金井武雄氏が1983年から始めたもので、世界中の難民の人達に「視力」を提供するというミッションです。
その活動は、眼鏡をただ送るだけでなく、富士メガネの社員がボランティアで現地に赴き、一人一人の目の状態を見ながら手渡しているそうです。
今まで134名が訪問して、毎年3000~4000組を手渡ししています。
会社が明確な社会貢献の方向を示し、社員がそれに賛同して、会社の存在意義を感じることは、社員同士強い絆が生まれると思います。
この活動は世界中から評価され、多くの賞を受賞しています。
富士メガネはまた、松下幸之助さんともつながりがあります。
創業者の金井武雄氏がテレビを見ていた時、松下幸之助さんが写っていて、その眼鏡がズレていたのを見つけました。
どうしても気になった金井氏は面識もない松下幸之助さんに、「メガネがずり下がっているのは不格好であり、海外へも行かれる機会が多い貴方が、そのようなメガネを使用されているのは日本のメガネ業界の恥のように思われるので、どうぞ調整させていただきたい」という内容の手紙を書きました。
松下さんからお礼の手紙をもらい、松下さんが翌年札幌に来られた時、富士メガネに立ち寄り眼鏡を作ってもらったそうです。
その時のサービスが良くて、松下さんから「世界一のメガネ屋さん」と言われ、お礼にとラジオもプレゼントされたそうです。
このことは富士メガネのホームページ、そして松下幸之助さんが書かれた本の中にも記載されています。
こう見てくると、この富士メガネと言う会社は一本筋の通った会社ですね。
ご興味がありましたが一度ホームページをご覧ください。
http://www.fujimegane.co.jp/
外交と社交
今朝の日経新聞に鳩山由紀夫前総理のことが書かれていました。
ロシア関係者の話として、「鳩山首相が2回もロシアに来るというので何か、重要な提案があるかと思ったら、ただの社交だった。何の戦略も無い日本とはつき合っても仕方がない」と言っています。
日本歴代の首相の中でも、このように外国の外交関係者から「外交でなく社交」と言われたことは、無かったのではないでしょうか。
会社の経営者の行動も同じことが言えます。
会社の関係する会合も、自分の趣味趣向で参加を決めている人がいます。
「外交」と言いながら「社交」になっているのです。
会社の経費を使って参加するからには、人脈を広げ、それによって会社の収益に結びつくことを意識して参加するべきです。
反対に、自分が参加したくないと思っても、それが会社の為であれば参加すべきです。
ある体面を重んじる社長は、自分が認められる場所には喜んで出ていきますが、逆に自分より偉い人が出てくる所には部下をやります。
どう見ても逆でしょう。
偉い人が出て行くところこそ社長自ら出て行き、高いレベルの情報を得てくるのです。それが社長の役目です。
社交的なお付き合いはそれこそ部下に任せればいいのです。
小樽商科大学の瀬戸教授があるセミナーで話していました。
「私は日本経済新聞が主宰する「世界経営者会議」に毎年出席しています。参加費は10万円、宿泊は会場の帝国ホテルです。1回参加すると全て入れて20万円以上かかりますが、自腹で参加します』
大事な会合だからこそ自腹で参加するそうです。
そこでは普段会えない、ビルゲイツやゴーン社長と会い、話をしてくるそうです。
世界のトップに会って得た情報は20万円以上の価値があると言います。
今、ローターリークラブやライオンズクラブに入会する人が少なくなっているそうです。
納得できる傾向だと思います。
もう一度ご自分の社外活動をチェックしてみませんか?
本当に価値があるかどうか。
繊細と豪胆
優れた経営者は常に気配りが出来ていて、時に大胆な決断をしてしまう人です。
元首相の故田中角栄という人は政治家ですが、そのような行動をしている人でした。
以前読んだ本にありました。
「冠婚葬祭は重要だ。特に『葬』は特に重要だ。『冠』『婚』『祭』の時は本人も喜んでいるし、周りの人達もお祝いに来て楽しい時。
でも、『葬』の時は喪主は悲しく、誰かの慰めが嬉しいもの。
だから、知人で不幸があったら、何をおいても駆けつけるべきである」と言ったそうです。
日常の些細な事でも、気にかけて上げると人は喜ぶのです。
逆に、些細な事だからこそ感激するのかもしれません。
田中元首相はチョット知っている人でも、その人の子供が小学校に入学する時には、秘書に行ってお祝いを届けたりしたそうです。
それでいて、田中元首相は「日本列島改造論」という大胆な施策をし、日本を大きく変えました。
田中元首相はロッキード問題で失脚しましたので、全てを認めているわけではありません。
しかし、強力なリーダーとして、理想的な姿かなと思います。
民主党の小沢一郎と言う人は、世間の評価では好き嫌いで大きくわかれます。
小沢さんは田中角栄さんに息子のように可愛がられました。
田中さんの考えを受け継いでいるように見ます。
京セラ名誉会長の稲盛和夫さんのお父さんが亡くなった時、小沢さんは忙しい身でありながら、鹿児島で行われたお通夜、告別式の両方に出席して、稲盛さんを感激させたそうです。
それが稲盛さんと小沢さんと親しくなったキッカケかもしれませんね。
隠れた高収益会社
昨夜、盛和塾札幌の勉強会がありました。
「我が経営を語る」というテーマでA社のK社長が話しました。
1時間30分にわたりましたが、大変興味深く聞きました。
経営するに大変参考になる話でしたので、その一部をご紹介します。
1984年に32歳の時7人で起業しました。
K社長は当初部長でしたがその後、常務、専務、そして社長となりました。
盛和塾には14年前に入塾し、「稲盛経営者賞」も受賞しています。
A社は従業員100名、関連会社も入れれば130名の会社です。
仕事の内容は主に港湾整備コンサルタントの仕事です。
A社の売上の利益率も高く、以前は経常利益率は20%、現在でも10%以上あります。
従業員の待遇も良く、ボーナスは年間一般社員は4カ月分、課長クラスは6カ月、部長クラスは8カ月です。
今の不景気の時代では特筆すべき会社です。
社員は専門技術者が多く、博士号を持っているものも多数います。
会社からアメリカやデンマーク等の大学への留学制度もあり、多くの人が行っています。
そのかわり仕事は厳しいみたいです。
K社長は第一に人、第二に人、人が財産と言います。
常に優秀な人材を求め、南は九州など日本中から集めています。
K社長が話した中で、私が心に残った言葉をご紹介します。
「どの山に登るか、これが決まれば半分登った様なモノ。ただし、山は手稲山か、羊蹄山か、富士山か、エベレストかによって、装備が違ってくる。手稲山に登る装備で、エベレストは登れない。」(手稲山は札幌近郊の山)
「誰と登るかも大事。信頼できる仲間と登ること。落ちていく人間は引き留めない。」
「会社とは夢で始まり、情熱で大きくなり、責任感で安定し、官僚化でダメになる」
「しつこく、しぶとく、したたかに」
K社長によるとA社は漁港に関してのコンサルタントでは世界一の技術と能力を持っていると言います。
尖閣問題で領土問題が取り上げられていますが、沖ノ鳥島も重要な領土です。
この沖ノ鳥島の面積を増やす方法があり、今その研究を進めているそうです。
島は人工的に作ってはいけないそうですが、潮流やサンゴなどを使って自然に砂が集まり、島が大きくなる方法があるそうです。
A社の技術ではそれが出来るようです。
益々A社の事業が拡大していきそうな勢いです。
不景気だと言われる北海道、札幌の中にもしっかり経営し、利益を出している会社があるのです。
景気が悪い会社は「儲かってない」と大きな声を上げます。マスコミもそれを取り上げます。
しかし儲かっている会社は「儲かっている」とは言いません。
大きな声を聞いて「どこもかしこも不景気だ。自分の会社も仕方がない」などと思っている社長もいます。
でも身の回りには、しっかり儲かっている会社、しっかり経営している社長がいるのです。
そんな会社を見習って頑張りましょう。
昨夜は大変有意義な勉強会でした。
会社発展の阻害要因は?
25日の土曜日18時から「大倉山ジャンプ競技会秋まつり」に行ってきました。
「札幌観光大使」の視察と懇親会を兼ねたモノです。私もとりあえず観光大使の一人です。
大倉山は90メートル級のジャンプ台です。
私は北海道に生まれ育ったのにもかかわらず、ジャンプを目の前で見たのは初めてです。
今はサマージャンプで、人工芝を敷いてその上から水を撒き滑りを良くして、雪の上と同じ様にします。
今回は舟木選手のジャンプも見ることが出来ました。
見学が終わり懇親会では北海道らしくジンギスカンです。
同じテーブルには、大手商社と電気メーカの北海道支社長、それと北海道の大きい印刷会社の会長と私の4人です。楽しく飲み食いしました。
その時、北海道支社長2人から、毎年設定する支社の売上計画の目標数字の話が出ました。
「高い目標を掲げ、一生懸命頑張っても、次の年はそれより高い数字を本社から要求される。
ほどほどの数字を目標にしなければ大変だ。」と言います。
それに対して、印刷会社の会長も私も何も言いませんでした。
確かに、私も営業担当の時同じ様な考えでした。
でも今、経営サイドに立つと見方が違ってきます。
「
会社発展の阻害要因」はこの考え方なのだなと思いました。
これを「自己保身だ」と言って責めることはなかなか出来ません。
その時に稲盛和夫さんが言っていたのを思い出しました。
「京セラがまだ小さな会社の時、先頭を走る大手会社に追いつくためには、マラソン競技を100メートル競走のような速さで走らないと、先頭集団に追い付き、追い越すことは出来ないと言って、全力で走ってきました。」
現場の責任者に、ほどほどの速さで走られては追いつきません。
社長がいくら怒っても解決しません。やはりそこには「仕組み」が必要です。
京セラではそれが社員の共通理念作りに必要な「京セラフィロソフィ」であり、「アメーバー経営」、そしてそれを浸透させるためのコミュニケーション作りの「飲み会」があってこそ、京セラは急成長したのではないかと思います。
人も会社も伸びる時には
、「もっともっと」と言って伸びることが必要です。
この時に「ほどほど」と考えると、伸びるものが伸びなくなります。
人には皆、ここだと思う時は、なりふり構わずやり抜ける力はあります。
その時大事なのは、阻害要因を取り除く自分なりの
「仕組み」なのではないでしょうか。

仕事を好きになる
今日は「仕事を好きになる」についてお話します。
この「仕事を好きになる」ということも「いまさら」と思われるでしょう。
稲盛さんが京セラフィロソフィに書いている内容ををご紹介します。
「自分が燃える一番良い方法は、仕事を好きになることです。どんな仕事であっても、それに全力を打ち込んでやり遂げれば、大きな達成感と自信が生まれ、また次の目標へ挑戦する意欲が生まれてきます。その繰返しの中で、さらに仕事が好きになります。そうなればどんな努力も苦にならなくなり、素晴らしい成果を上げることが出来るのです。」
稲盛さんは大学を出て就職難の中、やっと松風工業という碍子(がいし)会社に就職しました。
そこでは給料の遅配が当たり前、しょっちゅう労働争議が起き、業績も悪い会社でした。
同期で入った人間は5人が「こんなボロ会社は嫌だ」と言って1人、1人と辞めて行きました。
最後に稲盛さんともう1人が残ったそうです。
そこで、2人して一緒に自衛隊に入ろうとなり、試験を受け合格しました。
幹部候補生学校に入る為に戸籍抄本を取り寄せたのですが、稲盛さんがけ来なかったそうです。
最後の残った1人も「頑張れよ」と言って出て行って、稲盛さんだけが残されました。
1人残された稲盛さんは愚痴を言う相手もいず、どせなら一生懸命仕事に打ち込んでみようと気持ちを切り替えました。
研究室に布団や鍋釜を持ち込み、一生懸命仕事をするといい結果が生まれました。
研究していい結果が出ると面白くなり、さらに打ち込んで研究をし、ついに日本で初めてセラミック材料の合成に成功しました。
その技術が、後の京セラ設立の基になりました。
「好きこそものの上手なれ」と言われるように、仕事を好きになることは大きな仕事を成し遂げていくためには一番大切な事だと思います。
もう一つ、仕事との関係は恋愛に似ていると思います。
自分が一生懸命に相手を好きになり、手紙を書いたり、電話したりして努力を重ねた結果、相手も自分を好きになってくれます。
少しこじ付けかもしれませんが、そんな風に思います
自ら燃える
今日は「自ら燃える」を説明します。
起業を志している人、既に起業して経営に励んでいる人には、この言葉は「何をいまさら」と思うでしょう。
でも宜しければこの後も読んでください。
稲盛さんは京セラフィロソフィの中で「物には可燃性、不燃性、自燃性のものがあるように、人間のタイプにも火を近づけると燃え上がる可燃性の人、火を近づけても燃えない不燃性の人、自分でカッカと燃え上がる自燃性の人がいます。
何かを成し遂げようとする人は、自ら燃える情熱を持たなければなりません。
自ら燃える為には、自分のしていることを好きになると同時に、明確な目標を持つことが必要です。」と言います。
成功している経営者は自燃性の人ばかりです。
自燃性の人は「勝ち気」で「常に何事に対しても積極的」な人です。彼らにあるのは責任感と使命感です。
私は「自燃性」の人と言うと第一に思い浮かべるのはイチローです。今年も200本安打を打ちました。
私の手帳に、だいぶ以前に書かれたイチローに対しての新聞記事の切り抜きが貼ってあります。
「数字を目標にすると、そこに達した後の気持ちの持ちようが難しくなる。お金を目標にしても同じこと。でも、面白いからやるという姿勢で取り組めば、そこに限界はない。そこにやる気の泉を枯れさせないイチロー流の工夫がある。イチローは『野球は趣味に近いのも』と言います。野球が面白いから限界がないのです。」と書かれています。
そしてその記事では張本さんの言葉も載っていました。「一番すごいのはあの精神力。私なんかよりずっと強い。今の人達はすぐにお腹いっぱいになる。彼は全然違うね。あれだけの富と得て、なおかつあれだけの数字を重ねていくんだから本当にたいしたものですよ。」
自分を燃え上げさせ続けることは容易ではありませんが、面白いという心の持ちようは、成功した経営者が異口同音に言っていることです。
経営がこんなに面白いモノとは思わなかった。ゴルフより、酒を飲むより、女性と遊ぶより面白いと言う経営者は多くいます。
もう一つあります。それは「目標」と「目的」を間違わないことです。
自分の「目的」が1億円稼ぐことと決めれば1億稼いだ後はもうそれ以上頑張りません。お腹がいっぱいになってしまうからです。
「目標」とはなかなか達成できないものです。
例えば「全従業員の物心両面の幸福を追求する」という会社理念はそう簡単に達成できず、会社の発展を追求し続ける原動力になります。
自燃性の人間であっても、大切なのは一時的に燃え上がるのでなく、自分が燃え続ける目標を持つことです。
そして、それが心から面白いと思えるようになる時、成功への道を歩み出すのではないでしょうか。
地味な努力を積み重ねる
「地味な努力を積み重ねる」は21日に開催しました京セラフィロソフィ勉強会で学んだ3項目目です。
稲盛和夫さんは「大きな夢や願望を持つことは大切なことです。しかし、大きな目標を掲げても日々の仕事の中では、一見地味と思われることをしなければならないものです。時には『自分の夢と現実との間に大きな隔たりがある』と感じて思い悩むことがあるかもしれません。
素晴らしい成果を見出すまでには、改良・改善の取り組み、基礎的な実験やデーターの収集、足を使った受注活動などの地味な努力の繰り返しがあるのみです。」と言います。
一足飛びに夢を叶えるような魔法はないのです。
「でも、そうは言うものの、地味な仕事を毎日毎日繰り返していると、飽きてきてだんだん嫌になってきます。
そこで私は、嫌にならない為のコツでもあり、同時に、地味な努力を加速させていく方法を自分なりに考えました。それは『創意工夫をする』事です。」とも言います。
創意工夫とは周囲の人には何も変わっていない世に見えるくらい小さなことかもしれないのです。
それを毎日続けることが大切。
京セラはその積み重ねの結果多くの特許技術も取っていると稲盛さんは言います。
ある時、大手の会社が、どうしてそんなにアイデアが出るのか聞きに来たそうです。
大手の会社には頭のいい技術者がいて、頭を使って技術やアイディアを見つけようとします。
一方、中小企業の京セラは、小さな創意工夫の積み重ねの結果生まれ技術でありアイディアでした。
頭のいい人はそれが理解できないのかもしれません。
そう言えば以前にも書きましたが、ファミリーレストランの「サイゼリア」が高利益を出せるのは、毎日の創意工夫の結果です。
サイゼリアの時給は1200円前後と高く、メニュー平均金額が500円以下、それでいて、営業利益率が10%強と言われています。
10%の営業利益は驚異的です。
そのダントツの数字を出している要因は「生産性の向上」だそうです。
掃除の時間をいかに短くするか、パスタの茹でる時間をいかに短くするか、皿洗いを無くすことは出来ないか、吸排気の状況も調べ、冷暖法費の削減にも工夫しています。
その小さな創意工夫の結果が、従業員待遇の向上と高利益率の確保につながっています。
人知れず何かをし続けることが大切ですね。
それは会社もそして個人も
真面目に一生懸命仕事に打ち込む
今日は昨日の続きで京セラフィロソフィの中にある「真面目に一生懸命仕事に打ち込む」についてお話します。
この言葉は当り前のことで、小さい頃から言われてきた言葉ではないでしょうか。
稲盛さんが言われるのは「私たちが本当に心から味わえる喜びと言うのは、仕事の中にこそあるものです。仕事をおろそかにして、遊びや趣味の世界で喜びを見出そうとしても、一時的には楽しいかもしれませんが、決して真の喜びを得ることはできません。」
またこうも言います。「『仕事だけが人生ではない。趣味や娯楽も必要だ』と言う人がいます。しかし、私に言わせると、それは、本業である仕事に真剣に打ち込むことのできない人が、その代替として、趣味などに自分の喜びを見出そうとしていだけなのです」
働くと言うことに関して、欧米人と日本人は考え方に大きな隔たりがあります。
欧米人は働くことをLabor(レイバー)と言います。
Labor(レイバー)は苦役とも言います。辛いものです。
宗教的な観念で、キリスト教やユダヤ教では労働は罰とみなされています。
欧米人の多くは早くリタイヤして年金生活をするかを楽しみにしています。
一方日本人は死ぬまで仕事をしたいという考えを持った人が多いです。
これも宗教観でしょう。
お釈迦様は「精進」ということを言われます。一生懸命に努めることです。
日本人は生活のためもありますが、もう一方一生懸命働くことで、世の為になることをし、自分の魂を磨くという喜びも見出しているのだと思います。
私も稲盛さんが言われる「人が生まれてきた理由は魂を磨くことです」という言葉は私の信条にもなっています。
明日は「地味な努力を積み重ねる」について書きます。
6回目の京セラフィロソフィ勉強会を開催しました。
昨日(21日)京セラフィロソフィの勉強会を開催しました。
シルバーウィークの狭間で、参加者は少ないかなと思っていたのでが、22名と過去最高になりました。
今回は京セラフィロソフィにある「完全主義を貫く」「真面目に一生懸命仕事に打ち込む」「地味な努力を積み重ねる」「自ら燃える」「仕事を好きになる」の5項目を学びました。
参加者交互に本を読み上げ、項目ごとに皆で考えを述べ合います。
どちらかと言うと私が少し喋りすぎるのが、反省点です。
今日から5日間、このブログで学んだ内容を項目別に紹介します。
最初は
「完全主義を貫く」
「よく90%うまくいくと「これでいいだろう」と妥協してしまう人がいます。
しかし、そのような人には、完璧な製品、いわゆる「手の切れる製品づくり」はとうていできません。
「間違ったら消しゴムで消せばよい」と言うような安易な考えが根底にある限り、本当の意味で自分も周囲も満足できる成果を得ることはできません。・・・・・」
(京セラフィロソフィ―より)
「人間完璧でないのだから間違いは仕方がない」と言う言葉を良く聞きます。私も言っていました。
でも、間違いやミスの為、製作過程にあった材料費、光熱費、人件費、そして時間を全て無駄にしてしまうことを考えると、改めて見直してみることが必要です。
「消しゴムで消す」という発想は本来あってはいけないのです。
職人の中でも名人と言われる人は、完璧な自分の製品、作品を作るに、一切のミスは許されません。
勉強会の参加者の中に紅型(びんがた)染物の女性作家がいます。
この「完璧主義を貫く」という言葉に関して、彼女は「そのために、如何にして自分の精神と体を万全にして臨むか、それが大切」といいます。
また稲盛さんは完璧は「ベスト」ではなく「パーフェクト」だとも強調します。
京セラでは材料を仕入れる時、例えば1000個製品を作る場合1000個分だけの材料を仕入れます。
一般の会社では、ミスった時の為に10個位多目に仕入ます。
ここが違うのです。
多目に仕入れれば、心のどこかに甘えが生まれ、結果ミスが発生します。
しかし、ギリギリしか材料がなければミスれませんので、真剣にならざるを得ません。
結果、無駄な材料費が浮き、利益が高まります。
材料を多目に仕入れたところは、ミスが発生してコストが膨れます。
例えミスがなくても、無駄な材料が余り、どちらにしてもコストが多くなります。
「完璧主義を貫くこと」は利益率アップにつながることなのです。
明日は「真面目に一生懸命仕事に打ち込む」について書きます。
人と人を結びつける仕事
今朝「新現役ネット北海道エリアグループ」の朝食会がありました。
10人の人が集まり、今後の活動の話し合いました。
その話の中で感じたことは、参加者の多くは人の役に立ちたいと思っている人達だということです。
特にその中でも「人と人を結びつける」や「仕事と人を結びつける」ことに興味を持っているようでした。
「新現役ネット」は始めシニアの人達を対象に始まった集まりですが、今は若い人達も参加しています。
「人と人を結びつける」仕事は、未婚者の結婚のお世話をする、昔沢山いたお節介な年寄りの役目や、目指す方向が同じ人達を紹介することも考えられます。。
「人と仕事を結びつける」仕事は若い人達の就職や起業のお手伝い等があります。
「会社と会社を結びつける」こともあるでしょう。
私の周りを見渡すと、人のお世話をし、世の中の役に立ちたいと思っているシニアの人達と、元気で何かをしたいけど何をしたらよいか分からない若い人達がいます。
この二つの年代層をつなげる事は、今後の日本を考えると大変重要な事のように思われます。
それが事業として成り立つ可能性は十分あります。
「新現役ネット」は参加者が活動の中から事業を見出していくことも歓迎です。
起業の為のステップであってもいいと思っています。
改めてスタートしたばかりの「新現役ネット北海道グループ」が活動的な団体になるよう、私も幹事の一人として、頑張っていゆきます。
参考
「新現役ネット」:http://www.shingeneki.com/
「新現役ネット北海道エリアグループ」:http://shingeneki.jimdo.com/
「損して得取れ」について
今、「共同購入クーポン」なるモノが盛んにテレビで取り上げられています。
普段はなかなか行くことが出来ないような高いレストランや割烹などの店が、客集めで行うものです。
店側はネット上で客数限定で料理等を50~90%OFFと、驚くほど安く提供すると告知し、それを、ネット上で見た人が申込みます。
制限時間内に予定人数に達すれば実施される仕組みです。制限時間内に人数が集まらなかったら中止になります。
現在これを運営するサイトが多く出来ており、店側も一度契約すれば、自店の都合でいつでも募集することが出来ます。
このシステムについて一言あります。
ある店のマネージャーはテレビの中で、この安売りを「販促の手段です。」と言っていましたが、それは間違っています。
安売りをした時に来るお客様は安いから来るのであって、通常料金では顧客には決してなりません。
そういう意味で販促にななりません。
このシステムは、お客様が来店にいただけないと予想されるような時期に合わせて、利益は少なくてもいいから、来客数を稼ごうと考え、使われるのはいいです。
また、急にキャンセルがあって用意した食材を無駄にしない為にという時もあるでしょう。
このシステムはあくまでも補助的利用にとどめるべきです。
パソコンを操作すれば、簡単にすぐお客様が集まるという魅力に陥れば、安売りの魔力につかまります。
そうなれば、お客様はその店を安い店としてしか認識しなくなり、利益は少なくなります。
従来通常料金で払っていたお客様は離れていきます。
人は良く「損して得取れ。」と言います。
その意味するところは、「得をしたいと思うモノ以外はすべて損をせよ。」と言う意味と考えます。
会社でいえば、利益と言う「得」を得る為に、買いたいモノを買わずに経費を削減しようと我慢をすることです。
利益を「損」するという安易な安売りは、「損して損になる」ばかりです。
現在はデフレ経済と言われ、安くしないとお客様は来てくれないと言われますが、安易に安い売りをしない我慢が必要です。
デフレ経済はガマン経済かもしれません。
目標設定
仕事を一生懸命仕事をしている時、1日終わって「フッ」と思うと、何の為に仕事をしていたのかわからなくなる時があります。
それは、その日の目標が明確でないからです。
もっと大きく言えば、会社の目標が明確でないからかもしれません。
目標があっても目標の意識が希薄になる時があります。
希薄になっても、それを防ぐ方法を作ればいいわけです。
大事なのは会社が進む方向である目標を明確にすることです。
楽天の三木谷社長のいい言葉があります。
「月に行こうという目標があったからアポロは月に行けた。飛行機を改良した結果、月に行けたわけではない。」と言う言葉こそ、目標の大切さを言い得ているのではないかと思います。
単に毎日一生懸命仕事をしたから、何となくいつの間にか会社が良くなって行くのではないのです。
旅行をする時、行き先と言う目標が必要です。
目標のない旅は「流れ者」になり、放浪の旅です。風来坊です。
風来坊にならないよう、目標を明確にし、それを意識する仕組みを作りましょう。
これは改めて自分に言っている言葉でもあります。
「よそ者」の力
昨夜ある集まりがあり出席してきました。
25名ほどの人達が集まっての会です。
男性は5名ほどで、ほとんどが女性でした。
女性は人生経験を経た人が多く、団塊世代の人も多いようでした。
皆で30分ほど食事をし、その後メインゲストによるスピーチがありました。
スピーカーは「young(ヤング)」という健康飲料を作っている、ヤングブレイン(株)の鍬塚なほみ社長です。
鍬塚社長は三重生まれで、湘南で住んでいたそうです。
2年前の59歳の時、会社のオーナーから社長を任され北海道に来ました。
ヤングブレイン(株)は60年以上社歴があり、数多くの特許を保持し、ヤングと言うの1種類の健康飲料しか製造販売していません。
国内はもちろん、海外にも顧客がいるそうです。
鍬塚社長は仕事柄、健康のことに関してはしっかりした信念を持っています。
お話しの中で、健康で大事なのは「小さな便り」と「大きな便り」と言います。
体からの排出のことです。
それと「睡眠」です。
また、北海道で、会社の発展を目指すとともに、若い人達を育てていくのも自分の仕事とも言っています。
鍬塚社長は他の土地から来た
「よそ者」です。
「よそ者」は悪い意味で言っているのではありません。
昔から、その土地で何か新しいことを始める人は
「よそ者」「バカ者」「若者」と言われます。
その土地の慣習や縛りに束縛されないで、行動できる人を指しているのでしょう。
「バカ者」も大事です。大きなことをする可能性があります。
残念なのは「若者」です。
最近の若者の中には現状維持型の人が多いようです。
逆に団塊の世代の人には元気な人が多いです。
鍬塚社長もそうですが、私もそうです。
若者に元気を与え、時には一緒に行動する団塊世代の人達が増えることを期待しています。
一度、このピラミッド型工場に訪問して、ピラミッドパワーを受けてみようと思います。
鍬塚社長のようにパワーあふれる人間になれるかもしれませんね。
ピラミッド型工場

現場で確認する
昨日のブログでは「上に立つ者は率先垂範が大切」と書きました。
今日はそれに関連したことになります。
会社が少し大きくなってくると、なぜか社長は勘違いします。
自分は優れた社長で、何でも分かっていると思うのです。
本来社長は、「商品開発」「マーケティング」「財務」「営業」等、全ての分野に渡って現状を掌握しなければなりません。
担当責任者から話を聞きその情報を基に判断し、決断します。
会社が小さいうちは全て自分で確認しました。
それが会社が大きくなってくると権限の委譲が必要となり、担当責任者に任せます。
それは会社の拡大過程では必要な事です。
でも、勘違いする社長は、社長室から一歩も出ず、担当者からの報告を求めます。会議ばかりになります。
自分が納得するまで全ての情報を持って来させます。
会議ばかりですから、自分は凄く仕事をしたように思います。
その分担当責任者は社長の要求に応える為に奔走します。
それによって莫大な時間が費やされ、動きの遅い会社になり、世の中の流れに取り残されてしまいます。
社長が現場に出ればいいのです。
社長自身がお客様の声を聞き、研究員と話し、工場に足を運び、現状を把握すれば無駄な時間を費やすことはないのです。
社長が少し自分が偉いと思うと、社長スタッフを充実させようとします。。
私の好きな言葉があります。ソフトバンクの孫社長が言っていた言葉です。
「信じるな!疑うな!現場で確認せよ!」
現場中心の言葉です。社長の心得でしょう。
別の問題として、率先垂範をしない管理職もいます。
自分の仕事を抱え込んで、指示ばかりしています。
なぜかと言うと、現場で確認する時、技術的知識がない為、怖くて現場の担当者と話が出来ないからです。
昔ある人に教えられました。
「会社に入って一生懸命勉強しなければならない。その目的は、上に上がる為でもあるが、下に下がる為でもある」と
その意味するところは、上に上がる為とは昇進のためです。
下に下がる為とは、現場の人間と対等に話が出くるように現場の勉強もしなさいと言うことです。
会社の活性化は、社長以下管理職が率先垂範で行動した時、とてつもない力が生まれるのではないでしょうか。
「寝ていて人を起すな!」
「寝ていて人を起すな!」と言う言葉は、以前新聞の記事にあった潮田健次郎氏の言葉です。
いい言葉だなと思って私の「銘肝録」に書いておいたものです。
潮田氏はご存知の方も多いかと思いますが、現在のトステム(旧トーヨーサッシ)の創業者です。
「寝ていて人を起すな!」の意味するのは、「寒い朝、自分は温かい布団の中にいて、小僧さんだけを起すような事は絶対してはいけない。」ということです。
自分は楽な事をして、社員に厳しい要求ばかりする経営者になるな!と言うことです。
上に立つ者がよく陥りやすい心理を突いています。
この言葉は、読んだり、聞いたりすると「そんなこと当り前じゃないの」と思うでしょう。
でも、出来ていない経営者は結構います。
私の周りにもいました。
その社長は「うちの会社は社員の自主性を生かして、自由にさせているんです。」と言います。
そして彼はゴルフ三昧です。
確か1年に130回程行くと言っていました。
北海道は雪が降ります。ゴルフが出来る期間は限られています。せいぜい7カ月間でしょうか。
計算すると月平均18回、週平均4~5回行く勘定になります。
その上、彼は週末は行かないんです。と言いますから、行くのはウィークデーとなり、毎日ゴルフということになります。
社長としての仕事をしていないのです。
その会社は常に人の入れ替えが多いそうです。
業績も伸びていません。
「あまりにもゴルフに行きすぎ、社長としての仕事をしていない」と一度、私も指摘したことがありますが、変わりませんでした。
彼も稲盛和夫さんの盛和塾の塾生でした。今は退塾しました。
稲盛さんは、社長は常に先頭に立って経営しなさいと言います。率先垂範です。
一般によく言われることですが、社長は常に全体を見通して、正しい判断が出来るようにするために、後方にいて指揮を取るべきと言う人がいますが、稲盛さんはそれを否定します。
時として後方に下がることはあるが、社長は常に先頭にいるべきと教えてくれます。
社長が一所懸命働かないと、誰も働きません。
石川島播磨重工や東芝の社長を経験し、経団連、臨時行政調査会会長を歴任した土光敏夫氏は「社員は今までの3倍働いて欲しい。重役は10倍、私はそれ以上働く」と言った有名な言葉があります。
土光さんも私の尊敬する経営者です。
率先垂範するためには責任と努力が必要です。
社長は何の為に働くのか!その目的を明確にしなければ、その地位と権力で楽な方に流れてしまいます。
心しましょう!!
「小さく纏まるな!」
昨日若手経営者が来社されました。
まだ20代ですが、既に起業して5年、20名の社員がいる会社の社長です。
その時お話ししたことです。
以前にもブログで書いたことかもしれませんが、ドトールコーヒー創業者の鳥羽博道さんの話です。
日経新聞の私の履歴書の中に書いていました。
何かに機会があって、上司とよく料亭に行っていた時のこと。
ある芸者さんから言われました。
「鳥羽さんは、まだ若いのにとってもしっかりしています。でも、周りからそう言われるがために、自分自身を小さくしてしまうかもしれませんので、気を付けなさい」と
この言葉に対して鳥羽さんは「昔の芸者さんの厳しさに触れた思いがした。この言葉は私の脳裏に焼きつく言葉となった。」と書いてありました。
若いうちは「小さく纏まるな!」ということでしょう。
似たようなことはよく聞きます。
私の家内は若い頃絵を描いていました。
本人の話しでは、結構先生に評価されていたようです。
その先生から、若いうちは絵の審査会などに出さない方がいいと言われたそうです。
なぜかと言うと、まだ伸び代(のびしろ)がある内に出品し、それなりの評価を受けると、それに影響され、技法が固まって、伸びなくなるそうです。
どちらの話も、若いうちは思い切ってチャレンジすることが大切と言うことです。
「するは自分の責任。評価は他人の勝手」です。(私が作った言葉でよく口にします)
人の顔色を見て、行動するのは年を取ってからです。
年を取った時は、晩節を汚さないようにすることがありますが、若いうちは自由に挑戦してください。
人に迷惑をかけるることをしなければ、何をしてもいいでしょう。
昨日来社した若い社長にも私は期待をしています。
頑張れ若者!!
「商い」
先日上京した時、浅草寺へ行ってきました。
日中は別件があり忙しいので、朝の9時頃お参りに行きました。
私は以前から浅草寺と、その界隈が好きで、上京すると必ず行きます。
浅草寺の参道には仲見世が並んで、何時も観光客でにぎわっています。
今回私が行った時は朝の9時ですからまだ観光客もまばらで、店も開店の準備中でした。
仲見世を歩きながら、改めて考えることがあります。
小さな店でも、こんなに観光客が来るのだから、沢山儲かっているのでしょう。
儲かる仕事をするのは嬉しいモノですが、し続けると言うことは結構大変なことではないです。
朝から晩まで同じことを繰り返しますから、1年や2年ならいいでしょうが、5年10年と経つといくら儲かっていても飽きてくるものです。
仲見世は常連客は少なく、毎日違うお客様相手なのだけれど、毎日の仕事に飽きてきます。
儲かっていない時はそんな余裕はありませんが、儲かっているから起きる心境です。
それでも同じ仕事を親子代々続いている店もあります。
それは昔から言われるように、商売は商い(飽きない)なのでしょう。
時として、飽きに我慢できず、安易に新規事業とか事業拡大をすると、失敗し、儲かっている店さえ手放すことになります。
ここで重要なのは、商売の目的が明確かどうかです。
新規事業をするにしても、事業拡大するにしても、もっと儲かりたいとか、面白いことをしようと思うと失敗します。
お客様のことを第一に考え、お客様の為に事業を展開すれば成功の確率は高くなります。
老舗とは飽きずに商いをし続けたから、生き延びて来れたし、お客様のことを第一に考えたから常に工夫を考えてきました。
老舗と言えど、変化しなければ生き残れません。変化するのはお客様を考えた上で変わるのです。
お客様は時代と共に変化します。
お客様の変化を一歩先に感じ取り、店も変化するのです。
お客様を忘れた時はどのよな店、会社でも生き残ることはできません。
老舗は昔から事業の目的である「掟」(おきて)を明確にして来ました。
あの「虎屋」にも「掟書」と言うものがあるそうです。
最後に残念なことが一つ。
浅草に来るといつも食べていた「大黒屋」の天丼が今回は食べれませんでした。
銘肝録
「銘肝録」と言う言葉は初めて聞くと思います。
私が勝手に作った言葉で、私のノートに付けた名前です。
常に持ち歩いています。
これは名の通り、自分の肝に銘じる大事な言葉を書きとめたB6サイズのノートです。
10年ほど前から書き留めて、4冊目になります。
最初は1冊目から始まり、2冊目からは合冊してゆき、今は4冊が1冊になっています。
厚みは2cm位ですが、常に持ち歩き、時間があれば読み返ししています。
どのような事を書いているかと言えば、いろいろな言葉や情報です。
新聞、雑誌、本を読んでいて「いい言葉だな―」と思ったら書き写します。
時には新聞記事も小さければ、そのものを貼り付けます。
少し書いた内容を紹介します。
◆「人のお世話にならぬように
人のお世話をするように
そして酬(むく)いを求めぬように」
(後藤新平の言葉)
◆士、三日会わざあれば、刮目(かつもく)して、あい待つべし。
(三国志より)
◆悪魔はニコニコして近づいてくる
(稲盛和夫さんの話から)
◆出来ない理由を聞く暇はない。
どうすれば出来るかを言ってくれ
(スズキ社長 鈴木修氏)
◆生きていく上で必要なのは「夢」と「勇気」と「サムマネー」
(チャップリン)
私はパソコンもiPadも持っていますが、携帯性と見やすさから言えば断然ノートですね。
私はこのノートを常に持ち歩き、何かあったら読み返しています。
そして勇気と、慰めをもらっています。
最近、もう一つノートを作りました。
これにはまだ名前は付いていませんが、統計、データ、グラフなど大事だと思う資料を貼り付けたノートです。
同じようにA6サイズの大きさです。
何を張り付けているかといえば
例えば
◆「日本の失業者数・失業率の推移」
◆中小企業業種別1人当たりの年間粗利益
◆「結婚と年収の関係、所得が高いほど結婚データー」
◆「農業人口の推移表}
◆「1人事業所が増えている主要業種」等
あくまでも自分が興味あるモノだけです。
日常多くの情報が氾濫している中で、大事な言葉が知らずうちに流されて、気が付いた時はもうすでに見えなくなっていることが多い中で、言葉や情報を拾い集めたモノがこの2冊のノートです。
自分にとって大事な言葉や情報を集めた、
「自分だけの宝物」を作ってみてはいかがですか?

農業はサービス業?
「農業はサービス業」という概念はマーシャルが言った言葉です。
ある本に書かれていた言葉です。
マーシャルはイギリスの経済学者でケインズやサミュエルソンの先生でもありました。
「農業はサービス業」が意味するものは、モノを見る時、一つの見方だけでなく、色々な視点で見ることが出来、それが重要である。ということが再認識させられました。
マーシャルはこう言いました。
「農業をする人は、われわれは小麦を作って人々にパンを与えていると言うが、小麦の実を作っているのは小麦自身である。農民がしていることは肥料をやったり、草を取ったりだから、農業は小麦の親に対するサービス業である」と言う意味です。
また漁師に対しても「漁業をする人は魚をとってきて台所を豊かにしていると言うが、魚は元々海中にいるから、水産業者は魚を海中から海上に引き上げ、さらに都市まで持ってくる垂直と水平の輸送業者である。」と言います。
マーシャルが言っていることは極論に近いですが、当たっています。
経営者として、自らの事業内容認識を問うてみると、固定的にとらえていることに気付かされます。
それでは、世の中の流れに置いていかれる可能性があります。
例えば、下駄屋さんは昔よくありました。着物が主流の時は街には必ず一つはありました。
それが着物がすたれ、洋服を着る人が多くなってくると、下駄屋さんは商売がうまくいきません。
でも自社を「下駄屋」から「履物屋」ととらえてみると、靴も売れるし、サンダルも売れます。
自分の仕事範囲をがんじがらめに縛りつけていることが良く見受けられます。
家具のニトリは最初は私が住んでいる札幌の手稲区にあった小さな家具店でした。
それが家具店からインテリアショップに変わり、海外で生産する製造業になり、製品を国内に持ってくる輸入業者になりながら、どんどん変化し続けています。
ニトリは今自社を家具店とはとらえていないはずです。
経営者はなるべく固定観念にとらわれない為にも、多くの人の話や情報を集め、声を聞く行動こそが重要な仕事です。
特に起業したばかりの人は、独りよがりに陥りやすいですので、多くのネットワークを持ち、アドバイスを受ける心の余裕はとても必要なことです。
「棒振り」
2人の起業家を紹介します。
一人は55歳の男性で、今年の初めにエステサロンを開業しました。
しかし、うまく行かず毎月40~50万円も赤字で8月閉店しました。
本人はまだ続けたかったようですが、コンサルタントの意見で閉鎖する決心したようです。
彼はその報告に私のところに来ました。
今後のことを聞くと、まだ起業に興味があり再挑戦したいようです。
失敗した原因は私たち周りの人はわかりますが、本人はよく理解していないみたいです。
彼の話を聞くと、奥さんは起業の時反対したにもかかわらず、彼はそれを押し切って始め失敗しました。
奥さんにしてみれば、今後は就職して地道に生活していきたいという希望のようです。
私はその話を聞いて、最大のパートナーである奥さんの言われるように、今はリセットして、就職した方がいいと話しましたが、受け入れられませんでした。
彼は起業した時に知り合った人達とのネットワークを生かして、また起業を探したいと思っているようです。
就職についても彼は「私は年だから就職できるのは『棒振り』しかないです」と言います。
「棒振り」とは工事現場などで誘導棒を振って人や車の誘導をする仕事で、年配の人が多いです。
月に約15万円位の給料だそうです。
もう一人の起業家は40歳代の男性です。
彼は就職しようとした時「棒振り」の仕事さえ断られたと笑って答えました。
彼は真面目で、大人しく、自己主張がうまく行かず断られたのでしょう。
でも今はIT関連で起業して、彼の真面目さと優しさでお客様を増やしています。
同じ起業家でも、一人は「棒振り」の仕事を嫌がり、一人はその「棒振りの仕事」さえ出来なかったのです。
カッコ悪いからとか、給料が安いからと言って、そのような仕事を避けている人達がいます。
一方、そのような仕事でも一生懸命に働き、家族を養い、子供を育てている人達がいます。
仕事を避けて人達には失業手当や生活保護を受けて生活しています。
どんな仕事なでも一生懸命頑張っている人達がいるのに、それを嫌だと避けている人達に保護の手が差し伸べられています。
どう考えてもおかしいです。
どのような仕事でもやり遂げる人は起業した仕事がどのようになっても頑張ります。
いくらカッコ悪くても頑張ります。
カッコ良さを求めて起業する人は、地道に努力しません。
私の父の話しをします。
私がまだ赤ん坊の時、父の会社が人に騙されて、会社がダメだという時、母に言ったそうです。
「自分は炭鉱に働きに行ってお金を稼ぐ。それで再度挑戦する。それまでお前は畑を耕して生活し、子供を育てて待っていてほしい」と
当時は炭鉱の仕事はきつかったけれど給料が高かったそうです。
幸いそのようにならず会社は持ち直しました。
起業したからにはカッコ良さを求めす、どんなに見た目が悪くてもやり抜くことですね。
ギフトショー
昨日まで東京出張していました。
帰札の前にギフトショーに行ってきました。
このギフトショーはビックサイトを全館使用しての大規模なモノです。
出店数が多すぎて半日では三分の一程度しか回りきれませんでした。
出張を1日伸ばせればと後悔しました。
このショーを見る為だけに出張してもいいかもしれないと思わせるほどでした。
私は数年前まで東京勤務していましたので、東京で行われる展示会やショーは出来るだけを見て回るようにしていました。
そこでヒントを頂き、仕事にも生かされました。
私の周りにもこのような展示会やショーに積極的に出ていく人と、そうでない人がいます。
概して、野次馬根性が旺盛で、新しいモノ好きな人がよく見に行きます。
また、見に行っても、見て終わりの人と、それを仕事に生かせる人とがいます。
私は色々な刺激やヒント探しにこのよな展示会やショーには積極的に行きべきと考えます。
見て回り、「これはと!」思うものを展示している会社の人とその商品開発の裏話を聞くと大変参考になります。
自社の製品・商品に取り入れるヒントもあるかもしれません。
「オズボーンのチェックリスト」をご存じでしょうか?
知っている方も多いと思いますが、念のためご紹介します
1.他に利用したらどうか
2.アイデアを借りたらどうか
3.大きくしたらどうか
4.小さくしたらどうか
5.変更したらどうか
6.代用したらどうか
7.入れ換えたらどうか
8.反対にしたらどうか
9.結合したらどうか
例えばこのような「オズボーンのチェックリスト」を頭に浮かべながら見て回ると、自分の仕事に生かせるものが一つや二つは見つかるものです。
このギフトショーは10日、今日まで開催しています。
間に合う人は行ってみたらいかがですか?
仕入先を接待する
今日は「仕入先を接待する」について説明します。
一般には売上を上げるために、時として接待が必要になります。
私共の家具製造会社は昔、家具卸会社に売り込む為、頻繁に接待がしていました。
先方からの接待要求が当り前のように来る世界でした。
接待しなかったら、売上を上げるのが困難な業界でした。
今は時代も変わって、それほどでもありません。
この例は「得意先接待」です。
今回の「仕入先接待」というのは、時々仕入先の担当者をお昼にご馳走して上げることです。
食事程度ですから安いものです。
でも、仕入先の担当者にしてみれば、自分が接待するのが当然なのに、ご馳走になることに対して、恐縮してしまいます。
普通はしませんから。
そのように仕入先を大事にすると、思いがけない情報や、いい商品を持ってきてくれます。
自社の味方を増やすことになります。
万が一支払いが遅れるような時にも相談に乗ってくれます。
あまり他社がしていない「仕入先接待」は効果的な情報収集活動です。
ただし、この時重要なポイントがあります。
それは「親交は深めます」が、決して「甘やかさない」ことです。
「甘やかす」と「馴れ馴れしく」なります。
「馴れ馴れしく」すると、馬鹿にされます。
馬鹿にされると、いい商品を持って来ません。
他に回せない悪い商品を「あの人は『いい人』だから文句言わずに受け取ってくれる」と言って平気で回してきます。
これも実際にあった話です。
何事においても「けじめ」が大事です。
第一線を越させると、土足で入り込んで来ますので、その点は気を付けてください
リサイクルショップ
今日は起業・商売に関する情報について書きます。
先日新聞を見ていましたら、あるリサイクルショップが日本の中古家具などを販売する店をタイに作ったとありました。
「なるほど」と思いました。
私の会社は家具製造会社もありますので、家具には興味があります。
近年は海外の家具の輸入が盛んです。
中国から安い家具、ヨーロッパからは高くてもデザインのいい家具が輸入されています。
もう一つ輸入されているのは中古の有名デザイナー家具です。
この中古家具だとデザインのいい家具が新品の50%~70%位で購入でき、若い人達に人気があります。
今回の新聞記事は逆に日本の中古家具を売るというものです。
日本には多くのサイクルショップがあります。
そこにあるインテリアや家具類は私たち日本人にとっては見慣れて、特に欲しいと思うものが少ないです。
しかし見方を変えて見れば、外国の人からは珍しいものとして映るでしょう。
日本のモノは品質もいいです。
例え中国産のものでも、日本人の好みに合わせて作られたモノはそれなりに質が高いです。
一度周りにいる知合いの外国人をリサイクルショップに連れて行き、彼らの感想を聞くと面白い反応があると思います。
輸出する時、気を付けなければならないのは税関の問題でしょう。
税関がスムーズに通過する国とそうでない国があります。
タイならスムーズでしょうが、現在の中国は結構問題が発生し易いでしょう。
最後に日本人の見方と、外国人の見方では、同じものが全く違うモノとして映る例を書きましょう。
それは仏壇です。
以前にも書いたかもしれませんが、仏壇をアメリカ人がインテリア家具として、クローゼット代わりにしていると聞きました。
ある日本人は中古の仏壇を高い値段でアメリカに売っているそうです。
普通の日本人にして見れば「エッ」て驚くことだと思います。
罰が当たると思ってしまうでしょう。
改めて自分の身の回りを見回してみませんか?
自分が気が付かないモノに商売のネタがありそうです。
父からの教え
今日は父から教えてもらったことを書きます。
父は現在92歳です。
自分では2代目だと言っていますが実質創業者です。
20歳そこそこで地方から札幌に出てきて、当初はコンクリートで瓦や便層などの製品を作りました。
その後木材店、家具工場、商事会社、ホテル等と会社の規模を広げてきました。
最近その父から教えられたことを思いだします。
私がまだ小学生の時だと思います。
父がら質問されました。
「お前が家具工場の社長であったとして、ある日品物を卸していたお店が倒産するといううわさを聞いたので、
そのお店に行き、製品を引き上げようとした時、その店の社長と奥さんが『それを持っていかれると明日から生活できない』と泣きながら言われた場合お前はどうする?」と聞かれました。
私は、「かわいそうだから半分置いて、半分持ってくる」と答えました。
父は即座に「ダメだ。相手が泣いても、わめいても全て引き上げなければならない。」と言いました。
その理由は「もしも、その店の社長達が可哀そうだから言って、商品やお金を回収しないと、お前の会社がそれにより倒産するかもしれないのだぞ。」と言うのです。
当時、私はその話を聞いて、会社が倒産するということは大変怖いことだなと言う思いしか残りませんでした。
それから数十年経って、私が経営に携わって、改めて思い返すと、あの時の質問は社長の責任の重さを教えてくれたように思っています。
いざとなれば、社長として情に流されず、人でなしと言われても、身体を張って、会社を守り、従業員を守らなければならない覚悟を教えられたように思います。
父は当時同じような事を経験していたのでしょう。
勿論、50年近く前のことなので、今の時代と違う環境ですが、社長の心構えは変わらないのかと思います。
また、これからも私のブログの中で、父から教えられた事を書いてみます。
琴似神社
9月4日5日は琴似神社のお祭りです。
琴似神社は私の住んでいる琴似にあり、北海道では古い神社です。
そして琴似は明治の時に屯田兵が初めて入植したところです。
祀られている神様は「天照大御神」「豊受大神」「大国主命」「武早智雄神」「土津霊神」です
他では見られない神様がいらしゃいます。
この神社に最初に祀られた神様は、屯田兵の多く人達の出身地であった仙台藩亘理(わたり)伊達氏の祖
伊達成実「武早智雄神」でした。
また、「武早智雄神」は会津藩の始祖の保科正之を神格化したものです。
この2神は北海道の開拓の状況を表しています。
4日の昨日は宵宮、今日は本祭です。
私も宵宮祭に呼ばれてその行事に参加してきました。
神様が神輿に移る時は全ての灯りを消し、神主が「オー、オー」と声を出す中、ひっそりと移ります。
移る姿は参列者は皆が頭を下げているので見ることはできません。
今日は本祭り。私はこれから裃行列に出ます。ただ歩くだけです。
私たちの裃行列の前には、お稚児行列が歩きますので、大変可愛いいです。
私はいつも思うのです。
自分の住んでいるところの神様に好かれないと、家庭も仕事もうまくいかないと。
起業する人によく話しをするのは、商売をする時は「その場所を好きになること」と「その場所の神様に好かれること」が大事だということです。
さあ、これからお祭に行ってきます。
参考
屯田兵(とんでんへい)は、明治時代に北海道の警備と開拓にあたった兵士とその部隊である。明治7年(1874年)に制度が設けられ、翌年から実施、明治37年(1904年)に廃止された。(ウィキペディアより)


「新北海道時代」
最近は温暖化が進んだせいでしょうか、暑い日が続きます。
北海道・札幌の今年の夏は特に暑いです。
9月になっても気温が下がりません。
温暖化のせいか、植物や海の生物に影響が出てきているようです。
ただ、温暖化と言うとマイナスの面が強調されますが、プラスの面もあります。
いまさら言うことでもありませんが、北海道は農業国です。
それが温暖化により、もっと農業に向いた環境になってきています。
聞いた話ですが、北海道中央付近の気温は、50年ほど前の新潟の気温と同じになってきたそうです。
現在、コシヒカリやササニシキより美味しいと言われるお米が北海道で生産されています。
北海道米「おぼろづき」や「ふっくりんこ」がそうです。
農業とは別に運輸という面もこれから見直されそうです。
アメリカに飛行機でモノを運ぶ時、千歳空港から運ぶ方が成田から運ぶより距離が短かくコストも安くなるそうそうです。
その他に船もそうです。
以前から検討されてきたそうですが、温暖化で北極海の氷が解けてきたため、アジアとヨーロッパを結ぶ「北極海航路」が開拓されています。
アジアとヨーロッパをつなぐ航路は、現在スエズ運河経由ですがそれに比べ時間もコストも安くなります。
日経新聞の記事によりますと距離が3分の1(約10日)、燃料代も50万ドル(4200万円)節約できるそうです。
温暖化により北海道は農業ばかりでなく運輸基地として見直されてくることなるでしょう。
これから10年後の北海道は今まで以上に、皆があこがれる土地になっていると信じています。
ぜひとも北海道人がその推進の担い手になってほしいものです。
美味しいところを他の人に持っていかれないようにしましょう。
「新北海道時代」がもう始まっています。
「笑顔」
今日は笑顔について書きます。
仕事をする時、特にサービス業の人にとって笑顔は大切です。
私も以前ホテルの支配人をしていましたが、常に笑顔でいる為には努力が要ります。
ある人は笑顔を続けることは「筋肉の問題だ」と言った人がいます。
でも、作られたものでなく、自然に出てくる笑顔にはそれなりのコストが掛かるのです。
ホテルの場合です。ホテルの社長や支配人は部下に対して常に笑顔の大切さを話し、笑顔でいることを求めます。
しかし、そう簡単に作れません。
それは、お客様に対するホテルスタッフの対応は、ホテルの上司とスタッフとの対応に比例しているからです。
それなりの給料をもらい、待遇も良く、ホテルの上司とスタッフが共に笑顔でいれる環境が、そのままお客様への笑顔になっていきます。
逆に給料も安く、勤務状況も厳しく、常に命令されてばかりいる環境では笑顔が出ません。
いくら強制されても出て来ません。
そういう意味で笑顔にはコストが掛かるのです。
笑顔についてもう一つ
スーパーやコンビニへ行った時感じるのですが、笑顔が無いのです。
スーパーやコンビニの店員ではありません。
お客さんです。
お客さんがレジの前で無表情で黙ってモノを置き、お金を払い、黙って帰ります。
「お願いします」とか「ありがとう」とかの言葉も無く、無表情です。
見ていると怖い気持になります。
お客さんが「ありがとう」と言えば、店員はとても嬉しいものです。
「ありがとう」と言うと損するとでも思っているのでしょうか。
最近知ったのですが、アメリカアイダホ州にある「ポカテロ市」には「笑顔条例」があるそうです。
笑顔条例
1条 ポカテロ市民で不機嫌な顔をしているものは罰せられる。
2条 笑う習慣を身に付ける為、毎年「笑顔週間」を設ける。
3条 笑顔係を新設して、笑わない人を逮捕する特別官を置く。
4条 条例に違反した人は「笑顔作りの講習」を受けること。
こんな街があるとは知りませんでした。
笑顔があふれている街って素敵ですね。
皆さんも一度行ってみたいと思いませんか?
お客様は神様?
昨日、来社された人と「お客様に対しての対応」について話しあいました。
「買い物をした人はお客様であり、お客様の要求は全て聞くべきかどうか」ということです。
来社された人は、あるコンビニの駐車場で30分ほど駐車をしたので、そのお詫びの気持ちで買い物をしたら、コンビニの店長から「長時間駐車されると困る」と言われたそうです。
駐車した本人にしてみれば、お詫びの気持ちからコンビニで買い物をしたし、買い物したからは自分はお客なのでお客の駐車は許されるべきだ」と言うのです。
私は違うと思うのですが、なかなか納得してくれませんでした。
私が住んでいるこの地域のスーパーの駐車場は大きく、2時間・3時間は無料になっています。
そのためスーパーは空いているのに、いつも駐車場が混んでいます。
スーパーに関係ない他の用事で駐車している人が多いのでしょう。
初めはスーパーは買い物をしたお客だけ2時間・3時間の駐車を無料にしたのです。
でも今は買い物をしない人でも無料になっています。
その理由は「買い物をしようと思ったけど、お宅のスーパーではいいものなかったから買わないで帰る。それなのに駐車料金を払うのはおかしい」と言う声に押されて無料にしているのです。
でも実際はスーパーを使わないで駐車している人が多いのです。
この駐車場建築の投資額や維持費を考えると大変大きな金額になります。
スーパーは「理不尽」と思えるような神様の声に応えていかなければならないのでしょうか?
結果として、この「理不尽」な要望がコストに跳ね返り、消費者に返ってくるのです。
それともかスーパーの仕入れ業者に波及していくのかもしれません。
今の消費者の中には「お客が言うことは絶対である」とか「お客は神様だ」と言ってる人がいます。
「お客は神様である」という言葉は、本来、業者側が仕事をする上で心する言葉でした。
お客様から言われるモノではありませんでした。
「自分は神様」とはなかなか言えない言葉です。でも言っているお客様が多いのは事実です。
残念な気持ちと、日本人がここまで変わってしまったかというさびしい気持ちです。
そして、そんな日本人に自分もなっていないかと自問しています。
医療費の増加
今日は起業や経営とは違う話をします。
私の義弟は外科医で、本州の大きな病院で働いています。
先日1週間ほど家族たちと一緒に遊びに来ました。
彼は救急医療現場の責任者なので、この1週間の休みは楽しみにしていたようです。
ある日彼と飲んでいる時、医療費の話しが話題に出ました。
医療費が増えているのは高齢化が進んでいることが一番の要因です。
その時義弟が言ったのは
「医者が儲け過ぎていると言われるけど、一番儲けているのは製薬会社だ」とのことです。
確かに製薬会社は儲けているだろうとは、私も思っていました。
しかし少し話を聞いてみると考えさせられることがありました。
ガンの患者を例に出しましたが、ガンの患者の治療をしようとすると、最初に検査しそして手術をします。
その費用は100万円かかるとすればそれは病院の収入になります。
本当にお金が掛かるのはその後の薬代です。何百万円もかかるそうです。
また、ガンの患者では手術しても助からないという人もいます。
そのような人にも薬を投与して治療を続けます。
その薬代も高いものです。
でもその薬を投与しても助かりません。
義弟が言うに、医者から見てそんな高い薬を投与してもほとんど効き目がないとわかっていて、患者の家族の負担が重いと思っても、医者の立場から、「無駄だからやめなさい」とは言えないのです。
確かに私の父も前立腺がんで薬を頂いていますが、保険がきいても1錠が1千円以上支払します。
父はお陰様でまだまだ元気ですが、薬で効いているのか、老人になので、進行が遅れているか分らないそうです。
平成17年度65歳以上の高齢者の医療費は16.8兆円で全体の51%になります。
今後ますます高齢者向けの医療費が掛かります。
私も4~5年で高齢者になります。
財政負担が大変の日本、これからの若い人達への負担を考えると、複雑の思いで義弟の話を聞いていました。
経営者の姿
「理想的な経営者の姿は?」と問われれば、色々な答えが返ってくると思います。
「常に夢を追いかける」「熱い情熱を持っている」「常に冷静な判断をする」等もあるでしょう。
常に「ニコニコしていて優しい」というのもあるかもしれません。
一方「中庸」という言葉があります。
「中庸」とは偏らず、とらわれない心という意味です。
社長は常に「中庸」な心でいなければならないと言われる事もあります。
でも、この「中庸」の心境に社長がなれるかと言うと大変難しいものがあります。
私は以前社長は究極的にはこの「中庸」こそが理想だと思ったことがありました。
でも今は違う考えを持っています。
社長は人間的でなければならないとい思います。
時には怒り、ときには喜び、時には泣くような人間味がある社長でなければ人はついて来ません。
でも、喜怒哀楽が激しい人も社長としてだめです。
私が社長として素晴らしいと思える姿は「溢れるばかりの情を持ちながら、ときには冷徹な判断と決定が出来る」姿です。
それは自分の感情を極端な方向に走らせるのでなく、常に状況判断に応じて判断出来る心の在り様です。
私の知っている「成功している社長」を見てもそのような傾向が見えます。
「5W1H」から「5W4H」へ
「5W1H」はよく知られています。
知っている方が多いともいますが一応説明します。
①「What」:何を
②「When」:いつ
③「Where」:どこで、どこへ
④「Who」:誰が 誰と
⑤「Why」:なぜ
①「How」:どのように
以上の6つです。
これはどのような分野においても計画時にチェックする重要な項目です。
これにプラス「3H」を加えます。
「How many」:いくつ
「How much」:いくら
「How long」:どれくらいの期間
です。
事業をする者にとって「どのくらい売れ」「いくら儲かる」のか、そしてそのための「期間はどのくらい」必要なのか。
これは事業計画を立てる上で必要な項目です。
最初の「5W1H]はビジネスプランを考えるときに必要な6項目です。
それをより具体的な計画に落とし込む時に「3H」が必要です。
これを頭に入れておくと、ビジネスプランや事業計画を作る時大変便利です。
よろしければお試しください。
相手を選ぶ
「相手を選ぶ」とは自分や自社の取引先のことです。
ある人が言っていました。
「下手な選手と上手な選手がプレーすると下手な選手は上達するが、上手な選手は下手になる。
これは個人でも会社でも同じです。
会社でいいますと、自社ががこれから大きくなりたいと思う時は、優れた考え方・理念を持ち、そして伸びている会社と取引するべきです。
そういう会社は要求が厳しい会社です。
仕入先として厳しい会社と取引する時は、とことん厳しい品質管理、価格交渉、特異性等を求められます。
でも、その要求に必死に追いついていくと、いつの間にか自社も成長して行きます。
そして、そのような厳しい会社に育てられると、他社と取引する時は余裕をもってその要求に答えられます。
私がよくお話しする「小善は大悪に似たり。大善は非情に似たり。」そのものです。
非情だと思われるよな要求に必死に応えることが会社の成長になるのです。
昔に読んだ本の中で、松下幸之助さんが製品のコストダウンを図る時のことが書かれていました。
コストを下げるために、仕入値交渉をその会社としますが、その会社がこれ以上下がらないと行ったとき、幸之助さんが直接その工場に乗り込んで行き、工場を廻り、その会社の社長に無駄を指摘して歩いたそうです。
その結果仕入れ値が下がり、その上仕入会社の利益率アップに貢献したそうです。
「いくら松下電器でもそこまでしてほしくない」と言えば言えるでしょうが、取引はなくなりその上、工業の効率も改善しないままです。
ただ、取引している相手の会社が単に儲け主義だとそうはなりません。
だから、相手会社が優れた考え方理念を持っていることが重要だと思えます。
長い付き合いが出来、信頼が置ける、そして自社が成長できるパートナーとなるでしょう。
京セラフィロソフィ勉強会(居酒屋例会)
昨日19時から
「京セラフィロソフィ勉強会」の
居酒屋例会をしました。
場所はいつも勉強会場にしている私の事務所です。
参加者は16名。参加者の業種もさまざま方々です。
いつもの「京セラフィロソフィ勉強会」は京セラフィロソフィの本を5項目づつ読み合わせし、項目ごとに意見交換をしながら進めてゆきます。
現在は5回終了しましたが、毎月1回実施してもまだ、1年ほどかかりそうです。
今回の居酒屋例会の目的は、勉強会での意見交換が自由に出来るために、お互いを知り合うことでした。
写真のように大変盛り上がりました。
京セラフィロソフィの勉強会の参加費は無料です。
この居酒屋例会も参加費は無料ですが、参加者がそれぞれ飲物か食べ物を持ち込んでのパーティーでした。
次回の勉強会は9月21日(火曜日)の予定です。
毎月第3火曜日19時を定例化しています。
ご希望の方いましたらどうぞご参加ください。

「利他の心」
「利他の心」
これは京セラ名誉会長稲盛和夫さんから教えられた大事な言葉です。
説明するまでもなく、人に尽くす心です。
反対は「利己の心」です。
今「利他の心」が大事だと言われるれることは、逆にそれが無い世の中だからでしょうか。
自分が如何に人生を楽しむか、如何にお金を稼いでリッチな生活が出来るかを求めるのは利己でしょう。
以前、司馬遼太郎氏の「坂の上の雲」を読みましたが、そこには日本国民が欧米列挙に負けまいとして、「市井の人」として富国に協力している姿が描かれています。
そこには「利他の心」がありました。
戦後も、日本と言う国を復興するために、三等重役といわれる人達が会社を盛りたてました。政治家・官僚も国の復興に力を注ぎました。
私の好きな白州次郎さんもそうです。
城山三郎さんの「官僚たちの夏」にも通産省を舞台に日本の復興が書かれています。
「国の為」と言うとすぐ、軍国主義に結び付けてしまう人がいます。
私も戦後の学校教育の中でそのように教えられました。
でも、国の為に頑張るのは決して悪いことではありません
日本が元気な時は、皆が「利他の心」で頑張っていた時です。
「利他の心」ですれば「利己の心」より大きな力が出るのでしょう。
私が若い頃、お客さんの布団屋さんが大きなビルを建てました。その時、「どうしてそんなに儲けることが出来たのですか?」と聞いたところ、少し考え込んだ後、「お客さんのために一生懸命働いていたらそうなった」と言ったのを記憶しています。
「タライの水」の話を知っている方は多いと思います。
タライの水を自分の方に持ってこようとすると、逆に反対側に流れて行ってしまう。
タライの水を相手の方に向かって「どうぞ」と押し出すと、水は自分の方に帰ってきます。
この教えは利他と利己を表しています。
私はこの「タライの水」でもう一つ思うのです。
確実に自分に返ってくることを意図して、相手に水を押し出すというのも考えるれます。
見た目は利他ですが、実際は利己を目的としています。詐欺はこの心理を利用するのかもしれません。
物事全て単純ではなく、また人間の本能として利己をすべて捨てることはできません。
でも「利己の心」を薄くして、「利他の心」を抱くように生きてゆきたいものです。
デフレでも利益率の高い企業
昨日の日経新聞に「サイゼリヤが営業利益が5割増」と掲載されていました。
サイゼリヤはご存じの通り低価格てイタリア料理を提供しています。
「ミラノ風ドリア」が299円、「ハンバーグステーキ」が399円と驚くほどに安いです。
それでいて売上高990億円、連結営業利益が前期に比べ5割増の140億円です。
私が驚くのは14%もある営業利益率です。
これは飲食業界では驚異的に高い数字です。
価格を高くして利益率が高い飲食店は良くあります。
これほどの低価格で高利益率を出すのは企業努力しかありません。
材料費の仕入れルートが独自であるにしても、それは大手飲食チェーンでも同じです。
それでもそれほど利益率は高くありません。
例えばジョナサンは21年度決算では売上485億2千2百万円、営業利益26億3百万円、営業利益率5.4%です。
売値が安いのに仕入れ値は同じ。それでいて利益率が高いのは、材料費以外のコストの削減しかありません。
コストの削減はどこの会社でもやっているでしょうが、サイゼリヤの取り組み方が違います。
その一例として以前テレビでも紹介されていましたが、掃除も掃除機で隅々まで掃除するより、特注の幅の人いモップで1~2回拭けば済んでしまう。
目的は「きれい」することで、如何に短時間掃除をするか、秒単位・分単位の積み重ねでコスト削減をしています。
以前お菓子の「柳月」の田村社長の話を聞いた時も同じことを言っていました。
「家族3人が500円以内で生洋菓子が買える」価格設定をしています。
その価格は他社に比べ大変安いです。
それでいて美味しくなければなりませんから、同業者と同等かそれ以上の材料を使います。
それで利益率を10%保つにはやはり企業努力です。
工場生産性を上げるため、今までの無駄な遊び時間を無くすために、秒計算で歩ける効率を考えて機械配置をします。
「5歩」歩いてモノを取りに行っていたところを、「1歩」で済むようにします。
4歩少なくなると2秒短くなります。1日にその作業が100回行われると200秒、3分20秒です。
100人が同じようにして効率が高くなると、工場全体で5時間30分以上の時間の余裕が出来ます。
それが生産性の向上に貢献しています。
小さな改善の積み重ねが会社の方針である「3人家族が500で生洋菓子は食べれる」になり、利益率が高くなるのです。
計画を立てる時は大きな数字で押さえ、実行する時は秒単位の小さな数字を積み重ねる。
この二つが両輪となって企業は大きくなるのだと改めて考えさせられました
身の丈起業
昨日、ぐい飲みと小皿がが送られていました。
送ってくれた人は今月11日に「器と雑貨」のお店を開いた女性です。
彼女は札幌市の外郭団体「札幌産業振興センター」が主催した「起業道場」の卒業生です。
私は2年ほどそのお仕事のお手伝いをしていました。
「起業道場」はシニアと女性が対象でしたが、女性の受講者が多かったです。
私はその講座の中で、身の丈で起業するようにお話ししました。
「身の丈起業」とは、自分の力を見極め、お金と時間を計算し、出来る範囲で起業することです。
お店を開いた女性は受講生の一人です。
そして受講した女性の半分近くは「身の丈」で起業しているようです。
女性は起業をする時、堅実な計画を立て、仕事を進めます。
「ムリ・ムラ・ムダ」が少ないようです。
反対に男性は起業する時、「ムリ」して規模を大きくし、考えを詰めない「ムラ」のある計画を立て、必要ない「ムダ」なモノを買う人が多いです。
そして失敗。
やはり私の周りにいる起業者で順調に事業を拡大しているのは女性の方が断然多いです。
私の知人の女性で同じように「酒器」を専門にインターネットを中心に販売している女性がいます。
彼女も身の丈で起業しています。
紹介した女性は2人とも結婚されています。
ですからこそ、身の丈に徹底しているのです。
起業には「メガ起業」と「身の丈起業」があると思います。
若い人はぜひ「メガ起業」に挑戦してほしいです。若いうちは1度や2度失敗してもやり直しが出来ます。
50歳を過ぎてからの起業は、あまり冒険は出来ないとでしょう。老後のことがありますので「身の丈起業」になると思います。
札幌市には市が主催します、「ご近所先生」と言う講座があります。
私は来年1月、そこで「身の丈起業のすすめ」と題して5回の講座を開く予定です。
そこでもシニア・女性を対象にお話しようと思います。
「身の丈起業」をすることで、生活、人生を充実させ、そしてその事業が大きくなれば、札幌・北海道の経済発展に貢献できます。
頑張れ起業家!
皆さんガッツを持ちましょう!
今連日のように、日本経済の低迷、そして失業者の増加に関するニュースが溢れています。
失業に関しては、政府がその就職支援の事業を行っています。
でも一方企業側は大手企業を中心に海外へ生産拠点を移し、その海外生産比率が高まっています。
益々、国内の就職のパイが減っています。
企業が海外へ出て行くのを強制して止めることはできません。
政府は失業者対策 特に就職先が決まっていない学生向けに事業を行っています。
厚生労働省は「新卒者体験雇用事業」を開始し、経済産業省はインターシップ制度を行っています。
厚生労働省の「新卒者体験雇用事業」では学生を1カ月~3カ月受けれると、事業主は最大16万円のお金がもらえます。
経済産業省のインターシップ制度は、受け入れてくれた事業主には1日3500円、参加した学生には7000円くれます。
どちらも「企業体験」とか「いい人材なら雇用してほしい」と言う名目になっていますが、本音は「お金を出すから少しの間面倒を見てくれ」でしょうか。
全ての事業主とは言いませんが、お金目的で受け入れているところもあります。
それでも、政府は「一所懸命に雇用対策しています」との名目が立ちます。
企業側も就職希望者側もお金がもらえるから文句は言いません。
このような事を書くと皆さんから非難を受けること思います。
でも現にいるのです。
また起業についても以前書きましたが、起業支援事業と言って、北海道でも道庁からお金が出て、3年間事業として予算が何1千万円も出ます。
それを受ける機関はいつも決まった研究所や財団です。入札で決まるのですがいつもほとんど同じです。
その3年間の事業が終わればそれきり。
研究所や財団は支援事業を自分たちの収益事業としてとらえています。
道庁は起業支援事業を行っているという名目が立ちます。
今、失業問題や起業対策にお金を使いすぎです。
お金を出せば出すだけ、人はそれに甘え、頑張らなくなります。
人は「志」「夢」「やりがい」「生甲斐」を求め、それが喜びや楽しみにつながることを知らなければなりません。
頑張る人を1人でも増やすようにしましょう。
書いている私も「志」「夢」を追って頑張ります。
そしてこれからも私の周りにいる人達に、起業を勧め、その成功を支援して行きます。
お金は掛けなくても出来ることはいっぱいあるはずです。
昔はやった言葉ですが、ガッツを持ちましょう!
銀座「和光」
銀座の
「和光」が10月から土・日曜日も通常営業することが決まったそうです。
「和光」をご存じの方も多いと思いいますが、セイコーHDの子会社で高級ブティックを扱っている老舗です。銀座言えば必ず出てくる建物が「和光」の本館です。
大晦日で年が変わる時、テレビで良く紹介される時計台のあるビルです。(写真)
今までの「和光」は平日に訪れる富裕層の主婦や固定客で成り立っている店でした。
土・日曜に営業すると店内が混雑し古くからの顧客が離れる懸念があったのです。
「和光」の方針は「店内で顧客にゆったりした時間を過ごしてもらうこと」でした。
土・日曜日営業で新たな顧客を開拓するより従来の顧客の深耕が重要なのです。
この店は今までの豊かだった日本を代表する象徴的な店です。
顧客は富裕層です。それもスパーリッチです。
一般庶民は顧客として見てきませんでした。
その「和光」が土・日曜日営業をするということは、従来の富裕層だけを相手のやり方では成り立たなくなったことを意味するのでしょう。
それはある意味、日本の富裕層の購買力が落ちてきたことを意味しているのかもしれません。
チョット古いですが2001年11月22日の日経流通新聞の記事の内容を紹介します。
「和光」ではブランドを守るため値下げは一切しないそうです。
商品の6割は自社ブランドで、1品当たりの在庫を少なくし、売れ残りがないようにしています。
「売れなかった分は歯を食いしばって社員が買う」と当時の社長は言っていました。
今もそうなのか分かりませんが、ブランドを守るためとはいえ、社員は大変です。
今回の話は、日本を代表する大都会東京、その中もブランド力の高い銀座の高級店でも、その店のプライドを脱ぎ捨てなければ生き残っていけない時代なのだと、改めて考えさせられる出来事に思われます。

親の親
今、私は両親と同居しています。
私は二男ですが諸事情でそうなっています。
現在、娘が出産のため男の孫を連れて家に来ています。
無事孫娘生まれ、もうじき東京に帰ります。
この娘と孫がいる間は4世代の生活がありました。
親子孫と世代がつながるのを実感しています。
その時思ったのです。
「親は自分の子が誰かに大事にされると嬉しいもの」だと。そして大事にしてくれた人に感謝するのだと。
そして次に思ったのは、両親と一緒に暮らして、両親が喜んでくれれば、あの世から親の親、すなわち私の祖父・祖母が見て喜んでくれていると。
親孝行が大事だよと言うのは、親が喜んでくれることが第一だけれど、それが結果ご先祖様を喜ばすことになるのでしょう。
私が親と一緒に暮らしていると偉そうに言っても、実際に面倒を見てくれているのは妻です。
改めて妻に感謝の日々です。
最近は代々続くご先祖の「おかげ」を感じる日々です。
農地法が日本の国土を守る?
日本の農地法は2009年に改正されましたが、それまでは完全に農家だけの保護を目的としたものでした。
改正後は個人・法人を問わず農地を借りることが出来るようになりました。
しかし、依然として農地の売買は農地委員会の承認を受けなければならないという根本は変わりません。
ですから、一般に農地を購入したいと思ってもほとんど出来ないのが現状です。
農家として起業しようとしても、農地を買うことは出来ませんので、借りることになります。
この農地法が土地の売買を厳しく制限しているために、日本の一般法人が農業をする時は遊休農地を借りるしかありません。
これにより弊害もありますが、外国資本に農地を大規模に購入される恐れがありません。
世界では水不足が叫ばれ、各国とも水の確保は今後大きな問題になると予想されています。
水を確保するのは飲料水ばかりでなく、農業用水が大量に必要です。
専門家に聞きますと、「穀物を1トン収穫するためには1000トンの水が必要」とのことです。
農業には莫大の量の水が必要なのです。
おかげさまで日本は水が豊富な国です。
そして美味しい農産物が作られています。
特に私が住む北海道の農産物の人気は特に高いと聞いています。
農産物を輸入する事は水を輸入することと同じなのです。
日本としては農産物を輸出することは現状問題はないのですが、将来日本の農地が外国資本に買われ、農産物がその国に輸出されたらどうなるでしょうか?
もしも農地法のように土地購入制限の法律がなければ、農地が外国資本にドンドン買われてしまうのです。
現在各国は外国の農地買占めに走っています。
アフリカ諸国、ブラジルなどが時にひどいです。
ブラジルではアマゾンの55%が外国資本に買われてしまっている報道もあります。
いつの間にか日本で作られた農産物を私達が食べれないで、外国に運ばれていくということも、この農地法のおかげで防がれているのです。
私は現状の農地法に対して問題点ありと思っていますが、別の面からみるとまた違った見方が出来ました。
経営者にとって重要なパートナー
起業し社長となった時、パートナーは専務であり部長であり一般社員です。
その中でも経営のパートナーの中心となるのはやはり経営スタッフでしょうか。
もう一つ重要なパートナーは奥さんです。
社長は会社の全ての責任を負い、それでいて孤独です。
それを精神的に支えるのは奥さんです。
会社を経営する時、パートナーである専務などの経営スタッフと相談しても、決断を下すのは社長です。
その結果の全ての責任は社長です。
その仕事は誰も代わりが出来ません。
ですから、専務から社長になった人が一様に、「専務と社長とは全然違う」と言います。
その責任の重さが全然違うのです。
最近、菅総理大臣の夫人菅伸子さんの「あなたが総理になって、いったい日本の何が変わるの」と言う本が売れているそうです。
私は読んでいませんから論評できませんが、題名だけみると大変違和感を感じます。
そう思う人は多いかもしれません。
総理夫人が一国の総理より強い意見を持っているような表現のある題名を見ると、まるで会社の社長夫人が、夫の会社の経営方針に関して、自分の考えを公表しているように思います。
夫人の意見が反映される会社はほとんどダメになっていきます。
以前読んだ本の中で、松下幸之助さんは社長業の責任の重さについて書いていました。
重要で誰にも相談できないような仕事が社長にはある。例え専務にさえ言えないことがある。
そんな時本音を言ったり、愚痴を言ったり、弱音を吐くことができる相手は奥さんだけ。
そんな愚痴や弱音を言った時、奥さんは黙って聞いてくれるだけでいい。だから自分の気持ちを本当に知ってくれるのは奥さんしかいない。
確かそのような事を書かれていた気がします。
だから本当に重要なパートナーは奥さんなのです。
その奥さんが会社の人事や経営方針に口を出すと、会社組織は意味がなくなり、会社は滅茶苦茶になります。
私の父も社長でした。今は引退しています。
父と松下幸之助さんを比較するのは大変のおこがましいですが、父と母の関係がそうでした。
父は馬車馬のごとく前を切り開いていく。
母はその後をきれいにしながらついて行く感じがしました。
夜遅く飲んで父が帰ると、父は「じゃありがとう」と言ってそのまま家に入ってきますが、母は送ってきてくれた人に頭を下げでお礼を言い、タバコやお菓子を渡し、見送りました。
ですからいつも家にはタバコやお菓子がパッケージされ、用意されていました。
今改めて考えると、会社を本当に支えていたのは母ではなかったかと思います。
「京セラフィロソフィ」勉強会
昨夜
「京セラフィロソフィ」の勉強会を行いました。5回目になります。
ご存知の方も多いと思いますが、京セラ、KDDI創業者の
稲盛和夫さんが会社経営の基本としたのが「京セラフィロソフィ」です。
昨夜の勉強会に参加者した人は20名程度で、毎回のように参加する人もいます。
今回の勉強内容は
◆「常に謙虚であらねばならない」
◆「感謝の気持を持つ」
◆「常に明るく」
◆「仲間のために尽くす」
◆「信頼関係を築く」
の5項目を互いに音読し、それについて各自、実体験や経験に基づいた考えを述べ合いました。
項目別に下記の通り要約してみます。
◆「常に謙虚であらねばならない」では
謙虚、つまり謙る(へりくだる)と言えば、何かみっともないような感じを受けるかもしれないけれど、それは誤りです。
人は、自分に誇るモノがないからこそ威張り、ふんぞり返って自己顕示欲を満たそうとします。
◆「感謝の気持ちを持つ」では
感謝をするということは、自分自身が他の存在に対して謙らなければ、感謝ということは出てきません。
感謝することで素晴らしい人生を送れるのです。
逆に、愚痴、妬み、怒りの「三毒」は人の人生を暗くし、必ず不幸にします。
この「三毒」という言葉は勝間和代さんの本にもよく出てくる言葉です。
◆「常に明るく」では
自分の未来に希望を抱いて、明るく積極的に行動していくことが、仕事や人生をよりよくするための第一条件なのです。
不思議なことですが、人生がうまくいっている人は必ず明るい心を持っています。
自分の未来、人生はきっと素晴らしい幸運に恵まれているはずだと常に信じることが必要なのです。
◆「仲間のために尽くす」
人の行為の中で最も美しく尊いものは、人のために何かをしてあげるという行為です。
仲間のために尽くすということは、京セラのアメーバー経営の基礎を形成しています。
◆「信頼関係を築く」
信頼関係の上に立って仕事を進めています。
コンパや慰安旅行などの行事は全員が心を開き、結びつきを強める機会として重要視しています。
これらの行事は絶対参加でそれは仕事としてとらえています。
この行事により社員同士の絆を深めるのが目的です。
以上5項目を読見合い、意見交換することで、自分以外の考え方、見方を確認出来、京セラフィロシフィを一人で読む以上に理解度が高まりました。
26日には京セラフィロソフィの居酒屋例会を私の事務所でします。
色々な話が出るのが今から楽しみです。

「生活満足度」
今朝「新現役ネット北海道」の朝食会がありました。
今日が初めての朝食会です。
その時メンバーの1人が国民経済白書の中から抜粋した「生活満足度」の資料をもとに話が盛り上がりました。
1981年から2005年度までの統計資料でしたが、国民1人当たりの実質GDPは右肩上がりになっているのにもかかわらず、「生活満足度」は毎年のよう低下しています。(添付資料)
勿論、「生活に満足する」という意味は人それぞれ違うでしょう。
お金があるかないかが満足の基準の人もあれば、食べることが出来、家族が幸せであればそれで十分という人もいます。
日本人は他の国の人達と比べ、生活水準は高いです。
そして、生活の中でいろいろな情報が入ってきて、欲望が膨らんで行きます。
その欲望を追い続ければいつまでも満足出来ないでしょう。
その朝食会で出た話しでもう一つは、この恵まれた日本を作り上げたのは「働き過ぎの国民」とか「モーレツ社員」と言われた人達が懸命に働いた結果だということです。
現在日本には「いかに働かないでいい生活をしようか」と考える若い人たちが多いように思います。
一方他の国、例えば中国やベトナムの人達は、昔の日本のように「モーレツ」に働き、裕福な生活をしようとし頑張っています。
だいぶ前になりますが、私は中国の留学生と知り合い交流が長く続きました。
彼のお姉さんが留学で日本に来た時も保証人にもなりました。
ある時、その中国人の彼は、奥さんと子供、それに病気のお父さんを日本に残し、一人でアメリカに渡っていきました。
日本で色々あり、日本に失望して、アメリカに行ったのです。
アメリカに渡ってから3年後、彼はラスベガスで起業し10名ほどの社員を抱える社長になり、家族をアメリカに呼び寄せました。
彼には特別すごい才能があるようにも思いませんでした。日本語は喋れましたが、英語はそれほどでもなかったです。
でも、彼は「モーレツ」に働いたのだと思います。
彼は数年前高いブランディーをお土産に遊びに来ましたが、その後疎遠になり、今は交流はありません。
でも、時々彼を思い出すたび、彼の情熱を感じます。
昔、彼の家族と一緒に食事をし、水餃子の作り方を教えてもらいました。
また、水餃子食べたくなりました。
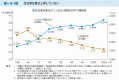
二宮尊徳
二宮尊徳は私が小学生だった頃、校内にその銅像が立っていました。
名前は尊徳ではなく、二宮金次郎だったと思います。
金次郎は勤勉・努力の人として教えられました。
少年期に両親を亡くし、伯父のもとで大変貧しい、そしてつらい生活を送りました。
その時寸暇を惜しんで勉強している姿が銅像となっています。
独力で生家を復興した尊徳は、疲弊した近隣農家の復興にも寄与しました。
田畑を開墾すると、従来の田畑より税の負担が軽くなることに注目して、開墾を奨励ました。
その農家経営能力が買われ小田原藩に招聘され、藩経営改善にも貢献しました。
二宮尊徳の言葉があります。
「道徳のない経済は犯罪に近い。経済のない道徳は寝言に近い。
私はこの言葉が好きです。
何か口にするとすぐ「金」「金」「金」と言う人がいます。
お金を稼ぐのはいいことですが、稼いだお金で何をするのか分かっていない人が多いです。
逆にボラアンティアに熱中して、自分の生活がおろそかになっている人もいます。
ボランティアや福祉でお金を稼いではいけないという人もいます。
人の為に良いことを言い、良いことをしても、自分の生活基盤がしっかりしていないと、今度は自分がボランティアや福祉を受ける立場になてしまいます。
「道徳のない経済は犯罪に近い」という考えは稲盛和夫さんの教えと同じです。
二宮尊徳の孫は北海道豊頃町付近に渡り、開墾・開拓を行いました。
その後札幌に住済んだそうです。
北海道は多くのフロンティア精神を持った開拓者が作り上げたところなのです。
「代表的日本人」
内村鑑三が書いた「代表的日本人」(岩波文庫)をご存じでしょうか。
この本は明治時代に日本を紹介するため、外国人向けに英語で書かれた本です。
他に、当時日本人を紹介するために英語で書かれた本は、新渡戸稲造の「武士道」でしょう。
「武士道」が日本人の精神的土壌の紹介であれば、「代表的日本人」はその精神的土壌の上で培われた5人の日本人を紹介しています。
だいぶ以前に聞いた話ですが、50年ほど前に日本の佐藤総理大臣が訪米し、ケネディ大統領に会った時、大統領が「一番尊敬する政治家は上杉鷹山です」と言ったそうです。
その時残念ながら佐藤首相は上杉鷹山を知りませんでした。
ケネディ大統領はこの「代表的日本人」を読んでいました。
この中には二宮尊徳、上杉鷹山、西郷隆盛、日蓮、中江藤樹、の「人」「業績」が書かれています。
内村鑑三は札幌農学校でクラーク博士のもとで学び、その影響からキリスト教徒です。
そのキリスト教徒の内村鑑三が仏教徒の日蓮を紹介しているのが面白いです。
私はこの5人の中で二宮尊徳、上杉鷹山、西郷隆盛が特に好きです。
この書籍「代表的日本人」は稲盛和夫氏から紹介されました。
明日はに二宮尊徳が言った心に残った言葉をご紹介いたします。
頑張れ!
「有限会社がんばれ社長」の武沢信行さんはメールマガジン「がんばれ社長」を発行しています。
何年も前から読んで、良き示唆をいただいています。
先日のメールマガジンに最近の風潮についてコメントが載っていました。
『本やセミナーで「がんばらなくていいんだよ」とか、「がんばれ!というのは逆効果ですよ」などと日本中が病人であるかのように教える人がいるが、それは間違っている。』と
私は武沢さんの考えに賛成です。
頑張る人がいたから、世の中が良くなったのです。
日本は明治の時、欧米列強の国々に負けないように頑張って国力を高めました。
第2次大戦後も焼け野原の日本を皆で頑張って復興しました。
頑張らなければなりません。
現在の日本は過去の人達の頑張りの結果です。
現在の繁栄は私たちが作ったのではなく、過去頑張った人達の結果です。
過去の人達の努力の産物を何もせず安穏として頂くだけではだめです。
将来の日本は今の私たちが頑張らなければ衰退してしまいまいます。
それは若い人ばかりでなく、私も含めた団塊の世代にも言えます。
以前にも紹介したかもしれませんが作家の水上勉さんの言葉があります。
晩年の水上勉さんが、同じ年齢の老人たちがゲートバールに興じているのを見て「なんだこの人達は、信じられないよ。まだまだ働けるのによくも皆で集まってゲートボール何かやっていられるものだと」嘆いていました。
人は学べる時は学び、働ける時は働くべきなのです。
頑張りましょう。若い人は次の時代を作るために。
年配者は、例え定年が過ぎても、自分の出来ることで頑張り、若い人たちに「良き日本」を渡しましょう。
武沢さんのメールマガジン「がんばれ社長」登録
http://www.e-comon.co.jp/magazine/index.html
クールビズと気遣い
今年の北海道、札幌の夏は異常に暑いです。
暑さに耐えられず、私はノーネクタイで仕事をしています。
今は役所も銀行もクールビズという事で、ほとんどの会社ではノーネクタイです。
先日、知人が東京から尋ねて来ました。
30度くらい暑い日でしたが、ちゃんとネクタイをしていました。
彼との話はそのネクタイが話題になりました。
彼は仕事柄多くの企業を営業で回るそうです。
東京の夏の暑さは35度を超すモノですから、さすがの彼も上着を手に持ち、ノーネクタイで歩き回ります。
でも、お客様の会社に近づくと、カバンに入れてあるネクタイ締めてから訪問します。
私が「今はどこの会社もノーネクタイでもOKでしょ?」と聞いてみると、「勿論、ほとんどの会社ではノーネクタイでいいようです。」と言います。
でも彼はネクタイを締めるのです。
先日、彼は大事なお客様を訪問した時、お会いした人がネクタイをし、上着を着て現れた時、「ネクタイして来て良かった」と思ったそうです。
何時、どんな高い地位の人が出て来るかわかりません。失礼があってはいけないと思うのです。その方がネクタイをしていたとすれば、尚更のこと、後から絶対後悔すると言うのです。
クールビズの時代ですから、例えネクタイをして行かなくても、そう問題にはならないと思います。
でも、相手が身なりを整えているのに、だらしなくしているのは、彼の流儀では許されなかったのでしょう。
彼はその業界ではトップセールスです。
暑い日にあえて服装を正して面談に行くことは、それなりに相手に真剣さを訴えることになるのです。
勿論、汗をダラダラ流していては不快に思われますから、彼は早めにその会社に着き、会社のロビ-で汗が引くのを待ってから面談申込をするのです。
クールビズでも、暑さに甘えず、真剣さを見せる心構えは大変参考になりました。
盆休みが明けたら私も、カバンにネクタイを入れ出社します。いつでも、誰にでも会えるように。
増えよ!挑戦者、起業家
新聞に円が対ドル84円台になったと新聞に大きく掲載されています。
日本の円が強いのでなくドルが弱いからですが、アメリカも日本型の不況になりつつあるといいます。
その中でも「さすがアメリカだ!」と思うのは、昨年のアメリカの起業数が月間平均56万件弱もあるのです。年間672万件です。
将来の成長の芽が育っています。
日本の起業数は2001年から2004年の4年間で約74万3千件。年間平均18万6千件です。
日本の人口1億3千万人とすると700人に1社の割合の起業率です。
アメリカの人口は近年、3億人を超し、約3億2百万人ですから、48人に1社の起業割合になりなります。
日本の14~15倍です。
私は以前からその国の経済の底力は起業家の数だと思っています。
日本とアメリカの教育が違っていますし、その中でも「お金を稼ぐ」を教育に取り入れているかどうかも大きいです。
アメリカの大学生は卒業したら「起業する」か「就職する」か選択するそうです。
考える時は起業が先に来ます。
一方、日本の学生の多くは就職が大前提にあります。私もそうでした。
現在の日本の就職状況は厳しく、就職できなく人生を悲観している人もいます。
大学には「インターシップ制度」とい就職前に起業体験をする制度があるそうです。
その「インターシップ制度」の目的は就職です。
私が提案したいのは、学生が2年生位になった時、大学・学生・地元企業の3者が、「新事業を興す」「起業する」を念頭にした具体的プロジェクトを作り上げるのです。
若い人と様々な経験をした人達とがアイディアを出し合い、市場調査をし、事業計画を作り、プチ商売をしてその可能性を探ります。
本格的に起業する時は皆で協力し、出資金も募ることもが出来ます。
日本の社会の中で起業は特別な事でなく、自分の進路を決める時、考慮される選択肢の一つにならなければなりません。
「イールドマネジメント」と「ツイッタ―」
「イールドマネジメント」
チョット難しそうな言葉から入りました。
「イールドマネジメント」については以前にもお話したかもしれませんが、「いかに最大収益を上げるか」を目的としたマネジメントです。
機会損失をしないためのマネジメントです。
これは元々航空会社の収益向上のために作られたモノですが、現在はホテルを中心にも使われています。
この考え方をその他の多くの商売に応用すれば、キット収益性が上がるとはずだと思います。
簡単な「イールドマネジメント」は、その店の過去の来客数、売上数、回転数等を集計し、そのデーターを将来のの予想に使うのです。
時間別にも分けるとより細かな対応が出来ます。
例えば、1年前2年前のお客様の動きをみると、8月のお盆時期の来客数が少ないと分かれば、あらかじめ単価を下げてでも、客数を増やす企画を作ります。
逆に、込み合うことが予想される時は、来客数を増やす努力より、客単価を上げる企画を作ります。
すなわち、「収益が最大になる」ように過去データー使い、3~6月後の戦術を立てるのです。
その「イールドマネジメント」を使いながらもう一つ、その時その時の状況に応じて、お客様に情報を提供する手段として「ツイッタ―」の利用が重要だと考えます。
今日はお客様が多く入ると思ったけど、思ったほどではないとしたら、「お得情報」をお客様にすぐ発信するのです。
特に常連のお客様でああれば、それをチェックしてくれ、来店してくれる見込みが高いはずです。
以前聞いた話ですが、東京銀座のあるデパートでは、メールアドレス登録されたお客様向けにタイムサービス情報を状況に応じて、流すそうです。
その時偶然に、銀座に来ていたお客様はそのメールを受け、デパートに向かい、特売品が買えたのです。
現在はメール発信よりツイッタ―のほうがよりタイムリーでしょう。
「イールドマネジメント」も「ツイッタ―」も機会損失をしないための道具として使うことをお勧めします。
企業の投資
現在、日本はデフレ、不景気という言葉で、なかなか気持も経済も上向きになれないでいます。
一方で企業の手元資金が増え、日本の企業だけでも140兆円を超えたそうです。
その金額は1990年のバブル期以来の高いものです。
大企業の手持ち資金が増えた理由は、経済の先行きが不透明で、事業拡大に慎重なのが大きな理由です。
その中でも、大企業の海外投資は新興国向けを中心に前年比35%増になっています。
国内投資は7%増です。
このような話しを聞くと「もっと社員に還元したらいいのに」となります。
法人税をもっと高くしたらいいのにという声が上がります。
でも、そうなれば益々、企業が海外投資を増やし、極端にいえば本社を海外へ移転することもあり得ます。
そうすれば、また日本の失業率は高くなります。
企業に日本で投資してもらうには、規制緩和、法人税の減税等の経済環境を変えなけらばなりません。
資金を沢山持っているのは、大企業ばかりではありません。
個人、中小企業でも潤沢な資金を持っているところもあります。
私の知っている北海道の中小企業はドル建で100万ドル以上保有しているところもあります。
少し前の資料ですが、日本の個人の金融資産は1400兆円と言われています。
お金のない人は「お金が無い、不景気だ」といいます。
お金持ちはただ黙っているだけです。「金を持っているよ!」とは決して言いません。
法人も個人も変化を見定め、変わる兆候を見つけて、一気に変わる予感がします
最低賃金の引き上げについて
最近の新聞で「最低賃金の引き上げ」問題が取り上げられています。
働く側から見れば、高い賃金を求めます。
会社側からは賃金が高いと収益が出なくなります。
政府は「20年までに全国最低800円、全国平均1000円」を目標に掲げています。
会社側、特に中小企業側からみると、現状のデフレを考えれば「最低賃金の引き上げ」は死活問題になります。
賃金が上がる時、会社が生き延びるには、利益性の高い事業をするか、小人数で経営できる体質改善が行われなければなりません。
現在の日本で利益性の高い事業を探すのは大変なこと。
そのため、少ない人数で仕事をこなすために、機会・設備の導入などが起きるでしょう。
悪くすると、会社規模を縮小して、アルバイトの数を減らす方向に行くかも知れません。
どちらにしても、デフレ経済のもとでは、賃金が高くなるば、雇用人数が減少します。
益々、失業者が増えます。
デフレ下では、ワークシェア―が行われるのが流れです。
個別の賃金が減少しても、仕事を分け合い失業者を増やさないことが大切です。
「最低賃金引き上げ」はそれに逆行しています。
将来、外国人労働者の受け入れなど、労働者の自由化問題が持ち上がると、この問題はもっと複雑化して行きます。
居酒屋で起業
起業する時、「どのよな業種ですればいいか」一番先に悩むことです。
起業のビジネスプランコンテストでは、面白く奇抜なプランが注目されます。
起業する時、検討される業種は衣食住に関することがほとんどでしょう。
その中でも起業し易い業種として選ばれるのは飲食店も多いでしょう。
私は起業する人にお話しするのは、「確かにビジネスプランは大事だけれど、やはりその仕事をやり抜く意欲の方が重要」と言います。
どんな仕事を始めてもうまくいく人はうまくいきます。
逆に、いくらいいビジネスプランを持ってやってもダメな人はだめです。
先日仲間に飲みに誘われ、札幌中央区にあるお店に行ってきました。
びっしり入っています。満席です。予約しないと入れないそうです。
そこは飲み放題料理8品(確か?)付いて2500円。
昔は飲み放題で4000円、5000円と言うところが多かったですが、デフレの今、その価格も下がり、飲み放題付きで4000円、3500円がほとんどです。
その上、ビールでなく発泡酒になっています。
私が行ったその居酒屋は中華料理店で、料理もそこそこ美味く、飲物もビールです。
採算合うのかな?と思ってしまうほどです。
その店は札幌中央区のビルの地下にありますから、家賃もそこそこ高いはずです。
飲みに誘ってくれた人によると、その店の主人は朝7時から店に出てきて仕事をし、12時までまで働き通しだそうです。
やはり経営者が「どこまで真剣に仕事をするか」が成功の要です。
この店に弟子入りして1年間は勉強すれば、いい仕事ができるでしょう。
その店はお客さんから「サラリーマンの味方」と言われています。
不動産新ビジネス
札幌の不動産業界は他の地域と違うようです。
貸アパートやマンションが過剰気味で、オーナーは借り手探しに苦労しているのは、札幌ばかりでなく他の地域でも同じでしょう。
そして借り手を探す時、不動産会社に依頼するのだと思います。
結果的に、オーナーと不動産会社との力関係は不動産会社の方が強くなります。
普通、貸アパート・マンションのオーナーは、不動産会社に借り手を斡旋してもらい、契約になれば賃料の1カ月分を不動産会社に支払うことになります。
しかし、札幌の不動産会社は違います。
札幌の場合、不動産会社はオーナーに対して手数料の他に「広告費」という名目で2~3カ月分の料金を請求します。
斡旋手数料は1カ月分と法律で決められていますが、「広告費」という名目ならOKということです。
勿論、「広告費」は強制ではないのですが、「広告費」を支払わないところには、お客を送りません。
結果、オーナーは支払わなければなりません。
これは表面的に法律違反ではありませんが、実質違反行為です。
私はこれを聞いた時「理不尽」だという気持ちでした。
これを逆手にしたビジネスプランを考えた人がいます
私が運営しているレンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」に入居した人が考えました。
昨年12月に入居した50歳を過ぎたシニア男性です。
入居当時は新しいビジネスを考え出そうと悩んでいました。
入居から3カ月経った頃、そのビジネスプランを作り上げたのです。
彼が考えたのは、貸アパート・マンションのオーナーが不動産会社に支払っていた「広告料」と同じ額の現金を直接借り手に渡した方が、喜んでアパートを借りてくれるのではないかということです。
彼は「オーナー」と「借り手」と結ぶ「会員制の仕組み」を作りました。
賃貸契約が成約なった時にオーナーは2~3カ月分の料金を借り手に支払うことにしたのです。
そしてこのビジネスプランのポイントは、彼の会社単独で始めたのではなく、札幌市内の大手プロパン会社と組んだことです。
プロパン会社の取引先は貸アパートの借主・オーナーです。
毎月検針に行ったついでに、チラシを配布することが出来ます。
これによりその会員制の仕組みを借主とオーナーに知らすことが出来たのです。
このビジネスはアパート・マンションオーナーに大変好評を得、スタート後、一気に盛況になりました。
入居した時、2名だったその会社は、6カ月後に社員5名・契約社員5名計10名の会社の社長として「札幌オフィスプレイス」を出て行きました。
その会社名は「アパオ」(http://apao.jp/)といいます。
その社長の素晴らしい企画力と行動力に感心し、本当に勉強になりました。
今でもお付き合いしています。
彼の他にも成功して「札幌オフィスプレイス」を出て行った人がいます。
彼らとも今でも交流があり、刺激を受けています。
街の中に「ベンチ」を
昨日ユニバーサルデザインを普及している人達と飲みました。
私も参加してる「北のユニバーサルデザイン協議会」の人達です。
本当のユニバーサルデザインとは何かを言い、喧々諤々と話が出ました。
現在のユニバーサルデザイン普及運動は、どちらかと言うと福祉の方に重点が置かれている風潮があると言うのがありました。
本来ユニバーサルデザインは健常者、障害者、老人、若者、幼児、男女の区別なく使いやすさを求めるモノです。
しかし、それを扱う人によってそれぞれの立場で解釈や行動は違って来ます。違っていいと思うのです。
ところで、私は身近なユニバーサルデザインを考えると、街中にあるっていいユニバーサルサービスは「ベンチ」だと思うのです。
私の父は92歳、母は85歳で、外出すると途中で何度も階段のところや、石の上に腰を下ろして休みます。
今住んでいる街の中「ベンチ」はありません。
そんな時、「もっと街の中にベンチがあったらいいのに」と思うのです。
「ベンチ」があれば、お年寄りばかりでなく、若い人も友達と日向ぼっこしながら話も出来ます。
妊婦の人にとっても助かります。
「ベンチ」が街の中にあると街の中に滞留する人も増えるので街中がにぎわいます。
これこそ多くの人達が使えるユニバーサルサービスになります。
そして人に優しい街になります。
ただ、人に聞きますと、「ベンチ」を歩道に置くので、現在は札幌市から許可をもらうのが大変だそうです。
でも出来ないことではないでしょう。
「ベンチ」に提供者の名前を入れるようにして、提供者を募り増やしていくのです。
結婚記念、出産記念、還暦祝いなどの名目で提供者がいるように思います。
これをNPO法人形式にして事業化するのも新しい起業かもしれません。
誰か一緒に事業化しませんか?

北海道の独立
昨日ある女性経営者とお会いしていと時の話です。
日本の食料自給率は50%を切っていますが、北海道の自給率は200%を越しています。
北海道は日本の食糧基地的存在です。
それなのに北海道の農業、漁業に従事している人達の所得は高くありません。
農家の平均所得は300万円を超す程度です
補助金頼りなところがあります。
今はデフレ経済であるからこそ、農産・水産物は安く叩かれ、スーパー等がその分利益を得ています。
昨日2人で考えた提案は「北海道民向けの農産・水産物の価格は安くし、北海道以外にはそれなりの利益を付けて高く売る北海道の政策」です。
販売先は本州ばかりでなく、海外にも積極的に売っていく。
中国では北海道ブランドが高く売れています。
北海道に住めば、食料品が安いので、北海道以外から移住者が増え、過疎問題も解決します。
北海道以外にそれなりの利益を付けて売るわけですから、北海道にお金が落ちるようになります。
農業や漁業の人達を中心に北海道民の所得も上がっていきます。
北海道には食料品基地と言う大きな武器があります。
北海道庁と北海道の農協、漁協の3者がタッグを組み、始めれば出来そうな気がします。
勿論、いろいろな問題が発生するでしょう。
しかし今北海道が持っている武器を使って自立するとすれば、このような方法もあることです。
いつまでも北海道が日本の植民地であってはならないのです。
日本の老舗企業
日本には創業が100年を超える老舗企業が2万社以上あるそうです。
その中でも金剛組は世界最古の会社で、西暦587年飛鳥時代創業ということですから、1400年の歴史があります。
ヨーロッパでの古い老舗起業はせいぜい600年位だそうです。
なぜ日本にこれほどの老舗企業が多いのでしょうか。
今、日経新聞では「200年企業」と題された連載物が115回続いています
そこには「成長と持続の条件」が書かれています。
老舗企業が生き延びてきた理由は、本業からはずれず、身の丈に合った挑戦をし続けてきたように思います。
金剛組は平成18年に倒産しました。
今は改めて再出発しています。
金剛組が倒産した理由は本業から外れたことをしたからです。
金剛組に伝わる教えでは
「お寺お宮の仕事を一生懸命やれ」
「大酒はつつしめ」
「身分にすぎたことをするな」
「人のためになることをせよ」
等があります。
本業以外の仕事であるマンション建築に手を付けたのが大きな原因と言われています。
会社は発展しなければ衰退します。
発展するために新規事業に挑戦することも必要です。
その時、「起業理念に基づいているか」「本業との位置関係はどうか」「その規模が適正か」が重要です。
でも、これがいいというものはありません。
思考錯誤で挑戦していくことです。
ただし、決して博打ではありません。
若い人に多いのですが、中途半端な調査で「エイ.ヤァ!」と決めてしまう人がいます。
1000回に1回位うまく行く時がありますが、そのような事はしてはいけません。
一度、どこか興味のある老舗企業をご自分で調べてみると、いいヒントがあるかもしれません
小善は大悪に似たり。大善は非情に似たり。
「小善は大悪に似たり。大善は非情に似たり。」
これは仏教の言葉だと思いますが稲盛和夫さんから教えられました。
その意味するところは
「人を甘やかすと、それはその人に善を施したように思うけれど、実際はその人をダメにしてしまう大きな悪です」
また「他人から見ると情けが無く厳しい行為は、結局はその人を鍛え、素晴らしい人間にし、その行為は大きな善となるのです」
最近、人と話をするのですが、北海道の人は「受け身」の人が多い気がします。
自分で積極的に何かを始める人が少ないのです。
「誰か」が「何か」をしてくれるのを「待つ」人が多いのです。
北海道民はもともと、高い志を抱き北海道に来た人達を先祖に持っています。
フロンティア精神のある人達です。
しかし北海道には「北海道開拓」と言う名目で長年、国の補助金が膨大に注がれてきました。
それがいつの間にか当たり前になり、現在のように「受け身体質」になってしまったのです。
同じことが沖縄にも言えます。
北海道、沖縄どちらも「開発庁」が設けられ、特別に多くの補助金が流れ込んでいました。
そして現在どちらも、日本で経済回復が遅れているところです。
アフリカ女性が書いた本が評判を呼んでいます。
その題名は「援助じゃアフリカは発展しない」というもので、副題は「従来型のアフリカへの援助は腐敗を助長させ、人々を益々貧困に陥れる」とあります。
これも北海道・沖縄と同じ構造です。
表面上、人に「いい事」をしているようでも、実際にはその反対に人を貶めることになっているのです。
今、財政再建の為、補助金が絞り込められて、初めて自立機運が生まれるのでしょうか。
その時こそ本当の力が出てくるのです。
隠れた起業家よ! 早く立ち上がれ!
レスター・サロ―教授
先日新聞にマサチューセッツ工科大学名誉教授のレスター・サロ―氏の話が載っていました。
辛口の話しの中で、特に興味を持ったのは「中国の経済成長率が10%は怪しい」という話しです。
教授の話では「10%成長は都市部に限った話で、地方に住む9億人はゼロ成長だ。中国全土が10%成長するには都市部の4億人が33%成長しなければ牽引できない。本当のところは3%であろう」ということです。
言われてみれば、理屈が合っています。
以前、名前は忘れましたがアメリカの有名な投資家が中国関連の投資から完全に手を引いたということを聞きました。
やはり中国政府が発表する数字に不信感を持ったからだそうです。
レスター教授は政府が発表する数字に関してこう言っています。
「GDP(国内総生産)を集計する人間が大統領や、首相に更迭される可能性がある国の統計数字を信じてはならない」
その国のトップの意思で数字が動かされる可能性があるものは信じられないのです。
以前から、中国はオリンピック・万博後の反動があると言われていました。
今後の中国を注目していきたいと思います。
「客家」(はっか)の思想
中国人と取引をすると騙されるとことが多いと聞きます。
拝金主義で、儒教の国とは思われないのです。
私の周りでも騙されたという人が多いです。
でも本当に中国は拝金主義者の人達ばかりでしょうか?
中国で成功している人の多くは
「客家」出身の人達だと言われてます
昨日TBSテレビの番組でその「客家」を紹介していました。
「客家」の人達は「円楼」という丸い砦のような建物に数十家族が共同生活をする民俗風習があります。
大変教育熱心で、そこでは昔から伝わる教えがあり、その中に利他主義の教えもあるそうです。
「客家」は孫文、鄧 小平・シンガポール初代首相のリー・クァンユー、フィリッピンのコラソン・アキノ等の数多くの指導者を生み出してきました。
「華僑」と呼ばれる人々には「客家」出身の人が多いそうです。
商売上手な「華僑」を多く輩出した「客家」の教えが商売をする上での重要な秘訣でもあるのだと思います。
拝金主義のように自分のことしか考えない「利己主義」では、一時的に儲かっても長続きしません。
商売をする上で大切な考えは世界共通です。
ところで、「客家」人達は「失われたユダヤ一族」と言われています。
今度「客家思想」を勉強してみたいと思いました。

日本航空の「鶴丸」
日本航空のシンボルマークに
「鶴丸」が復活するそうです。
「鶴丸」はご存じの方も多いともいますが、鶴が円の中に描かれたものです
鶴丸は2002年の日本エアシステムとの統合を契機に廃止になっていました。
このマークを復活させた理由は日本航空再建に伴い、傷ついたブランドイメージ回復の為です。
社員の心を一つにし、会社を再建する上で、明確な経営理念の共有と、シンボルマークの統一は働く者にとってはモチベーションを高めることになります。
この「鶴」がらみのお話しを一つ。
私も会員になっています「盛和塾」では、千羽鶴を日本航空に送ろうと会員が手分けして鶴を折っています。
「盛和塾」には6千社以上の社長が入会しています。
会員の会社が皆で日本航空の利用をする事で営業的支援は勿論、精神的な支援として「JAL応援カード」配布活動と合わせて日本航空に千羽鶴を送ることにしたのです。
会社は目標やお金の数字だけでなく、働く人達のモチベーションを高めることこそが大切です。

岡田ジャパンのチーム運営
昨日、日本サッカー代表チームの会見を見ていました。
いいチームで、岡田監督があと1試合させてやりたかったと言葉が心に残りました。
その時つくづくとサッカーチーム運営と会社運営は同じものだと感じました。
岡田監督は以前から「ベスト4を目指す」と言っていました。
前にも書いたかもしれませんが、1年前埼玉で行われた盛和塾の例会で
同じ盛和塾の塾生である岡田監督が、その懇親会場壇上から「ベスト4宣言」をしました。
ベスト4に対しては多くのメディアは否定的でした。
ワールドカップ前の試合でも負け込み、益々その実現は難しいように思われました。
批判的な環境の中、目標に向かって戦い抜いて行ったのです。
京セラ創業者の稲盛和夫さんが主宰いされている経営者の為の勉強会「盛和塾」で学んでいる
京セラフィロソフィにそれに通じることが書かれています。
「ベクトルを合わせる」「大家族主義を貫く」「実力主義に徹する」「パートナーシップを重視する」という言葉です。
「ベスト4を目指す」は「ベクトルを合わせる」に通じます。
「大家族主義を貫く」も、ある選手は「このチームはファミリーの様だ」と言っています。
「実力主義に徹する」は周りから疑問視されても、調子を落としていた中村俊輔選手を外した事。
「パートナーシップを重視する」はPKで外し、頭を抱える駒野を自分たちの列に引き入れた行為
このワールドカップでの日本チームの働きで、当り前のことを実行していくことの重要性を知りました。
ただ、わかっていても出来ないことも多いのですが、そんな時勝間和代さんの言葉があります。
「わかっているけれど出来ない」と言う人が多いけれど実はそれは、わかっていないから出来ないのです。
と言っています。
成功体験として腹に落としていないからです。
私もこれを機会に再度じっくり考えてみます。
新しい都市形態
先日、ある銀行の支店長さんが執行役員になり異動するので佐藤(仮名)さんと3人で送別会をしました。
佐藤さんとは最近支店長の紹介で知り合いました。
その佐藤さんの会社は今、札幌のJR琴似駅周辺で大規模な再開発を進めています。
佐藤さんはその中心人物です。
佐藤さんたち一族は琴似の周辺に多くの土地を持ち、その地域再開発を平成3年頃から行ってきました。
「イトーヨーカドーショッピングセンター」「30階建と40階建の高層マンションタワー」「コルテナという大型商業施設」等が建てられその区域総面積は11ha(?)ほどあります。
この再開発の凄さは、それらが全て、JR琴似駅も含め空中回廊でつながれています。
そこに住む人達は、雨が降っても濡れることなく、イトーヨーカドーにショッピング、商業施設内の各医院、レストラン、フィットネスクラブ、レンタルショップ、本屋に行けます。
また、JR琴似駅に直結していますので、通勤や買い物でJR札幌駅まで行くことも出来ます。
近いうちにJR札幌駅と大通の間に地下通路が出来ますので、より広範囲に行動できます。
この再開発で何よりいい環境になったのは、高齢者です。
北海道の冬は雪道の為道路は滑り、高齢者は思うように歩行ができなくなります。
そのため冬は運動不足になり、足腰が弱ってしまいます。
でもここに住んでいれば、冬でも自由に外出が出来ます。
また、JR琴似駅から電車で30分弱で千歳空港にも行けます。
ですから、ここのマンションの部屋の所有者の2割は東京方面の人だそうです。
この再開発も来年から最終的開発がおこなわれ、40階建ての高層マンションと商業施設の工事が始まります。
もちろん、そこも空中回廊でつながります。
JR琴似駅前のこの施設群は、一つのコミュニティタウンとして存在しています。
そして驚くのは、この施設群は公共開発ではなく、民間会社が開発していることです。
現在、この仕事の責任者である佐藤さんは、同時にこの琴似地域全体の活性化にも取り組みたいと、若手経営者への応援も行っています。
これからますます楽しみな地域です。
私はこの琴似生まれ、そして今も琴似に住んでいます。

追伸:図面は下記のHPにつないでご覧ください。
さっぽろの都市再開発
勤勉さと運
日経朝刊1面に「春秋」という欄があります。
朝日新聞では「天声人語」でしょうか。
何日か前のその欄に、人生の成功を決めるのは「勤勉さ」か「運やコネ」が書かれていました。
日本で「運やコネ」を選んだ人は41%。
米、中、韓では20%代、フィンランドでは10%台。
1995年の調査では日本での「運やコネ」派はまだ20%でした。
これを調べたのは労働経済学者の大竹文雄さんで著書「競争と公平感」でこのデータが公表されています。
大竹さんはここ10年で日本人の価値観が、勤勉から運やコネ重視に変化したと指摘しています。
この「運やコネ」に頼る日本人の割合の多さにびっくりしました。
そして日本の将来に不安を感じます。
近年は運を引き寄せる法則など運に関する本が沢山売られています。
そこには他力本願的なモノが見えます。
成功するには、勤勉さがあって初めてその後に運も付いてくるはずです。
それなのに、努力しないで、楽しく、いい思いだけを受けたいと思う人が多くなったのではないでしょうか。
生活が豊かになってくるとハングリーさがなくなり、その日暮らしでも生きていけると思っているからでしょう。
稲盛和夫さんの本に書いてあります。
仕事を一生懸命し、誰にも負けないように努力している姿を神様が見て、手を差し伸べてあげようかと思うくらい努力して初めてうまくいくのです。
そして、その人は後で振り返った時「私は運が良かった」というのです。
最後に稲盛さんの言葉
「小善は大悪に似たり」「大善は非情に似たり」
風に乗る
私は「風に乗る」という言葉を最近よく使います。
その意味は時流に乗るということでもあるのですが、
私は「自分に吹いている風に乗る」意味として使います。
今の自分を客観的に見てみると、その立場や環境、状況が判るのですが、
そこに「意地」というものが入ると、複雑になってしまいます。
時として折角吹いている風に逆らって、苦労することになります。
苦しくて、つらくて、それでも頑張ったけれども実入りがほとんどない
という状態になってしまいます。
大事なのは「素直な心」です。
意地を張るのも「素直な心」を忘れているからです。
ただ、勘違いされがちなのは、「成り行きに任せる」という生き方です。
そのような生き方とは全然違います。
一見同じように見えますが、「風に乗る」時には自分の目的や目標を
明確に持っているのです。行き先がわかっています。
「成り行き見任せる」生き方は無責任な生き方です。
だからこそ必要なのは「自分の生きる目的・目標は何なのか」を
しっかり持つことです。
そして「素直な心」になっていると、知らないうちに環境が良くなってきます。
少し考え方を変えるだけでいいのです。
これは私の経験でもあります
金持ちと貧乏人
「金持ちになる」か「貧乏人になるか」の大きな違いは考え方です。
「貧乏な人」「普通の人」「金持ちの人」の違いは、お金に対する考え方の違いです。
お金に対する考え方を少し変えただけで違ってきます。
そのことを少しお話したいと思います。
その話しを3つ。
話し1
ジュースをグラスに入れた時
貧乏人はジュースがグラスに満たないうちに次々飲み干します。
普通の人はジュースがグラスに一杯になってから飲みます。
金持ちはジュースがグラスに一杯になっても飲まず、グラスから溢れてきたジュースだけを飲みます。
だからいつもジュースがいっぱいあるのです。
話し2
あるところに、AとBがいました。2人は仲が良くずっと一緒に暮らしていました。
しかし、2人とも貧乏で、どうしても貧乏生活から抜け出せません。
そこで2人は「いつまでも2人でいるからダメなんだ。1人になってそれぞれ頑張ろう」ということで別れました。
それから20年経っても、Bは相変わらず貧乏でした。
そんな時、昔の友達Aが金持ちになったという噂話を聞き、Aのところを訪ねました。
AはBを懐かしがり、歓待し、屋敷に入れました。
早速、BはAに「なぜ金持ちになれたのかその理由を教えてほしい」と質問しました。
Aは黙ってBを庭に連れて行き、小さなリンゴの木を見せ、「この木のリンゴを好きなだけ食べていいよ」と言いました。
Bはお腹が空いていたので、全て食べました。
次にAは大きなリンゴの木のところに連れて行き、その木の前で、「このリンゴも好きなだけ食べていいよ」と言いました。
Bは一生懸命食べたのですが、食べきれません。
その時、Aが言いました。
「これはお金も同じこと。入ってきたお金をすぐ使うからお金が残らない。入ってきたお金を使わず、この木のように大きな金額にするまで我慢をすると、簡単にはなくならないののだよ。」と。
話し3
斉藤一人さんが言ったことです。
お金はお金が好きな人のところに行きます。
人に「お金が好きですか?」と聞くとほとんどの人が「好きです」と答えます。
でも、その人がお金を手に入れると、ルイビトンのバックを買ったり、美味しいものを食べに行ったりします。
その人はお金が好きだと言ってるけど、本当はルイビトンのバックが好きであり、美味しいものを食べるのが好きなのです。
本当にお金の好きな人はお金を使いません。
だから結果お金が残るのです。
ある統計では一般サラリーマンの平均生涯賃金は男性大卒で2億7590万円、高卒2億2120万円だということです。
この同じサラリーマンでもお金を「残せる人」「残せない人」が出てきます。
会社の経営者はこの金銭感覚こそが大事です。
どんなにお金を稼いでも残せる経営者と、残せないで会社を倒産させてしまう経営者がいます。
お金を残す訓練をしてみませんか?
その訓練として「手元貯金」をするといいです。
私もやっていますが、どんなことがあっても、決まった金額を積み立てていきながら、手元にある現金を使わず、誘惑に打ち勝つ心を育てるのです。
やってみると、わかります。
お金が無い時、欲しいものがあったら「欲しい、欲しい」という気持ちが強くなり、お金が入るとすぐ買ってしまいます。
でも手基貯金がある程度貯まると、「買いたいけど、今は少し我慢してみよう」という気持ちになります。
「決して買えないのではない。買えるお金はあるけど買わないのだ」という余裕のある気持ちになって、そう簡単にお金を使わなくなります。
一度「手基貯金」に挑戦してみてください。
考え方が変わりますよ
第一回「京セラフィロソフィ」勉強会を開催しました。
20日18時より「京セラフィロソフィ」勉強会を開催しました。
参加者は13名、スタッフ入れて15名でした。
当初は参加者は5~6名位かと思ったのですが、13名の定員を超える参加希望者があました。
お申込みいただきながら、参加出来なかった方々にはお詫び致します。
勉強会の目的は、稲盛和夫さんが「京セラ」創業以来、会社経営の経験を基に作られた「京セラフィロソフィ」を読み、少しでも深く理解し、それを各自の会社経営・仕事の中で生かすことです。
経営者でなく一般の会社勤めの人も参加しましたが、この勉強は人としての生き方の勉強でもあります。
「人として何が正しいのか」を価値基準にして生きることが書かれています。
「京セラフィロソフィ」の本を声を出して読み合い、項目ごとに話し合いました。
不思議のもので、何回か読んだ本でも、声に出して読んでみると書いてある意味が良くわかります。
「京セラフィロソフィ」は78項目に分かれて書かれています。
毎月の勉強会で7~8項目進めると10カ月かかります。
参加しようと思っても、開催日によっては参加出来たり出来なかったりすると思いますが、この本は、項目別に独立した話になっていますから、途切れながら参加しても、問題なく理解することができます。
勉強会の後、今後の勉強会開催の日時について話し合いました。
結果、勉強会は毎月第3火曜日19時から21時とすることにしました。
その方が予定を立てやすいのではと思っています。
次回は5月18日19時からになります。
改めて告知しますが、参加ご希望の方は予定に入れておいてください。
尚、勉強会で使う「京セラフィロソフィ」の本は、参加者され、購入希望される人にお分けします。
たとえ購入されなくても勉強する部分をコピーにしてお渡ししますので、本が無くても大丈夫です。
お気軽にご参加ください。
購入希望の方は、勉強会に参加された時に実費(2100円)でお分けします。
あと10冊あります。
JAL応援団
少し前になりますが、先月の29日に盛和塾の北海道世話人会がありました。
以前にも紹介しましたが、盛和塾というのは京セラの名誉会長、またこの度JALの会長に就任しました稲盛和夫さんが主宰する経営者の為の勉強会です。
現在塾生は5700名を超しています。
今回の集まりには、盛和塾生12名、盛和塾本部から1名、JALから3名計16名出席で始まりました。
今回のテーマは「JALを応援する」です。
稲盛さんがJALの会長になり、私たち盛和塾の塾生がどのような応援が出来るのか。
それは、JALを使うことでしかありません。
そして、周りの人達にも勧めることです。
盛和塾生1名当たり100枚の「JAL応援団」というカードが郵送さら、それを周りの人々に配り、利用をお願いすることになりました。
JAL側としても、紹介利用されたお客様に「LALさくらラウンジ」を利用できる等の特典も付ける予定です。
JALは販促運動を進める盛和塾生に対しても、何か特典をと考えていましたが、塾生のほとんどがそれを拒否しました。
JALを応援するのは、稲盛塾長を支えるのが目的です。
特典は必要ないとの意見です。
稲盛さんはJAL会長を受けた理由を就任の時述べています。
「日本を代表するJALをつぶしてはいけない。日本の損失である。」といい、また「4万人の従業員を路頭に迷わすことはできない」と、この2点が引き受けの理由でした。
そして常に私たちにお話ししています、「人生生きていく中で最も大事なことは、世のため人のために貢献すること」を実践しようとしているのです。
マスコミによると、それまでには他の経営者に打診があったそうですが、再建困難との理由で受けなかったそうです。
稲盛さんは今年78歳。今まで京セラ、KDDIを創り、優良企業に育ててきた実績を見れば、いまさらLAL会長を引き受けなくても、既に国内外から優れた経営者として認知されています。
それなのに、もしかしたら、失敗してその名声に傷を付けてしまうかもしれません。
それをあえて引き受けるのです。
私は60歳になりました。「もう年かな」と思うことがありましたが、まだまだです。
稲盛さんからまた勇気をもらいました。
「JAL応援団」のカードを使った人の話によりますと、飛行機に乗る時、応援メッセ―ジを書てキャビンアテンダントしたところ、大変喜んでわざわざ席まで来てお礼を言ったそうです。そして飛行機を降りるとき彼女から「頑張ります。ありがとうございました。」と書かれたメッセージカードを渡されたそうです。
JALのサービスが悪いからと言って責めるばかりでなく、「頑張れ」のメッセージを発することで、仕事に対するやる気と使命感を持たせることが出来るのです。
皆さんもどうぞJALを利用してください。
そしてJALで働く人たちに勇気と元気を与えてください。


旅立ち
昨日3月1日、三女が
「ホンジュラス」に旅立ちました。
JICA(ジャイカ)が運営する「青年海外協力隊」の一員として行きました。
娘は高卒の時、鍼灸(しんきゅう)指圧の学校へ進み、3年間勉強して国家資格を取りました。
その後、東京の鍼灸院で実践を積んでいました。
昨年急に「
ホンジュラスに行くことになった」と話があった時は驚きました。
「
ホンジュラスっていう国はどこにある?」から始まりました。
飛行機を乗り継いで、2日以上もかかって日本の裏側に行くのを、反対したい気持ちがありながら、現地では目の見えない子供たちに指圧を教えるという仕事を選んだ娘の心意気は嬉しかったです。
2年間は帰って来れないそうです。
親が死んだ時は、途中でも帰って来れるそうですが......
娘が新しいことにチャレンジする姿は、親の私に刺激をくれました。
人の為に生きることは、自分の為に生きる事です。
今まだ、飛行機のなかでしょうか。
少し寂しいですね。
※外務省のホンジュラスの説明
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/honduras/index.html
「就職」について考える
今回は「起業」とは違う話をします。
今朝の日経新聞の別紙に「日経就職ナビ」というものが一緒でした。
そこには来年卒業予定の大学3年生を対象としたアンケートの結果掲載されています。
人気第一位は「東京海上日動火災保険」二位は「三菱東京UFJ銀行」と続きます。
私の学生時代は「日本航空」がトップに来ていたと記憶しています。
現在の「日本航空」を見ると隔世の感があります。
先日テレビを見ていたら「国際教養大学」という、秋田にある大学が取り上げられていました。
就職率がほぼ100%の大学で、その授業風景が紹介されていました。
秋田にある公立大学ですが、教授は外国人が多く、授業は英語で行われます。
授業について行くのが大変で、大学の卒業率は47%だそうです。
勉強の仕方は従来の日本の大学と違い、アメリカの大学そのものです。
今もそうでしょうが、私の学生時代もそれほど勉強しなくても、ほとんどの人が卒業できました。
大学4年生の時、アメリカの「オクラホマ大学」に形だけ留学ということで行っていました。
その時知り合った日本人の大学生活を見ていると、勉強中心の生活でした。
大学への出席率、テストの結果によって落ちこぼれていく大学生が多い中、彼は懸命に勉強して卒業しました。
同じ大学生でありながら、その真剣さは大したものでした。
私の学生生活を振り返ってみると恥ずかしい限りでした。
今、日本では大学生の就職難が問題になっています。
ここで改めて企業側の採用姿勢の変化に注意する必要があります。
以前、企業は「100名採用する予定」を立てると、100名採用しました。
今は、ある程度の「レベル」の学生を採用することに主眼を置いています。
当初計画で100名予定でも、「レベル」に達せる学生がいなければ、80名でもいいのです。
人数が足りなければ、「レベル」に達した人を中途採用します。
以前のような「自前主義」にとらわれません。
企業側の採用姿勢は「数」から「質」に確実に変化しています。
大学も、学生もそれに気付き対応していかなければなりません。
有名大学さえ出れば就職できる時代ではなくなっています。
「国際教養大学」のような大学がますます注目されてくると思います。
参考
国際教養大学のHP:http://www.aiu.ac.jp/japanese/
起業を志す人にもっと支援を!
現在、不況のど真ん中。
高校、大学生の就職状況も深刻です。
2009年11月の日本の失業率(季節調整値)は5.2%になっています。
国は失業対策のため職業訓練に力を入れています。
失業手当はどんどん増え、生活保護世帯も増加しています。
働く場所が無いというのが大きな問題です。
今、大切なのは働き先の確保です。
失業手当を支給し、職業訓練をし、就職斡旋をしても、働く会社が不景気のため倒産してどんどん減っています。
重要なのは働く先の「創造」です。
それは起業・創業を志す人達の増加を促すことです。
起業・創業する人達は、自分の夢を持ち、それを達成するために、あえてリスクを負いながら挑戦する人達です。
「誰かが何かをしてくれるの待つ人達」ではないのです。
民主党が掲げたマニフェストの中に「100万社起業を目指す」と書かれています。
ご存じでしょうか?
項目36に書かれている「中小企業憲章の制定など、中小企業を総合的に支援する。」の「具体策」の最後に
「中小企業の技術開発を促進する制度の導入など総合的な創業支援策を講じることによって、『100万社起業』を目指す。」と書かれています。
従来の「起業支援」は「制度融資」「補助金」「起業相談」がほとんどです。
でも、本当にそれで「起業支援」でしょうか?
お金を出せば済むものではありません。
また、起業相談を受ける担当者の中には、優れた指導をする人もいるかもしれませんが、起業経験も会社経営経験も無い人が大部分だと思います。
そして、その起業相談も「起業するまで」というのがほとんどです。
起業は誰でも出来ます。
見栄えのいい事業計画書を作り、お金を借りて、会社設立すればすぐ出来ます。
でも大切なのは、起業した会社が倒産しないで、順調に業績を伸ばすことです。
本当の「起業支援」とは、起業したばかりの経営者に対して、日々起こる問題に対してフォローする仕組みです。
普通、公的機関の「起業支援」は起業するまでです。
起業したばかりの会社に対しての支援は特になく、商工会議所などに設けられた「経営相談」というものも、「困ったら来なさい」というものです。
起業したばかりの会社に対する対応は、従来からある企業と同じような対応です。
でも、生まれたばかりのヒヨッコ会社と百戦錬磨の会社とは全てに違います。
「銀行にお金を借りに行くことは初めて」
「集金に行って小切手をもらい、領収書を切ることも初めて」
一般の会社では当り前のことが起業したばかりの人には大変です。
そしてもっと重要なのは経営者としての考え方です。
「約束を守る」「素直」「すぐ行動する」「物おじしない」等、いまさら人に聞けないことでも大切のことがあります。
それを教え、フォローしてくれる人が必要です。
「起業支援」として、市などの公的機関にお願いしたいことは、すでに起業し成功している経営者達を組織し、マンツーマン的に起業家を育てる仕組みです。
例えば、起業してから1年間の期間、成功経営者に依頼し、起業家に対して、アドバイスをし、相談を受けてもらいます。
アドバイスするその経営者には、交通費程度の費用支払いは必要ですが、ほとんどはボランティアになります。
第一線を引いた経営者の中には社会貢献をしたいと思っている人たちがいます。
その人たちの成功体験、失敗体験こそが起業したばかりの経営者にとって、知識、知恵になっていきます。
現在経営に携わっている方々も、時間を見出しながら、周りにいる起業家に対して応援、支援をお願いいしたいと思います。
経営者にとって起業家たちと接点を持つことは、新しいネットワークを持つ機会となります。
「起業支援」はコミュニケーションこそが大切です。
京セラフィロソフィ
今日は「京セラフィロソフィ―」について書きます。
「京セラフィロソフィ―」は、「京セラ株式会社」の名誉会長である稲盛和夫さんが会社設立以来、会社経営していくうえで必要となる「哲学」を社員に話し、社員とともに実践してきたものです。
その「哲学」を冊子にし、京セラ関連会社の全従業員に携帯させています。
稲盛さんは「人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力」という方程式をよく話します。
「考え方」「熱意」「能力」は重要ですが、その中でも「考え方」が一番重要で、「考え方」こそが人生を大きく左右すると言います。
「京セラフィロソフィ」はその「考え方」をまとめたのです。
以前にも書きましたが、私はその稲盛さんが主宰している経営者の勉強会「盛和塾」に入っています。
稲盛さんのお話の中に「京セラフィロソフィー」のことがよく出てきます。
そこに書かれた内容が経営者としての大事な「考え方」でもあります。
この「京セラフィロソフィ」という冊子は、京セラの従業員だけに配られるもので、外部の人は手に入りません。
以前より盛和塾の会員からも、欲しいとの要望がありましたがいただけませんでした。
それがこの度やっと、盛和塾会員限定の本として「京セラフィロソフィ」が出版されました。
これは「京セラ」が従業員向けに作ったものと違い、より詳しく解説がなされ、項目別に稲盛さんの説明が書かれています。
600ページを超すボリュームになっています。
私は今、この本を読んでいる最中です。
あと100ページほどで読み終わりますが、この本は1度読んで終わりというものではなく、常に携帯し、何かの都度読み返す「実践の書」です。
この「京セラフィロソフィ」は昨年末に注文を受け、配送されましたが、盛和塾会員だけなのにかかわらず3万冊の注文があったそうです。
ある会社では100冊購入をして、社員教育に生かすそうです。
本来は3万冊の配布で終了する予定でしたが、再度購入希望が多く、あらためて増刷されることになりました。
私は前回は1冊しか購入しなかったのですが、身近の人で欲しいという人がいますので、今回は5冊注文しました。
よく読んで勉強します!!

「自分探し」
今朝の日経新聞の広告ページに「日本の起業家精神の展望」と題して、起業にかかわる仕事をしている人たちの話が載っていました。
その中で、ある大学院の教授が話した内容は少し引っかかる内容でした。
新聞に載っている内容を少し紹介します。
「イノベーションを起こすには、自分が何をやりたいかを見つけることだ。それを見つけられずに悩んでいる若者は、まず現場に行くことだ。」と話していますが、その通りです。
その後
「世界は広い、どこでもいいではないか。そこでいろいろな経験をし、様々な出会いから、人を知り、ネットワークが出来る、自分のやりたいことも見えてくる。
世界の問題を知り、友人と共感し、自分の燃える物を探す、目標が見えてくる。」とあります。
私が若い頃、当時の知識層の先生が同じようなことを言い、若者は「自分探し」と称して海外に行ったり、仕事を転々として定職を持たず、結局何も見つけられなかった人達が如何に多かったことか。
結局、自分の目の前にある現実を見据え、逃げずに、目の前にある自分の仕事を一生懸命することが、自分のするべきことが見るかる確実な方法です。
これは私が経験して実感したことです。
また、多くの成功した起業家が話していることでもあります。
若い人には「自分探し」と称して現実逃避することがないように。
そして年配者は、若い人に「自分探し」のような話をして惑わせないこと。
これは大人の責任だと考えます。
望年会をしました
昨日15日
望年会(忘年会)をしました。
手付かずの真新しい来年という1年に向かって、夢を語り合う会と思ったのですが、
単なる楽しい飲み会になりました。
札幌オフィスプレイスのメンバーとOBの方々合わせて
12名です。
札幌オフィスプレイスではいろいろ理由をつけて飲み会を行います。
春には花見、夏にはビール会、忘年会、新年会、
その合間に居酒屋ミーティングと称して私の部屋で飲み会をします。
お酒を飲まない方も参加します。
同じレンタルオフィスにいてもなかなかゆっくり話をする機会がありません。
このような機会にお互いの話をすることで、お互い協力できる仕事も発生しているようです。
今月28日に納会を私の部屋でします。
今年の締めくくりとして少しお酒を飲みながら来年の抱負を語り合いたいと思います。
あまり飲み過ぎないようにします。


さっぽろ起業道場
今月の5日に
「女性・シニアのための『さっぽろ起業道場』」に先輩起業家として参加し、お話をして
来ました。
この「
女性・シニアのための『さっぽろ起業道場』」は札幌市の関連団体である財団法人さっぽろ産業 興財団が数年前から毎年行っています。
年に3期行い、その都度参加者を募ります。1期は10講座です。
昨年から協力させていただいていますが、参加者はシニア男性の数は少なく、圧倒的に女性の参加者が
多いのが現状です。
今回も8名が参加しましたが、全員が女性です。
一般的に公的機関が主催する「シニアのための起業セミナーや講習」が行われますが、シニアが起業を
志す人は少ないように思います。
この講座の最後に「
女性・シニアのための『さっぽろ起業道場』」に参加した人たちのビジネスプラン
の発表がありました。
「デイサービス」「ウエディング企画」「生活器・用品販売」「結婚仲介」等のビジネスプランです。
それぞれのプランは、もう少し練る必要はあるにしても、方向性はいいと思います。
発表されたプランは、身の丈起業であり、人に喜ばれることを目指しているからいいのです。
自分の儲けばかり先行して考えるプランは失敗します。
17時からは懇親会があり、おおいに盛り上がりました。
これからも起業を志す人たちとの交流出来る場には、積極的に参加してゆきたいと思います。
がんばれ女性起業家! がんばれ未来の女性経営者! 

稲盛和夫さんが来札されました
今月3日に
稲盛和夫さんが来札されました。
今回は読売新聞の読売フォーラム主催の講演会の講師としてです。
ご存知の方も多いと思いますが、
稲盛さんは
京セラを創業し、また現在の
KDDIの前身である第二電電も創業しました。
現在は盛和塾という経営者の勉強会を主宰されています。
世界中に5700名以上、北海道には支部が札幌の他に函館、帯広、オホーツクにあり、札幌にも60名近くの塾生がいます。
私たちは
稲盛さんのことを塾長と呼んでいます。
その塾長が来られるということで札幌の塾生ばかりでなく北海道内の塾生が集まりました。
読売新聞主催の読売フォーラムに盛和塾の塾生も参加し、お話を聞きました。
講演題名は「不況を次の発展の飛躍台に」。
不況時の経営者の心構えを、ご自分の経験をもとに説かれました。
その中で、
「不況時の備え」として5つ提示されました。
1.全員で営業する。
生産現場の人も一緒になって営業をする
2.新製品の開発に全力を尽くす。
不況時は時間があるからこそ、新製品の開発に時間を使うこと出来る。
3.原価の徹底した下げを試みる。
仕入れ値の再点検
4.高い生産性を維持する。
受注が減ったからと言って従来の人数で生産すると、せっかく維持してきた高い生産性が下がってしまう。受注が半減すれば、半数の人数で、作業をして生産性を下げない努力をする。
一度落ちた生産性を上げるには大変な努力が必要となる。
5.従業員との良好な人間関係を作る。
不況だからと言って従業員を減らすのでなく、全員の賃金を下げて、従業員全員の雇用を確保するべきである。それによって良好な人間関係が維持される。
この5つの提言は盛和塾生にとっては常に機会あるごとに言われていることでした。
この
「不況時の備え」をしていると世の中が不況を脱した時、すぐさま飛び出すことができます。
不況を節目に大きくなっていった会社はこのような会社です。
ところが、ほとんどの会社はリストラで人を減らし、新製品開発もしていませんでしたので、景気回復
復してから、人を増やし、新製品開発を始めようとしても遅いのです。
5つの提言を実行していた会社は、はるか先を突っ走っています。
このフォーラムでの話を聞いて、私たち塾生も改めて
稲盛塾長に教えられました。
このフォーラムの後は盛和塾主体で
稲盛塾長を囲んでの懇親会、翌日は朝食会と続きました。
経営の師、人生の師とも尊敬する
稲盛さんと同じ場で過ごせた2日間は大変充実した日でした。


環境が変わるということ
先月29日日曜日に引っ越しをしました。
今まで住んでいたところから歩いて5分ほどのところです。
91歳の父84歳の母と同居するためです。
引っ越しの準備、引っ越し、荷ほどき、整理といつもと違う生活が始まりました。
その上、手違いで電話、テレビの工事が遅れています。
ラジオを聞きながら整理をし、本を読んでいる時、テレビが無いということは、いかに時間が豊富にあるかということを再認識させてくれました。
新鮮な気分です。
3日には両親が引っ越してきます。
また、今まで以上に違った生活が始まります。
自分の環境が変わることで、行動が変わり、行動が変われば、新しい出会いが生まれます。
その新しい出会いが、新しい考え方を生んでくれるかもしれません。
新しい挑戦が始まるかもしれません。
環境を変化させることは大切のように思います。
でも、自分で自分の環境を変えるには努力が必要でしょう。
これを「自力変化」と言えば、今回の引っ越しのように、自分の意志とは別に、止む得ず環境が変わることは「他力変化」です。
どちらも環境が変わることですが、「他力変化」の方が楽です。
仕方がなくそうせざるを得ないからです。
いつも引っ越しばかりできませんが、自分の周りを見回してきてください。
知らずに起きている変化の中に、自分の環境を変えるチャンスがあるかもしれません。
小さいからこそ出来る
スカイマークが頑張っています。
ご存じのように今、日本航空が会社存続の危機に陥っています。
全日空もリーマンショック以降、急激に収益が落ちています。
その中で、スカイマークは今年の4月~9月期の最終損益が19億円の黒字になったそうです。
前年同期20億円の赤字だったことを考えると急浮上です。
スカイマークの搭乗率は76%で前年と同程度の数字です。
それに対してJALや全日空は60%に落ちています。
急浮上の要因はいろいろあるでしょうが、その中で私が注目しているのは仕様機種をB737の1機種にまとめたことだと思います。
従来は280席のB767とB737の併用でした。
機種を1種類にまとめることで「部品在庫管理の簡素化」「メンテナンス手順の統一」など飛行機運営上の効率が高まりました。そして大きくコストが削減されました。
このスカイマークの運営方法はアメリカのサウスウエスト航空の戦略に倣ったものだと思います。
サウスウエスト航空のことは「破天荒『サウスウエスト航空驚愕の経営」』に詳しく書かれています。
サウスウエスト航空もジャンボのような大きい飛行機ではなく、B737のような中型機1種類に徹しました。
メンテナンスの効率化を目指し、着陸して機体点検、燃料補給をして出発するまでの時間が大幅に減少しました。
それまで飛行機の出発時間が遅れるのが当たり前のようになっていたところに、時間通り出発が出来るようになり、差別化が出来るようになったのです。
サウスウエスト航空はアメリカン航空やデルタ航空が収益を下げている時でも急激に売り上げを上げました。
その理由は大手航空会社が就航しない地方空港に中型機を飛ばすことで、地方便を独占するようになりました。そこれはブルーオ-シャン戦略そのものです。
今、日本の地方空港からJALや全日空が撤退する時、スカイマークの中型機の出番でしょう。
「主要空港と地方空港」、「地方空港と地方空港」という路線は、小回りが利く航空会社が適しています。
ますますスカイマークが躍進するのではないかという予感がします。
大きい企業が出来ない部分を小さな企業が占めて、収益を上げていく。
ご紹介したケースは「小さいからこそ出来る」を証明したように思います。
自分のビジネス環境を見直す
今、日本中不況と言われ、私の周りでも業績悪化の話をよく聞きます。
そうすると人は「悪いのは自分ばかりでない」と低レベルの連帯感を持ち、安心する人が多いです。
でも、そのような中でも、ものすごい勢いで儲かっている会社があるのです。
個人や小企業の会社でもびっくりする位儲けています。
そのような人が私の周りにもいます。
儲かっている人は大きい声で「儲かっています」とは決して言いません。
親しい人に小声で言います。
もっと慎重な人は儲かっていることをほとんど言わずに、ただ黙々と儲けています。
それは不景気の時に儲かっていると言うと、「妬み」「やっかみ」を受け、足を引っ張る人がいるのを恐れているからです。
儲かっている人の話を聞くと、自分の守備範囲はしっかり守りながら、ビジネスの新しい組み合わせを考えています。
自分の仕事の軸はブレず考えています。
大切なのは、軸がブレないことです。
一つ一つ見れば魅力ないモノでも、組み合わせでまったく新しい市場を開拓する例が沢山あります。
その時に大変重要なのは素直な心です。
成功している経営者のほとんどは素直な人です。
「あそこに行ってみたら」とか「あの人に会ってごらん」と言われてすぐ行動する人です。
「いいチャンス」「出会い」をキャッチ出来ない人のほとんどは素直でない人です。
もう一度素直な気持ちになり、見飽きている自分の周りを一度見直してみませんか?
「いい人」「いいモノ」に出会えると思います。
エコな生活
モノを大切に。日本では昔から言われていたことです。
でも、ある時から
「消費は美徳」などと言われ、「買っては捨てる」ことを繰り返してきて、その結果経済が拡大しました。
現在は
「エコ」と言われ、それに伴い新製品が生まれています。
CO2排出権というものも商品として考え出されています。
現在大事なのは、昔から言われている「モノを大切に」という考え方です。
ノーベル平和賞を受賞したケニアのワンガリ・マータイさんは日本の言葉の
「モッタイナイ」という言葉を「環境を守る言葉」として提唱しています。
「モノを大切にする」ということは、我慢して、質素に暮らすということではありません。
逆にリッチに暮らすということです。
「いいモノを買って長く使いましょう」ということです。
1万円の時計を何度も買うより、高くても自分が気に入って、長く使える時計を買うべきです。
100円ショップでも売られている料理用の道具より、柳宗理がデザインしたものはいかがですか?
柳宗理がデザインのレードは2000円ですが、丈夫でデザイン性に優れています。
料理を作るのが楽しくなります。
「安いニトリの椅子を買って、飽きたら捨て、新しいのを買う」より、「価格が高くても、座り心地がいい椅子を買い、長く使う」方が生活が豊かになります。
材料費は、安い製品も高い製品も若干の違いはありますが、売値ほどの価格差はありません。
製造会社も安いものを10個売るより、高くて利益率の高いものを1個売った方が儲かります。
そして何より、捨てられるものを大量に作るより、少量で長く使われるものを作る方が環境に優しいのです。
食卓用の椅子1脚はニトリでは8千円~1万円位からあります。
私が気に入っている
ウェグナーデザインの椅子や、
松本民芸家具の椅子は10万円程します。10倍です。
使われている木材の材質は違います。
材料費は違いますが、10倍も違うことはありません。
使われている材料は木材です。
木が家具用に育つには
50年以上の年月がかかります。
それを山から切り出した丸太を製材所が製材し、乾燥し、それを板材、角材にして出荷します。
家具会社は作る家具に寸法を合わせて板材・角材の厚みを削り、端を切り落とします。
結局、丸太から家具にされるまでに、3分の2くらいは捨てられます。
50年もかけて育てた木材も使われるのは、たった3分の1。
安い椅子も同じように作られます。
安いからといって買い、飽きたら処分するということは、いかに無駄で、環境に良くないかがわかると思います。
高くても、気に入った家具を買い
100年持たせる方が環境に優しいです。
ヨーロッパではおばあちゃんが使っていたチェストと孫娘が使っているという例がたくさんあります。
結果、いい家具を長く使うのは、環境に優しいばかりでなく、家計にも優しいことです。
物を大切に長く使い、気に入ったモノに囲まれることは、余裕が生まれる
贅沢な生活です。

柳宗理のレードル

松本民芸家具のキャプテンチェアー

ウェグナーのY-chair
お金持ちのお金の使い方
「貧乏な人」、「普通の人」、「金持ち」と大きく分けた時、それぞれの人たちのお金の使い方が違います。それはそのまま「なぜ『貧乏な人』、『普通の人』、『金持ち』なのか」の理由になっています。
お金をジュースに例えます。
ジュースをグラスに入れて差し出した時、
「貧乏な人」はグラスが一杯になる前に飲んでしまいます。
何回入れてもらっても、すぐ飲んでしまいます。
「普通の人」はグラスが一杯になるまで待ち、一杯になってから飲みます。
「金持ち」はどうすると思いますか?
「金持ち」はジュースがグラスに一杯になってもグラスのジュースは飲みません。
溢れて出てきたジュースだけを飲みます。
だから、お金も資産も出来るのです。
私は過去、これに似た情景をよく見ました。
久しぶりに寿司屋で食事をしていた時、それほど裕福に見えない家族が私の横で、「ウニ」「トロ」と高いネタを注文しています。
私は「赤身のマグロ」や「〆ザバ」などです。
一方、老舗の家では何代も前から使われている道具や着物を大事に使います。質素倹約を旨としています。決してお金に困っている訳ではなく、資産は沢山あります。
質素倹約だからこそお金持なのです。
会社運営も同じことが言えます。
お金を使い、景気よさそうに見えるところが倒産し、経費を切り詰めているところが生き延びています。
稲盛和夫さんは「経営の12カ条」の中に書いています。
「売上を最大に、経費は最小に」
売上が上がるのだから、それ相応の経費がかかるという考え方ではダメです。
売上が上がっても経費はそのまま増やさないというのが重要なところです。
やる気
クリス岡崎さんの本を読んでいて、「なるほど」と思うことがありましたのでご紹介します。
多くの人がやる気の欠如に悩んでいるのは「絶対的な理由を見つけられないから」と書かれています。
何が何でもやらないといけない理由を見つけてしまうと、ものすごい大きな力が発揮されてしまうのです。
クリス岡崎さんはその例をあげています。
「3ヶ月以内に中国語をマスターしてください」と言われると、ほとんどの人は「短すぎてマスター出来ない」とか、「語学能力がないから出来ない」と言うでしょう。
それが「3カ月以内に中国語をマスターしたら20億円あげるよ」と言われたら、どうでしょう。
俄然やる気が出て、出来ますと言ってしまうのではないでしょうか?
「出来る、出来ない」や「やる気がある、なし」は思い込みだということです。
するべきことの「絶対的な理由」を見つければ、出来るんだということをこのクリス岡崎さんの本を読んで納得しました。
「能力がない」「経験がない」などの理由より、20億円くれるならすぐ出来ますと言ってしまうほどの「絶対的理由」。
それがわかれば、次は自分にとっての「絶対的理由」は何かを見つけることです。
そのためにどうすればいいかもクリス岡崎さんは書いています。
初めは「夢を持って、それを実現しようとしている人」を、心から応援してあげればいいのです。
人の夢を応援するうちに、自分の心の中にもくすぶっていた「やる気や夢」が燃え上がっていくのです。
情熱は伝染していきます。
私がレンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」や「起業成功支援協会」を作って、皆さんの起業が成功するように応援していることも、同じことなのではないかと思います。
起業家の応援をしながら、いつの間にかその「やる気・情熱」を私も受けていることを実感しています。
中国北京に行ってきました。
21~24日中国北京に行ってきました。
北京滞在中に「滞在報告」のようにしてブログを書こうとしたのですが、私のレンタルサーバーにつながらず、帰国後の報告となりました。
やはり、中国での通信制限に引っ掛かったのでしょうか?
今回の旅行は、総勢5人のこじんまりしたグループ旅行でした。
「雇用・能力開発機構」の「創業サポートスポット」交流会のメンバーで構成され、その内「札幌オフィスプレイス」の会員は私を入れて3名です。
旅の目的の1つは異業種交流会「きっかけ会」で知り合い、今、北京に帰っている岑(ミネ)さんを訪ねること。
もう1つはバルーンアーティストのエリサさんの「バルーンアートパフォーマンス」の応援です。
今回の旅行グループには、同じ交流会メンバーの能味さんという、中国語が堪能で中国貿易を中心に起業した人が参加していただいているので、大変心強い水先案内人でした。
旅行日程は3泊4日とありますが、到着は夜遅く、最終日は朝4時30分起きてホテル出発なので、実質2日間でした。
2日間という短い時間ですが、数多くの出会いがあり、経験があり、中身が濃く楽しい時間を過ごせました。

食べ物で特筆するべきは、有名な
北京ダックを「全聚徳」という1864年清代に創業した大きな店で食べ、贅沢をしたことですね。
1人3500円位ですが、質・量とも充分で5人が皆、大満腹・大満足。
「エリサ」さんのパフォーマンスは7箇所で披露されました。
中国では道路上などの公衆が集まるところでパフォーマンスすることは禁止されています。
ですから、レストランや販売店の店頭でゲリラライブ的に行いました。
このパフォーマンスでバルンアートの凄さを改めて知りました。
先ほどまで愛想の無かった店員は、エリサさんがバルンアートを始めると笑顔いっぱいになり、キャーキャー言って彼女を取り囲みます。
ついにはその店主までもが一緒になって楽しんでいました。
習慣が違い、言葉が通じなくてもバルーンアートで人を喜ばせるという力を見せられました。
今回の旅は中身の濃い楽しい旅行でした。
帰国して今は、案内していただいた能味さんをはじめ、4人の皆さんに感謝です。

時間当たり生産性
私は現在、レンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」の運営をしていますが、家具工場の専務でもあります。
また、過去、いろいろな会社の経営を見て来ました。
経営の実態を見る上で、売上高、生産高、粗利益、営業利益等の数字の推移は大切です。
工場経営では、その中でも「1人当たりの生産性」「1人当たりの加工高」が重要視されます。
でも、もっと突き詰めれば、1人当たりの「時間当たり生産性」「時間当たり加工高」が重要です。
この「時間当たり生産性」は人的効率を表しています。
残業して生産高を上げるより、通常勤務時間内に高い生産を上げることは、会社にとっても従業員にとってもいいことです。
1人で起業した時は、この生産性の考えを取り入れてみてはいかがでしょう。
決めた目標に向かって進む時、計画を立てそれを遂行します。
しかし、一人だとつい気がゆるんで、効率が悪くなります。
起業した時、自分の「時間当たり」の作業効率を考えてみてください。
するべきことがあるのに、ついつい別のことをして時間が過ぎていきます。
一人で仕事をする時、いかに自己管理が大変かがわかると思います。
起業した時は一人ですから、誰かが話を聞いてくれる人がいません。
私が設立しました「起業成功支援協会」では、毎週1回、起業者とのミーティングを持ちます。
過去1週間の進捗状況の確認と、今後1週間のやるべきことを決めます。
自分を管理するのは難しいですが、管理するためのシステムを利用すれば
より早く目標が達成できます。
起業した時大切なのは早く成果を出すことです。
ゆっくりしている内に自分のモチベーションも下がり、成功する事業が頓挫してしまう恐れがあります。
時間を大切にしましょう。
「安売り」をせず 平成21年10月15日
今、日本はデフレ経済でどんどんモノが安くなっています。
新聞・テレビでは西友が5000円スーツを、紳士服のAOKIがワイシャツとネクタイがセットでスーツを7000円で売ると紹介されています。
800円ジーンズというのも出ています。
その中で茨城県つくば市の「みずほの村市場」という農産物直売所では安売り厳禁をルールにしていると日経で紹介されていました。
一般のスーパーより5割高くてもドンドン売れています。
品質の良いものを作れば高くても売れるとの考えです。
「価格競争は農家を疲弊させる」との考えが基本にあります。
そして、「みずほの村市場」の責任者は「高く買ってもらうには品質を磨くほかない」と言って「みずほブランド」に力を入れます。
安売りはいいように見えても最終的には会社を疲弊させてしまいます。
安売りは簡単です。知恵も工夫も何にも要りません。そして誰でも出来ます。
だから怖いのです。
でも、価格を決めるのは社長のです。そして社長の責任です。
京セラ名誉会長の稲盛和夫さんは「値付け」について次のように言っています。
「『この値段なら結構です』とお客さんが喜んで買ってくれる最高の値段を見抜くことである。これより安ければ、いくらでも注文が取れる。これより高ければ注文が逃げてしまう。そのぎりぎりの一点を射止めなければならない。」
安売りは麻薬です。始めるのは簡単ですが、やめられなくなります。
結果的に安売りをせざるを得なくなる時も、その前に知恵を出し、工夫をして、することをしてから、最後の手段だということを認識することが大切です。
「渇望感」について 平成21年10月12日
「渇望感」と言いう言葉をご存じでしょううか?
「渇望感」という言葉は最近あまり使われません。
ノドが渇いて、しきりに水を欲しがることを言います。
今、注目されている楽天の野村監督が、以前最近の野球選手のことが話題になった時、「渇望感が無い」と言っていたのを覚えています。
自分で高い目標をかかげ、それをどうしても達成したいと熱烈に思う心が「渇望感」を生むのでしょう。
野村監督は、昔の選手は技術を身につけるにしても、相手選手の癖や弱点をつかむにしても、常に心の中に「渇望感があった」と言っていました。
昔は技術も情報もすべて自分で探し、得ていかなければなりませんでした。
上を目指す時、技術や情報を盗んで自分のものにしました。
そこには、得るための並々ならない努力が必要です。
だからこそ、そこで得た技術や情報は本当に身になったのです。
今の野球は、球団にスコアラーがいて、技術や情報を教えてくれる人がいます。
情報知識はインターネットでも得ることができます。
しかし、そこに「渇望感」がありません。受け身です。
だから、吸収力が昔と比べると特段に引くくなります。
板金加工機では世界大手のアマダという会社は、全寮制の職業訓練コースを開講しました。
最近は親方・子方という徒弟制度もなくなり、技術の伝承ができなくなったためです。
板金加工会社の跡継ぎ候補者を対象に募集をし、1日7時間の講義を行います。
ここでも、単に教えてもらい、与えられるだけでは本当の技術は得ることはできないと思います。
調理の世界の話ですが、昔の調理人は親方や先輩の味や技術を得るのに、お客様が残した料理を素早く口にしたり、鍋の底に残ったスープを手ですくって味見しました。
多くの親方や先輩はその行為を許していましたが、意地悪な人は自分の味を盗まれないようにと調理して使い終わった鍋に素早く洗剤を入れて、味見させないようにしました。
だからこそ盗む方も真剣になって味を盗む努力をしました。
その中から本物の味や技術を習得したのです。
自分の目標を明確に持ち、常に満足しない「渇望感」を持った人が自分の夢をつかむのでしょう。
マリナーズのイチローのように。
トイザラス
トイザラスが20年前、日本に初出店をした店舗が閉められたと新聞に掲載されていました。
トイザラスとはアメリカの世界最大のおもちゃチェーン店の会社です。
20年前に入ってきた時の勢いはものすごいもので、影響をうけた日本中のおもちゃの店が次々と閉鎖されてゆきました。
日米の非関税障壁撤廃の象徴的な店舗でした。
トイザラスが衰退し、当時2000億円だった時価総額が、現在は十分の一の200億円になってしまいました。
その原因は少子化による需要の減少と、テレビゲームなどを売る電気販売店が新しい競争相手となって、戦うカテゴリーが変わってきことによるそうです。
経済ばかりでなく、社会的現象や環境が変わる中で、企業が生き続けるのは大変のことです。
ポケットベルも一時大変な勢いでしたが、現在はほとんど製品として存在しない状況です。
ワープロやパソコンが普及する前は、イタリアのオリベッティという会社のタイプライターが世界中で圧倒的なシェアーを占めていましたが、今は他社に買収されています。
常にアンテナを張り、現在の兆候とこれからの流れを見極め、自社をどのように展開させていくか、社長の責任はより大きくなります。
会社の規模は関係ありません。小さい会社も同様です。
でも、小さい会社だからこそ、影響を受けダメになってしまうか、逆に小さい会社だからこそ、小回りを利かすかは社長の力です。
毎日の変化を知るために、社長は会社を飛び出し、情報を仕入れ、それを生かす人脈を築かなければなりません。それができるのは会社で社長だけです。
「隠れ家」のような小さな家 平成21年10月8日
私は子供の頃から
「隠れ家」が好きでした。
小学校の時は、実際に友達と
「隠れ家」を作り、自分たちだけの世界を楽しんでいました。
その
「隠れ家」への思いは今でも続いていて、以前から
「コルビュジェの休暇小屋」や
「立花道造のヒヤシンスハウス」に関心を持っていました。
コルビュジェは有名な建築家であり、家具のデザイナーとして有名です。
立原道造は詩人として有名ですが、建築家でもありました。
「コルビュジェの休暇小屋」も
「立原道造のヒヤシンスハウス」も大きさは8畳ほどです。
手を伸ばせばほとんどの物にすぐ手が届く広さです。
最近ではルーヴィスという会社が開発した
PACO(パコ)という3メートル四方の大きさの家があります。
この
PACOの開発者は「無人島で一人で暮らしてみたい」という考えを具体的にした家だそうです。
方丈記を書いた鎌倉時代の鴨長明も3メートル四方の移動式の庵に住んでいました。
人間にとって究極の住宅は
「隠れ家」的な小さな家なのかもしれません。
これから一人で住むにはこのような小さな家が喜ばれるかもしれません。
建築費は安く、冷暖房などの維持費も安く、掃除も簡単で、家の中を動き回る必要もありません。
不必要なものを捨て、本当に大事なものだけ置き、無駄がありません。
誰かこのような小さな家を研究し専門会社を作れば、事業として拡大しそうな予感がします。




遅れている業界」に注目その2 平成21年10月7日
前々回のブログで書きました「『遅れている業界』に注目」の続きを、次回書きますと言って遅くなりました。
私が経験した「遅れている業界」の一つは「ホテル業界」でした。
その遅れている「ホテル業界」参入してきて、ブレイクしたのは「旅の窓口」(現在の楽天トラベル)です。
「旅の窓口」によって、自由にインターネット上でホテルの予約ができるようになりました。
ホテル側も宿泊料金や提供客室数を自由に決められるようになりました。
それまでは、ホテルの宿泊は近隣の契約会社かJTBのような旅行代理店にお願いするしかありませんでした。
旅行代理店との取引は、一旦提供した部屋については、ホテル側は料金も部屋数も変えることができません。
たとえ、ある日急にお客様が増えて部屋が足りなくなっても、提供した部屋は返してらえません。
と言って、旅行代理店は提供された部屋が売れ残っても保証してくれません。
自分のホテルの部屋なのに臨機応変に売ることができません。機会損失が大変多かったです。
そのうえ旅行代理店から送客されると、その売り上げの10%、多いところでは20%も手数料が取られます。
それでも、旅行代理店との取引を止めれなかったのは販売先が限られていたからです。
そのような「遅れているホテル業界」に風穴をあけたのは「旅の窓口」です。
自分のホテルの商品である客室を臨機応変に、価格と提供室数を自由に決めることができるようになりました。その上送客手数料も6%でした。
「旅の窓口」のおかげでホテルは商売の自由を得たのです。
確か「旅の窓口」は日立造船の新規事業部門で始まりましたが、たいへん多くの収益を出すようになりました。そして「旅の窓口」を楽天に売り、苦しかった本業立て直しの大きな要因になったそうです。
私は、このホテル業界に次に狙うべき「遅れている業界」は不動産業界だと思っています。
このことについては、またいつかお話しします。
社長塾 平成21年10月6日
毎回日経新聞記事を題材ににしています。
今朝の日経の札幌市内版によると、土屋ホールディングの土屋会長が無料で経営塾「人間社長塾」を開くそうです。
来年1月から10回行われ、「企業理念」「財務戦略」「営業」「事業継承」などにわたり、各回とも5時間の所要時間です。
土屋会長はご存じのように土屋ホームを創業され、「土屋経営」という経営マネジメント会社も経営されて、経営経験は大変豊富です。
土屋会長とは以前から面識があり、5年前には一緒に北欧へ視察旅行に行った折も、土屋会長からいろいろお話を伺いました。
今回社長塾を開き、若手経営者に経営体験を伝授するということは、大変素晴らしいことであり、「自社」を良くしたいと思われる経営者はぜひ参加するといいと思います。
私も参加したいのですが、この社長塾には50歳までの経営者という条件が付いています。
残念です。
「遅れている業界」を注目 平成21年10月3日
今朝の日経新聞の「春秋」に本の業界のことが書かれていました。
今月から来月にかけて幾つかの出版社が「責任販売制」を導入するそうです。
従来、本の業界では本の仕入れは「委託販売」という仕組みになっています。
これは、本屋が本を仕入れて販売して、もしも売れ残った場合は出版会社に、仕入れ価格で返却出来るというものです。
一般の業界では仕入れて売れ残った場合は、その店の責任で処理するのが普通です。
本の業界でもやっとその常識が始まります。
「委託販売」という制度は、売れ残りを引き取るということで、出版会社はそのリスク分を卸価格に上乗せしています。必然高くなります。
「委託販売」というのは問題あると昔から言われてきました。
もちろん「委託販売」によって、小さな本屋でも多くの種類の本を販売できるというメリットもあります。
しかし、この方式をとる本業界は「遅れている業界です」
「これから、起業・新事業を考える時、狙うべきは『遅れている業界』」と言った人がいました。私もそう思います。
次回のブログで、「遅れている業界」から新しい仕事が生まれた実例をお話しします。
売りは「楽しさ」 平成21年10月1日
商売をする時、いかにお客様が喜んでくださるかを考えます。
お客様が喜んで買っていただけるものを考えて売ります。
自分が儲かるものを売ろうとしても売れません。
これは言われてみれば、当たり前のことでしょう。
でも、起業したばかりの人はこれがなかなか出来ず、「売れない!売れない!」と苦しみます。
お客様が喜んで、買ていだだくものが見つからないときはとりあえず、楽しさを売ったらどうでしょうか。
「この人に会えば楽しい。」「この店に行くと面白いものがある。」でもいいのです。
今朝の日経新聞に「買い手のホンネ」という記事が載っていました。
今、全国各地に広がっているアウトレットの魅力は、ある調査によると「楽しさ」がダントツと書かれています。
節約意識は男性より強い女性が強いのに、アウトレットを利用する目的を調査すると、「節約できるから」よりも「楽しいから」としています。
楽しそうだから、買うものはなくても行ってみたいと思うのでしょう。
人もそうです。まじめで一生懸命は大事なことですが、面白みがなければお客様が来てくれません。
儲かっている商店の社長は、ほとんどの人が元気で、明るく、楽しく、悩みごとなど無いようです。
だからお客さまが引き寄せられるようにそのお店に行くのです。
芸能界でも少しくらいかっこいいい男性タレントより、お笑い芸人がもてるのは、一緒にいると「楽しい」からなのでしょう。
雑誌記事のバラ売り 平成21年9月29日
私はよく本屋に行きます
買う目的があるわけでなくても、何か面白そうな本はないかと2~3日に1回程度は行きます。
特に新聞広告で、興味ある分野が特集されている雑誌を見つけると必ず、チェックしに行きます。
でもその特集が5ページ程度だと買うのを躊躇します。
5ページのために500円、600円出すのがもったいないと思ってしまいます。
今日の日経新聞に「10月1日より雑誌記事のバラ売りが始まる」という記事が掲載されていました。
記事が1本10~50円で購入して、自分の携帯電話にダウンロードすることができるそうです。
14誌で始め、10月中に30誌に増やすとのことです。
検索機能もあり、興味ある情報の単語を記入すると各誌の情報が一覧できます。
現在は活字離れということで、雑誌の出版部数も減少しています。
「雑誌一冊を買ってくれないならば」という危機感から生まれたと新聞記事には書かれています。
私としては、携帯電話でなくパソコンにPDFでダウンロードできれば、「より使いやすい」と思います。
ただ、今回の記事を読んで思うことは、このようなサービスを始めることで、雑誌が今までより売れなくなるかもしれないというリスクを負いながら、それでも新しい可能性にチャレンジするという姿勢は素晴らしいことです。
リスクを怖がって、何もしないで「ゆでガエル」になる会社が多い中、勇気あることだと思います。
今後の推移を、興味をもって見ていきたいと思います。
札幌観光大使
突然ですが私、「札幌観光大使」です。8月からなりました。
とは言っても、現在「札幌観光大使」は207名の人が登録されています。
仕事は札幌の良さを他の地域に住む人たちに売り込むことです。
その「札幌観光大使」の集まりが9月25日にありました。
10月3日の「道産の日」を前に、北海道鮨商生活衛生同業組合が主催しました『「道産巻」で地産地消』のイベントと一緒に開催しました。
恥ずかしながら、10月3日が「道産の日」だというのは知りませんでした。
北海道の鮨組合の会員は106店舗あるそうですが、北海道地域ごとの太巻きが提供され、食べ放題。
勿論、16種類の太巻きの具材の全ては北海道産で、それぞれが美味しく、食べすぎました。
それでも16種類全ては食べきれませんでした。
北海道の食料自給率は200%と言われています。量ばかりでなく、その質の良さも高いものです。
また、食と観光は一体です。
地域ごとの特色ある観光を打ち出すには「食」が大事です。
ただ、従来のように単に新鮮さだけを売りにして、工夫もせず、あまり手を加えず、「食材」を出すだけではダメです。
今回のイベントのように、地域の特色を生かして魅力ある「商品」作りが大切なのではないでしょうか。
ところで、札幌在住で、出張が多く、札幌以外の人たちとの接点が多い人は観光大使になりませんか?
ご興味があればご連絡ください。
駅前商売
駅前で商売すると儲かります。
それは言われるまでもないことですが、それが出来るのに気が付かないことがあります。
今日の日経新聞に、東急ストアが東急電鉄の駅隣接地に小型店の展開を始めていると書かれていました。
標準タイプ店舗のサテライト店として運営されるそうです。
駅の乗降客がついでに買っていくことは多いはずです。
駅前に土地やビル・店舗を持っているところしか、駅前で商売出来ないかというとそうでもないようです。
ワゴン車を改造して自由に場所を移動して、商売をするというものあります。
でも車ですと駐車違反ということで難しいかもしれません。
それでは、自転車ではどうでしょう。
前と後ろの荷台に花を入れて駅前で売ったらどうでしょう。
工夫次第で買ってくれるお客様はいると思います。
3輪車の自転車だと、後ろの荷台が大きい分、多くの花を積んでおくことができます。
300円の花束にして50束売れば15000円になります。
場所代、光熱水道費はタダです。
交通費もかかりません。
札幌ではこのような商売見たことがありませんが、東京の方ではあるのではないでしょうか。
話題性があり、マスコミも取り上げてくれますから、結構お客様ができると思います。
早い者勝ちかもしれませんね。
起業支援セミナー 平成21年9月20日
18日金曜日に「KKRホテル札幌」で「北海道高齢・障害者雇用促進協会」が主催する起業支援セミナーでお話をしてきました。
1時間半の予定のところ少し時間オーバーしましたが、参加した方々は本当に熱心に聞いていただきました。
私は講演する時はいつも、事前に十分時間をかけて準備をしますが、今回は少し詰め込み過ぎました。
今回のセミナーの題名は、「無理をしない『身の丈起業』のすすめ」でした。
起業することの意味、それをするための準備、またそれ以前に自分自身を知るために、「自分の棚卸」、そして時間をす繰り出すための「自分時間の棚卸」について、表を作成してお話ししました。
セミナーの後、起業に関しての相談会も行われ、私も含め4人の相談員でお受けしました。
相談希望される方は結構多かったのですが、結果的に時間の制限ため、人数が限られてしまいました。
私がお受けたのはお二人。男性と女性です。
お二人とも大変熱心でした。
私は何時もこのようなセミナーで話をする度に、参加し、起業を志した方々の成功を支援する気持ちが高まります。
講演の機会を与えていただいた北海道高齢・障害者雇用促進協会さんにも感謝します。
北海道観光で起業 平成21年9月18日
私は現在は家具会社の専務をしながら、起業家向けのレンタルオフィスの会社を経営しています。
以前はホテルの仕事がメインで、札幌のホテルから始まり、東京のホテル支配人を経験しました。
6年ほど前、東京のホテルを離れて札幌の家具会社に移った時、北海道の観光について考えたことがありました。
観光とは風景を見、美味しいものを味あうだけのものではなく、その土地の生活を体験したいと思うのではないかと考えるのです。
自然豊かな北海道に来ても、宿泊するのはコンクリートで固められたホテルでは、少し味気ないのではないでしょうか。
やはり風の流れを感じ、寒さ温かさが感じられる滞在が好まれるのではないだろうかと考えます。
「都会にあるペンション」がいいと思います。
私の知り合いで東京根岸で和風旅館「澤の屋」を経営している澤さんは、木造2階建ての古い和風旅館を長年経営しています。
20年ほど前古くなった旅館をビジネスホテルに建て替えるか、廃業するか悩んだ末、和風旅館をそのままに、外国人向けの旅館として再スタートしました。
旅館の部屋は6畳間、8畳間でトイレ風呂は部屋にありません。
風呂も家庭用風呂のようなものです。
その旅館は現在常に100%近くの稼働率です。
外国のお客様は1週間以上「澤の屋」に宿泊して、日本、東京の生活を体験しているのです。
澤さんは外国人のお客様のために近隣の郵便局クリーニング屋さん、食堂などに協力を依頼して、外国語表示、案内、また食堂では外国人向けのメニューも用意されているそうです。
「地域でお客様を迎える」という考え方は、これから重要な観光のポイントではないでしょうか。
今日の日経新聞の北海道経済のページに「チェンジ北海道観光」の欄があり、そこにゲストハウスと呼ばれる宿泊施設の紹介が掲載されています。
栃木から来て起業し、ゲストハウスを経営している平野さんのことが掲載されています。
このような地域の生活を体験できる観光が脚光浴びることはいいことです。
そして、この分野はまだまだ起業の余地があると思います。
追伸
最後に私が以前に書いていたホテル経営に関しての「メールマガジン」をまとめたものがホームページ上に載せています。
ご興味がありましたらご覧になって下さい。
「小さいから楽しいホテルの経営」と検索していただければ出てくるはずです。
評価・批評の注意 平成21年9月15日
最近、人と話をしていて気付いたこと。
人と話していて第3者のことが話題になる時は、十分注意して話すようにしましょう。
その人の「いいところ」を話題にするのであれば、話が漏れても問題はありません。
ところがどうしても無意識に評価や批評をすると、たとえ悪意を持ってなくても、本人に悪く伝わる可能性があります。
「○○すればいいのにね」という言葉でも、話している相手によっては
「批評」を「批判」と受けとめ、本人に行き着く時は「悪口」になっていることが多いです。
最近は人と会うときは、「批評」⇒「批判」⇒「悪口」の流れになりやすいことは頭に置いて話すようにしています。
素直な人は騙される? 平成21年9月11日
昨日、ある人と話をしていた時です。
その人から「起業して成功する人の条件は何ですか?」と質問されました。
私が「それは素直な人が一生懸命すればいいと思います。」と応えた時
「素直な人は人に騙されやすいのではありませんか?」といわれました。
確かに、人の良さそうな人が詐欺にあって被害を受けています。
「一瞬そうだな・・」と思いました。
でも、違いました。
詐欺にあう人はほとんどが「儲かる」とか「得する」話が多いです。
それは自分だけが「儲かる」とか「得をする」ことなのです。
それは「利己」です。
「利己」の気持ちが大きいと騙されてしまいます。
商売をする時それがよく分かります。
「利己の心」が大きいと売れません。
最初から「この商品を何とか売って儲けたい」と思うと、なかなか売れません。
「売りたい、売りたい」と顔に書いている人のモノは誰も買いません。
お客様が喜ぶモノを売ろうと思う「利他」の心がないと駄目なのです。
これは稲盛和夫さんがよく言われます。
稲盛さんが書かれた「六つの精進」の中にもあります。
その3番目には「毎日の反省(利己の反省および利己の払拭)」と書いてあり
また5番目には「善行、他利行を積む」とあります。
成功する人は素直な気持ちで、一生懸命にお客様が喜ぶものを売る人なのです。
オレオレ詐欺にあう人も同一にしてしまっては、かわいそうかもしれません。
「利己」ではないように見えますが、孫や、子が困ることは自分が後で「なぜ出してくれなかったかと」責められる。それを回避したいからです。
やはり「利己」だと思います
お話してきました 平成21年9月8日
今日(9月8日)の9時30分から札幌情報未来専門学校で「仕事の仕方・考え方」と題してお話をしてきました。
12時30分までの3時間でした。
いつもは起業についてお話しているのですが、今回は職業訓練生向けということで、「仕事の仕方・考え方」と題して話をしました。
話す内容はやはり起業する人と同じ内容になります。
特に「考え方」、「どう生きるか」は、どのような仕事をする上でも同じです。
今回は稲盛和夫さんの『働き方』という本の中から、稲盛さんの考え方を説明しました。
私はこの本の内容を話すために、改めて繰返し読みました
専門学校で皆さんの前で説明し、稲盛さんの考え方を話しているうちに、私自身、自分のお腹に納まっていくよな気持ちになりました。
人に話しているのに、聞いている自分がいるように気がしました。
このような話す機会を与えていただいたことに感謝しています。
今度また、別のところですが話す機会が与えられました。
今月の18日に「社団法人北海道高齢者・障害者雇用促進協会」が主催する起業支援セミナーがあります。
題名は「無理をしない身の丈起業のすすめ」で私がお話します。
時間は18時30分~20時
場所はKKRホテル札幌7階「北斗」です。
参加者は若いでもOKとの事です。よろしければお出でください。

盛和塾全国大会に出席して
9月1日2日に横浜パシフィコで17回目の盛和塾全国大会が開催されました。
参加者は中国、アメリカ、ブラジルも含め2768名でした。
盛和塾の全会員数が5000名を超えたくらいですから、会員の半分以上が出席したことになります。2日間にわたって8人の経営体験発表を中心に進められ、、最後に稲盛塾長からの講話がありました。
この経営体験発表の中にはロート製薬の山田会長の発表もありましたが、一番印象深かったのは
㈱ざびえる本舗の太田社長の話でした。
大分県の代表的銘菓「ざびえる」を作っていた会社が8年ほど前に自己破産してしまいました。
太田氏は当時営業課長でした。そして55歳でした。
他の従業員と同様落胆の中にいたのですが、「ざびえる」というお菓子を売っていた営業課長としては、このお菓子に未練があり、またお客様からも惜しまれていました。
太田氏はそのお菓子の可能性を確信して、元従業員たちを中心にして会社を再建したのです。
経営経験も無い1サラリーマンであった太田さんが55歳で起業し、7年後の去年の8月期では5億5千万円の売上を達成し、経常利益率も10%以上になりました。
その過程では寝るのも惜しみ、誰にも負けない努力をしたそうです。
それを支えたのは、「さびえる」というお菓子をなくしてはいけないという使命感が背景にあったそうです。
そして、一生懸命努力していく中で、困難な面にあった時でも、不思議と思わぬ助けがあったりして、いい方にいい方にと好転して行ったそうです。
まるで神様が助けていただいているような気がしたそうです。
これは、稲盛塾長が書かれた「働き方」という本の中にも出てきます。
「『お前がそこまで努力したのなら、その願望が成就するように助けてやらなくてはなるまい』と、神様が重い腰を上げるくらいまでの、徹底した仕事への打ち込みが、困難な仕事にあたる時、また高い目標を成し遂げていく時には絶対必要になるのです」と書かれています。
太田氏の発表を聞いて、改めて自分の仕事の仕方、生き方を考えさせられました。
今回の全国大会も素晴らしい刺激を話を得ることが出来ました。
「起業成功支援協会」のブログを始めました。 平成21年8月17日
FC2のブロクで「起業成功支援協会」のブログを始めました。
起業した人が成功できるよう支援するために経営する時に必要な情報、システム、そして考え方をお伝えしてゆきます。
今回は次のようなブログを書きました。
起業成功方程式として「M⇒W⇒M」を説明しています。
起業して「成功する人」と「成功しない人」の違いはこの「M、W、M」にあります。
Mは「must」、Wは「want」のことです。
「must」は「have to」と同じで「~しなければならない」という意味です。
「want」は「~したい」です。
仕事は「~しなければならない」とか「~ねばならない」と思って仕事をすると、仕事はつらいものです。
ですから、「want」の「~したい」という仕事でなければ続きませんし、伸びません。
普通の人はここで終わるのですが、本当に仕事が出来る人はその後また、「must」の状態に自分を持っていきます。
楽しい仕事だけれど、より一層努力し、するべきことを誰にも負けない努力をする人は「must」の気持ちがなければ大きな成功は出来ません。
起業も同じです。そこそこの成功は「want」でも出来ます。
それなりの成功を求める人は「must」の「誰にもなけない努力」をします。
成功した人に成功したポイントを聞くと、ほとんどの人は「徹夜も当たり前」とか「休みはほとんどない」けれど、仕事が楽しいから出来るといいます。
つらい仕事ではそのような心境にはなれません。wantの仕事だから出来るのです。
成功法則「M⇒W⇒M」はどの世界でも存在します。
日本サッカー岡田監督に会いました 平成21年7月4日
7月1日に埼玉県浦和市で開催された、稲盛和夫さんの「盛和塾塾長例会」に出席するために、久しぶりに上京しました。
この盛和塾塾長例会には665名の塾生が集まり、2人の塾生が自社の経営体験を発表し、稲盛塾長がコメントする形式で行われました。
参加者の席は抽選で決められたのですが、私の席は会場の中央一番前にあるテーブルでした。
そのテーブルは、稲盛塾長の席にも近いところのうえ、あの岡田監督と一緒のテーブルでした。
幸運そのモノです。
岡田監督が着席されると、周りの席からは羨ましそうな目線を感じました。
特にホテルのスタッフのほとんど全員が監督の方ばかりを見ているのが印象的でした
さすが浦和はサッカーの盛んなところだけあります。
岡田監督と名刺交換し、握手をし、少しお話をしました。
岡田監督は3年ほど前から盛和塾に入塾されているということでした。
途中で退席されましたが、帰り際壇上に上がり、「ワールドカップではベスト4を目指します。」と宣言されました。
その時、こう言われました。
ベスト4を目指すと宣言した時、周りから「非現実的だ」とか、「無謀だ」と言われたそうです。
監督は「自分は自分に対してプレッシャーを与えないとやらないタイプ」だそうで、あえて宣言することで自分をその環境に追い込むのだそうです。
そして「出来ると思ってやって不可能なことはない」とも話していました。
稲盛塾長をはじめ665名が皆でエールを送り、拍手で見送りました。
握手した時、岡田監督の手も、稲盛塾長と同様物凄く柔らかだったのが印象的でした。
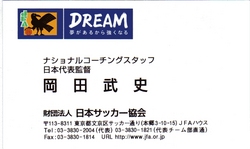


居酒屋ミーティング開店 平成21年6月19日
6月19日金曜日に、初めての「居酒屋ミーティング」を開きました。
参加者は札幌オフィスプレイスの会員とそのOB会員、合わせて10名ほどです。
私の事務所を居酒屋にし、暖簾とまではいかなかったのですが、ドアには営業中の看板を出しました。
会費は無料で、「おつまみ」や「お酒」は私の方で用意したのですが、参加された皆さんが差し入れしていただき、次回分まで集まりました。
外の居酒屋でするより話がすすみ、会員同士の親交も深まったようです。
また、他の会員の経営を直に聞け、これも良かったようです。
「居酒屋ミーティング」はこれから、札幌オフィスプレイスの恒例行事としていこうと思っています。


セミナーでお話します 平成21年5月14日
6月4日と6月24日に創業者向けのセミナーがあり、そこでお話をします。
6月4日は雇用・能力開発機構北海道センターさんが主催で「レンタルオフィスの可能性について(身の丈創業のすすめ)」を題材にお話します。
6月24日はさっぽろ産業振興財団さんが主催して「無理をしない身の丈創業のすすめ」が題材です
2つとも無理をしない自分にあった創業(起業)について、なるべく具体的にお話したいと思います。
創業(起業)する時のネタ探しのヒントなどもお話したいと思っています。
詳しくは添付しました案内書をご覧になってください。
セミナー共通リーフレット.pdf
「誰でも成功を手にする方法」を見つけました。
この連休中に本を何冊か読もうとがんばっています。
最初に読んだのは最近稲盛和夫さんが書かれた「働き方」という本です。
本を読んでいた気づいたことがあります。
ナポレオン・ヒルが書いた「成功哲学」や最近の「引き寄せの法則」の本と共通することが書いてあります。
「働き方」を読んだとき「やはり本当なんだ」とストーンと納得しました。
それは自分が思った通りのことが起きるということです。
このことは、いろいろな本に書いてありますが、改めて思い知りました。
稲盛さんはこの本の中では、働くということを中心に書いています。
「恋人のように惚れた仕事なら、好きな仕事なら、どんな仕事も耐えられる」と書いています。
これは「have to」ではなく「want to」なのです。
また、そのようにして仕事をした時『「お前がそこまで努力したなら、その願望が成就するよう助けてやらねばなるまい」と神が重い腰を上げるくらいまでの徹底した仕事への打ち込みが、困難な仕事にあたる時、また高い目標を成し遂げていく時には、絶対必要になるのです。』と書いています。
そして、「引き寄せの法則」にも同じことが書いています。
『人間の「思い」には、物事を成就させる力があるということ。特にその「思い」が気高く、美しく、純粋で、一筋なモノであるなら、最大のパワーを発揮して、困難と思われる計画や目標も必ず実現させていく。一般にはそのような人間の「思い」に素晴らしい力があることがよく理解されていません。そのために、新しい計画を立てたそばから、「予想もつかない障害に遭遇するかもしれない」とか「失敗したらどうしよう」などと、直ぐに余計な心配をし始める。しかし、そんな取り越し苦労をしたり、心に一抹の不安や危惧を抱いたりするだけで、「思い」が持つ力は大きく減衰してしまい、計画や目標を達成することが出来なくなってしまうことになるのです。』と書いています。
私は稲盛さんを尊敬して信じていますので、この言葉も信じます。
「良いことを思えば良き事を引き寄せ」「悪いことを思えば悪いことを引き寄せる」のは本当なのです。
そして神様が手助けするくらい一生懸命目標に向かって努力すれば、悪いことを思う暇もなく、成功への自信がつくのでしょう。
スポーツの世界には「練習は裏切らない」という言葉があると聴いたことがあります。
誰にも負けない練習をすれば必ず良い結果はついてくるという意味です。
お守りや幸福のグッズは、ただ持っているだけで成功するのではなく、その人間の「思い」のモチベーションを保つための御まじないなのかもしれませんね。
私は本当にいい本を読んだと思います。私の目標を達成する自信がつきました。
もしも本当に成功したいと思っている人がいましたら、読むことを薦めます。
常に創造的な仕事をする 平成21年4月16日
時間が少し空きましたが、以前ブログでご紹介しました「盛和塾の勉強会」の続きを書きます。
経営の12カ条の10番目にある「常に創造的な仕事をする」がテーマです。
稲盛さんが話される「常に創造的な仕事をする」ということは、「昨日より今日」「今日より明日」と常に改善をし続けることを意味しています。
そして、それが習慣として身についている事が大切。
365日、毎日毎日そのような改善を続けていくと、一つ一つは小さな変化かもしれませんが、1年後2年後には大きな変化になっていきます。
創造的な仕事と言われると、何かを発明をすることと思いがちですが、決してそうではありません。
創意工夫は発明発見とは違います。
参加メンバーのある人が言っていました
「コピー+コピー=オリジナル」と。
これに近いかもしれません。
新しいアイデアのほとんどは過去の何かの応用で考えられています。
最後にアイデアを考える時に使える「いいモノ」を教えましょう。
「オズボーンのチェックリスト」というのをご存知でしょうか?
紹介しますこの「オズボーンのチェックリスト」を頭に入れて、物を見たり、考えたりすると、フッといい考えが生まれることがあります。参考にしてください
1.他に利用したらどうか
今のままで新しい使い道はないか
少し変えて他の使い道はないか
2.アイデアを借りたらどうか
これに似たものはないか
他に似たアイデアはないか
3.大きくしたらどうか
何か加えたらどうか
もっと回数を多くしたらどうか
4.小さくしたらどうか
分割したらどうか
やめたらどうか
5.変更したらどうか
形式を変えたらどうか
意味を変えたらどうか
6.代用したらどうか
他の材料にしたらどうか
他の人にしたらどうか
7.入れ換えたらどうか
他の順序にしたらどうか
原因と結果を入れ換えたらどうか
8.反対にしたらどうか
役割を逆にしたらどうか
立場を変えたらどうか
9.結合したらどうか
目的を結合したらどうか
アイデアを結合したらどうか
4回目の起業サロン開催しました。
昨日(7日)起業サロン開催しました。
参加者は13名で定員一杯でした。
題材は平成18年6月にNHK教育テレビで4週にわたって放送された番組のDVDです。
今回は
第1回 リーダーの条件 (4月7日)
第2回 挫折だらけの青春 (4月7日)
を見て、参加者がそれぞれの経験の中から意見を述べていただきました。
内容は起業サロンのコーナーでお伝えしますが、皆さんのお話が私にとって参考になり勉強になりました。
次回は5月13日を予定しています。
FMラジオ「カロス」でお話をしました
今日6日午前9時から10頃まで、FMラジオ(78.1MHhz)の「カロス」でお話をしてきました。
今日から数ヶ月間、毎週月曜の9時から1時間「札幌オフィスプレイス」で
放送の枠をもらい、会員の皆さんが交代でお話をします。
第1週目の月曜日は私が担当で、「起業」についてお話をします。
第2週は「日本リンパ美容協会」の岩田さんが担当。
第3週は「ライフデザインラボ」の加藤さんが仏事についてお話をします。
第4週は「サムシングエルス」さんの堀川さんが「お店応援」ということで
お客様のお店のを紹介をします。
札幌オフィスプレイスの会員仲間が、自分の会社をラジオでアピールできる
番組が持てるというのは一つのチャンスです。
これからも他の会員で参加したい人達にはその機会を作りたいと思っています。
今日の私のはじめてのラジオデビューについては、改めてお話します。
ブログを始めます
今日よりブログをはじめます。
よろしくお願い致します。
私は「起業家が成功するのオフィス『札幌オフィスプレイス』」を
運営しています山地と申します。
このブログでは札幌オフィスプレイスの出来事を中心にご紹介し
入居されている会員の方々の活動もお伝えしたいと思います。
また、私は起業する人が成功するのを応援する「起業メンター」として、
起業に関することなども書いてゆきたいと考えています。
起業することは誰でも出来ます。
法務局に株式会社設立の書類を出せばそれで会社は出来ます。
大事なのは起業した会社が利益を出し、継続することです。
ホームページの「ごあいさつ」のところにも書きましたが一人で起業する時
一番の問題は孤独であることと、それによるモチベーションの低下です。
このブロクでは少しでもモチベーションが上がる話を書くように努めます。
改めて よろしくお願いいたします。
▲このページのTOPへ



 先日
先日 、サントリーの「山崎10年」ものを探したのですが、どこの店にも置いていません。
、サントリーの「山崎10年」ものを探したのですが、どこの店にも置いていません。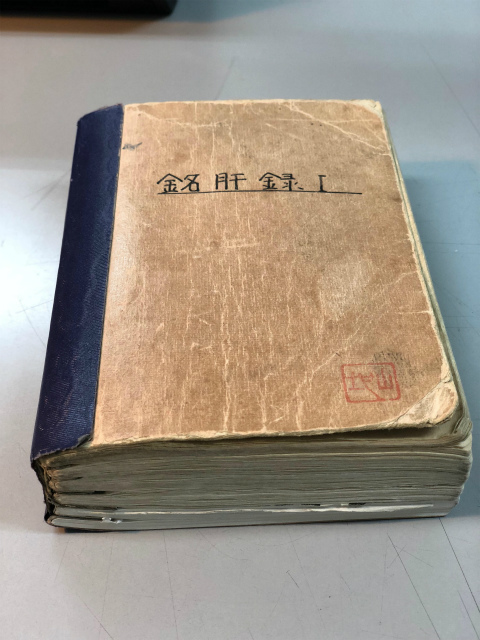









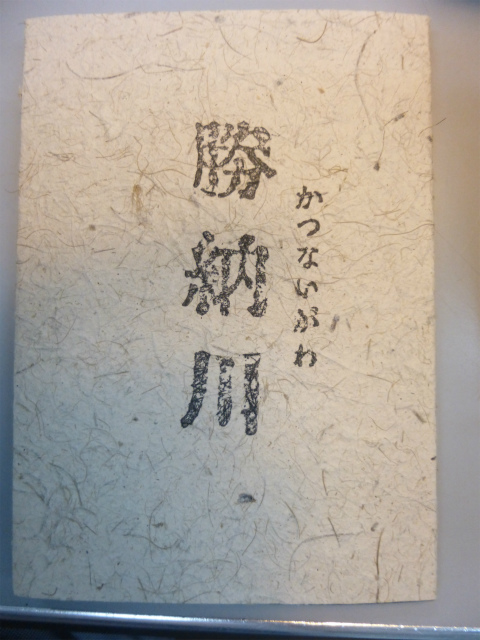

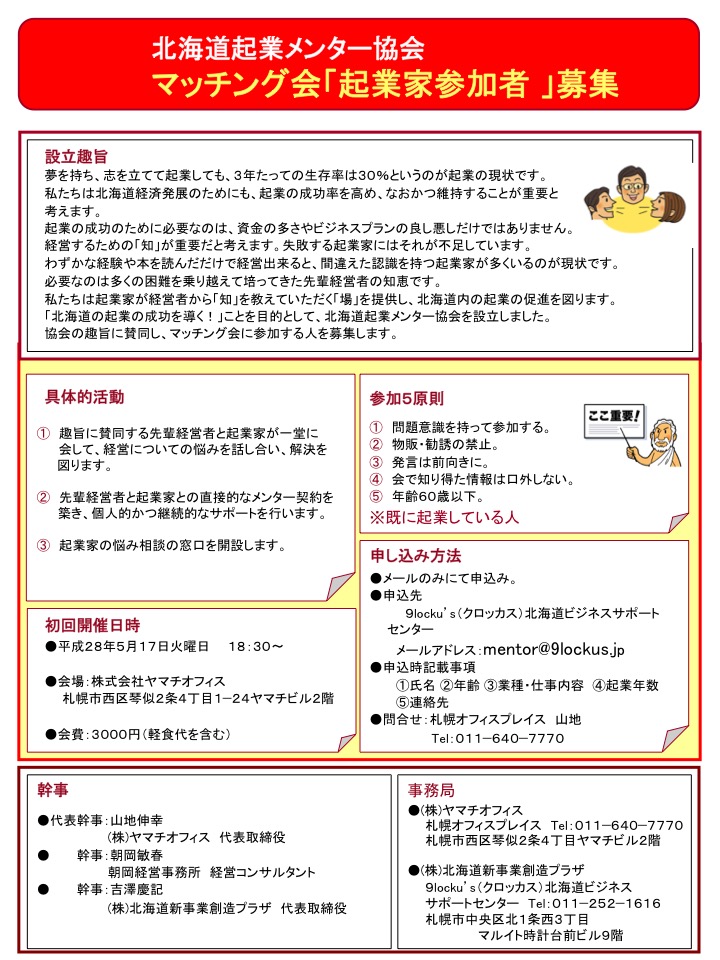



 先月末30日に初めてカシオペアに乗りました。
先月末30日に初めてカシオペアに乗りました。
 昨日、机の中を整理していたらプレジデントという雑誌の切り抜きが出てきました。
昨日、机の中を整理していたらプレジデントという雑誌の切り抜きが出てきました。

 今年の3月3日から始まった「琴似のランチ」を食べ尽くす「仕事」は昨日の7月22日に終了しました。
今年の3月3日から始まった「琴似のランチ」を食べ尽くす「仕事」は昨日の7月22日に終了しました。


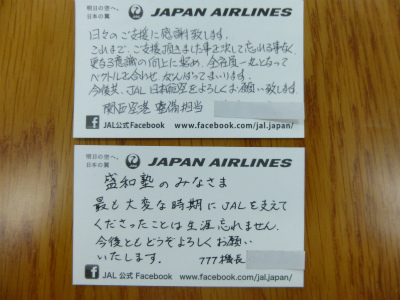



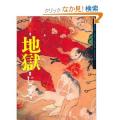






















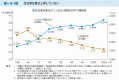












 柳宗理のレードル
柳宗理のレードル  松本民芸家具のキャプテンチェアー
松本民芸家具のキャプテンチェアー  ウェグナーのY-chair
ウェグナーのY-chair